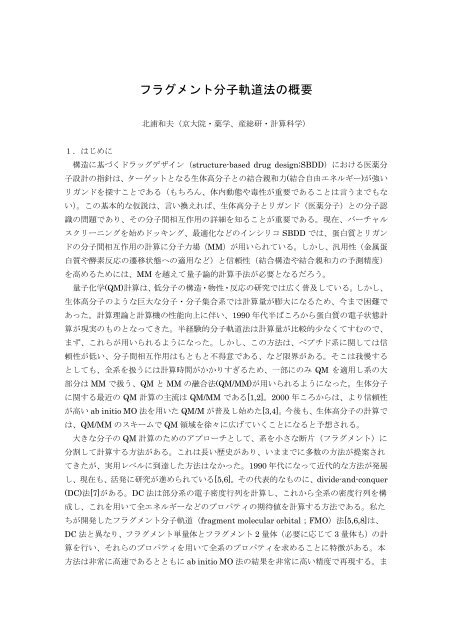フラグメント分子軌道法の概要
フラグメント分子軌道法の概要
フラグメント分子軌道法の概要
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
1.はじめに<br />
<strong>フラグメント分子軌道法の概要</strong><br />
北浦和夫(京大院・薬学、産総研・計算科学)<br />
構造に基づくドラッグデザイン(structure-based drug design;SBDD)における医薬分<br />
子設計の指針は、ターゲットとなる生体高分子との結合親和力(結合自由エネルギー)が強い<br />
リガンドを探すことである(もちろん、体内動態や毒性が重要であることは言うまでもな<br />
い)。この基本的な仮説は、言い換えれば、生体高分子とリガンド(医薬分子)との分子認<br />
識の問題であり、その分子間相互作用の詳細を知ることが重要である。現在、バーチャル<br />
スクリーニングを始めドッキング、最適化などのインシリコ SBDD では、蛋白質とリガン<br />
ドの分子間相互作用の計算に分子力場(MM)が用いられている。しかし、汎用性(金属蛋<br />
白質や酵素反応の遷移状態への適用など)と信頼性(結合構造や結合親和力の予測精度)<br />
を高めるためには、MM を越えて量子論的計算手法が必要となるだろう。<br />
量子化学(QM)計算は、低分子の構造・物性・反応の研究では広く普及している。しかし、<br />
生体高分子のような巨大な分子・分子集合系では計算量が膨大になるため、今まで困難で<br />
あった。計算理論と計算機の性能向上に伴い、1990 年代半ばころから蛋白質の電子状態計<br />
算が現実のものとなってきた。半経験的分子軌道法は計算量が比較的少なくてすむので、<br />
まず、これらが用いられるようになった。しかし、この方法は、ペプチド系に関しては信<br />
頼性が低い、分子間相互作用はもともと不得意である、など限界がある。そこは我慢する<br />
としても、全系を扱うには計算時間がかかりすぎるため、一部にのみ QM を適用し系の大<br />
部分は MM で扱う、QM と MM の融合法(QM/MM)が用いられるようになった。生体分子<br />
に関する最近の QM 計算の主流は QM/MM である[1,2]。2000 年ころからは、より信頼性<br />
が高い ab initio MO 法を用いた QM/M が普及し始めた[3,4]。今後も、生体高分子の計算で<br />
は、QM/MM のスキームで QM 領域を徐々に広げていくことになると予想される。<br />
大きな分子の QM 計算のためのアプローチとして、系を小さな断片(フラグメント)に<br />
分割して計算する方法がある。これは長い歴史があり、いままでに多数の方法が提案され<br />
てきたが、実用レベルに到達した方法はなかった。1990 年代になって近代的な方法が発展<br />
し、現在も、活発に研究が進められている[5,6]。その代表的なものに、divide-and-conquer<br />
(DC)法[7]がある。DC 法は部分系の電子密度行列を計算し、これから全系の密度行列を構<br />
成し、これを用いて全エネルギーなどのプロパティの期待値を計算する方法である。私た<br />
ちが開発したフラグメント分子軌道(fragment molecular orbital;FMO)法[5,6,8]は、<br />
DC 法と異なり、フラグメント単量体とフラグメント 2 量体(必要に応じて 3 量体も)の計<br />
算を行い、それらのプロパティを用いて全系のプロパティを求めることに特徴がある。本<br />
方法は非常に高速であるとともに ab initio MO 法の結果を非常に高い精度で再現する。ま
た、効率良く並列計算を行うことができるのも特徴である。現実に、光合成反応中心複合<br />
体(約 2 万原子系)の FMO による HF/6-31G*計算が 600CPU を用いて 3 日で行うことが<br />
出来た[9]。今後の計算機が CPU の数を増やすことで性能を上げる方向であることから、超<br />
並列計算が効率よく行えることが、高速計算のための重要な要件のひとつとなる。<br />
さらに、FMO 法では、フラグメントを単位として、分子内・分子間の相互作用エネルギ<br />
ーを求めることができる。これを解析手法として用いると、蛋白質内のアミノ酸残基間の<br />
相互作用や蛋白質とリガンドの相互作用をアミノ酸残基単位に分割して見ることができる。<br />
このような情報は蛋白質の分子認識機構の理解やそれに基づくドラッグデザインに有用な<br />
知見を与えるであろう。また、蛋白質のような巨大・複雑な分子の構造や安定性を理解す<br />
るには、全エネルギーなど全系のプロパティが求まるだけでは不十分で、分子内でのアミ<br />
ノ酸残基間の相互作用を知ることはよりよい理解に役立つであろう。<br />
本稿では、FMO 法の解説とそのドラッグデザインへの応用を目指した基礎的な応用例と<br />
して、FK506 結合蛋白質とそのリガンドの相互作用の解析と結合自由エネルギーの計算を<br />
紹介する。本稿が、量子化学計算を創薬研究の場で活用していただくきっかけになれば幸<br />
いである。<br />
2.量子化学計算<br />
1) Hartree-Fock 法<br />
まず、分子軌道法に関する用語の紹介を兼ねて、Hartree-Fock(HF)法について簡単に説<br />
明する。これは Schrödinger 方程式のもっとも荒い近似解であるが、分子の電子状態計算<br />
の基本となる方法である。分子軌道(MO)�i は、基底関数��(原子に中心を持つ原子軌道<br />
様の関数)の重ね合わせで、次式のように表される(以下、簡単のために分子は閉殻系と<br />
仮定する)。<br />
m<br />
�<br />
��1<br />
� � C<br />
(1)<br />
i<br />
� i � �<br />
MO 係数 C�i(i=1,2,…,m;m は基底関数の数)は、Fock 方程式と呼ばれる、次の一般化固<br />
有値問題を解くことで求めることができる。<br />
FC � SCε<br />
(2)<br />
F � H � G<br />
(3)<br />
H �� �<br />
1 Z a<br />
� � � � � 2 r � r<br />
�<br />
(4)<br />
a a<br />
� 1 �<br />
G �� � � D��<br />
����<br />
�� �� ��� �� ��<br />
(5)<br />
� , � � 2 �<br />
S � �<br />
(6)<br />
�� �
nocc<br />
�<br />
i�1<br />
D��<br />
� 2 Ci�C<br />
i�<br />
(7)<br />
F は Fock 行列、S は重なり積分行列、�は固有値行列(軌道エネルギーを対角要素に持つ対<br />
角行列)、C は MO 係数の行列である。F は一電子ハミルトニアン H(電子の運動エネルギ<br />
ーと電子と核電荷の相互作用の和)と電子-電子の相互作用 G の和である。D は密度行列<br />
で、MO 係数の積を被占軌道(nocc;電子数の 2 分の 1)について和をとる。Fock 方程式(式<br />
(2))は非線形であるため、最初に仮定の D を与えることから始めて、これが自己無撞着(self-<br />
consistent-field;SCF)になるまで繰り返し計算をするので、SCF 法とも呼ばれる。MO<br />
が求まると、全電子エネルギーE el は次式で計算される。<br />
E el<br />
1<br />
� Tr<br />
2<br />
�D�H � F��<br />
また、これに原子核間の反発エネルギーE NR を加えると分子の全エネルギーE が求まる。<br />
E<br />
el NR<br />
� E � E<br />
(9)<br />
ab initio MO 法では、式(4)から(6)の積分をまじめに計算するため、多くの計算時間が必<br />
要となる。特に、電子-電子相互作用を記述する 2 電子積分(μν|λσ)は、基底関数の 4<br />
つの組み合わせとなるので、計算しなければならない積分の数は m 4 となる。このため、ab<br />
initio MO 法の計算時間は、分子のサイズ(基底関数の数)の 3~4 乗に比例して計算時間<br />
が増大する(実際の計算では、小さな値を持つ積分は無視されるので依存性は4乗より低<br />
くなる)。AM1 法などの半経験的 MO 法では、実験値をパラメータとして使うことで、計<br />
算すべき積分の量を大幅に省略して、計算の高速化を達成している。この場合、最も計算<br />
時間がかかるのは固有値問題(式(2))を解くところで、この計算量は系のサイズの 3 乗に<br />
比例する。このように、分子軌道計算は分子のサイズが大きくなるにつれ急激に計算量が<br />
増えるため、たとえ半経験的 MO 法といえども、数千~数万原子からなる蛋白質のような<br />
巨大分子の計算は現実的に容易ではない。<br />
巨大分子・分子系の電子状態計算を可能とするためには、計算量が系のサイズの 1 乗に<br />
比例する程度の計算量となるアルゴリズムを開発することが重要な要件となることが明ら<br />
かで、1990 年代初めころから、この要件を満たす方法(リニアスケーリング法またはオー<br />
ダーN 法と呼ばれる)の研究が活発に進められている[10,11]。<br />
2)電子相関<br />
HF 法は、電子は、他の電子と核電荷が作る平均場の中で、独立に運動するとする近似で<br />
ある(独立粒子近似)。この近似は、分子の構造・物性をかなり精度よく記述するので、標<br />
準的な方法として用いられてきた。しかし、より高精度が要求される場合には、電子の相<br />
関運動(電子と電子は反発するので、お互いが近づくのを避けて運動する)を考慮した電<br />
子状態理論を用いる必要がでてくる。密度汎関数理論(density functional theory;DFT)<br />
は電子相関を考慮した最も簡便な理論であり、HF 法とほぼ同程度の計算量でありながら、<br />
(8)
より高精度の結果が得られるため、最近は HF 法に代わる標準的な電子状態計算法となって<br />
いる。<br />
電子相関は、HF 近似と正確な解との差(すなわち、HF 近似で扱えない部分)と定義さ<br />
れる。電子相関には性格の異なった 2 種類があると考えられ、これらは概念的に静的相関<br />
と動的相関と呼ばれる。HOMO-LUMO ギャップが小さい系(遷移金属原子を含む系や反<br />
応の遷移状態など)では、1つの電子配置波動関数を用いる方法(HF 法)の精度が格別に<br />
低下するため、複数の電子配置波動関数を重ね合わせた記述が必要になる(エネルギーの<br />
低い軌道に下から順番に電子をつめた電子配置とそれより上の軌道に電子をつめた配置の<br />
エネルギー差が小さくなる、すなわち、電子のつめ方が一通りに決まらない)。このような<br />
場合の電子相関が前者に分類される。これ以外の電子相関は動的相関とされ、非極性分子<br />
間に働く分散力や CH-πなど弱い相互作用で重要となる。蛋白質では水素結合をはじめと<br />
して多数の分子内非結合相互作用があり、これらが配座異性体の相対安定性を支配してい<br />
ると考えられるため、また、蛋白質とリガンドの分子間相互作用においても、非極性グル<br />
ープ間の相互作用を精度よく見積もるために、動的電子相関が扱える計算法を用いること<br />
が不可欠となる。<br />
残念なことに、簡便な電子相関理論である DFT は、現在のところ、分散力を評価できる<br />
汎関数が確立されていないために(このような汎関数の研究は非常に活発に行われており、<br />
近い将来、信頼性の高い計算が可能になることが期待される)、生体高分子の計算に用いる<br />
には限界がある。したがって、波動関数に基づく電子相関理論を用いることになる。一般<br />
に、電子相関理論の計算量は、HF 法に比べて格段に増えるとともに分子サイズ依存性もよ<br />
り急激である。最も簡便な Møller-Plesset の 2 次摂動論(MP2 法)でも、系のサイズの 5<br />
乗、より高精度な coupled cluster 理論では 7 乗(CCSD(T)の場合)に比例して計算時間<br />
が増える(計算時間のみならず膨大なメモリやディスク容量が必要になる)。電子相関理論<br />
においても、1980 年代から巨大分子が扱える方法として、局所相関理論(local correlation<br />
theory)[12,13]の開発が行われているが、タンパク質を丸ごと計算できるレベルには到達<br />
していない(これらの理論では HF 解が求まっていることを前提としているために、数千<br />
原子系に適用しようとすると、まず、HF 法が解けないという問題がある)。以下で説明す<br />
る FMO 法は、HF 法のみならず種々の電子相関理論の近似法としても用いることができる<br />
ため、巨大分子の電子相関レベルの計算が可能である。<br />
3.フラグメント分子軌道法<br />
1)概要<br />
フラグメント分子軌道(FMO)法は、巨大分子または分子集合体を、図1に示すように、<br />
数十原子程度の小さな N 個のフラグメントに分割し、フラグメント(以下、モノマーとい<br />
う)とフラグメントペア(ダイマー)について、ほぼ通常の ab initio MO 法と同様の計算<br />
を行うだけで、分子の全エネルギーなどのプロパティを計算する方法である。 全系の全
エネルギーは、モノマーの全エネルギーを EI、ダイマーの全エネルギーを EIJ として、次<br />
式で計算する。<br />
N<br />
N<br />
E � � EI<br />
� �<br />
I<br />
I �J<br />
双極子モーメントなど他のプロパティの計<br />
算にも同様の展開を用いる。式(10)は、<br />
最初に提案された FMO 法[14]を一般化し<br />
たもので、2 体展開で打ち切ったのがオリ<br />
ジナルの方法(FMO 法または FMO2 法)<br />
で、3 体展開まで拡張された方法を FMO3<br />
法[15]と呼んでいる。<br />
�E � E � E � � ( higher � body contribution)<br />
FMO 法では、大きな分子をそのまま計算<br />
する代わりに、多数の小さな ”分子” の<br />
ab initio MO 計算を行う。計算すべきモノマ<br />
ーの数は N 個で、ダイマーの数は N(N-1)/2<br />
IJ<br />
I<br />
J<br />
� (10)<br />
個となる。100 フラグメントの場合、100 個のモノマーと 4,950 個のダイマーを計算するこ<br />
とになる。そのため、100 原子程度以下の小さな分子であれば、通常の ab initio MO 計算の<br />
方が速い。しかし、ab initio MO 法は系のサイズの 3 から 4 乗に比例して計算時間がかかる<br />
のに対して、FMO 法のシステムサイズ依存性は2乗なので、系が大きくなればなるほど<br />
FMO 法が高速になる。また、MP2 などの電子相関レベルの計算では、もっと小さな系で<br />
も FMO 法の方が速い。また、FMO 法は、数百台の CPU による大規模並列計算が効率よ<br />
く行えるのが特徴である。数十台のパソコンがあれば数千原子からなる巨大分子の 1 点計<br />
算を、数百台あればその構造最適化計算を日常的に行うことができる。<br />
2)分子集合体<br />
まず、分子集合体の場合(系をフラグメントに分割する際に、共有結合を切断する必要<br />
がない場合)について説明する。これは、最初、Pair Interaction Molecular Orbital(PIMO)<br />
法として提案されたものである[16]。 式(10)の右辺にある EI および EIJ はそれぞれ他の分<br />
子が作る静電ポテンシャル(環境静電ポテンシャル)を受けて分極したモノマーI とダイマ<br />
ーIJ のエネルギーである。このような状態は、モノマーI やダイマーIJ の Fock 演算子に周<br />
りのモノマーからの静電ポテンシャル V (式(14))を付加した modified Fock 演算子F ~ (式<br />
(12))を用いて、Fock 方程式(式(11)。簡単のために閉殻系と仮定する。)を解くことによ<br />
り求めることができる。<br />
~<br />
F<br />
x<br />
C<br />
~<br />
図1 分子のフラグメントへの分割。<br />
x x x x<br />
� S C ε , (11)<br />
~ x ~ x x<br />
F � H � G ,<br />
(12)<br />
f4<br />
f3<br />
f2<br />
f1
~ x x x<br />
H � � V ,<br />
(13)<br />
��<br />
H �� ��<br />
��<br />
��<br />
x<br />
Z A<br />
K<br />
V �� � � ��<br />
� � � � � D��<br />
( �� �� ) �<br />
K �x �� A�K r � RA<br />
���K<br />
�� E<br />
x<br />
x ~ x ~ x NR<br />
� �H � ���<br />
E<br />
(14)<br />
1<br />
� Tr D F x<br />
(15)<br />
2<br />
ここで、モノマーとダイマーは、それぞれ、x=I と x=IJ である(FMO3 でのトリマーは x=IJK)。<br />
式(14)の環境静電ポテンシャル V は、核引力項と電子間反発項((μν|λσ)は 2 電子積分)<br />
からなる。<br />
さて、まず、モノマーの状態の求め方であるが、これを求めるには、他のモノマーが作<br />
る静電ポテンシャルが分かっている必要がある。2 次摂動の範囲内で導いた結果によると、<br />
事前に孤立分子を解いておいて、その電子分布を用いて静電ポテンシャルを計算すればよ<br />
い。しかし、物理的描像に従うな<br />
ら、求めるべきモノマーの状態は、<br />
系中の環境で分極した状態(“分<br />
子内モノマー”)である。これは、<br />
各モノマーの状態を、全モノマー<br />
が self-consistent になるまで繰<br />
り返し計算を行うことにより求<br />
める方が理にかなっている。この<br />
ようにすると、モノマーの分極相<br />
互作用に関して、N 体までの高次<br />
項を取り込むことができる。<br />
次に、ダイマー(“分子内ダイ<br />
マー”)計算であるが、これの状<br />
態は self-consistent になったモ<br />
ノマーが作る静電ポテンシャル<br />
中で一度だけ計算する(周りのモ<br />
ノマーと self-consistent に解く<br />
ことはしない)。一度だけの計算<br />
というのは、計算時間を節約する<br />
という目的ではないことに注意<br />
してほしい。式(10)の、ダイマ<br />
ーの和には過剰(2 倍)な分極相<br />
図 2 FMO-HF 計算のフローチャート
互作用エネルギーが含まれており、モノマーの分極エネルギーが差し引かれて正しく計算<br />
できるようになっている。したがって、モノマーとダイマー中のモノマー(仮想的に考え<br />
るだけ)は同じ分極エネルギーをもたないと、完璧にキャンセルしなくなり、この分だけ<br />
誤差となる。すなわち、系の分極エネルギーを過剰に計算しないために、ダイマーはモノ<br />
マーの状態を固定して、それらがつくる静電ポテンシャル中で解かなければならないので<br />
ある(以上の手順は、図 2 のフローチャートで示してある)。<br />
このようにして、全系の計算を一切行うことなく、モノマーとダイマー(FMO3 ではト<br />
リマーも)の計算を行うだけで、式(10)により全系のエネルギー(他のプロパティも同<br />
様)を求めることができる。<br />
3)共有結合の切断<br />
巨大分子系では、共有結合を切断して分子をフラグメントに分割しなければならない。<br />
FMO 法では、この分割は、切断する結合の電子対は保存したまま行う(2 つのラジカルに<br />
開裂させない)。分割は、電子の非局在化が少ない単結合を切断する(切り離す)のが良い<br />
(計算結果の精度が高い)。ポリペプチドの場合は図 3a,b のように C�-C で分割するのがよ<br />
い(結合を切り離した原子、今の場合 C�、を bond-detached atom;BDA と呼ぶ)。切り<br />
離した結合の電子対(2 電子)は図に示すように BDA の右側のフラグメントに帰属させる。<br />
BDA は両フラグメントで仮想原子として扱うが、その核電荷を電子数の割り振りにあわせ<br />
て配分する。すなわち、図 3cで、f:I フラグメントは1電子を隣のフラグメントに与え<br />
たので、このフラグメントの仮想原子の核電荷は、炭素原子の+6 から1引いた+5 とする。<br />
一方、f:I+1 フラグメントは、余分に割り振られた 1 個の電子に対応して、仮想原子の核<br />
電荷は+1 とする。両フラグメントのこれらの仮想原子はともに同じ位置に置かれるので、<br />
当然、これらの仮想原子間の核間反発エネルギーは無視する。このようにしてフラグメン<br />
トの電荷が元のものと同じになるようにしておくと、分子内で遠く離れたフラグメント間<br />
の非結合相互作用エネルギーが、ほぼ、分子間相互作用のエネルギーに相当する値になる<br />
ので、後で述べるように、分子内・分子間非結合相互作用の解析に使う場合に便利である<br />
(BDA の核荷電の割り振りは、してもしなくても、全エネルギーや他のプロパティの値は<br />
同じになることに注意してほしい)。<br />
共有結合を切断すると、境界をいかに処理するかが問題になる(水素原子でキャップす<br />
ることが多い)。FMO 法では、BDA の基底関数を混成軌道に変換して、これをフラグメン<br />
トに振り分けることで境界処理を行う。この振り分けは、必要な混成軌道以外の基底関数<br />
をそれぞれのフラグメントの MO 空間から排除するための射影演算子を用いることで容易<br />
に行える(図 3c)。具体的には、式(13)のコアハミルトニアンを、射影演算子を加えた次<br />
のもので置き換えればよい。<br />
~ x<br />
H �<br />
x x<br />
�V<br />
� B<br />
h<br />
� �<br />
h<br />
� � ,<br />
(16)<br />
��<br />
H �� �� �<br />
i<br />
i<br />
i<br />
i
ここで、φi は混成軌道で、B はパラメータである。B は一定値で、十分大きな値(10 6Hartree)<br />
を用いる。混成軌道は、どんな LMO から作ったものを用いても計算結果への影響は小さい<br />
が、NLMO(Natural Localized Molecular Orbital [17])をもとに作成することを推奨し<br />
ている。BDA が sp 3 炭素原子の場合、CH4 分子の NLMO から、炭素原子の MO 係数のみ<br />
取り出して、規格化したものを用いる(規格化は必須の要件ではない)。<br />
a)<br />
c)<br />
4)高速化のための近似<br />
bond-detached atom<br />
図 3 共有結合系のフラグメント分割と境界の処理。a)ペプチドのフラグメント分割例(2<br />
残基単位、点線円弧が切断部位を示す)、b)S-S 結合した Cys 残基の分割、c)フラグメン<br />
ト分割位置の原子(bond-detached atom)の電子、核電荷と基底関数の割り振り。<br />
FMO 法では、モノマーとダイマー(FMO3 ではトリマーも)のみ計算すればよいので、<br />
計算する系のサイズは小さいが、それぞれにかかる静電ポテンシャルの計算には 2 電子積<br />
b)
分が含まれており、この計算の負担が結構大きい。これは、遠くはなれたモノマーからの<br />
静電ポテンシャルの計算を、Mulliken 近似や点電荷近似で置き換えることによって高速化<br />
できる。この際、先に述べたように、FMO 法はモノマーとダイマーのエネルギーの微妙な<br />
バランス(分極エネルギーの相殺)の下に成り立っているので、近似を導入することによ<br />
りこのバランスをこわしてしまうと、大きく精度が低下する。モノマーとダイマーに個別<br />
に静電ポテンシャル近似を適用すると、このバランスが保障されない。したがって、この<br />
問題が起こらないように、全エネルギーの計算式(10)を(FMO2 の場合)、次のように書<br />
き換えておく[18]。<br />
ここで、<br />
IJ IJ<br />
� �E' IJ �E'<br />
I �E'<br />
J �� �Tr��<br />
V �� �<br />
E �<br />
D E'<br />
(17)<br />
I �J I �J<br />
I<br />
x x<br />
E' � E � Tr(<br />
D V )<br />
(18)<br />
x<br />
x<br />
� (19)<br />
IJ IJ I J<br />
D�� � D��<br />
� D��<br />
� D��<br />
である。式(17)では、ダイマーとモノマーの分極に起因する静電相互作用のうち、両者で相<br />
殺する分はすでに取り除かれて、正味の差だけを含んでいる。あからさまに含まれる環境<br />
静電ポテンシャルはダイマーのもののみで、モノマーの環境静電ポテンシャルは含まれて<br />
いないので全エネルギーに直接影響を与えない。この式を用いて全エネルギーを計算すれ<br />
ば、ダイマーとモノマーの微妙なバランスについて配慮することなく、静電ポテンシャル<br />
の近似を適用することができる。<br />
静電ポテンシャル近似のひとつは、2 電子積分の Mulliken 近似を用いて、<br />
V D ( x,<br />
K)<br />
� L<br />
(20)<br />
K<br />
K K<br />
�� � � ( S ) �� ( �� �� ) for Rmin<br />
��K<br />
と近似する(espap 近似)。これは比較的近距離のモノマーに適用できる。より遠距離のフ<br />
ラグメントには、Mulliken の原子電荷 Q A を用いた点電荷近似、<br />
Q<br />
V � R ( x,<br />
K)<br />
� L<br />
K<br />
A<br />
�� � � �<br />
A�K r � R A<br />
for min<br />
を用いる(esppc 近似)。これらは、モノマーとダイマーの計算ともに適用できる。<br />
ダイマー計算では、上記の静電ポテンシャル近似に加えて、遠く離れたモノマーで構成<br />
されるダイマーについては、Fock 方程式を解くことなく、モノマー間の静電相互作用エネ<br />
ルギーを計算するだけで十分な精度でダイマーのエネルギーが計算できる(esdim 近似)。<br />
I J<br />
J I<br />
I J<br />
�D u �� Tr�D<br />
�� � � D��<br />
D��<br />
��� ��<br />
�<br />
E' � E'<br />
�E'<br />
�Tr<br />
u<br />
(22)<br />
IJ<br />
I<br />
J<br />
ptc<br />
�� �I �� �J<br />
ここで、u I はフラグメント I の核引力積分行列である。この近似により、系が大きくなる(フ<br />
I<br />
aoc<br />
(21)
ラグメント数が増える)につれて、計算すべきダイマーの数が理論値の 1/10、1/100 と急減<br />
するため、計算量を大幅に減らすことができる。<br />
5)電子相関理論<br />
FMO スキームで計算できる電子相関理論は、密度汎関数理論(DFT)、MP2、CC およ<br />
び MCSCF が開発されている。DFT は、HF 法の交換項(式(5)の括弧内第二項)を電子密<br />
度の関数である交換相関項に置き換えるだけなので、HF 法とまったく同様に、FMO 法が<br />
適用できる(FMO-DFT 法[19])。MP2 と CC は、HF エネルギーと電子相関エネルギー別々<br />
に計算されるので、HF レベルの FMO モノマーとダイマーについて電子相関エネルギーの<br />
計算を行い、HF レベルの場合と同様に、多体からの寄与を順次加えて計算すればよい。他<br />
の、local correlation theory(localized orbital を用いる)と異なり、FMO 法ではモノマー<br />
とダイマーのカノニカル軌道を用いて、通常の ab initio 計算と同じ計算を行えばよい。た<br />
とえば、FMO-MP2 法[20]では、FMO-HF のモノマーとダイマーの MO と軌道エネルギー<br />
を用いて、それぞれの MP2 電子相関エネルギー、<br />
E<br />
corr<br />
x<br />
1<br />
� �<br />
4<br />
occ unocc<br />
� � ~ x x x<br />
� �<br />
~ � �<br />
~ � �<br />
i,<br />
j p,<br />
q<br />
p<br />
( ij || pq)<br />
q<br />
i<br />
2<br />
~ �<br />
x<br />
j<br />
を計算し(モノマーは x=I、ダイマーはx=IJ)、これらを用いて、次式によって全系の<br />
電子相関エネルギーを求める(2 体展開近似の場合)。<br />
E<br />
corr<br />
�<br />
�<br />
I<br />
E<br />
corr<br />
I<br />
�<br />
corr corr corr<br />
� �EIJ � EI<br />
� E J �<br />
I �J<br />
全エネルギーE は、これに HF エネルギーE HF を加えて得られる。<br />
E �<br />
HF corr<br />
� E E<br />
(25)<br />
FMO スキームの電子相関エネルギー計算では、距離が離れたダイマーからの相関エネル<br />
ギーへの寄与を無視することができ、計算すべきダイマーの数が減らせるので、計算が非<br />
常に高速である。FMO-MCSCF 法は、上記とは異なり、解き方は FMO-HF 法に近い(興<br />
味ある読者は文献[21]を参照して欲しい)。<br />
6)多階層 FMO<br />
計算する対象やプロパティによっては、系全体をすべて同じ精度で計算する必要がなく、<br />
重要な部分のみ高精度で、残の部分を精度は落ちるが高速な計算法で、といったやり方で<br />
ほとんど精度を落とすことなく計算時間が節約できる場合がある。たとえば、蛋白質とリ<br />
ガンドの結合エネルギーを計算する場合、結合ポケットの残基とリガンドのみ電子相関を<br />
考慮した計算で、残りは HF 計算で、といった例や、同じ波動関数でも高精度部分は大き<br />
な基底関数で、残りは小さな基底関数で扱うなどである。このような、ひとつの系で部分<br />
ごとに異なった波動関数と基底関数を用いることができるアプローチの代表的なものに<br />
(23)<br />
(24)
ONIOM 法[22]がある。<br />
FMO 法でも、系を階層的に計算できる方法<br />
が開発されている(多階層 FMO;MFMO[23])。<br />
MFMO 法では、全フラグメントをいずれかの<br />
階層に帰属させる。各階層のモノマーは、同一<br />
階層のモノマーと自分より高いすべての階層の<br />
モノマーで self-consistent にする(最低階層に<br />
属するモノマー以外は、ひとつのモノマーは異<br />
なった計算レベルで複数回計算することにな<br />
る)。そして、同一階層内のダイマーと、自分と<br />
より高い階層のモノマーからなるダイマーをす<br />
べて計算する。すなわち、階層間のペア相互作<br />
用は低い方のレベルで計算する。その際、自分<br />
より低い階層のモノマーからの静電ポテンシャ<br />
ル中で計算する。<br />
MFMO 法の全エネルギー(FMO2 の場合)は<br />
次式となる、<br />
N<br />
�<br />
N<br />
LIJ<br />
LIJ<br />
LIJ<br />
��E<br />
IJ � EI<br />
� J �<br />
LI<br />
E � E �<br />
E<br />
(26)<br />
I<br />
I<br />
I � J<br />
ここで、LI はモノマーI が属する階層を示し、LIJ は LI と LJ のうちの低い方の階層を示す。<br />
MFMO 法の現バージョンでは計算レベルはすべて ab initio 法に限定されているが、最低<br />
レベルの計算法として古典力場(MM)を加えることも可能であり、そのような融合法の開<br />
発が計画されている。<br />
7)精度<br />
図 4 MFMO の概念図(3 階層の例)。<br />
全フラグメントをいづれかの階層にア<br />
サインする。各階層のモノマーは、同一<br />
階層のモノマーと自分より高いすべて<br />
の階層のモノマーで self-consistent に<br />
する。同一階層内のダイマーと、自分と<br />
より高い階層のモノマーからなるダイ<br />
マーをすべて計算する。その際、自分よ<br />
り低い階層のモノマーからの静電ポテ<br />
ンシャル中で計算する<br />
FMO 法の精度(ab initio 計算の再現性)は、切断する結合の性質とフラグメントのサイ<br />
ズでおおよそ決まる。sp 3 炭素のように、できるだけ電子の非局在化が少ない位置で結合を<br />
切断するのがよい。フラグメントサイズは、大きくとるほど高い精度(ab initio MO 計算<br />
の結果に近い)が得られる。一方、フラグメントサイズが大きくなるほど、計算時間がか<br />
かる。また、フラグメントサイズが同じなら、基底関数が大きいほど誤差(ab initio の結<br />
果との差)が大きいという傾向がある。また、誤差はフラグメントの数にほぼ比例して増<br />
加する。これらの一般的傾向を念頭において、構造最適化など時間がかかる計算を行う場<br />
合は、事前にフラグメントサイズを大きくした計算で誤差評価をしておくことを推奨する<br />
(私たちの経験では、フラグメントサイズを倍にすると、全エネルギーの誤差がおおよそ<br />
1/2 になる。このことから、ab initio 計算ができない巨大分子であっても、誤差のオーダー<br />
は知ることができる)。あるいは、同じフラグメントサイズで FMO3 計算を行って、その結
果との差を見ることでも同様な誤差評価ができる。さらに、FMO3 計算からは、3 体効果<br />
が大きいフラグメントの組を知ることができるので、これを見てフラグメント分割をやり<br />
直すことで、誤差を減らせる可能性もある。いづれにしても、必要な精度を確保できる最<br />
小のフラグメントサイズを見出せば、計算時間が節約できる。<br />
蛋白質の FMO 計算では、2アミノ酸残基を 1 フラグメントにとると、全エネルギーの誤<br />
差は数 kcal/mol 程度であることが経験的に分かっている(6-31G*基底関数による 100 残基<br />
程度の蛋白質の場合)。FMO2 法の誤差の主な起源は、3 フラグメント間でのカップルした<br />
電荷移動相互作用であることが示されている[15]。この観点からも、適切なフラグメントの<br />
とり方を判断できる。水分子クラスターやポリペプチドのα-helix 配座は、カップルした水<br />
素結合が存在するため、相対的に<br />
誤差が大きくなる。したがって、<br />
このような系のいろいろな配座異<br />
性体の相対エネルギーを計算しよ<br />
うとする場合は、慎重に誤差を評<br />
価しなければならない。<br />
参考のために、表1に FMO2,<br />
3-RHF 法による水分子クラスタ<br />
ーとα-helix、β-strand ポリアラ<br />
ニンの誤差を示す。FMO3(2 残基/<br />
フラグメント分割)の誤差は、最大、<br />
2.3 ミリハートリー(6-31G*基底<br />
関数)である。6-311G*基底関数<br />
の誤差は、6-31G*に比べておおよ<br />
そ 2-3 倍 大 き い 。 表 2 に 、<br />
FMO2,3-MP2 に電子相関エネル<br />
ギーの誤差を示す。FMO3 で 2 残<br />
基/フラグメントの場合の誤差は、<br />
6-31G*と 6-311G*基底関数で、そ<br />
れぞれ、最大 1.2、5.0 ミリハート<br />
リーである(それぞれ、電子相関<br />
エネルギーの 99.996%、99.60%)。<br />
詳細およびその他の系、その他の<br />
プロパティの誤差については、文<br />
献[24]を参照されたい。<br />
表 1 FMOn/m による HF 全エネルギーの誤差(ab<br />
initio との比較)。エネルギーの単位はミリハートリ<br />
ー。n 体展開 FMO、m 分子(またはアミノ酸残基)/<br />
フラグメント分割。
表 2 FMOn/m による MP2 電子相関エネルギーの誤差(ab initio MP2 との比較)。<br />
エネルギーの単位はミリハートリー。n 体展開 FMO、m 分子(またはアミノ酸残基)/<br />
フラグメント分割。<br />
FMO 法のエネルギー勾配はほぼ解析的に計算できる[25]。静電ポテンシャル近似、特に、<br />
離れたダイマーに対する静電相互作用近似(式(22))は、ほとんど精度を落とすことなく計<br />
算を高速化できるので、実用上不可欠な近似である。この近似のエネルギー勾配も開発さ<br />
れ、いくつかのポリペプチド系で構造最適化計算が行われて、FMO 法と ab initio 法の HF<br />
レベルの最適化構造が比較された[26]。N-、C-末端を MeCO と NHMe 基でそれぞれキャ<br />
ップしたアラニン 10 量体の extended、α-helix、β-turn 配座異性体で、結合距離、結合<br />
角、2 面角(φ,ψ,ω)の誤差は RMSD(Root-mean-square deviation)で、それぞれ 0.0032<br />
Å、0.51�、7. 8�以内である(表3)。2 面角の誤差が大きいが、全原子のデカルト座標の RMSD<br />
(表3の all、最大 0.325 Å)は十分小さく、全体の構造はほぼ同じであることが分かる(図<br />
5)。2 面角の変化に伴うエネルギー変化は非常に小さくポテンシャル面がフラットである<br />
ため、この構造に伴うエネルギーのずれは小さいので(表4)、この誤差は、実際の応用計<br />
算では問題にならないだろう(基底関数依存性の方が大きい)。実在の 20 アミノ酸残基か<br />
らなるポリペプチド(PDB:1L2Y)についても、デカルト座標の RMSD は 0.198 Å (重い原<br />
子のみ)で、FMO2 は ab initio の構造を良く再現している(図6)。
表 3 MeCO-(ala)10-NHMe の FMO と ab initio 最適化構造の RMSD。基底<br />
関数は 6-31G*。m-residue/fragment 分割。<br />
図 5 FMO(エレメントカラー)と ab initio<br />
(紫)構造の重ね合わせ。<br />
FMO2 と ab initio それぞれの最適化構造での全エネルギーを表4に示す。同一構造での両<br />
方法のエネルギー差に比べて、最適化構造どおしではその差がおおむね小さくなっている。<br />
これは、FMO2 のポテンシャル面が ab initio のそれとパラレルで、ほんの少しだけずれて<br />
いる(構造の差の分)ことを示しており、FMO の好ましい性質のひとつと考えられる。配<br />
座異性体間のエネルギー差についても、FMO2 の誤差は 3-21G 基底関数で 3.7 kcal/mol、<br />
6-31G*基底関数で 2.0 kcal/mol 以内の誤差である。FMO3(FMO2 構造での 1 点計算)で<br />
Asn<br />
Ser<br />
Asp<br />
Lys<br />
Gly<br />
Gly<br />
図 6 Trp-cage mini protein の最適化構造。<br />
エレメントカラー:FMO、紫:ab initio、<br />
両者とも RHF で基底関数は 3-21G。
は、それぞれ 1.5 kcal/mol、1.1 kcal/mol となり、より精度が向上する。私たちの経験では、<br />
FMO 法の誤差は構造に依存するので、配座異性体間の小さなエネルギー差を議論するとき<br />
は、FMO3 を用いることを推奨する。<br />
表 4 MeCO-(ala)10-NHMe の FMO2 と ab initio 最適化構造における全エネルギー(Hartree)の<br />
比較。FMO3 の全エネルギーは FMO2 最適化構造で計算。カッコ内は、extended 配座をゼロ<br />
とした相対エネルギー(kcal/mol)。<br />
8)溶媒モデル<br />
生体高分子は水溶液中で機能を発揮するため、溶媒効果を考慮することが本質的に重要<br />
である。溶液の扱いは、溶媒分子をあからさまに含めるモデルと溶媒を誘電体で近似する<br />
方法がある。前者は古典分子動力学(MD)シミュレーションで普通に用いられるモデルで<br />
ある。電子状態計算で、MD シミュレーションを行ってアンサンブル平均を取るには膨大な<br />
計算時間がかかるため、現在のところ前者のアプローチは困難であり、主に後者のモデル<br />
が用いられる。QM/MM 法では、溶媒分子をあからさまに考慮した MD シミュレーション<br />
が行われている。一方、誘電体モデルは、古典 MD シミュレーションにおいても、<br />
MM-PB/SA[27]のように、タンパク質とリガンドの相互作用エネルギーを MD シミュレー<br />
シ ョ ン か ら 求 め 、 溶 媒 効 果 に つ い て は 、<br />
Poisson-Boltzmann(PB)方程式を解いて静電<br />
溶媒和エネルギーを、非極性溶媒和エネルギ<br />
ーを solvent accessible surface area(SASA)<br />
model による経験式で評価する、という使い<br />
方もされている。誘電体モデルは、パラメー<br />
タ理論であり荒い近似であるが、長時間 MD<br />
を行って十分なアンサンブル平均をとるのが<br />
困難な系では、現実的な選択肢である。<br />
電 子 状 態 計 算 で は 、 溶 媒 モ デ ル と し て<br />
polarizable continuum model(PCM)[28]が標<br />
準的に用いられている。このモデルは、溶媒<br />
を連続誘電体として、そこに溶質分子を入れ<br />
図7 誘電体モデルによる溶質分子<br />
と溶媒の静電相互作用の模式図。溶<br />
質分子の電荷により、空孔表面上に<br />
誘起される電荷と、溶質分子の電子<br />
分布が self-consistent になるように<br />
繰り返し計算を行い、溶質分子と溶<br />
媒との溶媒和静電相互作用エネルギ<br />
ーを計算する。
る空孔を作り、空孔中に置いた溶質分子の静電場により空孔表面上に誘起される電荷を求<br />
め、その誘起電荷による溶質の電子状態への影響を含めて、再び、溶質分子の電子状態を<br />
解き、誘起電荷と溶質分子の電子状態が無撞着になるまで繰り返し計算を行って、溶質分<br />
子と溶媒の静電相互作用エネルギーを求める方法である(図7)。溶媒和エネルギーは、溶質<br />
分子の内部エネルギーEint、上記のようにして求めた溶媒と溶質分子の静電エネルギー ele<br />
G 、 sol<br />
溶質と溶媒分子の交換反発エネルギー rep<br />
G sol 、溶質と溶媒分子の分散相互作用エネルギー<br />
G 、および空孔を作るに必要な自由エネルギー(キャビテーションエネルギー) cav<br />
G の<br />
disp<br />
sol<br />
和として与えられる。<br />
G � Eint<br />
� G � G � G � G<br />
(27)<br />
sol<br />
ele<br />
sol<br />
rep<br />
sol<br />
disp<br />
sol<br />
cav<br />
sol<br />
これらの溶媒和自由エネルギー成分のうち、Eint と ele<br />
G 以外は、経験的な関数が作られて<br />
sol<br />
いる(詳細は文献[28]を参照のこと)。なお、これらの成分はもとより、Eint と ele<br />
G も、空孔<br />
sol<br />
を作る原子半径のとり方(通常、溶質分子の原子を中心とした球を描き、これらの重なり<br />
部分を除いたものを空孔とする)で数値が変わるので、原子半径は重要なパラメータであ<br />
る。これは、基本的な分子の水和自由エネルギーの実験値をできるだけよく再現するよう<br />
に決められている。<br />
溶媒和静電エネルギー ele<br />
G は、溶質分子と空孔表面に誘起された電荷との静電相互作用エ<br />
sol<br />
ネルギーである。空孔表面に誘起される電荷 q は、空孔表面を小さな領域(テセラ)に分<br />
割し、各テセラに誘起される電荷を求める。<br />
� �1<br />
�1<br />
q � � C V<br />
4��<br />
q は各テセラの電荷を要素とするベクトル、C はテセラの座標と面積に依存する構造行列、<br />
εは溶媒の誘電率、V は溶質分子による各テセラでの静電ポテンシャルを要素とするべクト<br />
ル、である。誘起電荷による溶質分子への影響は、この電荷による静電ポテンシャル(W)<br />
を加えた Fock 行列を作り、これを用いて Fock 方程式を解く。<br />
F<br />
W<br />
w<br />
��<br />
��<br />
i<br />
��<br />
� F<br />
� �<br />
�<br />
0<br />
��<br />
NTS<br />
�<br />
i�1<br />
�W<br />
i<br />
��<br />
q w<br />
i<br />
��<br />
1<br />
�<br />
r � R<br />
i<br />
�<br />
ここで、F 0 は真空中の分子の Fock 行列である。溶質分子の電荷がキャビティ表面に電荷を<br />
誘起し、その電荷により溶質の電子分布が変化するので、両者が self-consistent になるま<br />
で繰り返し計算をする。<br />
FMO スキームによる PCM(FMO/PCM)[29]では、溶質分子に依る空孔表面(tessera i)<br />
での静電場を、他のプロパティ同様、1 体、2 体、・・・とシリーズ展開する。<br />
sol<br />
(28)<br />
(29)
V<br />
V<br />
i<br />
x<br />
i<br />
N<br />
I<br />
� �Vi<br />
��<br />
I �1<br />
N<br />
I �J<br />
IJ I J<br />
�V �V<br />
�V<br />
�� �<br />
i<br />
x i Z<br />
� � w �� �<br />
� R �<br />
i<br />
i<br />
�<br />
� �Tr<br />
D (31)<br />
R<br />
� X � i<br />
Vi の計算を何体展開で行うかによって、いくつかの近似が可能である。FMO2 のレベルで<br />
は、Vi に 2 体展開を用いると整合性が取れるが、そのためには溶質分子の電子状態をダイ<br />
マー計算まで行わなければならないので、真空中での FMO 計算の 10 倍程度(10 回程度の<br />
繰り返し計算が必要)の計算時間がかかる(ちなみに、ab initio の PCM では、通常の HF<br />
計算の 1 から 2 割増し程度の計算時間ですむ)。いくつかの近似レベルでテストした結果、<br />
V の 1 体展開近似は非常に精度が落ちるが、2 体展開で繰り返し計算を 2 回で留める近似<br />
(PCM[1(2)]と呼ぶ)が、計算時間と精度を考えて実用的であることを見出した。この近似に<br />
よると、標準 ab initio 計算の結果に対して1kcal/mol 程度の誤差となり、計算時間は気相<br />
の 2 倍程度で収まる。FMO/PCM「1(2)」による、いくつかの蛋白質(PDB コードで示す)につ<br />
いての水和自由エネルギーの計算結果を表5に示す。1L2Y は電荷+1、304 原子、1IO5<br />
(lysozyme)は電荷+9、1961 原子、2CGA(Chymotrypsinogen)は、電荷+6、3578 原<br />
子の系である。FMO 計算が可能なサイズの分子であれば、FMO/PCM 計算は現実的に可能<br />
である。<br />
表 5 蛋白質の水和エネルギーEsolv とその成分。FMO2-RHF/PCM[1(2)]<br />
と 6-31(+)G*基底関数(COO-にのみ diffuse 軌道を付加)による計算。<br />
9)フラグメント間相互作用<br />
式(17)は、静電ポテンシャル近似のために導かれたが、これはフラグメント間相互作用を<br />
定義する式でもある。第1項と第2項は、形式的に、2 体の量であるので、これらをまとめ<br />
てペア相互作用エネルギー(pair interaction energy; PIE)と呼ぶ。<br />
(30)
IJ<br />
IJ IJ<br />
�E� � E�<br />
� E�<br />
�� Tr��D<br />
�<br />
� E �<br />
V<br />
~<br />
IJ<br />
I<br />
J<br />
この第1項は、フラグメント I と J の直接相互作用エネルギーを、第 2 項はモノマー間で電<br />
荷移動などにより変化した電子分布が環境静電ポテンシャルで安定化または不安定化され<br />
るエネルギーを表す。式(32)の第 2 項があからさまに示すように、PIE は単純なペア相互作<br />
用エネルギーではなく、多体相互作用を含んでいることに注意して欲しい。系の全エネル<br />
ギーが、モノマーとペアエネルギーの和として精度よく書けるのは、多体相互作用の大部<br />
分がこれらに繰り込まれているからである。極性分子の分子間相互では、分極相互作用の<br />
多体効果が最も重要であるが、FMO 法ではこれはモノマーのエネルギーに含まれている。<br />
共有結合しているフラグメント間の PIE には、物理的に無意味な BDA 原子の“原子内相<br />
互作用”が含まれる。したがって、PIE による解析は、非結合フラグメント間の相互作用<br />
のみ有用である。<br />
分子内のフラグメント間の非結合相互作用は分子間相互作用と似ているので、その理解<br />
には分子間相互作用の知識が役立つ。分子間相互作用については、相互作用の性質を知る<br />
ために、相互作用エネルギーを静電、分極、交換反発、電荷移動などの成分に分割して解<br />
析する方法(energy decomposition analysis; EDA)がある。これを拡張して、PIE を同様<br />
な相互作用成分に分割する方法(pair interaction energy decomposition;PIEDA[30])が開<br />
発された。PIE とともに、このような分子内の相互作用の解析は、蛋白質など巨大分子の<br />
構造と安定性の理解に役立つだろう。また、蛋白質とリガンドの相互作用についても、ア<br />
ミノ酸残基を単位としてリガンドとの相互作用を解析することで、分子認識様式の理解が<br />
容易になるであろう。以下で、分子内非結合相互作用の PIEDA 解析例を示す(蛋白質とリ<br />
ガンドの相互作用についての PIEDA は、まだ、適用例がないが、PIE 解析については第4<br />
節で紹介する)。<br />
Trp-cage mini protein は、20 アミノ酸残基から<br />
なる合成蛋白質である。このポリペプチドは非常に<br />
短いにもかかわらず、自発的にコンパクトな構造(図<br />
8)へと折りたたまれる[31]。これが起きるのは、<br />
Trp6 を核として多数の非極性残基が疎水性コアを<br />
形成し、安定化するためであると考えられている。<br />
このポリペプチドの FMO-MP2/6-31(+)G*((+)は<br />
COO-に diffuse 軌道を付加したことを示す)による<br />
PIE およびそのエネルギー成分(一部のみ)を表6<br />
に示す。表中の”Bond”は相互作用の性質(エネルギ<br />
ー成分から、定性的に分類したもの)、Δq I→J はフ<br />
ラグメント I から J への電荷移動量を示す。例えば、<br />
Leu7 と Ile4 の相互作用(7-4)は水素結合で、Leu7<br />
図 8 Trp-cage mini protein<br />
の構造(PDB:1L2Y)とフラ<br />
グメント番号(残基名+番<br />
号)。点線は水素結合。<br />
(32)
が電子受容体(プロトン供与体)、その PIE は-8.9 kcal/mol であり、静電、交換反発、電<br />
荷移動+MIX、電子相関エネルギー成分は、それぞれ、-10.0 、9.1、-3.4 と-4.6kcal/mol<br />
であることを示している。Trp6 の相互作用に注目すると、Tyr3 とは水素結合、Gly11、Pro12、<br />
Pro19 との相互作用は電子相関エネルギーの寄与が大きいことから、これらの非極性残基と<br />
は分散相互作用で安定化していることが分かる(Pro12 とは Trp の側鎖インドール環の NH<br />
と Pro の主鎖 CO との水素結合もある)。Gln5 と Lys8 は、主鎖間と側鎖間で計 2 本の水素結<br />
合があること、さらに、Lys の側鎖は正電荷を持つので強い水素結合を形成するために、非<br />
常に大きな PIE(-39.4 kcal/mol)になっている。Arg16 と Asn9 の間でも、Arg の側鎖の正<br />
電荷のせいで大きな PIE(大部分が静電相互作用)になっている。<br />
ここでの相互作用エネル<br />
ギーは、真空中の値である<br />
ため、静電エネルギーが非<br />
常に大きく出ていることに<br />
注意されたい。水溶液中で<br />
あれば、静電相互作用は遮<br />
蔽され小さくなる(約 1/80<br />
になる)ので、分散相互作<br />
用を含めてその他の非静電<br />
相互作用の重要性が増すは<br />
ずである。Trp6 を中心とし<br />
た疎水性コアの形成が構造<br />
形成の重要な要因であるこ<br />
とを証明するには、PIE、<br />
PIEDA 解析では不十分で、溶<br />
媒効果を考慮する必要があ<br />
ることは明らかであるが、<br />
その一助となるであろう。<br />
次に分子間相互作用の解析について説明する。分子間の場合、各分子を図9のように分<br />
割すると、FMO 法での分子間相互作用エネルギーは、<br />
�E<br />
AB<br />
int<br />
� E<br />
��<br />
��<br />
� ��<br />
��<br />
��<br />
AB<br />
� �E<br />
� E<br />
AB<br />
� E�<br />
I � �<br />
I�A<br />
I �J<br />
I , J�A<br />
A<br />
PLd<br />
A<br />
� �E<br />
� E<br />
B<br />
PLd<br />
B<br />
表 6 Trp-cage mini protein の分子内非結合相互作用の<br />
PIE とその成分(PIEDA 解析、一部のみ示す)。エネル<br />
ギーの単位は kcal/mol。構造は PDB:1L2Y(図 8)を参<br />
照のこと。<br />
~<br />
�E<br />
� �E<br />
a フラグメントペア。番号は図 8 の残基番号を参照。<br />
b 水素結合、 c 静電相互作用、 d 電子相関、 e フラグメント<br />
間距離(vdw 半径の和を単位)、 f I から J への電荷移動<br />
量(Mulliken 電荷)、 g 静電相互作用エネルギー、 h 交換<br />
反発、 i 電荷移動+MIX、 j 電子相関エネルギー、 kPIE。<br />
AB<br />
IJ<br />
A�B<br />
int<br />
�<br />
�<br />
� � E<br />
�<br />
�<br />
A<br />
� ��<br />
� ��<br />
) ��<br />
��<br />
� ��<br />
� ��<br />
AB<br />
� E�<br />
K � �<br />
K�B<br />
K �L<br />
K , L�B<br />
~<br />
�E<br />
AB<br />
KL<br />
� �<br />
� B �<br />
� � E ��<br />
� �<br />
� �<br />
�<br />
~<br />
�E<br />
I�A<br />
, K�B<br />
(33)<br />
AB<br />
IK
と書ける。ここで、�EPLd は分極相互<br />
作用の不安定化エネルギーを示す(相<br />
互作用によりそれぞれの分子の電子分<br />
布が変形(分極)したための不安定化<br />
(孤立状態に比べて)。分極相互作用の<br />
安定化エネルギーは<br />
AB ~<br />
� の静電相互<br />
E int<br />
作用エネルギーの一部として含まれて<br />
いる)。 AB<br />
E ~<br />
� は、分子間のフラグメン<br />
IK<br />
ト間相互作用エネルギーである。これ<br />
により、A と B 分子の分子間相互作用<br />
で、それぞれでどのフラグメント間の相互作用が重要であるかを知ることができる。分子<br />
間の相互作用解析の例は、後ほど、FK506 結合タンパク質とそのリガンドの系で示す。<br />
3.FMO 計算のプログラム<br />
公開されている FMO プログラムとしては、ABINIT-MP[32]と GAMESS[33] がある。<br />
後者は、アイオワ大学の Gordon 教授らによって開発された量子化学計算プログラムのパ<br />
ッケージであり、利用許諾を得て無料で入手できる。FMO 計算プログラムは Fedorov 博士<br />
らによって開発され、GAMESS の May 26, 2004 版から公開されている。<br />
GAMESS で使える各種 FMO 法を表7に示す。エネルギー勾配は、HF、MP2、DFT<br />
のみ可能である。基底関数は、GAMESS がサポートしているすべてが使える。FMO 計算<br />
に関しては、計算できる最大原子数に制限はない。構造最適化で GAMESS のエンジンを使<br />
う場合、GAMESS の最大原子数の制限(2,000 原子)を受ける。この場合、runtyp=optfmo<br />
を指定すると原子数は無制限になるが、今のところ、使える最適化アルゴリズムは 2,3 種し<br />
か用意されていないので、最適化の効率は良くないかも知れない。<br />
A<br />
B<br />
I I+1<br />
図 9 分子間相互作用系 AB で、それぞれの分子<br />
をフラグメント分割すると、分子間のフラグメン<br />
ト間相互作用が求まる。<br />
FMO 法の大きな特徴は、並列計算処理が効率よく行えるところにある。GAMESS には<br />
FMO 計算に有効な 2 段階並列化の仕組み(GDDI[34])が実装されている。遅いネットワ<br />
ーク(FastEthernet)で接続されたパソコン 128 台のクラスターでも、並列化効率は、1024<br />
個の水分子クラスターの RHF/STO-3G 計算で約 90%、約 2000 原子からなる蛋白質の同<br />
じレベルの計算で約 80%(1CPU で計算する場合に比べて 1/102 の計算時間)であった。<br />
FMO 計算の入力データ作成は、分子の分割の情報や共有結合切断した原子の基底関数<br />
の割り振りなどの指定が必要で、結構面倒である。そのために、GAMESS での FMO 計算<br />
の入力データを容易に作成できるように、入力データ作成支援プログラム FMOutil を公開<br />
している。これは、GAMESS と一緒に配布されている(gamess/tools/fmo/ディレクトリに<br />
ある)。または、開発者の URL http://staff.aist.go.jp/d.g.fedorovから無料でダウンロードで<br />
I-1<br />
K-1<br />
K K+1
きる(このホームページでは、FMO 法に関する多数の情報が公開されている)。これを用<br />
いると、蛋白質に関しては、PDB データを入力して、会話形式で答えるだけで、ほぼ自動<br />
的に GAMESS-FMO のための入力データを作成できるので、是非、試していただきたい。<br />
表 7 GAMESS で可能な各種 FMO 計算<br />
方法 概要<br />
FMO2,3-RHF 2- and 3-body expansion RHF method<br />
FMO2,3-DFT FMO-based density functional theory.<br />
FMO2,3-MP2 FMO-based 2nd order Møller-Plesset perturbation theory.<br />
FMO2-MCSCF FMO-based multi-configuration SCF method.<br />
FMO2,3-CC FMO-based coupled cluster theory.<br />
MFMO FMO-based multilayer method.<br />
FMO/PCM FMO combined with polarizable continuum model (PCM).<br />
PIEDA<br />
FMO-TDDFT<br />
4.蛋白質とリガンドの相互作用解析と結合自由エネルギー計算<br />
1)相互作用解析<br />
ここでは、FMO 法による蛋白質とリガンドの分子認識機構の解析例として、仲西らによ<br />
る研究を紹介する[35]。この研究では、免疫抑制剤である FK506 と、これを含めた 4 種の<br />
リガンドと FK506 結合蛋白質(FKBP)との複合体(図 10)で、蛋白質とリガンドとの相互<br />
作用が詳細に解析・比較された。このような解析により、ドラッグデザインのための有用<br />
な情報が得られることが期待される。<br />
Pair interaction energy decomposition analysis<br />
FMO-based time dependent density functional<br />
theory(TDDFT)<br />
複合体構造は、PDB の構造データをもとに、アミノ酸残基の標準解離状態を仮定して水<br />
素原子を付加し、それらの位置を最適化した。これらはモデリングソフト SYBYL[36]を用<br />
いて行った。結合構造を精密化するために、リガンドとこれから約 5Å 以内にあるアミノ酸<br />
残基を取り出し、末端を水素原子でキャップしたモデル複合体を作り、リガンドの全原子<br />
とリガンドと水素結合しているアミノ酸残基の水素原子の位置を FMO-RHF/3-21G 計算で<br />
部分構造最適化を行った。このようにして最適化した座標を用いて、全系のエネルギーを<br />
FMO-MP2/6-31G*レベルで計算した。FMO 計算では、アミノ酸残基とリガンドのいくつ<br />
かの部分の相互作用エネルギーを求めるために、蛋白質は 1 アミノ酸残基単位で分割し、<br />
リガンドは図10に示すフラグメントに分割した。
図 10 FKBP と FK506 の複合体の構造(PDB:1FKF)と計算に用いた 4 種のリガンド<br />
の構造式(複合体の PDB コードで呼ぶ)。図中の点線はフラグメント分割位を示す。<br />
アミノ酸残基とリガンドの相互作用エネルギーを図 11a に、結合モードを図 11b に示<br />
す。フラグメント分割は C�位で行ったため、i 番目のアミノ酸残基の主鎖 C=O は i+1 番目<br />
のフラグメントにアサインされていることに注意して欲しい。本当のアミノ酸残基と区別<br />
するために、ここでは、残基番号の前に#記号をつけてある。4 つのリガンドは1FKB、1<br />
FKF、1FKG、1FKI の順に結合自由エネルギーが小さいことが知られている(表9)。<br />
PIE の和は、それぞれ、-159.2、-139.6、-97.6、-93.3 kcal/mol(負符号は相互作用が安定<br />
化であることを示す)であり、結合自由エネルギーとよい相関がある。図 11a から、Tyr#26、<br />
Val#55、Tyr#82 が 4 つのリガンドで共通して大きな相互作用エネルギーを持ち、結合に重<br />
要な役割を担っていることが一目瞭然である。このことは構造(図 11b)から推定できる<br />
ことであるが、相互作用エネルギーを知ることにより定量的な評価が可能になる。さらに、<br />
PIE の HF と電子相関(分散力)エネルギーの割合から、Val#55 と Tyr#82 は水素結合で 4<br />
つのリガンドでほぼ同じであるが、Tyr#26 の相互作用は結合が強いリガンド(1FKB と1<br />
FKF)では弱い分散力であるのに対して、結合が弱いリガンド(1FKG と1FKI)では相<br />
対的により強い水素結合が形成されることを示している(後述)。一方、強いリガンドは、<br />
弱いリガンドには見られない Asp#37 との強い水素結合が見られる。もっとも強い1FKB<br />
では、これに加えて、Glu#54 の安定化相互作用が大きい。構造的にも、1FKB のみがこ<br />
の残基と相互作用していることが理解できる。<br />
1FKB<br />
1FKF<br />
1FKG 1FKI
pair interaction energy (kcal/mol)<br />
さらに、必要に応じて、リガンドをフラグメント分割することにより、各部分ごとの重<br />
要性を見ることができる。その例を、表8に示す。リガンドのフラグメント#1(Lig#1)は、<br />
結合ポケットの底に結合し、多数のアミノ酸残基に囲まれている(図 12)。構造から、これ<br />
らの残基は結合ポケットの“壁”を作っていることが分かる。一方、PIE は、これらの残<br />
基は主に分散力でリガンドを安定化していることを示している。すなわち、これらの残基<br />
はリガンドに対して立体的な制約を加えると同時に、相補的な構造を持つリガンドに対し<br />
て、大きな安定化をもたらしている。<br />
以上のように、アミノ酸残基単位でリガンドとの相互作用エネルギーを解析して得られ<br />
る詳細な知見は、リガンドをより強い親和力を持つように最適化する際に有用なヒントと<br />
なることが期待される。<br />
a) b)<br />
residue number<br />
図 11 FKBP とリガンドの PIE (a)。黒棒は HF、白棒は電子相関エネルギーを示す。<br />
横軸はアミノ酸残基の番号。(b)はリガンドの結合モードの模式図。
表 8 FKBP と FK506 リガンドフラグメント<br />
のペア相互作用エネルギー(kcal/mol)。一部<br />
のみ示す。<br />
2)結合自由エネルギーと溶媒効果<br />
蛋白質とリガンドの結合自由エネルギーに対する溶媒和効果は、溶媒中での解離自由エ<br />
ネルギーを直接求めるのが困難であるため、図13に示す熱力学サイクルで評価されるこ<br />
とが多い。これによると結合自由エネルギーは次式で計算できる。<br />
C L P<br />
�G � G � G �� T�S<br />
gas<br />
� G � �G<br />
�<br />
(34)<br />
b<br />
b<br />
sol<br />
sol<br />
sol<br />
第一項は気相の蛋白質とリガンドの結合自由エネルギー、第二項は複合体形成に伴う(部分)<br />
脱溶媒和エネルギーで、第三項は配置エントロピーの寄与である。第三項は、複合体、蛋<br />
白質やリガンドが複数のコンフォメーションをとることからくるエントロピーの寄与で、<br />
ここではこれらをゼロとした。<br />
気相の結合自由エネルギー<br />
gas<br />
� G は、次式で評価した。<br />
gas<br />
b<br />
b<br />
vib<br />
b<br />
� G � �E<br />
� �G<br />
(35)<br />
� Eb<br />
は気相の結合エネルギーで、次のように計算した。<br />
� E b<br />
C P<br />
� E � E<br />
L<br />
� E � �Eint<br />
L<br />
� �Edef<br />
(36)<br />
� Eint C P L(C)<br />
� E � E � E<br />
(37)<br />
L L(C) L<br />
� Edef � E � E<br />
(38)<br />
E C は複合体の全エネルギー、E P は孤立した蛋白質の全エネルギーである。E L(C)は複合体中<br />
の構造でのリガンドの全エネルギーで、E L は孤立状態の構造でのリガンドの全エネルギー<br />
である。両者の差(式(38))は、リガンドの構造変形に伴う不安定化エネルギー(deformation<br />
energy)である。複合体の形成により蛋白質の構造も変化するが、これに伴うエネルギー<br />
変化を評価することが難しいため、ここでは一連の複合体でこのエネルギーは一定である<br />
と仮定した(すなわち、蛋白質の deformation energy は考慮しない)。複合体形成に伴う<br />
自由エネルギー変化は、調和振動子近似 � G で評価した。<br />
vib<br />
� G<br />
C<br />
� G<br />
P<br />
� G<br />
L<br />
� G<br />
(39)<br />
vib<br />
vib<br />
vib<br />
vib<br />
Trp59<br />
Lig#1<br />
Phe46<br />
Tyr82<br />
Tyr26<br />
Phe99<br />
Phe36<br />
図 12 リガンドのフラグメン<br />
ト#1(Lig#1、太いスティック)<br />
と周辺のアミノ酸残基。点線は<br />
水素結合を示す。
振動自由エネルギー G は、複合体、蛋白質とリガンドすべて cff91 力場(リガンドの原<br />
vib<br />
子電荷は FMO-RHF/6-31G*の Mulliken 電荷)で最適化した構造で振動解析を行い、298 K<br />
の値を求めた(振動解析には DISCOVER [39]を使用した)。<br />
図 13 溶媒中の蛋白質とリガンドの結合自由エネルギー sol<br />
� G の計算に用た熱力学サイ<br />
溶媒和自由エネルギーは、Poisson-Boltzmann/surface area (PB/SA)モデル[37]で計算し<br />
た。PB/SA の溶媒和自由エネルギーは、静電項 ele<br />
sol<br />
えられる。<br />
sol<br />
ele<br />
sol<br />
nonpolar<br />
sol<br />
G と非極性項 nonpolar<br />
G の和として次式で与<br />
G � G � G<br />
(40)<br />
ele<br />
G は溶質分子と溶媒の静電エネルギーで、溶質分子の電荷により誘電体溶媒に誘起される<br />
sol<br />
電荷分布を Poisson-Boltzmann 方程式で求めて、溶質の電荷との静電相互作用を計算する<br />
(理論の詳細は文献[38]を参照のこと)。 ele<br />
G は、蛋白質とリガンドのすべての原子の部分<br />
sol<br />
電荷として、FMO-RHF/6-31G*の Mulliken 電荷を用い、DelPhi プログラム[38]で計算した。<br />
その際、溶質の誘電率は 1、溶媒(水)の誘電率は 80 とした。<br />
G は、溶質分子と溶媒の分散力や空孔エネルギーなど ele<br />
G 以外のすべてを含み、溶<br />
nonpolar<br />
sol<br />
媒接触表面積(solvent accessible surface area;SA)の1次関数として与えられる[37]。係<br />
数は、多数の分子の水和自由エネルギーの実験値をできるだけよく再現するように決めら<br />
れている。本計算では、InsightII プログラム[39]の cff91 パラメータセット(次式)を用<br />
いた。<br />
gas-phase<br />
solution<br />
クル。C:複合体、P:蛋白質、L:リガンド。 C<br />
sol<br />
エネルギー。<br />
nonpolar<br />
G � 0.<br />
00682 � SA � 0.80<br />
(41)<br />
sol<br />
complex protein ligand<br />
gas<br />
�Gb<br />
C P + L<br />
C<br />
Gsol<br />
�Gb<br />
P<br />
Gsol<br />
C P L<br />
ここで、エネルギーの単位は kcal/mol、SA の単位は Å 2 である。<br />
b<br />
G 、 P<br />
G 、 L<br />
G はそれぞれの溶媒和自由<br />
sol<br />
sol<br />
sol<br />
+<br />
sol<br />
L<br />
Gsol
上述の計算法で求めた結合自由エネルギーを表9に示す。計算値は実験値に比べて最大<br />
7.2kcal/mol の過大評価となり、残念ながら、リガンドの結合親和力の大きさの順序の再現<br />
にも失敗した。しかし、気相での大きな結合エネルギー(-70 から-104 kcal/mol)が、溶媒<br />
和ペナルティ�Gsol を考慮することにより、実験値と同じオーダー(-10 数 kcal/mol)にな<br />
った。これらの蛋白質とリガンドの結合では、電子相関の寄与が非常に大きく(たとえば、<br />
1FKG では-103.9 kcal/mol のうち約 80%(82.0 kcal/mol)が分散エネルギーである)、こ<br />
れを考慮することなしに、溶媒中の妥当な結合エネルギーを得ることができないことは明<br />
らかである。すなわち、QM で蛋白質とリガンドの結合エネルギーを計算する際には、ここ<br />
で用いた MP2レベルの計算が最低限必要であると言える。結合自由エネルギーの QM 計<br />
算法としては、溶媒モデルや溶質分子の自由エネルギーの評価法を始めとして、多々、改<br />
良すべき点がある。溶媒モデルに関しては、FMO 法と組み合わせて使える PCM が開発さ<br />
れており、これを用いるこ<br />
とで信頼性が向上すること<br />
が期待されるが、蛋白質と<br />
リガンドの結合エネルギー<br />
計算に適用するには、キャ<br />
ビティの半径の取り方など<br />
検討すべき問題が残されて<br />
いる。これを含めて、今後、<br />
克服すべき多くの困難な課<br />
題がある。<br />
結合自由エネルギーを定量的に計算予測することは、まだまだ困難な状況にある。した<br />
がって、計算で得られる何らかの量が、結合自由エネルギーとよい相関を持つことが分か<br />
れば、QSAR 的に予測ができるので、ドラッグデザインに有用であろう。そのような量と<br />
して、蛋白質とリガンドの間の電荷移動量(おおよそ水素結合のエネルギーを反映する)[40]<br />
や気相の結合エネルギー、などが考えられる。また、QM の量ではないが、蛋白質とリガン<br />
ドの接触表面積などもある。<br />
5.まとめ<br />
表 9 FMO の気相結合エネルギーと PB/SA の溶媒和自由<br />
エネルギーから求めた FKBP とリガンドの結合自由エネル<br />
ギー(kcal/mol)。<br />
生体高分子の構造と機能の計算科学的研究の新たなツールとして、量子化学計算が使え<br />
るようになってきた。現在、量子・古典融合法(QM/MM)という形で、系の一部のみに量<br />
子化学計算を用いるシミュレーション手法が急速に普及しつつある。QM 領域が、蛋白質の<br />
リガンド結合領域のアミノ酸残基とリガンドを含めることが出来る程度に拡大されれば、
蛋白質とリガンドの相互作用については、計算結果のクオリティは実質的に QM レベルに<br />
なるであろう。そのためには、更に高速な QM 計算アルゴリズムの開発が待たれる。<br />
本稿では、蛋白質全系を QM クオリティで計算できる方法である FMO 法について解説<br />
し、ドラッグデザインに有用と思われる解析の例を示した。このような FMO 法の応用研究<br />
は徐々に増えており、これらについては最近の総説[6]でカバーされているので、興味<br />
ある読者は参考にしてほしい。今後の展開として、FMO 法と MM の融合法を開発し、蛋<br />
白質の MD シミュレーションを可能とすることが、最も優先度が高いと考えている。<br />
インシリコドラッグデザインで大きな課題の一つである蛋白質とリガンドの結合自由エ<br />
ネルギーを高精度で予測することについては、当然のことながら、QM シミュレーションが<br />
可能になるだけでは解決できない。自由エネルギーを高精度で求めることができる統計力<br />
学理論が不可欠である。昨年に開始された文部科学省の次世代スーパーコンピュータ開発<br />
プロジェクトでは、ペタフロップス級の性能を持つ計算機の開発が進められている。この<br />
ような高性能計算機が利用可能になる数年先には、計算科学の幅広い分野で革新が起こる<br />
可能性が高い。生体高分子のシミュレーションも例外ではないだろう。インシリコ創薬研<br />
究に携わる若い研究者・学生の皆さん、またとない絶好のチャンスなので、シミュレーシ<br />
ョン手法の革新を先導していただきたい。<br />
謝辞<br />
FMO 法は多数の研究者の協力の下、開発が進められてきた。方法論とプログラムの開発<br />
では、国立医薬品食品衛生研究所の中野達也博士、産業技術総合研究所・計算科学部門の<br />
Dmitri G. Fedorov 博士に負うところが大きい。ドラッグデザインへの応用は、京都大学・<br />
薬学研究科の仲西功准教授の下で進められている。FMO 法の開発と応用にご協力いただい<br />
たすべての方々に感謝します。<br />
本概要は、「構造活性フォーラム 2007」(2007 年 6 月 29 日、京都)の要旨集の原稿を一<br />
部改変したものであることを付記しておく。
参考文献<br />
1. J. Gao, D. G. Truhlar, Annu. Rev. Phys. Chem.,53 (2002) 467.<br />
2. R. A. Friesner, Y. Guallar, Annu. Rev. Phys. Chem. 56 (205) 389.<br />
3. M. B. Peters, K. Raha, K. M. Merz Jr, Current Opinion in Drug Discovery &<br />
Development, 9 (2006) 370.<br />
4. A. Cavalli, P. Carloni, M. Recanatini, Chem. Rev. 106 (2006) 3497.<br />
5. D. G. Fedorov, K. Kitaura, in "Modern methods for theoretical physical chemistry of<br />
biopolymers", E. B. Starikov, J. P. Lewis, S. Tanaka, Eds., pp 3-38, Elsevier,<br />
Amsterdam, 2006.<br />
6. D. G. Fedorov, K.Kitaua, J. Phys. Chem. A, in press.<br />
7. W. Yang, Phys. Rev. Lett., 66 (1991) 1438.<br />
8. T. Nakano, Y. Mochizuki, K. Fukuzawa, S. Amari, S. Tanaka, in "Modern methods<br />
for theoretical physical chemistry of biopolymers", E. B. Starikov, J. P. Lewis, S.<br />
Tanaka, Eds., pp 39-52, Elsevier, Amsterdam, 2006.<br />
9. T. Ikegami, T. Ishida, D. G. Fedorov, K. Kitaura, Y. Inadomi, H. Umeda, M.<br />
Yokokawa, S. Sekiguchi, Proc. of Supercomputing 2005, IEEE Computer Society,<br />
2005. http://sc05.supercomputing.org/schedule/pdf/pap138.pdf<br />
10. G.E.Scuseria, J.Phys.Chem.A, 103 (1999) 4782.<br />
11. S.Goedecker, Rev. Mod. Phys.,78 (1999) 997.<br />
12. P. Pulay, Chem. Phys. Lett.,100 (1983) 151.<br />
13. M. Schutz, G. Hetzer, H. Stone, H. –J. Werner, J. Chem. Phys., 111 (1999) 5691.<br />
14. K. Kitaura, E. Ikeo, T. Asada, T. Nakano, M. Uebayasi, Chem. Phys. Lett. 313<br />
(1999) 701.<br />
15. D. G. Fedorov, K. Kitaura, J. Chem. Phys. 120 (2004) 6832.<br />
16. K.Kitaura,T.Sawai,T.Asada,T.Nakano and M.Uebayasi, Chem.Phys.Lett.,312<br />
(1999) ,319.<br />
17. A. E. Reed, R. B. Weinstock, F. Weinhold, J. Chem. Phys., 83 (1985) 735.<br />
18. T. Nakano, T. Kaminuma, T. Sato, K. Fukuzawa, Y. Akiyama, M. Uebayasi, K.<br />
Kitaura, Chem. Phys. Lett. 351 (2002) 475.<br />
19. D. G. Fedorov, K. Kitaura, Chem. Phys. Lett. 389 (2004) 129.<br />
20. D. G. Fedorov, K. Kitaura, J. Chem. Phys. 121 (2004) 2483.<br />
21. D. G. Fedorov, K. Kitaura, J. Chem. Phys. 122 (2005) 054108.<br />
22. M. Svensson, S. Humbel, R. Froese, T. Matsubara, S. Sieber, K. Morokuma, J. Phys.<br />
Chem., 100 (1996) 19357.<br />
23. D. G. Fedorov, T. Ishida, K. Kitaura, J. Phys. Chem. A 109 (2005) 2638.<br />
24. D. G. Fedorov, K. Ishimura, T. Ishida, K. Kitaura, P. Pulay, S. Nagase, J. Comp.
Chem., 28 (2007) 1476.<br />
25. K. Kitaura, S.-I. Sugiki, T. Nakano, Y. Komeiji, M. Uebayasi, Chem. Phys. Lett. 336<br />
(2001) 163.<br />
26. D. G. Fedorov, T. Ishida, M. Uebayasi, K. Kitaura, J. Phys. Chem. A, 111 (2007)<br />
2722.<br />
27. W. Wang, P. A. Kollman, Pro. Natl. Acad. Sci. USA, 98 (2001) 14937.<br />
28. J. Tomasi, B. Mennucci, R. Cammi, Chem. Rev., 105 (2005) 2999.<br />
29. D.G. Fedorov, K.Kitaura, H. Li, J.H. Jensen, M.S. Gordon, J. Comp. Chem. 27<br />
(2006) 976.<br />
30. D. G. Fedorov, K. Kitaura, J. Comp. Chem. 28 (2007) 222.<br />
31. J. W. Neidigh R. M. Fesinmeyer, N. H. Anderson, Nature Struct Biol , 9 (2002)425.<br />
32. ABINIT-MP, http://www.rss21.iis.u-tokyo.ac.jp/result/download/<br />
33. GAMESS, http://www.msg.ameslab.gov/GAMESS/GAMESS.html<br />
34. D. G. Fedorov, R. M. Olson, K. Kitaura, M. S. Gordon, S. Koseki, J. Comput. Chem.<br />
25 (2004) 872.<br />
35. I. Nakanishi, D. G. Fedorov, K. Kitaura, Proteins-Struct. Funct. Bioinf., 68 (2007)<br />
145.<br />
36. SYBYL, ver 6.9.1, Tripos Inc., 2003.<br />
37. D. Sitkoff, K. A. Sharp, B. Honig, J. Phys. Chem., 98 (1994) 1978.<br />
38. W. Rocchia, S. Sridhara, A. Nicholls, E. Alexov, A. Chiabrera, H. Honig, J. Comp.<br />
Chem., 23 (2002) 128.<br />
39. Discover and InsightII; Accelrys Software Inc.: San Diego, CA.<br />
40. K. Fukuzawa, K. Kitaura, M. Uebayasi, K. Nakata, T. Kaminuma, T. Nakano, J.<br />
Comp. Chem. 26 (2005) 1.