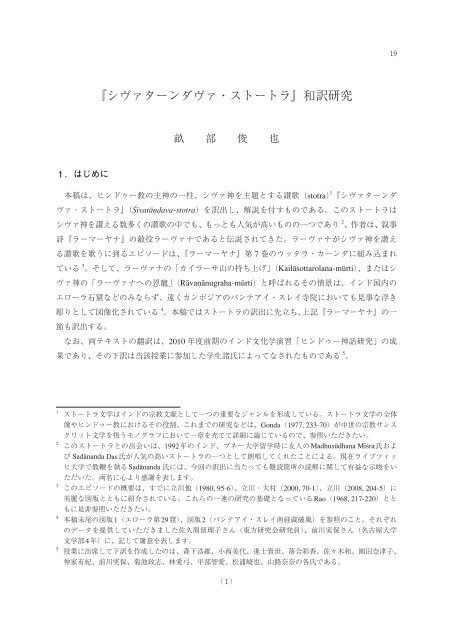Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
19<br />
<br />
<br />
1.はじめに<br />
stotra 1 <br />
Śivatāṇḍava-stotra<br />
2 <br />
<br />
7 <br />
3 Kailāsottarolana-mūrti<br />
Rāvaṇānugraha-mūrti<br />
<br />
4 <br />
<br />
2010 <br />
5 <br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
<br />
Gonda1977, 233-70<br />
<br />
1992Madhusūdhana Miśra<br />
Sadānanda Das<br />
Sadānanda <br />
<br />
1980, 95-62000, 70-12008, 204-5<br />
Rao1968, 217-220<br />
<br />
1292<br />
<br />
4<br />
<br />
<br />
( 1 )
20 <br />
2.『ラーマーヤナ』 第 7 巻 ウッタラ・カーンダ 第 16サルガについて<br />
7 <br />
1 <br />
6 3 1 <br />
Rāvaṇa<br />
16 bhakta<br />
<br />
<br />
Paṇśīkar 1940, 995-7 7 <br />
<br />
3.『ラーマーヤナ』7.16 訳 と 解 説<br />
§1 停 止 するプシュパカ<br />
1. ラーマよ、その 羅 刹 族 の 王 (ダシャグリーヴァ=ラーヴァナ)は、 兄 ダナダ(クベーラ= 毘 沙 門<br />
天 )を 制 圧 し、マハーセーナ(カールティケーヤ=スカンダ)の 生 誕 地 である、かの 大 いなる 蘆<br />
原 (śaravaṇa)に 赴 いた。<br />
2. さて、ダシャグリーヴァは、まるで 第 二 の 太 陽 であるかのように 光 線 の 網 に 覆 われ 金 色 に 輝 く 大<br />
いなる 蘆 原 を 見 た。<br />
3. 彼 (ダシャグリーヴァ)が 美 しい 森 の 中 程 の、ある 山 に 登 ると、そのときラーマよ、[ 彼 がダナダ<br />
から 奪 った 輿 ]プシュパカがそこで 止 まったのを 見 るのであった。<br />
4. 「この[プシュパカ]は[ 持 ち 主 の] 意 のままに 進 むのではないのか。いったいどうして 止 まってし<br />
まって 動 かぬのか」[と]、かの 眷 属 たちによって 囲 まれた 羅 刹 の 王 (ダシャグリーヴァ)は 考 えた。<br />
5. 「なにゆえに、わしの 意 のままにこのプシュパカは 動 かぬのか。これは 山 の 上 にいる 何 者 かの 仕 業<br />
であろう」[と]。<br />
6. するとそのとき、ラーマよ、マーリーチャという 知 恵 すぐれたる[ 家 臣 ]が 言 った。「 王 よ、プ<br />
シュパカが 動 かない、というこのことに 理 由 がないわけはありません。<br />
6<br />
7<br />
1980, 258-9.<br />
RāmāyaṇaśiromaṇiBhūṣana Mukhopadhyaya1990, 2785-9<br />
<br />
Oriental InstituteShah 1975, 101-7<br />
1980, 232<br />
<br />
<br />
<br />
( 2 )
21<br />
7. さては、このプシュパカはダナダ 以 外 の 者 の 乗 り 物 とはならないのでしょう。だから、 財 宝 の 主<br />
(ダナダ)なしでは、 動 きを 止 めた[のでありましょう]。」<br />
<br />
8 7 9 <br />
Viśravas<br />
16 <br />
<br />
<br />
<br />
2 <br />
Vaiśravana<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
6 <br />
<br />
§2 ナンディンの 警 告<br />
8. 以 上 の 彼 の 発 言 の 間 に、 恐 ろしげで、 暗 黄 色 で、 矮 小 にして、 異 形 、 禿 頭 であり、 腕 短 く、 剛 力<br />
であるナンディンが[ 現 れた]。<br />
9. そして、バヴァ(シヴァ)の 家 来 であるナンディーシュヴァラ(ナンディン)は、 傍 らまでやっ<br />
て 来 て、 恐 れることなく 羅 刹 族 の 王 (ダシャグリーヴァ)にこの 言 葉 を 語 った。<br />
10. 「 立 ち 去 れ、ダシャグリーヴァよ。 山 の 上 でシャンカラ(シヴァ)がお 戯 れである。 鳥 ・ 蛇 ・ 夜 叉 ・<br />
神 ・ガンダルヴァ・ 羅 刹 たちにとって、<br />
11. [すなわち]まさに 一 切 の 生 類 にとって、 山 は 立 ち 入 れないものとなっている」、というナンディ<br />
ンの 言 葉 を 聞 いて、[ダシャグリーヴァの] 耳 飾 りは 怒 りによって 震 えた。<br />
12. [ナンディンからこの 警 告 を 受 けた]けれども、 怒 りによって 目 を 赤 くした 彼 (ダシャグリーヴァ)<br />
はプシュパカから 降 り、「そのシャンカラとはいったい 何 奴 だ」と 言 って、 山 のふもとに 近 づいた。<br />
13. 彼 はそこに、 第 二 のシャンカラであるかのように 輝 く[ 三 叉 ] 戟 を 支 えて、[シヴァ] 神 から 遠 く<br />
ないところに 立 つナンディンを 見 た。<br />
8<br />
Shastri1959<br />
( 3 )
22 <br />
14. その 羅 刹 族 の 者 (ダシャグリーヴァ)は 猿 の 顔 をした 彼 を 見 て 侮 り、 水 を 保 つ 雲 が[ 雷 を 放 つ]<br />
ように、 高 笑 いを 放 った。<br />
<br />
9 <br />
<br />
29 <br />
10 <br />
§3 ラーヴァナが 猿 族 に 滅 ぼされることになる 因 縁<br />
15. シャンカラ(シヴァ)の 別 体 であり、そこ(カイラーサ 山 の 麓 )の 番 人 である 尊 者 ナンディンは、<br />
彼 に 腹 を 立 て、 近 づいてきた 十 面 の 者 (ダシャーナナ=ダシャグリーヴァ)にそこで 言 った。<br />
16. 「ダシャーナナよ、[お 前 は] 猿 の 姿 をした 私 を 侮 り、 落 雷 にも 似 た 嘲 り 笑 いを 放 ったから、<br />
17. それゆえに、 私 の 勇 気 を 備 え、 私 の 姿 と、 私 同 様 の 熱 情 を 持 つ 猿 たちが、 実 にお 前 の 一 党 の 殺 害<br />
のために 生 まれてくるであろう。<br />
18. 残 酷 な 者 (ダシャグリーヴァ)よ、 爪 や 牙 を 武 器 とし、 心 のようにすばやく 動 き 11 、 戦 いに 酔 いし<br />
れ、 力 勝 り、 山 々のように 広 がる、<br />
19. 彼 ら( 猿 たち)は、お 前 や、 家 来 および 息 子 の 持 つ、 様 々な 強 さや 自 尊 心 や 崇 高 さを、まとめて<br />
取 り 去 るであろう。<br />
20. おお、 夜 動 く 者 (ダシャグリーヴァ)よ、 今 私 はお 前 を 殺 すことができるけれども、[お 前 は 今 ]<br />
殺 されるべきではないのだ。というのは、 自 らの 諸 行 為 (カルマ)によってお 前 はまさに 既 に 殺<br />
されているのだから。」<br />
21. という 言 葉 を 発 したその 偉 大 な 神 (ナンディン)の 上 に、 諸 々の 神 の 太 鼓 が 鳴 り、そして 花 の 雨<br />
が 空 から 降 り 注 いだ。<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
9<br />
Rao1968, 455-602008, 170<br />
34<br />
<br />
<br />
10<br />
2000, 70.śāripaṭṭa<br />
2002, 72-7<br />
11<br />
<br />
<br />
(4)
23<br />
<br />
§4 カイラーサ 山 に 押 し 込 められるラーヴァナ<br />
22. そのとき、 大 きな 力 を 持 ったかのダシャーナナは、ナンディンの 言 葉 を 気 にとめずに、 山 に 近 づ<br />
き、[ 次 の] 言 葉 を 語 った。<br />
23. 「 私 が 進 んでいるのに、プシュパカの 進 行 が 途 切 れたのはどういうわけだ。お 前 のこの 山 を 根 こそ<br />
ぎにしてやるぞ、 牛 飼 い(シヴァ)よ。<br />
24. 何 の 権 限 があって、バヴァ(シヴァ)は 王 侯 のようにずっと 戯 れているのか。 知 らるべき 恐 怖 の<br />
原 因 が 近 づいているのに、 奴 は 知 らないのだ。」<br />
25. こう 言 った 後 に、ラーマよ、[ダシャグリーヴァは] 山 に 多 くの 腕 を 伸 ばし、それを 素 早 く 持 ち 上<br />
げたのであった。その 山 は 震 動 した。<br />
26. まさに 山 の 震 動 により、 神 (シヴァ)の 眷 属 たちは 震 動 した。パールヴァティーもまた 揺 れ、そ<br />
のとき、 偉 大 な 神 (シヴァ)にしがみついた。<br />
27. すると、ラーマよ、 神 々の 中 で 最 高 位 にある 偉 大 な 神 、ハラ(シヴァ)は、 足 の 親 指 でその 山 を<br />
戯 れに 押 したのであった。<br />
28. すると、 彼 (ダシャグリーヴァ)の、 山 の 柱 に 比 すべき 多 くの 腕 は 押 し 潰 された。そこでその 羅<br />
刹 の 家 来 たちは 驚 愕 した。<br />
29. 怒 りゆえに、また、 諸 々の 腕 の 痛 みゆえに、その 羅 刹 (ダシャグリーヴァ)により、それによっ<br />
て 三 界 が 震 えるほどの 叫 び 声 (virāva)が 突 如 放 たれた。<br />
30. 彼 の 家 臣 たちは、ユガ 末 ( 世 界 の 終 わり)における 雷 撃 だと 思 った。そのとき、インドラを 先 頭<br />
とする 神 々[でさえ]、 道 々でよろめいた。<br />
31. 海 々もたぎり、また、 山 々も 震 えた。[ヒマーラヤに 住 むという]ヴィドヤーダラ( 持 明 族 )や<br />
シッダ( 成 就 者 )たちが、「これはどうしたことか」と 言 うほどに。<br />
<br />
29 1<br />
<br />
12 <br />
12<br />
85-95<br />
Kala1988, 36-42; Fig. 32,33<br />
<br />
Berkson et. al1983, 34; Pl. 70<br />
<br />
<br />
2002, 71-104<br />
(5)
24 <br />
2 13 <br />
<br />
§5 「ラーヴァナ」という 名 の 由 来<br />
32. 「 偉 大 な 神 、 青 い 頸 を 持 つウマー(パールヴァティー)の 夫 (シヴァ)を 鎮 めて 下 さい。ダシャー<br />
ナナ 様 、 彼 を 措 いては、 他 の 避 難 所 (śaraṇa)をこの[ 世 界 ]に 私 たちが 見 ることはありません。<br />
33. 讃 辞 によって 敬 意 を 示 す 者 となって、まさに 彼 という 避 難 所 に 赴 いて 下 さい。 憐 れみ 深 いシャン<br />
カラ(シヴァ)は 鎮 まり、あなたのために 恩 寵 を 配 するでありましょう。」<br />
34. そのときこのように 家 臣 たちによって 言 われて、かのダシャーナナは、 雄 牛 を 旗 印 とする 者 (シ<br />
ヴァ)を 様 々な 種 類 の 詠 唱 や 讃 歌 によって 礼 拝 し、 讃 えたのであった。しかし、 嘆 く 羅 刹 (ダ<br />
シャーナナ)に 千 年 が 過 ぎ 去 った。<br />
35. それによって、 力 強 い 偉 大 な 神 (シヴァ)は、 山 の 頂 上 に 固 定 された[ダシャーナナ]に 満 足 し<br />
た。そして、 彼 の 諸 々の 腕 を 自 由 にして、ラーマよ、ダシャーナナに[ 次 のような] 言 葉 を 語 っ<br />
た。<br />
36. 「ダシャーナナよ、 私 は 勇 者 たるお 前 の 高 潔 さゆえに 満 足 である。 山 に 押 し 潰 されたお 前 により 放<br />
たれた、 大 変 恐 ろしげな 叫 び 声 (rāva)と、<br />
37. そして、[その 声 の] 響 き 渡 った(rāvita)この 三 界 が 恐 怖 に 到 ったことにより、 王 よ、お 前 はま<br />
さにラーヴァナ(Rāvaṇa)という 名 となるであろう。<br />
38. 神 々、 人 々、 夜 叉 達 、そして 地 上 にいるその 他 の 者 達 は、お 前 を「 世 界 を 叫 ばせる 者 」(Lokarāvaṇa)、「ラーヴァナ」とこのように<br />
呼 ぶであろう。」<br />
39. プラスティ 仙 の 子 孫 (ダシャグリーヴァ 改 めラーヴァナ)よ、お 前 が 望 む 道 にて 自 由 に 立 ち 去 れ。<br />
他 ならぬ 私 によって 許 されたのだ。 羅 刹 族 の 王 よ、どうぞ 行 くがよい。」<br />
1000 <br />
Rāvaṇa √ru<br />
2 rāva<br />
rāvita<br />
<br />
§6 シヴァによる 恩 寵 とその 後 のラーヴァナ<br />
40. しかし、このようにシャンブ(シヴァ)に 言 われて、ランカー 島 の 王 (ラーヴァナ)は 自 ら 言 っ<br />
た。「 偉 大 なる 神 よ、もしも 満 足 されたのでしたら、 請 うている 私 に 恩 恵 をお 与 えください。<br />
41. 神 、ガンダルヴァ、 悪 魔 たち、および、 羅 刹 族 の 者 たち、 秘 密 者 たち、 蛇 族 たちによっては、ま<br />
た、 他 のより 強 い 者 たちによって[さえ] 殺 されえない 性 質 が 私 によってすでに 得 られておりま<br />
13<br />
Giteau1967-68<br />
(6)
25<br />
す。<br />
42. 人 間 たちを 数 には 入 れません、 神 (シヴァ)よ。[というのも、] 彼 らは 私 にとって 取 るに 足 らな<br />
いものと 考 えられる[からです]。そして、 私 には、 梵 天 から 長 い 寿 命 がすでに 得 られています。<br />
三 都 城 を 滅 ぼす 者 (シヴァ)よ、[ 私 が] 望 んでいる、 寿 命 の 残 りと 武 器 とを、あなたは 私 にお 与<br />
え 下 さい。」<br />
43. すると、そのラーヴァナによってこのように 言 われたかのシャンカラ(シヴァ)は、「 月 の 笑 み」<br />
(candrahāsa)として 名 高 い 光 輝 く 剣 を 与 えた。そして、そのときに、 生 類 の 主 (シヴァ) 14 は 寿 命<br />
の 残 りをも 与 えた。<br />
44. 与 えると、その 後 シャンブ(シヴァ)は、「この[ 剣 ]はお 前 によって 軽 んじられてはならない。<br />
というのは、もし 軽 んじられることがあるならば、 他 ならぬ 私 [のところ]に 疑 うことをしない<br />
[その 剣 ]は 戻 ってくるであろうから。」[と] 述 べた。<br />
45. このようにして、まさに 大 主 宰 神 (シヴァ)によってつくられた 名 前 を 持 つかのラーヴァナは、<br />
偉 大 なる 神 (シヴァ)に 挨 拶 をすると、プシュパカに 乗 りこんだのであった。<br />
46. その 後 、ラーマよ、ラーヴァナは 地 表 を 征 服 していった。たいへん 大 きな 勇 気 を 持 つ 武 人 (クシャ<br />
トリヤ)たちを 次 から 次 へと 倒 しつつ。<br />
47. ある 者 たちは 力 強 い 勇 者 で、 戦 いにひどく 熱 心 な 武 人 であったが、 彼 (ラーヴァナ)の 命 令 に 従<br />
わず、 従 者 たちともども 滅 亡 した。<br />
48. 他 の 知 恵 を 備 えた 者 たちは、 羅 刹 (ラーヴァナ)が 打 ち 負 かし 難 いことを 知 って、「 我 々は 征 服 さ<br />
れました」と[その] 力 を 誇 る 羅 刹 族 の 者 に 話 しかけた。<br />
<br />
1000 <br />
<br />
<br />
<br />
42<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
14<br />
bhūta-patibhūta<br />
21<br />
(7)
26 <br />
4.『シヴァターンダヴァ・ストートラ』について<br />
<br />
1000 <br />
<br />
32 <br />
Pañcacāmara 16 4 <br />
15 <br />
<br />
<br />
<br />
Bhaktimala: Shiva, Vol .1, Music Today CD D92003, 1991 <br />
Ramanand Sagar’s Ramayan, DVD Disc 7, Episode 30, 2001<br />
<br />
<br />
111 <br />
<br />
16 <br />
<br />
<br />
<br />
17 <br />
Pandey1997<br />
<br />
15<br />
116<br />
8<br />
jaṭā ṭavī galaj jalap ravā hapā vitas thale<br />
⏑ – ⏑ – ⏑ – ⏑ – ⏑ – ⏑ – ⏑ – ⏑ –<br />
<br />
38<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
16<br />
1149<br />
17<br />
Agrawala1960<br />
<br />
(8)
27<br />
<br />
<br />
Pandey1997<br />
STpBhaktimala CD Music Today<br />
1992<br />
1912 <br />
Bṛhatstotraratnākara STj<br />
1 14 <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
1 <br />
<br />
<br />
5.『シヴァターンダヴァ・ストートラ』 訳 と 解 説<br />
§1 シヴァ 神 の 姿<br />
jaṭā-͡aṭavī-galaj-jala-pravāha-pāvita-sthale<br />
gale ’valambya lambitāṃ bhujaṅga-tuṅga-mālikām |<br />
ḍamaḍ-ḍamaḍ-ḍamaḍ-ḍaman-ninādavaḍ-ḍamarv ayaṃ<br />
cakāra caṇḍa-tāṇḍavaṃ tanotu naḥ śivaḥ śivam || 1||<br />
1. 巻 髪 の 森 より 落 ちる 水 の 流 れによって 清 められた 土 地 である 喉 頸 に、 垂 れ 下 がった 大 きな 花 輪 の<br />
ようなコブラを 懸 けて、「ダマッド、ダマッド、ダマッド」という 音 のする 太 鼓 を 伴 う、 猛 々しい<br />
舞 踊 (tāṇḍava)をかの 方 は 行 った。[その]シヴァ 神 は 我 々に 幸 せ(śiva)を 恵 みたまえ。<br />
jaṭā-kaṭāha-saṃbhrama-bhraman-nilimpanirjharīvilola-vīci-vallarī-virājamāna-mūrdhani<br />
18 |<br />
dhagad-dhagad-dhagaj-jvalal-lalāṭa-paṭṭa-pāvake<br />
kiśora-candra-śekhare ratiḥ prati-kṣaṇaṃ mama || 2||<br />
2. 鉢 状 の 巻 髪 に 渦 を 巻 き 彷 徨 う 神 聖 な 河 (nilimpanirjharī: ガンガー)のうねる 波 の 分 岐 に 輝 く 頭 を<br />
持 ち、「ダガッド、ダガッド、ダガッド」と 燃 える 額 の 表 面 に 炎 を 備 え、 細 い 月 を 頭 飾 りとする 者<br />
18<br />
STpmūrddhaniSTj <br />
(9)
28 <br />
(シヴァ 神 )に 対 し、 毎 瞬 毎 瞬 、 私 の 熱 情 がある。<br />
1. 2. 3. <br />
4. 5. <br />
6. <br />
3<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
§2 パールヴァティー 妃 を 伴 うシヴァ 神<br />
dharādharendra-nandinī-vilāsa-bandhu-bandhurasphurad-dig-anta-santati-pramodamāna-mānase<br />
|<br />
kṛpā-kaṭa-͡akṣa-dhoraṇī-niruddha-durdhara-͡āpadi<br />
kvacid dig-ambare 19 mano vinodam etu vastuni || 3||<br />
3. 山 の 王 (dharādharendra: ヒマーラヤ)の 娘 (パールヴァティー 妃 )と 美 しい 遊 び 仲 間 と[に 比 さ<br />
れる] 山 並 みの、 輝 く 四 方 位 の 果 てまでの 連 続 ( 稜 線 )を 喜 ぶ 御 心 (mānasa)を 持 ち、 慈 悲 の 一<br />
瞥 (kaṭākṣa)の 持 続 によって 耐 え 難 い 苦 難 を 制 した、 四 方 位 を 衣 とする 存 在 (vastu)[であるシ<br />
ヴァ 神 ]において、 心 が 喜 びに 赴 きますように。<br />
jatā-bhujaṅga-piṅgala-sphurat-phaṇā-maṇi-prabhākadamba-kuṅkuma-drava-pralipta-dig-vadhū-mukhe<br />
|<br />
mada-͡andha-sindhura-sphurat-tvag-uttarīya-medure<br />
mano vinodam adbhutaṃ bibhartu bhūta-bhartari || 4||<br />
4. 巻 髪 のコブラの 赤 茶 に 輝 く 襟 の 珠 の 輝 きによって、カダンバとクンクマの 液<br />
20 に 染 められたように<br />
[ 四 方 の] 天 空 の 乙 女 たち(dig-vadhū)の 顔 を[ 黄 色 や 赤 色 に 染 め]、 盲 いた 酔 象 の 輝 く 肌 を 滑 ら<br />
かな 上 衣 とする 生 類 の 主 (シヴァ 神 ) 21 において、 心 は 喜 びを 保 ちますように。<br />
19 STj: cid-aṃbare<br />
20<br />
<br />
<br />
21<br />
14 1980, 106<br />
bhūta-bhartṛ<br />
(10)
29<br />
22 <br />
<br />
<br />
<br />
mānasa<br />
<br />
Himavat 23 <br />
3<br />
phaṇā-maṇi <br />
<br />
<br />
§3 シヴァ 神 とインドラおよびカーマ<br />
sahasralocana-prabhṛty-aśeṣa-lekha-śekharaprasūna-dhūli-dhoraṇī-vidhūsara-͡aṅghri-pīṭha-bhūḥ<br />
|<br />
bhujaṅga-rāja-mālayā nibaddha-jāṭa-jūṭakaḥ<br />
śriyai cirāya jāyatāṃ cakorabandhu-śekharaḥ || 5||<br />
5. [ 頂 礼 する] 千 眼 の 者 (sahasralocana: 帝 釈 天 インドラ)をはじめとする 全 ての 神 々の 冠 から[ 落 ち<br />
る] 花 弁 と 花 粉 の 連 続 によって 色 づけられる 足 の 置 き 場 を 持 つ 者 であり、コブラの 王 でできた 花<br />
輪 によって、もつれた 髪 (jāṭa-jūṭa)を 結 ぶ 者 であり、チャコーラ 鳥 の 友 (cakorabandhu: 月 ) 24 を<br />
頭 飾 りとする 者 (シヴァ 神 )は、 長 き 吉 祥 のため、 生 起 しますように。<br />
lalāṭa-catvara-jvalad-dhanañjaya-sphuliṅga-bhānipīta-pañcasāyakaṃ<br />
naman-nilimpa-nāyakam |<br />
sudhā-mayūkha-lekhayā virājamāna-śekharaṃ<br />
mahā-kapāli sampade śiro jaṭālam astu naḥ || 6||<br />
6. 5 本 の 矢 を 持 つ 者 (pañcasāyaka: 愛 神 カ ー マ ) が[ そ の ] 額 の 祭 場 (catvara) で 燃 え る 炎<br />
(dhanañjaya)の 火 の 粉 と 輝 きに 飲 み 込 まれた 場 所 であり、 神 々の 指 導 者 (インドラ)が 礼 拝 する<br />
22<br />
3 “vilāsa-bandhu-bandhura”<br />
“vilāsa”“dalliance”Pandeya1997, 60<br />
<br />
<br />
23<br />
2008, 228-33<br />
24<br />
kavi-samaya<br />
<br />
(11)
30 <br />
対 象 である、 甘 露 を 光 線 とする 繊 月 によって 輝 く 頭 飾 りをつけた、 頭 蓋 骨 の 大 きな 25 結 髪 する 頭 が、<br />
我 々の 幸 せ(sampad)のためにありますように。<br />
karāla-bhāla-paṭṭikā-dhagad-dhagad-dhagaj-jvaladdhanañjaya-͡āhutīkṛta<br />
26 -pracaṇḍa-pañcasāyake |<br />
dharādharendra-nandinī-kuca-͡agra-citra-patrakaprakalpana-͡eka-śilpini<br />
trilocane ratir 27 mama || 7||<br />
7. [その] 恐 ろしき 額 の 表 面 で「ダガッド、ダガッド、ダガッド」と 燃 える 炎 に、 鋭 い 5 本 の 矢 を 持<br />
つ 者 ( 愛 神 カーマ)が 供 物 として 捧 げられた 者 であり、 山 の 王 の 娘 (パールヴァティー 妃 )の 胸<br />
の 先 に 色 とりどりの 彩 色 を 施 す 唯 一 人 の 職 人 である、 三 眼 の 者 (trilocana: シヴァ 神 )に 対 し、 私<br />
の 熱 情 がある。<br />
56 <br />
<br />
<br />
<br />
67 <br />
<br />
<br />
<br />
28 5 <br />
5 <br />
29 <br />
30 <br />
§4 荒 ぶる 神 としてのシヴァ 神 の 諸 相<br />
navīna-megha-maṇḍalī-niruddha-durdhara-sphurat-<br />
25<br />
<br />
1988, 219<br />
26 STj: ādharīkṛta<br />
27<br />
STj: matir<br />
28<br />
1980, 83-4.<br />
29<br />
Agrawala1960, 195<br />
<br />
30<br />
2008, 228-39<br />
<br />
(12)
31<br />
kuhū-niśīthinī-tamaḥ 31 -prabandha-baddha 32 -kandharaḥ |<br />
nilimpanirjharī-dharas tanotu kṛtti-sindhuraḥ<br />
kalā-nidhāna-bandhuraḥ śriyaṃ jagad-dhurandharaḥ || 8||<br />
8. とぐろを 巻 く 新 しい 雲 に 覆 われた、 抑 えがたく 輝 く 新 月 の 夜 の 暗 闇 の 連 続 と 結 合 した[かのよう<br />
に 青 黒 い] 頸 を 持 つ 者 、 神 聖 な 河 (ガンガー)を 支 える 者 であり、 象 皮 を 纏 う 者 であり、[ 月 の]<br />
欠 片 の 美 しい 置 き 場 であり、 世 界 という 重 荷 を 支 える 者 [であるシヴァ 神 ]は、 吉 祥 ( 富 )を 恵<br />
み 給 え。<br />
praphulla-nīla-paṅkaja-prapañca-kālima-prabhā-͡<br />
avalambi-kaṇṭha-kandalī-ruci-prabaddha-kandharam 33 |<br />
smaracchidaṃ puracchidaṃ bhavacchidaṃ makhacchidaṃ<br />
gajacchida-͡andhakachidaṃ tam antakacchidaṃ bhaje || 9||<br />
9. 満 開 の 青 い 蓮 より 放 散 する 青 黒 い 輝 きを[したコブラを] 掛 ける 喉 と、カンダリーの[ 白 い 花 の]<br />
光 と 結 びついた 首 を 持 つ、 愛 神 (カーマ=スマラ)を 滅 ぼす 者 であり、[ 魔 神 ターラカ 三 兄 弟 の]<br />
都 城 を 滅 ぼす 者 であり、 生 ( 再 生 )を 断 ち 切 るものであり、[ダクシャの] 祭 式 を 破 壊 する 者 であ<br />
り、 象 の 姿 をした 魔 神 (ガジャ・アスラ)を 滅 ぼす 者 であり、 魔 神 アンダカを 滅 ぼす 者 であり、<br />
死 神 (アンタカ)を 滅 ぼす 者 である 彼 (シヴァ 神 )に、 私 は 礼 拝 いたします。<br />
akharva 34 -sarvamaṅgalā-kalā-kadaṃba-mañjarīrasa-pravāha-mādhurī-vijṛmbhaṇā-madhu-vratam<br />
|<br />
smarāntakaṃ purāntakaṃ bhavāntakaṃ makhāntakaṃ<br />
gajāntaka-͡andhakāntakaṃ tam antakāntakaṃ bhaje || 10||<br />
10. カ ダ ン バ の 花 房 の 精 髄 の 流 れ で あ る 蜜 を 湛 え て 開 く 花 の よ う な 一 切 の 吉 祥 を 備 え た 者<br />
(sarvamaṅgalā: パールヴァティー)の 全 ての 支 肢 に[とまる] 蜂 (madhuvrata)であり、 愛 神<br />
(カーマ=スマラ)を 滅 ぼす 者 であり、[ 魔 神 ターラカの 三 人 の 息 子 の] 都 城 を 滅 ぼす 者 であり、<br />
生 ( 再 生 )を 断 ち 切 るものであり、[ダクシャの] 祭 式 を 破 壊 する 者 であり、 象 の 姿 をした 魔 神<br />
(ガジャ・アスラ)を 滅 ぼす 者 であり、 魔 神 アンダカを 滅 ぼす 者 であり、 死 神 (アンタカ)を 滅 ぼ<br />
す 者 である 彼 (シヴァ 神 )に、 私 は 礼 拝 いたします。<br />
8 ab 9 ab <br />
<br />
35 10 ab <br />
<br />
31 STptamaḥ STj <br />
32<br />
STj: bandhu<br />
33 STj 9ab: praphulla-nīla-paṅkaja-prapañca-kālimac-chaṭā-viḍambi-kaṇṭha-kandharā-ruci-prabandha-kandharam |<br />
34<br />
STj: agarva<br />
35<br />
<br />
(13)
32 <br />
4 <br />
<br />
9 cd 10 cd <br />
saṃhāra-mūrti 7 36 <br />
smara 67 <br />
3 3 <br />
pura 16 <br />
37 <br />
bhavakāla<br />
38 <br />
39 <br />
40 <br />
makha<br />
<br />
<br />
41 <br />
4 8 gaja<br />
<br />
<br />
42 <br />
andhaka<br />
43 <br />
<br />
<br />
<br />
36<br />
2008, 189<br />
Sadananda<br />
<br />
37<br />
1980, 87-8.<br />
38<br />
bhavāntaka <br />
1988, 2062002, 86<br />
39<br />
17<br />
2002, 105-262008, 206-11<br />
40<br />
Agrawala1960, 19.<br />
41<br />
1980, 90-2; 128-302008, 240-1.<br />
42<br />
1980, 84-6.<br />
43<br />
2008, 184.<br />
(14)
33<br />
<br />
44 <br />
antaka<br />
16 <br />
<br />
45 <br />
§5 シヴァ 神 のターンダヴァ 舞 踊<br />
jayatv adabhra-vibhrama-bhramad-bhujaṅgama-śvasad 46 -<br />
vinirgamat-krama-sphurat-karāla-bhāla-havyavāṭ | 47<br />
dhimid-dhimid-dhimid-dhvanan-mṛdaṅga-tuṅga-maṅgaladhvani-krama-pravartita-pracaṇḍa-tāṇḍavaḥ<br />
śivaḥ || 11||<br />
11. 多 くのとぐろを 巻 くコブラが、 呼 吸 し、 這 い 出 し、 順 にくねる、 恐 ろしき 額 に、 供 物 を 保 つ[ 炉<br />
のごとき 第 三 の 目 ]を 有 する 者 であり、「ディミッド、ディミッド、ディミッド」と 鳴 るムリダン<br />
ガ 太 鼓 の、 大 きく 吉 祥 なる 音 の 連 なりにかき 立 てられた 猛 々しい 舞 踊 (tāṇḍava)をなす、シヴァ<br />
神 に 勝 利 あれ。<br />
1 <br />
naṭa-rāja 48 <br />
<br />
49 <br />
50 <br />
44<br />
OFlaherty1983, 35-6<br />
45<br />
1980, 86-7.<br />
46<br />
STj: sphurad<br />
47 STj 11b: dhagad-dhagad-vinirgamat-karāla-bhāla-havyavāṭ |<br />
48<br />
1980, 104-7. Rao1968, 221-270.<br />
49<br />
1988, 225-91980, 106<br />
<br />
<br />
2007: 119-20<br />
<br />
lāsya<br />
<br />
<br />
50<br />
1988, 39, 402008, 6.17; 18; 20<br />
(15)
34 <br />
§6 詠 い 手 の 問 いかけ<br />
dṛṣad-vicitra-talpayor bhujaṅga-mauktika-srajor<br />
gariṣṭha-ratna-loṣṭayoḥ 51 suhṛd-vipakṣa-pakṣayoḥ |<br />
tṛṇa-͡aravinda-cakṣuṣoḥ prajāmahī-mahendrayoḥ<br />
samapravṛttikaḥ kadā sadāśivaṃ bhajāmy aham || 12|| 52<br />
12. 岩 でできた 極 彩 色 の 寝 台 を 持 ち、コブラの 珠 の 首 飾 りを 付 け、 至 高 なる 宝 の 塊 を 持 ち、 友 に<br />
も 敵 にも 味 方 となり、 草 のように[ 切 れ 長 で] 蓮 のように[ 輝 く] 目 を 持 つ 生 類 の 王 と 王 妃<br />
(prajāmahī-mahendra: シヴァ 神 とパールヴァティー 妃 )とに 同 じ[ 帰 依 の 心 を] 起 こしている 私 は、<br />
いつシヴァ 神 の 永 遠 相 (sadāśiva)を 礼 拝 できるでしょうか?<br />
kadā nilimpanirjharī-nikuñja-koṭare vasan<br />
vimukta-durmatiḥ sadā śiraḥ-stham añjaliṃ vahan |<br />
vilola 53 -lola-locano 54 lalāma-bhāla-lagnakaḥ<br />
śiva-͡iti mantram uccaran kadā sukhī bhavāmy aham || 13||<br />
13. 神 聖 な 河 (ガンガー)の 木 陰 の 洞 に 住 み、 悪 しき 考 えを 離 れ、 常 に 頭 の 上 に 合 掌 の 手 を 置 き、きょ<br />
ろつくことなく、 飾 りのついた 額 を 持 つ[シヴァ 神 ]に 献 信 し、「シヴァよ」というマントラを 唱<br />
えている 私 は、いったいいつ 幸 せを 備 えた 者 となるでしょうか?<br />
<br />
55 <br />
<br />
<br />
<br />
12.89 2 <br />
56 <br />
<br />
<br />
12 Agrawala1960, 20<br />
<br />
51<br />
loṣṭhayoḥをSTjにより 修 正 。<br />
52 STj 12d: samaṃ pravartayan-manaḥ kadā sadāśivaṃ bhaje ||<br />
53<br />
STj: vimukta<br />
54<br />
STj: locanā<br />
55<br />
1980, 107; 116Maheśa<br />
Srinivasan<br />
1990, 109; 140Sadāśiva<br />
O'Flaherty1983, 37-8<br />
56<br />
Sivaramamurti1951, 130-2.<br />
(16)
35<br />
<br />
<br />
ardhanārīśvara-mūrti 57 <br />
§7 読 誦 の 効 能 (phalaśruti)<br />
imaṃ hi nityam evam-uktam uttama-͡uttamaṃ stavaṃ<br />
paṭhan smaran bruvan naro viśuddhim eti santatam |<br />
hare gurau subhaktim āśu yāti na ͡anyathā gatiṃ<br />
vimohanaṃ hi dehināṃ suśaṅkarasya cintanam || 14||<br />
14. このように 説 かれた 最 上 なるこの 讃 辞 を、 常 に 読 み 上 げ、 記 憶 し、 唱 える 人 は 永 遠 なる 清 浄 性 に<br />
赴 く。ハラ(シヴァ 神 )という 師 に 対 する 良 き 信 仰 に 速 やかに 至 るのである。 別 の 方 法 では[そ<br />
こに] 行 くことはない。 人 々にとって、よきシャンカラ(シヴァ 神 )に 対 する 念 想 (cintana)こ<br />
そが、 妄 念 を 離 れること 58 なのだから。<br />
pūjā-͡avasāna-samaye daśavaktra-gītaṃ<br />
yaḥ śaṃbhu-pūjana-paraṃ 59 paṭhati pradoṣe |<br />
tasya sthirāṃ ratha-gajendra-turaṅga-yuktāṃ<br />
lakṣmīṃ sadā ͡eva sumukhīṃ pradadāti śaṃbhuḥ || 15||<br />
15. 供 養 の 終 わりに 際 して、 十 の 口 を 有 する 者 (daśavaktra: ラーヴァナ)によって 歌 われた、シャン<br />
ブ(シヴァ 神 )の 供 養 のうちの 最 高 のもの(であるこの 讃 歌 )を、 宵 に 唱 える 者 、その 者 には、<br />
車 駕 、 象 、 馬 を 備 えた 堅 固 なる 富 を、シャンブは、 喜 んで 与 える。<br />
iti śrī-rāvaṇa-kṛtaṃ 60 śiva-tāṇḍava-stotraṃ sampūrṇam |<br />
以 上 、ラーヴァナ 作 『シヴァターンダヴァ・ストートラ』、 了 。<br />
phalaśruti<br />
15 <br />
14 Vasantatilakā <br />
<br />
57<br />
1980, 99-100<br />
58<br />
vimohana confusion, perplexity seducing, fascinating<br />
cintana<br />
Pandey1997, 69<br />
<br />
59 STj: pūjanam idaṃ<br />
60 STj: viracitaṃ<br />
(17)
36 <br />
略 号<br />
STj Śivatāṇḍavastotra: Javaji (1912, 112-4).<br />
STp Śivatāṇḍavastotra: Pandey (1997, 58-70).<br />
Bibliography<br />
文 献<br />
Agrawala, Vasudeva S.<br />
1960 The Śivatāṇḍava Stotra of Rāvaṇa, Journal of the Oriental Institute, Baroda 10.1: 18-21.<br />
Berkson, Carmel, George Michell and Wendy Doniger OFlaherty<br />
1983 Elephanta: the Cave of Shiva, Princeton University Press: Princeton.<br />
Giteau, Madeleine<br />
1967-68 Two Tenth Century Bas-Reliefs Depicting the Rāvaṇānugrahamūrti, The Adyar Library Bulletin 31-31: 593-599.<br />
Gonda, Jan<br />
1977 Medieval Religious Literature in Sanskrit (A History of Indian Literature II-1), Wiesbaden: Otto Harrassowitz.<br />
Javaji, Tukaram<br />
1912 (ed.) Bṛhatstotraratnākaraḥ: 182 stotrasaṃkhyā, Bombay: Nirnaya Sagar Press.<br />
Kala, Jayantika<br />
1988 Epic Scenes in Indian Plastic Art, New Delhi: Abhinav Publications.<br />
Mudholakara, Shastri S.K.<br />
1990 (ed.) Rāmāyaṇa of Vālmīki, vol. vii (Uttarakanda), with the Commentary (Tilakā/Rāmāyaṇaśiromaṇi/Bhūṣana),<br />
Delhi: Parimal Publications.<br />
Music Today<br />
1992 Bhaktimālā, New Delhi: Living Media Ltd.<br />
OFlaherty, Wendy Doniger<br />
1983 The Myths depicted at Elephanta, in Berkson et. al (1983, 27-39).<br />
Pandey, Ramesh Kumar<br />
1997 Kalpalatā: A Collection of Devotional Poems, New Delhi: Sanskrit Sanskriti Pratishthanam.<br />
Paṇśīkar, Wāsudev Laxman Śāstri<br />
1940 (ed.) The Rāmāyaṇa of Vālmīki, with the Commentary (Tilakā) of Rāma (4th edn.), Bombay: Nirnaya Sagar<br />
Press.<br />
Rao, T. A. Gopinatha<br />
1968 Elements of Hindu Iconography, New York: Paragon Book Reprint Corp.<br />
Shah, U.P.<br />
1975 The Vālmīki-Rāmāyaṇa: the Uttarakāṇḍa, The Seventh Book of the Vālmīki-Rāmāyaṇa, Baroda: Oriental<br />
Institute.<br />
Shastri, Hari Prasad<br />
1959 (ed.) The Rāmāyaṇa of Vālmīki, vol.III (Yuddhakanda&Uttarakanda), London: Shanti Sadan.<br />
Sivaramamurti, C.<br />
1951 Ravana in the Kailāsa Temple at Ellora, Journal of the Ganganatha Jha Research Institute 8.2: 129-134.<br />
Srinivasan, Doris Meth<br />
1990 From Transcendency to Materiality: Para Śiva, Sadāśiva, and Maheśa in Indian Art, Artibus Asiae 50.1: 108-<br />
142.<br />
<br />
1980 376<br />
(18)
37<br />
<br />
2008 <br />
<br />
1980 <br />
<br />
2000 <br />
2002<br />
<br />
1988 <br />
<br />
2007Abhinayadarpaṇa1<br />
41: 105-126<br />
図 版 1 エローラ 第 29 窟 撮 影 : 佐 久 間 留 理 子 (2007.2.5)<br />
(19)
38 <br />
図 版 2 バンテアイ・スレイ 南 経 蔵 破 風 撮 影 : 前 川 実 保 (2009.12.15)<br />
図 版 3 シヴァ 神 の 容 姿 と 持 物<br />
(20)
39<br />
Abstract<br />
An Annotated Japanese Translation of the Śivatāṇḍava-stotra<br />
Toshiya UNEBE<br />
Śivatāṇḍava-stotra is a Sanskrit hymn of praise to the Lord Śiva in the Hindu religious tradition. It has been<br />
very popular in India and is famous for its high literary grace. And it is traditionally ascribed to Rāvaṇa, the rival<br />
of Rāma who is the hero of one of the two cerebrated Indian epics, Rāmāyaṇa.<br />
This article presents a Japanese translation of this hymn with annotation. The Rāmāyaṇa (chapter 7, section<br />
16) narrates the account of how Rāvaṇa became a devotee (bhakta) of Śiva and how he came to sing the hymn to<br />
him. This episode is also translated in this article.<br />
The hymn describes many mūrti (forms) of Śiva related to his various mythological episodes. The annotation<br />
explains these related episodes and the visual representations as well.<br />
(21)