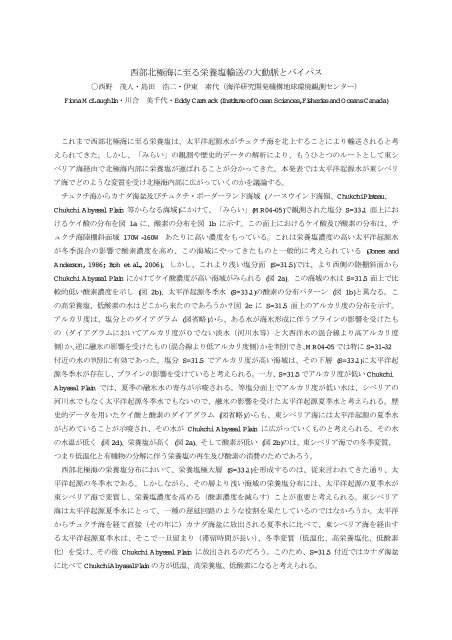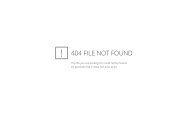You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>西部北極海に至る栄養塩輸送の大動脈とバイパス</strong><br />
○西野 茂人・島田 浩二・伊東 素代(海洋研究開発機構地球環境観測センター)<br />
Fiona McLaughlin・川合 美千代・Eddy Carmack (Institute of Ocean Sciences, Fisheries and Oceans Canada)<br />
これまで西部北極海に至る栄養塩は、太平洋起源水がチュクチ海を北上することにより輸送されると考<br />
えられてきた。しかし、「みらい」の観測や歴史的データの解析により、もうひとつのルートとして東シ<br />
ベリア海経由で北極海内部に栄養塩が運ばれることが分かってきた。本発表では太平洋起源水が東シベリ<br />
ア海でどのような変質を受け北極海内部に広がっていくのかを議論する。<br />
チュクチ海からカナダ海盆及びチュクチ・ボーダーランド海域 (ノースウインド海嶺、Chukchi Plateau、<br />
Chukchi A byssal Plain 等からなる海域)にかけて、「みらい」(M R04-05)で観測された塩分 S=33.1 面上にお<br />
けるケイ酸の分布を図 1a に、酸素の分布を図 1b に示す。この面上におけるケイ酸及び酸素の分布は、チ<br />
ュクチ海陸棚斜面域 170W -160W あたりに高い濃度をもっている。これは栄養塩濃度の高い太平洋起源水<br />
が冬季混合の影響で酸素濃度を高め、この海域にやってきたものと一般的に考えられている (Jones and<br />
Anderson, 1986; Itoh et al., 2006)。しかし、これより浅い塩分面 (S=31.5)では、より西側の陸棚斜面から<br />
Chukchi A byssal Plain にかけてケイ酸濃度が高い海域がみられる (図 2a)。この海域の水は S=31.5 面上で比<br />
較的低い酸素濃度を示し (図 2b)、太平洋起源冬季水 (S=33.1)の酸素の分布パターン (図 1b)と異なる。こ<br />
の高栄養塩、低酸素の水はどこから来たのであろうか?図 2c に S=31.5 面上のアルカリ度の分布を示す。<br />
アルカリ度は、塩分とのダイアグラム (図省略)から、ある水が海氷形成に伴うブラインの影響を受けたも<br />
の(ダイアグラムにおいてアルカリ度が0でない淡水(河川水等)と大西洋水の混合線より高アルカリ度<br />
側)か、逆に融氷の影響を受けたもの(混合線より低アルカリ度側)かを判別でき、M R04-05 では特に S=31-32<br />
付近の水の判別に有効であった。塩分 S=31.5 でアルカリ度が高い海域は、その下層 (S=33.1)に太平洋起<br />
源冬季水が存在し、ブラインの影響を受けていると考えられる。一方、S=31.5 でアルカリ度が低い Chukchi<br />
Abyssal Plain では、夏季の融氷水の寄与が示唆される。等塩分面上でアルカリ度が低い水は、シベリアの<br />
河川水でもなく太平洋起源冬季水でもないので、融氷の影響を受けた太平洋起源夏季水と考えられる。歴<br />
史的データを用いたケイ酸と酸素のダイアグラム (図省略)からも、東シベリア海には太平洋起源の夏季水<br />
が占めていることが示唆され、その水が Chukchi A byssal Plain に広がっていくものと考えられる。その水<br />
の水温が低く (図 2d)、栄養塩が高く (図 2a)、そして酸素が低い (図 2b)のは、東シベリア海での冬季変質、<br />
つまり低温化と有機物の分解に伴う栄養塩の再生及び酸素の消費のためであろう。<br />
西部北極海の栄養塩分布において、栄養塩極大層 (S=33.1)を形成するのは、従来言われてきた通り、太<br />
平洋起源の冬季水である。しかしながら、その層より浅い海域の栄養塩分布には、太平洋起源の夏季水が<br />
東シベリア海で変質し、栄養塩濃度を高める(酸素濃度を減らす)ことが重要と考えられる。東シベリア<br />
海は太平洋起源夏季水にとって、一種の遅延回路のような役割を果たしているのではなかろうか。太平洋<br />
からチュクチ海を経て直接(その年に)カナダ海盆に放出される夏季水に比べて、東シベリア海を経由す<br />
る太平洋起源夏季水は、そこで一旦留まり(滞留時間が長い)、冬季変質(低温化、高栄養塩化、低酸素<br />
化)を受け、その後 Chukchi A byssal Plain に放出されるのだろう。このため、S=31.5 付近ではカナダ海盆<br />
に比べて Chukchi Abyssal Plain の方が低温、高栄養塩、低酸素になると考えられる。
(a) (b)<br />
(a)<br />
(c)<br />
CP NW R<br />
CAP<br />
CB<br />
高ケイ酸<br />
大動脈<br />
ESS<br />
Chukchi Sea<br />
Siberia<br />
太平洋起源冬季水 太平洋起源冬季水<br />
Alaska<br />
図 1. 「みらい」(MR04-05)の観測より得られた塩分 S=33.1 面上の(a)ケイ酸と(b)酸素の分布.図 1(a)の ESS、CB、NW R、CP、<br />
CAPはそれぞれ East Siberian Sea (東シベリア海)、Canada Basin (カナダ海盆)、Northw ind Ridge (ノースウインド海嶺)、<br />
Chukchi Plateau、Chukchi A byssal Plain の略である.図 1(a)及び 1(b)の丸印はケイ酸及び酸素濃度の高い場所を示す.矢<br />
印は太平洋起源冬季水の経路を模式的に表したものである.この経路が栄養塩輸送の大動脈となる.<br />
(b)<br />
高ケイ酸 低酸素<br />
太平洋起源夏季水<br />
(d)<br />
大動脈<br />
バイパス バイパス<br />
高酸素<br />
図 2. 「みらい」(MR04-05)の観測より得られた塩分 S=31.5 面上の(a)ケイ酸、(b)酸素、(c)アルカリ度、及び(d)水温の分布.<br />
図 2(a)及び 2(b)の丸印はケイ酸濃度の高い場所及び酸素濃度の低い場所を示す.矢印は太平洋起源夏季水の経路を模式<br />
的に表したものである.このうち東シベリア海経由の経路が栄養塩輸送のバイパスとなる.<br />
太平洋起源夏季水