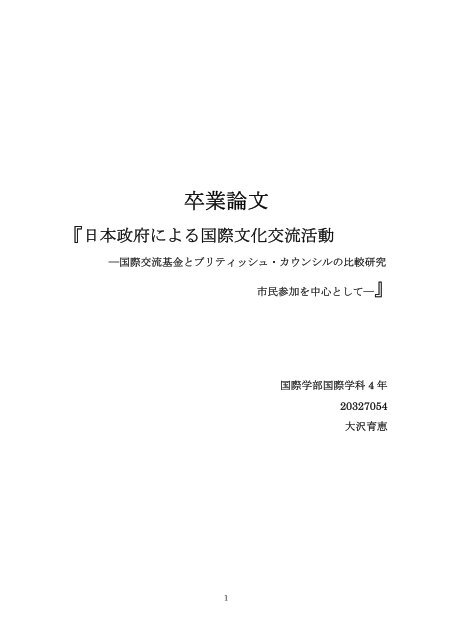卒業論文 - 桜美林大学
卒業論文 - 桜美林大学
卒業論文 - 桜美林大学
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
卒 業 論 文<br />
『 日 本 政 府 による 国 際 文 化 交 流 活 動<br />
― 国 際 交 流 基 金 とブリティッシュ・カウンシルの 比 較 研 究<br />
市 民 参 加 を 中 心 として―』<br />
国 際 学 部 国 際 学 科 4 年<br />
20327054<br />
大 沢 育 恵<br />
1
目 次<br />
はじめに p.1<br />
第 1 章 日 本 の 国 際 文 化 交 流 の 概 要 と 課 題 p.1<br />
第 1 節 国 際 文 化 交 流 とは p.1<br />
第 2 節 歴 史 とともに 多 様 化 してきた 主 体 p.2<br />
第 3 節 事 業 内 容 と 事 業 例 p.4<br />
第 4 節 現 状 と 今 後 の 課 題 p.6<br />
第 2 章 政 府 による 国 際 文 化 交 流 の 活 動 内 容<br />
― 国 際 交 流 基 金 とブリティッシュ・カウンシルの 比 較 ― p.7<br />
第 1 節 国 際 交 流 基 金 の 概 要 と 活 動 内 容 p.7<br />
第 2 節 ブリティッシュ・カウンシルの 概 要 と 活 動 内 容 p.11<br />
第 3 節 比 較 して― 参 考 となる 点 ― p.14<br />
第 3 章 政 府 による 国 際 文 化 交 流 機 関 の 市 民 参 加 の 課 題 と 対 策 p.15<br />
第 1 節 市 民 へのアプローチの 必 要 性 p.15<br />
第 2 節 ワンワールドフェスティバル:<br />
市 民 参 加 と 協 働 の 一 つの 成 功 例 p.18<br />
第 3 節 望 まれる 国 際 交 流 基 金 の 市 民 参 加 の 対 策 :<br />
より 参 加 しやすいボランティア 制 度 と 広 範 囲 な 情 報 提 供 の 実 施 p.19<br />
終 章 p.20<br />
参 考 文 献 p.21<br />
2
はじめに<br />
私 たちは、 普 段 の 生 活 の 中 で、 海 外 の 文 化 に 触 れることが 多 い 時 代 を 生 きている。 例 え<br />
ば 海 外 旅 行 に 行 ったとき、 海 外 の 食 品 や 日 本 に 住 む 外 国 人 と 出 会 ったときなど、 私 たちは<br />
自 国 とは 違 う 文 化 に 触 れる。 私 たち 日 本 人 は、 日 常 的 に 国 際 文 化 交 流 を 行 っていると 言 え<br />
る。<br />
筆 者 はそのような 時 代 だからこそ、 今 以 上 に 海 外 の 文 化 を 理 解 する 機 会 が 必 要 であり、<br />
どのようにすれば、より 深 く 海 外 の 文 化 を 理 解 することができるのだろうと 考 えた。もし<br />
少 しでも 多 くの 日 本 人 が 海 外 の 文 化 に 興 味 、 関 心 を 持 ち、その 違 いを 分 かることができた<br />
ら、 日 本 に 住 む 外 国 人 も 安 心 して 暮 らせ、 日 本 人 も 自 国 の 文 化 を 見 直 し、 同 時 に 海 外 の 文<br />
化 の 素 晴 らしさも 知 り、より 充 実 した 日 々が 送 れるのではないかと 考 えた。<br />
筆 者 は、 日 本 は 今 後 どのような 国 際 文 化 交 流 事 業 の 対 策 をとっていくべきなのかについ<br />
て 考 えたい。 本 論 では、 日 本 は 第 二 次 世 界 大 戦 後 から 現 代 に 至 るまで、どのような 国 際 文<br />
化 交 流 活 動 をしてきたのか、その 中 で、どのような 活 動 を 目 指 し、 実 際 にどういった 活 動<br />
をしてきたのかを 考 察 していく。そして 今 後 、さらに 他 国 との 連 携 が 必 要 不 可 欠 となって<br />
くる 時 代 にむけ、 日 本 における 国 際 文 化 交 流 は 何 を 目 的 とし、どのように 展 開 すべきなの<br />
かを 述 べていきたい。<br />
第 1 章 では 国 際 文 化 交 流 の 定 義 、そして 戦 後 から 現 在 にかけての 日 本 の 国 際 文 化 交 流 活<br />
動 の 歴 史 を 取 り 上 げる。 本 章 では、それら 通 じ、 国 際 文 化 交 流 が 必 要 とされ 始 めた 歴 史 的<br />
背 景 や、 多 様 化 していく 過 程 を 考 察 する。 第 2 章 では、 国 際 文 化 交 流 活 動 の 事 例 として 政<br />
府 の 機 関 を2つ 取 り 上 げ、その 活 動 内 容 を 比 較 する。 日 本 の 主 な 国 際 文 化 交 流 機 関 である<br />
国 際 交 流 基 金 と 同 様 の 機 関 であるイギリスのブリティッシュ・カウンシルを 事 例 に 挙 げる。<br />
第 3 章 では 今 後 の 日 本 の 国 際 文 化 交 流 活 動 の 課 題 や 対 策 について 論 じる。 本 章 では 実 際 に<br />
筆 者 が 行 った 国 際 交 流 基 金 での 就 業 体 験 からの 意 見 と、 第 2 章 で 取 り 上 げた 2 者 を 比 較 し<br />
た 結 果 の 意 見 を 合 わせ、 主 に 市 民 参 加 増 加 への 具 体 的 な 改 善 策 について 論 じていく。<br />
筆 者 は、 本 論 を 通 じて、 現 代 の 国 際 文 化 交 流 を 見 直 し、 国 際 文 化 交 流 事 業 への 市 民 参 加<br />
増 加 への 新 たな 対 策 を 考 え 出 すことで、 今 後 の 国 際 社 会 における 日 本 や 日 本 人 一 人 ひとり<br />
の 発 展 につなげていきたいと 考 えている。<br />
第 1 章 日 本 の 国 際 文 化 交 流 の 概 要 と 課 題<br />
第 1 節 国 際 文 化 交 流 とは<br />
ここではまず、 国 際 文 化 交 流 というものはどのようなものであり、どういった 目 的 、 特<br />
徴 があるのかを 述 べていきたい。<br />
現 代 では、 観 光 や 貿 易 など、ヒトやモノ、 情 報 の 国 境 を 越 えた 移 動 にともない、 異 なる<br />
文 化 の 接 触 が 自 然 に 起 こっている。 国 際 文 化 交 流 というのはそういった 異 文 化 接 触 を 意 図<br />
的 に 行 う 事 業 ・ 活 動 であり、 現 代 の 日 本 において、 必 要 不 可 欠 となっている。<br />
国 際 文 化 交 流 の 目 的 には、 異 なる 文 化 をもつ 人 たちがふれあい、 協 力 し 合 って 平 和 で 豊<br />
かな 世 界 を 築 き、ともに 調 和 して 生 きていける 社 会 をつくることが 掲 げられている[ 毛 受<br />
2003:218]。<br />
3
日 本 において 国 際 文 化 交 流 の 事 業 がどう 展 開 していったかというと、とくに 戦 後 からそ<br />
の 活 動 が 活 発 になってきた。 第 二 次 世 界 大 戦 後 の 連 合 軍 の 占 領 下 では、 日 本 の 国 際 的 な 信<br />
用 が 失 われたという 問 題 を 抱 えながら、 戦 後 に 日 本 をどのように 世 界 に 位 置 付 けていくか<br />
ということに 取 り 組 んでいくなかで、 国 際 文 化 交 流 への 期 待 が 高 まっていった。 軍 事 国 家<br />
としての 反 省 を 含 め、 民 主 主 義 を 徹 底 させ、 世 界 貢 献 を 目 指 し、 新 しい「 文 化 国 家 」 日 本<br />
として 復 帰 していこうとしたことが、 日 本 の 戦 後 の 国 際 文 化 交 流 事 業 の 始 まりともいえる<br />
[ 平 野 2005:3]。<br />
そして、 国 際 文 化 交 流 の 中 の「 文 化 」に 対 する 解 釈 の 仕 方 に 特 徴 がある。ここでいう、「 文<br />
化 」とは、 音 楽 、 文 学 、 絵 画 などの 芸 術 分 野 にとどまらず、 個 人 や 人 間 の 集 団 のもつ 伝 統 、<br />
価 値 、 生 活 様 式 などを 総 合 的 に 意 味 するものである。 国 際 文 化 交 流 とは、 異 なる 価 値 観 を<br />
理 解 し、 同 時 に 共 有 する 価 値 観 の 範 囲 を 広 げ、さらには 新 たに 文 化 を 創 造 することでもあ<br />
る。つまり 国 際 文 化 交 流 というのは、 自 己 を 深 め、 自 らの 文 化 環 境 を 豊 かにしていく 活 動<br />
ともいえる[ 毛 受 2003:218]。<br />
最 後 の 特 徴 として、 国 際 文 化 交 流 は 人 と 人 との 交 流 が 基 本 であることを 挙 げておきたい。<br />
第 2 節 歴 史 とともに 多 様 化 してきた 主 体<br />
日 本 の 国 際 文 化 交 流 の 主 体 は、とくに 戦 後 から 現 代 に 至 るまで 多 様 化 してきた。ここで<br />
は、その 活 動 を 行 う 主 体 にはどのようなものが 存 在 し、それらは 歴 史 とともにどのように<br />
多 様 化 してきたかについて、 歴 史 的 背 景 をみながら 述 べていきたい。<br />
主 体 は、 戦 後 、 政 府 、 国 家 機 関 など 国 家 レベルの 主 体 から、 自 治 体 、 民 間 、NGO などの<br />
国 家 レベル 以 外 の 主 体 が 増 加 の 傾 向 にあり、とくに 1970 年 代 以 降 大 きな 変 化 をみせた。<br />
国 際 文 化 交 流 活 動 の 主 体 は、 日 本 では 主 に 3 つに 分 類 することができ、 第 1に、 外 務 省<br />
や 文 部 科 学 省 などの 省 庁 や、 国 際 交 流 基 金 などの 政 府 が 運 営 している 国 家 レベルの 機 関 で<br />
ある。 第 2 に 自 治 体 などの 運 営 する 地 域 国 際 協 会 などの 地 方 自 治 体 レベルの 主 体 であり、<br />
地 域 の 安 定 と 発 展 を 目 的 としている。そして 第 3に、 民 間 団 体 、 市 民 団 体 レベルの 主 体 が<br />
ある。 前 者 には 例 えば、 財 団 法 人 や 社 団 法 人 といったような 団 体 がある。 民 間 の 団 体 が 現<br />
在 の 主 体 の 総 数 の 大 半 を 占 めており、 日 本 の 国 際 文 化 交 流 活 動 の 中 心 を 担 っている。 数 的<br />
データをみてみると 民 間 団 体 は 全 国 で 2545 団 体 ある 1 。 年 々 増 加 の 傾 向 にあり、とくに 1980<br />
年 代 に 入 ってから 急 増 しているという 傾 向 がある( 図 1)。<br />
700<br />
600<br />
500<br />
400<br />
300<br />
200<br />
100<br />
0<br />
1945 以 前 1951-55 1961-65 1971-75 1981-85 1991-95<br />
設 立 団 体 数<br />
図 1 団 体 設 立 状 況 ・ 設 立 年 別 団 体 数<br />
これらの 主 体 は、 戦 前 からその 時 々の 歴 史 的 背 景 に 対 応 しながら 設 立 されていった。こ<br />
1 国 際 交 流 基 金 (2001)『 国 際 交 流 活 動 団 体 に 関 する 調 査 アンケート 集 計 結 果 報 告 書 』に<br />
集 計 された 団 体 数 。<br />
4
こからは、 具 体 的 にどういった 歴 史 的 背 景 のとき、どのような 主 体 が 何 の 目 的 をもって 作<br />
られていったかについてみていきたい。<br />
戦 前 はとくに 国 家 レベルの 主 体 が 中 心 となっていた。 国 家 レベルの 国 際 文 化 交 流 事 業 の<br />
開 始 は 1900 年 の 義 和 団 事 件 が 関 連 し、その 賠 償 金 を 用 いて 開 始 された 1923 年 からの 対 支<br />
文 化 事 業 がある。 日 本 の 外 務 省 は 中 国 政 府 から 得 た 賠 償 金 を 基 金 にして、 中 国 からの 留 学<br />
生 の 受 け 入 れ 事 業 や、 中 国 の 学 術 研 究 などを 支 援 していった。その 他 1935 年 にアジアから<br />
の 留 学 生 支 援 を 目 的 とする 国 際 学 友 会 が 設 立 された 例 もある。 以 上 のように、 戦 前 は 国 家<br />
レベルでの 公 的 な 主 体 を 中 心 に、 海 外 に 日 本 の 文 化 を 伝 えていくような 事 業 のもと、アジ<br />
ア 諸 国 との 関 係 を 深 めていくような 目 的 がとられていったという 傾 向 がある[ 榎 田 1996:<br />
33]。<br />
次 に 戦 後 から 1970 年 代 までをみていきたい。この 時 代 は 戦 争 によって 失 った 信 用 を 回 復<br />
し、 国 際 社 会 で 他 国 と 協 働 していくという 目 的 があった。とくに 米 国 を 中 心 として 欧 米 の<br />
交 流 が 主 流 だったといえる。<br />
この 時 代 の 代 表 的 な 民 間 レベルの 主 体 として 1952 年 に、 国 際 文 化 会 館 が 設 立 された。 国<br />
際 文 化 会 館 は 米 国 のジョン・D・ロックフェラー3 世 の 資 金 協 力 により、 松 本 重 治 などに<br />
よって 設 立 された。 日 米 双 方 の 政 府 と 友 好 的 な 関 係 を 保 ちながら 主 体 性 をもって 活 動 する<br />
という 目 的 をもち、 民 間 団 体 としての 活 動 の 在 り 方 を 日 本 において 初 めて 確 立 した。<br />
そしてこの 時 代 の 主 体 に 関 してとくにいえることは、これらの 活 動 に 実 際 に 関 わること<br />
ができたのがエリートに 限 られていたということである。 国 際 文 化 交 流 事 業 は 人 と 人 との<br />
交 流 が 基 本 とされるが、この 時 代 においては 一 般 市 民 ではなく、エリート 2 が 直 接 的 な 主 体<br />
として 主 に 交 流 活 動 に 関 わっていた。<br />
1970 年 以 降 については、 国 際 文 化 交 流 活 動 全 体 に 大 きな 変 化 をもたらした 歴 史 的 背 景 が<br />
いくつか 挙 げられる。1971 年 の 米 国 によるニクソンショックや 日 本 の 経 済 や 日 本 人 の 生 活<br />
に 変 化 を 与 えた 1964 年 のオリンピック 開 催 、そして 海 外 渡 航 解 禁 、 高 度 経 済 成 長 という 背<br />
景 があり、 大 きな 要 因 となって 国 際 文 化 交 流 の 担 い 手 に 変 化 をもたらしていった[ 榎 田<br />
1996:33]。<br />
カンボジア 紛 争 の 影 響 からは、それを 契 機 に 日 本 において NGO という 市 民 によって 形 成<br />
された 国 際 協 力 を 行 う 団 体 が、 国 際 文 化 交 流 の 活 動 内 容 を 広 げていったという 点 が 挙 げら<br />
れる。1980 年 以 降 、カンボジア 難 民 支 援 活 動 を 通 じて、 市 民 団 体 レベルの 主 体 である NGO<br />
団 体 が 急 増 していった。カンボジア 紛 争 やベトナムからのボートピープルを 経 て、インド<br />
シナ 難 民 問 題 が 日 本 にも 伝 わるようになったことが 原 因 である。 日 本 政 府 は 国 際 難 民 条 約<br />
を 批 准 して、インドシナ 難 民 の 受 入 れを 開 始 した。この 問 題 により、 日 本 では 海 外 に 向 け<br />
て 大 きく 視 野 を 広 げ 関 心 を 深 める 市 民 が 増 え、NGO の 設 立 は 急 増 していった。<br />
1971 年 のニクソンショックによって、それまでの 日 米 関 係 は 壊 され、 米 国 への 信 頼 を 失<br />
い 始 めた。とくに 日 本 の 経 済 大 国 化 によって 生 じた 日 米 の 経 済 摩 擦 が 主 な 要 因 となり、そ<br />
2 ここで 言 うエリートというのは、「 国 際 的 な 事 柄 に 知 的 関 心 をもち、 国 際 社 会 とつながり<br />
を 持 つことができ、 得 られた 知 識 や 情 報 を 社 会 に 的 確 に 伝 達 する 術 をもつ 影 響 力 のある<br />
人 々[ 榎 田 1996:35]」のことを 指 す。<br />
5
れに 伴 うエコノミックアニマル 日 本 人 のイメージは 悪 化 し、 日 米 のお 互 いのイメージギャ<br />
ップを 解 消 しようとする 動 きもでてきた。その 例 として 1972 年 に 設 立 された 国 際 交 流 基 金<br />
が 挙 げられる。 国 際 交 流 基 金 は 主 に 米 国 との 関 係 改 善 を 目 的 として 設 立 され、その 後 の 国<br />
際 文 化 交 流 活 動 の 中 心 を 担 っている 国 家 レベルでの 主 体 である[ 平 野 2005:7]。<br />
一 方 で、1964 年 に 海 外 渡 航 が 解 禁 されたことから、それまで 容 易 にできなかった 一 般 市<br />
民 の 海 外 渡 航 が 可 能 になり、 国 民 がより 身 近 に 海 外 を 感 じるようになり、 国 際 文 化 交 流 の<br />
主 体 は 地 方 自 治 体 レベル、 民 間 、 市 民 団 体 レベルに 多 様 化 していった。 気 軽 に 海 外 に 行 く<br />
ことができ、 海 外 の 情 報 が 入 ってくると、 海 外 事 情 に 興 味 を 持 つ 人 が 増 えることが 原 因 だ<br />
ったといえる。<br />
さらに、この 時 期 から 地 方 の 時 代 が 叫 ばれた。 例 としては 1975 年 に 神 奈 川 県 知 事 となっ<br />
た 長 洲 一 二 により「 民 際 3 交 流 」の 概 念 が 推 進 され、1977 年 に 県 に 国 際 交 流 課 が 設 置 され、<br />
また 県 の 外 郭 団 体 として、 神 奈 国 際 交 流 協 会 が 設 立 されたことが 挙 げられる。この 協 会 の<br />
設 立 をモデルとして、 全 国 の 各 都 道 府 県 に 国 際 交 流 協 会 が 設 置 され、 地 方 自 治 体 レベルの<br />
主 体 が 全 国 に 増 加 し、「 民 際 交 流 」の 広 まりは、その 後 の 市 民 を 中 心 とした 主 体 の 増 加 にと<br />
っても 大 きな 要 因 となった。<br />
その 他 、 民 間 レベルに 属 する 財 団 法 人 としては、トヨタ 財 団 が 1974 年 に 設 立 され、1981<br />
年 には 三 菱 銀 行 国 際 財 団 も 設 立 された。どちらも 国 際 関 係 の 共 同 研 究 や 交 流 活 動 の 助 成 を<br />
行 う 企 業 財 団 として、 民 間 、 市 民 の 団 体 に 資 金 を 提 供 し、 自 らも 国 際 文 化 交 流 事 業 を 行 っ<br />
ていった[ 榎 田 1996:44-45]。<br />
以 上 を 見 てもわかるように、 時 代 背 景 とともに、 国 際 文 化 交 流 事 業 の 担 い 手 というのは、<br />
国 家 レベルでの 主 体 だけにとどまらず、 現 代 にいたるまで、 地 方 自 治 体 から 市 民 、 企 業 に<br />
まで 多 様 化 している。<br />
第 3 節 事 業 内 容 と 事 業 例<br />
ここでは、 現 代 の 国 際 文 化 交 流 の 事 業 内 容 について、どのようなものがあるのかを、 具<br />
体 的 な 例 を 挙 げながらみていきたい。 基 本 的 には、 芸 術 交 流 、 教 育 交 流 、 青 少 年 交 流 、ス<br />
ポーツや 知 的 交 流 などが 挙 げられる。<br />
まず 芸 術 交 流 についてだが、これは 舞 台 美 術 、 映 画 、 文 学 などの 交 流 を 通 して、 相 互 理<br />
解 を 図 ろうとするものである。この 事 業 は、 各 国 による 自 国 の 芸 術 作 品 の 紹 介 によって 価<br />
値 観 を 理 解 することに 効 果 的 な 交 流 である。<br />
例 としては 地 方 自 治 体 レベルの 富 山 県 井 波 町 による「いなみ 国 際 木 彫 刻 キャンプ」が 挙<br />
げられる。この 交 流 事 業 では 地 域 の 伝 統 文 化 財 をいかしながら、 新 たな 文 化 を 創 造 してい<br />
く 取 り 組 みを 行 っている。 初 回 は 1991 年 に 実 施 され、10 カ 国 から 11 名 の 彫 刻 家 が 参 加 し、<br />
それぞれの 国 の 歴 史 、 文 化 、 芸 術 の 違 いを 理 解 し 合 う 精 神 のもと 開 催 された。 各 国 の 彫 刻<br />
3 「 民 際 」という 言 葉 の 由 来 は、 長 洲 知 事 が「 地 方 の 時 代 」を 提 唱 し、 地 方 の 時 代 に 必 要 な<br />
ことは、「 国 際 」ではなく「 民 際 」であると 主 張 したことにある。「 民 際 」というのは、 国<br />
ではなく、 市 民 の 民 意 を 尊 重 した 国 際 交 流 という 意 味 である。<br />
6
家 は 独 自 の 技 術 で 制 作 し、 公 開 展 示 し、 国 の 文 化 の 違 いを 学 びあう 場 となった。この 交 流<br />
は 次 世 代 を 担 う 地 元 の 子 供 たちにとっても 地 域 の 歴 史 と 誇 りを 学 ぶ 場 になっていることは<br />
意 義 深 いものであり、 現 在 まで 続 いている[ 毛 受 2003:84-85]。<br />
第 2に 教 育 交 流 といわれる、 教 師 の 交 流 、 留 学 生 交 換 などの 教 育 の 現 場 での 交 流 を 通 し、<br />
相 互 理 解 の 基 礎 を 築 いていくものがある。 日 本 において、 留 学 生 を 受 け 入 れる 環 境 は 年 々<br />
改 善 されており、 留 学 生 受 け 入 れに 熱 心 な 大 学 も 増 加 し、これからも 日 本 で 学 習 する 留 学<br />
生 は 増 加 していくことが 期 待 されている。<br />
主 な 事 業 例 としては、 国 家 レベルの 主 体 である、 外 務 省 、 総 務 省 、 文 部 科 学 省 の 連 携 に<br />
よって 1987 年 より 実 施 されているJETプログラム 4 が 挙 げられる。 日 本 語 では「 語 学 指 導<br />
等 を 行 う 外 国 青 年 招 致 事 業 」と 呼 ばれ、このプログラムは、 地 方 自 治 体 などが 外 国 の 青 少<br />
年 を 招 致 する 事 業 であり、 日 本 における 外 国 語 教 育 の 充 実 を 図 るとともに、 市 民 レベルで<br />
の 国 際 交 流 を 推 進 することを 目 的 としているものである[ 毛 受 2003:188]。<br />
このプログラムでは 国 際 交 流 員 とスポーツ 国 際 交 流 員 という 二 つの 職 種 の 外 国 人 を 特 別<br />
職 の 地 方 公 務 員 として 雇 用 し、 日 本 での 外 国 語 の 刊 行 物 等 の 翻 訳 作 業 、イベント 等 の 通 訳 、<br />
中 学 校 、 高 等 学 校 での 英 語 やフランス 語 等 の 外 国 語 の 指 導 を 行 っている。<br />
参 加 者 は 2003 年 までの 合 計 では、3 万 人 以 上 にのぼり、 彼 ら 自 身 をはじめ 日 本 の 地 域 社<br />
会 や 学 校 関 係 者 から 高 い 評 価 を 得 ている。 海 外 における 参 加 者 は、その 後 大 使 館 や 日 本 関<br />
連 の 企 業 に 就 職 したり、 日 本 人 の 外 国 語 能 力 を 高 めるためのプログラム・コーディネータ<br />
ーの 仕 事 に 就 いたりして 活 躍 している。<br />
日 本 側 においても 学 校 では 生 徒 の 外 国 語 に 対 する 興 味 ・ 関 心 が 高 まり、 地 域 では、 国 際<br />
的 なイベントの 実 施 ・ 参 加 の 促 進 など 活 発 化 され 学 校 、 地 域 の 国 際 化 に 大 きな 効 果 をみせ<br />
ており、 今 後 も 期 待 される 事 業 となっている。<br />
第 3に 青 少 年 交 流 がある。これは、 比 較 的 偏 見 が 少 ない 時 期 の 若 者 ( 特 に 10 代 )を 中 心<br />
に 異 文 化 接 触 を 行 う 事 業 のことをいう。 青 少 年 交 流 の 目 的 は 次 世 代 を 担 う 若 者 たちが 出 会<br />
い、 共 同 生 活 をしながら、お 互 いの 文 化 、 歴 史 、 人 柄 について 理 解 し、 信 頼 できる 人 間 関<br />
係 を 築 くことである。<br />
例 としては、 市 民 レベルの 団 体 である 地 球 市 民 の 会 が 九 州 を 中 心 に 行 っている「 地 球 ユ<br />
ースサミット」「 地 球 隊 」が 挙 げられる。この 事 業 は 海 外 への 派 遣 事 業 であり、タイや 韓 国<br />
などのアジア 諸 国 へ 子 供 たちを 派 遣 し、 現 地 で 共 同 生 活 させる 活 動 を 実 施 している。この<br />
プロジェクトは、 体 験 を 通 して、 子 供 たちが 出 会 い、 対 話 、 協 力 のすばらしさを 学 び、21<br />
世 紀 の 地 球 人 、そしてアジアの 一 員 としての 認 識 を 深 めるために 行 われている[ 国 際 交 流 基<br />
金 1993:122]。<br />
さらに 国 家 レベルとしての 動 きとしては 1979 年 から 旧 総 務 庁 により 始 められた「 東 南 ア<br />
ジア 青 年 の 船 」 事 業 がある。この 事 業 は 日 本 とアジア 諸 国 の 青 年 が 共 に 船 に 乗 り、アジア<br />
各 国 を 訪 問 するという 内 容 のプログラムであり 様 々な 活 動 を 通 して 友 好 と 理 解 を 深 めてい<br />
くことが 目 的 とされている[ 国 際 交 流 基 金 1993:127]。<br />
その 他 の 種 類 の 事 業 内 容 としてはスポーツ 交 流 と 知 的 交 流 があり、 前 者 は 民 族 文 化 の 枠<br />
を 超 えたルールに 基 づいて 行 われるスポーツを 通 した 交 流 のことである。 事 業 例 には NPO<br />
4 英 語 では”Japan Exchange and Teaching Program(me)”といい、JET はその 頭 文 字 を 取 っ<br />
た 名 称 である。<br />
7
法 人 横 須 賀 国 際 交 流 協 会 が 平 成 9 年 から 実 施 している、 国 際 スポーツ 交 流 が 挙 げられる。<br />
事 業 内 容 は 日 本 といくつかの 海 外 のチームが、 国 別 でサッカーの 試 合 を 行 うという 内 容 で<br />
ある。この 協 会 ではとくに、 試 合 後 に 行 われるパーティーで、 各 国 がそれぞれの 伝 統 の 歌<br />
や 舞 踊 を 披 露 し 合 い、スポーツ 以 外 でも 交 流 を 深 められる 機 会 が 作 られている。<br />
知 的 交 流 というのは、 国 境 を 超 えて 知 識 人 を 結 集 させ、 現 実 にある 問 題 ・ 課 題 の 解 決 の<br />
ために 優 れた 才 能 、 知 恵 を 集 めるような 交 流 である。 様 々な 共 同 研 究 や 国 際 会 議 、など 人<br />
類 が 共 通 して 抱 える 課 題 5、アジア 地 域 に 共 通 の 問 題 が 話 し 合 われている。この 交 流 では、<br />
国 の 枠 にとらわれずに 政 策 提 言 することができ、より 現 実 社 会 に 目 に 見 えるかたちで 貢 献<br />
できる 事 業 として 期 待 されている。<br />
第 4 節 現 状 と 今 後 の 課 題<br />
最 後 に、 日 本 の 国 際 文 化 交 流 の 現 状 がどうなっているのか、そして、 今 後 の 課 題 として<br />
何 が 問 われているのかについてみていきたい。<br />
日 本 の 国 際 文 化 交 流 の 主 な 現 状 としては、「 共 同 作 業 」という 形 態 が 注 目 されてきている<br />
ということが 挙 げられる。 今 までは、 国 際 文 化 交 流 といえば 日 米 、 日 中 などでお 互 い 文 化<br />
紹 介 を 行 う「 二 国 間 」の 交 流 が 基 本 であった。しかし、 最 近 では、いくつかの 国 が 一 つの<br />
事 業 を 通 し、 同 じ 目 的 にむかい、 共 同 で 作 業 し、 一 つの 作 品 を 作 り 上 げたり、 問 題 解 決 を<br />
していったりするという「 多 国 間 」の 交 流 が 注 目 されてきている。この 事 業 はとくに 芸 術<br />
交 流 、 知 的 交 流 などの 分 野 において、 重 視 されている。 例 としては、 国 際 交 流 基 金 アジア<br />
センター 主 催 の 演 劇 「リア」が 挙 げられる。この 演 劇 は 当 センターで、これまでに 培 って<br />
きたアジアの 演 劇 人 との 共 同 作 業 による 国 や 劇 団 を 超 えた 作 品 である。アジア 6 ヵ 国 ( 中<br />
国 、タイ、インドネシア、シンガポール、マレーシア、 日 本 )からスタッフ・ 俳 優 を 集 め<br />
ての 演 劇 であり、 高 い 評 価 を 得 ている 事 業 である[ 国 際 交 流 基 金 HP 2006,11.21]。<br />
その 他 、 国 内 におけるアジア・ブームからくるアジア 諸 国 に 対 する 事 業 が 主 に 展 開 され<br />
てきているという 現 状 がある。とくに 芸 術 交 流 の 分 野 にいえることであるが、 地 方 自 治 体<br />
レベルでは 福 岡 市 が 1999 年 に 福 岡 アジア 美 術 館 を 設 立 し、アジア 地 域 に 特 化 した 事 業 が 活<br />
発 化 し、 映 画 祭 や 文 化 賞 なども 展 開 されてきている[ 平 野 2005:26-27]。<br />
今 後 の 課 題 としては、 各 民 間 市 民 団 体 は、 他 団 体 とのネットワークを 構 築 する 必 要 があ<br />
る。それぞれ 団 体 ごと 別 々に 活 動 しているので、 情 報 交 換 などの 相 互 協 力 を 円 滑 に 行 うこ<br />
とのできるようなネットワーク 構 築 を 確 立 し、 各 団 体 の 活 動 の 質 を 向 上 させていく 必 要 性<br />
が 問 われている。 地 方 自 治 体 レベルについては、 市 民 レベルと 分 業 化 した 上 での 事 業 展 開<br />
が 課 題 となっている。 地 域 社 会 の 多 様 化 にともない、 地 方 自 治 体 主 導 の 事 業 に 加 え、 市 民<br />
による 国 際 交 流 事 業 の 活 性 化 のための 動 きも 必 要 となってくる。つまり 地 方 自 治 体 が、 資<br />
金 、ノウハウの 面 で 協 力 し、 実 際 の 活 動 を 市 民 が 率 先 して 行 っていくという 分 業 化 が 必 要<br />
となってくるということである[ 榎 田 1997:124]。<br />
最 後 に 民 間 、 市 民 レベルに 対 しての 課 題 としては 主 に 人 材 育 成 が 挙 げられる。 市 民 団 体<br />
の 大 半 がプログラム・オフィサー6などの 専 門 家 をおいていないので、 今 後 は 活 動 の 企 画 、<br />
5 ここで 言 う 課 題 というのは、 環 境 問 題 、 民 族 問 題 、 貧 困 、ジェンダーなどの 世 界 が 共 通 し<br />
て 持 つグローバルな 問 題 のこと。<br />
6 事 業 団 体 の 目 的 を 果 たすために、 文 化 交 流 のプログラムを 企 画 、 運 営 、 実 践 する 専 門 家 。<br />
8
実 施 を 行 うにあたって、 現 場 での 研 修 を 取 り 入 れながら、 人 材 育 成 に 力 を 入 れていく 必 要<br />
があるとされている。とくに 財 源 を 確 保 することが 困 難 な 民 間 、 市 民 団 体 には 予 算 執 行 な<br />
どの 組 織 運 営 について 専 門 的 知 識 のある 専 門 家 の 力 が 重 要 となってくるといえる[ 榎 田<br />
1997:126]。<br />
第 2 章 政 府 による 国 際 文 化 交 流 の 活 動 内 容<br />
― 国 際 交 流 基 金 とブリティッシュ・カウンシルの 比 較 ―<br />
本 章 では、2つの 国 際 文 化 交 流 組 織 の 活 動 内 容 を 事 例 に 挙 げ、 実 際 の 政 府 による 国 際 文<br />
化 交 流 活 動 の 目 的 や 事 業 例 を 比 較 していく。 事 例 には、 日 本 の 国 家 レベルの 主 体 である 国<br />
際 交 流 基 金 ( 以 下 、 基 金 )と、イギリスのブリティッシュ・カウンシル( 以 下 、カウンシル)を<br />
とりあげる。その 理 由 は、 基 金 が 日 本 の 国 際 文 化 交 流 活 動 の 中 心 として 活 動 しているから<br />
である。そしてなぜカウンシルを 挙 げたかというと、カウンシルは 日 本 の 基 金 設 立 以 前 か<br />
ら 英 国 の 国 際 文 化 交 流 機 関 として 運 営 され、 基 金 設 立 時 のモデルであり、 今 も 海 外 に 多 く<br />
の 事 務 所 を 持 ち、 世 界 の 中 でも、 特 に 活 躍 している 国 際 交 流 機 関 の 一 つであると 言 えるか<br />
らである。 以 下 に、 基 金 とカウンシルの 活 動 内 容 に、どのような 違 いがあり、 日 本 の 国 家<br />
レベルの 代 表 的 な 主 体 に 何 が 足 りないのかを 見 ていきたい。そして 設 立 してから 今 まで 両<br />
機 関 はどのように 事 業 展 開 してきたのか、そして 現 在 どういった 事 業 を 中 心 に 活 動 してい<br />
るのかを 見 ていきたい。<br />
第 1 節 国 際 交 流 基 金 の 概 要 と 活 動 内 容<br />
概 要<br />
基 金 は 1972 年 に 外 務 省 所 管 の 特 殊 法 人 として 設 立 され、2003 年 に 独 立 行 政 法 人 化 した 7 。<br />
設 立 当 初 の 1970 年 代 はじめは、 日 米 の 経 済 摩 擦 や 東 南 アジアでの 反 日 運 動 など、 日 本 を 知<br />
ってもらうための 文 化 交 流 事 業 の 必 要 性 の 認 識 が 政 府 の 中 で 高 まった。その 結 果 、 大 規 模<br />
な 基 金 を 持 ち、さらに 強 力 な 国 際 文 化 交 流 を 実 施 する 機 関 の 設 立 準 備 が 始 められたという<br />
時 代 背 景 がある。1972 年 に 当 時 の 福 田 外 務 大 臣 は、 第 68 回 国 会 における 外 交 に 関 する 演<br />
説 の 中 で、 国 際 交 流 基 金 の 構 想 を 発 表 し、 同 年 、 国 際 交 流 基 金 法 案 が 公 布 された。その 後<br />
さらにその 法 案 によって 組 織 の 内 容 が、 国 内 各 界 の 有 職 者 からなる 設 立 準 備 会 議 で 検 討 さ<br />
れ、 同 年 の 10 月 2 日 、 国 際 交 流 基 金 ( 英 文 名 Japan Foundation)が 発 足 した。<br />
職 員 数 は 約 233 名 (2005 年 )で、 海 外 事 務 所 にそのうちの 約 60 名 が 勤 務 している。 事 業 所<br />
は 国 内 に 本 部 、 京 都 支 部 、2つの 附 属 機 関 ( 日 本 語 国 際 センター、 関 西 国 際 センター)があり、<br />
海 外 には 18 ヶ 国 に 19 ヶ 所 の 事 務 所 がある。 本 部 は 東 京 赤 坂 にあり、 海 外 の 日 本 語 教 師 の<br />
研 修 を 主 とする 日 本 語 国 際 センターは 埼 玉 県 の 浦 和 に、 外 国 の 外 交 官 の 日 本 語 研 修 を 主 と<br />
する 関 西 国 際 センターは 大 阪 府 の 泉 南 郡 にあり、それぞれ 活 動 している。<br />
資 金 は、 設 立 当 時 は 約 50 億 円 の 政 府 出 資 金 を 運 用 資 金 としていたが、その 後 追 加 出 資 が<br />
行 われ、2001 年 には 資 本 金 は 約 1062 億 円 にまで 増 加 した。 今 では 約 1110 億 円 を 財 政 的 基<br />
礎 として 運 営 している。 基 金 は 自 ら 国 際 交 流 事 業 を 行 うとともに、 他 団 体 、 機 関 に 対 して<br />
7 本 節 は、 主 として、 国 際 交 流 基 金 ホームページ(2006 年 1 月 6 日 )の「 国 際 交 流 基 金 年 報<br />
2004 年 事 業 報 告 」のイントロダクションを 参 照 。<br />
9
資 金 を 助 成 することで、 民 間 レベルの 国 際 交 流 の 主 体 を 支 援 してきている。<br />
活 動 内 容<br />
次 に、 基 金 の 活 動 目 的 や 内 容 についてみていきたい 8 。まず 目 的 についてだが、 基 金 は 独<br />
立 行 政 法 人 として、その 目 的 と 業 務 を 以 下 のように、 独 立 行 政 法 人 国 際 交 流 基 金 法 に 定 め<br />
ている。<br />
目 的<br />
独 立 行 政 法 人 国 際 交 流 基 金 は、 国 際 文 化 交 流 事 業 を 総 合 的 かつ 効 率 的 に 行 うこと<br />
により、 我 が 国 に 対 する 諸 外 国 の 理 解 を 深 め、 国 際 相 互 理 解 を 増 進 し、 及 び 文 化<br />
その 他 の 分 野 において 世 界 に 貢 献 し、もって 良 好 な 国 際 環 境 の 整 備 並 びに 我 が 国<br />
の 調 和 ある 対 外 関 係 の 維 持 及 び 発 展 に 寄 与 することを 目 的 とする。<br />
( 独 立 行 政 法 人 国 際 交 流 基 金 第 3 条 )<br />
業 務<br />
1、 国 際 文 化 交 流 の 目 的 をもって 行 う 人 物 の 派 遣 及 び 招 へい<br />
2、 海 外 における 日 本 研 究 に 対 する 援 助 及 びあっせん 並 びに 日 本 語 の 普 及<br />
3、 国 際 文 化 交 流 を 目 的 とする 催 しの 援 助 およびあっせん 並 びにこれへの 参 加<br />
4、 日 本 文 化 を 海 外 に 紹 介 するための 資 料 その 他 国 際 文 化 交 流 に 必 要 な 資 料 の 作<br />
成 、 収 集 、 交 換 及 び 頒 布<br />
5、 国 際 文 化 交 流 を 目 的 とする 施 設 の 整 備 に 対 する 援 助 並 びに 国 際 文 化 交 流 のた<br />
めに 用 いられる 物 品 の 購 入 に 関 する 援 助 及 びこれらの 物 品 の 贈 与<br />
国 際 文 化 交 流 を 行 うために 必 要 な 調 査 及 び 研 究<br />
6、 各 号 の 業 務 に 附 帯 する 業 務 ( 独 立 行 政 法 人 国 際 交 流 基 金 法 第 12 条 )<br />
以 上 のような 目 的 、 業 務 を 定 め、 基 金 は 実 際 には、 海 外 日 本 語 教 育 、 文 化 芸 術 交 流 、 日 本<br />
研 究 ・ 知 的 交 流 の3つの 主 な 事 業 に 取 り 組 んでいる。その3つの 事 業 の 事 業 分 野 別 シェア<br />
や 目 的 、 事 業 例 については 以 下 のとおりである。<br />
図 1、 国 際 交 流 基 金 の 事 業 分 野 別 シェア<br />
10%<br />
18%<br />
27%<br />
45%<br />
海 外 日 本 語 教 育 (45%)<br />
文 化 芸 術 交 流 (27%)<br />
日 本 研 究 ・ 知 的 交 流 (18%)<br />
その 他 一 般 管 理 費 (10%)<br />
( 出 展 : 国 際 交 流 基 金 (http://www.jpf.go.jp/j/)、 筆 者 作 成 )<br />
1) 文 化 芸 術 交 流 事 業<br />
基 金 は、 諸 外 国 との 相 互 理 解 を 深 める 活 動 として、 文 化 ・ 芸 術 交 流 事 業 を 行 っている。<br />
基 金 は、 造 形 美 術 ・ 舞 台 芸 術 ・ 映 像 ・ 出 版 などの 分 野 での 交 流 や、 文 化 財 や 伝 統 文 化 に 関<br />
わる 分 野 での 交 流 ・ 協 力 ( 脚 注 で 交 流 と 協 力 の 違 いを 述 べる)を 通 し、 新 しい 文 化 の 創 造 を 目<br />
8 本 節 は、 主 として 国 際 交 流 基 金 ホームページ(2006 年 1 月 6 日 )の 国 際 交 流 基 金 案 内 を<br />
参 照 。<br />
10
指 し、 活 動 している。 例 えば、 日 本 の 文 化 人 を 派 遣 したり、 逆 に 海 外 の 文 化 人 を 招 へいし<br />
たり、 多 様 な 文 化 の 発 展 に 貢 献 していることが 挙 げられる。その 他 、 海 外 の 文 化 財 保 存 の<br />
支 援 、 造 形 美 術 ・ 舞 台 芸 術 ・ 出 版 を 通 じた 芸 術 交 流 、 日 本 においての 異 文 化 理 解 教 育 など<br />
が 挙 げられる。<br />
過 去 の 例 としては、1980 年 に 英 国 で 行 われた「ジャパン・スタイル 展 」がある。これは、<br />
基 金 が 現 代 の 日 本 の 生 活 文 化 を 紹 介 するために 企 画 した 展 示 である。 基 金 は、 英 国 のビク<br />
トリア・アンド・アルバート 美 術 館 (V&A)において、V&A と 共 催 で 4 ヶ 月 間 展 覧 会 を 行 い、<br />
大 成 功 をおさめた。 企 画 に 至 った 背 景 には、 長 年 日 本 は 欧 州 から「 極 東 に 位 置 する 異 国 」<br />
という 意 識 を 持 たれていたことにある。 当 時 は、 日 本 の 経 済 大 国 化 にともなって、 日 本 が<br />
欧 州 から 異 国 趣 味 の 対 象 とみなされないよう、 現 代 日 本 の 生 活 文 化 そのものを 紹 介 してほ<br />
しいという 声 が 高 まったことが 企 画 の 要 因 とされる。その 企 画 では、キオスク、 寿 司 屋 、<br />
パチンコ 屋 などが 展 示 され、 欧 州 における 現 代 日 本 のへの 関 心 をさらに 掻 き 立 てる 結 果 と<br />
なった[ 榎 1999:188-192]。<br />
最 近 の 芸 術 分 野 の 事 業 例 としては 2005 年 9 月 28 日 から 12 月 18 日 に 行 われた 国 際 芸 術<br />
祭 「 横 浜 トリエンナーレ」があり、 基 金 主 催 で 大 きな 国 際 現 代 アートの 美 術 展 を 開 催 した。<br />
このイベントは 各 国 の 選 りすぐりの 現 代 アートの 芸 術 家 たちを 日 本 に 招 き、 共 同 で 一 つの<br />
美 術 展 を 作 り 上 げていくというものである。<br />
その 他 最 近 の 動 きとして 基 金 は、 漫 画 やアニメーション、テレビゲームなどの 日 本 文 化<br />
に 注 目 している。 現 代 日 本 文 化 が 着 実 に 世 界 中 に 浸 透 し、 国 際 文 化 交 流 の 担 い 手 が 多 様 化<br />
するなかで、 基 金 は 伝 統 から 現 代 までの 幅 広 い 日 本 の 文 化 芸 術 を 総 合 的 に 紹 介 する 役 割 を<br />
担 っている。 事 例 にはアメリカのニューヨーク 事 務 所 が 発 行 している“BRIDGES“という<br />
冊 子 が 挙 げられる。この 冊 子 には 日 本 の 美 術 、 映 画 、 学 術 などが 英 語 で 紹 介 されている。<br />
主 に 昔 から 現 在 までの 作 品 の 紹 介 が 載 せられていて、その 他 日 本 で 同 時 期 に 行 われている<br />
イベントや、 現 地 のニューヨークでの 最 新 のイベントについても 書 かれている。<br />
2) 海 外 での 日 本 語 教 育<br />
基 金 はこの 事 業 のなかで、 日 本 理 解 と、 国 際 相 互 理 解 を 深 める 観 点 から、 日 本 語 教 育 、<br />
学 習 を 支 援 し、 開 発 途 上 国 の 日 本 語 教 育 機 関 への 支 援 を 行 っている。 被 援 助 国 の 学 習 者 数<br />
は、 中 国 ( 香 港 を 含 む)、インドネシア、ブラジル、タイ、ベトナム、マレーシアの 順 ( 学 習<br />
者 数 載 せる)となっている。 主 な 活 動 内 容 は、 日 本 語 教 育 専 門 家 の 派 遣 、 良 質 な 日 本 語 教 材<br />
の 開 発 や 提 供 などであり、それによって 海 外 での 日 本 語 学 習 環 境 の 整 備 を 行 っている。そ<br />
の 他 の 主 な 活 動 に、 日 本 語 能 力 試 験 の 実 施 がある。 基 金 は、1984 年 に 日 本 国 際 教 育 協 会 と<br />
共 催 で、この 日 本 語 能 力 試 験 を 開 始 した。 当 時 の 受 講 者 数 は 国 内 外 合 わせてわずか 約 7,000<br />
人 であった。しかし、 現 在 では 毎 年 約 24 万 人 が 受 けている。 最 近 ではさらに、インターネ<br />
ットを 活 用 した 日 本 語 教 育 情 報 も 提 供 するようになっている。その 他 、 日 本 語 教 材 の 開 発<br />
や、 作 成 、 寄 贈 も 行 っており、 日 本 語 教 育 に 関 する 教 材 が 不 足 している 国 々に 対 して、 教<br />
科 書 やビデオを 送 っている。<br />
海 外 事 務 所 では、その 国 の 日 本 語 教 師 に 対 して 研 修 会 や 日 本 語 講 座 を 行 い、 日 本 語 教 育<br />
を 支 援 している。2003 年 度 に 基 金 が 調 査 した 結 果 によると、 海 外 の 日 本 語 学 習 数 は 235 万<br />
人 であり、5 年 前 より 12% 増 加 しており、 日 本 の 支 援 がさらに 重 要 となっているのがわか<br />
11
る。<br />
3) 日 本 研 究 ・ 知 的 交 流<br />
基 金 は、 海 外 の 有 職 者 や 一 般 市 民 の 日 本 理 解 や、 海 外 の 有 職 者 同 士 のネットワーク 形 成<br />
を 促 進 するため、 日 本 研 究 支 援 や、 知 的 交 流 の 事 業 を 行 っている。<br />
日 本 研 究 の 例 としては、 海 外 の 日 本 研 究 者 に 対 してフェローシップの 供 与 や、 日 本 に 取<br />
り 組 む 教 育 機 関 に 対 する 支 援 事 業 の 実 施 などを 行 っている。 基 金 は、 日 本 に 関 する 海 外 の<br />
有 職 者 による 多 面 的 な 見 方 が、 現 地 で 広 がり、 共 有 されることを 目 的 として、それらの 事<br />
業 に 協 力 している。 中 国 における 例 には、1985 年 に 設 立 した 北 京 日 本 研 究 センターがある。<br />
同 センターは、 北 京 外 国 語 大 学 と 北 京 大 学 の2ヶ 所 に 設 けられている。 現 在 、 各 センター<br />
には、 日 本 語 教 育 学 の 専 門 家 派 遣 、 大 学 院 生 ・ 研 修 生 の 招 へいや、 教 材 ・ 機 材 の 寄 贈 が 行<br />
われている。<br />
その 他 、 海 外 の 日 本 研 究 調 査 やウェブサイト 運 営 も 行 っており、 日 本 研 究 者 や 機 関 の 情<br />
報 交 換 やネットワークを 促 進 している。<br />
知 的 交 流 については、 世 界 や 地 域 に 共 通 する 課 題 への 理 解 を 深 めること、それらの 共 通<br />
課 題 を 解 決 することを 主 な 目 的 としている。 基 金 は、さまざまな 分 野 の 知 的 リーダーが、<br />
国 境 を 越 えて 協 力 、 共 同 して 取 り 組 む 研 究 などの 交 流 事 業 を 企 画 、 実 施 している。 基 金 は<br />
これらの 知 的 交 流 を 通 じて、 多 角 的 な 国 際 相 互 理 解 を 推 進 することで、 世 界 の 発 展 と 安 定<br />
にむけ 貢 献 しようとしている。 事 業 例 には、 中 東 に 対 する 関 心 の 高 まりの 中 の、 中 東 知 的<br />
交 流 セミナーの 助 成 事 業 がある。 同 セミナーは 2004 年 に 行 われた 民 間 レベルの 人 たちによ<br />
る 日 本 と 中 東 の 知 的 対 話 である。 基 金 は 同 セミナーに 対 し 支 援 を 行 い、これまで 圧 倒 的 に<br />
乏 しかった 中 東 への 直 接 対 話 を 実 施 した。<br />
今 後 の 事 業 展 開<br />
今 後 、 基 金 は 前 述 した 主 な3つの 事 業 分 野 への 既 存 事 業 の 整 理 統 合 、そして 新 たに「 情<br />
報 センター」を 新 設 するという 事 業 の 改 革 を 目 指 している。 前 者 は、3 事 業 グループ 制 を 確<br />
立 し、 細 分 化 した 部 署 を 大 きく 目 的 別 に 再 編 して、より 柔 軟 な 動 きがとれるよう 一 体 化 し<br />
て、 戦 略 的 な 展 開 を 可 能 とし、 内 外 のニーズに 対 応 していくことが 目 的 である。 後 者 の 目<br />
的 は、 外 部 の 国 際 交 流 団 体 との 連 携 を 促 進 させることである。 国 際 交 流 の 事 業 の 情 報 提 供<br />
や、 担 い 手 の 方 々への 事 業 仲 介 を 統 括 していこうとしている。その 他 、 運 営 上 の 改 革 とし<br />
て、 人 件 費 を 削 減 して、 自 己 収 入 を 増 やし、 事 業 の 共 催 等 を 行 い 事 業 費 の 効 率 化 が 目 指 さ<br />
れている。 事 業 の 共 催 を 通 じて、 他 団 体 との 連 携 を 深 めることもねらいの 一 つとして 考 え<br />
ている。<br />
第 2 節 ブリティッシュ・カウンシルの 概 要 と 活 動 内 容<br />
概 要<br />
ブリティッシュ・カウンシルは、1934 年 に、「 英 国 対 外 関 係 委 員 会 (The British Committee<br />
for Relations with Other Countries)」として、 民 間 のイニシアティヴと 外 務 省 の 協 力 を 得 て<br />
12
設 立 された 9 。1935 年 に「Committee」を「Council」と 改 め、「ブリティッシュ・カウン<br />
シル」を 正 式 名 称 とし、 外 郭 公 共 団 体 、チャリティ 10 として 認 可 され、 現 在 にいたっている。<br />
設 立 の 目 的 は、 英 国 の 対 外 交 易 を 優 位 にし、 教 育 、 文 化 、 科 学 技 術 の 諸 外 国 への 伝 播 ・ 提<br />
供 を 図 ることである。<br />
設 立 当 初 の 目 的 は 現 在 と 違 い、 第 2 次 世 界 大 戦 初 期 の 独 伊 枢 軸 勢 力 による「 文 化 プロパ<br />
ガンダ(cultural propaganda)」に 対 抗 し、 海 外 における 英 国 に 対 する 高 い 評 価 を 勝 ち 取 る<br />
ことと 英 語 教 育 の 普 及 であり、 諸 国 との 文 化 的 、 商 業 的 つながりを 発 展 させることであっ<br />
た。 当 時 は、 教 育 、 財 務 、 商 業 、 産 業 関 係 者 と 外 務 省 、 連 邦 省 、 貿 易 評 議 会 、 教 育 評 議 会 、<br />
海 外 貿 易 省 からの 代 表 者 で 構 成 されていた。 資 金 に 関 しても、 前 身 であった 外 務 省 情 報 部<br />
の 資 金 を 引 き 継 いでいたが、その 多 くは 民 間 による 寄 付 であり、 海 外 活 動 自 体 は 外 務 省 の<br />
スタッフによって 行 われていた。<br />
その 後 、カウンシルは 1940 年 に「 国 王 による 設 立 許 可 状 (Royal Charter)」を 授 与 さ<br />
れ、 意 思 決 定 機 関 は、カウンシルの 執 行 委 員 会 に 置 かれ、 構 成 役 員 の 一 部 は、 政 府 の 大 臣<br />
によって 任 命 されるという 現 在 のシステムが 確 立 した。そして 1941 年 には、 外 務 省 内 に、<br />
カウンシルの 政 策 や 資 金 管 理 をする「ブリティッシュ・カウンシル・セクション(British<br />
Council Section)」―のちの「 文 化 交 流 部 」―が 設 立 された。<br />
1942 年 には、 当 時 の 教 育 評 議 会 会 長 であったバトラー(R.A.Butler)が、 連 合 教 育 大 臣<br />
会 合 を 設 立 し、1942 年 から 1945 年 11 月 にかけて、カウンシルは 事 務 局 、 執 行 局 、 専 門 家<br />
委 員 会 、 書 籍 および 定 期 刊 行 物 委 員 会 を 設 立 した。さらに 1945 年 11 月 に、カウンシルの<br />
幹 部 は、 当 時 設 立 された UNESCO と 関 係 をもつ 協 力 団 体 の 代 表 を 務 めた。1948 年 には、<br />
Royal Charter が 一 部 改 正 された。その 後 、 戦 後 を 通 じて、ブリティッシュ・カウンシルは、<br />
数 々の 財 政 難 を 乗 り 越 えながら、 海 外 事 務 所 を 増 設 しつづけ、 英 語 教 育 、 海 外 の 教 育 機 関<br />
における 英 語 研 究 、 海 外 の 図 書 館 や 文 化 センターの 維 持 管 理 、 教 育 、 科 学 の 専 門 機 関 に 関<br />
する 事 業 をこなしてきた。<br />
活 動 内 容<br />
カウンシルの 主 な 事 業 は 6 つの 分 野 に 分 かれている 11 。その6つの 分 野 とそれらの 分 野 別<br />
シェアは 以 下 ( 図 2)のとおりであり、ここでは 各 分 野 の 目 的 や 具 体 的 内 容 などについて 述 べ<br />
ていく。<br />
図 2、ブリティッシュ・カウンシルの 事 業 分 野 別 シェア<br />
8%<br />
22% 1、 英 語 教 授<br />
2、 教 育 ・ 訓 練<br />
9 本 項 は、 主 として、 渡 辺 愛 子 (2003) 「Ⅳ 英 国 」 国 際 交 流 3、 基 芸 金 術 『・ 文 主 学 要 ・デザイン 先 進 国 における 国 際 交<br />
8% 38%<br />
4、 科 学 と 保 健 衛 生<br />
流 機 関 調 査 報 告 書 』、190 頁 、234-235 頁 を 参 照 。 5、ガバナンスと 社 会<br />
5%<br />
10 チャリティとは、 活 動 の 目 的 が、1 貧 困 の 救 済 、2 宗 6、 教 情 の 報 振 提 興 供 、3 教 育 の 振 興 、4 地 域<br />
社 会 に 対 する 利 益 をもたらすその 19% 他 の 活 動 、とチャリティ 委 員 会 で 認 められた 法 的 資 格 。<br />
11 本 項 は、 主 として、 渡 辺 愛 子 (2003)、 同 上 、193-199 頁 を 参 照 。<br />
13
( 出 展 :「Ⅳ 英 国 」 国 際 交 流 基 金 『 主 要 先 進 国 における 国 際 交 流 機 関 調 査 報 告 書 』、 筆 者 作 成 )<br />
1) 英 語 教 授<br />
カウンシルでは、とくに 若 者 の 英 国 に 対 する 見 方 に 影 響 を 与 えるため、 海 外 における 英<br />
語 の 語 学 教 育 のより 広 範 で 効 果 的 な 普 及 を 目 指 している。 具 体 的 には、 高 質 な ELT 教 材 を<br />
開 発 することで、 世 界 の 教 育 的 リーダーとしての 英 国 の 評 価 を 高 めることを 目 的 としてい<br />
る。 国 際 語 としての 英 語 を 促 進 することで、 専 門 的 ・ 社 会 ・ 経 済 的 発 展 を 促 し、 世 界 の 人 々<br />
との 交 流 の 機 会 を 作 り 上 げること、さらに 世 界 に 向 けて 英 国 に 関 する 知 識 を 深 化 させ、 現<br />
代 英 国 の 価 値 を 認 識 させることが 目 的 である。<br />
カウンシルは、 英 語 をグロ―バルな 言 語 として 重 要 視 し、 現 在 60 ヶ国 に 138 の 独 立 した<br />
教 育 訓 練 センターを 設 けている。2000 年 から 2001 年 の 実 績 をみてみると、 世 界 各 地 で 1,900<br />
名 以 上 の 有 資 格 教 師 が 約 120 万 時 間 教 授 していることがわかる。また、マルチ・メディア<br />
を 使 った 英 語 教 育 や 退 役 軍 人 の 職 能 訓 練 、 英 国 における 留 学 生 のための 英 語 教 育 なども 促<br />
進 している。マルチ・メディアに 関 しては、 学 生 向 けの CD-ROM や Open University( 日<br />
本 でいう 放 送 大 学 )と 提 携 し、「ビジネスのための 世 界 英 語 」などを 作 り、 生 涯 教 育 の 一 環 と<br />
して 活 用 されている。 留 学 生 の 教 育 に 関 しては、 公 的 ・ 民 間 セクターと 提 携 して、 現 在 375<br />
の 民 間 英 語 学 校 、カレッジ、 私 立 学 校 、 大 学 の 学 部 などを 認 定 し、 各 国 からの 留 学 生 を 受<br />
け 入 れている。<br />
2) 教 育 ・ 訓 練<br />
この 分 野 では、 主 に、 海 外 の 人 々へ 教 育 の 機 会 を 与 えるための 主 導 的 な 立 場 を 担 うこと<br />
や、 世 界 各 国 に 教 育 問 題 が 起 こったときの 指 標 になること、 国 際 市 場 において、 英 国 の 教<br />
育 サービスやプロダクトのシェアを 広 げ、 国 際 交 流 を 通 じ、 英 国 の 教 育 システムを 整 えて<br />
いくことが 目 標 とされている。<br />
これらの 目 標 達 成 のため、 留 学 フェアやセミナーの 開 催 、 教 師 や 学 生 の 人 物 交 流 を 展 開<br />
させている。 具 体 例 としては、2000 年 から 2001 年 に 行 われた「Education UK キャンペ<br />
ーン」がある。この 事 業 は、 海 外 の 企 業 一 般 人 向 けにマーケティング、コミュニケーショ<br />
ンキャンペーンを 実 施 し、 そのなかで 英 国 の 教 育 について 展 示 、PR を 行 うことで、 学 生 市<br />
場 のシェア 獲 得 を 期 待 して 行 われている。 例 えば 2000 年 には 中 国 で、 前 年 の2 倍 にあたる<br />
1 万 2500 人 に 対 し 英 国 への 留 学 ビザを 発 行 した。 その 他 、カウンシルでは、70 万 人 を 対 象<br />
として 様 々な 試 験 を 世 界 各 国 で 行 った。 内 訳 は、 英 語 の 語 学 試 験 が 約 44%、 専 門 資 格 の 試<br />
験 は 23%、その 他 英 国 の 中 学 ・ 高 校 の 一 斉 試 験 である O レベル、A レベル 試 験 が、 海 外 の<br />
14 万 3 千 の 学 校 で 実 施 された。 今 後 もこれらの 数 字 は 伸 びていくと 考 えられる。<br />
3) 芸 術 ・ 文 学 ・デザイン<br />
カウンシルはこの 分 野 で、 英 国 の 古 びたステレオタイプを 無 くすために、 芸 術 をとおし<br />
て、 英 国 を 世 界 に 伝 えようと 様 々な 事 業 を 行 っている。 例 えば、 国 際 フェスティバルや 講<br />
演 、 展 示 ツアーを 行 い、さまざまな 機 関 との 関 係 を 深 めるようにしている。 事 例 には、フ<br />
ランスで 行 われた 英 国 の 映 画 祭 がある。これはブリティッシュ・フィルム・インスティテ<br />
ュート(BFI)とポンピドゥー・センターとの 提 携 で 5 ヶ 月 間 行 われ、6 万 5 千 人 を 迎 え 入 れ<br />
14
た 映 画 祭 であった。その 他 近 年 では、カウンシルは 英 国 の 文 化 について 研 究 をする「 英 国<br />
研 究 」の 支 援 に 力 を 入 れている。 背 景 には 海 外 からのニーズが 高 まったのと、 米 国 研 究 が<br />
盛 んに 行 われていることへの 反 動 でもあるといえる。そして、 新 しい 英 国 を 伝 えることに<br />
よって、 海 外 の 目 に 映 る 英 国 に 対 する 間 違 ったイメージを 取 り 除 くということも 目 的 とし<br />
てある。<br />
4) 科 学 と 保 健 衛 生<br />
この 分 野 の 目 的 は、 英 国 の 最 先 端 の 科 学 技 術 を 地 球 規 模 で 展 開 し、 国 内 、 海 外 における<br />
保 健 衛 生 基 準 を 高 めることである。カウンシルは、 広 く、 生 物 や、その 他 医 学 、 天 文 学 、<br />
物 理 学 、 健 康 、 衛 生 の 充 実 を 図 るため、 科 学 面 では 科 学 の 研 究 プロジェクト、 出 版 活 動 を<br />
行 ったり、 衛 生 面 では、 健 康 関 係 の 情 報 を 配 布 したりするなどして、この2つの 面 の 充 実<br />
を 図 っている。 具 体 的 には、インターネットを 利 用 した 英 国 文 化 サイトの 開 設 が 挙 げられ<br />
る。このサイトは 2000 年 11 月 に 開 設 され、 日 常 の 科 学 の 役 割 について 理 解 を 深 めること<br />
ができるサイトである。このサイトを 通 して、 若 者 たちがオンラインでアイデアを 交 換 し<br />
たり、ゲー ムやグラフィックミュージックを 楽 しめるようにしたり 工 夫 している。 現 在 そ<br />
の英 国 文 化 サイトは 月 間 約 5 千 人 の 利 用 者 がいる。 英 国 の 科 学 技 術 に 関 しては、 海 外 で 認<br />
知 度 が 低 く、 先 進 国 では 米 国 のみがその 技 術 を 誇 るというイメージがあるため、とくに 若<br />
者 に 対 して 科 学 や 技 術 を 伝 えることもまた、 英 国 にとっては 重 要 であると 考 えられている。<br />
5)ガバナンスと 社 会<br />
この 分 野 では、 主 要 な 開 発 のアジェンダを 見 直 し、 継 続 的 な 開 発 をすすめるように、 積<br />
極 的 に 努 力 することが 目 的 とされている。 内 容 としては、 国 際 開 発 という 分 野 があり、 開<br />
発 途 上 国 の 貧 困 層 に 対 する 援 助 、 人 材 育 成 、 環 境 保 護 の 支 援 などを 行 っている。 具 体 的 な<br />
例 にはインドの 女 性 警 官 の 養 成 がある。インドでは 女 性 警 官 が 10% 以 下 で 不 足 しているの<br />
で、 養 成 する 事 業 を 行 っている。その 他 、シエラレオネで、 女 性 の 政 府 や 市 民 社 会 への 参<br />
加 を 促 進 するための 支 援 を 始 めたことが 挙 げられる。<br />
6) 情 報 提 供<br />
カウンシルは、 英 国 を 開 かれた 情 報 社 会 にするため、この 事 業 を 行 っている。 例 えば、<br />
世 界 各 国 に 英 国 に 関 する 情 報 開 示 を 促 したり、 英 国 と 海 外 の 専 門 家 の 情 報 交 換 を 効 率 的 に<br />
するための 事 業 を 行 ったりしている。 例 としては、カウンシルの 出 版 物 の 検 索 が 可 能 な 機<br />
能 の 開 設 、“LearnEnglish”などがある。“LearnEnglish”とは、 英 語 を 学 ぶためのプログラ<br />
ムであり、 全 世 界 の 英 語 学 習 者 、 英 語 教 師 、 英 国 に 関 心 がある 人 々に 対 して、インターネ<br />
ット 上 でサイトを 開 設 している。このサイトを 使 えば、いつでもどこでも 英 語 を 学 ぶこと<br />
ができる。とくに 英 語 を 学 ぶためのゲームや、 物 語 、 歌 やミュースを 満 載 したプログラム<br />
でもあり、 個 人 が 各 自 でインターネットを 通 じて、いつでも 情 報 収 集 できるようにしてい<br />
る。<br />
今 後 の 事 業 展 開<br />
カウンシルは 今 後 、EU 拡 大 のため、 発 展 途 上 国 支 援 から 市 場 経 済 移 行 国 ( 旧 ソ 連 や 東 欧 、<br />
15
中 央 アジア 諸 国 )との 関 係 づくりを 目 指 そうとしている。 従 来 、カウンシルは 発 展 途 上 国<br />
への 援 助 や、 西 欧 諸 国 との 関 係 促 進 を 主 な 事 業 としていたが、 現 在 それらの 見 直 しが 行 わ<br />
れ、 今 後 は 市 場 経 済 移 行 国 への 支 援 などの 事 業 を 目 指 そうとしている。 理 由 は、カウンシ<br />
ルの 広 範 囲 にわたる 文 化 ・ 教 育 促 進 能 力 や 実 績 などが、 市 場 経 済 移 行 国 のニーズに 合 って<br />
いると 考 えられるからである。その 他 、 海 外 事 務 所 の 拡 大 より、 現 在 ある 事 務 所 を 見 直 す<br />
ことも 目 指 されている。 現 在 は 個 々に 活 動 している 海 外 事 業 所 であるが、それらの 質 を 充<br />
実 させることが 挙 げられている。そして 最 後 に、 新 世 代 を 担 う 若 者 たちをターゲットにす<br />
るということも 目 指 されている。 主 な 内 容 としては、カウンシルとドイツのゲーテインス<br />
ティテュートと 共 同 で、 両 国 の 若 者 を 対 象 として、 英 国 のステレオタイプへ 対 抗 するプロ<br />
グラムを 開 始 することが 決 まっている。<br />
第 3 節 比 較 して― 参 考 となる 点 ―<br />
カウンシルの 事 業 から 基 金 に 参 考 になる 点 がいくつか 挙 げられる。<br />
第 一 に、 両 者 とも 自 国 の 言 語 を 海 外 で 普 及 させることに 力 を 入 れているので、カウンシ<br />
ルの 英 語 や 英 国 の 情 報 発 信 の 技 術 などは 参 考 にするとよいのではないかと 考 える。 特 にイ<br />
ンターネットを 使 った 言 語 習 得 や、 情 報 提 供 を 促 進 させようとしている 点 をより 細 かく 日<br />
本 に 取 り 入 れてみるとよいと 考 える。 基 金 も、その 存 在 や 事 業 内 容 をより 自 国 や 海 外 にま<br />
ず 知 ってもらうことが 必 要 であると 考 えるので、インターネットは 大 いに 活 用 すべきであ<br />
る。<br />
第 二 に、カウンシルが 英 国 の 情 報 を 発 信 する 相 手 を 若 者 に 絞 っている 点 が 今 後 参 考 にな<br />
る点 だと 感 じた。 国 際 文 化 交 流 や 各 国 の 情 報 発 信 の 対 象 や 方 向 性 を 明 確 にすることにより、<br />
相 手 に 合 わせた 内 容 の 情 報 が 提 供 できると 考 える。 漠 然 と 自 国 や 海 外 の 文 化 の 情 報 を 流 す<br />
のではなく、 誰 に、どんな 情 報 を 流 せばいいのかを 考 え、ターゲットを絞 って 活 動 してい<br />
くことも 必 要 だと 考 える。 日 本 も 今 後 参 考 にし、 主 に 学 生 にあたる 若 者 にむけて 事 業 を 展<br />
開 させていくとよいと 考 える。 筆 者 が 若 者 に 絞 る 理 由 は 二 点 あり、 第 一 に 多 くの 学 生 に 早<br />
くから 海 外 への 興 味 を 持 ってもらい、より 多 くの 時 間 を 費 やし 海 外 文 化 への 理 解 を 深 めて<br />
いって 欲 しいからである。 第 二 に、 特 に 今 後 の 国 際 社 会 を 担 っていく 者 がふさわしいと 考<br />
えるからである。 筆 者 は、より 多 くの 学 生 が 自 ら 海 外 文 化 に 対 する 興 味 を 持 ち、その 違 い<br />
の 理 解 に 励 んでいくことが、この 先 続 いていく 国 際 文 化 交 流 の 活 性 化 に 繋 がるのではない<br />
かと 考 える。<br />
第 3 章 政 府 による 国 際 文 化 交 流 機 関 の 市 民 参 加 の 課 題 と 対 策<br />
本 章 では、これまでの 国 際 交 流 基 金 の 活 動 を 通 してみられる、 現 在 の 基 金 の 課 題 と 現 状 、<br />
それに 対 する 対 策 について 論 じていく。 筆 者 は、 今 後 の 主 な 課 題 は、「 市 民 へのアプローチ<br />
の 強 化 」にあると 考 えており、その 理 由 や 具 体 的 な 問 題 点 や 現 状 、および 国 際 交 流 基 金 が<br />
取 るべき 対 策 について 述 べていきたい。<br />
第 1 節 市 民 へのアプローチの 必 要 性<br />
1) 課 題 設 定 の 理 由 : 基 金 での 国 際 学 インターン 12 を 経 験 して<br />
12 国 際 学 インターンとは、 桜 美 林 大 学 の 国 際 学 部 の 正 規 の 科 目 として、 学 部 生 が、 国 際 協<br />
力 、 国 際 交 流 機 関 、 国 際 NGO などの 事 務 所 で、 一 定 期 間 の 就 業 経 験 を 持 つことによって、<br />
16
筆 者 は、 基 金 は 一 般 の 市 民 との 繋 がりや 交 流 が 少 ないのではないかと 考 え、 課 題 を「 市<br />
民 へのアプローチの 強 化 」に 設 定 した。 基 金 は 今 後 、 海 外 だけではなく 日 本 にいる 市 民 、<br />
つまり 私 たちとの 繋 がりを 強 化 させる 必 要 があると 考 える。<br />
この 課 題 は 筆 者 が 大 学 在 学 中 に 経 験 した 基 金 でのインターンで 感 じたことであり、 理 由<br />
は 大 きく 2 つある。<br />
第 1に、 筆 者 は 基 金 という 国 際 文 化 交 流 機 関 を大 学 に 入 って 初 めて 知 った。インターン<br />
に 応 募 しようとするまで、 国 際 文 化 交 流 を 日 本 の 中 心 となっ て 促 進 させている 機 関 がある<br />
ということを 知 らなかった。その 時 、なぜそのような 機 関 が 広 く 私 たち 市 民 に 知 られてい<br />
ないのだと 思 った。そして、 基 金 の 存 在 が 国 民 にあまり 知 られていないことは 問 題 なので<br />
はないかと 強 く 感 じた。もっとより 多 くの 市 民 が 基 金 の 存 在 を 知 り、その 上 で 活 発 に 国 際<br />
交 流 のイベントに 参 加 したり、 海 外 の 文 化 や 人 を 知 ったりできればよいのにと 思 った。 基<br />
金 はもっと 市 民 に 対 して 広 報 活 動 をし、 存 在 をアピールするとよいのではないかと 考 えた<br />
のでこの 課 題 を 設 定 した。<br />
第 2 に、インターンでの 活 動 中 、 市 民 との 交 流 が 少 なかったことを 理 由 に 挙 げたい。<br />
筆 者 は 基 金 のスタッフの 一 員 として、 基 金 が 主 催 する 国 際 美 術 展 のトリエンナーレの 手<br />
伝 いをインターンの 研 修 として 2 週 間 経 験 した。 筆 者 は 横 浜 の 関 内 にあるトリエンナーレ<br />
に 参 加 する 国 内 外 のアーティストの 泊 まるレジデンスの 管 理 の 補 助 をした。<br />
問 題 は、そのレジデンスの 1 階 にある 小 さな 美 術 の 資 料 室 に 一 般 の 人 があまり 入 ってこ<br />
なかったことであった。その 資 料 室 はトリエンナーレや 現 代 アートについて 書 かれている<br />
チラシや 資 料 がたくさんあり、 一 般 の 人 に 開 放 されていた。 筆 者 はそのような 場 所 が 関 内<br />
や横 浜 に 住 む 人 に 基 金 やトリエンナーレを 知 ってもらう 大 きなチャンスであると 思 ってい<br />
た。しかし 筆 者 が 通 っている 期 間 に 一 般 の 人 が 入 ってくることは、とても 少 なかった。<br />
以 上 のようなことを 経 験 し、 今 以 上 に 国 民 に 基 金 の 存 在 を 知 ってもらい、 特 定 の 人 だけ<br />
ではなく、 広 く 一 般 の 市 民 とともに 国 際 文 化 交 流 を 行 っていく 必 要 があるのではないかと<br />
思 った。「 市 民 へのアプローチの 強 化 」を 目 指 していくことで、 日 本 全 体 としての 国 際 文 化<br />
交 流 への 意 識 を 高 めていくことが 大 切 であると 考 える。<br />
2) 国 際 交 流 機 関 の 課 題 と 活 性 化 する 市 民 活 動 の 現 状<br />
次 に、 実 際 に 国 際 文 化 交 流 機 関 が 抱 える 市 民 との 課 題 や、 現 状 についてみていきたい。<br />
(a) 市 民 の 参 加 を 望 む 国 際 交 流 機 関<br />
多 くの 日 本 の 国 際 交 流 機 関 は、「 事 業 への 新 しい 参 加 者 を 増 やす」ということを 現 在 直 面<br />
する 課 題 として 国 際 交 流 基 金 が 実 施 したアンケートに 答 えている 13 。 特 に 回 答 数 の 多 かった<br />
任 意 団 体 に 関 しては、その 課 題 に、「 地 域 住 民 の 関 心 、 参 加 を 向 上 させること」も 同 様 に 課<br />
題 として 重 要 視 している。つまり、 多 くの 機 関 が、 地 域 に住 む 住 民 の 参 加 者 を 増 やし、よ<br />
り 活 発 なイベントの 開 催 を 目 指 そうとしているのがわかる。<br />
このように 非 国 家 レベルの 主 体 も 市 民 の 積 極 的 な 事 業 への 参 加 を 目 指 している。この 課<br />
題 達 成 のためには、まず 政 府 による 主 体 が 市 民 にその 存 在 を 示 し、 日 本 の 国 際 文 化 交 流 の<br />
社 会 観 や 職 業 観 を 養 っていくプログラムである [ 桜 美 林 HP 2006,10,25] 。<br />
13 本 節 のアンケート 結 果 は 国 際 交 流 基 金 (2006)「 国 際 交 流 活 動 団 体 に 関 する 調 査 」の 39<br />
頁 参 照 。アンケートの 対 象 は 日 本 国 内 で 国 際 交 流 活 動 を 行 っている 1982 団 体 である。<br />
17
主 体 の 中 心 となって 市 民 に 各 事 業 への 参 加 などを 呼 びかける 必 要 があるのではないかと 考<br />
える。<br />
(b) 一 般 市 民 中 心 の 国 際 交 流 の 時 代 へ<br />
日 本 の 国 際 文 化 交 流 の 現 状 として、 市 民 が 主 体 となる 方 向 性 があると 考 える。 日 本 の 国<br />
際 文 化 交 流 はこれまで 様 々な 面 で 多 様 化 し 続 けてきた。その 中 でもとくに 変 化 がみられた<br />
のは、その 主 体 である。 戦 後 の 国 際 交 流 の 担 い 手 は 中 央 政 府 とエリート層 に 限 られていた<br />
が、その 後 中 央 から 地 方 へと 担 い 手 の 中 心 は 移 行 した。そして、 地 方 では 地 方 自 治 体 、 企<br />
業 、 財 団 、NGO、 市 民 へと 多 様 化 していった。さらに、 主 体 の 多 様 化 とともに 活 動 内 容 に<br />
も NGO やボランティア 団 体 の 活 発 化 がみられる。 国 際 社 会 のグローバル 化 、 地 球 規 模 の 諸<br />
問 題 の 発 生 とともに、その 解 決 のために 国 境 を 越 えて 市 民 レベルの 主 体 が 連 帯 して 活 動 し<br />
ていく 時 代 となった。そして、その 活 発 化 が、 従 来 の 相 互 理 解 と 友 好 親 善 という 国 際 交 流<br />
から、 課 題 解 決 型 ・ 共 同 作 業 型 の 交 流 へとシフトしている[ 榎 田 2004:20-21]。<br />
このように、 課 題 解 決 や 共 同 作 業 という 形 となっていく 今 、その 主 体 となる 市 民 の 国 際<br />
交 流 への 参 加 がますます 必 要 となってくる。 市 民 が 自 由 に 国 際 交 流 できる 時 代 になってき<br />
た 今 こそ、 海 外 に 対 してだけではなく、 国 際 交 流 基 金 は 第 一 に 日 本 にいる 市 民 に 対 するア<br />
プローチを 強 化 していく 必 要 があるのではないだろうか。<br />
(c) 官 と 民 とのネットワーク 形 成 へ<br />
今 後 国 際 文 化 交 流 を 行 うにあたっては、 官 ( 行 政 )と 民 (NGO や 市 民 )とのパートナー<br />
シップの 構 築 が 望 ましい。 官 と 民 は、お 互 いの 役 割 を 認 識 し、 地 域 の 将 来 を 見 据 えながら、<br />
より 良 い 地 域 社 会 をつくっていくためパートナーになることが 理 想 的 である。 そのために<br />
は、まず 官 と 民 とのネットワークを 形 成 していくことが 望 まれる。ネットワーク 形 成 のた<br />
めには、 何 を 成 し 遂 げたいのかという 社 会 的 使 命 や 大 義 名 分 を 明 確 にする 必 要 がある。 例<br />
としては、 活 動 情 報 の 交 換 、 人 的 交 流 、ノウハウの 相 互 交 換 への 新 しいネットワークのシ<br />
ステムづくりの 可 能 性 を 探 ることが 挙 げられる。そしてネットワークを 形 成 し、 協 働 する<br />
ことでメリットもデメリットもあるという 共 通 の 理 解 も 必 要 となってくる[ 榎 田 2004:23]。<br />
その 他 、それぞれの 役 割 を 考 える 際 に 行 政 にしろ NGO にしろ、 立 場 によって 見 える 世 界<br />
が 違 うことと、 双 方 の 長 所 と 短 所 を 理 解 することも 必 要 となる。たとえば、 政 府 は、 国 益<br />
を 優 先 することを 考 え、NGO は 草 の 根 レベルの 目 線 で 事 業 を 考 える。NGO などの 主 体 の<br />
長 所 としては、 行 政 に 比 べ、 創 造 性 や 柔 軟 性 、より 人 間 的 な 対 応 ができ、ボランタリー 精<br />
神 に 富 んでいる。 短 所 は 組 織 運 営 基 盤 や 財 政 基 盤 が 弱 く、 継 続 性 が 困 難 な 面 もある。それ<br />
ぞれ 違 う 特 徴 をもつ 主 体 がネットワークを 形 成 し、 平 等 な 立 場 でパートナーシップを 築 く<br />
ことが 望 まれ、 新 たな 課 題 となってきている。[ 榎 田 2004:24]<br />
このように、 行 政 と 市 民 はそれぞれの 役 割 をまず 知 り、それぞれに 何 ができるかを 理 解<br />
する 必 要 がある。 行 政 の 機 関 としてできることは、 市 民 が 一 番 身 近 に 地 域 の 国 際 化 を 感 じ、<br />
国 際 交 流 を 柔 軟 に 実 践 していくことができる 大 切 な 存 在 であることを 改 めて 市 民 に 知 らせ<br />
ることであるとも 考 えられる。 行 政 は、 市 民 に 市 民 の 立 場 として、 何 ができ、 何 をすべき<br />
かなどを 伝 えていくことが 可 能 でありより 必 要 になってくるのではないだろうか。<br />
(d)インターネットによる 国 際 交 流 の 市 民 化<br />
日 本 の 国 際 交 流 はインターネットを 通 じて 飛 躍 的 に 変 わってきた。 日 本 の 国 際 交 流 は 政<br />
府 と 企 業 が 中 心 であった 戦 後 の「 国 際 交 流 」から、 現 在 国 際 交 流 の「 草 の 根 化 」「 市 民 化 」<br />
18
へと 変 化 を 始 めている。インターネットの 発 達 により、 世 界 中 どこからでも 情 報 を 入 手 、<br />
発 信 することができ、 無 数 の 市 民 間 の 交 流 、 連 携 が 可 能 になってきている。 新 聞 というコ<br />
ミュニケーションの 手 段 が 国 民 国 家 を 可 能 にしたように、インターネットというコンピュ<br />
ーター・ネットワークが、グローバルな 市 民 社 会 の 基 礎 を 急 速 に 形 成 している。 日 本 の 民<br />
間 の 国 際 交 流 団 体 の 活 用 状 況 としては、まだホームページを 持 っている 団 体 は 少 ない。 今<br />
後 は 国 際 交 流 における 情 報 通 信 技 術 の 活 用 法 に 関 する 研 修 が 必 要 となってくる。 特 に 内 外<br />
の 先 進 事 例 (とくに 姉 妹 都 市 との 関 係 において)の 情 報 交 流 、 相 互 の 学 習 が 必 要 だと 言 え<br />
る[ 榎 田 2004:24-25]。<br />
以 上 のように、インターネットの 普 及 が 進 む 時 代 になったことで、より 情 報 が 手 に 入 り<br />
やすくなっている。 基 金 はこのチャンスをいかし、インターネットを 使 って、より 身 近 に<br />
日 本 の 市 民 に 海 外 の 情 報 を 届 け、 日 本 の 情 報 を 海 外 の 市 民 に 発 信 する 努 力 をすべきである。<br />
すでに 基 金 は 自 身 のホームページを 立 ち 上 げているが、カウンシルのように 若 者 向 けに 新<br />
たにモバイルサイトなども 構 築 すると、より 気 軽 に 国 内 外 の 情 報 を 発 信 できると 考 える。<br />
カウンシルの 実 施 するモバイルサイトとは、 携 帯 からアクセスできる 英 国 関 連 の 情 報 が<br />
見 られるウェブサイト(UK NOW)のことである。このサイトにアクセスすると 英 国 のライ<br />
フスタイルや、 学 生 生 活 、 食 文 化 などの 最 新 情 報 を 見 ることができ、 英 国 の 生 活 文 化 を 気<br />
軽 に 知 ることができる[British Council HP 2006,11.21]。<br />
日 本 の 政 府 による 国 際 文 化 交 流 機 関 もこれに 習 い、 今 まで 以 上 に 市 民 の 日 常 の 中 に 国 際<br />
交 流 情 報 や 自 国 の 文 化 などをより 身 近 に 発 信 させていくとよいのではないだろうか。<br />
(e) 参 加 者 の 固 定 化<br />
国 際 文 化 交 流 のもう 一 つの 問 題 として 国 際 交 流 に 積 極 的 に 参 加 する 人 が 一 部 に 限 られて<br />
いることも 挙 げられる。 時 代 とともに 変 化 してきた 国 際 文 化 交 流 だが、 一 部 の 事 業 は 時 代<br />
の 変 化 に 追 いつけずマンネリ 化 し、 主 体 の 新 陳 代 謝 が 進 まず、その 結 果 主 体 の 高 齢 化 や 組<br />
織 の 弱 体 化 も 生 じてきている。その 背 景 としては、 日 本 人 の 海 外 旅 行 の 日 常 化 や、 地 域 社<br />
会 にすむ 外 国 人 の 増 加 があり、 以 前 より 外 国 人 と 交 流 することへの 自 尊 心 をくすぐる 特 別<br />
な 思 いや 異 文 化 への 好 奇 心 が 薄 れてきている 現 状 がある。つまり、 相 手 に 関 する 関 心 もな<br />
いままに、 地 域 社 会 ではお 互 いが 間 近 で 生 活 しているということである[ 毛 受 2003:40-41]。<br />
このように、かつての 国 際 文 化 交 流 の 魅 力 が 薄 れてきた 今 、 一 般 の 人 々の 異 文 化 に 対 す<br />
る 興 味 を 引 き 出 す 新 しいプログラムの 開 発 が 求 められている。そしてまた、グローバル 化<br />
が 進 む 事 により、これまで 以 上 に 個 人 のレベルでの 異 文 化 コミュニケーション 能 力 が 問 わ<br />
れてきている。 今 後 地 域 社 会 全 体 の 異 文 化 理 解 を 進 めていくには、 対 象 に 合 わせた、とく<br />
に 参 加 者 が 事 業 に 参 加 する 事 で 自 己 の 再 発 見 や 喜 びを 最 大 限 に 引 き 出 しあえるような 事 業<br />
の 展 開 が 必 要 となってくる。そのためには、さまざまなアクター( 活 動 主 体 )による 共 同 キャ<br />
ンペーンや、マスメディアの 活 用 などをより 積 極 的 に 取 り 入 れていくことが 必 要 だといえ<br />
る[ 毛 受 2003:41]。<br />
新 しい 事 業 への 取 り 組 みに 関 しては、 共 同 キャンペーンとして 企 業 や 大 学 と 連 携 して 一<br />
般 市 民 に 海 外 の 生 活 文 化 の 情 報 やイベントの 参 加 を 呼 びかけるとよいと 考 える。とくに 若<br />
者 に 対 してはまずきっかけが 重 要 になってくると 考 えるので、 一 見 国 際 交 流 と 関 係 ないも<br />
のでも、 海 外 の 文 化 を 思 わせるものを 提 供 していくとよい。 例 えば 海 外 の 食 文 化 や 同 世 代<br />
の 中 で 何 が 流 行 り、どのような 毎 日 を 送 っているかという 内 容 から 始 めると、 親 近 感 がわ<br />
19
き 興 味 が 出 てくると 考 える。 今 後 は、より 市 民 に 対 して 日 常 的 な 身 近 な 外 国 人 との 異 文 化<br />
交 流 について 知 らせ、そして 国 内 外 の 文 化 やそれらの 違 いを 知 ることの 面 白 さに 関 して 知<br />
らせていくとよいのではないだろうか。<br />
第 2 節 ワンワールドフェスティバル: 市 民 参 加 と 協 働 の 一 つの 成 功 例<br />
筆 者 は、 以 上 に 述 べた 理 由 から、 今 後 の 基 金 や 行 政 による 国 際 交 流 機 関 は「 市 民 へのア<br />
プローチの 強 化 」が 必 要 であると 考 える。そして、そのために「 市 民 の 参 加 者 増 加 」を 一<br />
番 の 目 的 とした 対 策 を 今 後 目 指 すべきではないかと 考 える。 本 節 では 多 くの 市 民 の 参 加 者<br />
を 得 た 事 業 「ワンワールドフェスティバル」の 成 功 例 を 挙 げ、その 特 徴 をみていき、どの<br />
ような 対 策 を 目 指 していけばよいのかについて 考 えたい。<br />
1)「ワンワールドフェスティバル」について 14<br />
多 くの 市 民 やボランティアとのネットワークを 最 大 限 生 かした「 協 働 」 事 業 として 関 心<br />
を 集 めている「ワンワールドフェスティバル」という 事 業 がある。この「ワンワールドフ<br />
ェスティバル」は、 国 際 協 力 の 催 しとして 毎 年 大 阪 で 開 催 されている 事 業 である。 市 民 に<br />
広 く 国 際 協 力 の 大 切 さを 認 識 してもらい、 活 動 に 参 加 してもらう 機 会 を 提 供 しようとする<br />
目 的 で、ODA の 実 施 機 関 ( 国 際 協 力 機 構 JICA、 国 際 協 力 銀 行 JBIC)、( 財 ) 大 阪 府 国 際 交<br />
流 財 団 、( 財 ) 大 阪 国 際 交 流 センター、 関 西 経 済 4 団 体 などが 実 行 委 員 会 を 結 成 し、1993<br />
年 から 大 阪 城 公 園 や 花 博 記 念 公 園 観 見 緑 地 を 会 場 として 開 催 されている。 企 画 ・ 運 営 は、<br />
関 西 国 際 交 流 団 体 協 議 会 が 同 実 行 委 員 会 から 事 業 受 託 し、 関 西 を 中 心 に 活 動 する NGO や 国<br />
際 交 流 協 会 などで 運 営 委 員 会 を 組 織 して 担 ってきた。1993 年 から 実 施 されてきたこの 事 業<br />
の 主 な 成 果 としては、1 多 数 の 市 民 の 積 極 的 な参 加 、2 多 様 な 団 体 ・ 機 関 が 一 堂 に 会 し、<br />
主 体 的 に 参 加 、3 市 民 ボランティアの 成 熟 と 拡 大 、4 開 催 趣 旨 の 普 及 、5メディアとの 連<br />
携 、6 協 働 の 機 会 づくり、がある。<br />
そしてこのフェスティバルがとくに 評 価 されている 特 徴 としては、 主 体 的 で 多 様 な 実 行<br />
委 員 会 、 運 営 を 支 えるボランティアスタッフ、 企 業 との 連 携 の 3 点 があり、その 特 徴 は 以<br />
下 の 通 りである。<br />
(1) 主 体 的 で 多 様 な 実 行 委 員 会<br />
この 事 業 が 成 果 を 上 げているのは、 熱 意 のある 実 行 委 員 会 のメンバーとボランティアの<br />
運 営 によるものであると 言 える。 事 業 を 担 っている 実 行 委 員 会 は 実 に 多 様 である。 関 西 国<br />
際 交 流 団 体 協 議 会 会 員 をはじめ、 大 きな 政 府 機 関 (JICA,JBIC)から 小 さな 機 関 ( 事 務 所<br />
が 自 宅 という NGO)、 自 治 体 設 立 の 国 際 交 流 協 会 、 大 学 の 付 属 機 関 、 留 学 生 団 体 、 外 国 人<br />
支 援 NPO などというように 多 様 である。この 多 様 性 が 開 催 するプログラムの 内 容 を 豊 かに<br />
し、 幅 広 い 参 加 者 の 促 進 という 成 果 に繋 がっている。 特 にできるだけ 多 くの 団 体 が 会 議 に<br />
参 加 できるよう、 会 議 の 時 間 を 集 まりやすいよう 夜 間 に 設 定 している。この 一 堂 に 会 する<br />
場 をもつことで、 自 分 たちの 活 動 を 新 しい 視 点 で 見 ることができ、 発 想 の 転 換 にも 繋 がっ<br />
ている。<br />
(2) 運 営 を 支 えるボランティアスタッフ<br />
ボランティアの 熱 意 と 働 きもまた、この 事 業 の 支 えであり 成 果 に 繋 がっている。この 事<br />
14 本 節 は 榎 田 勝 利 編 著 (2004)『 国 際 交 流 の 組 織 運 営 とネットワーク』 明 石 書 店 、 第 9 章<br />
を 参 照 。<br />
20
業 に 関 わるボランティアには 多 様 性 があり、リピーターが 多 く、 事 業 参 加 者 が 次 回 ボラン<br />
ティアになるということで 発 展 性 もあることが 特 徴 である。ボランティアに 対 しては 事 前<br />
にフェスティバルの 意 義 や 目 的 を 説 明 し、 理 解 して 参 加 できるように 研 修 を 設 けている。<br />
そして、 参 加 者 の 世 代 も 学 生 からシニアというように 様 々なので、お 互 いの 社 会 経 験 と 力<br />
量 を 発 揮 し、 学 びあえる 機 会 も 多 くなっている。そして 200~300 人 ものボランティアを 主<br />
体 的 に 活 動 させるために、 専 属 のボランティア・コーディネーターを 配 属 しているのも 大<br />
きな 特 徴 である。コーディネーターは 以 前 の 経 験 を 生 かし、 業 務 にあたっている。<br />
(3) 企 業 との 連 携<br />
この 事 業 の 事 業 経 費 の 半 分 は 企 業 や 経 済 団 体 、 国 際 協 力 ・ 交 流 団 体 、 助 成 団 体 などに 協<br />
力 ・ 協 賛 を 依 頼 している。とくに 企 業 に 協 賛 を 依 頼 する 場 合 、「5つのお 願 い」をしている。<br />
その5つとは、1 資 金 的 協 力 、2 活 動 紹 介 ブースへの 出 展 、3 企 画 への 参 画 、4 社 員 ボ<br />
ランティア 参 加 、5 広 報 、である。 出 展 企 業 は 企 業 ごとにブースを 設 け、 社 名 の 看 板 を 掲<br />
げるのではなく、「 環 境 への 取 り 組 み」「 多 文 化 共 生 」などのテーマを 設 定 して、それぞれ<br />
の 取 り 組 みをパネルやスライドで 紹 介 するという「 企 業 枠 」を 超 えた 方 法 を 取 り 入 れてい<br />
る。このような 企 画 への 参 画 では、 企 業 の 社 会 貢 献 担 当 社 員 と 実 行 委 員 の NGO のスタッフ<br />
が 意 見 交 換 を 重 ねながら 取 り 組 んでいる。その 結 果 、 社 会 人 の 事 業 への 参 加 度 が 調 査 でき、<br />
広 報 や 活 動 への 理 解 と 参 加 の 働 きかけに 活 かすことができ、 社 会 人 ボランティアの参 加 の<br />
促 進 につなげる 事 ができている。<br />
第 3 節 望 まれる 国 際 交 流 基 金 の 市 民 参 加 の 対 策 :より 参 加 しやすいボランティア 制 度 と<br />
広 範 囲 な 情 報 提 供 の 実 施<br />
本 章 のこれまでに 述 べてきた 現 状 や「ワンワールドフェスティバル」の 成 功 例 から、 政<br />
府 による 国 際 交 流 機 関 の「 市 民 へのアプローチの 強 化 」の 対 策 として「より 参 加 しやすい<br />
ボランティア 制 度 と 広 範 囲 な 情 報 提 供 の 実 施 」を 挙 げたいと 考 える。 基 金 などが 主 催 する<br />
事 業 にも 市 民 が 気 軽 に 参 加 できるよう、もっとそのボランティア 制 度 や 情 報 提 供 の 改 善 に<br />
力 をいれるべきだと 考 える。 現 在 、 基 金 はすでに「JF ボランティア 制 度 」と「JF サポータ<br />
ーズクラブ」という 二 つの 大 きなボランティア 制 度 を 始 めている。<br />
「JFボランティア 制 度 」とは、 基 金 が 設 けているボランティアの 力 を 借 りて 日 本 と 諸 外<br />
国 との 国 際 文 化 交 流 を 促 進 しようとする 制 度 である。 基 金 はこの 制 度 を 通 して、 一 般 市 民<br />
に 対 し 海 外 の 日 本 語 教 師 の 派 遣 や、 文 化 交 流 企 画 運 営 補 助 などのプログラムの 参 加 を 呼 び<br />
かけている。しかし、そのプログラムの 種 類 をより 一 般 市 民 が 参 加 しやすい 内 容 にする 必<br />
要 があると 考 えた。 同 様 の 制 度 を 持 つ 青 年 海 外 協 力 隊 15は 特 別 な 資 格 がなくても 参 加 できる<br />
スポーツ 交 流 などもある。 基 金 のプログラムも、より 気 軽 に 参 加 しやすいものを 加 えると、<br />
多 くの 人 が 参 加 できるのではないかと 考 える。<br />
一 方 の「JF サポーターズクラブ」とは、 年 会 費 を 払 って 会 員 になり、 国 際 文 化 交 流 の 最<br />
新 情 報 などが 知 れるメールマガジンや 情 報 誌 の 特 典 があり、 様 々な 国 際 交 流 の 活 動 に 参 加<br />
15 青 年 海 外 協 力 隊 とは、 自 分 の 持 っている 技 術 や 知 識 、 経 験 を 開 発 途 上 国 の 人 々のために<br />
活 かしたいと 望 む 青 年 を 派 遣 する JICA の 事 業 である。 派 遣 期 間 は 原 則 として 2 年 間 で、 協<br />
力 の 分 野 は 農 林 水 産 、 加 工 、 保 守 操 作 、 土 木 建 築 、 保 健 衛 生 、 教 育 文 化 、スポーツの 7 部<br />
門 あり、 約 140 種 のプログラムがある[JICA HP 2007,1,11]。<br />
21
できる 制 度 である。しかし、この 制 度 も、 個 人 にむけて 細 かい 情 報 も 届 く 内 容 となってい<br />
るが、あまりその 情 報 が 私 たちに 広 まっていないことが 問 題 であると 考 えた。 様 々な 国 際<br />
交 流 活 動 に 参 加 できるという 情 報 を、より 多 くの 人 に 伝 え、 参 加 しようとするきっかけを<br />
作 っていくと 良 いのではないだろうか。より 市 民 に 身 近 になるには、メディアとしては 前<br />
述 したが、ホームページだけではなく、カウンシルが 活 用 しているモバイルサイトを 使 っ<br />
ての 基 金 の 事 業 やボランティアの 情 報 提 供 などを 試 みるのも 望 ましいと 考 える。<br />
その 他 、 基 金 は 政 府 による 組 織 で、 各 国 際 交 流 団 体 をまとめるという 役 割 ももちろんあ<br />
るが、その 存 在 自 体 をまず 市 民 に 伝 えていき、 市 民 にとっての 身 近 な 存 在 となり、 様 々な<br />
情 報 を 各 団 体 のメディアとなって 市 民 と 繋 っていく 必 要 があると 考 える。 基 金 や 各 団 体 の<br />
ことを 市 民 が 知 らないままでいるのは 国 際 文 化 交 流 の 促 進 にも 国 際 理 解 にも 繋 がらないと<br />
考 える。 基 金 やその 他 の 政 府 による 国 際 文 化 交 流 の 主 体 は「ワンワールドフェスティバル」<br />
のように 企 業 や NGO との 連 携 などを 活 かしながら、 今 以 上 に 広 い 世 代 にわたって情 報 公 開<br />
をしていくとよいのではないかと 考 える。<br />
そして、 何 より 基 金 のような 政 府 による 大 きな 国 際 交 流 機 関 のことをより 多 くの 一 般 市<br />
民 の 人 々に 知 ってもらうことが 大 切 だと 考 える。 今 後 さらに 一 般 市 民 の 国 際 文 化 交 流 事 業<br />
への 参 加 の 通 した「 異 文 化 理 解 の 楽 しさ」を、より 多 くの 人 、とくに 筆 者 と 同 世 代 の 学 生<br />
に 知 ってもらい、 共 に 今 後 の 国 際 社 会 への 若 者 の 参 加 に 役 立 てていけることが 望 ましい。<br />
一 部 の 人 だけではなく、より 広 い 範 囲 で 気 軽 に 国 際 文 化 交 流 、 異 文 化 理 解 をしていくため<br />
にも、 基 金 をはじめとする 大 きな 国 際 交 流 機 関 の 動 きに 期 待 したいと 考 えている。<br />
終 章<br />
本 論 を 通 して、 日 本 の 国 際 文 化 交 流 は 第 二 次 世 界 大 戦 後 、その 主 体 や 活 動 内 容 を 多 様 化<br />
させてきたことがわかった。その 他 、 日 本 の 政 府 による 国 際 文 化 交 流 機 関 である 国 際 交 流<br />
基 金 は 様 々な 事 業 分 野 において、 国 内 外 の 人 々に 情 報 提 供 をしていることや、 同 様 の 機 関<br />
であるブリティッシュ・カウンシルは 独 自 の 事 業 で、 英 語 の 学 習 者 に 対 してインターネッ<br />
トを 使 った 情 報 提 供 に 特 に 力 を 入 れようとしていることなどがわかった。そして、 今 後 の<br />
主 な 課 題 として 挙 げた、 日 本 の 国 際 文 化 交 流 事 業 への 市 民 参 加 の 増 加 に 対 しては、 特 に 若<br />
者 をターゲットにした 広 報 活 動 、 情 報 提 供 の 強 化 が 望 ましいという 考 えを 出 した。 国 際 文<br />
化 交 流 の 主 体 は、 今 や 個 人 のレベルにまで 広 がっており、 一 人 ひとりが 今 以 上 に 国 際 社 会<br />
の 中 に 生 きていると 実 感 すべき 時 代 となった。 今 後 、 日 本 の 政 府 による 国 際 文 化 交 流 機 関<br />
は、その 国 際 文 化 交 流 の 主 役 になる 個 人 一 人 ひとりにむけ 情 報 発 信 し、 私 たちにとってよ<br />
り 身 近 な 存 在 になることが 必 要 であると 考 えた。<br />
今 後 の 研 究 課 題 としては、 国 際 文 化 交 流 活 動 を 実 際 に 行 う 市 民 の 現 状 について 調 査 する<br />
事 を 挙 げたい。 事 業 を 主 催 する 市 民 の 意 見 や 実 態 、その 活 動 内 容 、 課 題 などを 調 べ、より<br />
参 加 しやすい 国 際 文 化 交 流 の 活 動 とは 何 かについて、さらに 研 究 していきたいと 考 える。<br />
そして 筆 者 は、この 研 究 を 通 じ、 今 後 の 日 本 での 国 際 文 化 交 流 を 私 たちにとって 身 近 なも<br />
のにしていき、より 多 くの 人 の 海 外 文 化 への 理 解 に 繋 げていきたいと 考 える。<br />
[ 参 考 文 献 ]<br />
22
榎 泰 邦 (1999)『 文 化 交 流 の 時 代 へ』 丸 善 ブックス<br />
榎 田 勝 利 監 修 (1996)『 国 際 交 流 入 門 』アルク<br />
榎 田 勝 利 編 著 (2004)『 国 際 交 流 の 組 織 運 営 とネットワーク』 明 石 書 房<br />
加 藤 淳 平 (1996)『 文 化 の 戦 略 ― 明 日 の 文 化 交 流 に 向 けて―』 中 央 公 論 社<br />
国 際 交 流 基 金 (1993)『 入 門 国 際 交 流 』 大 阪 国 際 交 流 センター<br />
国 際 交 流 基 金 (1997)『 実 践 国 際 交 流 』 大 阪 国 際 交 流 センター<br />
国 際 交 流 基 金 (2001)『 国 際 交 流 活 動 団 体 に 関 する 調 査 』 国 際 交 流 基 金<br />
国 際 交 流 基 金 (2003)『 主 要 先 進 国 における 国 際 交 流 機 関 調 査 報 告 書 』<br />
国 際 交 流 基 金 (2004)『 調 査 報 告 書 イギリスにおけるパブリックディプロマシー』<br />
国 際 交 流 基 金 (2006)「 国 際 交 流 化 活 動 団 体 に 関 する 調 査 」 国 際 交 流 基 金 報 告 書<br />
毛 受 敏 浩 編 著 (2003)『 草 の 根 の 国 際 交 流 と 国 際 協 力 』 明 石 書 店<br />
[ 参 考 HP]<br />
桜 美 林 大 学 HP (2006、10.25)http://www.obirin.ac.jp/index.html<br />
国 際 交 流 基 金 HP (2006、1,6) http://www.jpf.go.jp/j/index.html<br />
British Council HP (2006、10,25) http://www.britishcouncil. org/jp/japan-uknow.htm<br />
JICA HP(2007,1,11)http://www.jica.go.jp/activities/jocv/index.html<br />
23