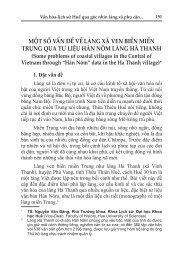慶山林堂遺跡出土古碑の内容とその歴史的背景
慶山林堂遺跡出土古碑の内容とその歴史的背景
慶山林堂遺跡出土古碑の内容とその歴史的背景
- No tags were found...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
慶 山 林 堂 遺 跡 出 土 古 碑 の 内 容 とその 歴 史 的 背 景篠 原 啓 方The Contents of Ancient Imdang Inscription andits Historical BackgroundSHINOHARA HirokataAt the beginning of the 6th century AD, the local communities of Silla weregoverned by local officials dispatched from the six clans of Gyeongju as well as theleading potentates living in these communities. Under such circumstances, inYeongcheon and Daegu, water utilization projects were carried out, led by lower-rankingofficials from the six clans. The ancient Imdang inscription in Gyeongsan, discussed inthis paper, is considered to include records concerning water utilization projects in the6th century. Therefore, the ancient Imdang inscription is worthy of attention as avaluable historical artifact that indicates how a group of central technicians hadpenetrated into local communities, the negotiations these technicians had with localpotentates, and how their techniques had been transmitted. However, the ancientImdang inscription is deemed to have been created by local potentates, and thus haveslightly different characteristics from other artifacts.キーワード: 新 羅 (Silla), 慶 山 (Gyeongsan), 林 堂 (Imdang), 碑 文 (Inscription), 六部 (Yuk-bu[Six Clans]), 中 古 期 (Middle age of Silla Dynasty), 6 世紀 ( 6 th century)はじめに慶 山 の 林 堂 洞 遺 跡 で 十 数 年 前 , 新 羅 時 代 のものと 思 われる 石 碑 が 見 つかった。 林 堂 古 碑 と 呼 ばれているこの 石 碑 は, 発 見 から 久 しいが, 韓 国 においてもあまり 注 目 されてこなかった 1) 。その 原 因 は, 遺 跡 の正 式 調 査 報 告 書 が 未 刊 であったこと,そして 碑 文 の 摩 滅 がひどく 内 容 の 把 握 が 困 難 であったことにあると 思 われる。筆 者 は 十 数 年 前 , 嶺 南 埋 蔵 文 化 財 研 究 院 ( 現 嶺 南 文 化 財 研 究 院 )の 発 掘 現 場 でこの 碑 を 見 学 する 機 会を 得 た。そして 昨 夏 , 今 度 は 調 査 の 名 目 で 同 院 を 訪 れ,その 際 に 碑 に 関 する 原 稿 執 筆 を 依 頼 され, 報 告1) 筆 者 の 知 る 限 りでは, 韓 国 国 内 で 行 われた 2 つの 特 別 展 図 録 に, 同 碑 が 紹 介 されている。 国 立 大 邱 博 物 館 『 押 督 사람들의 삶과 죽음』,2000 年 , 国 立 慶 州 博 物 館 『 文 字 로 본 新 羅 ― 新 羅 人 의 記 録 과 筆 跡 ―』,2002 年459
東 アジア 文 化 交 渉 研 究 第 3 号書 に 簡 単 な 考 察 を 書 かせていただいた 2) 。 本 稿 では,その 考 察 内 容 をもとにやや 踏 み 込 んだ 解 釈 を 加 え,林 堂 古 碑 の 史 的 背 景 に 関 する 私 見 を 述 べてみたい。1 林 堂 洞 遺 跡 について3)一 林 堂 洞 遺 跡 の 沿 革 と 林 堂 古 碑林 堂 洞 遺 跡 は, 慶 尚 北 道 慶 山 市 造 永 洞 522 番 地 一 帯 の 低 丘 陵 地 にある。 慶 山 市 は 洛 東 江 の 支 流 である 琴湖 江 の 中 流 に 位 置 している( 図 1 )。 同 地 域 が 林 堂 宅 地 開 発 事 業 地 区 に 指 定 されたことを 受 け, 開 発 の 事前 調 査 として,1993 年 の 試 掘 の 後 ,1995 年 から 本 格 的 な 発 掘 が 行 われた。 嶺 南 埋 蔵 文 化 財 研 究 院 による調 査 はF~I 地 区 で 行 われ, 石 碑 はI 地 区 において 見 つかった。慶 山 地 域 には 三 国 時 代 の 古 墳 群 が 散 在 しており, 林 堂 洞 遺 跡 には 林 堂 洞 古 墳 群 ( 史 蹟 第 300 号 )・ 造 永洞 古 墳 群 ( 史 蹟 第 331 号 )という, 高 塚 古 墳 と 呼 ばれる 大 型 の 墳 丘 を 有 する 古 墳 群 が 隣 接 している。また近 隣 地 域 には 土 城 や 山 城 が 分 布 している。 慶 山 は 慶 州 から 大 邱 方 面 に 抜 ける 最 も 平 坦 なルート 上 に 位 置しており,ここが 権 力 者 の 拠 点 であるともに 交 通 の 要 衝 であったことをうかがわせる。文 献 史 料 によると,この 地 域 には 押 督 国 があり, 新 羅 の 婆 娑 尼 師 今 の23 年 (102),その 国 王 が 降 伏 を申 し 入 れてきたという 4) 。この 記 事 を 紀 年 どおりに 用 いることはできないが,この 地 に 小 国 とよばれるような 政 治 勢 力 が 存 在 していたことは, 上 記 の 考 古 資 料 からも 明 らかである。林 堂 古 碑 が 見 つかったI 地 区 からは, 三 国 時 代 ~ 統 一 新 羅 時 代 の 住 居 , 溝 状 遺 構 , 建 物 , 竪 穴 , 柱 穴 ,図 1 林 堂 洞 遺 跡 の 航 空 写 真 (Google マップより) 図 2 林 堂 洞 遺 跡 I 地 区( 碑 石 出 土 地 域 のみ。 北 は 上 。 円 内 は, 左 が 井 戸 ・ 園 池 , 右が 建 物 址 , 下 が 排 水 路 と 敷 石 遺 構 )2) 嶺 南 文 化 財 研 究 院 『 慶 山 林 堂 洞 I 地 区 建 物 址 遺 跡 ― 三 国 時 代 ・ 近 代 ―』( 嶺 南 文 化 財 研 究 院 学 術 調 査 報 告 第 153冊 )。 同 報 告 書 は2010 年 3 月 に 刊 行 される 予 定 である( 以 下 、 報 告 書 と 略 称 )。3) 遺 跡 の 概 容 については, 嶺 南 埋 蔵 文 化 財 研 究 院 『 慶 山 林 堂 遺 蹟 現 場 説 明 会 ( 2 次 ) 資 料 』,1996 年 ,および 注 2 の 報告 書 を 参 照 して 作 成 した。4)『 三 国 史 記 』 巻 1 , 新 羅 本 紀 1 。「 秋 八 月 …, 悉 直 ・ 押 督 二 国 王 来 降 」460
慶 山 林 堂 遺 跡 出 土 古 碑 の 内 容 とその 歴 史 的 背 景 ( 篠 原 )園 池 , 井 戸 などが 検 出 された 5) 。 古 碑 はI 地 区 の 西 南 部 にある 排 水 路 ・ 敷 石 遺 構 西 端 の 攪 乱 層 付 近 で 発 見されたという( 図 2 )。 敷 石 遺 構 については, 歩 道 施 設 の 可 能 性 が 指 摘 されている。 周 辺 遺 構 から 出 土 した 土 器 編 年 は 5 世 紀 ~ 9 世 紀 と 幅 広 いが, 中 心 年 代 は 6 世 紀 の 第 1 四 半 期 ~ 7 世 紀 の 第 2 四 半 期 だとされている。2 林 堂 古 碑 の 外 観 と 釈 文碑 石 は 現 存 高 66.7cm, 幅 32.7cm( 最 大 値 ), 厚 さ20.2cm~6.5cm で, 材 質 は 花 崗 岩 系 である( 図 3 ) 6) 。これに 近 い 大 きさの 石 碑 として「 明 活 山 城 作 城 碑 」( 図 4 7) ,551 年 , 高 65cm, 幅 31cm, 以 下 明 活 碑 と 略称 )と「 南 山 新 城 碑 第 3 碑 」( 図 5 8) ,591 年 , 高 81cm, 幅 31cm, 以 下 新 城 3 碑 と 略 称 )があり,いずれも 新 羅 の 都 であった 慶 州 で 発 見 された 6 世 紀 の 石 碑 である。碑 文 が 確 認 されるのは 一 面 のみで,これを 便 宜 上 前 面 としておく。 右 側 面 は 前 面 とほぼ 直 角 をなして図 3 林 堂 古 碑 の 写 真 と 拓 本 ( 注 6 に 出 典 ) 図 4 明 活 山 城 作 城 碑 図 5 南 山 新 城 碑 第 3 碑おり, 面 も 平 らに 整 えた 形 跡 がみられるが, 文 字 は 確 認 できない。いっぽう 左 側 は, 前 面 からゆるやかな 弧 を 描 きつつ 後 面 につながっており, 前 面 と 左 側 面 の 境 界 線 が 不 明 瞭 であるが, 碑 石 の 幅 の 断 面 図 によっておおよその 見 当 がつく( 図 6 ) 9) 。まず 上 部 の 断 面 図 をみると, 上 辺 が 右 から 左 上 に 向 かい, 約 3分 の 1 の 地 点 から 3 分 の 2 の 地 点 までほぼ 水 平 をなし, 左 下 に 弧 を 描 きつつ 下 辺 につながる。また 下 部の 断 面 図 をみると, 上 辺 は 全 体 的 にほぼ 水 平 をなし, 左 端 で 左 下 へと 折 れている。 両 図 面 の 水 平 をなす5) 報 告 書 ( 前 出 )6) 写 真 は 国 立 慶 州 博 物 館 『 文 字 로 본 新 羅 』( 特 別 展 図 録 ),2002 年 , 拓 本 は 報 告 書 ( 前 出 )7) 国 立 慶 州 博 物 館 ( 前 出 書 )8) 国 立 慶 州 博 物 館 ( 前 出 書 )9) 報 告 書 ( 前 出 )461
慶 山 林 堂 遺 跡 出 土 古 碑 の 内 容 とその 歴 史 的 背 景 ( 篠 原 )図 7 林 堂 古 碑 下 面 図 8 林 堂 古 碑 上 面このように 碑 石 は, 様 式 においては 6 世 紀 の 新 羅 碑 に 類 例 が 多 く,また 下 部 の 損 壊 の 可 能 性 を 残 しているが, 碑 文 が 刻 まれた 面 が 大 きく 損 なわれた 可 能 性 は 低 いものと 思 われる。筆 者 による 林 堂 古 碑 の 釈 文 は 次 の 表 のとおりである。前 述 のように 碑 文 の 範 囲 は 現 存 の 前 面 の 中 に 収 まっていたと 考 えられるが, 摩 滅 や 剥 落 による 脱 漏 の有 無 を 確 認 しておく 必 要 がある。まず 前 面 の「 竢 」( 3 —1)と「 壹 」( 4 —1)の 上 部 は 碑 文 面 よりも 一 段 高 くなっており 10) ,その 表 面 は 碑 文 面 より 粗 く 文 字 の 痕 跡 も 確 認 されない。そのため 碑 文 の 各 行 は, 上 記 の 2 文 字 より 上 から 始 まる 可 能 性 は 低 いものと 判 断 される。また 下 部 については 前述 のように, 3 —13より 下 には 字 画 が 確 認 されない。 下 部が 地 中 に 埋 められた 可 能 性 を 考 慮 すると,これより 下 に 文字 はなかったと 考 えて 問 題 なかろう。次 に 碑 文 の 開 始 部 分 であるが, 第 1 行 に「 日 」( 1 —7)が 確 認 される。この「 日 」が 日 付 にかかわる 内 容 だとすれば,この 上 部 に 干 支 年 , 某 月 , 某 ( 日 )の 語 が 入 ることになり, 少 なくとも 6 文 字 分 の 空 間 が 必 要 となるが 11) , 第 3 ,第 4 行 との 比 較 でみると,「 日 」はほぼ 第 7 文 字 目 にあたる。いわゆる 新 羅 の 中 古 期 ( 6 世 紀 初 ~ 7 世 紀 中 葉 )に 製作 された 碑 文 は 第 1 行 の 冒 頭 に 干 支 年 の 入 る 例 が 多 く, 林堂 古 碑 の 右 端 の 行 もまた 碑 文 の 開 始 行 であり 日 付 が 記 されていたと 考 えて 問 題 なさそうである。なお「 日 」の 下 部 に表 1 林 堂 古 碑 の 釈 文4 3 2 1壹 竢 * 1借 起 * 2□ 任 * 3之 * 習 * 4令 * □ 者 * 5右 斯 □ 6尺 佊 論 日 7己 洹 * 8□ 百 * 9□ 亻土□ * 10□ 柯 * 得 * 11其 与 □ 12□吉13〈 凡 例 〉・* は 文 字 の 残 画 をもとに 推 読 した 文 字・□は 文 字 の 跡 が 確 認 されるが 不 明 の 文 字は 字 画 とおぼしき 痕 跡 もあり, 第 1 行 はさらに 下 へと 続 いていた 可 能 性 がある。碑 文 の 最 終 行 については, 第 4 行 が 手 がかりとなる。 第10)これは 碑 石 高 の 断 面 図 からも 確 認 される。11) 干 支 年 を 干 支 のみであらわす 事 例 を 考 慮 すると 5 文 字 の 可 能 性 もある。463
東 アジア 文 化 交 渉 研 究 第 3 号4 行 は, 4 —1~7にかけてはほぼまっすぐに 文 字 が 刻 まれてはいるが, 第 3 行 との 間 がしだいに 広 がっていく( 図 3 )。そして 下 部 に 至 ると, 第 3 行 にかなり 近 接 した 位 置 に 文 字 が 刻 まれている( 4 —11~12)。この 4 —11~12の 上 部 にも 字 画 と 思 われる 跡 があるが, 4 —7と 3 —7の 間 にある 幅 は 一 文 字 分 もなく,また 文 字 の 痕 跡 もない。したがって 下 部 の 文 字 は 4 —7とつながる 語 句 ( 第 4 行 目 )とみて 間 違 いない。このように 第 4 行 がまっすぐに 刻 めなかったのは,まず 4 —7の 次 に 文 字 を 刻 む 空 間 がなかったことに起 因 する。これはつまり 前 面 の 左 側 , 少 なくとも 碑 文 が 刻 まれるべき 面 が 製 作 当 時 から 現 在 のような 形態 であったことを 意 味 する。そしてもう 一 つは, 4 —1~7の 方 向 が 左 にずれたためである。 碑 文 を 刻 むにあたっては, 刻 字 における 失 敗 を 避 けるため,まず 碑 面 に 朱 液 などを 使 って 文 字 を 書 く( 朱 書 , 丹 書 )ことが 多 いが, 丹 書 をなぞるように 字 を 刻 んでも 失 敗 する 例 はあったであろう。だがここでの 失 敗 は,書 体 ではなく 行 の 方 向 そのものにある。 丹 書 の 目 的 が 第 3 , 4 行 を 縦 にそろえずに 書 くことだったとは考 えられず,だとすればやはり 刻 字 に 際 して 丹 書 そのものが 存 在 しなかった 可 能 性 を 考 えるべきであろう。 丹 書 の 工 程 を 認 めるとしても, 本 来 の 役 割 や 意 味 が 無 視 されたことになり, 知 識 や 技 術 の 拙 さを 指摘 せざるをえない。いずれにせよ 下 部 においては 第 4 行 の 次 には 行 が 存 在 しなかったと 考 えてよい。 第4 行 の 上 部 も「 壹 」( 4 —1),「 借 」( 4 —2)の 左 には 文 字 の 痕 跡 が 確 認 できない。これらの 点 から, 林堂 古 碑 の 碑 文 は 全 四 行 で 構 成 されているとみてほぼ 問 題 ない。以 上 のように 碑 文 の 範 囲 が 特 定 できるならば, 碑 文 の 本 来 の 文 字 数 は 前 掲 の 釈 文 表 にほぼ 収 まることになろう。したがって 林 堂 古 碑 の 総 字 数 は 一 行 13 字 前 後 × 4 行 となる。ところでこの 字 数 は,ほぼ 同 じ 大 きさの 石 碑 にくらべるとかなり 少 ない。 前 述 の 明 活 碑 は 一 行 22 字 ( 最大 )× 9 行 ( 計 147 字 )と 林 堂 古 碑 の 3 倍 弱 , 新 城 3 碑 は 一 行 23 字 ( 最 大 )× 6 行 ( 計 118 字 )と 2 倍 強 ある。この 2 つの 碑 が 古 碑 にくらべ 多 くの 文 字 を 配 することができたのは, 碑 文 面 のほぼ 全 体 を 水 平 に 整え, 文 字 を 小 さく 整 然 と 刻 んだからである( 図 4 , 5 )。これに 対 し 林 堂 古 碑 は, 画 数 が 多 ければ 文 字 が 大 きくなり, 少 なければ 小 さくなる 傾 向 にある。これは 縦 横 ( 行 と 列 )をそろえることが 念 頭 に 置 かれていなかったためと 思 われる。 丹 書 がほどこされなかった 可 能 性 が 高 いことを 考 えると, 文 字 のバランスの 悪 さは 当 然 ともいえよう。 明 活 碑 と 新 城 3 碑 の 製作 工 程 に 丹 書 が 存 在 したとは 断 定 できないが,あったとすれば 碑 文 製 作 の 知 識 や 工 程 において,なかったとしても 刻 字 の 技 術 において 林 堂 古 碑 との 格 差 が 存 在 したことになり, 両 者 の 優 劣 は 明 らかである。なお 筆 画 の 場 合 , 林 堂 古 碑 には 楷 書 ・ 隷 書 の 影 響 がともにみられるが, 刻 字 技 術 の 未 熟 さを 考 慮 すると筆 画 から 書 体 を 特 定 するのは 困 難 に 思 われる。以 上 , 林 堂 古 碑 の 製 作 技 術 と 書 体 , 刻 字 について 考 察 した 結 果 , 林 堂 古 碑 は 6 世 紀 の 石 碑 との 類 似 性をもつが, 慶 州 の 諸 碑 にくらべ 石 碑 製 作 の 知 識 や 技 術 が 低 いことが 分 かった。ただ 林 堂 洞 遺 跡 の 位 置 する 慶 山 と 新 羅 の 都 であった 慶 州 との 距 離 を 考 えると, 文 化 の 伝 播 に 大 きな 時 間 差 は 想 定 しがたい。したがって 製 作 技 術 面 のみからいえば, 古 碑 の 年 代 は 6 世 紀 代 とみておおよそ 無 理 がないものと 思 われる。二 碑 文 の 内 容碑 文 は 文 字 数 が 少 なく 判 読 も 困 難 であり, 前 後 の 文 脈 がとりにくい。そのためここでは 判 読 が 確 実 な464
慶 山 林 堂 遺 跡 出 土 古 碑 の 内 容 とその 歴 史 的 背 景 ( 篠 原 )語 を 中 心 に, 推 読 された 文 字 によって 文 脈 を 再 構 成 し, 全 体 像 の 復 元 を 試 みたい。前 述 のように, 碑 文 の 文 字 総 数 は 一 行 13 字 × 4 行 前 後 であった 可 能 性 が 高 く,この 短 い 碑 文 の 中 に 日付 , 主 体 , 行 動 ,そしてその 結 果 が 盛 り 込 まれていることになる。ならばその 叙 述 には 修 辞 などが 入 る余 地 がほとんどなく, 簡 略 ・ 単 純 なものであった 可 能 性 が 高 い。1 行 動行 動 に 関 する 内 容 としてまず 注 目 されるのは「 論 」( 2 —7, 図 9 )である。これは, 碑 文 においてある 主 題 について 論 じたという 内 容 があったことを 意 味 している。「 論 」の 字 は「 迎 日 冷 水 里 新 羅 碑 」(503年 , 以 下 冷 水 碑 と 略 称 )においても 確 認 される( 図 10)。 冷 水 碑 においては,「 節 居 利 」なる 人 物 の 財 産相 続 をめぐり,「 葛 文 王 」 12) をはじめとする 新 羅 六 部 の 代 表 者 7 人 が 協 議 し 13) , 相 続 人 を 決 定 , 宣 布 するという 内 容 が 登 場 する 14) 。つまり 冷 水 碑 の「 論 」とは, 碑 文 の 内 容 の 核 心 ( 新 羅 六 部 の 判 決 )を 導 き 出 すための 過 程 であった。 林 堂 古 碑 の「 論 」は 碑 文 の 前 半 部 に 登 場 するが, 碑 文 の 短 さを 考 えると「 論 」と 無関 係 な 内 容 が 間 に 割 り 込 む 余 地 はあまりないと 考 えられ, 後 半 部 は「 論 」の 結 果 に 関 係 する 内 容 である可 能 性 が 高 い。だとすれば, 林 堂 古 碑 における「 論 」もまた, 碑 文 の 核 心 となる 主 題 を 導 き 出 す 前 段 階と 理 解 して 問 題 なかろう。そのように 考 えると, 次 に 登 場 する 内 容 は,その「 論 」の 対 象 ということになろう。 論 の 次 の 文 字 は,左 偏 はさんずい( 氵 )とみてほぼ 間 違 いないと 思 われるが, 右 偏 は 残 画 から 確 定 するのは 困 難 である。試 釈 には「 水 の 流 れるさま」の 意 である「 洹 」( 2 —8)をあげているが,「 洄 」(さかのぼる,めぐり 流れる),「 洰 」( 水 中 に 物 が 多 くあるさま),「 泗 」( 川 の 名 ),「 河 」( 川 ),「 洒 」( 洗 う, 注 ぐ, 深 い)なども 候 補 としてあげておきたい。これらはいずれも 水 に 関 係 するもので, 周 辺 の 河 川 や 検 出 遺 構 ( 排 水 路 ,図 9 林 堂 古 碑 の「 論 」 図 10 迎 日 冷 水 里 新 羅 碑12) 葛 文 王 とは, 当 時 の 新 羅 君 主 ( 寐 錦 , 王 )につぐ 地 位 にあった 者 の 称 号 で, 王 の 父 や 王 妃 の 父 が 選 ばれた。13) 沙 喙 至 都 盧 葛 文 王 , 徳 智 阿 干 支 , 子 宿 智 居 伐 干 支 , 喙 尒 夫 智 壹 干 支 , 只 心 智 居 伐 干 支 , 本 彼 頭 腹 智 干 支 , 斯 彼 暮 智干 支 , 此 七 王 等 共 論 教 用 …( 前 面 3 —9~ 7 —9)14) 冷 水 碑 は1989 年 3 月 に 慶 尚 北 道 迎 日 郡 ( 現 浦 項 市 ) 神 光 面 で 発 見 された。 詳 しい 内 容 については 韓 国 古 代 史 研 究 会『 韓 国 古 代 史 研 究 』 3 ( 迎 日 冷 水 里 新 羅 碑 特 集 号 ),1990 年 を 参 照 。465
東 アジア 文 化 交 渉 研 究 第 3 号土園 池 )との 関 係 も 想 定 しておく 必 要 があろう。 続 く「 百 □ 得 」( 2 —9~11)については 定 かではないが,「 得 」は「 永 川 菁 堤 碑 」(536 年 , 以 下 菁 堤 碑 と 略 称 )において 長 さの 単 位 としての 使 用 例 がある 15) 。これについては 後 述 する。論 をへた 後 に 登 場 するのはその 結 果 に 関 する 内 容 であろう。それを 示 唆 する 文 字 としては「 与 」( 3 —12),「 借 」( 4 —2),「 令 」( 4 —5)がある。 与 は「 与 える」や 並 立 助 詞 (~と), 借 は「 借 りる」などと解 釈 されるが, 前 後 の 文 脈 がまず 把 握 されねばならない。「 令 」は 使 役 の 動 詞 と 考 えられるが, 字 形 からいえば「 今 」の 可 能 性 もあり 断 定 しがたい。このように 碑 文 は, 水 にかかわる 内 容 が「 論 」じられ,それを 受 けて 何 らかの 決 定 が 下 された 内 容 がおぼろげながら 浮 かんでくる。これらを 念 頭 におきつつ, 次 に 主 体 ( 登 場 人 物 )についてみていきたい。2 主 体 ( 登 場 人 物 )登 場 人 物 との 関 係 でまず 注 目 されるのが「 斯 佊 」( 3 —7)である。 斯 佊 は 冷 水 碑 に 登 場 する「 斯 彼 」( 前 面 6 —8~9)と 同 じものであり, 新 羅 の 六 部 16) の 一 つである 習 比 部 を 指 す。 冷 水 碑 の「 斯 彼 」は,いわゆる 新 羅 の 中 古 期 に 登 場 する 習 比 部 の 唯 一 の 実 例 であり, 碑 文 に 登 場 する 習 比 部 出 身 の「 斯 彼 暮 智干 支 」は, 碑 文 において「 七 王 」( 前 面 7 —3~4)とされる 六 部 の 代 表 者 のひとりであった。中 古 期 の 金 石 文 には, 人 名 の 列 記 においても 六 部 の 優 劣 が 明 確 にあらわれている。 喙 部 や 沙 喙 部 は 新羅 の 君 主 と 深 い 関 係 にあり, 高 位 官 人 の 出 身 としても 登 場 頻 度 が 高 く, 彼 らの 名 は 六 部 人 名 の 列 記 に 際してもほぼ 一 番 目 に 登 場 する。このように 2 つの 部 は 6 世 紀 初 においてすでに 六 部 の 中 心 勢 力 であった。それ 以 外 の 部 としては, 本 彼 ( 波 )が 5 例 , 岑 喙 が 2 例 , 斯 佊 は 1 例 が 確 認 され, 漢 祇 ( 韓 岐 , 漢 只伐 )はいまだ 実 例 の 報 告 がない。このように 習 比 部 の 地 位 は, 当 時 の 六 部 においてそれほど 高 くなかったものと 考 えられるが, 林 堂 古 碑 により 1 例 があらたに 加 わった 意 義 は 大 きいといえよう。いっぽう 習 比 部 の 異 表 記 については, 慶 州 の 雁 鴨 池 と 月 城 で 見 つかった 統 一 新 羅 時 代 ( 6 世 紀 後 葉 ~15) 塢 □ 六 十 一 得 , 鄧 九 十 二 得 , 汨 広 卅 二 得 , 高 八 得 , 上 三 得 , 作 人 …( 2 —1~ 3 —12)。 釈 文 は 朱 甫 暾 「 永 川 菁 堤 碑 」『 譯 註 韓 國 古 代 金 石 文 Ⅱ』( 新 羅 ・ 加 耶 篇 ), 駕 洛 國 史 蹟 開 発 研 究 院 ,1992 年 )によった。16) 朝 鮮 の 古 代 社 会 には「 部 」と 呼 ばれる 小 規 模 の 政 治 集 団 があり,それらが 離 合 集 散 を 繰 り 返 しつつ 古 代 国 家 へと 成長 していったことが 指 摘 されている。 盧 泰 敦 「 三 国 時 代 의 「 部 」에 関 한 研 究 — 成 立 과 構 造 를 中 心 으로—」(『 韓 国史 論 』 2 ,서울대학교 한국사학회,1975 年 )。 新 羅 においては 六 部 と 呼 ばれる 6 つの 有 力 集 団 を 中 心 に 国 家 が 形 成されていった。『 三 国 史 記 』を 基 準 に 六 部 の 表 記 をまとめると 以 下 の 表 のとおりである。資 料 名 資 料 の 成 立 年 代 楊 山 部 高 墟 部 大 樹 部 干 珍 部 加 利 部 明 活 部中 古 期 碑 文 6 C 初 ~ 7 C 中 葉 喙 沙 喙岑 喙牟 喙本 波 ( 彼 )斯 彼日 本 書 紀 720 年 㖨 沙 㖨 習 部三 国 史 記 ( 異 表 記 )1145 年 梁 部 牟 梁 部漢 岐 部漸 梁 部漢 祇 部牟 梁 部韓 岐 部三 国 遺 事 13 世 紀 後 半及 梁 部漸 梁 部沙 梁 部沙 涿漸 涿本 彼 部 韓 岐 部 習 比 部雁 鴨 池 出 土 塼 銘 調 露 二 年 (680) 漢 只 伐 部雁 鴨 池 出 土 瓦 銘 同 上 か?習 部習 府466
慶 山 林 堂 遺 跡 出 土 古 碑 の 内 容 とその 歴 史 的 背 景 ( 篠 原 )図 11 「 習 部 」「 習 府 」 銘 瓦 図 12 林 堂 古 碑 の「 竢 」935 年 )の「 習 部 」・「 習 府 」 銘 の 瓦 ( 図 11) 17) がある。 文 献 史 料 における 習 比 部 の 表 記 は 統 一 新 羅 期 のものに 近 く, 林 堂 古 碑 の「 斯 佊 」は 冷 水 碑 に 近 い。これは 林 堂 古 碑 の 製 作 年 代 が 早 ければ 6 世 紀 前 半 までさかのぼる 可 能 性 もあることを 示 唆 する。この 斯 佊 とともに 注 目 されるのが「 竢 」( 3 —1, 図 12)である。「 竢 」は 右 下 の 部 分 が 剥 落 してしまっているが、 字 形 からみて 喙 に 近 く, 六 部 の 一 つである 喙 部 を 指 す 字 と 判 断 される 18) 。 六 部 の 表 記 の 順 においても「 竢 」は「 斯 佊 」より 先 行 しており, 他 の 金 石 文 資 料 とも 矛 盾 しない。そのように 考 えると,「 竢 」と「 斯 佊 」の 間 に 入 る 4 文 字 ( 3 —2~5)は, 喙 部 出 身 者 の 人 名 にかかわるものになろう。 中 古 期 の 金 石 文 資 料 においても 4 文 字 を 超 える 人 名 ( 出 身 部 や 官 職 ・ 官 位 を 除 く)はほとんどみられず, 同 碑 の 表 記 もまたこれらと 矛 盾 しない。そのように 考 えれば, 斯 佊 の 人 名 もおおよそ 4 文 字 以 内 に 収 まる 可 能 性 が 高 いものと 思 われる。こうした 理 解 に 大 過 なしとすれば,「 斯 佊 己 □□ 亻 柯 」の 次 に 登 場 する「 与 」( 3 —6)の 解 釈 において 人名 を 考 慮 する 必 要 がなくなり, 前 述 した 二 通 りの 解 釈 をあてはめることができよう。まず「 与 える」の意 で 解 釈 した 場 合 , 与 の 前 に 登 場 する 六 部 の 人 物 が 主 語 となり, 彼 らが 何 かを「 与 える」 相 手 が 存 在 したことになる。 次 に 並 立 助 詞 として「~と」と 解 した 場 合 も, 六 部 の 人 物 とは 別 の 人 物 が 登 場 することになる。いずれの 場 合 にも, 六 部 とは 別 の 人 物 が 碑 文 に 登 場 することになる。吉ならば 彼 らの 名 は「 与 」から 碑 文 末 尾 にかけて 記 されていたことになろう。その 釈 文 は「□ 壹 借 □ 之令 右 尺 …□ 其 」であるが, 判 読 不 能 な 2 文 字 を 除 けば 竢 や 斯 佊 といった 六 部 を 指 す 語 は 登 場 しない。 金石 文 資 料 においては 六 部 出 身 者 に 部 名 を 冠 するのが 通 例 であり,それが 存 在 しない 以 上 , 彼 らを 六 部 出身 者 とはみなしがたく, 現 地 人 ,さらにいえば 林 堂 地 域 の 在 地 勢 力 だと 考 えるべきであろう。「 与 」 以 下に 収 まるのはおよそ10~13 文 字 であり,これらがすべて 人 名 だとは 考 えにくいが, 在 地 勢 力 の 人 名 が 複17) 国 立 慶 州 博 物 館 ( 前 出 書 )18) 竢 は 注 16の 表 のように 喙 や 涿 でも 表 記 される。すべて 発 音 が 異 なるが, 当 時 は 同 音 の 異 表 記 として 用 いられていた可 能 性 が 高 い。 中 古 期 の 金 石 文 において 最 も 多 く 登 場 するのは 喙 であるが, 啄 や 㖨 にみえる 字 も 登 場 する。 本 稿 では 林 堂 古 碑 文 の 引 用 に 際 しては「 竢 」を,それ 以 外 では 喙 を 用 いることにする。467
東 アジア 文 化 交 渉 研 究 第 3 号数 登 場 している 可 能 性 は 十 分 ある。最 後 に 考 えておきたいのは,「 論 」の 主 体 である。 彼 らの 名 は 剥 落 によって 確 認 できないが, 論 の 結 果が 六 部 の 官 人 と 関 係 しているとすれば, 彼 らの 行 動 について 論 じることのできる 存 在 としては, 碑 文 の六 部 人 より 高 位 の 地 方 官 ,もしくは 在 地 の 有 力 勢 力 ( 村 主 ) 19) などが 想 定 できる。ただ 在 地 勢 力 は 現 地 において 六 部 人 を 凌 駕 する 権 限 を 有 していたとは 考 えられても, 王 京 ( 都 である 慶 州 )から 派 遣 された 六部 官 人 の 行 動 に 対 する 決 定 権 ・ 命 令 権 を 独 自 に 行 使 できたとは 考 えがたく,いかなるかたちであれ, 六部 人 が 論 の 主 体 としてかかわっていたと 考 えて 問 題 はなかろう。既 存 の 金 石 文 資 料 に 類 例 を 求 めれば, 冷 水 碑 の 例 のごとく, 六 部 の 最 高 権 力 者 集 団 もしくは 君 主 ( 寐錦 王 )などがまず 想 起 されよう。だが 石 碑 の 製 作 技 術 や 書 体 の 粗 雑 さ, 記 述 の 少 なさなどからすると,碑 文 の 内 容 は 彼 らが 直 接 主 管 する 国 家 事 業 とは 考 えがたく, 彼 らの 名 が 入 る 可 能 性 は 低 いものと 思 われる。次 の 候 補 として, 論 の 後 に 登 場 する 六 部 官 人 や 在 地 勢 力 があげられる。この 場 合 , 論 の 主 語 と 後 の 内容 の 主 語 が 同 一 人 物 になるわけであるが,この 短 文 の 中 に 同 一 人 名 が 再 度 登 場 するというのはやはり 疑問 が 残 る。また 論 とその 後 の 行 動 の 主 語 が 同 じであれば,わざわざ 論 という 行 為 そのものを 記 録 する 必要 があったとも 考 えられない。これらの 点 を 考 慮 すると, 論 の 主 体 は,これまでにあげた 登 場 人 物 とは別 に 考 える 必 要 があろう。碑 文 第 2 行 目 の「 論 」の 上 部 には 6 文 字 ほどが 収 まると 思 われ,ここに 六 部 人 の 名 が 入 ることになるが, 問 題 は 人 数 である。「 論 」とは 基 本 的 に 1 人 ではなく 複 数 の 人 物 によって 行 われるものであるから,論 の 主 体 として 2 人 以 上 の 人 物 が 想 定 されなければならない。 金 石 文 資 料 においては, 同 じ 部 の 出 身 者であれば 2 人 目 以 降 は 部 名 が 省 略 される 例 もあるため 不 可 能 ではないが,やや 無 理 があるのも 事 実 である。 第 1 行 の「 日 」の 下 に 文 字 の 痕 跡 があることはすでに 指 摘 したとおりであるが, 第 2 行 に 人 名 が 収まりきらないのであれば, 第 1 行 から「 論 」にかかわる 人 名 が 列 記 されていたと 考 えるべきであろう。碑 文 の 配 置 からみて「 日 」と「 論 」の 間 に 入 る 文 字 は10~12 字 ほどになる。 林 堂 古 碑 の 人 名 表 記 によると 六 部 官 人 の 表 記 は 1 人 5 ~ 6 文 字 であり,おおよそ 2 人 が 収 まるものと 思 われるが, 在 地 勢 力 の 存 在を 考 慮 すると 3 人 の 可 能 性 もある。以 上 のように, 碑 文 はおおよそ(A) 六 部 の 地 方 官 がある 主 題 について 協 議 (「 論 」)し( 1 ~ 2 行 ),(B)その 論 をへて 六 部 ( 喙 部 , 習 比 部 )の 官 人 が 在 地 勢 力 となんらかの 関 係 を 結 んだ、もしくは 共 同 で作 業 した( 3 ~ 4 行 )-という 2 つの 内 容 で 構 成 されている。そして 論 やその 後 の 行 動 は、 水 に 関 する内 容 にかかわるものと 考 えられる。19) 村 主 とは 在 地 勢 力 の 長 に 与 えられる 官 職 の 一 種 である。 彼 らは 王 京 ( 都 である 慶 州 ) 人 とは 区 別 され, 王 京 人 の 京位 に 対 し, 外 位 と 呼 ばれる 別 の 体 系 をもった 官 位 を 与 えられていた。 外 位 は 6 世 紀 から 金 石 文 に 登 場 し, 7 世 紀 以降 ,しだいに 京 位 の 授 与 へと 転 換 していったが, 村 主 の 号 はそれ 以 降 も 用 いられた。 村 主 や 外 位 に 関 する 研 究 は 多いが, 代 表 的 なものに 村 上 四 男 「 新 羅 外 位 小 考 」(『 朝 鮮 古 代 史 研 究 』, 開 明 書 院 ,1979 年 ), 三 池 賢 一 「「 三 国 史 記 」職 官 志 外 位 条 の 解 釈 - 外 位 の 復 原 」(『 北 海 道 駒 澤 大 研 究 紀 要 』 5 ,1970 年 ), 権 悳 永 「 新 羅 外 位 制 의 成 立 과 機 能 」(『 韓 国 史 研 究 』50・51 合 ,1985 年 ), 河 日 植 「 外 位 制 의 整 備 와 展 開 過 程 」(『 新 羅 集 権 官 僚 制 研 究 』, 慧 眼 ,2006 年 )などがある。468
慶 山 林 堂 遺 跡 出 土 古 碑 の 内 容 とその 歴 史 的 背 景 ( 篠 原 )三 立 碑 の 主 体 と 立 碑 の 背 景1 立 碑 の 主 体石 碑 を 製 作 し, 立 てた 人 物 としてまずあげられるのは 碑 文 の 登 場 人 物 である。 彼 らについては, 前 半部 ( 論 の 主 体 )と 後 半 部 ( 論 の 決 定 事 項 を 実 行 する 六 部 人 と 在 地 勢 力 )に 分 けられる。 立 碑 の 実 行 者 としては 実 務 にかかわる 後 者 とみるのが 妥 当 にも 思 われるが, 必 ずしも 両 者 の 共 同 製 作 とは 限 らない。前 述 のように, 碑 石 の 製 作 技 術 ・ 書 体 ・ 刻 字 技 術 は 中 古 期 の 慶 州 のものにくらべると 粗 雑 であり, 在地 勢 力 による 製 作 の 可 能 性 があるが,これは 碑 文 の 人 名 表 記 からもうかがえる。 一 般 的 に 中 古 期 の 金 石文 においては「a 阿 良 邏 頭 b 沙 喙 c 音 乃 古 d 大 舎 」(「 南 山 新 城 碑 第 1 碑 」 2 —15~ 3 —5,591 年 )や「b喙 部 c 伊 史 夫 智 d 伊 干 支 」(「 丹 陽 新 羅 赤 城 碑 」 1 —13~ 2 —1, 6 世 紀 中 葉 )の 例 のごとく, 人 名 は 官 職(a), 所 属 部 (b), 名 前 (c), 官 位 (d)の 順 に 表 記 される 20) 。 官 職 が 記 されない 人 物 は 少 なくないが, 官 位 が 省 略 されることはほとんどない。これに 対 し 林 堂 古 碑 の 六 部 人 の 表 記 である「 竢 起 任 習 □ 者 」( 3 —1 ~ 5), 「 斯 佊 己 □□ 亻 柯 」( 3 —6 ~ 11)は, 部 名 から 始 まり,dと 思 われる 表 現 はみられない 21) 。aについては「 竢 」の 前 に 冠 されていた 可 能 性も 皆 無 ではないが, 現 在 のところ 得 の 字 を 含 む 新 羅 の 官 職 は 例 がなく,だとすると「 得 」( 2 —12) 以 下の 2 文 字 に 官 職 が 入 ることになる。「 論 」にかかわる 内 容 が 入 る 可 能 性 も 考 慮 すると 第 3 行 に 続 く 官 職 名があったとも 考 えがたい。ただこれに 関 しては, 前 述 のごとく 官 職 が 記 されない 人 名 も 少 なくないため,とりたてて 問 題 視 する 必 要 はない。いっぽうdの 官 位 についてはやはり 問 題 が 残 る。 彼 らは 六 部 人 として 同 地 域 に 派 遣 されてきたのであり, 当 然 ながら 京 位 の 所 持 者 だと 考 えられるが 22) , 上 記 の 人 名 にはそれとおぼしき 表 記 がない。これについては1 官 位 ( 地 位 )をもたない 人 物 であった 可 能 性2 官 位 ( 地 位 )の 表 記 に 通 常 とは 異 なるものが 用 いられた 可 能 性3 書 き 忘 れという 3 つの 可 能 性 が 想 定 される。1は 冷 水 碑 においても 六 部 人 の 中 に 官 位 が 表 記 されない 人 物 が 登 場20) 人 名 表 記 法 については 金 昌 鎬 「 新 羅 中 古 金 石 文 의 人 名 表 記 ( 1 )・( 2 )」(『삼국시대 금석문 연구』, 書 景 文 化 社 ,2009 年 )を 参 照 されたい。21)「 斯 佊 己 □□ 亻 柯 」の 次 にくる「 与 」の 字 も, 官 位 表 記 は 該 当 しない。22)『 三 国 史 記 』 巻 38, 雑 志 7 , 職 官 上 によると 新 羅 の 京 位 は 十 七 ある。やや 煩 雑 であるが 上 位 から 列 記 すると1 伊 伐 湌( 或 云 伊 罰 干 , 或 云 于 伐 湌 , 或 云 角 干 , 或 云 角 粲 , 或 云 舒 発 翰 , 或 云 舒 弗 邯 )2 伊 尺 湌 ( 或 云 伊 湌 ),3 迊 湌 ( 或 云迊 判 , 或 云 蘇 判 ),4 波 珍 湌 ( 或 云 海 干 , 或 云 破 弥 干 ),5 大 阿 湌 ,6 阿 湌 ( 或 云 阿 尺 干 , 或 云 阿 粲 ),7 一 吉 湌 ( 或云 乙 吉 干 ),8 沙 湌 ( 或 云 薩 湌 , 或 云 沙 咄 干 ),9 級 伐 湌 ( 或 云 級 湌 , 或 云 及 伐 干 ),10 大 奈 麻 ( 或 云 大 奈 末 ),11 奈麻 ( 或 云 奈 末 ),12 大 舎 ( 或 云 韓 舎 ),13 舎 知 ( 或 云 小 舎 ),14 吉 士 ( 或 云 稽 知 , 或 云 吉 次 ),15 大 烏 ( 或 云 大 烏 知 ),16 小 烏 ( 或 云 小 烏 知 ),17 造 位 ( 或 云 先 沮 知 )となる。 中 古 期 はこれらの 確 立 期 であり, 金 石 文 には 異 表 記 が 多 い。469
東 アジア 文 化 交 渉 研 究 第 3 号しており 23) , 実 例 として 認 められる。ただ 地 方 官 として 派 遣 されているにもかかわらず 無 官 であるということは, 林 堂 古 碑 の 彼 らが 高 い 地 位 ではなかったことを 意 味 するものといえよう。次 に2の 場 合 , 4 文 字 に 収 まる 人 名 をあえて 名 と 官 とに 分 けるならば,「 起 任 習 □ 者 」や「 己 □□ 亻 柯 」の後 2 文 字 ( 下 線 部 )を 官 の 表 記 と 考 えることもできよう。だがこれは, 碑 文 の 官 位 表 記 に 関 する 基 本 知識 が 製 作 者 になかったことを 意 味 するものであり, 在 地 勢 力 説 の 傍 証 となる。3の 場 合 も,「 所 属 部 + 人名 + 官 位 」という 中 古 期 の 書 式 に 対 する 理 解 不 足 を 意 味 するものといえ,やはり 在 地 勢 力 による 製 作 の可 能 性 を 高 めると 同 時 に,これが 六 部 における 公 式 の 碑 文 ではなかったことを 想 定 せしめる。このように 碑 文 からは, 立 碑 の 主 体 として 六 部 人 (1)と 在 地 勢 力 (2と3)の 両 方 の 可 能 性 が 想 定される。 碑 文 の 内 容 からみて 六 部 人 が 重 要 な 役 割 を 果 たしたことは 間 違 いなく,1の 可 能 性 がまったくないわけではないが, 製 作 ・ 立 碑 者 とは 切 り 離 して 考 えるべきであろう。 石 碑 の 製 作 技 術 などを 考 慮 すると, 現 時 点 では 在 地 勢 力 による 製 作 ・ 立 碑 を 想 定 するのが 妥 当 と 考 えられる。2 立 碑 の 背 景林 堂 古 碑 が 水 に 関 する 内 容 である 可 能 性 が 高 いことは 既 に 指 摘 したが,これを 考 えるにあたっては,まず 林 堂 洞 遺 跡 の 遺 構 との 関 係 を 検 討 しておく 必 要 があろう。 古 碑 が 見 つかったのはⅠ 地 区 の 南 端 にある 石 築 遺 構 ( 排 水 路 と 敷 石 遺 構 )の 西 端 であり, 一 帯 は 低 湿 地 で 周 囲 に 排 水 路 , 井 戸 , 園 池 などの 遺 構が 密 集 している( 図 2 )。 建 物 の 柱 は 根 石 の 上 に 立 てられ, 特 に 2 ~ 5 号 は「 冂 」 形 に 配 列 されており,同 時 期 に 建 てられた 官 衙 や 邸 宅 の 可 能 性 があるという。遺 構 から 出 土 した 土 器 編 年 は 5 世 紀 ~ 9 世 紀 と 幅 広 いが, 中 心 年 代 は 6 世 紀 の 第 1 四 半 期 ~ 7 世 紀 の第 2 四 半 期 である。 本 稿 で 指 摘 した 古 碑 の 製 作 年 代 はこの 中 心 年 代 に 含 まれるため, 遺 構 との 関 係 をある 程 度 想 定 してもよいということになる。これが 遺 構 と 古 碑 の 直 接 的 な 関 係 を 証 明 するわけではないが,立 碑 場 所 の 第 一 候 補 となるのはやはりここであり,この 地 に 立 てられてこそ 意 味 をなすものだったと 考えるべきであろう。だとすれば 碑 文 の 内 容 は, 自 然 の 河 川 よりも 水 利 施 設 ,つまり 人 為 的 な 水 利 事 業 にかかわるものと 理 解 しておくのが 妥 当 と 考 えられる。水 利 事 業 という 点 からあらためて 注 目 されるのは, 中 古 期 における 2 つの 石 碑 である。その 一 つが,前 述 の 菁 堤 碑 ( 図 13) 24) である。 菁 堤 碑 は 高 130cm, 幅 93.5cm で, 永 川 市 道 南 洞 にあり, 六 部 の 下 級 官人 が7000 人 を 動 員 して「 塢 」 25) を 築 いた 内 容 が 記 されている 26) 。 碑 文 の「 丙 辰 年 」は536 年 とするのが 定 説であり, 菁 堤 の 名 はこの「 丙 辰 年 」の 碑 面 の 裏 に 刻 まれた 銘 文 ( 唐 ・ 貞 元 十 四 年 ,798)にある「 菁 堤 治記 」の 語 にちなんでいる。古 碑 との 関 係 で 注 目 したいのは 菁 堤 碑 に 登 場 する「 得 」の 字 である。「 得 」は 菁 堤 碑 において 長 さの 単位 であろうということは 従 来 から 指 摘 されてきたが, 得 の 字 にそのような 意 味 はない。いっぽう 同 字 を23)「 喙 沙 夫 那 □ 斯 利 , 沙 喙 蘇 那 支 」(「 冷 水 碑 」 後 面 5 —1~ 6 —3)。24) 芸 術 의 殿 堂 『옛 拓 本 의 아름다움, 그리고 우리 歴 史 』,1998 年25) 塢 は「 堤 」を 意 味 するが, 貯 水 池 とする 見 方 もある。 朱 甫 暾 ( 前 出 書 ,1992 年 )26) 発 見 の 経 緯 については 鄭 永 鎬 「 永 川 菁 堤 碑 의 発 見 」(『 考 古 美 術 』102,1969 年 )。 研 究 史 については 李 宇 泰 「 永 川 菁堤 碑 를 통해 본 菁 堤 의 築 造 와 修 治 」(『 辺 太 燮 博 士 華 甲 紀 念 史 学 論 叢 』,1985 年 )を 参 照470
慶 山 林 堂 遺 跡 出 土 古 碑 の 内 容 とその 歴 史 的 背 景 ( 篠 原 )図 13永 川 菁 堤 碑長 さの 単 位 を 意 味 する「 獸 ( 尋 )」だとする 見 解 27) があり 注 目 される。 字 形 からは「 獸 」ではなく「 得 」とすべきであると 思 われるが( 図 14) 28) , 当 時 の 刻 字 技 術 や 漢 字 の 教 養 などを 考 慮 すれば,にかよった「 潯 」と「 得 」の 字 が 厳 密 に 区 別 されなかったともいえ,「 得 」が 獸 の 異 表 記 である 可 能 性 は 高 いといえ土よう。いっぽう 林 堂 古 碑 にみえる「 得 」をみると, 直 前 に「 百 □ 」( 2 —9~10)の 2 文 字 がある。 百 は土 土数 詞 であり, 断 定 は 避 けたいが「□ 」は「 壹 」の 上 部 に 該 当 する 可 能 性 もある。「 百 □ 得 」が 長 さであるとすれば,それは 水 利 施 設 の 長 さを 指 すものであっただろう。6 世 紀 の 水 利 事 業 に 関 するもう 一 つの 石 碑 が「 大 邱 戊 戌 塢 作 碑 」(578 年 , 図 15 29) 、 以 下 塢 作 碑 と 略 称 )である。 碑 は1946 年 に 大 邱 市 大 安 洞 で 発 見 され, 現 在 は 慶 北 大 学 校 博 物 館 に 保 管 されている。 碑 石 は 高図 14 菁 堤 碑 の「 得 」( 左 から 2 —6, 2 —11, 3 —10)27) 李 宇 泰 ( 前 出 書 )および「 新 羅 의 水 利 技 術 」(『 新 羅 文 化 祭 学 術 発 表 会 論 文 集 』13,1992 年 )28) 芸 術 의 殿 堂 ( 前 出 書 )29) 国 立 慶 州 博 物 館 ( 前 出 書 )471
東 アジア 文 化 交 渉 研 究 第 3 号図 15大 邱 戊 戌 塢 作 碑103cm, 幅 65~53cm, 厚 12cm で, 六 部 官 人 が 中 心 となり, 現 地 の 有 力 者 や 村 民 を 動 員 して 塢 を 造 成 したことが 記 されている 30) 。 六 部 官 人 には「 都 唯 那 宝 蔵 □ 阿 尺 干 」など 僧 侶 とおぼしき 人 名 もみられ, 当 時 の技 術 者 集 団 を 考 える 上 で 興 味 深 い。これら 三 碑 は 内 容 だけではなく, 地 域 的 にも 共 通 している。 林 堂 古 碑 を 中 心 にみると, 菁 堤 碑 は 東 北に 約 20km, 塢 作 碑 は 西 に 約 15km 離 れた 場 所 で 見 つかっている。 三 碑 はいずれも 慶 州 から 大 邱 に 向 かう地 形 の 平 坦 なルート,つまり 慶 州 ― 永 川 ( 菁 堤 碑 )― 慶 山 ( 林 堂 古 碑 )― 大 邱 ( 塢 作 碑 ) 間 における 在 地勢 力 の 拠 点 地 域 であり, 交 通 の 要 衝 であった。 菁 堤 碑 についてはすでに531 年 の 堤 防 修 理 の 記 事 31) との 関連 性 が 指 摘 されているが, 三 碑 と 水 利 事 業 のあり 方 を 考 えると,その 事 業 は 特 定 の 時 期 に 大 規 模 に 展 開されたのではなく, 王 命 以 降 , 少 しずつ 範 囲 を 広 げながら 進 められていったのである。 林 堂 古 碑 は, 大邱 - 永 川 間 の 地 理 的 空 白 を 埋 めるとともに, 6 世 紀 代 にこの 一 帯 で 広 範 な 水 利 事 業 が 実 施 されていたことを 示 す 貴 重 な 追 加 資 料 といえよう。ではこうした 空 間 的 な 理 解 に 対 し, 三 碑 を 時 間 的 に 位 置 づけることは 可 能 であろうか。それを 考 えるうえで 指 摘 しておきたいのが, 菁 堤 碑 と 塢 作 碑 に 登 場 する 塢 の 長 さの 単 位 である。 碑 文 は 判 読 が 困 難 であるが, 前 述 のように 菁 堤 碑 の 単 位 は「 得 」であり, 塢 作 碑 には「 高 五 歩 四 尺 」( 7 —12~16)の 文 字 が確 認 される。 二 碑 を 隔 てるおよそ40 年 の 歳 月 の 中 で, 従 来 「 得 」であった 塢 の 単 位 が「 歩 」と「 尺 」に取 って 代 わられているのである。30) 発 見 の 経 緯 については 任 昌 淳 「 大 邱 에서 新 発 見 된 戊 戌 塢 作 碑 小 考 」(『 史 学 研 究 』 1 ,1958 年 ), 研 究 史 については朱 甫 暾 「 大 邱 戊 戌 塢 作 碑 」( 前 出 書 ,1992 年 )を 参 照 されたい。31)『 三 国 史 記 』 巻 4 , 新 羅 本 紀 4 , 法 興 王 18 年 (531)。「 春 三 月 , 命 有 司 修 理 堤 防 」472
慶 山 林 堂 遺 跡 出 土 古 碑 の 内 容 とその 歴 史 的 背 景 ( 篠 原 )二 碑 の 水 利 事 業 が 六 部 官 人 によって 主 導 されたことを 想 起 すれば,この 変 化 の 背 景 には, 六 部 つまり都 における 基 準 単 位 の 変 更 があったとみてほぼ 間 違 いない。 新 羅 においては520 年 に「 頒 示 律 令 」の 記事 32) がみられる。これが 成 文 法 を 意 味 するものであろうことは 以 前 から 指 摘 されてきたが 33) ,1978 年 発 見の「 丹 陽 新 羅 赤 城 碑 」( 6 世 紀 中 葉 ),「 蔚 珍 鳳 坪 新 羅 碑 」(524 年 ,1988 年 発 見 ), 冷 水 碑 (1989 年 発 見 )など 新 出 の 金 石 文 資 料 によってさらに 明 確 になったといえよう 34) 。 菁 堤 碑 と 塢 作 碑 はいずれも520 年 以 降の 内 容 であるが,この 間 に 制 度 が 改 められたとしても 特 に 問 題 はなかろう。 林 堂 古 碑 を 含 む 三 碑 は 距 離的 にもさほど 離 れておらず,またいずれも 六 部 の 人 間 がかかわっているため, 旧 制 が 単 位 において 固 守されていた 可 能 性 はさほど 高 くないと 考 えられる。 林 堂 古 碑 の「 得 」が 長 さの 単 位 として 認 められるのであれば,その 製 作 年 代 は578 年 より 前 と 考 えられ, 六 部 による 水 利 事 業 が 新 羅 の 北 進 ルートの 一 つに 沿って 順 に 展 開 していく 様 相 ととらえることもできるが, 現 時 点 において 断 定 は 避 けたい 35) 。このように 林 堂 古 碑 は, 永 川 ― 慶 山 ― 大 邱 にかけて 広 範 に 展 開 していた 水 利 事 業 にかかわる 内 容を 記 載 したものである 可 能 性 が 高 いことが 分 かった。ただ 同 碑 は 在 地 勢 力 による 製 作 と 判 断 され、いわゆる 菁 堤 碑 や 塢 作 碑 のような 六 部 主 体 の 大 規 模 事 業 とは 性 格 を 異 にするようにも 思 われる。おわりにこれまでみてきたように, 林 堂 古 碑 は 6 世 紀 に 製 作 されたもので, 碑 文 は 新 羅 六 部 と 在 地 勢 力 が 行 った 水 利 事 業 に 関 する 内 容 である 可 能 性 が 高 い。6 世 紀 における 水 利 事 業 の 展 開 は, 地 方 官 の 派 遣 ともかかわっているものと 考 えられる。 考 古 学 の 見地 からも,これらの 地 域 の 首 長 らは,すでに 4 ~ 5 世 紀 の 段 階 で 慶 州 を 上 位 とする 政 治 的 な 結 びつきがあり, 6 世 紀 を 前 後 して 慶 州 からの 地 方 官 の 派 遣 が 本 格 化 するに 伴 い, 次 第 にその 独 自 性 を 失 っていったと 考 えられている 36) 。つまり 同 地 域 は, 6 世 紀 初 めには 成 立 していた 六 部 ( 慶 州 )との 上 下 関 係 を 背 景に, 六 部 の 地 方 官 と 在 地 の 有 力 者 ( 村 主 など)が 並 立 する 状 況 にあった。そのもとで, 六 部 の 下 級 官 人を 主 体 とする 水 利 事 業 が 進 められていったのである。開 発 とは, 技 術 の 保 有 者 が 長 期 にわたって 現 地 に 滞 在 することが 不 可 欠 であり, 彼 らの 派 遣 は, 地 方官 と 在 地 有 力 者 ( 村 主 など)との 政 治 交 渉 , 合 意 なくしては 不 可 能 である。 技 術 者 官 人 の 思 惑 がいかなるものであれ, 六 部 出 身 者 が 地 方 官 として 周 辺 地 域 に 進 出 していく 過 程 において, 水 利 ・ 土 木 の 技 術 力が 少 なからず 貢 献 し, 地 域 社 会 における 主 導 力 を 確 保 していったことは 否 定 できないであろう。その 中32)『 三 国 史 記 』 巻 4 , 新 羅 本 紀 4 , 法 興 王 7 年 。「 春 正 月 , 頒 示 律 令 」33) 武 田 幸 男 「 新 羅 ・ 法 興 王 時 代 の 律 令 と 衣 冠 制 」(『 古 代 朝 鮮 と 日 本 』, 龍 溪 書 舍 ,1974 年 )。34) 朱 甫 暾 「 蔚 珍 鳳 坪 新 羅 와 法 興 王 代 律 令 」(『 韓 国 古 代 史 研 究 』 2 ,1989 年 ), 武 田 幸 男 「 新 羅 ・ 蔚 珍 鳳 坪 碑 の「 教 事 」主 体 と 奴 人 法 」(『 朝 鮮 学 報 』187,2003 年 )35)ただ『 三 国 史 記 』の 記 事 (665 年 )によると, 獸 ( 尋 )は 長 さの 単 位 として 7 世 紀 中 葉 まで 使 用 されていた。「 絹 布旧 以 十 尋 為 一 匹 , 改 以 長 七 歩 ・ 広 二 尺 為 一 匹 」( 巻 6 , 新 羅 本 紀 6 , 文 武 王 5 年 )36) 新 羅 地 域 の 考 古 学 研 究 において 最 も 重 要 な 編 年 基 準 とされているのは 土 器 であるが, 特 に 4 ~ 6 世 紀 にかけての 土器 編 年 には, 研 究 者 によって 1 世 紀 ほどのひらきがある。473
東 アジア 文 化 交 渉 研 究 第 3 号において, 喙 部 とともに「 斯 佊 」 部 の 人 間 が 存 在 していたことは, 当 時 政 治 的 にはすでに 下 位 に 位 置 づけられていた 習 比 部 の 性 格 についても 多 くの 示 唆 を 与 えてくれよう。 林 堂 古 碑 , 菁 堤 碑 , 塢 作 碑 は, 政治 交 渉 の 結 果 としての 技 術 者 集 団 の 進 出 , 彼 らと 在 地 勢 力 との 交 渉 ,そして 技 術 の 伝 播 を 物 語 る 貴 重 な資 料 である。ただ 林 堂 古 碑 の 製 作 は 在 地 勢 力 の 手 によるものと 判 断 され, 残 りの 二 碑 とは 水 利 事 業 へのかかわり 方 が 異 なっていると 思 われるが,これについては 今 後 の 課 題 としたい。本 稿 は 林 堂 古 碑 の 本 格 的 な 釈 読 としては 最 初 のものであり, 今 後 検 討 ・ 批 判 されるべき 余 地 を 多 く 残していると 思 われる。 今 後 の 研 究 進 展 に 多 少 なりとも 寄 与 するところがあれば 幸 いである。最 後 に, 本 稿 の 作 成 においては 石 碑 の 図 面 を 大 いに 活 用 した。 筆 者 の 力 量 不 足 から 利 用 には 限 界 があったものの,いくつかの 情 報 を 得 て, 筆 者 なりに 年 代 の 参 考 資 料 とすることができた。 石 碑 は 文 字 のみが 活 用 され, 考 古 学 的 研 究 や 実 測 の 対 象 としては 高 く 評 価 されてこなかったように 思 われる。だが 木 簡研 究 の 進 展 にみられるように, 計 量 学 的 データは 貴 重 な 情 報 源 であり,その 蓄 積 が 研 究 に 寄 与 するところは 大 きいと 思 われる。 石 碑 の 実 測 例 が 今 後 さらに 増 えることを 期 待 したい。付 記 : 林 堂 古 碑 の 調 査 および 資 料 の 提 供 にあたっては、 嶺 南 文 化 財 研 究 院 の 朴 升 圭 先 生 、 禹 炳 喆 先 生 から 多 大 なご 配 慮 を 賜 った。 厚 く 感 謝 の 意 を 表 する。474