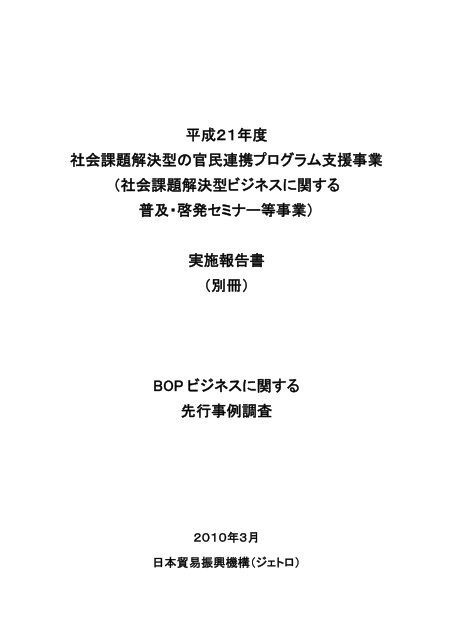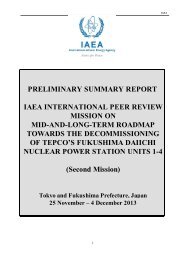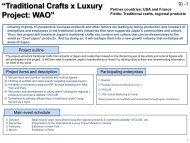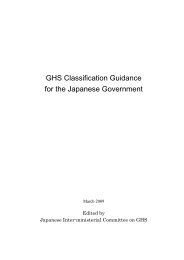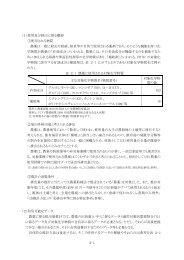平成21年度 社会課題解決型の官民連携プログラム支援事業 - 経済産業省
平成21年度 社会課題解決型の官民連携プログラム支援事業 - 経済産業省
平成21年度 社会課題解決型の官民連携プログラム支援事業 - 経済産業省
- TAGS
- www.meti.go.jp
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
平成21年度<br />
<strong>社会課題解決型の官民連携プログラム支援事業</strong><br />
(社会課題解決型ビジネスに関する<br />
普及・啓発セミナー等事業)<br />
実施報告書<br />
(別冊)<br />
BOP ビジネスに関する<br />
先行事例調査<br />
2010年3月<br />
日本貿易振興機構(ジェトロ)
は じ め に<br />
本書は、<strong>経済産業省</strong>が独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)に委託して実施した平成 21<br />
年度<strong>社会課題解決型の官民連携プログラム支援事業</strong>(社会課題解決型ビジネスに関する普及・<br />
啓発セミナー等事業)の一部、BOP ビジネスに関する先行事例調査の報告書である。<br />
本報告書で取り上げているテーマは、我が国企業が BOP ビジネスを検討する際に参考情報と<br />
して役立ててもらうことを狙いとして、欧米企業の先行事例等から学べることは何かという点であ<br />
る。<br />
本報告書における BOP(Base of the Economic Pyramid)層とは、年間所得が購買力平価(PPP)<br />
ベースで 3,000 ドル以下の開発途上国の低所得階層を意味し、BOP ビジネスとは、BOP 層を対象<br />
に、製品・サービスなどを彼らが購入可能な価格帯、販売形態で提供する持続可能なビジネスで<br />
あり、利益を求める純然たる企業活動であるが、同時に貧困問題などの社会課題の解決に資す<br />
ることが期待される新たなビジネスモデルである。BOP 層の人口規模を約 40 億人とする推計もあ<br />
り、開発途上国の経済成長と世界的な貧困削減努力があいまって、将来的には BOP 層の多くが<br />
中間所得層に上昇していくことが期待される。この観点から BOP 層はネクスト・ボリュームゾーン<br />
としても捉えられる。<br />
本報告書では、BOP ビジネスを活発に展開している欧米グローバル企業の戦略、ビジネスモデ<br />
ルの詳細、欧米企業の BOP ビジネスを支援している欧州政府の官民連携支援スキームの詳細、<br />
BOP ビジネス促進に果たす国際機関の役割とその調達メカニズム、国際 NGO の調達方針や民<br />
間企業との連携活動等の実態を明らかにした。<br />
本報告書が、我が国企業の方々が開発途上国とのビジネスの拡大や BOP ビジネス戦略を検<br />
討される上で参考となれば幸甚である。<br />
独立行政法人 日本貿易振興機構(ジェトロ)
Ⅰ.企業調査<br />
目 次<br />
1.バタ(Bata Shoe Company) ··············································································································· 7<br />
(1)BOPビジネスの事業概要 ···························································································································· 7<br />
(2)事例に見るBOPビジネス推進方法 ·········································································································· 9<br />
(3)公的機関、国際機関、NGO等との連携 ······························································································· 20<br />
2.シーメンス(Siemens) ························································································································· 27<br />
(1)BOPビジネスの事業概要 ························································································································· 27<br />
(2)事例に見るBOPビジネスの推進方法 ·································································································· 37<br />
(3)BOPビジネス推進に係る社内体制 ······································································································· 48<br />
(4)公的機関・NGO・国際機関等との連携 ································································································ 49<br />
3.ベスタゴー・フランセン(Vestergaard Frandsen) ······························································ 57<br />
(1)BOPビジネスの事業概要 ························································································································· 57<br />
(2)事例に見るBOPビジネス推進方法 ······································································································· 65<br />
(3)BOPビジネス推進に係る社内体制 ······································································································· 80<br />
(4)公的機関・国際機関・NGO等との連携 ································································································ 83<br />
4.クアルコム(Qualcomm) ···················································································································· 86<br />
(1)BOPビジネスの事業概要 ························································································································· 86<br />
(2)事例に見るBOPビジネス推進方法 ······································································································· 96<br />
(3)BOPビジネス推進に係る社内体制 ····································································································· 101<br />
(4)公的機関、国際機関、NGO等との連携 ····························································································· 103<br />
Ⅱ.政府支援機関調査<br />
1.オランダ ····················································································································································· 110<br />
(1)BOPビジネスに関わる政府の役割 ····································································································· 110<br />
(2)支援スキーム活用事例 ···························································································································· 120<br />
2
2.ドイツ ··························································································································································· 126<br />
(1)BOPビジネスに関わる政府の役割 ····································································································· 126<br />
(2)支援スキーム活用事例 ···························································································································· 144<br />
3.フランス ······················································································································································ 149<br />
(1)BOPビジネスに関わる政府の役割 ····································································································· 149<br />
(2)支援スキーム活用事例 ···························································································································· 162<br />
4.EU ································································································································································ 181<br />
(1)BOPビジネスに関わる政府の役割 ····································································································· 181<br />
(2)支援スキーム活用事例 ···························································································································· 221<br />
Ⅲ.国際機関調査<br />
1.ユニセフ物資供給センター (UNIPAC:United Nations Procurement and<br />
Assembly Center) ····························································································································· 237<br />
(1)活動概要 ······················································································································································· 237<br />
(2)拠点と役割分担 ·········································································································································· 238<br />
(3)調達の仕組み ············································································································································· 239<br />
(4)調達の実績 ·················································································································································· 248<br />
2.国連食糧農業機関 (FAO:Food and Agriculture Organization) ····················· 256<br />
(1)活動概要 ······················································································································································· 256<br />
(2)拠点と役割分担 ·········································································································································· 256<br />
(3)調達の仕組み ············································································································································· 257<br />
(4)調達の実績 ·················································································································································· 259<br />
3.国連世界食糧計画(WFP:World Food Programme) ················································ 262<br />
(1)活動概要 ······················································································································································· 262<br />
(2)拠点と役割分担 ·········································································································································· 262<br />
(3)調達の仕組み ············································································································································· 263<br />
(4)調達の実績 ·················································································································································· 265<br />
3
4.国連難民高等弁務官事務所 (UNHCR:United Nations High Commissioner<br />
for Refugees) ·········································································································································· 269<br />
(1)活動概要 ······················································································································································· 269<br />
(2)拠点と役割分担 ·········································································································································· 269<br />
(3)調達の仕組み ············································································································································· 269<br />
(4)調達の実績 ·················································································································································· 270<br />
5.世界保健機関(WHO:World Health Organization) ···················································· 275<br />
(1)活動概要 ······················································································································································· 275<br />
(2)拠点と役割分担 ·········································································································································· 275<br />
(3)調達の仕組み ············································································································································· 276<br />
(4)調達の実績 ·················································································································································· 280<br />
Ⅳ.国際NGO調査<br />
1.オックスファム(Oxfam) ··················································································································· 284<br />
(1)活動概要 ······················································································································································· 284<br />
(2)沿革 ································································································································································ 284<br />
(3)拠点と役割分担 ·········································································································································· 284<br />
(4)調達の仕組み ············································································································································· 284<br />
(5)収支と調達の実績 ····································································································································· 287<br />
(6)企業との連携 ·············································································································································· 290<br />
2.セーブ・ザ・チルドレン(Save the Children) ······································································· 293<br />
(1)活動概要 ······················································································································································· 293<br />
(2)沿革 ································································································································································ 293<br />
(3)拠点と役割分担 ·········································································································································· 293<br />
(4)調達の仕組み ············································································································································· 294<br />
(5)収支と調達の実績 ····································································································································· 294<br />
(6)企業との連携 ·············································································································································· 297<br />
3.国境なき医師団(MSF:Medecins Sans Frontieres) ················································· 300<br />
(1)活動概要 ······················································································································································· 300<br />
(2)沿革 ································································································································································ 300<br />
4
(3)拠点と役割分担 ·········································································································································· 300<br />
(4)調達の仕組み ············································································································································· 301<br />
(5)収支と調達の実績 ····································································································································· 301<br />
(6)企業との連携 ·············································································································································· 303<br />
4.マリー・ストープス・インターナショナル (Marie Stopes International) ·········· 304<br />
(1)活動概要 ······················································································································································· 304<br />
(2)沿革 ································································································································································ 304<br />
(3)拠点と役割分担 ·········································································································································· 304<br />
(4)調達の仕組み ············································································································································· 305<br />
(5)収支と調達の実績 ····································································································································· 305<br />
(6)企業との連携 ·············································································································································· 308<br />
5.プラン(Plan) ··········································································································································· 309<br />
(1)活動概要 ······················································································································································· 309<br />
(2)沿革 ································································································································································ 309<br />
(3)拠点と役割分担 ·········································································································································· 309<br />
(4)調達の仕組み ············································································································································· 310<br />
(5)収支と調達の実績 ····································································································································· 310<br />
(6)企業との連携 ·············································································································································· 312<br />
5
Ⅰ.企業調査<br />
1.バタ'Bata Shoe Company(<br />
2.シーメンス'Siemens(<br />
3.ベスタゴー・フランセン'Vestergaard Frandsen(<br />
4.クアルコム'Qualcomm(<br />
6
1.バタ'Bata Shoe Company(<br />
http://www.bata.com/us/<br />
NGOとの連携による、女性の雇用拡大と農村市場開拓<br />
'1(BOPビジネスの事業概要<br />
① BOPビジネス事業の位置づけ<br />
オーストリア=ハンガリー二重帝国時代の 1894 年、当時の Zlin'現在チェコ(でトーマシュ・バタ<br />
'Tomáš Bata(氏が兄弟とともに靴製造業を始め、同社を設立した。急成長する中で、工場の周辺<br />
に従業員のための住宅施設や学校、病院を建設し、福祉施設への慈善行為を行うなど、地元に<br />
貢献する活動を行ってきた。1939 年まではチェコに事業の本拠地があったが、同国がドイツに占<br />
領されると息子の Tomáš Bata 氏はカナダに移住し、独自に会社を設立した。第二次世界大戦後<br />
はチェコの社会主義政権によって事業が接収されたため、カナダに本拠地を移した経緯がある。<br />
現在はスイスのローザンヌを国際本社とし、チェコには販売子会社があるのみ。<br />
バタは市場を欧州、アジア、中南米、北米の 4 つに分け、各市場に地域統括拠点を設けている。<br />
その下に、国別の事業会社があり、現地会社は独立経営を行っている。ローザンヌ本社は、各地<br />
の経営戦略に介入せず、必要に応じて支援するという方針をとっている。<br />
世界 50 ヵ国以上に現地会社を持ち、一般小売店やバタのブランド名を掲げる直営店を通して<br />
販売するほか、業務用シューズ、スクールシューズなどの製造・販売も行っている。<br />
生産拠点は世界 26 ヵ国に 40 近くある。サプライチェーンの短縮によりコストを削減し、迅速な製<br />
品供給を図るとともに、地球温暖化ガス低減に貢献するため、現地工場の製品は主に現地市場、<br />
近隣市場に出荷されている。<br />
製品開発の拠点は、イタリア、中国、チリ、インドネシア、オランダ'産業用(、カナダ'スポーツ(<br />
と世界各地に分散して市場ニーズに合った製品を供給する体制が整っている。<br />
7
図表 1 バタの会社概要<br />
本社 ローザンヌ(スイス)<br />
地域統括拠点 欧州:スイス<br />
出所:http://www.batabd.com/bata/bata_today.php<br />
出所:バタ・ホームページ<br />
アジア・太平洋:シンガポール<br />
中南米:メキシコ<br />
北米:カナダ(トロント)<br />
4つの統括拠点はそれぞれ独立した事業ユニットの性格を持ち、市場<br />
の変化に迅速に対応し、事業拡大のチャンスをつかむ。<br />
各国の現地会社は独立経営だが、経理・総務などのバックオフィス・<br />
システム、商品開発や調達などは世界ネットワークを利用する。<br />
リテール店舗数 世界50ヵ国以上に4,600店以上<br />
従業員数 4万人以上<br />
生産拠点 26ヵ国に約40拠点<br />
一日あたりの訪問客数 100万人<br />
図表 2 世界の事業拠点<br />
アフリカ アジア・大洋州 欧州<br />
北米<br />
ボツワナ オーストラリア オーストリア マケドニア カナダ<br />
コンゴ バーレーン ボスニア・ヘルツェゴビナ ポーランド<br />
ケニア バングラデシュ ブルガリア ポルトガル<br />
マラウィ ブルネイ クロアチア ルーマニア<br />
モーリシャス 中国 キプロス ロシア<br />
南アフリカ インド チェコ セルビア<br />
ウガンダ インドネシア エストニア スロバキア<br />
ザンビア ヨルダン フランス スロベニア<br />
ジンバブエ レバノン ギリシャ スペイン<br />
マレーシア オランダ スイス 中南米<br />
ニュージーランド ハンガリー トルコ ボリビア<br />
オマーン イタリア ウクライナ チリ<br />
パキスタン コソボ 仏領ギニア コロンビア<br />
フィリピン ラトビア 仏領グアドループ エクアドル<br />
カタール リトアニア 仏領マルティニーク メキシコ<br />
シンガポール<br />
スリランカ<br />
タイ<br />
UAE<br />
ベトナム<br />
ペルー<br />
バタの靴は庶民の手の届く価格'affordable pricing position(で製品を提供し、途上国では圧倒<br />
的なブランド力を確立している。バタの途上国ビジネスは長い歴史、経験を持っている。たとえば<br />
インドでは 1931 年に設立、1973 年に上場している。インドでは最大の靴メーカーであり、過去 30<br />
年間にわたり築き上げた小売店舗網はバタ専門店だけ 1,250 店舗に達し、欧州全体の店舗数を<br />
上回っている。バタはインドでは生産、市場でリーダシップの役割を担っている。インドネシアには、<br />
1940 年にジャカルタで製造を始め、1942 年にはジャカルタ証券取引所に上場している。<br />
バタの新興市場開拓は、経済成長に伴い所得が増えている中間層や都市部の若者向き商品<br />
の品揃えに注力をしている一方で、BOP層への開拓が不十分であるという認識を持っている。中<br />
間 層 向 け に は ブ ラ ン ド メ ー カ と ト パ ー ト ナ ー シ ッ プ を 結 び 商 品 の 多 様 化 ' Marie Claire 、<br />
Bubblegummer、 Weinbrenner、 Power 、North Star、Pony、 Nautica、 Diesel and Timberland な<br />
ど(を進め、中・高級品市場に攻勢をかけている。BOP層向けには、バングラデシュやパキスタン<br />
で国際NGOのCAREと組んで農村市場開拓に実験的に取り組んでいる。また、地域コミュニティ<br />
の経済的発展を主とするCSR活動も、BOP層へのバタブランドの浸透を狙ったものである。<br />
8
② 主なBOPビジネス商品<br />
バタの主なBOPビジネス商品と販売体制は下表の通り。<br />
図表 3 主なBOPビジネス商品<br />
プレミアム・コレクション イタリアのデザインセンターが開発した快適性とデザイン性をアピール<br />
した商品ラインで、欧州のセレクトショップ、アジアや中東のデパート<br />
で販売している。<br />
産業用シューズ<br />
(Bata Industrials)<br />
バブルガマーズ<br />
(Bubblegummers)<br />
パワー<br />
(Power)<br />
マリー・クレール<br />
(Marie Claire)<br />
出所:バタ・ホームページ<br />
出所:バタ・ホームページ<br />
'2(事例に見るBOPビジネス推進方法<br />
① バタ・バングラデシュによる農村市場開拓<br />
図表 4 販売チャネル<br />
1(バングラデシュ子会社のBOPビジネス会社概要<br />
Bata Shoe Company (Bangladesh) Ltd http://www.batabd.com<br />
所在地:Tongi, Dhaka<br />
産業用、作業用の履き物、靴下類。製造は、アフリカ市場は南アフリ<br />
カ、アジア市場はオーストラリア、中南米はチリ、欧州はオランダが担<br />
当している。<br />
0~9歳までの子供用靴ブランド。品質、快適性、楽しさをアピールして<br />
いる。中南米ではトップブランドで、アジアや欧州でも販売拡大中。<br />
スポーツシューズ・ブランド。ランニング・シューズ、トレーニング・<br />
シューズ、室内・屋外競技シューズ、スケートボード用シューズなど。<br />
女性用デザインシューズ。日本と韓国を除く世界中で『マリー・クレー<br />
ル』商標使用権を持つ。<br />
シティストア 都市の一等地に構えた高級感をアピールする直営店<br />
大型店 都市とその周辺地域のショッピングセンター内に構えた大型直営店<br />
ファミリーストア 一般小売靴店<br />
工場直営店 2003年に導入した郊外型のアウトレットショップで、低価格と品ぞろえが魅力<br />
フランチャイズ イタリア子会社が統括して展開<br />
バングラデシュでは 1962 年に委託製造を開始し、1972 年に子会社を設立した。バタ・シューズ<br />
の製造・販売を行う。バングラデシュでは長年、有力シューズブランドとしての地位を確立している。<br />
バタはバングラデシュの靴市場で圧倒的なシェアを占有するリーダー企業である。しかし農村市<br />
場までは流通網が行き届かず、開拓できていない市場である。<br />
都市部の中間層向けには、独自ブランド『パワー』、『マリー・クレール』、『バブルガマーズ』など<br />
のほか、他の有名ブランド'Hush Puppies、Scholl、など(も販売する。ナイキのスポーツシューズ<br />
9
の販売も新たに開始し、ライフスタイルやスポーツで高い要望を持つ顧客にも対応している。同社<br />
はダッカ証券取引所とチッタゴン証券取引所に上場している。<br />
バタ・バングラデシュはその堅調な事業成長を評価され、Financial Mirror と Robintex Group が<br />
主催する、バングラデシュで最高の事業成長を遂げた外国企業に贈られる 2007-08 年度の『Best<br />
Multi-National Company with highest growth 』賞を受賞した。<br />
2(生産・供給体制<br />
図表 5 Bata Shoe Company (Bangladesh) の売上高'2008 年(<br />
出所:BATA Bangladesh Annual Report 2008<br />
a. 販売チャネルと生産拠点<br />
同社の販売チャネルは、小売店ネットワークと非リテール・ディーラーアウトレットの二つに分け<br />
られる。<br />
同社は、『ブランド・コーナー』コンセプトを導入し、都市部の大型店内に設けた販売コーナーを<br />
通しての販売も強化している。これは、ブランドイメージの強い直営店による販売に加えて、有名<br />
な小売チェーンを活用するという販売拡大戦略によるものである。Trust Family Needs'ウッタラ(、<br />
Mohammadia Sharee House'ガジプール(、Nandan Mega Shop'ウッタラ、グルシャン(などと提携し<br />
ている。<br />
出所:BATA Bangladesh Annual Report 2008<br />
図表 6 販売チャネル<br />
10<br />
'通貨単位:タカ(<br />
2008年 2007年 前年比増減(%)<br />
売上高 46億2,300万 39億8,500万 +16%<br />
税引き前利益 6億2,000万 4億9,400万 +25%<br />
当期利益 4億9,900万 3億6,200万 +38%<br />
2008年末従業員数 1,519人<br />
小売店<br />
ディーラーアウトレット<br />
国内に244<br />
店舗数<br />
うち 都市部のショップ 24<br />
家族経営ショップ 51<br />
バタ直営店・スーパー 65<br />
販売代理店 96<br />
閉店 8<br />
デポ(在庫管理所) 13<br />
ディーラーサポート・ショップ 481<br />
(Dealer Support Program)<br />
登録ホールセールディーラー・ショップ 349<br />
(Registered Support Program)<br />
売り上げ全体に<br />
占めるシェア<br />
2008年売上高の<br />
前年比増減率<br />
59% +22%<br />
39% +8%
. 品質管理<br />
図表 7 生産拠点<br />
商品の品質管理を強化するため、通常の品質管理体制に加えて、2008 年に社内コンテスト<br />
『Quality Contest 2008』を行った。これは、従業員の高品質への意識を高めると同時に、製造コス<br />
ト削減、生産目標達成、納品期日の厳守、品質・職場ムードの向上、チームワークの構築を目的<br />
としている。4 週間にわたるコンテストは 2 つの工場の様々な部門が参加した。<br />
c. 人材育成<br />
従業員の能力向上のため、さまざまな研修プログラムが実施されている。2008 年には 560 人が<br />
32 の国内研修、13 人が7ヵ国での海外研修に参加した。また、優秀な従業員を『今月の従業員』<br />
として表彰したり、工場従業員の勤労意欲を向上するための措置などをとっている。<br />
2008 年には、研修プログラム『Winning Merchandise Strategies and Dynamic Sales Management』<br />
を行い、40 人が参加した。バタの売上・利益改善方法や固定客の獲得方法など、販売管理に関<br />
するテーマで研修が行われた。<br />
d. 新しい販売チャネル―CAREバングラデシュとの提携<br />
バタ・バングラデシュは、CSRプログラムの一環として、国際NGOであるCAREのバングラデシ<br />
ュ支部と共同でBOPプロジェクトを推進している。これは、CAREバングラデシュが主催する貧困<br />
層の女性就労支援プログラムのひとつで、農村部の貧困女性を起業家として育成し、経済的に自<br />
立して所得を拡大できるよう支援することを目的としている。この『農村部販売プログラム'RSP(』<br />
への参加は、バタにとっては現地社会への貢献を果たすと同時に、未開拓の農村部という市場に<br />
進出するための効率的な販売チャネルを得るという大きな魅力があった。<br />
2004 年に 2 年間の計画でスタートしたプロジェクトは、2006 年には、『アパラジータ'Aparajita(』<br />
と名付けられた女性起業家'販売員(を 1,000 人に拡大し 100 のグループで活動するという目標を<br />
掲げて継続された。<br />
e. 当初プロジェクトの概要<br />
工場所在地 トンギ(Tongi)、ダムライ(Dhamrai)<br />
生産量(1日あたり) 11万足<br />
工場設備 年間500万平方フィートの皮革を加工できる最新の<br />
製革設備を備える。ハイテク技術を採用して、工場<br />
排水などに関わる環境措置も行っている。<br />
11
実施期間'当初( 2004-2005年<br />
実施資金 民間寄付<br />
図表 8 当初プロジェクトの概要<br />
実施内容 ● バタの靴を農村部で家庭訪問して販売。<br />
● 自営販売員グループの組織化<br />
販売員数 約50人<br />
● リーダーがBATAとの折衝や在庫管理、経理などを担当する。<br />
● BATAは事業立ち上げ資金を融資し、研修、販促材料などを提供する。<br />
● CAREは融資保証や研修など支援する。<br />
出所:バタ・ホームページ www.bata.com/about_us/care_in_bangladesh.php<br />
バタ・バングラデシュのマーケティング・マネージャー、クアダー(Quader) 氏は、CAREバングラ<br />
デシュとの合同プログラムRSPについて次のように説明している。<br />
「バタはCSRプログラムの一環としてCAREバングラデシュと提携し、農村地帯の女性とその<br />
家族の生活の向上させることを決めた。CAREバングラデシュと協力し、女性が所得を得る能力<br />
を発揮できるように援助、新しい就労機会を提供している。これはバタの製品'履物(を家庭訪問<br />
して販売するというもので、バングラデシュの北部および南部で展開している。」<br />
図表 9 バタ・シューズのアパラジータ<br />
背景は商品を仕入、保管するハブ<br />
出所:CARE France ホームページ<br />
「プログラムは、バタ・バングラデシュとCAREバングラデシュの共同パイロットプロジェクトとし<br />
て 2005 年に国内北部のナトーレ地方'Natore District(で 49 人の女性販売員を使ってスタートし<br />
た。この女性販売員は、『アパラジータ'Aparajita(』と名づけられた。これはベンガル語で「絶対に<br />
敗北を認めない女性」という意味。女性販売員は、最寄りのバタ・ホールセール拠点が指定したハ<br />
12
ブを通して靴を現金で仕入れる。バタは販売員ひとりひとりに見本を入れたバッグ、シューズ・カタ<br />
ログ、バッジ、顧客の靴のサイズを測るための足型、傘を提供するほか、定期的に研修プログラ<br />
ムを実施している。」<br />
* 足型が用意されているところから、販売員はまず、家庭訪問で顧客の靴サイズを確認し、<br />
希望の靴モデル・色などの要望を受けて注文を確定し、その後商品を仕入れて顧客に配<br />
達するというスキームと見られる。バッジはバタの公認販売員であることを示している。<br />
「RSPイニシアチブは『ハブ』と名づけられた仕入ショップを拠点として構成されている。これはさ<br />
らに地域(Region)レベルの中核ハブに分かれる。中核ハブにはハブマネージャーが配置され、各<br />
ハブの運営を監視する。ハブは、アパラジータに商品を供給し、バタの通常の在庫管理システム<br />
に基づいて在庫を管理する。アパラジータには販売額に応じてコミッションが支払われる。各ハブ<br />
に配置されたサービス責任者は、いつでも商品を供給できるよう在庫管理している。」<br />
② 公的機関、国際機関、NGO等との連携<br />
1(CAREバングラデシュの農村部販売プログラム'Rural Sales Program =RSP) 1<br />
国際NGO、CAREバングラデシュの経済発展部門が導入した農村部販売プログラム'RSP)の<br />
目的は、農村地方の貧困層に雇用と収入獲得の機会を提供することにある。雇用機会の提供者<br />
として民間会社を巻き込み、関係者すべてが利益を得ることができるディストリビューション・スキ<br />
ームの構築を目指して、2004 年にバタと一緒にプログラムをスタートした。RSPプログラムにより、<br />
農村部の貧困女性に対しては、就労により自らの所得を得る、起業活動を持続的に行うための知<br />
識を得ることができ、コミュニティに対しては、雇用創出・所得向上によるコミュニティ全体の生活<br />
水準の向上、参加企業に対しては、農村部を市場として開拓し、販売を拡大することが期待でき<br />
るとしている。<br />
� CAREバングラデシュの役割<br />
CAREバングラデシュは、民間会社とその販売員である農村女性との間の仲介役である。<br />
� 参加者の能力を確認する。<br />
� 女性起業家をアパラジータとして研修する。研修はグループ単位で行われ、販売、健康に<br />
関する知識、会計、商売上の交渉、他の事業運営に関わるスキルが教授。<br />
1 CARE Bangladesh: Rural Sales Program (RSP)、FDC、Libra Advisory Group: Social Enterprise Development<br />
Bangladesh Case Studies,、CARE バングラデシュ、プログラムマネージャー、ラシッド氏のコメントなどを参照<br />
13
� マイクロファイナンスを仲介する。<br />
� 販売にかかわるコストを抑えてヴァリュチェーンを確保できるよう、アパラジータと参加企業<br />
の間を取り持つ。<br />
� 企業のプログラム参加スキーム<br />
CAREバングラデシュと参加企業のプログラムへの関与の仕方をみると、CAREバングラデシ<br />
ュは前述のようにプログラムのコーディネーターとして、主に販売員'アパラジータ(の育成に力を<br />
入れる。参加企業は当初はバタのみだったが、現在はユニリーバ・バングラデシュ'UBL(や現地<br />
企業などが参加し、多角的な取組になっている。参加企業を募るうえで、商品ができるだけ競合し<br />
ないよう配慮している。各企業は、販売に関連したプロジェクトコストを負担し、自社商品の販売に<br />
関連した備品を提供し、アパラジータに報酬として販売手数料を払う。<br />
販売関連のプロジェクト<br />
コストを負担<br />
販売コミッションを提供<br />
セールスキットを提供<br />
成果を挙げたグループは<br />
プロジェクト終了後に<br />
ディーラーとして統合<br />
図表 10 CAREのマルチパートナープロジェクト<br />
出所:CARE France Strategic Alliance May 2009<br />
� ハブマネージャーの役割<br />
ディストリビューターとアパラジータの間には、商品を保管しアパラジータに引き渡す役割を持つ<br />
ディストリビューター'例えばバタ(のハブが設けられているが、そこには、ハブマネージャーという<br />
女性責任者が配置されている。ハブマネージャーには、ハブの運営を監視し、ディストリビュータ<br />
ーの在庫管理所と連絡して商品を仕入れる責任が課されている。ハブは参加企業の拡大に伴い、<br />
参加企業の商品を同時に扱う方向に向かうと見られる。<br />
� サービス責任者の役割<br />
BATA<br />
女性販売員の選択<br />
セールストレーニング提供<br />
販売実績のモニター<br />
持続可能な起業活動展開<br />
CARE<br />
農村地帯<br />
販売<br />
プログラム<br />
BATA・UBLと競合しない<br />
商品の販売<br />
14<br />
他社<br />
UBL<br />
販売関連のプロジェクト<br />
コストを負担<br />
販促キャンペーン・材料<br />
を提供<br />
バッグなど必要部品の<br />
提供
サービス責任者も女性で、ハブが常に必要な商品在庫を確保しているか監視し、輸送コストを<br />
削減し、幅広い商品を供給できるよう図る。<br />
� コミュニティファシリティー'Community Facilitator=CF(<br />
メインハブの活動がスムーズに行われるよう、CAREバングラデシュは、販売地域ごとに援助<br />
者'Community Facilitator(を指定している。プログラムに参加する民間会社との連携を図り、アパ<br />
ラジータと販売代表者を研修し、販売活動も監視する。販売地域あたり複数のCFが配置され、C<br />
AREが指定したテクニカル・オフィサーがこの活動を援助し、監督する。<br />
図表 11 RSPのディストリビューション・スキーム<br />
ディストリビューター: バタ、ユニリーバなど<br />
メインハブ<br />
▲ ▲ ▲<br />
販売代表者 販売代表者<br />
アパラジータ<br />
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲<br />
CARE Rural Sales Program (RSP)をもとに作成<br />
2(RSPの拡大―マルチ・パートナーシップへの進展<br />
前述のように、バタとCAREが提携したRSPプロジェクトは 2004 年に 50 人でスタートした。2006<br />
年にはプロジェクトの継続を継続して拡大することを決めた。だがCAREバングラデシュは、この<br />
雇用促進活動を本格的に展開するには、より多くの企業の参加が必要であると考えた。<br />
2006 年 12 月初め、CAREは日用消費財大手のユニリーバ・バングラデシュと新たな提携契約<br />
を交わした。ユニリーバはインドで農村部の女性の自立支援と販売促進を目指す『シャクティ<br />
'Shakti(』プロジェクトを推進しており、これを見本にバングラデシュでも 2003 年から『ジョイータ<br />
'Joyeeta(』プロジェクトを展開していた。バングラデシュでは農村部の約 2,000 人の女性に経済自<br />
立のチャンスを提供していた。ユニリーバ・バングラデシュは、RSPへの参加により、同社がまだ<br />
15<br />
CAREが<br />
販売地域ごとに<br />
指定した援助者<br />
(CF)
開拓しきっていない北部と東部地域の 20 以上の地区を市場として取り込むことが可能になった。<br />
2007 年から、段階的な提携拡大を経て、2009 年 7 月に、ユニリーバのジョイータはアパラジータに<br />
統合された。<br />
� RSP参加企業<br />
ユニリーバ・バングラデシュとの提携により、RSPの活動範囲と動員するアパラジータの数は<br />
2009 年夏に 3,000 人に増えた。<br />
その後、バングラデシュのテキスタイル・保存食品大手の SQUARE、生育の良い野菜の種を販<br />
売する EAST-WEST seeds が参加している。仏食品大手ダノンといった企業が参加している。また、<br />
農村部の零細企業が製造する製品も取り扱うようになった。<br />
「RSPが国際大手企業と組んで活動していることに、様々な方面から批判があった」とCARE<br />
バングラデシュでこのプログラムを担当するラシッド氏は言う。この企業が売っているものは、貧し<br />
い人々が必要としている生活必需品ではない、現地の産業奨励に貢献していないなどの指摘を<br />
受けて、プログラムチームは視野を映した。バングラデシュでグラミン銀行が先導を切り、マイクロ<br />
ファイナンスを資金に多数の起業家が誕生していた。これらの起業家や零細企業が作る製品をプ<br />
ログラムに取り込むことは、農村部の活性化を更に推進することができる。現在、アパラジータは<br />
バタの草履やユニリーバのシャンプーと一緒に、現地起業家の手工芸品なども販売している。将<br />
来的にはこれらの製品の比率を 30%程度に拡大したいとしている。<br />
仏食品大手のダノンは、2006 年にグラミン・グループの 4 つの会社'Grameen Byabosa Bikash、<br />
Grameen Kalyan、Grameen Shakti、Grammen Telecom(との合弁会社 Grameen Danone Foods を<br />
設立し、ヨーグルトの製造・販売を行っている。同社は独自の女性販売ネットワークを構築して、訪<br />
問販売しているが、全国的な展開を視野に入れ、RSPへの参加を決めた。先ごろ国内北部で行<br />
った試験販売が成果を出したことから、2010 年には本格的な参加を計画している。<br />
16
図表 12 RSP参加企業<br />
会社名 商品<br />
BATA Bangladesh 履物(ゴム草履など)<br />
Unilever Bangladesh シャンプー、石鹸、ケアクリームなど<br />
Square<br />
(バングラデシュのテキスタイル・保存食品大手)<br />
East-West seeds International<br />
(アジアの野菜の種製造・販売大手)<br />
出所:CARE Rural Sales Program (RSP)<br />
� マイクロファイナンス<br />
図表 13 現在のプロジェクト規模<br />
図表 14 バングラデシュにあるバタのハブ<br />
アパラジータは商品の仕入れコストとして 3,000~5,000 タカの初期投資が必要になる。このため<br />
CAREが独自に融資したり、各地に応じて、バングラデシュで活動する約 3 万 4,000 のNGOマイク<br />
ロファイナンス機関のいずれかを紹介している。アパラジータは毎週の売り上げから、例えば 75 タ<br />
カずつ返却するという形で、1 年ぐらいかけて返済している。<br />
17<br />
タオル、サニタリー用品、食用オイルなど<br />
各種野菜の種<br />
Danone ヨーグルト<br />
農村部の女性起業家、零細企業 手工芸品、食品など<br />
ハブ数 100<br />
販売地区<br />
(District)<br />
アパラジータ 約3,000人<br />
アパラジータの平均月収<br />
国内64のうち22をカバー(チッタゴン、ジョイプラート、<br />
ナトーレ、ノアカリ、ガイバンダ、ラングプール、クリグ<br />
ラム、ラルモニラートなど)<br />
1,000タカで、最高4,000タカを稼ぐ女性もいる。<br />
通常8時間労働。パートタイムや農閑期など得的の季節のみ<br />
就労する女性もいる。
③ 事業展望<br />
1(バタの事業に与える効果<br />
バタは、2006 年のRSP継続にあたり、100 のグループ、1,000 人のアパラジータへの活動拡大<br />
目標を掲げていた。これは、ユニリーバ『ジョイータ』プロジェクトの統合により、規模は一気に拡大<br />
し、現在では 40 の地域'Subdistrict(で約 3,000 人を動員する活動に発展している。<br />
クワダー氏によると、RSPを通したバタの販売地域は、主にベンガル南部および北部の農村地<br />
方で、たとえばチッタゴンやラジシャーニ地区で展開されている。今後、'ジョイータの活動している(<br />
他の地方への拡大も計画している。<br />
この販売モデルは、バタにとって初めての『家庭訪問販売』というマーケティング手法への取組<br />
である。「これを販売チャネルと位置付けて販売目標を立てることにより、当社の事業にポジティブ<br />
な影響を与えていると思う」とクワダー氏は言う。2009 年 10 月までに約 5 万 8,000 足を販売したと<br />
している。CAREバングラデシュによると、2008 年の売上高は 3,000 万タカで、このうち 5~6 割が<br />
バタ製品での売上だった。バタは、このプログラムの営業経費として年間約 150 万タカを見ており、<br />
十分な利益を出していると思われる。<br />
バタにとってRSPを通して、農村部に顧客開拓できたことは大きな利点だった。バングラデシュ<br />
には 100 万の小売業者がいるが、その 3 割しか正規のディストリビューション・システムに組み込<br />
まれていない。7 割、つまり 70 万の小売業者とは、市場や大手商店で商品を購入し、最終消費者<br />
に販売する小売アウトレットや露天商などであるが、これらの小売業も国内全域で営業しているわ<br />
けではない。アパラジータはこのような小売インフラから取り残された地域で、バタの販売活動を<br />
可能にし、新しいビジネスチャンスをとらえることができた。売上に貢献しており、すでに通常の販<br />
売チャネルとして組み込まれている。<br />
CAREは、このプログラムを通して女性の自立を奨励することにより、村の中での女性の地位<br />
向上が実現し、また男性に比べ、女性はヘルスケアや教育への出費を惜しまないため、コミュニ<br />
ティの貧困が全体的に減ったとしている。そして、農村部の人々はこれまで購入できる価格ではな<br />
かった、あるいは遠くの町まで買い物に行かなければならなかったような商品を、低価格で手にす<br />
ることができるようになった。<br />
18
2(今後の事業展望<br />
図表 15 RSP事業例'バタ(<br />
出所:CAREフランス http://www.careintjp.org/support/images/csr0511_2.pdf<br />
出所:CAREフランス http://www.careintjp.org/support/images/csr0511_2.pdf<br />
バタ・バングラデシュによれば、2010 年の農村市場開拓の取組として、①キャンペーン/ワーク<br />
ショップの開設、②販売員の研修、③カタログの更新、③認知度向上のためのドキュメントフィル<br />
ムの作成、④農村部販売促進のための新製品開発、⑤印刷物による成功事例の紹介などを企<br />
画している。また、ハブ拠点網の充実とアパラジタスの新規採用により農村市場での販売を一層<br />
拡大させる計画である。<br />
19
図表 16 バタ・バングラデシュの農村市場開拓の事業概要<br />
出所:BATA Bangladesh<br />
'3(公的機関、国際機関、NGO等との連携<br />
バタは、企業として消費者に良い製品やサービスを提供することのみならず、雇用や豊かさを<br />
提供することが、社会に対する企業価値であるという理念に基づき社会活動を行っている。バタが<br />
事業を展開している地域では、地場の経済や人々のスキル向上など地元のコミュニティの繁栄に<br />
貢献する活動を行っている。具体的には、創業以来、事業活動の拠点で住宅、学校、病院などを<br />
作ってコミュニティ作りに協力し、活発な福祉活動を行ってきた社風に根付いているといえる。<br />
「バタが繁栄すれば、バタが事業展開するコミュニティも繁栄する。バタはコーポレート・シティズ<br />
ンとなることをコミットメントとし、この活動を通して現地の雇用拡大、質の高い研修や教育機会の<br />
拡大に貢献する。ローカルビジネスとCSR活動をサポートすることにより、コミュニティの生活水準<br />
の向上を支援できることを誇りとしている。4万人の従業員に、学校、福祉団体、スポーツ活動の<br />
支援や災害地ボランティアなどの慈善活動に取り組むことを奨励している」'BATA Footprints よ<br />
り(。<br />
コミュニティへの貢献の中でバタが優先している分野が、教育とエンタープレナーシップ'起業家<br />
精神の育成(事業である。教育を支援し、エンタープレナーシップを奨励することで貧困を削減し、<br />
自立化をはかることを重視している。各地域にあるバタ子会社がバタ本社の方針を自主的に取り<br />
組んでいる。<br />
ハブ 販売員数 販売数<br />
(足)<br />
前年比<br />
(%)<br />
販売額<br />
(1,000タカ)<br />
2005年 3 49 18,000 963<br />
20<br />
前年比<br />
(%)<br />
2006年 25 899 65,000 361 4,565 474<br />
2007年 16 480 69,000 106 5,606 123<br />
2008年 48 1,500 164,000 238 16,000 285<br />
2009年 38 1,800 215,000 131 19,000 119<br />
2010年 70 2,500 250,000 114 24,000 120<br />
2011年 100 3,000 280,000 112 28,000 117<br />
2012年 112 3,500 320,000 114 32,000 114<br />
2013年 124 4,000 350,000 109 36,000 113<br />
(注)2010年以降は計画
① NGOとの連携<br />
図表 17 バタの取組<br />
バタはバングラデッシュのほかにパキスタンでもCAREと連携して事業を行っている。<br />
バタは、このほか学校と企業の橋渡しをしているJA'Junior Achievement(とは世界各地で連携<br />
を行っている。JAは 1919 年に米国で設立された団体で、子供に企業家精神とリーダーシップスキ<br />
ルを身につけさせる活動をおこなっている。バタはJAの主催するセミナーに社員を講師として派<br />
遣してバタの企業経営について子供たちに実践的なビジネスを教えている。また各地域のバタが<br />
JAの活動を支援している。<br />
教育 アントレプレナーシップ<br />
国名 プログラム 国名 プログラム<br />
バングラデシュ Anti-drug education バングラデシュ Care<br />
Supporting Children & Disabled Rural Sales Program<br />
Scholarship<br />
Disaster Relief インド Care<br />
Disaster Relief<br />
ケニア Disaster Relief<br />
ケニア Lions Club<br />
ジンバブエ Supporting Schools Junior Achievement<br />
オランダ Montessori schools タイ Lions Club<br />
Sports Sponsorship<br />
インド Supporting Schools & Orphanages<br />
欧州 Junior Achievement<br />
イタリア Pure sport Soccer sponsorship<br />
ジンバブエ Junior Achievement<br />
パキスタン SOS Children<br />
Supporting Schools & Orphanages シンガポール Fashion Sponsorship<br />
Environmental programs Disaster Relief<br />
南アフリカ HIV education, Health support チリ Sports Sponsorship<br />
Supporting Schools<br />
ザンビア Disaster Relief<br />
コロンビア Computers for education<br />
Adopt a school カナダ Local Community Development<br />
Environmental program<br />
シンガポール Children Education<br />
図表 18 各地域のバタによるJAの支援<br />
アフリカ 北米 アジア・太平洋 欧州<br />
ケニア カナダ オーストラリア チェコ<br />
南アフリカ 中国 フランス<br />
ジンバブエ 中南米 インドネシア イタリア<br />
ボリビア シンガポール オランダ<br />
チリ スリランカ ポーランド<br />
コロンビア ポルトガル<br />
エクアドル ロシア<br />
メキシコ スロバキア<br />
ニカラグア スイス<br />
ペルー 英国<br />
21
② バタ・チルドレン・プログラム基金(BATA Children Program Foundation)<br />
CSR活動は現地会社ベースで行われているが、これを補う目的で本社は、国際事業の経験を<br />
生かし、特別資金を設けて、バタ・チルドレン・プログラム基金を設置した。低価格のスクールシュ<br />
ーズの販売を主力事業としていたことから、教育施設や学校にフォーカスした支援活動を行って<br />
いる。基金の拠点はスイス・ローザンヌにある。<br />
バタ・チルドレン・プログラム基金のミッションは、事業展開している国の地元の子供たちに明る<br />
い未来を作ることである。<br />
1(CSR活動体制<br />
図表 19 バタ・チルドレン・プログラム基金の優先分野<br />
バタ・チルドレン・プログラム基金の下に、プロジェクト推進委員会がおかれ、そこでの施策決定<br />
が各市場統括拠点に指示される。<br />
南アジア<br />
出所:BATA Footprints<br />
優先分野 学校<br />
教育、スポーツ<br />
孤児院<br />
二次的分野 災害地支援<br />
起業家支援<br />
環境保護支援<br />
創造性支援<br />
図表 20 バタのCSR活動体制<br />
BATA Children's Program Foundation<br />
プロジェクトリーダー<br />
推進委員会<br />
アジア・太平洋 アフリカ<br />
南米 欧州<br />
22<br />
コンセプト開発<br />
ベストプラクティスの選択<br />
プロジェクト準備<br />
コミュニケーション統括<br />
ウェブサイト情報<br />
5人の地域リーダーと<br />
サステナビリティチームの<br />
設置<br />
資金集め<br />
実行
2(活動方法<br />
� 世界中のバタ現地会社をネットワーク化する。<br />
� コミュニティのインフラ支援では現地の提携会社と協力する。<br />
� 支援活動に協力する従業員'ボランティア希望者(との連絡活動。<br />
3(活動内容<br />
� よりよい学校環境作り<br />
� 学校設備の改善支援<br />
� 子供が学校に通えるよう、奨学金を支給する<br />
� 現地の教育インフラを支援する<br />
� 学校の整備、発展のためにノウハウを提供する<br />
� 通学支援<br />
4(CSR活動事例<br />
� タイ<br />
World Vision'キリスト教系慈善団体(が推進している貧しい子供を学校に通わせるプログラム<br />
“Back to school”に、2002 年からスクールシューズ 42 万足以上、ソックス 60 万足以上を支給して<br />
いる。この関係で、学校でのサイズ・フィッティングや直接納品などができるようになった。<br />
� スリランカ<br />
“Schoolbly Cricketer Awards”プログラムを主催し、国民的スポーツであるクリケットの学校対抗<br />
試合をスポンサーとして支援。<br />
� パキスタン<br />
慈善団体、学校、大学、孤児院、身体障害者福祉施設などへの寄付、募金活動のスポンサー、<br />
靴提供などを行っている。アフガニスタンのカンダハールの孤児院に 500 足のスクールシューズを<br />
寄付した。<br />
� インド<br />
インドで最大規模の孤児院 Udavum Karangal への靴の寄付や、スポンサー活動を行っている。<br />
また、World Wild Fund (WWF)の自然環境・野生動物保護の活動に参加。WWF キャンペーンTシャ<br />
23
ツを寄付。『ガンジス川を救え』プロジェクトでは植林活動にも参加。<br />
� インドネシア<br />
津波被害で破壊されたアチェ地域の学校再建、教員育成プログラム'Love tjpmgs omotoatove(<br />
に参加。被災地の子供たちに奨学金を支給した。<br />
� マレーシア<br />
New straits Times Press が主催した洪水被災者支援活動で、Joher State と Sri Medan の洪水<br />
被災者に 5,000 足のゴムぞうり'Slippers(を寄付。<br />
� ケニア<br />
ナイロビの Dr. Barnados home、バタの工場がある Limuru の近くの St. Anthony’s Children’s<br />
home などの学校に毎年靴を寄付している。<br />
政府の初等教育無料化政策の支援措置として、NGOのコネクト・スイス'Connect Swiss(にス<br />
クールシューズを寄付。ケニア西部の Vihiga District の Bunyore 北東地区の小学校 6 校の生徒に<br />
支給した。「どの子供たちも靴のサイズがぴったり合った。バタが用意したシューズにはミスがなか<br />
った。初めて新品の靴を履いた子供もいて非常に喜んでいた。中には靴を抱えてはだしで帰宅す<br />
る子供もいた。われわれを見るとうれしそうに手を振って『バタ』と大声で呼びかけてくる。バタはこ<br />
の町に大きなインパクトを与えた。両親も教師も感謝している」'Connect Swiss のル・ルー氏 Le<br />
Roux(<br />
� ジンバブエ<br />
1995 年にバタ小学校を設立し、現在では教室が 16 に増えている。同国の教育・スポーツ・文化<br />
省の規定に従って、バタが運営する私立学校である。<br />
24
� 南アフリカ<br />
出所:BATA Footprints<br />
図表 21 バタ小学校'ジンバブエ(<br />
現地の支援活動家と協力して、KwaYuluNatal にある障害児学校 Sihambakancane School の設<br />
備整備や教師育成に取り組んでいる。スクールシューズ、教材などを提供。<br />
� マラウィ<br />
Thyolo District の農業団体に作業シューズを寄付。これは同団体が行っている農作物コンペテ<br />
ィションで高品質の製品を生産した農家に贈られる。St.Lukets Anglican Hostiptal に感染防止用<br />
高質エプロンを寄付。<br />
� ザンビア<br />
ザンビアの首都ルサカから 20km南に位置するムンダワンガ自然動物植物園'Mundawanga<br />
Wildlife and Botanical Garden(を 2007 年から支援。<br />
� メキシコ<br />
バタの拠点がある Iztapalapa 地方の貧しい子供足しの支援団体である Avance International<br />
AssociationE にテニスシューズ 100 足を寄付。Avance は地方当局との協賛で各種の社会活動を<br />
行っている。募金活動も行い、子供たちに食品、衣類、靴、玩具、医薬品などを提供している。<br />
25
� コロンビア<br />
2007 年 10 月の洪水被害にあった子供たちに 6,000 足の靴を寄付。<br />
“Be Guardian Bubble gummers”キャンペーンを実施。子供たちに地球の環境保護について楽し<br />
みながら学ぶ機会を提供するもので、国内では企業が実施する社会活動キャンペーンの先行例<br />
となっている。<br />
� ボリビア<br />
1963 年に Manaco de Quillacollo に小学校 Thomas J. Bata Primary School を設立した。2000 年<br />
までは毎年 180 人の生徒を受け入れて 5 年間就学させたが、8 年まで延長し、生徒数が 2 倍にな<br />
った。当初はバタ・ボリビアが従業員の子供たちを無償で教育する目的で運営されたが、現在は<br />
全ての子供たちを受け入れ、能力に応じて奨学金を支給している。<br />
� チリ<br />
1963 年に Melipilla County に現地住民のスポーツ施設として Bata Soinca Stadium を寄付。<br />
� バタ財団'Bata Shoe Foundation(<br />
スイスのサン・モーリッツにはバタ財団'Bata Shoe Foundation(がある。慈善事業、研究、人材<br />
育成、学術・文化・教育・芸術・人道的活動などを支援している。<br />
26
2.シーメンス'Siemens(<br />
http://www.siemens.com/entry/cc/en/<br />
社員のボランティア精神を高揚させて長期的視点で BOP ビジネスに挑戦<br />
'1(BOPビジネスの事業概要<br />
① BOPビジネス事業の位置づけ<br />
シーメンスは、企業決定や事業遂行にあたり社会的責任を考慮するということは、同社の伝統<br />
かつ企業文化であり、企業としてイノベーションだけでなく、人材育成を通しても、遺産を次の世代<br />
に伝えていく義務があるとしている。グローバル企業として何を求められているのかを、従業員や<br />
顧客、公共機関などさまざまな立場の人から聴取し、そこで得た情報と社内分析に基づいて、持<br />
続可能な事業を目指すための活動分野を決めている。これがCR'Corporate Responsibility(プロ<br />
グラムの土台となっている。同社のCRプログラムには、2007 年から新たにミレニアム開発プログ<br />
ラムが加わった。これは、国連ミレニアム開発目標'MDGs(の達成に、シーメンスが企業として貢<br />
献するための製品とソリューションの開発に取り組むものである。<br />
シーメンスは、貧困の削減を目的としたプロジェクトなどに参加すると同時に、新興・途上国を<br />
“市場”として捉え事業拡大の可能性を開拓することにより、MDGsにコミットメントしようとしている。<br />
新興・途上国市場ではこれまで事業成長の可能性を十分に活用していなかったとし、今後は現地<br />
市民の利益創出に貢献すると同時に、企業として長期的観点から新しい事業チャンスを作り出す<br />
ということも含めてアプローチする、としている。<br />
シーメンスは 2005 年ごろから、企業として目指す未来像'Picture of the Future(を明確にして戦<br />
略的な計画を打ち出し、事業成長能力の拡大を目指すという基本方針を掲げている。現行の商<br />
品、テクノロジー、顧客のニーズに対するロードマップに基づいて未来像を検証するという方法か<br />
ら、各事業がターゲットとする市場の顧客、社会、経済、環境、テクノロジーなどさまざまな要素を<br />
取り入れ、そこから生まれた将来のビジネス・シナリオを通して新たな市場、テクノロジー、顧客の<br />
ニーズ、そして新たなビジネスの可能性を検証するという方法に大きく重点を移している。そして、<br />
二つのアプローチの接点で戦略的ビジョン'Strategic Visioning(を設定し、事業別の戦略シナリオ<br />
を打ち出そうとしている。その中で、シーメンスは経済ピラミッドの底辺'BOP(を視野に入れたビ<br />
ジネスを想定している 1 。<br />
1 2009 年 7 月 9 日付けプレゼンテーション資料:BoP-aber wie? Innovation, Mitarbeiter und BOP、Picture of the<br />
Future2009 年春号など<br />
27
その他の<br />
アジア・中東<br />
12%<br />
出所:Siemens Annual Report 2008<br />
図表 1 2008 年 9 月期の市場別売上げシェア<br />
インド 2%<br />
中国 6%<br />
北・南米<br />
'米国を除く(<br />
7%<br />
シーメンスのターゲット市場は4つに区分される。<br />
出所:BoP-aber wie?<br />
米国 19%<br />
総売上高773億2,700万ユーロ<br />
図表 2 シーメンスのターゲット<br />
M1 最先端技術を駆使した最高機能、高品質の製品・<br />
サービス<br />
M3 市場へのアプローチは厳密な意味でBOP戦略ではない。ここでは“SMART”というマーケ<br />
ティング戦略のもとに、新興国・途上国を対象にした低価格商品を開発している。SMARTは要約<br />
すると「基本的な技術を用いた低価格商品」で、現地'新興市場(主導で開発、製造している。<br />
28<br />
ドイツ<br />
17%<br />
欧州・アフリカ<br />
'独を除く(<br />
37%<br />
ハイエンド事業<br />
M2 先端技術を駆使した高機能、高品質製品・サービス 現状および将来の<br />
重点事業<br />
M3 基本的技術を採用し、機能は限定的、良品質、値ご<br />
ろな価格の製品<br />
M4 シンプルデザイン、低機能、低品質、最低価格帯の<br />
製品<br />
ローエンド事業<br />
“SMART”製品<br />
新事業としての可能性
図表 3 SMART戦略<br />
出所:2009 年 7 月 9 日付けプレゼンテーション資料:BoP-aber wie?<br />
経済ピラミッドの底辺にあたるM4 市場が、シーメンスの事業に組み込める市場であるか、ビジ<br />
ネスとして成り立つかなどについてはパイロット・プロジェクトなどを通して調査している。同社が展<br />
開する数多くのCRプログラムの中で、近年取り上げられたMDGs関連のプログラムには以下の<br />
ようなものがある。<br />
A) Millennium-Development-Poject'実施期間は 2007 年?~2008 年 9 月まで(<br />
B2BとB2Gを視野に入れたBOPに関するリサーチプロジェクト。フォーカスする事業セクタ<br />
ーと地域を確定するのが目的。<br />
B) Millennium-Development-Poject'実施期間は 2007 年?~09 年 4 月まで(<br />
特定のセクターとプロジェクト地域でシーメンスがどのように貢献できるかを判断するため<br />
のビジネス・インパクト調査。<br />
C) Millennium-Development-Poject'実施期間は 2007 年?~09 年 9 月まで(<br />
持続可能な発展を可能にする世界的プログラムを開発する。シーメンスの各事業のMDG<br />
s貢献方法を調査する。<br />
商品に求められること<br />
1.製品は堅牢であること。温度、埃、湿気、電圧、周波数、<br />
操作担当者の技術レベルなど、悪環境でも機能する<br />
2.基本的な仕様である<br />
3.消費者の購買力に合った価格である<br />
4.高品質で、国際基準に対応する<br />
5. 修理が可能である<br />
6. 農村部など地方の輸送条件にも対応できる<br />
D) Millennium-Development-Poject'実施期間は 2010 年 9 月まで(<br />
持続的発展への貢献という観点からビジネスとして成り立つかを、特定市場での実地テス<br />
トを通して検証するプロジェクト'ケニアでのオフグリッド照明システム(。<br />
持続可能性推進委員会'Sustainability Board(<br />
企業の社会責任と持続的成長の実現を、具体的な事業プロセスと価値創出の流れという観点<br />
から、以前にも増して強力に推進する目的で設置された。2008 年 11 月にサプライチェーン・マネジ<br />
メント担当取締役に就任したバーバラ・クックス'Barbara Kux(氏が Sustainability 責任者として同<br />
委員会の設置を提案したとされる。クックス氏は以前勤めていたフィリップスでも同分野を担当し、<br />
29<br />
SMARTバリューを満たす<br />
製品を現地で開発<br />
Simpleシンプル<br />
Maintenance-friendly<br />
手入れしやすい<br />
Affordable購入できる価格<br />
Reliable & robust<br />
信頼性・堅牢<br />
Timely to market<br />
タイムリーな市場導入
同様の委員会を率いた“その道のプロ”と見られている。委員長としてその活動を主導している。<br />
同委員会をサポートするための事務局も設けられた。<br />
② 主なBOPビジネス商品<br />
1(SkyHydrant'スカイハイドラント(-コンパクト浄水フィルター'詳細後述(<br />
地震や洪水などの被災地、あるいは途上国の水道インフラが未整備の地域の人々に安全な飲<br />
料水を提供することを目的とした浄水フィルター。操作が簡単かつ軽量で輸送しやすいという長所<br />
が災害地への投入に最適で、2004 年 12 月のインドネシア沖海底地震の津波被災地に初めて投<br />
入された。SkyHydrant を採用したセーフウォーター・キオスク'Safe Water Kiosk(は、地域の有料<br />
水供給システムという新しいビジネスモデルとして、ケニア'2 地域(とウガンダで実地テストが行わ<br />
れている。これまでに世界中で 700 基以上が設置されている。<br />
アジア<br />
図表 4 SkyHydrant の設置先<br />
インドネシア、東チモール、バングラデシュ、スリランカ、インド、パキスタン、<br />
ネパール、フィリピン、タイ、カンボジア、チベット、中国、ベトナム<br />
太平洋地域 フィジー島、キリバティ共和国<br />
アフリカ ケニア、ウガンダ、南アフリカ<br />
中近東 オマーン<br />
中南米 ペルー、メキシコ<br />
出所:Skyjuice Foundation ホームページ http://www.skyjuice.com.au/index.html<br />
30
図表 5 SkyHydrant<br />
出所:Skyjuice Foundation ホームページ http://www.skyjuice.com.au/index.html<br />
非営利団体スカイジュース財団'Skyjuice Foundation 2 、所在地オーストリア・シドニー(が供給母<br />
体として、他のNGO、現地当局などと提携して被災地や支援対象地域に設置している。シーメン<br />
スも独自の支援スキームを通して被災地に寄贈している。<br />
2(Umeme Kwa Wote (みんなのエネルギー) 3 ―オフグリッド照明プロジェクト<br />
シーメンスの照明事業子会社オスラム'Osram 4 (が、LEDランプと充電ステーション'キオスク(<br />
を組み合わせて開発した低コストの照明システム。アフリカの多くの地域では電力インフラが発達<br />
しておらず、多くの人々は灯油ランプを使っているが、これは照度が低く、燃料代が高くつく。途上<br />
国の貧しい人々の生活環境改善に貢献するとともに、CO 2 排出低減を視野に入れた環境性の高<br />
いシステムである。<br />
オスラムは、このシステムの実用性を検証するため 2008 年 4 月にケニアのビクトリア湖畔の漁<br />
村ムビタ'Mbita(でパイロット・プロジェクトを開始している。<br />
出所:シーメンスホームページ<br />
図表 6 オフグリッド照明プロジェクト<br />
2 www.skyjuice.com.au<br />
3 http://w1.siemens.com/responsibility/de/entwicklung/off_grid.htm<br />
4 http://www.osram.de/osram_de/index.html<br />
31
a. プロジェクト概要<br />
キオスクの屋根にソーラーパネルを設置し、太陽光で発電している。キオスクはエネルギー・ハ<br />
ブの役割を果たす。ここで日中、LEDランプのバッテリーを充電する。バッテリーはデポジット方式<br />
で、利用者は充電が必要になった時にキオスクに持って行き、充電済みのバッテリーと交換しても<br />
らう。その際に充電料金を支払う。ラジオなどの家電製品の電源に利用したり、携帯電話を充電し<br />
たりすることもできる。<br />
デポジット制には、ランプやバッテリーのメンテナンスや品質管理を定期的にでき、製品を長く<br />
利用できるという長所がある。また、灯油ランプからLEDランプに切り替えることにより、利用者は<br />
エネルギーコストを 30%節約することができる。<br />
オスラムが電源線を必要としない照明器具に取り組んだのは、これを電力供給システム、<br />
O-HUBと統合してサービスを提供できるからである。オスラムのオフグリッド照明システムの中<br />
核をなす O-HUBは、PV発電により最大 10kW の発電能力を持ち、当初、照明用インフラ設備と<br />
してコンセプトされたものだった。だが、投入する地域が水質問題を抱えていることに注目し、浄水<br />
システムとの統合を思いついた。オスラムの Puritec UVC ランプを投入し、紫外線によるバクテリ<br />
ア・ウィルスの殺菌により、毎日最高 3,000 リットルの飲料水を浄水することができる。<br />
b. O-LAMP2 in 1'ツー・イン・ワン(<br />
図表 7 オフグリッド照明プロジェクト<br />
出所:オスラムホームページ<br />
バッテリーを内蔵した頑丈なランタン。明るさは 2 段階で、7W の照<br />
度は約 400 ルーメンで最長 8 時間使用できる。LEDに切り替えれば<br />
使用時間はさらに長く、読書にも十分対応できる。<br />
32<br />
図表 8
c. O-LAMP Basic<br />
DULUX EL LOLAR (12V DC 11W)を搭載し、600 ルーメンの照度で<br />
室内全体を照明できる。水や汚れよけのランプシェードは取り外しが<br />
可能。バッテリーO-BOXと合わせて使用する。夜間の漁船作業で<br />
の使用に最適に設計されている。<br />
d. O-BOX<br />
バッテリーと充電用電子部品から成る。輸送上の問題が出ないよ<br />
う ケ ー ス と グ リ ッ プ は 頑 丈 な 仕 上 げ に な っ て い る 。 100Wh で<br />
O-LAMP Basic を 8 時間以上使用できる。ラジオや携帯電話の充<br />
電電源としても使える。<br />
33<br />
上記の写真 3 枚の出所:<br />
オスラムホームページ<br />
LEDランプやバッテリーの初期投資コストとして、ケニアのNGOである Osienala がマイクロクレ<br />
ジットを提供している。プロジェクトには、国際財団グローバル・ネイチャー基金'Global Nature<br />
Fund(が運営上の援助や現地組織への仲介などを行うほか、通信大手のノキアが資金援助、ケ<br />
ニアの電力会社テームズ・ライトニング'Thames Lighting(が協力する。ウガンダの実地プロジェク<br />
トでは、ウガンダの電力会社 Dembe Electrical が支援している。<br />
3(Protos'プロトス(―植物油を燃料とする調理用コンロ<br />
調理に薪などを使っている人々は世界中で約 25 億人にのぼるとされ、有害ガスやばい煙によ<br />
る室内空気汚染が健康に悪影響を及ぼしている。この人々は電気・ガスのインフラが整備されて<br />
いない開発の遅れた地域に暮らしているか、電気・ガス料金を支払えない貧困層である。シーメン<br />
スの家電事業子会社であるボッシュ・シーメンス・ハウスゲレート'Bosch-Siemens-Hausgerät=<br />
BSH( 5 は、この問題の解決策として、植物油を燃料とする環境にやさしい調理用コンロ Protos を<br />
開発した。<br />
Protos の燃焼システムはキャンプ用コンロに似ている。植物油用タンク内をエアポンプで最大 3<br />
バール加圧すると、植物油がチューブを通ってバーナー直前に取り付けられたパイプに送られる。<br />
5 1967 年設立の Robert Bosch GmbH との合弁事業 www.bsh-group.de<br />
図表 9<br />
図表 10
そこで加熱され、気化して燃焼される。<br />
図表 11 Protos<br />
出所:GTZ<br />
http://www2.gtz.de/dokumente/bib/gtz2008-9001de-ppp-28-asien-kochen.pdf<br />
2006 年にフィリピンでの実地テストが完了し、2008 年までに 1,000 台以上使用されているとして<br />
いる。価格は約 30 ユーロで通常の調理コンロよりも低価格。環境にやさしいだけでなく、植物油は<br />
灯油よりも安く、薪よりも早く調理できるという長所がある。性能が向上し安く製造できる新しいバ<br />
ージョンも開発している。現地の経済効果を高めるため、製造、技術サービス、メンテナンス、植物<br />
油生産をローカル化している。現在、タンザニアでも実地テストが行われており、中国、インドでも<br />
準備中としている。<br />
植物油の原料は現地調達しやすいよう、ヤシの実やヤトロファなどの熱帯・亜熱帯地方に豊富<br />
な植物が用いられている。5 人家族の食事を用意するのに必要な植物油は、1 週間わずか 2 リット<br />
ルで、エネルギー効率が高いため、薪よりもかなり早く調理できる。2009 年にはインドネシアでの<br />
生産開始を予定している。ここでの事業展開を確認したうえで、Protos の潜在ニーズがあり、植物<br />
油の原料を十分確保できる地域を選んで世界展開するとしている。<br />
4(SMART商品の事例 6<br />
インドにあるコーポレート・テクノロジー'CT(事業部にはSMARTイノベーション部門が設けら<br />
れ、SMART商品を開発している。<br />
a.検査用カメラ<br />
6 Pictures of the Future 2009 年春号を参照<br />
34
インドではプロセッサの処理能力が向上すると同時に価格が低下し、テーラーメードのプログラ<br />
ムの質がどんどん良くなっているおかげで、生産工程で使用する品質検査用カメラは購入しやす<br />
い価格になり信頼性も向上している。それだけに市場競争は厳しい。「このような製品をインドで<br />
生産するということは、ローカル企業との価格競争に対抗するためには重要だ」とムクル・サクセ<br />
ナ'Mukul Saxena(CT事業部長は述べ、インド子会社がなぜSMART戦略に力を入れているかを<br />
説明している。「顧客のそれぞれのニーズに合わせてカメラの性能を調整できるアルゴリズムは、<br />
サービスとアップグレードの料金をできるだけ低く抑えるためのカギにもなっている」と、Industry<br />
Automation 事業部のSMARTイノベーション部門部長のズービン・バルゲーゼ'Zubin Varghese(<br />
氏も、SMART商品が価格競争力を重視したものであることを強調する。例えば、たばこメーカー<br />
が品質向上のため検査用カメラの設定変更を要求してきた場合、新しい画像処理設定値に合うよ<br />
うカメラのソフトウエアを微調整すればすむので迅速に対応できる。クッキー製造工程の最適化の<br />
ために投入されたケースでは、エネルギーコストの 5%削減にも貢献した。<br />
SMARTカメラ技術の開発に投資することは利益拡大につながるという。つまり、この技術が顧<br />
客のニーズに柔軟にカスタマイズできるため、オーブン、センサー、酸素分析機器、コントローラー、<br />
ヒューマン・マシン・インターフェイスなど、同社の他の事業分野の商品にも投入できる道が開かれ<br />
たからだとしている。<br />
b. コンピュータ断層撮影装置―CT Somatom Spirit 7<br />
当初、中国の辺境地の病院を対象に開発された低価格で高品質のコンピュータ画像診断装置<br />
である。シーメンス上海の医療機器部門の研究開発責任者、Jun Kong 氏が開発を指揮した。マー<br />
ケティング、販売部門の協力を得て顧客の声を聞き、現場が求められている装置を定義した。<br />
� コストパーフォーマンスがよい<br />
� 信頼性が高い。<br />
� 操作が簡単。<br />
� 短期間で投資コストを回収できる。<br />
地方の小病院のニーズだけでなく、大病院が肺などの簡易な検査用に 2 台目の装置を必要と<br />
する場合も通常の装置より低価格なので適している。2006 年半ばまでに約 400 台を販売し、国外<br />
からの受注も 4 台あった。現地開発、現地製造、現地調達により、コストを先端モデルの約 6 分の<br />
1 に引き下げている。商品としての強みは、堅牢性、操作が簡単、場所をあまりとらない、スピーデ<br />
7 2009 年 7 月 9 日付けプレゼンテーション資料'前述(、Pictures of the Future2006 年秋号<br />
35
ィに設置'1 日(できること。同製品の成功は、「中国の顧客をターゲットにするなら中国人の商品<br />
マネージャーが必要。その市場を理解できるのは彼らしかいない」という事実を示している。<br />
c. 発電蒸気タービン 8<br />
ブラジルでは自動車燃料に占めるバイオ燃料の比率が高く、サトウキビを原料としたエタノール<br />
は約 4 割を占めている。エタノール工場では、エネルギー効率の向上を目的として、サトウキビの<br />
残留物を燃料としてバイオマス発電が行われている。シーメンス・ブラジルで産業用発電タービン<br />
の販売・マーケティングを担当するパウロ・コスタ'Paulo Costa(氏は、「この市場では初期投資コ<br />
ストと耐用期間による経費効率のトレードオフは、他の国とやや異なる」と述べ、現地顧客が価格<br />
に敏感であることを指摘している。<br />
シーメンスは、ブラジル顧客特有の要望に対し、欧州で実績のあるタービンモデルをブラジル市<br />
場のニーズに対応して改良、蒸気タービンの改良モデル SST300 を開発した。ドイツとブラジルの<br />
タービン事業部のエンジニアがチームを組み、ブラジル顧客の特殊なニーズを満たすよう、数ヶ月<br />
かけて改良した。また、ブラジルで調達できる材料・コンポーネントを使って製造できるようにもした。<br />
品質と安全性で妥協は許さず、価格は従来のモデルよりも約 30%安くし、ブラジルのどこのサトウ<br />
キビ加工工場でも購入できるようにした。エタノールの激しい価格競争で、製造工程の効率化とコ<br />
スト削減に取り組むサトウキビ業者には、改良タービンの性能が高く評価されている。現在は、ペ<br />
ルー、アルゼンチン、コロンビア、メキシコなどでも販売されている。<br />
5(Rural Center of Medical Excellence 9 ―辺境地医療センターネットワーク<br />
中国辺境部の医療サービスの改善を目的に、革新的な地方医療ネットワーク・モデルとして開<br />
発された。中国保健省の協力を得て、5 ヵ年で 1,000 万ドルを投資するプロジェクトとして、2007 年<br />
4 月に開始した。地域内の各集落に超音波画像診断装置やレントゲン診断装置'CT、MRI、X線<br />
透視装置など(を備えた医療センターを開設し、これらを近隣の病院とネットワーク化する。遠隔ラ<br />
ジオロジーシステム'Tele-Radiologie(により、州都である西安の大規模病院の医師と共同で画像<br />
を見て診断することができる。また、現地の医師、看護士、レントゲン技術者など医療従事者の教<br />
育にも役立っている。プロジェクトではシステム改良を目的に辺境地域の医療体制も並行して調<br />
査している。現在、中国山西省北部で調査が実施されており、他の地域に拡大していく計画だ。こ<br />
のプロジェクトはCS活動の一環として行っている。<br />
6(Village Connection―辺境地移動体通信サービス<br />
8 Pictures of the Future 2009 年春号'前述(<br />
9 http://w1.siemens.com/responsibility/de/entwicklung/rural_center.htm<br />
36
ノキア・シーメンス・ネットワーク'Nokia Siemens Networks 10 (が辺境地域向けに開発した、低コ<br />
ストで電力効率の良い移動体通信網を構築する。住民一人一人に恩恵があるだけでなく、医療や<br />
事業分野などの分野でもサービスが活用され経済効果を生むとしている。また、投資コストが低<br />
いため小さな町でも通信ネットワークを運営でき、雇用創出につながる新たなビジネスモデルと位<br />
置づけている。2009 年 10 月に International Telecommunication Union(ITU)と提携し、パイロット・<br />
プロジェクトに着手したばかり。実施母体はITUで、現地政府から政策、行政上の支援を受ける。<br />
第 1 弾として太平洋の島でテストする。群島に点在する 30 の村落をネットワーク化することを目的<br />
としている。<br />
'2(事例に見るBOPビジネスの推進方法<br />
① 商品・事業の開発プロセス<br />
SkyHydrant はシーメンスの Water Technologies 事業部の Memcor 薄膜技術を用いた浄水フィ<br />
ルターである。以下に説明するように、社会的使命感に燃えた一人の技術者の、途上国の安全な<br />
飲料水確保という問題への個人的な取組から生まれた。本来、販売を目的として開発されたもの<br />
ではなく、シーメンスもまだ事業として捉えていない。基本的には、安全な飲料水を飲むことができ<br />
ず健康が脅かされている人々を支援するためのツールとして、緊急支援用に設置されるケースが<br />
ほとんどである。ただ、ケニアで実施中の SkyHydrant を使ったコミュニティ向け浄水システム、ウ<br />
ォーター・キオスク・プロジェクトは、上水道インフラがない地域に安全な飲料水を持続的に供給す<br />
るためのビジネスモデルとして、その運営の進捗状況を見守っている。<br />
1(開発の経緯 11<br />
SkyHydrant は、途上国での务悪な水問題の実情を目の当たりにした浄水技術製品の販売担<br />
当マネージャーであるレット・バトラー'Rhett Butler(氏が、純粋に個人的な熱意から就業時間外<br />
に開発に取り組んだものである。エンジニアである同氏は、オーストラリアの薄膜テクノロジー先<br />
端企業、メムコア'MEMCOR(に 1986 年に販売マネージャーとして入社。メムコアは 2004 年にシー<br />
10 ノキアとシーメンスの合弁通信回線事業 www.nokiasiemensnetworks.com<br />
11 シーメンス作成小冊子:Notizen Impulse – Mehr. Wert. Schaffen. Engagement hat viele Gesicher 及び広報誌<br />
Pictures of the Future2008 年秋号掲載インタビュー:“Das globale Trinkwasserproblem ist lösbar”などを参照<br />
37
メンスに買収され、現在は Siemens Water Technologies に統合されている。同氏は仕事で世界中<br />
を駆け巡る中、汚染した水を飲料水として使っている途上国の生活実態を目の当たりにして、メム<br />
コアの製品がいかに高性能であるといっても、大きさ、操作性、価格などの観点から、本当に必要<br />
としている人々に利用してもらうには条件がまったく合わないということを痛感したという。途上国<br />
向けの解決策を見つけたいという一心で、バトラー氏は 2001 年から終業後、自宅のガレージで自<br />
社製品の材料の残りを使って独自に開発に取り組んだ。メムコアの最先端産業向け浄水装置と<br />
同じ薄膜フィルターを使って、単体として投入することができるコンパクトな浄水フィルター装置の<br />
プロトタイプを完成させた。<br />
当初の SkyHydrant'当時は現在のモデルよりもっと小型だった(への反応は冷ややかだったよ<br />
うである。バトラー氏はさまざまなNGOに無料提供を申し出たが相手にされなかったとしている。<br />
SkyHydrant が実際に投入されたのは、2004 年 12 月のインドネシア沖地震による津波の被災地だ<br />
った。インドネシア、タイ南部を中心とした被災地では、水源汚染などで安全な飲料水が不足し、コ<br />
レラなどの伝染病が発生する危険にさらされていた。バトラー氏は、オーストラリアのNGOである<br />
Clean Up Australia の支援活動に、メムコアの社員として参加した 12 。同僚とボランティアの助けを<br />
借りて、数週間で SkyHydrant を 100 基以上製造したという。これをスリランカに輸送し、ここを経由<br />
してインドネシアやタイの被災地にも送った。1 基約 16kg という軽量さが、緊急事態にある被災地<br />
に迅速な支援を提供するための最善策として評価されたとしている。<br />
バトラー氏は 2005 年に一時休職し、非営利目的のベンチャー組織、スカイジュース財団<br />
'SkyJuice-Foundation( 13 をシドニーに設立した。財団の活動目的は、途上国および被災地のコミ<br />
ュニティに、持続可能かつ購入可能で現地にふさわしい浄水システムを、さまざまなパートナーと<br />
協力して提供することであり、これにより国連ミレニアム目標'MDGs(の達成に貢献することであ<br />
る。バトラー氏を代表者とする設立メンバー8 人が、財団の資金管理と社会活動を行い、世界中各<br />
地での SkyHydrant の設置を手配している。対象地は被災地だけでなく、NGOなどからの要請や<br />
提案をも とに選び 出している。運営資金は多方面から の寄付に よる。スカイ ジュースは<br />
SkyHydrant の供給母体として、シーメンスから Memcor フィルターを購入し、製造している。シーメ<br />
ンスはサプライヤーであるだけでなく、数多くの寄付提供機関のひとつとして寄付金を提供するほ<br />
か、CSR活動の一環として、スカイジュースから SkyHydrant を購入し被災地に寄付するなどで普<br />
及に努めている。<br />
スカイジュース副代表のジャン・ヒュー氏は、シーメンスからの支援について以下のようにコメン<br />
トしている。<br />
12 Australian Broadcasting Corporation TV Program Transcript http://www.abc.net.au/<br />
7.30/content/2005/s1281749.htm<br />
13 www.skyjuice.com/<br />
38
� シーメンスは、同社が事業展開する国の自然災害の被災地にケアリング・ハンズ'シーメンス<br />
のCSR活動の主体となるNGO―詳細後述(を通して支援してくれている。ケアリング・ハンズ<br />
はスカイジュースから SkyHydrant を購入し、スカイジュース財団、あるいは現地NGOや国際<br />
NGOが被災地に設置している'過去にはオマーン、メキシコ、ペルー、ミャンマー、中国、フィ<br />
リピン、オーストラリアの例があり、ベトナムとインドネシアのプロジェクトはもうすぐ完了する<br />
予定(。<br />
図表 12 SkyHydrant 供給の流れ<br />
� シーメンスの従業員は、独自に定期的に募金活動し、集まった資金を寄付してくれる。私が<br />
担当者として、スカイジュースの活動パートナーが推進する人道的なプロジェクトに、寄付金<br />
を全額供与する。シーメンスの従業員は、スカイジュース財団の存在と、我々が過去に行っ<br />
たプロジェクトや、World Water Day、被災地救援活動に注目している。彼らの自主的な寄付<br />
を資金に、スカイジュースは先ごろのパダンやスマトラ西部の被災地や、インドの学校に<br />
SkyHydrant を設置した。<br />
� シーメンスの Water Technologies (SWT)事業部は寄付金を集め、World Water Day で資金提<br />
供のスポンサーになってくれた。2008 年は東チモールで 2 ヵ所、今年はチベットと中国で設置<br />
プロジェクトを実施している。<br />
2(SkyHydrant の製品概要<br />
シーメンス<br />
Water<br />
Technologies<br />
SkyHydrant の機能・特性は下記の通り。<br />
スカイジュース<br />
� 第 1 段階の除菌と粒子除去のためのマイクロフィルター'1 万のマイクロファイバーからなる(<br />
39<br />
国際支援機関<br />
コミュニティ<br />
ケアリングハンズ<br />
'シーメンスNGO(<br />
SkyHydrant<br />
y薄膜フィルター供給 注文・購入<br />
製造<br />
ボランティア支援<br />
SkyHydrant供給の流れ<br />
設置<br />
設置援助<br />
現地人指導<br />
安全な飲料水にアクセスできない被災地・コミュニティ
と、塩素殺菌機能の組み合わせにより、塩分をほとんど含まない地下水を安全な飲料水に<br />
浄化する。ミクロサイズの多孔減圧薄膜により、原水に含まれる汚染物質やバクテリア、寄<br />
生虫、一部のウィルスなどを除去できる。<br />
� 浄水機能、薄膜のクリーニング機能も非常に簡単で、手動操作で行える。高い浄水機能を維<br />
持するためには、薄膜のクリーニングを効率的に行うことが重要で、手作業で簡単かつ迅速<br />
に行うことができるようになっている。1 回のクリーニングに約 90 秒かかり、原水の濁度など<br />
により毎日~毎週の割合で実施する。さらには、水洗いでは除去できない残滓を除去し、微<br />
生物が繁殖しないよう、簡単なケミカルクリーニングを定期的に実施する必要がある。<br />
� 消耗パーツなし。浄水工程には可動パーツは使われていない。<br />
� 有害なろ過廃物や温暖化ガスを排出しない。<br />
� コンパクトでフレキシブルなデザイン。さまざまな場所に設置できる。<br />
図表 13 SkyTower<br />
スカイタワー:1基での設置モデル 複数での設置モデル<br />
出所:スカイジュース・ホームページ<br />
バトラー氏らは技術改良を続け、2008 年には SkyHydrant Mark2 という性能を向上させたバージ<br />
ョンを完成させた。初代 Mark1 がきわめて基本的なモデルであるのに対し、新しい Mark2 は性能<br />
がかなり優れていると同時に、より頑丈で軽く、操作しやすく、安く製造できるとしている。現在は、<br />
将来的に SkyHydrant のプラットフォームとするための Mark3 の開発に取り組んでいる。スカイジュ<br />
ースはホームページで、2009 年には完全なスタンドアローン・タイプの飲料水供給システムとして<br />
さらに高性能の装置を発表するとしているが 14 、11 月時点でまだ発表されていない。<br />
② 生産・供給体制<br />
当初は Siemens Water Technologies の設備を借りてスカイジュースのメンバー、ボランティア、<br />
14 SkyJuice Foundation の電子ニュースレター:Hightlights for 2008 参照<br />
40
シーメンス社員で製造していたと思われるが、2008 年夏以降はスカイジュースがシーメンスから<br />
Memcor フィルターを購入し、自主生産するという形に切り替わった。週 200 基の生産能力がある<br />
としている 15 。2005 年 1 月にスリランカに供給してから現在までの累計設置台数は 700 台を超える。<br />
NGO等への供給価格は約 3,000 米ドル程度とみられる 16 。<br />
2009 年の設置プロジェクトはタンザニア、ウガンダ、ケニア、ナイジェリア、フィリピン、キリバティ、<br />
カンボジア、インドで行われ、NGOや現地の支援団体と共同で活動している。<br />
③ 公的機関・NGO・国際機関等との連携<br />
SkyHydrant の供給と設置は、スカイジュースの主導で主にOXFAM、ワールドヴィジョン'World<br />
Vision(、国際赤十字、国際保健機関'WHO(、ADRA 'Adventist Development and Relief<br />
Agency(、ロータリークラブ'Rotary(、オーストラリア国際援助'Australian Aid International=AAI(、<br />
ユニセフ'UNICEF(、OZ Green、Samaritan’s Purse 等と共同で行っている。また、シーメンスのC<br />
SR活動ユニットであるケアリング・ハンズ、Water Technologies 事業部の社員、現地の社員なども<br />
協力している。<br />
SkyHydrant にかかわるプロジェクトが、公的機関やNGOとどのように協力して進められている<br />
か、以下に事例を紹介する。<br />
1(セーフウォーター・キオスク・プロジェクト 17<br />
ケニアのコミュニティレベルの水質改善や環境教育を目的として、オーストラリアのニューサウ<br />
スウェールズ州北部のトゥイード・シャイア市議会は、ケニア・モニタープログラム'Tweed Shire<br />
Council- Kenya Mentoring Program 18 =TSC-KMP(を推進している。この一環で、2007 年 3 月にセ<br />
ーフウォーター・キオスク・プロジェクトがスタートした。プロジェクトの実施地には、ビクトリア湖近く<br />
のオバンボ'Obambo(とカデンジ'Kadenge(というふたつの集落が選ばれた。この地域にはほとん<br />
ど雇用がなく、農作で自給生活をする人が多い(生計費 1 日 1 ドル以下)。汚染された水源からしか<br />
飲料水を得ることができない住民に衛生的な浄水を提供するため、スカイジュースがスカイステー<br />
ションを 1 台設置した。近隣のゴナ・ダムが水源となった。<br />
15 SkyJuice Foundation の電子ニュースレター:同上<br />
16 広報誌 Pictures of the Future2008 年秋号掲載インタビュー'前掲(<br />
17 Tweed – Kenya Mentoring Program Safe Water Project: Obambo-Kadenge<br />
18 トゥイードシャイア市と NGO“Gallamoro Network”'本拠地ナイロビ(が共同で実施。2004 年に毎年 1 万米ドルの<br />
予算で 5 年間プログラムとしてスタートした。<br />
41
図表 14 ウォーターキオスクと、ダムから水を引くための風力発電装置<br />
a. プロジェクト参加団体の役割<br />
出所:スカイジュース・ホームページ Phase I: Gona Dam Safe Water Kiosk-Kenia<br />
図表 15 セーフウォーター・キオスク・プロジェクト参加団体<br />
団体名 役割<br />
TSC-KMP 推進母体<br />
Tweed Shire Council<br />
国際河川財団(International<br />
River Foundation)<br />
スカイジュース スカイステーションを提供。<br />
現地コミュニティ 個人、団体、教会など<br />
数名の市職員が無給休暇を取り、同プロジェクトにボラン<br />
ティアとして参加。装置を輸送、現地での設置を援助する。<br />
河川や水源の保護、再生を目的として、途上国と先進国の<br />
長期的関係構築を目指して専門家ネットワーク作りを行う。<br />
このプロジェクトを通して、スカイジュースが仲介役となり、事業者としてのシーメンスと、受益者<br />
としてのローカルコミュニティが結ばれている構造が浮かび上がる。<br />
42
. 実施プロセス<br />
図表 16 シーメンスとローカルコミュニティ<br />
出所:2009 年 7 月 9 日付けプレゼンテーション資料'前掲(<br />
1. WHOの国際飲料水品質管理基準などを元に、水源政策、ガイドラインの検証、政府当局と<br />
のコミュニケーションを図る。<br />
2. 現状の水源・水質、供給状況を評価する。<br />
3. 浄水システムの設計を含め水質管理計画を開発する。<br />
4. 水質管理計画をモニターし、評価する。水質管理計画には水の管理に関するノウハウの指<br />
導、現状の飲料水取得方法の評価、リスク確認、新システムの設計、新システムの稼動とメ<br />
ンテナンス、新システムによる飲料水の品質評価、運営管理、プロジェクト評価などが含まれ<br />
る。<br />
c. 投入した SkyHydrant の性能<br />
SkyHydrant は、持ち運び可能で化学薬品を使用しておらず、また 1 人に付き年間 20 ユーロセ<br />
ント以下という低価格のため、最貧国・地域への配給も可能である 。また、シーメンス製の<br />
Memcor 低圧縮膜をシステム内に配置しており、原水の汚濁度によるが一般的に一日 2 万~3 万<br />
リットルを浄水、200 人の日常需要'一人当たり 50 リットル(を満たす。さらに SMF1 フィルターを通<br />
して一時間 2,200 リットルの飲料水を村落に供給できる 。<br />
シーメンスは SkyHydrant システムに改良を重ね、軽量化された SkyHydrant Mark 2 を 2008 年<br />
に発売した。デザインにも改良を施した Mark 3 も発売する予定であり、これを大量生産する計画<br />
である。<br />
d. プロジェクト:設置予算<br />
シーメンスWater Technologies ローカルコミュニティ<br />
� 潜在市場へのコミットメント<br />
� セーフウォーターキオスクは利用者<br />
から料金を徴収して運営<br />
� 低コストで社会に貢献<br />
� MEMCORフィルター技術の利用<br />
スカイジュース<br />
43<br />
� 持続的な給水設備を簡単に<br />
運営できる<br />
� 濁りのない安全で購入可能な<br />
価格の水を、一人当たり年間<br />
0.2ユーロ以下で提供<br />
� 浄水後の水質はWHOの全最低<br />
基準地をクリア
e. コミュニティの自主運営<br />
図表 17 プロジェクトの予算<br />
出所:Tweed – Kenya Mentoring Program Safe Water Project: Obambo-Kadenge<br />
ローカルコミュニティは、プロジェクトの遂行で最初から中心となって動けるよう、住民代表 12 人<br />
で構成する運営委員会を発足。設置用地の取得、キオスクの建設、タンクの設置、風力発電用の<br />
風車や発動機の選択にも関わった。これらの活動を通して、委員会メンバーにプロジェクト成功へ<br />
の自覚が強まったようである。<br />
浄水フィルターとポンプの操作やメンテナンスの訓練を担当するチームとして、担当委員会が設<br />
けられ、スカイジュースのオペレーション・メンテナンスマニュアルを使って、メンバーが簡単な操作<br />
を習得している。<br />
収入(主に寄付金) 米ドル<br />
Tweed Shire Councilのスタッフ拠出金スキーム 1,420<br />
Mr. Martin Albrecht(International Riverfoundation) 1,500<br />
Siemens –SkyJuice Foundation 1,500<br />
Tweed市(Murwillumbah SDAChurch, Murwillumbah Central Rotary, John<br />
Tyman, Pottsville Community Group,スタッフの寄付)<br />
44<br />
3,300<br />
――徴収済み収入合計―― 7,720<br />
Tweed Shire Councilのスタッフ拠出金スキームとTweed市の拠出金<br />
(向こう6ヵ月で支払い)<br />
7,780<br />
―――――合計――――― 15,500<br />
支出<br />
SkyStation'Skyhydrant3基( 11,500<br />
スタッフの航空運賃、保険、ビザ、医療費 3,500<br />
現地経費 500<br />
―――――合計――――― 15,500
図表 18 操作を研修した現地コミュニティのオペレーター<br />
出所:スカイジュース・ホームページ<br />
Phase I: Gona Dam Safe Water Kiosk-Kenia<br />
当初はプロジェクト支援団体の寄付を受けていたが、コミュニティは後にマイクロクレジット銀行<br />
から資金を借りて自営を始めた。小額の浄水使用料を月ベースで徴収して経費をまかなうレボル<br />
ビング方式で運営している。<br />
f. 第 2 プロジェクト 19<br />
図表 19 プロジェクトの概要<br />
利用住民数 推定2,500~3,000人<br />
一人当たりのコスト 年間50セント以下<br />
設計上の使用期間 10年<br />
プロジェクトコスト(管理費、事務所費含む) 一人当たり8~10米ドル<br />
推定システムコスト 一人当たり年間20セント<br />
1リットル当たりのコスト 0.002セント<br />
フィルターのマニュアルクリーニング 週1回<br />
フィルターのバックウォッシュ 1日3回<br />
マイクロファイナンス銀行 TBC<br />
出所:スカイジュース・ホームページ<br />
Skyjuice Foundation Phase I: Gona Dam Safe water Kiosk –Kenia<br />
セーフウォーター・キオスク・プロジェクトは、2008 年 11 月に第 2 プロジェクトに着手した。設置<br />
対象となったのは、ケニア西部のアレゴ'Alego(地域である。第 1 プロジェクトと住民の生活環境は<br />
19 Safe Water Project 2, Report on Project Delivery, November 2008<br />
http://www.tweed.nsw.gov.au/Kenya/Documents/Reports/SafeWater2ProjectDeliveryReportNovember2008.pdf<br />
45
似ている。このあたりは、森林伐採により河川の水量が減り、政府やNGOが井戸を掘ったりした<br />
が塩分を含むなど飲料水には適さない。雤期に水量を確保できるティンガ・ダム'Yawo Tinga(に<br />
スカイステーションが 1 台設置された。同プロジェクトでは、スカイジュースがスカイステーションや<br />
他の資材を合わせて総額 2 万米ドル相当を寄付した。<br />
セーフウォーター・キオスク 2 号は目覚しい成果を挙げているという 20 。コミュニティは 2009 年 2<br />
月に料金徴収制度を導入し、1 所帯当たり 1 ヵ月 20 ケニアシリングと登録料 50 シリングの徴収を<br />
始め、3 月末までに 303 所帯が登録した。月契約をしない場合は、20 リットル当たり 2 ケニアシリ<br />
ングで水を提供。ただ、料金を徴収するようになって浄水の利用が減ったという。いかに料金が安<br />
いといっても今までタダだったものにお金を払うことを敬遠する人は尐なくないと見られる。収入減<br />
尐はキオスク運営にとっては大問題で、「小さな負担でプロジェクトを持続的に運営することができ、<br />
コミュニティの住民の健康も保てる」ということを住民に理解してもらうよう、運営委員会は村長や<br />
村の長老たちと協力して溜池の水が非衛生であることを理解させる努力を続けているという。<br />
2(その他のプロジェクト―Face Africa のリベリア・クリーンウォータープロジェクト<br />
'Clean Water Liberia Project(<br />
アフリカの困窮するコミュニティを支援する米NGOの Face Africa は、スカイジュースを公式パー<br />
トナーに選んでいる。Face Africa は 2009 年、リベリア農村部のコミュニティが安全な飲料水を確保<br />
できるよう、クリーンウォータープロジェクトをスタートした。既存の井戸の再整備と併せて<br />
SkyHydrant の設置を行うとしている。<br />
④ 事業展望<br />
SkyHydrantに関する知的財産権はシーメンスとスカイジュースが共同で保有している。シーメ<br />
ンス、スカイジュースともにCSR活動の延長線上で最新技術をできるだけ安く提供することを目指<br />
しており、基本的に利益追求事業としては位置づけていない。バトラー氏は、「SkyHydrant は商用<br />
製品ではない。スカイジュースはこのユニットとシステムがNGOの手に渡りやすいようにするため<br />
の仲介役を担っている」 21 と言っている。<br />
ただし、シーメンスとバトラー氏は、共通の倫理的目的にもとづく事業であれば一般ビジネスとし<br />
て実施することは考えられるとし、条件付での商品化を容認している。スカイステーションを投入し<br />
たセーフウォーター・キオスク・プロジェクトには、泥水を使用していた住民に安全な飲料水を提供<br />
することでMDGsの達成に貢献するというだけでなく、スカイステーションがインフラの整備されて<br />
20 TKMP News2009 年 5 月号 www.tweed.nxw.gov.au/kenya/News.aspx<br />
21 Water Desalination Report 3. December 2007<br />
46
いないコミュニティで持続可能な浄水供給システムとして機能するかどうかを検証する役割があ<br />
る。<br />
セーフウォーター・キオスクは、2007 年の社内コンペであるコーポレートレスポンシビリティ賞<br />
'詳細後述(を受賞した。そこでバトラー氏ら受賞者は以下のような成果をもとに、ビジネスとして<br />
の将来性があることを指摘している。<br />
達 成<br />
目 標 = ゴール<br />
図表 20 セーフウォーター・キオスクの成果<br />
出所:SiemensWorld 12/2007 www.skyjuice.com.au/documents/swarticleDE2007.pdf<br />
ビジネスの可能性があるといっても、セーフウォーター・キオスクは、NGOなどの寄付や設置援<br />
助に頼っている現状を考えれば、具体化するには相当な時間がかかるとみられる。ビジネスとし<br />
て成り立つには、ローカルコミュニティの自主的な参加が必要であり、彼らが調達できる低価格を<br />
維持でき、自主運営がうまく機能することが前提である。商業生産となれば、相応の設備投資と人<br />
件費がかかり、低価格を維持するためには相当の苦心・工夫が必要になるだろう。このようなこと<br />
から、シーメンスにとっては SkyHydrant が普及すれば Memcor 薄膜フィルターの販売が増えるの<br />
で収益にはつながるが、これは基本的にはCSRの延長線上にあり、企業イメージ向上に貢献す<br />
る活動と位置付けていると思われる。<br />
シーメンス本社CSR担当部署のブットケライト氏は、「シーメンスにとってBOPビジネスとは何<br />
か」という質問に対し、「シーメンスの事業はかなりの部分がB2Bであり、BOPはあまり重要な事<br />
業分野ではない。現状ではOSRAMの事業'オフグリッド照明システム(にしか具体的な可能性は<br />
見ていない」ときっぱりと回答している。<br />
� きれいで安全な飲料水をひとり当たり1年間50セント以下で提供できる。<br />
� 水質は最低基準値を全てクリアできる。<br />
� システムは世界中で投入が可能。潜在市場規模は200万ユニット以上。<br />
� 水の衛生に関する教育プログラムを推進できる。<br />
� 十分なコスト・ベネフィット・レシオを確保できる。<br />
� 新たなプロジェクト実施地を探す。<br />
� 潜在市場を開拓する。<br />
インフラ事業大手のシーメンスが、BOP市場にアプローチするとき、その商品が途上国のロー<br />
カルコミュニティのためのマイクロ・インフラシステムであるというのは明確である。ただ、そのシス<br />
テムがコミュニティの一人一人に利用され社会全体の生活向上につながるためには、持続可能な<br />
管理・運営が実現できるかどうかにかかっている。ケニアで行われているオフグリッド照明システ<br />
ムの実地検証も、同じ理由では根気を要する取組であると見られる。<br />
47
'3(BOPビジネス推進に係る社内体制<br />
シーメンスは、“イノベーション”がテクノロジー企業としての生命線を握ると考え、イノベーション<br />
にはトップダウンとボトムアップの双方から取り組んでいる。次の図はシーメンスグループの本体<br />
であるドイツ・シーメンス'AG(のモデルである。<br />
図表 21 シーメンス AG のトップダウン・ボトムアップのスキーム<br />
ト<br />
ッ<br />
プ<br />
ダ<br />
ウ<br />
ン<br />
出所:SiemensAG プレゼンテーション資料 2005 年 9 月 11 日<br />
① コーポレートレスポンシビリティ賞(Corporate Responsibility Award)<br />
従業員には、技術的な挑戦に取り組むだけでなく、社会問題の解決に持続的に取り組むため<br />
のプロジェクト推進を奨励している。このような取組を評価するため、コーポレートレスポンシビリテ<br />
ィ賞'Corporate Responsibility Award(が設けられた。2007 年の第 1 回の選考には、35 カ国から<br />
182 のプロジェクトが提出された。従業員のモチベーション高揚に役立っている。<br />
選定では、特にMDGs達成に企業としていかに責任を果たせるかという観点が重視される。し<br />
たがって、製品そのものではなく、それを使うことにより現地社会でどのような価値創造を実現で<br />
きるかのビジネスモデルが問われる。<br />
シーメンスAGのトップダウン・ボトムアップのスキーム<br />
イノベーションのビジョンとミッションの提示<br />
トップマネジメントの関与<br />
絶えず社内、社外のコミュニケーションをとる<br />
イノベーションの推進と管理の規則<br />
基礎研究の推進<br />
提携先や大学・研究機関との協力<br />
従業員に提案を促すインセンティブプログラム<br />
48<br />
ボ<br />
ト<br />
ム<br />
ア<br />
ッ<br />
プ
図表 22 2007 年受賞プロジェクト:セーフウォーター・キオスク<br />
受賞チーム I&S Water Technologiesオーストラリア(レット・バトラー、トニー・ハンダカス、<br />
ブルース・ビルトフトの3氏)<br />
成功要因<br />
受賞者チームは賞金'金額不明(をスカイジュースに寄付した。寄付金は、SkyHydrant をバング<br />
ラデシュに約 30 基、東チモールに 3 基設置する資金の一部に当てられた 22 。<br />
2008 年は Umeme Kwa Wote 'オスラムのオフグリッド照明サービスシステム(が受賞した。<br />
このほかにも、社内コンペが活発である。3 年に 1 度授与される環境賞は、商品、製造プロセス<br />
に関するイノベーションや、環境保護に寄与する取組に贈られる。また事業所単位での提案シス<br />
テム、発明コンペ、イノベーション・コンペもあり、全体としてイノベーションや新たな取組にやる気<br />
がでるような社風がある。<br />
'4(公的機関・NGO・国際機関等との連携<br />
シーメンスはインフラ関連業界の世界大手として現地政府や当局と長年にわたる密接な関係を<br />
構築しており、新興国・途上国での企業活動で大きな強みを持つ。<br />
シーメンスは、企業が利益を生むためには社会環境が安定し社会が繁栄することが必要であ<br />
るという信念から、世界中で社会活動に取り組み、ローカルコミュニティの一員として広く認められ<br />
るよう努力している'コーポレート・シティズンシップの促進(。そしてこれら活動を通して、シーメン<br />
スの評判が高まることを期待している。なぜなら、インフラ・ソリューションを提供する企業として、<br />
社会に根を張り、社会で高い評価を得ることは事業成功の最大の要因と捉えているからだ。この<br />
方針に沿って、現地企業がそれぞれの現地コミュニティで社会活動を行っている。<br />
22 Siemens News April 2008<br />
� 関係者全てに支援を求め、プロジェクトの全ての段階においてローカルコミュニ<br />
ティを巻き込んだ。<br />
� スカイジュース財団と協力した。<br />
� 消耗パーツ、化学材料、可動パーツを使わないローコスト・テクノロジーを採用<br />
した。<br />
� コミュニティのメンバーにフィルターとポンプの稼動やメンテナンス技術を指導<br />
し、現地人が自主管理できるようにした。<br />
� コミュニティがシステムを保有し、明確な料金体系で運営している。<br />
49
① CSR活動<br />
1(シーメンス・ケアリング・ハンズ'Siemens Caring Hands(<br />
シーメンスは事業を展開している地域の発展に貢献し、ローカルコミュニティの役に立つ義務が<br />
あるとして、寄付、スポンサーシップ、商品やノウハウの提供などさまざまな形で持続的な貢献を<br />
行っている。この活動を世界レベルでコーディネートする目的で、ケアリング・ハンズは 2005 年、N<br />
GOとして立ち上げられた。シーメンスの災害支援や社会福祉などの社会貢献活動を取りまとめ、<br />
また寄付金を管理している。<br />
支援のキーポイント<br />
� コンセプトのない社会的寄与は行わない―目的、支援するグループ、活動を通して伝えるこ<br />
と、方法、支援で何を得ようとするのかを明確にする。<br />
� 資金収集―支援効果を拡大するため、従業員からの募金額に会社として同額を加える。<br />
� 個人的な支援は行わない―会社としての社会寄与であることを明確にする。<br />
� シーメンスのイメージ向上に寄与する―人々、社会、環境に同社の技術、活動を投入する。<br />
� 持続性と長期性―社内外のイメージ効果が出るには通常、最低 1 年間かかる。<br />
� 関連組織などへの情報提供により、活動を広く知らしめる。<br />
� 支援団体・活動の基準―児童・青尐年関連、教育、外国人差別、障害者援助、エイズ、ホー<br />
ムレス、老人、災害などの支援活動を行う。<br />
� 個人的な寄付要請には応じない。個人口座への送金は行わない、など。<br />
ケアリング・ハンズは災害地への支援が必要であると確認すると、緊急救援チーム'Emergency<br />
Task Force(を発足させて迅速な対応にかかる。シーメンスが災害地にどのような支援を提供した<br />
か、2008 年の中国四川省大地震のケースを例に見てみる。<br />
50
人的支援<br />
図表 23 四川省大地震'2008 年(に対するシーメンスの支援<br />
出所:シーメンスホームページ<br />
コーポレートボランティア、社会寄与、学校・大学へのスポンサー活動、災害支援などについて<br />
は社内規定がある。コーポレートボランティアでは、従業員が勤務時間中に現地の公益団体にボ<br />
ランティアとして活動することを認めている。<br />
企業の社会責任遂行を目的として、一部の支援組織をサポートし、社会プロジェクトのスポンサ<br />
ーになり、公共目的の活動を促進する。国際的な慈善団体に協力しているが、これは長期的に存<br />
続しうるものであるかどうかという点を重視した上で行っているとしている。<br />
2(SkyHydrant に係わる支援活動 23<br />
� 東チモール<br />
2008 年の国連 World Water Day の支援の一環で集めたシーメンス Water Technologies とケアリ<br />
ング・ハンズの募金で、東チモールのグレノ村の公営孤児院とディリにある病院に SkyHydrant を<br />
設置した。シドニーの Water technologies から社員 1 人、スカイジュースから 2 人がボランティアと<br />
して現地で設置などを手伝った。スカイジュースの現地パートナーであるオーストリアの NGO、<br />
Australian Aid International (AAI)が現地での準備やプロジェクトの進行監督を引き受けた。<br />
23 スカイジュース・ホームページ:partnered projects<br />
現地社員が被災地の病院に出向き、医療機器を修理し、24 体制でオペレー<br />
ションを支援。<br />
通信会社と共同で遠隔診断システムを稼動し、現場の医師とのコミュニケー<br />
ションを可能にした。<br />
Qing Chuanに浄水フィルターを設置し、安全な飲料水の確保に貢献した。<br />
物的支援 同社の医療機器(約37万ユーロ相当)などを提供した。<br />
寄付金<br />
その他<br />
全社的な募金キャンペーンを通して従業員から総額40万ユーロが集まった。<br />
現地従業員は社員旅行の中止などにより、10万ユーロを寄付。<br />
全額を国際赤十字に寄付した。<br />
従業員が、赤十字が実施する医療施設の再建などでボランティアとして参加。<br />
また、学校へ教材を寄付。<br />
51
� インドネシア<br />
図表 24 東チモールへの支援<br />
2009 年 9 月のスマトラ沖地震で被災したパダン市の特に被害の大きかった地区に、スカイジュ<br />
ースが現地NGOの Susila Dharma、オーストラリアNGOの Surfaid、UNICEF、Arche Nova などと<br />
協力して SkyHydrant 5 基を設置した。設置資金はシーメンス Water technologies のオランダ、米国<br />
従業員、Susila Dharma、スカイジュースの家族や友人を含めたスカイジュースの協力先の寄付金<br />
による。<br />
設置場所<br />
グレノ村<br />
� インド・ニューデリー<br />
Hope community Ohphanage<br />
図表 25 インドネシアへの支援<br />
Asia Water Foundation、スカイジュース、シーメンスの従業員とその友人などが資金援助して、<br />
2009 年 4 月にニューデリーの貧困地区の 2 つの学校に設置した。浄水供給システムが持続可能<br />
なものになるよう、インドの子供たちの生活環境改善に力をいれる現地NGO、Plan India を巻き込<br />
んで管理運営が継続できるようにした。スカイジュースと Asia Water Foundation は、ニューデリー<br />
での学校プロジェクトを通して衛生教育プログラムなども実施した。<br />
52<br />
ディリ市<br />
Bairo Pite Clinic<br />
問題点 2004年に設立された孤児院で現在35人の子供 1999年に難民の治療施設として設立され、現<br />
の世話をしている。ここで使っている浄水は 在は毎日平均300人以上の市民を無料診察し、<br />
バクテリアの含有率が高く、飲料水はボトル 入院患者や家族の宿泊も受け入れている。市<br />
水を購入している(10リットルあたり1米ド の上水は汚染度が高く、ボトル水も先進国の<br />
ル)。<br />
水準には届いていない。<br />
改善点 SkyHydrantの浄水能力で安全な水をいつでも<br />
十分使用できるようになった。電気を必要と<br />
しないので、夜間に電力供給が途絶えること<br />
があっても、問題がない。<br />
Jati Bawah Buluh Kubu Anau<br />
(アガム地区)<br />
約120所帯が利用。<br />
中期的な浄水供給システムとして<br />
使用される。<br />
SkyHydrantを設置し、給水ポイントを3ヵ所設<br />
けた。現地AAIのメンバーが定期的にメンテナ<br />
ンスしている。病院はボトル水の購入が不要<br />
になり、その金額を医療にあてることができ<br />
るようになった。<br />
Padang Karambia<br />
(パリアマン地区)<br />
約170所帯と近隣の村民が利用。 143所帯の約500人と近隣の村民が利用。
� チベット・中国<br />
図表 26 インドへの支援<br />
シーメンス Water Technologies の従業員と事業部の寄付金で 2009 年 8 月にチベットの首都ラ<br />
サから 1,000km 離れた農村の学校に、9 月には中国の農村に設置した。寄付金で SkyHydrant2<br />
基、タンクスタンド、目的地までの輸送費などをカバーした。スカイジュースの現地パートナーであ<br />
る Asia Water Foundation がウォータータンクを調達し、設置要員の確保や実施上の手配を引き受<br />
けた。<br />
3(ユニセフとの提携<br />
シーメンス財団を通してユニセフの『アフリカに学校を』プログラムを支援している。内紛で特に<br />
貧困問題が深刻なアンゴラ、マラヴィ、モザンビーク、ルアンダ、ジンバブエ、南アフリカなどの学<br />
校建設、教材提供、児童教育などを支援している。この活動はこれまでケアリング・ハンズが行っ<br />
ており、これまでに従業員とシーメンスの合計寄付金額は 60 万ユーロを超える。従業員約 1,800<br />
人がこのプロジェクトに推進者として参加し、定期的に学校建設などに寄付している。<br />
)シーメンス財団<br />
Prerna Vidyalaya School NHC School<br />
生徒数425人の小学校。非衛生的な井戸水を使用<br />
していた。<br />
シーメンスは事業展開する現地社会への貢献を目的として多様な活動を展開してきたが、この<br />
取組をさらに強化し、持続可能なものにするため、2008 年 9 月に設立された。活動開始は 2009<br />
年。提携先と協力して教育・社会問題、社会・技術、芸術・文化という 3 つの分野で活動展開する。<br />
シーメンスの社会的活動'コーポレートシティズンシップ(は段階的にシーメンス財団に移管されつ<br />
つある。財団資金 3 億 9,000 万ユーロは公益目的に使われている。<br />
4(ノキア・シーメンス・ネットワークのインド人材育成プロジェクト 24<br />
通信・IT分野での生徒・大学生の育成に取り組む„Uniting Communities“プログラムを 2008 年末<br />
に立ち上げた。現地NGOの Swechla との提携によるネットワーク・トレーニング、ニューデリーの<br />
公立学校6校への通信回線提供や育成プログラム'隔週土曜日に現地社員が指導(、Amity<br />
Institute of Telecom Technology & Management (AITTM)の学生に奨学金を提供するなどの支援<br />
24 Nokia Siemens Network プレスリリース 2008 年 12 月 18 日付け:“Bridge the Gap”<br />
53<br />
生徒数575人の小学校。浄水は汚染され、衛生設備<br />
がなかった。<br />
スカイステーションと給水ポイントを設置。 スカイステーションと給水ポイントを設置。
活動を実施している。<br />
② 官民提携(PPP)の活用<br />
1(ドイツのPPPスキーム<br />
連邦経済協力開発省'BMZ(が以下の公的機関に資金を供与し、民間企業の途上国・新興国<br />
での投資プロジェクトを支援している。事業者の投資が持続性なものであることを確認するための<br />
基準'事業規模など(と、投資計画が現地社会の持続的な成長に貢献するものであるかを計る基<br />
準'投資目的など(を満たすことが前提条件となる。PPPを承認された企業には、投資額の半額<br />
'最高 20 万ユーロ(が資金援助され、2 年間現地で行政上、運営上の支援が提供される。支援期<br />
間は状況に応じて 1 年延長することができる。<br />
以下の機関が直接の支援を提供する。<br />
� ドイツ開発投資公社'Deutsche Entwicklungsfinazierungsinstitut=DEG(:ドイツ復興金融金<br />
庫'Kreditanstalt für Wiederaufbau=KfW(傘下の融資会社として、民間企業の途上国・新興<br />
国での投資を融資している。融資の対象は、開発政策、企業経営の観点から有意義であり、<br />
環境や社会に好影響を与えるプロジェクトとしている。<br />
� ドイツ技術協力公社'Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit=GTZ(:提携<br />
先と共同で、プロジェクトのコンセプトと実施措置を開発し、実施する。世界 92 ヵ国に事務所<br />
を構え、120 カ国以上で活動を展開する。<br />
� セクア'Sequa(:ドイツ商工会議所'DIHK(と手工業会議所(ZDH)が、海外事業での相互協力<br />
を目的として 1991 年に合同設立した。産業連盟や商工会議所との密接な連携を利用して、<br />
職業分野のスペシャリストの斡旋や職業訓練の分野で企業の海外事業を支援する。<br />
シーメンスは途上国のインフラ事業で長年、公的支援スキームを活用してきたが、1997 年に新<br />
しいPPPスキームが導入されてから、以前ほど利用できなくなったとしている。その理由は、同社<br />
の途上国でのプロジェクトは、現地社会の活性化に持続的に貢献するという基準を満たすが、「公<br />
的支援がなければ企業単独としては実施できない」プロジェクトであるという条件が課されている<br />
ためである。世界インフラ大手のシーメンスはこの条件をクリアするのが難しいとしている 25 。<br />
25 E+Z – Entwicklung und Zusammenarbeit Nr.4, April 2000: PPP – Interessant für die wirtschaft?, Erfahrung von<br />
Siemens<br />
54
とはいえ、シーメンスがPPPスキームを利用していないというわけではない。途上国でのプロジ<br />
ェクトでは特に技術者などの養成にこれを活用しているようである。例えば、ベトナムではGTZの<br />
協力を得て、コントロール・エンジニアリングの技術者研修センターを設立し、学生、シーメンス社<br />
員、職業学校の教師などを訓練している。現地の Viet Duc Training Centre との提携により、技術<br />
トランスファーが持続的に行われるよう確保した。同様にインドネシアでも、シーメンスの実習生、<br />
大学教授、職業学校の教師の研修を目的としたメカトロニックの研修施設の設置で、公的援助を<br />
得ている。<br />
2(Protos の商品化にみる官民提携'PPP(の活用例 26<br />
シーメンスの家電事業子会社BSHは、植物油を使った環境にやさしい調理コンロ Protos の商<br />
品化をフィリピンのレイテ島で行った。この実地テストは 2004 年、PPPプロジェクトとしてスタートし<br />
た。DEGが、投資コストの約 3 分の 1 を供与した。GTZも、長年のネットワーク基盤を使って現地<br />
で実務上のサポートを提供した。<br />
プロジェクトの実施地としてこの島が選ばれたのは、植物油の研究が盛んなレイテ国立大学の<br />
協力を得られることと、農業が盛んで、都市部と農村部の両方を備え Protos の実地テストにとって<br />
理想的な環境であることによる。また、ココナツ油を製造する団体は多数あり、燃料の調達に事欠<br />
かないという好条件である。<br />
プロジェクトの内容<br />
� 約 1,000 の家庭に 1 台ずつ Protos を供給し、実用テストを行った。<br />
� 現地生産を委託する複数の中小工場を確定した。<br />
� 販売担当者を研修・育成した。<br />
� Protos 用植物油の製造と販売を行う農業協同組合を指導・研修した。<br />
このプロジェクトは、空気を汚染しない調理コンロを低価格で提供するという本来の目的を達成<br />
したことに加えて、現地生産により雇用創出し、経済的にも社会的にも好影響を与えた。特に、環<br />
境を配慮して、燃料の材料がココナツに集中することなく土壌が長期的に活用されるよう、さまざ<br />
まな植物を栽培するよう指導した。農家も副収入を得て、所得が向上している。<br />
26 Chancen – Das Magazin der Kfw Bankgruppe 2007 年第 2 号、GTZ PPPreport 28: Ein Project mit der DEG<br />
55
「異なるコンタクト先、観点、経験を持つパートナーがそばにいてくれて、非常に助けになった。<br />
DEGのサポートにより、このようなプロジェクトには常について回るリスクが軽減された。公的パー<br />
トナーを得て、プロジェクトの信ぴょう性と成功見通しが高まった」と、BSHのプロジェクト実行責任<br />
者、ザームエル・シーロフ'Samuel N. Shiroff(氏は言っている。<br />
3年間にわたったプロジェクトは 2008 年に終了した。2009 年にはインドネシアでDEG とGTZ<br />
とのPPPプロジェクトを新たに実施したほか、タンザニアでも導入されているもよう。中国とインド<br />
でも導入に向け準備作業を進めている。<br />
56
3.ベスタゴー・フランセン'Vestergaard Frandsen(<br />
http://www.vestergaard-frandsen.com/<br />
国際機関・NGO との広域・密接な連携活動で商品開発<br />
'1(BOPビジネスの事業概要<br />
① BOPビジネス事業の位置づけ<br />
1(会社概要<br />
同社は 1957 年、ミッケル・ベスタゴー=フランセン現社長の祖父、カイ・ベスタゴー=フランセン<br />
氏により、作業服用生地の製造会社としてデンマークのコルディングに設立された。1970 年に現<br />
社長の父、トルベン氏が経営を引き継ぎ、ホテル、レストラン、小売業などの作業着・制服を主力<br />
商品として事業を拡大した。<br />
1992 年に現社長が入社し、毛布、防水シート、テントなどの救援用品分野に進出した。これをき<br />
っかけにアフリカでの難民支援活動を展開する国際機関や支援団体との関係が密接になった。<br />
1997 年、事業戦略を大転換し、マラリア媒介蚊防御用の殺虫剤加工ネットをはじめとした救援・衛<br />
生用テキスタイル製品に特化した。本格的な生産体制を構築するため、1997 年ベトナムのハノイ<br />
に生産拠点を設けた。2005 年に本社をデンマークからスイスのローザンヌに移転したが、同社が<br />
密接な関係にあったWHOジュネーブ本部との連携が取りやすいという地理的利便性が決定要因<br />
となったと思われる。<br />
57
a. 拠点<br />
b. 従業員数<br />
出所:ベスタゴー・フランセン・ホームページ<br />
図表 1 ベスタゴー・フランセンの拠点<br />
約 180 人'下記の人数合計は 175 人。米国の社員数、工場の従業員数は不明(<br />
)2005 年末時点 約 80 人<br />
図表 2 会社概要<br />
出所:ベスタゴー・フランセン・ホームページ<br />
社名 所在地<br />
本社 Vestergaard Frandsen Group S.A. スイス(ローザンヌ)<br />
事業所<br />
北ヨーロッパ Vestergaard Frandsen ApS デンマーク(コルディング)<br />
南北アメリカ Vestergaard Frandsen Inc. 米国(アーリントン)<br />
中東 Vestergaard Frandsen Middle East ドバイ(アラブ首長国連邦)<br />
東アフリカ Vestergaard Frandsen (EA)Ltd. ナイロビ(ケニア)<br />
西アフリカ Vestergaard Frandsen West Africa Ltd. アクラ(ガーナ)<br />
中央アフリカ<br />
Vestergaard Frandsen Nigeria Ltd. ラゴス(ナイジェリア)<br />
Nigeria Ltd. 支部 アブジャ(ナイジェリア)<br />
南アフリカ Vestergaard Frandsen (SA) (Proprietary) Ltd. ヨハネスバーグ(南アフリカ)<br />
南アジア<br />
Vestergaard Frandsen (India) Pvt.Ltd. ニューデリー(インド)<br />
Vestergaard Frandsen (Asia) Pvt.Ltd. ニューデリー(インド)<br />
西太平洋 PT Vestergaard Frandsen Indonesia ジャカルタ(インドネシア)<br />
コミュニケーション担当 Vestergaard Frandsen New York ニューヨーク(米国)<br />
工場・ラボ Vestergaard Frandsen Vietnam ハノイ(ベトナム)<br />
工場・ラボ Vestergaard Frandsen チョンブリ(タイ)<br />
ローザンヌ本社<br />
CEO:Mikkel Vestergaard Frandsen(社長)<br />
COO:Per Reimer(副社長)<br />
上記含め41人(販売、マーケティング、リテール、広報、商品開発、サプライ<br />
チェーン、人事、法務、財務、IT、総務)<br />
コルディング 4人(公的保健機関のサポート、商品開発、農薬関連プロジェクト企画、総務)<br />
ドバイ 4人(公的保健機関のサポート、総務)<br />
ナイロビ<br />
アクラ<br />
24人(公的保健機関のサポート、PermaNet®とLifeStraw®のリテール・商業販売、<br />
ローカル事業、コーポレート事業、人事、財務、総務)<br />
12人(公的保健機関のサポート、PermaNet®とLifeStraw®のリテール・商業販売、<br />
財務、総務、物流)<br />
ラゴス 7人(リテール顧客のサポート、財務、物流)<br />
アブジャ 7人(公的保健機関のサポート、公共衛生水媒介疾病関連)<br />
ヨハネスバーグ 3人(公的保健機関のサポート、総務)<br />
ニューデリー<br />
インド社<br />
ニューデリー<br />
アジア社<br />
ジャカルタ 1人<br />
ニューヨーク 広報(人数不明)<br />
ハノイ<br />
8人(公的保健機関のサポート、PermaNet®、LifeStraw®のリテール・商業販売)<br />
21人(ベクター・水媒介疾病関連事業、サービス、マーケティング、物流、IT、<br />
財務、総務)<br />
16人(サプライチェーン、製造)ほか、ベクター・コントロール・ラボ17人、<br />
ウォーター・ラボ7人。<br />
工場の従業員数は不明。<br />
チョンブリ 3人(製造、サプライチェーン、品質管理)。工場およびラボの従業員数は不明。<br />
58
c. 売上規模<br />
米経済誌フォーブズ 2005 年 12 月 26 日号に掲載された記事 1 によると、売上高は 1997 年が 550<br />
万ドル、2003 年が 1,500 万ドル。2005 年は 4,000 万ドルで税引き前利益 500 万ドルだった。<br />
d. 事業理念<br />
前述のようにベスタゴー・フランセンは救援用品という人道的な目的に投入される製品の製造・<br />
販売を本業としている。従って、BOPビジネスの捕らえ方は、大手国際企業がこれを新しい事業<br />
拡大のチャンスと見るのとは根本的に異なる。同社のビジネス・モデルは、「目的のために利益を<br />
得る'profit for purpose(」という考えに立つものである。<br />
ミッケル・ベスタゴー・フランセン社長は、同社が新しいタイプのユニークな企業であることを以<br />
下のように語っている'書面インタビュー(。<br />
「我々は、ビジネスは利益のためであり、利益は目的のためであるという信念を持っている。<br />
我々は、家族経営のテキスタイル事業を世界的な保健事業分野のリーダーに変身させることで、<br />
このコミットメントを明確にした。これにより、全くオリジナルなビジネスのやり方を創出した。当社<br />
は、これを人道的起業家精神'Humanitarian Entrepreneurship(と呼んでいる。持続可能な発展を<br />
確実なものにするため、人道的起業家精神には、利益性と人道的責任という、相反すると思われ<br />
がちな二つの要素が結びついている。なぜ当社がこのようなビジネス・モデルの推進をコミットメン<br />
トしたのかという説明は簡単だ。当社には他と違うことができるということがはっきりわかったから<br />
だ。過去数十年間にわたって高品質のテキスタイルを製造してきた経験から、当社にはテキスタ<br />
イル技術と表面加工に関するしっかりした基盤がある。このノウハウを使ってイノベーションに懸<br />
命に取り組んだ結果、数百万の人々の生死を分ける製品を生み出すことにつながった。当社は、<br />
利益を追求すること人々を救援することの間に利害衝突はないと考える新しいタイプの企業だ。<br />
良いことをすることは良いビジネスであるということが、実際に経験してわかった。」<br />
国連ミレニアム開発目標'MDGs(では、特に小児死亡率の低減、HIV/AIDS・マラリアの撲滅、<br />
安全な飲料水の確保をコミットメントしている。<br />
「当社の戦略には、国連ミレニアム開発目標が取り込まれている。たとえば、マラリアや<br />
HIV/AIDS のような伝染病の拡大を止めて減尐させること、育児中の女性の健康状態の改善、子<br />
供の死亡者数低減、男女平等の促進、発展を目指す世界的提携の構築などである。ベスタゴー・<br />
フランセンのMDGsへのコミットメントは事業目標達成への駆動力であり、イノベーションに持続的<br />
1 http://www.forbes/cp,/free_forbes/2005/1226/071_2.html<br />
59
に取り組むための刺激となっている。」'ベスタゴー・フランセン社長(<br />
② 主なBOPビジネス商品<br />
1(PermaNet®<br />
熱帯・亜熱帯地方では、マラリアのベクターである蚊の撃退策として、殺虫剤加工ネット<br />
'Insecticide-Treated Net=ITN(が使用されている。だが、殺虫剤の効果の持続期間が短く、定期<br />
的に改めて殺虫剤を沁み込ませる必要がある。PermaNet®はこの問題の解決を目指して開発さ<br />
れた殺虫剤効果持続ネット'Long-lasting Insecticide-treated Net=LIN(で、1999 年に生産がスタ<br />
ートした。効力を改善した PermaNet®2.0 は 2004 年初め、WHOの殺虫剤評価スキーム'WHOP<br />
ES(の推奨を受けて販売が急拡大し、同社のトップ商品として事業成長を牽引している。<br />
図表 3 PermaNet<br />
出所:PermaNet®製品説明書<br />
一方、殺虫剤加工ネットに使用されている殺虫剤の有効成分ピレトロイドに抵抗力を持つ蚊が<br />
ブルキナ・ファゾ、カメルーン、ベトナムなどで確認されはじめた。農薬としても使用されていること<br />
が原因で、マラリア撲滅活動の新たな問題となっている。2008 年に開発した PermaNet® 3.0 は、<br />
そのソリューションである。<br />
PermaNet® 3.0 は 2 種類の素材と 2 種類の化学成分を使って、殺虫剤抵抗力を持つ蚊に対す<br />
る殺虫効果を強化している。まず天井部に止まってから下に降りてくるという蚊の習性に注目して、<br />
天井部の殺虫成分デルタメトリンの含有量を側面部より多くし、共働剤'PBO(を化合している。共<br />
働剤が、蚊の体内に殺虫成分が吸収されるのを促進すると同時に、殺虫剤を分解する蚊の酵素<br />
を抑制し、効果を高めている。WHOPESからは 2008 年末に仮推奨を受けた。供給先はマラリア<br />
媒介蚊の抵抗力が強まっていると見られる地域に限定されている。<br />
60
PermaNet®の供給地は、サブサハラ地方'サハラ砂漠以南のアフリカ諸国で、ガーナ、ギニア、<br />
コートジボワール、シエラレオネ、ナイジェリア、ニジェール、ブルキナファソ、カメルーン、ウガンダ、<br />
エチオピア、ケニア、タンザニア、セネガルなど(、アジア'ベトナム、カンボジア、フィリピン、タイ、ミ<br />
ャンマー、インドネシア、マレーシア、中国など(、中南米'グアテマラ、ホンジュラス、コロンビア、エ<br />
クアドルなど(。<br />
入り口のドアを開け放して生活する習慣が多い熱帯地方では、日中からデング熱、フィラリア、<br />
チャガ病などのベクターに刺されることが多い。この対策として、PermaNet®技術を採用したカー<br />
テンも販売している。<br />
素材<br />
強度<br />
2(ZeroFly®<br />
メッシュ<br />
効果物質:<br />
デルタメトリン 2<br />
図表 4 PermaNet 製品仕様<br />
100%ポリエステル<br />
(75または100デニールの単繊維36本で紡織)<br />
75デニール:最低250kPa<br />
100デニール:最低250kPa<br />
25穴/cm2=161穴/inch 2<br />
(最低156穴/inch 2 )<br />
55mg/㎡±25%(最低45mg/㎡)<br />
6回の洗濯実験後の濃度は最低25mg/㎡<br />
出所:PermaNet®2.0 及び 3.0 製品パンフレット、<br />
www.vestergaard-frandsen.com/permanet2-0.htm など<br />
殺虫剤効果が持続するプラスチックシート。避難シェルターとしてキャンプの設営に使用され、<br />
同時にマラリア・ベクターに対する殺虫効果も発揮する。2004 年のインドネシア沖地震の津波被<br />
災地や 2005 年のパキスタン大地震被災地、内紛が続くダフールなどで大量に投入されている。<br />
61<br />
ルーフ部分 側面部分<br />
100%ポリエチレン<br />
最低35kPa<br />
最低156穴/inch 2<br />
100デニール<br />
濃度4.0g/kg<br />
共働剤(PBO) ― 25g/kg ―<br />
サイズ サークル、角型、ハンモック型<br />
形状<br />
PermaNet ®2.0<br />
サークル:S・M・L<br />
角型:SS・S・M・L・LL<br />
ハンモック:240x65x<br />
120cm<br />
色 白、青、黄、ピンクなど全10色<br />
角型<br />
100%ポリエス<br />
テル<br />
上部:最低<br />
250kPa<br />
下部:最低<br />
320kPa<br />
13938-2(2999),<br />
頭部7.3cm2<br />
75デニール<br />
濃度2.8g/kg<br />
160x180x150cm、190x180x150cm<br />
白(ルーフは青)<br />
PermaNet ®3.0
3(LifeStraw®<br />
図表 5 ZeroFly<br />
出所:ベスタゴー・フランセン・ホームページ<br />
素材<br />
図表 6 ZeroFly 製品仕様<br />
出所:ZeroFly 製品パンフレット<br />
www.vestergaard-frandsen.com/zerifly.htm を参照<br />
LifeStraw®Personal はストロー式のポータブルな簡易浄水フィルターで、MDGsが掲げる「2015<br />
年までに安全な飲料水にアクセスできない人の数を半減する」という目標への貢献を目的に開発<br />
された。口で吸い込む際に、汚れた水の中のバクテリアや不純物がフィルターで除去され、安全な<br />
飲料水として飲むことができる。周囲に汚染した水源しかない場所で、いつでも誰でも簡単に使用<br />
できることが大きな長所である。<br />
62<br />
詳細<br />
高密度ポリエチレン'HDPE(<br />
両面ラミネートのセンター織<br />
メッシュ 10x10ヤーン/inch 2<br />
強度 100N<br />
剥落強度:30-120N'補強バンド部(<br />
発火性 200℃'発火点(<br />
温度耐性 氷点下20℃~80℃<br />
紫外線耐性 1,500時間の照射後の張力損失5%未満
出所:LifeStraw®製品説明書<br />
図表 7 LifeStraw<br />
LifeStraw® Family は固定式タイプで、家庭などで複数の人が共同で使用することを念頭に開<br />
発された。EPA品質基準に基づくフィルター能力は最低 18,000 リットル。可動パーツがなく、電源<br />
や電池を必要としないので、どこにでも設置できる。LifeStraw®はUNICEF、WHO、FAO、多数<br />
のNGOによる難民支援ルートと、慈善団体や市民グループなどの寄付活動を通して、アフリカ、<br />
アジア、中南米諸国に供給されている。<br />
図表 8 LifeStraw 製品仕様<br />
素材 ポリスチレン'首かけ用の紐つき(<br />
効果物質 ハロゲン化合樹脂:活性ハロゲンを吸入した水に放出してバクテリアを殺菌する。<br />
陰イオン交換樹脂:マイナス負荷のハロゲン残余量を吸着する。<br />
粒状活性炭'シルバー飽和(:活性ハロゲンの残余量を吸着する。<br />
浄水能力 700リットル以上。1日あたり2リットルの水を消費するとして約1年間使える。<br />
フィルター 2層微粒子フィルターで125ミクロン~15ミクロン'最小(単位で濾過できる。<br />
外形サイズ 長さ31cm、直径2.9cm<br />
重量 乾燥状態:140g<br />
濡れた状態:160g<br />
バクテリア除去性能<br />
'700リットル浄水テスト結果(<br />
出所:LifeStraw®製品パンフレット<br />
www.vestergaard-frandsen.com/lifestraw-introduction..htm<br />
浄水プロセス 2<br />
� 第 1 フィルター'プレフィルター(:孔径約 100 ミクロンのメッシュフィルターで、吸入した原水か<br />
ら粒子の大きい不純物をろ過する。<br />
� 第 2 フィルター:孔径約 15 ミクロンのポリエステルフィルターでバクテリアや不純物をろ過す<br />
る。<br />
� 第 1 チャンバー:ヨウ素'ハロゲン(加工された粒が充填されており、通過する水中のバクテリ<br />
2 http://lifestraw.wikispaces.com/、http://www.greenmarketing.tv/category/social-entrepreneurs<br />
63<br />
詳細<br />
E.faecalis:99.999990~99.999997%以上<br />
E.coli B:99.99975~99.99996%以上<br />
MS-2:98.4~98.7%
ア、ウィルスなどを殺菌する。<br />
� 第 2 チャンバー'浄水仕上げ(:活性炭が充填されており、水からヨウ素のにおいを消去す<br />
る。<br />
図表 9 LifeStraw Family<br />
処理能力 最高20,000リットル。6人家族で2年間分の飲料水を供給できる。<br />
1リットルを5分以下で浄水できる。<br />
浄水プロセス 27ミクロンのプレフィルターで事前に不純物を除去。<br />
孔サイズが20nmの薄膜カートリッジでバクテリア、ウィルスなどを除去。<br />
バクテリア除去能力 バクテリア:99.9999%<br />
ウィルス :99.99%<br />
原虫のう胞:99.9%<br />
出所:LifeStraw 製品パンフレット<br />
www.vestergaard-frandsen.com/lifestraw-introduction..htm を参照<br />
4(CarePack<br />
PermaNet® や LifeStraw®、コンドーム等を取りまとめた健康対策セット。ケニアで行った<br />
HIV/AIDS 予防キャンペーンは、多くの人々に HIV 検査への自主的参加を促すことを目的として実<br />
施され、参加者へのインセンティブというコンセプトで無料配布された。予想以上に多くの参加者<br />
が集まり大きな効果が確認されたため、他の地域での同様の活動に投入することを視野にいれ<br />
て商品化したものと見られる。CarePackの内容物は最低 3 年間の有効期限があるようにセットさ<br />
れている。ベトナム工場で内容物をダンボール箱に詰め、投入される国・地域に発送される。現地<br />
の事情に応じて他の商品を追加できるようにしてある。<br />
図表 10 CarePack の内容<br />
出所:CarePackwww.vestergaard-frandsen.com/carepack.htm<br />
64<br />
詳細<br />
内容物 目的<br />
PermaNet®2.0:<br />
1、2枚'当該国の普及率次第(<br />
LifeStraw®Family:<br />
1個<br />
抗生物質'オプション(:<br />
Co-trimoxazole prophylaxis'配布<br />
量は当該国の事情次第(<br />
コンドーム'オプション(:<br />
120個または適宜<br />
添付資料:製品使用説明書、HIV・<br />
マラリア予防、健康、水、衛生に関す<br />
るアドバイス集、その他適宜<br />
マラリアなど昆虫が媒介する疾病の感染を予防し、小児の死亡率を低下させる。<br />
下痢など水が媒介する病気の予防。下痢の発症率の大幅減尐を図る。<br />
この抗生物質の使用により死亡率を半減。<br />
発症低下率はマラリア72%、下痢31%、入院治療は31%減尐するという統計がある。<br />
HIV、他の性病の感染予防。<br />
特にHIVや、他の病気の感染リスクがある行為について注意を促す情報を提供し、<br />
感染、発病リスクを低下させる。
'2(事例に見るBOPビジネス推進方法<br />
① 商品・事業の開発プロセス<br />
図表 11 CarePack<br />
出所:CarePack製品説明書<br />
ベスタゴー・フランセンは、救急用テントなどの供給を通して難民救済に取り組む国際機関やN<br />
GOとの関係を強める中で、現場が抱える避難シェルター、食糧、清潔な水、基本的医療品の確<br />
保という困窮地での課題の解決に、企業として協力する事業戦略を固めた。同社の商品開発は<br />
全て、難民救済現場の具体的なニーズに対処することを目的に行われている。<br />
1(PermaNet® 3<br />
一般的な殺虫剤加工ネット'ITN(は、一定期間が経つと効果が薄れるため、改めて殺虫剤を浸<br />
潤させる必要がある。だが、NGOなど外部からの援助がなくなると、現地の人々だけでは自主的<br />
にこのような作業は行われなくなるというのが実情だった。WHOが行ったアフリカでの広域使用<br />
実態調査により、ITNは利用者が正しい使い方をして殺虫剤効果が持続していれば、マラリア予<br />
防に非常に効果があることが確認されていたため、このような問題を解決する必要があった。<br />
フランス政府の海外調査機関である国際科学開発研究所'ORSTOM( 4 のモンペリエ研究所は<br />
1998 年、研究者や関連企業を集めて新しい取組について議論した。同研究所が提示した課題は、<br />
殺虫剤を何度も浸潤させなければならないという手間とコストがかからず、洗濯に耐えうる殺虫剤<br />
定着方法を開発して、ITNの効果を高めることだった。唯一このアイデアの実現に協力を申し出た<br />
3 www.insectcontrol.net/permanent_partnership/index.php、Vestergaard Frandsen Quarterly September 2004 な<br />
どを参照<br />
4 現在の L’institut de recherché pour le development(IRD)<br />
65
のが、ベスタゴー・フランセンの前社長であり商品開発責任者のトルベン・ベスタゴー=フランセン<br />
氏だった。同社はすでに殺虫剤効果の持続方法について米国の科学者に開発を依頼していたが、<br />
思うような進展が見られなかったとされる。こうしてORSTOMと同社の共同開発が始まった。OR<br />
STROMからはベクター研究者のオレ・スコヴマント'Ole Skovmand( 5 氏が開発の中心となった。<br />
同氏は ZeroFly の開発にも関わっている。<br />
ラボでの検査で、殺虫剤の定着効果は 27 回の洗濯に耐えるという結果が得られた。アフリカの<br />
貧困層はネットをこれほど頻繁には洗濯しないということから、この結果は商品化のゴーサインと<br />
なった。生産体制を整えるため、ベスタゴー・フランセンはベトナムの工場に新たな生産設備を導<br />
入した。同社が製造委託する 10/10 textile Company の工場は縫製技術が高いことで知られてい<br />
たが、これまで薬品等の加工工程を行ったことがなく、LINの製造は初めてだった。同社の初代<br />
PermaNet®には製造工程に起因すると見られる性能のムラ'効果持続期間にばらつきがある(が<br />
あることが、実地テストの担当者や現地NGOからの指摘でわかった。同社は技術改良を進めると<br />
同時に、実際に蚊を使って効果テストを行うバイオアッセイ・ラボと化学分析を行う品質管理ラボを<br />
工場敷地内に設置し、さらには現地でマラリア研究を行っているベクター研究者チームや有能な<br />
化学者らを雇用して、データ収集とその分析を進めた。<br />
こうして改良された PermaNet®2.0 は、2000 年 12 月にウガンダ西部の Kenjojo District で実地<br />
検証されることになった。WHOPES、ウガンダ保健省、ドイツ技術協力公社'GTZ(、Comercial<br />
Market Strategies 6 、米疾病対策センター'The Centers of Disease Control(のマラリア部門がプロ<br />
ジェクトの提携パートナーとなった。ここで大きな効果が実証された結果、PermaNet®2.0 は 2004<br />
年初め、WHOの推奨という品質保証を受け、以降、飛躍的な成功を収めている。<br />
住友化学はベスタゴー・フランセンより数年も前にLINを開発し・商品化していた。同社の<br />
Olyset®は PermaNet®2.0 より 3 年も早くWHOの推奨を受けていたにもかかわらず、なぜ市場を<br />
制覇できなかったのか。USAIDのアルバート・キリアン氏は、「'住友化学のLINは(フィールドテ<br />
ストの結果はよかったが、素材が硬く'ポリエチレン(、消費者があまり魅力を感じなかった。この<br />
製品はごく最近まで'2004 年(真剣な取り組み方で市場に出されていなかった」と、その理由を示<br />
唆している 7 。<br />
同社は、LINに使用される殺虫剤に抵抗力を持つ蚊の出現が問題視されるようになると、ただ<br />
ちにこれに対処できる新しい商品の開発に取り組んだ。LIN業界をリードする企業としての自信と<br />
責任が推進力である。<br />
5 Intelligent Insect Control 社を設立し、同氏の開発技術の商品化を行っている。<br />
6 USAIDが出資する社会マーケティングプロジェクト<br />
7 Vestergaard Frandsen Quarterly 2004 年 9 月号<br />
66
「当社はピレトロイドに抵抗力のあるマラリア・ベクターへの殺虫効果を向上した世界初の新世<br />
代LIN、PermaNet®3.0 を開発した。PermaNet®3.0 のすぐれたテクノロジーがピレトロイドの持続的<br />
な効果を確保しているため、何回も洗濯した後でも素早く殺虫剤が再生する。また、独自のウォー<br />
ル構造がネットの寿命を高めている。この技術で、ピレトロイドに抵抗力がある、あるいはその疑<br />
いのあるマラリア・ベクターを確実に殺すことができる。」'ベスタゴー・フランセン社長(<br />
2(ZeroFly® 8<br />
WHOの調査によると、2008 年の世界のマラリア感染者数は 2 億 7,200 万人。このうち 86%が<br />
アフリカの居住者である。また数値はやや古いが 2000 年のマラリアの年間死亡者数は世界中で<br />
110 万人に上り、アフリカの犠牲者がこの 9 割以上を占める。このうち 3 人に 1 人は内紛などによ<br />
り難民生活を強いられている人々で、栄養不良や粗悪な衛生環境の中で体力が衰えているため<br />
犠牲になりやすい。通常の難民救援措置では、避難シェルターがまず設営され、その後に難民生<br />
活が中長期化する見通しとなった段階で、生活に必要なインフラが整備されていく。従って、マラリ<br />
ア予防用の殺虫剤加工ネット'ITN(のような、長期的に使用される目的の用具が迅速に投入され<br />
ないという状況が起こりやすい。<br />
この問題を解決するため、WHO本部内に設けられたマラリア撲滅緊急対策チーム'Roll Back<br />
Malaria=RBM 9 Complex Emergencies Team(が、NGOなどの難民支援団体、研究機関、民間<br />
企業に協力を呼びかけ、既存の緊急支援用具をもとにマラリア予防とシェルターとしての二重機<br />
能を持つツールの開発プロジェクトを立ち上げた。これにベスタゴー・フランセンも避難用テントメ<br />
ーカーとして参加し、ロンドン衛生・熱帯医学研究所'London School of Hygiene and Tropical<br />
Medicine(、ヘルス・ネット・インターナショナル'Health Net International(、WHOと共同開発に取り<br />
組んだ(2000~2001 年ごろとみられる)。殺虫剤加工プラスチックテントの試作品は、NGOを通じて<br />
西アフリカやパキスタンで実験的に投入され、マラリアや下痢の要因となるベクターに対して優れ<br />
た殺虫効果が確認された。その後、アフリカの難民キャンプで発症状況の確認テストが行われた<br />
後商品化された。<br />
3(LifeStraw® 10<br />
LifeStraw®の開発の前段階として、米元大統領のジミー・カーター氏が主催するNGO、カータ<br />
ーセンターが推進するギニア病撲滅プログラム『Global 2000』への協力があった。カーターセンタ<br />
8<br />
International Aid & Trade (IA&T) review, January 2002: The challenges of developing new tools for malaria<br />
prevention in complex emergencies, IA&T Africa 2003 など<br />
9<br />
1998 年に発足したWHO、UNICEF、UNDP、世界銀行のプロジェクト で、世界のマラリア死亡者数を 2010 年<br />
までに特にアフリカに重点を置いて半減することを目指す。<br />
10 Vestergaard Frandsen Quarterly 2004 年 9 月号など<br />
67
ーは、1980 年代に世界中で年間 350 万人の犠牲者を出していたギニア病の撲滅を目指して、<br />
1986 年から活動していた。ベスタゴー・フランセンはこれに 1996 年から協力し、病気の原因となる<br />
ギニア虫の幼虫を水中から除去するための布フィルターやパイプ型フィルターを提供した。ステン<br />
レス製のポータブル型“ストロー”フィルターは、これまで 2,300 万本近くがアフリカのサブサハラ地<br />
方に供給され、今日も使われているという。『Global 2000』の活動はギニア病をほぼ撲滅するとい<br />
う大きな成果をあげた。<br />
この“ストロー”フィルターが安全な飲料水を提供するという課題の解決策として最適であること<br />
に注目し、ベスタゴー・フランセンが次に取り組んだのが、LifeStraw®である。ジフテリアやコレラな<br />
ど、水が媒介する病気の感染予防策として開発された。コンパクトタイプの浄水ツールは軍事用<br />
やキャンプ用としてすでにあったが、LifeStraw®は途上国向けの衛生用具として広く普及できるよ<br />
う、低価格で提供できること、可動パーツや交換部品がなく電力を必要としないことが大きな特徴<br />
である。2005 年にコンゴ、エチオピア、インドで実地テストを行った後、販売を開始した 11 。<br />
LifeStraw®Family はロンドン衛生・熱帯医学研究所と共同開発した。<br />
ベスタゴー・フランセンは 2008 年、ベルギーの Prime Water International'PWI(の過半数資本を<br />
取得した。同社は 1990 年前半に創立された薄膜フィルター技術の新興企業で、ベスタゴー・フラン<br />
センに LifeStraw®Family 用のフィルターを供給している。PWIのマイクロフィルター薄膜にはポリメ<br />
リックと鉱物性化合物の合成素材が使用され、POU(Point of Use)アプリケーションに最適のソリュ<br />
ーションであるとしている。「PWIのテクノロジーは非常に先進的で、今回の買収で浄水分野での<br />
技術競争で最先端に躍進する」と、この事業分野を強化する構想があることをほのめかしている。<br />
② 生産・供給体制<br />
1(生産拠点<br />
ベトナム'ハノイ(の生産施設は 1997 年に開設されたが、ホームページ情報では自社工場とは<br />
明記されていない。同社のニュースレター『Vestergaard Frandsen Quarterly』2004 年 9 月号には、<br />
「10/10 textile Company の生産施設に新しいテキスタイル検査ラボを設置した」となっており、委<br />
託生産拠点であることが考えられる。同工場は 1999 年に初代 PermaNet®の生産を開始してい<br />
る。<br />
PermaNet®の生産体制を整備するため、ベスタゴー・フランセンはデンマーク国際開発援助<br />
11 http://www.heise.de/tp/r4/artikel/21/21638/1.html など<br />
68
'Danish International Developmental Assistance=DANIDA(の民間企業投資支援プログラムを利<br />
用した。DANIDA から 3 年間で 50 万米ドル超の資金援助を受け、ベトナム生産拠点の製造設備<br />
を刷新し、最新技術を投入して国際基準を満たす製造工程を確立した。「DANIDAからの支援が<br />
なければ、PermaNet®を研究室から生産レベルに移すための高額の資金を調達できなかった」 12<br />
としている。<br />
タイ・チョンブリの工場は 2001 年に PermaNet の製造を開始した。生産量はベトナム工場に比べ<br />
かなり尐ないと見られる。<br />
2000年初め 月産30,000枚<br />
2003年初め 月産500,000枚<br />
2004年<br />
2005年~<br />
図表 12 PermaNet の生産能力<br />
1月にWHOPESの推奨を受け、生産キャパを<br />
月産1,000,000枚に拡大した。<br />
年半ばまでに月産2,000,000枚を目標とする<br />
年産30,000,000枚<br />
2006年半ば 月産5,000,000枚に拡大<br />
2009年春<br />
大幅な生産拡大措置をとったとしているが、<br />
具体的な数値は不明。<br />
出所:Vestergaard Frandsen Quarterly などを参照に作成<br />
上の表にあるように、PermaNet®の生産キャパシティは、WHOPESの推奨を受けた 2004 年に<br />
月産 100 万枚台に乗り、以降、毎年急ペースで拡大している。これは、高品質との保証がついたこ<br />
とにより、NGOや現地政府からの受注が急増したことに加えて、マラリア撲滅運動が一段と推進<br />
され、LINの絶対需要数が増えたことにもよる。<br />
UNICEFは 2004 年、今後 5 年間で毎年 3,000~4,000 万枚のLINが必要であるのに対し、業界<br />
全体の年間生産量が 1,300 万枚'当時(では供給が追いつかないとして、メーカーは増産すべきと<br />
の警告を発していた 13 。また、2015 年までにマラリア死亡者数をほぼゼロにするには、2009 年以<br />
降さらに 7 億 3,000 万枚のネットを製造しなければならないとする、Global Malaria Action Plan(GM<br />
AP)の報告もある。一年おきに生産能力を大幅に引き上げたのは、このような切実な要望に応え<br />
たものであるが、「需要ピークが過ぎて減産しなければならないような状態になるのは困る」と、社<br />
長は経営者としての厳しい視点も示している。<br />
このような状況の中で、ベスタゴー・フランセンはマラリア撲滅支援団体などから、アフリカでの<br />
現地生産を求められていたが、回答はノーであった。アフリカへの技術移転、生産移転について<br />
12 Vestergaard Frandsen Quarterly 2004 年 1 月<br />
13 UNICEF 2004 年 9 月 23 日付けプレスリリース<br />
69<br />
1999年からの累積販売数は500万枚。<br />
2009年4月までで累積1億7,500枚を生産。
は、PermaNet®がそれまで維持してきた品質管理を徹底できるかということを問題点として指摘し<br />
ている。LINの購入者であるNGOなどや利用者である消費者は、商品を見ただけではその効果<br />
を判断することはできない。価格競争が激しくなれば品質をごまかす試みが出てくるのではないか<br />
と懸念する。一方、住友化学は 2002 年にWHOとRBMからアフリカでの現地生産の要請を受け<br />
入れ、タンザニアの A to Z Textile Mills に技術移転している。<br />
2005 年には、中国青島州の Shandongtex (Hiking Group 傘下の会社)に委託生産を開始してい<br />
る 14 。受注急増に対応するのが目的で、「PermaNet2.0 の全生産工程で行っている重要で厳しい<br />
品質管理を緩めることなく生産を拡大する。この投資では PermaNet®2.0 の製造担当者の研修と<br />
教育に重点を置く」と、Sicco Roorda 氏'ポリエステル製造責任者(は言っている。Shandongtex は<br />
専用工場を建設し、品質検査用のテキスタイルラボと、化学ラボも設置するとしているが、現在ど<br />
のようになっているかは不明。<br />
2(品質管理<br />
WHOの品質基準'WHOPES(をクリアするため、ハノイ'ベトナム(の自社バイオアッセイ研究<br />
室で、自家培養した蚊を使って PermaNet®のノックダウン'殺虫(効果を検査するための円錐<br />
'Cone(テストやトンネルテストを行っている。<br />
ハノイとタイの工場には、それぞれ化学研究室とテキスタイル研究室が併設されている。化学<br />
研究室ではネットに含まれる化学物質の配合量を計測、テキスタイル研究室ではネットのメッシュ<br />
幅や重量、紡織素材の強度、洗濯・乾燥による縮み度などを検査している。徹底的な品質管理に<br />
より、WHO推奨の品質をすべての製品で確保する体制を整えている。<br />
14 Vestergaard Frandsen Quarterly 2004 年 4 月号<br />
70
3(供給体制<br />
出所:PermaNet2.0®製品パンフレット<br />
a. 独自のディストリビューション拠点<br />
図表 13 行程管理の流れ<br />
世界 11 ヵ所に設けた地域担当事務所'前述(が、国際機関や現地のNGOなどとコンタクトを取<br />
り、迅速な出荷を手配する。アフリカでは現地ディストリビューターと提携し、奥地の目的地までス<br />
ムーズな配達できるようにしている。<br />
b. 現地ディストリビューター<br />
デルタメトリン純正・QCテスト<br />
紡績糸特性テスト<br />
付属品チェック<br />
作業場のチェック<br />
欠陥のカウント・取り出し<br />
欠陥の分類<br />
作業場のチェック<br />
色合いマッチテスト<br />
色定着<br />
Azo-free染色剤の確認<br />
作業場のチェック<br />
物理特性テスト(幅、重量、縮み度、引っ張り強度、メッシュ)<br />
Netco Rockville (ガーナ)、Transcol (ガーナ)、Reiss & Co. (ガーナ)、Ets. Simpara (マリ)、Negitra<br />
(セネガル)、Nett Shoppe (ウガンダ)など<br />
ナイジェリア<br />
スーダン南部<br />
作業場の監視<br />
有効成分含有量(約1トンごと)<br />
WHOPES 1による洗濯耐性<br />
裁断・縫製の検査<br />
包装前に製品の視覚検査<br />
社内品質検査<br />
外部検査(SGS、ITS)<br />
出所:PermaNet®2.0 及び 3.0 製品パンフレット<br />
図表 14 近年の主な配送実績<br />
71<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
紡績糸の納入<br />
↓<br />
撚り・紡織<br />
↓<br />
染色<br />
(カラー製品の場合)<br />
↓<br />
加熱処理<br />
↓<br />
効果剤浸潤<br />
↓<br />
裁断・縫製・包装<br />
↓<br />
仕上げ<br />
↓<br />
品 質 証 明 書 を 発 行<br />
2008-09年、4つの地域にPermaNet480万枚を陸路で配送'コンテナ180個(。<br />
2009年、3つの州に250万枚を陸路で配送'コンテナ97個(。<br />
2009年、7州の30郡にPermaNet®300万枚を陸路、荷船、空路で配送'コンテナ143個の<br />
うち132個は購入(。<br />
エチオピア 2007年、3つの地域'16ヵ所(にPermaNet®300万枚を陸路で配送'コンテナ105個(。<br />
中国南部 2008年、8つの州'29ヵ所(にPermaNet®約52万7,000枚を陸路で配送'コンテナ12個(。
4(NetMark のプロジェクトへの参加<br />
NetMark 15 は、サブサハラ地方'エチオピア、ガーナ、ナイジェリア、セネガル、ウガンダ、ザンビ<br />
ア、ジンバブエなど(でのマラリア患者削減のため、USAIDの期限付き資金援助を受ける非営利<br />
団体である。ネットメーカーと国レベルのマラリア対策プログラムの協力を得て、殺虫剤加工ネット<br />
の需要拡大と販売普及を推進している。44 の民間企業'アフリカ 35、国際企業 9(が参加し、1999<br />
年の活動開始以来、1,800 万米ドル以上を活動諸国に投資し、全ての住民が一般防虫ネット・殺<br />
虫剤加工ネットを購入できるよう、販売市場の構築に取り組んできた。5 歳未満の幼児、妊婦など<br />
発病リスクの高いグループにはITN 16 を無料もしくは低価格'助成金補助(で配給するが、7 億人近<br />
い対象地域の住民全てを寄付金で措置することは不可能であり、長期的にITNを供給するルート<br />
として早急に一般市場を確立する必要があった。<br />
多方面からの機動力を結集して販売市場を開拓する、このような大規模でシステマチックな活<br />
動に参加することは、企業にとって非常に効率的な市場参入の手法であることは確かである。<br />
NetMark のネット提携先はベスタゴー・フランセン、A to Z Textile Mills、Siamdutch Mosquito<br />
Netting、Sunflag、Mossnet Industries、Rosies Textiles である。殺虫剤加工ネットは NetMark 活動<br />
開始以前にはあまり使われていなかったが、ITNのマラリア予防効果について公共キャンペーン<br />
などを通して地域住民の啓発が進み、ITNの利用は着実に拡大し、現在ではサブサハラ地方で<br />
使われているネットの 65%を占める。提携メーカーによるITN総販売枚数は 2004 年に合計 530<br />
万枚に上り、2007 年 10 月までの累積販売枚数は 2,800 万枚となったもよう。エチオピア、ガーナ、<br />
ザンビア、マリ、セネガル、ウガンダでは殺虫剤及びネット素材への関税・国内課税が免除され市<br />
場流通を促進するとともに、メーカーの競争が活発化して安く手に入るようになったようである。<br />
出所:NetMark<br />
15 http://www.netmarkafrica.org/<br />
図表 15 アフリカ各国におけるネットとITNの販売価格<br />
2001年'ネット( 2004年'ITN(<br />
エチオピア $6.50 $2.54<br />
ガーナ $7.14 $4.78<br />
ナイジェリア $3.64 $2.75<br />
セネガル $8.00 $5.29<br />
ウガンダ $14.29 $4.50<br />
ザンビア $5.39 $4.57<br />
ジンバブエ $27.29 $7.95<br />
16 ここ以下で言及されるITNはLLINを含めた全ての殺虫剤加工ネットを指す。<br />
72<br />
調査地域のITNの価格帯は<br />
$1~$20。
5(高い普及率'政府調達(<br />
ベスタゴー・フランセンの PermaNet®は、WHOの推奨を受けて以来、国際機関やNGOを通し<br />
て、マラリア危険地域の住民に無料あるいは補助金付で供給されたため、ITNの中でもっとも広く<br />
普及し、 知名度も圧倒的に高い。<br />
米上院議員トム・コバーン氏のウェブサイトに掲載された寄稿 17 によると、2004~2006 年までの<br />
LIN政府調達の大部分が、WHOの推奨を受けた PermaNet®'1億枚以上(と Olyset'約 3,000 万<br />
枚(であった。ベスタゴー・フランセンは世界のLIN流通量の 75%を占め、また世界の生産能力の<br />
60%を持っている。同社のLIN製品の 95%が政府調達向けとされる。この圧倒的優位はひとえに<br />
WHOの推奨によるものである。<br />
WHOPESの品質テストに時間がかかるため、WHOは意図せずして市場競争をゆがめている<br />
という指摘がある。米国政府は、ブッシュ前大統領のマラリア・イニシャティブの調達をWHOの推<br />
奨を受けていない Tana Netting 社の Dawa Plus とし、ウガンダに提供した。この 1 枚あたりの調達<br />
価格は 4.93 米ドルで、UNICEFが調達する PermaNet ®と Olyset の価格 18 より平均 50%安い。そ<br />
れでもなお、WHO推奨へのこだわりは強く、新しく発足した民間支援団体 Malaria No Mora も、W<br />
HO推奨のLINをUNICEF経由でてしか買わないとしている'平均 8 米ドル(。市場競争の活発化<br />
でネットの価格低下を加速させたい NetMark は、世界銀行、グローバルファンド、国際赤十字など<br />
マラリア撲滅活動の中心団体がWHOの方針に従うことに、非常に不満を持っているようである。<br />
NetMark が行ったITNに関する現地追跡調査報告書 19 によると、ナイジェリアの調査対対象国<br />
の特定地域で住民を対象に行ったヒアリング調査象者が保有していたITNは、2004 年には全体<br />
の 2%のシェアに過ぎなかった PermaNet®が、2008 年には 57%を占め首位ブランドに躍進した。<br />
政府が提供するITNが主に PermaNet®であることが高い普及率につながっている。一方、<br />
PermaNet®はガーナではすでに 2004 年に 13.8%の最大シェアを獲得し、2008 年には 58.2%で圧<br />
倒的優位に立っている。<br />
17<br />
Richard Tren, Philip Coticelli Business Day (South Africa) April 25, 2007: Red tape slows initiatives against<br />
disesase http://coburn.senate.gov/oversight/index.cfm?FuseAction=LatestNews.<br />
18<br />
ビジネス情報誌『Portfolio』の 2008 年 5 月 12 日号は PermaNet®の価格を 5 米ドルとしている。<br />
19 NetMark 2008 Household Survey on Insecticide-Treated Nets (ITNs) in Nigeria および Ghana<br />
73
a. ブランドシェア<br />
図表 16 ナイジェリアにおける PermaNet のシェア<br />
出所:NetMark 2008 Household Survey on Insecticide-Treated Nets (ITNs) in Nigeria および Ghana<br />
出所:同上<br />
b. 入手ルート<br />
図表 17 ガーナにおける PermaNet のシェア<br />
図表 18 ナイジェリアにおける ITN の入手先<br />
出所:同上<br />
2008年 (%) 2004年 (%)<br />
ブランド 全体 都市 地方 ブランド 全体 都市 地方<br />
PermaNet® 56.7 49.9 64.5 Roll Back Malaria 11.6 7.9 13.3<br />
Olyset 7.0 8.6 5.1 Iconet 10.7 15.5 8.4<br />
Net Protect 3.1 4.2 2.0 Sunflag 3.5 7.6 1.6<br />
Sleeping Beauty 2.4 1.5 3.5 PermaNet® 2.0 3.2 1.4<br />
Icon Life 2.0 2.2 1.9 NetMark 1.8 4.5 0.6<br />
ブランド名を知らない 16.1 16.5 15.6 ブランド名を知らない 62.8 46.8 70.2<br />
調査数 638人 402人 236人 調査数 788人 335人 453人<br />
2008年 (%) 2004年 (%)<br />
ブランド 全体 都市 地方 ブランド 全体 都市 地方<br />
PermaNet® 58.2 56.6 59.7 PermaNet® 13.8 15.9 12.4<br />
Olyset 15.4 15.5 15.4 NetMark 10.9 19.8 4.7<br />
UNICEF &SiamDutch 4.3 4.5 4.1 UNICEF &SiamDutch 10.8 6.6 13.8<br />
UNICEF 2.3 1.8 2.8 KO Net 10.3 4.6 14.3<br />
SiamDutch 2.3 1.8 2.8 SiamDutch 7.7 3.5 10.6<br />
ブランド名を知らない 10.5 10.8 10.2 ブランド名を知らない 35.8 40.8 32.3<br />
調査数 1852 人 910人 942人 調査数 480人 219人 261人<br />
74<br />
2008年(%) 2004年(%)<br />
小売(市場、ショップなど) 38.3 64.3<br />
小売以外<br />
プロジェクト<br />
病院<br />
学校<br />
女性グループ<br />
雇用者<br />
現地政府<br />
キャンペーン<br />
54.5<br />
34.2<br />
0.2<br />
0.3<br />
0.3<br />
-<br />
2.1<br />
16<br />
19.4<br />
1.2<br />
16.7<br />
0.1<br />
0.4<br />
9<br />
-<br />
-<br />
その他・分からない 7.1 16.4<br />
調査数 740人 154人
出所:同上<br />
c. リテール販売促進キャンペーン<br />
図表 19 ガーナにおけるITNの入手先<br />
2004 年にはテレビとラジオを使い、小売市場でのマーケティング戦略に着手した。PermaNet®<br />
はアフリカでは主にNGOを通して供給されていたが、「これからは小売市場で消費者をターゲット<br />
にする。従って、実際の消費者に対して効果的な方法で PermaNet®を知ってもらうキャンペーンが<br />
必要だとしている。テレビ・コマーシャルでは、子供の興味を引くようにアニメーションで<br />
PermaNet®が蚊に対していかに威力を発揮するかを宣伝した。ウガンダ、ガーナ、マリ、セネガル、<br />
ナイジェリア、ザンビアでテレビ・キャンペーンが実施された。ウガンダではキャンペーン開始から<br />
1ヵ月で、同地のディストリビューターNett Shoppe の販売量が 20%伸び、明らかな効果が得られ<br />
た。<br />
PermaNet®の小売価格は不明。<br />
6(LifeStraw®の供給ルートの例<br />
同社は LifeStraw®の製造コストを 1 本 5 米ドルとしているが、NGOなどへの販売価格は不明で<br />
ある。ビジネス情報誌『Portfolio』の 2008 年 5 月 12 日号は 1 本 4 米ドルとしている。<br />
LifeStraw®Family は 15 米ドルで、NGOや国際機関などからの受注が活発で、これまでに 100 万<br />
所帯以上に安全な水を提供しているとしている。<br />
国際ロータリークラブが、被災地支援活動の一環として、あるいは汚染された飲料水による子<br />
供の罹病を減らそうとする動の一環として、LifeStraw®を現地に送るための募金活動を行ってい<br />
る。ロータリークラブは、募金協力者が寄付購入する LifeStraw®の数量をとりまとめ、ベスタゴー・<br />
フランセンに発注。現地のロータリークラブを通して配給する。<br />
75<br />
2008年(%) 2004年(%)<br />
小売(市場、ショップなど) 27.9 67.6<br />
小売以外<br />
プロジェクト・NGO<br />
医療機関<br />
キャンペーン<br />
学校<br />
女性グループ<br />
現地当局、コミュニティ<br />
68.4<br />
1.7<br />
48.7<br />
16.5<br />
0.7<br />
0.2<br />
0.6<br />
32.4<br />
1.1<br />
30.2<br />
-<br />
0<br />
0.5<br />
-<br />
贈り物 1.7 3.1<br />
調査数 1851人 740人
Rotary Club of Brynmayr<br />
'英国(<br />
Rotary Club of Fort Lauderdale<br />
'米国・フロリダ(<br />
Rotary Club of Menorca<br />
'スペイン(<br />
図表 20 LifeStraw<br />
出所:www.lifestraw.org.uk/, lifestraw.123yourweb.com/,<br />
www.rotaryclumenorca.org/donate.php<br />
③ 公的機関・国際機関等・NGOとの連携<br />
ベスタゴー・フランセンは救援用品に特化した企業として、公的機関やNGOの協力なしに企業<br />
目的を遂行することはできないということを認識している。難民・貧困救済活動において、国際機<br />
関、NGO、民間企業が共通目標に向かって手を組んで初めて、最善の解決策が生まれると考え<br />
る。ミッケル・ベスタゴー=フランセン社長は、国連広報誌 International Aid & Trade 'IA&T(<br />
Review にマラリア防止策の共同取組に関する論文をRBMや研究機関などの関係者らと数多く合<br />
同寄稿 20 しており、それを参照して同社の提携についての考え方を見てみる。<br />
民間企業は開発目標を『自社の利益』に結びつけて考える必要がある。一方、公共機関は『救<br />
済』にフォーカスしなければならない。ベスタゴー=フランセン社長は、「民間セクターは、公共セク<br />
ターを顧客と見るのではなく、ターゲットとする消費者に商品を届けるための配給チャネルと見る<br />
必要がある。公共セクターは自分たちが民間セクターと難民の間を取り持つリンクであることを受<br />
け入れる必要がある」 21 と、役割分担の認識が必要であると強調している。<br />
マラリア感染防止ツールの開発で採用された提携モデルは、商品開発技術はあるが開発作業<br />
中に試作品の効果を実地で確かめる機会がほとんどない民間企業と、現場のニーズや投入方法<br />
はわかっているが開発能力に欠けるNGOと国連機関が知識を補い合い、その上でRMB/WHO、<br />
研究機関、最終ユーザーが商品の効果を確認するというスキームである。ここでのRMB/WHO<br />
20 IA&TNY 2002: “Imagineering”, IA&T 2002: “The challenges of developing new tools for malaria prevention in<br />
complex emergencies”, IA&T AFRICA 2003: “Cash and crisis”, IA&T EUROPE 2004: “Public-private<br />
partnership”<br />
21 International Aid & Trade Review IA&T AFRICA 2003 掲載寄稿『Cash and crisis』'Richard Allan, Matthew Burns,<br />
Mikkel Vestergaard Frandsen 共著(より<br />
76<br />
寄付内容など<br />
これまでに5万本のLifeStraw®を寄付した。<br />
1本あたりの価格は、1~19本の場合で6ポンド、450~500本の場<br />
合で5ポンドと、寄付購入する数量によって異なる。<br />
LifeStraw®Familyは1台25ポンド。<br />
1本あたり6.50米ドル。タンザニア、ケニア、マラウィ、ガーナに寄付<br />
している。<br />
現地での配達は、世界中で車椅子の寄付活動を行っているWheel<br />
Chair Foundationが担当する。これは輸入関税を回避する措置と<br />
している。現地のロータリークラブがベスタゴー・フランセンの現地社<br />
員と共同で研修を実施するなど密接に協力している。<br />
1本あたり3.50ユーロ。<br />
他通貨での寄付も受け付けている。
の役割は、現場のニーズを確定し、これを開発計画に移し、民間企業に開発を依頼し、学術研究<br />
機関を通して確実に製品を評価することである。NGOは製品のエンドユーザーとして現場の実情、<br />
製品投入上の問題点、現場作業者のニーズを把握し、 “効果の享受者”である現地の人々の状<br />
況が開発プロセスや製品デザインに活かされるよう協力する。NGOはまた、実地テストのパート<br />
ナーとしても重要な役割を担っている。<br />
マラリア感染防止プロジェクトでは、RBMを通して米国民・難民・移民局からの資金援助があっ<br />
た。これにより、製品の安全性や効果の評価に必要な経費が確保でき、開発プロセスのスピード<br />
アップや全体のコスト削減につながった。これは民間企業にとっては「迅速な商品化」という重要な<br />
インセンティブになるとしている。<br />
作業を進める上で、技術上の障害や要求を明確に定義し、解決策が投入する地域の文化土壌<br />
の中で受け入れられるかどうか、コストの制約はどうか、配給方法を改善できるかなどについて、<br />
公共セクターと民間セクターが協力しあうことが不可欠である。例えば、殺虫剤加工プラスチック<br />
シートの開発と効果の評価については、国際製品テストにより迅速な効果追跡調査が行われ、米<br />
ジョーンズ・ホプキンス大のMENTORグループが、WHOPESと西アフリカの現地NGOパートナ<br />
ーと共同で大規模なフィールドテストを実施した。このような提携モデルは、刷新的で効果的な商<br />
品を迅速に開発する上で有望な方法であるとしている。<br />
④ 事業展望<br />
「事業は利益を得るためにあり、利益は目的のためにある。これが事業を持続的なものにし、利<br />
益を責任あるものにする。利益は重要なツールだが、最終的なゴールではない。これ'同社の事<br />
業(は純粋な形での資本主義ではない」 22 と、社長は同社の事業が利益を目的としたものであるこ<br />
とを明言にする。PermaNet®を通して「我々はこれがビジネスだということを他の企業に証明し<br />
た。」<br />
前述のように同社は 2005 年に税引き前利益が 500 万米ドルに達したと見られ、その後<br />
PermaNet®の生産を毎年急拡大していることから考えて、安定した利益構造を確立していると思<br />
われる。<br />
1(PermaNet®の成功の理由<br />
PermaNet®の成功の理由を社長に問うと、たくさんの理由があるとしたうえで、次のように説明<br />
22 ファイナンシャルタイムズ'FT(2005 年 10 月 26 日付け記事より<br />
http://news.ft.comcms/s/1a19cfb6-457a-11da-981b-00000e2511c8.html<br />
77
している。<br />
「まず、当社は PermaNet®'の製品価値(を信じ、製造工程の各段階をつぶさに監視して全体の<br />
品質が確保できるよう特に努力している。この品質管理行程のおかげで、マラリアと他のベクター<br />
による伝染病の防止策としてWHOPESの完全推奨を得ることができた。ベスタゴー・フランセン<br />
は、WHOPESの規定に合致するために必要な厳しい品質管理基準を採用し、WHOのプロトコ<br />
ルに従った社内バイオアッセイ・ラボを持つ唯一のベッドネット・メーカーだ。ベトナムにあるこのラ<br />
ボでは、実験用の蚊を独自に育て、コーンテストとトンネルテストを行って、PermaNet®の殺虫力、<br />
ノックダウン、吸血を阻止する効果を確認している。」<br />
「もうひとつは、当社が重視する 5 つの価値のひとつである反応スピードだ。複雑な配送の手配<br />
に苦心する時も、タイムリーにオーダーに対処する時も、当社のすぐれた顧客サービスが他に差<br />
をつけてくれる。ベスタゴー・フランセンは世界中に 13 の事務所を構え、顧客によりよいサービス<br />
を提供している。このような国際的なプレゼンスは、現地市場に溶け込み、現地で雇用機会を提<br />
供し、当社の人命救助製品のための販売土壌を開発するという当社のコミットメントを強固にする<br />
ものだ。」<br />
ここで社長が言及している同社が重視する 5 つの価値とは、イノベーション、情熱のある人々、<br />
責任、精確さ、反応スピードである。これらが、PermaNet®だけでなく、他の商品開発とマーケティ<br />
ングの推進力になっている。<br />
ベスタゴー・フランセンへのデルタメトリン供給契約を担当した独化学大手バイエル'Bayer<br />
Environmental Science(のゲアハルト・ヘッセ氏は 2004 年初め、同社の急成長を、「規模は比較的<br />
小さいが、きわめてフォーカスした事業にアプローチしており、やる気のある会社だ。迅速かつ柔<br />
軟な経営判断と行動力が、ベスタゴー・フランセンの大きなパフォーマンスを生み出している」と評<br />
価している。<br />
2(今後のビジョン<br />
社長は、世界中でヘルスケアの格差がなくならない限り、ベスタゴー・フランセンは途上国に直<br />
接向けた救命製品を刷新し続けるとしている。<br />
また、ベスタゴー・フランセンのこれまでの急成長が主力商品 PermaNet®に過剰に依存してい<br />
ることは疑いないことであり、同社が商品の多角化によりバランスのとれた収益源を確保できる事<br />
業体制を目指しているのは明らかである。Prime Water International'PWI(への資本参加が、<br />
LifeStraw®で築いた浄水事業の拡大・強化を狙ったものであるように、同社はすでに PermaNet®<br />
78
の先を見た商品開発に取り組んでいる。この行動力は、同社がいかに大きなイノベーション・マイ<br />
ンドを持ち、企業成長に勢いがあるかということを裏付けるものである。<br />
a. 新商品の開発―殺虫剤加工耐久壁紙 Durable Residual Wall Lining=DL<br />
ベスタゴー・フランセンは 2009 年 2 月、マラリア撲滅を目指す新商品を開発するため、非営利団<br />
体で社会投資ファンドであるアキュメン・ファンド'Acumen Fund(、マラリアのスペシャリストである<br />
リチャード・アラン氏'Richard Allan(と、合弁事業 Durable Activated Residual Textiles S.A. (DART)<br />
を設立すると発表した 23 。マラリア・ベクターを寄せ付けない殺虫剤加工した耐久壁紙'Durable<br />
Residual Wall Lining=DL)の大量生産へ向けた開発に取り組むとしている。DARTの社長にはベ<br />
スタゴー・フランセン COO のライマー氏が就任する。<br />
現状一般的に使われている屋内のマラリア・ベクター対策ツールは、LINと殺虫剤噴霧'Indoor<br />
Residual Spraying=IRS(である。ふたつの措置の殺虫効果は実証されているものの、それぞれに<br />
難点がある。LINは 5 年ぐらい確実に効果があるが、ネットの下で眠るのは快適とは言えない。一<br />
方、IRSは睡眠習慣への影響はないが、壁の表面が滑らかで殺虫剤が壁の奥にしみ込むことが<br />
ないなどの条件があるうえ、特殊な装置を使い 4~6 ヵ月ごとにこれを繰り返す必要があり、手間<br />
がかかる。DLの開発は両者の長所を合体させ、難点を排除することを目的としたものである。通<br />
常の壁紙のように壁面に貼り、殺虫剤の効果はLINと同じぐらい、あるいはもっと長く持続させると<br />
いうものである。ネットの下で暑苦しい思いをして眠る必要もなくなる。<br />
DLのもうひとつの斬新さは、通常の壁紙のように模様や柄を入れて内装材として利用できるこ<br />
とである。DLを考案したアラン氏は、カンボジアで部屋の壁を壁紙できれいにしているのを見て、<br />
これをマラリア防止策とつなげられないものかという発想が浮かんだようである。<br />
DLに注目されるのは、将来的に殺虫スプレーにとって代わるマラリア防止ツールとしての可能<br />
性である。DARTは耐久壁紙をこの問題を解決できるよう設計し、マラリア危険地域に住む貧困<br />
層の人々が購入できる価格で入手できるように商品化する。独自のディストリビューション方法を<br />
考案するとしているのは、NGOと国際機関がほぼ独占するような、現状のマラリア防止ツールの<br />
ディストリビューションを通してこのような商品を供給するのは、難しいと見ているためと思われる。<br />
� アキュメン・ファンド'Acumen Fund(<br />
2001 年にロックフェラー財団、シスコ・システムズ財団、3 人の篤志家で設立された、貧困問題<br />
の解決に取り組む事業に投資する米国の非営利ベンチャーファンドである。個人や団体から資金<br />
を集めている。投資ポートフォリオは、水関連事業'2008 年末投資額 380 万米ドル(、健康関連事<br />
23 2009 年 2 月 10 日付プレスリリースおよび Acumed Fund ホームページ Durable Activated Residual Textiles<br />
79
業'同 2,110 万米ドル(、住宅関連'同 480 万米ドル(、エネルギー関連事業'同 240 万米ドル(、農<br />
業関連事業'290 万米ドル(。<br />
� リチャード・アラン氏<br />
コンゴでの医師活動などを経て、2000 年にRBMのマラリア危険国担当コーディネーターとして<br />
NGOの技術サポートなどに携わった。2002 年に自らマラリア撲滅活動を推進するNGO、MENT<br />
ORを興し、代表を務める。<br />
'3(BOPビジネス推進に係る社内体制<br />
① ミッケル・ベスタゴー・フランセン社長のリーダーシップ<br />
同社の事業成功は、国際機関やNGOなどとの広範な連携活動によるところが非常に大きいが、<br />
社長自身の旺盛な起業家精神なしには語れない。<br />
ミッケル・ベスタゴー=フランセン氏は 1972 年、同社の創業地であるデンマークのコルディング<br />
で生まれた。ハイスクール卒業後、19 歳でヒッチハイクなどをしながら中東・アフリカを回るうちに、<br />
ナイジェリアのラゴスに腰をおろし、中古車やその部品、古着の輸入で生計を立てるようになる。<br />
ここに「人道的な事業で利益を得る」という現ベスタゴー・フランセン社の事業戦略の芽を見ること<br />
ができる。1992 年に軍事クーデターが勃発して帰国を余儀なくされた。父親の経営する会社に入<br />
社したミッケル氏は、まず救援用品の事業に進出するが、これはアフリカでの経験や人脈などが<br />
活かされたものと思われる。1994 年にはケニアに販売・物流センターを立ち上げるため一時移り<br />
住んでいる 24 。同氏は 1998 年に社長に就任した。<br />
ミッケル・ベスタゴー・フランセン社長は 2009年10 月、同氏の斬新的な起業家活動に対し、英経<br />
済誌『エコノミスト』から 2009 年度イノベーション賞を贈られた。<br />
「ミッケル・ベスタゴー・フランセンは、ユニークな人道的起業家精神のビジネス・モデルで自身<br />
の会社を率いる独創的な考えの人物だ。その Profit for Purpose というアプローチが人道的責任を<br />
主力事業にしている。ミッケルは途上国に対して直接イノベーションを提供し、商品ユーザーを消<br />
費者ととらえ、患者や犠牲者とは見ていない。彼の会社の疾病防止のための製品やコンセプトは、<br />
貧困者の生活救済に甚大なインパクトを与え、健康管理の革命に力を貸す。彼のビジョン、仕事、<br />
ビジネスに取り組むポジティブな態度は、『エコノミスト』のイノベーション賞が評価し奨励しようとす<br />
24 フォーブズ記事'前述(<br />
80
ることの素晴らしい見本だ」と、選考委員メンバーのアンドレア・プファイファー氏'AC Immune 社<br />
CEO(は同氏の受賞理由を述べている。<br />
図表 21 ミッケル社長'ケニアでの HIV/AIDS キャンペーンで(<br />
出所:ベスタゴー・フランセン・ホームページ<br />
社長の「人道的な事業で利益を得る」という経営方針と、救援事業に対する情熱と斬新な事業<br />
アプローチは、従業員にも大きなモチベーションを与えている。<br />
同社の R&D 部門には、例えば、タンザニアで 6 年間マラリア・ベクターの研究を続けた経験のあ<br />
るヘレン・パテス=ジャメット'Dr. Helen Pates Jamet(氏のような、マラリア撲滅への使命感に燃え<br />
る研究者が多い。事業の成功を通して、社会的使命の達成感が得られ、それがさらに研究意欲を<br />
かき立てていると見られる。<br />
② イノベーション<br />
自社をテクノロジー企業と認識する同社は、利益配当を抑え、新商品開発だけでなく既存製品<br />
の機能向上のために投資し続けている。例えば、2005 年には売上高'4,000 万米ドル(の 8%を研<br />
究開発に投資している 25 。この努力は、PermaNet や LifeStraw などの 8 つの特許として実を結んで<br />
いる。<br />
LifeStraw は世界の有力誌から斬新な商品として高く評価されている。<br />
25 フォーブズ記事'前述(<br />
81
③ CSR活動との関係<br />
図表 22 LifeStraw の受賞一覧<br />
賞の主催者 受賞名<br />
2008年サーチ&サーチ賞 世界を変えるアイデア<br />
2006年Well-Tech 刷新テクノロジー賞<br />
2005年INDEX:賞 国際デザイン賞<br />
2005年フォーブズ誌 “我々の生活を変える10のもの”<br />
2005年タイムズ紙 “ベストインベンション”<br />
リーダーズ・ダイジェスト誌 “欧州のベストインベンション”<br />
エスクワイア誌 “今年のイノベーション”<br />
Gizmagマガジン'デザイン週刊誌( “今世紀のインベンション”<br />
ニューヨークタイムズ紙 “命を救う浄水器”<br />
ポピュラーサイエンス・マガジン誌 “大衆向け浄水器”<br />
ニューズウィーク誌 “安全な飲料水を作るちょっといい物”<br />
出所:ベスタゴー・フランセン・ホームページ<br />
1(統合予防キャンペーン'Integrated Prevention Demonstration)<br />
ベスタゴー・フランセンは 2008 年、統合予防キャンペーン'Integrated Prevention Demonstration<br />
=IPD Campaign(を企画した。この目的は、途上国の住民が自主的に HIV のカウンセリングとテス<br />
ト'HCT(に参加するよう促すと同時に、PermaNet®や LifeStraw®などをセットにした CarePack を<br />
インセンティブとして無料配布することにより、マラリア感染予防に貢献することである。これを企<br />
画した背景には、2010 年までにケニアの成人人口の 80%にHCTへの自主参加を目指す国家レ<br />
ベルの計画を支援するというコミットメントがある。それと同時に、このキャンペーン・コンセプトを<br />
普及させて、HIV/AIDS やマラリアなどの感染患者数の増加を 2015 年までに食い止め、その後減<br />
尐させる、また、安全な飲料水が手に入らない人の数を 2015 年までに半減させるとするMDGsの<br />
目標達成に貢献することを視野に入れている。<br />
IPDキャンペーンは 2008 年 9 月 16~22 日にわたり、ケニア西部のルランビ地区で 15 から 49<br />
歳の男女を対象に実施され、CarePack は地区内の 30 ヵ所で手渡された。これまでの HIV テスト<br />
への参加は現地住民の 20%以下にとどまっていたが、キャンペーンには 80.2%にあたる 5 万人近<br />
くが参加した。このテストで HIV 陽性と診断された約 2,000 人には医療処置が施され、抗生剤<br />
'cortimoxazole prophylaxis(が 3 か月分渡された。<br />
キャンペーンの 2 ヵ月後、ITN'PermaNet®とは特定していない(の保有・使用状況を調べたとこ<br />
ろ、住民の 95%以上が持っていると回答。85%以上が寝るときに使用していることが分かった。一<br />
82
方、浄水フィルターを所有する所帯の比率は、キャンペーン前には 5%以下だったが、LifeStraw®<br />
の無料配布により 75%近くに増え、このうち 75%が実際に使用していると回答した。<br />
このように、キャンペーンが住民の衛生環境の改善に大きな効果を与えたことが確認されたこ<br />
とから、2010 年には、2 回目の CarePackキャンペーンの実施を計画している。キャンペーンを通<br />
して、短期間に数百万の人々に HIV 感染の有無を知る機会を提供するとしている。<br />
'4(公的機関・国際機関・NGO等との連携<br />
前述のように、ベスタゴー・フランセンの事業活動にとって、公的機関・NGO・国際機関との連<br />
携は不可欠なものである。<br />
「官民提携は当社にとって極めて重要なだけでなく、途上国での課題に取り組む上でも極めて<br />
重要だ。ベスタゴー・フランセンは、最も必要とする人々にタイムリーに当社の製品が届くよう、NG<br />
O、政府、国連機関、学術機関と直に協力し合っている。オープンで誠実なコミュニケーションを保<br />
ち、パートナーのニーズを平等に考慮しながら、当社は数多くの深刻な問題を回避することができ<br />
た。当社の特性のひとつである柔軟性が、事が計画通りに進まない時に解決策を見つけるのに<br />
役立っている。」'ベスタゴー・フランセン社長(<br />
① 主な提携NGO<br />
NetMark、SFH、GFATM、UNICEF、国際赤十字、 World Malaria Day、Mentor、Union<br />
Solidarity and development Association、Samaritan’s Purse、World Vision、Convoy of Hope、<br />
Global Fund、ロータリークラブほか多数<br />
② シエラレオネでの連携事例<br />
ベスタゴー=フランセン社長は、シエラレオネでの現地当局、国際機関との共同活動をマルチ<br />
提携の好例として、次のように語っている'書面インタビュー(<br />
「2006 年、ベスタゴー・フランセンはシエラレオネでの多角的なキャンペーンに参加した。当社は、<br />
保健省、政府機関、世界銀行、カナダ赤十字、カナダ国際開発公社'Canadian International<br />
Development Agency (などと提携した。同国ではマラリアが風土病となっており、1 年間の 8~10<br />
ヵ月も感染率が高い期間が続くことから、緊急な対策が切望されていた。ネットの使用率は非常に<br />
83
低く、7 所帯に 1 所帯しかLINを保有していなかった。2005 年に行われた調査によると、就寝時にL<br />
INを使用していたのは子供の 10%、妊婦の 12.4%にすぎなかった。<br />
大きな障害に対して、唯一の解決策は新しいタイプのマラリア防止戦略を試みることだった。こ<br />
のプログラムがユニークだったのは、PPPプロジェクトだったということだ。実際にはこのような提<br />
携は大きな課題に直面した'社長は詳細について言及していない(。<br />
だが、このキャンペーンでは我々は、ネットの無料配布を期限付補助金によるネット販売と、そ<br />
れによる持続可能なコマーシャル・マーケットの構築につなげることに成功した。実際、プログラム<br />
で当社のパートナーになった団体は、PermaNet®を住民に無料で配布することにより市場の下地<br />
を作り、LINを使用することがいかに重要かを大衆に教育してくれた。この提携は、社会的立場で<br />
のマーケティングと商業的な宣伝キャンペーンを通して、継続的な性格を強めた。無料配布は当<br />
初、商業市場に一時的にネガティブな影響を与えるが、シエラレオネでの活動は'LIN市場の(成<br />
長と持続可能性のためのプラットフォームとなった。持続可能なインパクトを市場にもたらすという<br />
目標は、競争によってではなく、シナジーを得る努力を通して達成された。異なるアプローチを通し<br />
て、当社はシエラレオネのマラリア患者数削減に貢献し、存続可能なリテール市場も創出すること<br />
ができた。」<br />
③ 緊急支援<br />
ベスタゴー・フランセンの製品は、被災地住民の緊急支援のためにも多く投入されている。2004<br />
年のインドネシア沖地震による津波被災地、2005 年のカシミールの地震被災地などをはじめ、<br />
2008 年にはミャンマーの台風被災地に、PermaNet®74 万 4,000 枚、LifeStraw®1 万 6,200 本が配<br />
送された。USAID、WHO、Union Solidarity and development Association、Samaritan’s Purse、<br />
American Red Cross、Rotary International、World Vision、Convoy of Hope など多数の国際機関、<br />
NGOがドナーとなっている。<br />
④ 国際赤十字との連携活動<br />
2005 年 12 月、国際赤十字連盟と Red Crescent Societies が支援するニジェールの小児麻痺・<br />
マラリア撲滅キャンペーンで、5 歳未満の子供を持つ母親に PermaNet®が贈られた。エイズ、結核、<br />
マラリア撲滅を目的とした Global Fund と、Canadian International Development Agency'カナダ赤<br />
十字を通して寄付(、米国赤十字、ノルウェー赤十字が合計 225 万 5,000 枚を寄付した。「これだけ<br />
のネットの配給で 4 万人の子供たちの命を救えると思う」'ジュネーブ国際赤十字本部の公共保健<br />
担当者、ジャン・ロイ氏(<br />
84
国際赤十字連盟は、2004 年にもトーゴでのはしかキャンペーンでは 100 万枚近い PermaNet®<br />
を寄付した。<br />
⑤ 積極的なコミュニケーション活動<br />
同社の特筆すべき点は、各種のキャンペーン、会議などへの参加を通した積極的な対外コミュ<br />
ニケーション活動にある。以下がその例である。<br />
� 国際マラリア会議<br />
2008 年 4 月 21~22 日にドイツのボンで開催され、アフリカ、欧州、北米など 20 ヵ国から 120 人<br />
が集まった。ここでベスタゴー・フランセンのベクター商品開発部門のジャメット氏'前述(は、抵抗<br />
力を持つマラリア媒介蚊の問題について講演し、同社が強力な対処策として PermaNet®3.0 を開<br />
発したと発表した。<br />
� 世界マラリア・デー<br />
2009 年 4 月にナイロビで開かれた世界マラリア・デーで、同社はケニア保健省と合同でホストを<br />
務めた。シンポジウムのテーマは、LLINに対するマラリア媒介蚊の抵抗力だった。<br />
� ベトナム農村地域でLLINを無料配布<br />
2008 年 7 月、ベトナムの農村地域にあるカンビン地区でのマラリア防止キャンペーンに、2007<br />
年度ミス・ユニバースの森理世さんを動員してLINを無料配布'数量不明(した。2008 年度ミス・ユ<br />
ニバース世界大会がベトナムで開催されることを当て込んだ企画と思われる。<br />
85
'1(BOPビジネスの事業概要<br />
① BOPビジネス事業の位置付け<br />
1(企業概要<br />
4.クアルコム'Qualcomm(<br />
http://www.qualcomm.com<br />
CSRでBOP市場開拓の基盤を形成<br />
クアルコム'ナスダック上場(は 1985 年、業界のベテランエンジニア 7 人が「QUALity<br />
COMMunications'高品質の通信(を構築したいと考えたことをきっかけに創立された。彼らが力を<br />
合わせて考えた計画が進化し、クアルコム・インコーポレイテッド'Qualcomm Incorporated(という<br />
通信業界最大の起業サクセスストーリーが誕生したのである。クアルコムは、CDMA 方式の携帯<br />
電話の実用化成功で大きく成長し、全世界に 3G'第3世代携帯電話(および次世代ワイヤレスを<br />
発展させる上で中心的な役割を果たしている。<br />
クアルコムは積極的な研究開発活動を行っており、2006 年度からは R&D 費は売上高比率で<br />
20%を超え、85 年以降、累計で約 134 億ドルを投じている。また、現在保有する特許権の総数は<br />
2010 年1月時点で米国内 1 万 1,900 件、海外 5 万 6,100 件'いずれも出願中含む(、全世界 175<br />
社以上の通信機器メーカーとライセンス契約を結んでいる。2010 年 1 月現在、9 億 4,500 万人が<br />
3G CDMA に加入、166 カ国に 615 以上の3G 通信事業者がおり、4,000 以上の CDMA 対応端末<br />
モデルがある。年商 100 億ドル超に成長したクアルコムは、全世界に 146 拠点、米国国内に 76 拠<br />
点を設け、従業員数は約 1 万 6,000 人にのぼる。<br />
2(BOPビジネスに向けた戦略的プログラム<br />
ビジネスの世界において、企業の「責任」の中心は昔から、利益を上げ、株主の利益を高めるこ<br />
とだった。言い換えれば、企業の財務上の責任だけが重要な原動力だったのである。しかしこの<br />
10 年の間に、環境、現地コミュニティ、労働条件、そして倫理的実践に対する、より幅広い企業責<br />
任を明確にする動きが勢いを増し、確立されるに至った。こうした新しい流れが、企業の社会的責<br />
任'CSR(と呼ばれるものである。CSRは、しばしば企業の「トリプルボトムライン」とも呼ばれる。<br />
トリプルボトムラインは、企業経営における経済的、社会的、環境的パフォーマンスを総合的に表<br />
す言葉である。ビジネス界は職場、市場、コミュニティにおいて、企業の社会的責任への投資を拡<br />
大しつつある。<br />
86
ワイヤレス・リーチは、クアルコムが実施する企業のCSR活動である。ワイヤレス・リーチは、同<br />
社の長期的ビジネス目標をサポートする戦略的プログラムと捉えられている。ある国のインターネ<br />
ット普及率が1%上昇するごとに、一人当たりの国内総生産'GDP(はおよそ 10%増加する。また、<br />
モバイル通信の普及率が 1%上昇するごとに、一人当たりのGDPはおよそ 5%増加する。<br />
こうした数字は、ワイヤレスコネクティビティへのアクセスに制約があるコミュニティに存在する<br />
「デジタルデバイド」を克服することの重要性を浮き彫りにしている。この問題の解決に向けて活動<br />
するクアルコムのワイヤレス・リーチ・イニシアチブは、恵まれないコミュニティの人々が、意思を伝<br />
達し、学び、医療を受け、グローバル市場に手を伸ばすための新しい方法を作り出すことによって、<br />
生活を向上させることを目的としている。プロジェクトの主な目的は下記の通り。<br />
� クアルコムはハードウェアとワイヤレスシステムを提供し、技術の利用を可能にすることに<br />
より、技術の市場が形成される。<br />
� 農民、漁師、企業などにハードウェアとワイヤレスシステムを寄付することにより、今後、必<br />
要に迫られたときにそれらを使用できるレベルまで、生活水準を押し上げることができる。<br />
� クアルコム・ブランドの認知度と評価を高めている。<br />
ワイヤレス・リーチは、同社の長期的ビジネス目標をサポートする戦略的プログラムと捉えられ<br />
ており、ワイヤレス・リーチを運営するための費用は年間予算に組み込まれ、クアルコムの事業資<br />
金から拠出されている。<br />
② 主な BOP ビジネスサービス<br />
~ワイヤレス・リーチ・イニシアチブの主なプロジェクト紹介<br />
クアルコムのワイヤレス・リーチ・イニシアチブは、22 カ国で 37 のプロジェクトとして実施されて<br />
いる'各プロジェクトの開発段階はそれぞれ異なる(。同社のワイヤレス技術やソリューションの画<br />
期的な使用法や導入を促すことを目的としている。プロジェクトの実施地は、情報通信'ICT(技術<br />
に対するニーズとコミュニティの目標、ワイヤレスの受信可能地域、電話回線の欠如、現地のNG<br />
Oや事業者との関係、新しい画期的なワイヤレス・ソリューションのモデルになりうるかどうかによ<br />
って選定され、政策の優先順位'地方の接続、教育の充実、医療の充実、テレデンシティの向上など(に適う分野を選定する。<br />
こうしたプロジェクトは純粋に慈善事業に分類されるものから、持続的に収益を上げる可能性の<br />
あるものまで多岐にわたる。個々の事業が収益を上げているかどうかの情報は明らかでないため、<br />
同社の事業内容から判断して (a) 慈善事業'CSR(=収益・利益モデルへの転換は困難または<br />
相当先と思われる、(b) 現時点ではCSRだが中長期的に収益モデルに発展する可能性がある、<br />
(c) 低所得層向けビジネス'BOP(としてみなすことができる、または近い将来その可能性がある<br />
87
――に分けて紹介する'ただし分類は、プログラムの性格をわかりやすくするための便宜的なもの<br />
であり、同社やパートナーのスタンス、政府支援、経済環境、実際の事業収支などによって異なっ<br />
てくる点は了解願いたい(。<br />
1(慈善事業'CSR(: 収益・利益モデルへの転換は困難または相当先と思われる<br />
a) 中国農村へのネット導入プロジェクト――農村の学校に通信機器を無償提供。長期的に市<br />
民の所得が上昇すればパソコンや携帯電話の購入へと進む可能性はあるが、現在所得水準は<br />
極めて低くプロジェクト規模も小さい。収益・利益を上げるにはかなりの時間を要すると見られる。<br />
分<br />
類<br />
教<br />
育<br />
国<br />
中<br />
国<br />
図表 1 ワイヤレス・リーチ事例'中国(<br />
プロジェクト名 パートナー 目的・内容<br />
'農村へのインターネッ<br />
ト導入(<br />
* China Unicom 社<br />
* Chinese Ministry of<br />
Science and<br />
Technology<br />
'中国科学技術部(<br />
* PKUnity 社<br />
� 中国内陸の農村地域は、東岸地域に比べ社会面、経済面にお<br />
いて遅れをとっている。クアルコムでは PKUnity Microsystems<br />
社と提携し、教育と技術を通して中国の情報格差を是正し、人々<br />
の暮らしを向上させている。このプログラムでは、重慶市、江西<br />
省、雲南省の 8 つの学校に、CDMA2000 1X データカードを使用<br />
したワイヤレスのインターネット・アクセスや PKUnity 製のサー<br />
バー、ネットワークコンピュータを提供した。<br />
� 北京市内にある出稼ぎ労働者の児童向け特別学校にもワイヤ<br />
レス・インターネット機器を提供しネットを通じて様々な情報・知<br />
識が得られる環境を提供している。教師が教材をサーバーにダ<br />
ウンロードすると、生徒が個別のネットワークコンピュータからア<br />
クセスできる。<br />
出所: Qualcomm ワイヤレスリーチ・プログラム。' (で書かれたプロジェクトは正式名称がないもの。<br />
b) インドネシアの農村に対する EV-DO 導入事業――情報から隔絶されたインドネシアの農<br />
村にインターネット環境を提供。市民の所得水準は極めて低く、プロジェクト規模も 5 校と小さい。<br />
これ自体で収益・利益を上げるモデルにするのは困難かかなりの時間を要すると見られる。<br />
88
分<br />
類<br />
教<br />
育<br />
国<br />
イ ンドネシア<br />
図表 2 ワイヤレス・リーチ事例'インドネシア(<br />
プロジェクト名 パートナー 目的・内容<br />
'農村への EV-DO 導<br />
入(<br />
* Axesstel Inc.社<br />
* IndoNet 社<br />
* Sampoerna Telekomunikasi<br />
Indonesia 社<br />
* Minister for Information<br />
and Communication<br />
Technology<br />
'インドネシア情報通信技術<br />
省(<br />
* State Ministry for the<br />
Accelerated Development of<br />
Disadvantaged Regions<br />
'条件不利地域の開発促進<br />
を促すインドネシアの政府機<br />
関(<br />
89<br />
� プログラムの主な目的は、ワイカナン県にある 5 つの高等学<br />
校'Buay Bahuga 、 Negeri Besar 、 Negara Batin 、 Rebang<br />
Tangkas、Pakuan Ratu(にコンピュータラボを開設し、1,000 人<br />
以上の生徒がインターネットを利用できるようにすること。<br />
Wireless Reach は、ランプン州ワイカナン県の遠隔地の町村<br />
に対し EV-DO 高速データアクセスのできる電話回線やイン<br />
ターネットの普及率上昇を図る。Sampoerna Telekomunikasi<br />
Indonesia'STI(社は、農村部やサービスの行き届かない地域<br />
の受信範囲を拡大するとともに、高度な音声サービスや高速<br />
データサービス通信に最適な 450MHz の周波数帯域幅を使<br />
用している。<br />
� これまでインドネシアのスマトラ島にあるランプン州のような<br />
孤立した村落は、通信インフラが最低限しか整備されていな<br />
いため、生徒たちは荒れた砂利道を 6 時間もかけて運転しな<br />
ければ外部と連絡とることができなかったが、今では、インタ<br />
ーネットを使って様々な情報に触れることができる。<br />
出所: Qualcomm ワイヤレスリーチ・プログラム。' (で書かれたプロジェクトは正式名称がないもの。<br />
c) ペルーにおける農村診療所ワイヤレス事業――農村の診療所にワイヤレス通信機器を無<br />
償提供する。普段から満足な診療を受けられない人々が治療の対象であり、診療所で働く医師た<br />
ちもボランティア。収益・利益を上げるビジネス形態への発展は当面困難と見られる。<br />
分<br />
類<br />
医<br />
療<br />
国<br />
ペ ルー<br />
図表 3 ワイヤレス・リーチ事例'ペルー(<br />
プロジェクト名 パートナー 目的・内容<br />
'農村の診療所にワイ<br />
ヤレス導入(<br />
* Kausay Wasi Health<br />
Clinic<br />
* FACES Foundation<br />
'顔面変形のある子ども<br />
に手術を行う財団法人(<br />
* Capitol City Medical<br />
Teams<br />
'米国内の非営利医療組<br />
織(<br />
� マチュ・ピチュから数時間先のコーヤという農村にある小さな<br />
診療所では、インカの「聖なる谷」に暮らす先住民に医療サー<br />
ビスを提供している。米国からやってくる医師団は、医療への<br />
アクセスのない住民を対象にボランティアで働く。1 週間に 500<br />
人もの患者が診察を受けに来ることもある。2005 年から運営<br />
されるこの診療所では、地域の 19,000 人以上の患者を診察<br />
し、600 件以上の手術を施し、小規模ながら高い効果が認め<br />
られている。<br />
� クアルコムが参加する以前は、診療所には通信環境が一切<br />
なかった。固定回線による通信を試みたこともあったが、険し<br />
い山岳地帯があるために実現困難だった。過去 2 年間、<br />
Wireless Reach は、この診療所に、ノートパソコン、携帯電<br />
話、IT機器、接続料を提供している。現在、診療所および派遣<br />
医師は世界各地の同僚医師や医療専門家とリアルタイムで<br />
通信することができる。<br />
出所: Qualcomm ワイヤレスリーチ・プログラム。' (で書かれたプロジェクトは正式名称がないもの。
2(現時点ではCSRだが中長期的に収益モデルに発展する可能性はある<br />
a) グアテマラ「未来の学校」プロジェクト――学校に機器を無償提供。長期的に市民の所得が<br />
上昇すればパソコンや携帯電話の購入する可能性はある。400 校が便益を受けるなど実施規模<br />
も大きく、学校による継続的な機材調達ニーズも見込める。<br />
分<br />
類<br />
教<br />
育<br />
国<br />
グ アテマラ<br />
図表 4 ワイヤレス・リーチ事例'グアテマラ(<br />
プロジェクト名 パートナー 目的・内容<br />
未来の学校 * Fundación Sergio Paiz<br />
'セルジオ・パイス基金(<br />
*Ministry of Education'グア<br />
テマラ教育省(<br />
* TELGUA 社<br />
'América Móvil の子会社(<br />
* United States Agency for<br />
International Development<br />
'米国国際開発庁(<br />
出所: Qualcomm ワイヤレスリーチ・プログラム<br />
� クアルコムでは Wireless Reach プログラムを利用してグアテマ<br />
ラ教育省'MINEDUC(の取組を支援している。高度なワイヤレス<br />
技術を尐数の学校に導入し、その中からモデル校を作り出し、将<br />
来的にはグアテマラのすべての学校がそのモデル校に倣うこと<br />
を目標としている。現在 400 校がこのプログラムの利益を受け<br />
ている。教育省のほか Fundación Sergio Paiz 'セルジオ・パイス<br />
基金(、USAID、TELGUA'América Móvil 社の子会社(とも提携し<br />
て、農村部の学校を支援するためのリソースを提供している。<br />
� アルタ・ベラパス、エスクイントラ、ペテン、サンマルコスなどの地<br />
域から 15 校を選出し、インフラを整備したうえで、各校にコンピュ<br />
ータ 17 台、高速 EV-DO ワイヤレス接続、指導用ソフトウェアお<br />
よびトレーニングを提供している。<br />
b) ベトナムのコミュニティ向け教育・訓練センター――教育・訓練センターの設立が主目的で<br />
あり、一般市民がクアルコムの機器やサービスを購入する仕組みにはなっていない。ただし 64 の<br />
省庁に機器を導入するなど実施規模は大きく、また訓練施設も成人向けであるため、彼ら向けの<br />
サービスへのニーズが生じる可能性はある。<br />
分<br />
類<br />
教<br />
育<br />
国<br />
ベ トナム<br />
図表 5 ワイヤレス・リーチ事例'ベトナム(<br />
プロジェクト名 パートナー 目的・内容<br />
TOPIC64<br />
'2006 年~(<br />
*Electricity Vietnam Telecom<br />
社<br />
* Hewlett-Packard 社<br />
* Microsoft 社<br />
* Center for Research on<br />
Management and Consulting<br />
'経営・コンサルティング研究セ<br />
ンター(<br />
*United States Agency for<br />
International Development<br />
'米国国際開発庁(<br />
出所: Qualcomm ワイヤレスリーチ・プログラム<br />
90<br />
� 中国内陸の農村地域は、東岸地域に比べ社会面、経済面に<br />
お い て 遅 れ を と っ て い る 。 ク ア ル コ ム で は PKUnity<br />
Microsystems 社と提携し、教育と技術を通して中国の情報<br />
格差を是正し、人々の暮らしを向上させている。このプログラ<br />
ム で は 、 重 慶 市 、 江 西 省 、 雲 南 省 の 8 つ の 学 校 に 、<br />
CDMA2000 1X データカードを使用したワイヤレスのインター<br />
ネット・アクセスや PKUnity 製のサーバー、ネットワークコン<br />
ピュータを提供した。<br />
� 北京市内にある出稼ぎ労働者の児童向け特別学校にもワイ<br />
ヤレス・インターネット機器を提供しネットを通じて様々な情<br />
報・知識が得られる環境を提供している。教師が教材をサー<br />
バーにダウンロードすると、生徒が個別のネットワークコンピ<br />
ュータからアクセスできる。
c) タイの診療所に遠隔医療用設備、教育設備導入――貧しい人々に対する遠隔医療を実施<br />
する機材を提供。医療・教育施設ともに規模は限定的。ただし前述のペルーの医療事業と異なり<br />
医療自体は有償であり、また機器・サービスの定期的な買い替えやアップグレードなどのニーズ<br />
が期待できる。<br />
分<br />
類<br />
医<br />
療<br />
国<br />
タ イ<br />
図表 6 ワイヤレス・リーチ事例'タイ(<br />
プロジェクト名 パートナー 目的・内容<br />
'遠隔地診療所に<br />
ネット導入(<br />
* Axesstel Inc.社<br />
* CAT Telecom Public<br />
Company Limited 社<br />
* Ministry of Education<br />
'タイ教育省(<br />
* Ministry of Public Health<br />
'タイ保健省(<br />
* National<br />
Telecommunications<br />
Commission<br />
'タイ国家電気通信委員<br />
会(<br />
* Office of the<br />
Non-Formal Education<br />
Commission<br />
'非公式教育委員会(<br />
� パニー島やヤオヤイ島の村落の医療・教育面でのニーズに応え<br />
るために、クアルコムとパートナーは、EV-DO 高速ワイヤレスサ<br />
ービスを提供している。このプロジェクトでは遠隔地の 2 つの診療<br />
所において、遠隔医療機器と高速インターネット・アクセスを通じ<br />
て本土の病院と通信できるようになった。医療従事者は、耳鼻咽<br />
喉鏡、検眼鏡、皮膚拡大鏡、一般検診用カメラ、デジタル電子聴<br />
診器、心電図、デジタル呼吸計などの画像システムや照射システ<br />
ム、コンピュータ、ノートブック PC、ワイヤレス接続機器などを用<br />
い 、 遠 隔 で 医 療 情 報 を や り 取 り で き る。 CAT Telecom 社の<br />
EV-DO ネットワークを使用して、診療所から本土の病院にいる医<br />
師にグラフや画像を送ることができる。<br />
� 教育に関する取組では、タイ教育省非正規教育委員会'ONFEC(<br />
のモバイル学習プログラムの一環として、パンガー県の 2 つの図<br />
書館で住民に高速インターネットアクセスを提供。タッププー公立<br />
図書館とクラブリ公立図書館に通信センターを設置し、クアルコム<br />
がデスクトップコンピュータ、Axesstel 社が D800 EV-DO モデム<br />
を提供した。CAT Telecom 社の EV-DO ネットワークを使用する<br />
データカードを備えたラップトップコンピュータ 4 台も提供されてい<br />
る。<br />
出所: Qualcomm ワイヤレスリーチ・プログラム。' (で書かれたプロジェクトは正式名称がないもの。<br />
d) インドの Fisher Friend'詳細は'2(-①(――現時点ではCSRだが中長期的に収益モデル<br />
に発展する可能性がある。漁師たちの収入は極めて低く、携帯電話は無償提供されている。今の<br />
ところ携帯電話の使い方も情報収集にとどまっており、オペレータビジネスのような裾野の広がり<br />
がない。ただし長期的に個人またはグループで携帯電話を購入する、あるいは携帯電話を使った<br />
新種のサービスが生まれるといった可能性はある。<br />
91
分<br />
類<br />
公<br />
衆<br />
安 全<br />
国<br />
イ ンド<br />
図表 7 ワイヤレス・リーチ事例'インド(<br />
プロジェクト名 年 パートナー 目的・内容<br />
Fisher Friend 2007 * Astute Systems<br />
Technology 社<br />
* M.S. Swaminathan<br />
Research Foundation<br />
'M.S.スワミナタン研<br />
究財団(<br />
* Tata Teleservices<br />
社<br />
92<br />
� 2007 年に津波に見舞われたインドのタミルナードゥ州の漁師<br />
に BREW アプリケーションを備えた携帯電話を供与。重要情<br />
報の伝達ができない状態を解消するために開発され Fisher<br />
Friend によって、漁師たちに必要なデータが即時に配信され<br />
るようになった。漁師はワンクリックで天候、漁獲可能地域、<br />
魚の市場価格などの重要情報を現地の言葉で素早く確認す<br />
ることができる。<br />
� Fisher Friend は、①漁村地域への情報提供に貢献する非営<br />
利団体 M.S. Swaminathan Research Foundation 'M.S.スワミ<br />
ナタン研究財団: MSSRF(、②漁村地域に携帯電話および 3G<br />
CDMA 通信を提供する通信事業会社 Tata Teleservices<br />
社 、 ③ BREW プ ロ グ ラ ム を 開 発 し た Astute Systems<br />
Technology 社の共同事業によって実施されている。クアルコ<br />
ムとそのパートナーは、先進技術によって世界の漁師やその<br />
家族の暮らしをよくすることが可能であることを示したいとの<br />
思いがある。<br />
出所: Qualcomm ワイヤレスリーチ・プログラム。' (で書かれたプロジェクトは正式名称がないもの。<br />
3(低所得層向けビジネス'BOP(としてみなすことができるまたは近い将来その可能性がある<br />
a) 中国「PlaNet Finance」――通信サービスの行き届いていない地域の起業家に携帯端末を<br />
授与。起業を目指す人々を PlaNet Finance'NGO(のマイクロファイナンスで支援。携帯端末を有<br />
償'貸与(する仕組みか、マイクロファイナンスを申込んだ場合にクアルコムに収入が入る仕組み<br />
にできればBOPの可能性も。ただし市民の所得は依然低水準。<br />
分<br />
類<br />
起<br />
業<br />
家 精<br />
神<br />
国<br />
中<br />
国<br />
図表 8 ワイヤレス・リーチ事例'中国(<br />
プロジェクト名 パートナー 目的・内容<br />
PlaNet Finance * China Unicom 社<br />
* PlaNet Finance<br />
'マイクロファイナン<br />
スを支援するNGO(<br />
出所: Qualcomm ワイヤレスリーチ・プログラム<br />
� 先進的ワイヤレス技術を利用し、通信サービスの行き届いていない中<br />
国西部の陝西省、貴州省、寧夏回族自治区などで起業家を支援する。<br />
CDMA2000 の携帯端末 2,000 台を寄付し、端末には China Unicom 社<br />
から最長 2 年間有効の利用クーポンが予め付与されている。携帯端末<br />
は、PlaNet Finance に参加しているマイクロファイナンス企業・融資担<br />
当者やマイクロローン利用者'=起業家(に配布される。起業家は携帯<br />
端末を使ってモバイル通信ができるようになり、PlaNet Finance プログ<br />
ラムの有効性を高めている。<br />
� 携帯端末は、PlaNet Finance とのこれまでの取引に問題がなく、トレー<br />
ニングプログラムに定期的に参加しているローン利用者に配布される。<br />
China Unicom 社 の サ ー ビ ス 利 用 ク ー ポ ンを 使 用 す る と 、 PlaNet<br />
Finance からマイクロファイナンスのパートナーおよびローン利用者に<br />
様々な市場価格'例えば家畜の飼料価格(や融資情報などが配信され<br />
る。ローンを利用して市場に積極的に参加できるようになり、また遠方ま<br />
で足を運ぶ必要がなくなりマイクロファイナンスの融資が受けやすくなっ<br />
た。
成功事例<br />
図表 9 中国・PlaNet Finance プログラム:過疎地域の発展と起業家精神<br />
出所: Qualcomm ワイヤレスリーチ・プログラム<br />
Shengfang Li 氏は中国 Shaanxi 地方に住む極めて貧しい農民だったが、Wireless Reach プログ<br />
ラムによって携帯電話を与えられた。電話には利用クーポン'Voucher(が付与されている。<br />
Shengfang は 2005 年に PlaNet Finance から 132 ドルを借り、2006 年にはさらに 265 ドルの資金を<br />
借り、豆腐の製造装置を購入した。現在彼女は年間 2,640 ドルを稼ぐようになり、借りた資金を返<br />
済するだけでなく、家族と十分な暮らしができている。携帯電話によって、農産品や豆腐の市場価<br />
格を知ることができ、また顧客との間で不要な行き来もなくすことができた。<br />
出所: Qualcomm ワイヤレスリーチ・プログラム<br />
b) インドネシア Village Phone――マイクロローン→電話事業キット→通信サービスの普及→<br />
起業家に収入→返済という仕組みで。ウガンダでも同様の事業を実施。マイクロローン提供者か<br />
らすればBOPとして成立しているが、クアルコムが設備投資を回収出来ているか'いつできるか(<br />
は不明。<br />
93
分<br />
類<br />
起<br />
業<br />
家 精<br />
神<br />
国<br />
イ ンドネシア<br />
図表 10 ワイヤレス・リーチ事例'インドネシア<br />
プロジェクト名 パートナー 目的・内容<br />
Village Phone<br />
(村落電話)<br />
* Grameen<br />
Foundation<br />
'グラミン財団(<br />
出所: Qualcomm ワイヤレスリーチ・プログラム<br />
成功事例<br />
� 通信手段のない地元の起業家がマイクロファイナンス機関からマイクロロ<br />
ーンを受け、起業家はこのマイクロローンを利用し「村落電話キット」'電話<br />
機、アンテナ、電源、信号、関連のマーケティング資料(とサービスプランを<br />
購入し、自身の友人や近所の人々に電話使用料を「分単位」で小売りする<br />
仕組み。このシステムでは当事者のいずれにもメリットがある。<br />
① マイクロファイナンスのローン利用者は、持続性のあるICT事業の運営<br />
ができる。<br />
② 地域の人々は、低価格の遠隔通信サービスが利用できる。<br />
③ 通信事業者は、既存インフラを使用する加入者および通信時間が増大<br />
し利益を得る。<br />
� インドネシアの農村地域の電話回線密度が増加し、新たな機会が生まれ、<br />
マイクロファイナンスを利用した堅実な事業を営む起業家が増加するという<br />
期待が持てる。バングラデシュでは、30 万人以上が村落電話事業者<br />
'VPO(になっており、貧困の連鎖を断つ手段となっている。VPO の平均収<br />
入は全国平均を上回っている。ウガンダでは VPO の平均収入は全国平均<br />
のほぼ 3 倍となっている。<br />
インドネシア・ボゴールの南に位置する Neglasari 村で食料品店を営む Halimah さんは、Village<br />
Phone のオペレータでもある。彼女の店では割安な価格で電話サービスを受けられると評判だ。<br />
携帯電話を自宅に持って帰れるのでプライバシーが守れる上、ヤギ・ウダ製アンテナのお陰で受<br />
信状態も良好だ。Halimah さんは、お金のない人は支払えるようになったら払えば良いという仕組<br />
みにしている。自分の経験からそうしているそうだ。<br />
彼女が食料品店を始めたのは 2 年前。夫が心臓病で倒れ職を失ってからだ。地元銀行から尐<br />
額の資金を借り、その後計画的に返済をしたことが評価され、またローンを借りることができた。<br />
現在彼女は携帯電話サービス事業で 20%の利益率を確保する。食料品店の収入に加え携帯電話<br />
事業収入を得ることができるようになり、彼女は「一人息子を大学に送りたい」と言う。<br />
出所: Qualcomm ワイヤレスリーチ・プログラム<br />
94
図表 11 インドネシアでの Village Phone Project に参画するグラミン銀行。<br />
ノーベル平和賞受賞者でありグラミン銀行創設者の Muhammad Yanus 氏'2008 年(<br />
出所: Qualcomm ワイヤレスリーチ・プログラム<br />
c) スリランカのHSDPAプロジェクト――スリランカの農村地域にインターネットセンターを作り、<br />
起業家はそのオーナー'フランチャイズ(になる。各オーナーは自身の工夫を凝らしたサービスで<br />
利用率を高め尐額の利用料を受け取る仕組み。クアルコムが設備投資を回収出来ているか'い<br />
つできるか(は不明。<br />
分<br />
類<br />
起<br />
業<br />
家 精<br />
神<br />
国<br />
ス リランカ<br />
図表 12 ワイヤレス・リーチ事例'スリランカ(<br />
プロジェクト名 パートナー 目的・内容<br />
HSDPA<br />
プロジェクト<br />
'2007 年~(<br />
* Dialog Telekom 社<br />
* National Development<br />
Bank<br />
'スリランカ国立開発銀<br />
行(<br />
* Synergy Strategies<br />
Group 社<br />
* United States Agency<br />
for International<br />
Development<br />
'米国国際開発庁(<br />
出所: Qualcomm ワイヤレスリーチ・プログラム<br />
� スリランカの農村地域に Dialog Telekom 社の HSDPA ネットワー<br />
クを使用した 「Easy Seva インターネットセンター」を 25 カ所開設し<br />
た。Easy Seva センター設立の第一の目的は、地元の起業家が<br />
Easy Seva フランチャイズに加盟'投資(する機会を提供することで<br />
ある。Easy Seva インターネットセンターには Wireless Reach とそ<br />
のパートナーから一括購入した機器、ソフトウェア、コンテンツ、サ<br />
ービスなどの標準パッケージが用意されており、新規にワイヤレス<br />
事業に参入する際の障壁を低くし、立ち上げ費用を最小限にしてい<br />
る。<br />
� 第二の目的は、通信手段のない地域社会に 3G HSDPA インター<br />
ネット接続を備えたコンピュータセンターを設立すること。農村の住<br />
民は、オンライントレーニングによる新たなスキルの習得、求人情<br />
報の検索、マイクロファイナンスやその他の銀行サービスの利用、<br />
海外の家族や親族との格安な通話などの便益を受けられる。<br />
95
成功事例<br />
スリランカ Wennappua 地方の Chaminda 氏は、Easy Seva のオーナーとなり、その後先進的なサ<br />
ービスを顧客に提供して成功している。2007 年 8 月の開設以来、施設利用率は約 50%。開業時間<br />
の同じ他の施設が 15%~20%であることを考えると非常に高い。彼と彼のスタッフによる経営姿勢、<br />
コミュニティの場での PR 資料、高性能な HSPDA などが評価されているようだ。調査員が訪問した<br />
際、老人が子供たちから届いた e-mail の開き方やデジカメで撮った写真の送信の仕方などを教<br />
わっているところだった。スタッフの教え方は熱心であり、受けた訓練の効果を示していた。<br />
Chaminda 氏は「HSDPA のスピードが非常に早く、顧客は音楽のダウンロード、ビデオ会議、<br />
e-mail、ネットの閲覧などを自由にできる」という。今後はコンピュータをアップグレードし、他のサ<br />
ービスも付加したいと言う。<br />
図表 13 スリランカのワイヤレスリーチ「Easy Seva project」のビジネスオーナー、<br />
Chaminda 氏と息子<br />
出所: Qualcomm ワイヤレスリーチ・プログラム<br />
d) ケニアの医療情報整備プロジェクト'詳細は'2(-②(――低所得層向けビジネス'BOP(と<br />
して成立する可能性がある。現在のところ HIV/AIDS 対策として人道的見地から通信機器の提供<br />
が行われている。しかし医療機関や政府機関が対象であるため、今後機器の買い替えやアップグ<br />
レードが定期的に発生する。また抗レトロウィルス薬メーカーにとっても利益があるため持続性が<br />
高い。民間医療機関や一般市民の間に遠隔医療・通信技術を使ったビジネスが生まれる可能性<br />
もある。<br />
'2(事例に見るBOPビジネス推進方法<br />
① インドにおけるBOP層へのサービス提供事業<br />
クアルコムはインドのプロジェクトでは収益性は最優先せず、ワイヤレス通信を利用する手段を<br />
持たない漁師、農民、企業等が抱える通信のニーズを満たすことに重点を置いている。このプロ<br />
ジェクトでは、地方の漁師がリアルタイムで市況や気象に関する情報にアクセスできるようにした<br />
り、また地方の農民が日々の物価情報にアクセスできるようにしたりすることに可能性を見出した。<br />
96
これにより、作物をいつ市場に出荷すべきかを知ることができる。また農民や企業家は、BREW で<br />
接続された村々のネットワークを通じて、商品やサービスを紹介したり、検索したりすることができ<br />
る。<br />
インドにおけるワイヤレス・リーチ活動はタタ・コンサルタンシー・サービシズ、NASSCOM財団<br />
などの現地パートナーとの一連の合弁事業であり、標準的なハードウェアおよび周辺機器、インド<br />
におけるワイヤレス・リーチ・プロジェクトに特有のソフトウェアアプリケーション'Fisher Friend、<br />
Mobile Classifieds など(を組み合わせたものである。プロジェクト資金はクアルコムが提供し、クア<br />
ルコム・インドがプロジェクトを管理しているが、基本的には管理のみで新製品開発はほとんど行<br />
われていない。クアルコムの自社機器に関しては、知的財産権はクアルコムにある。<br />
アプリケーションとプログラミングはこのプロジェクト独自のものである。タタ・コンサルタンシー・<br />
サービシズが農民の収穫高向上を支援するための携帯通信アプリケーションを設計し、ユナイテ<br />
ッド・ビレッジが vBay'BREW 技術を利用した地方の農家向け携帯用オークションサイト(を開発し<br />
て、サポートを提供している。携帯電話と CDMA ベースの無線インターネット接続機器などのハー<br />
ドウェアはこのために作られたものではなく、一般にも販売されているため、価格もクアルコム側<br />
が設定したものではない。<br />
図表 14 インドにおける携帯電話を活用した情報提供<br />
出所:2008 Qualcomm Social Responsibility Report (クアルコム)<br />
図表 15 インドにおける携帯電話を活用した情報提供プロジェクト<br />
ユナイテッド・ビレッジ<br />
事前調査の実施、製品開発、サポート提供<br />
NASSCOM ISAP<br />
インターネット無線接続提供 地方の漁師・農民・企業経営者 各種訓練を提供<br />
タタ・コンサルタンシーズ<br />
携帯通信アプリケーションを開発設計<br />
リアルタイムで市場や気象に関する情報受<br />
信、日々の穀物相場情報受信、自分の品<br />
物をネットに載せたり他の製品を検索可能<br />
クアルコム<br />
BREW技術・無線インターネット接続の提供<br />
97<br />
携帯電話と無線インターネット<br />
接続機器は一般製品
成功事例<br />
・Puducherry 地区の漁師 Devandant 氏は一日 Rs 200-300 (約 US $3~6) だった収入が Fisher<br />
Friend によって Rs 500-800 (約 US $10~16) に増えたと言う。「このシステムで風向きや魚群の<br />
位置、波の高さなどを知ると、私はそれを村のみんなに伝えている。収穫が増えて全員ハッピ<br />
ーだ」。<br />
・同じく Puducherry 地区 の Ramalingam 氏はこの道 30 年のベテラン漁師。例えば船が破損した<br />
ような場合でも Fisher Friend で連絡し仲間に曳航してもらったり、皆に波の高さを知らせ危険な<br />
場合は漁に出ないように伝えている。「安心感がある」という。<br />
・Ramnijam 氏は 15 才の時から漁に出て、既に 4 人の子供がいる経験者だが、Fisher Friend を使<br />
う前は燃料も時間も無駄にしていたという。「今はこの機器が伝える場所に行って、網を張り、魚<br />
を取るだけだ」。<br />
出所:クアルコム<br />
② ケニアにおけるサービス提供事業<br />
クアルコムは、ケニアで抗レトロウィルス薬'ARV(をより効率的に供給するため、最新式 3G ワ<br />
イヤレス・イベント・テクノロジーを公共医療機関に提供する方法を考案した。 HIV/AIDS は、ケニ<br />
アが抱える医療問題の中で最も対策が急がれる問題の一つである。抗レトロウィルス薬による治<br />
療'ART(の提供は、HIV/AIDS に関係する罹患率と死亡率の抑制を目的とする政策の最優先課<br />
題である。クアルコムは、現地政府の政策をサポートするプロジェクトを優先していることから、こ<br />
のプロジェクトに着手した。<br />
ケニアのプロジェクトでは、ワイヤレス・リーチ・イニシアチブにより、ケニア全土の抗レトロウィル<br />
ス薬を管理する際、これまで非効率的であった手作業で記録を行う必要がなくなった。ケニアに提<br />
供した製品'コンピュータおよび周辺機器(には、大幅な変更は加えてられていない。ソフトウェア<br />
'Daily Activity Register software (DAR)=日常医療業務登録ソフト(は著名な研究機関であるRTIイ<br />
ンターナショナル'本部:米ノースカロライナ州リサーチ・トライアングル・パーク(が設計した。RTIの<br />
クライアントにはUSAID、米保健社会福祉省'DHHS(、航空宇宙局'NASA(などが名前を連ねて<br />
いる。<br />
98
ロジスティクス管理<br />
部門(LMU) KEMSA<br />
DAR ソフトウェア<br />
医療センター<br />
ロジスティクス管理<br />
部門(LMU)<br />
KEMSA<br />
標準化された<br />
レポート<br />
DAR ソフトウェア<br />
医療センター<br />
Center<br />
出所: rtidemo.org<br />
図表 16 ケニアにおけるブロードバンドを活用した医療情報整備<br />
ブロードバンド<br />
ブロードバンド 3G CDMA EV-DO Rev<br />
ブロードバンド<br />
ブロードバンド 3G CDMA EV-DO Rev<br />
医療センターは、ワイヤレスコネクティビティの確立に必要なコンピュータと周辺機器を受領する。<br />
コンピュータを CDMA2000'Qualcomm 3G EV-DO Rev(をベースとするテレコム・ケニアのオレン<br />
ジ・ブロードバンド・ネットワークに接続すれば、アップグレードすることにより、ケニア医薬品供給<br />
公社'KEMSA(へのオンラインレポーティングが容易になり、医療センター、地域、ケニア地方医<br />
療局'PMO(の間の調整が円滑化される。<br />
Broadb<br />
and 3G<br />
CDMA<br />
EV-DO<br />
Rev<br />
地方医療局<br />
地域医療局<br />
地方医療局<br />
標準化された<br />
レポート<br />
地方医療局<br />
99<br />
標準化された<br />
レポート<br />
1) 医療センターに日常医療業務登<br />
録ソフト'DAR(を設定。<br />
2) 患者情報がブロードバンドを通<br />
じて地域・地方医療局に伝達される<br />
3) 情報には投薬された薬名、患者<br />
の基本情報、薬の在庫状況など<br />
が含まれる<br />
4) 同様の情報が関係する医療機<br />
関全てに行き渡る。以降患者の治<br />
療状況は該当機関がアップデート<br />
し、定期的に全者で共有<br />
5) ケ ニ ア 医 薬 品 供 給 公 社<br />
'KEMSA(は情報を基に抗レトロウ<br />
ィルス薬の在庫・供給を管理
図表 17 ケニア医療センターの自動相互プログラムのデモンストレーション:医療情報をデジタル<br />
で処理し送信することで、患者に届ける重要な薬を早く確実に安価に届ける<br />
出所:クアルコム<br />
DAR ソフトウェアの主な機能、表示情報<br />
� 「在庫なし」の自動表示<br />
� 薬の受領数と薬の有効期限<br />
図表 18 DAR ソフトウェアの機能と共有情報の例<br />
� 患者情報: 療法、次の予約日、使用した薬の数<br />
� 在庫数、療法'複数(、患者リスト、予約時に現れなかった患者リスト<br />
PMOおよびRTIインターナショナルでのカスタマイズは、ケニア全土の抗レトロウィルス薬の管<br />
理を目的とした手作業による記録システムをもとにRTIが設計したオープンソース・ソフトウェアを<br />
利用して行われた。医療センターで使用するために新システムを修正する。また PC スキルと新し<br />
いソフトウェアを ART 現場の医療スタッフに指導するトレーナーを対象として、キャパシティビルデ<br />
ィングを提供している。<br />
100
図表 19 ケニアにおけるブロードバンドを活用した医療情報整備プロジェクト<br />
③ 公的機関・NGOなどとの連携<br />
クアルコム・インドは、情報通信技術を利用して、恵まれない人々に力を与え、生活を変革する<br />
ために設立された Nasscom 財団'http://www.nasscomfoundation.org/index.php(と連携している。<br />
Nasscom 財団は、インド・ソフトウェア・サービス協会'NASSCOM(傘下の非営利団体であるた<br />
め、インドの IT 普及状況を非常によく理解している。Nasscom 財団がプログラム開発に関するイン<br />
ドのNGOパートナーであるのに対し、トレーニングに関してはクアルコムはインド農業ビジネス専<br />
門家協会'Indian Society of Agribusiness Professionals('ISAP(と協力している。<br />
もう一つのパートナーは、タタ・コンサルタンシー・サービシズ'TCS(である。タタ・グループの一<br />
角をなすTCSは、ユニークなグローバル・ネットワーク・デリバリー・モデルを通じて、コンサルテ<br />
ィングを主体とし、IT と IT をベースとしたサービスの総合的ポートフォリオを提供している。グロー<br />
バル・ネットワーク・デリバリー・モデルは、ソフトウェア開発の粋を極めるベンチマークとして認め<br />
られている。<br />
RTIインターナショナル 協力 テレコム・ケニア、アクセステルAxesstel<br />
オープンソース・ソフトウェアはRTIが設計 オンラインネットワーク提供<br />
ケニア通信委員会<br />
Public health centers<br />
患者への分配<br />
'3(BOPビジネス推進に係る社内体制<br />
協力 協力<br />
ワイヤレス・リーチの推進方法には次のような特徴がある。<br />
第一にクアルコムはコミュニティにソリューションを押し付けないことである。コミュニティのパート<br />
ナーは、ワイヤレス・リーチ・プロジェクトの資金提供を求めてクアルコムに申請を行う。その結果、<br />
このイニシアチブはコミュニティが感じるニーズを常に満たすことができる。BOPイニシアチブを成<br />
功に導く重要なポイントの一つは、予めリサーチを行い、現地のニーズを把握することである。ワ<br />
イヤレス・リーチでは、クアルコムが提案を審査する前にこのリサーチは行われている。適切なプ<br />
ロジェクトのための独自の判断基準に照らし、提案の是非の判断はクアルコムに任される。<br />
協力<br />
101<br />
ケアルコム<br />
公的医療センターへ先進的3G無線技術を提供<br />
先進的3G無線技術を提供によりARVsの分配に貢献<br />
Kenya Medical Supplies Agency (KEMSA)<br />
各保健所・医療機関へのARVs分配調整<br />
ナイロビ地方医療局<br />
ARVsの入手、患者への分配
すなわち、情報通信'ICT(技術に対するニーズとコミュニティの目標、ワイヤレスの受信可能地<br />
域、電話回線の欠如、現地NGOや事業者との関係、新しい画期的なワイヤレス・ソリューションの<br />
モデルになるかどうか、政府の政策の優先順位に適っているかどうか、拡張可能で持続可能なプ<br />
ロジェクトかどうかなどの判断基準である。選定はトップダウンだが、このリサーチは、トップダウン<br />
ではなくボトムアップで行われている。決まり次第、クアルコムは直ちに民間部門のパートナー、<br />
非営利団体、政府機関などからなる現地チームの結集に動く。<br />
図表 20 ワイヤレスリーチのロゴ<br />
出所: クアルコム<br />
第二に、クアルコムにとって、今のところワイヤレス・リーチ・イニシアチブでの収益性は最優先<br />
事項ではないため、パートナーは資金を用意した上で交渉の席に着く必要がない。インドやケニア<br />
などワイヤレス・リーチの実施例では多くの場合、クアルコムがプログラムの資金を拠出し、現地<br />
の通信会社を使ってサービスを提供、民間企業を使ってプログラミングを処理し、現地の非営利<br />
団体を通じてトレーニングを実施している。<br />
今後BOPとして収益性を上げていくには、いくつか難しい問題に取り組まなければならない。1<br />
日 2 ドル以下で生活する人々が手を出せるような製品またはサービスをどのように作るのか。そ<br />
のような価格水準を満たすため、サプライチェーンとどのように交渉するか。需要と普及を牽引す<br />
る集団にどうやって売り込むか。追加資金を獲得するため、将来の資金提供者をどのように取り<br />
込むか、などである。<br />
第三にクアルコムのワイヤレス・リーチ・プロジェクトはそれぞれ独立しており、ソリューション、<br />
製品、利用者、パートナー等は、その地域・場所によって異なる。それをサンディエゴのワイヤレ<br />
ス・リーチ・オフィスで一元管理している。<br />
クアルコムのトップの経営陣がワイヤレス・リーチをサポートし、プロジェクトの発表・設立に参加<br />
している。新たなワイヤレス・リーチ・プログラムの提案は常時受け付けており、クアルコムが新た<br />
な機会の発見に注力する必要はなく、選定されたプログラムを必ず成功させることに専念できる。<br />
またクアルコムは、ワイヤレス・リーチ活動専任のチームを設けており、本社サンディエゴの政府<br />
担当副社長の指示を受けるワイヤレス・リーチの政府担当シニアマネージャーをインドに置く予定<br />
102
である。<br />
プロジェクトが一旦立ち上がり、動き出した後、現地パートナーがプロジェクト管理を引き継ぎ、<br />
トレーニングの提供、求人情報掲示板のようなデータベースのアップデートを行っている。クアルコ<br />
ムはニューデリーとムンバイ、およびハイデラバードには R&D 施設があり 100 人以上を雇用してい<br />
るが、ワイヤレス・リーチ専属の人員は置いていない。<br />
'4(公的機関、国際機関、NGO等との連携<br />
① CSR活動の位置づけ<br />
クアルコムは、同社が「故郷」と呼ぶコミュニティのパートナーとして重要な役割を担っていると<br />
考え、近隣の非営利団体とつながりを持つよう努めている。最終的に、クアルコムのビジネスは、<br />
コネクティビティ'接続性(が基盤だからである。クアルコムはまた、社員がプロフェッショナルとして、<br />
また市民として成長するための場所として、コミュニティの組織が重要であると考えている。クアル<br />
コムの最高経営責任者 Paul Jacobs 博士は言う。<br />
「技術革新で世界をリードするクアルコムは、常に全世界にポジティブなインパクトを与えようと<br />
努力している。当社が市場に送る製品、サービスは、あらゆる場所にいる人々が意思を伝達し、<br />
情報にアクセスし、学び、働き、遊ぶ、その方法を変革することによって、生活の質を高めることを<br />
目指している。それと同じくらい重要なのが、社員全員の努力に裏打ちされた、持続可能性と素晴<br />
しい企業市民であることに対する当社のコミットメントである」<br />
図表 21 クアルコムの共同創設者 Irwin Jacobs 博士'現 CEO, Paul Jacob 氏の父(<br />
'K-Nect プロジェクトについて「モバイル教育カンフェレンス」、<br />
ワシントン DC、2009 年 2 月 16-17 日(<br />
出所: Wireless Reach Quarterly Newsletter, May 2009 (クアルコム)<br />
企業の社会的責任に普遍的定義は存在しないが、一般に企業の社会的責任は、倫理的価値<br />
観をよりどころとし、法律に従い、人、コミュニティ、環境を尊重する透明なビジネス慣行を指す。す<br />
103
なわち、企業は収益を上げることだけでなく、人々と地球に与える影響全体に対して責任を負うの<br />
である。「人々」とは、社員、顧客、ビジネスパートナー、投資家、供給業者・ベンダー、政府、コミュ<br />
ニティといった企業のステークホルダーで構成される。ステークホルダーは、企業が事業活動を行<br />
うにあたり、さらに大きな環境的、社会的責任を担うことを期待している。ビジネスの世界で、CSR<br />
は「コーポレートシチズンシップ」とも呼ばれる。これは基本的に、ホストコミュニティにおいて企業<br />
が「良き隣人」でなければならないことを意味する。<br />
BOPプログラムにおいては、プロジェクトを通じて新製品の開発を推進し、流通戦略を考え、品<br />
質や効率性と高めるということに対しても、スタッフが時間をかける。ピラミッドの底辺においては、<br />
一貫性と創造性が非常に重要になってくる。<br />
米国の多国籍企業は、ほぼ必ずCSRイニシアチブを実施し、企業の多くは、さまざまなコミュニ<br />
ティと接触する。クアルコムのワイヤレス・リーチは、BOPとして持続的な収益を上げていく段階に<br />
は達していないが、このプログラムに接触したコミュニティにプラスの影響を及ぼしており、経営陣<br />
はしばしばこれをポジショニング・ステートメントで取り上げている。<br />
② パートナーの選定<br />
クアルコムは、認知度を高めるため、ワイヤレス・リーチ・イニシアチブを公表し、クアルコムが<br />
掲げるワイヤレス・リーチの目的に適合するプロジェクトが申請者から提案されるよう促している。<br />
クアルコム側にプロジェクトが提案されると、委員会がこの提案を検討し、資金拠出の基準を満た<br />
しているかどうかを判断する。その後、ワイヤレス・リーチ・チームがさまざまなステークホルダー<br />
'民間企業、非営利団体、NGO、大学および/または政府機関(を集め、クアルコムの最新技術<br />
と、現地コミュニティに利益をもたらすソリューションを活用したワイヤレスコネクティビティ拡張・向<br />
上プロジェクトを立案する。ステークホルダーは、プロジェクトによって、また国によって異なる。<br />
インドにおけるクアルコムのワイヤレス・リーチ活動の例をみると、2 つの民間企業との連携を<br />
通じて実施されている。一つはユナイテッド・ビレッジである。ユナイテッド・ビレッジは、米国マサチ<br />
ューセッツ州ケンブリッジに本部を置く営利団体で、2003 年にマサチューセッツ工科大学から独立<br />
した。製品とサービスの提供および配給によって地方の人々に寄与することを目的として、インド、<br />
カンボジア、ルワンダ、パラグアイでワイヤレス技術をベースとしたサービスを提供している。イン<br />
ドには 2005 年に拠点を設立、インドで初めてのモバイルをベースとした地方のサプライチェーンを<br />
スタートさせた。もう一つは、前述したタタである。<br />
ケニアにおけるワイヤレス・リーチ・イニシアチブは、複数の民間プレイヤーとの共同プログラム<br />
である。テレコム・ケニア、アクセステル、RTIインターナショナルが民間パートナーとなっている。<br />
104
③ USAID<br />
米国国際開発庁'USAID(も様々な形でクアルコムの Wireless Reach プログラムに協力してい<br />
る。スリランカでは 2007 年 8 月、クアルコム、Dialog Telekom、National Development Bank らと共<br />
同で最初の Wireless Reach プロジェクトを立ち上げ、25 ヶ所のインターネットセンターを開設した。<br />
グアテマラでは同国教育省と協力し、「未来の学校」プロジェクトに協力。400 を超える学校に 3G<br />
CDMA 技術を行き渡らせることに尽力した。ベトナムでも 2006 年 3 月から、コミュニティ向けの情<br />
報技術トレーニング・オンライン・プログラム「TOPIC64」プロジェクトの立ち上げに協力した。<br />
USAIDはその戦略の柱を 7 つ定めている。①平和と安全の確保、②法治と民主化、③人材へ<br />
の投資、④経済成長と繁栄、⑤人道的支援の提供、⑥国際的相互理解の促進、⑦領事・管理業<br />
務の強化--である'Strategic Plan FY 2007-2012, USDA(。企業のCSRやBOPへの支援は主<br />
に③人材への投資、④経済成長と繁栄、⑤人道的支援の提供に関わるが、長期的・間接的には<br />
他の戦略にも合致する。このようにCSRやBOPはUSAIDの活動との親和性が高く、今後も同種<br />
のプロジェクトは増えるだろう。また下記予算推移にあるように、米国の海外活動予算は景気悪化<br />
の影響下にありながら、2008 年から 2010 年にかけ 26%増加する見込み。中でもUSAIDの予算は<br />
この間に 83%増と大きく伸びると見られる。<br />
図表 22 米国海外活動'Foreign Operation(予算の推移'項目は主なもの(<br />
国際問題対応<br />
2008年度<br />
'当初*補正(<br />
42,914,005<br />
1) 海外活動 27,769,768<br />
USAID 930,136<br />
二国間経済援助 20,300,842<br />
独立機関 1,925,774<br />
財務省 50,290<br />
国際安全保障支援 5,065,064<br />
多国間経済支援 1,587,243<br />
国際金融機関 1,277,289<br />
2) 国務省 12,501,265<br />
国際問題対応管理費 8,991,159<br />
国際機関 3,473,654<br />
3) 放送委員会 684,004<br />
4) その他プログラム 94,804<br />
5) 農務省 2,160,164<br />
6) 前年予算との調整 (296,000)<br />
2009年度<br />
'当初*補正(<br />
49,497,528<br />
31,966,159<br />
1,249,459<br />
23,463,800<br />
1,270,000<br />
85,000<br />
5,524,100<br />
1,845,500<br />
1,493,000<br />
出所 http://www.usaid.gov/policy/budget/cbj2010/2010_CBJ_Summary_Tables.pdf:<br />
105<br />
14,731,063<br />
10,468,513<br />
4,108,800<br />
715,483<br />
107,923<br />
2,020,900<br />
(44,000)<br />
2010年度要求 2008/2010伸び率<br />
53,872,901<br />
34,847,665<br />
1,698,300<br />
24,871,347<br />
1,851,200<br />
142,070<br />
5,681,073<br />
2,697,855<br />
2,341,305<br />
16,256,249<br />
12,069,539<br />
4,057,000<br />
745,450<br />
134,037<br />
1,889,500<br />
-<br />
25.5%<br />
25.5%<br />
82.6%<br />
22.5%<br />
-3.9%<br />
182.5%<br />
12.2%<br />
70.0%<br />
83.3%<br />
30.0%<br />
34.2%<br />
16.8%<br />
9.0%<br />
41.4%<br />
-12.5%
図表 23 ベトナムの TOPIC64 施設を訪れる Michael Michalak 駐越米国大使<br />
出所 Qualcomm ワイヤレスリーチ・プログラム<br />
図表 24 グアテマラでの Wireless Reach プログラムの紹介'USAIDニュースレター(<br />
④ 国連ミレニアム目標の達成<br />
出所 USAID<br />
インド政府は、国連ミレニアム目標とUNDPの目標の両方をサポートしている。インド政府は、ミ<br />
レニアム開発目標の No.1'2015 年までに極度の貧困と飢餓を撲滅(の達成につながる、雇用、収<br />
入の創出、保護施設、栄養、食糧安全保障といった問題への取組を通じ、地方と都市部の貧困問<br />
題を撲滅することに関係した国家計画と関連活動に重点を置いている。インドにおけるワイヤレ<br />
ス・リーチ・プロジェクトは、インド政府の開発目標に密接に対応するものと考えられる。<br />
ケニアのプロジェクトは、国連ミレニアム開発目標の No.6「HIV/AIDS、マラリアその他の疾病<br />
の蔓延防止」のターゲット 2「2010 年までに、必要とするすべての人々の HIV/AIDS の治療への普<br />
遍的アクセスを実現する」に直接対応している。<br />
106
********************************************************************************<br />
クアルコム幹部へのインタビューより<br />
企業のBOPビジネス開始を後押しするにあたり、政府、資金援助機関、国連、NGO、財団が果た<br />
す役割は何ですか。<br />
→インドにおいて、ワイヤレス・リーチ活動は、国連ミレニアム開発目標とUNDPが同国に関して<br />
掲げる目標と非常によく噛み合っている。国際機関が果たしうる最大の役割は、測定可能な影響<br />
を持ち、スケジュールが明確に示された開発目標を策定すること、これらの目標を達成するため<br />
官民による新たなパートナーチップ構築を促すことであると考えられる。開発を主導することに関<br />
して、インドのNGOはインド政府より有能だと聞いている。従って、現地政府に与えられた役割は、<br />
進展の邪魔をしないことだと思われる。<br />
御社のプロジェクトは、現地政府の開発目標に対応していますか。対応している場合、具体的な<br />
目標は何ですか'例:2015 年までに地方の住民の 50%に飲用水を供給するなど(。<br />
→対応している。ナイロビ地方医療局が、クアルコムに支援を要請した。HIV/AIDS の発病率を低<br />
減し、患者が治療を受けられるようにすることがケニア政府の重要な目標である。<br />
NGOとの協力関係をどのようにしてスタートさせましたか。貴社製品の消費者として接触したので<br />
すか。それとも流通チャンネルまたはプロモーターとして接触したのですか。<br />
→ケニアでワイヤレス・リーチ・プログラムを成功させるため、クアルコムはナイロビ地方医療局<br />
'政府機関(、ケニア通信委員会、テレコム・ケニア'民間企業(、アクセステル'民間企業(、RTIイ<br />
ンターナショナル'世界有数の独立系非営利研究開発機関(とパートナーを組んだ。自らが設計し<br />
たオープンソース・ソフトウェアを使用し、'地方医療局とともに(プロジェクトを実施、管理すること<br />
がRTIインターナショナルの役割である。<br />
NGOをビジネスパートナーに引き入れることの問題点とポイントは何ですか。<br />
→RTIインターナショナルのプロジェクトを見ると、米国政府の優先分野や政策、その他様々なビ<br />
ジネス、産業界、学術界による取組が反映されていることがわかる。加えてクアルコムはRTIの活<br />
動を資金的に支援しており、RTIがクアルコムのパートナーに加わればむしろ米政府のサポートと<br />
後ろ盾を得られるなど、クアルコムには便益が多い<br />
107
出所:RTI<br />
図表 25 RTIの契約先と助成金一覧<br />
現地政府からの助成やODAによる支援を期待しましたか。<br />
→ナイロビ地方医療局からの助成はなかった。クアルコムは助成を期待しなかった。<br />
現地政府やODAによる助成または支援を獲得するにあたって問題はありましたか。また、助成ま<br />
たは支援を獲得する際のポイントは何ですか。<br />
→現地政府'ナイロビ地方医療局(がクアルコムに支援を求めた。政府は、この活動を強く支援し<br />
ているだけでなく、活動の主導者でもある。しかし、それは、クアルコムに対して何らかの対価また<br />
はインセンティブが与えられることを必ずしも意味しない。ケニア通信委員会も、官民パートナーシ<br />
ップへの参加と、ケニアの恵まれない人々への情報通信技術'ICT(の提供の一環として、このプ<br />
ロジェクトをサポートしている。<br />
BOPプロジェクト実施の過程で国際機関に何を期待しましたか。<br />
→国際機関は関与していない。<br />
企業のBOPビジネス開始を後押しするにあたり、政府、資金援助機関、国連、NGO、財団が果た<br />
す役割は何ですか。<br />
→クアルコムは、ワイヤレス・リーチ活動をスタートさせるにあたり、何らの後押しも必要としなかっ<br />
た。独自に活動を開始したのである。ナイロビ地方医療局は、資金提供を求めるために提案をま<br />
とめただけである。<br />
108
Ⅱ.政府支援機関調査<br />
1.オランダ<br />
2.ドイツ<br />
3.フランス<br />
4.EU<br />
109
(1)BOPビジネスに関わる政府の役割<br />
① 政府の支援方針・体制<br />
1.オランダ<br />
オランダの政府開発援助政策は、外務省が援助の主管官庁として担い、全ODA予算の8割以<br />
上を掌握している。これに大蔵省を加えると9割。残りの1割を開発協力関連9省が分け合ってい<br />
る。オランダのODA予算は 1997 年 1 以来、一貫して対GNP比 0.8%と国連のODA目標を上回る<br />
水準で推移、2009 年のODA予算は約 50 億ユーロとなっている。<br />
オランダの政府開発援助政策の中で、BOPプロジェクトは特に重視されておらず、BOPプロジ<br />
ェクトのみを対象とした特別の手段はない。しかし、オランダの開発援助政策の基本的な政策目<br />
標の一つは、発展途上国のビジネス環境を整備することにある。オランダ政府ならびにNGOはい<br />
ずれも、民間セクターの協力があって初めて政府開発援助が持続可能であると考えているからで<br />
ある。したがって、オランダ企業のみならず、オランダ国籍以外の企業に支援先の途上国でBOP<br />
市場開拓を含んだビジネスを促すようなスキームが各種、用意されている。<br />
BOPプロジェクトに対するオランダ企業の関心は、多国籍企業の場合は主に社会的責任(CS<br />
R)を果たす必要性と企業内の若手中間管理者の熱意である。一方、中小企業のBOPプロジェク<br />
トに対する関心は、多くの場合、潜在的市場の開拓にあると指摘されている。<br />
図表 1 2009 年のODA予算(推定値)<br />
2009年ODA予算最大額 5,250.1<br />
出所:オランダ議会<br />
一般的に、オランダのODA資金は国連などの国際機関、発展途上国の政府、盟友ドナー国、<br />
国際およびオランダのNGO、政府や市民組織、企業、研究機関など異なるセクター間の協力など、<br />
5 種類の窓口を通じて供給される 2 。<br />
1 PEER REVIEW OF THE NETHERLANDS - OECD 2006, page 27<br />
2 www.minbuza.nl/en/Key_Topics/Development_Cooperation/Partners_in_Development<br />
110<br />
(単位:100万ユーロ)<br />
GNP推定値 632,840.0<br />
GNP比0.8%の固定予算 5,062.7<br />
ODAローン推定返済額 80.2<br />
ODA推定収入額 42.2<br />
再生可能エネルギー 50<br />
2008年予算残額 15
国際機関<br />
(UN、EUなど)<br />
予算の約25%<br />
② 支援機関・支援スキーム<br />
図表 2 オランダのODA –実施体制<br />
オランダ政府が援助するビジネス環境改善に貢献するODA事業の実施プログラムは以下の7<br />
つである。<br />
� PPP:外務省が資金を拠出し管理する官民パートナーシップ(PPP)である民間セクター開<br />
発プログラム<br />
� PSI:民間セクター投資プログラム。外務省が資金を拠出しオランダ外国貿易庁(EVD)が<br />
管理する発展途上国の民間セクター投資のための助成金。<br />
� ORIO:外務省が資金を拠出しEVDが管理するインフラ開発ファシリティ。<br />
� FOM:オランダ開発金融会社(FMO)が管理する発展途上国の企業を対象とする新興市<br />
場ファンド(FOM)よる金融支援(融資)。<br />
� 国別プログラム:外務省が資金を拠出しがEVD管理するウルズガン(アフガニスタン)、ベ<br />
トナム、インドネシアのファシリティ。<br />
� マッチメーキング・ファシリティ:外務省が資金を拠出しEVDが管理する発展途上国向けマ<br />
ッチメーキング。<br />
オランダ政府のODA総予算はGDPの0.8%<br />
2009年のODA予算:約50億ユーロ<br />
外務省によって分配<br />
発展途上国の政府 盟友ドナー国<br />
(オーストリア、カ<br />
ナダなどMOPAN<br />
参加国)<br />
� 成長のためのパッケージ:外務省が資金を拠出しEVDが管理する。<br />
ODAをBOPプロジェクトに適用する場合、上記プログラムのうち、PPP、PSI助成金、ORIO助<br />
成金、FOM、および主にオランダのODA供与を受ける開発NGOによって提供される手段(例:NCD<br />
O BiD(オランダ国際協力・持続可能な開発委員会によるビジネス開発)プロジェクト、ICCO(プロテス<br />
タント系教会間開発協力組織))の5つの手段が利用できる。<br />
111<br />
NGO<br />
(プロテスタント系<br />
教会間開発協力組織<br />
(ICCO)、<br />
Oxfam Novibなど)<br />
予算の約25%<br />
パートナーシップ<br />
(各国政府、NGO、<br />
ビジネスセクター、リ<br />
サーチセクター)<br />
注)MOPAN:Multilateral Organizations Performance Assessment Network、多国籍間パフォーマンス評価ネットワーク。二国間援助を<br />
行う諸国からなるグループによって開発されたもので、主な目標は協力して各国レベルで多国籍機関の機能を検討すること。参加国はオース<br />
トリア、カナダ、デンマーク、オランダ、ノルウェー、スウェーデン、スイス、英国、フィンランド
NCDO<br />
(自治行政権を<br />
有する機関)<br />
PPP<br />
主管官庁:<br />
外務省<br />
図表 3 ビジネス環境改善に貢献する ODA 事業実施プログラム<br />
FOM<br />
主管官庁:<br />
FMO<br />
1)PPP民間セクター開発プログラム(外務省)<br />
PPP民間セクター開発プログラムの主要な目的は、オランダ企業及び現地企業の協力のもとでミレ<br />
ニアム開発目標(MDGs)の達成に貢献することであり、オランダ外務省は当プログラムを通じて発展<br />
途上国の事業活動に対して広範囲にわたり財政を支援している。2009 年 10 月時点では 73 件のプロ<br />
ジェクトが実施中で、合計 185 社(発展途上国の企業を含む)が関与している。PPPプログラムへの申<br />
請は随時行われ、2004 年以降、7 億 5,000 万ユーロが投入されている。<br />
外務省は各プロジェクトへのグラント拠出にあたっては、BOPプロジェクトを特に優先することはない。<br />
PPPプロジェクトは様々な経緯で策定され、個別に判断されるため、実施状況は各プロジェクトによっ<br />
て異なる。民間企業のコア・コンピタンスを活用することにより、最も効率的に解決され得る発展途上国<br />
の問題を特定することから始められる。従って各プロジェクトは単なる慈善事業ではなく、企業にとって<br />
経済的な重要性を持つ必要がある。外務省は、企業のリスクが通常よりも高いプロジェクトを支援して<br />
いるため、資金調達の配分は 60%が企業、40%が外務省という比率が目標であるが、実際にはそれ<br />
ぞれ 50%となるケースが多い。<br />
PPP民間セクター開発プログラムは、オランダ外務省がリストアップした 40 カ国 3 のプロジェクトを対<br />
象としている。しかし、この 40 カ国以外の国についても、MDGsの視点から取り組むべきプログラムが<br />
あれば例外として対応する。<br />
外務省<br />
ウルズガン、インドネ<br />
シア、ベトナム<br />
主管官庁:EVD<br />
これまでのPPPプログラムの主な事例は下記の通り。<br />
� モザンビークの飲料水プロジェクト:外務省が資材、輸送、工作機械用の資金として 100 万ユーロ<br />
を拠出。専門知識を共有するため、Vitens(オランダの飲料水会社)が FIPAG(モザンビークの飲<br />
料水用インフラ整備会社)にスタッフを提供。<br />
マッチメーキング<br />
主管官庁:EVD<br />
� アフリカに安全な光を「皆に手頃な価格の照明器具を」(Green Light for Africa ‘Affordable<br />
Lighting For All (ALFA))プロジェクト:外務省が 300 万ユーロを拠出。Philips Lighting(300 万ユ<br />
3 対象国:アフガニスタン、アルバニア、アルメニア、バングラデシュ、ベナン、ボリビア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルキナファソ、<br />
ブルンジ、カーボベルデ、コロンビア、コンゴ、エジプト、エリトリア、エチオピア、グルジア、ガーナ、グアテマラ、インドネシア、ケ<br />
ニア、コソボ、マケドニア、マリ、モルドバ、モンゴル、モザンビーク、ニカラグア、パキスタン、パレスナ自治区、ルワンダ、セネガ<br />
ル、南アフリカ、スリランカ、スーダン、スリナム、タンザニア、ウガンダ、ベトナム、イエメン、ザンビア<br />
112<br />
ORIO<br />
主管官庁:EVD<br />
PSI<br />
経済省<br />
主管官庁:EVD<br />
Package4Growth<br />
主管官庁:EVD
ーロ)、現地のNGOが参加<br />
� TCX:外貨建てローンを利用しなければならない場合、現地通貨の為替リスクを抱えることに<br />
なる。事業が円滑に進むようにこの為替リスクを補うのがTCX。外務省が 5,000 万ユーロを出<br />
資。<br />
� 公正取引スキーム:例えば Max Havelaar Fair Trade Coffee の場合、現地コーヒー農園経営<br />
者、Cargill やオランダのスーパーマーケット・チェーンなどの企業を含む流通チャンネルの当<br />
事者すべてに対し、話し合いなどを通じて公正な取引に参加させるべく働きかけを行うもの。<br />
PPPプログラムを成功させるための要因としては、現地政府の関与、参加企業のコア・コンピタ<br />
ンスとの適合性がカギとなる。今後の課題としてあげられるのは、市場の混乱や国家支援を回避<br />
しつつ、いかにプロジェクトの資金調達の段取りをつけるか、という点である。<br />
2)民間セクター投資プログラム(PSI)助成金(外国貿易庁)<br />
PSIの目的は、アフリカ、アジア、ラテンアメリカ、中東欧の新興市場への投資を奨励することに<br />
ある。このプログラムでは発展途上国の持続可能な経済開発の原動力として、民間セクターへの<br />
投資を奨励している。PSIプログラムでは 70%の成功率を目標としており、対象はハイリスク市場<br />
におけるハイリスクプロジェクト、そのうちの 40~50%が農業やアグリビジネスである。プロジェクト<br />
の申請がオランダ企業によって行われることが多いため、PSIの申請および審査はオランダのハ<br />
ーグに集中している。<br />
PSIが成功するための重要な要因は、申請者自身がデューデリジェンスの実行を含むプロジェ<br />
クト全体の責任を負うことである。このプログラムに申請されるBOPプロジェクトでは、新興市場の<br />
迅速な経済成長と裕福な中産階級の拡大を背景に、現地市場向けの生産に関心を持つオランダ<br />
企業による案件が増えている。<br />
このプログラムのもとで行われる案件の一般的なモデルは、発展途上国で先進国向けの輸出<br />
向け商品を開発するというものである。よく知られた事例として、オランダの花き業者がエチオピア<br />
で英国向けに切り花を生産する例が挙げられる。輸出市場からBOP市場への展開は企業にとっ<br />
てメリットがある。現地市場向けの生産は輸出市場の変動や為替リスクの影響をそれほど受けな<br />
いため、リスク低減の視点からもBOPプロジェクトは関心が高い。しかし、PSIプログラムの主な<br />
目標は雇用創出と経済成長であるため、BOPプロジェクトの申請に対して特別な優遇措置は講じ<br />
ていない。現時点でもモルダビアなどの国々で進行中の農業プロジェクトでは、現地市場があまり<br />
にも小さく、対ロシア輸出が必要とされている。さらに、オランダでは農産物の大半が輸出向けで<br />
あるため、輸出モデルに馴染みがあるという背景もある。<br />
PSIプログラムは行政的には外務省が管轄し、資金をすべて拠出しているが、管理は経済省に<br />
所属するオランダ外国貿易庁(EVD)が行う。プロジェクト適格国の選定は外務省が行うが、経済<br />
113
省もある程度の影響力を持つ。一般的に、経済省はオランダ企業がPSI助成金スキームから利<br />
益を得られるように、ベトナムやブラジルなど発展の度合いの高い国々からの早まった撤退は行<br />
わないという強い意向を持っている。<br />
2009 年はPSIプログラムの第一次募集では 97 件の申請があり、49 件が承認された。一般的に、<br />
途上国向けのプロジェクトはタイド(ひも付き)であるのに対して、最貧国向けプロジェクトはアンタ<br />
イド(ひもなし)である。アンタイド案件に対する、オランダ国籍以外の企業からのプロジェクト申請<br />
は歓迎されている。しかし審査の重要な項目である会計規則や制度が国ごとで大きく異なること<br />
などが原因で、実際には外国企業からのプロジェクト申請の審査は難しい場合が多い。プロジェク<br />
トの大半は純粋に商業ベースであり、企業の動機は第一に利益追求である。CSRは動機として<br />
は二次的なものにすぎない。対象とするプロジェクトはアフリカ、アジア、ラテンアメリカ、中東欧の<br />
新興市場 4 における現地パートナーと協力して投資を実施するオランダの企業 5 であり、業種の制<br />
限はない。グラントは最大で投資額の 50%、プロジェクト総予算の上限が 150 万ユーロであるため、<br />
グラントの上限額は 75 万ユーロである。また、PSIグラントの対象となるためには、以下の要件を<br />
満たす必要がある。(非オランダ企業が特別措置対象国でのプロジェクトを申請する場合、以下の<br />
項目にある「オランダ企業」を「企業」に読み替えて対応する。)<br />
� オランダ企業およびプロジェクトが実施される国の現地パートナー。<br />
� PSI国での新規活動の立ち上げを目指し、長期的な協力を行う。<br />
� 申請者および現地パートナーは、健全な財務内容および当該セクターに関連する専門知識<br />
と経験を有する。<br />
� 申請者は商工会議所またはそれに相当する当局で商業登記を行っている企業でなければな<br />
らない。現地パートナーは PSI 国において正式な登記を行っている民間企業でなければなら<br />
ない。<br />
� 申請者は計画を実行するための財政手段を持っていない、もしくは銀行から事業計画のため<br />
の融資を受けることができない。<br />
� 提案は中長期的にみて商業的に実行可能であり、雇用、技術移転、生活・環境・女性の地位<br />
の向上という面でPSI国の経済にプラスの影響を及ぼす。<br />
� プロジェクト期間終了後も追加投資と生産拡大が見込める。<br />
� オランダ企業と現地パートナーの双方が貢献資金を自力で確保できる。<br />
4 PSI 適格国:アルバニア、アルメニア、バングラデシュ、ベナン、ボリビア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブラジル(北<br />
部および北東部のみ)、ブルキナファソ、カーボベルデ、コロンビア、エジプト、エチオピア、ガンビア、グルジア、<br />
ガーナ、グアテマラ、ホンジュラス、インドネシア、ケニア、コソボ、マケドニア、マダガスカル、マラウイ、マリ、モ<br />
ルドバ、モンゴル、モロッコ、モザンビーク、ナミビア、ネパール、ニカラグア、パキスタン、ペルー、フィリピン、ル<br />
ワンダ、セネガル、南アフリカ、スーダン、スリナム、タンザニア、タイ、ウガンダ、ベトナム、イエメン、ザンビア。<br />
ただしアフガニスタン、ブルンジ、パレスチナ自治区、シエラレオネ、南スーダンについては、「PSI プラス」として<br />
柔軟な条件を備えた個別プログラムが利用可能である。<br />
5 次の国々のプロジェクトに関しては、非オランダ企業も PSI グラントの応募資格がある:バングラデシュ、ベナン、<br />
ボリビア、 ブルキナファソ、カーボベルデ、エチオピア、ガンビア、ガーナ、ホンジュラス、マダガスカル、マラウイ、<br />
モザンビーク、ネパール、ニカラグア、ルワンダ、セネガル、南アフリカ、スーダン、タンザニア、ウガンダ、イエメ<br />
ン、ザンビア<br />
114
3)インフラ開発ファシリティ(ORIO)助成金(外国貿易庁)<br />
以前のORET(開発関連輸出取引)スキームに代わり、2009 年、新たにインフラ開発ファシリティ(O<br />
RIO: Facility for Infrastructure Development)スキームが導入された。ORIOはオランダの開発協力省<br />
の管轄の下、外務省が資金拠出し、発展途上国のインフラ工事に対してグラントを供与する。商業的<br />
には採算性がなく、国際入札を通して調達される財・サービスが対象で、内容としては公共工事の開発<br />
コストのほか、実行(建設・改修)、運営・保守管理コストが含まれる。プロジェクトの実施主体は受け手<br />
国側の中央政府である。対象セクターはプロジェクト実施国側のプライオリティーが高いセクターとなり、<br />
プライオリティーが低いセクターのプロジェクトの場合は当該国のオランダ大使館からの推薦状が必要<br />
となる。プロジェクトの費用総額は 200 万~6,000 万ユーロ。<br />
2009 年のORIO利用可能資金は 1 億 8,000 万ユーロで、このうち 7,000 万ユーロが 2009 年第 2 次<br />
募集で利用可能である。プロジェクトのプロポーザル作成に必要なコストの 50~100%、実施、運営、<br />
保守管理のコスト(金融コストおよび研修費用を含め)の 35%、50%もしくは 80%が交付金として支給され<br />
る。ORIOの評価基準は、①経済成長に対する貢献度、②民間セクターの発展に対する貢献度、③開<br />
発における貧困削減重視の度合い、④実行可能性および持続可能性、⑤プロジェクトが社会および環<br />
境に与える影響、⑥中小企業の参加、の以上6点。<br />
ORIOは 2009 年第 1 次提案募集における提案プロジェクトの評価を終え、90 件の提案のうち下記の<br />
9 件が選出された。グラント総額は 1 億ユーロ。<br />
� ボリビア:Santa Cruz の総合病院<br />
� ガンビア:地方都市における水の供給<br />
� ガーナ:ガーナにおける結核患者の発見の促進<br />
� ガーナ:厚生施設の建設<br />
� ガーナ:水の供給計画<br />
� ガーナ:Upper East 地域における水の供給<br />
� 南アフリカ:貧困地域における持続可能な水資源・衛生開発プログラム<br />
� タンザニア:診断・救急サービスの復旧プロジェクトの拡張<br />
� ベトナム:Ba Ria Vung Tau 省の農村地域における給水プラント建設プロジェクト<br />
115
図表 4 国別の利用可能予算<br />
4)オランダ金融開発公社(FMO)が管理する新興市場ファンド(FOM)<br />
オランダ金融開発公社(FMO)はオランダの半官半民の開発銀行で、オランダ政府 51%、オラ<br />
ンダ大手銀行 42%、雇用者団体および労働組合 7%のほか、100 を超える企業および個人投資<br />
家が出資し、資金供給、知識の共有、パートナーシップの組成を手掛けている。FMOはオランダ<br />
政府の要請を受け、新興市場ファンド(FOM)プログラムを管理している。<br />
FOMプログラムでは、事業資金を必要としながらも民間銀行からの融資を受けられない現地<br />
の子会社やオランダ企業との合弁会社を対象に、FMOが資金と助言を提供する。資金は最大<br />
1,000 万ユーロ。FOMプログラムへの資金はFMOが外部から資金を調達して提供する。オランダ<br />
経済省が融資の一部を保証し、FMOが経済省に年間保証手数料を支払う。FOMプログラム適<br />
用の主な条件は、オランダの親会社(オランダ企業)に経済効果をもたらす投資であること、民間<br />
銀行から融資を断られたこと等であり、発展途上国へ事業全体の移転を計画している場合、資金<br />
は提供されない。<br />
プロジェクトの選定基準は、財務成績、CSR、事業の持続可能性、現地経済への貢献度である。<br />
ファンドの融資は厳格なプロセスを経て行われることから、融資後のプロジェクトの運用に対して<br />
原則的にFOMが関わることはない。しかし、例外的に特定のプロジェクトが社会的問題などを生<br />
じさせた場合などは、コンサルタントを通じてプロジェクトに関して調査が行われることもあり、FO<br />
Mが監査役会に参加や年数回にわたりプロジェクトの進捗について運用主体側と議論することも<br />
ある。<br />
開発コストの 100%、実行、運営・保守管理コストの 50%<br />
アンゴラ¹、バングラデシュ¹、ベナン¹、ブータン¹、ブルキナファソ¹、エチオピア¹、ガン<br />
ビア¹、イエメン¹、マラウイ¹、モルディブ¹, マリ¹、モザンビーク¹、ニジェール¹、ウガン<br />
ダ¹、ルワンダ¹、サントメプリンシペ¹、セネガル¹、タンザニア¹、ザンビア¹<br />
開発コストの 100%、実行、運営・保守管理コストの 35%<br />
ボリビア¹、ガーナ¹、ニカラグア¹<br />
開発コストの 50%、実行、運営・保守管理コストの 35%<br />
アルバニア、アルジェリア、アルメニア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、コロンビア、エジプ<br />
ト、フィリピン、グルジア、グアテマラ、インドネシア、カーボベルデ、ケニア、コソボ、<br />
マケドニア、モロッコ、モンゴル、モンテネグロ¹、パキスタン、ペルー、セルビア¹、スリ<br />
ナム、タイ、ベトナム、南アフリカ¹<br />
開発コストの 100%、実行、運営・保守管理コストの 80%<br />
アフガニスタン¹、 コンゴ民主共和国¹、パキスタン、パレスチナ自治区、スーダン¹<br />
¹ 国際競争入札が必須<br />
FOMはBOPプロジェクトと他のプロジェクトとの区別はしていない。FOMプログラムにおいてB<br />
OPプロジェクトは「現地の経済発展に貢献し、社会の最下層への波及効果を持つとみなされるあ<br />
らゆるプロジェクト」という極めて広く定義されている。<br />
FOMプログラムは 6 年前にスタートしたが、融資期間が長いため、収益性はまだ明らかではな<br />
く、おそらく収支は均衡または小幅な損失を計上しているとみられる。FMOの予算総額に占めるF<br />
OMの比率は 2%に過ぎず、損失はFOMがカバーする。<br />
FOMプログラムの今後の課題としては、国家支援の定義との距離をいかに保つか、使命を明<br />
116
確に理解している適切な人材の発掘、予備資金の確保、現地オーナー側にいかに長期的な目標<br />
を保持させるか、等である。<br />
これまでのFOMプログラムの主な事例は下記の通り。<br />
� Van der Knaap Group:スリランカの工場でココナッツ樹皮を有機基質に加工するプロジェクト。<br />
投資総額は 250 万ユーロ、FMOが 110 万ユーロを融資。<br />
� VAR World Wide Recycling:バングラデシュにおける廃棄物の回収、廃棄物の堆肥への加工な<br />
どを行うリサイクリング・プラント設置プロジェクト。投資総額は 1,200 万ユーロ、FMOが 580 万<br />
ユーロを融資。<br />
③ NGO等によるBOPプロジェクト支援<br />
1)オランダ国際協力・持続可能な開発委員会(NCDO)<br />
(Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling)<br />
NCDOは外務省が資金提供する自治行政権を有する機関である。NCDOの主な活動は、オラン<br />
ダ国民やオランダ企業への情報提供により国際開発協力への参加を促すことである。また、同機<br />
関は助成金や助言も提供する。開発協力における政府や市民の取組について理解と協力を得る<br />
ために、キャンペーン、ディベート、教育活動、展覧会、メディア制作、文化プロジェクトなどを計<br />
画・実施する。活動資金は全てオランダ外務省が提供する。<br />
NCDOには「ビジネス開発」(BiD:Business in Development)というプログラムがある。BiDは<br />
「ベストプラクティスの事例」を示し、発展途上国のビジネスチャンスを積極的に広報し、オランダ<br />
企業が発展途上国においてプロジェクトを立ち上げることを奨励するものである。広報の対象は<br />
生産設備の立ち上げなどのインフラ整備、途上国からの仕入れ、フェアトレードに加えて、BOPプ<br />
ロジェクトも含まれる。BOPプロジェクトを促進するため、NCDOには以下の 2 つの主要な手段が<br />
ある。<br />
� BiDマッチング・データベース:オランダおよび発展途上国の企業が事業提案を登録できる<br />
オンライン・データベース。 http://www. bidnetwork.org/<br />
� グローバル・アントレプレナーシップ・プログラム:オランダの多国籍企業の若手専門家に<br />
対し、自社のためのBOPプロジェクトモデル開発という課題を与え、企業側がビジネスモ<br />
デルを実施する段階までNCDOが指導。(現在、オランダ大手技術コンサルティング会社<br />
Arcadis と Philips の下で 2 つのプロジェクトが立ち上げ段階にある。)<br />
BOPプロジェクトの成功に対してNCDOは、管理職レベルにおけるコミットメントや新規アイデ<br />
アに対し商業的な成功の有無に関わらない報酬、などが要因になりうると見ている。また今後の<br />
117
課題として、BOPプロジェクトの商業的成功の判断基準 6 や、世界的な経済危機によるBOPプロ<br />
ジェクトへの投資意欲減退を指摘している。<br />
2)プロテスタント系教会間開発協力組織(ICCO)<br />
オランダのODAにおいて、NGOは非常に重要な役割を果たしている。ODAの年間予算総額<br />
の約 25%が一括で協調融資機関(CFA)へ供与され、各NGOへプロジェクトベースで資金を分配<br />
する。MFS)へ支給される。支給を受けられるNGOは 4 年に 1 度公募で決定され、大型NGOでも<br />
成果指標によって減額、支給停止されることがある。ICCO、Cordaid、Hivos、Oxfam Novib が現在<br />
の四大NGO。<br />
ICCOは基本的な社会サービスへのアクセスの提供、公正な経済発展の実現、平和と民主主<br />
義の促進にコミットする世界中の現地組織やネットワークに対して財政支援や助言を与えている。<br />
年間予算は 1 億 3,000 万ユーロ(2008 年度) 7 。ICCOでは、公正かつ持続可能な経済開発部<br />
(Department for Fair and Sustainable Economic Development)がビジネス界とのパートナーシップ<br />
を担当する。BOPプロジェクトが一般的な要件を満たしている場合、例えば当該プロジェクトが現<br />
地経済、流通システム、保守能力への貢献や、単なるマーケティング・広告に留まらない情報提<br />
供を行うなど明白な発展効果がある場合にICCOは支援を行う。ICCOの役割は、①直接的な資<br />
金調達ではなく、現地アドバイザーへの資金援助や現地スタッフの訓練などの資金面での協力、<br />
②専門知識の共有、企業への助言、仲介、パートナーの紹介などコンサルティング等である。これ<br />
までの具体例としては、オランダの大手化学メーカーDSMに対しインドのNGOパートナーを紹介、<br />
などがある。<br />
ICCOはBOPプロジェクトの今後の課題として、ビジネスの進展が遅いこと、不採算性が高いこ<br />
と、パートナー間での利害の対立などをあげている。<br />
3)救済と発展のためのカトリック機関(Cordaid)<br />
緊急援助と貧困撲滅を目的とした組織で、アジア、アフリカ、南米 36 ヵ国に数千のパートナー組<br />
織を持つ。a.エスニック、宗教的マイノリティーの市民権、b.スラムの自治、社会的なサポート、c.女<br />
性と暴力、d.災害救助、e.ヘルスケア、f.老人、子供、障害者などの社会的弱者、g.HIV/AIDs、h.小<br />
農家の質の標準化への援助、i.マイクロファイナンス、の 9 つをテーマに活動している。<br />
6 BOPプロジェクトは社内における標準的な商業基準では基準を満たすことはできないケースが多い。しかし<br />
Shell のように社外組織(Shell の場合は Shell 基金)に BOP プロジェクトを組み込むことにより、この問題を解決<br />
する場合もある。<br />
7 ICCO Annual Report 2008<br />
118
4)Hivos(人道主義的組織)<br />
貧困削減、市民社会の建設、安定的な経済成長を目的に、30 ヵ国以上で 800 のパートナー組<br />
織と活動している。活動は以下の 3 種類に分けられる。<br />
a. マイクロファイナンスとフェアトレードによる貧困削減<br />
固定住所を持っていないがために担保がなく、ローンを組むことの出来ない小企業家への援助<br />
を目的に、途上国でマイクロファイナンスを行う金融機関へ経済援助、技術援助を行う。Hivos の<br />
援助によって行われたマイクロファイナンスは既に 178 万人へ融資し、その 68%は女性である。フ<br />
ェアトレードは、開発途上国の地元コンサルティング会社と Hivos が協力し、貿易を通して開発途<br />
上国産品の質を国際水準に近づけるべく農家への指導を行っている。<br />
b. 安定した生産<br />
消費者と卸売業者の国内および国際マーケットへのアクセスを改善し、国際/社会基準に合う<br />
商品を作ることを目的とする。安定生産のためのエネルギー供給、農薬・遺伝子組み換え産品に<br />
関する正しい知識の伝授、モノカルチャー改善などの生態系改善などの活動を行っている。<br />
c. ICT<br />
ICTメディアを使った民主主義の促進。<br />
5)Oxfam Novib<br />
貧困問題の解決を命題に、60 ヵ国以上で 800 のパートナー組織と活動している。主な活動は、<br />
a.女性支援、b フェアトレード、c.武器管理、d 貧困削減。<br />
6)BOP Learning Lab Benelux<br />
BOP Learning Lab Benelux は、もともとは米国のコーネル大学を拠点とする世界的な BOP<br />
Learning Lab のベネルクス支部である。 BOP LL Benelux は 2005 年に正式に設立され、現在、将<br />
来的な活動に向けた実践的な戦略を開発している。目標に掲げるのは、研究機関、NGO(ICCO、<br />
Oxfam Novib)、企業との連携を通じて、専門知識のネットワークセンターおよびBOPの課題解決<br />
のプラットフォームとなることであり、尐なくともオランダ企業 10 社が積極的に関与することを目指<br />
119
している。<br />
図表 5 外務省から資金を提供されている主要NGO(2007~2010 年)<br />
ICCO<br />
5 億 2,500 万<br />
ユーロ<br />
(2)支援スキーム活用事例<br />
Oxfam Novib<br />
5 億 900 万<br />
ユーロ<br />
公正かつ持続可能な経済開発局(Department<br />
for Fair and Sustainable Economic Development)<br />
ビジネス支援:<br />
1. 間接金融<br />
2. コンサルタント的な役割<br />
例:現地の NGO を DSM に紹介<br />
① 多結晶(PV)モジュールの製造プラント(ケニア、ナイロビ)<br />
東アフリカ地域、特にケニアは太陽光発電機器の需要が急速に高まっている。このプロジェクト<br />
では東アフリカで初めての高品質多結晶(PV)モジュール製造プラントを設立、太陽光発電利用<br />
の更なる普及に貢献しようというもの。当プロジェクトに合わせて低電圧小型ソーラー・ホーム・シ<br />
ステム(SHS)を開発、従来製品と比べて画期的な低価格での市場投入を図る。さらに欧州の工<br />
場から運ばれる再利用可能な廃棄太陽電池を小型電池に変換する際に利用する高性能レーザ<br />
ー技術や太陽電池の発電効率を高める薄膜生産技術などの先進技術を導入するなど低価格化<br />
や発電効率向上のための様々な工夫が取り入れられており、太陽光発電のさらなる利用促進が<br />
進むと期待される。現在、東アフリカでは太陽電池の生産は行われておらず、当プロジェクトによ<br />
る高度な技術移転と訓練が見込まれる。また太陽エネルギーを応用する現地企業に対する投資<br />
環境の改善が図られ、さらに低価格な商品を市場に投入することが可能となれば、低所得者層と<br />
いう新たな市場の開拓につながると期待される。<br />
120<br />
外務省<br />
対 NGO 資金供与のための協調融資制度(MFS)<br />
Cordaid<br />
4 億 2,000 万<br />
ユーロ<br />
(計 21 億ユーロ)<br />
Hivos<br />
2 億 6,000 万<br />
ユーロ<br />
中小 NGO<br />
SNV<br />
7 億 9,500 万<br />
ユーロ(2007 年<br />
~2015 年)<br />
MFS 枠外の特別<br />
な地位を確保
セクター エネルギー<br />
図表 6 PVモジュール製造プラントの概要(ケニア)<br />
申請者 Ubbink B.V.(オランダ、Doesburg)( Centrotec Group 傘下)<br />
現地パートナー Largo Investments Ltd(ケニア、ナイロビ)(子会社の Chloride Exide Kenya Ltd.と連携)<br />
期間 2009 年 6 月1日~2011 年7月 30 日<br />
予算総額 148 万 1,500 ユーロ(PSI 供与:50%)<br />
目標<br />
東アフリカで初めての太陽光発電用多結晶(PV)モジュール製造プラントの稼働。パイロッ<br />
ト生産終了時点の生産量は 1 万 5,000 モジュール<br />
成果 合弁会社の設立、生産設備の建設・設置、パイロット生産・訓練<br />
CSR<br />
影響<br />
雇用・労働条件<br />
技術移転<br />
連鎖効果<br />
環境への影響<br />
女性の地位<br />
その他<br />
両企業とも CSR 方針を統合した点において高い評価を得ている。プロジェクトの CSR 方針<br />
には以下の側面がある。<br />
従業員の行動規範、魅力的な給与、健全な労働基準<br />
衛生安全対策(基本的な医療保険などの有益なパッケージ)<br />
健全な環境基準、環境への悪影響の軽減<br />
人権、汚職防止、製品の品質、チェーンにおける責任<br />
パイロット生産終了後 2 年間で追加投資 105 万ユーロ(第 2 次生産ラインへの投資:40 万ユ<br />
ーロ、新規の高級用途開発投資:15 万ユーロ、ソーラーシステムの送電網市場への参入投資:<br />
50 万ユーロ)を計画。パイロット生産終了の 2 年後における年間予想売上高は 290 万ユーロ<br />
(145 万ユーロが PSI 投資による)。<br />
プロジェクト期間中に 32 名を雇用、うち 5 名は中・上級スタッフ。パイロット生産終了の 2<br />
年後にはそれぞれ 48 人と 9 人の見込み。賃金は現地メーカーの同等地位の最低賃金を大きく<br />
上回る。福利厚生は訓練、職場での昼食、成果報酬・賞与、住宅手当、医療費の払い戻し、<br />
通勤手当、年金制度など。労働条件は良好で、職場の安全衛生には十分な注意が払われる。<br />
合弁会社は既存の CEKL 規範に沿った従業員の行動規範を策定する。<br />
生産過程に関わる訓練はすべて現地にとっては新規のものであり、最新の技術と生産概念が<br />
導入される。当プロジェクトにおける広範な訓練パッケージは、組織全体にわたり従業員の<br />
新たな知識と技能に貢献する上で重要な役割を果たす。<br />
太陽光発電機器の現地生産により、商品を低価格で市場に供給することができれば供給量が<br />
増加し市場が拡大する。政府がこの新規市場への参入を支援することで、他社の市場参入を<br />
促進させる可能性もある。長期的に利益を得るとみられる当事者は、販売業者/小売業者、<br />
システム統合企業、最終ユーザー(オフグリッド(ライフラインの網から外れた形態)の家<br />
庭、小規模企業、学校、病院)、現地部品メーカーなどである。また、尐なくとも請負業者 3<br />
社または他の製品/サービス・サプライヤーに雇用と収入をもたらす。<br />
電池や灯油から太陽光エネルギーへの代替が進展するのに伴い、環境に好影響を与えると期<br />
待。生産設備の建設に先立ち、限定的な環境影響評価(EIA)が実施される。米国電機工業<br />
会(NEMA)の認証には、職場の安全衛生リスク・リストの他に環境スクリーニングが含ま<br />
れる。<br />
大半のポジションに占める女性の比率は 50%と予想される。ハイテク環境下では正確さが必<br />
要とされるため、生産レベルでは 50%を上回る可能性がある。女性は同等ポジションの男性<br />
と同じ報酬であり、産休の権利がある。<br />
太陽光システムの広範な利用は、農村部を中心にケニアの人口の 70%以上を占めるオフグリ<br />
ッドの家庭や小規模企業の生産能力に好影響を与える。<br />
② Dairy Factory Peru 乳加工製品の製造プラント(ペルー、Arequipa)<br />
ペルー南部の Arequipa には高付加価値製品を生産する乳加工工場がない。地元農家が生産<br />
する牛乳はすべて大手乳製品加工業者(Gloria)が買い取り、地元工場で生乳を濃縮し、リマに輸<br />
送して加工を行う。現地パートナーの Agricola Pampa Baja(APB)は 1 日当たり 3 万リットルの牛<br />
乳を生産する地元農業企業で、ヨーグルトやチーズなどを地元で生産することにより付加価値を<br />
高めたいと考えている。申請者の Machinehandel Lekkerkerker B.V.(ML)は Lopik で乳工場を運<br />
121
営する他、食品業界向けに加工装置の製造も手掛ける。MLはペルーでの近代化された乳工場<br />
の運営および製品の販売に大きなビジネスチャンスがあるとみている。同社は合弁企業を設立し、<br />
果物入りクリームヨーグルト、成熟ゴーダチーズ(乳脂肪率 48%以上)、学校給食向け特殊容器<br />
入り殺菌乳の生産のため、Arequipa 市から約 100 キロの場所に乳加工工場を建設した。同地域<br />
における雇用創出にも期待される。<br />
図表 7 乳加工製品製造プラントの概要(ペルー)<br />
セクター 農産業<br />
申請者 Machinehandel Lekkerkerker B.V.(オランダ、Lopik)<br />
現地パートナー Agrícola Pammpa Baja SAC(ペルー、Arequipa)<br />
期間 2009 年 7 月 15 日~2011 年 11 月 15 日<br />
予算総額 149 万 5,000 ユーロ(PSI 供与:50%)<br />
目標<br />
成果<br />
CSR<br />
影響<br />
雇用・労働条件<br />
③ バラ栽培(エチオピア、Debre Zeit)<br />
トロピカルフルーツ入りクリームヨーグルト、ゴーダチーズ(乳脂肪率 48%<br />
以上)、政府の学校プログラム向け殺菌乳の生産のため、Arequipa で乳加工<br />
工場を建設。<br />
合弁会社の設立、加工工場の建設、全設備の設置及び運営、従業員との契約<br />
および訓練、果物供給契約、商業運転の開始、流通システムの実行<br />
危害分析重要管理点(HACCP)による認証の他、ペルーの保健所からの認<br />
証も取得。現地パートナーは農場全体を対象とする独自の CSR 方針を持つ。<br />
乳処理能力の増強、第 2 殺菌設備の建設および低温貯蔵室の拡張(従来比 2<br />
倍)に向けた 450 万ユーロの追加投資<br />
プロジェクト期間中に 30 名を雇用。生産作業員の給与は法定最低賃金の 2<br />
倍。パイロット生産の 2 年後の正規雇用数は 53 名に増加予定。<br />
従業員は良好な基本的労働条件の他、福利厚生として年間 13 カ月分の給与、<br />
健康保険、年金制度、昼食、年間 30 日の休暇、交通費が提供される。<br />
技術移転 濃縮果物入りクリームヨーグルトの生産技術(ペルーでは新規生産)<br />
連鎖効果<br />
主要な効果は果物供給契約であり、尐なくとも 100 件の小規模果物生産者に<br />
収入を生み出す。また、リマの現地企業が最新の加工工場で年間 6,000 トン<br />
の果物を濃縮果肉に加工し、無菌パックに詰めて供給する、という内容の長<br />
期契約を締結、<br />
女性の地位 従業員の約 50%が女性。<br />
現在、世界の切りバラ生産のうちアフリカの 40%のシェアを占めるが、2009 年まで、バラの育種<br />
(品種改良)は西欧で実施されている。品種改良されたバラはアフリカの気候環境には適応しない<br />
ため、国際市場におけるアフリカ産のバラ価格は概ね低水準にとどまっている。当プロジェクトは<br />
オランダのバラ栽培生産会社 De Ollies B.V.と現地の Olij Roses Ethiopia PLC.が合弁企業を設立、<br />
バラの育種をエチオピアに導入し、抵抗力、生産量、日持ちという点でより優れた新種の開発を目<br />
指し、赤道付近の地域のバラ栽培業者の国際競争力強化を目指す。<br />
122
図表 8 バラ栽培プロジェクトの概要(エチオピア)<br />
セクター 園芸/花栽培<br />
申請者 De Ollies B.V.(オランダ、De Kwakel)<br />
現地パートナー Olij Roses Ethiopia plc(エチオピア、Debre Zeit)<br />
期間 2009 年 6 月 1 日~2012 年 5 月 31 日<br />
予算総額 150 万ユーロ(PSI 供与:50%)<br />
目標 エチオピアでのバラ農園の立ち上げ<br />
成果 合弁会社の設立、栽培設備の建設および設置、パイロット生産<br />
CSR<br />
影響<br />
雇用・労働条件<br />
技術移転<br />
連鎖効果<br />
環境への影響<br />
女性の地位<br />
④ 乳製品開発プロジェクト(インド)<br />
オランダの大手化学メーカーDSMはライフサイエンスおよびマテリアルサイエンスの分野にお<br />
けるグローバル企業であり、食品、健康関連製品から自動車用コーティング剤に至るまで様々な<br />
製品を取り扱っている。DSMでは若手研究者グループが事業としてのBOPプロジェクトの可能性<br />
を調査することを提案し、「現地の人々の収益拡大」を焦点に人々が何に対して購買意欲を持ちD<br />
SMの技術をどう利用できるかを調査するため、すでに同社の事業ネットワークがあるインドへ研<br />
修員を派遣した。その結果、インドの乳牛の乳生産量がオランダに比べて非常に尐ないことに着<br />
目し、牛乳に関わるプロジェクトの立ち上げを決定した。同プロジェクトは、①乳牛の健康増進用<br />
のサプリメントを販売、②乳牛の繁殖に関する専門知識を導入、③付加価値のついた小売製品<br />
(ヨーグルトなど)の開発に関する専門知識を導入、という段階からなり、協力はすべて農家の生<br />
活協同組合を通じて実行される。<br />
MPS-ABC(花き環境認証プログラム)、MPS-SQ(雇用・社会責任認証プロ<br />
グラム)、Fair Flowers Fair Plants(FFP)、エチオピア園芸生産輸出業者組<br />
合(EHPEA)の認証を取得。これらの認証では CSR のあらゆる側面が考慮<br />
される。<br />
プロジェクト完了後、同社はバラ栽培業者に直接バラを引き渡すことができ<br />
るよう、バラの育苗を独自に開始する。<br />
プロジェクト期間中に 15 名を雇用。そのうち 7 名は中・上級レベルの従業<br />
員。育苗事業への投資後、従業員総数は 65 名に増強予定。生産労働者の賃<br />
金は当セクターの最低賃金よりも 3 ブル高い 12 ブルからスタートする。労<br />
働条件は Fair Flower Plants 基準を順守。福利厚生として昼食手当て、作業<br />
着、通勤のための交通手段、医療費の払い戻しを提供。<br />
育種過程およびその登録手続きに関わる知識は全てエチオピアでは新規技<br />
術。現地で高度な技能を持つスタッフの教育を実施。<br />
エチオピアで生産されるバラのラインナップが低価格品から高級品まで揃<br />
う。欧州市場向け新品種の開発はアフリカで生産されるバラの市場価格の上<br />
昇につながると予想され、アフリカの全栽培者に利益をもたらすと期待。さ<br />
らに新種により単位生産量を増加させることができれば、アフリカのバラ栽<br />
培セクターの競争力が増加。<br />
病気に比較的強く、農薬使用の必要性が低い品種が開発できれば、生産地域<br />
における環境に好影響を与えると期待。当事業は環境影響評価(EIA)が実<br />
施され、生産は MPS-ABC、MPS-SQ、FFP に基準に従って認証される。<br />
経営管理者(管理者および農業経営専門家)および大半の従業員には女性が<br />
登用され、女性の地位上昇に貢献。<br />
その他 学校開設支援などの社会プロジェクトを実行。<br />
このプロジェクトにより、酪農家の生乳生産量は増加し、生活協同組合は乳牛の健康と繁殖、<br />
新製品の開発と小売販売について知識を取得することができる。同プロジェクトには現在 1,000 件<br />
の酪農家およびその周辺事業者が関与、将来は生活協同組合の 10%、約 85 万件の酪農農家(3<br />
123
州のみ)が関与する可能性があると推定される。<br />
通常DSMでは、プロジェクトの収支は 3 年以内に均衡することを求めている。しかし当プロジェ<br />
クトでは 7 年という年数を設定し、現在が 3 年目である。通常よりも緩和された事業実施基準の適<br />
用を可能とするため、BOPプロジェクトは通常の事業部門ではないDSMイノベーション・センター<br />
で管轄している。<br />
インドはオランダのODA供与リストに掲載されていないため、DSMはオランダ政府から財政支<br />
援を受けられなかった。そのためDSMはインドの適切なNGOパートナーと接触するため、NGO<br />
のICCOのネットワークを利用した。<br />
将来的には当プロジェクトが利益を生み出し、例えば中国の養豚農家など他の地域でのプロジ<br />
ェクト実施が期待される。また、DSMはエネルギー源としての牛糞の使用(バイオガスを生成し、<br />
現地の火力、調理用ガス、オフグリッド電力のエネルギー源として使用)によりプロジェクトを次の<br />
段階に移行させ、これらの活動をDSMのカーボン・クレジット・システム(クリーン開発メカニズム)<br />
に統合する可能性にも期待している。<br />
BOPプロジェクトに対するODA支援について、DSMは次のような改善を提案している。現在オラン<br />
ダ政府による援助資金は、オランダ国関係者向けにしか行われていない。インドのケースでは、D<br />
SM側のみに資金提供が行われている。しかし、より効率的な事業の実施とより高度な結果を求<br />
めるならば、現地のパートナーに対する資金援助も行うべきである。さらにプロジェクトの実施にあ<br />
たり、オランダ政府がBOPプロジェクトの収支が均衡するまでBOPプロジェクトに対応することで<br />
余計に生じるスタッフの賃金(当プロジェクトでは通常のプロジェクトの期間 3 年を超える 4 年分の<br />
賃金)を負担すると、企業としてより積極的にBOPプロジェクトに参入することができると指摘して<br />
いる。<br />
⑤ クリーンエナジーへの投資<br />
クリーンエナジー事業の開発途上国への投資を行う非営利企業 E+co 社は、1 件 2 万 5,000 ド<br />
ル以上で、アフリカ、アジア、中南米の 28 ヵ国へ投資および技術援助を行っている。投資基準は<br />
a.事業のアイデアが明確であり、地元やスポンサーに受け入れられていること、b.信頼出来る手ご<br />
ろな価格の技術であること、c.社会に貢献し環境に資するものであり、伝統エネルギーとの競争性<br />
があるもの、d.経済的に自立可能なポテンシャルがあること、の 4 つである。<br />
投資家への利益率は 3%であり、通常の 8%より低いが、この差をCSRとしてアピールできると<br />
参加企業が捉えている。<br />
124
125<br />
図表 9 オランダの主なBOPプロジェクト関連支援スキーム<br />
概要<br />
主管官庁等<br />
予算<br />
申請手続き<br />
事例数<br />
官民パートナーシップ(PPP)による<br />
民間セクター開発プログラム<br />
ミレニアム開発目標(MDGs)の達成<br />
に貢献することを目的に、オランダ企<br />
業および現地企業の協力のもと、官<br />
民連携により行われる事業活動を財<br />
政支援。<br />
民間セクター投資プログラム(PSI)<br />
途上国の持続可能な経済開発、雇用の<br />
創出を目的として、新興市場への投資を<br />
助成。途上国向けのタイド助成と最貧国<br />
向けのアンタイド助成。プロジェクト対象<br />
国によっては非オランダ企業も助成対<br />
象。<br />
オランダ外国貿易庁(EVD)<br />
外務省持続的経済開発局<br />
3,000万ユーロ(2009年)<br />
7億5,000万ユーロ(2004年~2009年<br />
企業に対して年2回の募集(第二次募集<br />
10月)<br />
の受付開始は2009年12月10日)<br />
外務省に申請<br />
EVDに申請<br />
73件のPPPに計185社(開発途上国<br />
企業を含む)が参加<br />
49件(2009年)<br />
インフラ開発ファシリティ(ORIO: Facility<br />
for Infrastructure Development)<br />
途上国の公共インフラ工事(商業的に<br />
は採算性がなく、国際入札を通じて調<br />
達される財・サービスが対象)に対して<br />
助成金を供与。実施主体は受けて国側<br />
の中央政府。<br />
オランダ外国貿易庁(EVD)<br />
1億8,000万ユーロ(2009年)<br />
年2回の募集<br />
EVDに申請<br />
9件(2009年第一次募集)。第二次募集<br />
は12月に実施。<br />
対象地域 40ヵ国(例外あり) 50ヵ国 51ヵ国(第二次募集時)<br />
資金負担の<br />
割合<br />
上限額<br />
セクター<br />
プロジェクト具<br />
体例<br />
民間企業60%、外務省40%が目標(実<br />
際には各50%となるケースが多い)<br />
プロジェクト総額の最大50%<br />
開発コストの50%もしくは100%、実<br />
施、運営・保守管理コストの35%、50%<br />
もしくは80%。<br />
新興市場ファンド(FOM: Fund<br />
Upcoming Markets)<br />
民間銀行からの融資を受けられない途<br />
上国のオランダ企業子会社やオランダ<br />
企業との合弁会社が行うプロジェクトを<br />
対象に、資金提供・助言を行う。オラン<br />
ダ企業(親会社)に経済効果をもたらす<br />
投資であること、民間銀行からの融資<br />
が受けられないことが条件。<br />
オランダ開発金融会社(FMO)<br />
FOMプログラムを通じて1,900万ユーロ<br />
を投資(2008年)<br />
FMOに申請<br />
17件(2008年)<br />
オランダ企業の現地子会社もしくは合<br />
弁事業が拠点を構える世界銀行加盟<br />
国(高所得国、EU加盟国除く)<br />
事例に応じて決定。中小企業以外の場<br />
合、最大負担割合は新興国における子<br />
会社等の総資産の35%<br />
ビジネス開発(BiD: Business in<br />
Development)<br />
オランダ国民やオランダ企業への情報<br />
提供により国際開発協力への参加を促<br />
進することを目的に、途上国のビジネス<br />
チャンスを広報。オランダ及び発展途上<br />
国の企業が事業提案を登録するデータ<br />
ベース運営、イントラプレナーのビジネス<br />
モデルの指導など。<br />
オランダ国際協力・持続可能な開発委<br />
員会(NCDO)<br />
NCDOの補助金予算総額は年間1,650<br />
万ユーロ<br />
NCDOに申請<br />
グローバル・アントレプレナーシップ:4<br />
件。マッチング用ウェブサイト:提案9,200<br />
件、メンバー2万7,144人。MDGスキャン:<br />
61件<br />
DAC対象国地域で広報・技術指導<br />
プロジェクト総額の50%まで(広報、技術<br />
指導など)。指導、助言およびその他の<br />
サービスは無償。<br />
上限なし(現時点での最大供与額は<br />
TCX通貨リスクファンドの5,000万ユー 75万ユーロ<br />
ロ)<br />
4,800万ユーロ 1,000万ユーロ(融資) 5万ユーロ(例外として10万ユーロ)<br />
全セクター(優先セクター:持続可能<br />
性、気候、エネルギー、ヘルスケア)<br />
・安全な飲料水プロジェクト(モザン<br />
ビーク)<br />
・「アフリカに安全な光を」プロジェクト<br />
(アフリカ)<br />
全セクター 公共インフラ 全セクター 全セクター<br />
・多結晶(PV)モジュールの製造プラント<br />
(ケニア)<br />
・サンタクルスの総合病院(ボリビア)<br />
・地方都市の水供給プロジェクト(ガンビ<br />
ア)<br />
・ココナッツ樹皮加工プロジェクト(スリラ<br />
ンカ)<br />
・廃棄物回収・堆肥加工プラント(バング<br />
ラディシュ)<br />
スリッパの品質向上・販売ルート開拓<br />
(南アフリカ)<br />
水工場の設立、浄水した水の販売(ケニ<br />
ア)
(1)BOPビジネスに関わる政府の役割<br />
① 政府の支援方針・体制<br />
2.ドイツ<br />
ドイツの開発援助政策の根幹は、2001年に閣議決定された「貧困削減のための 2015 年行動計<br />
画」にある。同計画ではミレニアム開発目標(MDGs)を達成するための具体的な課題として、(i)<br />
経済開発と社会的弱者の経済活動への参加促進、(ii)食料確保と農業改革の実現、(iii)公正な貿<br />
易への参画促進、(iv)債務の削減と金融の発展、(v)社会サービスの確保と弱者保護の強化、(vi)<br />
資源と環境の保全、(vii)人権擁護の実現と労働基準の尊重、(viii)ジェンダーへの配慮、(ix)社会的<br />
弱者の政治的経済的自立、良い統治の実現、(x)人間の安全保障・軍縮の促進を通じての紛争の<br />
平和的解決、の 10 項目を挙げている。シュレーダー政権時に定められたものであるが、開発政策<br />
の理念を定めたものであるとして第一次、第二次メルケル政権にも引き継がれた。<br />
ドイツはEUのODA増額の方針の元、2010 年までにODAをGNI比 0.51%に、2015 年までに<br />
0.7%にすると発表している。実際には 2008 年に対GNI比 0.38%と達成は難しいが、毎年堅実に<br />
実績を伸ばしている。<br />
図表 10 ドイツのODA額、対GNI比の推移<br />
(100万ユーロ)<br />
10,000<br />
9,000<br />
8,000<br />
7,000<br />
6,000<br />
5,000<br />
4,000<br />
ODA総額 ODAの対GNI比<br />
03年 04年 05年 06年 07年 08年<br />
ドイツのODA予算は人道支援や金融機関への援助の一部を除き、その殆どを連邦経済協力<br />
開発省(BMZ)が所管している。BMZは開発援助業務に関わる独立省庁であり、KfW開発銀行<br />
やドイツ技術協力公社(GTZ)などの開発援助支援機関を通して行う二国間協力、国連、欧州開<br />
発基金(EDF)などへの資金の他、NGOへの資金も拠出している。<br />
126<br />
%<br />
0.39<br />
0.37<br />
0.35<br />
0.33<br />
0.31<br />
0.29<br />
0.27<br />
0.25<br />
出所:BMZホームページ
図表 11 2009 年BMZ予算<br />
出所:BMZホームページより<br />
BMZは職員 600 人ほどの小さな官庁で、政策の企画立案を行い、資金協力、技術協力などの<br />
執行は複数の開発援助協力機関が担っている。<br />
BMZの援助対象国は政治的安定性や法的枠組みや規制などの存在、当該国とドイツとの二<br />
国間関係などを鑑みて決定される。対象国は重点化により数が減尐されており、現在 57 ヵ国であ<br />
る。これらの対象国では支援重点セクターが 1 ヵ国につき最大 3 つ決められ、その分野に各機関<br />
からの援助を集中させ、効率的に開発援助効果を得ることが出来るようにしている。<br />
KfW<br />
開発銀行<br />
地方銀行<br />
3%<br />
欧州開発<br />
基金(EDF<br />
)<br />
14%<br />
食料安全と<br />
環境保護<br />
3%<br />
連邦省庁<br />
1%<br />
NGO、NPO<br />
企業集団<br />
10%<br />
特別措置<br />
0%<br />
図表 12 BMZ傘下の開発援助政策見取り図<br />
資金協力 技術協力<br />
DEG<br />
ドイツ開発<br />
投資銀行<br />
InWEnt<br />
国際再教育<br />
開発公社<br />
総額:58億1,377万9,000ユーロ<br />
DED<br />
ドイツ開発<br />
援助サービス<br />
世銀、IMF<br />
14%<br />
出所:BMZ他各機関ホームページより作成<br />
127<br />
国連など国<br />
際組織<br />
6%<br />
BMZ<br />
(経済協力開発省)<br />
GTZ<br />
技術協力<br />
公社<br />
CIM<br />
国際人口<br />
移動センター<br />
官民連携<br />
プログラム<br />
DEG<br />
ドイツ投資<br />
開発銀行<br />
二国間開<br />
発援助<br />
49%<br />
NPO NGO<br />
企業集団<br />
sequa<br />
経済開発・<br />
資格付与財団<br />
EU<br />
国際機関<br />
開発銀行<br />
社会改善<br />
ネットワーク<br />
KOLPING International<br />
ドイツ・カリタス<br />
AWO International<br />
DGB<br />
DGRV<br />
IIZ/DVV<br />
BORDA
② 支援機関・支援スキーム<br />
BMZの政策決定の下、KfW開発銀行、ドイツ投資開発銀行(DEG)が資金協力を担当し、ドイ<br />
ツ技術協力公社(GTZ)、国際人口移動センター(CIM)、ドイツ開発援助サービス(DED)、国際<br />
再教育開発公社(InWEnt)が技術協力を行う。99 年から新設された官民連携プログラムは、GT<br />
Z、DEG、ドイツ経済開発・職業訓練財団(sequa)が携わっている。各プロジェクトの資金および、<br />
産業別の規模は表 1、2 のとおり。<br />
図表 13 2008 年ドイツの開発援助の推移(資金援助、技術援助、官民連携)<br />
単位:100万ユーロ、%<br />
プロジェクト数<br />
公的資金<br />
金額 構成<br />
民間資金<br />
金額 前年比<br />
合計<br />
金額<br />
官民連携プログラム 73 13.1 40.7 19.1 59.3 32.2<br />
DEG 30 4.9 34.8 9.2 65.2 14.1<br />
GTZ 32 6.4 47.1 7.2 52.9 13.6<br />
KfW 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0<br />
sequa 11 1.8 40.0 2.7 60.0 4.5<br />
技術協力 120 7.1 35.7 12.8 64.3 19.9<br />
CIM 11 0.6 54.5 0.5 45.5 1.1<br />
DED 61 0.6 37.5 1.0 62.5 1.6<br />
GTZ 46 5.8 34.1 11.2 65.9 17.0<br />
Inwent 2 0.1 50.0 0.1 50.0 0.2<br />
資金協力 109 895.7 36.0 1,593.3 64.0 2,489.0<br />
KfW 43 229.8 28.0 590.7 72.0 820.5<br />
DEGの長期融資 66 665.9 39.9 1,002.6 60.1 1,668.5<br />
全体 302 915.9 36.0 1,625.2 64.0 2,541.1<br />
出所:Annual Report 2008, BMZ<br />
図表 14 ドイツの分野別開発援助(1999~2008 年)<br />
(資金援助、技術援助、官民連携)<br />
官民連携<br />
プログラム 技術協力<br />
教育 35 104 3 142 4.6 0.1<br />
エネルギー 60 45 21 126 4.1 1.3<br />
保健 79 52 43 174 5.6 1.6<br />
農業 122 146 12 280 9.1 0.3<br />
交通・通信 24 28 9 61 2.0 0.7<br />
環境 203 155 0 358 11.6 0.5<br />
水 86 37 35 158 5.1 1.9<br />
持続的経済発展 456 558 0 1,014 32.8 1.0<br />
その他 44 71 19 134 4.3 0.3<br />
金融システム 1 0 123 124 4.0 3.5<br />
投資促進 0 0 520 520 16.8 88.9<br />
合計 1,110 1,196 785 3,091 100.0 100.0<br />
出所:Annual Report 2008, BMZ<br />
128<br />
件数<br />
資金協力<br />
および<br />
DEG長期融資<br />
合計<br />
(単位:件、%)<br />
金額<br />
構成比<br />
構成比<br />
構成比
1)ドイツ復興金融公庫(KfW)<br />
ドイツ復興金融公庫(KfW)は 1948 年にODA資金の受け入れ組織として設立された連邦政府<br />
の国内・国際公共政策目標を遂行する公共機関である。KfW助成銀行、KfW中小企業銀行、Kf<br />
W IPEX銀行、KfW開発銀行/ドイツ投資開発銀行(DEG)から成り、ODA関連業務はKfW開発<br />
銀行およびDEGが担当している。<br />
a.KfW開発銀行<br />
図表 15 KfWバンキンググループの組織図<br />
貧困削減、グローバル化のなかでの公平性、自然資源保護、平和実現を使命とし、BMZに代<br />
わって二国間援助など政府対政府の資金協力を行っている。職員は約 450 人で、取り扱い資金<br />
額と比較して現地に派遣できる人間が限られているため、ローカルNGOなどをパートナーとして<br />
いる。援助対象分野は気候変動、平和活動、教育、エネルギー、金融システムの発展、ガバナン<br />
ス、健康、廃棄物処理、水の 9 分野。<br />
BOP層を対象にした業務ではマイクロファイナンスがメインであり、15 年前にグラミン銀行の援<br />
助を始めた業界のパイオニア的存在。政府間協定により地場の銀行やNGOに直接融資すること<br />
もある。援助のプロセスとしては、(a)マイクロファイナンスを扱う金融機関を援助相手国の大都市<br />
に設立する、(b)GTZ等と連携して地場のスタッフへの技術支援を行い、資金運用のノウハウなど<br />
業務内容を教える、(c)資金協力を行い、経営を軌道に乗せる、(d)地方都市に支店を建設する、<br />
の順序。<br />
KfWバンキンググループ<br />
ドイツおよび欧州への<br />
投資支援<br />
中小企業支援<br />
中小企業銀行<br />
住宅、環境・気候<br />
保護、教育、<br />
インフラ、<br />
社会問題<br />
助成銀行<br />
輸出および特<br />
定事業に対す<br />
る融資<br />
輸出および特定<br />
の事業に対する<br />
融資、<br />
投資、企業金融<br />
IPEX銀行<br />
業績評価は手国側へもたらした直接的な利益、開発援助政策の視点でのプロジェクトの正当<br />
性・重要性、コスト効率性、の 3 点で図られる。マイクロファイナンスの場合、初期に資金を借りた<br />
人間が返済するまでにかかる期間の長さが最大の指標となり、大規模融資で 3~4 年、小規模の<br />
129<br />
開発途上国<br />
援助<br />
開発途上国援助<br />
KfW開発銀行:相<br />
手国政府への資<br />
金協力<br />
DEG:民間へ融資<br />
開発銀行<br />
コンサルタント業<br />
および、その他<br />
サービス<br />
民営化などに<br />
関する政府に<br />
対してのコンサ<br />
ルタント業務<br />
出所:DEG資料
場合は更に年月を必要とする。次に、借り入れをしていた顧客が貯蓄を行うことを目標とし、最終<br />
的には施設が自己資金で運用できる程の安定性をもつことを目指す。ただ、最終段階まで辿り着<br />
くには 10 年近くの年月が必要となる。<br />
b.ドイツ投資開発銀行(DEG)<br />
図表 16 KfW開発銀行の開発融資金額の推移<br />
出所:Annual Report 2008on coorperation with Developing Countries<br />
開発途上国に進出するドイツ企業の支援機関として、100%政府出資で 1962 年に設立された<br />
有限会社。現在の海外拠点は 11 ヵ国 11 都市。従業員数約 400 名。2001 年にドイツ政府がKfW<br />
にDEGの全株を譲渡し、KfWグループの一員となった。開発に関わる民間企業の支援を通じて<br />
の途上国の持続的成長と生活水準の向上を目的としており、BMZの監視の下で金融部門を中<br />
心に幅広いセクターへ投資している。官民連携プログラムの実施機関のひとつでもある。<br />
支援する企業はドイツや欧州諸国の企業に限定されておらず、またドイツの利益と関わらない<br />
事業も行っている点で、他国の開発銀行と異なっている。<br />
DEGと民間企業が業務提携する形態としては、(a)DEGが企業にアプローチする、(b)企業がD<br />
EGにアプローチする(特に資金協力に多い)、(c)オランダ開発金融公社(FOM)など他国の開発<br />
期間やアジア開発銀行など国際開発金融機関などがDEGにアプローチする(プロジェクトが大き<br />
すぎてひとつの開発銀行では実行できないとき他機関に声がかかる)の 3 つのパターンがある。<br />
業務内容は大きく分けて以下の 5 つ。<br />
(ア)資金協力<br />
(100万ユーロ)<br />
4,000<br />
3,500<br />
3,000<br />
2,500<br />
2,000<br />
1,500<br />
1,000<br />
� 長期融資(メザニンファイナンスと合わせて 10 億 2,900 万ユーロ(08 年))<br />
開発途上国の地場銀行は 3 ヵ月~1 年程度の短期融資しか行っておらず、中~長期ローンは<br />
失われた市場であり、DEGの支援対象となっている。<br />
500<br />
0<br />
1,577<br />
1,934<br />
1,881<br />
2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年<br />
通貨は原則ユーロまたはドル、期間は 4~10 年。融資額は原則最高 2,500 万ユーロだが、欧州<br />
開発銀行団体(EDFI) 1 の他メンバーとの共同融資の場合はこの金額を超える。DEGはEDIFのメ<br />
1 16 の欧州の開発金融組織がメンバー。開発途上国およびエマージングマーケットでビジネスを行う民間企業の支<br />
援を行う。本部ブリュッセル。DEGの他、FMO、PROPARCO、CDC(英国英国連邦開発公社)などがメンバー。<br />
130<br />
2,445<br />
3,002<br />
3,681
ンバーであるオランダ開発金融公社(FMO)やフランス経済協力振興出資会社(PROPARCO)<br />
との共同融資を行うことも多くある。他、アジア開発銀行(ADB)などの開発銀行や国際金融公社<br />
(IFC)などとシンジケートローン 2 を行うことも多い。<br />
� 自己資本による資本参加(1 億 6,300 万ユーロ(08 年))<br />
開発援助プロジェクトの対象となっている企業に資本参加する。カンボジアのACLEDA銀行へ<br />
の援助(「Ⅱ.3.ALCEDA銀行」参照)が好例。取締役のメンバーとなり、議決権を持つ場合もあ<br />
る。<br />
� メザニンファイナンス(2 億 5,300 万ユーロ(08 年))<br />
融資と出資の中間の形態で、出資より返済条件が厳しいが、通常融資よりは柔軟。この形態の<br />
資金協力の場合、DEGは企業経営に関与しない。<br />
� 金融保証(3,300 万ユーロ(08 年))<br />
返済における為替リスクを減らすための現地通貨による長期融資や債権。<br />
資金協力は近年右肩上がりに伸びており、2008 年のDEGの新規融資は 12 億 2,500 万ユーロ<br />
と 2000 年の 3 倍以上となった。地域別の資産規模を見ると、2008 年末で 44 億ユーロ、そのうち<br />
16 億ユーロをアジアが占めている。<br />
出所:DEG資料<br />
図表 17 DEG 新規融資の推移<br />
2 シンジケートローン:複数の金融機関が協調して、ひとつの融資契約書に基づき同一条件で融資を行う資金調<br />
達方法。<br />
(100万ユーロ)<br />
1,400<br />
1,200<br />
1,000<br />
800<br />
600<br />
400<br />
200<br />
0<br />
360<br />
412<br />
464<br />
558<br />
601<br />
131<br />
702<br />
930<br />
1,206 1,225<br />
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
(イ) 技術協力<br />
BMZからの公的資金および、DEGの自己資本を利用した援助。援助相手国の金融機関へ資<br />
金協力すると同時に、リスクマネジメントなどの業務に必要な技術を教える、農業団体に長期融資<br />
をする傍ら環境基準改善のためのコンサルタントをするなど、資金協力や官民連携プログラムと<br />
同時に行うことが多い。2008 年の支援実績は 56 件。<br />
(ウ)官民連携プログラム(PPP Program)<br />
民間企業との連携プログラム。2008 年の実績は 31 プロジェクト、490 万ユーロ。99 年からの積<br />
算で 500 プロジェクトを取り扱っており、連携相手の 3 分の 2 は中小企業である。官民連携プログ<br />
ラムの取り扱い金額は小さなシェアに過ぎず、業務を取り扱う部署も技術協力と同じ一部門に過<br />
ぎないが、BMZが重要視している若いプログラムである。<br />
(エ)気候保護<br />
90 年代から始まった戦略課題。再生可能エネルギー分野、再生可能原料、CDMプロジェクトな<br />
どに投資している。2008 年の実績は 9,800 万ユーロ。<br />
(オ)中小企業支援<br />
開発途上国において資金調達を行う手段は、マイクロファイナンスか商業銀行による大企業相<br />
手の巨額なもののどちらかである。その結果、中小企業が借りるに適切な金額の長期融資が存<br />
在しないことが、ビジネスの障壁となり開発を妨げているとの考えに基づき、DEGが支援を行って<br />
いる。<br />
DEGは、開発途上国でビジネスを行う中小企業へ資金協力を行うと同時に、その企業へ他の<br />
民間資本からの投資が集まるよう手助けをする。援助形態は、開発途上国およびドイツ資本の中<br />
小製造業、サービス業、インフラなどに直接供与する場合と、他金融機関などを通じて間接的に<br />
資金協力すると同時に、DEG側で技術協力や官民連携プログラムを補完的に利用する場合があ<br />
る。2011 年までに支援金額を 10 億ユーロまで増やす予定。<br />
DEGの当初の設立目的に基づく業務である。現在では設立当初より業務は多様化し、様々な<br />
形態での開発を支援するゆえに中小企業支援の全体業務に占める割合は相対的に低下したが、<br />
現在も戦略的ターゲットのひとつとなっている。<br />
業績評価は毎年企業ごとに行っている。評価基準は、プロジェクト財務の安定および長期の収<br />
益性、開発援助の持続的安定性(雇用、環境社会基準、CSRなど)、DEGがコンサルタントおよ<br />
び開発援助の双方の役割を担っているか、DEGの株主資本利益の 4 つであり、総合点で「大変<br />
優秀」から「明らかに不十分」まで 6 段階に分けられる。2008 年の成果は、政府歳入 3 億 6,300 万<br />
ユーロ、対外資産残高 21 億ユーロ、新規雇用 3 万 5,000 人となり、評価が始まった 2002 年以来<br />
最高の数値となった。<br />
132
2)ドイツ技術協力公社(GTZ)<br />
連邦政府が 100%出資した有限会社として、1975 年設立された。現在 87 ヵ国に海外拠点を持<br />
ち、従業員は約 1 万 3,000 人(うち 1 万人は現地スタッフ)。130 ヵ国以上で開発業務を展開してお<br />
り、官民連携プログラムも実施している。<br />
二国間協定で決定した業務をBMZから委託することが業務の多くを占めているほか、他省庁<br />
や民間企業、EU、国連、世銀などからの業務の受注もある。<br />
2008 年の粗利益は 12 億 2,400 万ユーロでこのうち 9 億 8,500 万ユーロがBMZなど公的機関<br />
のプログラムからのもの。近年、プロジェクト受注数、粗利益共に順調に伸びている。<br />
図表 18 GTZの粗利益とプロジェクト契約数の推移(2005 年~2008 年)<br />
出所:GTZ Annual Report 2007,2008<br />
業務分野は大きく分けて以下の 6 つ。<br />
a.経済発展と安定的な雇用<br />
職業訓練、経済政策に対する助言、金融システムの発展、民間セクターの促進、安定的なビジ<br />
ネスにより、競争力を強化し、特に社会的弱者に対する安定的雇用をもたらす。<br />
b.民主主義と貧困削減<br />
05年<br />
06年<br />
07年<br />
08年<br />
政治改革は開発戦略の鍵のひとつであり、貧困削減、環境保護、男女同権の促進などにも繋<br />
がるという考えの下、緊急災害援助(食料供給、災害地域の再建)、平和構築活動と危機回避(紛<br />
争地域における和解と復興プロセスの支援、兵士の動員解除や社会復帰への手助けなど)、良<br />
い統治(法律および司法制度改革、財政改革、公的機関における女性の地位向上、地方自治改<br />
革など)、都市部の持続的発展(都市部のインフラおよび環境問題の改善、中小企業支援を行う<br />
地方自治体への支援など)、構造的な貧困削減(国家規模の貧困削減戦略を改善するためのキ<br />
ャパシティ・ビルティング)に取り組んでいる。<br />
粗利益 受託 進行中の委託契約<br />
876<br />
918<br />
1,153<br />
1,057<br />
1,061<br />
c.教育、健康および社会保障における人権の保障<br />
1,224<br />
1,554<br />
133<br />
1,327<br />
2,591<br />
2,707<br />
2,636<br />
2,887<br />
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000<br />
(100万ユーロ)
教育の向上(教育関係の省庁の包括的改革、教育機関や教師の質の向上、女性や障害者に<br />
対する教育の普及など)、薬物規制(麻薬栽培農家が代替産物に生産転換するための支援、栽<br />
培地の居住者の生活環境改善、中毒者のための医療施設建設・医療機器支援)、子供および若<br />
者の権利向上、HIV/AIDS 対策、社会保障の充実、に取り組んでいる。<br />
d.農業、漁業、食品産業の従事者の生活・労働環境の向上<br />
地方居住者の食料確保、経済開発と雇用確保、居住地域における天然資源の持続的管理を<br />
支援する。具体的には、沿岸域管理 3 、土地管理、農業および食料供給システムに関わる官民双<br />
方への支援、辺境居住者の生活改善に取り組んでいる。<br />
e.環境およびインフラの改善<br />
エネルギー、水、廃棄物処理、輸送などのインフラを適切に管理することで、生活改善を図る。<br />
具体的には、廃棄物管理(廃棄物処理システムが存在しない地域において、廃棄物収集、取り扱<br />
い、処理方法などについて技術支援を行う)、エネルギー安定性(地方都市への再生可能エネル<br />
ギーの普及など)、自然保護(森林保護、生物多様性の保護)、交通(道路網整備、交通網の発達<br />
による大気汚染対策など)、国際的な環境制度の改善、各国の環境政策の改善、水管理に携わ<br />
っている。<br />
f.民間部門との連携<br />
グローバルコンパクト 4 の実現を目指し、ドイツ企業のCSRを促進するほか、官民連携プログラ<br />
ム(PPP Program)に携わっている。官民連携プログラムについては一つの部署が独立して業務に<br />
あたる形態ではなく、アフリカ・中央アジア・ラテンアメリカおよびアジアの地域セクションのそれぞ<br />
れに担当者がおり、合計 50 人弱が担当している。<br />
各プロジェクトはGTZの自己評価、外部機関およびコンサルティング会社による独立評価、BM<br />
Zによる評価の 3 つの評価方法によりにより効果を判定される。評価基準はプログラムは妥当性<br />
があったか、当初の目的を達成できたか、包括的な開発援助の達成に貢献することが出来たか、<br />
コスト効率は良かったか、プロジェクトの結果は永続的に安定性のあるものか、の 5 つ。<br />
3)ドイツ経済開発・職業訓練財団(sequa)<br />
1991 年にドイツ商工会議所連盟(DIHK)、ドイツ手工業中央連盟(ZDH)が共同で設立した非<br />
3 国家、州政府、NGOなどが連携して海洋、海岸線、沿岸域にまたがる土地利用、資源管理をそれぞれの役割<br />
分担と市民参加により計画的に行うこと。<br />
4 1999 年の世界経済フォーラで、コフィー・アナン国連事務総長(当時)が企業に提唱したイニシアティブ。企業に<br />
対し、人権の保護、不当な労働の排除、環境への対応、腐敗の防止に関する 10 原則を順守し実践するよう要請<br />
している。<br />
134
営利企業。後にドイツ連邦経営者連盟(BDA)、ドイツ産業連盟(BDI)が株主に加わり、株の 51%<br />
を 4 団体が、49%をGTZが取得している。職員 13 人の小さな財団。<br />
4 つの商工会議所の企業ネットワークやGTZとの連携を活用し現在までに 100 ヵ国で 600 以上<br />
のプロジェクトに取り組んできた。GTZが国家機関なのに対し、sequa は企業から生まれた機関で<br />
あり、民間に近いといえる。業務の 80%がKfWからの委託であり、EU、UNIDO、世銀などの国際<br />
機関からの受注も受ける。<br />
開発途上国における社会的市場経済の発展と職業教育の向上を目的とし、民間セクター開発<br />
(官民連携プロジェクト含む)、ビジネス団体の設立支援、途上国との情報交換、職業教育・訓練、<br />
専門家派遣を業務としている。特に主たる業務は、大掛かりな共同出資プロジェクトにおいてキャ<br />
パシティ・ビルディングやビジネス団体設立の支援の実行。<br />
企業側からリクエストがあればプロジェクトに必要な技術者を探すが、多くの企業は深く関与さ<br />
れることを嫌う傾向にある。官民連携プログラムには 2001 年より参加、4 人の職員が担当してい<br />
る。<br />
4)国際人口移動開発センター(CIM)<br />
1980 年にGTZとドイツ連邦雇用庁による共同運営機関として設立された。職員数は 50 人。資<br />
金の大半をBMZから得ており、他省庁、NGO、民間企業とも一部連携し、専門家派遣を仲介して<br />
いる。派遣対象は国家機関、NGO、民間企業など多岐に渡る。派遣条件は、当該地域において<br />
有能で国際的業務の経験がある専門家がいないこと、雇用する組織が当該国の開発において重<br />
要な役割を担っていること、ドイツの開発援助政策の目的に合致していること、派遣された専門家<br />
は現地企業と直接契約を取り交わし、現地の標準的な給与にて採用されること、の 4 つである。派<br />
遣方法は以下の 2 種類。<br />
a.専門家派遣プログラム<br />
ドイツで就業しているドイツおよびEU諸国の専門家の派遣プログラムで、期間は 1~6 年。現地<br />
の低基準の給与にて直接雇用されるため、CIMが不足分を補完する。2004 年のインドネシアの<br />
津波災害の際にも貢献した。現在アジア、アフリカ、中南米、中・東欧の 75 ヵ国に 800 人のマネー<br />
ジャーや技術者を送り込んでいる。<br />
b.帰国者支援プログラム<br />
現在ドイツに居住し、ドイツで就業経験のある開発途上国出身の人間が、母国に帰国し開発援<br />
助業務につくことを希望している場合に、その就職斡旋および資金援助を行う。<br />
a.、b.の双方の専門家に必要な条件は、(a)最低 3 年の就業経験、(b)深い専門的知識を持ち<br />
派遣国の現地語会話に問題がない、(c)異文化を理解する高い能力を持ち、相手国の仕事のやり<br />
方に深い理解があること、(d)ドイツもしくは他のEU諸国の市民権を持っていること、の 4 つであ<br />
135
る。<br />
5)ドイツ開発援助サービス公社(DED)<br />
1963 年ドイツ政府により設立された非営利団体。貧困削減、安定的成長、資源保護などを目<br />
的とし、専門家派遣を業務としている。業務は、(a)援助対象国の政府および非政府組織の求めに<br />
そって、環境・社会基準の専門家や従業員教育のための人材を派遣する、(b)地域市民社会と地<br />
方自治体の体制をサポートし、必要な場合資金協力を行う、(c)28 歳までの新卒者を 1 年間援助<br />
対象国に派遣し、開発援助研修を行う、(d)ドイツ国内に開発途上国の実態を広め、問題意識を高<br />
める、の 4 つである。農林産物のマーケティングや、資源・水管理、HIV/AIDS 対策を含む、地域社<br />
会における健康管理体制の強化にも力を入れている。2002 年より、開発途上国の中小企業をドイ<br />
ツおよびEU諸国のサプライヤーに育てる事業を開始した。<br />
現在アフリカ、アジア、中南米の 44 ヵ国に海外拠点を持ち、職員は 270 人。47 ヵ国に 1,200 人<br />
の専門家を派遣している。<br />
6)国際再教育開発公社(InWEnt)<br />
カール・デュイスベルグ協会(CDG)とドイツ国際開発財団(DSE)の統合により 2002 年に設立<br />
された公益法人。職業訓練、人材育成を通じた国際交流を中心に調査研究などの事業も展開し<br />
ており、職業に関する専門教育コーディネート機関としては欧州最大。国内 14、海外 12 の拠点を<br />
持つ。業務の 60%はBMZの委託。他省庁、EU、世銀、IMFなどからも業務委託を受ける。<br />
職業訓練分野における官民連携も 2000 年から行っており、50 ヵ国 190 のプロジェクトを実行し<br />
ている。訓練分野は交通インフラ、環境、水、エネルギー、経営、健康、職業訓練、環境社会基準<br />
の 6 つ。<br />
7)社会改善ネットワーク(AGS)<br />
BMZが出資し設立した共同体。NGOなど 7 つの組織がアフリカ、アジア、中南米、中・東欧で<br />
活動している。メンバーは成人教育、地域開発、マイクロクレジット、社会的弱者の代弁などの社<br />
会活動に取組、開発途上国の持続的な社会制度構築や貧困削減を目指す。メンバーは以下のと<br />
おり。<br />
a.労働者福祉教会(AWO international)<br />
1998 年設立のNGO。アジアと中南米 7 ヵ国で人道援助を行っている。職員 140 名。<br />
136
.ブレーメン海外研究開発連合(BORDA)<br />
1977 年設立のNGO。2001 年よりアジアやサブサハラアフリカの貧困層に対して、水、保健衛生<br />
などのサービス提供を中心に活動。例えばベトナムでは、農村給水プロジェクトを実施中で、現地<br />
ニーズにあった給水ポンプの開発・提供を実施。ドイツ中小企業と共同で途上国プロジェクトを実<br />
施するケースもある。全世界 250 人の従業員。<br />
c.ドイツ・カリタス(Caritas)<br />
国際NGOカリタス・インターナショナルの傘下組織。世界各地の緊急、災害援助、子供や若者、<br />
障害者、傷病者などの社会的弱者に対する社会活動を主に行っている。<br />
d.ドイツ労働総同盟(DGB)<br />
1949 年設立。ドイツの労働組合の中央組織。ドイツと援助対象国にILOの労働基準を取り入れ<br />
るロビー活動を行うほか、ブラジル、ネパールなどで失業者支援プログラムを立ち上げている。<br />
e.ドイツ協同組合・ライフアイゼン連合体(DGRV)<br />
ドイツの協同組合の上部組織。傘下に 9 万の企業と 1,600 万人のメンバーを有している。開発<br />
途上国の金融、農業セクターや中小企業などにおける協同組合の設立・改良について支援を行っ<br />
ている。<br />
f.ドイツ成人教育協会国際協力研究所(IIZ/DVV)<br />
1963 年設立。ドイツの 1,000 の成人教育センターの国際的連携機関で、非営利のNGO。開発<br />
途上国における成人教育の発展を支援している。<br />
g.KOLPING International<br />
1850 年に設立された教会組織。60 ヵ国 45 万人の会員がいる。開発途上国の収入向上のため<br />
の職業教育機関の設立や、教育施設の充実に取り組んでいる。<br />
官民連携プログラム 5<br />
ⅰ)設立の背景<br />
1990 年代、ドイツでは開発援助に関わる民間企業の数が増加し、国有企業の民営化支援や、<br />
開発途上国における環境保護やマイクロファイナンスへの出資などが多数行われていた。当初B<br />
MZは、多大な開発援助効果のある巨大プロジェクトのみに支援をしていたが、ドイツにおけるOD<br />
5 インフラや学校などを作る際に公的機関と民間企業が連携する「官民連携」は多くあるが、ここで言う「官民連携<br />
プログラム」とは 99 年に BMZ が設立した「PPP facility(現在の「PPP Program」)のことである。「PPP Program」<br />
以外には、「PPP Program」に関わるGTZ、DEG、Sequaの他、DED、CIM、InWEnt も民間との共同プログラム<br />
を実行している。<br />
137
A予算の減尐により開発援助政策の目標達成が難しくなったことから、民間の資金を幅広く利用<br />
するべきという議論が出るようになり、1999 年、官民連携ファシリティ(Public Private Partnership<br />
Facility)が設立された。開発援助に民間企業のリソースを投入して官のみで行うよりも効果的か<br />
つ効率的な結果を得る一方、開発援助機関は障害が多い開発途上国ビジネスにおいて民間企<br />
業をサポートし、スムーズなビジネス展開を手助けする、WIN-WIN の関係を目指したプログラムで<br />
ある。既に対象国で社会的ビジネスを行っている場合や、相手国への投資、ジョイントベンチャー<br />
なども対象にしている。<br />
2009 年にスキームを分かりやすく改編し、官民連携プログラム(Public Private Partnership<br />
Program)となった。<br />
ⅱ)官民連携プログラムの近年の実績<br />
1999 年から 2008 年までの 10 年間、ドイツで公的機関と民間企業が連携して行った開発援助は<br />
70 ヵ国以上、総計 186 億ユーロ規模、約 3,100 件にのぼる。連携のツールとして、官民連携プログ<br />
ラム、技術協力、資金協力及びDEGの長期融資の 3 つの形態に分類される。<br />
図表 19 ドイツの開発援助における、官民連携事業の資金提供規模の変遷<br />
官民連携プログラム 技術協力<br />
出所:BMZ(2009), Annual report 2008<br />
138<br />
(100万ユーロ)<br />
資金協力及びDEG<br />
(長期融資) 合計<br />
官 民 官 民 官 民<br />
1999 13.5 19.8 3.3 4.7 103.7 35.8 180.8<br />
2000 22.2 37.2 6.9 6.2 291.5 383.3 747.3<br />
2001 18.0 32.7 1.2 1.3 416.6 1,163.7 1,633.5<br />
2002 19.2 29.7 5.3 4.5 488.9 1,051.2 1,598.8<br />
2003 15.7 26.9 12.6 12.7 334.4 1,843.7 2,246.0<br />
2004 17.2 26.0 9.0 22.0 612.1 922.7 1,609.0<br />
2005 22.0 35.1 12.5 16.3 669.9 977.9 1,733.7<br />
2006 17.5 29.2 11.7 19.0 799.7 1,640.6 2,517.7<br />
2007 23.3 33.6 14.3 16.8 891.7 2,854.2 3,833.9<br />
2008 13.1 19.1 7.1 12.8 895.7 1,593.3 2,541.1<br />
計 181.7 289.3 83.9 116.3 5,504.2 12,466.4 18,641.8
図表 20 官民連携プログラム、技術協力、資金協力の分布<br />
(1999 年~2008 年)<br />
金融システム<br />
(KfW開発銀行)<br />
4%<br />
その他<br />
4%<br />
出所: Annual Report 2008, BMZ<br />
官民連携プログラム、技術協力、金融協力をあわせた資金規模を見ると、資金協力及びDEG<br />
長期融資の規模が 9 割を占める。<br />
持続的経済発展<br />
33%<br />
図表 21 官民連携プログラム、技術協力、資金協力の産業別規模<br />
(1999 年~2008 年)(資金規模)<br />
エネルギー<br />
1%<br />
教育<br />
0%<br />
投資促進<br />
(DEG長期融資)<br />
17%<br />
出所:Annual Report 2008, BMZ<br />
2008 年には世界金融危機にもかかわらず、計約 25 億ユーロ、300 件以上の案件が実施された。<br />
ここ 10 年の資金協力、技術協力も含めた官民連携プロジェクトの地域分布をみると、アジア<br />
(1,111 件)、アフリカ(812 件)、ラテン・アメリカ(592 件)の順となる。<br />
保健<br />
2%<br />
農業<br />
0%<br />
交通・通信<br />
1%<br />
139<br />
教育<br />
4%<br />
環境<br />
0% 水<br />
2%<br />
その他<br />
0%<br />
エネルギー<br />
4%<br />
保健<br />
6%<br />
農業<br />
9%<br />
水<br />
5%<br />
金融システム<br />
(KfW開発銀行)<br />
4%<br />
投資促進<br />
(DEG長期融資)<br />
89%<br />
交通・通信<br />
2%<br />
環境<br />
12%<br />
持続的経済発展<br />
1%
図表 22 官民連携プログラム、技術協力、資金協力の地域分布<br />
(1999 年~2008 年)(プロジェクト数)<br />
(件)<br />
アフリカ アジア ラテン・アメリカ 中東 東欧 複数地域 合計<br />
官民連携プログラム 276 473 190 34 116 21 1,110<br />
技術協力 361 391 246 12 181 5 1,196<br />
金融協力及びDEG融資 175 247 156 39 149 19 785<br />
合計 812 1,111 592 85 446 45 3,091<br />
出所:BMZ(2009), Annual report 2008<br />
ⅲ)官民連携プログラムの構成<br />
本プログラム資金源はBMZで、具体的な実行は各フレームワーク担当の実施機関(DEG、GT<br />
Z、sequa)と民間企業に委ねられる。対象となる民間企業はドイツおよび欧州企業、もしくは資本<br />
を欧州に持つ欧州域外の支店。2009 年、従来の「官民連携ファシリティ」を「官民連携プログラム」<br />
に改編、PPP プログラムは、a.develoPPP.topic、b.develoPPP.innovation、c.develoPPP.alliance<br />
の 3 つの枠組みを編成された。<br />
・再生可能エネ<br />
ルギー<br />
・産業環境保護<br />
(2009年)<br />
出所:BMZ(資料)<br />
a.develoPPP.topic<br />
図表 23 官民連携プログラムの枠組み<br />
develoPPP.de<br />
(BMZの官民連携プログラム)<br />
プロジェクトは企画競争で決定する(公的支援は最大で20万ユーロ)<br />
develoPPP.topic develoPPP.innovation develoPPP.alliance<br />
・エネルギー効率<br />
・健康・社会安全<br />
(2009年)<br />
・職業教育<br />
・教育<br />
・品質管理<br />
(2009年)<br />
deveoPPP.topicに<br />
入らないトピック<br />
高度に革新的な<br />
プロジェクト<br />
予め決定された分野における民間ビジネスを支援するスキーム。分野はBMZにより毎年決定<br />
される。官側の実施機関は、DEG(09 年のテーマは再生可能エネルギー、産業環境保護)、GTZ<br />
(エネルギー効率、健康・社会安全)、sequa(職業教育、教育、品質管理)。<br />
develoPPP.topic を実行するための必須条件は(a)ドイツ政府の開発目標・目的に沿っている、<br />
(b)官民の相互補完により目的をより効率的、効果的に達成できる、(c)官なしに実行出来ないプロ<br />
140<br />
"Strategic Alliance"<br />
・複数の企業が複数の国で実行<br />
・高い開発援助効果<br />
・公的支援が20万ユーロ超<br />
With DEG With GTZ With sequa With DEG With GTZ With DEG With GTZ
ジェクトである、(d)競争の中立性が確保される。民間企業とDEG/GTZ/sequaとの協業は全企<br />
業に開かれており、情報交換も透明性高く実施される、(e)官民連携プログラム実施にあたり企業<br />
は財政的・人的貢献をする(民間セクターの貢献は尐なくとも全コストの 50%)、の 5 つである。ま<br />
た、企業側の資金は借入金ではなく、自己資金であることが求められている。<br />
b.develoPPP.innovation<br />
develoPPP.topic に入らない分野および、高度に革新的なプロジェクトを実施する民間ビジネス<br />
を支援。官側の実施機関はDEGとGTZ。<br />
a、b のプロジェクト実行の条件は、10 人以上の従業員がいる企業であること、3 年以上相手国<br />
市場における経験があること、1 年当たり 100 万ユーロ以上の売上高を確保出来ること、予算は<br />
最大 40 万ユーロであり、企業は最低 50%のコストを負担し、援助機関からの資金供与は 1 プロジ<br />
ェクト当たり最大 20 万ユーロであること、対象国におけるビジネスに長期にわたって関わり、プロ<br />
ジェクトが安定的になるまでのフォローアップをすること、(f)BMZが定めた国/テーマであること、<br />
の 6 つとなっている。<br />
図表 24 官民連携プログラムの公開スケジュール<br />
テーマ 締め切り 実行機関<br />
教育 2010年2月15日~3月31日 sequa<br />
エネルギー効率 2010年2月15日~3月31日 GTZ<br />
再生可能エネルギー 2010年2月15日~3月31日 DEG<br />
健康 2010年2月15日~3月31日 GTZ<br />
産業環境保護 2010年2月15日~3月31日 DEG<br />
イノベーション<br />
出所:BMZ ホームページ<br />
2010年2月15日~3月31日 DEG,GZ<br />
プロジェクトは企画競争により選定され、支援機関より全費用の最大 50%、最大 20 万ユーロま<br />
での支援を受けることができる。期間は最大 3 年間。企画競争スケジュールについてはBMZが運<br />
営の develoPPP.de ホームページにて公開されている。<br />
上記に記したとおり、プロジェクトを行う上での最低参加条件は定められているが、最低資本金<br />
額や最低従業員数といった規定はなく、また上限も無い。中小企業から大企業まで幅広く支援を<br />
行っているが、零細企業では上記の基準を満たすことは難しい。<br />
141
【企画競争】<br />
毎年 4 回締切りがあり、企業は官民連携プログラムのアイデアをGTZ/Sequa/DEGに提出す<br />
る。BMZはガイドラインを作る役割を担い、コンペの審査には参加しないため採択決定権は各援<br />
助機関にある。2009 年のsequaのコンペでは、毎回 16~18 件の応募があり、最終的には半数程<br />
度が審査に通った。<br />
審査過程:<br />
ア.官民連携プログラムに関心のある企業が、各機関のテーマごとに定められた締切りに従い、<br />
プロジェクトの概要を提出する(英語も可)。<br />
イ.既存の審査基準に従い、各機関の担当者が提出プログラムの可否を審査する。この際、プ<br />
ロジェクトを緑(非常に良い)、黄(改善の余地有)、赤(官民連携プログラムとして機能していない)<br />
に分けて、緑と黄を合格とし、3 週間以内に審査プロセスと結果を企業に知らせる。<br />
ウ.企業とディスカッションを重ね、プロジェクトの全体像や援助期間を決定すると同時に、より<br />
官民連携の理念に近づくようにフォローアップする。ファイナンスの状況、実際にかかるコストなど<br />
もこの時点で詳細を詰める。援助機関側はこのプロセスを非常に重要視している。例えば、ある<br />
企業から提示されたプログラムが援助対象国の支店における現地スタッフの訓練施設の建設だ<br />
とすれば、援助機関側はトレーニングの対象を、プログラム提示企業の社員だけでなく他企業の<br />
スタッフにも広げることにより、開発援助としての意義を高めていく。<br />
エ.企業と契約し、スタートアップのために資金の 3 割を与える。<br />
オ.企業が成果をレポートし、援助機関は更に資金の残りを与える。<br />
c.develoPPP.alliance<br />
複数企業による地域をまたぐ大規模プロジェクト。官側の実施機関はDEGとGTZ。下記の量的<br />
条件、質的条件のうち、最低 6 つ(うち 2 つ以上が質的条件)を満たしていることがプロジェクト実<br />
行基準である。<br />
量的条件とは、最低 2 ヵ国以上(ブラジル、インド、中国の場合は最低 2 地域以上)で実行され<br />
ること、最低 2 社の民間企業がプロジェクト実行の主な役割を果たすこと、プロジェクトの合計資金<br />
が、官民合わせて最低 75 万ユーロであることの 3 種。<br />
質的条件とは、開発援助政策にとって、平均水準以上に意義があり、他のプロジェクトの手本と<br />
なること、援助相手国の重要機関(経済構造枠組みなどに顕著な影響を与える機関)がプロジェク<br />
トに関わること、多数の利益団体が関わるプロジェクトであり目的も多岐に渡ること、経済的・社会<br />
的に恵まれない人口層に対して広く好影響を与えること、高度に革新的なプログラムとして突出し<br />
142
ていること、ベストプラクティスとして将来再現可能なプロジェクトであること、二国間開発援助に定<br />
められたテーマとつながりがあること、の 7 つである。<br />
ⅳ)官民連携プログラムの問題点<br />
企画競争において、多くの企業はGTZ/Sequa/DEGのうちどの機関が自分のプロジェクトに<br />
ふさわしいか分からずに援助機関に問い合わせ、また援助機関側もそれに明確な回答を返すの<br />
が難しいことがある。また、プロポーザルの正式なプロセスが無い。官民連携ファシリティから官<br />
民連携プロジェクトへの編成で多尐は是正されたが、未だ大きな問題点。また、官民連携プロジェ<br />
クトは資金協力や技術協力と違い、各プロジェクトの規模が小さすぎるため、プロジェクト終了後<br />
の評価は出来ないのが現状。時折プロジェクトを行った国を訪ねて後の状況を見たりするが、機<br />
会はかなり尐ない。<br />
ⅴ)ドイツにおける官民連携プログラムの認知度<br />
民間企業への認知が最も重要。パンフレットなどの宣伝資料を多数作成し、多くの企業に関心<br />
の高い開発途上国・地域のサミット、セミナーなどでプレゼンするほか、ドイツ工業連盟(BDI)など<br />
他機関と共にセミナーやイベントを開いている。ドイツ国内での認知度は 10 年前のスタート時期よ<br />
りも高まっているが、他国においてどの程度広まっているかは不明であり、企画競争に他国が応<br />
募する機会はいまだ尐ない。<br />
ⅵ)「官」と「民」との連携<br />
ドイツの官民連携プログラムは民間企業へ投資を呼びかけるプロモーションとは異なり、企業<br />
側がどの国でどのようなプロジェクトを行うのかを全て決定するため、官側が企業のコアビジネス<br />
へ関わることはなく、この点は現在描かれている我が国の<strong>経済産業省</strong>のプログラムと異なってい<br />
る。<br />
開発支援と民間企業ビジネスの目的は必ずしも一致しないが、ドイツの官民連携ではあくまで<br />
この両方を追及することを前提としている。往々にしてビジネスサイドに近いプロジェクトであるほ<br />
どに、企業側は商業利益の拡大や、その前段階である将来のマーケットを確保するための改善<br />
策を積極的に実践し、成功し安定性を得られる確率が高い。<br />
社会民主党(SPD)が政権政党となったここ 10 年、特に大連立後にBMZの大臣がSPD出身と<br />
なって以降は、「貧困とは政府が主体となって解決すべき問題であり、その支援形態は政府対政<br />
府の巨額事業で行うべき」という考え方が主流だった。そのため二国間援助は旧来型の道路、病<br />
院などの建設のための資金供与が主であり、マイクロファイナンスや民間企業による開発援助は<br />
低調だった。しかし、2009 年9月の政権交代により自由民主党(FDP)の閣僚がBMZ大臣となり、<br />
民間企業の開発援助参加への関心が強いことから、今後政権政党のバックアップによる規模拡<br />
大を期待できる。他国でもドイツと同じく開発援助と民間利益を融合したビジネスを官側でサポー<br />
トする動きがあり、現在はオーストリアでのプログラム設立のためにGTZから人材を派遣してい<br />
143
る。<br />
ただ一方で、ドイツは国の産業が重工業中心であり、発電所や自動車に代表されるようにひと<br />
つの商品は高額かつ巨大。日本や韓国のように消費者グッズや細かな電気機器などに強い産業<br />
構造ではなく、そもそもBOP層に向く製品を取り扱う企業が尐ないため、ビジネスチャンスとして<br />
のBOP市場への進出には限界があるとも考えられる。<br />
また、BMZは独立した省庁であるが、小規模の組織であるため、開発援助の一助を担う外務<br />
省や、国内の利益追求を重視する経済技術省など大省庁の利害の違いに挟まれて方針が決ま<br />
らないことも多く、官民連携が始まって 10 年の現在でもこの問題は解決されていない。<br />
(2)支援スキーム活用事例<br />
① KAEFER AIDS RELIEF PROGRAM(KARP)<br />
KAEFER 社(ドイツ断熱材メーカー大手/本社ブレーメン)とGTZの官民連携プログラム。同社は<br />
南アフリカに 30 年前から進出しており、同地で 1,400 人の労働者を雇用している。従業員の多くは<br />
元から HIV/AIDS への感染率が高く、衛生教育が行き届かない地域に住んでおり、社内検査で<br />
25~30%の社員が HIV/AIDS に感染している危険があるという結果が出た。2005 年に従業員 6 人<br />
が死亡したことをきっかけに、感染者の欠勤、死亡による生産性の低下を改善するため、CSR活<br />
動の一環として KAEFER 南アフリカ社は「KAEFER AIDS RELIEF PROGRAM(KARP)」を立ち上げ<br />
た。自発的カウンセリングとテスト法 6 を実行するための地元住民を含むスタッフのトレーニング、<br />
エイズ予防キャンペーンの実施などを行い、2006 年にはNPO法人の南ア HIV/エイズビジネス連<br />
盟(SABCOHA)も同プログラムに参画した。<br />
KAEFER ドイツ本社が KAEFER 南アフリカ社に代わってGTZへ官民連携プログラムの実行を申<br />
請し、2008 年連携が始まった。GTZは資金面、技術面の双方から協力し、衛生教育を行うための<br />
スタッフの提供や、教育プログラムの効果予測を行い、地元に健康管理センターを設立するため<br />
の交渉に取り組んだ。KAEFER 社は衛生教育を低収入層に受けさせ、医療ケア施設へのアクセス<br />
改善に取り組んだ。<br />
2008 年にはカウンセリングおよび陽性検査は年に 2 回、全ての建設現場で行われるようになり、<br />
従業員の 78%がこのプログラムを利用し、陽性判定を受けた人間の 80%以上が、独立基金による<br />
健康管理サービスを受けている。<br />
6 HIV 抗体テストや感染予防カウンセリングなど自主的に受けるエイズ予防プロジェクト<br />
144
② Compware Medical 社の代替治療システム<br />
Compware Medical 社(代替治療のソフト・ウェア開発および販売業務/本社:ゲルンスハイム)と<br />
GTZの官民連携プログラム。<br />
同社は 1996 年に「MeDoSys システム」をドイツ国内で実用化した。これは、ヘロインなどの麻薬<br />
中毒者に対する麻酔薬である、メタドンによる代替治療システムであり、コンピューターによって患<br />
者のデータを管理し、患者の状態に応じたメタドン治療のスケジュールを作成し、薬の服用量を調<br />
整するシステムで、ドイツを中心とする欧州内で 1 日 2 万人の患者に対応している。対象者は麻薬<br />
中毒者のため、365 時間 24 時間体制で管理を行う。<br />
2007 年、GTZから Compware Medical 社へアプローチし、インド、ネパール、インドネシアにおい<br />
て 37 万 5,000 ユーロを半々の資金負担で官民連携プログラムを開始した。GTZは医薬品専門家<br />
の教育と、代替医療の普及のためのスタッフ教育を請け負い、Compware Medical 社はメタドンに<br />
よる代替治療のモデルとなる診療所の開設場所を決定し、メタドンの安定供給と代替医療関連機<br />
器の配付を行うほか、24 時間 365 日体制の英語および現地語でのホットラインを開設した。2009<br />
年4月にはネパールで第一の診療所が開かれ、イラン、パキスタン、マラウイなどからも同プロジ<br />
ェクトへの関心が寄せられている。<br />
Compware Medical 社は事業収益を上げるところに至ってはいない。将来のビジネスチャンスの<br />
ための先行投資として行っており、代替治療システムや関連機器の販売・リースへ繋がる形を期<br />
待している。<br />
③ ACLEDA 銀行<br />
KfW、GTZ、国連開発計画(UNDP)、米国国際開発局(USAID)、国際労働機関(ILO)など多<br />
数の国際機関、開発途上国支援機関が援助に参加したプロジェクト。1993 年に 30 名弱で発足し<br />
たカンボジアの零細企業発展のためのNGO”ACLEDA”へのグラント事業として始められた。ドイ<br />
ツの援助機関の中では、KfWがグラント資金の援助、GTZが技術協力を行い、DEGはNGOから<br />
銀行へ形態を変えた際に投資している。援助が始められた当初はグラント援助の金額が 100 万ユ<br />
ーロレベルと小さかったこともあり批判が多く、その程度の金額では何も意味が無いという声が殆<br />
どだったが、マイクロファイナンスの成功によりカンボジア全土に支店を構えるようになり、事業が<br />
安定したため、2003 年に商業銀行となった。<br />
現在ではカンボジア最大の銀行として国内全県・都市に 232 の支店、7,000 人超の社員を抱え<br />
る銀行へと成長し、2000 年から 2008 年までの平均資産成長率は年間 53%増、2008 年の総資産<br />
額は 6 億 9,300 万ドルとなった。2008 年 1 月、ラオスへ 3 支店を開設し、海外進出を果たしたほか、<br />
国内に独自のマイクロファイナンス訓練センターを設立して、地場の銀行に金融トレーニングを行<br />
っている。<br />
145
④ Financial Wellness Program<br />
BMW 南アフリカ社とGTZの官民連携プロジェクト。2001 年に行われた調査の結果、南アの自動<br />
車産業に従事する約 3 分の 1 に収入以上の負債があった。これらの人々は毎月の収入が殆ど支<br />
払いに消えてしまうため、労働意欲が低下し、生産性悪化し、更に収入が減り負債の返済が滞る、<br />
という悪循環に陥っていた。<br />
この結果を鑑みて、2005 年に BMW 南アフリカ社はプレトリア大学の協力を得て金融知識の教<br />
育キャンペーンを始めた。同年、GTZに Financial Wellness Program を提案、負債/収入管理、法<br />
的アドバイス、紛争予防、精神・社会的ケアを含む包括的職場プログラムを実行した。結果、2008<br />
年のプログラム終了までに、BMW南アフリカ社の社員全体の負債を57%減らすことに成功した。労<br />
働意欲の向上により常習的欠勤が減尐し、BMZ南アフリカ社の利益は向上した。<br />
⑤ Fruit Trading Academy<br />
ドイツ卸売・貿易業連合会(BGA)とsequaの官民連携プロジェクト。エジプトは欧州市場にとっ<br />
て重要な生鮮果物、野菜の供給地であるが、エジプトの多くの輸出業者はEUの複雑な輸入規<br />
制・規則や高品質商品の貿易障壁について知識がない。そのため、ドイツの輸入業者は、通関の<br />
遅れや必要以上に高額となる輸送費、時には全ての品物が通関で止められてしまう被害にあっ<br />
ていた。<br />
sequaとBGAはこの状況を改善するため、ローカルNGOのエジプト農業連盟(EAGA)などと<br />
協力し、2003 年に“Fruit Trading Academy”を設立した。エジプトの貿易会社に勤める従業員 120<br />
名を 2005 年までに訓練し、欧州エジプト間の貿易に対する知識を身につけさせた。結果、不正確<br />
なラベリングや貿易の遅延が減尐し、ドイツの貿易会社のロスタイムが減尐した。<br />
⑥ Cotton made in Africa(CmiA)<br />
“Strategic Alliance”のひとつ。サブサハラアフリカでは現在約 2 千万人が綿花で生計を立てて<br />
おり、品質の良さにも関わらず、その多くが生産性の低い小さな土地で農業を営んでおり、綿花の<br />
低価格と支払いの遅延に苦しめられている。また、識字率が低く化学肥料の取り扱い説明書を読<br />
めないことから、使用方法を誤り、健康被害を起こすことも多い。<br />
CmiAは 05 年に OTTO グループ(通信販売大手)がイニシアティブを取りはじめたプロジェクト。<br />
小規模農家の生産性を高めて収入を守り、彼らの健康状態を改善することにより、高品質のアフ<br />
リカ綿花を確保するという目的で行われている。OTTO 社を中心とする衣料品業者が連携し、アフ<br />
リカ産木綿製品の長期かつ安定的な買い入れを約束すると同時に、DEGは資金援助を行い、G<br />
TZが綿花の品質の保ち方、農薬および肥料の安全かつ適切な使用方法を教え生産性を向上し<br />
アフリカ綿花の競争力を高める役割を担った。また、世界自然保護基金(WWF)やドイツ世界飢餓<br />
146
援助機構(DWHH)などの、NGOや民間機構などの支援も受けている。<br />
CmiAで生産された商品は、共通ロゴを付けられ、ひとつのブランドを形成し、高品質を保障す<br />
ると同時に、取り扱い企業のCSRのアピールともなっている。取り扱い業者は、当初は OTTO 他 2<br />
社だったが、現在 20 社以上に拡大した。2009 年までに農業訓練を受けた数は 12 万人に上り、<br />
2010 年の綿花買い入れ予定は 6 万トンとなっている。<br />
147
148<br />
概要<br />
図表 25 ドイツの主な支援機関の活動<br />
支援金額(2008年)<br />
事例数(2008年)<br />
出所:各機関ホームページ等によりジェトロ作成<br />
GTZ DEG sequa CIM DED inWEnt KfW<br />
ドイツ連邦政府が100%出資<br />
した有限会社。二国間協定で<br />
決定した業務をBMZから委託<br />
されることが業務の大半だ<br />
が、他省庁や民間企業、EU、<br />
国連などからの受注も。<br />
1,220万ユーロ(PPPファシリテ<br />
640万ユーロ、技術協力580<br />
万ユーロ)<br />
78件(PPPファシリティ32件、<br />
技術協力46件)<br />
開発に係る民間企業の支援<br />
を通じた途上国の持続的成長<br />
と生活水準の向上が目的。<br />
BMZの監視下で金融部門を<br />
中心に幅広いセクターに投<br />
資。支援企業はドイツ企業に<br />
限定されておらず、ドイツの利<br />
益と関わらない事業も。<br />
PPPファシリティ490万ユーロ、<br />
DEG長期融資6億6,590万<br />
ユーロ<br />
PPPファシリティ31件、DEG長<br />
期融資66件<br />
ドイツの4つの商工会議所が<br />
職業訓練、人材育成を通じた 貧困削減、グローバル化のな<br />
出資する非営利企業。途上国 GTZとドイツ連邦雇用庁によ 連邦政府による非営利団体。<br />
国際交流を中心に調査研究 かでの公平性、自然資源保<br />
における社会的市場経済の る共同運営による専門家派 貧困削減、安定的成長、資源<br />
などの事業を展開するなど、 護、平和実現を使命とし、BM<br />
発展と職業教育の向がを目 遣を仲介機関。派遣にはドイ 保護などを目的とし、専門家<br />
職業に関する専門教育コー Zに代わって二国間援助など<br />
的。主たる業務は大規模な共 ツの開発援助政策の目的に 派遣に従事。途上国の中小<br />
ディネート機関としては欧州 の資金協力を実施。BOP層を<br />
同出資プロジェクトにおける 合致することなどの条件に合 企業をドイツ・EUのサプライ<br />
最大の公益法人。業務の6割 対象にした業務ではマイクロ<br />
キャパシティ・ビルディングや 致する必要あり。<br />
ヤーに育てる事業も開始。<br />
はBMZの委託。<br />
ファイナンスがメイン。<br />
ビジネス団体設立支援など。<br />
PPPファシリティ180万ユーロ 技術協力60万ユーロ 技術協力60万ユーロ 技術協力10万ユーロ 資金協力2億2,980万ユーロ<br />
PPPファシリティ11件 技術協力11件 技術協力61件 技術協力2件 資金協力43件<br />
資金負担割合 最大50% 最大50% 最大50% 最大50% 最大50% 最大50%<br />
パートナー企業の国籍 EU<br />
パートナー連携支援<br />
現地BOP層への普及活動<br />
技術開発の促進<br />
ビジネスインフラ整備<br />
プロジェクト具体例<br />
EU(中小企業支援については<br />
BMZ決定した支援対象国資<br />
本も)<br />
現地の供給・請負業者の選<br />
開発途上国およびドイツ資本<br />
定、スペシャリスト・マネジメン<br />
の開発途上国ビジネス支援<br />
ト人材育成<br />
農耕能力構築、環境・社会標<br />
準の普及<br />
農業関連技術の活性化、研<br />
究教育機関育成、パイロット<br />
設備<br />
金融システムの確立、資産運<br />
用、環境基準の改善<br />
職業訓練システムの強化、健<br />
康保険の導入、雇用者に対 資産運用、金融リスクマネー<br />
するメディカルケアシステムの<br />
ジメント<br />
導入支援、金融部門育成<br />
ドイツ断熱材メーカー大手<br />
のKAEFER社と連携し衛生教育のスタッ<br />
フ派遣や健康管理センターの設立に協<br />
力(南ア)<br />
EU 支援対象国<br />
現地の職業教育・訓練<br />
CIMが決定した場所に対する<br />
民間企業専門家の派遣<br />
ビジネス団体の設立支援 環境・社会基準の普及、市場<br />
指向型組織の形成<br />
EUもしくはBMZが決定した支<br />
援対象国<br />
サプライヤー育成(パートナー<br />
は開発途上国企業)<br />
環境基準の改善、気候保護 - - 資源・水管理<br />
- -<br />
Cotton Made in Africa<br />
サブサハラの綿花の品質保全と競 貿易取引を円滑に進めるため ディーゼル発電(ガーナ、タン<br />
争力強化を目指 (サブサハラアフリ のトレーニング(エジプト) ザニア、マラウイ)<br />
カ)<br />
不明<br />
(各種融資スキームなどが存<br />
在)<br />
EUもしくは開発途上国 支援対象国など<br />
専門家派遣、職業訓練<br />
ドイツを含むEU諸国へのサプ<br />
職業訓練、環境・社会基準の<br />
ライヤー育成、環境社会基準<br />
普及<br />
の普及<br />
農林産物のマーケティング、<br />
HIV/AIDS対策<br />
絹の生産<br />
(ルワンダ)<br />
交通インフラの整備、環境、<br />
水、エネルギー保護<br />
技術者、経営者を対象とした<br />
上級教育<br />
バイオガス<br />
(中国)<br />
貧困層の貧困削減、生活状<br />
況改善に資する諸活動支援<br />
マイクロファイナンスの普及<br />
気候変動、エネルギー、金融<br />
システムの発展、ガンバナン<br />
ス、健康、廃棄物処理、水<br />
資産運用、金融リスクマネジ<br />
メント<br />
ALCEDA銀行<br />
(カンボジア)
(1)BOPビジネスに関わる政府の役割<br />
① 政府の支援方針・体制<br />
1)開発支援政策<br />
3.フランス<br />
1789 年に勃発したフランス革命以降、フランスは一貫して「人間的な連帯」(solidarité humaine)<br />
を求めてきた。この原則は 1848 年の 2 月革命、アフリカにおけるフランスの植民地政策を明確に<br />
した 1944 年のブラザビル会議をはじめ、戦後のフランスの海外支援の基本となっている。<br />
「連帯」と同時にフランスの対外支援政策を特徴づけているのは「フランスの栄光」、とくに文化<br />
的な側面での栄光であり、支援全体の大半が旧植民地であるフランス語圏アフリカ向けという事<br />
実がこのことを物語っている。これに加え、支援政策が「国益」に合致していること、この 3 点がフ<br />
ランスの開発支援政策の柱といえる。ポンピドゥー首相(当時)は 1968 年に、開発支援政策の中<br />
で、「全人類にとって価値のある道徳的・人道的理由」から開発政策を進める旨を明らかにしてい<br />
る。この原則はジスカールデスタン大統領(当時)にも引き継がれ、その後に大統領に就任したミ<br />
ッテラン大統領(当時)もこの路線を踏襲、開発政策を「(先進諸国と途上国の)相互の連帯と責任」<br />
と規定した。シラク氏が大統領に就任(1995 年)したあとの 1998 年以降、開発援助機関や組織の<br />
一連の改革(後述)が実施されたが、援助政策の概念は基本的にはこれまでの伝統に立脚するも<br />
のであった。2007 年 5 月に新たに大統領に就任したサルコジ氏は伝統的にフランスとの結びつき<br />
の強い仏語圏以外にも経済力や地域における重要性が増しつつある国(例:アンゴラ、南アフリカ)<br />
との提携関係を深めるといったより現実的で戦略的なアプローチをとり、これまでのフランスの途<br />
上国開発政策と一線を画している。<br />
フランスの開発支援をみると、支援スキームという狭義の概念ではなく、むしろより広義の支援<br />
概念(「共同開発」と「国際移動」)が存在し、それに基づいてプロジェクトを策定、実施しているよう<br />
である。<br />
80 年代にでてきた「共同開発」(Codéveloppement)の概念は、アルジェリア、インド、メキシコな<br />
どの新興国とフランスとの間でパートナーシップ契約を結ぶことを目的としていた。90 年代にはい<br />
ると上記の「共同開発」の概念が「国際移動」(Migrations internationales)の概念へと発展した。す<br />
なわち、開発途上国からフランスに移住している人々(主に高学歴者など)に対して本国の経済発<br />
展のために帰国させる、あるいはこれらの人々が本国でビジネス活動などを行なう際にNGOを通<br />
じて支援する方向を打ちだした。「共同開発と国際移動」の概念は内容に若干の変化がみられる<br />
ものの、引き続きフランスの開発途上国支援の中核をなしている。<br />
149
支援対象地域は旧仏領植民地を中心としたアフリカ諸国に重点が置かれている。90 年代半ば<br />
以降は、英語圏、あるいはカリブ諸国へと拡大しているものの、支援の 3 分の 2 はアフリカに向け<br />
られている。実際アフリカは 2000 年に策定された国連ミレニアム計画の目標達成のために最も支<br />
援が必要な地域であり、フランスは 2001 年に設立されたアフリカ開発のための新パートナーシッ<br />
プ(Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique、NEPAD)・イニシアティブを通じて支<br />
援している。<br />
「共同開発」を推進するため、フランスは国際協力開発のための政府間委員会 (Comité<br />
Interministériel pour la Coopération Internationle et le Développement、CICID)を 1998 年に設置<br />
した。2004 年の会合では、国連ミレニアム計画(給水と水処理、保健とエイズ撲滅、農業と食品安<br />
全、サブサハラ諸国のインフラ整備、環境・生物多様性の保護)実施に向けたフランスの目標が<br />
策定された。2005 年には、優先連帯地域(Zone de Solidarité Prioritaire、ZSP) 1 を対象に、支援の<br />
ための新ツール「提携枠組み文書 (Document Cadre de Partenariat、DCP 2 )」を導入している。<br />
一方、開発途上国開拓のための先進国企業の進出が 1980 年代以降活発化してきたことに加<br />
え、フランスではODA予算の制約によりODAだけで独占的に大型事業に融資を行なうことが困<br />
難になった。このため政府は企業、協会、大学、研究所などの公的機関以外の組織も途上国支<br />
援のプレイヤーに加えることを試みている。<br />
フランスは 1998 年に国際協力体制の改革に着手し、ZSP、フランス開発庁(AFD)の設置をは<br />
じめ、国際協力高等理事会(Haut Conseil à la Coopération Internationale、HCCI、国際協力のた<br />
めの民間の様々なプレイヤー間の定期的な調整を行なう)、国際協力・開発総局(DGCID)内にも<br />
非政府系協力のためのミッション(Mission pour la Coopération noNGOuvernementale、MCNG)が<br />
設置された。改革の目的は、a.国際協力活動の透明性の改善、b.支援対象を旧植民地以外に<br />
も拡大する、c.多数の当意者間で関連予算の管理が細分化するのを回避することにあった。98<br />
年の改革により、外務省、経済・財政・産業省、AFDの 3 組織を柱とする関連機関の国際協力に<br />
おける役割分担が明確化された。<br />
� 外務省の国際協力・開発総局(DGCID):グローバリゼーション・開発パートナーシップ総<br />
局(DGMOP)が国レベルの機能の支援(法国家、ガバナンス)<br />
� 経済財政産業省管轄の国庫・経済政策総局(DGTPE):債務帳消し、西部アフリカおよび<br />
中部アフリカの CFA フラン圏(かつては 1 フランス・フラン=100CFA で固定、事実上のユー<br />
ロ圏)への経済援助、多国間援助を実施<br />
� AFD:インフラ、農村開発、環境、教育、人材養成、医療、民間機関支援、都市開発などを<br />
実施<br />
1 支援対象国を多様化するために 1998 年に設立、以前のフランスの支援対象国よりも多い 55 ヵ国が対象となっ<br />
ている。これらの諸国への支援のため、優先連帯基金(Fonds de Solidarité Prioritaire、以下FSP)を設置した。<br />
2 DCPは各国政府の経済、開発プログラムに応じて策定される 4 ヵ年のプログラムである。<br />
150
2)支援方針:官民連携型ODA<br />
AFDの使命は現地の民間企業を支援することにある。AFDによるODA支援はアンタイド援助<br />
なのでAFDのプロジェクトを必ずしも仏企業が実施するわけではないが、仏企業が落札した場合<br />
は、当該企業とプロジェクト推進のために協力する(事例:ブラジルの路面電車、エチオピアの風<br />
力発電など)。<br />
AFDは以前より上下水道整備、道路、鉄道整備などのインフラ整備を官民パートナーシップ<br />
(PPP)方式で進めている開発途上国のプロジェクトを支援している。例えばモロッコではラバト、タ<br />
ンジール、テトゥアン、カサブランカなどで国際入札が行われ、ベオリアやスエズが落札している。<br />
AFDのモロッコヘの支援の約 40%は水事業に充当されており、2006 年末の時点で 3 億 5,100 万<br />
ユーロが拠出された。2002 年には、タンジール/テトゥアン市、および Rabat-Salé 市が国際入札<br />
を行ない Amendis(ベオリアの子会社)、および Redal(ベオリアの子会社)が落札した。モロッコの<br />
自治体がベオリアに事業を託すための財源の一部をAFDに求め、インフラ整備が進められる。<br />
2007 年 1 月には、2007~2011 年をカバーする第 2 次戦略的指針プロジェクト(POS)が策定さ<br />
れた。この中でAFDは予算の尐なくとも 60%をアフリカ・サブサハラ諸国への援助に充当すること、<br />
民間部門ヘの支援(自己資本の強化、新興国における仏事業者のフォローなど)を強化すること<br />
などが明記された。支援は経済協力振興出資会社(PROPARCO)あるいはAFDを通じて行われ<br />
る。第 2 次POSではとくにNGOとの協力強化を謳っており、AFD内にNGO連携課 (Division du<br />
partenariat avec les ONG、DPO)を設立。また、これまで外務省のDGCID内にあったNGOによる<br />
国際行動支援ミッション(Mission dAppui à Action Internationale des ONGs、MAAIONG) 3 はADF<br />
の管轄となった。<br />
2009 年 9 月には、新興国・開発途上国での経済成長に仏企業が更に貢献することを目指して、<br />
AFDとフランス企業振興会(Ubifrance)は枠組み協定を締結した。<br />
3)BOPビジネスヘの支援策に対する方針・考え方<br />
BOPビジネスヘのAFDによる支援策などの現状をAFDのベルムネス氏(企業関係担当)は以<br />
下のように説明する。<br />
「近年は企業の社会的責任(CSR)・環境保全などの新しい流れの中で仏企業との新しい関係<br />
が生まれ、企業との共同融資、BOPビジネス、フェアートレード、現地生産などの新しい試みが進<br />
められている。このうちBOPビジネスについては、貧困層が製品・サービスにアクセスすることが<br />
できるような新しい戦略を模索中であり、現地生産についてはフランスの大企業が現地に進出す<br />
3 MAAIONGは仏NGOによる国際的連帯・開発プロジェクトに協調融資する。<br />
151
る際の現地調達率を高くするため、下請け企業を選択する際の支援を行なっている。現在は、民<br />
間部門(例:Total , France Telecom)との事業や協力が非常に増えている。AFDは様々なプレイ<br />
ヤーと協力して様々なセクターのプロジェクトに最大限の資金を投入する、あるいは企業に最大<br />
限の協力を求めるよう試みている。<br />
BOPビジネスの概念は 2 年前にでてきたもので、現在はBOPに関する情報収集、職員の関心<br />
を高める啓発の段階にある。ビジネスを通じて貧困を軽減する、というこれまでのODAを初めとす<br />
る開発援助の概念を完全に打ち崩すものであるため、メンタリティーを完全に新しくしなくてはなら<br />
ず、新しい協力関係の構築などについて企業、NGO、IMS(Institut du Mécénat de solidarité-<br />
Enrepriendre pour la Cité)などと検討している段階である。事業化調査や評価などはその後に行<br />
なうことになろう。BOPプロジェクト関わる問題点を抽出するため、BOPワークショップを設置して<br />
いる。BOPイニシアティブが開発途上国の開発を促進するということが証明されなければ実際に<br />
BOPをビジネスとしては行なわない。NGOはラファルジュ(セメントメーカー)やEDF(フランス電<br />
力公社)と協力して、プロジェクトを明確化し現地の販売網などを研究している。ワークショップで<br />
は 3 ヵ月ごとに関係者が集まり意見を交換している。2010 年までに 1 つか 2 つのプロジェクトをみ<br />
つけ、そのインパクトを予想することができればよかろう。」 4<br />
4)BOP支援スキームの必要性をどのように認知したか<br />
前述したように、フランスでは近年ようやく伝統的なアプローチだけでは開発途上国支援は不十<br />
分として、企業の革新的なアプローチも必要なことを公的機関が認識しはじめた段階で、現在は<br />
企業の経験を政府が「認識」し、情報交換を密にする段階といえる。例えば、AFDとCSRに特化し<br />
た企業連盟であるIMS(Axa 元会長の Claude Bébéar が会長)が共同で開発途上国支援のための<br />
ソーシャル・ビジネスに関する会議を 2008 年 12 月に開催した。仏公的機関のほか、国際機関、N<br />
GO、CSR Europe、すでにBOPビジネスを手がけているユニリーバ、トタル、ダノンなどの大企業<br />
が集まり、開発のための革新的金融商品の提供、企業はいかに開発途上国の市場を拡大するか<br />
などについて意見を交換した。<br />
5)官民の連携におけるNGOの役割<br />
NGOは現地の事情に精通しており企業あるいはAFDなどの公的機関が現地企業を支援する<br />
際にも非常に大きな役割を果たす。2009 年 1 月より、NGOの予算の管轄が外務省からAFDに移<br />
管されたことからも明らかなように両者の関係は強化されつつある。<br />
4 2009 年 12 月 11 日AFDの Fadila Belmounèes 氏(企業関係担当)とのインタビューより作成<br />
152
2007 年 1 月に監査会で採択された第 2 次戦略的指針プロジェクトでは、AFDはNGOとの協力<br />
が開発途上国の発展事業でAFDが地位の強化を図れる鍵になるとしている。近年、開発途上国<br />
支援のプレイヤーは自治体、基金、民間企業、NGOなどに多様化しており、支援を効率良く進め<br />
るためにはこれらのプレイヤーとの良好で効率のよい関係を構築することが大切である。<br />
6)官民連携をスムーズに進めるための工夫<br />
照)<br />
AFDと Ubifrance の協力(後述する②支援機関・支援スキーム、②-4)フランス企業振興会を参<br />
AFDと PROPARCO は、開発途上国の民間部門の成長・強化を支援の重要な鍵と認識しており、<br />
この強化は仏企業の進出及び技術移転、とくに現地企業と仏企業の協力を通じて可能となる。現<br />
在、AFDは仏銀行ネットワークが開発途上国の入札を獲得できるよう支援している。<br />
【企業にとって利益を生まないBOPビジネスに関心を高めるための工夫】<br />
フランスでは企業の方が積極的にCSRやソーシャル・ビジネスを意識し、NGOや国際機関の<br />
提唱するプロジェクトに参加するケース、あるいは現地のソーシャル・ビジネスを行なう企業と共同<br />
で事業を進めるケースが見られる。ダノンのベルナール・ジロー持続的開発担当副社長は、「ビジ<br />
ネスにより開発途上国の貧困層の生活レベルをあげていける、という社会的側面への関心・興味、<br />
企業の社員の自負が大切」と指摘している 5 。<br />
企業、その他の識者の関心を高めるためのセミナー開催、意見交換、発想の転換が必要であ<br />
る。その意味で 2008 年 12 月に行われたAFDとIMSが共同で開催したBOPビジネスに関するセミ<br />
ナーは評価できよう。同セミナーは仏外務省、経済・産業・雇用省。欧州委員会、CSR Europe の<br />
協賛で実現したもので、欧州内のドナー、UNDP、世銀、IFCなどの国際機関、国際金融機関、ダ<br />
ノン、EDF、GDF-SUEZ、ベオリア、CEMEX、マイクロソフト、ニュートリセットなどの仏内外の大企<br />
業及び開発途上国で事業を展開している企業、NGOなどが参加し、「途上国の開発にむけた企<br />
業のイノベーション、成功の条件」、「開発に向けて関係者間の協力をいかに改善するか」、「企業<br />
はいかにして新しいビジネスを貧しい消費者のニーズに応えていくか」などについて議論が戦わさ<br />
れた。<br />
5 2009 年 12 月 11 日、ダノン本社でインタビュー<br />
153
7)開発目標である成果指標をどのように評価しているか<br />
国連のミレニアム開発目標を実現するために効率の高い開発援助が求められることから、2005<br />
年 3 月、開発関連の機関、プレイヤーがパリに集まり開発支援の効率に関する宣言を行なった。<br />
評価は、経済・財政・産業省内のDGTPE、外務省内のDGMDP、AFDのメンバーから成るパ<br />
イロット委員会(comité de pilotage)により行われる。OECDの開発援助委員会の原則に基づき、<br />
各プロジェクトはプロジェクト終了後 6~12 ヵ月以内に評価されなければならない。評価方法もOE<br />
CDの評価に則って行われる。<br />
② 支援機関・支援スキーム<br />
1)仏開発庁(AFD)<br />
フランスで開発支援を行なう公的機関は、1941 年に大蔵省・中央銀行としての役割を果たす自<br />
由フランス中央金庫として発足し、その後 58 年には経済協力中央金庫(CCCE)として旧フランス<br />
植民地に対する経済支援機関に改組、92 年にはフランス開発金庫(CFD)となり、98 年に開発庁<br />
(AFD、Agence Française de Développement)と改組され現在に至っている。現在では、プロジェク<br />
ト援助の主要実施機関として位置づけられており、外務省、経済・財政・雇用省、移民・同化・国民<br />
アイデンティティ・開発協力省の 3 省の管轄下にある。<br />
AFDの主な業務は無償資金協力の一部、有償資金協力の実施、開発途上国の民間プロジェ<br />
クトヘの貸付、保証など。また 2005 年以降は技術協力プロジェクトが外務省から一部移管された<br />
ため、有償・無償技術協力を担う開発銀行と援助実施機関の両面を持つ包括的な支援組織へと<br />
発展してきている。<br />
ここ 10 年の間、活動が活発化している。近年は非ソブリン融資も多く、2008 年に非ソブリン融資<br />
額が初めてソブリン融資額を上回った。20 年前はAFDだけで活動していたが、近年は他の国際<br />
機関、NGO、基金、及び企業などと協力して活動することが多くなっている。<br />
AFDは主に、優先連帯地域(ZSP)、とりわけ最貧国を対象とした二国間支援を実施している。<br />
その使命は、開発途上国の経済成長、および環境保全を支援することにあり、これらの目標は<br />
2000 年 9 月にニューヨークで開催された国連ミレニアム・サミットで採択された国連ミレニアム宣言<br />
の内容に合致している。AFDの 2008 年の支援執行可能総額は 45 億ユーロ(前年比 25%)で、支<br />
援総額の 41%がアフリカ向け、続いて地中海・中東諸国向け 26%、アジア諸国向け 25%、ラテン<br />
アメリカ・カリブ諸国向け 8%となっている。<br />
154
2002 年 3 月にはAFD業務のロードマップとなる「戦略的指針プロジェクト」(POS:Projet<br />
d’Orientation Stratégique )が策定され、金融機関や民間部門、市民社会とのパートナーシップを<br />
強化していく方針が明らかにされた。<br />
2)経済協力振興出資会社(PROPARCO)<br />
AFDグループ傘下の経済協力振興出資会社(PROPARCO)は、AFDが資本の約 60%を出<br />
資する企業で、インフラ整備、金融システムの近代化と保証、途上国の民間部門の投資を促進す<br />
ることを使命としている。PROPARCOは、経済的に成長が見込まれ、社会的に公正で環境に留<br />
意し、財政面で利益のあがるプロジェクトに融資する。<br />
図表 26 地域別支援(出典:AFD2008 年度年次報告)<br />
25%<br />
図表 27 セクター別支援(出典:AFD2008 年度年次報告)<br />
7%<br />
10%<br />
3%<br />
14%<br />
26%<br />
14%<br />
8%<br />
27%<br />
25%<br />
155<br />
41%<br />
アフリカサブサハラ諸国<br />
地中海・中東諸国<br />
アジア<br />
ラテンアメリカ.カリブ<br />
諸国<br />
インフラ整備・都市開発<br />
生産部門<br />
環境・天然資源<br />
水・下水道整備<br />
社会部門<br />
農業・食品の安全<br />
その他
3)関連組織・機関<br />
図表 28 業務別支援(出典:AFD2008 年度年次報告)<br />
政府間委員会(Comité interministériel pour la coopération internationle et le développement、<br />
CICID)<br />
国際協力開発のために 1998 年に設置されたCICIDは、外務省と経済省が共同で運営する、政<br />
府内の国際協力の協議及び調整機関である。2004 年の会合で、国連ミレニアム計画実施(給水<br />
と水処理、保健とエイズ撲滅、農業と食品安全、サブサハラ諸国のインフラ、環境・生物多様性の<br />
保護)に向けたフランスの目標を策定した。2005 年には、優先連帯地域(ZSP)を対象に、支援の<br />
ための新ツール「提携枠組み文書 (DCP)」を導入した。DCPは、各国と 4 年計画で、現地政府の<br />
開発政策の内容にも適合するよう開発援助の全てのプレイヤー(企業、協会、大学、研究所など<br />
公的機関以外のプレイヤーも含む)を包括し、開発戦略を策定する。これにより、支援主体により<br />
ばらばらだったプログラムを総合的に見ることが出来る 6 。<br />
・国際協力高等理事会(Haut Conseil à la Coopération Internationale、HCCI)<br />
HCCIは、国際協力に関わるNGO、労働組合等政府外の関係者と定期的に協議するために設<br />
置された機関である。1998 年の発足以来、国際協力の重要なテーマについて多くの提言を行なっ<br />
てきたが、2008 年 3 月、国際協力の合理化の一環により廃止され、代わってODA戦略評議会<br />
(Conseil stratégique sur l’aide publique au développement、CSAPD)が設置された。CSAPDの<br />
役割など詳細は不明である。<br />
借款‘補助金<br />
予算支援<br />
保証<br />
自己資本<br />
海外領土支援<br />
海外領土運営<br />
(単位:百万ユーロ)<br />
6 OECDの開発援助委員会(Comité d’Aide au Développement、CADと表記)はDCPが支援対象となる政府の開<br />
発優先事項を含めて開発戦略を策定している点を評価している。2006-2010 年のチュニジアのDCPの例を挙げ<br />
ると、DCPでは 2004 年の大統領プログラム及び第 10 次開発計画の方向性を踏まえて、a.企業の近代化と経済<br />
の競争力強化、b.住民の生活改善、c.持続的環境整備等を挙げている。<br />
156<br />
433,0<br />
435,9<br />
598,1<br />
286,51<br />
4468,9<br />
32,8<br />
94,1
グローバリゼーション・開発パートナーシップ総局(Direction Générale de la Mondialisation, du<br />
Développement et des Partenariats、DGMDP)<br />
これまでの国際協力・開発総局(DGCID)に代わって、2009 年 3 月に創設された。開発のため<br />
の協力ならびに文化・科学・教育・技術協力を進めることを使命としている。<br />
国庫経済政策総局(Direction Générale du Trésor et de la Politique Economique、DGTPE)<br />
2004 年に行われた組織再編により、経済・財政・産業省内の対外経済関係局(DREE)、国庫局、<br />
予算局がDGTPEとして統合された。DGTPEは、借款、国際機関への拠出、債務削減、無償資<br />
金協力に関わる政策決定を行なっている。<br />
a.DGTPEの管理するDGTPE管轄下の開発途上国支援ツールは、民間部門支援・調査基金<br />
(Fonds d’aides et d’études au secteur privé、FASEP) と新興国準備金(Réserve Pays<br />
Emergents、RPE)、フランス地球環境基金(Fonds français pour l’environnement mondial、FFE<br />
M)などがある。<br />
b.FASEPは、新興国に進出する施主に対し、プロジェクトがスタートする前に技術支援を無料<br />
で供与している(支援は贈与の形で行われる)。主要支援セクターは、飲料水、下水処理、水資源<br />
管理、環境保護、公共輸送、エネルギー(特にクリーン・エネルギー)<br />
c.RPEは水、電気、輸送などのインフラ整備プロジェクトに低利率で融資(年間 2 億ユーロを拠<br />
出)する。貸付条件はケースバイケースでプロジェクト毎にDGTPEと相手国の財務省が交渉し決<br />
定する。主な支援対象セクターは、都市輸送、公共輸送、上下水網の整備である。<br />
157
図表 29 フランスの援助実施体制(2009 年 12 月末現在)<br />
出所:外務省など各種資料をもとに作成<br />
4)フランス企業振興会(Ubifrance)<br />
フランス企業振興会(Ubifrance)は、仏企業の海外進出を支援する経済・産業・雇用省管轄下<br />
の商工業的公施設法人(EPIC)で、世界 44 ヵ国に事務所を配置している。Ubifrance は元来フラ<br />
ンスの中小企業が先進国へ進出するのを支援する(例:現地のディストリビュータをみつける)機<br />
関であり、国際見本市/サロン等に参加する企業(特に中小企業を対象)の支援が第一の使命で<br />
ある。新興国、開発途上国で行われるイベントへの参加については、企業が参加しやすいように<br />
特別料金を設定している。<br />
2009 年 9 月は、新興国・開発途上国での経済成長に仏企業が更に貢献することを目指して、A<br />
FDと Ubifrance は枠組み協定を締結した。これにより今後 3 年間、ア.双方は支援、あるいは進出<br />
しようとする地域の一般情報(経済・金融状況、インフラ、ビジネス環境、産業セクター別の見通し<br />
など)を共有する、イ.AFDグループはグループの金融ツール、AFDが融資するプロジェクト情<br />
158
報・入札情報の詳細を Ubifrance に提供する、ウ.AFDグループの金融ツールを駆使して仏中小<br />
企業の現地への進出の可能性を検討する。<br />
2010 年 3 月にAFDとセミナーを開催する予定。仏企業がAFDおよびAFDのプロジェクトを知り、<br />
その内容を理解することを目指す。この機会にAFDは革新性の高い金融製品も紹介する予定で<br />
ある。<br />
AFDの支援先の施主、あるいは世銀、JICAなどの国際機関が入札を行なうときに、Ubifrance<br />
は仏企業を支援(入札情報を含めた情報の交換、事業セクター別の調査、どのように応札するか<br />
など)する。開発途上国の人口は 40 億人前後であり、ビジネスのポテンシャルは高い。<br />
AFDは現地の企業を支援するのに対して、Ubifrance は仏企業を支援し仏企業の現地での発<br />
展を支援する。ただし、(Ubifrance は)企業がNGOに近づいたり協力関係を構築したりすることに<br />
は介入しない。Ubifrance が支援する企業の進出先は全ての国であるが、中国、インド、南アフリカ<br />
共和国、エジプト、ブラジルに特に注力している 7 。<br />
5)支援スキーム<br />
開発途上国の経済発展には民間部門の成長・強化が不可欠だが、開発途上国政府は民間セ<br />
クターが成長するような環境整備を進める力が不足していることから、AFDを初めとする国際機<br />
関や先進国のドナーは、民間事業の発展に適切な環境作り(すなわち、現地の中小企業が銀行<br />
にアクセスできるよう資金面でのアクセス、貿易へのアクセス、人材育成、情報ヘのアクセス、国<br />
際的レベルでの環境整備および社会的責任の構築)に注力している。AFDの開発途上国民間部<br />
門支援プロジェクトは以下の通りである。<br />
a.商業的能力強化プログラム:<br />
(Programme de Renforcement des Capacités Commerciales、 PRCC)<br />
上記のテーマに沿って、AFDと仏国庫・経済総局(DGTPE)は 2002 年に開発途上国の商業的<br />
能力を強化するプログラムを策定した。2006 年 4 月に 3 年の予定で更新された。予算総額は<br />
2,500 万ユーロ。具体的には生産および流通、管理・監視システムの設置、企業のレベルアップな<br />
どを進め、輸出可能な企業となるようサポートする。2002 年から 2007 年の間に 35 プロジェクトに<br />
対し補助金の形で支援した。<br />
b.企業のキャッチ・アップ・プログラム:Mise à niveau des enterprises<br />
7 2009 年 12 月 11 日、Ubifrance の Aurérie CARIA「プログラム・フランス」課長および Chantal du MAZEL 理事長<br />
付きパートナーシップ部門責任者とのインタビューより作成<br />
159
かなり以前から実施されているプログラムで、開発途上国の中小企業が生産性の向上や諸外<br />
国との競争に打ち勝つことができるよう、様々なサービス(人材教育、技術進歩、設備)を提供して<br />
いる。最近では 2007 年にチュニジア政府に 2,500 万ユーロを貸与したほか、セネガルの中小企業<br />
100 社余りを支援するため、同国政府に 1,100 万ユーロの補助金を拠出した。<br />
c.キャピタル・インベストメント:Capital-investissement<br />
AFDグループ傘下の PROPARCO による民間部門への融資。PROPARCO は特に持続可能な<br />
開発、国連ミレニアム計画の目標達成、雇用創出、経済成長などを促進するプロジェクトに融資し<br />
ている。<br />
AFDではこのほか、3 年毎に各国別の支援戦略を明確化した「介入枠組み」( Cadre<br />
d’intervention par pays、CIP)を策定している。<br />
また、外務省も 2001 年以降、「アフリカにおける企業の役割強化支援プロジェクト」の枠組みで<br />
企業・開発ネットワークが同業者組合(Compagnonnage)パートナーシップ・プログラムを進めてい<br />
る。同プログラムは先進国及び開発途上国間の同業者のパートナーシップの構築を目指しており、<br />
中小企業を対象としている。プログラムが打ち上げられて以来これまでにマグレブ諸国、サブサハ<br />
リ諸国との間で 250 の企業協力が締結された。<br />
③ 産業界の取組<br />
1)フランス企業運動(Mouvement des Entreprises de France、MEDEF)<br />
1945 年に設立された仏経営者団体連盟(Conseil National du Patronat Français、CNPF)が<br />
1998 年 10 月にMEDEFに改編された。MEDEFの会員数は 75 万社にのぼる。<br />
MEDEFは国レベル、地方レベル、国際レベル、の 3 つのレベルから成る。このうち開発途上国<br />
ビジネスは国際部門が担当しており、MEDEFは開発途上国の開発プロジェクトに応札を希望す<br />
る仏企業に情報を提供している。MEDEFの Lys Vitral 国際ビジネス・アドバイザーはMEDEFの<br />
開発途上国ビジネスの取組などについて以下のように説明する。<br />
「企業はBOPビジネスを通じて開発途上国を援助することを望んでいるが、企業は現地のニー<br />
ズに応じた製品を開発、生産する必要があり、そのために現地の事情に詳しいNGOと協力する<br />
160
必要がある。またBOPビジネスではマイクロファイナンスも非常に重要な要素であるといえる。M<br />
EDEFでは、経済のグローバリゼーションや気候変動などにより、開発途上国を含めた開発が必<br />
要となっていることを痛感しており、企業とNGOがこれらの問題に共同で対処しなければならない、<br />
との感を近年一層強めている。このためMEDEFはNGOの Coordination Sud 8 とともに、「企業と<br />
国際的NGOとの関係」を見直し、検討するため、コンサルタント会社 Be-Linked に調査を委託した。<br />
同社は 2008 年から 2009 年にかけて企業やNGOにアンケート調査を実施した。同社はこの回答<br />
をもとに、企業とNGOが希望するパートナーシップのあり方について5つの可能性を抽出している。<br />
第 1 の可能性は企業メセナでのパートナーシップの 40%がこれに該当する。企業にとっては宣伝、<br />
イメージの向上につながり、NGO にとっては資金調達、公共機関に対しての独立を確保できると<br />
いう利点が挙げられる。第 2 の可能性はBOPであった。ただし、40 件の回答しか得られず、その<br />
回答から判断すると、企業がBOPに特化したNGOとパートナーとなる場合、より戦略的なパート<br />
ナーとなることができる。また、回答から、企業が何をターゲットとすべきか明確になっていない状<br />
況であることが判明した。BOPに関する企業とNGOとのパートナーシップに関しては、今後検討<br />
すべき事柄が多くある。アンケートに回答した大企業の 80%は、進出した外国でビジネスがうまく<br />
いかなかったことがあると回答し、その解消のためにNGOとパートナーを組むべきと指摘している。<br />
ただし、今回の調査で企業はNGOに関する情報が不足していることも明らかになった。すでに開<br />
発途上国に進出している企業は現地でNGOを見つけパートナーとしているが、これから海外に出<br />
ていく企業については Coordination Sud がNGOとのマッチングをしており、BOPビジネス推進の<br />
ためには、企業と公的機関、現地NGO、国際NGOの提携が必要である。」 9<br />
2)IMS Entreprendre pour la cité<br />
IMSは 1986 年にフランスの企業リーダーが設立した非営利団体で約 200 社の企業が会員であ<br />
る。IMSは企業のCSRおよび総合的な利益に関わる事業をサポートしており、具体的には、関係<br />
者との意見交換、調査、評価、プロジェクトのフォロー、BOPビジネスや企業のCSRの啓発活動<br />
などを行なっている。MEDEFが企業経営者の団体で、一般的な事項を取り扱うのに対して、IMS<br />
は企業の社会的責任に特化している企業連盟である、という点がMEDEFとの相違といえる。<br />
IMSは 2007 年にBOPビジネスに関する研究行動プログラム(programme de recherché –action)<br />
を立ち上げた。同プログラムには 20 社あまりの企業が参加している。グループは、イノべーティブ<br />
で戦略的なテーマを研究課題としている。現在は、企業のBOPに関する経験や情報を交換し、研<br />
究している段階である。2008 年 12 月には「開発のための企業活動(Entreprendre pour le<br />
8 Coordination Sud は 1994 年に創設されたNGOで 6 つのNGOグループと国際的な分野で活動する 130 の仏N<br />
GOをメンバーとしている。通常これらのNGOは戦争、自然災害等の緊急事態の時に活動する。<br />
9 2009 年 12 月 9 日、MEDEF本部でのインタビュー<br />
161
développement)」をテーマにAFDとシンポジウムを開催した。BOPについてこれまで各プレイヤ<br />
ーが個別に対応していたが、このシンポジウムでは関係者が協力して作業を進め、フランスでの<br />
経験をもとに、BOPビジネスをうまく機能させるために、公的機関、ドナー、企業、NGOなどが協<br />
力し、いかに官民パートナーシップを構築させるかを議論した。IMSはまた CSR Europe のパート<br />
ナーであり 2007 年に創設されたBOPラボラトリーに参加し、欧州委員会に対してBOPイニシアテ<br />
ィブをサポートするよう求めている。<br />
2009 年 3 月にはBOPパイロット・プジェクトを開始させている。プロジェクトにはGDFスエズ、ラ<br />
ファルジュ、オレンジ/フランステレコム、BNP/パリバの 4 社が参加し、情報や経験談を交換し、B<br />
OPプロジェクトをサポートするための行動などを研究している。<br />
2010 年はオランダ、スイスのグループとBOPビジネスにおける資金調達、テクノロジー、パート<br />
ナーシップなどをテーマにシンポジウムを開催する予定である。<br />
(2)支援スキーム活用事例<br />
① ベオリア・ウォーター(Veolia Eau 10 )<br />
ベオリアは、1853 年の勅令によりジェネラル・デゾー(Compagnie Générale des Eaux、CGE)とし<br />
て創設された。同社の誕生は、フランスの産業革命の時期に一致している。当初の目的は、農地<br />
の灌漑と都市部への水の供給であった。同社は、リヨン市と最初のコンセッション契約を締結、<br />
1860 年にはパリ市と給水契約を締結した(コンセッション期間は 50 年)。1880 年代にはいると海外<br />
に進出し、ベニス、コンスタンティノープル、ポルト各都市と次々とコンセッション契約を締結し、現<br />
地の公共機関に代わってサービスを提供した。浄水、給水のほか、下水処理、ゴミ処理など環境<br />
関連事業全般に進出し、関連企業の買収、合併、売却などを経て、2003 年に現在の社名ベオリ<br />
ア・エンバイオメント(Veolia Environnement)になった。同社の事業部門は、浄水、上水/下水道サ<br />
ービス、ゴミ処理、エネルギー、輸送、都市暖房などいわゆる「ソーシャル・ビジネス(affaires<br />
sociales)」で、公的機関にかわって提供している。公共サービスの受託者で、政府を初めとする公<br />
的機関からの委託サービスを実施している。<br />
ベオリアのCSRは、「連帯」、「チャリティー」などの言葉で表現されるもので、先進国では低所<br />
得層が給水を断たれないよう留意し、開発途上国ではサービスを現地の状況に適合させるよう注<br />
力している。特に、ベオリアは水部門での経験が豊富であり、アジア(特にインド)およびアフリカ<br />
(特にモロッコ)でモデル事業を実験した。最も経験の多いモロッコでは、水のネットワークのない<br />
場所では、無料の給水スタンド (borne fontaine)の設置、移動式事務所の導入など様々な試みを<br />
10 Eau はフランス語で水を意味する。英語社名は Veolia Water(べオリア・ウォーター)。<br />
162
行なっている。<br />
ベオリアの事業や活動が人々の生活の改善に繋がることを常に意識し、出来るだけ個人の利<br />
益と公共の利益を合致させるよう努力している。同社は事業部門の性格上、早くから持続可能な<br />
開発に関心を持った。2004 年 5 月には仏内外の持続可能な開発プロジェクトを支援する目的でプ<br />
ログリオ CEO(当時)のイニシアティブでベオリア・エンバオメント基金が設立された。「連帯」、「環<br />
境」、「責任」(自分たちの事業が必ず人々の日常生活の向上に繋がるという意識)はベオリア・エ<br />
ンバオメントの事業活動の優先順位であり、各プロジェクト実施に際しては必ずグループの職員<br />
がフォローし、これらの価値の実現に努めている。同社は設立当初から、公共機関に委託され公<br />
共サービスを提供しており、開発途上国でのサービスも基本的には現地の公共機関のオファーを<br />
落札し、コンセッション契約などを締結して上下水道事業を展開している。<br />
ベオリア・エンバオメントの水サービス事業を担当するベオリア・ウォーターは、水事業部門では<br />
世界最大の事業者である。2008 年の売上は 126 億ユーロ、従業員数 9 万 3,400 人、1 億 3,900<br />
万人に給水している。最貧困層も水サービスへのアクセスが出来るよう、ベオリア・ウォーターは<br />
開発途上国の状況に合わせた特別のプログラムを子会社の Veolia Water AMI (Afrique、<br />
Moyen-Orient、Inde) 11 を通じて、策定・実施している。2004 年には持続可能開発部門(Direction<br />
Développement Durable) を設置した。Veolia Water AMI も、いうまでもなく、「連帯」、「環境」、「責<br />
任」をモットーに事業を進めている。本報告書では、従来のビジネス・モデルである PPP 方式(モロ<br />
ッコ 12 )と、新しいビジネス・モデルであるソーシャル・ビジネス(バングラデシュ)の例を紹介する。<br />
1)モロッコ<br />
a.事業の概要、ビジネス・モデル<br />
モロッコを初めとして、ニジェール、ガボンなど大半はべオリアと現地公的機関との間でコンセッ<br />
ション契約を締結している。<br />
モロッコでは 2002 年 1 月、タンジール、テトゥアン両市当局とコンセッション契約を締結した。契<br />
約期間は 25 年で、上下水サービス、および電力サービスを子会社 AMENDIS(Veolia Water AMI<br />
が 81%出資)を通じ住民 140 万人に提供する。同年 10 月には、ラバト・サレ市と同様のコンセッシ<br />
ョン契約を締結、契約期間は 26 年で、子会社 REDAL(Veolia Water AMI が 80.2%を出資)を通じ<br />
11<br />
2008 年 1 月、IFCと PrROPARCO は地域のインフラ整備を支援するため、それぞれ Veolia Water AMI 資本の<br />
13.89%、5.56%を獲得した。<br />
12<br />
べオリア・ウォーターは世界 64 ヵ国で事業を行なっているが、モロッコでの 3 プロジェクト(総額 5 億ユーロ)が最<br />
大である。<br />
163
住民220万人に水サービスを提供する。現地公的機関の実施した入札の結果、ベオリアが契約を<br />
獲得した。<br />
タンジールでの事業目標は以下の通り<br />
・コンセッション契約により、インフラの改修・近代化を進め上下水道および電気ヘのアクセスを<br />
向上させるとともに衛生・保健状況を改善する<br />
・タンジール周辺の水質の向上<br />
・廃水の 90%を収集<br />
・既存のインフラ設備の改善<br />
・上下水道、電気供給網の拡大、特に都市部での拡大を目指す<br />
・低所得世帯の上下水道網および電力網への接続<br />
(Redal、Amendis の子会社を通じ契約締結から 5 年内に、低所得者 3 万 5,000 世帯への飲料水<br />
網接続、と 4 万世帯への下水網への接続を予定している。)<br />
事業内容<br />
・環境保全を目指し排水処理工場を設置<br />
・汚水処理ネットワークの拡大、タンジール周辺の汚染除去・防止、洪水防止<br />
・顧客サービスの改善(代理店での顧客への対応の改善、移動式代理店の創設、顧客へのサ<br />
ービスに対するアンケート調査、顧客管理システムの導入)<br />
・現地職員の職業訓練を通じ能力を高め最適化する(2006 年末迄に合計 7,000 日の研修を実<br />
施)<br />
・2002 年以降、低所得層 1 万 5,000 世帯に給水網を接続、1 万世帯に電力網を接続した<br />
・2008 年末の時点で、Amendis は人口 85 万人に年間 3,400 万 m3 を給水している。また 73 万<br />
人に対して下水サービスを提供している。収集した排水の量は 2,730 万 m3<br />
・このほか付随的事業として、就学支援、クリーン・ビーチ、清潔な街等のプロジェクトを実施し<br />
ている。<br />
b.市場ニーズの把握やサービスに関する情報は現地公的機関の入札情報として入手<br />
ベオリアの顧客は国や地方自治体などの公共機関である(例:モロッコは地方自治体、ガボン、<br />
ニジェールは国)。これらの公共機関の行なう入札にベオリアが応札、落札して、事業が委託され<br />
た。<br />
入札情報は専門誌で入手、関心のある場合は専門会社に事前調査を依頼し仕様書を作成、応<br />
札する。<br />
164
c.商品の生産(現地自社工場での生産、生産委託、資材調達)は現地で実施<br />
d.価格の設定方法<br />
水の価格は地方自治体が決定する。ベオリアはコストを相手に伝える。価格は契約提携時に<br />
設定する。開発途上国は社会的料金(tarification sociale)が`導入され、貧困層には、一定量まで<br />
無料で給水する。<br />
モロッコの地方自治体は、いくつかの価格帯を設定し最低価格である「社会的価格」は毎月 6m 3<br />
を上限に、原価よりも低く設定している。富裕層が貧困層の水道料金を肩代わりする形の価格シ<br />
ステムを導入することによりベオリア・ウォーターは出来るだけ多くの人に水を給水している 13 。水<br />
道料金を廉価にすると同時に供給網への接続費用も出来るだけ低く抑えるようなメカニズムも導<br />
入した。メーターの設置などは現地当局が住民に貸付を行ない、住民は長期間のローンで返済す<br />
る。<br />
これは国内外のドナーによる融資および目的税(taxe)の利用、現地の収入などを合わせ利用<br />
者と地理的環境などすべての要素を考慮して設定する。<br />
例えば 2006 年、タンジールのべオリア・ウォーター子会社 Amendis では、世銀とGPOBA<br />
(Global Partnarship for Output Based Aid) 14 から「結果に基づく支援」パイロット計画の枠組みで<br />
200 万ドルの資金提供を受けた。このタイプの支援は、達成すべき数量的な目標が予めわかって<br />
いるため、民間資本を利用しつつドナーからの支援、国の予算を最も効率良く利用することができ<br />
る。Amendis はこの方法により 3,000 以上の貧困世帯を給水および下水網に接続することに成功<br />
した。Amendis と地方当局は財政リスクを担い投資を先行した。これにより、モロッコでは 2003 年<br />
から 2008 年の間に約 25 万人が自宅での給水が可能となり、10 万人が下水網に接続された。<br />
e.販売方法(マイクロファイナンスの活用、NGOの活用等)~自動給水スタンド“Saqayti” 15 ~<br />
モロッコでは、給水網への接続が地理的あるいは経済的理由で難しい場合は、“Saquayti”方式<br />
を利用する。村落で予めリスト・アップされた貧困家庭に対して、IC カード(太陽光パネルで作動)<br />
を手交する。カードは毎月 6m 3 (これ以上は利用者負担)の使用分がコミュニティによりチャージさ<br />
れる。これまでも低所得者向けに給水スタンド(bornes-fontaines)が存在したが、既に給水網に接<br />
13 ガボンでもこれに類似した価格体系を導入している。<br />
14 GPOBAは、「アウトプットに基づく支援」(Output-based aid : OBA)を行なう国際的なドナー及び組織のグルー<br />
プ。GPOBAは、開発途上国の基礎的なサービスやインフラ整備を可能とするプロジェクトの策定、財政支援、<br />
フォローを行なう。<br />
15 アラビア語で「私の泉」の意<br />
165
続している世帯や企業も給水スタンドを利用でき、本当にそれを必要としている住民達(給水網に<br />
接続されていない)がサービスを充分享受することができなかった。また、水はただであるという概<br />
念から、水の浪費を生み水の消費をコントロールすることは難しく、コミューンにとって非常にコス<br />
ト高となった。<br />
新方式は、2006 年にテマラでテストされた後、2008 年 5 月にテトゥアン市の Oued El Maleh 地区<br />
に最初の“Saqayti”が導入された。その後、ラバト・サレ、タンジールでも導入されている。<br />
“Saquayti”は、ベオリア・エンバイオメントのモロッコが現地企業 2 社と開発したもので、1 スタンド<br />
設置にかかるコストは 2 万 5,000(約 30 万円)-4 万ディルハム(約 47 万円)で、今後 45 のスタンド<br />
を設置する予定である。“Saquayti”は 2009 年 3 月、「Aujourd’hui Maroc」紙の主催するエコロジ<br />
ー・コンクール「エコ製品」部門で優勝した。上述したように IC カードで作動するため、水の消費を<br />
50~75%まで削減するとともに、太陽光パネルを使用しているので省エネ効果もある。<br />
図表 30 自動給水スタンド:Saqayti<br />
出所:べオリア(Expertise et engagement développement durable de Veolia Water AMI, Synthèse 2008)<br />
(copyright : Phototech Veolia Environnement)<br />
f.スキームによる成果指標への評価<br />
現在は、モロッコその他の開発途上国で様々なモデル、工夫などの面で実験段階であり、その<br />
効果や結果などの分析はこれから行なう。<br />
・Poverty Action Lab(PAL)による社会的給水接続網プログラムへの評価<br />
2007 年 5 月から 2008 年 12 月の間に、人的開発国家イニシアティブ(INDH:Initiative Nationale<br />
pour le Développement Humain)の枠組みで Amendis の行なった社会的給水網接続サービスを享<br />
受している世帯の生活条件ヘのインパクトを米マサチューセッツ工科大学(MIT)の研究機関であ<br />
る J-PAL が行なった。世帯はこのサービスに非常に満足している、という結果がでている。<br />
166
〈参考1〉<br />
ベオリア・エンバイオメントは、グループの 4 部門(水、ゴミ収集、エネルギー、運輸)の持続的開<br />
発におけるCSRに関する評価を外部機関 BMU Ratings に依頼している。グループはこの評価結<br />
果を踏まえて、持続的開発における同社の戦略や方針を策定・修正したりする。BMU Ratings によ<br />
る評価は、2005、2006 の両年は A ++ であったが、2007 年以降は AA + とランクが上がっている。<br />
このほか、Veolia Water AMI は 2006 年、同社の事業全般のパフォーマンスを改善するためのシ<br />
ステム(systeme d’amélioration de nos performances)を導入し、同社の傘下となる各地の子会社<br />
のパフォーマンスを示すことの出来るような指標を準備した。<br />
① 基礎的データ:契約締結時期、事業、サービス提供地域の住民数・コミューンの数<br />
② サービスへのアクセス<br />
③ 上水:上水サービス加入者数、飲料水生産量、水の購入給水量、世帯接続により給水され<br />
る住民数、2008 年に行われた社会的接続数、契約締結時以降設置された社会的接続数、<br />
給水スタンドの数、給水スタンド利用者数<br />
④ 下水:下水サービス加入者数、下水網に接続している住民の数、2008 年に設置された社<br />
会的接続の数、契約締結開始以降接続された社会的接続の数<br />
⑤ 電気:給電網接続者数、発電量、電力購入量、サービス享受者数、2008 年の社会的接続<br />
件数、契約締結以来の社会的接続件数<br />
⑥ 環境:ネットワークの効率=飲料水給水率、配電率、給水される水の衛生項目達成のカバ<br />
ー率、その他の項目もあわせたカバー率<br />
⑦ 顧客管理:代理店の数、コール・センターの数<br />
⑧ 社会的データ:従業員数、労災の件数、労災のために失われた日数、労災の発生する確<br />
率、重大な事故の発生する率、人材養成=人材にかかる予算、参加人数、職業訓練に費<br />
やす総時間<br />
⑨ 補足的データ:売上、契約締結以来の投資額、水部門への年間投資額、電力部門への投<br />
資額、下水部門への投資額、年間総投資額<br />
g.NGO、国際機関との連携を上手に行なうポイント<br />
・NGO、国際機関主催会議、プログラムヘの参加<br />
ア.ベオリア・エンバイオメントは国連の主要機関との協力を続け、国連ミレニアム計画の目標<br />
達成に貢献している。グループはまた、モナコ・アルベール国王基金主催のシンポジウム<br />
にも出席、スペインで開催された社会的排斥撲滅のための都市サービス会議にUNDP、I<br />
DB、UNESCO等とともに出席した。<br />
イ.Amendis とベオリア・エンバイオメント基金は 2003 年以降、モロッコ政府とユニセフ(UNICE<br />
167
F)による多年度計画「質のよい学校」プログラムに参加しており、特にその中の「環境部門」<br />
の計画に参加している。このプロジェクトの枠組みでタンジールの小学校 30 校以上の衛生<br />
施設の創設と改修を進めた。また ユニセフ 、文部省、NGOの科学教 育職員協会<br />
(Association des Enseignants des Sciences de la Vie et de la Terre :AESVT)と協力して環<br />
境保全への啓発プログラム「衛生・環境教育プログラム」を進めている。<br />
ウ.ベオリアはBOPに特化したラボラトリーは持っておらず、会議等で他の企業や専門家と意<br />
見を交換している。<br />
〈参考2〉:ベオリア・エンバイオメント基金<br />
同基金は「連帯」、「環境」、「社会復帰」などをテーマに仏内外での持続可能な発展に関わる<br />
700 件以上の公的利益(すなわち非営利目的)のプロジェクトを実施中である。基金は現地のイニ<br />
シアティブによるプログラムの財政支援、および自然災害後の緊急支援や人道的支援を行なう。<br />
ベオリアの独自性は、プロジェクトには必ずベオリアの社員(Veoliaforce)が参加することにある。<br />
基金がスポンサーとなるプロジェクトは、ベオリアの社員の立案したものに限る。プロジェクトを立<br />
案して、基金の執行部により認められた場合、立案者が自動的にプロジェクトの責任者となり、基<br />
金のスタッフの支援を受けて調査、フォロー、評価などを行なう。<br />
ベオリアはまた、途上国の緊急支援や人道支援のため、NGOや国際機関などから要請があれ<br />
ばミッションを派遣して調査やノウハウを提供する。基金の設立当初の支援は水部門に限定され<br />
ていたが、現在はベオリアの他の事業部門にも及ぶ。これらの社員はボランティアとして現地で活<br />
動するが、現在の規模は 600 人以上である。ボランティアはNGOや国際機関と協力して、プロジ<br />
ェクトやミッション(特に地震、津波などの自然災害後の緊急支援)に参加する前に、最新のテクノ<br />
ロジー、緊急援助機器について、赤十字、UNICEFの職員などとともに 3 日間の研修を受ける。<br />
現在、ベオリア基金では複数年に跨がる環境や保健に関するプロジェクト(マダガスカルの保健<br />
センター、ニジェールの学校、ベトナムのデング熱撲滅)を経済・財政・産業省、外務省、AFD、サ<br />
ノフィ−アベンティス、パスツール研究所、などと提携して進める予定である。このほかコンゴ民主<br />
共和国で、同国厚生省、在コンゴ仏大使館、UNICEF、NGOである Solidarité、AFDと協力しコレ<br />
ラ撲滅プロジェクトを策定し、実施することを希望している。ベオリア・エンバイオメント基金は現在<br />
のところ、2013 年末まで活動を行なう予定で年間予算は 720 万ユーロである。<br />
h.社内におけるBOPビジネス人材育成<br />
Veolia Water AMI では給与総額の 2.91%を従業員の教育に充当している。<br />
ベオリア・エンバイオメント基金の枠組みで行なうプログラムでは、プロジェクトに参加する社員<br />
は、3 日間の研修を受ける。<br />
168
i.その他(モロッコ)<br />
ベオリア・ウォーターは顧客サービスを最適化するために「移動式事務所」としてバスで巡回し、<br />
給水網への接続、水道料金の支払など消費者の様々な要求に対応している。この「移動式事務<br />
所」は予め住民と日程を決め巡回する。このサービスにより、べオリア・ウォーターは給水サービ<br />
スにより生じる間接的コスト、すなわち支払のための交通費、オペレータと話すための電話代など<br />
を消費者が節約することを可能とする。<br />
図表 31 移動(巡回)事務 所<br />
出所:べオリア(Expertise et engagement développement durable de Veolia Water AMI, Synthèse 2008)<br />
(copyright : Phototech Veolia Environnement)<br />
ただし、モロッコでは上記のようなシステムの導入にもかかわらず国民全員が給水の恩恵を受<br />
けることが出来なかったため、コミュニティがプリペイド方式で”Saqayti”と呼ばれる新タイプの給水<br />
スタンドから月 6m 3 をこれらの貧困層に給水する制度を導入、その後 IC カード利用による自動給<br />
水スタンドを開発した。<br />
ベオリア・ウォーターはまた、飲料水サービスを享受する人々に水の正しい利用法を教えること<br />
も必要と考え、NGOとともに「保健衛生」ヘの関心を高めるため、住民への啓発活動も併せて行<br />
なっている。これら全ての活動を継続的に評価することも必要で、タンジールでの社会的給水網<br />
接続については、f.で述べたように、2007 年以降 Poverty Action Lab がそのインパクトを評価して<br />
いる。<br />
2005 年にはモロッコ政府が人道・開発のためのイニシアティブ(Initiative Nationale pour le<br />
Développement Humain、INDH)を打ち上げたのを機に、べオリア・ウォーターはラバト、タンジール、<br />
テトゥアンの 3 都市とINDHの枠組み協定を締結、9 万世帯を飲料水・下水網に接続することを目<br />
指している。INDHは 2015 年までに上下水道へのアクセスが出来ない人口を半減するという国連<br />
ミレニアム宣言の目的に合致している。プログラムの進行を早めるため、べオリアは当該地区で<br />
の接続作業を進めると同時に商品化のプロセスも開始し、サービス開始までの時間を短縮するよ<br />
う努めている。また上記「移動式事務所」の利用で接続手続きが迅速になり、料金についても、無<br />
169
利子で 10 年払いが可能になった。給水網への接続費用と水道使用料金で利用者の負担分は月<br />
9 ポンドを超えないこととし、残りは補助金で賄う。<br />
・JIWAR<br />
ベオリア・エンバイオメント・モロッコは近隣サービスJIWARを提供している。これは、商店が水<br />
道料金支払を受け付けることデ毎日 8 時から 22 時の間に住民が水道料金を払えるよう便宜をは<br />
かったもの。2008 年末の時点での料金支払受付拠点数は 136 で、支払全体の 17%がJIWARで<br />
行われている。このほかに従来の代理店 49 店舗と移動代理店 7 店舗がある。JIWAR導入にあ<br />
たり、ベオリア・エンバイオメント・モロッコは 2008 年 10 月より取り扱い店に関してラジオや広告な<br />
どを通じ大々的にキャンペーンを繰り広げている。<br />
図表 32(左) 2004~2008 年のモロッコにおける Jiwar 件数の推移<br />
図表 33(右) 2004~2008 年のモロッコにおける代店、移動式事務所の件数の推移<br />
出所:べオリア(Expertise et engagement développement durable de Veolia Water AMI, Synthèse 2008)<br />
出所:ベオリア各種資料より作成<br />
図表 34 ベオリア(モロッコの場合)<br />
170
2)バングラデシュ<br />
a.事業の概要、ビジネス・モデル<br />
・事業の背景:<br />
バングラデシュでは地下水の深度が浅いため 70 年代、80 年代と 800 万余りの井戸がほられ、<br />
現在国民の 90%近くは水にアクセスしている。しかしながら、地下水の大半は地質学的な理由か<br />
ら砒素に汚染されていることが多く、90 年代に入り、地元の病院などで問題が取上げられるように<br />
なった。現在慢性砒素中毒になった患者数は 3,000 万人以上といわれている。このような背景から<br />
グラミン銀行とべオリア・ウォーターはバングラデシュの最も貧しい村の住民に安心して飲めるよう<br />
な水を供給できるよう、協力することを決めた。<br />
べオリア・ウォーターの子会社 Veolia Water AMI とグラミン銀行の衛生・保健部門の子会社グラ<br />
ミン・ヘルス・ケアは 2008 年 3 月に折半出資で共同会社グラミン-べオリア・ウォーター<br />
(Grameen-Veolia Water Ltd.)を創設した。<br />
新会社はべオリアの専門技術と現地従業員へのノウハウの移転、及びグラミン銀行の現地に<br />
関する情報・知識及びネットワークを駆使し、全部で 5 ヵ所の村にそれぞれ浄水・給水施設の設置<br />
と運営を行ない、飲料水の供給を目指す。各家庭の給水網への接続予定は現在のところない。<br />
2009 年 6 月 24 日より首都ダッカの東約 100km の Goalmari の工場で浄水を開始し、村の住民 4<br />
万人への給水が可能となった。給水は、貯水タンク、給水スタンドなどのシステムを通じて行われ<br />
る。今後は新たに 4 工場でも浄水を開始し、最終的には国内の中央部・南部の人々約 10 万人へ<br />
の給水を目指す。<br />
各世帯は 1 日 30 リットルまで購入が可能で、価格は 1 リットル当たり 0.2~0.5 サンチーム。ボト<br />
ル入りの水の 100 分の 1 の価格。投資額は 50 万ユーロで、最終的には 10 万人に供給する見通<br />
しである。べオリア・ウォーターはこれにより、国連ミレニアム計画の目標の 1 つである、開発途上<br />
国住民の「飲料水・水処理」アクセスに貢献する。<br />
バングラデシュのケースは「ソーシャル・ビジネス」モデル、すなわち「損失は出さないが配当金<br />
もない(従って、住民への援助、寄付はいっさいない)」というもので、投資分は住民から水道料金<br />
として回収し、別の同タイプのプロジェクトに再投資する。<br />
このプロジェクトにより住民を現地の経済に組み入れることが出来、人間の基本的なニーズを<br />
満たすことが出来る。このサービスは飲料水の供給とともに、住民に衛生などの観念を啓発する<br />
ことを可能にする。<br />
b.市場ニーズの把握やサービスに関する情報はグラミン銀行から入手<br />
171
c.商品の生産(現地自社工場での生産、生産委託、資材調達)<br />
グラミン-べオリア ウォーターが現地に設立した浄水施設で行なう。水は地上水を利用し、WH<br />
Oの基準に則り浄水作業を進める。Goalmari 村への給水は川の水を利用する。<br />
d.価格の設定方法<br />
飲料水サービスにかかる全てのコスト、および住民の経済状況を鑑み、「ソーシャル・ビジネス」<br />
の基本である損失を出さない価格を割りだした。<br />
一世帯 6 人家族で 1 日の使用料は 30 リットルと見積もられる。<br />
「ソーシャル・ビジネス・モデル」に基づくと、飲料水は浄水場を出る段階で 1 リットルにつき 0.1 タ<br />
カ(0.1 サンチーム)、そのあとは、浄水場から給水地点迄の距離や、経済状況に応じて 0.2~0.5<br />
サンチーム/リットルとなる。<br />
e.販売方法(マイクロファイナンスの活用、NGOの活用など)<br />
Goalmari では、村の最も貧困層に優先的に給水する。給水方法は村の集落にある水道の蛇口<br />
までパイプラインで運ぶ予定。またより孤立した地帯では人力車で水を運ぶシステムも検討中で<br />
ある。水は給水スタンドでも販売される予定で、グラミン・レディースが 1 日のうちのある時間に給<br />
水する。<br />
第 2 地帯(Padua)では 2010 年より浄水が開始され、残りの 3 ヵ所の村落でも 2012 年までにス<br />
タートする。<br />
f.スキームによる成果指標をどのように評価しているか<br />
プロジェクトは開始したばかりで、まだ評価には至っていない。<br />
g.その他<br />
べオリア・ウォーターはプロジェクトのための事前調査は行なわなかったが、このプロジェクトの<br />
推進により(2015 年までに世界で飲料水ヘのアクセスが出来ない人口を現在の 2分の 1 にする)、<br />
国連ミレニアム計画の目標の 1 つに貢献する、と考えている。<br />
べオリア・ウォーターの同プロジェクト責任者エリック・ルシュール(Eric Lesueur)氏は、「プロジェ<br />
クトの推進により、我が社が持続可能な発展で大きな役割を演じ、従来の伝統的な水事業から社<br />
会のニーズを満たすような、より大きな規模の事業に発展する絶好の機会となる。ソーシャル・ビ<br />
172
ジネスは伝統的なビジネスと同じように機能するが、人道上の利益という要素がはいってくること<br />
が従来のビジネスと異なる。このビジネスであげた利益は次の水関連の別のプロジェクトの発展<br />
のために再投資される。このプロジェクトにより 2015 年までに、世界で飲料水へのアクセスが出来<br />
ない人口数を現在より半減することを狙っている」と述べている。一方、Veolia Water AMI のパトリ<br />
ス・ホンラドーサ(Patrice Fonlladosa)CEOは「最貧民層に水を供給するには『技術的及び社会的<br />
に」』革新的な方法 16 を導入しなければならない」と指摘している。<br />
BOPビジネスの専門家のペロー氏 17 は、ベオリアのバングラデシュでのビジネスをパイロット・<br />
プロジェクトとして捉え、「バングラデシュでの経験を活かして、他の国でこのモデルをまた利用し<br />
たいようだ」と述べ、さらに、「ベオリアは新興国の地方自治体と水サービス事業の交渉を進める<br />
際、富裕層の多い地区だけで事業を展開したいだろうが、現地の自治体は、貧困層の多い地区<br />
でも事業を行なって欲しいので圧力をかけるだろう。そのときにバングラデシュでの経験が役立つ<br />
と考えられる」と分析する。<br />
図表 35 ベオリア(バングラデシュの場合)<br />
出所:ベオリア・ウォーター「Expertise et engagement développement durable de Veolia Water AMI, Synthèse 2008」<br />
② エシロール(Essilor)<br />
1972 年、Essel と Silor の 2 社が合併して誕生したエシロールは創設以来一貫して、人と人との<br />
相互尊重と信頼、連帯、帰属意識、コミュニティーへの忠誠心などをモットーとして事業活動をす<br />
すめている。これは Essel の前身がシャルル・フリエ(理想的共同体の提案、産業主義の批判)の<br />
16 モロッコでの Jiwar や移動式事務所、Saqayti などの試みが挙げられる。<br />
17 エコール・ポリテクニック(フランス国立理工科大学)の博士課程に在学中で仏セメント大手ラファルジュのBOP<br />
ビジネスにかかわるインドネシアでのパイロット・プロジェクトに参加している。2009 年 12 月 12 日にインタビュー<br />
を実施。<br />
173
影響を受けた「眼鏡職人友愛組合」(1849 年創設)であることに拠っていることが大きい。また「よ<br />
りよい生活の質」を求めるエシロールにとって、「よりはっきりと見える」ことが「生活の質の向上」に<br />
結びつくと考えられているためである。<br />
このような価値観に基づき、エシロールは先進国はもとより各市場に適した戦略により、開発途<br />
上国市場にも現地スタッフを駆使して進出している。ただし、独立精神に富み、社員の 25%が株<br />
主(2008 年末時点)であるエシロールでは、政府との提携ではなく自らのイニシアティブでビジネス<br />
を進めている。早くから「視力と発展」の関連性(すなわち、視力が矯正されれば雇用機会が増え、<br />
貧困の軽減に繋がる)を指摘しているエシロールは、ユネスコをはじめとした国際機関のプログラ<br />
ムにも積極的に参加している。<br />
Essilor の概要<br />
1972 年に創設された。2008 年の売上は 30 億ユーロ、従業員総数は 3 万 4,320 人、レンズ生産<br />
2 億 4,500 万個、R&D センター3、生産工場は日本、インド、中国、タイ、フィリピン、米国など計 15<br />
箇所、世界 100 ヵ国に進出している。<br />
1)事業の概要、ビジネス・モデル<br />
長年にわたり、先進国諸国は開発途上国に古い眼鏡を配布していた。これらの眼鏡はもちろん<br />
慈善事業(チャリティー)であり、無料であるが、必ずしも消費者のニーズに合っていなかった。実<br />
際、南の国では長い間、近視の人たちが老眼鏡をかけていた。このような状況のなかでエシロー<br />
ルは、90 年代半ばから、開発途上国の中の最貧困層にも眼鏡を超低価格で「販売」することを決<br />
めた。クロード・ダルソー(Claude Darsault)持続開発部長は「これは慈善事業ではなく、眼科・眼鏡<br />
サービスを享受できない何百万人の人々にこのサービスを受けることができるようにすることだ」<br />
と述べている。<br />
エシロール(矯正用レンズ、眼鏡、年商 30 億ユーロ)は 2008 年、インドの貧しい農村地域で移<br />
動式オプティカル・ショップを立ち上げ、超低価格(175 ルピー=3 ユーロ、5 ドル 18 )で矯正用眼鏡の<br />
販売を開始した。エシロールはこのプロジェクトを慈善事業(チャリティー)ではなく、収益を挙げる<br />
可能性のある経済モデルとみなしている。価格は非常に低いが、生産および販売コストをカバー<br />
しており、より長期的には、これまで市場として認識されていなかったこの市場でリーダーとなるこ<br />
とを目指している。<br />
2)市場ニーズの把握やサービスに関する情報は現地での事前調査及び現地病院からのコンタク<br />
トにより入手<br />
18 当時の為替レート<br />
174
エシロールがプロジェクトを立ち上げる前、インドにおける眼鏡着用の割合は人口のわずかか<br />
約 7%で欧州の 60%に比べ非常に低く、眼鏡屋が車で巡回して 1 週間に 15 分、1 ルピーで裁縫<br />
や手紙を読んだり出したりする必要のある住民に眼鏡を貸し出していた。しかも 1,200 万人が眼病<br />
の適切な治療を受けられないために失明する、という悲惨な状況であった。<br />
このような状況のなかで、白内障の手術で有名な Madurai の Aravind 病院の眼病治療センター<br />
(非営利組織)は、1 億人以上の人々に超低価格で治療を提供することを目指していたが、質の高<br />
いプラスチック製のレンズが必要なため、エシロール・インディア(Essilor India)とコンタクトをとった。<br />
同病院は年間 20 万件の白内障の手術をしており、エシロールの協力により病院内に眼鏡部門を<br />
設立した。同部門のスタッフはエシロールが養成し、眼病/眼科用の近代的機器やレンズ・フレー<br />
ム製造用の装置が装備され、眼科専門学校、R&D 実験室等も設けられている。<br />
病院のスタッフは村を巡回し住民の目の検診を行い、失明の原因となる白内障の患者をピック<br />
アップした。同病院のトラックで現地を視察したエシロールのスタッフは、インドにおける眼鏡普及<br />
のための最大の問題は不便な交通事情(交通最低往復 2 日と交通費)にあることが必要なことを<br />
突き止めた。<br />
3)商品の生産(現地自社工場での生産、生産委託、資材調達)<br />
レンズとフレームは現地の工場で生産するので、中間コストやマーケティング・コストは発生しな<br />
い。現地工場(Bangalore)はエシロール・グループの工場の中でも屈指の規模を誇りフランス、米<br />
国、日本市場にも製品を供給している。インドの村落向けの商品は 30年ほど前に米国で販売され<br />
ていた古いモデルで、高品質だがレンズが厚い。これらのレンズを生産するため、エシロールは<br />
米国で使われなくなった成型を利用している。フレームは中国から輸入しているが、フレームの選<br />
択肢は、顧客の要請により広がった。<br />
眼鏡の単価は 175 ルピー(5 ドル)で、これまで 1 万個の眼鏡を販売した。一般の眼鏡店での販<br />
売規模は毎日 6~7 個だが、巡回車では 20~25 個とエシロール・インディアの Jayanth<br />
Bhuvaraghan 氏は指摘する。<br />
4)価格の設定方法<br />
現地の生活水準から割出し 5 ドルなら購入できる、という結論に達した。<br />
5)販売方法(マイクロファイナンスの活用、NGOの活用等)<br />
175
エシロールは事前調査で眼鏡販売の最大の問題は交通が不便なことが判明したため、当初は<br />
パートナーである Aravind 病院に対して眼鏡販売用のミニバスを用意するよう提案した。2006 年半<br />
ばには、エシロール自らミニバスを導入した。以後、眼科検診用のミニバスと眼鏡用レンズのカッ<br />
トおよび眼鏡販売専用のミニバス 2 台が人口 2,000 人程度の村落を巡回するようになり、現在ミニ<br />
バスの台数は 5 台に増えた。<br />
6)スキームによる成果指標をどのように評価しているか<br />
2003 年以降、「環境指標」、「社会指標」を導入している。2003 年の段階で Global Reporting<br />
Initiatives(GRI)を手本にして、財務状況以外の指標も年次報告に入れるようにしている。<br />
7)NGO、国際機関との連携を上手に行なうポイント<br />
持続可能な成長や企業のCSRを重視する同社は国際機関やNGOの主催するプログラムに積<br />
極的に参加している。<br />
WHOが毎年主催する『Vision et Développement』に毎回参加している。このフォーラムにはUN<br />
ESCOなどの国際機関が参加し、プログラムの進捗状況を報告する。エシロールは会議での決<br />
定事項などをフォローしている。2005 年のダカールで開催されたフォーラムのあと、エシロールは、<br />
WTO西アフリカ支部から学校での眼の定期検診や、失明予防のための技術支援を要請された。<br />
エシロールは、同じくWHOおよび国際失明予防協会(IAPB)ほかいくつかの国際NGOが進め<br />
る国際プログラム『Vision2020』、UNESCOの進める『Education pour tous(「皆のための教育」)』<br />
プログラムに参加している。<br />
このほか、独エシロールはUNICEFと世界の子供たちの視力回復・矯正に協力しており、視力<br />
矯正に関する絵本出版を支援し、販売で得た収入の大半をUNICEFに寄付している。<br />
8)社内におけるBOPビジネス人材育成<br />
現地の人々を「眼鏡販売店員」となるよう養成する。<br />
エシロールは、現地の状況に則したビジネスを進めている。特に、開発途上国でのビジネスを<br />
進めるためには、眼鏡ビジネスの全分野において、現地スタッフの専門知識・技術・能力を強化す<br />
ることが必要である。この目的から、エシロールは 2006 年、パートナーである Aravind Eye Care<br />
System と Aravind School of Optometry を開校し、眼鏡ビジネスの人材を養成する。このほか<br />
Varilux Academy では、アジア・太平洋地域の 7 ヵ国で、眼鏡レンズの専門家を養成する。<br />
176
9)その他:将来の計画<br />
エシロール・インディアの Bhuvaraghan 氏によると、現在ビジネスは損益均衡点に達しているが、<br />
今後収益を挙げるためには、1 日の販売個数を 30~35 個に引き上げなければならない。インドの<br />
農村人口は 6 億 5,000 万人、そのうちの半数にあたる 3 億人(仏市場の 10 倍)が眼鏡を必要とす<br />
ると見積もられているため目標を達成できる可能性は高い。フォンタネ(Fontanet)社長は「プロジ<br />
ェクトが成功するためには、コスト削減及び現地の住民のニーズに合った製品を提供することが<br />
必要」とした上で、「これまでのところ、眼鏡の販売個数は多いが売上は尐ない。しかしこれは持続<br />
可能な発展モデルの戦略に基づいており、『慈善』の精神に基づくビジネスに比べはるかにインパ<br />
クトが大きい」と述べている。<br />
エシロールは今後、人口 1 万人程度の村にも徐々に進出する意向だ。インドの中間階層の成<br />
長は目覚ましく年 15%程度の伸びを示している。エシロールは既に繊維関連の小規模企業を訪<br />
問し、企業経営者に従業員の眼鏡着用を奨めている。またより富裕層には最新の商品の販売も<br />
試みている。インドでのモデルは他の開発途上国にも当てはめられるかという点について、クロー<br />
ド・ダルソー(Claude Darnault)持続可能開発部長は「それぞれの国でのモデルはその国の文化、<br />
人々の行動パターンなどにも依拠するため、そのビジネス・モデルを他の国でそっくりコピーするこ<br />
とはできない」と述べている。<br />
図表 36 エシロールの協力体制<br />
出所:エシロール「Mleux voir le monde 2003, 2006, 2007 年次報告書」<br />
③ ニュートリセット(Nutriset)<br />
ニュートリセットは食品加工専門の技術者ミッシェル・レスカンヌ(Michel Lescanne)氏が製薬会<br />
社を辞職後、1986 年に地元のノルマンディに創設した企業である。学生時代から子供の栄養失調<br />
に高い関心を持っていた同氏は、開発途上国向けに栄養価の高い製品の生産から販売まで一括<br />
177
して行なうことを目指し、1993 年に学者、NGOと協力して栄養食品『F100』を開発、その後『F75』<br />
などほかの補助的製品を開発した。同氏は産業界や金融界から独立して自由に事業を行ない、<br />
開発途上国の栄養失調の子供の数を尐なくすること目指しており、ニュートリセットの唯一の株主<br />
である。「独立」して「自由」に、開発途上国の栄養失調撲滅にかかわることがモットーであるため、<br />
仏政府支援プログラムは利用していない。プロジェクトは民間プロジェクトで、補助金は一切受け<br />
ていない。ただし、NGOや国際機関の専門家やスタッフとは協力している。2004 年以降は緊急事<br />
態に対応するため商品の現地生産も進め、現地企業に製品のライセンスを無料で譲渡している。<br />
同氏は利益の 80%を R&D に投入している。同氏にとってこのビジネスは利益をあげて儲けること<br />
ではなく、利益により新たな製品を開発し、開発途上国の栄養状態の改善に貢献することを目的<br />
としている。<br />
1)事業の概要、ビジネス・モデル<br />
人道的な食品プログラムに 100%貢献する食品事業を展開している。<br />
製品の開発にあたっては栄養食品を専門とするNGOやWHOの助言により、子供の成長に必<br />
要な無機塩やビタミン入りの粉ミルク『F-75』、『F-100』を開発した。粉ミルクは国連、あるいは国<br />
境なき医師団(MSF)や Save the Children などのNGOを通じてアフリカや東南アジアで利用された。<br />
しかし、『F-75』や『F-100』は清潔な水で薄め、衛生上のルールに則って利用しなければならず、<br />
医療関連センターでのみ販売された。このため、栄養失調の治療を必要とする子供の母親はセン<br />
ターに通わなければならず、結局治療を途中で断念するケースが多かった。<br />
その後 1996 年、同社のミッシェル・レスカンヌ(Michel Lescanne)社長と開発研究局(Institut de<br />
Recherché pour le Développement、IRD) 19 の研究者アンドレ・ブリエン(André Briend)氏はピーナ<br />
ッツをベースとし、水で薄める必要がなく取り扱いが簡単で、保存期間の長い(2 年)栄養価の高い<br />
製品『Plumpy’nut』の開発に成功した。<br />
製品は、地元のノルマンディ工場で生産のほか、近年は開発途上国とフランチャイズ契約を締<br />
結し現地企業が生産に関わるケースも増えている。<br />
2)市場ニーズの把握やサービスに関する情報は人道関係の国際機関やNGOから入手<br />
3)商品の生産(現地自社工場での生産、生産委託、資材調達)<br />
当初は、ノルマンディ工場(2004 年の 4,000 トンから 2009 年には 3 万 3,000 トンに増加)のみで<br />
19 開発途上国の開発のための研究を行なう科学・技術に関する公施設法人<br />
178
生産していたが、2005 年以降、現地企業と契約を締結しフランチャイズ生産を開始した。ドミニカ<br />
共和国、エチオピア、マラウイ、ニジェールの各国は 2005 年以降、ニュートリセットとフランチャイ<br />
ズ契約 20 を締結し、現地生産ネットワーク(Plumpy Field)を構築した。このうちエチオピアは開発途<br />
上国の中で最大の生産ユニットを持ち、UNICEFの枠組みで年間 8 万人の子供に製品を配布す<br />
ることが可能である。上記 4 ヵ国の生産量は 2008 年には 2,000 トンに達した。2009 年にはコンゴ<br />
民主共和国、モザンビーク、タンザニア、ガーナ、マダガスカルの各国とも契約を締結しネットワー<br />
クをさらに拡大し、開発途上国の総生産能力は 2009 年の 7,000 トンから 2010 年には 1 万 8,000<br />
トンに達する見通しである 21 。<br />
このほか、ブルキナファソでは 2007 年 7 月に発足した同国の開発を目指すアソシエーション『ブ<br />
ルキナ 76』 22 が、同国首都の北部 120km にある KoNGOussi に生産ユニットを設立することを決定<br />
した。生産工場は、『Plumpy’Nut』とフランチャイズ契約を締結し生産ネットワーク(Plumpy Field)<br />
に組み込まれる見通し。ニュートリセットは、プロジェクト実施に向けて『ブルキナ 76』をブランド、特<br />
許、ノウハウなどの点から支援する。これと交換に現地メーカーは生産方法や製品の仕様を遵守<br />
する。プロジェクトはベオリア・ウォーターがスポンサーとなり 2 万ユーロを寄付する。<br />
一方、年間 50 トン以下の小規模生産について、ニュートリセットは生産を希望するNGOに製品<br />
生産の準備、生産ガイドを提供するとともに、NGOからの技術支援、トレーニング・モジュール、在<br />
庫管理支援などの要望にも応じる。これによりNGOは、規模の小さな栄養失調治療や人道プロ<br />
グラムの実施が容易になる。<br />
4)価格の設定方法<br />
NGOとの話し合いで決定する。<br />
5)販売方法(マイクロファイナンスの活用、NGOの活用等)<br />
ニュートリセットは「自己診断」を回避するため、店頭販売を行なわずNGOを通じてのみ販売さ<br />
れる。価格は 1 袋 0.26 ユーロ(92 グラム、500 キロカロリー)。「国境なき医師団」(MSF)は、2005<br />
年秋よりニジェールの 22 のセンターで『Plumpy’nut』の配布を開始しており、MSFの医師は<br />
「『Plumpy’nut』により栄養失調の子供の 4 分の 3 を治療できる」と述べている。<br />
6)スキームによる成果指標をどのように評価しているか<br />
NGOと共同で評価<br />
20 フランチャイズ生産は製品のニーズが高い国で行われる。フランチャイズ契約締結により、ニュートリセットの特<br />
許、ブランド、ノウハウの使用が可能となる<br />
21 このほか 2009 年には米国の人道組織などからのニーズを満たすために同国の非営利団体 Edesia もネットワ<br />
ークに加わった。2010 年の米国での生産能力は 4,000 トン<br />
22 アソシエーションは、ブルキナファソ北の Baam 地方とフランスのセーヌ・マリティム県が姉妹県協定を締結した<br />
枠組みで発足したもので、76 は同県の県番号<br />
179
7)NGO、国際機関との連携を上手に行なうポイント<br />
事業の性格上、常に国際機関やNGOと連携して製品の開発、製造、販売を実施。製品の開発<br />
時に栄養失調撲滅を目指すNGOや栄養専門家などと意見を交換し、最初の製品『F-75』や<br />
『F-100』が誕生した。<br />
8)社内におけるBOPビジネス人材育成<br />
フランチャイズ生産が進むに連れてフランチャイズ提携先の現地企業の職員がニュートリセット<br />
を訪れ 15 日から 3 ヵ月の研修(技術者や栄養士の養成)を受けている。2006 年以降これまで 25<br />
人の外国人が研修を受けた。またNGOからの技術支援、トレーニング・モジュール、在庫管理支<br />
援などの要望にも応じる。<br />
9)その他:今後の計画<br />
『Plumpy’nut』はNGOの間で大きな成功を収め、2008 年の売上は 5,900 万ユーロに達した。従<br />
業員数 140 名。利益の大半は製品の R&D に再投資される。ニュートリセットは製品の多様化につ<br />
とめている。また 2009 年 9 月には社内に持続可能発展部門が設置された。<br />
図表 37 ニュートリセット<br />
出所:ニュートリセット各種資料より作成<br />
180
(1)BOPビジネスに関わる政府の役割<br />
① 政府の支援方針・体制<br />
1)EUのBOPへの取組<br />
4.EU<br />
欧州連合(EU)および加盟国の開発援助は、主要先進国による援助全体の 60%近くを占め<br />
(2008 年:486 億ユーロ)、米国(同 22%)を大きく上回っている。また、EUは、一部の加盟国がア<br />
フリカ諸国の旧宗主国であったことなどからアフリカ大陸とのつながりが深く、ロメ協定やこれに取<br />
って代わったコトヌ協定などを通じ、積極的にアフリカへの援助に取り組んでいる。<br />
しかし、欧州委員会のミッシェル元委員(開発政策担当)も言うように「『チャリティー』をベースと<br />
したこの 50 年間の開発政策は、期待された成果をもたらさなかった。」<br />
EUでは、民間レベルではユニリーバ(英・蘭)やフィリップス(蘭)、ボーダフォン(英)、ダノン(仏)<br />
のような企業がすでにBOP層を対象としたビジネスに取り組んでいるが、欧州委員会のような官<br />
のレベルでの取組は遅れている。後述するように CSR Europe のBOPラボラトリーの報告書を踏<br />
まえ、欧州委員会も開発援助の効率改善という観点からBOPのような新しいビジネスモデルによ<br />
うやく関心を持ち始めた。<br />
a.援助効率の改善<br />
※『欧州コンセンサス』<br />
このためEUは、援助効率の改善に力を注いでいる。その中核となるのが、開発援助の主要な<br />
原則、目標を定めた開発援助政策に関する『欧州コンセンサス』で、『欧州コンセンサス』はEUと<br />
加盟国が補完性の精神に基づき、各々が開発援助政策を実施するための共通原則の枠組みを<br />
規定している。<br />
持続可能な開発の枠内での貧困の撲滅、特に「ミレニアム開発目標」の達成がEUの開発援助<br />
政策の最優先の目標で、民主主義、グッドガバナンス、人権の尊重の奨励なども目標となる。サ<br />
ハラ以南のアフリカ諸国は「ミレニアム開発目標」の達成に関し、世界の他の国々に比べ大きく遅<br />
れをとっており、このためEUは、アフリカに開発援助を集中している。<br />
181
※「オーナーシップとパートナーシップ」<br />
『欧州コンセンサス』は、開発援助の共通原則として「オーナーシップとパートナーシップ」、「政<br />
治対話の深化」、「市民社会(civil society)の関与」、「男女平等」、「国家の不安定化防止のため<br />
の継続的支援」を挙げている。<br />
開発戦略や開発プログラムを自分のものとし、自国の資源を動員するのに適した国内環境を作<br />
る責任を負うのは被援助国で、EUは開発途上国とパートナーシップの枠内で協力し、責任と義務<br />
を分かち合う。<br />
欧州委員会のミッシェル元委員も、「EUは、グローバルな開発政策に必要な変化、開発途上国<br />
とのパートナーシップへと向かう変化を牽引している」ことを強調している。<br />
EUの開発援助の実施は、対象となる国あるいは地域で個別に実施される。開発援助措置は、<br />
対象国あるいは地域のニーズや戦略、優先課題などに基づき個別に策定される。被援助国の多<br />
様性や達成すべき目標の違いから、差別化されたアプローチの採択は不可避となる。<br />
※『開発政策における役割分担に関する行動規範』<br />
欧州委員会は、EUの開発協力政策のパフォーマンスを改善するため、開発途上国におけるE<br />
Uの援助提供者(欧州共同体と加盟国)間の役割の補完性を強化し、より良い役割分担を実現す<br />
るための行動規範を策定している。<br />
行動規範は開発協力分野における補完性の原則を定めるもので、現地で獲得されたグッドプラ<br />
クティスをベースとしている。また、『援助効果の向上に関するパリ宣言』に含まれる原則(オーナ<br />
ーシップ、ハーモナイゼーション、成果指向、被援助国のシステムへの適合、相互責任)や、補完<br />
性を重視する『欧州コンセンサス』を踏襲している。<br />
欧州委員会は、行動規範を「人的資源、財源の最良な使用を実現するための様々な関係者間<br />
の役割の最適な分担」と定義している。各関係者は、他の者がすることと比較し、自分が最も付加<br />
価値をもたらすことのできる比較優位の分野での協力に集中するのが望ましい。比較優位にある<br />
分野の分析、拡大を通じEUの援助提供者は、自分が他と比較して優位にある分野の評価を深め、<br />
専門化に努める。<br />
※民間部門の発展の重視<br />
EUは、援助効率改善に果たす民間部門の役割にも注目している。開発援助への「市民社会<br />
182
(civil society)の関与」は、『欧州コンセンサス』の共通原則の 1 つとして挙げられている。また、コ<br />
トヌ協定 1 は、民間企業が経済成長や貧困削減の加速に果たす役割の重要さを認め、ACP諸国<br />
における民間部門の発展の重要さを強調している。<br />
ミッシェル元委員は、「貧しい国の発展における民間部門の役割は非常に重要である。地元の<br />
経済、市場を良く理解することが成功をもたらす」との認識を示している。<br />
『Intra-ACP Cooperation—第 10 次欧州開発基金(EDF):戦略文書並びに多年度指標プログラ<br />
ム(2008—2013) 2 』は、「中小企業(金融へのアクセス、公式経済への道など)にもっと注目すべき<br />
である。マイクロファイナンス・イニシアティブのさらなる強化を考慮すべきであり、他の手段のもと<br />
で計画されている行動との補完性を保証する必要がある。革新的ビジネスモデル(innovative<br />
business model)や、フラッグシップ・プロジェクトを通じた貧困層のための新製品あるいは新サー<br />
ビスの提供も考慮されなければならい」と指摘している。<br />
同戦略文書では、民間部門の発展(マイクロファイナンス、ビジネス環境改善プログラム、革新<br />
的フラッグシップ・プロジェクト)に、「貿易・民間部門の発展」に充当される 9,500 万ユーロの予算<br />
のうち 3,000 万ユーロを充当することが提案されている。<br />
b.新ビジネスモデルに関心を向けるEU<br />
金融危機、地域統合、経済パートナーシップ協定、中小企業の金融へのアクセス、革新的ビジ<br />
ネスモデル(innovative business model)の支援、官民対話といった新しい問題、ニーズがビジネス<br />
環境における重要な要素となるという状況を背景に欧州委員会は、開発援助の効率改善の一環<br />
としてBOPのような新しいビジネスモデルに関心を持ち始めている。<br />
欧州委員会の開発総局は、政府やNGOなどとの対話はあるが、企業との対話は尐なく、CSR<br />
Europe のBOPラボラトリーなどから新しいアプローチを学んでいる。BOPラボラトリーでは、「BO<br />
Pプロジェクトは様々な形態をとるが、いずれにしても真のパートナーシップの構築が中核となる。<br />
BOPプロジェクトを成功に導くために企業は、国内のあるいは国際的な開発機関、地元の共同体、<br />
NGO、開発途上国政府などと真のパートナーシップを構築する必要がある。例えば欧州の場合、<br />
1 コトヌー協定の 21 条(投資並びに民間部門の発展)<br />
・民間投資やダイナミックで競争力のある民間部門の発展に適した環境を作り出すため、国レベルや地域レベル<br />
で必要な経済改革や制度改革を支援する。<br />
・民間企業に提供される金融サービス、非金融サービスの質、有用性、利用しやすさの改善を支援する。<br />
・金融サービス、非金融サービスへのアクセスを改善することで極小企業の発展を支援する。<br />
2 http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/strategy_paper_intra_acp_edf10_en.pdf<br />
183
欧州委員会と企業のパートナーシップが重要となる」との認識が示されているが、「こうしたパート<br />
ナーシップが双方に利益をもたらすのは明らかだが、欧州委員会の開発政策の枠組みには、企<br />
業とパートナーシップを構築するための明確な枠組みがまだ存在しない」と指摘されている。<br />
BOPラボラトリーでは、「民間のBOPプロジェクトとEUの開発アジェンダ間には補完性が存在<br />
する」との結論が出され、企業と欧州委員会は双方のシナジーを深めるため対話を継続する。<br />
※フィジビリティー調査<br />
欧州委員会は、2009 年 11 月にはBOPを含む革新的フラッグシップ・プロジェクトに関するフィジ<br />
ビリティー調査『Study for Innovative Flagship Projects Programme 3 』をデンマークのコンサルタン<br />
ト会社 NTU 4 に委託、本格的に動き出した。調査期間は 4 ヵ月間で、2010 年 2 月には報告書が提<br />
出される予定となっている。調査予算は 500 万ユーロ。この調査では、BOPという名称は使われ<br />
ず、「革新的フラッグシップ・プロジェクト(Innovative Flagship Projects)」という名称が使われてい<br />
る。この問題に関しては、EuropeAid の E 局の Jan Ten Bloemendal 氏が中心となる。<br />
なお、公式文書においては、「革新的フラッグシップ・プロジェクト(Innovative Flagship Projects)」<br />
はまた、「革新的ビジネスモデル(Innovative Business Models)」、「包括的ビジネスモデル<br />
(Inclusive Business Models)」とも呼ばれている。<br />
同調査の主眼は、ACP事務局や欧州委員会の意思決定者に、ACP諸国での「革新的フラッグ<br />
シップ・プロジェクト(Innovative Flagship Projects)」を支援するための包括的な提案を行うことにあ<br />
る。<br />
また、同調査では、広範な潜在的顧客グループのための技術、製品、サービスのイノベーショ<br />
ンを含む新ビジネスモデルの開発を目的とする「革新的フラッグシップ・プロジェクト(Innovative<br />
Flagship Projects)」を類別するための明確な基準が示される。欧州委員会は、このフィジビリティ<br />
ー調査の成果をACP諸国でのBOPなどの新戦略につなげたい意向で、2010 年末には、EUの戦<br />
略が策定される予定。<br />
る:<br />
※調査の課題<br />
同調査は特に以下の点に関し、如何にして新しいビジネスモデルを創出するかに焦点を当て<br />
� 既存のソリューションでは高価すぎる、あるいは複雑すぎることから、市場から閉め出され<br />
3 http://www.pem-consult.de/pem//upload/124_job_download.pdf<br />
4 http://www.ntu.eu/idn84.asp<br />
184
ている広範な潜在的顧客グループのニーズに対応する機会。これには製品をローカルな<br />
ニーズやキャパシティーに適応させることによる、新興市場での製品の民主化の機会が含<br />
まれる[ピラミッドの底辺(bottom of the pyramid)に触れる]。<br />
� ブランド-新テクノロジーを強化する機会、あるいは全く新しい市場でテクノロジーをテスト<br />
する機会。<br />
同調査では、プログラムの一般的目標や個別の目標が示され、目標達成のための活動が提示<br />
される。また、適切と看做される活動は、貧困層に恩恵をもたらす新ビジネスモデルを暖めている<br />
企業、あるいは実施する企業の支援のみに焦点を当てるべきではなく、ネットワークやグッドプラ<br />
クティスの拡大促進、地元のキャパシティ・ビルディング、公共部門との対話の円滑化といった活<br />
動も含まれる。<br />
このほか以下のような課題が提示されている:<br />
� 「革新的ビジネスモデル(Innovative Business Models)」は、貧困層を消費者としてだけでな<br />
く、起業家、イノベーターあるいは生産者、サプライヤー、流通者、小さな投資家などとして<br />
取り込むべきである。<br />
� 「革新的フラッグシップ・プロジェクト(Innovative Flagship Projects)」のターゲットとなる貧困<br />
層あるいは脆弱な共同体、低収入の共同体は、起業的な側面と社会的な側面を組み合わ<br />
せるべきである。起業的側面は、商品やサービスのリスクを負う利益指向の生産や交換に<br />
より特徴づけられるのに対し、社会的側面は、低収入の共同体への恩恵によって特徴づ<br />
けられる。<br />
� 「包括的ビジネスモデル(Inclusive Business Models)」は、相互の利益のため企業と貧困<br />
層の間に橋をかけるビジネスを行う方法である。このモデルは、貧困層を顧客、消費者と<br />
して需要サイドに、ヴァリューチェーンの様々なステージにおいて被雇用者、生産者、企業<br />
オーナーとして供給サイドに含める。<br />
� 同調査は、「革新的ビジネスモデル(Innovative Business Models)」と「ピラミッドの底辺<br />
(Base of the Pyramid)」の関係を説明しなくてはならない。UNDPの「Growing Inclusive<br />
Markets Initiative」では、「包括的ビジネスモデル(Inclusive Business Models)」に取り組む<br />
ことは、企業の競争力に寄与するイノベーションにつながる。貧困層の嗜好やニーズに対<br />
応するため企業は、新製品やサービス、ビジネスモデルの開発を余儀なくされる。<br />
BOPは、「貧困対策+富の創出」という新しいアプローチで、社会、環境へのインパクトが大きく、<br />
雇用創出などで地元の人を支援しながらミレニアム目標の達成にも貢献する。また、通常の企業<br />
のパフォーマンスモデルとは異なり、利益は尐ないが、新市場の獲得といった他のメリットがある。<br />
企業にとっては、製品のイノベーションの機会ともなる。ACP BUSINESS CLIMATE の M’Hamed<br />
185
CHERIF 所長は、「BOPはCSRの 1 つと考えるより、新しいビジネスモデルと考えるべきで、このモ<br />
デルでは、社会的なものの達成も可能となる」との見方を示している。<br />
欧州委員会はまだ、開発援助政策にBOPのような新しいビジネスモデルを導入しようとする段<br />
階にすぎないが、「地域間、企業間の競争の問題も絡み、BOPは今後のキーエリアとなる可能性<br />
がある。」(CSR Europe の Jan NOTERDAEM シニア・アドバイザー)<br />
2)EUの開発援助政策<br />
a.開発援助の主要な原則、目標<br />
※「開発のための欧州コンセンサス」<br />
欧州委員会、欧州議会、理事会の委員長、議長は、2005 年 12 月 20 日、EUの開発援助政策に<br />
関する新しい宣言、『「欧州コンセンサス」と命名された欧州連合の開発援助政策に関する理事会、<br />
加盟国政府代表、欧州議会、欧州委員会の共同宣言』 5 に署名した。<br />
共同宣言では、EUと加盟国が補完性の精神に基づき、各々が開発援助政策を実施するため<br />
の共通原則の枠組みが初めて定義された。共同宣言の第 1 部では、共通のビジョン(目標や原則)<br />
が謳われている。<br />
ア.共通の目標<br />
最優先の目標は、持続可能な開発の枠内での貧困の撲滅で、特に国連の「ミレニアム開発目<br />
標」の達成が重要課題となる。<br />
宣言ではまた、持続可能な開発の概念には、グッドガバナンスや人権、政治的、経済的、社会<br />
的、環境的な側面が含まれることや、貧困対策においては、開発、天然資源の保護、経済成長に<br />
関連する活動間の均衡を保つ必要があることが確認されている。<br />
5 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:046:0001:0019:EN:PDF<br />
186
イ.開発援助の対象<br />
開発援助の対象となるのは、全ての開発途上国で、特に低所得国(LICs)、中所得国(MICs)。<br />
中でも後発開発途上国(LDC)が優先される。<br />
ウ.共通の原則<br />
共通の原則としては次のとおり。<br />
� オーナーシップとパートナーシップ:被援助国が、開発戦略や開発プログラムを自分のもの<br />
とし、自国の資源を動員するのに適した国内環境を作る責任を負う。また、EUと開発途上<br />
国は、パートナーシップの枠内で共に努力し、責任と義務を分かち合う。<br />
� 政治対話の深化:政治対話は、開発目標の実現に寄与する重要な手段となる。グッドガバ<br />
ナンスや人権、民主主義の原則、法治国家の遵守状況は、EUの機関や加盟国が主導す<br />
る政治対話の枠内で、共通のビジョンを分かち合い、支援措置を特定するため定期的な<br />
評価の対象となる。汚職対策、不法移民、人身売買なども政治対話の対象となる。<br />
� 市民社会(civil society)の関与:援助対象国の労働組合、経営者団体、民間企業、NGO<br />
は民主主義、人権、社会正義の推進役として重要な役割を演じる。EUは、政府以外の関<br />
係組織の開発プロセスへの参加を強化し、政治、社会、経済対話を促進するため、政府以<br />
外の関係組織の能力向上支援を強化する。<br />
� 男女平等:男女の平等や女性の権利は必要不可欠なものであり、社会正義の面からも重<br />
要であることから、EUは開発途上国に関係する全ての政策、行動に、男女平等に関する<br />
重要な要素を盛り込む。<br />
� 国家の不安定化の防止のための継続的支援:世界の貧困者の 3 分の 1 が生活する政情<br />
不安な国家に対する支援活動を改善し、紛争防止や汚職対策、食糧安全保障などに力を<br />
入れる。EUは国連平和構築委員会を含む多国間の枠組みで行動し、不安定な国々での<br />
オーナーシップやパートナーシップの原則の確立を目指す。<br />
エ.援助の増額、援助の質の向上<br />
� 援助の増額<br />
EUは、加盟国の国民総所得(GNI)に占める開発援助額の割合を 2015 年までに 0.7%(ミ<br />
レニアム開発目標の定めた数字)に引き上げることを目標とする。また、中間目標として、<br />
2010 年までにこの割合を 0.56%にする。開発援助における加盟国の優先課題を尊重しつつ<br />
187
も、増額される援助の尐なくとも半分はアフリカ大陸への援助に充当する。EUの援助額は、<br />
2010 年に 660 億ユーロに達する予定。<br />
「ミレニアム開発目標」を達成するため、後発開発途上国やその他の低所得国(LICs)へ<br />
の援助が優先される。中所得国(MICs)への援助も継続する。EUの開発途上国向けの全<br />
ての援助は、貧困の削減に集中して充当される。<br />
� 援助の効果改善<br />
EUは援助の増額を行うだけでなく、その質の改善を図る。援助の効果改善のため、2010<br />
年までに達成すべき具体的目標を定めることなどにより、援助のフォローアップに力を入れ<br />
る。その際、「援助の恩恵を受ける国によるオーナーシップ」、「援助のコーディネーション、ハ<br />
ーモナイゼーション」、「被援助国のシステムへの適合」、「成果指向(result orientation)」が<br />
基本的な原則となる。<br />
状況が許すならば、被援助国のオーナーシップを強化し、被援助国の国内での義務や手<br />
続きを支え、貧困削減の国内戦略に資金を供給するとともに、公共財政の健全かつ透明な<br />
運営を促進するため、「一般予算あるいはセクター別予算への支援」を強化する。<br />
また、EUは安定した先の見通せる援助メカニズムを構築し、被援助国が効率的なプラン<br />
を立てられるようにする。さらには、ひも付きでない援助(アンタイド援助)の割合を高め、こ<br />
の割合に関するOECDの現行の勧告を超えるものとする。<br />
オ..コーディネーションと補完性<br />
EC条約の精神に照らし、欧州共同体と加盟国は、コーディネーションと補完性の改善に努める。<br />
補完性を保証する最善の方法は、国レベル、地域レベルで被援助国の優先課題に答えることで<br />
ある。EUは、「援助のコーディネーション、ハーモナイゼーション」、「被援助国のシステムへの適<br />
合」という原則を促進する。<br />
EUはまた、被援助国の貧困削減などのための戦略に基づく多年度共同プログラム、共通実施<br />
メカニズム、協調融資(co-financing:政府とNGOによる出資)のメカニズムの使用に努めることで、<br />
援助提供者間のコーディネーションや補完性の改善を推進する。<br />
188
カ.開発援助政策の整合性<br />
EUは貿易、環境、気候変動、治安、農業、グローバル化の社会的側面、雇用、移民、研究、イ<br />
ノベーション、情報社会、運輸、エネルギーといった分野での開発援助政策の整合性を増すため<br />
の措置をとる。<br />
キ.EUの開発援助政策の在り方の定義<br />
共同宣言の第2部では、同宣言の第 1 部(ア.~カ.)で述べられたEUの開発援助のビジョンを<br />
実施する上でのEUの開発援助政策の在り方が定義され、EUレベルでの具体的行動の優先課<br />
題が明確にされている:<br />
� 開発援助分野のEUレベルの政策は、加盟国の政策を補完するものでなくてはならない。<br />
� 第1部で定義されたように持続可能な開発の枠内での貧困の撲滅、特に「ミレニアム開発<br />
目標」の達成、民主主義、グッドガバナンス、人権の尊重の奨励がEUの開発援助政策の<br />
主要な目標となる。EUレベルでは、全ての開発途上国でこれらの目標を追求し、域外国と<br />
の全てのEU協力戦略の構成要素である開発援助にこれらの目標が盛り込まれる。<br />
� EUは第1部で定義された全ての原則、特に援助の効果に関する原則「被援助国のオーナ<br />
ーシップ、パートナーシップ、コーディネーション、ハーモナイゼーション、被援助国のシステ<br />
ムへの適合、成果指向(result orientation)]を適用する。<br />
ク.EUの固有な役割<br />
EUは、世界レベルでのプレゼンス、援助実施のノウハウ、開発援助政策の整合性やグッドプラ<br />
クティスの奨励における役割、援助のコーディネーション、ハーモナイゼーションの円滑化におけ<br />
る役割、民主主義、人権、グッドガバナンスの支持、市民社会の参加の推進、南北間の連帯の促<br />
進における役割などを通じ、開発援助政策に付加価値をもたらす。<br />
ケ.状況やニーズに応じた差別化されたアプローチ<br />
EUの開発協力の実施は、対象となる国あるいは地域で個別に実施される。開発援助措置は、<br />
対象国あるいは地域のニーズや戦略、優先課題などに基づき個別に策定される。被援助国の多<br />
様性や達成すべき目標の違いから、差別化されたアプローチの採択は不可避となる。<br />
189
コ.柔軟性を保ちつつ、集中(concentration)の原則を適用<br />
国別、地域別の援助プログラムの策定に当たり、援助の効率を保証するのに重要な集中の原<br />
則が適用される。多くの分野に援助を分散する代わりに、行動分野を限定して援助プログラムを<br />
策定する。<br />
サ.EUの行動分野<br />
援助対象国のニーズに答えるため、EUは以下のような分野に活動を集中する:<br />
� 貿易、地域統合<br />
� 環境、天然資源の持続可能な管理<br />
� インフラ、コミュニケーション、運輸<br />
� 水、エネルギー<br />
� 農村開発、国土整備、農業、食糧安保<br />
� ガバナンス、民主主義、人権、経済改革や制度改革の支援<br />
� 紛争防止、国家の不安定化の防止<br />
� 人間開発(健康、教育、文化、男女平等)<br />
� 社会的結束、雇用<br />
シ.「メインストリーム化」アプローチの強化<br />
全てのイニシアティブに適用される一般原則に関係するため、多角的アプローチが必要となる<br />
一部の問題に関しては、EUは、「メインストリーム化」のアプローチを強化する。民主主義、人権、<br />
グッドガバナンス、子供や原住民の権利、男女平等、持続可能な環境、エイズ対策といった問題<br />
がこれに該当する。<br />
ス.ニーズやパフォーマンスに応じた開発援助の実施方法<br />
援助方法は、援助対象国のニーズや状況に応じて採択される。条件が揃っている場合は、経<br />
済、財政改革、貧困削減戦略(PRS)への支援方法として、「予算への支援(budget support)」が<br />
選択される。<br />
190
EUは常に、成果とパフォーマンス指標に基づくアプローチをとる。提示される条件は段階的に、<br />
成果の観点から定式化され、交渉により得られた相互の約束に基づく「契約」の形態に変えられ<br />
る。<br />
セ.マイクロファイナンスをベースとするアプローチ<br />
マイクロファイナンスをベースとするアプローチは、近年の重要なイノベーションといえる。能力<br />
の向上(capacity building)、必要なノウハウを持つ組織の設置に重点を置きながら、マイクロファ<br />
イナンスのようなタイプの支援を拡大する。<br />
参考1 EUの無償援助(grant)拠出の原則<br />
EUの援助は、主に無償援助(grants) 6 の形で実施される。この形態は、特に最貧国や返済能<br />
力が限定されている国々に最も適している。<br />
以下がその原則となる。<br />
・一部の例外を除き 100%の援助は行わず、必要な資金を補完する。<br />
・援助の支給を受ける者を利益に導くことが目的ではなく、援助対象となる活動の財政的均衡<br />
を目指す。<br />
・毎年、援助のための作業プログラムを策定し、その枠内で提案の募集を行う。<br />
・募集の際に定められた基準に従い提案の評価を行い、選出された案件に補助金を拠出する。<br />
※ミレニアム開発目標<br />
EUは、開発援助において持続可能な開発の枠内での貧困の撲滅を最優先課題としており、中<br />
でも国連の「ミレニアム開発目標」の達成を重視している。<br />
ミレニアム開発目標:<br />
� 極度の貧困と飢餓の撲滅<br />
� 初等教育の完全普及の達成<br />
� ジェンダー平等推進と女性の地位向上<br />
� 乳幼児死亡率の削減<br />
� 妊産婦の健康の改善<br />
6 http://ec.europa.eu/grants/introduction_en.htm<br />
191
� HIV/エイズ、マラリア、その他の疾病の蔓延の防止<br />
� 環境の持続可能性の確保<br />
� 開発のためのグローバルなパートナーシップの推進<br />
欧州委員会は、『ミレニアム開発目標の達成に向けた進歩の加速—EUの寄与』と題するコミュ<br />
ニケーション(指針)[COM(2005)132] 7 において、ミレニアム開発目標の達成を加速するため、<br />
「援助の増額」、「援助の質の改善」、「開発援助政策の整合性」、「アフリカへの援助の優先」を提<br />
案した。<br />
ア.援助の増額<br />
加盟国は、国民総所得に占める開発のための公的援助予算の割合を 2010 年までに 0.51%<br />
(新加盟国は 0.17%)とすることを目標とする。EU全体では、この割合は 0.56%となり、2015 年に<br />
は国連の定めた目標(0.7%)に近づくことになる。<br />
イ.援助の質の改善<br />
援助の提供者間のコーディネーション、ハーモナイゼーションを強化し、被援助国の開発戦略<br />
に沿った援助を実施することにより、援助の効率が改善され、コストの削減にもつながる。<br />
ウ.開発援助政策の整合性<br />
ミレニアム開発目標の達成のためには、開発援助政策は不可欠といえるが、それだけでは十<br />
分とはいえず、開発援助政策以外の他の政策も重要となる。EUの殆ど全ての政策が、開発途上<br />
国に直接的、間接的に影響を及ぼすことを考慮し、その整合性に留意する。<br />
エ.アフリカへの援助の優先<br />
サハラ以南のアフリカ諸国は「ミレニアム開発目標」の達成に関し、世界の他の国々に比べ大<br />
きく遅れをとっている。このためEUは、アフリカに開発援助を集中する。そのためにEUは、「アフ<br />
7 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0132:FIN:EN:PDF<br />
192
リカ諸国のガバナンスの改善」、「アフリカ諸国間のネットワーク(インフラ、サービス)、貿易の接<br />
続」、「公平な社会、基本的なサービスや一定水準の職業へのアクセス、持続可能な環境実現の<br />
ための努力」といった分野に努力を傾注する。<br />
参考 2 『アフリカのためのEU戦略』<br />
欧州委員会は 2005 年 10 月、『アフリカのためのEU戦略:アフリカの開発を加速するための欧<br />
州-アフリカ協定[COM(2005)489]』 8 を提案、同年 12 月の欧州首脳会議で同戦略が採択された。<br />
『アフリカのためのEU戦略』は、ミレニアム開発目標達成のためアフリカ諸国のために展開され<br />
ている努力を支援するため、EU加盟国のための行動の枠組みを規定するもの。<br />
旧ロメ協定、これに取って代わったコトヌ協定、あるいは南アフリカ共和国との通商・開発・協力<br />
協定(TDCA)、欧州-地中海連合協定など、EUとアフリカ諸国の間には多くの国際協定が存在す<br />
るが、『アフリカのためのEU戦略』では、アフリカとEUの関係を規定する以下のような基本原則が<br />
定められた:<br />
から<br />
・相互の制度尊重や相互の集団的利益の定義を基盤とする対等な関係<br />
・パートナーシップ:貿易や政治面での協力を基盤とする関係の発展<br />
・オーナーシップ:開発戦略、開発政策は、援助の対象となる国自身のためのものであり、外部<br />
強制されるものではない。<br />
EUは、ミレニアム開発目標達成のための前提条件とみなされる分野、つまり経済成長、貿易、<br />
社会的結束などに適した環境を作るための平和、治安、グッドガバナンスといった分野での援助<br />
を強化する。<br />
貧困削減に寄与するためEUは、アフリカ諸国のマクロ経済の安定を支援し、地域統合市場の<br />
形成を助けることで、アフリカにおける経済成長を加速させる。アフリカでは、輸送や通信サービ<br />
ス、水、エネルギー、衛生設備へのアクセスが限定されていることで、経済成長にブレーキがかか<br />
っている。こうした状況を改善するためEUは、「インフラのためのEU-アフリカ・パートナーシップ」<br />
を提案した。<br />
8 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0489:FIN:EN:PDF<br />
193
参考 3 『EU-アフリカ戦略的パートナーシップ』<br />
『アフリカのためのEU戦略』の採択から 2 年後の 2007 年 6 月、欧州委員会は、『カイロからリス<br />
ボン:EU-アフリカ戦略的パートナーシップ[COM(2007)357]』 9 と題するコミュニケーション(指針)<br />
で、『EU-アフリカ戦略的パートナーシップ』を提案した。<br />
EUとアフリカ諸国は、『アフリカのためのEU戦略』の次ぎの段階として、共同戦略の策定が必<br />
要との認識で一致、単なる開発援助の枠内に留まらず、共通の政治的課題や共通の利害に関係<br />
する問題にまで政治対話を拡大、強化するため『EU-アフリカ戦略的パートナーシップ』が採択さ<br />
れた。<br />
『EU-アフリカ戦略的パートナーシップ』は、次の4つの政治的課題を追求する。<br />
・対等な真のパートナーシップを構築するため、両者のパートナーシップを強化する。<br />
・平和、治安、ガバナンス、人権、貿易、地域統合、といった開発の鍵となる問題への取組。<br />
・世界レベルの挑戦への共同の取組。<br />
・広範かつ多様で人を中心としたパートナーシップの促進。<br />
欧州委員会は、具体的には以下のような共同イニシアティブを提案している。<br />
エネルギーに関するパートナーシップ<br />
このパートナーシップは以下のような目的を持つプラットフォームを形成する。<br />
・エネルギー資源へのアクセス、エネルギー安保といった問題に関する既存の対話を強化<br />
する。<br />
・エネルギー・インフラへの投資を強化する。<br />
・石油や天然ガスから得られる収入の多くを開発関連の活動に充当する。<br />
・開発協力に気候変動問題を統合する。<br />
このパートナーシップでは、「インフラのためのEU-アフリカ・パートナーシップ」やエネルギーの<br />
ためのEUイニシアティブ、ACP-EUエネルギー基金、第 10 次欧州開発基金の枠内での国内・地<br />
域指標プログラムなどが活用される。<br />
気候変動に関するパートナーシップ<br />
このパートナーシップでは、次のような分野での協力を強化する。<br />
・大災害に関連するリスクの削減<br />
・森林伐採との戦い<br />
・世界炭素市場への開発途上国の参加<br />
9 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0357:FIN:EN:HTML<br />
194
・環境に優しい技術の利用促進<br />
・気候変動の環境への影響のフォローアップの改善<br />
移民、モビリティー、雇用に関するイニシアティブ<br />
移民に関しては、アフリカ移民監視所ネットワークを構築、アフリカ諸国間、アフリカとEU間の<br />
移民のフローに関するデータの収集、分析を行う。モビリティー分野では、移民に関する情報管理<br />
分野でのアフリカ諸国の能力強化を行い、雇用分野では、欧州への移民に取って代わる選択肢<br />
をアフリカの人々に与えるため、アフリカでの雇用創出に力を入れる。<br />
民主的ガバナンスに関するイニシアティブ<br />
アフリカ諸国の市民社会、国会、地方議会、地域機関などを結集するガバナンス・フォーラムを<br />
設置し、人権、天然資源の管理といった共通関心事項のガバナンスの問題に関する対話を強化<br />
する。<br />
② 支援機関・支援スキーム<br />
1)開発援助の実施<br />
出所:欧州委員会<br />
図表 38 EUの援助実施体制<br />
195
a.開発総局<br />
欧州委員会の開発総局は、総合的な開発政策やセクター別の開発政策を企画立案する役割<br />
を担う。同総局がカバーするテーマやセクターとしては、「貿易と開発のリンク、地域統合と地域協<br />
力のリンク」、「マクロ経済政策への支援」、「社会サービスへの公正なアクセスの促進」、「交通の<br />
改善」、「食品安全の促進」、「持続可能な農村部の発展」、「制度強化の支援」のようなものが挙<br />
げられる。<br />
2010 年度(暦年)の開発協力予算(EU予算)は 25 億ユーロで、2009 年(24 億ユーロ)に比べ<br />
3.9%増加している。このほかACP諸国や加盟国の海外国・領土(OCT)向けの開発援助に使用<br />
する財源としては、欧州開発基金(EDF)が存在する。EDFは、EU予算に組み込まれておらず、<br />
加盟国が直接資金を提供している。2008 年から 2013 年までをカバーする第 10 次EDF予算は 226<br />
億 8,200 万ユーロで、このうち 97%がACP諸国向けのもの。<br />
開発総局は、ACP諸国およびOCTとの関係に責任を持つ。これに対した以外関係総局は、ア<br />
ジア、中南米、中東といったACP以外の域外国との関係に責任を持つ。援助の実施は、欧州開<br />
発援助協力局(Europeaid)の役割となる。<br />
b.欧州援助協力局(Europeaid)の役割<br />
Europeaid 10 は、援助の管理、実施のハーモナイゼーション、簡素化を図り、援助をより効果的な<br />
ものとするため、2001 年 1 月に創設された。<br />
Europeaid は、欧州委員会の総局(Directorate General)の 1 つで、対外援助のプロジェクトやプ<br />
ログラムの実施を担当する。Europeaid は、EUの近隣諸国、ロシア、アフリカ・カリブ海・太平洋諸<br />
国(ACP)、ラテンアメリカ諸国、アジア諸国と緊密に協力して活動する。<br />
プロジェクトの実施に際し Europeaid は、援助の提供に関するEUの長期的な戦略、プログラム<br />
を考慮する。これらの戦略や関連政策は、ACP諸国に関しては開発総局で、その他の域外国に<br />
関しては対外総局で策定される。<br />
Europeaid はまた、対外援助実施の整合性、補完性、コーディネーションを保証するため、市民<br />
社会の組織(NGOを含む非国家主体)、国際機関、EU加盟国の議会、EUの諸機関と緊密に協<br />
10 http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm<br />
196
力する。<br />
Europeaid は次の役割を担う。<br />
� EUが提供する援助がEUの開発政策の目的や国連のミレニアム開発目標の達成に寄与<br />
することを保証する。<br />
� 援助の必要性が特定されると、フィジビリィティ調査を実施し、必要な全ての財政面でのコ<br />
ントロール、決定の準備を行い、入札や監視、評価に要求される手続きを策定する。<br />
� 開発援助政策の具体的な実施や、「予算への支援(budget support)」、「セクター別アプロ<br />
ーチ」といった新しい援助の提供方法の開発を行う。<br />
c.欧州援助協力局(Europeaid)の構造<br />
Europeaid は、対外関係を担当するアシュトン副委員長(EU外務・安全保障上級代表兼務)の<br />
指揮下にある。また、欧州近隣諸国政策(ENP)を担当するフィーレ委員や、欧州委員会で開発<br />
政策を担当し、ACP諸国との関係の責任者でもあるピエバルグス委員も Europeaid の活動に重要<br />
な役割を演ずる。<br />
Europeaid は、欧州委員会のデグフト委員(通商担当)やフィーレ委員(拡大も担当)、レーン委<br />
員(経済・財政問題担当)といった対外関係に関連する欧州委員のグループ(議長:バローゾ欧州<br />
委員会委員長)に定期的な報告を行う。<br />
EU予算や欧州開発基金(EDF)を財源とする欧州委員会の対外援助手段の実施を担当する<br />
Europeaid 総局には、7 つの部局が存在する 11 :<br />
A 局:欧州、地中海南部、中東、近隣諸国政策に参加する国々を担当<br />
B 局:ラテンアメリカを担当<br />
C 局:サハラ以南のアフリカ諸国、カリブ海・太平洋諸国を担当<br />
D 局:アジア、中央アジアを担当<br />
E 局:援助プログラムの質を監視<br />
F 局:特定の地域に限定されない全ての横断的プログラム(人権、環境保護、食糧安保、原子<br />
力安全等)を監督するテーマ別プログラムを担当<br />
G 局:総局の使命を達成するのに必要な人材、財源などを供給<br />
A〜D 局は、国毎、地域毎の活動実施のプランニングを行い、プロジェクトの特定、評価のため、<br />
現地で援助の実施を担当する欧州委員会代表部向けのガイドラインや指令を採択する。E 局との<br />
11 http://ec.europa.eu/europeaid/who/documents/organigramme_europeaid_en.pdf<br />
197
協力のもと、援助実施方法の整合性や質を保証する。資金拠出の決定に至るまでの手続きを管<br />
理する。現地で援助の実施を担当する欧州委員会代表部を支援する、あるいは代表部に委任で<br />
きない活動を指揮し、プロジェクトの効果、インパクトの最大化を図る。<br />
d.援助プログラムの策定<br />
EUの開発援助は、複数年の援助プログラムの形で実施される。ACP諸国への援助に関して<br />
は開発総局と、その他の域外国への援助に関しては対外総局とのコーディネーションのもと、援<br />
助が実施される。<br />
欧州委員会は援助対象国の所轄当局との協議を通じ、プログラムを策定、運営する。協議を通<br />
じEUと援助対象国との間に戦略文書 12 が締結される。<br />
プログラム策定の段階で、国レベル、セクター・レベルの状況分析が行われ、協力を実施する<br />
際の問題点や制約、可能性などが特定される。状況分析では、経済社会指標、EU並びに援助対<br />
象国の優先課題の評価が行われる。プロジェクトやプログラムを定義し、準備するのに適切かつ<br />
実現可能な枠組みを構築するため、開発援助のための主要な目標やセクター別の優先課題を特<br />
定することがその目的となる。<br />
ア.政策の整合性<br />
EUの支援戦略は、「開発のための欧州コンセンサス」や「貧困対策」、「持続可能な開発の奨<br />
励」、「国連ミレニアム開発目標の達成」といった文書に述べられるEUの開発政策の優先課題に<br />
適合した形で定義される。支援戦略の採択に当たっては、EUの開発政策以外の分野の政策(貿<br />
易、環境、移民、雇用、社会的結束、農業等)との整合性を保証するための努力が行われる。<br />
イ.オーナーシップ<br />
EUは、開発援助に際し援助対象国の「オーナーシップの原則」を適用する。援助対象国は、同<br />
国を対象とする戦略やプログラムの策定に全面的に関わる。援助対象国のオーナーシップは、対<br />
12 http://ec.europa.eu/external_relations/sp/index_en.htm<br />
198
象国固有のニーズにより良く合致するEUの開発援助の柔軟性を強化することになる。<br />
また、援助プログラムの策定に当たっては、援助対象国、EU加盟国やその他の二国間援助、<br />
多国間援助の提供者との協議が行われ、各々の援助活動の補完性が保証されるようにする。共<br />
同プログラムの策定や役割の分担に関する協議も検討される。<br />
ウ.共同決定プロセス<br />
欧州議会、EU加盟国の政府、議会は、援助プログラムの策定プロセスに参加する。これらの<br />
機関は、欧州委員会の提案する政策、多年度の財政見通し、年度予算の修正、承認に関わり、<br />
欧州委員会が運営する各プログラムのための戦略にそれぞれの見解を示す。<br />
援助対象国毎の戦略文書は、加盟国の代表に提示され、その同意を得て欧州委員会が最終<br />
的な決定を下す。<br />
e.援助の運営・フォローアップの欧州委員会代表部(European Commission Delegations)への移<br />
管<br />
欧州委員会は 2000 年に、域外での対外援助、開発援助の組織、実施の改善を図るための改<br />
革に着手した。援助対象国のニーズに援助活動を適合させ、援助提供者間のコーディネーション<br />
を円滑に行うため欧州委員会は、対外援助の管理の責務を域外国に存在する欧州委員会代表<br />
部に委ねることを決定した。<br />
現在、アフリカ・カリブ海・太平洋、アジア、西バルカン、東欧、ラテンアメリカ、地中海、中東に約<br />
110 の欧州委員会代表部が存在する。代表部は、駐在する国の状況を欧州委員会に報告すると<br />
ともに、現地の政府や市民社会に対する欧州委員会のスポークスマンの役割を果たす。<br />
対外援助、開発援助に関しては、代表部はプロジェクトの特定、フィジビリティの評価、援助の<br />
実施、成果の評価を行う。ブリュッセルの EuropeAid は、援助活動全体を統轄し、必要な支援を行<br />
う。また、原子力発電部門での改革支援といった非常に特殊な分野の援助、複数の国々を対象と<br />
する地域援助プログラムや横断的な援助プログラムに関しても、EuropeAid がブリュッセルから直<br />
接運営に当たる。<br />
199
代表部はまた、「援助効果の向上に関するパリ宣言」や「ミレニアム開発目標」のような多国間<br />
協定や合意の実施に当たり重要な役割を演ずる。<br />
代表部が現地で援助の管理を行うことで以下のような利点がもたらされた:<br />
・EUの援助がより迅速かつ効果的に実施される。<br />
・EUの対外援助のもたらすインパクトが改善される。<br />
・現地でEU加盟国がより緊密に協力できる。<br />
・欧州委員会がアクセスし易い援助パートナーと見なされる。<br />
なお、OECDは 2007 年、EUの開発援助の政策やプログラムの評価を実施、「代表部への権限<br />
の移管は、現地で援助対象国の高い評価を受けており、EUの援助効果改善に大きく寄与したと<br />
見なされている」と結論している。<br />
f.援助方法<br />
援助は、セクター別アプローチによる特定のプロジェクトの形で、あるいは援助対象国政府の予<br />
算支援の形で実施される。<br />
欧州委員会は、NGOや民間企業の実施する公共部門以外のイニシアティブへの支援にプロジ<br />
ェクト別アプローチを使用する。また、セクター別アプローチあるいは予算支援のアプローチが使<br />
用できない場合に、プロジェクト別アプローチが使用される。<br />
EuropeAid は、EUの政策が追求する目的と援助対象国のそれが合致する形でプロジェクトを運<br />
営する。開発援助の効果の原則に従い、プロジェクトは、援助対象国の国内政策を支援するもの<br />
であるとともに、持続可能で、現実的な目標を掲げたものでなくてはならない。<br />
欧州委員会は援助対象国の政府、援助提供者、その他のステークホルダーと共に活動するた<br />
めセクター別アプローチを採用する。このアプローチは近年、頻繁に使用されるようになっている。<br />
欧州委員会は可能である場合、援助対象国のオーナーシップを強化する援助方法である予算<br />
への支援を優先する。<br />
200
ア.セクター別アプローチ<br />
このアプローチは、自国の開発に関する政策や戦略、支出のオーナーシップを援助対象国の<br />
政府に保証する。また、同アプローチは、国内政策、セクター別の政策、資金の割当、支出行為を<br />
より整合性のあるものとする。<br />
イ.セクター別政策支援プログラム(Secteur Policy Support Programme:SPSP)<br />
援助対象国の政府のセクター別プログラムを支援するために策定された欧州委員会のプログ<br />
ラムで、次のようなものをその財源とする:<br />
� 可能であれば、セクター別の予算支援が優先される。これは、ステークホルダー間で合意<br />
に達したセクター別の目標達成のために使用するため、援助対象国政府の国庫に資金を<br />
補充するもの。<br />
� セクター別プログラムの特定の活動グループのための共通資金あるいは共通バスケット<br />
資金(様々なドナーが提供した資金をプールしたもの)。通常、援助提供者の中の一人が<br />
プールされた資金のコーディネーション、管理を行う。定められた基準に従い、援助対象国<br />
の政府に移転される。<br />
� 契約や政府調達に関する規則に従う欧州委員会の手続き。<br />
ウ.プログラムをベースとするアプローチ(PBA)<br />
PBAは、援助対象国の開発プログラムへの協調支援の原則をベースとする開発協力を実施す<br />
るための手段。プログラムの策定、実施、資金運用、監査、評価に援助対象国のシステムを使用<br />
するために払われる努力もPBAの重要な特性となる。セクター別アプローチは、あらゆるセクター<br />
におけるPBAといえる。<br />
g.援助プログラムの質の評価<br />
開発援助のプロジェクトやプログラムが、高いレベルの質に達し、それを維持するため、評価や<br />
フォローアップが実施される。<br />
201
ア.対外援助の質の評価<br />
EuropeAid の対外援助の見直しを行うのは品質支援事務所グループ(OQSGs:Office Quality<br />
Support Groups)で、援助の策定段階(programming、identification、formulation)や援助の効率、<br />
インパクト、成果を重視する欧州委員会が開発援助政策や開発援助の質を改善するのに不可欠<br />
の機関となっている。<br />
OQSGsは、援助計画の準備段階の初期に介入し、質の高い措置の特定、策定を支援する。O<br />
QSGsはまた、援助策定段階における現地の欧州委員会代表部と欧州委員会の情報交換を円<br />
滑なものにする。<br />
現在、OQSGsは5つ存在し、EuropeAid の地域別の部局(A〜D 局)にそれぞれ1つ、テーマ別<br />
予算の対象となる援助を担当するものが1つある。主に EuropeAid の人員が配置されるが、対外<br />
総局や開発総局の援助策定の責任者や欧州委員会代表部のメンバーもOQSGsの会合に参加<br />
できる。<br />
イ.プロジェクトやプログラムの質の評価<br />
EuropeAid は、「成果指向モニタリング(result oriented monitoring:ROM)」により、プロジェクト<br />
やプログラムの進捗状況の概観を得ることができる。 プロジェクトやプログラムが、期待される成<br />
果を得られる形で策定されたか否かが非常に重要となる。<br />
ROMシステムは、外部の専門家が現地で実施する進行中のプロジェクトやプログラムの定期<br />
的な評価を基盤とする。評価基準の指標パラメータは、「計画に従って実施された」と定義される。<br />
適切性、効率、効果、潜在的インパクト、持続可能性といった基準について、「計画よりも良好」あ<br />
るいは「計画に及ばない」といった評価がくだされる。平均的パフォーマンスを実現しているプロジ<br />
ェクトは、計画を遵守しており、期待される成果をもたらす可能性が高いことになる。<br />
ROMシステムの評価の対象となるのは、EUが 100 万ユーロあまりを拠出するプロジェクトで、<br />
それ以下の規模のものに関しては、評価対象として全体の 10%がサンプル抽出される。<br />
202
h.加盟国との協力、補完性<br />
欧州委員会は、『開発政策における役割の分担に関するEU行動規範[COM(2007)72]』 13 と題<br />
するコミュニケーション(指針)において、EUの開発協力政策のパフォーマンスを改善するため、<br />
開発途上国におけるEUの援助提供者(欧州共同体と加盟国)間の役割の補完性を強化し、より<br />
良い役割分担を実現するための行動規範を提案した。行動規範は、2007 年 5 月 15 日の一般問<br />
題・対外関係理事会で採択された。<br />
援助が同じ国、同じセクターに集中するのは良くあることだが、その場合、援助対象国において<br />
余分なコストが発生するほか、汚職のリスクが増すといった問題が発生する。一方で、一部の<br />
国々には全く援助が行われないと行った状況が現出する。<br />
こうした事態を避けるため欧州委員会は、行動規範の策定を提案した。欧州委員会は、行動規<br />
範を「人的資源、財源の最良な使用を実現するための様々な関係者間の役割の最適な分担」と<br />
定義している。各関係者は、他の者がすることと比較し、自分が最も付加価値をもたらすことので<br />
きる比較優位の分野での協力に集中するのが望ましい。<br />
行動規範は開発協力分野における補完性の原則を定めるもので、現地で獲得されたグッドプラ<br />
クティスをベースとしている。また、「援助効果の向上に関するパリ宣言」に含まれる原則(オーナ<br />
ーシップ、ハーモナイゼーション、成果指向、被援助国のシステムへの適合、相互責任)や、補完<br />
性を重視する『欧州コンセンサス』を踏襲している。<br />
補完性の原則を規定するガイドラインとして、次のようなものが挙げられている:<br />
� 被援助国での特定分野(focal sector)に活動を集中する:EUの援助提供者(EU加盟国、<br />
諸機関、企業、NGO等)は、それぞれの比較優位性がある2分野に援助を集中するのが<br />
望ましい。<br />
� 国内レベルの他の活動(non-focal sector)に援助を再配分する:『non-focal sector』に関し<br />
ては、援助提供者は協力協定の枠内で援助を継続するか、同セクターへの援助を止め予<br />
算への支援に財源を再配分する。<br />
� 各優先セクターでの筆頭援助提供者合意の締結を奨励する—コスト削減のため、各優先<br />
セクターの援助提供者間のコーディネーションを担当する責任者:決める。<br />
� 委任協力/パートナーシップ合意の締結を奨励する—筆頭援助提供者が、全ての援助提<br />
13 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0072:FIN:EN:PDF<br />
203
供者を代表して財源の管理や、援助対象国政府との実施措置に関する対話を行う。<br />
� 戦略的セクターへの適切な支援の実施を保証する—尐なくとも1人の援助提供者が、貧困<br />
の削減にとり重要とみなされるセクターで積極的に活動する。また、各セクターに最大3〜<br />
5の援助提供者が存在するようにする。<br />
� 地域レベルでの役割の分担を行う。<br />
� EU内での話し合いを通じ、各援助提供者のための限定された優先援助対象国を指定す<br />
る。<br />
� 援助の対象となりにくい国々(国情が不安定な国)にも適切な援助を行い、多額の援助を<br />
受ける国とのバランスをとる。<br />
� 比較優位にある分野の分析、拡大:EUの援助提供者は、自分が他と比較して優位にある<br />
分野の評価を深め、専門化に努める。<br />
� 補完性の強化:国レベル、地域レベル、国際レベルで実施される類似の援助活動間のシ<br />
ナジーを推進する。<br />
� 援助システムの構造改革に取り組む。<br />
行動規範は、現地での経験や成果のフォローアップからの教訓を活かしながら更新される予定<br />
で、2010 年までに見直しが行われる。<br />
i.民間部門の役割<br />
欧州委員会にとり、開発援助の現場のニーズを知る上で、NGOを含む市民社会(civil society)<br />
の 組 織 は 不 可 欠 の パ ー ト ナ ー で あ る 。 開 発 援 助 に お け る 市 民 社 会 組 織 ( civil society<br />
organisations:CSO)あるいは非国家主体(non-state actors:NSO)の役割は、プロジェクトの実<br />
施に限定されず、被援助国のオーナーシップに立脚した貧困との戦いにおいて国家と責任を分担<br />
する方向に向かっている。<br />
NGOやその他の市民社会組織は、テーマ別プログラムや地域別プログラムの提案募集に応じ<br />
ることで、EuropeAid から資金の提供を受けることができる。<br />
ア.地域別プログラム<br />
同プログラムでは、市民社会組織への支援は、戦略的優先課題と位置づけられており、開発戦<br />
略に関する国家機関との対話への参加を市民社会組織に奨励している。また、EUは、市民社会<br />
組織の能力強化統合プログラムを通じ、市民社会組織の強化に取り組んでいる。<br />
204
同プログラムの財源は、次のとおり。<br />
� 欧州開発基金(European Development Fund:EDF)<br />
� 開発協力手段(Development Co-operation Instrument:DCI)<br />
� 欧州近隣連携手段(European Neighbourhood and Partnership Instrument:ENPI)<br />
イ.テーマ別プログラム<br />
テーマ別の活動は、人権の保護、民主主義の奨励、貧困の撲滅、食糧自足、教育、環境や衛<br />
生に関するプロジェクトといった分野で実施される。同プログラムは地域別プログラムと異なり、欧<br />
州委員会と援助対象国間の直接交渉の成果ではなく、大部分が市民社会組織の寄与により開か<br />
れている。<br />
次のようなテーマ別プログラムにおいて、市民社会組織は重要な役割を果たしている。<br />
� 開発における非国家主体と地方自治体<br />
� 欧州民主主義・人権手段<br />
� 社会的、人的開発<br />
� 環境と持続可能な開発<br />
� 食糧安全保障<br />
� 移民と亡命<br />
参考 4 官民パートナーシップ(Public-Private Partnerships:PPP)<br />
PPPは、公的機関と民間企業間の協力形態を指すもので、運輸、国民健康、教育、治安、廃棄<br />
物管理、水供給あるいはエネルギー供給といった分野で活用される。EUレベルでは、「成長のため<br />
の欧州イニシアティブ」や「欧州横断輸送ネットワーク(TEN-T)」の実現に寄与している。PPPは、<br />
その形態によっては政府調達に関するEUの指令の適用対象となる。<br />
PPPという表現が頻繁に使用されるようになったのは 1990 年代で、EUにはPPPの単一モデル<br />
は存在しない。PPPは、財政面での制約に直面する加盟国にとり、公共部門が必要とする民間部<br />
門による資金面での支援をもたらすものとなる。また、公共部門は、PPPを通じ民間部門の持つノ<br />
ウハウの恩恵を享受できる。経済分野における国家の役割が、直接のオペレーターという役割から<br />
組織、規制、管理という役割に移行していることもPPPが多くの分野で活用される一因となってい<br />
る。<br />
205
欧州では、空港、鉄道、道路、橋、トンネル、環境関連設備、学校、病院、刑務所といった公共イ<br />
ンフラの建設に関連する新たな投資が、加盟国によってその度合いは異なるが、しばしばPPPの<br />
枠内で実施されるようになった。<br />
欧州におけるPPPは、まず道路や鉄道といった運輸部門に集中し、次いで教育や国民健康部門<br />
に波及した。廃棄物、環境、港湾、エネルギーといった部門でもPPPが活用されるようになっている<br />
が、欧州投資銀行(EIB)によると「まだ臨界量に達していない」という。<br />
EU加盟国でPPPの先駆者と言えるのは英国で、これにポルトガル、スペイン、ギリシャ、オラン<br />
ダ、デンマーク、スウェーデンなどが続く。アイルランド、イタリア、フランス、ドイツなどでもPPPの顕<br />
著な増加が観察される。<br />
EIBのPPPに関する 2004 年 7 月 15 日付けのレポート『PPPにおけるEIBの役割』 14 によると、英<br />
国では、650 以上のプロジェクトがPPPの枠内での調達の対象となり、このうち 400 以上のプロジェ<br />
クトが始動。PPPに関連する投資支出は約 480 億ポンドに達した。英国のPPP市場は、EUのPPP<br />
市場の 25%あまりを占めている。<br />
EIBによると、2008 年 9 月の時点で、PPPによる投資額は 2,000 億ユーロに達し、2013 年までに<br />
さらに 1,000 億ユーロ以上が投入されると予想される 15 。<br />
また、EIBはPPPプロジェクト支援の枠内で 250 億ユーロあまりを融資しているが、融資はPPP<br />
タイプのプログラムが最も発達した国々に集中している。EIBが融資を行ったPPPプロジェクトの約<br />
80%は運輸部門(オランダの高速鉄道、フランスやスペインの都市交通等)に関するもので、残りの<br />
20%あまりは国民健康、教育、エネルギー、水の供給や汚水の処理に関するものだった。<br />
2)対外協力プログラム<br />
a.欧州開発基金(EDF)<br />
欧州開発基金(EDF)は、1957 年にローマ条約によって創設され、1959 年に初めて使用された。<br />
EDFは、アフリカ・カリブ海・太平洋(ACP)諸国や加盟国の海外国・領土(OCT)の開発援助にE<br />
Uが使用する主要な財源となっている。<br />
EDFは、「経済開発」、「社会的、人的開発」、「地域協力、地域統合」といった分野でACP、OC<br />
14 http://www.eib.org/attachments/thematic/eib_ppp_en.pdf<br />
15<br />
http://www.eib.europa.eu/about/press/2008/2008-078-european-institutions-take-lead-on-ppp-expertise.htm<br />
206
Tにおいて実施される行動を支援する。なお、EDFは、EU予算に組み込まれておらず、加盟国が<br />
直接資金を提供している。<br />
EDFには、次のような手段がある。<br />
� 欧州委員会の運営する無償援助(grants)<br />
� 投資基金の枠内で欧州投資銀行(EIB)が運営する民間部門へのリスクキャピタル、融資<br />
� 輸出収入の不安定さの否定的な影響を矯正することを目的とするフレックス・メカニズム<br />
EDFは、多年度(通常 5年間)にわたるもので、EUと援助対象国間に締結された国際協定の枠<br />
内で使用される。2008 年から 2013 年までの第 10 次EDFは、ACP-ECパートナーシップ協定によ<br />
り実施される。<br />
第 10 次EDF予算の規模は 226 億 8,200 万ユーロで、内訳はACP諸国向けのものが 219 億<br />
6600 万ユーロ(全体の 97%)、OCT向けのものが 2 億 8,600 万ユーロ(同 1%)、プログラム策定<br />
やEDF実施に関連する欧州委員会の支出のためのものが 4 億 3,000 万ユーロ(同 2%)となって<br />
いる。<br />
ACP諸国向けのEDFは次のように分配される。<br />
� 国レベルや地域レベルの指標プログラムに 177 億 6,600 万ユーロ(全体の 81%)<br />
� ACP諸国間、地域間の協力資金に 27 億ユーロ(同 12%)<br />
� 投資基金の資金に 15 億ユーロ(同 7%)<br />
EDFの恩恵を受けることができるのは、<br />
� ACP諸国あるいはEU加盟国の自然人あるいは法人<br />
� 国際機関、並びに国際機関の規則に従って適切と認められる自然人あるいは法人<br />
� 地域レベルで実施される行動に資金供与を行う場合は、当該行動に参加する国の自然人<br />
あるいは法人<br />
ア.マイクロファイナンスに関するACP-EUフレームワーク・プログラム<br />
同プログラムは、ACP諸国の貧困層の金融商品や金融サービスへのアクセスを改善すること<br />
を目的とするもので、2005 年 1 月に開始された。予算は、第 9 次EDFを財源とし、6 年間で 1,500<br />
万ユーロ。<br />
2005 年 6 月に同プログラムの枠内での提案募集が行われ、100 以上の提案が寄せられたが、<br />
207
最終的にマイクロファイナンス機関の強化に資する 11 の提案が採択され、援助が行われた。財源<br />
不足から新たな提案募集は予定されていない。<br />
○採択された提案<br />
※金融サービス、金融商品の多様化<br />
・中央アフリカの貧困層における貯蓄の奨励:ルワンダ、ブルンジ、コンゴ民主主義共和国(実<br />
施パートナー:URWEGO Community Banking SA)<br />
・新商品の開発および透明性の改善によるマイクロファイナンス機関の持続性の強化:ガーナ、<br />
ケ ニヤ、マラウイ、モザンビーク、ウ ガンダ、ザンビア(実施パートナー: Opportunity<br />
International UK)<br />
※新技術の導入<br />
・ProCredit Bank Congo の能力強化:コンゴ民主主義共和国(実施パートナー:ProCredit<br />
Holding)<br />
・マイクロファイナンス部門の専門化:セネガル(実施パートナー:Aquadev、Etimos)<br />
・過疎地でのマイクロファイナンスの強化、マイクロファイナンス部門の透明性の強化:サハラ以<br />
南のアフリカ諸国、ハイチ(実施パートナー:SIDI、Alterfin、MAIN)<br />
・Caisse Villageoises d’Epargne および Credit Autogerees のネットワークの再編:カメルーン(実<br />
施パートナー:MIFED、CIDR)<br />
・農村部の金融サービス協会の能力強化:ケニヤ(実施パートナー:Kenya Development<br />
Agency、Africa Now)<br />
※透明性の改善<br />
・市場のトレンドに追随するマイクロファイナンス機関や情報力のある消費者のための透明性<br />
のイニシアティブ:ウガンダ(実施パートナー:ウガンダ・マイクロファイナンス機関協会)<br />
・選択されたアフリカのマイクロファイナンス機関のリスク・マネージメントおよび透明性に関する<br />
パフォーマンスの公表のメインストリーム化:ウガンダ、ガーナ、タンザニア、ガンビアを含む<br />
アフリカ諸国(実施パートナー:Toriodos International Fund Management、FACET)<br />
※グリーンフィールド型マイクロファイナンス機関の設立<br />
・マダガスカルでのグリーンフィールド型マイクロファイナンス機関の設立(実施パートナー:LFS<br />
Financial Systems)<br />
・カメルーンでのグリーンフィールド型マイクロファイナンス機関の設立(実施パートナー:Horus<br />
Devlopment Finance)<br />
同プログラムの契約には、成果指向が重要な要素として盛り込まれている。プログラムの実施<br />
208
パートナーが立案し、定めた活動のパフォーマンス目標に応じ、3〜5 の基本指標が選択され、目<br />
標達成のための最低限のパフォーマンスが規定されている。最低限のパフォーマンスは、パフォ<br />
ーマンス目標よりも低く設定される。最低限のパフォーマンスが満たされなければ、フレームワー<br />
ク・プログラムの枠内での補助金が打ち切られることになる。パフォーマンス目標の達成状況は、<br />
四半期毎に検証される。<br />
る。<br />
ACP諸国におけるマイクロファイナンス活動を改善するため、次のようなアプローチがとられ<br />
・キャパシティ・ビルディング:リテール・サービスでの能力不足が、ACP諸国におけるマイクロフ<br />
ァイナンスの主要な制約の 1 つとなっている。こうした状況を改善するため、「マイクロファイナ<br />
ンスに関するACP-EUフレームワーク・プログラム」 は 2005 年 6 月の提案募集を通じ、11<br />
の提案に補助金を提供している。補助金は、「貧困者を対象とした金融サービスの多様化」、<br />
「マイクロクレジット以外の新金融商品の開発」、「テクノロジー利用の改善、透明性の強化」<br />
などに使用される。<br />
実施に当たっては、貧困層支援相談グループ(CGAP:Consultative Group to Assist the Poor)<br />
のようなマイクロファイナンス部門の専門機関が協力する。CGAPは、「マイクロファイナンスに関<br />
するACP-EUフレームワーク・プログラム」 における EuropAid の重要なパートナーであり、同フレ<br />
ームワーク・プログラムのコーディネーションのために人員を派遣している。このほか、欧州投資<br />
銀行(EIB)や自立的開発支援(ADA:Appui au Development Autonome)なども重要なパートナー<br />
となっている。<br />
CGAPやADAを含むプログラム実施パートナーのリストは注 16 参照。<br />
・格付け並びに情報システム—同プログラムでは、CGAPが監督する「格付け基金(Rating<br />
Fund)」を通じ、ACP諸国の 90 あまりのマイクロファイナンス機関(MFI)を特徴づけるリスク<br />
やパフォーマンスについて入手できる情報を改善するため、MFIの評価に対する協調融資<br />
(co-finance)が行われた。2008 年 1 月からは、情報システム・プログラムへの援助が開始さ<br />
れた。<br />
・透明性と効率の改善:フレームワーク・プログラム並びにCGAPはともに、MFIや金融商品の<br />
多様化の促進、透明性や規制環境の強化に取り組んでいる。CGAPは、アフリカを対象とし<br />
たイニシアティブを実施、アフリカ諸国の政府や中央銀行に助言を行っている。<br />
16 http://ec.europa.eu/europeaid/where/acp/regional-cooperation/microfinance/partners/links_en.htm<br />
209
2008 年 5 月に実施された『マイクロファイナンスに関するACP-EUフレームワーク・プログラム<br />
の中間評価』 17 では、5 年間で達成すべき目標の大半が 3 年間で達成されており、「キャパシティ・<br />
ビルディングやMIFの格付け、透明性並びに効率の改善を通じ、ACP諸国におけるマイクロファ<br />
イナンス活動の効率を改善するという目標は達成された」との結論が出されている。<br />
また、中間評価は『マイクロファイナンスに関するACP-EUフレームワーク・プログラム』を引き<br />
継ぐ新たなプログラムの策定を勧めている。<br />
イ.ACP-EUエネルギー基金(ACP-EU Energy Facility)<br />
図表 39 ACP-EUエネルギー基金 (ACP-EU Energy Facility)<br />
出所:Europeaid<br />
エネルギー基金は、ACP諸国の農村部や都市周辺部での持続可能かつ安価なエネルギー・<br />
サービスへのアクセスを改善するプロジェクトを支援するための協調融資(co-finance)の手段で、<br />
2005 年 6 月 24 日のACP-EU理事会において基金の創設が承認された。<br />
ACP諸国の農村部での電力へのアクセス率は全体の 10%あまりに過ぎない。エネルギーへの<br />
アクセスを保証することが、経済成長や社会福祉の前提条件となることから欧州委員会も同基金<br />
の設立を支持した。<br />
17 http://ec.europa.eu/europeaid/where/acp/regional-cooperation/microfinance/documents/mid_term_review_eu<br />
acp_microfinance_programme_en.pdf<br />
210
欧州委員会は、「EUエネルギー・イニシアティブ(EUEI)」 18 の枠内でエネルギー基金を設立した。<br />
EUEI は、ミレニアム開発目標達成のための努力の一環として、2002 年の持続可能な開発に関す<br />
る世界首脳会議(WSSD、ヨハネスブルク・サミット)の際にEUが開始したイニシアティブで、EUEI<br />
自体は、エネルギー問題を解決するために新たな資金を供与することはない。関係者の対話を通<br />
じ、既存の人材、資金の利用方法を調整し、効率的に活用するための枠組みとパートナーシップ<br />
を構築することが EUEI の役割となる。<br />
� 第 1 次エネルギー基金<br />
第 1 次エネルギー基金は、第 9 次EDFの枠内で開始され、予算総額は 2 億 2,000 万ユーロ。<br />
2006 年 6 月 19 日にプロジェクトの提案募集が開始され、欧州委員会は 2007 年 7 月 17 日、最終<br />
的な提案の選択を承認した 19 。最終的に承認されたプロジェクトは 74 件だった(プロジェクトの詳細<br />
は脚注 20 を参照)。第 9 次EDFからの協調融資(co-finance)のための援助総額は 1 億 9,600 万ユ<br />
ーロで、全プロジェクトの総コストは 4 億 3,000 万ユーロ。<br />
選択されたプロジェクトのタイプは、農村部、都市周辺部でのエネルギー・サービスへのアクセ<br />
スの改善に関わるもので、小規模のイニシアティブに全体の 30%、大規模インフラ・プロジェクトが<br />
61%、エネルギーに関する経営、ガバナンスの改善が 5%、エネルギー部門における国境を越え<br />
た協力の改善が 4%だった。<br />
欧州委員会の拠出した援助の 67%は、ACP諸国の申請者に与えられ、26%は欧州の申請者<br />
に与えられた。残りの 7%は国際機関に与えられた。援助の大部分(8,200 万ユーロ)は、ACP諸<br />
国の公的機関に供与された。また、選択されたプロジェクトに参加したNGOの数は 26(EU:19、A<br />
CP:7)に達し、殆どが小規模なイニシアティブに参加している。<br />
援助の恩恵を受けた民間企業は 12(ACP諸国:7、EU:5)で、小規模イニシアティブや大規模<br />
インフラ・プロジェクトに参加した 21 。これらの企業は、エネルギー基金から総額 7,400 万ユーロ(基<br />
金の 38%)の援助を受け、協調融資(co-finance)により援助総額は最終的に 7,900 万ユーロに達<br />
した。一方、参加企業の出資総額は 1,460 万ユーロ(ACP企業:1,080 万ユーロ、EU企業:380 万<br />
ユーロ)だった。<br />
18<br />
http://www.euei.net/<br />
19<br />
http://ec.europa.eu/europeaid/where/acp/regional-cooperation/energy/documents/analysis_of_1stcfp_results_en.pdf<br />
20<br />
http://ec.europa.eu/europeaid/where/acp/regional-cooperation/energy/documents/1ef_cfp_contracted_projects_en.<br />
pdf<br />
21<br />
http://ec.europa.eu/europeaid/where/acp/regional-cooperation/energy/documents/private_sector_position_paper_en<br />
.pdf<br />
211
エネルギー基金の擁する手段は無償援助(grants)であり、融資や長期保証は含まれない。ま<br />
た、エネルギー基金の無償援助(grants)に適用される規則 22 によると、プロジェクト実施期間中に<br />
無償援助が利益を生み出すことがあってはならない。このため民間企業にとりこの種の事業に参<br />
加するメリットは、「新市場への進出」、「企業イメージの改善」、「知識や経験の蓄積」、「顧客との<br />
関係強化」などということになる。<br />
74 プロジェクトのうち 48 のプロジェクトは、エネルギーの生産、変換、送電活動に集中。また、34<br />
件のプロジェクト(全体の 77.27%)は、エネルギー生産源として再生可能エネルギーのみを使用<br />
するものだった。化石燃料のみを使用するプロジェクトは 1 件だけだった。最終的に第 1 次エネル<br />
ギー基金の恩恵を受けた人の数は総計 670 万に達した。<br />
� 第 2 次エネルギー基金<br />
第 2 次エネルギー基金では、農村部や都市周辺部に住むACP諸国の貧困層の持続可能かつ<br />
近代的なエネルギー・サービスへのアクセスを改善するため、ガバナンスに関係するプロジェクト<br />
や活動への協調融資を行う。また、同基金では、再生可能エネルギーやエネルギー効率関連の<br />
プロジェクトを優先し、気候変動対策に寄与する。第 2 次エネルギー基金は第 10 次EDF(2009~<br />
2013 年)の枠内で拠出され、予算総額は 2 億ユーロ。<br />
※優先課題:<br />
・貧困層への利益供与を主眼としたエネルギー・サービスへのアクセス<br />
・再生可能エネルギー、エネルギー効率、地元の資源活用<br />
・基本的なサービスを超えたエネルギーの生産的使用<br />
・援助対象国の計画枠組みとの整合性<br />
・永続性のあるエネルギー政策、戦略の奨励<br />
・民間部門の参加への障害除去<br />
第 2 次エネルギー基金では、民間企業、特に中小企業の参加を奨励する。中でも地元の中小<br />
企業や地方自治体などの参加が優先される。プロジェクトの実施に当たり、援助対象国の『オー<br />
ナーシップ』を確保するためにも地元の企業や公的機関とのパートナーシップは必須となる。この<br />
ためEUの申請者には、地元の企業や公的機関とのパートナーシップの形成が要求される。<br />
22 http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/practical_guide/documents/2008new_prag_final_en.p<br />
df<br />
212
※提案募集<br />
第 2 次エネルギー基金では、提案募集を 2 回に分けて実施する。1 億ユーロ分の 1 回目の提案<br />
募集は、2009 年 11 月に開始された。2010 年 1 月末までに簡略なコンセプト・ノートを提出、評価<br />
委員会がその評価を行う。コンセプト・ノートに基づき選択されたプロジェクトに関しては、詳細な<br />
提案の提出が求められる。最終的な選考結果の発表は、2010 年 10 月に行われる予定。<br />
提案の募集は次の 2 分野で行われる。<br />
・農村部や都市周辺部に住む貧困層のための近代的かつ安価で持続可能なエネルギー・サー<br />
ビスに関するプロジェクト:再生可能ネルギー、エネルギー効率、地元での解決策が重視され<br />
る。<br />
・地域レベル、国レベル、地方自治体レベルでのガバナンスやエネルギーの一般的枠組みの<br />
改善を目指す活動。特に再生可能エネルギーの利用促進やエネルギー効率のための活<br />
動。<br />
出所:Europeaid<br />
図表 40 協調融資の最低額、最高額<br />
第 2 次エネルギー基金では、提案募集以外にも次の 2 つの手法が導入された。<br />
・欧州の資金提供者や開発金融機関が参加する中規模のプロジェクトのためのプーリング・メ<br />
カニズム<br />
・EUエネルギー・イニシアティブの対話・パートナーシップ基金(EUEI-PDF) 23<br />
ウ..ACP-EU水基金(ACP-EU Water Facility)<br />
EUは 2004 年、EU水イニシアティブ(EUWI) 24 を補完する形で、第9次EDFを財源とする総予<br />
算 5 億ユーロ(2004 年:2 億 5,000 万ユーロ、2005 年:2 億 5,000 万ユーロ)の第 1 次水基金をス<br />
タートさせた。<br />
23 http://www.euei-pdf.org/africa-eu-energy-partnership.html<br />
24 http://www.euwi.net/<br />
213
EUWIは、ミレニアム開発目標達成のための努力の一環として、2002 年の持続可能な開発に<br />
関する世界首脳会議(WSSD、ヨハネスブルク・サミット)の際にEUが開始したイニシアティブで、<br />
EUWI自体は、水問題を解決するために新たな資金を供与することはない。関係者の対話を通じ、<br />
既存の人材、資金の利用方法を調整し、効率的に活用するための枠組みとパートナーシップを構<br />
築することがEUWIの役割となる。<br />
ACP諸国における貧困の削減、ミレニアム開発目標の達成が水基金の主要な目的で、給水や<br />
浄水のためのインフラ設置、ACP諸国における水関連のガバナンス、水資源の統合管理の改善<br />
を目指す。<br />
※水基金の主要な原則<br />
図表 41 ACP-EU水基金 (ACP-EU Water Facility)<br />
出所:Europeaid<br />
・オーナーシップ:水基金は需要をベースとするもので、水関連の政策の策定、実施へのACP<br />
諸国の関係者の関与を強化する手段となる。<br />
・イノベーション、フレキシビリティ:基礎的なインフラ工事のため、補助金と他の資金(ソフト・ロ<br />
ーン、融資保証、マイクロファイナンスの利用等)を融合させることで最大限の効果が期待で<br />
きる。補助金はプロジェクトを始動させるための資金を提供する。<br />
・統合的アプローチ:水基金の重要な原則。当事者の参加する水資源の統合管理(IWRM)、<br />
最貧困層の重視、ジェンダー問題への配慮は、資源の総合管理という文脈における水関連<br />
のサービスの統合を保証するのに不可欠のアプローチとなる。<br />
・ガバナンス:水基金は、水資源の効率的かつ近代的な管理に向けた真の国内政策の策定を<br />
行おうとするACP諸国を支援する。制度の強化や規制枠組みの策定に向けた活動に対し援<br />
助する。制度や規制枠組みは、新たな投資を呼び込むための前提条件となる。<br />
・オープン・アプローチ:提案募集により、オープンで透明なアプローチが保証される。<br />
提案募集は、ア.水の管理、ガバナンスの改善、イ.水供給インフラ、衛生インフラ、ウ.市民社<br />
214
会のイニシアティブ、の 3 分野で行われた。<br />
※1回目の提案募集<br />
2004 年 11 月に提案募集が開始され、2005 年 1 月に締め切られた。最終的に 796 件の提案が<br />
提出された。このうち非国家主体が申請者である提案は 500 件に達した。プロジェクトの総額は約<br />
50 億 1,200 万ユーロで、要請された補助金の総額は約 27 億 6,300 万ユーロだった。分野別では、<br />
「水の管理、ガバナンスの改善」に関する提案が 204 件(全体の 25%)、「水供給インフラ、衛生イ<br />
ンフラ」に関するものが 276 件(同 35%)、「市民社会のイニシアティブ」が 300 件(同 38%)だった。<br />
最終的に選択された提案は 97 件 25 ・ 26 だった。<br />
※2 回目の提案募集<br />
2006 年 3 月に 2 回目の提案募集が開始され、6 月に締め切られた。550 件の提案のうち、78<br />
件が選択された 27 。<br />
参考 5 エネルギー基金、水基金の中間評価<br />
Gruppo Soges S.p.A の実施した「エネルギー基金、水基金の中間評価」によると、水基金に関し<br />
ては、2 回目の提案募集の際にACPの民間企業が 1 社だけ提案を提出した。また、3 社がパート<br />
ナーとして参加した。EU側では、3社が共同ドナーとして、5社がパートナーとして参加した。「中間<br />
評価」 28 は、企業はより商業的なエネルギー基金の方に興味を示しており、水分野への民間企業<br />
の参加が尐ないのは、運営上の問題や構造的な問題に起因するとしている。また、民間企業の<br />
定義を変え、民間投資家としての共同体の参加を容易にすることも選択肢の 1 つであると提案し<br />
ている。<br />
民間企業の参加に関して、「中間評価」は次のような勧告を行っている。<br />
・水、衛生インフラ部門における革新的な金融を強化するためには、水基金への民間企業の参<br />
加を強化する必要がある。<br />
・民間企業がエネルギー部門に興味を惹かれるのは、様々なタイプのマネージメントが可能で<br />
あることや、エネルギーが公益に係るものであるにもかかわらず、多くの国でありふれた『商品』と<br />
みなされていることに起因している。こうしたことから水とエネルギーのマネージメントを統合してし<br />
まうことを革新的アプローチの 1 つとして提案できる。欧州では、水とエネルギーのマネージメント<br />
が統合されているケースが多い。<br />
・民間投資家に直接援助を行わず、現地の金融仲介機関を動員することも選択肢の 1 つとして<br />
25 http://ec.europa.eu/europeaid/where/acp/regional-cooperation/water/documents/cfp1-approved-list_en.pdf<br />
26 http://ec.europa.eu/europeaid/where/acp/regional-cooperation/water/documents/cfp1-statistics_en.pdf<br />
27 http://ec.europa.eu/europeaid/where/acp/regional-cooperation/water/documents/cfp2-approved-list_en.pdf<br />
28 http://ec.europa.eu/europeaid/where/acp/regional-cooperation/water/documents/mtr_exec_en.pdf<br />
215
挙げられる。これは、特別な投資基金の形で実施される。『民間の当事者(private actors)』の定<br />
義 を 、 地 元 の マ イ ク ロ フ ァ イ ナ ン ス ・ メ カ ニ ズ ム に よ り 資 金 提 供 を 受 け る 消 費 者 団 体<br />
(consumer-based institutions)に拡大する必要がある。消費者団体は、尐なくとも一部の国で、非<br />
常に良い資金運営能力を示しており、リスク評価する能力を備えている。エネルギー基金や水基<br />
金は、金融機関が小規模のプロジェクトへの融資を受入れるのに必要な資金を提供する。<br />
・地元のコミュニティー自身あるいはマイクロファイナンス機関を源泉とする民間融資を一定の<br />
割合含むプロジェクトを優遇することも選択肢の 1 つとして挙げられる。<br />
・民間部門の参加を促すには、協調融資や地元の金融機関の参加といった革新的な提案の褒<br />
賞を考慮することも重要である。<br />
・エネルギー基金、水基金を欧州投資銀行のACP投資基金と結びつけるというオプションも検<br />
討する必要がある。<br />
b.開発協力手段(DCI)<br />
2007 年 1 月から使用されている手段で、『ラテンアメリカ、アジアの開発途上国への財政的、技<br />
術的援助、当該諸国との経済協力に関する理事会規則(EEC)no.443/92』という過去に使用さ<br />
れてきた様々なテーマ別、地域別の援助手段に取って代わった。DCIでは、貧困撲滅への協力や<br />
ミレニアム開発目標の達成が主要な目標となる。<br />
DCIは次の 3 種類に分類される。<br />
ア.地域別プログラム<br />
ラテンアメリカ諸国、アジア並びに中央アジア諸国、湾岸地域(イラン、イラク、イエメン)、南アフ<br />
リカ共和国の 47 の開発途上国向け開発協力を支援する。<br />
次の分野における行動を支援する。<br />
� 貧困撲滅、並びにミレニアム開発目標の達成<br />
� 住民の基本的なニーズ、特に教育と健康<br />
� 社会的結束、雇用<br />
� ガバナンス、民主主義、人権、制度改革支援<br />
� 貿易、地域統合<br />
� 環境保護や天然資源の持続可能な管理を通じた持続可能な開発<br />
� 水資源の持続可能かつ統合された管理、エネルギー分野での持続可能な技術のさらなる<br />
使用の奨励<br />
216
� インフラ開発、情報通信技術の使用の強化<br />
� 危機後の状況への支援、政情不安な国々への支援<br />
イ.テーマ別プログラム<br />
出所:Europeaid<br />
図表 42 地域別プログラム(DCI)<br />
全ての開発途上国(DCIだけでなくEDF、ENPIの対象となる国々も含む)を支援する。<br />
次の分野での行動を支援する。<br />
� 人的資源への投資<br />
� 環境、エネルギーを含む天然資源の持続可能な管理<br />
� 開発における非国家主体並びに地方自治体<br />
� 食糧安全保障<br />
� 移民、亡命<br />
ウ.砂糖議定書に署名したACP18 ヵ国のための付随措置プログラム<br />
EUにおける砂糖部門の制度改革に対応しなくてはならない国々への支援措置。<br />
図表 43 テーマ別プログラム、砂糖議定書付随措置プログラム(DCI)<br />
出所:Europeaid<br />
2007~2013 年度(暦年)のDCI予算は 169 億ユーロで、次のように分配される。<br />
・地域別プログラムに約 100 億 6,000 万ユーロ(全体の 60%)<br />
217
・テーマ別プログラムに 56 億ユーロ(同 33%)<br />
・砂糖議定書に署名したACP18 ヵ国のための付随措置プログラムに 12 億 4,000 万ユーロ(同<br />
7%)<br />
2007~2013 年度のアジアへの総援助額は 51 億 8,700 万ユーロで、アジア 19 ヵ国の各国の開<br />
発援助にその 81%が充当される。地域援助には 16%が充当され、地域統合を支援する。<br />
中央アジアへの援助額は 7 億 1,900 万ユーロで、その 30~35%は地域協力に関連する活動に<br />
充当される。「人権、法治国家、グッドガバナンス、民主主義」、「未来への投資:青年、教育」、「経<br />
済、貿易、投資の発展促進」、「エネルギー、運輸に関する関係強化」、「持続可能な環境、水」、<br />
「共通の脅威、挑戦への対処」、「文化間の対話」の 7 つが主要なテーマとなる。<br />
ラテンアメリカ諸国への援助額は約 30 億ユーロで、「貧困や社会的不平等との戦い」、「グッド<br />
ガバナンスの強化、和平の促進」、「経済協力、貿易の発展、地域統合への援助」が優先課題とな<br />
る。<br />
DCIの恩恵を受けることができるのは、<br />
� 記述した国々や地域、その機関<br />
� 記述した国々の地方自治体<br />
� EUと援助対象国が設立した共同機関<br />
� 非国家主体<br />
� 国際機関<br />
� EUの機関<br />
③ 企業の社会的責任(CSR)とBOPビジネス<br />
1)欧州委員会の担当部局<br />
欧州委員会では、CSRに関しては企業・産業総局 29 ・ 30 と雇用・社会問題・機会均等総局 31 が共<br />
同責任を負い、両総局に人員が配置されている。欧州委員会は、CSRを「企業が、社会問題や環<br />
境問題に対する配慮を企業活動や利害関係者との関係に自主的に統合すること」と定義し、企業<br />
の「自主性」を強調しているが、CSRの社会的側面よりビジネス的側面が重視される傾向が顕著<br />
29 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/index_en.htm<br />
30 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/corporate-social-responsibility/index_en.htm<br />
31 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=331&langld=en<br />
218
になりつつあり、CSRに関しては、雇用・社会問題・機会均等総局よりも企業・産業総局の比重が<br />
増しているといわれる。<br />
『持続可能な開発』は、EUの追求する目標の 1 つであり、経済、環境、社会という 3 つの側面を<br />
持つ。「競争力と持続可能性は相反するものではなく、相互に強化されるコンセプトだ」とする企<br />
業・産業総局は、企業の持続可能な開発への寄与の最大化を図ることを支援するため、欧州企<br />
業の繁栄を可能にする条件作りに取り組んでいる。<br />
欧州委員会は、「CSRは、EUの競争力向上に向けて前進するために必要かつ自然な要素」で<br />
あり、「企業の責任ある態度は、市場経済や貿易の自由化、グローバリゼーションへの信頼を築く<br />
のに不可欠である」と認識している。<br />
CSRの主役はあくまで企業であり、CSRにおけるEUの主要な役割は、「CSRに関する理解を<br />
向上させる」、「EUレベルでのグッドプラクティスに関する情報交換を容易にする」、「CSRに関す<br />
る議論や行動を深める問題についての討議の場を組織する」といった調整役的ものとなってい<br />
る。<br />
このため欧州委員会は、CSR Europe のような機関や「CSRに関するマルチステークホルダー・<br />
フォーラム」、「CSRのための欧州同盟(European Alliance for CSR)」などを活用する。<br />
2)CSR Europe のCSRラボラトリー<br />
「CSRのための欧州同盟(European Alliance for CSR)」の枠内で実施される企業を中心とした<br />
プロジェクトで、企業やその利害関係者、EUの代表などを結集して社会的・経済的挑戦に取り組<br />
む。2007 年初頭以来、20 のラボラトリーが設置された。<br />
イノベーション分野のラボラトリーの 1 つに「Base of the Pyramid(BOP)における持続可能なビ<br />
ジネス」に関するラボラトリーがある。ダノンを企業リーダーとするプロジェクトで、CSR Europe がま<br />
とめ役(facilitator)となった。<br />
※「Base of the Pyramid(BOP)における持続可能なビジネス」<br />
国連のミレニアム開発目標達成のため、企業が如何にして貧困対策に寄与できるかを探る多く<br />
の国際的なイニシアティブがとられている。このイニシアティブは、ピラミッドの底辺に経済活動を<br />
生み出すための新たなビジネスモデルを開発し、低所得層に衛生、栄養、教育、通信といった人<br />
間の基本的なニーズを満たす製品やサービスへのアクセスを提供することを目標としている。<br />
219
このラボラトリーでは、BOPアプローチを「既存のビジネスモデルの再設計により、新興市場に<br />
社会的な成果を生み出す企業活動」と定義、特に官民パートナーシップを加速するため、公的部<br />
門と民間部門間の協力強化の道を探る。<br />
このプロジェクトではまず、現状の分析を行い、民間部門の視点からBOPイニシアティブの誕<br />
生の背景を探り、さらには誕生を妨げるあるいはスローダウンさせる障害の評価を行う。現在のE<br />
Uの開発援助政策や財政メカニズムへの理解を深めることを通じ、企業や利害関係者、欧州委員<br />
会、その他の機関が共同で如何にしてBOPイニシアティブを促進し、加速させることができるかを<br />
探る。<br />
る。<br />
このプロジェクトの成果としては、BOPに関する政策提言とプロジェクトの提案が予定されてい<br />
� 政策提言<br />
� 開発作業(developmental work)における官民協力の様々な側面に焦点を当てるワーキン<br />
グペーパーの形で政策提言を行う。<br />
BOPラボラトリーの提出した報告書を踏まえ、欧州委員会も開発援助の効率改善という観点か<br />
らBOPのような新しいビジネスモデルにようやく関心を持ち始め、2009 年 11 月にはBOPを含む<br />
革新的フラッグシップ・プロジェクトに関するフィージビリティ調査を開始した。<br />
※GAINの「ビジネス・アライアンス」<br />
GAIN(Global Alliance for Improved Nutrition)は主としてビルゲイツファンドなど出資した基金に<br />
より運営されており、知識の普及を通じて貧困層への適切な栄養供給を図ることをミッションに掲<br />
げ、10 億人の栄養供給への貢献達成を目標にしている。そのほか、USAIDやカナダ国際開発庁、<br />
オランダ外務省、TCI(The Children’s Investment Fund)などが資金提供している。GAINは基本<br />
的にはNGOであるが、国際機関、特に、WHOとの恒常的なコンタクト関係は欠かせない。歴史<br />
的にはかつて米国にあったが、現在はジュネーブにベースを置く理由はそこにある。UNICEFの<br />
ほか、世界各国の援助組織ともパートナーシップを持っており、GAINのボードメンバーにもNGO<br />
も含め多く参加している。<br />
BOPに関しては 2005 年に、ビジネス・アライアンスを立ち上げ(同年にドバイでグローバル・フ<br />
ォーラムというメンバー以外の国際機関、NGOなども交えた、知識や経験の交換を行うフォーラ<br />
ムを開催)、13 企業が参加し、良い栄養摂取を低価格で提供するBOPのための知識や経験を交<br />
換している。メンバー13 企業とは、日本企業の味の素のほか、アクゾノベル、ブリタニア、カーギル、<br />
ダノン、DSM、フィルメニッヒ、フォルティテック、マース、ペプシコ、テトラ・パック、ユニリーバ、コカ<br />
コーラ。<br />
220
2007 年にグローバル・フォーラムをブリュッセルで開催したことがきっかけで、CSR Europe が調<br />
整役(ファシリテーター)であるEUレベルでのBOPラボラトリーに参加することになった。フランス<br />
のCSRに特化した企業連盟であるIMSと同様に調整役を担った。このBOPラボラトリーは 16ヵ月<br />
かけて計 4 回の会合を経て、成果を報告書にとりまとめ、欧州委員会に提出した。これが、欧州委<br />
員会が 09 年 11 月に着手したBOPに関する調査に繋がった。これにより、GAINも欧州委員会や<br />
CSR Europe のBOPラボラトリー参加メンバーとの恒常的なコンタクトができるようになった。欧州<br />
委員会の EuropeAid の Jan Ten Blomendal 課長はBOPの中心的な人物。<br />
GAINにとって、上述の CSR Europe のBOPラボの役割は、貧困層への栄養補給の観点からの<br />
媒介役。欧州委員会は、BOPについてやっと勉強を開始したところであり、BOPラボの活動を通<br />
じて政策当局にもBOPコンセプトを広げる狙いであった。<br />
(2)支援スキーム活用事例<br />
① マイクロファイナンスに関するACP-EUフレームワーク・プログラムの事例<br />
カメルーンでのマイクロファイナンスに特化した金融機関<br />
(グリーンフィールド型マイクロファナンス機関)の設立<br />
「マイクロファイナンスに関するACP-EUフレームワーク・プログラム」の枠内で選択されたマイ<br />
クロファイナンス機関の強化に資する 11 のプロジェクトの 1 つ。<br />
・EUが提供した補助金:89 万 132 ユーロ<br />
・実施パートナー:Horus Develeopment Finance(フランス、金融)<br />
221
図表 44 ケーススタディ:Horus Developement Finance のケース<br />
出所:Advans グループ、Horus Development<br />
極小企業、中小企業は、開発途上国の経済発展の主要な源泉とみなされている。開発途上国<br />
の企業の約 95%は従業員 50 人以下の企業で、こうした企業は主に国内の労働者を雇用する。こ<br />
のため、失業者が多く、貧困層が大半を占める国々において、こうした企業は収入源として大きな<br />
役割を果たしている。しかし、極小企業や中小企業は、好条件で質の高い金融サービスにアクセ<br />
スすることが難しい。<br />
Horus Develeopment Finance とそのパートナーである Horus Systemes d’Information は、カメ<br />
ルーンにグリーンフィールド型マイクロファイナンス機関『Advans Cameroun』を設立、2007 年 5 月<br />
に開業した。Horus は、『Advans Cameroun』の開業、運営に必要な融資商品や貯蓄商品の開発、<br />
監査メカニズムの設置、適切な経営情報システムの設置といったテクニカルアシスタンスにEUの<br />
補助金を充当した。<br />
『Advans Cameroun』はまず、普通の銀行から融資を受けられない極小企業や中小企業への融<br />
資活動に専念、3 年間で尐なくとも 5,600 の顧客を獲得することを目標にスタートした。カメルーン<br />
政府からの開業許可がなかなか下りなかったことから、開業が 4 ヵ月遅れたが、この点を考慮に<br />
入れても顧客数は当初の予想を下回るペースで推移した。<br />
・2007 年 12 月 31 日の時点で、預金者数は 300、融資を受けた顧客は 443 を数えた。<br />
・2008 年 3 月 31 日の時点で、預金者数は 432、融資を受けた顧客は 521 を数えた。<br />
・2008 年 9 月 30 日の時点で、預金者数は 836、融資を受けた顧客は 1,500 を超えた。<br />
222
「マイクロファイナンスに関するACP-EUフレームワーク・プログラム」の契約には、成果指向が<br />
重要な要素として盛り込まれており、実施パートナーが立案し、定めた活動のパフォーマンス目標<br />
に応じ、3~5 の基本指標が選択され、目標達成のための最低限のパフォーマンスが規定される。<br />
最低限のパフォーマンスは、パフォーマンス目標よりも低く設定されるが、最低限のパフォーマン<br />
スが満たされなければ、同プログラムの枠内での補助金は打ち切られる。パフォーマンス目標の<br />
達成状況は四半期毎に検証される。<br />
1)Horus Develeopment Finance(Horus) 32<br />
Horus は、コンサルタントや監査、投資といった活動を行うマイクロファイナンスのスペシャリスト<br />
で、同部門の能力強化に貢献している。同社は 2005 年 8 月、欧州投資銀行(EIB)、ドイツ復興金<br />
融公庫(KfW)、フランス開発庁(AFD)、オランダ開発金融会社(FMO)、国際金融公社(IFC)な<br />
どの協力を得て Advans SA(旧 La Fayette Investissement) 33 を設立した。Horus は、アフリカのみ<br />
ならず欧州、アジアでも多くのマイクロファイナンス機関を支援しており、これまでの活動の質の高<br />
さから Advans プロジェクトにEIBやKfWなどの支援を得られた。<br />
2)Advans Cameroun 34<br />
図表 45 Advans SA の資本構成<br />
出所:Advans グループ<br />
Advans Cameroun は 2006 年 8 月に設立され、カメルーンの財務省の許可を得て 2007 年 5 月<br />
にドゥアラで開業した。2008 年 4 月には、ヤウンデに支店を開設。Advans Cameroun は、2012 年<br />
までに新たに 10 支店の開設を予定している。<br />
カメルーンの人口は 1,820 万人で、国内総生産は 140 億ドル、経済成長率は安定しており、他<br />
のサハラ以南のアフリカ諸国に比べダイナミックな経済を持つ。カメルーンには、地域のハブ港で<br />
32 http://www.horus-df.com/<br />
33 http://www.advansgroup.com/<br />
34 http://www.advansgroup.com/index.php?id=32<br />
223
あるドゥアラ港があり、石油資源もあるうえ、農業にも潜在力がある。しかし、都市部には失業者<br />
が多く、失業率は 18%に達している。住民の 40%は貧困層。<br />
カメルーンでは、中小企業が 450 万人(都市部では 140 万人)を雇用、経済面で重要な役割を<br />
果たしている。こうした企業は、雇用や収入の源泉であるだけでなく、日常的な製品やサービスの<br />
主要な提供者となっている。重要な役割を演じてはいるものの、中小企業の金融サービスへのア<br />
クセスは限られている。金融機関から融資を受けられた家庭は、カメルーンの家庭全体の 1%と<br />
言われている。<br />
民間企業への銀行融資は、国内総生産の 9.7%に留まっており、サハラ以南のアフリカ諸国の<br />
平均(15%)を下回っている。また、1 万 5,000 ユーロ以下の融資はほとんど存在せず、極小企業<br />
や中小企業は銀行融資から閉め出されたような状況にあった。<br />
カメルーンには、公式には 500 のマイクロファイナンス機関があると言われる。しかし、マイクロ<br />
ファイナンス部門は人口の 3.5%しかカバーしていないうえ、貯蓄業務や送金業務に活動が集中し<br />
ており、融資活動は非常に尐ない。<br />
Advans Cameroun の主要な株主は Advans SA(57.5%)、フランスのソシエテジェネラルの系列<br />
会社SGBC(カメルーン・ソシエテジェネラル・バンク、20%)、IFC(国際金融公庫、19%)。<br />
② ACP-EUエネルギー基金の事例<br />
図表 46 Advans Cameroun(2009 年 9 月末現在の状況)<br />
出所:Advans グループ<br />
マダガスカルの SAVA 地方(26 の村と 2 つの町)での電化プロジェクト<br />
第 1 次エネルギー基金の提案募集の枠内で選択されたプロジェクト<br />
・EUの提供した補助金:600 万ユーロ<br />
・EUの補助金の申請者:フランス電力公社(EDF)<br />
224
図表 47 ケーススタディ:フランス電力公社のケース<br />
出所:EDF<br />
エネルギー基金は、ACP諸国の農村部や都市周辺部での持続可能かつ安価なエネルギー・<br />
サービスへのアクセス改善プロジェクトを支援するための協調融資(co-finance)の手段で、採択<br />
されたプロジェクトの 91%(小規模のイニシアティブも含む)は、「農村部、都市周辺部でのエネル<br />
ギー・サービスへのアクセス改善」を目的とするプロジェクトだった。<br />
こうしたプロジェクトでは利益を挙げることは容易ではなく、エネルギー部門では多額の投資が<br />
必要となることから補助金なしでは実施が難しい。このため、エネルギー基金からの補助金と他<br />
のドナーからの補助金、欧州投資銀行やその他の金融機関からの融資、民間資本のブレンドを<br />
可能にする「プーリング・メカニズム」を利用して資金を捻出したりする。<br />
なお、エネルギー基金の補助金に適用される規則によると、プロジェクト実施期間中に補助金<br />
が利益を生み出すことがあってはならない。<br />
1)フランス電力公社(EDF)の申請したプロジェクト<br />
このプロジェクトは、Sava 地方の町 Andapa と Sambava の間に点在する 26 の村(1 万 6,000 世<br />
帯、総計 8 万人の住民)や中小企業(手工業)、市場、学校、診療所などの電化プロジェクト。同時<br />
に Andapa と Sambava の電化も進める。<br />
マダガスカルでは、住民の 95%が電力にアクセスできない。電力にアクセスできる 5%の住民<br />
は、化石燃料から生産される電力の供給を受けている。また、貧困層の 83%は、電力へのアクセ<br />
ス率が 2%に満たない農村部で生活している。<br />
225
2007 年 12 月 11 日にマダガスカルの財務・予算省で契約への調印が行われた。プロジェクトの<br />
実施期間は 60 ヵ月で、総コストは 2,340 万ユーロ。このうち 600 万ユーロをEUが、ACP-EUエネ<br />
ルギー基金の枠内で補助金として拠出する。このほか参加企業が 600 万ユーロを出資、ドイツ復<br />
興金融公庫(KfW)やフランス開発庁(AFD)などの金融機関が 1000 万ユーロ融資する。<br />
a. 目的<br />
・貧困対策<br />
出所:EDF<br />
図表 48 プロジェクトのコスト<br />
・最良の価格で恒常的にエネルギーを供給することで、地元での収入を得られる活動(商業活<br />
動)の活性化を促す<br />
・温暖化ガスの排出削減<br />
b. 事業の概要<br />
フランス電力公社(EDF)は、マダガスカル電力公社(EDM)と提携し、Lokoho 川に6MW の水<br />
力発電所を建設、送電、配電網を整備する。先進国からはEDF以外に、ドイツの電力会社RWE、<br />
カナダの Hydro Quebec や、ドイツのGTZ社(持続可能な開発のための国際協力企業)などがパ<br />
ートナーとして参加する。<br />
EDF、RDE、Hydro Quebec は、水力発電所の建設、Andapa と Sambava 間の送電網や農村部<br />
への配電網の敷設を支援する。また、3 社はプロジェクトの運営を行うほか、配電会社の設立を助<br />
け、電力供給の恒久性を保証する。さらには、地元で設立される電力生産会社、農村部電化会社<br />
の株主となる。プロジェクトの持続可能性が保証された時点で、3 社は地元の企業に経営を委ね<br />
る。<br />
建設される水力発電所は、生産した電力を地元で創設される農村部電化会社と Andapa や<br />
Sambava に配電を行っている国営電力会社(JIRAMA)に売る。JIRAMAは、現在のコストの高<br />
226
い火力発電により生産される電力よりも安い電力を購入できるほか、配電網を整備でき、新しい<br />
個人や企業の顧客にアクセスできるようになる。<br />
このプロジェクトでは、制度的枠組みの最適化が重要な要素となるが、マダガスカルの農村部<br />
電化促進庁(ADER)や電力規制事務局(ORE)がその任に当たり、ドイツのGTZ社が制度的枠<br />
組みの効率改善などを支援する。<br />
2)フランス電力公社(EDF)の取組 35<br />
フランス電力公社(EDF)は、フランス政府との公共サービスに関する契約に、電気代の支払い<br />
が困難な国内の貧困層への電力供給を保証することを明記している。また、EDFグループ企業<br />
間の企業の社会的責任(CSR)に関する協定にも同様の趣旨が盛り込まれており、貧困層の電<br />
力へのアクセスを手助けしている。<br />
EDFグループは、こうした行動を開発途上国にも拡大しており、「エネルギー、サービスへのア<br />
クセス(Access)」のようなプログラムを策定し開発途上国の電化を促進したり、「国境なき電気技<br />
師(ESF)」のようなNGOを支援したりしている。<br />
a. EDFのCSRの変遷<br />
・1994~2000 年:質の高い公共サービスを提供するという精神に基づく、「援助協力」、「連帯」<br />
のための人道援助という性格が強かった。<br />
・2000~2005 年:農村部電力サービス会社(Rural Electricity Services Company:RESCO)とい<br />
う新しいビジネスモデルの開発:農村部の電化を、適切な技術を利用すれば利益を挙げられる可<br />
能性のある経済活動とみなす。<br />
2005 年以降:EDFの新しいCSR政策の枠組みにおける Access プログラムへの取組の拡大を<br />
目指す。CSRの枠内にはあるものの、先進国の企業と開発途上国の政府との官民パートナーシ<br />
ップ(PPP)という形態で、途上国の農村部において様々な技術(ディーゼル、水力、太陽光等々)<br />
を用いて電力を販売する。<br />
b. RESCOモデル<br />
・官民パートナーシップと補助金、報酬を組み合わせる。<br />
EDFやそのパートナーとなる企業の資本+世界銀行、EUなどからの補助金+顧客からの<br />
35 http://developpement-durable.edf.com/accueil-com-fr/edf-developpement-durable-150001.html<br />
227
収入<br />
・地元の法律の枠内で、地元の労働力を利用して活動する。<br />
・EDFやそのパートナーとなる企業は出資者で、15~20 年という長期的な展望で事業を行う。<br />
・限定されたゾーンで、農村部の尐なくとも 1 万 5,000 家庭にサービスを提供する。<br />
c. 課題<br />
・農村部の電化事業も原油価格の高騰など外的要因の影響を受ける。補助金の見直しがなけ<br />
れば、こうした外的要因を価格に転嫁せざるを得なくなり、貧困層には手が届かなくなる。こう<br />
した制約に対処するため、事業モデルをどのように変えていくべきか。<br />
・開発途上国での官民パートナーシップ(PPP)は、「官」が決定を下すのに必要な権限を常に<br />
持たない、「民」の自主性が保証されていない、官民の関係に柔軟性がないことなどから真<br />
のPPPとは言えない。<br />
・収支均衡の調整やサービス多様化の機会を持つことなしに、利益を挙げることと、貧困層の<br />
みを対象とした質の高い公共サービスの提供を保証することの矛盾が存在する。如何なる<br />
形態の企業が最適と言えるか。<br />
・EDFやそのパートナー企業だけでなく全てのパートナーが長期的な責任を負うべきで、地元<br />
の政府は、地元の投資家が参加できるように環境を整備すべき。<br />
d. 「エネルギー、サービスへのアクセス(Access)」プログラム 36<br />
Access プログラムを通じEDFは、開発途上国において、配電網から遠く離れた農村部への電<br />
力供給を可能にするため、地元での発電所の建設、農村部の電化会社の設立を支援している。<br />
また、開発途上国の都市周辺部では、安価なエネルギー・ソリューションの提供を行っている。<br />
EDFは 2006 年末、同プログラムの枠内でマリ、モロッコ、南アフリカ共和国での4つの農村部電<br />
化プログラムに参加した 37 。総計 26 万人あまりがこのプログラムの恩恵を受け、電力へのアクセス<br />
が可能になった。このほかガラパゴス諸島での風力-ディーゼル・ハイブリッド発電、ケニアでの農<br />
村部の電化、チュニジアでの海水の淡水化、風力発電、ニカラグアやマダガスカルでの小型水力<br />
発電などの事業を行っている。<br />
EDFはまた、フランスの環境エネルギー管理庁(ADEME)と協力し、アフリカのフランス語圏と<br />
36 /http://developpement-durable.edf.com/accueil-com-fr/edf-developpement-durable/nos-defis/favoriser-l-acces-a<br />
-l-energie/acces-a-l-energie-dans-les-pays-en-developpement-150170.html<br />
37 /http://developpement-durable.edf.com/accueil-com-fr/edf-developpement-durable/base-documentaire/telecharg<br />
ements/garantir-l-acces-a-l-energie/garantir-l-acces-a-l-energie-150134.html<br />
228
の南北間での新たな形態の技術移転を試みている。さらには、世界エネルギー基金(Fondem)<br />
との協力で、ラオスやブルキナファソ、セネガル、マダガスカルでの電化促進プロジェクトに取り組<br />
んでいる。<br />
国境なき電気技師(ESF)は、電気技師の無料奉仕活動により、アフリカ西部、マダガスカル、<br />
あるいはアジアなど 40 ヵ国あまりで、開発途上国での農村部におけるエネルギーへのアクセスを<br />
改善している。EDFは、現役あるいは退職した電気技師 800 人あまりを年間約 4000 日、こうした<br />
無料奉仕に派遣している。<br />
③ CSRラボラトリー(CSR Laboratories)の事例<br />
「Base of the Pyramid(BOP)における持続可能なビジネス」<br />
� 企業リーダー:ダノン・グループ<br />
� 調整役(facilitators):CSR Europe、IMS-Entreprendre pour la Cite<br />
� 参加ステークホルダー:ACP Business Climate Facility(BIZ CLIM)、Global Alliance for<br />
Improved Nutrition(GAIN)、Solidar、Gesellschaft fur Technische Zusammennarbeit(GTZ)<br />
� 参加企業:Unilever、Vodafone、British Telecom、France Telecom、GDF Suez、Microsoft、<br />
Nestle、Novartis、Procter& Gamble<br />
図表 49 ケーススタディ:CSRラボラトリーのケース<br />
出所:CSR Europe<br />
229
このラボラトリーでは、BOPアプローチを「既存のビジネスモデルの再設計により、新興市場に<br />
社会的な成果を生み出す企業活動」と定義、特に官民パートナーシップを加速するため、公的部<br />
門と民間部門間の協力強化の道を探る。<br />
このプロジェクトではまず、現状の分析を行い、民間部門の視点からBOPイニシアティブの誕<br />
生の背景を探り、さらには誕生を妨げるあるいはスローダウンさせる障害の評価を行う。現在のE<br />
Uの開発援助政策や財政メカニズムへの理解を深めることを通じ、企業や利害関係者、欧州委員<br />
会、その他の機関が共同で如何にしてBOPイニシアティブを促進し、加速させることができるかを<br />
探る。<br />
1)目標<br />
・新興経済国における社会、経済発展に果たす官民の革新的役割について、公共部門と民間<br />
部門間の相互理解を深める。<br />
・社会的かつ持続可能なビジネスの創設を容易にすることを目的とするプロジェクト向けの財源<br />
を結集するため、公的部門、民間部門、その他の利害関係者が共に利益を得、相互に支援<br />
し合える分野を探る。<br />
・実用的な経験を分かち合い、行動するための具体的な分野を特定する。<br />
このプロジェクトの成果としては、BOPに関する政策提言とプロジェクトの提案が予定されてい<br />
る。<br />
・政策提言<br />
・開発作業(developmental work)における官民協力の様々な側面に焦点を当てるワーキングペ<br />
ーパーの形で政策提言を行う。<br />
開発作業には、以下のようなものが含まれる。<br />
・ピラミッドの底辺(BOP)における持続可能な企業イニシアティブの定義<br />
・BOP並びに官民の開発イニシアティブの全体像の提示<br />
・BOPイニシアティブの障壁、欠陥の分析<br />
・現在のベスト・プラクティス並びに使用可能な公的援助に焦点を当て、ソリューションのための<br />
ガイドを提示<br />
230
2)ワーキングペーパーの要旨 38<br />
BOPプログラムは、開発途上国や新興経済国の、コミュニティーに直接利益をもたらす持続可<br />
能なビジネスを創出しようとする試みで、win-win-win 戦略となる潜在力を秘めている(住民やコミ<br />
ュニティーの win、企業の win、開発パートナー、政府パートナーの win)。<br />
経済界には今日、世界の貧困層問題への取組は、長期的なビジネスの成功につながるとの認<br />
識が深まりつつある。しかし、これまでのビジネスモデルを貧困層とのビジネスに当てはめるだけ<br />
ではビジネスの成功は覚束ない。BOPアプローチは、現地のニーズに適合する新製品の開発、<br />
サプライチェーン・モデルの刷新といった既存のビジネスモデルの再設計を必要とする。<br />
BOPプロジェクトは様々な形態をとるが、いずれにしても真のパートナーシップの構築が中核と<br />
なる。BOPプロジェクトを成功に導くために企業は、国内のあるいは国際的な開発機関、地元の<br />
コミュニティー、NGO、開発途上国政府などと真のパートナーシップを構築する必要がある。例え<br />
ば欧州の場合、欧州委員会と企業のパートナーシップが重要となる。こうしたパートナーシップが<br />
双方に利益をもたらすのは明らかだが、欧州委員会の開発政策の枠組みには、企業とパートナ<br />
ーシップを構築するための明確な枠組みがまだ存在しない。<br />
BOPプロジェクトの基盤はそのプロセスにあり、製品にはない。ダノン・グループの持続可能な<br />
開発・社会的責任を担当する Bernard GIRAUD 副社長は、BOPを次のように定義している。<br />
『貧困層に何かを売ることは、ピラミッドの底辺(BOP)での持続可能なビジネスではない。BO<br />
Pイニシアティブとみなされるためには、提供される製品やサービスが貧困層に明確な社会的な<br />
価値をもたらすものでなくてはならない。これは特別なBOPビジネスのモデルは存在しないことを<br />
意味する。新たな社会的価値を創出するには、現地固有の状況に即して行動する必要がある。B<br />
OPプロジェクトは、短期的にも長期的にもネガティブな外部性(externalities)にまさるポジティブな<br />
外部性をもたらすものであることが理想的だ。」<br />
a. 企業が他の組織とBOPイニシアティブを発展させるのに不可欠な要素<br />
・BOPプロジェクトの成功に最も重要な要素は、最終製品あるいはサービスの適切性で、企業<br />
は貧困層のニーズを理解し、地元コミュニティーの開発目標に寄与する製品を市場に投入し<br />
なくてはならない。<br />
・購買力や市場アクセスを考慮し、提供する製品やサービスのコストを削減する必要がある。新<br />
38 http://www.csreurope.org/data/files/toolbox/Base_of_the_pyramid_workingpaper.pdf<br />
231
しいビジネスモデルでは、パッケージング戦略、価格戦略、さらには製品そのものの適応な<br />
どを通じ、手頃な単価の製品を提供しなくてはならないことが多い。<br />
・生産、流通、販売ネットワークに関連する交通インフラがないことから、ピラミッドの底辺の<br />
人々に到達するのは容易ではない。こうした状況を改善するため、企業は新しい生産や流通、<br />
マーケティングの方法を考案する必要がある。生産拠点をBOPコミュニティーの近くに持って<br />
くるのが、BOP環境に生産プロセスを適応させる最善の方法といえる。輸送コストを削減で<br />
きるし、コミュニティーに雇用や収入をもたらす。流通やマーケティング・プロセスの適応はし<br />
ばしば、移動体通信やバーチャル・プラットフォームの使用を通じて行われる。ただし、こうし<br />
たプラットファームが常にどこでも使用可能とは限らない。<br />
・BOPビジネスモデルは、ネガティブな外部性を最小化し、ポジティブな外部性を促進しようとす<br />
る。このためには進出国の政府との対話や、同政府の支援が不可欠となる。政府の演ずる<br />
役割は国によって、あるいは経済部門によって異なるが、如何なるケースにおいても官民は<br />
責任を分担すべきである。<br />
b. これまでの経験から得られた成功するBOPアプローチの要素<br />
「パートナーシップ」、「緊密な対話」、「共同クリエーション」、「イノベーション」、「共通の価値<br />
(mutual value)」。これらの要素は相互依存的で、相互に他の要素を強化する。<br />
BOPイニシアティブは、ビジネス・オペレーションの全く新しい形態ではない。BOPは、開発途<br />
上国での従来のビジネスの限界からポジティブな要素を抽出し、ソリューションを開発するという<br />
形で、開発途上国でのビジネスの経験から生まれた。<br />
・通常のビジネスの限界<br />
新しいビジネスは雇用を創出し、富を生み出す(貧困の削減)。さらには提供される製品やサー<br />
ビスが消費者の選択の幅を広げ、経済成長につながる。こうして新市場が生まれると他の企業が<br />
進出してきて、競争が行われる。しかし、こうした論理が機能するためには、市場の発展を支援し、<br />
正しい方向に導くための政治制度、社会制度が不可欠となる。こうした制度が存在しないと、コミ<br />
ュニケーションやコーディネーションの欠如からネガティブな外部効果が生じる。<br />
・ビジネス・ソリューションとしてのBOP<br />
BOP戦略はまず、製品の市場への適合性という要素の解決を試みた。品質を維持しながら手<br />
頃な価格の製品やサービスを提供することで開発目標を達成することが主眼となったが、方向は<br />
正しいものの、必要かつ十分なアプローチとはいえなかった。<br />
232
新しい形態のBOPでは、ピラミッドの底辺にいる人々やコミュニティーをビジネス発展のための<br />
パートナーとみなす。<br />
出所:CSR Europe<br />
図表 50 新世代のBOP戦略<br />
民間部門のBOPプロジェクトとEUの開発アジェンダの間には基本的な補完性が存在する。今<br />
後も欧州委員会やその他の国際機関、ローカルなステークホルダーとの対話を深める必要があ<br />
る。<br />
EU・アフリカ・ビジネス・フォーラム 39 では、フォーラムのプロジェクトの立案、実施は、アフリカの<br />
起業家への知識やスキルの移転といった、BOPに機会を提供することも含め、ミレニアム開発目<br />
標に沿ったものとすることで合意が形成された。同フォーラムは、協同フレームワークにおいて最<br />
新のBOPプロジェクトを広め、実施するためのアクセスポイントを提供する。<br />
参考6 BizClim について<br />
BizClim は、欧州委員会の「ACPビジネス環境 facility」プロジェクトで、2006 年 4 月に開始され、<br />
2009 年 9 月 30 日に終了する予定だった。9 月 28~29 日にケニア・ナイロビで開催された第3回E<br />
U・アフリカ・ビジネス・フォーラムのために、3 ヵ月延長されたが、09 年年末に終了した。欧州開発<br />
基金(EDF)から 2,000 万ユーロの資金が充当された。<br />
現在、欧州委員会の入札に提案している 30 ヵ月のプロジェクト予算が通れば(面談時はまだ審<br />
査中だった)、2010 年 7 月から新たな BizClim としての活動を再開する可能性がある。<br />
BizClim のこれまでの活動として、アフリカ・カリブ・太平洋(ACP)諸国におけるビジネス環境の<br />
39 2005 年 12 月に採択された『アフリカのための EU 戦略』の一部をなすもので、「国連ミレニアム開発目標」を達成<br />
するためのアフリカ諸国の努力を支援するためのもの。アフリカの民間部門の発展を促すとともに、欧州からの<br />
アフリカへの投資を奨励することで、アフリカ経済の世界経済への統合を促進する。第 1 回のフォーラムは、<br />
2006 年 11 月にブリュッセルで開催された。<br />
233
改善を行っている。具体的にはACP諸国の法制度の枠組みの改善を支援し、ビジネス環境の改<br />
善や、ノウハウを提供する。ビジネス環境に関係する全ての分野が活動対象となる。<br />
BizClim は、シンクタンクとしての機能も持つ。シンクタンクとして、企業に対するノウハウの提供<br />
を行うとともに、EUアフリカ・ビジネス・フォーラムとも緊密に協力している。同フォーラムは欧米企<br />
業のみならず、現地企業、NGOなどの関係者がフランクな意見交換を行い、ベスト・プラクティス<br />
を共有する非常に有益な機会となっている。第 3 回EUアフリカ・ビジネス・フォーラムでは、貿易、<br />
インフラ、ICT、企業家精神と中小企業、エネルギー・原材料の5つをテーマに議論および意見交<br />
換が行われた模様。詳細は次の URL を参照(http://www.euafrica-businessforum.org/)。<br />
○BizClim のプロジェクトについて<br />
BizClim のプロジェクトについては、サハラ以南のアフリカ諸国が対象で、西アフリカ、中央アフ<br />
リカのほとんどの国をカバーした。エジプトやリビアなどでのプロジェクトが不可能というわけでは<br />
ない。具体的な事例としては、カメルーンのマイクロファイナンス・プロジェクト、ガーナのインフラコ<br />
リドール・プロジェクト、東カリブ海でのモバイルバンキング・プロジェクトなどがあげられる。<br />
法規制分野では、ガボンでビジネス法の改善に取り組んだ。ガボンでの成功を受け、ブルキナ<br />
ファソなど他の国でも実施している。ICT分野では、特にガーナや、中央アフリカでのビジネス環境<br />
の改善に取り組んだ。ブルキナファソでは、マイクロソフトと協力した。多くの分野のプロジェクトに<br />
係ったが、72 ある大規模プロジェクトの多くは地域プロジェクトだった。<br />
○BOPへの取組について<br />
CSR Europe のBOPラボラトリーには、シンクタンク活動の一環として参加した。BOPには特に<br />
大企業が関心を示しているが、NGOや中小企業も関心を示している。BOPはCSRの一つと考え<br />
るより、新しいビジネスモデルと考えるべきで、このモデルでは、社会的な課題の問題解決も可能<br />
となる。<br />
234
235<br />
図表 51 EUの開発援助スキーム<br />
(参考) EUの開発援助スキーム<br />
予算<br />
マイクロファイナンスに<br />
関するACP-EUフレーム<br />
ワーク(EDF)<br />
1,500万ユーロ<br />
(2005年~2011年)<br />
主管官庁 欧州委員会(開発総局、<br />
Europeaid)<br />
ACP-EUエネルギー基金<br />
(EDF)<br />
2億2,000万ユーロ<br />
(2005年~2009年)<br />
欧州委員会(開発総局、<br />
Europeaid)<br />
ACP-EU水基金<br />
(EDF)<br />
環境、エネルギーを含む 開発における非国家主<br />
天然資源の持続可能な 体、<br />
管理(DCI)<br />
地方自治体(DCI)<br />
5億ユーロ 4億7,000万ユーロ<br />
(2004年~2005年) (2007年~2010年)<br />
欧州委員会(開発総 欧州委員会(対外関係<br />
局、Europeaid) 総局、Europeaid)<br />
16億ユーロ<br />
(2007年~2013年)<br />
欧州委員会(対外関係<br />
総局、Europeaid)<br />
食糧安全保障(DCI) 移民、亡命(DCI)<br />
9億2,500万ユーロ<br />
(2007年~2010年)<br />
欧州委員会(対外関係<br />
総局、Europeaid)<br />
3億8,400万ユーロ<br />
(2007年~2013年)<br />
社会的、人的開発<br />
(DCI)<br />
10億ユーロ<br />
(2007年~2013年)<br />
国境を越えた協力<br />
(ENPI)<br />
11億1,843万4000ユー<br />
ロ(2007年~2013年)<br />
欧州委員会(対外関係 欧州委員会(対外関係 欧州委員会(対外関係<br />
総局、Europeaid) 総局、Europeaid) 総局、Europeaid)<br />
事例数 11件 74件 97件 不明 不明 不明 不明 不明 15件 25件<br />
対象地域 ACP諸国 ACP諸国 ACP諸国<br />
資金負担の<br />
割合<br />
上限額<br />
80%が上限<br />
100万ユーロ(下限額:25<br />
万ユーロ)<br />
インフラ関連のプロ<br />
小規模プロジェクトの場合<br />
ジェクトの場合は<br />
は75%が上限で、インフラ<br />
50%が上限。その<br />
関連プロジェクトの場合は<br />
他のプロジェクトの<br />
50%が上限と、プロジェク<br />
場合は75%が上<br />
トにより異なる。<br />
限。<br />
小規模プロジェクトの場合<br />
は250万ユーロ(下限額:<br />
20万ユーロ)、インフラ関<br />
連プロジェクトの場合は<br />
1000万ユーロ(下限額:<br />
250万ユーロ)と、プロジェ<br />
クトにより異なる。プロジェ<br />
クトによっては、上限額が<br />
150万ユーロで、下限額が<br />
20万ユーロという場合もあ<br />
インフラ関連のプロ<br />
ジェクトの場合は<br />
2000万ユーロが上<br />
限(下限額:100万<br />
ユーロ)。<br />
EU加盟国、先進工業国<br />
を除く全ての国<br />
不明<br />
不明<br />
先進工業国を除く全て<br />
の国(ただしEU加盟国を<br />
含む)<br />
援助対象国の非国家主<br />
体および地方自体への<br />
援助の場合は90%<br />
(75%の場合もある)、<br />
不明<br />
EUの非国家主体および<br />
地方自体への援助は<br />
75%まで。下記の具体<br />
例の場合は75%。<br />
プロジェクトにより異なる<br />
(100万ユーロ、400万<br />
ユーロなど)。下記の具 不明<br />
体例の場合は75万ユー<br />
ロ。<br />
EU加盟国、先進工業<br />
国を除く全ての国<br />
EU加盟国、先進工業<br />
国を除く全ての国(た<br />
だしEUの近隣諸国を<br />
優先)<br />
下記の具体例の場合<br />
は78%。<br />
下記の具体例の場合<br />
は127万5000ユーロ<br />
EU加盟国、先進工業<br />
国を除く全ての国<br />
近隣諸国のための投資<br />
基金(ENPI)<br />
7億ユーロ(2007年~<br />
2013年)<br />
欧州委員会(対外関係<br />
総局、Europeaid)<br />
モロッコ、アルジェリア、 モロッコ、アルジェリア、<br />
チュニジア、リビア、エジ チュニジア、リビア、エジ<br />
プト、イスラエル、パレス プト、イスラエル、パレス<br />
チナ自治政府、ヨルダ チナ自治政府、ヨルダ<br />
ン、シリア、レバノン、ウ ン、シリア、レバノン、ウ<br />
クライナ、ベラルーシ、モ クライナ、ベラルーシ、モ<br />
ルドバ、グルジア、アル ルドバ、グルジア、アル<br />
メニア、アゼルバイジャ メニア、アゼルバイジャ<br />
ン、ロシア<br />
ン、ロシア<br />
不明 最大90%が上限 不明<br />
下記の具体例の場合<br />
は年平均1800万ユー<br />
ロ。<br />
プロジェクトにより異なる 不明<br />
申請手続き Europeaidに申請<br />
る。<br />
Europeaidに申請 Europeaidに申請 Europeaidに申請 Europeaidに申請 Europeaidに申請 Europeaidに申請 Europeaidに申請 Europeaidに申請 Europeaidに申請<br />
セクター マイクロファイナンス エネルギー 水<br />
天然資源の持続可能な 非国家主体、地方自治<br />
管理<br />
体の能力強化<br />
食糧安全保障<br />
健康、教育、男女平<br />
移民、亡命分野での技<br />
等、社会的結束、文化<br />
術的、財政的支援<br />
等<br />
環境、国民健康、組織<br />
犯罪対策、国境管理な<br />
ど<br />
エネルギー、水、交通イ<br />
ンフラ、金融など<br />
グリーンフィールド型マイ<br />
プロジェクト具<br />
SAVA地方での電化プロ<br />
クロファイナンス機関の<br />
体例<br />
ジェクト(マダガスカル)<br />
設立(カメルーン)<br />
アフリカ、カリブ海に 国内森林プログラムの<br />
おける水の統合管 ためのメカニズム(ACP<br />
理のためのキャパシ 諸国など57カ国と4地<br />
ティー・ビルディング 域)<br />
青年、女性、移住民の 食品・栄養安全の統合 亡命申請者の保護(ク<br />
ための統合開発プロジェ 推進の支援(ニカラグ ロアチアおよび西バル 教育と能力開発<br />
クト<br />
ア)<br />
カンの地域)<br />
ルーマニア-ウクライナ-<br />
モルドバ・プログラム<br />
黒海での送電システム<br />
(グルジア)
Ⅲ.国際機関調査<br />
1.ユニセフ物資供給センター 'UNIPAC:United Nations Procurement and<br />
Assembly Center(<br />
2.国連食糧農業機関 'FAO:Food and Agriculture Organization(<br />
3.国連世界食糧計画'WFP:World Food Programme(<br />
4.国連難民高等弁務官事務所 'UNHCR:United Nations High Commissioner for<br />
Refugees(<br />
5.世界保健機関'WHO:World Health Organization(<br />
236
1.ユニセフ物資供給センター<br />
'UNIPAC:United Nations Procurement and Assembly Center(<br />
'1(活動概要 1<br />
① ユニセフの活動<br />
病気、栄養失調、清潔な水や公衆衛生の欠如、紛争、自然災害などが世界の子どもの命を脅<br />
かし、現在、世界で毎日 2 万 6,000 人の 5 歳未満の乳幼児が、予防可能な病気で死亡していると<br />
言われている。ユニセフはこれまで 60 年以上、このような状況を打破するための活動を行ってき<br />
ており、特に子どもの権利条約に従い、2015 年までのミレニアム開発目標'MDGs(達成に向け、<br />
下記の 6 つの優先課題に焦点を当てている。<br />
� 子どもの生存と成長<br />
� 基礎教育と男女平等<br />
� エイズ<br />
� 緊急時対応<br />
� 子どもの保護<br />
� 子どもの権利に関する方針分析・擁護・協力関係<br />
② UNIPACの活動概要<br />
ミレニアム開発目標達成に向けユニセフの活動を持続的に推進していくためには、物資の安定<br />
供給・タイムリーな出荷・配送が必要不可欠であり、その役割をユニセフ購買サービス物資供給セ<br />
ンター'UNIPAC(が担っている。また技術援助、マネージメントサービス、サプライサービスを含<br />
めた供給管理、国民の地位構築など、物資供給に関連した幅広い取組も行っている。<br />
一般的に非営利団体は、ユニセフの購買サービスを利用することができる。その財源は政府、<br />
非政府組織どちらでもよい。ユニセフはユニセフ自体の活動に加え、以下に挙げる団体・組織の<br />
代行として購買活動を請け負っている。逆に、個人、営利団体、アルコール・煙草・地雷の生産・<br />
販売に関わる企業のプログラムなどの購買活動代行は決して行わない 2 。<br />
1 http://www.unicef.org/supply/files/supply-annual-report-2008.pdf (page 1-3)<br />
2 http://www.who.int/3by5/unicef_procurement/en/<br />
237
� 各国政府<br />
� 非政府組織'NGO(<br />
� その他国連組織<br />
� 国際金融機関<br />
� 慈善団体<br />
� 大学機関<br />
ユニセフは世界保健機関'WHO(の基準を満たした商品のみ購買し、WHOから推奨のあるサ<br />
プライヤーの最新リストに記載されている企業からのみ物資を調達する 3 。<br />
2008 年には、コペンハーゲンの物資供給センターの倉庫から、特別注文セットを含む 38 万<br />
4,000 品目が包装・発送され、現地援助活動、物資調達・発送など 1 億 530 万ドル相当が費やされ<br />
た。倉庫は、医療製品貯蔵と流通に関する適正流通規範'GDP:Good Distribution Practice(の<br />
基準をクリアしており、面積は 2 万 5,000 平方メートル'サッカー競技場 3 つ相当(である 4 。<br />
この倉庫には、ユニセフが供給する 750 品目以上が保管されているのに加え、国連難民高等<br />
弁務官事務所'UNHCR(と国際赤十字社・赤新月社連盟'IFRC(に、緊急時用物資を貯蔵する<br />
ためのスペースを貸し出している。なお、これら団体の在庫量は、全体の 30%となっている。<br />
'2(拠点と役割分担<br />
ユニセフは、コペンハーゲンの物資供給センターの倉庫のほか、ドバイ'アラブ首長国連邦)、コ<br />
ロン'パナマ(、上海'中国(の 3 拠点を、緊急時用ハブとして運営している。これら 4 拠点には、25<br />
万人が 3 週間過ごすのに十分な緊急用援助物資が保管されており、緊急時には、災害の発生の<br />
連絡を受けた 48 時間以内に必要な物資が発送される。<br />
ユニセフ供給課は、物資調達、契約、物流管理、積荷、薬理学、健康商品技術、品質管理、検<br />
品、倉庫保管、工学、教育、建築、救急、財務、人材、情報・通信技術の専門家から構成されてい<br />
る。96 カ国 134 国籍 800 人以上の人材が、UNIPACと 158 カ国・地域にある現地事務所に配置さ<br />
れており、政府機関、その他国連機関、NGO、産業界、学会や企業などと共同で、子どものニー<br />
ズに適した物資供給が行われるよう活動を行っている 5 。<br />
3 http://www.who.int/3by5/unicef_procurement/en/<br />
4 http://www.unicef.org/supply/index_warehouse.html<br />
5 http://www.unicef.org/supply/index_protection.html<br />
238
ユニセフが物資を配給する国の多くでは、配送システムが整然と効率よく機能しているとは限ら<br />
ない。このため、現場での安定供給に向けたスタッフ教育とともに、現場のシステムやインフラの<br />
構築・整備について現地政府への働きかけも行っている。<br />
2008 年以降、ユニセフ各国事務所の決定権限が拡大され、国際調達を行う明確な優位性がな<br />
い場合、各国事務所の裁量で地域市場から物資を調達できるようなった。ユニセフは、これにより<br />
地域経済に貢献するとともに、プログラムの効率性・持続可能性を向上できるとしている 6 。<br />
'3(調達の仕組み<br />
① 調達窓口連絡先<br />
まずユニセフの調達では、連絡優先順位第 3 位の個人名は 2009 年 12 月時点で今回調査のた<br />
め連絡の取れたスタッフであり、国連スタッフが数年契約で入れ替わることを鑑み第 3 位連絡先と<br />
している。<br />
ホームページ<br />
登録先<br />
図表 1 ユニセフ調達窓口連絡先<br />
'ユニセフ供給課(http://www.unicef.org/supply<br />
(国連世界市場データベース)http://www.ungm.org/Index.aspx<br />
連絡優先順位 1 2 3(個人)<br />
連絡先名 UNICEF Supply UNICEF New York Supply Ms Yvonne Thoby<br />
Division<br />
Centre<br />
住所/役職 UNICEF Plads,<br />
Freeport<br />
UNICEF House Communication Assistant<br />
2100 Copenhagen Ø 3 UN Plaza, H-6L UNICEF Supply Division<br />
Denmark New York, N.Y. 10017 USA (以下1と同住所)<br />
電話番号 +(45) 35 27 35 27 +1(212) 32 67 490 +(45) 35 27 32 19<br />
ファクス +(45) 35 26 94 21 +1(212) 32 67 477 -<br />
Eメール supply@unicef.org - ythoby@unicef.org<br />
国連世界市場データベース'UNGM:United Nations Global Marketplace(は国連関連機関の購<br />
買窓口としての役割を担っている。サプライヤー候補企業にとっては、それぞれの機関に登録す<br />
る手間を省き、UNGMへの一度の登録で数機関にサプライヤー登録申請を行うことができるとい<br />
うメリットがある。国連機関にとっては、申請時選択した 6 桁のコードから成る商品・サービスコード<br />
'UNCCSコード(により、登録サプライヤーをデータベースから即座に選定できる。また、登録サ<br />
プライヤーは商品・サービスの最新入札情報を E メールにて受け取ることができる。なお、UNGM<br />
の具体的な使用方法のマニュアルはウェブサイト 7 で参照可能。<br />
6 http://www.unicef.org/supply/files/supply-annual-report-2008.pdf (Page 7, 10)<br />
7 http://www.ungm.org/Publications/UserManuals/UserManual_Supplier.pdf<br />
239
② 基本方針<br />
ユニセフは、国連調達共通ガイドライン'Common Guidelines for Procurement by Organizations<br />
in the UN System(に従い、調達活動の目的を、費用価値に見合った適切な物資・サービスを効率<br />
的に適時獲得すること、ユニセフの基準を満たすこと、競争入札が公平・誠実・透明性を確保して<br />
いること、としており、これを踏まえた調達指針 8 を提示している。<br />
図表 2 ユニセフの物資調達指針<br />
●ユニセフの基準を満たす商品、設備・備品のみ調達する<br />
●主としてメーカー、委託販売者から調達する<br />
●共同事業を行うサプライヤーを継続的に評価する<br />
●全ての調達で競争入札を実施する<br />
●競争入札に関し、広範なサプライヤー候補を指名する<br />
●国際技術規格に適合する商品を調達する<br />
●児童・未成年を雇用している企業、および地雷およびその関連する部品製造者からの調達を禁止する<br />
●非倫理的、無認証、搾取的な活動に従事する企業からの調達を禁止する<br />
ユニセフは、子どもの権利条約に署名しており、サプライヤー候補企業に対しても、子どもの経<br />
済的搾取・有害な労働からの保護を訴える、同条約第 32 条の遵守を義務付けている。ユニセフ<br />
はサプライヤーが児童労働に関し、その国の労働法や条例を順守していないことが判明した場合、<br />
法的責任は負わず、無条件にその契約を打ち切る権利がある。<br />
またサプライヤーは、系列会社・関連会社も含め、対人地雷およびその部品の製造・販売に従<br />
事していないことを証明する必要があり、サプライヤーがこの規定に違反した場合、ユニセフはそ<br />
の契約を打ち切る権利がある 9 。<br />
ユニセフが海外から調達する物資は、ワクチン・予防接種補給品、調合薬・微量栄養素、医療<br />
設備・機器、教育備品、治療食、車両、IT機器など約 2,000 品目で、ユニセフ供給カタログにリスト<br />
アップされている。カタログには、ほとんどの物資に技術仕様書・明細事項が添付されている。ユ<br />
ニセフは、中古の商品はいかなるものでも調達せず、食品は緊急事態用の特定治療食を除いて<br />
調達しない。また、特別な緊急支援用を除き、衣類も調達しない 10 。<br />
11 12<br />
③ 調達・購買の重点分野とその方針<br />
ユニセフは毎年、数千種の物資を調達しており、この中には子どもの生存と成長に直接、影響<br />
8 http://www.unicef.org/supply/index_become_a_supplier.html<br />
9 http://www.unicef.org/supply/index_procurement_policies.html<br />
10 http://www.unicef.org/supply/index_unicefsupplies.html<br />
11 http://www.unicef.org/supply/files/CommodityEnglish.pdf<br />
12 http://www.unicef.org/supply/index_procurement_services.html<br />
240
を与える重要かつ必要不可欠な物資も含まれる。これらは、国際市場で簡単に手に入るものもあ<br />
れば入手困難なものもある。こうした市場制約を乗り越え、子どもの命をつなぐ商品への容易なア<br />
クセスを保証することが、ユニセフの戦略的課題であり中心的責務である。重点分野における購<br />
買方針は以下の通り。<br />
1(蚊帳、殺虫剤、マラリア処方薬<br />
ユニセフは世界最大の蚊帳の購買者である。防虫剤処理蚊帳と防虫剤処理用セットをメーカー<br />
に大量注文し、長期契約を結ぶことで、価格を大幅に抑えている。調達する蚊帳は全て、世界保<br />
健機関殺虫剤評価スキーム'WHOPES(の基準に適合していなければならない。<br />
� 防虫剤処理蚊帳'ITNs:Insecticide-treated mosquito nets(<br />
防虫剤処理蚊帳は、ネットと防虫剤処理セットで構成されている。糸の品質は、防虫剤の吸<br />
収能力に関わり非常に重要なため、WHOのネット原材料規格に厳密に従っている。<br />
ITNs は、WHOが推奨する防虫剤により定期的に防虫剤処理しなければならない。防虫剤<br />
は、一回分ずつ個包装されたものか、処理用セットとして大量にユニセフによって注文されるが、<br />
効率性の観点からセットが好まれる。処理用セットは、一回分の防虫剤と、手袋、計量バッグ、<br />
フランス語と英語の取扱説明書で構成され、要望に応じ、その他の言語での説明書も梱包され<br />
る。<br />
� 長期残効型防虫処理済蚊帳'LLINs:Long Lasting Insecticide-treated Nets(<br />
アフリカなどで、防虫剤処理蚊帳の防虫剤再処理率が低かったことを踏まえ、防虫剤加工済<br />
みの長期残効型防虫処理済蚊帳が開発された。長期残効型防虫処理済蚊帳は、使用期限内<br />
は防虫剤処理をする必要がないため、ユニセフのプログラムにおいて推奨されている。<br />
長期残効型防虫処理済蚊帳の開発により、防虫剤処理蚊帳の調達量は近年著しく減尐して<br />
いる。なお 2007 年の調達総量が減尐しているのは、より多くの企業、NGO、慈善団体などが協<br />
力し、ユニセフを経由せずに蚊帳の供給を行うようになったことによる 13 。LLINs の価格変化は<br />
図表の通り 14 。<br />
13 http://www.rollbackmalaria.org/partnership/wg/wg_itn/docs/rbmwin4ppt/2-13.pdf<br />
14 http://www.unicef.org/supply/files/2009_LLIN_Overview_and_Challenges_by_Elena_Trajkovska%281%29.pdf<br />
241
図表 3 ユニセフによる蚊帳調達量<br />
出所:UNICEF Supply Division, WIN-4 Meeting, Ber 15<br />
マラリア処方薬に関しては、多くの国がクロロキンとその代替薬であるピリメタミン・スルファドキ<br />
シンから、アルテミシニンをベースにした混合療法に移行している。ユニセフは、今後もパートナー<br />
との協力により、各国が将来何を必要とするかを正確に予測する必要がある。<br />
2(ワクチン、安全な注射機器<br />
ユニセフ供給課は、途上国の子どもたちに必要なワクチンの約 40%'250 万回分相当(を調達、<br />
パートナーと共同でワクチンの安全性を保障し、最貧国にいつでも供給できる体制を整えている。<br />
ユニセフは、はしか、ジフテリア、百日咳、破傷風、結核、B型肝炎、ヘモフィラス・インフルエン<br />
ザ菌タイプB、ポリオなど、必須の基本的なワクチンを、一回分あるいは数十回分単位で調達して<br />
いる。ユニセフは、WHOの基準をクリアし、医薬品適正製造基準'GMP:Good Manufacturing<br />
Practice(に準拠した生産者からのみワクチンを調達している。また注射の安全性を保障するため、<br />
再使用不可の注射器あるいは一回分で個包された再使用防止装置の使用を促進し、使用済注<br />
射器の廃棄用ボックスも提供している。<br />
日本企業の例としては、日本ビーシージーサプライ'日本ビーシージー製造株式会社の子会<br />
社(がBCGワクチンを供給している。<br />
図表 4 ワクチンの価格概算'120 円/ドルで換算(<br />
ワクチン名 一人分単位<br />
ポリオ(小児マヒ) 約20円<br />
MMR(はしか、おたふく風邪、風疹) 約114円<br />
BCG(結核) 約7円<br />
はしか 約95円<br />
DPT(ジフテリア、百日咳、破傷風) 約9円<br />
出所:UNICEF Supply Division 16<br />
15 http://www.rollbackmalaria.org/partnership/wg/wg_itn/docs/rbmwin4ppt/2-13.pdf (Page 3)<br />
242
3(低温流通システム<br />
ワクチンは、正しく取り扱わないと、効能が簡単に失われてしまうため、ユニセフは低温・冷凍室、<br />
圧縮冷蔵・冷凍庫、吸収冷蔵・冷凍庫、太陽光発電冷蔵・冷凍庫、冷蔵庫予備部品、低温ボック<br />
ス、検温器・測定器など、現場の状況に応じ最適な低温流通システムを提供している。これらの商<br />
品は、WHOの低温流通に関する性能規定を満たしていなければならない。<br />
日本企業の例としては、2008 年度にアラノ貿易が冷凍トラックをUNHCRに供給している。<br />
4(医療機器―消耗品、設備・装置<br />
ユニセフは、様々な医療機器セットを開発し、大規模な実地試験を行ってきた。その結果、現在、<br />
さまざまな医療機器セットが配布可能となっている。セットは、必要性に応じ中身を変更することが<br />
可能で、ユニセフの供給カタログにおいても、構成商品を個別に注文できるようになっている。医<br />
療機器メーカーは、医療機器規制国際整合化会合'GHTF:Global Harmonization Task Force(に<br />
よって推奨されている品質システム基準に基づき、必須条件を満たしていなければならない。また<br />
商品は、GHTFが設定した医療機器の安全性および性能の基本原則'Essential Principle of<br />
Safety and Performance of Medical Devices(に準拠していなければならない。<br />
日本企業の例としては、富士レビオが 2008 年度にユニパック、2007 年度にWHOに対し、医療<br />
診断検査キットを、アラノ貿易と日世貿易がそれぞれユニパック、UNHCRに対し医療機器を供給<br />
している。<br />
16 http://www.jcv-jp.org/vaccine/encyclopedia.html<br />
243
図表 5 医療機器セット内容<br />
セット名 梱包物 対象<br />
新緊急時用<br />
健康セット<br />
basicキット×10組―12種の基礎医薬品、医療用品・設備。<br />
医療従事者使用。1,000人が3カ月間に必要な量。<br />
4つの補助キット×1組―基本キットに含まれていない<br />
1.医薬品、1a.マラリア薬・要低温流通医薬品・向精神<br />
薬、2.医療機器、3.再生可能医療機器。専門医療従事<br />
者・医師使用。1万人が3カ月間に必要な量。<br />
使用マニュアル<br />
助産セット 以下一組づつ6種のキットで構成されている。<br />
1.基礎医薬品<br />
1a.補助医薬品―通常は輸入許可が必要な医薬品(麻酔<br />
剤・向精神薬梱包物)<br />
2.医療設備―分娩室・産科病棟一室に必要な基礎医療設備<br />
3.再生可能医療機器<br />
C.滅菌装置―確実に滅菌できる基本的な蒸気消毒機器<br />
Basic.蘇生器具<br />
助産師・助産技術を持つ看護師・医師使用。<br />
産科手術セット 助産セットの6種のキット(滅菌装置・蘇生器具のみ2組ず<br />
つ)に加え、以下4種の産科外科補助キットが含まれる。<br />
補助1.医療品―帝王切開手術など平均50回の出産に対応<br />
補助1a.補助医療品―同上<br />
補助2.医療設備―分娩室・手術室一室に必要な手術機器<br />
補助3.再生可能医療機器―帝王切開手術などに対応<br />
助産師・看護師・医師・産科医・婦人科医・外科医・麻酔<br />
医使用。<br />
消毒セット 以下のキットが含まれる。<br />
C.滅菌装置―確実に滅菌できる基本的な蒸気消毒機器<br />
蘇生セット 以下のキットが含まれる。<br />
Basic.蘇生器具<br />
手術用器具セット ― ―<br />
応急措置セット ― ―<br />
出所:UNICEF Commodities and Supply Services 17 、Technical Bulletin No.3 18 、4 19 、5 20<br />
5(調合薬、微量栄養素<br />
244<br />
1万人が3カ月間に必要な薬・<br />
医療用品・基本的な医療機器<br />
約50回の出産に必要な薬・再<br />
利用可能な医療用品・医療機<br />
器・簡易助産/産科手術装備<br />
約100回の出産に必要な量を<br />
想定、50の合併症および手術<br />
(平均25回の帝王切開手術を<br />
含む)にも対応可能<br />
ユニセフ供給課には、薬剤と微量栄養素に関する専門家チームがあり、プロジェクトと製品仕<br />
様の向上を支援している。サプライヤーは、医薬品及び医薬部外品について製造管理及び品質<br />
管理の基準、あるいはGMPの基準をクリアしていなければならない。<br />
ユニセフ供給課は、オランダ医薬局より適正流通規範'GDP(の認可を受けており、コペンハー<br />
ゲンのUNIPAC倉庫は、医薬品の人体への使用に関するGDPを基にした欧州共同体ガイドライ<br />
ンに従い、国連の倉庫で唯一、医薬品・調合薬品の卸売の認可を取得している。<br />
6(エイズ関連処方薬・診断法<br />
ユニセフは、エイズ関連処方薬・診断法の選択の際、WHOの技術ガイダンスに従っている。サ<br />
17 http://www.unicef.org/supply/files/CommodityEnglish.pdf<br />
18 http://www.supply.unicef.dk/Catalogue/bulletin3.htm<br />
19 http://www.supply.unicef.dk/Catalogue/bulletin4.htm<br />
20 http://www.supply.unicef.dk/Catalogue/bulletin5.htm<br />
―<br />
―
プライヤーは、ユニセフから抗レトロウイルス薬の発注を受けた場合、医薬品規制と特許状況を<br />
調べる必要がある。また、国や薬剤の供給先から輸送援助を依頼された場合は、知的所有権の<br />
貿易関連の側面に関する協定'TRIPS(に基づき、緊急輸入制限措置の実施状況をユニセフに<br />
提出しなければならない。ユニセフはWHOに事前に推奨されたもののみ調達している。<br />
7(水・環境と公衆衛生<br />
ユニセフは、手頃で安全な飲料水のアクセスがない世帯数を、2010 年までに 3 分の 1 以下まで<br />
減らすという目標を掲げ、その達成に向けて必要なサービス・設備を提供している。提供している<br />
設備は一般家庭向けから一時避難所や村落で提供する水供給システムまで様々である。供給シ<br />
ステムを現場で実行に移すため、ユニセフは、適切な部品、設備、システム稼動に必要な電源装<br />
置、消耗材'フィルター・凝固剤含む(なども調達している。サプライヤーは、ISO9001 / EN46001、<br />
あるいはISO9002 / EN46002 の認証を取得している必要がある。<br />
日本企業の例としては、ヤマト科学株式会社が 2007 年度にWHOに対し、原水をヒーターで熱<br />
し、蒸気から蒸留水を製造する商品、純水製造装置オートスチルを供給している。<br />
8(教育設備・備品<br />
ユニセフは過去数十年、各国政府と協調し子どもたち、特に女子に適切な教育用品を供給して<br />
きた。緊急時対応など現場のニーズを調査し、独自に教育・レクリエーション目的の教育備品セッ<br />
トを開発した。<br />
図表 6 教育備品セット内容<br />
セット名 梱包物 対象 在庫<br />
スクールイン<br />
ボックスセット<br />
レクリエーショ<br />
ンセット<br />
鉛筆(80)、ノート(80)、木製時計<br />
(1)、計算用のプラスチック製サイ<br />
コロ(80)、フィルム加工したポス<br />
ター(アルファベット、掛け算、<br />
数字の表)<br />
それぞれのゲームに対応したボー<br />
ル、スポーツウェア、チョーク、<br />
境界線を引くためのメジャー、<br />
笛、スコアボード<br />
科学教育セット 研究用ゴーグル、小型試験管、<br />
バーナー、検温器、多目的液体混<br />
合用プラスチックプレート(12×<br />
2ml、48×0.3ml)、化学物質[1]<br />
245<br />
教師1名と生徒80人が<br />
使用できる基本的教育<br />
備品<br />
40人までの生徒が使用<br />
できる体育用品。各国<br />
文化別・男女別スポー<br />
ツの相違に対応可能<br />
15回までの科学実験に<br />
必要な装置・備品。<br />
4、5年間耐久<br />
緊急輸送用にコペン<br />
ハーゲン倉庫に5,000<br />
セット、ユニセフ・南<br />
アフリカ倉庫に500セッ<br />
トの在庫を常備<br />
コペンハーゲン倉庫に<br />
200セット、南アフリカ<br />
倉庫に100セットを常備<br />
出所:UNICEF Commodities and Supply Services 21 、Technical Bulleitn No.10 を基に作成<br />
これらの商品及びセットは、欧州玩具安全規格'EN71(に適合し、そのパッケージにはCEマー<br />
ク、あるいはそれと同格の国際的な玩具の安全規格が貼付されていなければならない。<br />
21 http://www.unicef.org/supply/files/CommodityEnglish.pdf
④ 具体的流れ<br />
商品のグローバルな安定供給のためには、産業界と共同で効率的なシステムを確立させる必<br />
要があるが、その一方で価格を手の届く範囲に抑え、国際規格に沿った品質を保たなくてはなら<br />
ない。さらに緊急事態においては、臨機応変に素早く対応する必要がある。これを踏まえ、物資供<br />
給センターと世界各地の現地事務所スタッフは下記のような流れで商材調達・配布を行っている。<br />
この流れの中で、ユニセフのパートナーやサプライヤーが関わるのは、調達及び納入・決済であ<br />
る。<br />
図表 7 商材調達から配給までの手順<br />
内容 詳細<br />
1 必要物資の決定 ユニセフと現地政府によりプログラムを組織、どのような商品が必要であるかを決定<br />
2 予算策定・企画立案 数年前から前もって計画を立案、予算の獲得、支給がいつ必要であるか日程を決定<br />
3 調達 競争入札、最高の価値を持つ商品の獲得、健全な市場と品質の確保、注文書の発行<br />
4 納入・決済 サプライヤーからの集荷、輸送、輸入関税の決済<br />
5 検品 受け取った商品の数量、状態、品質チェック<br />
6 倉庫保管・流通 数回の国内貯蔵庫から受給者への商品の輸送<br />
7 受給者による利用 プログラムの遂行、子どもたちとその母親への商品の配給<br />
8 モニター・評価 商品の数量・適切なタイミングでの配給・目的にかなった商材であるかの評価<br />
9 供給インフラの改善 サプライチェーンの継続的な改良・改善<br />
出所:UNICEF Supply Annual Report 2008 22<br />
図表 8 サプライヤー登録・選定手順<br />
1 ユニセフが関心を持つような製品を販売し、その製品がユニセフ購買方針と適合し、<br />
輸出能力が確立されているかを確認する。<br />
2 企業略歴・カバーレター等をUNGMに登録・申請する。<br />
3 商品がユニセフの品質基準を満たしているかどうかユニセフ供給課により審査され、<br />
登録の可否が決定される。<br />
4 入札企業は、以下の情報をコペンハーゲン事務所にあるユニセフ品質保証・サプライ<br />
ヤー評価ユニットに送付する。<br />
A)前年の数字も含んだ、最新の監査済み財務諸表一式のコピー;会社の監査・会計法<br />
人の署名入り(財務諸表が英語で記述されていない場合は、英語翻訳も必要)<br />
B)商品の(売買する市場域・国での)品質システム検査済証明<br />
5 ユニセフによる企業・商品情報の評価と認定により、契約締結となる。<br />
出所:UNICEF 23<br />
物資輸出能力が十分ではない場合、サプライヤーはユニセフ購買サービスを利用することがで<br />
きる。こうしたサプライヤーはユニセフとの契約締結後、商品を納入する際に手数料を支払う。こ<br />
れはユニセフの利益になるわけではなく、ユニセフが購買活動を持続していく上で必須の費用で<br />
あり、それぞれの費用見積の中に含まれる。<br />
� 商品の 6~8%の費用、最低 300 ドル'ユニセフ倉庫にストックされるか否かで決定(<br />
� 商品の 10%の市場変動・外国為替変動に対応する費用'商品がユニセフ倉庫にストックさ<br />
れず直接現地に輸送される場合(、商品がエンドユーザーに行き渡った時点で余剰額があ<br />
れば返金<br />
22 http://www.unicef.org/supply/files/supply-annual-report-2008.pdf (Page 4-5)<br />
23 http://www.unicef.org/supply/index_become_a_supplier.html<br />
246
サプライヤーは、ユニセフと契約のある輸送サービス業者から輸送費と保険料を請求される。<br />
ユニセフ各国事務所は、ユニセフ購買サービスにより調達された商品の国内での引取り・保管・配<br />
給などの複合輸送サービスを現地業者に委託する。要求があれば、ユニセフは技術支援と輸送<br />
支援を別々のパッケージとして提供する。物資の輸送費と保険料は費用見積りに含まれ、ユニセ<br />
フの輸送サービス業者がプロジェクトの現場に最も近い通関まで物資を配送する 24 。<br />
⑤ 製品開発・サプライヤー選定例 25<br />
1(Hib ワクチン<br />
ワクチンと予防接種のための世界同盟'GAVI(が設立された 2000 年当時、五種混合ワクチン<br />
は 1 社のメーカーが独占供給しており、供給量も十分ではなかった。メーカーにとっては、製造シ<br />
ステムを確立に多額の投資が必要であり、更にWHOに推奨されるまでに最低 5 年間は必要であ<br />
った。そこで、ユニセフとGAVIは協力して正確な需要予測を行い、メーカーに対し頻繁に相談に<br />
応じることにより、メーカーの新規市場参入を促した。2006 年には2社目のメーカーがWHOによ<br />
る基準をクリアし、2008 年には新たに 2 社が加わった。ユニセフ供給課は、2010~2012 年の間に、<br />
尐なくとももう 1 社が加わると期待している。<br />
2(ピーナッツを原料とした調理済み治療食<br />
ピーナッツを原料とした調理済み治療食は、半数以上の子どもの死亡原因である飢餓を治療で<br />
きるにも関わらず、2007 年度末時点で国際的に認知されたサプライヤーは 1 社のみであり、ユニ<br />
セフは、世界的需要に対応しきれていなかった。そこで、ユニセフ供給課は競争入札を実施、新た<br />
なサプライヤーとして、南アフリカ、ケニア、インド、米国の企業、及びこれら企業とフランチャイズ<br />
契約のあるマラウイ、ニジェール共和国、エチオピア、ドミニカ共和国の企業を選定した。この 2 年<br />
間でユニセフの購買額は 450%増え、1 万 1,000 トンとなった。<br />
3(長期残効型防虫処理済蚊帳<br />
2007年度までは、WHOの基準をクリアする長期残効型防虫処理済蚊帳のメーカーは 2 社のみ<br />
24 http://www.sho.int/3by5/unicef_procurement/en/<br />
25 http://www.unicef.org/supply/files/supply-annual-report-2008.pdf (Page 8, 15, 18, 19)<br />
247
'住友化学とベスタゴー(であった。ユニセフ供給課はパートナーと共同で、市場予測、市場の再<br />
建、メーカーとの頻繁なインタビューを実施し、発送期間の短縮、新規メーカーの参入を促した。ユ<br />
ニセフは、世界保健機関殺虫剤評価スキーム'WHOPES(推奨の長期残効型防虫処理済蚊帳<br />
のサプライヤー数を、2008 年度に 5 社、2009 年度には 6 社にすることを目標としている。<br />
4(亜鉛錠剤<br />
ユニセフの基準を満たす亜鉛錠剤を生産するサプライヤーは、2006 年度において 1 社のみで<br />
あった。そこでWHOとの協力により、潜在的サプライヤーに対し商品の改良と市場参入を促した。<br />
2008 年度、ユニセフ供給課は 2 回目の競争入札で 1 社を選定し、2009 年下期には 3 度目の入札<br />
を予定している。<br />
'4(調達の実績 26<br />
① 概要<br />
2008 年度の物資調達実績は、2007 年度に比べ着実に増加した。ユニセフは、途上国から物資<br />
を調達することを誓約しており、2007 年度は上位 20 カ国中、途上国は 9 カ国であったが、2008 年<br />
度は 11 カ国へと増加した。<br />
図表 9 2008 年度調達実績概要<br />
項目 実績<br />
物資調達総額 14億6,000万ドル<br />
国際調達額 11億ドル以上<br />
国際輸送費 8,880万ドル<br />
国際発送数 11,000回<br />
ユニセフ倉庫から発送された物資総額 1億530万ドル<br />
輸送・発送先国数 106カ国<br />
輸送・発送総額 6億9,900万ドル<br />
他国連機関との共同調達割合 76%以上<br />
出所:UNICEF Supply Annual Report 2008 27 を基に作成<br />
26 http://www.unicef.org/supply/files/supply-annual-report-2008.pdf (page 10, 14, ANNEX 2 & 3)<br />
27 http://www.unicef.org/supply/files/supply-annual-report-2008.pdf (Page 10 etc.)<br />
248
② 品目別内訳<br />
ユニセフが 2008 年度にサプライヤーから調達した品目の一位'金額ベース(は、ワクチン・生物<br />
学的製剤で、金額は 6 億 3,300 万ドル相当であった。<br />
(100万)<br />
700 633<br />
600<br />
500<br />
400<br />
300<br />
200<br />
100<br />
0<br />
図表 10 2008 年ユニセフ物資調達額上位 10 品目'単位:100 万ドル(<br />
135<br />
100 92 89 86 72 59 49 47<br />
ワ<br />
イ<br />
剤 ク<br />
ド<br />
・ チ<br />
・<br />
血 ン<br />
抗<br />
液 ・<br />
毒<br />
製 ト<br />
素<br />
剤 キ<br />
製<br />
ソ<br />
そ<br />
の<br />
他<br />
医<br />
薬<br />
品<br />
蚊<br />
帳<br />
・<br />
家<br />
庭<br />
用<br />
機<br />
器<br />
医<br />
療<br />
用<br />
品<br />
・<br />
設<br />
備<br />
教<br />
育<br />
備<br />
品<br />
栄<br />
養<br />
素<br />
・<br />
栄<br />
養<br />
食<br />
品<br />
出所:UNICEF Supply Annual Report 2008 を基に作成<br />
③ 供給元国・地域別内訳<br />
2008 年度のユニセフへの物資供給額が 100 万ドル以上のサプライヤーのうち、首位はインド、<br />
次いで国連の倉庫があるスイス、ベルギー、フランス、ユニパックの倉庫があるデンマークなどが<br />
続いている。日本はデンマークに次いで6番目の供給国。<br />
( 100万ドル)<br />
295<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
209<br />
179<br />
249<br />
水<br />
・<br />
公<br />
衆<br />
衛<br />
生<br />
印<br />
刷<br />
機<br />
器<br />
図表 11 ユニセフサプライヤー上位 20 カ国対価<br />
148 136<br />
57<br />
出所:UNICEF Supply Annual Report 2008 28 を基に作成<br />
I<br />
T<br />
・<br />
事<br />
務<br />
用<br />
品<br />
輸<br />
送<br />
機<br />
器<br />
36 35 31 28 24 22 20 18 14 13 12 12 11 11<br />
28 http://www.unicef.org/supply/files/supply-annual-report-2008.pdf (Page 11, Annex 1)
ユニセフのサプライヤーは世界各地で事業活動を行っているが、サプライヤーとその商品の支<br />
給先が、国内ないし同じ地域内である場合、商品の輸送費を抑えることができ、さらに現地の雇<br />
用を創出するという好循環が生まれる。これはユニセフが近年掲げた目標であり、途上国の企業<br />
がサプライヤーであるケースが増加している実績からも、ユニセフがその目標を実行に移している<br />
ことが読み取れる。<br />
2008 年度における取引額上位であるサプライヤー'外国企業現地法人含む(は下表の通り。現<br />
地・地域サプライヤーとは同じ地域内に物資を供給している企業、国際サプライヤー'ほぼ先進国<br />
企業(とは物資を国際的に供給している企業を指す。国際サプライヤーは、現地・地域サプライヤ<br />
ーに比べユニセフとの取引額が非常に大きく、上位 19 位までがワクチン・生物学的錠剤やその他<br />
の医薬品など高度な技術および繊細な輸送手段を要するものとなっている。<br />
図表 12 現地・地域調達 ユニセフ上位サプライヤー購買額実績'取引額 200 万ドル以上(<br />
サプライヤー 国名 商品・サービス<br />
1 Techno Relief Services Ltd ケニア<br />
2 Mahar Kyaw Department Store ミャンマー<br />
250<br />
農業・蚊帳と家庭用機器・衣服・<br />
靴・教育備品<br />
蚊帳と家庭用機器・教育備品・衣<br />
服・靴・通信機器<br />
取引額<br />
(ドル)<br />
9,253,463<br />
5,011,603<br />
3 Insta Products (Epz) Ltd ケニア 栄養物 3,314,176<br />
4 Span Pumps Pvt Ltd インド 水と公衆衛生 2,598,700<br />
5 Indus Motor Company Ltd パキスタン 輸送機関 2,587,419<br />
6 Dynamic Eng. & Gen. Trading Co. Ltd ミャンマー<br />
教育備品・標識・避難所・現場機<br />
器・水と公衆衛生<br />
2,576,895<br />
7 Qingdao Koly Industrial Co. Ltd 中国 避難所・現場機器 2,529,879<br />
8 Shwe Naing Ngan Printing House ミャンマー 印刷 2,464,823<br />
9 Ajay Industrial Corporation インド 倉庫・水と公衆衛生 2,453,123<br />
10 Al-Sami General Trade Co. Ltd イラク 教育備品・水と公衆衛生 2,361,430<br />
11 Longman Botswana ジンバブエ 教育備品 2,189,797<br />
12 Myanmar Pipes & Accessories Co. Ltd ミャンマー<br />
蚊帳と家庭用機器・倉庫・医療備<br />
品・医療/栄養分セット<br />
2,148,521<br />
13 Zydus Pharmaceuticals (Bhasin Int Co. Ltd) ミャンマー 衣服・靴・教育備品・標識・倉庫 2,082,015<br />
14 English Press Ltd ケニア 教育備品・印刷・人材派遣 2,070,094<br />
15 International Master Trade Co. Ltd 中国<br />
出所:UNICEF Supply Annual Report 2008 29 を基に作成<br />
29 http://www.unicef.org/supply/files/supply-annual-report-2008.pdf (Annex 2)<br />
衣服・靴・医療備品・輸送機関・<br />
水と公衆衛生<br />
2,009,229
図表 13 国際調達 ユニセフ上位サプライヤー購買額実績'取引額 1,000 万ドル以上(<br />
サプライヤー 国名 商品・サービス<br />
取引額<br />
(ドル)<br />
1 Glaxo SmithKline Biologicals ベルギー ワクチン・トキソイド・抗毒素製剤・血液製剤 153,977,759<br />
2 Berna Biotech Ltd スイス ワクチン・トキソイド・抗毒素製剤・血液製剤 143,451,205<br />
3 Panacea Biotec Ltd インド ワクチン・トキソイド・抗毒素製剤・血液製剤 115,160,293<br />
4 Sanofi Pasteur フランス ワクチン・トキソイド・抗毒素製剤・血液製剤 77,938,004<br />
5 Nutriset SAS フランス 栄養物・その他医薬品 56,725,626<br />
6 Serum Institute of India Ltd インド ワクチン・トキソイド・抗毒素製剤・血液製剤 45,752,298<br />
7 Vestergaard Frandsen Group SA スイス 家庭用品 43,403,303<br />
8 Kuehne & Nagel デンマーク 貨物輸送 38,351,211<br />
9 住友化学 日本 家庭用品 35,692,180<br />
10 Shantha Biotechnics Ltd インド ワクチン・トキソイド・抗毒素製剤・血液製剤 34,219,701<br />
11 Novartis Vaccines and Diagnostics イタリア ワクチン・トキソイド・抗毒素製剤・血液製剤 27,528,195<br />
12 DHL Global Forwarding デンマーク 貨物輸送 26,006,870<br />
13 Scan Global Logistics デンマーク 貨物輸送 24,400,640<br />
14 Hetero Drugs Ltd インド その他医薬品 23,569,302<br />
15 Becton Dickinson International ベルギー 研究用備品・再生可能医療備品 18,418,244<br />
16 Novartis Pharma AG スイス その他医薬品 16,918,767<br />
17 Ranbaxy Laboratories Ltd インド その他医薬品・倉庫 13,876,304<br />
18 Atea A/S デンマーク 通信機器・ITと事務用品 12,408,321<br />
19 Aurobindo Pharma Ltd インド その他医薬品 10,998,461<br />
出所:UNICEF Supply Annual Report 2008 を基に作成<br />
水関連資材では、インド、ミャンマーのサプライヤーの名前が上位に挙がっており、現地調達あ<br />
るいは地域調達の割合が多いことが窺える。なお、ベスタゴーのライフストローはユニセフでは家<br />
庭用機器となっておりこのカテゴリーには含まれていない。<br />
④ 支給先国・地域別内訳<br />
図表 14 水・公衆衛生商材調達先メーカーと国名'100 万ドル以上(<br />
企業名 国名<br />
251<br />
支援物資輸送額<br />
(ドル)<br />
1 Span Pumps Private Limited インド 2,598,699<br />
2 Ajay Industrial Corporation インド 2,441,869<br />
3 Myanmar Megasteel Industries Ltd. ミャンマー 1,788,320<br />
4 Medentech Ltd アイルランド 1,760,944<br />
5 Dynamic Engineering & Gen. Trading Co., Ltd ミャンマー 1,613,535<br />
6 International Master Trade Co., Ltd 中国 1,588,363<br />
7 Grundfos Dk A/S デンマーク 1,311,105<br />
8 Diesel Generator Co., Ltd. スーダン 1,309,989<br />
9 Evenproducts limited 英国 1,205,004<br />
10 Atlas Copco Kompressorteknik A/S デンマーク 1,165,296<br />
11 Azoom Plastic Factory スーダン 1,095,786<br />
12 Myanmar Pipes & Accessories Co., Ltd. ミャンマー 1,051,794<br />
13 Techno Relief Services Ltd. ケニア 1,029,231<br />
出所:2008 Annual Statistical Report 30 を基に作成<br />
ユニセフの物資支給先は、サブサハラ・アフリカとアジアで全体の 87%を占める。最大の物資<br />
受入国はインドとエチオピアである。<br />
30 http://www.ungm.org/Publications/Documents/ASR_2008.pdf (Page 144-161)
図表 15 2008 年度ユニセフ物資輸送先地域割合<br />
地域 %(金額ベース)<br />
サハラ以南のアフリカ 56<br />
アジア 31<br />
中東、北アフリカ 8<br />
中央・南アメリカ、カリブ海諸国 3<br />
中央・東ヨーロッパ 2<br />
出所:UNICEF Supply Annual Report 2008 31 を基に作成<br />
図表 16 ユニセフ支援国・物資輸送額上位'2,500 万ドル以上(<br />
(100万ドル)<br />
160<br />
140<br />
120<br />
100<br />
140<br />
⑤ 日本企業からの調達状況<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
114<br />
82<br />
65 65 63<br />
54 52<br />
46<br />
252<br />
42 42<br />
出所:UNICEF Supply Annual Report 2008 32 を基に作成<br />
34<br />
30 29 28 28 27 27 27<br />
ユニセフサプライヤーとしては、日本企業の入札数は主要先進国と比べて尐ないが、取引額は<br />
比較的大きい。国内最大のサプライヤーは、住友化学株式会社のオリセット蚊帳であり、購買額<br />
は 3,569 万ドルと、第 2 位のトヨタ自動車の 4 倍以上となっている。<br />
図表 17 入札に招待され、それに応じた主要国企業数'国際調達(<br />
350<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
314<br />
197<br />
297<br />
159<br />
227<br />
193<br />
132 133<br />
177<br />
156<br />
110 104<br />
出所:UNICEF Supply Annual Report 2008 33 を基に作成<br />
31 http://www.unicef.org/supply/files/supply-annual-report-2008.pdf (Page 10)<br />
32 http://www.unicef.org/supply/files/supply-annual-report-2008.pdf (Annex 3)<br />
入札招待企業数 入札参加企業数<br />
125<br />
51<br />
112<br />
60<br />
21<br />
13<br />
13<br />
5
⑥ 日本企業の製品の事例<br />
図表 18 日本のサプライヤー'日本法人含む(と品目'3 万ドル以上(<br />
1(住友化学 ―オリセット蚊帳<br />
サプライヤー 品目 調達額(ドル)<br />
住友化学 家庭用備品 35,692,180<br />
トヨタ自動車 輸送機関 8,483,589<br />
ジェー・ガーバー商会 輸送機関 5,847,298<br />
日本ビーシージーサプライ ワクチン・生物学的製剤 3,503,712<br />
日産トレーディング 通信設備・機器、輸送機関 3,256,337<br />
富士レビオ 医療診断検査キット 165,644<br />
アラノ貿易 医療機器 94,630<br />
TOA 通信設備 82,814<br />
豊田通商 輸送機関 54,600<br />
オリンパス 研究所・製造所備品 40,824<br />
出所:2008 Annual Statistical Report on Procurement 34 を基に作成<br />
2003 年 9 月 24 日、ユニセフと住友化学は、マラリア撲滅のため日本政府・民間企業・国連と共<br />
に、防虫剤の効果が長く持続する蚊帳'製品名:オリセット蚊帳(の独自技術をアフリカのメーカー<br />
に提供するというパートナーシップを締結した。従来の蚊帳は半年に一度、防虫剤を浸透させる<br />
必要があるが、オリセット蚊帳は尐なくとも 5 年以上 35 、最近の調査によれば 7~8 年その効用が<br />
続くとされている。 36<br />
オリセット蚊帳は、2001 年にWHOPESより最初に長期残効型蚊帳としての推奨を受けた商品<br />
である。住友化学は 2003 年、WHOの要請に応じタンザニアのアルーシャにある現地蚊帳メーカ<br />
ー AtoZ Textile Mills Ltd に対し、無償で設備と製造管理技術を供与し、長期残効型防虫処理済<br />
蚊帳の量産にアフリカで初めて着手、数千人の雇用を創出した。その後 2005 年までに、中国 2 ヵ<br />
所とベトナムにも生産拠点を設立し、生産能力を増強している。また、貧困削減を目指す米国の<br />
団体ミレニアム・プロミス 37 に、33 万 6,000 張を寄付している。<br />
33 http://www.unicef.org/supply/files/supply-annual-report-2008.pdf (Annex 4)<br />
34 http://www.ungm.org/Publications/Documents/ASR_2008.pdf (Page 152)<br />
35 http://www.accessmylibrary.com/coms2/summary_0286-24737644_itM<br />
36 http://www.olyset-net.jp/olysetnet/story/story.html<br />
37 http://www.millenniumpromise.org<br />
253
図表 19 タンザニア・アルーシャ工場のオリセット蚊帳生産能力の推移<br />
出所:住友化学 38<br />
オリセット蚊帳を含む長期残効型防虫処理済蚊帳の標準サイズ'高さ 150cm×長さ 190cm×幅<br />
180cm(の価格は、2005 年度は 4.7~5.1 ドル、2007 年度は 4.5~5.3 ドルであったが、今後需要が<br />
拡大しメーカーの参入が続けば、競争により価格上昇を抑えられるとユニセフは予測している 39 。<br />
ユニセフが取り扱っている蚊帳で、2009 年 8 月時点でUNIPACに在庫がある、もしくはユニセフ供<br />
給カタログにリストアップされている長期残効型防虫処理済蚊帳、およびWHOPESによる仮推奨<br />
を受けているのは6社8製品である。<br />
る。<br />
図表 20 WHOPESによる推奨・仮推奨を受けている長期残効型蚊帳<br />
'2009 年 8 月時点(<br />
サプライヤー(所在国) 商品名 素材 防虫剤 処理方式 状況<br />
住友化学(日本) Olyset ポリエチレン ペルメトリン 繊維練込 2001推奨<br />
Vestergaard Frandsen S.A.<br />
(スイス)<br />
BASF South Africa PTY Ltd.<br />
(ドイツ)<br />
Intelligent Insect Control<br />
(フランス)<br />
Clarke Mosquito Control<br />
(米国)<br />
PermaNet2.0 ポリエステル デルタメトリン コーティング 2003推奨<br />
PermaNet2.5 ポリエステル デルタメトリン コーティング<br />
PermaNet3.0<br />
ポリエステル<br />
(側面)<br />
ポリエチレン<br />
(天井)<br />
254<br />
デルタメトリン<br />
(側面)<br />
デルタメトリン/PBO<br />
(天井)<br />
コーティング<br />
(側面素材)<br />
繊維練込<br />
(天井素材)<br />
Interceptor ポリエステル アルファシペルメトリン コーティング<br />
Netprotect ポリエチレン デルタメトリン 繊維練込<br />
DuraNet ポリエチレン アルファシペルメトリン 繊維練込<br />
Tana Netting Co., Ltd.<br />
(タイ)<br />
Bayer Environmental Science<br />
と協業<br />
DawaPlus2.0 ポリエステル デルタメトリン コーティング<br />
出所:WHOPES Working Group Meetings40 を基に作成<br />
仮推奨<br />
(フェーズⅢ裁<br />
定中)<br />
蚊帳が最終的に推奨されるまでには、WHOPESの以下に示す検証試験段階を経る必要があ<br />
38 http://www.olyset-net.jp/olysetnet/qa/qa2.html<br />
39 http://www.rollbackmalaria.org/partnership/wg/wg_itn/docs/rbmwin4ppt/2-13.pdf<br />
40 http://www.who.int/whopes/Long_lasting_insecticidal_nets_Aug09.pdf
フェーズⅠ:研究室実験'防虫剤効果、人体および環境への影響の関する検証など(<br />
フェーズⅡ:数カ国での現地試験'蚊以外への地域特有の動物生体への影響検証など(<br />
フェーズⅢ:大規模現地評価'防虫剤効果、未洗濯時の検証、住民の受容検証など(<br />
フェーズⅣ:明細事項'仕様書など(の設定<br />
現在、推奨を受けている住友化学のオリセット蚊帳とベスタゴーの PermaNet2.0 の違いは、素<br />
材からくる価格の差異であり、オリセット蚊帳が 2 年早く推奨を得たにも関わらず、ベスタゴーのシ<br />
ェアは 55%、住友化学はシェア 35%で第 2 位となっている。しかし、ベスタゴーが主に使用するポ<br />
リエステルは、住友化学が使用するポリエチレンに比べ破れ・ほつれが生じやすく、繊維へのコー<br />
ティングのみのため耐用年数も短い。住友化学では、現在ベスタゴーとは価格面で差があるが、<br />
価格を下げるために品質を犠牲にするようなことをしなければ、今後、丈夫さおよび耐用年数によ<br />
り需要が増加すると期待している 41 。<br />
ユニセフは過去数年間、この分野への新規参入を促した結果、現在 6 製品がフェーズⅢの裁定<br />
中である。また、フェーズⅡ以下で裁定中であるスイス企業 Syngenta の蚊帳 ICON Maxx-Net はラ<br />
ムダサイハロスリンを防虫剤としてコーティングしたものを採用している 42 。さらに中国企業も蚊帳<br />
市場に積極的に参入してきており、Tianjin Yorkool によるデルタメトリンをポリエステルにコーティ<br />
ングした蚊帳 Yorkool'仮称(がフェーズⅠを獲得している 43 。<br />
2(日本ビーシージーサプライ―BCG'結核(ワクチン<br />
日本ビーシージーサプライは、親会社の日本ビーシージー製造株式会社'2007 年 11 月時点、<br />
日本で唯一BCGワクチンを製造(の供給を行っている 44 。「ワクチンの製造や研究を通じて得た優<br />
れた知識、技術を生かし、高品質な製品を安定供給し、独創的な製品を開発することを通じて、世<br />
界の人々に貢献する」ことを基本方針としており、ユニセフと米州保健機構'PAHO(を主要な取<br />
引先としている 45 。乾燥BCGワクチンのユニセフのサプライヤーであるほか、精製ツベルクリンの<br />
供給、結核菌検査用培地などの関連商品も取引きしている 46 。<br />
41 2010.1 9 週刊東洋経済より<br />
42 http://whqlibdoc.who.int/hq/2009/who_HTM_NTD_whoPES_2009_1_eng.pdf (Page 90-112)<br />
43 http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241598712_eng.pdf (Page 55-66)<br />
44 http://www.yokogawa.co.jp/ns/customer/bcg/ns-bcg01-ja.htm<br />
45 http://www.bcg.gr.jp/bcg/profile/index.html<br />
46 http://www.bcg-qft.com/09.html<br />
255
'1(活動概要<br />
2.国連食糧農業機関<br />
'FAO:Food and Agriculture Organization(<br />
国連食糧農業機関'FAO(は、世界の飢餓撲滅に向け 1945 年に設立された国際機関であり、<br />
途上国や、農林漁業の近代化を通じ、国民への栄養供給に取り組む国々を支援している。特に、<br />
貧困と飢餓に苦しむ人々の 70%が農村地域に居住していることから、FAOは設立以来、農村地域<br />
の開発に注力している 1 。FAOは、グローバル必達目標として下記の 3 つを挙げている。<br />
� 全ての人がいつでも、栄養豊富で安全かつ十分な量の食糧を手にすることができるように<br />
し、2015 年までに、慢性的な栄養不足状態である人々の数を半分に減らす。<br />
� 持続可能な農業と漁業および林業を含めた農村地域の開発により、経済・社会の進展と<br />
人々の健康に継続して貢献する。<br />
� 土地・水・森林・漁場を含む天然資源と食糧・農業に関係する一般資源を、保全維持、改<br />
善し持続可能な利用を行う。<br />
'2(拠点と役割分担<br />
FAOは、192 の国と欧州共同体で構成されており、本部はローマ、130 カ国以上に現地オフィス<br />
を構えている。具体的には、5 つの地域オフィス、10 ヵ所のサブ地域オフィス、総合専門チーム、73<br />
の各国事務所、技術スタッフあるいはFAO代表出向先の 9 つのオフィスがあり、また先進国に 5<br />
つのリエゾンオフィスと 4 つの情報オフィスが設置されている 2 。<br />
図表 1 FAOオフィスのある都市・国名'各国事務所は除く(<br />
地域オフィス サブ地域オフィス 総合専門チーム リエゾンオフィス<br />
アクラ(ガーナ) アピア(サモア) サンティアゴ(チリ) ワシントン(米国)<br />
バンコク(タイ) リブリビレ(ガボン) 東京(日本)<br />
ブタペスト(ハンガリー) パナマシティー(パナマ) ブリュッセル(ベルギー)<br />
サンティアゴ(チリ) アンカラ(トルコ) ニューヨーク(米国)<br />
カイロ(エジプト) ブタペスト(ハンガリー) ベルン(スイス)<br />
出所:FAO 3<br />
アジスアベバ(エチオペア)<br />
チュニス(チュニジア)<br />
ハラレ(ジンバブエ)<br />
アクラ(ガーナ)<br />
ブリッジタウン(バルバドス)<br />
2009 年 4 月 1 日時点で、農業・林業・漁業・家畜の専門家、栄養士、社会学者、経済学者、統計<br />
学者など 1,641 人の専門家と、1,894 人のサポートスタッフで組織されており、その約 66%がローマ<br />
1 http://www.fao.org/about/en/<br />
2 ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/012/i1023e/i1023e00.pdf<br />
3 http://coin.fao.org/cms/do/en/index.html<br />
256
本部に勤務している。<br />
'3(調達の仕組み<br />
① 調達窓口連絡先<br />
2009 年 12 月から 2010 年 1 月にかけてアプローチを行ったFAO購買サービスの担当者は下記<br />
の通り。<br />
② 基本方針<br />
ホームページ<br />
登録先<br />
連絡先部署<br />
図表 2 FAO調達窓口連絡先<br />
(FAO購買サービス)<br />
http://www.fao.org/unfao/procurement/en/index.html<br />
(国連世界市場データベース)http://www.ungm.org/Index.aspx<br />
AFSP PROCUREMENT SERVICE<br />
氏名 Ms Sabine Adotévi Mr Andrea Banzi<br />
役職 Chief, Procurement Service Vendor Registration<br />
電話番号 +39 06 5705 6588 +39 06 5705 4817<br />
ファクス +39 06 5705 4959 +39 06 5705 4959<br />
Eメール AFSP-Procurement-Service@fao.org AFSP-Vendors-list@fao.org<br />
FAOは限られた場合を除き一般・公開入札を行わないが、商品購買における競争性と透明性<br />
の確保に尽力している。FAOはサプライヤーをUNCCSコードで管理しており、5,000 ドル以上の<br />
調達額が見込まれる場合、FAOがUNCCSコードより発注候補企業を選定し、入札案内を送付<br />
する。<br />
FAOが契約するサービスとしては、天然資源管理、動物の健康管理、有害廃棄物の除去、農<br />
業の発達に関連するインフラの建設など技術分野のものが多い。また清掃、建築物総合維持管<br />
理、配膳、保険、システム・ソフトウェア開発、システムプログラミング、電気通信、トレーニングな<br />
ども含まれる。<br />
FAOが調達する物資としては、農業機械・車両・産業機器・通信機器・建物・灌漑システム・建<br />
設機械・事務用品・補給品など、機器・設備が多い。また緊急時にいつでも対処できるよう、大量<br />
の植物の種子・用具・肥料・防虫剤・農業に必要な備品の調達も行っている。この他FAOの販売<br />
局が販売する免税物品あるいは総務局のサービスの購買も行われている 4 。<br />
4 http://www.fao.org/unfao/procurement/en/46919/index.html<br />
257
③ 調達条件 5<br />
商品購入の場合、2 万 5,000 ドル以上のものは、封印入札方式が採用される。入札はFAOの事<br />
務所に送付され、入札公開パネル'Tender Opening Panel(により開封される。特別の場合を除き、<br />
商品規格を満たす最安値の入札者に決定する。ただし緊急時で配送期間が選考基準の最優先<br />
事項となる場合は、その旨が入札要綱に記述される。<br />
サービス契約の場合、技術仕様方式と価格入札方式という 2 つの方法がある。技術仕様方式<br />
の場合、入札者が技術企画書と予算案の双方を提出し、予算内で最も評価の高い技術企画案に<br />
決定する。評価が一番高い企業が予算を上回る場合は、二番目に高い評価を得た企業との契約<br />
についても検討する。価格入札方式の場合は、FAOの技術仕様水準に基づき企業が入札し、最<br />
安値を掲げた企業と契約を締結する。<br />
④ 具体的な流れ<br />
FAOは独自のサプライヤーデータベースを管理していたが、2010 年 2 月 2 日よりこのデータベ<br />
ースをUNGMに移行した。FAOサプライヤー候補企業はまずUNGMで登録申請を行い、登録が<br />
認められた時点から、登録商品・サービスがFAOの需要に一致すれば競争入札に招待される。<br />
図表 3 FAOサプライヤー登録手順<br />
1 UNGMのウェブサイト'www.UNGM.com(で“SIGN UP FREE”ボタンをクリックする。<br />
2 “Register as Supplier”ページで、企業情報(輸出活動実績など)、社内担当者の<br />
メールアドレスなどを入力し保存する。<br />
3 入力したメールアドレスに送られてくる、アクティベーションリンクよりUNGMアカ<br />
ウントを有効にする。<br />
4 再度メールアドレスに、UNGMにアクセスするためのログイン情報が送られてくる。<br />
5 UNGMのウェブサイトに戻り、4のログイン情報を用いてUNGMアカウントに入<br />
る。UNGM登録番号がページの下部にあれば申請登録を開始したことになる。“Edit<br />
/ Complete your application form1”をクリックし、14ステップある詳細な企業情報<br />
を入力する。<br />
登録情報を十分見直したうえで、申請ボタン“Submit”をクリックする。この時点で、<br />
6<br />
公式にFAOとUNGMにサプライヤー情報を申請できたことになる。<br />
注)<br />
・登録申請機関としてFAOを選択すること。<br />
・1ステップ毎に入力情報を保存“SAVE”すること。<br />
出所:FAO Procurement Services6 登録申請後、FAO本部にある購買サービスにて企業と商品またはサービスの評価が行われ、<br />
FAOの調達条件を満たしていればサプライヤーとして登録される。<br />
ほとんどの物資調達活動はFAOローマ本部にて行われている。FAO購買サービス'AFSP(は<br />
特定の場合を除き、民間企業からの調達に対し全責任を負う。ただし、現地注文あるいは国際的<br />
5 http://www.fao.org/unfao/procurement/en/4/index.html<br />
6 http://www.fao.org/unfao/procurement/en/1/index.html<br />
258
に発行する現地発注'FPOs(の場合は、現地オフィスにも物資を調達する代理権がある。現地オ<br />
フィスは代理権の範囲内でサービス契約を結ぶことができ、その限度額はFAO代表オフィス・プロ<br />
ジェクトで 2 万 5,000 ドル、サブ地域オフィスで 5 万ドル、地域オフィスで 10 万ドルである。<br />
'4(調達の実績<br />
① 概要 7<br />
2008/2009 年の予算は 2 年間で 9 億 2,980 万ドルである。2008 年度には、FAO支援のプロジェ<br />
クトに企業・政府からの寄付金 5 億 4,860 万ドルが使われ、現地プログラムの 61.8%の費用がナ<br />
ショナルトラスト基金から賄われた。<br />
② 品目別内訳<br />
FAOの 2008 年度の物資調達総額は、1 億 857 万ドル'物資 7,273 万ドル、サービス 3,583 万ド<br />
ル(で、その 45.86%は発展途上国のサプライヤーからの調達である。<br />
図表 4 2008 年度物資・サービス調達実績'総額 1 億 857 万ドル(の品目別割合<br />
③ 供給元の国・地域別内訳<br />
特殊取扱機械<br />
5.2%<br />
医療電気器具、精<br />
密・光学機器<br />
5.2%<br />
情報技術<br />
5.6%<br />
建築・工学・その<br />
他技術サービス<br />
8.4%<br />
修理保全サービス<br />
9.3%<br />
加工済金属<br />
製品、機械装置で<br />
ないもの<br />
5.0%<br />
輸送機器<br />
12.2%<br />
259<br />
農産物<br />
19.7%<br />
輸送・貯蔵と<br />
その工程管理<br />
12.5%<br />
農化学薬品<br />
17.0%<br />
出所:2008 Annual Statistical Report 8 を基に作成<br />
FAOが 2008 年度に調達した 7,273 万ドル相当の物資の供給元は、先進国 22 カ国で 41%、発<br />
展途上国と移行経済諸国が 59%を占める。<br />
7 ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/i0765e/i0765e15.pdf<br />
8 http://www.ungm.org/Publications/Documents/ASR_2008.pdf (Page 99)
図表 5 FAO物資調達先'総額 7,273 万ドル(の地域別比率と先進国調達率内訳<br />
ヨーロッパ・<br />
CIS諸国<br />
4.3%<br />
ラテンアメリ<br />
カ・カリブ海諸<br />
国<br />
4.6%<br />
アジア諸国<br />
17.2%<br />
アフリカ諸国<br />
16.3%<br />
アラブ諸国<br />
16.4%<br />
先進国<br />
41.3%<br />
出所:2008 Annual Statistical Report 9 を基に作成<br />
④ 日本企業からの調達状況<br />
日本<br />
5.2%<br />
260<br />
ドイツ<br />
2.8%<br />
米国<br />
3.5%<br />
ベルギー<br />
2.7%<br />
オーストリア<br />
6.7%<br />
スウェーデン<br />
2.6%<br />
オランダ<br />
9.1%<br />
その他<br />
7.3%<br />
デンマーク<br />
9.2%<br />
イタリア<br />
23.1%<br />
フランス<br />
13.1%<br />
2001 年以降のFAOの調達総額は 1 億ドル前後で推移しており、日本企業からの調達額は<br />
2005 年度を除けば 1%程度であり大きな変化はない。2005 年度は、ジェー・ガーバー商会が一部<br />
出資するプロジェクトで 88 万 5,000 ドルで 360 台のバイクを調達、インド洋でのプロジェクトのため<br />
58 万 8,400 ドルで桃井製網株式会社の魚網・漁具を調達されたことが大きく影響している。<br />
図表 6 FAOの調達に占める日本企業の実績推移'単位:1,000 ドル(<br />
英国<br />
14.8%<br />
日本 FAO全体<br />
日本企業<br />
からの調<br />
商品 サービス 合計 商品 サービス 合計 達割合<br />
2008 1,547.88 0 1,547.88 72,730.77 35,834.67 108,565.44 1.43%<br />
2007 654.26 0 654.26 54,041.01 30,802.24 84,843.25 0.77%<br />
2006 712.93 8.55 721.48 58,363.35 41,116.99 99,480.34 0.73%<br />
2005 4,617.12 0 4,617.12 65,443.98 45,804.24 111,248.22 4.15%<br />
2004 427.3 67.26 494.56 60,241.38 35,273.81 95,515.19 0.52%<br />
2003 1,377.24 0 1,377.24 278,061.49 98,436.67 376,498.16 0.37%<br />
2002 1,304.04 0 1,304.04 83,713.67 18,268.41 101,982.08 1.28%<br />
2001 1,160.17 0 1,160.17 126,200.21 26,827.45 153,027.66 0.76%<br />
出所:2001~2008 Annual Statistical Report 10 , 11 を基に作成<br />
⑤ 日本企業の製品の事例<br />
FAOの 2008 年度調達物資で、3万ドル以上の日本からの調達実績は下表の通り。<br />
9 http://www.ungm.org/Publications/Documents/ASR_2008.pdf (Page 68-70)<br />
10 http://www.ungm.org/Publications/Documents/ASR_2008.pdf (Page 68-70,86-88)<br />
11 http://www.ungm.org/Publications/Documents/ASR_2007.pdf (Page 22-24,40-42)
図表 7 日本企業'日本法人含む(からの調達実績と品目'3 万ドル以上(<br />
サプライヤー 品目 調達額(ドル)<br />
アラノ貿易 車両(プロジェクト用) 42,865.00<br />
バイク(配送先:チャド) 392,130.00<br />
ジェー・ガーバー商会 ヤマハバイク × 18台 37,260.00<br />
バイク(DRC) 172,050.00<br />
日産トレーディング 日産ステーションワゴン 33,050.00<br />
トヨタランドクルーザー × 3回分発注書 136,371.60<br />
トヨタ自動車<br />
トヨタランドクルーザーステーションワゴン 49,386.79<br />
その他車両 418,520.68<br />
出所:2008 Annual Statistical Report12 を基に作成<br />
12 http://www.ungm.org/Publications/Documents/ASR_2008.pdf (Page 107)<br />
261
'1(活動概要 1<br />
3.国連世界食糧計画'WFP:World Food Programme(<br />
国連世界食糧計画'WFP(は、世界の飢餓を撲滅するために活動している任意拠出による世<br />
界最大の人道主義的国連組織である。緊急時には食糧を必要なところに配布し、戦争・内紛・自<br />
然災害の犠牲者の命を救うとともに、緊急時の収拾後も食糧の配布を通し精神的に傷を負った<br />
人々や地域社会の再生を支援する役割を担っている。<br />
1962 年の設立以来、万人が活動的で健康な生活を送るために必要な食糧に常時手が届くよ<br />
うにするという目標を掲げ、ローマに本部を置く国連食糧農業機関'FAO(、国際農業開発基金<br />
'IFAD:International Fund for Agricultural Development(、その他国連機関、各国政府、NGOパ<br />
ートナーとともにこの目標達成に向けた活動を行っている。WFPが掲げる 2008~2011 年度の戦<br />
略的長期計画は以下の 5 つである 2 。<br />
� 緊急時に人々を助け、その命を守る<br />
� 深刻な飢饉の発生を防ぎ、緊急時への準備・収拾対策に投資する<br />
� 紛争・災害などの緊急時の後に人々の活力を取り戻し、再生への道を示す<br />
� 慢性的な飢饉・栄養失調を世界中で減尐する<br />
� 知識・経験の転移、現地調達などにより国家の能力を強化し、飢饉を減らす<br />
WFPは、2008 年度時点で 1 万 200 人のスタッフが活動に従事、そのうち 91%が世界各地の<br />
現地事務所に配置されている 3 。<br />
'2(拠点と役割分担<br />
WFP各国事務所は、輸送されてくる物資の損失や損傷があった場合、その事実を法的海事<br />
サービス'LEGM:Legal Maritime Service(に直ちに報告する義務がある。またLEGMは、あらゆ<br />
る面から損失を未然に防ぎ、損失を減らすためのアドバイスを各国事務所に行っている。<br />
各国事務所には栄養士が配属されており必要に応じて配給する物資の栄養相談を行う。事務<br />
所に栄養士がいない場合、地域事務所またはローマ本部が対応する。食品技術に関しても、W<br />
1 http://www.wfp.org/about<br />
2 http://www.wfp.org/about/strategic-plan<br />
3 http://www.wfp.org/wfp-numbers<br />
262
FP各国事務所が相談を受け、食品技術者が配置されていない場合、地域事務所の配送責任<br />
者・購買責任者あるいはローマ本部の栄養サービス・購買サービスが対応する 4 。<br />
'3(調達の仕組み<br />
① 調達窓口連絡先<br />
WFP購買サービスの連絡先は下表の通り。連絡優先順位 2 位の個人名は 2009 年 12 月時点<br />
で今回調査のため連絡の取れたスタッフであり、国連スタッフが数年契約で入れ替わることを鑑<br />
み第 2 位連絡先としている。<br />
② 基本方針<br />
ホームページ<br />
登録先<br />
図表 1 WFP調達窓口連絡先<br />
連絡優先順位 1 2(個人)<br />
連絡先名 WFP Food Procurement Service Ms Deborah Ambrosini<br />
住所/役職<br />
Via C.G.Viola 68/70<br />
Parco dei Medici 00148 Rome, Italy<br />
263<br />
United Nations World Food Programme,<br />
Procurement Division<br />
電話番号 +39 06 65131 +39 06 6513 2993 (Direct)<br />
ファクス<br />
(WFP購買サービス)http://www.wfp.org/procurement<br />
(国連世界市場データベース)http://www.ungm.org/Index.aspx<br />
+39 06 6513 2339<br />
+39 06 659 0632<br />
Eメール food.procurement@wfp.org Deborah.Ambrosini@wfp.org<br />
WFPは、WFP公式基準、各国基準、国際食品規格委員会'Codex Alimentarius Committee(<br />
など必須基準を満たした食糧を供給している。サプライヤーの供給する物資は以下の条件をす<br />
べて満たしていなければならない。<br />
� 品質・外見・配送条件<br />
� 生産・包装・貯蔵・輸送を行う場所<br />
� 大きさ・重量・色・栄養分<br />
� 検査過程の詳細<br />
� 特定の包装・ラベルに関する要件<br />
WFPの調達する物資は細かく分類されており、それぞれに詳細な定義・調達基準がある。具<br />
4 http://foodquality.wfp.org/ServicesAvailable/tabid/120/Default.aspx<br />
-
体的なWFPの食品基準はウェブ 5 で参照できる。<br />
図表 2 WFP調達品目一覧<br />
部類 詳細<br />
穀物 コーン・米・小麦・モロコシ<br />
豆類 豆・平豆・エンドウ豆<br />
小麦粉 コーンミール・小麦粉・全粉小麦粉<br />
混合食品(補強食品) 米・モロコシ・小麦とコーンの混合食品など<br />
ビスケット(強化食品)<br />
油(補強油) パーム油・菜種油・大豆油・ひまわり油・ココナツ油<br />
麺類(補強食品) 乾燥麺・即席麺<br />
魚・肉 魚類・牛肉・鶏肉<br />
種々の食品 牛乳・塩・砂糖・紅茶・ナツメヤシ<br />
食品規格 魚の缶詰・乳幼児食も含めた食品規格照合<br />
治療食 ミルク・ビスケット・ピーナツペーストなどを基にした食品<br />
ハラル食品 イスラム教に準じた食品<br />
出所:WFP Food Quality Control 6 を基に作成<br />
WFPのサプライヤーは、食品安全プログラムHACCP'Hazard Analysis and Critical Control<br />
Point(に準拠していなければならない。これに加えて、品質基準ISO9000、環境基準ISO14000、<br />
食品流通体系基準ISO22000:2005、製造管理および品質管理基準GMP'Good Manufacturing<br />
Practice(の認証を取得している必要がある 7 。<br />
③ 具体的な流れ<br />
WFPとそのパートナーは食糧の調達・貯蔵・輸送・加工・配給というあらゆる角度から、食糧の<br />
品質・安全性を確保する必要がある。更に、様々な栄養素を含み、多様な健康状態の人々に受<br />
給できるものでなくてはならない 8 。<br />
サプライヤー選定に際しては、建物・設備・人材の質・衛生管理などが一定の基準を満たして<br />
いなければならない。サプライヤーの能力評価には以下 5 つのステップを踏む。<br />
図表 3 WFPサプライヤー選定手順<br />
1 WFPのサプライヤー候補企業にアンケートを送付<br />
2 資格を持つ検査官(ISO22000によりサプライヤーを監査する検査官あるいは<br />
GMP/HACCP公認監査役)にアンケートを提出、検査官がサプライヤー<br />
を監査し、アンケートの記述と現実が合致しているかを調査<br />
3 企業の事業形態・生産体制・財政状態を評価<br />
4 製品価格の比較<br />
5 サプライヤーの過去の業績をチェック(あるいは、その市場におけるサプライ<br />
ヤーおよび商品の信頼性に関する情報を監査役から収集)<br />
出所:WFP Food Quality Control9 5 http://foodquality.wfp.org/FoodSpecifications/tabid/56/Default.aspx<br />
6 http://foodquality.wfp.org/FoodSpecifications/tabid/56/Default.aspx<br />
7 http://foodquality.wfp.org/FoodSafetyandHygiene/FoodQualitySystems/tabid/290/Default.aspx<br />
8 http://foodquality.wfp.org/Home/tabid/36/Default.aspx<br />
9 ahttp://foodquality.wfp.org/QualityProcedures/Commoditypurchase/SuppliersManufacturers/tabid/484/Default.aspx<br />
264
'4(調達の実績 10<br />
① 概要<br />
2008 年は、78 カ国、1 億 210 万人に食糧供給を実施し、総支出額は 37 億 2,000 万ドル、その<br />
うち約 88%が食糧の費用と輸送費であった。2009 年は、推定で 74 カ国 1 億 800 万人に食糧援<br />
助を実施した。<br />
② 品目別内訳 13<br />
図表 4 2008 年度WFP実績概要 11<br />
支援状況 人数(万人) 数量/金額・割合<br />
緊急時・救援活動 6,230 任意拠出寄付(食糧) 110.0万トン<br />
開発プロジェクト 1,760 現金調達(食糧) 282.5万トン<br />
子ども 6,220 食糧調達額 14億ドル<br />
国内避難民 950 発展途上国73カ国からの購買額 11億ドル<br />
難民 190 発展途上国からの購買額割合 75.6%<br />
エイズ患者 240<br />
出所:World Food Programme 12<br />
2008 年度物資調達額 37 億 2,000 万ドルの内訳と、その 37.9%、総額 14 億ドルを占める食糧<br />
の品目別割合は下図の通り。<br />
図表 5 物資調達額'総額 37 億 2,000 万ドル(と食糧調達額の品目別割合<br />
訓練・会議・コ<br />
ンサル手数料<br />
1.2%<br />
貯蔵・物流管<br />
理、プレハブ・<br />
防水シート等<br />
2.9%<br />
車両<br />
1.2%<br />
事務サービ<br />
ス、保険、賃<br />
貸・公共料金<br />
3.1%<br />
その他<br />
サービス<br />
19.9%<br />
輸送関連費<br />
33.9%<br />
食糧<br />
37.9%<br />
265<br />
コーン その他<br />
ミール<br />
2.2%<br />
4.1% 野菜油<br />
3.8%<br />
小麦粉<br />
4.4%<br />
モロコシ<br />
4.4%<br />
豆類<br />
8.4%<br />
混合食品<br />
11.8%<br />
米<br />
15.7%<br />
出所:2008 Annual Statistical Report 14 , WFP Food Procurement Annual Report 2008 15<br />
③ 供給元国・地域別内訳<br />
10 http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/newsroom/wfp204445.pdf<br />
砂糖<br />
2.1%<br />
小麦<br />
21.7%<br />
コーン<br />
21.6%<br />
11 http://www.wfp.org/wfp-numbers<br />
12 http://www.wfp.org/wfp-numbers<br />
13 http://www.wfp.org/sites/default/files/2008%20Food%20Procurement%20Annual%20Report.pdf<br />
14 http://www.ungm.org/Publications/Documents/ASR_2008.pdf (Page 104)<br />
15 http://www.wfp.org/sites/default/files/2008%20Food%20Procurement%20Annual%20Report.pdf (Page 4)
2008 年度は、発展途上国 73 カ国、先進国 12 カ国、合計 85 カ国から物資を調達した。<br />
億ドル<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
20.7<br />
5.0<br />
図表 6 国別寄付金実績'1億ドル以上(と日本の寄付金内訳<br />
3.6<br />
2.8<br />
出所:WFP Annual Report 2009 16 を基に作成<br />
緊急時<br />
26.8%<br />
途上国<br />
開発費<br />
11.9%<br />
2.2 1.8 1.7 1.4 1.2 1.2 1.1 1.0 1.0<br />
266<br />
その他<br />
1.5%<br />
持続的救済<br />
収拾活動<br />
59.8%<br />
図表 7 食糧・食糧輸送関連物資 調達国実績'1,500 万ドル以上(<br />
(100万ドル)<br />
180<br />
164<br />
160<br />
140<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
100 98<br />
89<br />
63<br />
54 53<br />
45 44 43 42<br />
出所:WFP Food Procurement Annual Report 2008 17 を基に作成<br />
37 35 33 30 30 30 27<br />
22 22<br />
18 17 15 15<br />
2008 年には、緊急時の活動の効率性を高めるため、民間企業パートナーを増強要員として管<br />
16 http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/newsroom/wfp204445.pdf (Annex 2)<br />
17 http://www.wfp.org/sites/default/files/2008%20Food%20Procurement%20Annual%20Report.pdf (Page 7-10)
理費の追加なしに起用した。また、2008 年の中国・ハイチ・インド・モザンビーク・ミャンマーでの<br />
緊急事態配送チームも、下記の企業の支援を受けた。<br />
④ 支給先国・地域別内訳<br />
億ドル<br />
7<br />
6.4<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
図表 8 WFP主要パートナー会社名<br />
活動パートナー 食糧配送チーム<br />
Caterpillar Agility<br />
Citigroup TNT<br />
Google UPS<br />
Pepsi<br />
TNT<br />
出所:WFP Annual Report 2009 18<br />
図表 9 プロジェクト・食糧支給先国実績'5,000 万ドル以上(<br />
2.9<br />
2.0<br />
1.8 1.6 1.6<br />
出所:WFP Annual Report 2009 19 を基に作成<br />
⑤ 日本企業からの調達実績 20<br />
1.2 1.0 0.9 0.9 0.8 0.8 0.7 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5<br />
日本企業のWFPに対する寄付金は、米国、ロシア、EU、カナダに次ぐ。これは 2007~2008<br />
年度にかけ、「学校給食緊急支援キャンペーン~hope~」に対し、様々な企業の協力で 2,200 万<br />
円の寄付を行ったことを筆頭に、ミャンマーサイクロン被災者救済に対する寄付 2,750 万円など、<br />
民間企業やボランティア団体からの多数の寄付が得られたことによる。また、食糧の寄付金額に<br />
関しては 2008 年度、世界第 24 位'先進国中第 7 位(であった。<br />
食糧関連物資'食糧供給のための輸送機関の調達額(については、2008 年度、日本企業から<br />
の調達額は 1,509 万ドルであった。2008 年度の詳細は不明なため 200 年度について 3 万ドル以<br />
上の発注額の詳細を見ると、下表の通りとなっている。<br />
18 http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/newsroom/wfp204445.pdf (Page 6)<br />
19 http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/newsroom/wfp204445.pdf (Annex 1)<br />
20 http://www.wfp.or.jp/kyokai/kifu2008.html<br />
267
図表 10 2007 年度日本企業からの調達実績と品目'3 万ドル以上(<br />
サプライヤー 品目 調達額(ドル)<br />
トヨタ自動車アフリカ事業部 ランドクルーザー、ランクルハイラックス 3,462,357.66<br />
トヨタ自動車 ランドクルーザー、ランクルハイラックス 3,068,901.72<br />
豊田通商 ランドクルーザー、ランクルハイラックス 106,854.15<br />
アラノ貿易 タイヤ(チューブ、ホイール) 89,115.88<br />
出所:2007 Annual Statistical Report 21<br />
21 http://www.ungm.org/Publications/Documents/ASR_2007.pdf (Page 178)<br />
268
4.国連難民高等弁務官事務所<br />
'UNHCR:United Nations High Commissioner for Refugees(<br />
'1(活動概要 1<br />
国連難民高等弁務官事務所'UNHCR(は、1950 年 12 月 14 日に設立された国連機関で、ス<br />
イス・ジュネーブに本部を構えている。世界中の難民の保護、難民問題の解決に向けた国際的<br />
な取組を主導・調整する役割を担い、難民の権利・健康を守ることを原則としている。全ての人が、<br />
他国に安全な避難所を見つけた後、母国に帰還するか、その地域に定住するか、第三国に出国<br />
するかの3つの選択権が与えられるよう努力し、無国籍者の支援を行っている。<br />
'2(拠点と役割分担 2<br />
現在約 6,650 人のスタッフが 118 カ国以上で毎年約 3,440 万人の難民を支援している。スタッ<br />
フの 80%以上が、108 の各国・地域事務所ないし 151 のサブ・リモートオフィスで難民救済活動を<br />
行っている。<br />
'3(調達の仕組み<br />
① 調達窓口連絡先<br />
UNHCR供給管理サービスの連絡先は下表の通り。連絡優先順位 2、3 位の個人名は 2009<br />
年 12 月時点で今回調査のため連絡を取ったスタッフである。<br />
ホームページ<br />
登録先<br />
図表 1 UNHCR調達窓口連絡先<br />
連絡優先順位 1 2(個人) 3(個人)<br />
連絡先名 Supply Management Service Mr David Gervais Koutangni Mr Mats Hulgren<br />
住所/役職<br />
電話番号<br />
(UNHCR供給管理サービス)http://www.unhcr.org/pages/49c3646c4a0.html<br />
(国連世界市場データベース)http://www.ungm.org/Index.aspx<br />
Case Postale 2500<br />
CH-1211 Genève 2 Dépôt Suisse.<br />
+41 22 739 8111<br />
(automatic switchboard)<br />
Desk Officer<br />
Genève<br />
- -<br />
269<br />
Senior Supply Officer<br />
Eメール hqsms@unhcr.org KOUTANG@unhcr.org HULTGREN@unhcr.org<br />
1 http://www.unhcr.org/pages/49c3646c2.html<br />
2 http://www.unhcr.org/pages/49c3646cbc.html
② 基本方針 3<br />
以下の活動に従事している企業、もしくは子会社が以下の活動に従事している企業は、UNH<br />
CRとパートナーシップを結ぶことはできない。<br />
� 武器・その部品の販売・生産<br />
� 組織的で継続した強制労働・児童労働<br />
� 国連の制裁措置を受けている国での活動<br />
また過去にこの条件を満たしていなかった企業や、契約によりUNHCRの評判を損なった企<br />
業とは、パートナーシップを結ばない場合がある。<br />
③ 具体的な流れ 4<br />
サプライヤー候補企業は、まずUNHCRベンダー登録フォームに記入し、最新の財務諸表な<br />
どと共にUNHCRジュネーブ本部に送付する。また、UNHCRが国連世界市場データベース'U<br />
NGM(を使って発注候補企業を見つける場合もある。<br />
'4(調達の実績 5<br />
① 概要 6<br />
UNHCRの 2009 年予算は 23 億ドルであり、世界各地の国内避難民・難民・帰還者・無国籍<br />
者・難民保護施設希望者など約 3,000 万人に対する援助物資として分配される。<br />
② 品目別内訳<br />
UNHCRが、難民救済のためにサプライヤーから調達する物資品目を以下の通り。2006 年度<br />
は避難施設とそれに付随する備品・サービス・運搬のための調達額が全体の 89%を占めており、<br />
この割合は最近数年間、大きな変化はない。<br />
3 http://www.unhcr.org/pages/49c3646c2ba.html<br />
4 http://www.unhcr.org/pages/49c3646c4a3.html<br />
5 http://www.unhcr.org/pages/49c3646c4a0.html<br />
6 http://www.unhcr.org/pages/49c3646cbc.html<br />
270
③ 供給元国・地域別内訳<br />
図表 2 2006 年度 ジュネーブ本部による調達品目割合<br />
健康器具<br />
1%<br />
水・農業<br />
・技術<br />
2%<br />
避難施設・<br />
家庭用備品<br />
33%<br />
IT・通信機器<br />
装置<br />
7%<br />
271<br />
運送機関・<br />
システム<br />
11%<br />
事業サービス<br />
30%<br />
車両・部品<br />
15%<br />
出所:UNHCR Procurement Statistics 2006 7<br />
事務用品<br />
・消耗品<br />
1%<br />
物資の供給元はUNHCR本部のあるスイスと国連倉庫のあるデンマークが筆頭であるが、現<br />
地調達を推奨する国連の指針に基づき、インド・ケニア・パキスタンなど途上国が上位 20 カ国中<br />
5 カ国を占めている。<br />
(100万ドル)<br />
19.1<br />
20<br />
18<br />
16<br />
14 12.4<br />
12<br />
10<br />
8.7<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
図表 3 上位サプライヤー貢献額<br />
6.5 5.8 5.5 4.2 3.4 3.3 3.0 2.4 1.7 1.7 1.6 1.6 1.0 1.0 0.9 0.8 0.8<br />
出所:UNHCR Procurement Statistics 2006 8<br />
UNHCRサプライヤーの購買額上位 15 企業を以下に示す。2006 年度第 2 位のトヨタ自動車<br />
は、2003 年度以降毎年上位に入っている。<br />
7 http://www.unchr.org/47b01ec0b.html (Page 6)<br />
8 http://www.unhcr.org/47b01ec0b.html (Page 8)
図表 4 2006 年度上位サプライヤー企業名と購買額<br />
国名 サプライヤー 注文額 注文数 概要<br />
1 デンマーク Kuehne & Nagel A/S 8,158,914 317 種々の輸送機関<br />
2 日本 トヨタ自動車 5,336,859 57 車両<br />
3 ケニア Corrugated Sheets Ltd 3,398,207 1 屋根材<br />
4 パキスタン Natonal Tent House 3,344,770 15 テント、生理用ナプキン生地<br />
5 中国 Qingdao Gyoha En Tech Co Ltd 3,342,399 25 プラスチック多目的防水シート<br />
6 英国 Cedar Consulting UK Ltd 3,129,693 11 ITコンサルティングサービス<br />
7 スイス SPG 2,408,027 4 建物賃貸サービス<br />
8 大韓民国 Puyoung Ind. Co. Ltd 2,379,533 14 プラスチック多目的防水シート<br />
9 英国 Toyota Gibraltar Stockholdings Ltd 2,312,288 25 車両、車両部品<br />
10 スイス UNOG 2,241,151 12 国連事務・財務サービス、会議用設備<br />
11 イタリア Ferrino & C.S.p.A 2,163,520 2 軽量テント<br />
12 スイス FIPOI 2,053,424 6 建物賃貸サービス<br />
13 中国 Shenzhen Palm Beach Camping Manuf. 1,974,000 5 軽量テント<br />
14 インド Vandana Logistics 1,842,138 14 台所セット、20リットルバケツ<br />
15 インド Parkash Woolen Industries 1,688,345 16 毛布<br />
出所:UNHCR Procurement Statistics 2006 9<br />
④ 支給先国・地域別内訳<br />
調達された物資がどの国に輸送されているかを下図の通り。スイスとデンマークへは貯蔵の<br />
ための輸送であるが、その他の国々にはサプライヤーあるいはUNHCRパートナーから直接物<br />
資が輸送されている。<br />
35<br />
30.7<br />
30<br />
(100万ドル)<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
⑤ 日本企業の調達実績<br />
5<br />
0<br />
図表 5 2006 年度 物資輸送先国<br />
7.3 7.2 6.5 5.7 4.3 3.8 3.0 2.0 2.0 2.0 1.6 1.3 1.3 0.9 0.8 0.8 0.7 0.5 0.5<br />
出所:UNHCR Procurement Statistics 2006 10<br />
日本は、企業からの調達や慈善団体・企業のCSR活動からの寄付によりUNHCRに大きく貢<br />
献している。また、北欧を除く欧州圏、中東・アジア地域の貢献も大きい。また、UNHCRが日本<br />
のサプライヤーから調達する物資は車両がその大半を占めており、2003~2006 年は注文数、供<br />
9 http://www.unhcr.org/47b01ec0b.html (Page 11)<br />
10 http://www.unchr.org/47b01ec0b.html (Page 4)<br />
272
給額で 80%以上をトヨタ自動車が独占している。<br />
注文数<br />
供給額<br />
(ドル)<br />
(内訳)<br />
図表 6 2006 年度 物資寄付と調達元 国名・地域<br />
その他<br />
ヨーロッパ<br />
38%<br />
北ヨーロッパ<br />
11%<br />
273<br />
アフリカ<br />
6%<br />
アメリカ大陸<br />
2%<br />
中東・アジア<br />
30%<br />
日本<br />
12%<br />
出所:UNHCR Procurement Statistics 2006 11<br />
図表 7 日本企業サプライヤー実績<br />
オセアニア<br />
1%<br />
2003年 2004年 2005年 2006年<br />
計 80 103 94 69<br />
トヨタ自動車 69 93 92 57<br />
その他 11 10 2 12<br />
計 5,255,923 6,988,518 5,242,582 5,770,921<br />
トヨタ自動車 5,076,744 6,646,548 4,988,346 5,336,859<br />
その他 179,179 341,970 254,236 434,062<br />
車両・部品 5,255,923 6,899,675 5,140,766 5,692,119<br />
避難施設・家庭用機<br />
器<br />
0 0 1,585 0<br />
輸送機関 0 52,555 25,868 34,769<br />
事務用品・備品 0 36,288 37,068 1,132<br />
水・農業・技術 0 0 37,295 42,901<br />
出所:UNHCR Procurement Statistics 2003 – 2006 12 , 13 , 14 , 15 を基に作成<br />
⑥ 日本企業の製品の事例 16<br />
2008 年度にUNHCRが日本企業'日本法人企業含む(から調達した物資・サービスは、物資<br />
1,051 万ドル、サービス 73 万 5,340 ドルで、UNHCR購買総額の 3%を占めた。また、企業のCS<br />
R活動の一環としてUNHCRに貢献している企業もある。<br />
11 http://www.unhcr.org/47b01ec0b.html (Page 10)<br />
12 http://www.unhcr.org/415bd2e44.html (Page 12)<br />
13 http://www.unhcr.org/430205ef2.html (Page 11)<br />
14 http://www.unhcr.org/45a788c52.html (Page 11)<br />
15 http://www.unhcr.org/47b01ec0b.html (Page 11)<br />
16 http://www.ungm.org/Publications/Documents/ASR_2008.pdf
図表 8 2008 年度日本企業'日本法人含む(からの調達実績と品目'3 万ドル以上(<br />
ゴールデンアロー<br />
ジェー・ガーバー商会<br />
アラノ貿易<br />
日産トレーディング<br />
サプライヤー 品目 調達額(ドル)<br />
トヨタ ハイエース(商業用バス) 128,517.49<br />
車両メンテナンスサービス 64,452.68<br />
ヤマハ オフロードバイクDT12 105,218.16<br />
ヤマハ 交換部品 132,980.48<br />
4X2 水タンカー 86,238.95<br />
冷凍トラック 812,000.00<br />
日産 パトロール(サファリ)4X4 SW GL4200 1,086,594.87<br />
日産 パトロール 4X4 SW GL4800 54,049.44<br />
日産 ピックアップ 4X4 DC3200CC 34,710.63<br />
日世貿易 医療機器 139,100.00<br />
Saud Bahwan Automotive LLC (オマーン) トヨタ 車両交換部品 49,622.70<br />
Toyota East Africa LimITed(ケニア) トヨタ ランドクルーザー 4X4 SW GX4200 124,859.13<br />
トヨタ自動車<br />
出所:2008 Annual Statistical Report 17<br />
1(商船三井グループ ―海上輸送機関 18<br />
トヨタ ランクル(救急車)4X4 LWS 570,292.29<br />
トヨタ ハイエース(救急車)2400D 113,684.00<br />
トヨタ コースター(バス)26S 67,085.27<br />
トヨタ ハイエース(商業用バス) 550,946.47<br />
トヨタ ランクル(ピックアップ)4200HZJ79 139,275.19<br />
トヨタ ハイラックス(ピックアップ) 422,749.33<br />
トヨタ 車両交換部品(+オプション部品) 251,809.38<br />
トヨタ カローラ SED 1800CC/1600CC 385,393.18<br />
トヨタ ハイエース 救急車 2700P 710,715.79<br />
トヨタ ランドクルーザー 3,962,508.64<br />
トヨタ LCプラド 4X4 ディーゼル/ガソリン 230,539.70<br />
トヨタ プラド 4X4ワゴン 3000CC 157,569.58<br />
商船三井グループは、海運という事業領域に根差したCSR活動を行うことを基本方針とし、海<br />
洋観測調査への協力、海岸美化活動、環境・海事教育への協力、義援金活動に加え、世界の貧<br />
しい人々への支援として国際的な援助物資輸送を行っている。その一部として、UNHCRの緊急<br />
物資購入の際の資金援助や、中国からアラブ首長国連邦への援助輸送を無償で行っている。<br />
2(ユニクロ ―衣服 19<br />
2001 年 9 月よりユニクロは、顧客にとって不要となった販売済フリースを回収・リサイクルを始<br />
め、2006 年度からは全衣料に拡大、毎年 3 月と 9 月、2009 年度からは 6 月も加え、「サンキュー<br />
リサイクル」と名付けた活動を行っている。当初、回収した衣料はエネルギー資源や工業用繊維<br />
へとリサイクルされていたが、2009 年現在、約 90%の回収衣料がUNHCR、NPO法人日本救<br />
援衣料センターの協力のもと、世界の難民キャンプで再利用されている。<br />
17 http://www.ungm.org/Publications/Documents/ASR_2008.pdf (Page 74-76, 92-94, 138-144, 256-263)<br />
18 http://www.mol.co.jp/ir-j/shiryo/pdf/ar-j2008_13.pdf<br />
19 http://www.uniqlo.com/jp/corp/pressrelease/2009/05/20093.html<br />
274
'1(活動概要 1<br />
5 世界保健機関'WHO:World Health Organization(<br />
世界保健機関'WHO(は、スイス・ジュネーブに本部を置く国連組織であり、世界の人々の健<br />
康管理・調整を行っている。1945 年の国連立ち上げ時、世界的な健康問題に対処する組織の必<br />
要性が討議され、1948 年 4 月 7 日、世界保健機関として設立された。4 月 7 日はそれ以来、世界<br />
保健デー'World Health Day(となっている。<br />
WHOは、世界の健康問題に対しリーダーシップを発揮し、健康に関する研究方針・課題をま<br />
とめ、国際基準を定め、各国を技術面からサポートし、健康に関する世界の動向を観察・査定す<br />
るという役割を担っている。<br />
WHOは 2006~2015 年の目標として、下記を掲げている。<br />
� 健康に関する重要課題に対しリーダーシップを発揮し、それを実現するため協力関係が<br />
不可欠ならば企業とパートナーシップを結ぶ。<br />
� 研究方針・課題をまとめ、人々を刺激し、価値ある知識の転換・普及を促進する。<br />
� 国際基準を設定し、その実行を促進・測定する。<br />
� 倫理的で証拠に基づく政策を統合する。<br />
� 技術面のサポート、変化を促し、持続可能な組織力の形成を支援する。<br />
� 健康状態を管理し、健康に関する世界の動向を査定する。<br />
'2(拠点と役割分担 2<br />
ジュネーブ本部、6 つの地域事務所'アフリカ、アメリカ、東南アジア、ヨーロッパ、東地中海、西<br />
太平洋(、147 の各国事務所が、150 カ国以上に配置されており、合計 8,000 人以上のスタッフが<br />
従事している。<br />
WHOではジュネーブ本部にて大部分の必要物資および設備を調達しているが、代理権の範<br />
囲内で地域事務所が調達を行っている。地域事務所の調達比率はジュネーブ本部の 5 分の 1<br />
以上であり、本部の権限委譲度合が大きいことが伺える。またWHOのフィールドプロジェクトは、<br />
1 http://www.who.int/about/en/<br />
2 http://www.who.int/about/structure/en/index.html<br />
275
6 つのWHO地域事務所の責任のもと計画され実行に移される 3 。<br />
2006 年時点において、多くの国で国民健康保健システムは確立されていない。今後も最低限<br />
必要な健康保健システムを確立できないであろうとWHOが認識した国は 57 カ国で、このうちほ<br />
とんどは、サブサハラ・アフリカ、東南アジアの国々である。これらの国々に対しWHOの地域・各<br />
国事務所は、国民健康保健システム構築に必要な技術支援、才能のある人材の発掘、調査、助<br />
言などを行っている 4 。<br />
'3(調達の仕組み 5<br />
① 調達窓口連絡先<br />
WHOの調達窓口連絡先は下表の通り。連絡優先順位 2 位の個人名は 2009 年 12 月時点で<br />
今回調査のため連絡を取ったスタッフである。<br />
② 基本方針<br />
図表 1 WHO調達窓口連絡先<br />
ホームページ<br />
(WHO)http://www.who.int/en/<br />
連絡優先順位 1 2(個人)<br />
連絡先 Contracting and Procurement Services (WHO/CPS) Mr Thomas Abraham<br />
住所/役職<br />
World Health Organization<br />
Avenue Appia 20 1211 Geneva 27 Switzerland<br />
-<br />
電話番号 +41 22 791 2801 -<br />
ファクス +41 22 791 4196 -<br />
Eメール procurement@who.int abrahamt@who.int<br />
世界の人々の寿命と健康状態の向上、貧困と不公平な医療制度の撲滅、良質の基準・標準<br />
の構築によってより健康な世界を創出すること、基本的な医療を通して全ての人々が健康である<br />
よう努力し続けること、予防接種と基本的医薬品の入手を通して人々の命を守ること、病気の根<br />
絶と健康促進に対する賢明な投資、これらの目標をともに達成することのできるサプライヤーを<br />
WHOは求めている。<br />
3 http://www.ungm.org/Publications/Documents/gbg_master.pdf<br />
4 http://www.who.int/whr/2007/whr07_en.pdf (Page 57)<br />
5 http://www.ungm.org/Publications/Documents/gbg_master.pdf (Page 81-82)<br />
276
③ 調達・購買の重点分野とその方針<br />
WHOが主導するグローバル健康戦略'GHI:Global Health Initiatives(に関連する物資、例え<br />
ばポリオ・ハンセン病・ギニア虫症の根絶、ロールバックマラリア'RBM:Roll back Malaria(プロ<br />
グラム、結核の撲滅、タバコのない世界構想'TFI: Tabacoo Free Initiative(プログラムに関連す<br />
る物資を優先的に調達する。また基礎医薬品の入手、輸血の安全性を世界的に向上させるため<br />
の調達活動も重要である。<br />
④ 具体的流れ<br />
下記にWHOが必要とする物資を供給できるサプライヤーの登録および選定手順は下表の通<br />
り。ただしコンサルティングサービスを提供する企業の場合、購買サービス課'WHO/CPS(では<br />
サービス契約を取扱わないため、プログラムの活動によって、技術サービス課'Technical<br />
Services(など担当する部署にに直接連絡を取る必要がある。<br />
図表 2 サプライヤー登録・選定手順<br />
1 WHOが関心を持つような製品を有する企業はその製品カタログと価格リストを、製品が世界市<br />
場で競争力のあることを明確にした上でWHO購買サービス課アドバイザーに送付する。<br />
2 WHO購買サービスのアドバイザーによる製品評価が行われる。<br />
3 企業プロフィールフォームに企業の詳細を記入する。<br />
4 商品が必要な時に、その商品を供給できるサプライヤーが1と3の書類を基に選定され、入札案内<br />
が送付される。<br />
* 医薬品を取扱う企業の場合、その生産国で製品の販売と使用が登録あるいは許可されていること<br />
を証明する書類が必須である。<br />
出所:United Nations System General Business Guide 6<br />
⑤ 製品開発・サプライヤー選定例<br />
1(ワクチン 7<br />
1980 年に医薬品適正製造基準'GMP(が導入されて以来、ワクチン産業では設備やスタッフ、<br />
GMPを維持・順守するための投資が増大し、ワクチンの生産コスト増加に繋がっている。それぞ<br />
れのワクチン製造手順は文書化され、認証を受けていなければならない。製造量の増加に伴い<br />
ワクチンメーカーは、生産工程の一部を他メーカーに委託している。現在WHOは、28 メーカーに<br />
ワクチン開発過程の一部を契約のもと実施できる認証を与えている。<br />
6 http://www.ungm.org/Publications/Documents/gbg_master.pdf (Page 81-83)<br />
7 http://www.who.int/immunization_supply/introduction/economics_vaccineproduction.pdf<br />
277
国連機関が調達するワクチン数・サプライヤー数は、多国籍企業と途上国・新興市場に拠点<br />
を持つ企業の参入により、着実に増加している。<br />
図表 3 国連機関ワクチン調達'BCG 除く(<br />
ワクチン数 サプライヤー数 途上国・新興国サプライヤーの割合<br />
1986 4 7 0%<br />
1996 5 14 50%<br />
2001 6 12 58%<br />
出所:WHO Department of Vaccines and Biologicals 8<br />
2(Lifestraw -Vestergaard Frandsen 9<br />
スイスに本社を置くベスタゴー社の商品ライフストローは、ミレニアム開発目標の達成に向け<br />
てNGO団体カーターセンターと共同で開発され 10 、2005 年より製造され始めた。商品に内包され<br />
ている 7 枚の水フィルターは、99.9999%の水媒介性のバクテリア、98%のウイルス、15 マイクロン<br />
までの微粒子を除去するもので、その効用は 1 人の年間消費量である 700 リットル以上持続する。<br />
また電力を必要としないため、どのような状況下でも使用することができるというのも大きな特徴<br />
である。<br />
ライフストローは、通常の 2ドル程度の価格であるが、先進国の消費者が旅行用などに購入す<br />
る際、金額を上乗せして支払い、その分NGO団体に寄付ことができる。そしてNGOがこの寄付<br />
金を活用し途上国の人々にライフストローを配給している 11 。<br />
ベスタゴーは Prime Water International'PWI、2008 年 2 月に持ち株会社化(のウルトラフィル<br />
トレーション膜'UF膜(をライフストローに採用しており、そのフィルターを通した後の水中の銀の<br />
残余濃度はWHO基準以下であり、ヨウ素も残存しないかWHO基準以下である。そのため人体<br />
に影響はなく安心して使用できる。また、2008 年 2 月より最低 1 万 8,000 リットルから 2 万リット<br />
ルの水をフィルターできる家族向け製品ライフストローファミリーも販売を開始した。2009 年 7 月<br />
からは最新のライフストローファミリーのUF膜にBASF社の製品を使用し始めた。英国ロンドン<br />
大学公衆衛生学熱帯医学校'LSHTM:London School of Hygiene and Tropical Medicine(、感染<br />
熱帯病講座の 2009 年 6 月の報告によると、5 人家族の平均使用量に換算して一人 1 年 1 ドル<br />
以下、また 1 リットルに 0.1 セントの費用でライフストローファミリーを使用できる。<br />
最近の事例では、2008 年 5 月のミャンマーでのサイクロン、2008 年 8 月の中国四川省大地震<br />
8 http://www.who.int/immunization_supply/introduction/economics_vaccineproduction.pdf (Page 15)<br />
9 http://www.vestergaard-frandsen.com/lifestraw-claims.htm<br />
10 http://www.adweek.com/aw/content_display/creative/features/e3ie188ab48abcdb04998cf19a98a69e688<br />
11 http://www.vestergaard-frandsen.com/lifestraw-specifications.htm<br />
278
に、非政府組織と協力しライフストロー、ライフストローファミリーを配送した 12 。特にミャンマーの<br />
サイクロン被害者には、1万6,200本のライフストローが米国際開発局'USAID(、WHO、連邦連<br />
帯開発協会'USDA(、Samaritan’s Purse、米国赤十字、国際ロータリークラブ、ワールド・ビジョ<br />
ン、Convoy of Hope などの協力の下、速やかに被災者に配給された 13 。<br />
3(PUR 'Purifier of Water(-Procter & Gamble 14<br />
P&Gは 1995 年より米国疾病対策センター'CDC(と協同してPURを開発し始めた。P&Gは<br />
PURを営利目的で販売する計画で開発を進め、2000 年に一袋 8~10 セントでグアテマラ、モロッ<br />
コ、パキスタンにてテスト販売を開始したが、3 年間で 300 万袋を販売、消費者のリピート率も 5<br />
~25%と低く、利益も出ず失敗に終わった。<br />
そこでP&Gは、この商品をCSRの一環として再開発、ユニセフ、WHO、CDC、国際NPOの<br />
PSI'Population Services International(などとパートナーシップを結び、世界の貧困層に安全な<br />
水を届けるため、2004 年に一袋 4 セントの製造原価で人道主義的団体に販売を始めた。P&G<br />
の Children’s Safe Drinking Water プログラムなどの寄付金により、2006 年度末までに 5,700 万<br />
袋を供給し、利益も出ている状況である 15 。現在のPURの生産拠点はパキスタンである 16 。<br />
PURの小袋一袋は、汚濁した致死性の成分を含んだ 10 リットルの水を簡単に浄化し、飲料水<br />
に変えることができる。また、その他の浄水装置と異なり粉末状であるため輸送場所を取らない。<br />
PURは、WHOにより効率的な技術であるとして認められており、現在世界のPUR使用者の<br />
60%が子供である 17 。<br />
Children's Safe Drinking Water プログラムによって、2004 年度以降にPUR 1 億 6,000 万袋'水<br />
16 億リットル相当(が人々に支給された。2007 年度単年では 8,300 万袋、2008 年度単年でも、46<br />
万の子どもたちに 2,000 万袋'水 2 億リットル相当(が支給された 18 。PURの小袋が、様々なプロ<br />
グラムとパートナーにより定期的に配給されている国々は、12 カ国に上り、また緊急援助活動で<br />
は全て寄付金にて配給されている。2009 年末現在、PURを配給するための国連プロジェクトは<br />
終了しているが、P&Gの Children’s Safe Drinking Water'CSDW(Program としては 2010 年現<br />
12 http://www.asiapacific.basf.com/apw/Japan/Japan/ja_JP/function/conversions:/publish/Japan/upload/new/<br />
Press2009/P305-Ultrason-JP.pdf<br />
13<br />
http://www.vestergaard-frandsen.com/press-releases.htm<br />
14<br />
http://www.pgbrands.com/Portals/0/Documents/Sustainability/P&G%20Global%20Sustainability%20Report%20<br />
2007.pdf<br />
15<br />
http://www.nextbillion.net/news/p-gs-partnerships-with-ngo-to-deliver-water-purification-produc<br />
16<br />
http://jp.pg.com/topics/0907pakistan/index.htm<br />
17<br />
http://www.pginvestor.com/phoenix.zhtml?c=104574&p=irol-newsArticleMain&ID=907975&highlight=<br />
http://www.csdw.org/csdw/pur_packet.shtml<br />
18<br />
http://www.csdw.org/csdw/csdw_program.shtml<br />
279
在でも積極的に活動している。<br />
ケニア<br />
図表 4 P&G の Children’s Safe Drinking Water プログラムによる PUR 配布事例<br />
国名 年月・供給形態 パートナー 詳細<br />
2007年度<br />
3か月間無償<br />
P&G East Africa、Local NGO<br />
280<br />
地方の46校の子どもたちに、3カ月間無料でPUR<br />
を配布<br />
ベトナム 2007年度 UNICEF、Ministry of Health、P&G Vietnam 児童に届けるため、PURを250,000パケット輸送。<br />
インドネシア<br />
コンゴ民主共和国<br />
2007年度<br />
P&G寄付<br />
2007年度<br />
1袋10セント<br />
Yayasan Dian Desa、Assyiah、<br />
AmarITan’s Purse、CARE、USAID、etc.<br />
Children’s Safe Drinking Water Programme<br />
2006年、ジャワ島中部地震被害にあったジョグ<br />
ジャカルタにある52,000家庭に配布。<br />
ミャンマー 2008年5月 World Vision Singapore 2,000万リットル以上相当のPURを配布<br />
ジンバブエ<br />
パキスタン<br />
2009/1/1<br />
無償<br />
2009年7月<br />
P&G資金援助<br />
PSI、AmeriCares<br />
出所:P&G 2007 Global Sustainability Report 19<br />
'4(調達の実績<br />
① 概要 22<br />
World Vision、<br />
パキスタン国内支援団体<br />
図表 5 プログラム配給国と主要パートナー'順不同(<br />
プログラム配給国 パートナー<br />
ハイチ Population Services International(PSI)<br />
ドミニカ共和国 Defending Dignity, Fighting Poverty(CARE)<br />
コンゴ共和国 UNICEF<br />
1,000万リットル相当(約1万世帯、4~6万人に3カ<br />
月間必要な量)<br />
飲料水2,500万リットルに相当する250万パックを<br />
13万人に配布<br />
コンゴ民主共和国 United States Agency for International Development(USAID)<br />
インドネシア US Centers for Disease Control(CDC)<br />
パキスタン International Council of Nurses<br />
コートジボアール Save the Children<br />
ウガンダ SamarITan’s Purse and AmeriCares<br />
マラウイ World Vision<br />
ケニア Aquaya Institute<br />
エチオピア Johns Hopkins University Center for Communication Programs<br />
ナイジェリア<br />
出所:2007 P&G Global Sustainability Report 20 、Children’s Safe Drinking Water 21<br />
WHOは 2007 年度、1 億 4,210 万ドル相当の物資を調達し、そのうち 22.98%が発展途上国お<br />
よび移行経済国からの調達であった。<br />
② 品目別内訳 23<br />
19 http://www.pgbrands.com/Portals/0/Documents/Sustainability/P&G%20Global%20Sustainability%20Report%20<br />
2007.pdf (Page 45-50)<br />
20<br />
http://www.pgbrands.com/Portals/0/Documents/Sustainability/P&G%20Global%20Sustainability%20Report%20<br />
2007.pdf (Page 52)<br />
21<br />
http://www.csdw.org/csdw/csdw_program.shtml<br />
22<br />
http://www.ungm.org/Publications/Documents/ASR_2008.pdf (Page 5)<br />
23<br />
http://www.ungm.org/Publications/Documents/ASR_2007.pdf (Page 57)
WHOが調達する物資は、毎年ほぼ 50%が医療関連備品や薬となっている。<br />
③ 供給元国・地域別内訳 25<br />
図表 6 WHO調達総額'1 億 4,210 万ドル(の品目別割合<br />
病院用備品<br />
・消耗品<br />
4.3%<br />
緊急時収拾<br />
4.9%<br />
ワクチン<br />
4.0%<br />
車両<br />
7.3%<br />
研究用器具<br />
7.5%<br />
蚊帳<br />
7.6%<br />
その他<br />
8.1%<br />
調合薬<br />
7.7%<br />
281<br />
抗マラリア薬<br />
25.9%<br />
出所:2007 Annual Statistical Report 24<br />
IT機器<br />
13.8%<br />
診断法・研究用<br />
生物学的製剤<br />
8.9%<br />
WHO調達額の半分以上を占める医療関連機器・医薬品などは、品質が非常に重要であり開<br />
発費用もかさむため、先進国からの調達比率が 75%以上と高い。中でも、米国からの調達割合<br />
が全体の 4 分の 1 強を占めている。<br />
図表 7 WHO物資調達先'総額 1 億 4,210 万ドル(の地域・国別比率<br />
アラブ諸国<br />
3.5%<br />
アフリカ諸国<br />
5.0%<br />
アジア諸国<br />
13.3%<br />
その他先進国<br />
16.9%<br />
フランス<br />
6.4%<br />
ラテンアメリカ・<br />
カリブ海諸国<br />
1.0%<br />
ドイツ<br />
7.1%<br />
米国<br />
26.3%<br />
日本<br />
9.5%<br />
ヨーロッパ・CIS<br />
諸国<br />
0.2%<br />
オランダ<br />
10.6%<br />
出所:2007 Annual Statistical Report 26 を基に作成<br />
④ 日本企業の調達実績<br />
た。<br />
2007 年度WHOは、日本企業から 1,356 万ドル相当'WHO全体の調達額の 9.5%(を調達し<br />
24 http://www.ungm.org/Publications/Documents/ASR_2007.pdf (Page 57)<br />
25 http://www.ungm.org/Publications/Documents/ASR_2007.pdf (Page 34-36)<br />
26 http://www.ungm.org/Publications/Documents/ASR_2007.pdf (Page 34-36)
⑤ 日本企業の製品の事例<br />
WHOの 2007 年度調達物資で、日本からの調達実績'3 万ドル以上(の詳細は下表の通り。<br />
図表 8 2007 年度日本企業'日本法人含む(からの調達実績と品目'3 万ドル以上(<br />
サプライヤー 品目 調達額(ドル)<br />
富士レビオ Serodia HCV, 簡易検査100回分 34,125.00<br />
ジェー・ガーバー商会 バイク(DT125,123CC,2ストローク,2シート,日常用モデル) 96,199.75<br />
バイク(YB100,98CC,ビジネス用モデル) 44,494.07<br />
株式会社 高研 病院用備品 126,026.06<br />
日産トレーディング 日産ピックアップ 4X4ダブルキャブ 419,786.84<br />
日世貿易 ホンダバイク(XL125SL/DK,124CC,1シリンダー,4ストローク) 284,921.61<br />
オリンパス<br />
顕微鏡フレーム(顕微鏡検査用) 83,907.26<br />
油浸レンズX100(CX21顕微鏡用) 30,389.92<br />
住友化学 オリセットネット(ペルメトリン製剤処理済) 1,327,750.00<br />
ヤマト科学 純水製造装置 オートスチル(WA570,AC200V,50/60Hz,20A) 41,880.34<br />
トヨタ自動車<br />
トヨタ ハイラックス 1,209,777.50<br />
トヨタ ハイエース 224,800.58<br />
トヨタ ランドクルーザー 1,222,209.59<br />
トヨタ ランドクルーザー 救急車 302,128.75<br />
トヨタ カローラ 54,536.84<br />
トヨタ その他車両 252,142.87<br />
トヨタ 車両部品 115,447.00<br />
出所:2007 Annual Statistical Report27 を基に作成<br />
27 http://www.ungm.org/Publications/Documents/ASR_2007.pdf (Page 184)<br />
282
Ⅳ.国際NGO調査<br />
1. オックスファム'Oxfam(<br />
2.セーブ・ザ・チルドレン'Save the Children(<br />
3.国境なき医師団'MSF:Medecins Sans Frontieres(<br />
4. マリー・ストープス・インターナショナル 'Marie Stopes International(<br />
5.プラン'Plan(<br />
283
'1(活動概要<br />
1.オックスファム'Oxfam( 1<br />
貧困と不正の克服を目指し、世界 100 カ国以上で、3,000 以上のパートナーと共に活動を行って<br />
いる。緊急支援と長期開発プログラムの 2 つを軸とし、社会に対する啓発活動、政策決定者や企<br />
業への働きかけ、政策研究なども行っている。具体的な活動分野は、緊急支援、気候変動、教育、<br />
保健、ジェンダー、貿易など多岐に渡る。また国により、フェアトレード製品やリサイクル品などの<br />
販売も行っている。2006/07 年のプログラム支出'管理費用を含まない(は、世界全体で約 7 億<br />
500 万ドル、内訳は「緊急援助、安全」が 37%、「生活」が 24%、「人権」が 13%などである。<br />
'2(沿革<br />
第二次世界大戦中の 1942 年に、英国オックスフォードでギリシャ人への食料供給を目的とし<br />
「オックスフォード飢餓救済委員会'Oxford Committee for Famine Relief(」として設立された。1961<br />
年に初の海外事務所を設立、以降、活動に賛同する団体がオックスファムに加わるなど、次第に<br />
世界に活動が広がった。1995 年にオックスファム・インターナショナル設立、オックスファム・ジャパ<br />
ンは 2003 年 12 月に設立された。<br />
'3(拠点と役割分担<br />
オックスファムは世界 16 カ国・地域 2 の民間団体から構成されている'2008 年 4 月時点(。支部・<br />
本部などはなく、各国・地域団体は対等な関係にある。具体的なプログラム実施の決定などは各<br />
国オックスファムに委ねられており、各国オックスファムの支援とコーディネートのみ、上部組織と<br />
してオックスファム・インターナショナルが担当しており、事務局は英国オックスフォードにある。こ<br />
の他、キャンペーンオフィスやアドボカシー・オフィスを、ワシントンとニューヨーク'米国(、ブリュッ<br />
セル'ベルギー(、ジュネーブ'スイス(、ブラジリア'ブラジル(、ローマ'イタリア(に構えている。<br />
'4(調達の仕組み<br />
1 http://www.oxfam.org<br />
2 アイルランド、オランダ、ドイツ、香港、米国、カナダ、ニュージーランド、メキシコ、英国、ケベック、フランス、スペ<br />
イン、オーストラリア、インド、ベルギー、日本<br />
284
① 基本方針<br />
オックスファムの中で最も活発に活動しているオックスファム・GBをみると、「供給方針'Oxfam<br />
GB Supply Policy(」 3 として、経済性の追求、安全や環境への配慮、法令順守などを明記している。<br />
また 1997 年に「倫理購買方針'Ethical Purchase Policy(」を独自に設定し、下記の 2 つの条件を<br />
満たした製品・サービスを調達すると定めている。<br />
� 「Ehical Trading Initiative」 4 の基本行動規範'Base Code(を満たしており、製造や配送の過<br />
程で、どのような人に対しても虐待や搾取が行われていない。<br />
� 気候変動、環境への影響が最小限である。<br />
このため、オックスファム・GBのサプライヤー'及びさらにそのサプライヤー(は、この行動規範<br />
を遵守し、さらにこのうち労働と環境の行動規範については、継続的に改善に向けた努力を行わ<br />
なくてはならない。また、オックスファム・GBは、人道的支援を行う団体のロジスティクス担当者の<br />
ネットワーク「Inter-Agency Procurement Group」 5 に参加しており、倫理購買方針の進捗について<br />
毎年報告を行っている。児童労働を行う企業などと提携していることが発覚した場合、これまで築<br />
いてきた評判と信頼を全て失う可能性があるため、サプライヤーの選定には非常に慎重になって<br />
いる。 6<br />
3 http://www.oxfam.org.uk/resources/suppliers/supply.html<br />
4 労働環境改善のための企業や NGO のアライアンス http://www.ethicaltrade.org/<br />
5 オックスファム、セーブ・ザ・チルドレン、マリー・ストープスなど 15 の機関のロジスティクス担当者のネットワーク。<br />
知識を共有することで、人道支援のロジスティクスの水準を高め効率化することを目指す。サプライヤーに関す<br />
る情報共有などが具体的活動内容である。http://www.iapg.org.uk/<br />
6 オックスファム・GBインタビュー<br />
285
② 分野別方針<br />
労働<br />
図表 1 オックスファム・GBのサプライヤー行動規範<br />
・就労が自由意志によるものである。<br />
・労働者の結社の自由と団体交渉が認められている。<br />
・労働環境が安全で衛生的である。<br />
・児童労働が行われていない。<br />
・生活水準を満たすだけの賃金が支払われている<br />
・労働時間が過剰でない。<br />
・採用、昇進などにおける差別がない。<br />
・法令に基づき正規雇用が行われている。<br />
・従業員が非人道的扱いを受けていない。<br />
・気候変動政策を妨げる活動を積極的に行わない。化石燃料使用の拡大を要請しない。<br />
・オーストラリア、ベラルーシ、ブルガリア、カナダ、クロアチア、EU 、アイスラ<br />
ンド、日本、リヒテンシュタイン、モナコ、ニュージーランド、ノルウェー、ルーマニ<br />
ア、ロシア、スイス、ウクライナ、米国の企業は、事業活動に伴う直接・間接温室効果<br />
ガス排出量を絶対量で測定、目標設定、削減し、公表しなければならない。二酸化炭素<br />
排出量の尐ない材料、輸送手段、包装、エネルギー源を積極的に調べ、導入しなければ<br />
ならない。自社のサプライヤーのうち上記以外の国の企業が二酸化炭素削減計画を策定<br />
する際、支援をしなければならない。<br />
・上記の国の企業は、可能な限り自社製品のカーボンフットプリントを調査し、オック<br />
スファムに対し、より二酸化炭素排出量の尐ない代替製品について助言しなくてはなら<br />
ない。 ・上記以外の国の企業は、二酸化炭素削減計画を設定しなければならない。<br />
・実施している気候変動対策を分かりやすく示す。<br />
・オックスファム・GB英国事務所から供給される全ての紙製品と、オックスファムのブ<br />
ランドを付けた全ての新製品(フェアトレードマークが付いたものなどを除く)は、リ<br />
サイクル素材を利用したもの、もしくは適切に管理されたと認証された森林の木材を利<br />
用したものでなくてはならない。<br />
・決して意図的に不法伐採に関わってはならない。購入した木材製品が原産の段階で、<br />
法定最低であったことを確認する。<br />
・廃棄物が最小化され、適切にリサイクルが行われている。土壌汚染物質、大気汚染物<br />
廃棄物 質、水質汚染物質が効率的に管理されている。有害物質の緊急対応計画が整備されてい<br />
る。可能な限りリサイクル素材を用い、またリサイクル可能なものとする。<br />
包装 ・過剰・不必要に、包装や紙の消費が行われていない。リサイクル素材が適切に使用さ<br />
れている。<br />
自然保護<br />
・事業活動をモニタリングし、水、動植物、生産性の高い土地など希尐資源保護のた<br />
気候変動<br />
環<br />
境<br />
紙・木材<br />
め、必要に応じ修正を行う。<br />
サプライヤー及びその親会社が下記の活動に関わってはならない。<br />
・武器の製造<br />
・次の国々に対する武器の販売や輸出:組織的に市民に対する人権侵害を行っている<br />
国、内戦が行われている国、武力的な緊張状態にある国、武器の購入により地域の平和<br />
と安全が脅かされる国<br />
・タバコの製造と販売<br />
事業領域<br />
・WHOの行動規範に準拠しないベビーミルクの販売<br />
・FAOの農薬小売ガイドラインに準拠しない農薬の販売<br />
・資源採掘産業<br />
・アダルトエンターテイメントの製造、販売、放送<br />
・政治的活動とみなされるもの<br />
・その他オックスファムの活動の受益者の基本的権利を侵害するもの<br />
出所:オックスファム・GBウェブサイト7より作成<br />
前述の基本方針に加えて、「Product Approval Questionnaire」において、製品別に購買品に関<br />
する条件と関連情報が記されている。サプライヤーはこれらの条件を必ず満たさなくてはならない。<br />
最終的には、価格、倫理問題への対応、品質、環境影響の全てを考慮の上、調達を行うかどうか<br />
決定する 8 。<br />
7 http://www.oxfam.org.uk/resources/suppliers/ethicalpurchasing.html<br />
8 オックスファム・GBインタビュー<br />
286
図表 2 製品別の購買品条件と関連情報<br />
分野 条件・関連情報<br />
食物 フェアトレードマークが付いたもの。<br />
テキスタイル<br />
紙、板紙、木材製品<br />
油、ろう<br />
プラスチック製品<br />
フェトレード認証を受けた素材でできているもの。もしくは、リサイクル、リユース素材<br />
でできているもの。染料は植物染料か泥染料が望ましい。<br />
オックスファム・GBは、不法伐採、不法取引による木材製品の利用撤廃と、認証木<br />
材製品の購買増加を目指すUK Forest and Trade Networkに参加している。<br />
FSCのロゴが付いた製品が望ましいが、FSC製品が入手不可能な地域においては、<br />
フェアトレード製品も受け入れる。<br />
オックスファム・GBは、ヤシ油の持続的成長と持続的利用を目指す'RSPO:<br />
Roundtable on Sustainable Palm Oil(に参加している。<br />
リサイクル材料を含み、消費期間の長いもの。内分泌攪乱化学物質'EDCs:<br />
Endocrine Disrupting Chemicals(など、オックスファム・GBの「重要化学物質リスト」<br />
を含まないもの。<br />
金属、鉱物 リサイクル素材が望ましい。鉛など、環境や人体に有害な重金属を含まないもの。<br />
出所:オックスファム・GBウェブサイト9 より作成<br />
③ 具体的な流れ<br />
小売分野のサプライヤーとなるには、下記のプロセスのうち、1 から 7 を経る必要がある。さらに<br />
2 万 5,000 ポンド以上の場合はステップ 8、紙・木材製品のサプライヤーはステップ 9も必要となる。<br />
'5(収支と調達の実績<br />
図表 3 オックスファム・GBのサプライヤー行動規範<br />
1 オックスファムの倫理購買方針を熟読する<br />
2 Oxfam New Supplier Formを記入、返送する<br />
3 Oxfam Activities Ltd Agreementに署名する<br />
4 Oxfam's Trading Supplier Questionnaire - Ethicsを記入、返送する<br />
5 Homeworkers questionnaireを記入、返送する<br />
6 Oxfam Product approval questionnaireを記入、返送する<br />
7 SEDEX'Supplier Ethical Data Exchange(に参加する<br />
8 総額2万5,000~10万ポンドのサプライヤーはSedex SMETA Auditを行う<br />
9 木材供給源に関する情報を提供する<br />
出所:オックスファム・GBウェブサイト 10 より作成<br />
① オックスファム・インターナショナル<br />
2006/07 年のプログラム支出'管理費用を含まない(は、約 7 億 500 万ドルである分野別では、<br />
「緊急援助、安全」が 37%、「生活」が 24%、「人権」が 13%など、地域別では、アフリカと中東が<br />
9 http://www.oxfam.org.uk/resources/suppliers/downloads/blank_product_questionnaire_dec_07.doc<br />
10 http://www.oxfam.org.uk/resources/suppliers/ethical-requirements-sheet.html<br />
287
42%、アジアが 26%などとなっている。<br />
図表 4 オックスファム・インターナショナルの 2006/07 年の分野別支出内訳<br />
'単位:100万ドル(<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
緊<br />
急<br />
援<br />
助<br />
・<br />
安<br />
全<br />
生<br />
活<br />
人<br />
権<br />
288<br />
社<br />
会<br />
基<br />
サ<br />
ー<br />
本<br />
ビ<br />
的<br />
ス<br />
出所:オックスファム・インターナショナル「Annual Reports 2007」 11 より作成<br />
図表 5 オックスファム・インターナショナルの 2006/07 年の地域別支出内訳<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
② オックスファム・GB 12<br />
'単位:100万ドル(<br />
350<br />
50<br />
0<br />
中<br />
南<br />
米<br />
ア<br />
フ<br />
リ<br />
カ<br />
と<br />
中<br />
東<br />
東<br />
欧<br />
・<br />
旧<br />
ソ<br />
連<br />
ア<br />
ジ<br />
ア<br />
太<br />
平<br />
洋<br />
ア<br />
イ<br />
デ<br />
ン<br />
テ<br />
ィ<br />
テ<br />
ィ<br />
国<br />
内<br />
プ<br />
ロ<br />
グ<br />
ラ<br />
ム<br />
等<br />
出所:オックスファム・インターナショナル 「Annual Reports 2007」より作成<br />
20070/8 年の収入は約 2 億 9,970 万ポンド、支出は約 2 億 9,840 万ポンドであった。支出のうち、<br />
「プログラム活動費用」の内訳は、「開発プログラム」が 52%、「緊急援助」が 39%、「キャンペー<br />
ン」が 9%となっている。なお、企業などからの現物寄付は「寄付等」に収入として含まれている。調<br />
達の 3 分の 1 が製品、3 分の 2 がサービスである。オックスファムはオックスファムショップを運営<br />
しているため、2,000 という非常に数多くのサプライヤーから物品を購入している。英国企業が過<br />
半数を占め、日本企業からの購入はない。輸入品の多くはフェアトレード品である。また、中国か<br />
11 http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/OI-annual-report-2007-en_1.pdf<br />
12 http://www.oxfam.org.uk/resources/downloads/reports/report_acounts07_08.pdf<br />
そ<br />
の<br />
他
らの輸入もある 13 。<br />
図表 6 オックスファム・GBの 2007/08 年の収入<br />
'単位:100万ポンド(<br />
その他 9.8<br />
公的機関<br />
からの出資<br />
70.1<br />
289<br />
寄付等<br />
142.1<br />
事業収入<br />
77.7<br />
出所:オックスファム・GB「Annual Reports & Accounts 07/08」より作成<br />
図表 7 オックスファム・GBの 2007/08 年の支出<br />
'単位:100万ポンド(<br />
ファンド<br />
レイジング<br />
費用 23.5<br />
事業費用<br />
60.6<br />
その他 2<br />
プログラム<br />
活動費用<br />
212.3<br />
出所:オックスファム・GB「Annual Reports & Accounts 07/08」より作成<br />
図表 8 オックスファム・GBの収入'2007/08 年(のうち「寄付等」の内訳<br />
13 オックスファム・GBインタビュー<br />
'単位:100万ポンド(<br />
恒常的な寄付 59.0<br />
一般からの寄付、ファンドレイジングイベントなど 32.4<br />
災害緊急委員会'DEC:Disasters Emergency Committee) 19.5<br />
遺産 11.6<br />
DFID 10.4<br />
現物寄付 8.6<br />
サービス・施設の寄付 0.6<br />
合計 142.1<br />
出所:オックスファム・GB「Annual Reports & Accounts 07/08」より作成
③ 事例<br />
図表 9 オックスファム・GBの収入'2007/08 年(のうち「公的機関からの出資」の内訳<br />
'単位:100万ポンド(<br />
欧州連合 25.0<br />
他のオックスファム 14.6<br />
英国政府'DFID( 10.3<br />
他の国連機関 7.9<br />
英国以外の政府 5.5<br />
他の国際機関 3.7<br />
他の英国機関 1.5<br />
ビックロッタリーファンド 0.7<br />
国連難民高等弁務官事務所 0.5<br />
英国連邦教育基金 0.3<br />
英国政府'その他( 0.1<br />
合計 70.1<br />
出所:オックスファム・GB「Annual Reports & Accounts 07/08」より作成<br />
オックスファム・GBが「ルル・ワークス・トラスト」という企業から石けんを購入し、南部スーダン<br />
に配布している。この企業は、以前オックスファムの支援を受けた女性が運営しているもので、現<br />
地の素材を利用した、石けん、スキンケア製品などを製造している。<br />
'6(企業との連携<br />
① 基本方針<br />
民間企業は利益を上げるための組織と認識しており、BOPビジネスや Cause-Related<br />
Marketing に対して反対はしないが、公正なビジネスで、また長期的な開発につながるものである<br />
べきと認識している。オックスファム・GBは、先進国企業の消費者としてのBOPビジネスより、製<br />
造者として途上国の零細企業育成に、より関心がある。オックスファム・GBは貧困層への製品販<br />
売に関する経験は乏しいが、貧困層のビジネス促進については多くの経験がある 14 。<br />
オックスファム・GBは、民間企業に限らず、政府、市民団体など多くの外部組織とパートナーシ<br />
ップ形成している。特定のプロジェクトごとのパートナーシップ、貧困削減に向けた中長期の戦略<br />
的パートナーシップ、特定の目標に関する他の組織とのアライアンスという 3 つの方法があり、パ<br />
ートナーシップ形成の方針として、5 つの原則から成るパートナーシップ・ポリシー を設けている。<br />
また、民間企業とのパートナーシップの事例として、Marks & Spencer、Accenture などとの事例が<br />
ある。<br />
14 オックスファム・GBインタビュー<br />
290
補完的目的と付加価値<br />
図表 10 オックスファム・GBのパートナーシップ・ポリシー<br />
パートナーと目的を共有する。オックスファムは現地の団体の活動を<br />
置き換えるのではなく、補完する。<br />
価値観、信条の相互尊重 パートナーとの違いを認識しながらも、共通の価値を見つける。<br />
役割、責任、意思決定の明確性 良いコミュニケーションにより、パートナーとの信頼関係を構築する。<br />
透明性と説明責任 財務管理に真剣に取り組む。<br />
コミットメントと柔軟性 予算の制約の中で、長期の戦略パートナーシップの割合を高める。<br />
出所:オックスファム・GBウェブサイト 15 より作成<br />
Marks & Spencer<br />
Accenture<br />
図表 11 オックスファム・GBと企業のパートナーシップの事例<br />
企業 内容<br />
Marks & Spencerの洋服をオックスファムを通じてリサイクルすると、Marks<br />
& Spencerでの買物に利用できる5ポンド相当のバウチャーが付与される。<br />
オックスファムが北インドで実施している、小規模農家、漁業者への技術支<br />
援プログラムに、Accentureが寄付をしている。<br />
オックスファムと共同で、途上国の生活・労働環境改善に向けたキャンペー<br />
Co-operative Group ンを行っている。また、Co-operative Groupが携帯電話リサイクルキャン<br />
ペーンなどを実施し、集めた資金をオックスファムに寄付している。<br />
オックスファムの金融支援プログラムOxfam365に対しThe Vodafone<br />
The Vodafone Foundation<br />
Foundationが出資している。<br />
出所:オックスファム・GBウェブサイトより 16 作成<br />
Cause-Related Marketing は、うまく機能する場合もあるが、オックスファム・GBとしては、古い<br />
スキームであるという印象を持っており、それほど力を入れていない。むしろ、フェアトレードを通し<br />
て公正なビジネスの促進をする方が効果的ではないかと考えている。オックスファム・GBは、<br />
Cause-Related Marketing よりもフェアトレードが今後の主流となることを望んでいる。<br />
企業との連携事例として Marks & Spencer が挙げられるが、同社との関係は、当初はキャンペ<br />
ーンからスタートしたが、慎重に関係を構築した結果、このようなパートナーシップへと発展してい<br />
った。企業とNGOが良い関係を築くためには、組織のトップマネジメント層が深く関与することが<br />
大切と考えている。また、パートナーシップの一環として知り得たお互いの情報を守秘することは<br />
必須である。このほかオックスファム・GBは、特定の企業との連携を行う際、事前にその企業に<br />
ついて詳細に調査を行っているが、同時に企業側も提携するNGOを慎重にチェックすべきと考え<br />
ている 17 。<br />
② The Enterprise Development Programme'EDP(18<br />
アフリカ、アジア、南米の中小企業に投資し、栄養・健康・教育などの分野に関する起業や事業<br />
拡大を支援するプログラムである。ローンや補助金などの金銭的支援だけでなく、事業開発スキ<br />
15<br />
http://www.oxfam.org.uk/resources/accounts/downloads/partnership_policy.pdf<br />
http://www.oxfam.org.uk/resources/learning/partnershipevaluation/index.html<br />
16<br />
http://www.oxfam.org.uk/get_involved/companies/partners.html<br />
17<br />
オックスファム・GBインタビュー<br />
18<br />
https://www.oxfam.org.uk/donate/edp/index.html<br />
https://www.oxfam.org.uk/donate/edp/docs/edp_overview.pdf<br />
291
ルの提供も行い、30 社を支援することで合計 100 万人以上の貧困脱却に寄与することを目指して<br />
いる。個人や団体から集めた資金を元にポートフォリオ形式で運用しているが、2009 年 12 月の段<br />
階では出資者には金銭的リターンを得られない仕組みである。ただし今後は、本物の投資として<br />
出資者へ金銭的リターンを出せるようにすることを目指している 19 。<br />
投資家は、年 20 万ポンドを最低 2 年間出資し、ポートフォリオ全体に投資する「役員'Board<br />
member(」と特定のプロジェクトにのみ出資する「共同投資家'co-investor(」に大別される。役員<br />
会には、オックスファムのメンバーのほか、米国の投資ファンドテキサス・パシフィック・グループ'T<br />
PG(のメンバーなども参加している 20 。<br />
出資対象企業は、提案書をもとに、商業的可能性、女性の経済的自立や現地の経済活性化へ<br />
の貢献度などの観点から審査・選定され、「投資委員会'Investment Committee(」の推薦に基づ<br />
き、最終的に役員会が承認する。投資委員会には、オックスファムのメンバーのほか、シェル財団<br />
などのメンバーも参加している。<br />
2008/09 年に 6 つのプロジェクト、2009/10 年に 5 つのプロジェクトが開始され、これまでの投資<br />
総額は 150 万ポンドとなっている。プログラム全体としては 5 カ年の継続を予定している。プロジェ<br />
クトの主要事例として、スリランカにおける乳製品販売会社のケースがある。<br />
期間 2009/10年度から3年間<br />
図表 12 スリランカの乳製品販売会社のケース<br />
目的 ビジネス開発を通じた貧困の削減<br />
概要 北部スリランカにおける、女性経営の乳製品販売会社の育成<br />
企業名 Vavuniya District Livestock Breeders'Cooperative Societies Union Ltd'VLBCS(<br />
EDP貢献分 £125,000<br />
ローン運営者 FOSDO'マイクロファイナンスを手掛けるNGO(<br />
期待される効果 スリランカ教育省との契約獲得、家庭宅配サービスの開始、新製品販売促進などにより、売上を<br />
約8万ポンドから約60万ポンドに増加させ、マーケットシェアを30%から60%に拡大させる。<br />
出所:オックスファム・GBウェブサイト 21 より作成<br />
③ 日本企業との連携について<br />
オックスファム・GBで把握している限り、オックスファム・GBは日本企業からの物品調達は行っ<br />
ていない。日本に限らず特定の国の企業と活動を行う際は、基本的にその国のオックスファムを<br />
通して行うことになっている。ただし、オックスファム・GB とオックスファム日本が協力することは<br />
あり、またEDPに対してオックスファム日本から関心が寄せられていることから、今後何らかの形<br />
で連携することもあるかもしれない 22 。<br />
19 オックスファム・GBインタビュー<br />
20 https://www.oxfam.org.uk/donate/edp/docs/EDP_external_annual_review_single_pgs.pdf<br />
21 https://www.oxfam.org.uk/donate/edp/srilanka.html<br />
22 オックスファム・GBインタビュー<br />
292
'1(活動概要<br />
2.セーブ・ザ・チルドレン'Save the Children( 1<br />
全ての子どもが尊重される世界、全ての子どもが希望を持てる世界を目指し、緊急支援、教育、<br />
安全、健康、飢餓・栄養不良などの分野で、世界 120 カ国で活動を行っている。活動国は途上国<br />
に限らず、先進国では子育てに関するプログラムなどを実施している。法人や個人から広く募金を<br />
集めるとともに、国により、スポンサーシッププログラムの提供やグッズ販売などを行う加盟団体も<br />
ある。2008 年の収入の規模は世界全体で約 12 億 8,000 万ドルで、米国と英国の 2 カ国でその 6<br />
割以上を占めている。また分野別支出は「緊急援助」が 27%、「健康」が 23%、「教育」が 19%な<br />
どとなっている。<br />
'2(沿革<br />
第一次世界大戦後の 1919 年、オーストリアや東欧の子どもたちへの食糧援助を目的に、英国<br />
のエグランタイン・ジェブ'Eglantyne Jebb(氏により設立される。1923 年にジェブ氏が「the Rights<br />
of the Child」草案を作成、翌 1924年に国際連盟に採択される。多くの戦争や紛争を経て世界に活<br />
動が拡大し、1972 年にセーブ・ザ・チルドレン世界連盟が発足する。セーブ・ザ・チルドレン・ジャパ<br />
ンは 1986 年に設立された。<br />
'3(拠点と役割分担<br />
欧州 13 カ国、米州 7 カ国、アジア 4 カ国・地域など世界 29 カ国がセーブ・ザ・チルドレン世界連<br />
盟に加わっている。世界連盟の事務局は英国・ロンドンにあり、アドボカシー・オフィスをエチオピ<br />
ア・アディスアベバ、ベルギー・ブリュッセル、スイス・ジュネーブ、米国・ニューヨークの 4 カ所に構<br />
えている。活動は世界約 120 カ国で行っている。<br />
欧州<br />
図表 1 セーブ・ザ・チルドレン世界連盟加盟国・地域<br />
アイスランド、イギリス、イタリア、スイス、ドイツ、オランダ、スウェーデン、スペイン、<br />
デンマーク、ノルウェー、フィンランド、ルーマニア、リトアニア<br />
米州 米国、カナダ、グアテマラ、ドミニカ共和国、ホンデュラス、メキシコ、ブラジル<br />
大洋州 オーストラリア、ニュージーランド、フィジー<br />
アジア 韓国、日本、インド、香港<br />
中近東・アフリカ スワジランド、ヨルダン<br />
出所:セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンウェブサイト 2 より作成<br />
1 http://www.savethechildren.org<br />
2 http://www.savechildren.or.jp/about_sc/global_net.html<br />
293
'4(調達の仕組み<br />
① 基本方針<br />
セーブ・ザ・チルドレン世界連盟として共通化の方向に向かっているが、2009 年 12 月時点では、<br />
各国団体が個別に調達を行っている。基本的に活動を行う現地での調達を心がけており、企業か<br />
ら購入することも現物寄付を受けることもどちらもある。セーブ・ザ・チルドレン・US は、これまでワ<br />
クチンや医薬品の調達を行ってきていないが、今後これらの調達を開始する際には、WHOやユ<br />
ニセフの基準を参照するつもりである 3 。セーブ・ザ・チルドレン・UK は、オックスファムらと同様<br />
Inter Agency procurement group に参加している。<br />
'5(収支と調達の実績<br />
① セーブ・ザ・チルドレン世界連盟<br />
2008 年のセーブ・ザ・チルドレンの収入は、合計約 12 億 8,000 万ドルである。国別でみると、米<br />
国と英国で 6 割以上を占め、スウェーデン、ノルウェーなどがこれに続いている。また、収入・支出<br />
の内訳は下図の通りであり、より詳細な内訳は各国別で世界全体のデータはない 4 。<br />
'単位:100万ドル(<br />
500<br />
450<br />
400<br />
350<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
米<br />
国<br />
図表 2 各国セーブ・ザ・チルドレンの 2008 年の収入<br />
英<br />
国<br />
ス ウ ェーデン<br />
ノ<br />
ル<br />
ウ<br />
ェ<br />
ー<br />
オ<br />
ー<br />
ス<br />
ト<br />
ラ<br />
リ<br />
ア<br />
デ<br />
ン<br />
マ<br />
ー<br />
ク<br />
イ<br />
タ<br />
リ<br />
ア<br />
294<br />
フ<br />
ィ<br />
ン<br />
ラ<br />
ン<br />
ド<br />
オ<br />
ラ<br />
ン<br />
ダ<br />
出所:セーブ・ザ・チルドレン世界連盟ウェブサイト 5 より作成<br />
3 セーブ・ザ・チルドレン・US インタビュー<br />
4 セーブ・ザ・チルドレン・US インタビュー<br />
5 http://www.savethechildren.net/alliance/about_us/mission_vision/index.html<br />
韓<br />
国<br />
ス ペ イン<br />
カ<br />
ナ<br />
ダ<br />
ニ<br />
ュ<br />
ー<br />
ジ<br />
ー<br />
ラ<br />
ン<br />
ド<br />
日<br />
本<br />
そ の 他
図表 3 セーブ・ザ・チルドレン世界連盟の 2008 年の収入内訳<br />
'単位:%(<br />
財団等 4<br />
企業からの<br />
寄付 5<br />
その他 9<br />
企業からの<br />
現物寄付 4 小売業等から<br />
の収入 1<br />
寄付 31<br />
295<br />
政府からの<br />
資金提供 45<br />
出所:セーブ・ザ・チルドレン世界連盟ウェブサイト 6 より作成<br />
図表 4 セーブ・ザ・チルドレン世界連盟の 2008 年の支出内訳<br />
<br />
'単位:%(<br />
その他プログ<br />
ラム費用 5<br />
ファンドレイジ<br />
ング等 8<br />
一般管理費<br />
8<br />
国内<br />
プログラム 10<br />
ガバナンス 1<br />
海外<br />
プログラム 70<br />
子どもの<br />
貧困削減 4<br />
HIV/AIDS 5<br />
'単位:%(<br />
飢餓からの<br />
開放 5<br />
子どもの<br />
人権 3<br />
子どもの<br />
保護 11<br />
教育 19<br />
出所:セーブ・ザ・チルドレン世界連盟ウェブサイトより作成<br />
② セーブ・ザ・チルドレン・UK<br />
キャンペー<br />
ン等 2<br />
緊急援助 27<br />
健康 23<br />
'単位:%(<br />
ラテンアメリカ<br />
とカリブ海諸<br />
国 7<br />
オセアニア 1<br />
欧州 7<br />
北米 6<br />
アジア 38<br />
アフリカ 41<br />
2008/09 年の収入は約 2 億 1,600 万ポンド、支出は約 2 億 800 万ポンドであった。支出につい<br />
ては、「プログラム活動費用」の内訳は「飢餓」が 35%、「教育」が 26%、「保護」が 20%、「健康」<br />
が 13%、「キャンペーン等」が 6%となっている。なお、企業などからの現物寄付は収入に含まれて<br />
いる。<br />
6 http://www.savethechildren.net/alliance/about_us/mission_vision/index.html
図表 5 セーブ・ザ・チルドレン・UK の 2008/09 年の収入<br />
'単位:100万ポンド(<br />
小売収入 7.8<br />
296<br />
その他 5.0<br />
寄付等 203.2<br />
出所:セーブ・ザ・チルドレン・UK「Annual Reports 2008/09」 7 より作成<br />
図表 6 セーブ・ザ・チルドレン・UK の 2008/09 年の支出<br />
'単位:100万ポンド(<br />
ファンドレイジン<br />
グ費用 27.3<br />
ガバナンス費用<br />
1.0<br />
プログラム<br />
活動費用<br />
179.9<br />
出所:セーブ・ザ・チルドレン・UK「Annual Reports 2008/09」より作成<br />
図表 7 収入'2008/09 年(のうち「寄付等」の内訳<br />
'単位:1,000 ポンド(<br />
金品の寄付 56,299<br />
遺贈 15,589<br />
現物寄付 29,339<br />
各種機関からの補助金 101,979<br />
合計 203,206<br />
出所:セーブ・ザ・チルドレン・UK「Annual Reports 2008/09」より作成<br />
7 http://www.savethechildren.org.uk/en/54_9301.htm
③ 事例<br />
図表 8 「各種機関からの補助金」の内訳<br />
'単位:1,000ポンド(<br />
欧州委員会 21,202<br />
英国政府 18,145<br />
セーブ・ザ・チルドレン世界連盟 13,403<br />
米国政府 11,941<br />
国連 10,796<br />
スウェーデン政府 3,489<br />
オランダ政府 3,396<br />
デンマーク政府 1,853<br />
ノルウェー政府 1,242<br />
アイルランド政府 1,136<br />
オーストラリア政府 520<br />
日本政府 215<br />
カナダ政府 200<br />
他の政府 1,075<br />
英国地方自治体 1,192<br />
コミックリリーフ 988<br />
3 Disease funds 916<br />
テトララベル 865<br />
世界基金 684<br />
ロッタリーファンド 658<br />
ELMA Philanthropies 648<br />
赤十字国際委員会 505<br />
ビル&メリンダゲイツ財団 476<br />
企業基金 229<br />
その他 6,205<br />
合計 101,979<br />
出所:セーブ・ザ・チルドレン・UK「Annual Reports 2008/09」より作成<br />
セーブ・ザ・チルドレン・US は、P&Gが関与する財団「Greater Cincinnati Foundation」からの補<br />
助金をもとに、P&GからPURという浄水剤 100 万袋を 5 万ドルで購入した'1 袋当たり 5 セント( 8 。<br />
このほか、多くの企業から、製品・サービスの現物寄付を受けている。例えばマイクロソフトから、<br />
事務所などで使用するハードウェア、ソフトウェアの提供を受けており、ボストンコンサルティング<br />
から無料のコンサルティングサービスを提供されている 9 。<br />
'6(企業との連携<br />
① 基本方針<br />
セーブ・ザ・チルドレン世界連盟は、世界のより多くの子どもたちを保護・支援するため、企業と<br />
8 セーブ・ザ・チルドレン・US インタビュー<br />
9 http://www.savethechildren.net/alliance/corporate/index.html<br />
297
の有意義な対話を求めている 10 。セーブ・ザ・チルドレン・UK では、企業との連携について、商業パ<br />
ートナー、プロジェクトの直接サポート、ボランティア、スタッフによる資金集めという 4 つの方法を<br />
提示している 11 。セーブ・ザ・チルドレン・US は、パートナーシップを成功させるには、内部の強力な<br />
サポート、明確な事業戦略、企業システムの効率的な利用、従業員や消費者が関わった目標、内<br />
部と外部のコミュニケーションが必要と述べている。また、パートナーがお互いの期待値を見抜く<br />
こと、お互いの長所をよく見極めることも必要である 12 。<br />
② 外国企業の事例<br />
セーブ・ザ・チルドレンと企業とのパートナーシップの事例は下表の通り。<br />
P&G<br />
企業<br />
Johnson &<br />
Johnson<br />
図表 9 セーブ・ザ・チルドレンと外国企業のパートナーシップの事例<br />
298<br />
内容<br />
途上国の多くの女子生徒が、毎月生理の際に学校を欠席しているという現状に対し、「Protecting Futures」と<br />
題するプロジェクトにおいて、2006年以降、セーブ・ザ・チルドレン含む8つのパートナーと共同で、17カ国合計8<br />
万人の女子生徒に、性教育と行うとともに生理用品を現物寄付している [14] 。<br />
2004年にCSR活動の一環として、「Children’s Safe Water Program 'CSWP(」を開始。米国疾病管理予防セン<br />
ター'CDC(と共同開発した「PUR」という浄水剤を途上国に配布し、下痢などの疾病の緩和に努めている。米国NPO<br />
の国際人口サービス'PSI:Population Services International(も関与している [15] 。現地までの輸送はコスト負担も含<br />
めP&Gが担当し、配布はセーブ・ザ・チルドレンと現地NGOが行った。セーブ・ザ・チルドレンはPUR100万袋を5万ド<br />
ルで購入したが、このきっかけはP&G側の要請によるもの [16] 。<br />
2008年の四川大地震の際、セーブ・ザ・チルドレン、中国赤十字、ユニセフ、プロジェクトHOPEらと共同し、物資と金銭<br />
的な支援を行った。<br />
出所:各種資料を基に作成<br />
パートナーシップは、企業側からの働きかけによるものと、セーブ・ザ・チルドレン側からのもの<br />
とどちらの場合もある。企業が持つビジネスノウハウや研究開発スキル、市場調査スキルはNGO<br />
にとって有用であり、パートナーシップの成功に貢献する。一方で、企業側が製品の販売チャネル<br />
として、NGOに過度に期待しているケースもあり、お互いのニーズのすり合せが難しいという課題<br />
がある。また価格や品質の面でも、必ずしもNGOが求めるものを企業が提供できるとは限らない<br />
ため、NGOの中には、企業との連携に慎重になっているところもある。企業とNGOは異質の存在<br />
であり、NGOと企業の連携がうまくいっている場合は、企業の中にNGO出身者がいるというケー<br />
スが多い 13 。<br />
企業とNPOなどの団体が手を組み、製品・サービスなどを通じて社会や環境に貢献する活動<br />
から企業・団体・消費者それぞれがメリットを受けるコーズ・リレーテッド・ マーケティング<br />
'Cause-Related Marketing(については、社会問題に対する認知度を高めるという点で、一定の効<br />
10 http://www.savethechildren.net/alliance/corporate/index.html<br />
11 http://www.savethechildren.org.uk/en/8856.htm<br />
12 セーブ・ザ・チルドレン・US インタビュー<br />
13 セーブ・ザ・チルドレン・US インタビュー
果がある。一部の企業は、マーケティング手段として利用し過ぎているきらいがあるが、消費者は<br />
賢くなってきており簡単に見抜くことができると思う。むしろ、Cause-Related Marketing の利用によ<br />
って、消費者が離れてしまうのではないかと懸念している。BOPビジネス全般については、適切な<br />
製品を適切な方法で流通させるのであれば望ましいと思うが、貧困層のニーズに合わない製品を<br />
作って、売ろうとするのであれば賛成できない。企業によっては、GEのように、BOP製品は販売<br />
ではなく寄付するべきと述べている企業もある。また、北欧政府の中にはBOPビジネスに慎重に<br />
なっているところもある 14 。<br />
③ 日本企業の事例<br />
セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンと企業とのパートナーシップの事例は下表の通り。<br />
図表 10 セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンと日本企業等のパートナーシップの方法・例<br />
方法 内容 企業例<br />
スポンサー契約 企業がセーブ・ザ・チルドレンに定額寄付を行う。企業は、 IKEA<br />
セーブ・ザ・チルドレンの名称やロゴを用い、セーブ・ザ・ サンヨー食品株式会社<br />
チルドレンの活動を支援していることを対外的にアピールで サラヤ株式会社<br />
きる。<br />
株式会社イデアインターナショナル<br />
ファンドネット証券株式会社<br />
株式会社ホテルオークラ東京<br />
ライセンス契約 企業がセーブ・ザ・チルドレンに定額寄付を行う。企業は、<br />
株式会社レモール<br />
セーブ・ザ・チルドレンのロゴやオリジナル・キャラクター<br />
オゴー産業株式会社<br />
を利用した商品を製造・販売できる。<br />
事業支援契約 企業がセーブ・ザ・チルドレン特定の事業の一部または全部<br />
をサポートする。<br />
299<br />
株式会社ファミリーマート<br />
株式会社クリード<br />
共同事業契約 企業とセーブ・ザ・チルドレンが共同で特定の事業を行う。 株式会社INAX<br />
(水環境についての環境教育)<br />
イベント・<br />
プロモーション契約<br />
協働ファンド<br />
レージング活動<br />
企業が行うイベントなどの収益金の一部また全部をセーブ・<br />
ザ・チルドレンに寄付する。<br />
企業の発行するポイントやマイルを顧客がセーブ・ザ・チル<br />
ドレン寄付し、セーブ・ザ・チルドレンが利用する。<br />
現物支給 企業が、自社の製品やサービスをセーブ・ザ・チルドレンに<br />
現物で寄付する。<br />
募金箱 企業が店頭に募金箱を設置し、顧客にセーブ・ザ・チルドレ<br />
ンへの寄付を促す。<br />
MHD ディアジオ モエ ヘネシー株式会社<br />
タリーズコーヒージャパン株式会社<br />
KDDI株式会社<br />
ノースウェスト航空<br />
株式会社小森コーポレーション<br />
株式会社ボストンコンサルティンググループ<br />
株式会社ファミリーマート<br />
サトレストランシステムズ株式会社<br />
従業員参画型活動 従業員が寄付を行う、ボランティアとして活動するなど。 松下電器産業株式会社<br />
株式会社リコー<br />
出所:セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンのウェブサイト 15 より作成<br />
14 セーブ・ザ・チルドレン・US インタビュー<br />
15 http://www.savechildren.or.jp/partnership/par_company/com_support/index.html
'1(活動概要<br />
3 国境なき医師団'MSF:Medecins Sans Frontieres( 1<br />
被災地、紛争地、難民キャンプなどに、医師や看護師を派遣し、現地政府やスタッフとともに緊<br />
急医療活動等を行う。2008 年度時点で、世界 65 か国以上に 4,600 人以上のスタッフを派遣してい<br />
る。また現地情報の発信を通じて、人権問題などに関する啓発活動も行っている。2007 年の収入<br />
は約 5 億 9,300 万ユーロである。<br />
'2(沿革<br />
1971 年に、医師とジャーナリストらによりフランスで設立される。1972 年にニカラグアの地震に<br />
対し初の緊急援助を実施し、以降、世界の震災被災地や紛争地に援助活動を拡大していく。1980<br />
年以降、フランス国外に支部が設立され、1990 年にMSFインターナショナルが発足する。日本に<br />
おいては、1992 年に事務局が開設された後、1997 年に日本支部が設立された。1999 年、それま<br />
での功績が評価されノーベル平和賞を受賞した。<br />
'3(拠点と役割分担<br />
世界 19 カ国に支部があり、オペレーション支部とパートナー支部とに分かれている。オペレーシ<br />
ョン支部が医療援助プログラムを担当し、パートナー支部は活動参加者の募集、広報活動、資金<br />
援助などを行っている。19 の全てが支部であり、本部は存在しない。また、救援物資の品質を確<br />
保し、迅速に供給できるように、フランスとベルギーに独自の物資調達センターを持ち、医薬品、<br />
ワクチン、食品、医療機器などについて、購入、保管、配送まで一貫して手掛けている。<br />
図表 1 国境なき医師団の支部<br />
オペレーション支部 フランス、ベルギー、オランダ、スイス、スペイン<br />
パートナー支部<br />
英国、イタリア、オーストリア、ギリシャ、スウェーデン、デンマーク、ドイツ、<br />
ノルウェー、ルクセンブルグ、日本、香港、オーストラリア、カナダ、米国<br />
出所:国境なき医師団日本ウェブサイト 2 より作成<br />
1 http://www.msf.org<br />
2 http://www.msf.or.jp/about/about.html<br />
300
'4(調達の仕組み<br />
① 医薬品の調達方針 3<br />
MSFへの医薬品サプライヤーとなるには、下記 2 つの手順からなるMSF認証スキーム'MSF<br />
Qualification Scheme(を満たさなくてはならない。ただしWHOのGMPについては、検査の重複を<br />
防ぐため、過去 24 ヶ月以内に行われたWHO等の検査結果により省略される場合がある。<br />
� WHOの医薬品適正製造基準'GMP(の準拠を確認するための、製造工場検査<br />
� 関連書類のアセスメント<br />
原則として全ての医薬品メーカーはMSFサプライヤーとして名乗りを上げることができる。MS<br />
F認証スキームの詳細を読み、製造者情報書類'MIF:Manufacturer Information File( 4 に記入し、<br />
パリの MSF International Pharmaceutical Coordination まで電子メールまたは郵便で送付する。た<br />
だし、MSFは 27 分野約 500 種の医薬品のみを扱っているため、それ以外のものは調達の対象外<br />
となる。<br />
この他、WHOの医薬品事前承認プログラム'Prequalification of Medicines Program(に認証さ<br />
れたもの、または規制の厳しい国で認証されたものは自動的にMSFに認証される。つまり下記の<br />
3 つ医薬品が調達の対象となる。<br />
� WHOの認証を受けた製品<br />
� 規制に厳しい国で登録されている製品 5<br />
� WHO GMPを満たし、かつMSFの審査を通った製品<br />
'5(収支と調達の実績<br />
① 2007 年の収支<br />
国境なき医師団の 2007 年の収入は約 5 億 9,300 万ユーロ、支出は約 5 億 7,700 万ユーロであ<br />
った。<br />
3 http://www.msf.org/msfinternational/content/medical/pharmaceutical/index.cfm?&mode=view<br />
http://www.msf.org/msfinternational/invoke.cfm?objectid=5C7D4794-5056-AA77-6C0D63CF9A18661E&comp<br />
onent=toolkit.article&method=full_html&mode=view<br />
4 http://www.msf.org/source/pharma/documentation/MIF.doc<br />
5 具体的な国名の記載がないが、MFS QS は欧州、英国、米国の薬局方を参照している<br />
301
図表 2 国境なき医師団の 2007 年の収入<br />
'単位:100万ユーロ(<br />
民間機関 79.8<br />
公的機関 54.2<br />
302<br />
その他 19.8<br />
個人 438.9<br />
出所:Médecins Sans Frontières International Financial Report 2007 6 より作成<br />
図表 3 国境なき医師団の 2007 年の支出内訳<br />
<br />
'単位:100万ユーロ(<br />
マネジメント<br />
32.8<br />
ファンドレイジ<br />
ング 76.9<br />
税金 0.1<br />
社会ミッション<br />
活動 467.6<br />
'単位:100万ユーロ(<br />
出版 11.0<br />
コミュニケー<br />
ション 20.1<br />
専門サービス<br />
12.3<br />
ロジスティク<br />
ス・公衆衛生<br />
23.3<br />
広告費 38.7<br />
医薬品・栄養<br />
78.6<br />
出所:Médecins Sans Frontières International Financial Report 2007 より作成<br />
事務所費 25.0 その他 27.3<br />
旅費・交通費<br />
69.7<br />
図表 4 国境なき医師団の 2007 年の収入のうち「公的機関」の内訳<br />
'単位:100万ユーロ(<br />
EU非加盟<br />
欧州政府<br />
11.7<br />
EU加盟<br />
欧州政府<br />
33.3<br />
その他 0<br />
欧州委員会人道<br />
援助局、欧州連<br />
盟機関 4.8<br />
米国政府 2.7<br />
国連機関 1.7<br />
出所:Médecins Sans Frontières International Financial Report 2007 より作成<br />
6 http://www.msf.org/source/financial/2007/MSF_Financial_Report_2007.pdf<br />
人件費 271.2
'6(企業との連携<br />
① 顧みられない病気のための新薬イニシアティブ'DNDi:Drugs for Neglected Diseases initiative( 7<br />
1999 年のノーベル平和賞の賞金をもとに、オズワルド・クルーズ財団'ブラジル(、ケニア中央<br />
医学研究所、インド医学研究評議会、マレーシア保健省、パスツール研究所'フランス(、国境なき<br />
医師団、国連熱帯病研究訓練特別計画の 7 機関により、2003 年に設立された。アフリカ睡眠病、<br />
内臓リーシュマニア症、シャーガス病、マラリアといった感染症の新薬開発を目的に、2014 年まで<br />
に 6-8 種の治療方法を確立することを目指している。サノフィ・アベンティス社と共同で、抗マラリア<br />
合剤を開発するなど、民間製薬会社や公的機関とのパートナーシップを結んでいる。スイス・ジュ<br />
ネーブを拠点とし、このほかに、米国、ケニア、インド、ブラジル、マレーシア、コンゴ、日本に事務<br />
所を構えている。<br />
② 日本企業の事例<br />
国境なき医師団日本のホームページにおいて、長期的に寄付を行うコーポレートサポータプロ<br />
グラム、寄付、イベント協賛、マッチングギフトなどが方法として記されている。 8<br />
図表 5 国境なき医師団日本と日本企業のパートナーシップの方法<br />
方法 内容 企業例<br />
コーポレート<br />
サポータープログラム<br />
HIV/エイズなど、国境なき医師団が長期的に関わるプログラムに、<br />
年単位で寄付を行う。1口500万円から。<br />
303<br />
株式会社シグマ<br />
銀座ステファニー化粧品株式会社<br />
イベント等への協賛 国境なき医師団が主催するイベント等に協賛する。 株式会社小学館<br />
株式会社公文教育研究会<br />
日本ヒューレット・パッカード株式会社<br />
社団法人日本医師会<br />
寄贈 [8] 企業が、自社の製品やサービスをセーブ・ザ・チルドレンに現物で寄<br />
付する。<br />
マッチングギフト 企業の発行するポイントを顧客が国境なき医師団に寄付し、国境な<br />
き医師団が利用する。<br />
随時の寄付 クレジットカード、郵便払込、銀行振替で任意の金額を寄付する。<br />
1日50円キャンペーン 1日当たり50円'一月1,500円(もしくは任意の金額を、金融機関の<br />
口座振替などを利用し、毎月継続的に寄付する。<br />
出所:国境なき医師団日本のウェブサイト9 より作成<br />
7 http://www.dndi.org/<br />
8 MSF が「寄贈」という単語を用いている<br />
9 http://www.msf.or.jp/donate/corporate.html<br />
http://www.msf.or.jp/donate/corporate3.html<br />
マイクロソフト株式会社<br />
日本ヒューレット・パッカード株式会社<br />
ノースウエスト航空会社<br />
株式会社リコー<br />
など<br />
多数
'1(活動概要<br />
4. マリー・ストープス・インターナショナル<br />
'Marie Stopes International( 1<br />
望まない妊娠・出産を防ぐという目的に向けて、世界の貧困層に対して、家族計画、中絶、母子<br />
の健康、HIVなど、リプロダクティブ・ヘルス'性と生殖(に関するプログラムを手掛けている。家族<br />
計画については、各種避妊具と正しい知識の提供を行い、中絶については、クリニックを運営し安<br />
全な施術を行うとともに、金銭的理由で手術を選択できない人々が危険な中絶方法で命を落とす<br />
ことを防ぐために、中絶ピルに関するソーシャル・マーケティングなどを行っている。クリニックの収<br />
益構造は、英国など先進国や途上国の都市部で患者から対価を受け取り、得られた利益を用い<br />
て、途上国の農村部などでサービスを無料で提供するという形となっている。2007 年の収入は約<br />
7,940 万ポンドである。<br />
(2)沿革<br />
1921 年に英国の医師マリー・ストープ氏が、英国で初めて、家族計画に関するクリニックを開設<br />
する。50 年以上の英国内での活動の後、1976 年にティム・ブラック氏らが、同様のサービスをグロ<br />
ーバルに手掛けることを目的に、マリー・ストープス・インターナショナルを設立する。その後、アイ<br />
ルランド、スリランカ、ケニアなどにに相次いで海外にクリニックを開設する。現在の活動国数は<br />
42 カ国である。<br />
(3)拠点と役割分担<br />
アフリカ、アジア太平洋、欧州など世界 42 カ国で活動し、クリニックの数は合計 572 にのぼる。<br />
ロンドンのサポートオフィスにおいて、キャパシティビルディング、テクニカルアシスタントなど、マリ<br />
ー・ストープス・インターナショナル全体のパートナーシップ促進と経験共有のためのサポート活動<br />
を行い、オーストラリア・メルボルンのサポートオフィスにおいて、主にアジア太平洋地域のための<br />
活動を行っている。この他、ベルギー・ブリュッセルにアドボカシー・オフィスを構え、EUの政策決<br />
定者にリプロダクティブ・ヘルスに関する情報発信を行っている。また、米国のファンドレイジング・<br />
オフィスにおいて、ドナーへの情報提供を行っている。<br />
1 http://www.mariestopes.org<br />
304
(4)調達の仕組み<br />
企業選定の前提として、国連のブラックリストに該当する企業や、違法行為や財務上の問題が<br />
ある企業とは取引を行わない。このほか、医薬品についてはWHOのGMPを満たしている製品、<br />
医療機器についてはISOを満たす製品など、個別に条件を定めている。<br />
基本的に活動を行う現地での調達を心がけているが、求める水準の製品を現地で調達できな<br />
い場合は他国から輸入を行う。例えばアフリカでは、施術に必要な高品質の鉄製の道具を調達す<br />
ることが難しいため、パキスタンで製造されたものを輸入している。このパキスタンの製造工場は、<br />
価格と品質だけでなく、注文と生産の柔軟性という観点からも、マリー・ストープスにとって非常に<br />
優れたサプライヤーである。手術用手袋など一般的な製品は入札で購入しているが、施術に必要<br />
な道具で一般に市場に出回っていないものについては、マリー・ストープスが独自に開発を行って<br />
いる。オックスファムらと同様 Inter Agency procurement group に参加している 2 3 。<br />
'5(収支と調達の実績<br />
① 2007 年の収支<br />
マリー・ストープス・インターナショナルの 2007 年の収入は約 7,940 万ポンド、支出は約 6,640 万<br />
ポンドであった。支出のプロジェクト活動費用の内訳は、「家族計画とリプロダクティブ・ヘルス」が<br />
86%、「啓発運動」が 5%、キャパシティビルディングが 9%であった。収入のうち寄付によるものの<br />
割合が小さいが、これは、寄付金募集のための費用を考慮し、寄付金募集に力を費やしていない<br />
ためとのことである 4 。<br />
2 マリー・ストープスの調達担当者によれば、Inter Agency procurement group は基本的に英国拠点の団体のネッ<br />
トワークであるため、国境なき医師団が参加していないのは、調達拠点を英国に持たないためではないかとの<br />
こと。プラン・インターナショナルについては明確な理由は分からないが、Inter Agency procurement group に参<br />
加するためには、定例の会議参加などが伴われるため、様々な事情を考慮の上現在のところは参加を見合わ<br />
せているのではないかとのこと。<br />
3 マリー・ストープス・インターナショナルインタビュー<br />
4 マリー・ストープス・インターナショナルインタビュー<br />
305
図表 1 マリー・ストープス・インターナショナルの 2007 年の収入<br />
'単位:100万ポンド(<br />
患者からの<br />
対価<br />
46.7<br />
投資収入 1.0<br />
その他 3.6<br />
306<br />
寄付等 0.1<br />
補助金 27.9<br />
出所:マリー・ストープス・インターナショナル「Financial statements」 5 より作成<br />
図表 2 マリー・ストープス・インターナショナルの 2007 年度の支出<br />
'単位:100万ポンド(<br />
ガバナンス<br />
費用 0.1<br />
ファンドレイ<br />
ジング費用<br />
0.0<br />
プログラム<br />
活動費用 66.2<br />
出所:マリー・ストープス・インターナショナル「Financial statements」より作成<br />
図表 3 2007 年の収入のうち補助金の内訳<br />
'単位:100万ポンド(<br />
英国国際開発省 946<br />
欧州連合 2,551<br />
国連'国連人口基金( 1,071<br />
パッカード財団 445<br />
ドイツ復興金融公庫 1,000<br />
オランダ外務省 363<br />
フィンランド外務省 238<br />
英国内の財団等 1,154<br />
海外の財団等 19,959<br />
その他 193<br />
合計 27,920<br />
出所:マリー・ストープス・インターナショナル「Financial statements」より作成<br />
5 http://www.mariestopes.org/documents/Financial-Statements-2007.pdf
② 事例<br />
性感染病予防と家族計画のため、避妊具メーカーとソーシャルマーケティングを行っている。既<br />
存製品のマーケティングだけでなく、フィジーの「Try Time」、ウガンダの「Lifeguard」'コンドーム(な<br />
ど、製品の共同開発も行った。マリー・ストープスが使用している避妊具のリストは下表の通り。<br />
図表 4 マリー・ストープスが利用している避妊具のブランド<br />
国 製品 ブランド<br />
コンドーム Aramish<br />
アフガニスタン<br />
避妊ピル<br />
避妊注射<br />
Aramish Feminyl<br />
Aramish Femiject<br />
子宮内避妊器具 Aramish FemIT<br />
オーストラリア コンドーム Snake<br />
For You<br />
コンドーム<br />
For You More<br />
Adore<br />
アルバニア<br />
避妊ピル Sigorol<br />
緊急避妊ピル Postinor 2<br />
避妊注射 Depo Provera<br />
妊娠検査薬 No brand name<br />
コンドーム<br />
Thril<br />
Fire<br />
避妊ピル Kushi - Oral Contraceptive Pill<br />
インド<br />
避妊注射 Kushi Injectable<br />
子宮内避妊器具 Kushi IUD<br />
医療中絶 Kushi<br />
妊娠検査薬 Kushi Pregnancy Test Strips<br />
ケニア<br />
コンドーム<br />
Raha Non Scented<br />
Raha Scented<br />
緊急避妊ピル Smart Lady<br />
マラウイ コンドーム Manyuchi<br />
Prudence Clasico (3 & 100)<br />
メキシコ<br />
コンドーム<br />
Prudence Aroma (3 & 100)<br />
Frenzy<br />
注)メキシコで売られ てい<br />
Economix<br />
る の は 全 て DKTと い う ブラ<br />
ンドのもの<br />
モンゴル<br />
デンタルダム Hoja de Latex<br />
緊急避妊ピル<br />
コンドーム<br />
307<br />
Postinor<br />
Postinor 2<br />
Trust<br />
Trust Single<br />
Trust Strawberry<br />
Trust Orange<br />
Trust Banana<br />
Frenzy Menthol<br />
Lady Trust (female condom)<br />
避妊ピル Feminyl<br />
避妊ピル Sure<br />
ミャンマー<br />
緊急避妊ピル Pregnon<br />
避妊注射 Sure Injectable<br />
Cool Ryder<br />
ナミビア コンドーム<br />
Cool Ryder Smooth<br />
Life’s Choice<br />
Femidon (female condom)<br />
ネパール<br />
コンドーム<br />
避妊ピル<br />
Jodi Gold<br />
Feminyl<br />
パキスタン<br />
コンドーム<br />
ExcITe<br />
Xtacy<br />
妊娠検査薬 Xact<br />
フィジー コンドーム Try-Time<br />
スリランカ<br />
コンドーム<br />
避妊ピル<br />
Sathuta<br />
Romantic and Maximum (supplier’s brand)<br />
Feminyl<br />
緊急避妊ピル Pregnon<br />
タンザニア<br />
コンドーム<br />
Raha Scented<br />
Lifeguard<br />
妊娠検査薬 Jibu Hakika Pregnancy Test Strips<br />
ウガンダ<br />
コンドーム<br />
Lifeguard Blue<br />
Liefguard Pink<br />
妊娠検査薬 Easy Life Pregnancy Test Strips<br />
コンドーム<br />
Thiqah<br />
Protec<br />
イエメン<br />
避妊ピル Protec<br />
避妊注射 Protec Injectable<br />
子宮内避妊器具 Protec IUD<br />
出所:マリー・ストープスのウェブサイト6より作成<br />
6 http://www.mariestopes.org/Health_programmes/Family_planning/Social_marketing/Products_%5E_brands.aspx
'6(企業との連携<br />
① ソーシャルフランチャイジング'Blue Star ブランド(<br />
より多くの人に質の高い医療サービスを届けるため、直接運営するクリニックとは別に、Blue<br />
Star というブランドを用い、既存の民間のクリニックや薬局のフランチャイズ化を行っている。ケニ<br />
アで 2004 年に開始されたもので、2009 年 9 月の段階で、8 カ国、合計 931 のクリニックや薬局が<br />
フランチャイズに参加している。Blue Star というブランドを利用するには、医療器具の品質やスタッ<br />
フの技能について、マリー・ストープスの定める一定の基準を満たさなくてはならない。また、基準<br />
を満たしているかどうか、チェックされている 7 。<br />
② バウチャースキームモデル<br />
図表 5 Blue Star ブランドを掲げたクリニック・薬局数<br />
国名 クリニック・薬局数<br />
エチオピア 209<br />
ケニア 186<br />
パキスタン 100<br />
フィリピン 110<br />
ガーナ 99<br />
シエラレオネ 88<br />
ベトナム 79<br />
マラウイ 60<br />
合計 931<br />
出所:マリー・ストープス・インターナショナルへのインタビューより作成<br />
貧しい人々に、質の高い医療サービスを受けるためのバウチャーを配布するという活動も行っ<br />
ている。例えば、5 ドルのバウチャーで、マリー・ストープスが認定した医療機関で安全に出産をす<br />
ることができる。将来的には、Blue Star ブランドとこのバウチャースキームモデルを組み合わせた<br />
ビジネスモデルとすることを計画している 8 。<br />
7 マリー・ストープス・インターナショナルインタビュー<br />
8 マリー・ストープス・インターナショナルインタビュー<br />
308
'1(活動概要<br />
5 プラン'Plan( 1<br />
子どもの人権向上と貧困の削減のため、教育、健康、水・衛生、保護、経済的安定、緊急支援、<br />
子どもの参画、性に関する健康という 8 つの分野について、世界 48 カ国で活動を行っている。活<br />
動国の子どもや住民と、手紙などを通じ交流できる、スポンサーシップ制度を設けているのが特<br />
徴で、この他、国によって商品販売なども行っている。2007/08 年の収入は約 4 億 7,400 万ユーロ<br />
である。<br />
'2(沿革<br />
1937 年に英国人ジャーナリスト John Langdon-Davies 氏らによって、スペイン内戦で被災した子<br />
どもへの緊急援助を目的に「Foster Parents Plan for Children in Spain」として設立される。第二次<br />
世界大戦中、支援の対象を欧州の広域と中国にまで広げ、1950 年代からは、戦争の被災児に限<br />
らず、世界の開発途上国の子どもの支援を開始する。1970 年代に「Plan International」と名称を変<br />
更、1980 年代にベルギー、ドイツ、日本など多くの国が活動に加わり、活動が世界的に広がって<br />
いった。<br />
'3(拠点と役割分担<br />
欧州 12、アジア・太平洋 5、米州 4 の計 21 カ国で資金を調達し、アフリカ 23 カ国、アジア 13 カ<br />
国、アメリカ大陸 12 カ国の計 48 カ国で支援活動を行っている。本部は英国である。<br />
欧州<br />
図表 1 プランの支援国・地域<br />
英国、アイルランド、オランダ、スウェーデン、デンマーク、ドイツ、<br />
ノルウェー、フランス、ベルギー、フィンランド、スペイン、スイス、<br />
アジア・太平洋 オーストラリア、韓国、日本、香港、インド<br />
アメリカ大陸 米国、カナダ、コロンビア、ブラジル<br />
出所:プラン・インターナショナルウェブサイト 2 より作成<br />
図表 2 プランの活動国<br />
東南アジア インドネシア、タイ、中国、フィリピン、ベトナム、カンボジア、東ティモール、ラオス<br />
南アジア インド、スリランカ、ネパール、パキスタン、バングラデシュ<br />
アフリカ<br />
中南米<br />
ウガンダ、エジプト、エチオピア、ガーナ、カメルーン、ギニア、ギニアビサウ、ケニア、ザンビ<br />
ア、ジンバブエ、スーダン、セネガル、タンザニア、トーゴ、ブルキナファソ、ベナン、マラウィ、<br />
マリ、シエラレオネ、ニジェ-ル、モザンビーク、ルワンダ、リベリア<br />
エクアドル、エルサルバドル、グアテマラ、コロンビア、ドミニカ共和国、ニカラグア、ハイチ、<br />
パラグアイ、ブラジル、ペルー、ボリビア、ホンジュラス<br />
出所:プラン・ジャパンウェブサイト 3 より作成<br />
1 http://plan-international.org<br />
2 http://plan-international.org/where-we-work/fundraising-countries<br />
309
'4(調達の仕組み<br />
供給のスピードや価格といったロジスティクス上の観点、またメンテナンスなどを考慮した結果、<br />
活動に必要な物資は基本的に活動を行う現地で調達している。企業からの購入の場合も、現物<br />
寄付による場合も双方ある。活動国'いわゆる途上国(のサプライヤーに対して、要請事項をプラ<br />
ン・インターナショナル共通で設けている。WFPを通じて食品を調達するなど、食品や医薬品は国<br />
連機関経由で購入することが多い 4 。<br />
'5(収支と調達の実績<br />
① 2007 年度の収支<br />
プラン・インターナショナルの 2007/08 年の収入は約 4 億 7,400 万ユーロ、支出は約 4 億 4,200<br />
万ユーロであった。プログラム活動の支出内訳は、食料援助、医療健康などが 15%、教員指導、<br />
教育施設建設などが 17%、水供給施設建設などが 11%などとなっている。なお、現物寄付は収<br />
入として扱われている。<br />
図表 3 プラン・インターナショナルの 2007/08 年の収入<br />
'単位:100万ユーロ(<br />
補助金など<br />
90.5<br />
現物寄付 11.2<br />
その他寄付<br />
30.6<br />
310<br />
事業収入 4.3<br />
チャイルドス<br />
ポンサーシッ<br />
プによる収入<br />
333.2<br />
投資による<br />
収入 4.0<br />
出所:プラン・インターナショナル 「Plan International Worldwide Combined Financial<br />
Statements For the year ended 30 June 2008」 5 より作成<br />
3 http://www.plan-japan.org/country/1140.html<br />
4 プラン・ジャパンインタビュー<br />
5 http://plan-international.org/files/global/publications/about-plan/PlanReportandAccounts2008.pdf
図表 4 プラン・インターナショナルの 2007/08 年の支出<br />
'単位:100万ユーロ( 外国為替<br />
による損失<br />
10.9<br />
その他<br />
活動費用 40.1<br />
ファンドレイ<br />
ジング費用<br />
47.2<br />
311<br />
プログラム<br />
活動費用<br />
339.5<br />
事業支出 3.9<br />
出所:プラン・インターナショナル「Plan International Worldwide Combined Financial<br />
Statements For the year ended 30 June 2008」より作成<br />
図表 5 2007/08 年の支出のうちプログラム活動費用の内訳<br />
'単位:%(<br />
事務所家賃、機<br />
器購入、専門<br />
サービスなど<br />
11%<br />
現場のプログラ<br />
ム管理費用 20%<br />
スポンサーと<br />
チャイルドの関<br />
係構築など 15%<br />
その他 6%<br />
食料援助、医療<br />
健康など 15%<br />
教員指導、教育<br />
施設建設など<br />
17%<br />
水供給施設等建<br />
設など 11%<br />
金融、職業訓練<br />
など 5%<br />
出所:プラン・インターナショナル「Plan International Worldwide Combined Financial<br />
Statements For the year ended 30 June 2008」より作成<br />
図表 6 プラン・インターナショナルの 2007/08 年の支出分野別内訳<br />
(単位:100万ユーロ)<br />
プロジェクト支払い 155.3<br />
人件費 110.3<br />
マーケティング、メディア 40<br />
交通費 24.4<br />
物資、自動車、その他事務費用 24.2<br />
コンサルタントなど費用 21.1<br />
その他人件費 19.5<br />
通信費 16.7<br />
家賃等 12.2<br />
外国為替による損失 10.9<br />
減価償却費 6.9<br />
合計 441.6<br />
出所:プラン・インターナショナル「Plan International Worldwide Combined Financial<br />
Statements For the year ended 30 June 2008」より作成
'6(企業との連携<br />
① プラン・インターナショナルの基本方針 6<br />
武器、兵器、タバコ、アルコールの製造会社とはパートナーシップを結ばない。また、下記の 4<br />
つの条件に当てはまる企業からの支援は受け入れない。さらに、連携企業は企業の社会的責任<br />
及びに対するコミットメントを表明するとともに、プランの掲げる使命・価値観を支持しなくてはなら<br />
ない。<br />
・人権、特に子どもの人権を侵害している<br />
・認識の上で継続的に人権を犯し、子どもに危害を加えている<br />
・人権、環境、財務に関する国際的基準に違反し、法的措置を取られている<br />
・国際基準の違反が頻繁に起こる分野について、活動の透明性が欠けている<br />
具体的連携方法としては 4 つの方法がある。プロジェクトの実施の際、現地NGOと連携するこ<br />
とが多くあるが、あくまでもプロジェクトのオーナーシップはプランにある 7 。なお、企業との連携の<br />
際は、企業の本社所在地国の支部と行うことになっている 8 。<br />
長期戦略<br />
パートナーシップ<br />
図表 7 プラン・インターナショナルと企業のパートナーシップの方法<br />
開発問題を解決するための<br />
革新的パートナーシップ<br />
世界・国・地域規模での<br />
ファンドレイジング/マーケティング/<br />
コミュニケーションパートナーシップ<br />
企業の持つ製品、コミュニケーションチャネル、知識などを<br />
活用し、共通の目標達成に向け協働する。<br />
民間企業の技術・システム開発のスキルを活用し、開発問題の解決に<br />
役立てる。浄水器による安全な水供給、タンザニア農村地域での太陽<br />
光発電による電気供給など [9] 。<br />
プランが実施するプロジェクトに企業が出資する。プランで<br />
は、出資者に正確な報告を行うため、全てのプロジェクトに<br />
ついて、投資対効果の詳細な分析を行っている。<br />
技術移転と従業員のエンゲージメント<br />
企業の従業員をプランに派遣し、各種スキルを活用する。<br />
によるパートナーシップ<br />
出所:プラン・インターナショナルのウェブサイト9 より作成<br />
② プラン・ジャパンの事例<br />
プラン・ジャパンでは、企業との提携にあたり、会計報告の徹底などを通じてプロジェクトの透明<br />
性を高めることを心がけている。寄付の方法として、特定のプロジェクトに 500 万円程度のまとまっ<br />
た金額を寄付する「特別プロジェクト 10 」というものがあるが、このような連携のきっかけは、何らか<br />
6 http://plan-international.org/what-you-can-do/corporate-partnerships/corporate-partnerships-policy<br />
7 プラン・ジャパンインタビュー<br />
8 http://plan-international.org/what-you-can-do/corporate-partnerships/start-a-partnership-with-plan<br />
9 http://plan-international.org/what-you-can-do/corporate-partnerships/how-plan-works-with-companies<br />
10 http://www.plan-japan.org/join/1213.html<br />
312
の形でプランの活動を知った企業からのアプローチによるものが多い 11 。この特別プロジェクトで<br />
は、企業側が提供するのは金銭のみである。特別プロジェクトを含めたプラン・ジャパンと日本企<br />
業とのパートナーシップの事例は下記の通り。<br />
森永製菓株式会社<br />
株式会社日能研<br />
イオン株式会社<br />
図表 8 プラン・ジャパンと日本企業のパートナーシップの事例<br />
企業 内容<br />
朝日ライフ アセットマネジメント<br />
株式会社<br />
出所:プラン・ジャパンのウェブサイト 12 より作成<br />
2003年から、特定の製品の売上の一部をプラン・ジャパンに寄付しており、寄付金が<br />
フィリピン、カメルーン、ガーナでの学校建設などに利用されている。<br />
1991年から、チャイルドスポンサーとして、合計15名以上を支援している。また1996年<br />
から、アジアにおける学校建設プロジェクトなどに寄付を行っている。<br />
2008年から、ジャスコ店舗においてペットボトルキャップの回収キャンペーンを実施し、<br />
回収したキャップの対価をプラン・ジャパンを含む団体に寄付している。<br />
2002年度から、SRIファンド「あすのはね」の信託報酬の一部をプラン・ジャパンに寄付<br />
している。寄付の対象プロジェクトは、同社社員アンケートによって選ばれている。<br />
プラン・ジャパンでは、Cause-Related Marketing は、開発問題への入り口としてはよいと考えて<br />
いる。ただし、企業からの全ての寄付の申し出を受けるわけではなく、明らかにNGOを利用しよう<br />
としている企業については断る場合もある。<br />
寄付以外の事例としては、アフリカの小学校に太陽光発電を設置するプロジェクトで、三菱系列<br />
の企業から太陽電池の現物寄付を受けた。今後このようなプロジェクトが増加していくと考えてい<br />
るが、日本の製品は値段が高く、NGOとしてはなかなか購入することは難しい。仮に太陽電池を<br />
購入するのであれば現実的には値段の安い中国製を選ぶ可能性が高い。ただし途上国向けにス<br />
ペックを落とした廉価版の給水設備などがあれば、購入が検討されるものと思われる。<br />
プラン・ジャパンでは、BOPは食品や衣料品といった消費財が適していると考えられる。プラン<br />
が関わっている案件としては、オランダのコーヒー焙煎会社が 1999 年からウガンダでコーヒーの<br />
フェアトレードに関するプロジェクト行っている。プランはこの中で、コーヒー豆生産者に対するスキ<br />
ル開発の部分を担当した。第 3 フェーズまで進み、コーヒーだけでなく、穀物生産にまで拡大して<br />
いる。企業側は良質のコーヒー豆が調達できるというメリットがある。このように、プランがメーカー<br />
と協力してBOPプロジェクトを手掛けていくという可能性がある。BOPには製品の販売だけでなく<br />
様々な方法があるが、マイクロファイナンスのような金融は、貸し倒れのリスクを考えると難しいと<br />
思われる。<br />
日本企業では住友化学以外のBOP事例は尐ないが、三菱商事が現在、BOPビジネス開拓に<br />
力を入れている 13 。また、中小企業も現地サプライヤーの育成という観点から取り組んでいる。<br />
11 プラン・ジャパンインタビュー<br />
12 http://www.plan-japan.org/csr/<br />
13 プラン・ジャパンインタビュー<br />
313
(この印刷物は、印刷用の紙へリサイクルできます。)