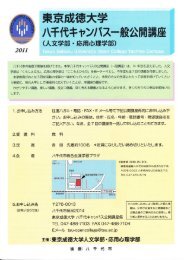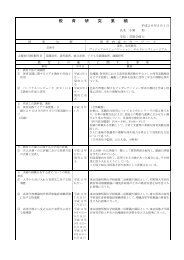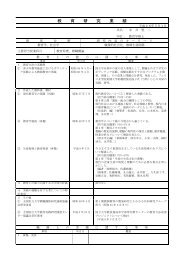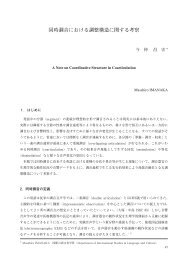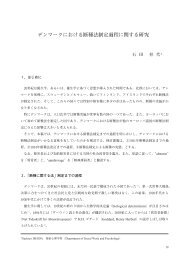Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
自 閉 症 の「 発 見 」と 精 神 分 析<br />
加 地<br />
*<br />
雄 一<br />
The “Discovery” of Autism and Its Psychoanalysis<br />
Yuichi KAJI<br />
This paper reports on the “discovery” or origins of autism. Although the “discoverers” of the cases of<br />
autism were Kanner, L. (1943, 1944) and Asperger, H. (1944), preceding them, there were influences<br />
from psychoanalytical concepts of “Autoerotismus” (Freud, S., 1905) and “Introvertierten Denktypus” (or<br />
“Introversion”) (Jung, C. G., 1921). Moreover, it is mentioned that the origins of autism can be dated back<br />
to Ancient Rome (Ovidius and Tertullianus, Q. S. F.). The “discoverers”, both Kanner, L. (1943, 1944) and<br />
Asperger, H. (1944), regarded the studies of Bleuler, E. (1911) as the beginning of their studies. The studies<br />
of Bleuler, E. (1911) were achieved by his combination of Psychoanalysis and Science with each other. It is<br />
pointed out that introducing Psychoanalysis into approaches to mental disorders (not only autism) is useful.<br />
1.はじめに<br />
自 閉 症 はその「 発 見 」 以 降 、 今 日 に 至 るまで 注 目 され 続 けている 障 害 である。 近 年 では 自 閉 症 に 対<br />
する 精 神 分 析 的 アプローチはあまり 一 般 的 でない。しかし、 精 神 分 析 が 自 閉 症 の「 発 見 」に 及 ぼした<br />
影 響 は 決 して 小 さくはなく、 精 神 分 析 的 アプローチが 持 つ 観 察 力 や 洞 察 力 は、 見 落 とし( 見 過 ごし)<br />
がちな 症 状 や 障 害 を「 発 見 」、 理 解 するのに 今 日 でも 有 用 であると 考 えられる。 本 論 文 では、 自 閉 症<br />
の 言 葉 の 起 源 や 概 念 の 成 立 過 程 および、 自 閉 症 の「 発 見 」に 対 する 精 神 分 析 の 貢 献 について 概 観 す<br />
る。<br />
* Yuichi KAJI<br />
福 祉 心 理 学 科 (Department of Social Work and Psychology)<br />
21
東 京 成 徳 大 学 研 究 紀 要 ― 人 文 学 部 ・ 応 用 心 理 学 部 ― 第 19 号 (2012)<br />
2.Autismus (Bleuler, E., 1911)<br />
自 閉 症 あるいは 自 閉 性 (Autismus)という 言 葉 を 世 界 で 初 めて 用 いたのはBleuler, E.(1911)であ<br />
るが( 平 井 , 1968)、 元 々は 統 合 失 調 症 の「 基 本 症 状 」を 記 述 するために 用 いられた 言 葉 である。 自<br />
閉 症 は、 統 合 失 調 症 の 他 の 基 本 症 状 である 連 合 弛 緩 (Störung der Assoziation)、 感 情 障 害 (Störung<br />
der Affektivität)、 両 価 性 (Ambivalenz)と 合 わせて、Bleuler's 4A と 呼 ばれている。 自 閉 症 という<br />
言 葉 はギリシャ 語 の 自 己 (autos)という 言 葉 が 由 来 だと 言 われている(Spensley, 1994)。<br />
Bleuler, M.(Bleuler, E. の 息 子 )(Bleuler, E., 1911の 邦 訳 書 に 寄 せた「 日 本 語 版 への 序 文 」)に<br />
よれば、Bleuler, E. は1857 年 にチューリヒ 近 郊 の 農 家 で 生 まれ、1886 年 から1898 年 の12 年 間 スイス<br />
のライナウ 州 立 病 院 の 医 長 として 働 き、その 後 の1898 年 から1927 年 にかけてチューリヒ 大 学 教 授 と<br />
大 学 付 属 ブルクヘルツリ 病 院 院 長 を 務 めた。Bleuler, E.(1911)は、ブルクヘルツリ 病 院 での 共 同<br />
研 究 者 の 中 でも 特 に 部 下 のJung, C. G. の 名 を 挙 げ 感 謝 の 意 を 表 している。Bleuler, M. によれば、<br />
Bleuler, E.(1911)が 書 かれた 背 景 には、Kraepelin, E. の 自 然 科 学 的 見 解 とFreud, S. の 精 神 分 析 的 見<br />
解 の 両 者 を 受 け 入 れ、 補 完 するという 過 程 があったという。つまり、 自 閉 症 という 言 葉 は、Bleuler,<br />
E.(1911)による 精 神 分 析 と 自 然 科 学 の 補 完 という 背 景 から 生 まれた。<br />
Bleuler, E.(1911)は、 自 閉 症 の 定 義 はFreud, S.(1905)の 自 体 愛 (Autoerotismus)と 同 義<br />
であると 述 べている( 邦 訳 p.73)。ただし、Freud, S. が 用 いた 概 念 は 広 く、 誤 解 を 招 くとBleuler,<br />
E.(1911)は 考 え、 自 閉 症 を 次 のように 定 義 づけている。すなわち、「 叶 えられたと 思 っている 願 望<br />
や 迫 害 されているという 苦 悩 を 携 えて 繭 の 中 に 閉 じこもるように 自 己 の 内 に 閉 じこもり、 外 界 との 接<br />
触 をできる 限 り 制 限 している。 内 面 生 活 の 相 対 的 、 絶 対 的 優 位 を 伴 う 現 実 からの 遊 離 のこと」( 邦 訳<br />
p.73)を 自 閉 症 と 呼 ぶとしている。 次 にBleuler E.(1911)がAutismus と 同 義 であるとしたFreud, S.<br />
(1905)の 自 体 愛 の 概 念 について 確 認 しておきたい。<br />
3.Autoerotismus (Freud, S., 1905)<br />
Freud, S.(1905)は 自 体 愛 を、「 他 人 に 向 けられたものではな」く「 自 分 の 身 体 で 自 ら 満 足 する」<br />
欲 動 と 定 義 している( 邦 訳 p.46)。 例 として「おしゃぶり」が 挙 げられている。 欲 動 を 満 足 させるた<br />
めに( 他 の 対 象 物 ではなく) 自 らの 身 体 を 用 いる 理 由 として、「 自 分 ではまだ 自 由 にすることのでき<br />
ない 外 界 から 独 立 していられるから」( 邦 訳 p.46)と 説 明 している。Freud, S.(1905)は 自 体 愛 とい<br />
う 概 念 を「 幼 児 性 欲 」を 説 明 するために 用 いているが、 不 自 由 な 外 界 から 独 立 していたいがために 欲<br />
動 が 自 己 へと 向 かう、という 考 え 方 は 今 日 で 言 うところの「 自 閉 症 」( 特 に、 常 同 行 為 や 自 己 刺 激 的<br />
行 動 などの 症 状 )を 精 神 分 析 的 に 理 解 するうえで 有 用 であろう。<br />
Freud, S.(1914)と 小 此 木 (1985)によれば、 自 体 愛 と 自 己 愛 (Narzißmus)の 違 いについては<br />
次 のように 考 えられる。すなわち 自 体 愛 は、 統 一 的 な 自 我 が 発 達 する 前 の 原 初 的 なリビドーの 状 態 を<br />
意 味 する。これに 対 し 自 己 愛 は、 統 一 的 な 自 我 が 発 達 した 段 階 において 自 己 表 象 へリビドーが 割 り 当<br />
てられた 状 態 を 意 味 する。<br />
22
自 閉 症 の「 発 見 」と 精 神 分 析<br />
そしてFreud, S. の 文 献 をレビューした 小 此 木 (1985)によれば、 自 己 愛 は 一 次 的 自 己 愛 から、 二<br />
次 的 自 己 愛 、 対 象 愛 へと 発 達 していく。 一 次 的 自 己 愛 の 段 階 では、 外 界 の 対 象 は 自 己 から 分 化 された<br />
ものとして 存 在 していないため、まだ 外 界 の 対 象 表 象 に 対 するリビドーの 備 給 は 行 われていない。 自<br />
他 分 離 が 進 んだ 二 次 的 自 己 愛 の 段 階 では、 外 界 の 対 象 表 象 が 登 場 し、 快 を 与 える 対 象 は 自 己 の 中 に 取<br />
り 入 れられ、 不 快 なものは 外 界 に 追 い 出 される。 次 の 対 象 愛 の 段 階 になると、 快 ・ 不 快 は 対 象 表 象 に<br />
関 する 関 係 を 意 味 するようになり、 快 を 与 える 対 象 に 近 づき、 不 快 を 与 える 対 象 からは 遠 ざかるよう<br />
になる。 先 に、 今 日 の 自 閉 症 が 示 す 常 同 行 為 や 自 己 刺 激 的 行 動 について 理 解 する 上 で 自 体 愛 の 概 念 が<br />
有 用 と 述 べたが、 対 象 に 対 する 無 関 心 さについて 理 解 するには 自 己 愛 の 概 念 が 有 用 であると 思 われ<br />
る。<br />
なお、Freud, S.(1905)の 自 体 愛 (Autoerotismus)という 言 葉 は、Ellis, H.(1898)の 自 体 愛<br />
(Auto-eroticism)から 借 用 されたものである。そこで、Ellis, H. の 元 々の 定 義 を 次 に 確 認 しておき<br />
たい。<br />
4.Auto-eroticism (Ellis, H., 1898)<br />
Ellis, H.(1898)は、 自 体 愛 を 自 己 嘆 美 することに 耽 る 性 的 感 情 ととらえ、ナルキッソス 的 傾 向<br />
(Narcissus-like tendency)と 表 現 した。そして 後 に、 自 体 愛 を 外 的 刺 激 なしで 生 じる 自 発 的 な 性 的<br />
感 情 と 定 義 した(Ellis, H., 1927)。<br />
ナルキッソスとは 古 代 ローマの 詩 人 Ovidius(B.C.43-A.D.17)が 書 いた 神 話 『 変 身 物 語<br />
(Metamorphosen )』(n. d.)に 登 場 する「 美 少 年 」( 河 神 ケピソスと 水 の 妖 精 の 間 に 生 まれた 子 ど<br />
も)のことを 表 す。ナルキッソスのエピソードには、 今 日 の「 自 閉 症 」を 連 想 させる 記 述 があるた<br />
め、 次 に 紹 介 したい。<br />
5.Narcissus and Echo (Ovidius, n.d.)<br />
Ovidiusの『 変 身 物 語 』に「ナルキッソスとエコー(Echo)」という 物 語 が 書 かれている。この 物<br />
語 の 概 要 を 一 言 で 表 せば、「やまびこの 妖 精 エコーが 美 少 年 ナルキッソスに 恋 するも 相 手 にされず、<br />
ナルキッソスは 泉 にうつった 自 分 の 姿 に 恋 してしまい、 泉 から 離 れられずに 衰 弱 死 してしまう」と<br />
なる。エコーはナルキッソスに 対 し、 彼 と「おなじ 呼 び 声 」で、「おなじ 言 葉 」で 応 えることしかで<br />
きない( 邦 訳 p.99)が、これは 今 日 の「 自 閉 症 」が 示 す「 反 響 言 語 (echolalia)」の 症 状 を 連 想 させ<br />
る。また、エコーがナルキッソスに 抱 きつこうとする 場 面 で、ナルキッソスは「 手 をのけてくれ。<br />
抱 きついたらいやだ。 死 んだ 方 がましだよ、きみの 思 いどおりになるくらいなら!」と 叫 ぶ( 邦 訳<br />
p.99)。このエピソードも、 人 に 触 れられるのを 嫌 がる、という 今 日 の「 自 閉 症 」の 特 徴 を 思 わせる<br />
ものである。<br />
Jung, C. G.(1943)によれば、 個 人 に 内 在 化 された 無 意 識 的 なイメージは、 様 々な 神 話 に 共 通 し<br />
て 見 られるという。Ovidiusは 今 日 で 言 うところの「 自 閉 症 」が 示 す 特 徴 を 見 聞 きし、それを 無 意 識<br />
のうちに 神 話 として 記 述 していた 可 能 性 が 考 えられる。そう 考 えると 自 閉 症 の 起 源 は 古 代 ローマ、<br />
23
東 京 成 徳 大 学 研 究 紀 要 ― 人 文 学 部 ・ 応 用 心 理 学 部 ― 第 19 号 (2012)<br />
Ovidiusの 時 代 までさかのぼることができる。それでは、 今 日 の「 自 閉 症 」はいつ「 発 見 」されたの<br />
だろうかこの 点 について 次 に 述 べる。<br />
6.Early infantile autism (Kanner, L., 1943, 1944)<br />
Kanner, L. は1943 年 に 今 日 の「 自 閉 症 」について、 初 めての 症 例 報 告 を 行 った(Kanner, L.,<br />
1943)。 彼 は「これまでに 報 告 されてきたことのない 非 常 にユニークな 症 状 を 呈 する 一 群 の 子 どもた<br />
ち」( 邦 訳 p.10)11 例 ( 男 性 8 名 、 女 性 3 名 )を 報 告 し、この 子 どもたちを「 情 緒 的 交 流 の 自 閉 的 障 害<br />
(Autistic Disturbances of Affective Contact)」と 呼 んだ。そして 翌 年 の1944 年 に、この 障 害 を「 早<br />
期 小 児 自 閉 症 (Early infantile autism)」と 名 づけた(Kanner, L., 1944)。Kanner, L.(1943, 1944)<br />
が 用 いたAutism(Autistic)という 言 葉 は、 先 述 のBleuler, E.(1911)のAutismusが 由 来 である。<br />
Kanner, L.(1943)は、 自 閉 症 の 子 どもたちの 特 徴 として「 極 端 な 自 閉 的 な 孤 立 」、「 自 発 的 構 文 の<br />
欠 如 と 反 響 言 語 的 構 成 」、「 同 一 性 保 持 への 強 迫 的 願 望 」などを 挙 げている。これらの 特 徴 につい<br />
て、Kanner, L.(1943)が“CASE 1”として 最 初 に 報 告 した“Donald T.”の 症 例 に 沿 って 見 てい<br />
く。<br />
極 端 な 自 閉 的 な 孤 立 :「 部 屋 の 中 に 入 れられると、 彼 は 人 を 無 視 して、 物 、それも 回 すことのでき<br />
る 物 のところにすぐ 行 った。どうしても 無 視 できない 命 令 や 行 動 は 迷 惑 でありじゃまであり 不 快 に 思<br />
われた。しかし 彼 は 干 渉 する 人 にはけっして 腹 を 立 てなかった。 彼 はじゃまな 手 を、あるいは 彼 のブ<br />
ロックを 踏 みつけた 足 を 怒 って 押 しのける」( 邦 訳 p.14)。Kanner, L.(1943)はこの 特 徴 を「 極 端 な<br />
自 閉 的 な 孤 立 」と 表 現 し、「 分 裂 病 的 な 子 どもやおとなのように、 初 めに 存 在 していた 関 係 からの 離<br />
脱 」でもなく、「 以 前 存 在 していた 参 加 からの『ひきこもり』」でもなく、「 初 めから、 外 からやっ<br />
てくるものはなるべく 無 視 してかえりみず、 閉 め 出 そうとする」ものとしている( 邦 訳 p.44)。<br />
自 発 的 構 文 の 欠 如 と 反 響 言 語 的 構 成 :「 話 しかけられ 聞 いたことばをおうむ 返 ししているようで、<br />
聞 いたままの 人 称 代 名 詞 を 用 い、その 抑 揚 までまねた」( 邦 訳 p.13)。Kanner, L.(1943)はこれを<br />
「 自 発 的 構 文 の 欠 如 と 反 響 言 語 的 構 成 」と 呼 び、「じゃまされないでいたいという 欲 求 」の 強 さと、<br />
「 外 部 からもたらされること、 外 的 なあるいは 内 的 な 環 境 を 変 えること」が「 恐 るべき 侵 入 」である<br />
とみなされるためであるとした( 邦 訳 p.47)。<br />
同 一 性 保 持 への 強 迫 的 願 望 :「 自 発 的 な 行 動 にははっきり 限 界 がある。 笑 いながら 歩 き 回 り、 指 を<br />
常 同 的 に 動 かし、それらを 空 中 で 交 差 させた。 頭 を 左 右 に 振 り、3 拍 子 でつぶやいたりした。 回 せる<br />
ものなら 何 でも 喜 んで 回 した。 床 に 物 を 投 げつづけ、その 音 を 楽 しんでいるようだった。 彼 は、ビー<br />
ズや 棒 やブロックをさまざまな 系 列 の 色 にわけて 配 列 した。これらの 行 為 の 一 つが 完 成 したときはい<br />
つでも、きいきい 声 をあげて 飛 び 跳 ねた。それ 以 外 のことはいつも( 母 親 からの) 指 示 を 要 し、 彼<br />
が 夢 中 になる 限 られたものごと 以 外 に 自 発 的 に 行 動 することはなかった」( 邦 訳 pp.12-13)。Kanner,<br />
L.(1943)はこうした 特 徴 を「 同 一 性 保 持 への 強 迫 的 願 望 」( 邦 訳 p.48)と 呼 び、「 外 観 と 位 置 を 変<br />
えない 物 は 同 一 性 を 保 持 しており、 子 どもの 孤 立 をじゃまするおそれがまったくないので、 自 閉 的 な<br />
子 どもにすんなりと 受 け 入 れられる」( 邦 訳 p.50)としている。<br />
Kanner, L.(1943)が 挙 げたこれらの 特 徴 は、 今 日 のDSM(アメリカ 精 神 医 学 会 が 定 めた『 精 神<br />
24
自 閉 症 の「 発 見 」と 精 神 分 析<br />
障 害 の 診 断 と 統 計 の 手 引 き』)とICD( 世 界 保 健 機 構 が 定 めた『 疾 病 及 び 関 連 保 健 問 題 の 国 際 統 計 分<br />
類 』)に 書 かれている 診 断 基 準 にも 受 け 継 がれている。<br />
7.Autistischen Psychopathen (Asperger, H., 1944)<br />
Kanner, L.(1943, 1944)と 同 時 期 にAsperger, H.(1944)は「Autistischen Psychopathen( 自 閉<br />
的 精 神 病 質 )」という 概 念 を4つの 症 例 ( 男 性 4 名 )とともに 報 告 した。 当 時 は 第 二 次 世 界 大 戦 中 で<br />
あったため、アメリカのKanner, L.とオーストリアのAsperger, H.はお 互 い 関 係 なく 独 立 に 同 時 期 に<br />
論 文 を 自 閉 症 に 関 する 論 文 を 発 表 したとされる( 平 井 , 1968)。Autistischen Psychopathenという 名<br />
称 の 由 来 についてAsperger, H.(1944)は、「 医 学 上 の 命 名 として、もっとも 偉 大 な 言 語 学 的 、 概 念<br />
的 創 造 のひとつと 考 えるこの 表 現 は、 周 知 の 如 くBleuler, E. に 由 来 する」( 邦 訳 p.36)と 述 べている。<br />
Asperger, H.(1944)によれば、「 自 閉 的 精 神 病 質 の 本 質 的 異 常 は、 周 囲 に 対 する 生 き 生 きとし<br />
た 関 係 が 障 害 されていることであり、これからすべての 異 常 が 説 明 される」( 邦 訳 p.57)。「 積 極 的<br />
注 意 の 障 害 」も 彼 が 報 告 した 子 どもたちに 共 通 して 見 られたものであるという。すなわち、 最 初 か<br />
ら 外 界 に 注 意 を 向 けて 集 中 することがない。「 日 常 とは 遠 くかけ 離 れた 勝 手 な 問 題 を 追 いかけてい<br />
て、 邪 魔 を 許 さず、 他 人 に 覗 かせようとしない」( 邦 訳 p.58)。 対 象 との 関 係 については、「 周 囲 の<br />
諸 事 物 をまったく 認 めず、 玩 具 にぜんぜん 興 味 を」 持 たないか、 特 定 の 対 象 (「 鞭 や 棒 切 れ、 壊 れ<br />
た 人 形 」)から 片 時 も 目 を 離 さないという( 邦 訳 p.61)。この 対 象 との 関 係 のあり 方 は、 先 に 述 べた<br />
Freud, S. の 二 次 的 自 己 愛 を 連 想 させる。<br />
Asperger, H.(1944)は 自 らが 報 告 した 子 どもたちの 類 型 と、Kretschmer, E. の「Schizothym<br />
( 分 裂 気 質 )」やJaensch, E. R. の「Desintegrierte( 不 統 一 人 格 )」との 間 に 類 似 性 を 見 出 してい<br />
る。 特 にJung, C. G. の「Introvertierten Denktypus( 内 向 的 思 考 型 )」との 間 に 類 似 性 が 見 られる<br />
という。そこで、 次 にIntrovertierten Denktypus(Jung, C. G., 1921)について 触 れる。<br />
8.Introvertierten Denktypus (Jung, C. G., 1921)<br />
内 向 的 思 考 型 (Introvertierten Denktypus)の 特 徴 は、 客 観 的 事 実 よりも 主 観 的 基 盤 を 理 念 に 置<br />
き、 客 体 に 対 しては 否 定 的 な 関 係 を 結 ぶというものである(Jung, C. G., 1921)。 内 向 的 思 考 には、<br />
「 主 観 的 要 因 を 基 準 にして 自 らを 方 向 づけ」( 邦 訳 p.409)、「 具 体 的 な 経 験 から 出 発 して 再 び 客 観<br />
的 な 事 物 へ 戻 るのではなく、 主 観 的 な 内 容 に 向 かう」( 邦 訳 p.410)という 特 徴 が 見 られ、「この 思<br />
考 は 主 体 の 中 で 始 まり 主 体 に 戻 る」( 邦 訳 p.410)。そして、この 型 の 人 の 具 体 的 な 特 徴 としては、<br />
「 自 らの 理 念 に 忠 実 なあまり」、「たいてい 頑 固 、 強 情 で、 他 人 の 言 には 耳 をかさない」( 邦 訳<br />
p.415)といったものが 見 られる。<br />
Asperger, H.(1944)は 内 向 的 性 格 と 自 閉 的 精 神 病 質 との 間 に 類 似 点 が 多 いとも 述 べているため、<br />
そもそも「 内 向 (Introversion)」とは 何 かについてここで 確 認 しておきたい。Jung, C. G.(1921)<br />
によれば、 内 向 とは「リビドーが 内 へ 向 かうこと」であり、「 主 体 が 客 体 に 対 して 消 極 的 な 関 係 を<br />
も」ち、「 関 心 が 客 体 に 向 かわずに、 客 体 から 主 体 へ 引 き 戻 される」ことである( 邦 訳 p.475)。 内 向<br />
25
東 京 成 徳 大 学 研 究 紀 要 ― 人 文 学 部 ・ 応 用 心 理 学 部 ― 第 19 号 (2012)<br />
型 において 客 体 は、 意 識 的 には 関 心 が 向 けられないが、 無 意 識 的 には 不 安 をもたらすほどの 関 心 が 向<br />
けられる。したがって、 内 向 型 の 人 は「 安 心 を 得 るために 儀 式 体 系 を 自 分 の 周 りにはりめぐら」( 邦<br />
訳 p.408)せる。 無 意 識 においては、 客 体 からの 影 響 力 に 圧 倒 され、「『 自 分 を 保 つ』ために、ぞっ<br />
とするような 内 的 作 業 を 絶 えず 必 要 としている」( 邦 訳 p.408)のである。こうした 記 述 は、 神 経 症<br />
の 形 態 の 一 つについての 説 明 であるが、 自 閉 症 (が 示 す 儀 式 的 行 為 )にも 通 じるものと 考 えられる。<br />
対 象 ( 客 体 )との 関 係 については、 無 意 識 的 、 原 始 的 であり、 客 体 は「あたかも 呪 術 的 な 力 を 備 えて<br />
いるかのようになる」( 邦 訳 p.409)という。 新 奇 な 客 体 は 恐 怖 や 不 安 の 対 象 になるのに 対 し、なじ<br />
みのある 客 体 は「 見 えない 糸 」で「 魂 につながれているかのようである」という( 邦 訳 p.409)。こう<br />
した 客 体 との 関 係 のあり 方 は、Asperger, H.(1944)が 報 告 した「 周 囲 に 関 心 を 示 さないが、 特 定 の<br />
対 象 には 片 時 も 目 を 離 さない」という 自 閉 的 精 神 病 質 の 子 どもの 特 徴 と 重 なるものと 考 えられる。<br />
Jung, C. G.(1921)は、「 内 向 的 思 考 人 の 古 典 的 な 代 表 者 」として 古 代 ローマ 時 代 のカルタゴのキ<br />
リスト 教 教 父 ( 反 異 端 教 父 )Tertullianus, Q. S. F.(ca.A.D.160-ca.A.D.220)を 挙 げている。Jung, C.<br />
G.(1921)によれば、Tertullianus, Q. S. F. は「 鋭 い 精 神 によって 哲 学 的 な 知 やグノーシス 的 な 知 が<br />
劣 っていることを 見 ぬき、これを 軽 蔑 して 退 け」( 邦 訳 p.20)、 自 分 自 身 の 不 合 理 な 内 的 事 実 を 合 理<br />
的 な 哲 学 に 対 抗 するための 原 理 とした。このような 特 徴 は、Asperger, H.(1944)が 報 告 した 自 閉 的<br />
精 神 病 質 の 子 どもの「 日 常 からかけ 離 れた 問 題 を 追 いかける」という 特 徴 と 通 底 する 部 分 がある。<br />
9.おわりに<br />
以 上 、 自 閉 症 の「 発 見 」や 起 源 について 述 べてきた。 症 例 としての 自 閉 症 を「 発 見 」したのは<br />
Kanner, L.(1943, 1944)とAsperger, H.(1944)であるが、その 背 景 にはFreud, S.(1905)の<br />
AutoerotismusやJung, C. G.(1921)のIntrovertierten Denktypus(あるいはIntroversion)といった<br />
精 神 分 析 的 概 念 の 影 響 を 認 めることができた。 起 源 はさらに、 古 代 ローマのOvidiusやTertullianus,<br />
Q. S. F. にまで 遡 ることができる 可 能 性 についても 触 れた。 自 閉 症 「 発 見 者 」のKanner, L.(1943,<br />
1944)とAsperger, H.(1944)の 両 者 とも、Bleuler, E.(1911)を 自 らの 研 究 の 端 緒 としている。そ<br />
のBleuler, E.(1911)の 研 究 は、 精 神 分 析 と 自 然 科 学 のどちらかに 傾 倒 することなく 両 者 を 補 完 す<br />
ることによって 成 し 遂 げられた。 自 閉 症 に 限 らず 今 日 の 精 神 的 問 題 にアプローチする 上 で、Bleuler,<br />
E.(1911)のように 自 然 科 学 を 補 完 する 形 で 精 神 分 析 を 取 り 入 れることは 有 用 であると 考 えられる。<br />
引 用 文 献<br />
Asperger, H.(1944). Die "Autistischen Psychopathen" im Kindesalter. Archiv für psychiatrie und<br />
nervenkrankheiten, 117, 76–136.(アスペルガー, H.( 詫 摩 武 元 ・ 髙 木 隆 郎 ( 訳 )(2000). 小 児 期 の<br />
自 閉 的 精 神 病 質 高 木 隆 郎 ・ラター, M.・ショプラー, E.( 編 ) 自 閉 症 と 発 達 障 害 研 究 の 進 歩 2000 /<br />
Vol. 4 星 和 書 店 , pp.30-68.)<br />
Bleuler, E.(1911). Dementia praecox oder gruppe der Schizophrenien . Leipzig und Wien: Franz<br />
Deutike.(ブロイラー, L. 飯 田 真 ・ 下 坂 幸 三 ・ 保 崎 秀 夫 ・ 安 永 浩 ( 訳 )(1974). 早 発 性 痴 呆 また<br />
26
自 閉 症 の「 発 見 」と 精 神 分 析<br />
は 精 神 分 裂 病 群 医 学 書 院 )<br />
Ellis, H.(1898). Auto-eroticism: A psychological study. Alienist and Neurologist, 19, 260-299.<br />
Ellis, H.(1927). Studies in the Psychology of Sex, Volume II: Sexual Inversion. 3rd Ed. , Project<br />
Gutenberg.<br />
Freud, S.(1905). Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie. In Gesammelte Werke Vol. 5. London:<br />
Imago.(フロイト, S. 懸 田 克 躬 ・ 高 橋 義 孝 ほか( 訳 )(1969). 性 欲 論 3 篇 フロイト 著 作 集 第 5 巻<br />
性 欲 論 ・ 症 例 研 究 人 文 書 院 )<br />
Freud, S.(1914). Zür Einführung der Narzissmus. Jahrbuch der Psychoanalyse, 6, 1-24.(フロイト,<br />
S. 懸 田 克 躬 ・ 高 橋 義 孝 ほか( 訳 )(1969). ナルシシズム 入 門 フロイト 著 作 集 第 5 巻 性 欲 論 ・ 症 例<br />
研 究 人 文 書 院 )<br />
平 井 信 義 (1968). 小 児 自 閉 症 日 本 小 児 医 事 出 版 社 .<br />
Jung, C. G.(1921). Psychologische Typen. Zürich: Rascher.(ユング, C. G. 林 道 義 ( 訳 )(1987). タイ<br />
プ 論 みすず 書 房 )<br />
Jung, C. G.(1943). Über die Psychologie des Unbewussten . Zürich: Rascher(ユング, C. G. 高 橋 義<br />
孝 ( 訳 )(1977). 無 意 識 の 心 理 人 文 書 院 )<br />
Kanner, L.(1943). Autistic Disturbances of Affective Contact. Nervous Child, 2, 217-250.(カナー, L.<br />
十 亀 史 郎 ・ 斉 藤 聡 明 ・ 岩 本 憲 ( 訳 )(2001). 情 緒 的 交 流 の 自 閉 的 障 害 精 神 医 学 選 書 < 第 2 巻 > 幼<br />
児 自 閉 症 の 研 究 黎 明 書 房 , pp.10-55.)<br />
Kanner, L.(1944). Early infantile autism. Journal of Pediatrics, 25, 211–217.<br />
小 此 木 啓 吾 (1985). 現 代 精 神 分 析 の 基 礎 理 論 弘 文 堂 .<br />
Ovidius,(n.d.). Metamorphoses .(オウィディウス 田 中 秀 央 ・ 前 田 敬 作 ( 訳 )(1966). 転 身 物 語 人<br />
文 書 院 )<br />
Spensley, S.(1994). Frances Tustin . London: Routledge(スペンスリー, S. 井 原 成 男 ・ 斉 藤 和 恵 ・<br />
山 田 美 穂 ・ 長 沼 佐 代 子 ( 訳 )(2003). タスティン 入 門 : 自 閉 症 の 精 神 分 析 的 探 究 岩 崎 学 術 出 版<br />
社 )<br />
27