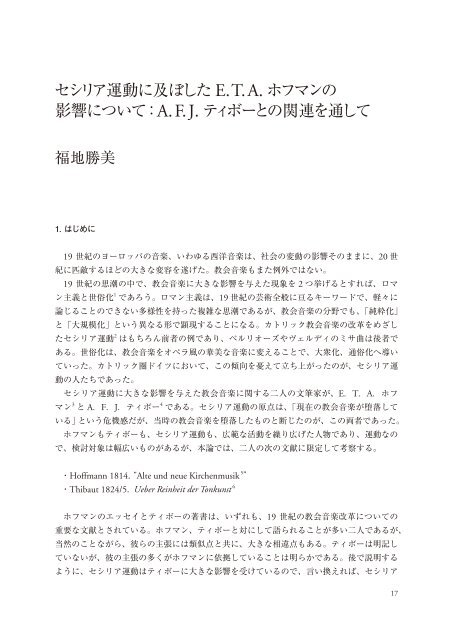AFJ ティボーとの関連を通して - 成城大学
AFJ ティボーとの関連を通して - 成城大学
AFJ ティボーとの関連を通して - 成城大学
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
セシリア 運 動 に 及 ぼした E. T. A. ホフマンの<br />
影 響 について:A. F. J. ティボーとの 関 連 を 通 して<br />
福 地 勝 美<br />
1. はじめに<br />
19 世 紀 のヨーロッパの 音 楽 、いわゆる 西 洋 音 楽 は、 社 会 の 変 動 の 影 響 そのままに、20 世<br />
紀 に 匹 敵 するほどの 大 きな 変 容 を 遂 げた。 教 会 音 楽 もまた 例 外 ではない。<br />
19 世 紀 の 思 潮 の 中 で、 教 会 音 楽 に 大 きな 影 響 を 与 えた 現 象 を 2 つ 挙 げるとすれば、ロマ<br />
ン 主 義 と 世 俗 化 1 であろう。ロマン 主 義 は、19 世 紀 の 芸 術 全 般 に 亘 るキーワードで、 軽 々に<br />
論 じることのできない 多 様 性 を 持 った 複 雑 な 思 潮 であるが、 教 会 音 楽 の 分 野 でも、「 純 粋 化 」<br />
と「 大 規 模 化 」という 異 なる 形 で 顕 現 することになる。カトリック 教 会 音 楽 の 改 革 をめざし<br />
たセシリア 運 動 2 はもちろん 前 者 の 例 であり、ベルリオーズやヴェルディのミサ 曲 は 後 者 で<br />
ある。 世 俗 化 は、 教 会 音 楽 をオペラ 風 の 華 美 な 音 楽 に 変 えることで、 大 衆 化 、 通 俗 化 へ 導 い<br />
ていった。カトリック 圏 ドイツにおいて、この 傾 向 を 憂 えて 立 ち 上 がったのが、セシリア 運<br />
動 の 人 たちであった。<br />
セシリア 運 動 に 大 きな 影 響 を 与 えた 教 会 音 楽 に 関 する 二 人 の 文 筆 家 が、E.T.A.ホフ<br />
マン 3 と A.F.J.ティボー4 である。セシリア 運 動 の 原 点 は、「 現 在 の 教 会 音 楽 が 堕 落 して<br />
いる」という 危 機 感 だが、 当 時 の 教 会 音 楽 を 堕 落 したものと 断 じたのが、この 両 者 であった。<br />
ホフマンもティボーも、セシリア 運 動 も、 広 範 な 活 動 を 繰 り 広 げた 人 物 であり、 運 動 なの<br />
で、 検 討 対 象 は 幅 広 いものがあるが、 本 論 では、 二 人 の 次 の 文 献 に 限 定 して 考 察 する。<br />
・Hoffmann 1814. “Alte und neue Kirchenmusik 5 ”<br />
・Thibaut 1824/5. Ueber Reinheit der Tonkunst 6<br />
ホフマンのエッセイとティボーの 著 書 は、いずれも、19 世 紀 の 教 会 音 楽 改 革 についての<br />
重 要 な 文 献 とされている。ホフマン、ティボーと 対 にして 語 られることが 多 い 二 人 であるが、<br />
当 然 のことながら、 彼 らの 主 張 には 類 似 点 と 共 に、 大 きな 相 違 点 もある。ティボーは 明 記 し<br />
ていないが、 彼 の 主 張 の 多 くがホフマンに 依 拠 していることは 明 らかである。 後 で 説 明 する<br />
ように、セシリア 運 動 はティボーに 大 きな 影 響 を 受 けているので、 言 い 換 えれば、セシリア<br />
17
成 城 美 学 美 術 史<br />
第 17 号<br />
運 動 はティボーを 通 して、ホフマンの 影 響 を 受 けて( 受 容 して)いたことになる。<br />
ティボーがホフマンから 何 を 受 け 継 ぎ、 何 を 拒 んだか。 同 様 に、セシリア 運 動 がティボー<br />
の 考 えのうちから 何 を 受 け 継 ぎ、 何 を 拒 んだかを、 考 察 することにより、セシリア 運 動 がホ<br />
フマンから 何 を 学 んだか、が 見 えてくる。<br />
2. E. T. A. ホフマン<br />
E. T. A. ホフマンは、プロイセン 大 審 院 判 事 という 法 律 家 の 顔 のほか、 作 家 、 作 曲 家 、 音<br />
楽 評 論 家 、 画 家 として、 文 学 、 音 楽 、 絵 画 の 多 彩 な 分 野 で 才 能 を 発 揮 した 当 代 屈 指 の 知 識 人<br />
であった。 彼 は、ティボーと 並 んでセシリア 運 動 に 影 響 を 与 えたとされることが 多 いが、セ<br />
シリア 運 動 ( 盛 期 セシリア 運 動 )との 関 連 、 影 響 関 係 については、 具 体 的 に 論 じられたこと<br />
は 殆 どない。<br />
今 回 、ア・カペラと 「 器 楽 付 き 教 会 音 楽 」 への 対 応 をキーワードとして、 考 察 を 試 みるこ<br />
ととする。<br />
ホフマンは、 一 般 には 器 楽 音 楽 の 推 進 者 として 知 られているが、こと 教 会 音 楽 に 関 しては、<br />
19 世 紀 の 教 会 音 楽 は「 堕 落 」していて、 音 楽 家 はパレストリーナのような 昔 の 教 会 音 楽 を 手<br />
本 にすべきと 主 張 した。パレストリーナの 音 楽 は、「 歌 の 声 部 が 他 の 楽 器 の 伴 奏 なしに 書 か<br />
れていたので、ごちゃごちゃした 伴 奏 音 型 に 圧 倒 されることがなかった」として、ア・カペ<br />
ラ 様 式 を 推 奨 したと 考 えられることが 多 いようだが、 実 際 に 彼 自 身 ア・カペラ 作 品 を 作 って<br />
もいる。<br />
彼 の 論 攷 を 丁 寧 に 読 むと、 教 会 音 楽 においても、 決 してア・カペラ 一 辺 倒 ではなく、 他 の<br />
音 楽 ジャンル 同 様 、 器 楽 音 楽 優 位 説 の 信 奉 者 であったことがわかる。<br />
本 文 の 検 討 に 入 る 前 に、ホフマン 自 身 の 作 った 教 会 音 楽 作 品 について 見 てみよう 7 。 下 記<br />
に 全 容 をまとめた。<br />
●ホフマン 作 の 教 会 音 楽 作 品<br />
1802–3 Messen und Vespern, darunter die Messe für 2 Soprane, 2 Violinen und Orgel ( 消 失 )<br />
Einzelne Motetten, Ave Maria, Salve Regina und andere vierstimmige Chöre a cappela<br />
( 消 失 )<br />
1805 Messe d– moll für vier Stimmen mit Orchester (2Cl, 2Fg, 3Pos, Pk, Str.)<br />
1808 Canzoni per 4 voci alla cappella<br />
(1) Ave maris stella<br />
(2) De profundis,<br />
(3) Gloria Patri, (4) Salve Redemptor, (5) O sanctissima, (6) Salve Regina,<br />
1809 Miserere für Soli, Chor und Orchester<br />
1813 Hymnus für Singakademie in Dresden( 消 失 )<br />
(Allroggen 1970: 16)<br />
18
セシリア 運 動 に 及 ぼした E. T. A. ホフマンの 影 響 について:A. F. J. ティボーとの 関 連 を 通 して<br />
彼 は、1802 年 から 翌 年 にかけ、 消 失 した 作 品 だが、 器 楽 付 きのミサ 曲 とヴェスプレと、<br />
そしてア・カペラの 曲 を 作 っている。その 後 1805 年 に、オーケストラ 伴 奏 ミサ 曲 を、1808<br />
年 には、ア・カペラ《 四 声 の 合 唱 曲 op. 36》を 作 った。その 翌 年 に 代 表 作 といわれる 大 規 模<br />
な 管 弦 楽 伴 奏 付 き《ミゼレーレ》を 作 曲 し、その 後 1813 年 に、 賛 歌 Hymnus(ヒムヌス)を<br />
作 った 後 、 教 会 音 楽 創 作 から 手 を 引 いたようである。このように、 彼 の 立 場 は 一 貫 しておら<br />
ず、 吉 田 寛 はこの 理 由 の1つを、「ホフマンの 歴 史 観 の 変 化 」と 指 摘 している 7 。<br />
2–1 ホフマンの 教 会 音 楽 観<br />
“Alte und neue Kirchenmusik”は、1814 年 8 月 から 9 月 に、3 回 に 分 けて、ロッホリッツ 8<br />
主 筆 の AMZ に 掲 載 された。 新 ホフマン 全 集 の 編 者 シュタインエッケは、このエッセイを 4<br />
つの 部 分 に 区 分 して 解 説 している。 以 下 に、 彼 の 解 説 をふまえて、セシリア 運 動 との 関 連 部<br />
分 を 要 約 、 引 用 してみよう。<br />
第 1 部 冒 頭 で 彼 は、 当 時 の 教 会 音 楽 が、18 世 紀 後 半 の 啓 蒙 主 義 とナポレオン 戦 争 による<br />
混 乱 などから「 軽 薄 さ」にまみれてしまっていて、しかも、その「 軽 薄 さ」が、 教 会 音 楽 のみ<br />
ならず、すべての 芸 術 分 野 にわたっていると 指 摘 する。<br />
Es ist auch in der Tat nicht zu leugnen,daß wohl schon seit länger als zwanzig Jahren ein<br />
Leichtsinn ohne Gleichen in jedes Kunststudium einriß.(Hoffmann 1985: 503)<br />
この 20 年 以 上 にわたり、 今 までになかったほどの 軽 薄 さがあらゆる 芸 術 活 動 に、 入 り<br />
込 んできた 事 実 は 否 定 できない 9 。<br />
第 2 部 では、いったん 彼 の 時 代 を 離 れ、 教 会 音 楽 の 本 質 とそれまでの 歴 史 についての 見<br />
解 が 述 べられる。 彼 は、「 音 楽 」の 本 質 を、「 宗 教 的 礼 拝 religiöser Kultus 」にみる。<br />
Die Ahnung des Höchsten und Heiligsten,der geistigen Macht, die den Lebensfunken<br />
in der ganzen Natur entzündet, spricht sich hörbar aus im Ton, und so wird Musik,<br />
Gesang, der Ausdruck der höchsten Fülle des Daseins —Schöpferlob!— Ihrem innern,<br />
eigentümlichen Wesen nach, ist daher die Musik, wie eben erst gesagt wurde, religiöser<br />
Kultus, und ihr Ursprung einzig und allein in der Religion, in der Kirche, zu suchen und zu<br />
finden, (ibid. : 504)<br />
生 命 の 火 花 をその 本 質 において 燃 えたたせるところの、もっとも 高 いものと 聖 なるもの、<br />
すなわち 精 神 的 な 力 、の 予 感 は、 音 によって 耳 に 聞 こえる 形 で、 語 られる。そして、 音<br />
楽 すなわち 歌 は、 存 在 のもっとも 高 いものとして 満 ち 足 りたものの 表 現 となる。すなわ<br />
ち、 創 造 者 への 賛 美 なのだ。 音 楽 は、その 内 的 で 特 有 な 本 質 にしたがって、 今 述 べたば<br />
かりのように、 宗 教 的 礼 拝 であり、その 起 源 は、ただ 宗 教 の 中 にのみ、 教 会 の 中 にのみ、<br />
探 し 求 められ、 見 いだされるべきだ。<br />
19
成 城 美 学 美 術 史<br />
第 17 号<br />
教 会 音 楽 の 歴 史 についての 考 察 においてホフマンは、パレストリーナの 時 代 、 即 ち 16 世<br />
紀 を 教 会 音 楽 の 頂 点 と 説 く。 彼 によれば、「パレストリーナの 音 楽 は、 簡 素 で、 真 正 で、 子<br />
供 のように 純 真 で、 敬 虔 で、 力 強 く、 堂 々としている。Palestrina ist einfach, wahrhaft,<br />
kindlich, fromm, stark und mächtig......」<br />
続 いて、その 様 式 の 特 徴 を 次 のように 述 べる。<br />
Noch war es in der Ordnung, bloß für Singstimmen, ohne Begleitung anderer Instrumente,<br />
höchstens der Orgel, zu setzen, und schon dieses erhielt die Einfachheit des choralartigen<br />
Gesanges, der durch keine bunten Figuren der Begleitung übertäubt wurde. (ibid. : 504)<br />
そこでは、 楽 器 の 伴 奏 なしで( 使 ってもせいぜいオルガン)、ただ 声 楽 声 部 のために 作<br />
曲 することは、また 規 範 に 則 していた。そしてそのことで 既 に、コラール 風 の 歌 の 簡 素<br />
さを 得 、その 歌 唱 は 伴 奏 の 色 とりどりの 音 型 で 耳 が 張 り 裂 けることはなかったのだ。<br />
彼 はパレストリーナを「 音 楽 の 父 Altvater der Musik」と 呼 び、その 活 躍 した 16 世 紀 をも<br />
って「 教 会 音 楽 ( 即 ち、 音 楽 一 般 )の 最 もすばらしい 時 代 がはじまった」と 称 える。それは、<br />
その 後 、 約 200 年 間 にわたり、キリスト 教 文 化 に 威 厳 と 力 を 与 え 続 けた。しかし、この 理<br />
想 的 な 時 代 は、18 世 紀 後 半 に 終 わりを 告 げる。ホフマンによれば、その 原 因 は、オペラの<br />
影 響 による「 旋 律 の 跳 躍 」の 流 行 に 始 まり、 器 楽 伴 奏 の 濫 用 にあった。<br />
彼 は 続 けて 述 べる。<br />
Aus der Kirche wanderte die Musik in das Theater, und kehrte aus diesem, mit all dem<br />
nichtigen Prunk, dem sie dort erworben, dann in die Kirche zurück.(ibid.: 506)<br />
音 楽 は 教 会 から 出 て 劇 場 に 移 り、そこで 獲 得 したあらゆるくだらない 華 美 さをもって、<br />
そこから 転 じ、 教 会 に 戻 ってきた。<br />
この 状 況 に、さらに 追 い 打 ちをかけたのは、 云 うまでもなく、 啓 蒙 主 義 である。<br />
In der letzten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts brach nun endlich jene Verweichlichung,<br />
jene ekle Süßlichkeit in die Kunst ein, die, mit der so genannten, allen tieferen religiösen<br />
Sinn tötenden Aufklärerei gleichen Schritt haltend, und immer steigend, zuletzt allen<br />
Ernst, alle Würde aus der Kichenmusik verbannte. Mag es hier unverhohlen gesagt werden,<br />
dass selbst der in seiner Art so große unsterbliche J. Haydn, selbst der gewaltige Mozart,<br />
sich nicht rein erhielten von dieser ansteckenden Seuche des weltlichen, prunkenden<br />
Leichtsinns. Mozarts Messen, die er jedoch bekanntlich auf erhaltenen Austrag nach der<br />
ihm vorgeschriebenen Norm componierte, sind beynahe seine schwäaachsten Werke. (ibid.<br />
: 522)<br />
20
セシリア 運 動 に 及 ぼした E. T. A. ホフマンの 影 響 について:A. F. J. ティボーとの 関 連 を 通 して<br />
18 世 紀 の 後 半 、とうとう 芸 術 の 中 に 柔 弱 さと 不 快 な 甘 ったるさが 押 し 入 った。それら<br />
は、あらゆる 深 遠 な 宗 教 的 感 情 を 殺 してしまう、いわゆる 啓 蒙 主 義 と 同 じ 歩 調 でいなが<br />
ら、しだいに 情 勢 を 増 大 し、ついには 教 会 音 楽 からすべての 真 摯 さと 威 厳 を 締 め 出 した。<br />
偉 大 で 不 滅 なハイドンや 力 強 いモーツァルトでさえも、この 世 俗 的 で 華 美 で 軽 薄 な 悪 疫<br />
から 免 れることはなかったということを、あからさまに 言 ってもよかろう。モーツァル<br />
トのミサ 曲 群 は、 彼 の 作 った 作 品 中 のレベルでは、 最 も 劣 悪 なものである。<br />
続 く 第 3 部 で、 危 機 を 迎 えた 教 会 音 楽 の 状 況 に 対 応 するために、ホフマンが 説 いている<br />
のは、 単 なる「パレストリーナに 帰 れ」という 呼 びかけではない。 冒 頭 でホフマンは、 現 代 (19<br />
世 紀 )の 作 曲 家 は、パレストリーナと 同 じように、 曲 を 作 ることはできない、と 述 べている<br />
のは 重 要 である。<br />
Rein unmöglich ist es wohl, daß jetzt ein Komponist so schreiben könne, wie Palestrina,<br />
Leo, und auch wie später Händel u. a.–Jene Zeit, vorzüglich wie das Christentum noch in<br />
der vollen Glorie strahlte, scheint auf immer von der Erde verschwunden, und mit ihr jene<br />
heilige Weihe der Künstler. (ibid. : 55)<br />
今 日 、ある 作 曲 家 がパレストリーナやレオ、さらに 後 の 時 代 のヘンデルその 他 の 作 曲 家<br />
のように 書 くことは、まったく 不 可 能 なことである。あの 時 代 、とりわけキリスト 教 が、<br />
いまだに、 栄 光 あふれて 輝 きに 満 ちていた 時 代 は、 永 久 に 地 上 から 姿 を 消 したように 思<br />
われる。そしてそれとともに、 芸 術 家 のかの 神 聖 な 荘 厳 さも 消 えたように 思 われる。<br />
ここにおいてホフマンが、19 世 紀 初 めに 盛 んであった 「パレストリーナに 帰 れ!」 という<br />
復 古 主 義 と、 一 線 を 画 したことに 注 目 したい。ホフマンは、「われわれ 自 身 の 様 式 を 持 たね<br />
ばならない」と 主 張 する。われわれ 自 身 の 様 式 とは、 何 か。ホフマンは、それをウィーン 古<br />
典 派 の 器 楽 作 法 に 求 めるのだが、ウィーン 古 典 派 の 作 曲 家 たちが、それを 使 いこなしたとは<br />
言 い 難 い、と 彼 は 考 える。<br />
Es ist nämlich wohl gewiß, daß die Instrumentalmusik sich in neuerer Zeit zu einer Höhe<br />
erhoben hat, die die alten Meister nicht ahnten, so wie an technischer Fertigkeit die neuern<br />
Musiker die alten offenbar weit übertreffen.Haydn, Mozart, Beethoven entfalteten<br />
eine neue Kunst, deren erster Keim sich wohl eben erst in der Mitte des achtzehnten<br />
Jahrhunderts zeigte.Daß der Leichtsinn, der Unverstand, mit dem erworbenen Reichtum<br />
übel haushaltete, daß endlich Falschmünzer ihrem Rauschgolde das Ansehen der<br />
Gediegenheit geben wollten, war nicht die Schuld jener Meister, in denen sich der Geist so<br />
herrlich offenbarte. (ibid. : 526)<br />
近 年 においては 器 楽 音 楽 が、かつての 巨 匠 たちが 予 想 もしなかったような 高 みに 達 し<br />
ていることはおそらく 間 違 っていないであろう。 同 様 に、 近 年 の 音 楽 家 [= 作 曲 家 ]は、<br />
技 術 的 な 巧 みさで、かっての 音 楽 家 をはるかに 凌 駕 しているということも。ハイドン、<br />
21
成 城 美 学 美 術 史<br />
第 17 号<br />
モーツァルト、ベートーヴェンは 新 しい 芸 術 を 展 開 させたが、その 芸 術 の 最 初 の 萌 芽 は、<br />
おそらく 18 世 紀 半 ばになってようやく 現 れたのだ。 軽 薄 さと 無 理 解 が、 獲 得 した 富 を<br />
浪 費 してしまったこと、そして 贋 金 作 りが 自 分 たち 偽 造 通 貨 に 優 れた 作 品 だという 外 見<br />
を 与 えようとしたこと、それは 彼 らのような 巨 匠 たちの 罪 ではない。 彼 らの 中 では 精 神<br />
性 がきわめて 輝 かしくあらわれていた。<br />
ホフマンに 従 えば、 器 楽 を 教 会 音 楽 に 濫 用 してはならないし、また 歌 ( 声 楽 )をなおざり<br />
にすべきではない、とする 大 きな 課 題 が 残 る。<br />
Wahr ist es, daß beinahe in eben dem Grade, als die Instrumentalmusik stieg, der Gesang<br />
vernachlässigt wurde, und daß mit dieser Vernachlässigung, die von den Komponisten<br />
ausging, jenes völlige Ausgehen der guten Chöre, das von mancher kirchlichen Einrichtung<br />
(Aufhebung der Klöster u. s. w.) herrührte, gleichen Schritt hielt ; daß es unmöglich ist, jetzt<br />
zu Palestrinas Einfachheit und Größe zurückzukehren, wurde schon gesagt: inwiefern aber<br />
der neu erworbene Reichtum ohne unheilige Ostentation in die Kirche zu tragen sei, das<br />
fragt sich noch. (ibid. : 527)<br />
器 楽 音 楽 の 占 める 度 合 いが 増 大 するのとほとんど 同 じ 度 合 いで、 声 楽 がなおざりにされ<br />
るということ、( 修 道 院 の 廃 止 など) 一 連 の 教 会 の 施 設 に 由 来 する 優 れた 合 唱 団 のあの<br />
完 全 な 欠 乏 が、 作 曲 家 たちに 起 因 するこのおろそかにするという 行 為 と 歩 調 を 合 わせた<br />
ことは 真 実 である。 現 代 においてパレストリーナの 簡 潔 さと 偉 大 さに 戻 ることが 不 可 能<br />
であるということは、 既 に 述 べた。だが、 新 たに 獲 得 された 富 〔= 器 楽 音 楽 のこと〕を、<br />
不 信 心 なひけらかしなしに、どの 程 度 まで 教 会 に 取 り 入 れるか、ということは、 今 なお、<br />
疑 問 である。<br />
第 4 部 でホフマンは、これから 教 会 音 楽 を 作 ろうと 志 す 若 い 作 曲 家 向 けに 語 る 形 で 結 論<br />
を 述 べる。「 真 の 威 厳 ある 教 会 音 楽 」を 書 こうとする 者 は、まず 自 らの 内 部 に「 真 実 と 敬 虔 の<br />
精 神 」が 宿 っているかを 確 かめねばならない。この 精 神 なくしては、「 天 の 国 の 驚 異 」につい<br />
て 語 ることができないからである。この 精 神 は「 内 面 的 」なものでなければならない。わず<br />
かでも 世 俗 的 な 欲 望 や 知 識 のひけらかしといった「 外 的 な 動 機 」があれば、 誤 謬 と 不 遜 に 陥<br />
ってしまうと 説 く。<br />
Ist der junge Komponist nicht durch den Leichtsinn der Welt verdorben, so werden ihn die<br />
Werke der alten Meister auf wunderbare Weise erheben …(ibid. : 527)<br />
世 の 軽 薄 さに 堕 落 していない 若 い 作 曲 家 ならば、 過 去 の 巨 匠 たちの 作 品 が、 彼 をすばら<br />
しいやり 方 で 高 めることであろう。<br />
そのためには 特 に 対 位 法 を 学 習 しなければならない、そして、 真 に 教 会 的 な 旋 律 ( 主 題 )<br />
を 創 り 出 す(Invention)ことができるかどうかが、その 作 曲 家 の 試 金 石 となると、ホフマン<br />
22
セシリア 運 動 に 及 ぼした E. T. A. ホフマンの 影 響 について:A. F. J. ティボーとの 関 連 を 通 して<br />
は 主 張 する。<br />
Alles harmonische Ausarbeiten, dem Kirchenstil gemäß, verbirgt nicht das profane Thema;<br />
so kann eine, im theoretischen Sinn, rein gearbeitete Fuge gar nicht kirchenmäßig sein; so<br />
können oft kunstreiche Imitationen den hüpfenden, dem Konzertsaal oder dem Theater<br />
abgeborgten Satz nur noch mehr nach seinem ursprünglichen Charakter ins Licht stellen.<br />
(ibid. : 527)<br />
教 会 様 式 にふさわしい 和 声 付 けで 仕 上 げることは、 世 俗 的 な 主 題 を、しばしば 巧 妙 な 模<br />
倣 も 隠 せないし、 理 論 的 な 意 味 での「 純 粋 なフーガ」に 仕 上 げても、 教 会 音 楽 らしくは<br />
ならない。<br />
技 巧 に 富 んだ 模 倣 の 数 々も、 演 奏 会 場 や 劇 場 から 取 り 込 んだ 楽 曲 を、もっとあからさま<br />
に、その 本 来 の 性 格 に 沿 ってむきだしにしてしまう。<br />
また、 現 代 の 作 曲 家 は、 多 彩 な 楽 器 という 時 代 特 有 の 状 況 に 置 かれている。それを、 生 か<br />
すか、どうかは 作 曲 家 にかかっている、と 言 う。この 主 張 はホフマンがこのエッセイで 訴 え<br />
たかった 大 きな 論 点 の1つであるが、 教 会 音 楽 について 検 討 する 本 論 の 趣 旨 からは 外 れるの<br />
で、これ 以 上 触 れない。<br />
器 楽 と 教 会 音 楽 の 関 係 について、 彼 はこう 続 ける。<br />
Der Glanz der mannigfachen Instrumente, von denen manche so herrlich im hohen<br />
Gewölbe tönen, schimmert überall hervor: und warum sollte man die Augen davor<br />
verschließen, da es der forttreibende Weltgeist selbst ist, der diesen Glanz in die<br />
geheimnisvolle Kunst des neuesten, auf innere Vergeistigung hinarbeitenden Zeitalters<br />
geworfen hat ? Es ist nur der falsche Gebrauch dieses Reichtums, der ihn schädlich macht:<br />
er selbst ist ein wohlerworbenes, herrliches Eigentum, das der wahre, fromme Komponist<br />
nur zu größerer Verherrlichung des Hohen, Überirdischen, das seine Hymnen preisen,<br />
anwendet. (ibid. : 527)<br />
だが 現 代 の 富 の 多 くが 音 楽 に 与 える 飾 りの 場 合 とは 違 って、 音 楽 がその 内 面 で 今 日 の 作<br />
曲 家 に 開 花 することがほとんどない、ということは 確 かである。 多 彩 な 楽 器 の 輝 き―<br />
それらの 中 のいくつかは 非 常 に 堂 々と 高 い 丸 天 井 にまで 鳴 り 響 くのだが―は、 至 るとこ<br />
ろで 輝 きを 発 している。そして、それが「 進 み 続 ける 世 界 精 神 」そのものであり、また<br />
その 精 神 が 内 面 的 な 精 神 化 に 向 かって 努 力 している 最 も 新 しいこの 時 代 の 神 秘 的 な 芸 術<br />
に 輝 きを 与 えるものであるならば、なぜそこから 目 をそらす 必 要 があろうか。この 富 を<br />
恥 ずべきものにするのは、それを 誤 って 使 用 した 時 だけである。それ 自 体 は、 正 当 に 得<br />
られた 威 厳 のある 所 有 物 であり、 真 の 敬 虔 な 作 曲 家 であれば、それをただ 自 らの 賛 歌 が<br />
讃 える 高 尚 で 現 世 を 超 えたものを、より 力 強 く 称 賛 することのみに 用 いるのである。<br />
ホフマンによれば、 真 の 教 会 音 楽 、とりわけ 聖 歌 が 完 全 に 没 落 するのを 食 い 止 めているの<br />
23
成 城 美 学 美 術 史<br />
第 17 号<br />
が、ジングアカデミーや 合 唱 協 会 などの、 賞 賛 されるべき 音 楽 協 会 の 活 動 であり、 彼 は、こ<br />
れらを 国 家 の 活 動 とすべきと 主 張 する。<br />
最 後 に、ホフマンは、 遠 くない 時 代 に、 真 の 教 会 音 楽 を 復 興 しようという 希 望 がかなうか<br />
もしれないとの 期 待 をにじませて、このエッセイを 閉 じる。<br />
Immer weiter fort und fort treibt der waltende Weltgeist; nie kehren die verschwundenen<br />
Gestalten, so wie sie sich in der Lust des Körperlebens bewegten, wieder: aber ewig,<br />
unvergänglich ist das Wahrhaftige, und eine wunderbare Geistergemeinschaft schlingt ihr<br />
geheimnisvolles Band um Vergangenheit, Gegenwart und Zukunf. Noch leben geistig die<br />
alten, hohen Meister: nicht verklungen sind ihre Gesänge ...(ibid. : 531)<br />
支 配 的 な 世 界 精 神 は、 前 へ 前 へと 流 れていく。 消 え 去 った 形 象 は、 肉 体 的 生 の 喜 びのな<br />
かで 動 いていたように、 再 び 戻 ることはない。しかし 真 理 は 永 遠 で、 不 滅 である。そし<br />
て 素 晴 らしい 心 霊 共 同 体 は 過 去 、 現 在 、 未 来 をその 秘 密 に 満 ちた 帯 で 巻 き 付 ける。 過 去<br />
の 偉 大 な 巨 匠 たちはまだ 霊 魂 において 生 きていて、 彼 らの 歌 はまだ 鳴 り 止 まない。…<br />
Mag die Zeit der Erfüllung unseres Hoffens nicht mehr fern sein, mag ein frommes Leben in<br />
Friede und Freudigkeit beginnen, und die Musik frei und kräftig ihre Seraphimsschwingen<br />
regen, um aufs neue den Flug zu dem Jenseits zu beginnen, das ihre Heimat ist, und von<br />
dem Trost und Heil in die unruhvolle Brust des Menschen hinabstrahlt !(ibid. : 531)<br />
我 々の 希 望 がかなう 時 代 は 遠 くないかもしれないし、 敬 虔 な 生 活 は、 平 和 と 喜 びのうち<br />
に 始 まるかもしれない。そして 音 楽 は 自 由 で 力 強 く 天 使 セラフィムの 翼 をはばたかせる<br />
かもしれない、 新 たに 彼 岸 へと 飛 翔 をはじめるために。そこ( 彼 岸 )は 音 楽 の 故 郷 であり、<br />
そこから 慰 めと 至 福 の 光 が、 人 間 の 不 安 な 胸 に 射 し 入 るのだ!<br />
以 上 、セシリア 運 動 に 関 連 する 箇 所 を 中 心 に、このエッセイを 読 み 下 してみたが、これが<br />
後 述 のティボーの 著 書 の 約 10 年 前 に 書 かれていることに 驚 く。あたかも 年 代 が 逆 転 してい<br />
るように 思 えるではないか。ここでホフマンが、 初 期 ロマン 主 義 者 たちが 金 科 玉 条 としてい<br />
た「パレストリーナ 回 帰 」の 理 念 を 否 定 し、 現 代 の 作 曲 家 には、パレストリーナのような 作<br />
品 を 創 ることはできないと 断 じていることは、 当 時 としては 目 新 しい 主 張 で、 後 のティボー<br />
やセシリア 主 義 者 たちに 引 き 継 がれていく。<br />
なお、ホフマンにおける、ア・カペラ 愛 好 と 器 楽 優 位 観 の 関 係 について、 研 究 者 James<br />
Garratt は 次 のように 説 明 している。<br />
With Hoffmann —as with Tieck— a cappella choral music and absolute instrumental music<br />
are not simply placed in opposition, but rather are cast in a complex reciprocal relation.<br />
(Garratt 2006: 53)<br />
ホフマンやティークにとって、ア・カペラ 聖 歌 の 音 楽 と 絶 対 器 楽 音 楽 は、 単 純 に 対 立 す<br />
24
セシリア 運 動 に 及 ぼした E. T. A. ホフマンの 影 響 について:A. F. J. ティボーとの 関 連 を 通 して<br />
る 存 在 ではなく、むしろ 相 互 補 完 の 関 係 にあった。<br />
自 身 、オペラ 作 曲 をしたり、 生 活 のため 劇 場 の 音 楽 監 督 を 務 めた 10 ホフマンにとって、 器<br />
楽 音 楽 を 捨 てることは、 絶 対 にできなかった。 一 方 で、ロマン 主 義 者 から 教 えられた 古 いア・<br />
カペラの 教 会 音 楽 にも 惹 かれるものがあった。そうした 彼 にとって、 両 者 の 関 係 は、 対 立 す<br />
るものでなかった、という Garratt の 解 釈 は、 説 得 力 を 持 つ。<br />
タイトルの「 新 旧 の 教 会 音 楽 」に 戻 ると、「 旧 」とは、 器 楽 を 伴 わない、 声 楽 のみによるパ<br />
レストリーナのような 教 会 音 楽 で、「 新 」とは、その 逆 の、 器 楽 を 伴 う 当 代 ( 現 代 )の 教 会 音<br />
楽 となろうか。(しかし、 現 代 の 教 会 音 楽 の 担 い 手 たちは、「 器 楽 」 を、 十 分 に 使 いこなし<br />
ていないとする)ホフマンの 中 では、 旧 =「キリスト 教 的 」= 「 純 粋 な 声 楽 」 という 理 念 と、<br />
そして、「 新 しい 教 会 音 楽 」= 「ロマン 主 義 的 」 という 理 念 が 想 定 されていると 考 えられる。<br />
Garaatt に 倣 えば、この2つは 対 立 軸 でなく、「 相 互 補 完 」 の 関 係 にあることになる 11 。<br />
2–2 ホフマンの 受 容 と 影 響<br />
ホフマンは 人 気 作 家 であったものの、 同 時 代 ではハイネなど 一 部 の 識 者 を 除 いては、 文 学<br />
的 な 評 価 を 得 ておらず、 通 俗 作 家 、 戯 作 家 の 評 価 に 甘 んじていた。ホフマンはむしろドイツ<br />
国 外 で 高 く 評 価 され、 特 にフランスにおいてバルザック、ユゴー、ゴーティエ、ジョルジュ・<br />
サンド、デュマ、ネルヴァル、ボードレール、モーパッサンなどの 作 家 達 に 大 きな 影 響 を 及<br />
ぼした。ロシアではプーシキン、ドストエフスキーなどがホフマンを 愛 好 し、その 影 響 はエ<br />
ドガー・アラン・ポーにも 及 んでいる。ドイツでホフマンが 評 価 されるのは、19 世 紀 後 半<br />
になってからとされる 12 。<br />
彼 の 音 楽 評 論 が、シューマンに 大 きな 影 響 を 与 えたことは 有 名 だが 13 、ダールハウスは、<br />
AMZ の 定 期 購 読 者 であったベートーヴェンが、ホフマンのこの 評 論 を 読 んだことが、《ミサ・<br />
ソレムニス》を 作 曲 する 動 機 の1つとなった 可 能 性 がある、との 見 解 を 述 べている(ダール<br />
ハウス 1997: 287)。ダールハウスの「ベートーヴェンは 古 い 教 会 様 式 と 現 代 器 楽 との 橋 渡 し<br />
の 困 難 さを 感 じていた」という 指 摘 は、ホフマンが 直 面 していたものでもあった。ベートー<br />
ヴェンの《ミサ・ソレムニス》(1824 年 初 演 )は、まさにその 解 答 であったが、1822 年 に 死<br />
去 したホフマンは、それを 耳 にすることができなかった。<br />
このように、 彼 の 音 楽 評 論 は 専 門 家 の 間 では 知 られていたが、1814 年 のエッセイ "Alte<br />
und neue Kirchenmusik" は 単 行 本 化 されず、 読 者 は 限 られており、この 評 論 の 趣 旨 は、 数 年<br />
後 に 刊 行 された『セラーピオン 朋 友 会 員 物 語 』 内 の 同 題 の 挿 話 によって、 広 まった。<br />
セシリア 主 義 者 たちが、ホフマンの 著 作 を 読 んだか、については、 何 の 証 左 も 見 出 せない。<br />
ティボーがホフマンを 読 んだかについても 同 様 だが、ティボーの 思 想 にホフマンの 影 響 があ<br />
ることは、 後 述 のように、 多 くの 評 者 が 認 めるところである。 以 下 では、セシリア 主 義 者 た<br />
ちが、ティボーを 通 してホフマンを 知 った、という 可 能 性 を、 追 求 していこう。<br />
25
成 城 美 学 美 術 史<br />
第 17 号<br />
2–3 真 の 教 会 音 楽<br />
真 の 教 会 音 楽 とは 何 か、という 疑 問 は、 声 の 大 小 はあるものの、いつの 時 代 にも、 問 いか<br />
けられてきた。ほかならぬモーツァルト 自 身 の 手 紙 の 中 にも 見 受 けられるほどである 14 。<br />
18 世 紀 末 から 19 世 紀 初 めにかけての 教 会 音 楽 をめぐる 音 楽 思 潮 を、ホフマンの 音 楽 エッ<br />
セイ 集 の 英 訳 編 者 チャールトン 15 が “Alte und neue Kirchenmusik” の 節 に 施 した 優 れた 解 題<br />
を 参 考 に、 考 察 してみよう。 彼 は 最 初 に、 有 名 なズルツァー16 の 芸 術 事 典 の Kirchenmusik<br />
の 項 目 を 紹 介 する。<br />
Man hat diesem Chorale nicht nur noch mehrstimmig gemacht, sondern ihm noch<br />
verschiedene andere Formen gegeben, und einige Stimmen davon verschiedentlich<br />
ausgeziert: daher der sogenannte figurierte Gesang entstanden ist, von dem gegenwärtig so<br />
viel Mißbrauch gemacht wird, dass man oft sich den der Kirchenmusik besinnen muß, ob<br />
man in der Kirche, oder in der Oper sey. (Sulzer 1792–1799: 20)<br />
このコラール[ 聖 歌 ]は 多 声 で 作 られたのみならず、[ 教 会 以 外 の]いろいろな 形 式 を 与<br />
えられ 二 三 の 声 部 は 様 々に 装 飾 された。そこから、いわゆる「 手 の 込 んだ[ 装 飾 された]<br />
歌 」が 生 じた。そういった 音 楽 が 目 下 たいへん 濫 用 されているので、 教 会 音 楽 を 聴 いて<br />
いる 人 は、 果 たして 自 分 は 教 会 にいるのか、オペラ 劇 場 にいるのか、しばしば 考 えなけ<br />
ればならない[わからなくなる]ほどだ。<br />
チャールトンは、18 世 紀 末 の 教 会 音 楽 の 状 況 を 説 明 するのに、この 文 献 を 引 用 したに 過<br />
ぎないのだが、 上 の 文 章 がセシリア 運 動 の 主 張 と 何 と 似 通 っていることか、 著 者 名 を 伏 せ<br />
て 読 めば、 半 世 紀 後 の 人 たちの 文 章 と 勘 違 いするかもしれない。ズルツァーのこの 事 典 は、<br />
1775 年 に 出 版 されており、こういった 思 潮 は、 既 に 1770 年 代 前 半 には、かなり 広 まって<br />
いたと 考 えられる。<br />
19 世 紀 になってからでは、 同 じくチャールトンの 言 及 している 初 期 ロマン 派 の 作 家 、ル<br />
ートヴィッヒ・ティーク 17 の 文 章 をみてみよう。 彼 は、 小 説 『 夢 の 神 Phantasus』の 中 で、エ<br />
ルンストという 登 場 人 物 を 通 して、 現 在 の 教 会 音 楽 は 堕 落 していて、 真 の 教 会 音 楽 の 名 に 値<br />
するのは、パレストリーナからペルゴレージまでのイタリアの 大 家 の 作 品 だけとの 発 言 をし<br />
ている。それに 続 けて 彼 は、 音 楽 の 歴 史 を 3 つの 時 代 ( 現 代 も 含 めると 4 期 )に 分 けて 説 明<br />
しようと 試 みる。 最 初 は、パレストリーナに 代 表 される 時 代 で、 歌 は、 激 しい 動 きなしに、<br />
魂 の 中 に 永 遠 の 像 を 呼 び 覚 ます。 続 いては、 人 が 太 古 の 昔 に 失 った 純 粋 な 潔 白 さを 取 り 戻 そ<br />
うとして、 楽 園 を 再 び 手 に 入 れようとする 時 代 で、レオとマルチェロが 活 躍 する。 第 三 の 時<br />
期 は、 音 楽 は 無 邪 気 な 子 供 のように、 痛 みと 喜 びを 甘 い 旋 律 の 中 で 混 ぜ 合 わせる、ペルゴレ<br />
ージの 時 代 である。そして 現 在 (19 世 紀 )、 音 楽 は、その 神 々しい 純 白 さを 失 ってしまって<br />
いる 18 。 後 述 のティボーの 時 代 区 分 と 照 らし 合 わせると 興 味 深 い。<br />
このように、「 現 代 の 教 会 音 楽 がオペラ 的 で 堕 落 している」 という 認 識 は、18 世 紀 末 には、<br />
かなり 広 まっていた。ホフマンの 評 論 は、こうした 認 識 のもとで、 生 まれた。<br />
26
セシリア 運 動 に 及 ぼした E. T. A. ホフマンの 影 響 について:A. F. J. ティボーとの 関 連 を 通 して<br />
3. ティボーの 主 張<br />
ティボーは、ハイデルク 大 学 の 法 学 教 授 を 長 く 務 めた 有 名 な 学 者 であるが、 同 時 に 熱 烈 な<br />
音 楽 愛 好 者 として 知 られていた。 彼 はハイデルベルク 大 学 に 赴 任 する 前 から、 古 い 宗 教 音 楽<br />
に 関 心 を 持 っていたが、そこに 来 てからは、 女 性 詩 人 で 教 育 家 のカロリーネ・ルドルフィの<br />
家 で 毎 日 曜 日 に 開 かれる 合 唱 サークルの 指 揮 をした。 彼 女 が 亡 くなってからは、 集 会 の 場 を<br />
彼 の 自 宅 に 移 して 活 動 を 続 けた。 彼 の 合 唱 団 は、ツェルターの 有 名 なジング・アカデミーに<br />
比 肩 するほどの 評 判 を 取 るようになっていく。 演 奏 会 は 毎 週 木 曜 に 行 われ、 彼 の 亡 くなる<br />
1840 年 まで 続 いたが、 年 4 回 の 外 部 見 学 会 を 除 いては 非 公 開 とされたため、 数 少 ない 見 学<br />
会 の 日 には、ゲーテやメンデルスゾーン、シューマンらの 著 名 人 も 押 しかけるほどの 人 気 を<br />
博 した。 彼 の 演 奏 会 は、ピアノによる 通 奏 低 音 を 伴 ったア・カペラで 行 われることが 多 かっ<br />
た 19 。<br />
ティボーは、その 経 験 をふまえて、1824 年 に Ueber Reinheit der Tonkunst( 音 芸 術 の 純 粋<br />
性 について)という 小 型 版 の 書 物 を 出 版 した 20 。この 書 は 好 評 を 得 て 版 を 重 ね、 後 のヴィッ<br />
トらのセシリア 運 動 に 大 きな 影 響 を 与 えることになる 21 。<br />
彼 の 主 張 の 一 部 を 引 用 してみよう。<br />
So sind denn unsere neueren Messen und andere Kirchenstücke oft in ein rein verliebtes,<br />
leidenschaftliches Wesen ausgeartet und tragen ganz und gar das Gepräge der weltlichen<br />
Oper und sogar wohl der gesuchtesten, also der recht gemeinen Oper welches freilich dem<br />
Haufen am behaglichsten ist, und den Vornehmen noch mehr wie den Geringen. Selbst die<br />
Kirchensachen von Mozart und Haydn verdienen jenen Tadel, und beide Meister haben ihn<br />
auch selbst ausgesprochen. Mozart lächelte unverhohlen über seine Messen, und mehrmals,<br />
wenn man eine Messe bei ihm bestellte, protestierte er, weil er nur für die Oper gemacht<br />
sei. Allein man bot ihm wohl für jede Messe 100 Louis d'ors und da konnte er nicht<br />
widerstehen, erklärte aber lachend, was Gutes in seinen Messen sei, das werde er nachher<br />
schon für seine Opern von dorther abholen ... (Einstein 1947 : 362 22 )<br />
かくしてわれわれの 近 代 のミサ 曲 その 他 の 教 会 音 楽 は、しばしば 全 く 浮 薄 な 情 熱 的 な 存<br />
在 にまで 堕 落 してしまい、 徹 頭 徹 尾 、 世 俗 的 なオペラの、あまつさえ 最 新 流 行 の、つま<br />
り 非 常 に 卑 俗 なオペラの 特 性 を 帯 びているのである。 当 然 のことながら、 特 性 たる、 大<br />
衆 にとってきわめて 快 適 なものであり、 身 分 の 高 い 人 々は 庶 民 たちよりもいっそうそれ<br />
を 歓 迎 するのである。モーツァルトとハイドンの 教 会 楽 曲 でさえ、この 非 難 に 値 するし、<br />
両 巨 匠 自 身 がこのことを 口 にしている。モーツァルトは、 彼 のミサ 曲 について、あから<br />
さまに 笑 いものにしたし、ミサ 曲 を 注 文 されると、 自 分 はただオペラのためにのみふさ<br />
わしいのだからと 称 して 何 度 も 異 議 を 申 し 立 てた。しかしながら 彼 は、ミサ 曲 1 曲 に<br />
対 しておよそ 100 ルイドールを 提 供 されると、もはや 抵 抗 できなかった。だが、ミサ<br />
曲 の 中 の 優 れたところは、あとで 必 ずオペラのために 取 ってくるだろうと、 笑 いながら<br />
宣 言 した。(Einstein = 浅 井 、1961:430)<br />
27
成 城 美 学 美 術 史<br />
第 17 号<br />
ティボーの 主 張 によれば、 音 楽 の 本 質 とは、「 心 情 を 鼓 舞 し、 醇 化 し、 高 めるもの」であり「 感<br />
覚 、 感 情 、 情 緒 のあらゆる 状 態 を、 力 強 さと 純 粋 さのうちに 表 現 する」ものでなければなら<br />
なかった。( 海 老 澤 1972: 149)<br />
著 書 Ueber Reinheit der Tonkunst の 構 成 は、 以 下 のようなものである。<br />
Ⅰ Ueber den Choral. ( 聖 歌 について 23 )<br />
Ⅱ Ueber Kirchenmusik ausser dem Choral. ( 聖 歌 以 外 の 教 会 音 楽 について)<br />
Ⅲ Ueber Volksgesänge. ( 民 謡 について)<br />
Ⅳ Ueber Bildung durch Muster. ( 模 範 による 陶 冶 について)<br />
Ⅴ Ueber den Effekt. ( 効 果 について)<br />
Ⅵ Ueber das Instrumentiren. ( 楽 器 付 けの 扱 いについて)<br />
Ⅶ Ueber genaue Vergleichung der Werke großer Meister( 巨 匠 の 作 品 の 正 確 な 比 較 につい<br />
て)<br />
Ⅷ Ueber Vielseitigkeit. ( 多 面 性 について)<br />
Ⅸ Ueber Verdarbenheit der Texte. ( 歌 詞 の 頽 廃 について)<br />
Ⅹ Ueber Singvereine. ( 合 唱 団 について)<br />
ティボーは 同 書 の 中 で、 音 楽 の 様 式 を、 次 の 3 つに 分 類 している。<br />
Auf diese Art entstehen dann für die Musik drei Stile: der Kirchenstil, allein der<br />
Frömmigkeit gewidmet, der Oratorienstil, welcher das Große und Ernste auf menschliche<br />
Art geistreich nimmt, und der Opernstil, welcher alles, was von den Sinnen und der<br />
Leidenschaft ausgeht, durch poetische Darstellung vergegenwärtigt. (Thibaut 1851: 50)<br />
即 ち、<br />
(1) 「 教 会 様 式 Kirchenstil」=ひたすら 敬 虔 さ、 信 仰 に 捧 げられる<br />
(2) 「オラトリオ 様 式 Oratorienstil」= 人 間 的 な 偉 大 さやまじめさを 表 す<br />
(3) 「オペラ 様 式 Opernstil」= 感 覚 や 情 熱 に 由 来 するもののすべてを 詩 的 な 表 現 によっ<br />
て 実 現 する。<br />
そして、これらの 混 合 した 様 式 は「 考 えられない」とした。<br />
彼 は、(1) の 代 表 として、パレストリーナを 賞 賛 し、(2) に、バッハ、ハッセ、グラウン、<br />
ヘンデルなどをあげたあと、 最 近 半 世 紀 の 音 楽 の 状 況 について、「『 教 会 様 式 』は 殆 どまった<br />
く 失 われてしまい、『オラトリオ 様 式 』はほとんど 至 るところで「オペラ 様 式 』に 移 っていっ<br />
てしまっているが、『オペラ 様 式 』は、しばしば 不 純 なもの、 気 狂 いじみたもの、 卑 俗 なもの、<br />
常 軌 を 逸 したものに 陥 っており、しかもその 様 式 は、 教 会 の 中 にひそかに 持 ち 込 まれようと<br />
28
セシリア 運 動 に 及 ぼした E. T. A. ホフマンの 影 響 について:A. F. J. ティボーとの 関 連 を 通 して<br />
している」と、「オペラ 様 式 」に 対 する 嫌 悪 の 感 情 を 生 々しく 述 べている。<br />
そして、「 教 会 様 式 」の 教 会 音 楽 においては、すべてが「 中 庸 (mäßig)で、 真 面 目 (ernst)<br />
で、 尊 厳 を 保 ち(würdig gehalten)、 高 尚 で 静 穏 の 中 にある」べきであるとし、これが 実 現<br />
されているのが、ほかならぬパレストリーナの 音 楽 であるとした。( 同 : 149)<br />
このようにティボーの 眼 にも、 当 時 の 教 会 音 楽 は、まさに「 堕 落 」した 状 況 に 映 った。<br />
ところで、 彼 が 著 書 の 中 で、 口 を 極 めて 激 賞 していたのは、ヘンデルの《メサイア》であ<br />
る。 彼 にとって、 最 高 の 存 在 は「 教 会 様 式 」であるが、それが 失 われた 現 在 、 頼 れるのは『オ<br />
ラトリオ 様 式 』で、その 代 表 が《メサイア》であった 24 。<br />
ティボーの 主 張 の 拠 ってたったのは、18 世 紀 後 半 から 精 々 19 世 紀 初 めの 音 楽 史 的 知 識 で<br />
あった。 彼 の 著 者 は 19 世 紀 末 まで 版 を 重 ね 受 け 入 れられた。<br />
3–1 ティボーとホフマン : 類 似 点 と 相 違 点<br />
当 時 の 教 会 音 楽 を、 堕 落 した 状 況 と 捉 えるティボーの 主 張 は、 多 くの 点 で、ホフマンと 共<br />
通 している。 彼 が、 合 唱 指 揮 を 通 じ 実 践 したのは、「 昔 の 音 楽 、 古 典 的 な 音 楽 の 復 興 」であった。<br />
すなわち、 当 時 の 堕 落 した 音 楽 趣 味 を 純 粋 化 するために、 過 去 の 大 家 の 宗 教 曲 、 特 にパレス<br />
トリーナやヘンデル、およびその 同 時 代 人 の 音 楽 の 重 要 性 を 説 いたのである。 随 所 で 古 いア・<br />
カペラ 音 楽 を 激 賞 するティボーであるが、この 書 をよく 読 めば、 彼 が、パレストリーナと 並<br />
んでヘンデルを 尊 敬 していたように、 単 純 な 器 楽 排 斥 論 者 でなかったことがわかる 25 。<br />
このことを、 次 の2つの 引 用 によって 確 認 しよう。<br />
Die große alte Kirchenmusik ist bloß für Singstimmen gesetzt und gewiß mit vollem<br />
Recht, insofern man auf vollendete Sänger rechnen kann. Denn kein Instrument hat den<br />
seelenvollen Ausdruck der menschlichen Stimmen. (Thibaut 1826 : 176)<br />
偉 大 な 古 い 教 会 音 楽 は、 歌 の 声 楽 部 のみで 出 来 ていて、 完 成 された 歌 手 に 頼 ることがで<br />
きるという 限 りにおいては、 間 違 いなく 全 面 的 な 正 当 性 をもっている。というのは、ど<br />
んな 楽 器 も 人 間 の 声 の 感 情 のこもった 表 現 ができないからだ。<br />
Kein Vernünftiger wird es in Abrede stellen, daß die Instrumente ihren eigenen hohen<br />
Wert haben, weil sie nämlich viel mehr mit Leichtigkeit behandelt werden können als die<br />
menschliche Stimme, einen viel größeren Umfang haben und insofern dazu beitragen, daß<br />
man imstande ist, die musikalische Mannigfaltigkeit ins Unendliche zu vervielfältigen.<br />
(Thibaut 1826 : 124)<br />
分 別 ある 人 なら、 楽 器 がそれ 固 有 の 高 い 価 値 を 持 っていることを 否 定 することはないだ<br />
ろう。なぜなら、 楽 器 は、 大 きな 音 域 を 持 ち、それゆえに 音 楽 的 な 多 種 多 様 さを 限 りな<br />
く 増 大 する 能 力 があるということに 貢 献 するという 限 りにおいて、 人 間 の 声 より 容 易 に<br />
扱 われうるからである。<br />
このように、ティボーは、ア・カペラによる 古 い 教 会 音 楽 を 推 奨 していたものの、しかし、<br />
29
成 城 美 学 美 術 史<br />
第 17 号<br />
単 純 な 器 楽 排 斥 論 とは 一 線 を 画 していたことがわかる 26 。<br />
ポイントは、ホフマンが、 現 代 (19 世 紀 )の 作 曲 家 は、パレストリーナと 同 じような 無 伴<br />
奏 の 曲 を 作 ることはできないとして、 器 楽 を 活 用 した 教 会 音 楽 を 作 るべきと 主 張 していたの<br />
と 同 様 に、ティボーが、 器 楽 をうまく 活 用 したヘンデルのオラトリオを 愛 していたことである。<br />
ティボーのア・カペラと 器 楽 付 き 教 会 音 楽 への 対 応 は、これまで 述 べてきたように、 多 少<br />
の 表 現 の 違 いはあれ、 大 筋 はホフマンと 変 わりないように 思 われる。ティボーにおいても、<br />
ホフマンと 同 様 、その2つは、 対 立 軸 でなく、 相 互 補 完 の 存 在 であったと 言 えよう。 大 きく<br />
異 なるのは、 新 しい 教 会 音 楽 創 作 の 姿 勢 で、ティボーは、 創 作 を 手 がけず、もっぱら 合 唱 運<br />
動 と 呼 応 して、 彼 の 推 奨 する 古 い 時 代 の 作 品 の 演 奏 普 及 に 努 力 したということである。<br />
4. カトリック 教 会 の 伝 統<br />
セシリア 運 動 の 検 討 に 入 る 前 にカトリック 教 会 の 伝 統 的 な 思 考 法 について 簡 潔 に 確 認 して<br />
おきたい。セシリア 運 動 は 教 会 内 の 改 革 運 動 なので、その 思 考 法 が 教 会 の 伝 統 を 踏 まえたも<br />
のであるのは 自 明 なことである。カトリック 教 会 = 教 皇 庁 が 「 器 楽 付 き 教 会 音 楽 」 をどう 考<br />
えてきたか、18 世 紀 の 回 勅 、19 世 紀 末 の 教 皇 自 発 教 令 、20 世 紀 の 典 礼 憲 章 の 3 つで 確 認 し<br />
ておこう 27 。<br />
1 回 勅 Enciclica Annus qui<br />
1749 年 、 教 皇 ベネディクトス 十 四 世 は、 典 礼 音 楽 がオペラ 風 な 華 美 に 傾 くことを 戒 める<br />
ためこの 回 勅 を 発 した。 回 勅 では、 教 会 内 での 「ティンパニ、ホルン、トランペット」 など<br />
の 使 用 を 禁 止 したが、 歌 の 補 助 に 使 用 される 弦 楽 器 と 一 部 管 楽 器 の 使 用 を 容 認 したことが、<br />
オーケストラを 事 実 上 黙 認 したと 拡 大 解 釈 され、 実 際 の 運 用 では、 前 記 楽 器 はおろか、 禁 止<br />
したはずのティンパニなどの 楽 器 まで 教 会 内 で 堂 々と 演 奏 されたことは、モーツァルト 時 代<br />
のザルツブルクの 状 況 を 見 れば 明 らかである。 結 果 として、この 回 勅 は、その 意 図 に 反 し 世<br />
俗 化 を 促 進 させる 事 態 を 招 いたと 評 価 されることもあるが、その 基 本 理 念 は、これから 検 討<br />
するヴィットの 主 張 と 一 致 するものであることがわかる。<br />
2 教 皇 自 発 教 令 Motu proprio Tra le sollecitudini<br />
Motu proprio は 教 皇 が 発 する 自 発 教 令 と 呼 ばれるもので、 歴 代 教 皇 が 幾 多 のものを 残 し<br />
ているが、1903 年 にピウス 十 世 が 発 布 した Motu proprio "Tra le sollecitudini" は、セシリア<br />
運 動 の 主 張 を 大 きく 取 り 入 れたものと 言 われている。この 教 令 は、グレゴリオ 聖 歌 を 至 高<br />
のものと 位 置 付 け、そして、パレストリーナを 賞 賛 する 一 方 で、「 世 俗 的 なものを 教 会 に 持<br />
ち 込 まないよう」「 特 にオペラ 様 式 はふさわしくない」と 指 示 したほか、ラテン 語 の 厳 守 や、<br />
勝 手 な 反 復 や 省 略 の 禁 止 等 を 指 示 した。<br />
3<br />
典 礼 憲 章<br />
30
セシリア 運 動 に 及 ぼした E. T. A. ホフマンの 影 響 について:A. F. J. ティボーとの 関 連 を 通 して<br />
戦 後 の 第 二 バチカン 公 会 議 を 経 て 1963 年 に、「 典 礼 憲 章 」 が 発 布 された。 現 在 のカトリッ<br />
ク 教 会 のミサ 等 の 典 礼 は、これに 則 って 行 われている。そこでは、グレゴリオ 聖 歌 を 典 礼<br />
の「 首 位 」に 位 置 付 けているが、 他 の 種 類 の 音 楽 も、「 典 礼 精 神 にのっとる 限 り」 排 除 されな<br />
い。オルガンを 尊 重 するが、 他 の 楽 器 も「 聖 なる 用 途 に 適 合 して」、「 聖 堂 の 品 位 にふさわし<br />
く」さえあれば、 司 祭 らの 承 認 を 得 て、 礼 拝 に 取 り 入 れることができるとしている。この 結<br />
果 、ゴスペルやギター 伴 奏 の 聖 歌 、ジャズ・ミサ 曲 の 演 奏 も 試 行 されるようになり、 近 年 で<br />
は、その 行 き 過 ぎの 是 正 が 求 められている。<br />
これら、 教 会 の 教 えに 共 通 するのは、「 原 則 禁 止 だが、 教 会 にふさわしい、 司 祭 が 認 める、<br />
などの 条 件 付 きで 弾 力 的 な 運 用 を 容 認 するという」いわば 建 前 と 本 音 の 使 い 分 けともいえる<br />
ような、 思 考 法 、 考 え 方 だが、それらは、これから 触 れるセシリア 運 動 にもそのまま 共 通 す<br />
る。 以 下 の 検 討 において、この 通 底 する 思 考 法 を 忘 れてはならない。<br />
5. セシリア 運 動 とホフマン、ティボー<br />
5–1 セシリア 運 動 とア・カペラ 様 式<br />
セシリア 運 動 は、19 世 紀 に 南 ドイツを 中 心 に 展 開 されたカトリック 教 会 の 典 礼 音 楽 改 革<br />
運 動 であるが、 評 者 によって 定 義 が 多 様 である。 一 般 的 な 理 解 の 例 として、 西 洋 音 楽 史 教 科<br />
書 として 名 高 いグラウト=パリスカの 著 書 における 記 述 を 参 照 してみよう。<br />
19 世 紀 の 中 葉 に、ローマ・カトリック 教 会 の 内 部 で、 音 楽 の 改 革 を 煽 る 動 きが 起 こっ<br />
た。 音 楽 の 守 護 聖 人 である 聖 チェチーリア(178 頃 没 )に 因 んで、チェチーリア 運 動 と<br />
呼 ばれるようになった。この 動 きは、ひとつには、 過 去 の 音 楽 に 対 するロマン 時 代 の 関<br />
心 に 刺 激 されたものである。それは、16 世 紀 のア・カッペッラ 様 式 を 復 活 させ、グレ<br />
ゴリウス 聖 歌 を 本 来 の 形 と 思 われる 姿 に 戻 す 役 割 を 果 たした。(グラウト 2001 : 87)( 下<br />
線 は 筆 者 )<br />
このように、この 運 動 には、ア・カペラを 推 進 したというイメージが 定 着 している。 現 実<br />
の 演 奏 の 場 で 演 奏 される 曲 も、 殆 どそうであったようだ。K. A. Daly という 研 究 者 によれば、<br />
1874 年 8 月 にマインツで 開 催 された 第 4 回 のセシリア 協 会 (ACV) 総 会 の 公 式 行 事 で 演 奏<br />
されたのは、 次 の 曲 であった。 彼 の 著 書 からの 引 用 で 示 す(Daly 1995: 38)。<br />
*Monday 18. August<br />
At 3 p. m. Reception<br />
4 p. m. Solemn Vespres in the Cathedral, Antiphons and Hymn, Plain Chant & etc<br />
5 p. m. Meeting of members and instructive rihersal,conducted by R.F. Koen<br />
8 p. m. Friendly assembly.<br />
31
成 城 美 学 美 術 史<br />
第 17 号<br />
*Tuseday19. August<br />
At 9 a. m. High mass in the Cathedral<br />
Kyrie, Cloria, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei : Missa “Qual donnna”<br />
—Orland di Lasso<br />
Introitus, Alleluiaet, Credo, Communio—Plain Chant<br />
Graduale––– (Recited)<br />
Offertoria “Assumpta est Maria” (V. voc.) —Palestrina<br />
3:30 p. m Service in the Cathedral<br />
execution of a variety of Church Music, with Sermon and Benediction<br />
of the Most Holy Sacrament<br />
1. Sancta et Immaculata, (V. voc.) — Croce<br />
2. Vinea mea, (IV. voc.) — Viadana<br />
3. Christus factus est, (IV. voc.) — Palestrina<br />
4. Nos autem (IV. voc.) — Plain Chant<br />
5. Ave Maria (IV. voc.) — P.Piel<br />
6. Ave Maria (IV. voc.) — M.Haller<br />
7. Dum complerentur (IV. voc.) — Palestrina<br />
8. Krie and Qui tollis, (from “Missa octavi toni” (IV. voc.) — Croce<br />
9. Cloria in festes semid — Plain Chant<br />
10. Miserere,3 first verses — Orland di Lasso<br />
11. Assenditi Deus (V. voc.) — Palestrina<br />
12. O Sacrum Convivium, (IV. voc.) — Vittoria<br />
13. Tantum ergo, (V. voc.) — Aichinger<br />
*Wednesday 20. August<br />
At 8:30 a. m. High mass in the Cathedral<br />
Kyrie, Gloria, Agnus Dei: Missa “Sine nomine”—Palestrina<br />
Credo: Missa “Iste Confessor”—(do)<br />
Introit, Alleduia et Versus, Sanctus, Benedictus, Commmunio<br />
—Plain Chant Gradual—(Recited)<br />
After the Procession: “O Salutaris Hostis” (V. voc.) — O. di Lasso<br />
このように、 公 式 行 事 とはいえ、 演 奏 されたのは、すべてパレストリーナをはじめとする<br />
15 ~ 6 世 紀 の 大 家 たちの 作 った 四 声 、または 五 声 の 無 伴 奏 声 楽 曲 や Plain Chant、 即 ちグレ<br />
ゴリオ 聖 歌 である。セシリア 運 動 がア・カペラを 推 進 したというのは、 紛 れもない 事 実 であ<br />
り、 彼 らにそういったイメージが 定 着 したのも 当 然 といえよう。<br />
32
セシリア 運 動 に 及 ぼした E. T. A. ホフマンの 影 響 について:A. F. J. ティボーとの 関 連 を 通 して<br />
5–2 セシリア 運 動 と 器 楽<br />
上 記 のような、セシリア 運 動 がア・カペラを 推 進 したというイメージに 反 駁 したのが、<br />
Raymond Dittrich である。 彼 は、2009 年 に 発 表 した 論 文 冒 頭 で、 次 のように 断 言 した。<br />
Es ist ein weitverbreitetes Mißverständnis, Franz Xaver Witt und die ihm folgende Richtung<br />
des Cäcilianismus lehnte die Instrumentalbegleitete Kirchenmusik grundsätzlich ab<br />
zugunsten ausschließlich unbegleitet gesungener Vokalmusik. (Dittrich 2009b: 204)<br />
フランツ・クサヴァー・ヴィットとそれに 従 うセシリア 運 動 の 方 針 が、 専 ら 無 伴 奏 で 歌<br />
われる 声 楽 のために、 器 楽 伴 奏 付 教 会 音 楽 を 拒 絶 したという、これまで 広 く 信 じられて<br />
きた 誤 解 がある。<br />
ここで、Dittrich は、セシリア 運 動 について 一 般 に 語 られてきた、 当 時 の 教 会 音 楽 の 主 流<br />
である 器 楽 伴 奏 付 き 教 会 音 楽 を 排 斥 し、ア・カペラ 音 楽 を 推 進 としたという 見 方 を、「 広 く<br />
信 じられてきた 誤 解 」と 断 じている。<br />
Dittrich の 論 文 を 検 討 する 前 に、ヴィットの 主 張 を 整 理 しておこう。<br />
セシリア 運 動 の 指 導 者 ヴィットの 「 器 楽 付 き 教 会 音 楽 」 への 対 応 は 複 雑 かつ 錯 綜 したもの<br />
との 印 象 を 強 く 受 ける。 現 実 主 義 者 であった 彼 の 言 動 は、 相 手 と 発 表 媒 体 に 合 わせて、ニュ<br />
アンスを 巧 みに 使 い 分 けており、いわば「 玉 虫 色 」の 色 彩 を 帯 びているといっていいかもし<br />
れない。<br />
彼 の 主 張 を、まず 彼 らの 拠 ってたった 組 織 、ACV の 会 則 から 見 てみよう。<br />
セシリア 協 会 の 会 則 (Statuten) 抜 粋<br />
1868 年 バンベルクでの ACV 第 1 回 総 会 席 上 で 決 定 した “Statuten des allgemeinen<br />
deutschen Cäcilien–Vereins für katholische Kirchenmusik” の 抜 粋 。<br />
Ⅱ 協 会 の 目 的 : 聖 なる 教 会 の 意 図 と 精 神 (Sinn und Geist)において、 教 会 の 決 定 と 指<br />
導 の 基 盤 に 則 りカトリック 教 会 音 楽 の 発 展 と 促 進 〔を 図 る〕。 協 会 は 後 者 の 実 践 を 援 助<br />
する。<br />
〔そのために〕 協 会 は 以 下 のような 配 慮 を 行 う。<br />
a) グレゴリオ 聖 歌 〔の 復 興 〕<br />
b) 古 い 時 代 と 新 しい 時 代 のポリフォニー 声 楽 の 演 奏<br />
c) 自 国 語 による 教 会 聖 歌 〔の 制 作 〕(Kirchenlied in der Volkssprache)<br />
d) 教 会 的 なオルガン 音 楽 の 演 奏 。<br />
e) 器 楽 音 楽 は、 教 会 の 精 神 に 抵 触 しない 範 囲 で、 教 会 内 に 存 在 しうる。<br />
(Instrumentalmusik, wo sie besteht, soweit sie nicht gegen den kirchlichen Geist verstößt.)<br />
〈 後 略 〉 (Lickleder 1988: 72)( 下 線 は 筆 者 )<br />
ここで、 器 楽 音 楽 について、「 教 会 の 精 神 に 抵 触 しない 範 囲 で、 教 会 内 に 存 在 しうる」と、<br />
33
成 城 美 学 美 術 史<br />
第 17 号<br />
容 認 している 事 実 に 注 目 したい。 創 立 当 時 既 に、セシリア 運 動 は 器 楽 排 斥 、とのイメージが<br />
あったらしく、それを 払 拭 すべくわざわざ 明 記 したように 見 える 28 。<br />
続 いて、2つの 資 料 を 見 てみよう。<br />
1ヴィット 自 身 の 作 品 目 録 から<br />
Op. 9. M. “Exulet”für 2 Singst. (S. u. A. od. T. u. B)u. Orgel. Rg. A. C. Später hat der<br />
Componist T. u. B. Streichquartett 2 Hörn. und Baßposaune ad libit. Rg. F. P. erscheinen<br />
lassen. (C. K. 8)u. F. B. 76. (Kirchenmusikalisches Jahrbuch 1890: 110)<br />
2 声 (ソプラノとアルト、 又 は、テノールとバス)とオルガンのためのミサ 曲 Exulet。<br />
レーゲンスブルク、アルフレッド・コッペンラート 出 版 社 。 作 曲 者 は 後 に、テノールと<br />
バス、 弦 楽 四 部 と 2 つのホルンと、 任 意 (ad libit.)でバス・トロンボーンを 追 加 しても<br />
よいとした 版 をレーゲンスブルクのフリードリッヒ・プーステット 出 版 社 から 刊 行 した。<br />
『セシリア 協 会 作 品 目 録 8 号 』と、Fliegende Blätter 1876 年 号 に 収 録 。<br />
2 Karl Greith (1828–1887) の 作 品 目 録 から<br />
Missa in honorem Sancti Josephi, ad quatuor voces impares, comitatibus 2 Violinis, Viola,<br />
Bassis, Organo, Flauto, 2 Oboe, 2 Cornibus, 2 Clarinis, (et 3 Trombonis cum Tympanis) ad<br />
libitum, Opus XVI (Lickleder 2006: 205)<br />
引 用 の 前 者 は、ヴィット 自 身 「 器 楽 伴 奏 付 き 教 会 音 楽 」 を 作 っていた 事 実 を 示 している。<br />
後 者 の Karl Greith は、ヴィットの 盟 友 でセシリア 協 会 の 有 力 メンバーであった。ヴィット<br />
及 び 幹 部 たちの 作 品 に、 任 意 といいながらも、ティンパニやトロンボーンなどの 楽 器 指 定 が<br />
あることに 驚 く。<br />
ここで、Dittrich の 論 文 の 続 きを 検 討 しよう。<br />
Dittrich によれば、ヴィットは 運 動 の 最 初 期 から、 彼 の 改 革 において「すべての 楽 器 を 完<br />
全 に 追 放 するわけではない」との 態 度 を 表 明 していた。ヴィットは、 教 会 内 で 演 奏 される 音<br />
楽 を 聖 歌 やパレストリーナ 様 式 のものだけではない、ことを 認 めていた。ヴィットが 喫 緊 の<br />
課 題 としたのは、 教 会 音 楽 にはびこっている 通 俗 さや 下 品 さの 撲 滅 であったと 言 う。<br />
さらに Dittrich は、ヴィット 自 身 器 楽 作 品 を 作 曲 していたことや、 他 者 の 器 楽 付 きミサ 曲<br />
を 演 奏 したことを 紹 介 した 上 で、ヴィットの 言 う 典 礼 にかなった 器 楽 の 使 い 方 を、 次 のよう<br />
に 示 した。<br />
・ 楽 器 のオブリガートは、 聖 歌 の 伴 奏 にのみ 許 されること。<br />
・ 伴 奏 が 劇 場 的 な 性 格 を 持 つことは 許 されない、そして、 打 楽 器 をオブリガートとして<br />
使 うことや、トランペットやホルンをファンファーレ 風 に 使 うことも 許 されない。<br />
・ 大 がかりな、とりわけヴィルトゥーゾ( 名 人 芸 ) 的 な 器 楽 独 奏 やフィギュレーション<br />
は、 絶 対 に 避 けるべきである。<br />
34
セシリア 運 動 に 及 ぼした E. T. A. ホフマンの 影 響 について:A. F. J. ティボーとの 関 連 を 通 して<br />
Dittrich は 明 記 していないが、ヴィットのこの 主 張 は、オペラ 風 に 堕 落 した 教 会 音 楽 の<br />
改 革 を 目 指 した 1749 年 の 教 皇 回 勅 Annus qui に、うり 二 つであることがわかる。つまり、<br />
Dittrich のこの 指 摘 は、ヴィットの 主 張 がカトリック 教 会 の 伝 統 に 沿 ったものであったこと<br />
を 示 している。<br />
ここでこれまで 触 れてこなかった 点 も 含 め、ヴィットの 主 張 を 再 度 整 理 してみよう。<br />
まず、グレゴリオ 聖 歌 の 復 興 を 第 一 の 目 標 に 掲 げている。 但 し、 以 前 から 行 われてきたオ<br />
ルガン 伴 奏 付 けは 否 定 せず、むしろ 聖 歌 普 及 のため 自 らも 推 進 した。 単 純 なア・カペラ 主<br />
義 者 でなかったことは、このことからも 明 らかである。 彼 のパレストリーナ 崇 敬 は、 教 会<br />
のほかに、 師 のプロスケを 通 じてのものであった。そのプロスケは、ティボーの 著 書 Ueber<br />
Reinheit der Tonkunst を 通 じてパレストリーナの 音 楽 の 価 値 を 知 ったと 言 われるので、ヴィ<br />
ットもまたティボーの 書 から、パレストリーナを 教 えられたことになる 29 。<br />
ヴィットは、セシリア 主 義 者 たちの 創 作 活 動 について、パレストリーナを 模 範 とするよう<br />
奨 めながらも、 単 なる 模 倣 に 陥 らないよう 何 度 も 警 告 している。ヴィット 自 身 は 作 曲 家 とし<br />
ての 自 負 から、「ヴィット 様 式 」を 主 張 した。セシリア 主 義 者 たちの 作 品 は「セシリア 協 会 カ<br />
タログ」として 機 関 誌 に 掲 載 されたのみで、 殆 ど 出 版 されることなく、 音 楽 史 の 上 では、パ<br />
レストリーナの 「 模 倣 」 として 殆 ど 無 視 された。ヴィット 様 式 を 自 認 したヴィットの 作 品 も<br />
その 例 外 ではなく、 現 在 では 殆 ど 演 奏 されることがない。<br />
後 述 するように、ヴィットは 自 らの 発 案 ではないものの、ティボーの 著 書 のセシリア 協 会<br />
版 を 刊 行 するほど、ティボーの 著 書 に 愛 着 を 持 っていた。 器 楽 教 会 音 楽 への 対 応 について、<br />
当 時 から「セシリア 運 動 は 反 ・ 器 楽 」とのイメージが 持 たれていたようで、そのことは 運 動<br />
の 推 進 にマイナスになると 考 えたのであろう。そのイメージを 払 拭 すべく、 何 度 となく、そ<br />
れに 反 論 を 試 みている。<br />
つまり、 教 会 にふさわしく、 典 礼 の 規 則 に 沿 うという 条 件 に 合 う 「 器 楽 付 き 教 会 音 楽 」 で<br />
あれば 容 認 する、ことを 表 明 し、 自 らも 作 曲 し、 演 奏 ( 指 揮 )も 行 っている。しかし、この<br />
規 準 が 曖 昧 なものであったことは 否 定 しようがない。<br />
もちろん、 彼 らの 行 動 はこれら 曲 の 制 作 だけに 留 まらず、 聖 職 者 や 一 般 信 徒 の 音 楽 レベル<br />
向 上 、キリスト 教 の 司 牧 としての 広 宣 活 動 、グレゴリオ 聖 歌 集 の 整 備 やパレストリーナ 全 集<br />
出 版 など 多 方 面 にわたっていたことも 忘 れてはならない。<br />
5–3 セシリア 協 会 編 によるティボーの 著 書 Ueber Reinheit der Tonkunst の 新 版<br />
セシリア 協 会 編 の 注 釈 付 き(コンメンタール)と 名 打 ったティボーの 著 書 Ueber Reinheit<br />
der Tonkunst の 新 版 が、1876 年 にレーゲンスブルクの 出 版 社 から 刊 行 されたという 事 実 は、<br />
これまでも 知 られていたが、 詳 細 は 明 らかでなかった。2009 年 に 発 表 された Dittrich の 論<br />
文 によって、その 経 緯 が 詳 かになった。 以 下 にその 内 容 を、 簡 潔 に 記 す。(Dittrich 2009a:<br />
113f)<br />
発 端 は 1874 年 2 月 、ライプツィヒの 出 版 社 F. E. C. Leuckart の 支 配 人 コンスタンティン・<br />
35
成 城 美 学 美 術 史<br />
第 17 号<br />
ザンダー が、ヴィットに、ヴィットの 執 筆 した 注 釈 の 入 ったティボーの 著 書 の 新 版 (コンメ<br />
ンタール 版 ) 発 行 という 計 画 を 提 案 したことに 始 まる。ザンダーは、500 部 をセシリア 協 会<br />
関 係 者 が 購 入 すれば 採 算 が 取 れる、と 持 ちかけた。<br />
提 案 を 聞 いたヴィットは、この 企 画 を、ティボーの 著 書 の 本 来 の 版 元 であるムーア 社 に 持<br />
ち 込 んだらしい。この 年 の 5 月 に、ムーア 社 はヴィットに、 注 釈 入 りではなく、セシリア 協<br />
会 会 員 向 けに、ヴィット 自 身 による 前 書 きと 後 書 きを 付 した 特 別 版 を 発 行 するという 代 替 案<br />
を 提 示 した。ヴィットはこの 提 案 を 断 り、この 企 画 を 今 度 は、セシリア 協 会 と 親 密 な 関 係 に<br />
あるレーゲンスブルクの 出 版 社 プーステット Pustet に 持 ち 込 んだ。<br />
計 画 が 進 む 中 、ヴィットは、 多 忙 と 健 康 不 安 から 自 身 による 執 筆 を 断 念 し、 執 筆 を、 著<br />
名 な セ シ リ ア 協 会 会 員 August Wilhelm Ambros (1816–1876) や Utto Kornmüller (1824–<br />
1907) に 依 頼 したが、 彼 らの 承 諾 を 得 られず、 最 終 的 に 協 会 会 員 でギムナジウムの 教 師<br />
G. W. Birkler (1820–77) の 手 に 委 ねた 30 。<br />
新 版 は、1876 年 末 に 完 成 し、プーステットから 下 記 タイトルを 付 けて 発 行 された。 校 正<br />
に 手 間 取 り、 実 際 に 印 刷 が 完 了 して 配 本 されたのは、1877 年 初 めであった。<br />
Ueber Reinheit der Tonkunst von Ant. Friedr. Just. Thibaut.<br />
Mit einem Commentar herausgegeben von Professor Birkler,<br />
Haupt=Vereinesgabe (pro 1876)<br />
des allgemeinen deutschen Cäcilien–Vereines,<br />
Regensburug, New York & Cincinnati.<br />
Druck von Friedrich Pustet. 1876 ( 下 線 は 筆 者 )<br />
Dittrich によれば、ヴィットは、 完 成 した 本 の 内 容 に 不 満 だったようで、この 著 作 は 版 を<br />
重 ねることはなかった。<br />
筆 者 は、 最 近 、 海 外 の 古 書 店 から、この 書 物 を 入 手 した。 残 念 ながら 完 本 でなく、 後 半 の<br />
数 十 頁 が 散 逸 しているが、 表 紙 、 前 書 き、 本 文 の 大 半 を 備 えており、 概 要 の 把 握 は 可 能 であ<br />
る( 巻 末 図 版 参 照 )。<br />
Birkler の 書 いたコメントの、いくつかについて 見 てみよう。 上 述 のように、 本 文 とほぼ<br />
同 量 (Dittrich によれば、およそ 80%)を 占 めている。<br />
最 初 のコメントで、 彼 は、ティボーが「 過 去 の 古 典 的 な 模 範 」の 音 楽 について、 彫 刻 や 文<br />
学 に 比 べて 研 究 が 著 しく 遅 れていると 嘆 いていることを 紹 介 する。そして、この 50 年 (テ<br />
ィボーの 初 版 が 出 てから、このコメンタール 版 が 出 るまでの 間 )に、 事 情 は 変 り、ティボー<br />
の 切 望 したことのいくつかが、プロスケらの 努 力 により、かなりの 程 度 実 現 されてきた。つ<br />
まり、 彼 らセシリア 運 動 によるものだ、と 運 動 の 成 果 を 披 瀝 している。<br />
続 いては、トリエント 公 会 議 で 示 された( 教 会 音 楽 の) 基 準 と、 最 近 の 音 楽 事 情 に 関 して<br />
の 神 学 上 の 解 釈 論 議 に 触 れている。さらに、アメリカでのセシリア 協 会 設 置 など 海 外 にも 進<br />
出 しているセシリア 運 動 の 状 況 も 紹 介 している。<br />
その 次 のコメントでは、セシリア 協 会 幹 部 でヴィットの 弟 子 であるハーベルルの 編 纂 した<br />
36
セシリア 運 動 に 及 ぼした E. T. A. ホフマンの 影 響 について:A. F. J. ティボーとの 関 連 を 通 して<br />
プーステット 版 グレゴリオ 聖 歌 集 を 称 賛 し、 推 奨 している。<br />
このように、Birkler のコメントは、ティボーの 字 句 解 釈 を 超 えて、 現 在 の 情 勢 をティボ<br />
ー 執 筆 時 の 状 況 との 違 いをふまえて 分 析 している 傾 向 が 強 いように 見 える。<br />
これらのコメントは、ヴィットら 幹 部 以 外 のセシリア 協 会 会 員 の 認 識 の 一 端 に 触 れること<br />
のできる 一 次 資 料 として、 貴 重 な 存 在 と 評 価 できる。いずれにせよ、この 企 画 は、きっかけ<br />
こそ 他 から 持 ちかけられたものとはいえ、ティボーの 書 を、いわば 「 教 科 書 」 にしようとす<br />
る 試 みであり、 彼 らセシリア 主 義 者 たちが、いかにティボーの 主 張 に 心 酔 していたかを 示 し<br />
ている。<br />
6. まとめと 今 後 の 課 題<br />
これまで 検 討 してきたようなヴィットらの 言 動 をホフマン、ティボーと 比 較 した 時 、どう<br />
位 置 付 けるべきか。 次 の 表 で 再 確 認 してみよう。<br />
信 仰 ア・カペラへの 対 応 器 楽 教 会 音 楽 への 対 応 改 革 の 方 針<br />
ホフマン<br />
ティボー<br />
ヴィット<br />
プロテスタント<br />
プロテスタント<br />
パレストリーナ 復 興<br />
運 動 の 推 進<br />
ア・カペラ 称 賛<br />
自 作 も 試 みるが 後 に<br />
転 向 した<br />
ア・カペラ 称 賛<br />
楽 譜 の 収 集<br />
カトリック 聖 職 者 グレゴリオ 聖 歌 ・パ<br />
レストリーナを 称 賛<br />
し、 演 奏 を 推 進 する<br />
楽 譜 の 収 集 ・ 出 版<br />
器 楽 音 楽 重 視 の 原 則 を<br />
固 守<br />
合 唱 運 動 に 呼 応 し、 昔<br />
の 巨 匠 の 作 品 を 復 活 演<br />
奏 ( 自 らの 演 奏 は、ピ<br />
アノ 伴 奏 付 きに 留 ま<br />
る)<br />
「 教 会 にふさわしい」<br />
器 楽 音 楽 を 模 索<br />
パレストリーナ 復 興<br />
運 動 の 推 進 合 唱 運 動<br />
を 国 家 主 導 で 推 進 す<br />
る<br />
器 楽 を 活 用 した 新 し<br />
い 教 会 音 楽 制 作 を 提<br />
唱<br />
古 い 教 会 音 楽 やヘン<br />
デルのオラトリオの<br />
演 奏 を 推 進 。《メサ<br />
イア》を 激 賞<br />
グレゴリオ 聖 歌 の 復<br />
興 、ヴィット 様 式 に<br />
よる 新 しい 教 会 音 楽<br />
の 創 作 を 主 張<br />
ホフマン、ティボーはプロテスタントで、ヴィットはカトリック 教 会 の 司 祭 であった。ア・<br />
カペラを、ホフマンはヴァッケンローダーらロマン 主 義 者 を 通 じて、ティボーはルターの 教<br />
えをもとに 受 容 した。ヴィットは、プロスケを 経 由 して、ティボーを 知 った。 彼 らの 器 楽 教<br />
会 音 楽 への 対 応 、 改 革 の 方 法 の 違 いについては、 表 に 掲 げた 通 りである。<br />
これまで 述 べてきたように、ヴィットはティボーへの 称 賛 を 隠 していないが、その 言 動 の<br />
中 に、ホフマンの 名 は 登 場 していない。 前 述 したように、19 世 紀 後 半 、ホフマンの 名 が 通<br />
俗 作 家 として 著 名 だったこともその 理 由 の1つかもしれない 31 。<br />
しかし、これまでの 考 察 を 振 り 返 ると、ことア・カペラや 器 楽 音 楽 への 対 応 については、<br />
ホフマン、ティボーとの 類 似 点 が 多 いことに 気 付 く。 一 番 問 題 となるのは、ホフマンがあげ<br />
37
成 城 美 学 美 術 史<br />
第 17 号<br />
た「 器 楽 を 活 用 した 新 しい 教 会 音 楽 の 創 作 」だが、これもヴィットは、 積 極 的 ではないかも<br />
しれないにせよ、 数 曲 の 実 作 を 遺 しているし、「 器 楽 伴 奏 付 き 教 会 音 楽 」 の 演 奏 も 行 なって<br />
いる。このように、ヴィットが 意 識 していたか 否 かは 別 にして、セシリア 主 義 者 たちは、カ<br />
トリック 教 会 の 伝 統 をふまえた 上 で、ホフマンの 志 向 した 道 をたどったように 思 える。<br />
今 回 、ホフマンとヴィットの 間 の 直 接 の 影 響 を 明 示 するに 至 らなかったが、ティボーとヴ<br />
ィットに 共 通 するア・カペラ 推 進 者 というイメージが 偏 ったものであることを 示 すことがで<br />
きたのは、1つの 収 穫 と 考 える。<br />
ホフマンの 考 察 で 得 た、ア・カペラ 推 進 と 器 楽 推 進 が、「 対 立 軸 」でなく「 相 互 補 完 」であ<br />
ったという 視 点 が、ティボーやセシリア 運 動 に 妥 当 するかを、さらに 多 くの 作 品 や、 彼 らの<br />
言 動 の 考 察 により 検 証 したい。あわせて、 彼 らを 取 り 巻 いたロマン 主 義 を 含 めた 当 時 の 思 潮<br />
についての 考 察 を 続 けていきたい。<br />
( 本 稿 は、2009 年 春 に 成 城 大 学 大 学 院 文 学 研 究 科 に 提 出 した 修 士 論 文 の 一 部 と、 同 年 秋 の 美 学 会 全 国 大 会 若<br />
手 研 究 者 セミナーでの 発 表 をもとに、 大 幅 加 筆 修 正 したものである。)<br />
註<br />
1 1803 年 レーゲンスブルクにおける 神 聖 ローマ 帝 国 代 表 者 会 議 主 要 決 議 (Reichsdeputationshauptschluss)に<br />
より、 小 規 模 領 邦 国 家 と 帝 国 都 市 の 廃 止 、 大 諸 侯 領 へ 編 入 ( 陪 臣 化 )と 共 に、マインツ 大 司 教 以 外 のす<br />
べての 聖 界 諸 侯 領 の 俗 界 諸 侯 領 への 併 合 が 決 まった。 後 者 を、 世 俗 化 ( 独 die Säkularisierung、 英 the<br />
secularization)という。この 結 果 、ドイツの 多 くのカトリック 教 会 や 修 道 院 が 閉 鎖 され、 教 会 の 弱 体 化<br />
が 促 進 した。(『 新 カトリック 大 事 典 』 第 3 巻 、2009 ほか)<br />
2 Cäcilianismus については、いまだに 定 訳 がなく、チェチーリア 運 動 、ツェツィーリア 運 動 など、 様 々な<br />
呼 称 が 使 われているが、 本 稿 では 引 用 以 外 、セシリア 運 動 で 統 一 する。<br />
セシリア 運 動 は、19 世 紀 に 南 ドイツで 起 こった 教 会 音 楽 の 改 革 運 動 である。その 名 称 は 殉 教 者 で 音<br />
楽 の 守 護 聖 人 とされる 聖 セシリアに 由 来 する。 当 時 の 教 会 音 楽 が 世 俗 的 なオペラ 風 の 音 楽 に 堕 落 してい<br />
ると 批 判 し、グレゴリオ 聖 歌 や 16 世 紀 のパレストリーナ 様 式 の 音 楽 に 理 想 を 求 め、その 復 興 やそれに<br />
倣 った 音 楽 の 作 曲 に 尽 力 すると 共 に、ウィーン 古 典 派 の 教 会 音 楽 、ヨーゼフ・ハイドンやモーツァルト<br />
の 教 会 音 楽 を 排 斥 したとされる。 一 般 に、1868 年 フランツ・ヴィット( 後 述 )により 設 立 された「 総 ド<br />
イツ・セシリア 協 会 ACV 」によって 運 動 の 最 盛 期 を 迎 えたと 言 われている。その 運 動 の 開 始 時 期 や 区<br />
分 をめぐっては、 諸 説 がある。 筆 者 は 修 士 論 文 において、セシリア 運 動 の 開 始 を 1820 年 頃 とした 上 で、<br />
初 期 、 中 期 ( 盛 期 )、 後 期 の 3 期 に 区 分 することを 提 唱 した( 福 地 2009 参 照 )。 本 稿 では、ヴィットを<br />
中 心 とする 盛 期 セシリア 運 動 を 対 象 に 論 じる。<br />
3 Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (1776–1822)<br />
4 Anton Friedrich Justus Thibaut (1772– 1840)<br />
5 ホフマンの 音 楽 評 論 “Alte und neue Kirchenmusik ( 新 旧 の 教 会 音 楽 )”の 主 旨 は、 前 年 一 般 音 楽 新<br />
聞 (Allgemeine Musikalische Zeitung, AMZ) に 寄 稿 し た “Beethoven C–Dur Messe( ベ ー ト ー ヴ ェ<br />
ン「ミサ 曲 ハ 長 調 」 論 )”に 見 られる。 大 幅 な 加 筆 を 経 て、 翌 年 に 現 在 のタイトルの 論 文 として 同 紙<br />
上 に 三 回 にわたって 掲 載 された。1819 年 に 会 話 体 に 変 更 した 上 、 分 量 を 大 幅 に 圧 縮 したものが “Die<br />
Serapionsbrüder”(ゼラーピオン 同 人 集 )に 同 じ 題 名 で 組 み 込 まれた。 従 って、このタイトルの 作 品 は2<br />
つ 存 在 している。 本 論 では、1814 年 の 論 文 をもとに 論 じる。<br />
6 ティボーの 著 書 Ueber Reinheit der Tonkunst は、 最 初 1824 年 に 無 署 名 ( 匿 名 )で 少 部 が 出 版 された 後 、 翌<br />
1825 年 に 本 名 による 初 版 が 刊 行 された。その 後 ネーゲリらの 批 判 に 応 え 大 幅 に 書 き 換 えた 改 訂 第 二 版<br />
が 1826 年 に 出 版 された。ティボーの 死 後 の 1851 年 、カール・ベーアによる 校 訂 とその 序 文 付 きの 第<br />
38
セシリア 運 動 に 及 ぼした E. T. A. ホフマンの 影 響 について:A. F. J. ティボーとの 関 連 を 通 して<br />
三 版 が 刊 行 され、 以 降 の 底 本 となる。その 後 も 好 評 に 迎 えられ 1890 年 代 には 第 七 版 が 発 行 された。な<br />
お、ティボーの 原 書 では、 著 書 名 、 各 章 名 とも、 先 頭 の Über はウムラウトなしの「e 付 記 」(Über でな<br />
く、Ueber)で 表 記 されている。 本 論 では、 他 書 からの 引 用 以 外 、そのように 表 記 する。<br />
7 吉 田 によれば、このときの「 決 定 的 な 要 因 」の 一 つは、ホフマンが、 初 期 ロマン 派 の 唱 えたパレストリ<br />
ーナ 復 興 運 動 から、「 器 楽 を 活 用 した 新 しい 教 会 音 楽 の 制 作 」への 転 換 を 計 ったものとされる。( 吉 田 、<br />
2001:170)<br />
8 Johann Friedrich Rochlitz (1769–1842) ドイツの 編 集 者 、 音 楽 評 論 家 。1798 年 ライプツィヒで、 一 般 音<br />
楽 新 聞 (AMZ) を 創 刊 、 主 筆 として 活 躍 した。<br />
9 この 節 の 翻 訳 にあたって、 吉 田 寛 の 訳 があるものについては、それを 参 考 にした。 訳 語 のいくつかは、<br />
踏 襲 させて 頂 いた。<br />
10 ホフマンは、1810 年 にバンベルク 劇 場 の 指 揮 者 として 招 かれ、 作 曲 家 、 舞 台 装 置 家 、 画 家 として 活 躍 し<br />
た。1813 年 には、ドレスデンのオペラ・カンパニーの 音 楽 監 督 となった。なお、ケーニヒスベルクとい<br />
うプロテスタント 地 域 に 生 まれたホフマンは、 当 然 のようにプロテスタントとして 人 生 を 歩 んだ。( 彼<br />
の 母 方 は 牧 師 や 法 律 家 の 家 系 であった。)ロマン 主 義 の 洗 礼 を 浴 びてからは、 多 くの 初 期 ロマン 主 義 者<br />
同 様 、カトリックの 理 念 への 親 近 感 を 隠 さなかった。(イエーナ・ロマン 派 の 中 には、フリードリヒ・<br />
シュレーゲルのようにカトリック 改 宗 に 踏 み 切 る 者 まであった。)しかし、 彼 の 愛 好 は 理 念 的 なもので、<br />
( 伝 記 の 伝 える) 実 生 活 においては、 教 会 に 通 うようなことはなかったようだ。( 樋 口 、2006:24 ほか)<br />
11 樋 口 梨 々 子 によれば、ホフマンのこの 論 文 の 主 旨 は、 古 い 教 会 音 楽 での「キリスト 教 的 」と、 新 しい 教<br />
会 音 楽 での「ロマン 主 義 的 」を、 二 項 対 立 構 造 と 考 えるものとされる。そして、それにもかかわらず、<br />
ホフマンは、 最 終 的 に「どちらに 対 しても 肯 定 的 な 姿 勢 を 取 る」 という「 不 思 議 な 選 択 をしている」 と 指<br />
摘 する。キーワードとなるのが、「 器 楽 」 である。 理 想 の 教 会 音 楽 は 「 簡 素 」であるべきと 考 えるホフマ<br />
ンにとって、 器 楽 を 用 いた 当 代 の「 新 しい 教 会 音 楽 」は、「 華 麗 さ」を 追 い 求 める 俗 世 的 なものに「 堕 落 」<br />
したものとなる。しかし、 器 楽 は、 本 来 、ホフマンにとって 最 高 度 の 芸 術 として 扱 われていたはずであ<br />
る。ここにホフマンの 自 己 撞 着 が 始 まる。<br />
樋 口 は、 自 己 撞 着 に 陥 ったホフマンの 出 した 結 論 は、 次 のようなものであったと 説 明 する。<br />
「ホフマンは、 人 間 の 声 すらも 楽 器 の 一 種 と 考 えていた。」 「つまりホフマンは、パレストリーナの 楽 曲<br />
を 純 枠 な 声 楽 曲 としてよりも、 人 間 の 声 という 楽 器 が 用 いられ、 極 めて 簡 素 に 創 作 された 器 楽 曲 という<br />
感 覚 で 聴 いたのではないか。」 「ホフマンにとって、 教 会 音 楽 の 言 語 ( 歌 詞 )は、『せいぜい 敬 度 な 気 分 を<br />
引 き 出 す 糸 口 に 過 ぎない』ものであった。」( 樋 口 、2006:30-31)この 樋 口 の 見 解 は、 別 の 機 会 に、あ<br />
らためて 検 証 していきたい。<br />
12 例 えば、ロータースは 次 のように 述 べている。<br />
「ドイツ 人 は、ホフマンの 扱 いについて― 比 較 的 少 数 の 愛 好 家 グループを 除 いて―、つねに 及 び 腰 で<br />
あった。 十 九 世 紀 全 体 を 通 じて『お 化 け 作 家 』と 呼 ばれ、 子 供 を 驚 かすだけのものでしかない 通 俗 文 学<br />
とされていたのである。[ 中 略 ]この 評 価 は 今 日 に 至 るまで 基 本 的 にあまり 変 わっていないとさえ 言 える。<br />
ドイツの 古 典 主 義 文 学 やロマン 主 義 文 学 に 通 暁 している 読 書 人 の 間 ですら、 独 特 なホフマン 抑 制 の 態 度<br />
が 見 受 けられる。(ロータース= 金 森 2000: 294)」<br />
13 シューマンのピアノ 曲 集 『クライスレリアーナ』が、ホフマンの 同 名 のエッセイや、 小 説 『 牡 猫 ムルの 人<br />
生 観 』の 登 場 人 物 である 楽 長 クライスラーに 触 発 されて 作 られたことは、よく 知 られている。<br />
14 ウィーン 移 住 後 の 1783 年 4 月 、ザルツブルクの 父 レ-オポルトに 宛 てた 手 紙 の 中 で、モーツァルトは<br />
「 真 の 教 会 音 楽 」に 言 及 している。それは、「 屋 根 裏 部 屋 にしまいこまれていて」 思 いがけない 時 に 発 見<br />
されると 記 述 されているのみで、 詳 細 は 明 らかではない。(Bauer & Deutsch = 海 老 沢 、 高 橋 編 訳 『 書 簡<br />
全 集 5』1995:359)<br />
15 David Charlton (1946– )<br />
16 Johann Georg Sulzer (1720–1779)<br />
17 Ludwig Tieck (1773–1853)<br />
18 この 部 分 はチャールトンの 英 文 解 説 と、 吉 田 寛 の 論 攷 、 原 文 を 参 照 して 要 約 した。(Tieck 1828: 425)<br />
(Charlton 1989: 352-3)( 吉 田 2001: 169)<br />
19 ティボーの 伝 記 や 演 奏 会 の 情 報 は、 海 老 澤 1972 や 宮 本 2006 に 拠 る。<br />
39
成 城 美 学 美 術 史<br />
第 17 号<br />
20 シューマンは、ティボーのこの 著 書 を 次 のように 推 奨 している。<br />
Ein schönes Buch über Musik ist das „Über Reinheit der Tonkunst“ von Thibaut. Lies es oft, wenn du älter<br />
wirst. (Schumann. c1964: 16)<br />
(ティボーによる『 音 楽 芸 術 の 純 粋 性 について』という 音 楽 についての 素 晴 らしい 本 がある。 君 が 大 人 に<br />
なったら、それを 何 度 も 読 んでみることだ。)<br />
21 プロテスタントであるティボーの 著 書 が、カトリックの 教 会 音 楽 改 革 運 動 に 大 きな 影 響 を 与 えたことは、<br />
なんとも 皮 肉 なことである。<br />
22 ティボーの 同 書 は、 初 版 発 行 後 まもなくなされたネーゲリの 批 判 に 対 応 するため、 大 幅 な 改 訂 を 施 した<br />
第 2 版 が 翌 年 発 行 され、 以 降 これが 定 本 となる。 初 版 は 稀 覯 本 で 入 手 が 困 難 である。この 文 章 は、そ<br />
の 初 版 の 中 から、オットー・ヤーンやアルフレート・アインシュタインの 著 書 で 引 用 され 有 名 になった。<br />
この 部 分 は、 原 語 、 訳 ともども、アインシュタインの 著 書 、 訳 書 から 引 用 した。(ドイツ 語 で 書 かれた<br />
アインシュタインの 著 書 は、 諸 事 情 から 最 初 に 英 訳 版 が 出 版 され、 数 年 後 にドイツ 語 版 が 刊 行 された)<br />
23 ここでの 訳 は、 海 老 澤 1972 を 参 照 した。<br />
24 ティボーは、 著 書 の 第 5 章 において、モーツァルトによる《メサイア》 編 曲 の 楽 器 使 用 法 や 和 声 などに<br />
ついて、 長 文 を 費 やして 批 判 している。<br />
25 残 念 ながら、ティボーの 合 唱 団 の 演 奏 会 は 非 公 開 であったことから、 演 奏 実 践 の 状 況 は 知 られていない。<br />
彼 の 著 書 や 書 簡 から 推 定 するしかない。ベルリンのジングアカデミーは、 大 規 模 作 品 演 奏 の 際 に、 他 の<br />
オーケストラとの 共 演 を 行 ったが、ティボーの 演 奏 会 では、そのようなことは 明 らかでない。《メサイ<br />
ア》などの 演 奏 も、おそらくピアノ 伴 奏 であったと 推 定 される。<br />
26 海 老 澤 は、ティボーの 器 楽 観 について 次 のように 述 べている。<br />
「[ティボーは] 十 二 分 に 器 楽 の 価 値 を 認 めたうえで、とくに 教 会 音 楽 の 分 野 での 声 楽 の 優 位 を 説 くの<br />
である( 海 老 澤 1972:150)。」<br />
なお、 英 語 版 の 訳 者 (W. H. Gladstone) 序 文 によると、ティボーのヘンデルのオラトリオへの 偏 愛<br />
ともいえる 熱 中 は、 当 時 の 読 者 の 間 に、 注 目 と 同 時 に 当 惑 も 呼 んだようである。(Thibaut=Gladstone.<br />
1875: xi)<br />
27 本 項 の 記 述 は、 南 山 大 学 1986、 野 村 1963、 野 村 1967、 相 良 1993 等 を 参 照 した。<br />
28 この 項 については、セシリア 協 会 の 会 則 (Statuten)の 補 足 の 欄 に 下 記 記 述 がある。セシリア 協 会 は、 教<br />
会 精 神 に 適 う 器 楽 の 導 入 を、「 協 会 の 指 示 、 監 督 下 」 という 条 件 付 きで 認 めるものの、 教 会 音 楽 の 本 質<br />
はテクストの 演 奏 、つまり 歌 にあり、 器 楽 は、あくまで 副 次 的 (Sachermach)なものに 留 まると 考 えて<br />
いることがわかる。<br />
ad Ⅱ. e) Zur Neueinführung instrumentirter Kirchenmusik will der Verein seine Hand nicht bieten;<br />
wo sie schon besteht und wo man sie auch ferner beibehalten will, soll er ihre Übung nach dem kirchl.<br />
Geiste, der sie nicht verbietet, aber ihr eine untergeordnete Stelle anweist, regeln. 〔……〕Da das Wesen der<br />
Kirchenmusik im Vortrage des Textes, also im Gesange ruht, die Instrumente (mit Ausnahme der Orgel)<br />
von der Kirche als pure Nebensache betrachtet werden, so ist nicht abzusehen, warum der Verein die<br />
Instrumentalmusik irgendwo neu einführen soll. (Fliegende Blatter fur Katholische Kirchenmusik 3 (1868)<br />
S. 81ff)<br />
29 ヴィットによれば、ティボーの 著 書 は、プロスケをパレストリーナに 導 く、「Wecker( 覚 醒 者 )」の 役 割<br />
を 果 たしたとされる。また、 自 らの 修 業 時 代 を、「シュレームス* を 聴 き、プロスケに 学 んで 過 ごした」<br />
と 述 懐 している。つまり、ヴィットのティボー 受 容 は、プロスケを 通 してのものであったことがわかる。<br />
(Lickleder 1988: 110)〔 * Joseph Schrems (1815–1872) レーゲンスブルグ 大 聖 堂 の 楽 長 としてプロスケに<br />
協 力 〕<br />
30 ムーア 社 は、 翌 1875 年 既 存 の 第 三 、 四 版 と 同 内 容 の 第 五 版 を 急 遽 出 版 して、この 動 きに 対 抗 した。<br />
31 セシリア 主 義 者 らが、ホフマンを 無 視 した 理 由 の1つに、 彼 の 娯 楽 小 説 に 顕 著 な 反 カトリック 性 がある<br />
と 考 えるのは、 無 理 ない 推 測 であろう。 彼 の 小 説 の 舞 台 として、しばしば 登 場 する 修 道 院 のあまりにも<br />
「 不 気 味 」な 描 写 は、 敬 虔 なカトリック 教 徒 にとって 不 快 極 まるものであったことは 疑 いない。<br />
32 本 論 では、 限 られた 紙 幅 の 中 で、 三 者 の 関 連 を 論 じたため、それぞれの 考 察 がいささか 表 面 的 なものに<br />
とどまった。 準 備 中 の 博 士 論 文 においては、さらに 詳 細 な 考 察 を 試 みたい。<br />
40
セシリア 運 動 に 及 ぼした E. T. A. ホフマンの 影 響 について:A. F. J. ティボーとの 関 連 を 通 して<br />
セシリア 運 動 関 連 年 表 ( 本 論 に 関 連 するもののみ)<br />
1749 ベネディクトゥス 十 四 世 、 回 勅 Annus qui 公 布<br />
1814 ホフマン、”Alte und neue Kirchenmusik” を AMZ に 寄 稿 。<br />
1822 ホフマン、 死 去 。<br />
1824 ティボー、Ueber Reinheit der Tonkunst 初 版 、 刊 行 。<br />
1853 プロスケ、Musica Divina 第 1 巻 刊 行 (1862 年 完 結 )<br />
1865 ヴィット、Der Zustand der katholischen Kirchenmusik zunächst in Altbayern 刊 行 。<br />
1866 ヴィット、 雑 誌 Fliegende Blätter für katholische Kirchenmusik 創 刊 。<br />
1868 ヴィット、Allgemeiner Deutscher Cäcilien–Verein = ACV( 総 ドイツセシリア 協 会 ) 創 立 。( 出 席 者 330 名 )<br />
機 関 誌 Musica sacra 創 刊 。<br />
1868 ハーベルル 編 纂 のグレゴリオ 聖 歌 集 (レーゲンスブルク 版 )、 教 皇 庁 に 公 認 される。<br />
1870 教 皇 ピウス 九 世 、ACVを 認 可 。<br />
1876 セシリア 協 会 編 と 銘 打 ったティボーの 著 書 Ueber Reinheit der Tonkunst 新 版 刊 行 。<br />
1888 ヴィット 死 去 。<br />
1894 ハーベルル、ブライトコップフ&ヘルテルのパレストリーナ 全 集 ( 旧 全 集 ) 完 成 。<br />
1903 ピウス 十 世 、 教 皇 自 発 教 令 Motu proprio Tra le sollecitudini を 発 布 。<br />
1962 ~ 5 第 二 バチカン 公 会 議<br />
1963 典 礼 憲 章 公 布<br />
参 考 文 献 ( 本 論 に 関 連 するもののみ)<br />
〈 事 典 〉<br />
上 智 学 院 新 カトリック 大 事 典 編 纂 委 員 会 編 、1996–2009『 新 カトリック 大 事 典 』 研 究 社<br />
上 智 大 学 、 独 逸 ヘルデル 書 肆 編 、1940–77『カトリック 大 辞 典 』 冨 山 房<br />
日 本 基 督 教 協 議 会 文 書 事 業 部 キリスト 教 大 事 典 編 集 委 員 会 編 、1968『キリスト 教 大 事 典 』 教 文 館<br />
( 註 :ニューグローヴ 世 界 音 楽 大 事 典 や MGG については、 省 略 した。)<br />
〈 一 般 〉<br />
Allroggen, Gerhard. 1970. E. T. A. Hoffmanns Kompositionen. ein chronologisch–thematisches Verzeichnis seiner<br />
musikalischen Werke mit Einführung. . Regensburg: G. Bosse.<br />
Altenburg, Detlef.1994. “Thibauts Idee der ‘Reinheit der Tonkunst’” in: Studien zur Kirchenmusik im 19.<br />
Jahrhundert : Friedrich Wilhelm Riedel zum 60. Geburtstag. herausgegeben von Christoph-Hellmut Mahling.<br />
(Mainzer Studien zur Musikwissenschaft, Bd. 32) H. Schneider, 1994.<br />
朝 山 奈 津 子 、2008.「カール・リーデル(1827-1888)とライプツィヒ・リーデル 合 唱 団 の 活 動 」 博 士 論 文 、<br />
東 京 芸 術 大 学 .<br />
Bäcker, Carlernst. 1989. „Zum Palestrina–Bild in den deutschsprachigen Musikgeschichten um 1800“<br />
in: Palestrina und die Idee der klassischen Vokalpolyphonie im 19. Jahrhundert, zur Geschichte eines<br />
kirchenmusikalischen Stilideals. Unter Mitarbeit von Michael Jacob, Martina Janitzek und Peter Luttig hrg.<br />
von Winfried Kirsch. (Palestrina und die Kirchenmusik im 19. Jahrhundert ; Bd. 1) Regensburg: G. Bosse.<br />
(pp. 55–64)<br />
Bauer,Wilhelm A. & Deutsch.Otto Erich. 1962-1975. Briefe und Aufzeichnungen, Gesamtausgabe Mozart;<br />
herausgegeben von der Internationalen Stiftung Mozarteum, Salzburg. Kassel, New York. Bärenreiter. = 海 老<br />
沢 敏 、 高 橋 英 郎 編 訳 『モーツァルト 書 簡 全 集 第 5 巻 (ヴィーン 時 代 前 期 )』 白 水 社 , 1995.<br />
Charlton, David. 1989. Ernst Theodor Amadeus: E. T.A. Hoffmann’s musical writings; translated by Martyn<br />
41
成 城 美 学 美 術 史<br />
第 17 号<br />
Clarke. Cambridge University Press, New York.<br />
Daly, Kieran Anthony. 1995. Catholic church music in Ireland 1878—1903. Four Courts Press, Dublin.<br />
Dahlhaus, Carl. c1988. Klassische und romantische Musikästhetik. Laaber–Verlag<br />
Dahlhaus,Carl. 1987. Ludwig van Beethoven und seine ZeitLaaber–Verlag, Laaber =『ベートーヴェンとその<br />
時 代 』 杉 橋 陽 一 訳 、 西 村 書 店 、1997.<br />
Dittrich, Raymond. 2009a. “Die von Franz Xaver Witt veranlaßte Neuausgabe von Anton Friedrich Justus<br />
Thibauts Schrift ‘Ueber die Reinheit der Tonkunst’”in: Dr. Franz Xaver Witt 1834–1888 Reformer der<br />
katholischen Kirchenmusik. Zum 175. Geburtstag. herausgegeben von Paul Mai Verlag Schnell & Steiner,<br />
Regensburg 2009.<br />
Dittrich, Raymond. 2009b. “Franz Xaver Witt und die Instrumentalmusik’” in: Dr. Franz Xaver Witt<br />
1834–1888 Reformer der katholischen Kirchenmusik. Zum 175. Geburtstag ......<br />
Day–O‘Connell, Jeremy. 2007. Pentatonicism from the eighteenth century to Debussy. University of Rochester<br />
Press. Rochester, NY.<br />
Dobat, Klaus–Dieter. 1984. Musik als romantische Illusion: eine Untersuchung zur Bedeutung der Musikvorstellung<br />
E. T. A. Hoffmanns für sein literarisches Werk. Tübingen: Niemeyer.<br />
Einstein, Alfred. 1945 (translated by Arthur Mendel and Nathan Broder) Mozart, his character, his work. New<br />
York ; London. Oxford university press =『モーツァルト : その 人 間 と 作 品 』 浅 井 真 男 訳 、 白 水 社 、1961.<br />
海 老 澤 敏 、1972『 音 楽 の 思 想 』 音 楽 之 友 社 .<br />
Feldges, Brigitte. & Stadler, Ulrich. c1986. E. T. A. Hoffmann. Epoche - Werk - Wirkung. München. Beck.<br />
福 地 勝 美 、2010「F. X. ヴィットと J. E. ハーベルト : セシリア 運 動 内 のドイツ 派 とオーストリア 派 の 対 立<br />
をめぐって」『 成 城 美 学 美 術 史 第 16 号 』 成 城 大 学 文 学 研 究 科 17–48 頁<br />
Garratt, James. 2002. Palestrina and the German romantic imagination. Cambridge; Cambridge University Press<br />
(Cambridge musical texts and monographs).<br />
Geck, Martin. 1965. “E. T. A. Hofmanns Anschauungen über Kirchenmusik” in: Beiträge zur Musikforschung im<br />
19. Jahefundert. hrsg. von Walter Salmen, Regensburg Bosse.<br />
Gerstmeier, August. 1988. „Das Geschichtsbewußtsein in den musiktheoretischen Schriften des frühen 19.<br />
Jahrhunderts als Wurzel des Caecilianismus“ in: Der Caecilianismus: Anfänge, Grundlage, Wirkungen. Tutzing,<br />
pp.17–34<br />
Grout, Donald J. & Palisca, Claude V. 1980. A history of Western music. New York: Norton =『グラウト: 新<br />
西 洋 音 楽 史 ( 下 巻 )』 戸 口 幸 策 、 津 上 英 輔 、 寺 西 基 之 共 訳 、 音 楽 之 友 社 . 1998.<br />
Harnoncourt, Philip. 1988. “Der Liturgiebegriff bei den Frühe Cäcilianern und seine Anwendung auf die<br />
Kirchenmusik” in: Der Caecilianismus. Hrsg. Von H. Unverricht. Tutzing: Schneider (75–108).<br />
Hayburn, Robert F. c1979. Papal legislation on sacred music, 95 A. D. to 1977 A. D. Collegeville, Minn,<br />
Liturgical Press.<br />
半 田 元 夫 、 今 野 国 雄 1989『キリスト 教 史 (2)』 山 川 出 版 社 .<br />
樋 口 梨 々 子 、2006「E.T.A. ホフマンの『 新 旧 の 教 会 音 楽 』: ロマン 主 義 的 なもの」との 関 連 において 」『 研<br />
究 報 告 』 京 都 大 学 大 学 院 独 文 研 究 室 .<br />
Hoffmann, E. T. A. 1982.<br />
Die Serapionsbrüder: Zweiter Band [Alte und neue Kirchenmusik] (1819) in: E.T.A. Hoffmanns sämtliche<br />
Werke, in fünfzehn Bänden. [Bd. 6–7] herausgegeben mit einer biographischen Einleitung von Eduard<br />
Grisebach. 19––?. =「セラーピオン 朋 友 会 員 物 語 」『ホフマン 全 集 第 4 巻 』 深 田 甫 訳 、 創 土 社 . 1982.<br />
Hoffmann, E. T. A. 1985<br />
Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus. Sämtliche Werke in sechs Bänden; herausgegeben von Wulf Segebrecht<br />
und Hartmut Steinecke, unter Mitarbeit von Gerhard Allroggen und Ursula Segebrecht. Deutscher Klassiker<br />
Verlag. Bd. 2/2.. 1985.<br />
Jaschinski, Eckhard. 2005. Kleine Geschichte der Kirchenmusik. Freiburg: Herder.<br />
上 智 大 学 中 世 思 想 研 究 所 編 訳 、1997a『キリスト 教 史 (7) 啓 蒙 と 革 命 の 時 代 』 平 凡 社<br />
上 智 大 学 中 世 思 想 研 究 所 編 訳 、1997b『キリスト 教 史 (8 ) ロマン 主 義 時 代 のキリスト 教 』 平 凡 社<br />
42
セシリア 運 動 に 及 ぼした E. T. A. ホフマンの 影 響 について:A. F. J. ティボーとの 関 連 を 通 して<br />
亀 井 伸 治 、2009『ドイツのゴシック 小 説 』 彩 流 社<br />
Kindermann, Jürgen. 1965. «Romantische Aspekte in E. T. A. Hoffmanns Musikanschauung» in: Beiträge zur<br />
Musikforschung im 19. Jahefundert. Hrsg. von Walter Salmen, Regensburg. Bosse<br />
Kirsch, Winfried. (Hrsg.) 1989. Palestrina und die Idee der klassischen Vokalpolyphonie im 19. Jahrhundert.<br />
(Palestrina und die Kirchenmusik im 19. Jahrhundert ; Bd. 1). G. Bosse.<br />
Kirsch, Winfried. 1994. „ Wahrhaft frommer Sinn und Selbstverleugung ‚ E. T. A. Hoffmanns Canzoni per 4<br />
voci alla Cappella‘“ in: Studien zur Kirchenmusik im 19. Jahrhundert. Hrsg. von Christoph–Helmut Mahling.<br />
Tutzing: Schneider pp. 13–34.<br />
Lickleder, Christoph. 1988. Choral und figurierte Kirchenmusik in der Sicht Franz Xaver Witts anhand der<br />
Fliegenden Blätter und der Musica sacra, Feuchtinger & Gleichauf, .<br />
Lickleder, Christoph. 2009. „Franz Xaver Witt–ein streitbarer Kirchenmusiker zwischen dem 19. und<br />
21. Jahrhundert“ in: Dr. Franz Xaver Witt 1834–1888 Reformer der katholischen Kirchenmusik. Zum 175.<br />
Geburtstag. Hrsg. von Paul Mai Verlag Schnell & Steiner, Regensburg, 2009.<br />
三 村 利 恵 、2001 「19 世 紀 初 期 における 教 会 音 楽 とチェチーリア 運 動 」『 兵 庫 大 学 短 期 大 学 部 研 究 集 録 』<br />
(10–21 頁 ).<br />
宮 本 直 美 、2006『 教 養 の 歴 史 社 会 学 : ドイツ 市 民 社 会 と 音 楽 』 岩 波 書 店 .<br />
南 山 大 学 監 修 、1986『 第 2 バチカン 公 会 議 公 文 書 全 集 』 東 京 :サンパウロ .<br />
西 原 稔 、1990『 聖 なるイメージの 音 楽 』 音 楽 之 友 社 .<br />
野 村 良 雄 、1963『 宗 教 音 楽 の 歩 み』 音 楽 之 友 社 .<br />
野 村 良 雄 、1967『 世 界 宗 教 音 楽 史 』 春 秋 社 .<br />
Overath, Johannes. 1962. Musicae sacrae ministerium; Beiträge zur Geschichte der kirchenmusikalischen<br />
Erneuerung im XIX. Jahrhundert. (Festgabe für Karl Gustav Fellerer zur Vollendung seines 60. Lebensjahres<br />
am 7. Juli 1962.) Unter Mitarbeit seiner Schüler und Freunde. Hrsg. von Johannes Overath. Köln:<br />
Luthe–Druck.<br />
Pfeiffer, Harald.1989. Heidelberger Musikleben in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. B. Guderjahn, Heidelberg.<br />
Roters, Eberhard. 1985. E. T. A. Hoffmann. Stapp, Berlin. = 2000 『E.T.A. ホフマンの 世 界 : 生 涯 と 作 品 』 金<br />
森 誠 也 訳 、 吉 夏 社 .<br />
Salomon, Gerhard. 1983. E. T. A. Hoffmann: Bibliographie. Hildesheim. G. Olms<br />
相 良 憲 昭 、1993『 音 楽 史 の 中 のミサ 曲 』 音 楽 之 友 社 .<br />
Scharnagl, August.1980. Einfuhrung in die katholische Kirchenmusik..Heinrichshofen, Hamburg,<br />
Scharnagl, August. 1988. „Regensburg als zentrale Pflegestätte des Caecilianismus“. in: Der Caecilianismus:<br />
Anfänge, Grundlage, Wirkungen. Tutzing, pp. 279–294<br />
Schumann, Robert. c1964. Musikalische Haus- und Lebensregeln. Bärenreite<br />
Schwermer, Johannes. 1976. „Cäcilianismus“ in: Geschichte der katholischen Kirchenmusik. Mitarbeit zahlreicher<br />
Forscher des In – und Auslandes herausgegeben von Karl Gustav Fellerer. Bärenreiter–Verlag, Kassel<br />
1972–1976<br />
Sulzer, Johann Georg.1967–1970 (1792–1799) Allgemeine Theorie der schönen Künste, in einzelnen, nach<br />
alphabetischer Ordnung der Kunstwörter aufeinanderfolgenden, Artikeln abgehandelt. Hildesheim: G. Olms.<br />
(Reprint. Originally published 2. verm. Aufl. Leipzig, 1792–1799)<br />
滝 藤 早 苗 、2006「 真 の 教 会 音 楽 をめぐる 論 争 と E. T. A. ホフマン― 彼 のロマン 主 義 的 宗 教 音 楽 観 」『 慶 應<br />
義 塾 大 学 独 文 学 研 究 室 研 究 年 報 』23 号 、「 研 究 年 報 」 刊 行 会 . 101–115 頁 .<br />
Thewalt, Patrick. c1990. Die Leiden der Kapellmeister : zur Umwertung von Musik und Künstlertum bei W.H.<br />
Wackenroder und E.T.A. Hoffmann. P. Lang, Frankfurt am Main ; New York.<br />
Thibaut, Anton Friedrich Justus. 1826. Ueber Reinheit der Tonkunst. Akademische Verlagshandlung von J. C. B.<br />
Mohr Heidelberg (1851)〔 原 著 の 第 3 版 〕.<br />
Thibaut, Anton Friedrich Justus. 1876. Ueber Reinheit der Tonkunst. Mit einem Commentar herausgegeben von<br />
Profrssor Birkler, Haupt=Vereinesgabe (pro 1876) des allgemeinen deutschen Cäcilien–Vereiness. Druck von Friedrich<br />
Pustet, Regensburug, New York & Cincinnati.<br />
43
成 城 美 学 美 術 史<br />
第 17 号<br />
Thibaut, A, F, translated Gladstone. W. H. 1877. On Purity in Musical Art. John Murray, London.<br />
鶴 巻 保 子 、2000 「ピオ 10 世 の Motu Proprio による 教 会 音 楽 の 影 響 と 課 題 」『 東 京 純 心 女 子 大 学 紀 要 (4)』<br />
東 京 純 心 女 子 大 学 .<br />
吉 田 寛 、2001「E. T. A. ホフマンの 音 楽 美 学 にみる 歴 史 哲 学 的 思 考 ― 器 楽 の 美 学 はいかにして 進 歩 的 歴 史<br />
観 と 結 びついたか」『 美 学 芸 術 学 研 究 』20 号 . 東 京 大 学 大 学 院 人 文 社 会 系 研 究 科 ・ 文 学 部 美 学 芸 術 学 研<br />
究 室 .<br />
44
セシリア 運 動 に 及 ぼした E. T. A. ホフマンの 影 響 について:A. F. J. ティボーとの 関 連 を 通 して<br />
参 考 図 版<br />
図 版 1 セシリア 協 会 版 Ueber Reinheit der Tonkunst 表 紙 ( 筆 者 ( 福 地 ) 所 蔵 )<br />
45
成 城 美 学 美 術 史<br />
第 17 号<br />
図 版 2 セシリア 協 会 版 Ueber Reinheit der Tonkunst 編 者 による 序 文 冒 頭<br />
46
セシリア 運 動 に 及 ぼした E. T. A. ホフマンの 影 響 について:A. F. J. ティボーとの 関 連 を 通 して<br />
図 版 3 セシリア 協 会 版 Ueber Reinheit der Tonkunst 本 文 2 頁<br />
47
成 城 美 学 美 術 史<br />
第 17 号<br />
E. T. A. Hoffmann’s and A. F. J. Thibaut’s Influence on the Cecilian Movement<br />
FUKUCHI Katsumi<br />
E. T. A. Hoffman’s “Alte und neue Kirchmusik” (1814) and A. F. J. Thibaut’s Ueber Reiheit<br />
der Tonkunst (1824) were two works that greatly influenced the so-called the Cecilian Movement of<br />
German church music in the early nineteenth century. Though these writers were Protestant, their<br />
ideas were widely accepted by Catholic Church musicians, the leaders of the movement who strove<br />
to reform church music. In this paper I explore not only how Hoffmann’s and Thibaut’s writings<br />
were noticed but also accepted as part of the movement. Also I discuss in detail Hoffmann’s<br />
influence in particular to which little academic attention has been paid so far.<br />
48