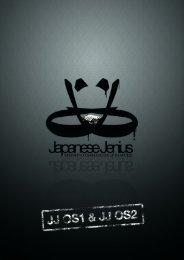こちら(PDF)
こちら(PDF)
こちら(PDF)
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
米国には ASGRAE ガイドラインがあるが、施主はまだ費用支払について一般的に受け入れていな<br />
い。NIST としてはコミッショニングのコストを重要と考えている。すなわち、自動的手法やモデ<br />
ル手法を駆使したものとしたい.コミッショニングの型に関しては Continuous Commissioning に興<br />
味がある。1996 にオークリッジの 44 件のビルで実施された再コミッションニング(Retro-<br />
Commissioning)では,5~15%の省エネルギーが達成できた.コミッションニングにより省エネル<br />
ギーだけではなく IAQ も向上した.コミッションニングは Re-コミッションニング,Continuous(継<br />
続)-コミッションニング,Re-コミッションニングとに分けて考えている.<br />
□ ベルギー<br />
制御系のコミッションニングが通常あまり行われていないことが問題である.これはセンサー,<br />
アクチュアーター,アルゴリズムに分けてコミッションニングする必要がある.特にアルゴリズム<br />
は通常,設計でしっかり記載されていないので問題が多い.このコミッションニングにはシミュレ<br />
ーションが役立つだろう.チェックリストによるコミッションニングは高価であり問題である.今<br />
後,ライフサイクルマネジメントが重要になる(京都議定書).建物コミッションニングとシステ<br />
ムコミッションニングを区別する必要がある.建物コミッションニングでは HVAC システムだけで<br />
はなく,消火や建物自身も含むべきだと考えている.コミッションニングはオーナーを代表する性<br />
質のものである.今より多くのこと設計段階でなされるべきである.<br />
□ カナダ<br />
コミッションニングツールは新しい技術の追加ができるフレキシブルな構造であるべきだと思<br />
う.また,空調システムには非常に沢山のコンポーネントがあるので,これにどのように対応する<br />
かが重要である.アプリケーションを標準化して品質を上げコストを低減すること、BEMS を使っ<br />
て、コンポーネントとシステムの性能(エネルギ性能を含む)を検証することを提案。またアプリ<br />
ケーションが標準化されれば、常時の計測と故障の発見も Database や AI Tools などを使い自動化で<br />
きる。<br />
□ オランダ<br />
オランダには ISSO(ISO とは異なる)によってコミッションニングがなされている.今後は QA<br />
(Quality Assurance)が重要と考える.そのためには誰がユーザーかを明確にする必要があろう.そ<br />
こで問題のあった建物を、MQA(Matrix for Quality Assurance)を用いて、管理項目が建設のそれぞ<br />
れのフェーズでどうであったのか分析した。企画段階ではドキュメント化がなされてい、計測しよ<br />
うにも実施に問題があり不可能であったなどが洗い出された.<br />
□ 日本<br />
中原が、日本でのコミッショニング活動の状況、その前提となる建築教育と建築資格の現状につ<br />
いて述べ、とくに日本の SHASE(空気調和・衛生工学会)で提案するコミッショニングの定義を<br />
ASHRAE(米国)や BSRIA(英国)の定義と比較してよりグローバルなものとし、その目的を省エネル<br />
ギーと室内及びグローバルな環境保全、建物の使いやすさの実現とし、ライフサイクルに亘ること<br />
の必要性を強調した.また BOFD とコミッショニング、及び TAB との関係を明確にし、本 Annex の<br />
あり方に示唆を与えた.次いで試験的に実施中の実際プロジェクトのコミッショニングの実施状況、<br />
及び竣工後一年以上にわたってエネルギー性能をフォローし越すとダウンと省エネルギーに成果<br />
を上げたレトロコミッショニング、または継続コミッショニングの例を示した.<br />
■ 最終的なプロジェクト枠組みと各国の興味の対象<br />
これについては後章の企画書第5案(英文)に詳しいが、この最終案は第2回のワークショップの討<br />
議に基づいて、フランスの Visier 氏がまとめたもの(第4案)を内容に関しては中原の、また用語に関し<br />
て米国からのコメントを取り入れて最終的に出来上がったもので ECBCS の執行委員会に提出された<br />
ものである.この中で参加希望国は第2回ワークショップの参加者が個人の判断で手を上げたもので、<br />
7