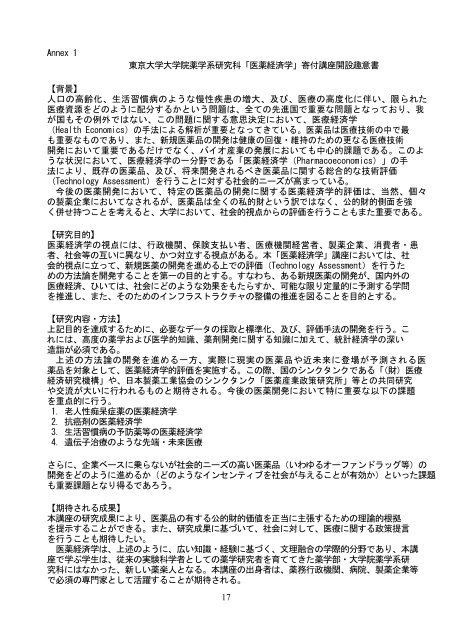Untitled - 東京大学 大学院薬学系研究科・薬学部
Untitled - 東京大学 大学院薬学系研究科・薬学部
Untitled - 東京大学 大学院薬学系研究科・薬学部
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Annex 1<br />
<strong>東京大学</strong>大学院薬学系研究科「医薬経済学」寄付講座開設趣意書<br />
【背景】<br />
人口の高齢化、生活習慣病のような慢性疾患の増大、及び、医療の高度化に伴い、限られた<br />
医療資源をどのように配分するかという問題は、全ての先進国で重要な問題となっており、我<br />
が国もその例外ではない、この問題に関する意思決定において、医療経済学<br />
(Health Economics)の手法による解析が重要となってきている。医薬品は医療技術の中で最<br />
も重要なものであり、また、新規医薬品の開発は健康の回復・維持のための更なる医療技術<br />
開発において重要であるだけでなく、バイオ産業の発展においても中心的課題である。このよ<br />
うな状況において、医療経済学の一分野である「医薬経済学(Pharmacoeconomics)」の手<br />
法により、既存の医薬品、及び、将来開発されるべき医薬品に関する総合的な技術評価<br />
(Technology Assessment)を行うことに対する社会的ニーズが高まっている。<br />
今後の医薬開発において、特定の医薬品の開発に関する医薬経済学的評価は、当然、個々<br />
の製薬企業においてなされるが、医薬品は全くの私的財という訳ではなく、公的財的側面を強<br />
く併せ持つことを考えると、大学において、社会的視点からの評価を行うこともまた重要である。<br />
【研究目的】<br />
医薬経済学の視点には、行政機関、保険支払い者、医療機関経営者、製薬企業、消費者・患<br />
者、社会等の互いに異なり、かつ対立する視点がある。本「医薬経済学」講座においては、社<br />
会的視点に立って、新規医薬の開発を進める上での評価(Technology Assessment)を行うた<br />
めの方法論を開発することを第一の目的とする。すなわち、ある新規医薬の開発が、国内外の<br />
医療経済、ひいては、社会にどのような効果をもたらすか、可能な限り定量的に予測する学問<br />
を推進し、また、そのためのインフラストラクチャの整備の推進を図ることを目的とする。<br />
【研究内容・方法】<br />
上記目的を達成するために、必要なデータの採取と標準化、及び、評価手法の開発を行う。こ<br />
れには、高度の薬学および医学的知識、薬剤開発に関する知識に加えて、統計経済学の深い<br />
造詣が必須である。<br />
上述の方法論の開発を進める一方、実際に現実の医薬品や近未来に登場が予測される医<br />
薬品を対象として、医薬経済学的評価を実施する。この際、国のシンクタンクである「(財)医療<br />
経済研究機構」や、日本製薬工業協会のシンクタンク「医薬産業政策研究所」等との共同研究<br />
や交流が大いに行われるものと期待される。今後の医薬開発において特に重要な以下の課題<br />
を重点的に行う。<br />
1. 老人性痴呆症薬の医薬経済学<br />
2. 抗癌剤の医薬経済学<br />
3. 生活習慣病の予防薬等の医薬経済学<br />
4. 遺伝子治療のような先端・未来医療<br />
さらに、企業ベースに乗らないが社会的ニーズの高い医薬品(いわゆるオーファンドラッグ等)の<br />
開発をどのように進めるか(どのようなインセンティブを社会が与えることが有効か)といった課題<br />
も重要課題となり得るであろう。<br />
【期待される成果】<br />
本講座の研究成果により、医薬品の有する公的財的価値を正当に主張するための理論的根拠<br />
を提示することができる。また、研究成果に基づいて、社会に対して、医療に関する政策提言<br />
を行うことも期待したい。<br />
医薬経済学は、上述のように、広い知識・経験に基づく、文理融合の学際的分野であり、本講<br />
座で学ぶ学生は、従来の実験科学者としての薬学研究者を育ててきた薬学部・大学院薬学系研<br />
究科にはなかった、新しい薬楽人となる。本講座の出身者は、薬務行政機関、病院、製薬企業等<br />
で必須の専門家として活躍することが期待される。<br />
17