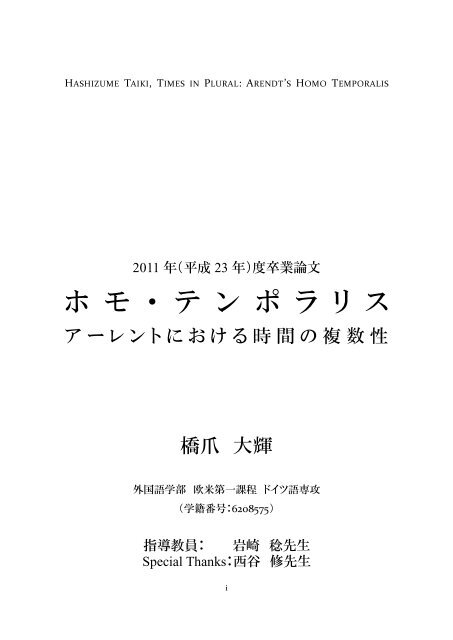You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
HASHIZUME TAIKI, TIMES IN PLURAL: ARENDT’S HOMO TEMPORALIS<br />
2011 年 ( 平 成 23 年 ) 度 卒 業 論 文<br />
ホ モ ・ テ ン ポ ラ リ ス<br />
ア ー レ ン ト に お け る 時 間 の 複 数 性<br />
橋 爪 大 輝<br />
外 国 語 学 部 欧 米 第 一 課 程 ドイツ 語 専 攻<br />
( 学 籍 番 号 :62<strong>08</strong>575)<br />
指 導 教 員 : 岩 崎 稔 先 生<br />
Special Thanks: 西 谷 修 先 生<br />
i
目 次<br />
序 論 部 時 間 論 一 般 、およびアーレント 政 治 学 の 基 礎 概 念 範 疇 への 導 入<br />
第 一 章 時 間 論 一 般 への 導 入 ........................................................................................................ 1<br />
第 1 節 時 間 論 をなぜ 問 うか ....................................................................................................... 1<br />
第 2 節 社 会 学 的 時 間 論 ............................................................................................................ 2<br />
a) 反 復 的 な 時 間 ...................................................................................................................... 2<br />
b) 円 環 的 な 時 間 ...................................................................................................................... 3<br />
c) 線 分 的 な 時 間 ...................................................................................................................... 4<br />
d) 直 線 的 な 時 間 ...................................................................................................................... 5<br />
第 3 節 言 語 に 表 われる 時 間 意 識 ............................................................................................. 6<br />
第 4 節 古 典 ギリシア 語 の 四 つの 語 に 見 られる 時 間 意 識 ......................................................... 9<br />
a) クロノス ................................................................................................................................. 9<br />
b) カイロス .............................................................................................................................. 10<br />
c) ホーラ(ホーライ) ............................................................................................................... 11<br />
d) アイオーン ......................................................................................................................... 12<br />
第 5 節 時 間 一 般 の 形 式 .......................................................................................................... 13<br />
第 6 節 時 間 の 複 数 性 .............................................................................................................. 18<br />
第 二 章 アーレント 政 治 学 の 基 礎 的 な 概 念 範 疇 .......................................................................... 20<br />
、、、、<br />
第 7 節 アーレントの「 政 治 学 」――「 形 而 上 学 」に 裏 打 ちされたものとして............................ 20<br />
第 8 節 活 動 的 生 活 と 精 神 的 生 活 ........................................................................................... 22<br />
第 9 節 観 想 的 生 活 に 関 するハイデガーの 解 釈 ..................................................................... 23<br />
第 10 節 観 想 的 生 活 と 活 動 的 生 活 ――『 人 間 の 条 件 』における 理 解 ................................... 26<br />
第 11 節 観 想 的 生 活 から 精 神 的 生 活 へ――『 精 神 の 生 活 』における 理 解 ........................... 27<br />
本 論 部 アーレントの 時 間 論<br />
第 一 部 活 動 的 生 活 の 時 間 性<br />
第 三 章 仕 事 の 時 間 性 .................................................................................................................. 30<br />
第 12 節 活 動 的 生 活 の 三 活 動 力 の 共 存 ................................................................................. 30<br />
第 13 節 仕 事 = 制 作 ――ハイデガーにおける 制 作 の 概 念 ................................................... 32<br />
第 14 節 「 世 界 」の 概 念 ―― 物 の 世 界 性 ................................................................................. 35<br />
第 15 節 仕 事 の 目 的 論 的 性 格 ................................................................................................ 39<br />
第 16 節 目 的 論 的 時 間 了 解 .................................................................................................... 41<br />
ii
第 四 章 労 働 の 時 間 性 .................................................................................................................. 47<br />
第 17 節 二 つの 生 の 区 別 ........................................................................................................ 47<br />
第 18 節 労 働 の 活 動 力 とその 生 産 物 ...................................................................................... 50<br />
第 19 節 円 環 的 時 間 経 験 ―― 永 劫 回 帰 ................................................................................ 52<br />
補 論 時 計 的 時 間 ...................................................................................................................... 57<br />
第 五 章 活 動 の 時 間 性 .................................................................................................................. 62<br />
第 20 節 活 動 の 性 格 ―― 唯 一 性 と 始 まり ................................................................................ 62<br />
第 21 節 「 始 まり」の 時 間 論 的 性 格 .......................................................................................... 64<br />
第 22 節 物 語 と 歴 史 ................................................................................................................. 68<br />
第 23 節 活 動 の 遂 行 的 性 格 ――エネルゲイアないしプラクシスとして.................................. 70<br />
補 論 革 命 の 時 間 論 .................................................................................................................. 73<br />
a) 「 革 命 revolutio」の 原 義 .................................................................................................... 73<br />
b) 革 命 の 制 作 的 モデル――フランス 革 命 ........................................................................... 75<br />
c) 自 由 の 創 設 としての 革 命 ――アメリカ 革 命 ...................................................................... 76<br />
第 二 部 精 神 的 生 活 の 時 間 性<br />
第 六 章 思 考 の 時 間 性 .................................................................................................................. 80<br />
第 24 節 精 神 的 生 活 の 時 間 論 ................................................................................................ 80<br />
第 25 節 思 考 する 自 我 の「 場 所 」と「 一 者 のなかの 二 者 two in one」 ...................................... 81<br />
第 26 節 思 考 の 意 味 ―― 他 の 精 神 の 働 きと 区 別 しつつ ........................................................ 84<br />
第 27 節 思 考 の 時 間 経 験 ――「 静 止 セル 現 在 nunc stans」 ................................................... 87<br />
第 七 章 意 志 の 時 間 性 .................................................................................................................. 90<br />
第 28 節 意 志 の 哲 学 史 ............................................................................................................ 90<br />
第 29 節 意 志 に 関 する 思 考 の 源 泉 ――ハイデガー・ヤスパース........................................... 94<br />
第 30 節 意 志 の 時 間 経 験 ――「まだない not yet」 ................................................................ 100<br />
補 論 決 断 を 巡 る 思 考 ――シュミット....................................................................................... 104<br />
第 八 章 判 断 の 時 間 性 ................................................................................................................ 110<br />
第 31 節 観 客 としての 判 断 者 ................................................................................................. 110<br />
第 32 節 判 断 と 歴 史 ............................................................................................................... 112<br />
第 33 節 判 断 はどのように 働 くのか―― 趣 味 、 構 想 力 、 共 通 感 覚 ...................................... 114<br />
第 34 節 範 例 ―― 判 断 を 補 助 する 特 殊 事 例 ........................................................................ 116<br />
第 35 節 判 断 の 時 間 経 験 ――「もうない no more」 ............................................................... 118<br />
iii
結 論 .................................................................................................................................................. 123<br />
参 考 文 献 .......................................................................................................................................... 126<br />
あとがき ............................................................................................................................................. 131<br />
iv
序 論 部 時 間 論 一 般 、およびアーレント 政 治 学 の 基 礎 概 念 範 疇 への 導 入<br />
第 一 章 時 間 論 一 般 への 導 入<br />
ではいったい、 時 間 とはなんなのだろうか。だれも 私 にたず<br />
ねないときには、 私 は 知 っている。たずねられて 説 明 しようと<br />
すると、 知 らないのである。<br />
――アウグスティヌス『 告 白 』<br />
第 1 節<br />
時 間 論 をなぜ 問 うか<br />
本 論 が 問 題 とするのは、ハンナ・アーレントにおける「 時 間 論 」である。<br />
アーレントは 20 世 紀 を 代 表 する 思 想 家 の 一 人 であるが、 自 ら「 政 治 学 」の 専 門 家 を 自 称 し、「 政<br />
治 」や「 政 治 的 なるもの」に 対 する 強 い 関 心 を 示 していた。『 全 体 主 義 の 起 源 』、『 人 間 の 条 件 』、『 革<br />
命 について』、『 精 神 の 生 活 』と 見 ていっても、 彼 女 の 作 品 に「 時 間 」を 主 題 的 に 問 うた 作 品 は 見 つ<br />
からない。なぜ、アーレントの 時 間 論 を 問 うのか。それを 問 うことに 意 義 はあるのか。<br />
勿 論 、 問 う 意 義 があると 私 が 考 えているのは、 本 論 を 書 くこと、「アーレントの 時 間 論 」という 問 題<br />
パフォーマティヴ<br />
を 立 てること 自 体 が、 遂 行 的 に 明 らかにしていると 言 える。だが、 少 なくともなぜ 問 うことが 必 要 であ<br />
ると 考 えるのか、それを 詳 らかにする 必 要 はあろう。けだし、それは 人 間 存 在 にとっての 時 間 のステ<br />
イタスに 関 わる 問 題 である。 論 文 のはじめに 若 干 紙 面 を 割 き、 時 間 そのものについて、また 時 間 論<br />
なるものについて、 一 般 的 な 考 察 をしてみよう。つまり、なぜ 時 間 という 問 題 が 人 間 にとって 重 要 で<br />
あるのか。<br />
時 間 と 聞 いて、 物 理 学 的 な 時 間 、すなわち 時 計 的 ・ 数 量 的 時 間 を、 単 純 に 想 像 してはならない。<br />
そのような 時 間 の 経 験 が 主 流 となったのは―― 言 い 換 えるならば 時 間 を 時 計 で 測 ることの 可 能 な、<br />
数 的 にのみ 把 握 しうるものとして 経 験 し、そのほかの 仕 方 では 経 験 しえないとしたのは―― 数 学 的<br />
、、<br />
認 識 が 世 界 に 対 する 支 配 的 な 態 度 となり、しかも 時 計 が 浸 透 して、 数 的 な 時 間 経 験 が 広 く 共 有 さ<br />
れてからのことに 過 ぎない。 数 学 、あるいはその 影 響 を 受 けた 物 理 学 の 作 りだした 数 的 な 時 間 経 験<br />
が、 逆 に 我 々の 時 間 経 験 を 大 部 分 規 定 したのであり、 時 計 が 我 々の 時 間 経 験 をも 時 計 的 にしてい<br />
るのである。 我 々はこのような 物 理 学 的 ・ 数 的 時 間 という、 認 識 的 な 時 間 経 験 の 影 響 を 受 け 過 ぎて、<br />
時 間 のイメージを 縮 減 させているとも 言 うことが 出 来 る。<br />
むろん、そのような 数 的 な 時 間 経 験 も、 時 間 の 様 態 の 一 であることは 間 違 いない。しかしながら、<br />
時 間 は 人 間 存 在 にとってもっと 多 様 なものであると、 我 々は 考 える。 時 間 は 人 間 の 行 為 から 発 源 し、<br />
行 為 の 様 態 に 従 ってさまざまに 様 態 化 する。 数 的 時 間 経 験 もまた、 時 間 の 経 験 の 一 様 態 であって、<br />
その 全 てではない。<br />
、、、<br />
だがまずは、 数 的 = 物 理 学 的 = 時 計 的 時 間 経 験 を 相 対 化 する 目 的 で、いくつかの 時 間 論 のモ<br />
デルを 参 看 しておきたい。 導 入 として 社 会 学 や 人 類 学 が 発 見 した 時 間 を 見 よう。それらは 多 様 な 時<br />
1
間 の 経 験 の 様 態 を 含 んでいる。そのような 時 間 経 験 の 発 源 の 多 様 性 を 見 れば、 少 なくとも 数 的 時<br />
間 経 験 を 相 対 化 する 目 的 には 資 する。<br />
第 2 節 社 会 学 的 時 間 論<br />
時 間 論 の 広 がりを 見 るための 一 例 として、 社 会 学 的 な 時<br />
間 論 を 見 よう。ここで 主 に 依 拠 するのは、 真 木 悠 介 の 比 較<br />
社 会 学 的 考 察 である(『 時 間 の 比 較 社 会 学 』)。<br />
、、、<br />
真 木 は、ヴェーバーの 概 念 を 借 りて、「 理 念 型 Idealtypus<br />
、、、、<br />
、、、、<br />
としての四 つの 時 間 形 態 を〔 略 〕 純 化 して設 定 しておくこと<br />
、、、、、<br />
が、 方 法 として有 効 であるように 思 う」 1 と 述 べている。すな<br />
わち、 実 際 には 多 様 なヴァリエーションが 時 間 概 念 ・ 時 間<br />
意 識 にはあるが、 真 木 は 四 つの 方 向 性 を 措 定 することによ<br />
り、 極 限 的 な 純 粋 形 態 をとりだそうと 試 みるのだ。その 四 つ<br />
の 時 間 意 識 とは、a) 反 復 的 な 時 間 、b) 円 環 的 な 時 間 、c) 線 図 1 四 つの 時 間 意 識 ( 真 木 悠 介 『 時 間 の<br />
分 的 な 時 間 、d) 直 線 的 な 時 間 である。 更 に 真 木 はその 四 比 較 社 会 学 』 岩 波 現 代 文 庫 、163 頁 の 表 )<br />
つを「 型 の 変 数 」pattern variables(パーソンズ)により 解 析<br />
する。そして 上 記 の 四 つの 時 間 性 を、 四 つの「 型 の 変 数 」の 合 成 により 説 明 する。その 四 つの「 型 の<br />
変 数 」とは、1) 質 としての 時 間 、 対 、2) 量 としての 時 間 。それに 加 えて、3) 可 逆 性 としての 時 間 、 対 、<br />
4) 不 可 逆 性 としての 時 間 、である。 以 上 をまとめた 表 が、 図 1 である。それでは、それぞれがどうい<br />
った 時 間 意 識 であるのかを、 以 下 で 一 つずつ 順 番 に 見 てゆく。そのなかで「 時 間 意 識 の 形 態 」や<br />
「 型 の 変 数 」の 持 つ 意 味 も、よりよく 了 解 されるだろう。<br />
a) 反 復 的 な 時 間<br />
時 代 的 に 見 て、 最 初 に 出 現 した 時 間 経 験 は、 反 復 的 な 時 間 である。 真 木 はこれを〈 原 始 共 同<br />
体 〉の 時 間 とも 名 指 している。「 型 の 変 数 」の 組 み 合 わせとしては、「 質 としての 時 間 」かつ「 可 逆 的<br />
な 時 間 」、ということになる。<br />
真 木 が 指 摘 するように、「 近 代 の 時 間 論 がしばしば 時 間 の 観 念 の 二 つの 基 礎 的 な 類 型 として 設<br />
定 するように、〈 直 線 としての 時 間 〉にたいする〈 円 環 としての 時 間 〉という 考 え 方 には、すでにわれ<br />
われの 先 入 見 である『 時 間 は 連 続 的 に 動 いてゆくはずだ』という 前 提 が 入 り 込 んでいる」 2 。しかし 原<br />
初 の 時 間 の 表 象 は「 一 般 に 不 可 逆 の 直 線 ではなく、 循 環 する 円 ですらなく、たんに 反 復 する 対 極<br />
性 であった」 3 。 真 木 は、 我 々の 時 間 に 関 する 予 断 ―― 時 間 は 連 続 的 であるという 予 断 ――を 相 対<br />
化 するために、アフリカやアメリカ、オーストラリアの 原 住 民 の、そして 古 代 日 本 人 の 時 間 意 識 を 分<br />
析 する。そこでは 時 間 は 反 復 的 である。 真 木 はその 時 間 意 識 の 説 明 として、 人 類 学 者 エドマンド・リ<br />
1<br />
2<br />
3<br />
真 木 悠 介 『 時 間 の 比 較 社 会 学 』 岩 波 現 代 文 庫 、2003 年 ( 原 著 1981 年 )、164 頁 。<br />
同 上 、19 頁 。<br />
同 上 、100 頁 。<br />
2
ーチを 引 用 している。<br />
実 際 、いくつかの 未 開 社 会 においては、 時 間 の 経 過 は、…… 同 じ 方 向 へたえず 進 行 してゆく<br />
という 感 覚 も、また 同 じ 輪 のまわりをまわり 続 けるという 感 覚 も 存 在 しない……。 反 対 に、 時 間 は、<br />
持 続 しない 何 か、 繰 り 返 す 逆 転 の 反 復 、 対 極 間 を 振 動 することの 連 続 として 経 験 される。すな<br />
わち 夜 と 昼 、 冬 と 夏 、 乾 燥 と 洪 水 、 老 齢 と 若 さ、 生 と 死 という 具 合 にである。このような 図 式 にあ<br />
っては、 過 去 は 何 ら「 深 さ」をもつものではない。すべての 過 去 は 等 しく 過 去 である。それは 単<br />
に 現 在 の 対 立 物 にしかすぎない。 4<br />
たとえば、このような 時 間 意 識 は、 次 のような 表 象 にも 現 われる。「メキシコの 国 立 民 族 学 博 物 館 の<br />
入 口 に、アステカの 時 間 意 識 を 表 現 した 巨 大 な 壁 画 があるが、それは 太 陽 神 と 夜 の 神 との 永 劫 に<br />
つづく 戦 いである。 夜 明 けのくるたびに 太 陽 神 は 夜 を 駆 逐 する。けれども 日 暮 れのくるたびにふた<br />
たび 夜 の 神 は 昼 を 放 逐 する。この 相 克 は 世 のつづくかぎりくりかえされる」 5 。このような 時 間 意 識 に<br />
とって、 対 立 する 二 つの 時 間 は、いわば 二 つの 別 の 世 界 ――すなわち 一 方 から 他 方 への「 移 行 が<br />
、、<br />
ひとつの 危 機 であるほどに 異 質 な 二 世 界 」 6 ――なのだ。「 原 始 共 同 体 に 一 般 的 な 時 間 の 表 象 は、<br />
、、、、、<br />
〔 略 〕おなじくくりかえすものであっても、 円 形 あるいは 循 環 というものではなく、『くりかえす 逆 転 の 反<br />
復 、 対 極 間 を 振 動 することの 連 続 』であった」 7 。<br />
このような 時 間 は 当 然 数 で 数 えうる「 量 」であることはありえない。しかるに、この 時 間 は「 質 として<br />
の 時 間 」である。 逆 にいえば、この 時 間 意 識 において 時 間 は 一 種 の「 質 」であり、 真 木 の 言 い 方 を<br />
借 りれば「 世 界 」ということになる。かつ、「 昼 」から「 夜 」への 移 行 の 後 に「 夜 」から「 昼 」への 移 行 があ<br />
るように、 時 間 は( 我 々の 目 からすれば)「 可 逆 的 」である 8 。こうして「 反 復 的 な 時 間 」は「 可 逆 的 な、<br />
質 としての 時 間 性 」と 特 徴 付 けられる。<br />
b) 円 環 的 な 時 間<br />
円 環 的 な 時 間 を、 真 木 は「ヘレニズムの 時 間 」とも 名 指 している。 真 木 がギリシアの 時 間 性 にお<br />
いて 重 要 であると 見 做 すのは、 数 量 性 である。 真 木 は、ギリシアにおける 鋳 貨 の 開 始 という 現 象 の<br />
本 質 を、 数 量 化 として 見 出 す。<br />
、、<br />
鋳 貨 の 特 質 は、〔 略 〕 事 物 を 量 として 換 算 するのみではなく、それ 以 上 分 解 しえない 単 位 を<br />
、、、、<br />
基 礎 とする 数 として表 現 することである。〈 万 有 は 数 である〉というピュタゴラス 学 派 の 根 本 テー<br />
4<br />
同 上 、19-20 頁 。(LEACH, Edmund R., Rethinking Anthropology, 1961. 青 木 保 、 井 上 兼 行 訳 『 人 類 学 再 考 』 思 索<br />
社 、1974 年 、212-213 頁 。)<br />
5<br />
同 上 、55 頁 。<br />
6<br />
同 上 、160 頁 。<br />
7<br />
同 上 。<br />
8 「 可 逆 」という 言 い 方 は 本 来 であれば 適 切 とは 言 えない。なぜなら「 可 逆 」ということはすでにひとつの 方 向 性 を 前<br />
提 としており、「 逆 」という 方 向 はある 方 向 から 弁 証 法 的 に 規 定 されるものであるからだ。よって「 逆 」という 言 い 方 はす<br />
でに 直 線 的 な 時 間 性 を 前 提 していると 言 わざるを 得 ない。 我 々からすれば「 夜 」から「 昼 」への 移 行 は「 逆 」 方 向 の 運<br />
3
ゼは、このような 生 活 世 界 に 基 礎 をおく 宇 宙 了 解 であるように 思 われる。 9<br />
こうした 数 としての 宇 宙 把 握 と、「 輪 廻 」 観 念 を 持 つオルフェウス 教 とが 出 会 い、ギリシア 的 円 環 的 時<br />
間 が 生 じたと 真 木 は 考 える。<br />
、、、<br />
オルフェウス 教 自 体 はむしろ、 固 有 の 意 味 でのヘレニズム 文 明 以 前 の、 農 耕 共 同 体 の 時 間<br />
感 覚 を 基 礎 としている。この 時 間 感 覚 が、ヘレニズム 文 明 世 界 の 客 体 化 し 数 量 化 する、したが<br />
ってまた 抽 象 的 に 無 限 化 してゆくロゴスと 出 会 った 時 に、その 交 叉 するところに 必 然 に 生 まれ<br />
、、<br />
てくるのが、 円 環 としての 時 間 のイメージであったのではないか。 円 形 はギリシャの 人 間 が 無<br />
限 を 表 象 するときの 形 式 であった。はるかな 原 始 共 同 体 にまで 通 底 するオルフェウス 教 の 生<br />
、、、<br />
、、、<br />
死 の 反 復 する 感 覚 が、 数 量 化 するロゴスによって 対 象 化 されたときの 形 象 が、ヘレニズム 的 な<br />
、、<br />
時 間 の 円 環 であったはずである。 10<br />
すなわち、 我 々が 第 一 に 見 てきた 反 復 的 時 間 が、 数 的 な 合 理 性 を 獲 得 することを 通 して、 円 環 的<br />
な 性 質 を 得 るということである。それゆえギリシア 人 の 時 間 性 は、 質 というよりは 量 的 な 時 間 性 であり、<br />
かつ「 円 環 」であるから 可 逆 的 である( 厳 密 には 可 逆 ――すなわち、 逆 流 可 能 である――というより<br />
は、 巡 り 巡 って 同 じ 時 が 帰 って 来 るということだが)。 故 にヘレニズムの 円 環 的 時 間 は、「 可 逆 的 で、<br />
量 的 な 時 間 」である。<br />
c) 線 分 的 な 時 間<br />
前 述 の 円 環 的 時 間 がヘレニズムの 時 間 と 名 指 されていたのに 対 し、 線 分 的 時 間 は「ヘブライズ<br />
、、、、<br />
ムの 時 間 」と 名 づけられる。その 重 要 な 要 素 は 不 可 逆 性 である。そして「ヘブライズムの 直 進 する 時<br />
、、、<br />
間 の 意 識 は 終 末 論 をその 起 源 としている」 11 。なぜ 時 間 が 終 末 論 において 線 分 となるのか。 真 木 は<br />
クルマンを 引 いてこう 述 べる。「なぜならば、『 始 め』と『 終 わり』が 問 題 とされるからである。『 始 め』と<br />
、、、、、、<br />
『 終 わり』とが 区 別 せられるならば、 直 線 がそれに 適 合 した 形 だからである」 12 。そのことを 真 木 は 次<br />
、、、、、、、、、、、、<br />
の 如 くまとめ 直 す。「すなわちヘブライズムの 時 間 は、カイロスの 間 をむすぶものとして 直 線 なので<br />
、、、、、、、<br />
、、、、、 カイロス<br />
あり、 尺 度 として 直 線 であるわけではない。いいかえれば 質 としての〈 時 〉のあいだに 張 られた 緊 張<br />
、、、、、<br />
としての『 直 線 』なのであり、 量 としての実 体 的 な 直 線 であるのではない」 13 。「すなわちヘブライズム<br />
の 時 間 は、 無 限 にのびてゆく 均 質 性 としてのニュートンの 絶 対 時 間 との 対 比 においてあえて 形 象<br />
、、<br />
化 していうならば、『 始 めと 終 わり』(アルケーとテロス)によって 区 切 られた 線 分 としての 時 間 である」<br />
動 に 映 るかもしれないが、「 昼 」と「 夜 」が 前 後 性 に 規 定 されていないのだから「 逆 」ということもあり 得 ないのである。<br />
9<br />
真 木 、 前 掲 書 、177 頁 。<br />
10<br />
同 上 、179 頁 。<br />
11<br />
同 上 、183 頁 。<br />
12<br />
同 上 、160-161 頁 。(CULLMANN, O., Christus und die Zeit, 1946. 前 田 護 郎 訳 『キリストと 時 』 岩 波 書 店 、1954 年 、<br />
36 頁 。)<br />
13<br />
同 上 、161 頁 。<br />
4
14 。 真 木 の「カイロス」という 言 葉 の 使 い 方 には 十 分 注 意 を 払 わねばならない 15 が、それはともかく、<br />
ア ル ケ ー テ ロ ス 、、<br />
ヘブライズムの 時 間 というのは、 要 するに 始 まり= 原 理 と 終 わり= 目 的 という 二 つの 画 期 によって 区<br />
、、<br />
テ ロ ス テ レオ ロジ ー<br />
切 られた 線 分 であるということである。それゆえ、この 時 間 性 は、 目 的 へと 向 かう 目 的 論 的 性 格 をも<br />
つようになる。だから、 時 間 には( 始 まりから 終 わりへという) 方 向 性 が 生 じ、 且 つ 出 来 事 が 一 回 的 で<br />
あるために 可 逆 的 ではない( 物 事 は 取 り 返 しがつかない)。ただし、まさにその 起 源 と 目 的 を 持 つと<br />
いう 性 質 のゆえに、 線 分 的 時 間 のように 単 純 に 数 量 的 であることは 免 れ 得 ている。なぜなら、この 時<br />
間 性 においては、ある 特 権 的 な 時 間 、 特 権 的 な 瞬 間 というものがあり、それゆえ 時 間 が 均 質 でない<br />
からである。<br />
かくしてヘブライズムの 時 間 ( 線 分 的 時 間 )は、 真 木 の「 型 の 変 数 」に 従 えば、「 不 可 逆 的 にして、<br />
質 的 な 時 間 」という 性 格 を 得 る。<br />
d) 直 線 的 な 時 間<br />
かくして 我 々は 三 つの 時 間 性 を 得 たわけであるが、 第 四 の 時 間 である 直 線 的 な 時 間 は、いわば<br />
第 二 ( 円 環 的 )の 時 間 と 第 三 ( 線 分 的 )の 時 間 とを 止 揚 したようなものである。すなわち 直 線 的 な 時<br />
間 性 は、 直 線 と 表 象 されることからも 明 らかなように、 線 分 的 時 間 同 様 可 逆 的 ではない。というのは、<br />
時 間 は 一 つの 方 向 ( 過 去 → 現 在 → 未 来 )を 持 ち、それゆえに 取 り 返 しがつかないためである。ただ<br />
し、 線 分 的 時 間 とは 異 なり、「 始 まり」や「 終 わり」といったような、 特 権 的 時 間 表 象 を、この 時 間 性 は<br />
持 っていない。かくして 時 間 はどの 瞬 間 も 均 質 であり、 等 質 とされた。ために、この 時 間 性 は 質 的 で<br />
はなく、 円 環 的 時 間 性 同 様 量 的 である。かくして、 我 々は 始 まり( 原 因 )もなく 終 わり( 目 的 )もない、<br />
そして 反 復 や 逆 転 もない、 均 質 な 時 間 を 得 たのである。<br />
真 木 はこのような 直 線 的 時 間 こそ、 現 代 社 会 を 生 きる 我 々の 時 間 性 であると 主 張 する。このような<br />
時 間 性 において、 人 間 は 原 因 や 目 的 を 立 てることが 出 来 ないために「 意 味 」を 見 失 い、 且 つ 時 間<br />
的 な 反 復 性 を 失 ったために、 永 遠 の 死 という 観 念 を 抱 くようになった、というのが 真 木 の 診 断 であ<br />
る。<br />
我 々は、 真 木 悠 介 の 比 較 社 会 学 的 時 間 論 を 参 看 してきた。この 作 業 を 通 して、 時 間 の 多 様 な 側<br />
面 、つまり 時 間 経 験 の 多 様 な 様 態 を 見 ることができた。このことは 大 きな 意 義 があったと 思 われるし、<br />
実 際 、 得 られた 社 会 学 的 な 時 間 概 念 の 区 別 は、 後 に 見 てゆくアーレントの 時 間 概 念 を 整 理 する 上<br />
でも、( 少 なくとも 類 推 的 には、であるが) 大 いに 資 するところがあろう。しかし、 同 時 にいくつかの 点<br />
で 不 満 を 禁 じえないのも 事 実 である。<br />
第 一 に、これは 社 会 学 的 な 時 間 論 であり、すなわち、これらの 時 間 性 は 社 会 に 規 定 されていると<br />
いうことであるが、しかし、 上 のような 時 間 の 区 別 は、 本 当 に 社 会 の 区 別 と 同 根 源 的 なのだろうか、と<br />
14<br />
同 上 。<br />
15<br />
真 木 は、クルマンやブルトマンからカイロスの 概 念 を 引 きだしているが、 彼 らの 著 作 は 神 学 的 概 念 に 基 づいてい<br />
るので、パウロの 解 釈 が 影 響 していると 考 えられるためである。 古 典 ギリシア 語 のカイロス 概 念 と、 新 訳 聖 書 における<br />
カイロスの 概 念 が 一 致 するかどうかは、 考 察 の 余 地 がある。<br />
5
いう 点 である。 素 朴 な 一 例 をあげれば、 我 々はなるほど、おそらくは 真 木 の 言 うとおり 直 線 的 な 時 間<br />
を 生 きていると 思 われる。しかし 我 々は 昼 と 夜 のグラデーションを 持 つ 一 日 を 生 き、 四 季 が 連 続 して<br />
巡 る 一 年 を 生 きている。そして、いまだ 世 の 中 から 消 え 去 るには 至 っていないアナログ 時 計 の 形 状<br />
、、<br />
は、「 円 環 」である。 様 々な 時 間 性 が、このように 一 つの 社 会 に「 同 居 」している。 真 木 はこのことを 全<br />
く 意 識 していないとは 言 わない。(さもなければ、 直 線 的 時 間 性 からの「 解 放 」の 可 能 性 を 呈 示 する<br />
ことは 出 来 ないだろう。)しかし、 時 間 性 の「 共 存 」をうまく 説 明 できているとも 言 えないと 思 う。もちろ<br />
ん、 真 木 はこの 説 明 が「 理 念 型 」という 社 会 学 的 方 法 に 則 っているということに 意 識 的 であって、 時<br />
間 意 識 の 類 型 そのものが 方 法 論 的 に 整 備 された 概 念 であって、 実 際 に 存 在 する 時 間 意 識 が 混 淆<br />
的 であることは 真 木 自 身 百 も 承 知 であるだろう。<br />
だから 次 の 問 題 のほうがより 根 本 的 と 言 えるかもしれないが、 第 二 の 問 題 点 として、 時 間 性 の 区<br />
、、<br />
別 を「 社 会 」という 観 点 から 説 明 しているために、ある 時 間 性 が、そもそもなぜ人 間 という 存 在 者 にと<br />
、、、、、、、<br />
って 可 能 であるのか、を 説 明 し 損 ねている、といえるのではないか。 言 いかえれば、 人 間 の 存 在 仕<br />
方 の 可 能 性 そのもののうちに、そしてその 可 能 性 を 規 定 する 人 間 の 条 件 human condition のうちに、<br />
上 記 の 諸 時 間 へと 展 開 しうる 根 源 が 見 出 し 得 るのではないか、ということである。しかし 社 会 学 は―<br />
― 社 会 という 側 面 から 時 間 を 説 明 する 限 りは――そうした 時 間 の 根 源 としての、 人 間 の 存 在 様 態 そ<br />
のものに 迫 ることは、 不 可 能 ではないとしても 困 難 だろう――アーレントならば、そのように 言 うので<br />
はないかと 私 は 考 える。<br />
第 3 節<br />
言 語 に 表 われる 時 間 意 識<br />
社 会 学 的 時 間 論 は、 時 間 の 多 様 性 、 諸 々の 時 間 経 験 を 導 きだしてきた。ところで、 古 典 ギリシア<br />
語 は、その 言 語 のうちに、 様 々な 単 語 というかたちで、すでに 時 間 の 多 様 性 なるものを 備 えていると、<br />
私 は 考 えている。 詳 細 はこれから 見 るとしても、 一 つの 言 語 が 多 様 な 時 間 経 験 を 暗 示 する 単 語 の<br />
数 々を 備 えているという 事 実 は、 非 常 に 示 唆 的 である。というのもシモーヌ・ヴェイユが 言 うように、<br />
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、<br />
「ことばはそれ 自 体 すでに 思 想 を 内 包 している」 16 からである。ただし、 思 想 とは、 言 葉 が 直 観 的 に<br />
掴 みだした 世 界 の 構 造 や 関 係 を、 跡 づけ 的 に 論 理 にもたらしたものである、と 言 ったほうが 幾 分 適<br />
、、、<br />
切 かもしれないが。それはさておき、 一 言 語 を 共 有 する 一 社 会 において、その 言 語 が 複 数 の 時 間<br />
性 を 示 唆 する 単 語 を 含 むことは、 一 つの 社 会 の 形 態 と 一 つの 時 間 意 識 とが 対 応 するという 前 提 に、<br />
単 純 に 反 駁 する。さらに、その 時 間 の 多 様 性 が 言 語 に 現 われているという 点 から、「 社 会 」よりも 根<br />
源 的 な 次 元 に、 人 間 の 条 件 そのものに、 時 間 の 多 様 性 が 根 ざしていることも、 示 唆 される。<br />
たしかにヴェイユが「ことばは 社 会 が 自 然 につくりだしたものであって、 私 たちがある 語 を 考 えだ<br />
すのは 完 全 に 不 可 能 なこと」 17 であると 言 っているように、 言 葉 が 社 会 において 生 まれるのは 事 実 で<br />
ある。しかし「 社 会 がことばを 作 りだす」とここで 言 うときヴェイユが 意 味 しているのは、 社 会 構 造 が 先<br />
立 ち、その 表 出 として 言 語 や 言 葉 が 形 成 されてゆくということではなく、 社 会 、すなわち 複 数 の 人 間<br />
16 WEIL, Simone. 渡 辺 一 民 / 川 村 孝 則 訳 『ヴェーユの 哲 学 講 義 』ちくま 学 芸 文 庫 、1996 年 、103 頁 。ただし、 翻 訳<br />
では 原 文 イタリック 体 に 対 応 する 個 所 を《…》で 囲 むというように 対 応 しているが、 引 用 に 際 し《》を 外 し、 傍 点 を 付 す<br />
ことにした。<br />
17<br />
同 上 。<br />
6
のなかでの 流 通 がなければ 言 語 は 成 立 しえないということであろう。アーレント 風 に 言 い 換 えれば、<br />
ヴェイユの 示 唆 は、 言 語 が 複 数 性 という 人 間 の 条 件 に 基 づくという 事 実 を 指 摘 しているにすぎない<br />
と 思 われる。<br />
もちろん、「 社 会 構 造 が 先 立 ち、その 表 出 として 言 語 や 言 葉 が 形 成 されてゆく」ということが 全 くな<br />
いわけではない。むしろ、そうしたことはよくある、といえるだろう。たとえば 階 級 構 造 の 存 在 が、 言 葉<br />
や 言 語 を 規 定 する、というように。<br />
しかし 私 がここで 問 題 としたいのは、ある 言 葉 のより 根 源 的 な 形 成 要 因 である。たとえば、 蝙 蝠 が<br />
文 明 を 築 いたとしても、 彼 らの 言 語 には「 見 る」という 語 彙 は 生 まれえないだろう。なぜなら 彼 らの 存<br />
在 仕 方 、 存 在 構 成 にはそもそも 原 理 的 に「 見 る」ことが 含 まれないためである。 我 々はたしかに「 蝙<br />
蝠 は( 目 が) 見 えない」ということが 出 来 る。しかしこれは、たまたま「 見 る」ことが 存 在 の 可 能 性 に 含<br />
まれている 人 間 という 存 在 者 が 言 語 を 持 ったために、そのように 言 いうるということに 過 ぎない。 言 い<br />
換 えれば、「 見 えない」というのは「 見 る」ということの 欠 如 態 にすぎず、そもそも「 見 る」ことが 不 可 能<br />
な 存 在 者 にとって、「 見 えない」という 言 い 方 も 不 可 能 である、ということである。そもそも、 蝙 蝠 の 言<br />
語 に「 見 る」に 類 する 語 彙 は 含 まれえない。それは、 我 々に「 超 音 波 で 認 識 する」というような 動 詞 、<br />
語 彙 がないのと 同 様 である。 我 々はせいぜいその 蝙 蝠 の 認 識 法 を「 超 音 波 で 認 識 する」と 説 明 的<br />
に 了 解 するか、あるいは「 聞 く」という 人 間 に 備 わった 存 在 の 可 能 性 から 類 比 的 に 了 解 するかしか<br />
ない。 同 様 に、 我 々は 蝙 蝠 が「( 目 が) 見 えない」ことも 根 源 的 に 理 解 しえない。 我 々は 目 を 瞑 ったと<br />
きに「 見 えない」を 理 解 したような 気 になっているが、それは「 見 る」から 欠 如 的 な 仕 方 で 理 解 された<br />
「 見 えない」に 過 ぎない。そもそも 見 るという 可 能 性 が 備 わっていないことを 理 解 することは、 現 実 に<br />
、、、、、、、<br />
は 不 可 能 である。このような、 言 葉 の 形 成 の 可 能 性 そのものを 規 定 しているような「 事 実 性 」が 存 在<br />
する。<br />
またアーレントも、 労 働 labor と 仕 事 work という 二 つの 人 間 的 活 動 力 の 差 異 が、 理 論 においては<br />
混 同 されながらも、 言 語 においては 別 々の 動 詞 として 保 存 されているという 事 実 を 捉 えて、 次 のよう<br />
に 語 っている。<br />
〔 略 〕 最 初 に 注 目 した 言 語 の 場 合 と 理 論 の 場 合 の 奇 妙 な 食 い 違 いは、 私 たちが 語 る、<br />
ワ ー ル ド ・ オ リ エ ン テ ッ ド<br />
世 界 に 根 拠 をもつ 「 客 観 的 」 言 語 〔world-oriented, “objective” language〕と、 理 解 するために 用<br />
マ ン ・ オ リ エ ン テ ッ ド<br />
いる、 人 間 に 根 拠 をもつ主 観 的 理 論 〔man-oriented, subjective theories〕の 食 い 違 いであること<br />
が 判 る。〔 略 〕そのこと〔= 労 働 と 仕 事 の 違 い〕を 私 たちに 教 えてくれるのは、 理 論 ではなく、 言<br />
語 であり、 言 語 の 基 礎 になっている 基 本 的 な 人 間 の 経 験 である。 18<br />
理 論 というものは、 対 象 を 客 体 化 する 作 業 を 通 して 得 られるものであり、そうして 得 られた 客 体 には<br />
対 象 化 する 人 間 の 主 観 の 作 用 が 入 り 込 んでしまっている。アーレントが「 客 観 」と 名 指 すのは、この<br />
ような 主 観 にとって 客 体 化 されたものではなく、 人 間 の 主 観 とは 独 立 的 に 存 在 する 作 用 のことであ<br />
18 ARENDT, Hannah, The Human Condition, 2nd ed., with an introduction by Margaret CANOVAN, The University of<br />
Chicago Press, Chicago/London, 1998, p.94. ( 志 水 速 雄 訳 『 人 間 の 条 件 』ちくま 学 芸 文 庫 、1994 年 、148 頁 。)<br />
7
る。こういってよければ、 意 識 に 対 するその 働 きかけ 方 は、フロイトの「 無 意 識 」のそれに 似 ている 19 。<br />
無 意 識 もまた 主 観 から 働 きかけることは 出 来 ないが、 主 観 に 対 して 働 きかけてくるものである。そし<br />
てそのような「 客 観 的 」なものが 開 けてくる 現 場 は 経 験 20 であり、 経 験 が 言 語 を 基 礎 づけるのである。<br />
それはさておき、 我 々が 言 語 に 注 目 する 際 、このように 人 間 の 主 観 によっては 変 形 を 加 えられず、<br />
むしろその 言 語 によって 構 築 される 理 論 に「つねにすでに」 影 響 を 及 ぼしているような、そういう 言<br />
語 の 側 面 の 方 をこそ、 見 なければならないだろう 21 セ ン ス<br />
。 語 源 や 言 葉 の 原 的 な 意 味 方 向 を 考 えることの<br />
意 味 はここに 存 する。<br />
我 々が 問 題 としている 時 間 に 関 しても、 時 間 経 験 の 直 観 的 な 表 象 が 言 葉 に 表 れることはあると 考<br />
えられる。つまり 人 間 という 存 在 者 の 可 能 性 に 諸 々の 時 間 経 験 可 能 性 が 含 まれている 為 に、 人 間<br />
の 言 語 に「 時 」に 類 する 語 が 含 まれるのである。それと 比 べるとき、 社 会 構 造 から 生 じた 言 葉 はまだ<br />
根 源 的 ではないと 言 える。 言 い 換 えれば、こういう 場 合 、 思 想 や 社 会 に 限 界 づけられている 言 葉 で<br />
、、、、、、、、、、、、、 、、<br />
はなく、 思 想 や 社 会 を 限 界 づけている言 葉 を 探 らねばならない。<br />
時 間 の「 定 義 」は、ひとつの 学 問 的 な 体 系 秩 序 に 従 って 規 定 される。 我 々がすでに 見 た 社 会 学<br />
的 なそれに 関 して 言 えば、 人 間 と 世 界 を「 社 会 」という 観 点 から 了 解 することを 通 して 生 じるひとつ<br />
の 視 界 において、 時 間 の 経 験 をもその 視 界 に 位 置 付 け、 社 会 学 という 学 問 体 系 にそって 時 間 を 把<br />
捉 しようとする。それに 対 して 時 間 を 表 現 する「 言 葉 」は、 人 間 の 時 間 経 験 そのものを 直 観 的 に 表 現<br />
しようとする。その 直 観 は 言 葉 が 言 語 や 学 問 として 体 系 化 されることを 通 して 忘 却 されるが、 言 葉 と<br />
して 客 観 化 することにより、 保 存 される。それは、あたかも 時 間 と 人 間 との 関 係 が 言 葉 というかたちで<br />
滲 みだしてきているかのような 言 葉 である。 人 間 という 存 在 者 の 可 能 性 と 人 間 の 条 件 との 端 的 な 表<br />
現 であるような、そういう 言 葉 は、 人 間 の 原 的 な 時 間 経 験 のなにほどかを 保 存 していると 考 えられる。<br />
そこでは 人 間 の 存 在 仕 方 そのものが、 言 葉 をして、ある 特 定 の 形 を 取 らしめている。それゆえ 言 葉<br />
において、 人 間 の 存 在 の 仕 方 としての「 時 間 」が 表 現 されている 可 能 性 があると 考 えられる。<br />
19 フロイトにおける「 無 意 識 」や「 記 憶 」がもつ「 客 観 性 」については、 次 の 論 文 を 参 照 されたい。TERDIMAN, Richard,<br />
“Memory in Freud,” in: Susannah RADSTONE and Bill SCHWARZ (eds.), Memory: Histories, Theories, Debates, New<br />
York, Fordham University Press, 2010, pp.93-1<strong>08</strong>.<br />
20 アーレントは 基 礎 経 験 experience, menschliche Grunderfahrung という 現 場 において、 主 観 = 客 観 という 認 識 論 的<br />
な 構 造 (ここでは 理 論 theory と 呼 ばれている)を 超 えようと 試 みている。 主 観 = 客 観 というカント 的 な 枠 組 みを 超 えよ<br />
うという 試 みは 既 にハイデガーやヤスパースにも 見 られた。 例 えばヤスパースは、 存 在 は「 包 括 者 」das Umgreifende<br />
であり、 存 在 は 対 象 化 する 悟 性 には 見 いだせないと 考 えた(JASPERS, Karl. 草 薙 正 夫 訳 『 哲 学 入 門 』 改 版 、 新 潮 文<br />
庫 、2005 年 、38 頁 以 下 参 照 )。また 初 期 ハイデガーも、 主 観 = 客 観 という 分 裂 を 超 えて、「 事 実 的 生 経 験 」faktische<br />
Lebenserfahrung という 場 に 現 われるものを 捉 えようとした(その 試 みは 存 在 論 へと 繋 がってゆく)。Vgl. HEIDEGGER,<br />
Martin, Phänomenologie des religiösen Lebens (Gesamtausgabe, Bd. 60), Vittorio Klostermann: Frankfurt a.M., 1995<br />
etc.<br />
21 エートル<br />
フーコーが 言 語 の「 存 在 être」ということを 言 うときも、 我 々がここで 提 示 したのと 同 じ 問 題 意 識 があると 思 われる。<br />
「 構 造 主 義 は、 記 号 的 な 形 式 (フォルム:forme)の 水 準 にある、 言 語 の 意 味 表 示 的 な 組 織 ないし 構 造 に 分 析 の 眼 を<br />
向 けていた。この 意 味 作 用 の 水 準 において、 言 語 は 意 味 されるものを 現 前 させるために 自 らは 消 え 去 る、 透 明 な 媒<br />
体 のように 考 えられている。それは 他 の 何 か〔を〕 意 味 するために、 自 分 自 身 の 厚 みを 見 えなくさせているのである。<br />
だが、 言 語 は 決 して 透 明 な 媒 体 ではなく、それ 自 身 の 制 度 的 にも 物 質 的 にも 制 約 された『 存 在 』(エートル:être)を<br />
もっている。 明 らかにされねばならないのは、 言 語 が 意 味 するために 見 えなくなっている、この 言 語 の『 存 在 』そのも<br />
のである」( 内 田 隆 三 『ミシェル・フーコー』 講 談 社 現 代 新 書 、1990 年 、123 頁 )。<br />
8
第 4 節 古 典 ギリシア 語 の 四 つの 語 に 見 られる 時 間 意 識<br />
前 節 で 見 てきたような、 言 葉 が 時 間 の 経 験 を 保 存 していることの 実 例 として、 我 々は 古 典 ギリシア<br />
語 の 時 間 概 念 を 眺 めてみたいと 思 う。 古 典 ギリシア 語 には「 時 」を 表 す 語 がいくつかあるが、よく 言<br />
及 されるのは、クロノスとカイロスという 二 つの 時 間 性 である。この 二 つの 概 念 は、 宗 教 や 哲 学 の 文<br />
脈 で、また 最 近 では 精 神 医 学 や 心 理 学 の 文 脈 22 で 問 題 とされることも 多 くなってきた。しかしながら、<br />
管 見 の 限 り 古 典 ギリシア 語 には 四 つの「 時 間 」を 意 味 する(「 時 間 」と 翻 訳 しうる) 語 が 存 し、かつそ<br />
、、、、 、、、、<br />
、、、 、<br />
れぞれが 別 の 意 味 方 向 を 持 っている。それは a) クロノス、b) カイロスの 二 つに、c) ホーラ、d) ア<br />
、、、、<br />
イオーンという 二 つを 加 えた、 四 つである。( 無 論 、 私 はギリシア 語 の 知 識 は 乏 しく、 以 下 で 指 摘 す<br />
る 時 間 を 表 す 語 の 意 味 やその 違 いが 適 切 でない 可 能 性 は 十 分 ある。 私 は 古 代 ギリシア 人 が 四 つ<br />
の 語 を、 私 が 言 うような 意 味 で 用 いたと 強 弁 するわけではない。しかしながら、 四 つの 単 語 がどれも<br />
「 時 」と 訳 されうるという 事 実 が 何 を 示 唆 しているかを 考 えることは 有 意 義 であると 思 われる。)<br />
a)クロノス<br />
クロノス χρόνος は、 漠 然 とした“ 時 間 ”の 観 念 である。 辞 書 によれば、「( 不 定 的 に)《 時 間 》。また<br />
シ ー ズ ン<br />
《ある 特 定 の 時 間 》、《 一 期 間 》、《 季 節 ( 時 期 ) 》、《 時 間 のあいだ》」 23 を 意 味 するとある。このことを 踏<br />
まえれば、クロノスは、ひとつの 漠 然 とした 包 括 的 概 念 、 類 概 念 としての「 時 間 」を 意 味 する 言 葉 で<br />
あると 言 えるだろう。<br />
ところでクロノスという 概 念 には、ギリシャ 神 話 のクロノス 神 のイメージが 付 きまとう。クロノス 神 は 自<br />
分 の 子 供 たちを 端 から 食 べてしまった 神 である。それで、この 神 話 は 時 間 の 暴 力 性 のようなものを<br />
描 いていると 考 えられてきた。ヘシオドスはクロノス 神 を 次 のように 描 く。<br />
ところが 大 いなるクロノスは これらの 子 供 たちを 呑 みこんでしまわれたのだ<br />
その 子 供 たちが 聖 い 母 胎 から 膝 へ 生 まれ 落 ちる 片 端 から。 24<br />
真 木 悠 介 もクロノスのこうした 側 面 ――「みずからの 生 んだ 子 供 を 追 いかけて 食 べてしまう」 25 ――<br />
を 見 て、 時 間 の 消 滅 させる 力 を 読 みとっている。しかし、 時 間 の 神 クロノスと 神 々の 王 クロノスは、 本<br />
来 別 物 であるが、 後 世 に 混 同 されたという 26 。そのため、 神 々の 王 たるクロノスの 描 写 から、 時 間 の<br />
消 滅 的 な 力 が 神 話 に 表 象 されていると 端 的 に 結 論 付 けてよいかは、 疑 問 である。むしろ、 時 間 神 ク<br />
22 たとえば、 斎 藤 環 『 戦 闘 美 少 女 の 精 神 分 析 』ちくま 文 庫 、2006 年 や、 河 合 隼 雄 『 昔 話 の 深 層 』 講 談 社 プラスアル<br />
ファ 文 庫 、1994 年 などは、その 例 である。ただし、 彼 らのクロノス、カイロスの 理 解 が 正 当 であるかどうかは 怪 しい。<br />
23 LIDDELL & SCOTT, A Lexicon Abridged from Liddell and Scott’s Greek-English Lexicon, Oxford U. P., Oxford,<br />
1983, the article on “χρόνος”. ( 拙 訳 、 以 下 この 辞 書 の 項 目 はすべて 同 様 。)<br />
24 HESIODUS, Theogonia, 459-460.( 廣 川 洋 一 訳 『 神 統 記 』 岩 波 文 庫 、1984 年 、60-61 頁 。)<br />
25<br />
真 木 『 時 間 の 比 較 社 会 学 』( 前 掲 )、5 頁 。<br />
26 ジャック・アタリの 指 摘 によれば、 時 間 ( 神 )である Χρόνος(Chronos)と 創 世 神 Κρόνος(Kronos)は 本 来 別 物 である<br />
という(ATTALI, Jacques. 蔵 持 不 三 也 訳 『 時 間 の 歴 史 』 原 書 房 、1986 年 、24 頁 以 下 )。 日 本 語 の 文 字 で、 強 いて 両 者<br />
の 発 音 を 分 けて 表 記 するならば、 時 間 神 Χρόνος は「クフロノス」( 帯 気 音 の ch)、 神 々の 王 たる Κρόνος は「クロノス」<br />
と 表 記 できる。ギリシア 人 にとっては 本 来 別 の 音 のであるが、 彼 らにとっても 似 た 音 であるらしく、 後 代 両 者 は 混 同 さ<br />
れたという。<br />
9
ロノスの 表 象 の 少 なさは、 時 を 意 味 する「クロノス」の 性 格 づけの 少 なさを 裏 付 けていると 言 えるので<br />
はないか。 言 い 換 えれば、 類 概 念 としての「 時 」をそれは 指 しているのではないか。 日 本 語 でも「 時<br />
間 」ではなく「とき」といった 場 合 、 類 概 念 的 な 包 括 性 を 持 っているのと 同 様 であると 思 われる 27 。<br />
b)カイロス<br />
すでに 上 でも 出 てきたカイロス καιρός は、「( 時 間 的 に) 正 しい 時 期 、 行 動 をおこすのに 正 しい 時 、<br />
決 定 的 瞬 間 」 28 を 意 味 するという。ラテン 語 の opportunitas にあたるというから 29 、「 機 会 」「チャンス」と<br />
言 い 換 えることも 出 来 る。 先 ほど「とき」という 日 本 語 も 類 概 念 的 な 包 括 性 を 持 つということについて<br />
とき<br />
若 干 言 及 したが、「 秋 」という 漢 字 をあてるとき、「 秋 」はカイロスに 近 い 意 味 を 持 つ。 神 話 において<br />
擬 人 化 されていて、「のち 彼 は 前 部 には 長 い 頭 髪 があるが、 後 部 は 禿 の 姿 で 彫 刻 に 表 わされてい<br />
る」 30 。 所 謂 西 洋 の 諺 に 言 うところの、「チャンスの 後 ろ 頭 は 禿 げている」というものを 思 い 浮 かべれ<br />
ばよい(だからチャンスは 通 り 過 ぎてからは 捕 まえることができない)。<br />
ところでカイロスの 語 はヒポクラテスが 用 いたことでも 有 名 であり、「ヒポクラテス 文 書 は、 重 症 の 疾<br />
患 においては、 患 者 の 状 態 が 悪 化 に 向 かうか 軽 快 に 向 かうかの 分 かれ 目 の 瞬 間 が 存 在 すると 教 え<br />
ている。 短 期 間 しか 続 かない 症 状 がいくつも 現 れるが、 熟 練 した 医 師 はそれらを 即 座 に 何 であるか<br />
と 同 定 して、ただちに 望 ましい 処 置 を 講 じなければならない。『 技 術 は 長 く、 時 は 短 く、 機 会 (カイロ<br />
ス)は 去 りやすく、 経 験 は 間 違 いを 犯 す』という 有 名 な 金 言 はこのことをいわんとしている」 31 。すなわ<br />
ち、カイロスという 語 は「 二 千 五 百 年 前 には 一 般 医 学 の 用 語 であって、 医 学 的 介 入 のまさにしかる<br />
とき とき<br />
べき 秋 を 意 味 していた〔 略 〕( 例 えば 腫 瘍 が 熟 して 切 開 すべき 秋 である。)」 32 。しかし、エランベルジ<br />
ェによれば、その 用 法 は 姿 を 消 してしまった。その 後 この 語 は 新 約 聖 書 に 現 われ、「 宗 教 的 回 心 に<br />
とき<br />
適 した 秋 のことを 指 す」 33 ものとして 用 いられたという。いずれにしても、カイロスは、そのような 機 会 、<br />
特 権 的 瞬 間 として、クロノスとは 異 なる「 時 」であったことは 間 違 いない。クロノスという 時 に 質 的 な 飛<br />
躍 や 強 度 がないのに 対 して、カイロスには 時 間 を 意 味 付 ける 強 度 がある、とでも 言 えばよいだろう<br />
か。<br />
27 ちなみに 近 年 の 時 間 をめぐる 議 論 においては、クロノスを「 時 計 的 時 間 」と 見 做 す 場 合 が 多 い。しかしこの 傾 向 は、<br />
現 代 の 論 者 が、 後 述 するカイロスという 時 間 性 の 特 殊 性 と 対 置 して、「 特 殊 でない」 時 間 性 、すなわち 我 々が 慣 れ 親<br />
しんでいる 時 間 性 としての 時 計 的 時 間 を、クロノスと 名 指 した、というのが 実 際 のところではないかと 思 われる。たとえ<br />
ば、 河 合 隼 雄 は 次 のように 書 いている。「われわれは 時 計 によって 計 測 しうる 時 間 としてのクロノスと、 時 計 の 針 に 関<br />
係 なく、 心 のなかで 成 就 される 時 としてのカイロスとを 区 別 しなければならない。 時 計 にこだわる 人 は、 重 大 なカイロ<br />
スを 見 失 ってしまう」( 河 合 隼 雄 『 昔 話 の 深 層 ユング 心 理 学 とグリム 童 話 』 講 談 社 プラスアルファ 文 庫 、1994 年 、<br />
165-166 頁 )。たしかに、 真 木 悠 介 が 円 環 的 時 間 としてまとめた 時 間 性 は 数 量 性 を 含 んでおり、その 限 りでは 時 計 的<br />
時 間 とも 呼 びうるのかもしれないが、なによりも 現 実 問 題 として、 当 時 時 計 が 一 般 化 してはいなかったという 点 を 考 え<br />
ても、クロノスを 時 計 的 と 見 做 すことは 過 ちに 繋 がっていると 考 えてよいだろう。 現 代 の 議 論 において、 特 殊 的 な 時<br />
間 性 としてのカイロスをまず 措 定 し、その 後 、そのカイロスと 対 立 する 没 特 殊 的 な 時 間 性 としてのクロノスを、 時 計 的<br />
時 間 性 として 設 定 した、というのが、 彼 らの 概 念 設 定 の 実 状 ではないかと 思 われる。<br />
28 LIDDELL & SCOTT, op.cit., the article on “καιρός”.<br />
29 Ibid.<br />
30<br />
高 津 春 繁 『ギリシア・ローマ 神 話 辞 典 』 岩 波 書 店 、1960 年 、「カイロス」の 項 。<br />
31 とき<br />
ELLENBERGER, Henri F. 中 井 久 雄 訳 「 精 神 療 法 におけるカイロスの 意 味 ―― 理 解 と 真 の 解 釈 の 秋 」 中 井 久 雄 編<br />
訳 『エランベルジェ 著 作 集 2 精 神 医 療 とその 周 辺 』みすず 書 房 、1999 年 、233 頁 。<br />
32<br />
同 上 、243 頁 。<br />
33<br />
同 上 。<br />
10
c)ホーラ(ホーライ)<br />
ホーラ ὥρα とは、「 自 然 法 則 に 規 定 された《 限 定 的 時 間 、 期 間 全 般 》、《ある 季 節 》。 複 数 形 にお<br />
いては《 諸 季 節 》。それ 故 複 数 形 では 季 節 に 依 存 しているものとしてのある 国 の《 気 候 》も〔 意 味 す<br />
、、、<br />
、、<br />
る〕」 34 。いわば 自 然 的 な 時 間 性 であり、 生 命 の 時 間 性 を 表 現 していると 言 っていいかもしれない。<br />
なお、ホーラはラテン 語 でも hora である 35 。ラテン 語 においてはただの「 時 間 」や「 時 計 」を 意 味 して<br />
いて、 現 代 の 西 洋 語 にもこの 単 語 から 派 生 した 語 が 存 在 している 36 。 既 に 見 た 真 木 による 社 会 学 的<br />
時 間 論 の 時 間 性 の 区 別 では、 反 復 的 時 間 や 円 環 的 時 間 という 時 間 性 が、ホーラの 時 間 意 識 に 通<br />
ずるところがあると 言 える。<br />
ホーラが 複 数 形 ホーライ Ὥραι になると、 季 節 の 擬 人 化 としての 女 神 たちとなる。ヘシオドスの『 神<br />
統 記 』をふたたび 見 てみよう。<br />
ホ ー ラ<br />
ゼウスは 輝 かしいテミスを 娶 られた。 彼 女 は 季 節 女 神 たち すなわち<br />
エウノミア<br />
秩 序<br />
デ ィ ケ<br />
正 義<br />
エ イ レ ネ<br />
咲 き 匂 う 平 和 を 生 まれたが<br />
この 方 がたは 死 すべき 身 の 人 間 どもの 仕 事 に 心 を 配 られる。 37<br />
ホーライは「 季 節 女 神 」とはいっても、 春 夏 秋 冬 の 擬 人 化 などではない。それは「 秩 序 」や「 正 義 」、<br />
ヒエロス・ガモス<br />
「 平 和 」といった 概 念 とむしろ 繋 がっているのだ。またゼウスとの 聖 婚 によってホーライを 生 んだテ<br />
ミス 神 は、「 掟 」の 人 格 化 である。たしかに「 一 般 には 彼 女 たちは 植 物 や 花 を 生 長 させる 自 然 の 季 節<br />
の 女 神 とされ」 38 ている、すなわち 自 然 の 季 節 的 運 行 を 司 っているとされているが、「 季 節 の 運 行 と<br />
いう 自 然 の 秩 序 は、 人 間 社 会 の 秩 序 やその 社 会 の 構 成 員 たる 個 々 人 の 行 動 における 秩 序 と、 必<br />
ずしも 整 然 と 区 切 られて 考 えられていなかった」 39 。だからホーライは「 自 然 の 正 しい 移 り 変 りと 人 間<br />
社 会 の 秩 序 の 二 様 の 女 神 と 見 なされている」 40 のである。すなわち、 春 夏 秋 冬 が 正 しく 巡 ること、 自<br />
然 が 正 しく 循 環 することがホーラという 時 間 性 なのであると 言 えよう。そしてそのホーラという 時 間 性<br />
は 自 然 を 通 して 人 間 社 会 にも 反 映 されるのである。<br />
その 点 、ホーラが「 仕 事 」とも 結 びついている(「 人 間 どもの 仕 事 に 心 を 配 られる」)という 事 実 は 興<br />
エ ル ガ<br />
味 深 い。 廣 川 洋 一 は、ヘシオドスにおいてホーライが「『 死 すべき 身 の 人 間 どもの 仕 事 ( 畑 作 物 ・ 農<br />
作 業 )の 保 護 ・ 監 督 に 心 を 配 る』といわれている」 41 ことに 注 目 している。ホーラ( 季 節 )の 時 間 性 は<br />
人 間 の 労 働 ( 農 作 業 )にも 大 きく 影 響 するのだ 42 。ここには、 労 働 の 時 間 性 に 関 する 起 源 的 思 考 が<br />
34 LIDDELL & SCOTT, op.cit., the article on “ὥρα”.<br />
35 Ibid.<br />
36<br />
英 語 hour、フランス 語 heure など。<br />
37 HESIODUS, op.cit., 901-903.( 前 掲 訳 書 、112 頁 。)<br />
38<br />
高 津 春 繁 、 前 掲 書 、「ホーラーたち」の 項 。<br />
39<br />
保 坂 幸 博 『ソクラテスはなぜ 裁 かれたか』 講 談 社 現 代 新 書 、1993 年 、78 頁 。<br />
40<br />
高 津 春 繁 、 同 上 。<br />
41 HESIODUS, op.cit.の 訳 者 による 注 釈 。 前 掲 訳 書 、148 頁 。<br />
エルゴン ポ ノ ス<br />
42<br />
先 取 りになるが、 厳 密 アーレント 的 な 活 動 力 の 区 別 に 従 えば、「 仕 事 」(ἔργον, work)というよりは「 労 働 」(πόνος,<br />
labor)に 当 たる。ARENDT, The Human Condition (ibid.), p.83, note 8 ( 前 掲 訳 書 、201 頁 、 注 8)を 参 照 のこと。とはい<br />
11
見 られる。<br />
d)アイオーン<br />
最 後 はアイオーン αἰών という 時 間 性 である。これについては 記 述 が 少 ないが、 辞 書 によれば<br />
「《 時 間 のあいだや 期 間 》、《 人 生 の 時 間 》、《 人 生 》」という 意 味 が 最 初 にあり、 次 に「(より 長 い 期 間<br />
について)《 一 時 代 》、《 世 代 》、《 時 期 》」とある。 最 後 に「《 無 限 に 長 い 時 間 のあいだ》、《 永 遠 》」とい<br />
う 意 味 が 現 れる 43 。『 新 約 聖 書 ギリシャ 語 小 辞 典 』によれば、「もともと 一 定 の 時 間 的 スペースをあら<br />
わす 語 」 44 である(「もともと」というのは、『 新 約 聖 書 』の 用 法 に 対 して、 古 典 ギリシア 語 の 用 法 を 指 し<br />
ていると 思 われる)。 神 格 化 もされているようだが、 記 述 は 簡 潔 で、「 時 または 永 劫 の 擬 人 神 。 前 5 世<br />
紀 以 後 諸 所 でその 崇 拝 、 祭 礼 があったことが 知 られている」 45 とあるのみである。<br />
一 つ 示 唆 的 な 事 実 は、ホメロスにおける 用 法 では、「 人 生 の 期 間 ( 時 間 )」という 意 味 で 用 いられ<br />
ている 46 ということである。アイオーンの 原 義 はおそらくこの 意 味 、すなわち「 人 生 の 時 間 」という 区 切<br />
られた 時 間 であり、その 意 味 から 一 時 代 、 世 代 というやはり 区 切 られた 時 間 を 意 味 するに 至 ったの<br />
だろうと 考 えられる。 現 代 ではアイオーン(イーオン)は、「 永 遠 」という 意 味 のほうがよく 知 られている<br />
が、この 意 味 もおそらく 上 のような「 区 間 」 的 な 時 間 が 引 き 伸 ばされるようにして 生 まれたのだろう。<br />
上 述 の、「 無 限 に 長 い 時 間 のあいだ」というやや 矛 盾 的 な 言 い 回 しもそのことを 示 唆 している。『 新<br />
約 聖 書 ギリシャ 語 小 辞 典 』によれば、「 永 遠 へと 無 限 につながっている 一 連 の 時 代 の 一 つ、の 意 か<br />
ら 転 じてこのような 時 代 の 無 限 の 連 続 、〔つまり〕 永 遠 」 47 を 意 味 する。<br />
またアイオーンは、コスモス κόσμος やオイクーメネーοἰκουμένη という 語 とも、 共 通 の 類 語 群 に 含<br />
まれている。コスモスとは「 秩 序 ある 宇 宙 、この 世 界 の 物 的 秩 序 、 世 界 中 に 住 んでいる 人 間 、この 世<br />
のもの、この 世 のことがら」 48 という 意 味 での、「 世 界 」である。オイクーメネーは「 居 住 する οἰκῶ」とい<br />
う 動 詞 に 由 来 し、「 人 の 居 住 している 場 所 としての 世 界 」 49 である。それにたいし、アイオーンは「 時<br />
間 の 面 から 見 た 世 界 、 一 つの『 時 代 』、『 世 代 』」 50 を 意 味 する。<br />
とにかくアイオーンは 原 義 としては「いつか 始 まりいつか 終 わる」 生 命 の 時 間 を 指 している。 始 まり<br />
と 終 わりをもつ 時 間 という 点 では 真 木 の 言 う「 線 分 的 時 間 」にも 類 似 していると 言 えるだろう。そして<br />
その 意 味 が「 永 遠 」へと 拡 張 されるとき、それは「 肯 定 的 な 永 遠 」である。すなわち、キリスト 教 の 神<br />
表 象 における「 無 時 間 」としての 神 の 永 遠 、 時 間 の 否 定 としての 永 遠 とは、 異 なる。いわば 線 分 の 始<br />
え、 本 論 において、アーレントにおける 労 働 を 考 える 際 、ヘシオドスが 述 べている 内 容 は 示 唆 的 である。けだし、 労<br />
働 の 時 間 性 はいま 見 たような、 自 然 の 秩 序 との 繋 がりを 抱 えた、ホーラ 的 な 時 間 性 に 通 ずるところがある。その 点 は<br />
後 に 労 働 の 時 間 性 を 考 える 際 に、 重 要 な 観 点 になる。<br />
43 LIDDELL & SCOTT, op.cit., the article on “αἰών”.<br />
44<br />
織 田 昭 編 『 新 約 聖 書 ギリシャ 語 小 辞 典 』 改 訂 第 2 版 、 大 阪 聖 書 学 院 、1965 年 、「αἰών」の 項 。<br />
45<br />
高 津 、 前 掲 書 、「アイオーン」の 項 。<br />
46 AUTENRIETH, Georg, trans. fr. the German by Robert P. KEEP, revised by Isacc FLAGG, A Homeric Dictionary for<br />
Schools and Colleges, New York, Harper & Brothers, 1895, the article on “αἰών”.<br />
47<br />
小 田 編 、 前 掲 書 、 前 掲 の 項 。<br />
48<br />
同 上 。<br />
49<br />
同 上 。なお、オイクーメネーというギリシャ 語 は、 近 代 語 においてはエクメーネ/アネクメーネ Ökumene/<br />
Anökumene という 区 別 、すなわち「 人 間 の 居 住 可 能 地 域 / 不 可 能 地 域 」という 地 理 学 上 の 区 分 として 残 存 してい<br />
る。<br />
12
めと 終 わりが 外 れてしまったような 時 間 であり、その 意 味 では 今 度 は「 直 線 的 時 間 」にも 似 通 ってく<br />
る。<br />
以 上 で、 古 典 ギリシア 語 のいくつかの 語 の 考 察 を 終 える。 上 の 考 察 は 文 献 学 的 な 知 識 にも 殆 ど<br />
依 っていないし、 厳 密 な 考 察 をするような 力 は 私 には 全 くない(もとよりそれは 本 論 の 意 図 するとこ<br />
ろではない)。また、たまたまここではギリシア 語 を 取 り 上 げた 51 が、 同 様 の 事 実 は 多 くの 他 の 言 語 に<br />
も 恐 らく 認 められることであるはずだ。しかし、 私 の 試 みは 単 に 一 つの 言 語 のなかにも 複 数 の 時 間<br />
経 験 が 併 存 することもあるという 一 つの 事 実 を 指 摘 することを 超 えるものではない。ここの 考 察 はこ<br />
れくらいで 終 えておこう。<br />
第 5 節<br />
時 間 一 般 の 形 式<br />
これまでの 分 析 において、ある 一 つの 疑 問 が 生 ずる。すなわち、 時 間 がこうも 多 様 に 経 験 され、<br />
表 象 されるその 一 方 で、なぜそれらに「 時 間 」という 共 通 した 名 前 を 与 え 得 るのか、という 疑 問 だ 52 。<br />
社 会 学 的 な 時 間 の 分 析 にも、ある 言 語 に 含 まれる 複 数 の 時 間 の 表 現 にも、 我 々は 時 間 が 複 数 的<br />
な 仕 方 で 語 られているのを 見 てきた。それらの 経 験 は 多 様 ではあるが、ともに 時 間 と 名 指 しうる 以 上<br />
は、なんらかの 第 三 項 を 共 有 しているはずである。つまり、 時 間 の 一 般 的 な 形 式 的 規 定 があるので<br />
はないか、ということだ。<br />
時 間 を 多 様 性 として 了 解 する 試 みは、 時 間 をひとつの 窮 極 的 な 定 義 で 了 解 することとは、 反 対<br />
の 試 みである。それゆえ、ここで 求 められるのは 時 間 のひとつの 窮 極 的 定 義 を 定 めることではない。<br />
時 間 を 窮 極 的 に 定 義 することと、 時 間 の 一 般 的 形 式 性 を 求 めることは、 同 じではない。 時 間 を 定 義<br />
ポ ジ テ ィ ー フ<br />
するとは、 時 間 を 積 極 的 ( 実 証 的 ) に、 概 念 的 に 把 握 しようと 試 みるものである。それに 対 して 時 間<br />
の 形 式 的 規 定 性 とは、 人 間 の 現 実 が 時 間 という 形 式 においてしか 展 開 しえないという 事 実 をただ<br />
アフィルマティーフ ヴィッセンシャフト<br />
肯 定 的 に 記 述 したときにあらわれるものである。 定 義 とは、ある 概 念 を、ある 学 の 体 系 のな<br />
かに、 確 かな 位 置 をもつものとして 設 置 することである。それにたいし、 我 々は、そのような 体 系 性<br />
への 組 み 込 みを 通 して 行 われるような 定 義 に 際 しても、 遂 行 的 に 承 認 されているような 形 式 的 規 定<br />
性 を 記 述 しようと 試 みる。 時 間 を 窮 極 的 にひとつに 定 義 するということは、ある 体 系 性 において 積 極<br />
的 に 定 義 された 時 間 性 を、ただ 一 つ 在 り 得 る 時 間 性 の 定 義 として 絶 対 化 しようという 試 みであると<br />
言 えるが、そうした 定 義 は、ある 体 系 性 の 内 側 では 妥 当 性 を 持 ち 得 るが、 絶 対 化 し 全 体 化 したとき<br />
にその 妥 当 性 は 失 われる。そうではなくて、 時 間 の 形 式 的 な 規 定 とは、 時 間 というものが 少 なくとも<br />
存 在 するための、 可 能 性 の 条 件 を 表 現 している。<br />
50<br />
同 上 。<br />
51 もちろんギリシア 語 を 取 り 上 げたのも 全 く 故 なしではない。クロノスとカイロスといった 概 念 が 巷 間 もてはやされて<br />
いるという 点 もその 理 由 の 一 つであるし、さらに 上 の 時 間 性 を 表 す 語 が 全 て、「 時 間 の 神 」として 神 話 的 に 表 象 され<br />
ているというのも、 取 り 上 げた 理 由 である。<br />
52 この 疑 問 は、2011 年 6 月 3 日 の 演 習 内 で 行 った 卒 業 論 文 発 表 について、 後 日 最 上 直 紀 氏 ( 東 京 外 国 語 大 学 大<br />
学 院 博 士 後 期 課 程 )により 提 示 されたものである。 本 節 全 体 は、 最 上 氏 の 疑 問 に 対 する 応 答 という 性 格 を 少 なから<br />
ず 有 している。 見 逃 していた 論 点 に 注 意 を 向 けて 頂 いたことにこの 場 を 借 りてお 礼 申 し 上 げたい。<br />
13
、、、 、、、、、、、、、、、、、、、、<br />
形 式 的 には、さしあたり、 時 間 は、 運 動 や 変 化 があるところに 存 在 する。<br />
アリストテレスによれば、「とにかく、 時 間 は 転 化 なしにはありえない。というのは、われわれ 自 らが<br />
自 らの 思 想 をすこしも 転 化 させないとき、あるいはそれが 転 化 していてもこれに 気 づかないでいると<br />
きには、われわれには『 時 がたった』〔 時 間 が 経 過 した〕とは 思 われないからである」 53 。「それゆえ、<br />
時 間 は 運 動 ではないが、 運 動 なしに 存 在 するものでもないこと、 明 白 である」 54 。「ところが、 時 間 は<br />
運 動 そのものではないから、それは 運 動 のなにかであること 必 然 である」 55 。 時 間 は、 転 化 ないし 運<br />
動 、なにかが 変 わることないし 動 くことがあるために、 存 在 する。 逆 に 言 えば、なにも 変 化 せず、 同<br />
一 であるなら、 時 間 があるとは 言 えない。 例 を 挙 げればきりはないが、たとえば 地 球 は 回 転 するため<br />
に 時 間 的 であり、 人 間 は 成 長 し 老 いるために 時 間 的 であり、 食 物 は 腐 敗 して 朽 ちるがゆえに、ない<br />
し 何 かに 食 されて 解 体 され 消 化 されるがゆえに 時 間 的 である。 永 遠 に 自 己 同 一 的 であるものは、<br />
時 間 的 ではない。<br />
ところで、それでは 転 化 するないし 運 動 するとはいったいどういうことを 意 味 するのか、という 問 い<br />
が 生 じるだろう。「 時 間 をわれわれが 認 知 するのは、ただわれわれが 運 動 を、[ 略 ] 前 と 後 で 限 定 し<br />
ながら、 限 定 するときにである。そしてまた、われわれが『 時 がたった』と 言 うのは、われわれが 運 動<br />
における 前 と 後 の 知 覚 をもつときにである」 56 。 運 動 を 認 知 するためには、 前 / 後 という 区 別 がなく<br />
てはならない。それは、 変 化 や 運 動 そのものが、 前 / 後 という 差 異 を 生 み 出 すことに 他 ならないか<br />
らである。かくして、 時 間 は、 差 異 を 生 み 出 してゆくものとしての 変 化 や 運 動 や 生 成 があるところに、<br />
、、、、 、、、、、、、、 、、<br />
存 する。アリストテレスは 最 終 的 に「 時 間 とは[ 略 ] 前 と 後 に関 しての 運 動 の 数 である」と 定 義 するが、<br />
、、<br />
我 々はここで「 数 」として 定 義 することは 避 けようと 思 う( 時 間 を 認 識 的 に 把 握 するのは 数 を 以 てでな<br />
、、、、、、<br />
ければ 困 難 かもしれないが、 時 間 を 経 験 することは 数 を 持 たずとも 可 能 であろう)。<br />
アウグスティヌスにおいて 本 来 的 な 時 間 とは、「あるものが 先 行 しあるものがそれに 遅 れて 経 過 し、<br />
それらが 同 時 に 存 在 することのできぬような 変 化 をもつ 運 動 のことなのである」 57 という。この 形 式 的<br />
な 規 定 は、アリストテレスの 考 えをほとんどそのまま 受 け 継 いでいるが、アウグスティヌスにおいては、<br />
それは 被 造 物 の 存 在 仕 方 に 関 わる。「そのものの 変 化 や 運 動 において 時 間 が 経 過 するというような<br />
被 造 物 がまったく 存 在 しないところに、そもそも 時 間 というものは 存 在 することはできない」 58 。 時 間<br />
的 なものと 対 置 されるのは 永 遠 の 神 であり、「 時 間 は 可 変 性 をとおして 移 行 していくのであるから、<br />
それが 不 可 変 の 永 遠 性 と 等 しく 永 遠 であることはできない」 59 。つまり、 人 間 の 時 間 性 は、 神 の 永 遠<br />
性 と 対 比 的 に 理 解 される。アウグスティヌスにおいては、 可 変 的 な 存 在 者 である 世 界 と 天 使 と 人 間<br />
53 ARISTOTELES, Physica, 218b21-23. ( 出 隆 / 岩 崎 允 胤 訳 『アリストテレス 全 集 3 自 然 学 』 岩 波 書 店 、1968 年 、<br />
168 頁 。 尚 、 亀 甲 括 弧 〔…〕 内 は、 訳 者 による 捕 捉 である。 橋 爪 が 語 句 などを 加 える 場 合 、これと 区 別 するために 大<br />
括 弧 […]で 囲 んで 表 示 するようにする。 以 下 も 本 書 からの 引 用 は 同 様 に 対 応 する。 英 訳 ・ 仏 訳 ・ 原 文 は、with an<br />
English trans. by Philip H. WICKSTEED/ Francis M. CORNFORD, Aristotle IV: Physics I, revised ed., Cambridge/<br />
Massachusetts: Harvard Univ. Press, 1970 [orig. 1929] および texte établi et trad. par Henri CARTERON, Aristote<br />
Physique (I-IV), 7 ème tirage, Paris : Les Belles Lettres, 1990 [orig. 1926] を 参 照 した。)<br />
54 Ibid., 219a1-2. ( 前 掲 訳 書 、169 頁 。)<br />
55 Ibid., 219a9-10. ( 同 上 。)<br />
56 Ibid., 219a22-25. ( 前 掲 訳 書 、170 頁 。)<br />
57 AUGUSTINUS, Aurelius, De civitate Dei, XII, XVI. ( 服 部 英 次 郎 訳 『 神 の 国 』3 巻 、 岩 波 文 庫 、1983 年 、136 頁 。)<br />
58 Ibid. ( 前 掲 訳 書 、138 頁 。)<br />
59 Ibid. ( 同 上 。)<br />
14
とが 創 造 されて 初 めて、 時 間 も 存 在 するようになるのだ。すなわち 可 変 的 な 存 在 者 たちと 時 間 とは<br />
同 根 源 的 である。 神 は 時 間 が 存 在 する 以 前 に 存 在 していたのであるが、その「 以 前 」は 時 間 的 には<br />
理 解 されてはならない( 時 間 的 に 理 解 されてしまったならば、 神 もまた 時 間 的 で 可 変 的 であるという<br />
ことになってしまう)。 永 遠 とは、むしろ 時 間 が 存 在 しないことであり、 神 が 時 間 に 先 行 するというのは、<br />
神 は 時 間 の 存 在 しない 普 遍 の 永 遠 性 を 存 在 していたことを 意 味 しているのだ 60 。 永 遠 性 は、 時 間 の<br />
否 定 として 理 解 される。それは 運 動 = 変 化 の 否 定 である。アリストテレスにあっても、 端 的 には 神 で<br />
あるとはされなかったにせよ、 永 遠 性 はそのように 把 握 されていた。<br />
、、<br />
常 に 存 在 するものどもは、 常 に存 在 するものどもとしてのかぎり、 時 間 のうちには 存 在 しないこ<br />
と、 明 白 である。というのは、それらは、 時 間 によって 包 まれてもおらず、それらのあり 方 も 時 間<br />
によっては 測 られないからである。その 証 拠 は、それら 常 に 存 在 するものどものいずれも 全 く<br />
時 間 によって 作 用 されないということである。そしてこのことは、それらが 時 間 のうちには 存 在 し<br />
ないものであることを 意 味 している。 61<br />
神 学 や 哲 学 の 対 象 は、アリストテレスやアウグスティヌスの 理 解 に 従 って、このような 永 遠 的 なもの<br />
でありつづけた。 時 間 的 なものは 現 象 にすぎず、 本 質 や 存 在 そのものは 無 時 間 的 で 不 変 的 なもの<br />
であるという 信 念 が、 哲 学 者 たちの 理 解 を 導 いていた。 人 間 のあらゆる 行 為 は、 彼 らにおいては、<br />
究 極 的 には 永 遠 なるものを 観 想 する「 観 想 的 生 活 」のために 捧 げられるべきものであったのだった。<br />
こうした 傾 向 は、ヘーゲルまで 共 有 されていた。ただしヘーゲルに 関 して 言 えば、そうした 無 時 間 的<br />
な 究 極 性 を 了 解 する 行 為 は、 時 間 的 に 理 解 されていたのであるが。 彼 において 永 遠 性 の 了 解 は、<br />
精 神 が 自 己 発 展 を 遂 げる 弁 証 法 的 な 過 程 として 理 解 された。その 過 程 そのものは 時 間 的 であり 歴<br />
、、、、、、、、、<br />
史 的 であったが、 過 程 はひとつの 過 程 として目 的 論 的 な 時 間 性 を 備 え、 時 間 の 終 わりにおいて 永<br />
遠 性 が 把 握 されるという 次 第 であった。 彼 の「 概 念 的 に 把 握 すること begreifen」は、 永 遠 性 を 把 握<br />
モ メ ン ト アウフヘーブング<br />
する 営 みに「 否 定 」と「 否 定 の 否 定 」という 契 機 ( 止 揚 )を 持 たせることを 通 して、 時 間 的 で 有 限 な<br />
人 間 と 無 時 間 的 で 無 限 な 絶 対 精 神 とが 繋 がる 可 能 性 を、 歴 史 というかたちで 確 保 するための、 方<br />
法 であった。いずれにしても、 究 極 的 には「 時 間 的 な temporal」ものは、 不 変 化 的 で 永 遠 の 存 在 に<br />
比 して 価 値 のないものであった。 変 化 する、「 無 常 な temporal」ものはそれゆえ 哲 学 の 対 象 ではな<br />
かった。<br />
しかし、ハイデガーによって、 究 極 的 には 無 時 間 的 なものに 導 かれているこの 哲 学 は、 峻 拒 され<br />
る。ハイデガーは『 宗 教 現 象 学 入 門 』という 講 義 において、 人 間 的 現 存 在 の 事 実 的 生 経 験 を 了 解<br />
するための 方 法 を 見 出 そうとしていたが、この 事 実 的 ということの 意 味 は、「〈 歴 史 的 なもの(das<br />
Historische)〉という 概 念 からのみ 理 解 できるようになる」 62 。そして「〈 歴 史 的 〉ということばはここでは<br />
60 「まことに 神 は、それらの 被 造 物 なくしていかなる 時 間 も 存 在 しないのではあるけれども、それらのものの 前 に 存<br />
在 されたのであって、 移 行 する 時 間 の 間 隔 によってそれらのものに 先 んじられるわけでなく、 永 遠 性 に 留 まられるこ<br />
とによって 先 んじられるのである」(Ibid. 〔 前 掲 訳 書 、139 頁 〕)。<br />
61 ARISTOTELES, op.cit., 221b3-5. ( 前 掲 訳 書 、178 頁 。)<br />
62 HEIDEGGER, Phänomenologie des religiösen Lebens (Gesamtausgabe, Bd. 60) (ebenda), S.9. 但 し、この 文 章 は、<br />
15
〈 生 成 すること(Werden)〉、〈 発 生 すること(Entstehen)〉、〈 時 間 の 内 で 経 過 すること(in der Zeit<br />
Verlaufen)〉を 意 味 する」 63 と 述 べていた。この 時 点 のハイデガーにとって 哲 学 ( 現 象 学 )は、 時 間 的<br />
なもの(ハイデガーの 言 い 方 では 歴 史 的 なもの)を 了 解 するためのものであった。<br />
ところで、 哲 学 史 において 時 間 が 問 題 となるさい、「 時 間 は、それ 自 身 独 立 の 存 在 ではなく、 出<br />
来 事 に 還 元 されるべきものである」 64 のか、「それ 自 身 独 立 の 存 在 概 念 である」 65 のかということが 問<br />
われてきた。 換 言 すれば、 時 間 は 人 間 の 経 験 にすぎないのか、それとも 時 間 は 実 在 するのか、とい<br />
うことである。 我 々は 時 間 が 運 動 や 変 化 から 生 じるということを 見 てきた。たしかに、 変 化 や 運 動 は<br />
人 間 が 存 在 しなくとも 存 在 するはずである。 宇 宙 は 人 間 が 生 じるまえから 存 在 し、 展 開 し、 変 化 して<br />
きたはずだ。そしてその 展 開 は 時 間 的 であったはずである。ところが、そうした 変 化 や 展 開 は、 人 間<br />
がそれをなんらかの 様 式 で 経 験 しないかぎりは、 時 間 として 経 験 されることはない。 時 間 は、 意 識 存<br />
在 としての 人 間 によって 経 験 されないかぎり、 存 在 しないのである。 時 間 は、 変 化 や 運 動 の 経 験 とし<br />
て 存 在 する 66 。<br />
、、<br />
逆 に 言 えば、 時 間 は、つねにすでに 時 間 の 経 験 である。いいかえれば、それは 厳 密 には 時 間 そ<br />
のものではない。 時 間 としての 時 間 を 人 間 は 経 験 することはできない。 時 間 は、 人 間 にとって、 変 化<br />
や 運 動 の 経 験 として、つねになんらかのかたちで 様 態 化 されている。つまりそれは 様 態 化 された 時<br />
間 の 経 験 である。それはちょうど 存 在 そのものは 存 在 せず、 存 在 者 のみが 存 在 するのと 似 ている。<br />
「 時 間 そのもの Zeit an sich」は 物 自 体 Ding an sich のように 接 近 できない。 人 間 にとっての 時 間 は、<br />
つねにすでに、 経 験 された 時 間 である。<br />
時 間 は、 人 間 存 在 にとってのみ 開 明 される。その 点 で、 人 間 存 在 とは、 時 間 がそこで 明 らかにな<br />
る「そこ Da」である。ハイデガーにとって 人 間 は、そこで 存 在 の 問 題 が 開 示 される「そこ」としての 現<br />
存 在 =そこ 存 在 Dasein であったが、それと 同 様 に、 人 間 は 時 間 の 問 題 がそこであきらかになる 現<br />
存 在 であると 言 える 67 。 時 間 は 実 在 するのか/ 時 間 は 人 間 の 経 験 なのか、という 両 命 題 は、それゆ<br />
え、 対 立 的 に 捉 えられるべきではなくて、 弁 証 法 的 に 捉 えられるべきであろう。 両 方 とも 正 しく、 両 方<br />
とも 誤 りである。すなわち、 時 間 はたしかに 変 化 や 生 成 や 運 動 が 時 間 的 に 起 こるという 意 味 では 人<br />
間 が 存 在 しなくとも 存 在 するが、 時 間 が 問 題 化 されるとき、その 時 間 はつねにすでに 人 間 に 経 験 さ<br />
氣 多 雅 子 「 事 実 と 事 実 性 ――ハイデッガーとアーレントを 中 心 に――」『 京 都 大 學 文 學 部 研 究 紀 要 』45 号 、 京 都 大<br />
學 大 學 院 文 學 研 究 科 ・ 文 學 部 、2006 年 、12 頁 に 引 用 されており、 訳 文 もそこから 取 った。<br />
63 Ebenda, S.32. 訳 文 は 気 多 、 前 掲 論 文 、 同 頁 から 引 用 。<br />
64<br />
荒 川 幾 男 他 編 『 哲 学 辞 典 』 平 凡 社 、1971 年 、「 時 間 」の 項 。<br />
65<br />
同 上 。<br />
66 アーレントは「 人 間 が 存 在 しなくても、 運 動 や 変 化 は 存 在 しうるであろう。しかし、 時 間 は 存 在 しないだろう」と 述 べ<br />
ている(ARENDT, Hannah, The Life of the Mind: Two/ Willing, San Diego/ New York/ London: Harcourt Inc., 1978,<br />
p.42 〔 佐 藤 和 夫 訳 『 精 神 の 生 活 下 第 二 部 意 志 』 岩 波 書 店 、1994 年 、52 頁 〕)。<br />
67 ハイデガーが 次 のように 述 べる 時 、このことを 意 味 していたのである。「 確 かに 人 間 がいなかった 時 もあった。だが<br />
厳 密 に 考 えれば、 人 間 がいたことのない 時 というものはない。 時 間 は 人 間 があるかぎりでのみ 時 熟 する〔sich zeitigt〕<br />
からである。 人 間 がいなかった 時 というものはない。それは 人 間 が 永 遠 このかた 永 遠 にわたってあるからではなく、<br />
むしろ 時 間 は 永 遠 ではないから、 時 間 は 人 間 的 = 歴 史 的 現 存 在 としてそのつど 或 る 一 時 時 熟 するのみだからであ<br />
る」(HEIDEGGER, Martin, Einführung in die Metaphysik (Gesamtausgabe Bd.40), Vittorio Klostermann: Frankfurt a.M.,<br />
1983, S.90 〔 川 原 栄 峰 訳 『 形 而 上 学 入 門 』 平 凡 社 ライブラリー、1994 年 、142-143 頁 〕)。<br />
16
れた 時 間 としての 時 間 であって、 時 間 そのものではない。ここでは、 時 間 という 言 葉 で、 時 間 そのも<br />
のではなく、 経 験 された 時 間 を 意 味 することにする。<br />
形 式 的 に 把 捉 された 時 間 は、 変 化 や 運 動 の 経 験 として、 永 遠 不 変 に 存 在 する 神 を 措 いて、あら<br />
ゆる 存 在 者 に 妥 当 するものであると 言 える。それゆえ 人 間 の 認 識 や 発 展 、 生 存 、あるいは 学 問 も、<br />
時 間 的 に 行 われる。 人 間 の 行 為 は 遍 く 時 間 的 であり、 時 間 のかからない 行 為 は 存 在 しないのだ。<br />
それはなぜかといえば、 行 為 とは 自 らで 自 らを 差 異 化 してゆくことであり、つまり 自 発 的 に 変 化 し 運<br />
動 することである。そして 差 異 化 = 変 化 はそれ 自 体 変 化 の 源 泉 であり、 時 間 的 にしか 起 こり 得 ない<br />
ものであるからだ。ベルクソンは「 時 間 はすべてのものがいっぺんに 与 えられることを 妨 げているも<br />
のである。 時 間 は 遅 れさせる、というよりもむしろその 遅 延 である」 68 と 言 うが、それは 人 間 のあらゆる<br />
営 みは 時 間 的 にしか 展 開 できないということを 意 味 している( 人 間 の 営 みは、「 光 あれ、すると 光 が<br />
あった」というようなものではない)。むしろ、 人 間 がなにかを 達 成 するためには「 営 み」というかたち<br />
を 取 らねばならないことこそが、 人 間 を 時 間 的 にしている。<br />
このことを 逆 向 きに 表 現 すれば、 人 間 は 行 為 において 時 間 を 生 み 出 してゆくとも 言 える。 人 間 は<br />
行 為 において「 自 らを 時 間 化 する sich zeitigen」 69 。 行 為 は 人 間 を 時 間 化 する。そして、 行 為 の 様 態<br />
が 時 間 の 様 態 を 決 定 してゆく。<br />
こうして 見 てきたように、 人 間 は 二 重 の 意 味 で 時 間 的 temporal である。 第 一 に、 人 間 は 永 遠 不 変<br />
の 神 とは 異 なり、 変 化 にさらされた 無 常 な temporal 存 在 者 として、 時 間 的 に 存 在 するという 点 にお<br />
いてそうである。それゆえに、 人 間 の 行 為 も 時 間 的 であり、 人 間 は 行 為 において 自 らを 時 間 化 する<br />
のである。 第 二 に、そのような 時 間 は、 人 間 が 経 験 することを 通 して 初 めて 開 示 される。 時 間 の 存 在<br />
が 明 らかになるのは、 人 間 においてである。 時 間 の 存 在 は 人 間 においてはじめて 明 らかになるの<br />
だが、そうした 時 間 はつねにすでに「 経 験 された 時 間 」としての 時 間 であって、 時 間 そのものではな<br />
い。このような 時 間 の 生 起 、すなわち 人 間 が 行 為 を 時 間 的 に 展 開 し、 時 間 的 に 展 開 する 行 為 にお<br />
いて 時 間 を 経 験 することを、 時 間 性 temporality と 名 づける。<br />
ホ モ ・ テ ン ポ ラ リ ス 、、、、、、<br />
アウグスティヌスは、このような 人 間 を「 時 間 的 人 間 」と 呼 んだ。「 神 は〔 略 〕 時 間 的 な 人 間<br />
〔hominem temporalem〕を 時 間 のうちにつくられたのであって、その 人 間 の 以 前 にはだれひとり 人<br />
68 BERGSON, Henri, « Le possible et le réel », dans : La Pensée et le mouvant : Essais et conferences, 4 ème éd., Paris:<br />
Librairie Félix Alcan, 1934, p.118. (「 可 能 性 と 事 象 性 」 河 野 与 一 訳 『 思 想 と 動 くもの』 岩 波 文 庫 、1998 年 、141 頁 。)<br />
69 「 自 らを 時 間 化 する sich zeitigen」は、ハイデガーの 表 現 であるが、 本 来 は 人 間 が 主 語 にはならない。 本 来 は、 自<br />
ら 時 間 化 する、ないし 時 熟 するのは 時 間 そのものである。 時 間 は 存 在 者 のように 存 在 するわけではないから、 時 間<br />
が「ある sein」とは 言 うことはできない。 時 間 は 人 間 において 自 ら 時 間 化 する= 時 熟 するsich zeitigt のだ( 注 67 参 照 )。<br />
しかし、 時 間 は 人 間 においてのみ 時 間 化 するのであれば、 時 間 の 本 質 は 人 間 であるということもできる(「つまり、た<br />
んに『 時 間 の 内 に』 生 きているだけでなく、 本 質 的 に 時 間 的 である 被 造 物 は、いわば、 時 間 の 本 質 なのである」<br />
〔ARENDT, The Life of the Mind: Two/ Willing (op.cit.), p.1<strong>08</strong> ( 前 掲 訳 書 、132 頁 )〕)。アーレントは「 人 間 はただ 時 間<br />
、、、、、<br />
的 である〔temporal〕のみではない。 人 間 が 時 間 なのである」(Ibid., p.42 〔 前 掲 訳 書 、52 頁 〕)と 述 べているが、つま<br />
りそれは 人 間 自 身 が 時 間 として 存 在 を 展 開 してゆくことを 意 味 する。だからここでは 敢 えてわざと、 時 間 化 の 主 語 を<br />
人 間 とした。<br />
17
間 は 存 在 しなかった」( 傍 点 は 橋 爪 ) 70 。 人 間 という 存 在 者 は 時 間 (のなか)を 生 きている。<br />
アーレントは、 人 間 が 時 間 的 であることをよく 認 識 していた。 彼 女 は 人 間 の 生 きる 現 実 を 神 や 絶<br />
対 精 神 という 永 遠 的 なものとの 関 係 において 考 えることはしない。 人 間 的 実 存 は 時 間 的 である。 人<br />
間 的 実 存 そのものも、それを 取 り 囲 む 世 界 も、 変 化 し、 運 動 する。そのようなものとしての 人 間 的 実<br />
存 を 理 解 するには、 時 間 的 なものを 理 解 するような 方 法 というものがなくてはならない。なぜなら 人<br />
間 は、すくなくともその 存 在 の 始 めから 終 わりまで、 一 貫 して 時 間 的 でありつづけるからだ。アーレ<br />
ホ モ ・ テ ン ポ ラ リ ス<br />
ントの 政 治 学 は、まさにこのような 時 間 的 な 人 間 homo temporalis を、 時 間 において、 理 解 しようとい<br />
う 試 みなのである。それは 単 に「 神 なき 時 代 の 人 間 」を 理 解 するというだけではない。 人 間 は 時 間 的<br />
にしか 存 在 できないという 人 間 の 条 件 からすれば、 人 間 を 時 間 的 に 了 解 するということが 人 間 存 在<br />
と 人 間 的 行 為 を 根 底 的 に 了 解 する 上 での 要 であるということは、 明 らかであろう。<br />
今 や、「アーレントの 時 間 論 という 問 題 を 問 うことに 意 味 はあるのか」という 問 いには、 完 全 に 答 え<br />
られただろう。たしかにアーレントの 時 間 論 という 問 題 を 考 究 するさい、たしかに 彼 女 は「 時 間 論 」と<br />
題 された 本 をものしていないが、それに 関 してはアーレント 自 身 が、「カントの 政 治 哲 学 」について<br />
述 べた 言 葉 71 をパラフレーズしてこう 述 べることができるだろう。すなわち、「そもそもアーレントの 時<br />
間 論 なるものがあるとすれば、 私 たちはそれを 彼 女 の 著 作 全 体 の 内 に 見 出 せるはずだ」、と。<br />
第 6 節 時 間 の 複 数 性<br />
我 々は、 社 会 学 的 時 間 論 の 分 析 において 複 数 の 時 間 が 社 会 によって 異 なる 発 源 の 仕 方 をして<br />
いるのを 見 たが、 時 間 が 社 会 と 同 根 源 的 であるという 点 に 関 しては、 一 例 として 古 典 ギリシア 語 を 見<br />
ることによって、 一 つの 言 語 にも 複 数 の 時 間 性 が 併 存 していることを 示 して 反 駁 した。さらに、 時 間<br />
の 形 式 的 規 定 性 を 見 ることによって、 人 間 の 行 為 そのものから 時 間 が 発 源 していること――つまり<br />
人 間 は 行 為 を 通 して 自 らを 時 間 化 すること――を 見 てきた。つまり 時 間 は 行 為 に 由 来 するのであり、<br />
人 間 の 行 為 を 何 処 に 向 けて 投 企 するかによって、 時 間 経 験 の 様 態 そのものが 変 わるのである。そ<br />
れは 一 つの 社 会 の 内 部 においてもそうであって、 一 つの 社 会 のなかにも 時 間 は 併 存 していると 考<br />
えるべきである。 真 木 が 四 つの 時 間 意 識 の 類 型 を、あくまで「 理 念 型 」としてしか 描 けなかったのも、<br />
同 様 の 理 由 によるだろう。<br />
、、、、、、、<br />
今 村 仁 司 は、 上 で 指 摘 したような 時 間 が 併 存 するという 事 態 を、 既 存 の 哲 学 や 歴 史 学 は 見 逃 し<br />
てきたと(アルチュセールに 依 りつつ) 論 ずる。「 歴 史 のなかの 社 会 構 造 は、 複 数 の 領 域 から 構 成 さ<br />
れている( 政 治 、 経 済 、 文 化 の 三 層 構 造 、さらに 各 構 造 が 階 層 的 になっている) 72 」。<br />
これらの 領 域 はそれぞれ 独 自 の 運 動 リズムをもって 動 くのであり、けっして 大 文 字 の 唯 一 の<br />
時 間 なるものに 還 元 されることはありえない。 政 治 領 域 には、 政 治 に 特 有 の 時 間 性 があり、 経<br />
済 には 経 済 独 自 の 時 間 性 があり、 文 化 とイデオロギーにはそれ 独 特 の 時 間 性 がある、 等 々。<br />
70 AUGUSTINUS, op.cit., XII, XV. ( 前 掲 訳 書 、132 頁 。)<br />
71 ARENDT, Hannah. ロナルド・ベイナー 編 、 仲 正 昌 樹 訳 『 完 訳 カント 政 治 哲 学 講 義 録 』 明 月 堂 書 店 、2009 年 、59<br />
頁 。<br />
72<br />
今 村 仁 司 『マルクス 入 門 』ちくま 新 書 、2005 年 、53 頁 。<br />
18
複 数 の 時 間 性 は、 等 質 でないから、 互 いにずれている。 時 間 論 の 観 点 からいえば、 経 済 の<br />
運 動 のリズムは 政 治 のリズムを 決 定 しないし、ましてやイデオロギーのリズムを 決 定 しない。 社<br />
会 と 歴 史 の 科 学 的 認 識 は、 各 領 域 自 体 が 複 数 の 時 間 性 をもつことを 認 識 することから 始 めて<br />
(たとえば 経 済 構 造 は、 労 働 時 間 、 生 産 時 間 、 生 産 期 間 、 回 転 期 間 、 等 々のように 複 合 時 間 を<br />
もっている)、ついで 各 領 域 の 独 自 の 運 動 様 式 を 確 認 しつつ、 複 数 の 領 域 の 時 間 的 連 関 、す<br />
なわち 異 質 時 間 相 互 の 分 節 化 と 編 成 を 分 析 するのでなくてはならない。〔ゴシック 体 での 強 調 は<br />
今 村 〕 73<br />
このような 時 間 の 複 数 性 、ないし 時 間 の 多 層 性 は、 歴 史 学 にも 知 られつつあるようである。つまり 近<br />
代 的 歴 史 学 は 発 展 的 な 像 を 持 つ 線 分 的 時 間 を 前 提 しており、それゆえに 政 治 的 出 来 事 や 思 想 的<br />
著 作 のような、 発 展 をリードする 個 別 事 象 に 焦 点 を 合 わせてきたが、「 歴 史 のより 基 底 にあって 人 と<br />
社 会 を 枠 づけている 構 造 的 要 素 」 74 や、「 歴 史 なき」 非 ヨーロッパ 世 界 、 非 近 代 的 要 素 へと 眼 を 向 け<br />
るとき、「 歴 史 認 識 における 時 間 は、 単 一 の 短 期 的 なものではすまなくなってくる」 75 。それゆえ 歴 史<br />
的 時 間 の 多 層 性 が 認 識 されなければならない。すなわち、「 人 や 社 会 の 歴 史 からすればほとんど<br />
動 かざるものにすらみえる 非 常 に 長 期 的 な 地 理 的 時 間 から、ゆるやかな 変 動 を 示 す 社 会 諸 構 造 の<br />
歴 史 や 心 性 の 歴 史 といった 中 間 的 な 時 間 をへて、 日 々の 事 件 における 短 期 的 な 時 間 に 至 るまで、<br />
歴 史 認 識 における 時 間 枠 組 の 設 定 は 多 様 であるべきことが 認 識 された」 76 。このように、 歴 史 もまた<br />
複 数 の 時 間 性 の 複 合 として 了 解 されつつある。<br />
、、、、、<br />
我 々は、 上 のような 立 場 を 受 け 入 れ、アーレントにもそのような 時 間 の 複 合 を 見 ようとする。ただし<br />
、、 、、<br />
我 々は、そのような 時 間 が 政 治 領 域 や 経 済 領 域 から 発 源 するとは 考 えない。すでに 見 たように、 人<br />
間 の 時 間 は、 人 間 の 行 為 から 発 源 する。アーレントは 人 間 の 行 為 を 活 動 力 activity, Tätigkeit と 名<br />
づけている。つまり、 我 々は 諸 々の 時 間 性 は 人 間 の 活 動 力 から 発 源 すると 考 える。そしてそのよう<br />
、、、、、、、、、、、、<br />
に 捉 えたとき、アーレントの 人 間 の 活 動 力 に 関 する 議 論 は 必 然 的 に 時 間 論 を 含 みこむこととなる。<br />
なぜなら、 時 間 は、 存 在 論 的 にいえば 人 間 の 活 動 力 (と 人 間 の 条 件 )から 発 源 するからである。そし<br />
てそのような 時 間 論 は、 人 間 の 条 件 と 活 動 力 が 単 一 ではないために、 単 一 の 時 間 を 論 じる 時 間 論<br />
、、、 、、、、、、、、、、、、、、、、、、 、、、、、、、、、、、<br />
を 棄 却 する。かくして 我 々は、 人 間 の 条 件 と 活 動 力 が 複 数 であるために、 複 数 の 時 間 性 を 論 じるこ<br />
、、、、<br />
とになる。さらに、この 議 論 がおそらく 歴 史 学 にとっても 新 しい 点 は、アーレントにおける 労 働 と 仕 事<br />
と 活 動 、そして 精 神 的 活 動 力 という 区 別 が 導 入 される 点 である。 時 間 性 の 区 別 は、 単 純 に「 基 層 に<br />
ある 時 間 」や「より 長 期 的 時 間 」といったような 分 類 ではなく、 活 動 力 そのものからなされることになる。<br />
もちろん、そうした 区 別 も 結 果 的 には、「 長 期 的 時 間 」や「 基 層 的 時 間 」として 理 解 しうるようなものと<br />
して 了 解 可 能 ではある。しかし 活 動 力 そのものを 時 間 化 として 捉 えることに、 我 々の 議 論 の 新 しさが<br />
幾 分 かあろうと 思 う。そして、このような 時 間 の 複 数 性 、 複 合 性 こそ、アーレントの 時 間 論 のもっとも<br />
独 創 的 な 点 のひとつであると、 我 々は 考 えるのである。<br />
73<br />
74<br />
75<br />
76<br />
同 上 、53-54 頁 。<br />
福 井 憲 彦 「 歴 史 的 時 間 」 今 村 仁 司 編 『 現 代 思 想 を 読 む 事 典 』 講 談 社 現 代 新 書 、1988 年 。<br />
同 上 。<br />
同 上 。<br />
19
第 二 章 アーレント 政 治 学 の 基 礎 的 な 概 念 範 疇<br />
レーベン<br />
時 間 とは 生 活 である。<br />
――ミヒャエル・エンデ『モモ』<br />
第 7 節<br />
、、、、<br />
アーレントの「 政 治 学 」――「 形 而 上 学 」に 裏 打 ちされたものとして<br />
我 々はアーレントの 時 間 論 を 問 題 にするわけであるが、その 時 間 論 は 彼 女 の 政 治 学 の 全 体 と 連<br />
関 し、なかでも 人 間 存 在 や 人 間 的 活 動 力 の 彼 女 の 理 解 の 仕 方 と 深 く 結 びついている。それゆえま<br />
、、、、、、<br />
ずアーレントの 哲 学 的 な、あるいは 形 而 上 学 的 な、 基 本 的 概 念 範 疇 を 参 看 しよう。<br />
アーレントの「 政 治 学 」における 時 間 論 を 我 々は 見 るのだが、その 概 念 範 疇 の 一 番 基 礎 として、<br />
「 政 治 学 」という 範 疇 の 意 味 から 出 発 する 必 要 があろう。というのも、 彼 女 が 自 らの 理 論 を「 政 治 学 」<br />
と 呼 んでいること 自 体 が、 彼 女 の 政 治 学 に 対 する 誤 解 を 招 いている 側 面 があることは 否 めないと 思<br />
われるからだ。 彼 女 の 学 問 を「 政 治 学 」と 呼 ぶのは、 実 際 彼 女 自 身 である。「 自 分 が『 哲 学 者 』である<br />
とか、カントが 皮 肉 抜 きで 職 業 思 想 家 (Denker von Gewerbe)と 呼 んだ 者 のうちに 数 えられるとか、<br />
ポリティカル・セオリー」を<br />
私 はそういう 主 張 もしなければそういう 野 心 もない」 77 ポリティカル・サイエンス<br />
彼 女 はと 述 べて、「 政 治 学 と 政 治 理 論<br />
、、、<br />
「 比 較 的 安 心 な 分 野 」と 呼 んでいる 78 。 彼 女 の 主 要 な 問 題 関 心 はたしかに 政 治 学 であるし、それを<br />
否 定 することは 実 際 その 著 作 を 読 み 損 ねることに 違 いない。 勿 論 ここで 彼 女 の 関 心 が 政 治 学 でな<br />
、、、、、、、、<br />
かったと 主 張 するつもりはない。しかしその 著 作 を 精 密 に 読 むならば、 彼 女 が、 狭 義 の 政 治 学 がそ<br />
、、<br />
、、、、<br />
うするように哲 学 や 形 而 上 学 を 無 視 するということはせず、むしろそれらと 正 面 から 取 り 組 み、その<br />
対 決 において 自 身 の 理 論 を 組 み 上 げているということに 気 づくであろう。<br />
このような 問 題 を 考 える 上 で 示 唆 的 な 一 節 が、『 人 間 の 条 件 』のなかに 見 出 せる。すなわち、 労<br />
働 ・ 仕 事 ・ 活 動 という「 三 つの 活 動 力 とそれに 対 応 する 諸 条 件 は、すべて 人 間 存 在 の 最 も 一 般 的 な<br />
条 件 である 生 と 死 〔birth and death〕、 出 生 と 必 死 性 〔79〕 〔natality and mortality〕に 深 く 結 びついてい<br />
る。〔 略 〕 創 始 〔initiative〕という 点 では、 活 動 の 要 素 、したがって 出 生 の 要 素 は、すべての 人 間 の 活<br />
動 力 に 含 まれているものである。その 上 、 活 動 がすぐれて 政 治 的 な 活 動 力 である 以 上 、 必 死 性 で<br />
77 ARENDT, Hannah, The Life of the Mind: One/Thinking, Harcourt Inc., San Diego/New York/London, 1978, p.3.<br />
( 佐 藤 和 夫 訳 『 精 神 の 生 活 上 第 一 部 思 考 』 岩 波 書 店 、1994 年 、5 頁 。)<br />
78 Ibid. ( 同 上 。)<br />
79 ここで「 必 死 性 」としたのは、mortality である。 志 水 訳 では「 可 死 性 」となっているが、 可 死 性 とした 場 合 、 文 字 通 り<br />
「 死 ぬことが 可 能 である」ということを 意 味 してしまうと 思 われる。この mortalityという 表 現 は、ラテン 語 の mortalis、ギリ<br />
シア 語 の βροτός という 形 容 詞 の 訳 語 mortal の、 名 詞 形 にあたる。その 古 典 語 の 形 容 詞 の 意 味 の 中 心 は「 死 に 得 る」<br />
という 可 能 性 よりは、「 死 なねばならない」という 不 可 避 性 にあり、この 死 の 不 可 避 性 が 古 代 ギリシア 人 やローマ 人 の<br />
哲 学 や 思 考 の 基 礎 にあった。たとえばホメロスの『イリアス』を 見 ると、その 基 底 に 流 れる 感 覚 は、まさにこの「 死 なね<br />
ばならない」という 不 可 避 性 の 感 覚 である。「『イーリアス』には、 人 間 の 悲 惨 に 対 する 嘆 きが、 全 編 を 通 奏 低 音 のよう<br />
に 流 れて」いる( 川 島 重 成 『『イーリアス』 ギリシア 英 雄 叙 事 詩 の 世 界 』 岩 波 書 店 、1991 年 、44 頁 。また、 同 書 、234<br />
頁 以 下 なども 参 照 )。<br />
とにかく、この mortal は 死 の 不 可 避 性 を 表 わしており、それゆえ 一 般 に「 死 すべき」と 訳 される。その 名 詞 形<br />
mortality は「 死 すべきこと」を 意 味 するが、その「…べき」は 可 能 を 表 すのではなく 不 可 避 を 表 わすゆえ、ここでは<br />
「 必 死 性 」という 耳 慣 れない 訳 語 を 当 てた。( 加 えてここで 断 っておくが、 以 下 ここでするように 訳 語 を 本 論 の 論 旨 に<br />
合 わせて 変 更 することがある。その 際 ここでしたようには 特 に 断 らないこともあるが 容 赦 されたい。ただし、その 際 は<br />
改 めた 訳 語 の 横 に 亀 甲 括 弧 〔…〕に 入 れて 原 語 をなるべく 表 示 することにする。)<br />
20
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、<br />
はなく 出 生 こそ、 形 而 上 学 的 思 考 と 区 別 される 政 治 的 思 考 の 中 心 的 な 範 疇 であろう〔 傍 点 は 橋 爪 〕」<br />
80 。「 必 死 性 と 出 生 」といったカテゴリーは 後 に 取 り 上 げるので 詳 論 しないが、ここで 理 解 されたいの<br />
は、 形 而 上 学 的 思 考 と 政 治 的 思 考 の 関 係 性 である。 出 生 natality は、 活 動 との 結 びつきが 強 いた<br />
めに、 政 治 的 思 考 の 中 心 的 カテゴリーである。ならば 形 而 上 学 的 思 考 の 中 心 的 カテゴリーを 構 成<br />
するのはなんであろうか その 点 は『 人 間 の 条 件 』のドイツ 語 版 『ウィータ・アクティーワ』に 幾 分 詳<br />
述 されている 81 。『ウィータ・アクティーワ』では 同 じ 部 分 に 次 のように 補 筆 が 加 えられている。「そして<br />
さらに 活 動 Handeln はすぐれて 政 治 的 な 活 動 力 であるから、 出 生 Natalität は 政 治 的 思 考 にとって<br />
ファクトゥム<br />
ひとつの 決 定 的 な、 範 疇 形 成 的 な 事 実 Kategorien-bildendes Faktum を 意 味 するであろう。ちょうど<br />
必 死 性 Sterblichkeit が 西 洋 において、 遥 か 昔 から、 少 なくともプラトン 以 来 、 形 而 上 学 的 = 哲 学 的<br />
思 考 の 火 をつける 原 因 となった 実 際 的 状 況 であったのと 同 様 に」 82 。この 一 文 で 明 らかなように、 哲<br />
学 = 形 而 上 学 の 思 考 は 死 、 必 死 性 に 関 わる。それに 対 して 政 治 学 の 思 考 は 生 と 出 生 に 関 わるの<br />
であるから、その 点 で 形 而 上 学 と 政 治 学 は 切 っても 切 れない 関 係 にある。つまり、アーレントは 形 而<br />
上 学 の 限 界 において 政 治 学 に 遭 遇 したのだ。あたかも、 形 而 上 学 が「 死 」の 思 考 を 突 き 詰 めていっ<br />
たその 果 てで、 思 考 が 反 転 し、「 生 」の 領 野 へと 投 げ 返 されたかのように――そのようにして 彼 女 は<br />
政 治 学 の 思 考 を 展 開 しているのだ。<br />
アーレントの「 政 治 学 」は、 形 而 上 学 に 裏 付 けられている。つまり、その 試 みは「 形 而 上 学 」の 限<br />
界 において 行 なわれ、まさにそれゆえに「 形 而 上 学 」が 解 体 しかねない 地 平 を 開 いている。 逆 に 言<br />
えば、その 政 治 学 はいかにも 形 而 上 学 に 転 化 しやすいものでもある。いずれにしても、アーレント<br />
の 思 考 を 無 反 省 に「 政 治 学 」と 呼 んでしまうと、その 思 考 の 射 程 を 矮 小 化 させてしまう 恐 れがある。<br />
それはたしかに「 政 治 学 」だが、「 政 治 学 」そのものを 解 体 させかねないという 意 味 で、すぐれて「 非<br />
デ ィ ス ク ー ル<br />
= 政 治 学 的 」である。というのも、それは「 形 而 上 学 」に 裏 打 ちされた 言 葉 遣 い で 語 り 思 考 するから<br />
だ。 換 言 すれば、アーレントは 政 治 学 と 形 而 上 学 を、コインの 裏 表 のように 理 解 しているのだ。だか<br />
ら、アーレントの 思 考 、その 独 特 の《 政 治 学 》は、 形 而 上 学 ( 哲 学 )と 政 治 学 の 両 方 にとって、 極 限 的<br />
、、、、、、、、、、、、、、<br />
なものと 映 るだろう。それらを 片 面 しか 存 在 しないかのように――すなわち 政 治 にとって 形 而 上 学 が<br />
存 在 しないかのように、あるいは 形 而 上 学 にとって 政 治 など 問 題 にならないかのように―― 語 って<br />
しまえば、 両 面 共 に 語 り 損 なってしまうと 彼 女 は 考 えるのだ。 形 而 上 学 の 裏 面 が 政 治 学 であり、 政<br />
治 学 の 裏 面 が 形 而 上 学 なのである。それゆえアーレントの「 政 治 学 」はいわば「 反 転 した 形 而 上 学 」<br />
、、、、、、、、、、、<br />
とも 呼 べるし、 敢 えて 言 えばその 政 治 学 の 形 而 上 学 的 側 面 こそ、 本 論 が 問 題 とする 領 野 であると 言<br />
80 ARENDT, The Human Condition (op.cit.), p.9. ( 前 掲 訳 書 、21 頁 。)<br />
81 このドイツ 語 版 Vita activa は、 周 知 のように、はじめ 英 語 で 書 かれた The Human Condition を 著 者 であるアーレン<br />
ト 自 らがドイツ 語 に 翻 訳 したものである。といっても、アーレントにとって 英 語 は 後 から 身 に 付 けた 外 国 語 であり、ドイ<br />
ツ 語 の 方 が 母 語 であるから、 表 現 の 点 ではドイツ 語 版 のほうがずっと 巧 みであるし、 然 るに 英 語 からの 純 粋 な 翻 訳 と<br />
して 読 むことはできない。 本 論 文 では、 依 拠 している 邦 訳 ( 志 水 速 雄 訳 、 前 掲 )が 英 語 版 からの 翻 訳 であることから、<br />
現 点 も 基 本 的 には 英 語 版 The Human Condition に 依 拠 し、 必 要 な 場 面 ごとに Vita activa をも 参 照 することにする。<br />
というのは、 単 語 のニュアンスや、 先 行 する 思 想 (『 人 間 の 条 件 』ではとりわけハイデガーやマルクス)をどのように 取<br />
り 入 れているのかを 確 認 するうえで、ドイツ 語 でどういう 表 現 をとり、どういう 単 語 を 選 んでいるかといったようなことを<br />
調 べるのは 非 常 に 有 益 と 思 われるからである。さらに、 英 語 版 よりも 文 章 が 足 され 補 筆 されている 場 合 もある。このよ<br />
うな 補 筆 については、 当 然 書 き 足 すだけの 重 要 性 があるとも 考 えられるし、 可 能 な 限 り 確 認 したい。<br />
82 ARENDT, Hannah, Vita activa oder Vom tätigen Leben (ungekürzte Taschenbuchausgabe, 6. Aufl. München/Zürich,<br />
21
ってもよい。というのも 本 論 の 主 題 は「 時 間 論 」という、どちらかといえば 形 而 上 学 的 なカテゴリーに<br />
属 する 問 題 であるからだ。<br />
第 8 節<br />
活 動 的 生 活 と 精 神 的 生 活<br />
アーレントは、 人 間 の 生 life の 様 式 を 大 きく 二 つに 区 別 している。 第 一 は「 活 動 的 生 活 」vita<br />
activa, tätiges Leben であり、 第 二 は「 精 神 的 生 活 」life of the mind, geistiges Leben である。さらにそ<br />
アクティヴィティ<br />
れぞれのなかに 三 つの 主 要 な 活 動 力 を 認 めている。すなわち、 活 動 的 生 活 における「 労 働 」work、<br />
「 仕 事 」labor、「 活 動 」action の 三 つ、および「 観 想 的 生 活 」における「 思 考 」thinking、「 意 志 」willing、<br />
レー ベ ン<br />
「 判 断 」judging である。 故 にこの 二 つの 生 活 の 区 別 を、この 時 間 論 の 分 析 における 基 本 的 な 範 疇 と<br />
してまず 画 定 しておくことは、 今 後 の 論 の 展 開 においても 重 要 である。 実 際 、 後 に 見 るように、 二 つ<br />
の 生 活 様 式 の 違 いそのものが 時 間 性 の 違 いに 通 じていて、それぞれの 生 活 において、それぞれ<br />
ジ ッ ヒ ・ ツ ァ イ テ ィ ゲ ン<br />
の 仕 方 で 人 間 は 自 らを 時 間 化 する 。ここでは 本 来 的 な 意 味 で「 時 間 とは 生 活 である Zeit ist Leben」<br />
83 。<br />
しかし 我 々はアーレントにおける 活 動 的 生 活 と 精 神 的 生 活 の 区 別 を 見 る 前 に、 先 ず 活 動 的 生 活<br />
、、、、、<br />
と 観 想 的 生 活 という 対 立 概 念 の 問 題 を 確 認 しておく 必 要 がある。 彼 女 は『 人 間 の 条 件 』の 段 階 では、<br />
「 活 動 的 生 活 」vita activa, βίος πολιτικός に 対 立 する 生 活 として、 伝 統 的 区 別 に 従 い「 観 想 的 生 活 」<br />
vita contemplativa, βίος θεωρητικός を 立 てていた。 一 瞥 した 限 りでは、この 観 想 的 生 活 vita<br />
contemplativa は、アーレントが『 精 神 の 生 活 』において 扱 っている 精 神 的 生 活 life of the mind と 等<br />
しく 見 える。しかしこの 二 つには 実 は 相 違 があると 考 えられる。アーレントは『 人 間 の 条 件 』から『 精<br />
神 の 生 活 』に 至 るあいだに―― 実 際 、このあいだに 十 年 以 上 が 経 過 している―― 活 動 的 生 活 対 観<br />
想 的 生 活 という 構 図 から、 活 動 的 生 活 対 精 神 的 生 活 という 構 図 84 への 転 換 を 図 っていると 考 えられ<br />
るのだ。<br />
アーレントは『 人 間 の 条 件 』に 次 のように 書 いている。「 本 書 は、 人 間 の 条 件 の 最 も 基 本 的 な 要 素<br />
を 明 確 にすること、すなわち、 伝 統 的 にも 今 日 の 意 見 によっても、すべての 人 間 存 在 の 範 囲 内 にあ<br />
るいくつかの 活 動 力 だけを 扱 う。このため、あるいはその 他 の 理 由 で、 人 間 がもっている 最 高 の、そ<br />
しておそらくは 最 も 純 粋 な 活 動 力 、すなわち 思 考 〔thinking〕という 活 動 力 は、 本 書 の 考 察 の 対 象 と<br />
レイバ ワ ー ク アクション<br />
はしない。したがって、 理 論 上 の 問 題 として、 本 書 は、 労 働<br />
ー、 仕 事 、 活 動 に 関 する 議 論 に 限 定 され」<br />
る 85 。この 文 章 から 差 し 当 たり 指 摘 できることは、 活 動 的 生 活 に 対 置 される 活 動 力 としては、この 段<br />
階 では 思 考 thinking のみが 考 えられているということである。 無 論 、アーレントが 意 志 willing や 判<br />
断 judging という、 後 に『 精 神 の 生 活 』で 問 題 化 されるような 精 神 的 活 動 力 にまるで 気 が 付 いていな<br />
ファクトゥム<br />
Piper Verlag, 2007, S.18. 拙 訳 。なお「 事 実 」に 関 しては 第 12 節 を 参 照 のこと。<br />
83 ENDE, Michael, Momo oder Die seltsame Geschichte von den Zeit-Dieben und von dem Kind, das den Menschen<br />
die gestohlene Zeit zurückbrachte; Schulausgabe mit Materialien, Stuttgart/Wien: Thienemann Verlag, 2005, S.75.<br />
( 大 島 かおり 訳 『モモ 時 間 どろぼうと 盗 まれた 時 間 を 人 間 にとりかえしてくれた 女 の 子 のふしぎな 物 語 』 岩 波 書 店 、<br />
1976 年 、61 頁 。)<br />
84<br />
念 のため 指 摘 しておくが、ここで 用 いた「 対 」という 表 現 は、 別 に 敵 対 的 対 立 を 表 わすものではなく、 対 称 概 念 とし<br />
て 扱 われていることを 意 味 しているにすぎないものである。<br />
85 ARENDT, The Human Condition (op.cit.), p.5. ( 前 掲 訳 書 、16 頁 。)<br />
22
かったと 言 うことは 出 来 ない。むしろそのような 意 志 や 判 断 という 概 念 は、 萌 芽 的 なかたちとはいえ、<br />
『 人 間 の 条 件 』にもたしかに 見 られる。しかし、 少 なくとも 理 論 的 には、それらの 活 動 力 は 閑 却 されて<br />
いる。<br />
アーレントは 同 じ『 人 間 の 条 件 』のなかでこうも 書 いている。「〈 活 動 的 生 活 〉vita activa という 用 語<br />
、、、、、、、、、、、、、、<br />
はすべての 人 間 の 活 動 力 を 包 含 し、 観 想 という 絶 対 的 な 静 との 対 比 において 定 義 されて」いる( 傍<br />
点 は 橋 爪 ) 86 。ここでアーレントが「すべての 活 動 力 」と 書 いたのは、 端 的 には 活 動 的 生 活 という 用 語<br />
を、 労 働 ・ 仕 事 ・ 活 動 の 三 活 動 力 を 包 括 的 に 示 す 術 語 ( 上 位 概 念 )として 提 示 する 目 的 のためだっ<br />
たと 思 われる。それでも 言 葉 の 厳 密 な 意 味 を 取 れば、この 一 文 は 活 動 的 生 活 の 他 に 一 切 活 動 力 が<br />
ないということを 意 味 してしまうだろう。このことは『 精 神 の 生 活 』において 思 考 ・ 意 志 ・ 判 断 を 精 神 的<br />
活 動 力 mental activity と 見 做 していることと 矛 盾 する。アーレントの 言 葉 遣 いの 慎 重 さから 考 えると、<br />
この 矛 盾 が 単 純 に 看 過 されてしまったとは 考 えにくい。むしろ、『 精 神 の 生 活 』のアーレントは、『 人<br />
間 の 条 件 』の 時 点 での 自 らの 概 念 区 分 を 深 化 させ、 活 動 的 生 活 以 外 にもなんらかの 活 動 力 が 存 在<br />
することを 認 めることで 自 らの 思 想 を 再 び 乗 り 越 えようとしていると 考 えるほうが、 我 々にとっては 自<br />
然 であろう。<br />
第 9 節<br />
観 想 的 生 活 に 関 するハイデガーの 解 釈<br />
従 って 先 ず、 観 想 的 生 活 をアーレントがどう 解 釈 しているのか 明 確 にしておきたい。そしてその<br />
解 釈 そのものは、 基 本 的 には 伝 統 的 解 釈 に 依 拠 していると 考 えられる。それゆえ 伝 統 的 解 釈 その<br />
ものがいかなる 由 来 に 発 し、いかに 受 け 継 がれているかを 簡 単 に 見 ておこうと 思 う。その 伝 統 的 解<br />
釈 そのものは、アリストテレスに 発 する。 彼 は『ニコマコス 倫 理 学 』の 第 一 巻 第 五 章 において、 人 間<br />
の「 生 活 βίος」を 三 種 類 に 分 ける。「ひとびとの 実 際 の 生 活 から 察 するに、 世 上 一 般 の 最 も 低 俗 なひ<br />
とびとの 解 する 善 とか 幸 福 とかは――それは 理 由 のないわけではないが――<br />
ヘードネーにほかならない<br />
快 楽<br />
アポラウスティコス<br />
ように 思 われる。 彼 らの 好 む 生 活 は 享 楽 的 なそれ〔τὸν ἀπολαυστικόν〕だといえる 所 以 である。けだ<br />
し、およそ 主 要 な 生 活 形 態 に 三 通 りがあるのであって、いまいうごとき 生 活 〔= 享 楽 的 生 活 〕と、<br />
ポ リ テ ィ コ ス テオレーティコス<br />
政 治 的 な 生 活 〔ὁ πολιτικὸς〕と、 第 三 に 観 照 的 な 生 活 〔ὁ θεωρητικός〕とがそれである」 87 。<br />
第 一 のそれ、<br />
ヘードネーに 快 楽 関 わる 享 楽 的 生 活 βίος ἀπολαυστικός は、アーレントはさして 重 要 視 してい<br />
ない 88 ビ オ ス<br />
。 彼 女 にとって――それゆえ 我 々にとって―― 重 要 なのは、 第 二 、 第 三 の 生 活 、すなわち<br />
86 Ibid, p.15. ( 前 掲 訳 書 、29 頁 。)<br />
87 ARISTOTELES, Ethica Nicomachea, 1095b15-19. ( 高 田 三 郎 訳 『ニコマコス 倫 理 学 』 上 、 岩 波 文 庫 、1971 年 、22 頁 。<br />
なお 原 文 は、with an English trans. by H. RACKHAM, Aristotle XIX: The Nichomachean Ethics, new and revised ed.,<br />
Cambridge/ Massachusetts: Harvard Univ. Press, 1975 [orig.1926] 所 収 のものを 参 照 した。)<br />
88 ただし、<br />
ヘードネーについて、 快 楽 田 崎 英 明 は 次 のように 述 べている。「 快 楽 は 可 能 性 とは 関 係 がない。 快 楽 には 現 実 態<br />
しかない。 快 楽 は、アリストテレスによれば、 完 全 性 を 示 している」(『 無 能 な 者 たちの 共 同 体 』 未 来 社 、2007 年 、17<br />
頁 )。 快 楽 はそれゆえ、 連 続 的 な 時 間 を「 切 断 」するハイデガー 的 「 決 断 」とは 異 なり、 連 続 性 そのものと 関 わりをもた<br />
ない「 中 断 」である。 田 崎 によれば、ハイデガーは「 決 断 」 的 契 機 に 依 り、「 中 断 」 的 契 機 を 見 逃 したために、<br />
ツァイトリッヒカイト テンポラリテート<br />
時 間 性 から 時 節 性 への 移 行 (つまり『 存 在 と 時 間 』の 後 半 部 )に 失 敗 したのだと 捉 える。<br />
実 は 田 崎 がこのように 論 じる 際 に 念 頭 にあったのは、アーレントの<br />
ヘードネーに 快 楽 関 する 議 論 であったと 思 われる。アー<br />
レントが 快 楽 の 問 題 に 触 れるのは、 思 考 の 時 間 経 験 を 問 題 にするときである。「アリストテレスが、 持 続 する 現 在 にお<br />
ける 時 間 のこの 停 止 を 最 初 に 述 べたように 思 われる。そして、 興 味 深 いことだが、このことは、『ニコマコス 倫 理 学 』の<br />
23
ビ オ ス ・ ポ リ テ ィ コ ス ビ オ ス・ テ オ レティ コ ス<br />
政 治 的 生 活 と 観 想 的 生 活 である。ジャック・タミニオーによれば、アーレントは、この 二 つの 生 活 の<br />
古 典 的 区 別 に 関 するハイデガーの 解 釈 を、1924/25 年 のプラトン『ソピステス』に 関 する 講 義 89 にお<br />
いて 聞 いていた。<br />
タミニオーによると、ハイデガーは、「 哲 学 、すなわち 形 而 上 学 であるが、その 主 要 な 形 態 とは、<br />
学 説 ではなく、むしろ 実 存 existence の 一 形 態 であり、 最 高 の 形 態 ですらある」 90 と 強 調 していたとい<br />
ダ ー ザ イ ン<br />
う。ハイデガー 曰 く、「プラトンは 人 間 的 現 存 在 Dasein を、その 極 限 的 可 能 性 のひとつにおいて 考<br />
エクシステンツ<br />
察 していた。すなわち 哲 学 的 実 存 Exsitenz において、である」 91 。その 哲 学 的 実 存 の 形 態 を、より<br />
アレーテイア<br />
明 確 に 定 義 したのがアリストテレスなのである。ハイデガーは、そのアリストテレスにおける 真 理 の<br />
問 題 を 考 えようとする。ハイデガーは 言 う。「それゆえ 確 かに、 真 理 は、〔 我 々に〕 出 会 って 来 るような<br />
存 在 者 の 性 格 である。しかし、 本 来 的 な 意 味 においては im eigentlichen Sinne 人 間 的 現 存 在 その<br />
ものの 存 在 規 定 である」 92 。タミニオーはそのことについて 次 のような 注 釈 を 付 す。「アリストテレスは、<br />
人 間 に 接 近 可 能 な 真 理 = 内 = 存 在 〔In-der-Wahrheit-sein〕の 様 々なあり 方 を、 注 意 深 く 踏 査 した。<br />
もっとも、 哲 学 的 実 存 、つまりソピアすなわち 存 在 者 の 存 在 の『 本 来 的 了 解 』(eigentliches Verstehen)<br />
に 献 身 することに、 最 高 の 地 位 を 与 えてはいるが。だから、ハイデガーは『ニコマコス 倫 理 学 』を 現<br />
存 在 の 存 在 論 と 等 しいと 見 做 す」 93 。ハイデガーは「 哲 学 」、つまり 存 在 の 了 解 ( 存 在 論 )もまた、 人<br />
間 的 現 存 在 の 存 在 可 能 性 のひとつであるとする。すなわちそれも 人 間 ( 現 存 在 )の 実 存 の 仕 方 な<br />
のである。 存 在 の 了 解 もまた、 真 理 = 内 = 存 在 、つまり 真 理 を 了 解 する 一 つのありかたである(なお、<br />
ここでの 真 理 = 内 = 存 在 の 概 念 は、『 存 在 と 時 間 』における 現 存 在 分 析 においては「 開 示 態<br />
Erschlossenheit」と 言 いかえられている 94 )。しかし、 同 時 にアリストテレスは、さまざまな 真 理 = 内 =<br />
存 在 の 在 り 方 を 探 求 していた。その 他 の 在 り 方 とはなにか。<br />
第 十 巻 における 快 楽 、つまりヘードネー〔hedone〕の 議 論 で 述 べられているのである。 彼 は 言 う、『 快 楽 は 時 間 の 中<br />
にない。 一 つの 今 の 中 で 起 きることは 一 つの 全 体 だから』、 運 動 は 存 在 しないのである。そして、 彼 によれば、 思 考<br />
の 活 動 は、『 純 粋 さと 確 実 性 において 驚 くべきものであり』、 一 切 の 活 動 の 中 で、『もっとも 快 楽 に 満 ちたもの』だった<br />
ので、アリストテレスは、 明 らかに、 運 動 を 欠 いた 今 〔motionless Now〕、つまり、 後 の 静 止 スル 現 在 〔nunc stans〕につ<br />
いて 語 っていたのである」(ARENDT, Hannah, The Life of the Mind: Two/ Willing (op.cit.), p.12 〔 前 掲 訳 書 、15 頁 〕)。<br />
アーレントは 享 楽 的 生 活 (ビオス・アポラウスティコス)については 語 っていないが、 快 楽 (ヘードネー)の 問 題 はこの<br />
ようなかたちで 扱 っていることに 注 意 すべきだろう。<br />
ここではこれ 以 上 踏 み 込 むことはしないが、アーレントはハイデガー 的 決 断 とは 異 なる 時 間 の 停 止 ないし 中 断<br />
suspension をも、その 時 間 論 のなかに 組 み 込 んでいたことになる。 思 考 の 活 動 力 における 時 間 の 停 止 に 関 しては、<br />
本 論 文 の 第 六 章 で 扱 う。<br />
89 HEIDEGGER, Martin, Platon: Sophistes (Gesamtausgabe Bd.19), Frankfurt a.M.: Vittorio Klostermann, 1992.<br />
90 TAMINIAUX, Jacques, trans. fr. the French by Michael GENDRE, The Thracian Maid and the Professional Thinker:<br />
Arendt and Heidegger, Albany: State Univ. of New York Press, 1997, p.4. 拙 訳 。 以 下 もこの 本 からの 引 用 は 拙 訳 。<br />
91 HEIDEGGER, Platon: Sophistes (ebenda), S.12. Cited in: TAMINIAUX, ibid. 拙 訳 。ただしハイデガーの 原 文 から 直<br />
截 訳 した。 以 下 も 同 様 。<br />
92 Ebenda, S.23. Cited in: TAMINIAUX, ibid.<br />
93 TAMINIAUX, ibid., pp.4f.<br />
94 「ところで 真 理 とは、 存 在 者 が 打 ち 明 けられ( 発 見 され)てあることを 意 味 し、そして 打 ち 明 けられてあることは、 存<br />
在 論 的 には、すべて、もっとも 根 源 的 な 真 理 、すなわち 現 存 在 の 開 示 態 にもとづいている。 現 存 在 は、 開 示 し 発 見<br />
する 存 在 者 として、 本 質 上 、『 真 理 の 内 に』 存 在 している」(HEIDEGGER, Martin, Sein und Zeit, 11. unveränderte Aufl.,<br />
Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1967, S.256 〔 細 谷 貞 雄 訳 『 存 在 と 時 間 』 下 、ちくま 学 芸 文 庫 、1994 年 、71 頁 〕)。<br />
24
人 間 の〔 真 理 〕 解 明 uncovering の 可 能 性 についてのアリストテレスの 記 述 のうちにハイデガ<br />
ーが 感 知 しているものは、〔 人 間 の〕 二 種 の 振 舞 いに 対 応 する、 二 種 の 存 在 様 態 の 階 層 秩 序<br />
である。 下 位 に 熟 慮 的 な deliberate、 活 動 的 な 振 舞 いが、 上 位 に 観 想 的 で 理 論 的 な 振 舞 いが<br />
ある。〔 略 〕<br />
熟 慮 的 な 振 舞 いそのものも 二 種 の 活 動 力 に 分 かたれ、その 二 種 も 同 じ 水 準 にはない。その<br />
二 種 とは、ポイエーシスと 呼 ばれる 制 作 の 活 動 力 と、 上 位 に 置 かれるプラクシスと 呼 ばれる 活<br />
動 の 活 動 力 である。これら 二 種 の 活 動 力 、ないし 振 舞 いには、 二 種 の〔 真 理 〕 解 明 、 二 種 の 真<br />
理 = 内 = 存 在 が 対 応 している。 95<br />
上 位 に 分 類 される 観 想 的 な 振 舞 いというものは、 存 在 を 了 解 する 真 理 = 内 = 存 在 であるが、それ<br />
はひとまず 措 き、 下 位 の 熟 慮 的 な 振 舞 いと 呼 ばれているものを 見 よう。その 振 舞 いもまた 二 つの 活<br />
ポイエーシス<br />
動 力 に 分 類 されるのである。そしてその 二 種 の 活 動 力 に 対 応 する 真 理 解 明 の 仕 方 があり、 制 作 に<br />
ノ ウ ・ ハ ウ プラクシス<br />
対 しては 方 法 知 (テクネー)、 活 動 に 対 してはプロネーシスという 真 理 = 内 = 存 在 が 対 応 する。ポイ<br />
テ ロ ス<br />
エーシス=テクネーにおいては、その 終 わり= 目 的 が 制 作 行 為 そのものの 外 にあり、 他 方 プラクシ<br />
テ ロ ス<br />
ス=プロネーシスにおいて、 終 わり= 目 的 は 活 動 行 為 そのものの 内 にある、といった 差 異 があるた<br />
めに、それ 自 体 で 完 結 するプラクシスが、 完 成 した 活 動 力 として 上 位 に 置 かれるのである。それは<br />
さておき、このように、プラクシスやポイエーシスもまた 人 間 的 現 存 在 の 存 在 可 能 性 であり、それぞ<br />
れの 活 動 力 にはそれぞれに 対 応 した 真 理 解 明 が 備 わっているのだ。<br />
しかしながら、アリストテレスにおいて 真 に 重 んじられる 真 理 解 明 、 真 理 = 内 = 存 在 は、 観 想 的 ・<br />
ビ オ ス・ テ オ レティ コ ス<br />
理 論 的 振 舞 い、すなわち 観 想 的 生 活 に 備 わる 真 理 解 明 である 存 在 の 了 解 であった。「この 卓 越 し<br />
た〔 真 理 解 明 の〕 可 能 性 こそソピアであり、すなわちハイデガーが 言 うところの『 存 在 の 本 来 的 な 了<br />
解 』である」 96 。<br />
コンテンプレーション ビ オ ス・ テ オ レティ コ ス<br />
ソピアとは 純 粋 な 観 想 であり、 観 想 的 生 活 を 体 験 している 哲 学 者 はそれによって 不 死 化<br />
され、エウダイモニアへと 至 る。このエウダイモニアという 言 葉 を、ハイデガーは 躊 躇 なく「 本 来<br />
性 」(Eigentlichkeit)と 訳 すのである。 97<br />
ハイデガーはこうした 独 自 の 解 釈 から 出 発 し、 存 在 了 解 という 可 能 性 を、 時 間 的 に 有 限 的 な( 人 間<br />
的 ) 現 存 在 のなかに 移 すに 至 るのだが、この 点 には 深 入 りしないでおく。このような 真 理 と 振 舞 いと<br />
活 動 力 との 関 係 に 関 する 解 釈 が、『 存 在 と 時 間 』における 現 存 在 の 分 析 、つまり 基 礎 的 存 在 論 に 繋<br />
がって 行 くのだ。<br />
アーレントは、 観 想 を 重 視 することはないとはいえ、ひとまずこのハイデガー 的 な 解 釈 から 出 発 し<br />
ビ オ ス ・ ポ リ テ ィ コ ス<br />
て、「まさにハイデガーの 基 礎 的 存 在 論 の 諸 テーマを―― 政 治 的 生 活 の 観 点 から―― 新 たに 考 察<br />
する」 98 ことになる。その 作 業 こそ『 人 間 の 条 件 』であった。<br />
95 TAMINIAUX, op.cit., p.5.<br />
96 Ibid., p.7.<br />
97 Ibid. なお、エウダイモニア εὐδαιμονία というギリシャ 語 は、 普 通 「 幸 運 」などと 訳 される。<br />
25
第 10 節 観 想 的 生 活 と 活 動 的 生 活 ――『 人 間 の 条 件 』における 理 解<br />
アーレントは、アリストテレス 解 釈 を 踏 まえたハイデガーの 人 間 の 存 在 可 能 性 理 解 ――すなわち<br />
ビ オ ス ビ オ ス・ テ オ レティ コ ス<br />
二 つの「 生 活 」――を 受 け 継 ぎながらも、 観 想 的 生 活 が 優 位 に 考 えられているという 点 に 疑 問 を 抱<br />
き、 二 種 の 生 活 様 式 の 関 係 を 捉 え 直 そうと 試 みる。『 人 間 の 条 件 』――そのドイツ 語 版 のタイトルは<br />
ビ オ ス・ テ オ レティ コ ス<br />
既 述 の 如 く『ウィータ・アクティーワ』、つまり「 活 動 的 生 活 」であった――においても、 観 想 的 生 活<br />
ビ オ ス ・ ポ リ テ ィ コ ス ウ ィ ー タ・ ア ク テ ィ ー ワ<br />
(ウィータ・コンテンプラティワ)は、 政 治 的 生 活 ( 活 動 的 生 活 ) 99 との 対 照 において 捉 えられている。<br />
ビ オ ス・ テ オ レティ コ ス<br />
アーレントは、アリストテレスにおいて 観 想 的 生 活 は、「 永 遠 なる 事 物 の 探 究 と 観 照 に 捧 げられる 哲<br />
学 者 の 生 活 であって、この 永 遠 なる 事 物 の 不 朽 の 美 は、 人 間 が 介 入 してもたらすこともできなけれ<br />
ば、 人 間 がそれを 消 費 することによって 変 えることも 出 来 ないのである」 100 と 述 べる。それに 対 して<br />
ビ オ ス ・ ポ リ テ ィ コ ス<br />
政 治 的 生 活 は、「 人 間 事 象 の 領 域 だけをはっきりと 指 し 示 しており、しかもその 領 域 を 確 立 し 維 持<br />
プラクシス<br />
するのに 必 要 な 活 動 を 強 調 している」 101 。アリストテレスにおけるこの 二 種 の 生 活 様 式 の 対 置 は、 中<br />
世 哲 学 においてより 著 しい 対 照 をなすようになる。「〈 活 動 的 生 活 〉vita activa という 用 語 はその 特 殊<br />
に 政 治 的 な 意 味 を 失 って、この 世 界 の 物 事 にたいするあらゆる 種 類 の 積 極 的 な 係 わりを 意 味 する<br />
ようになった」 102 。アリストテレスにおいては、 活 動 は、 労 働 ・ 仕 事 の 活 動 力 に 対 して 相 対 的 に 上 位<br />
に 置 かれていたが、 中 世 哲 学 に 至 り「 活 動 も 今 や 現 世 的 生 活 の 必 要 物 の 一 つとなり 下 がり、したが<br />
って 観 照 生 活 (vita contemplativa, bios theoretikos)だけが 唯 一 の 真 に 自 由 な 生 活 様 式 として 残 っ<br />
たのである」 103 。すなわち、 活 動 もまた、 労 働 ・ 仕 事 同 様 、 観 想 という 人 間 の 存 在 仕 方 を 妨 げるもの<br />
として、 貶 められたのだった。「〈 活 動 的 生 活 〉vita activa という 用 語 はすべての 人 間 の 活 動 力 を 包<br />
含 し、 観 照 という 絶 対 的 な 静 との 対 比 において 定 義 されて」 104 いる。この 対 比 において、すべての<br />
活 動 力 の 目 的 は 観 想 ( 的 生 活 )である。「あらゆる 種 類 の 活 動 力 は、 単 なる 思 考 の 過 程 でさえ、 観<br />
照 の 絶 対 的 静 の 極 みに 達 しなければならない」 105 のだ。「したがって 伝 統 の 面 からみれば、〈 活 動<br />
的 生 活 〉vita activa という 用 語 はその 意 味 を〈 観 照 的 生 活 〉vita contemplativa から 得 ている。そして<br />
98 Ibid., p.17.<br />
ビ オ ス ・ ポ リ テ ィ コ ス ウィータ・ アクティーワ<br />
99<br />
実 は 政 治 的 生 活 と 活 動 的 生 活 は、 厳 密 にイーコールであるとは 言 えない。ビオス・ポリティコスは、ポリスにおける<br />
プラクシス アクション<br />
政 治 的 な 活 動 を 内 実 とした 生 活 様 式 であり、アーレントの 言 う 活 動 と 実 質 的 に 一 対 一 対 応 している。それに 対 して<br />
ウィータ・アクティーワという 概 念 は、 観 想 に 対 立 する( 観 想 を 妨 げる)すべての 人 間 的 活 動 力 を 内 包 しており、もち<br />
ろん 政 治 的 な 活 動 力 である 活 動 をも 含 むのであるが、それ 以 上 に 広 く 労 働 や 仕 事 をも 含 みこんでいる。アリストテレ<br />
プラクシス<br />
スのビオス・ポリティコスという 概 念 は、むしろそれでも 活 動 が 上 位 に 位 置 づけられていたということを 意 味 しているの<br />
だ。ウィータ・アクティーワに 対 応 する 概 念 はというと、それは「アリストテレスがすべての 活 動 力 を 示 すのに 用 いたギ<br />
アンクワイエット<br />
リシア 語 のアスコリア(「 非 静 寂 」)という 語 にいっそう 近 い」(ARENDT, The Human Condition [op.cit.], p.15 〔 前 掲 訳<br />
書 、29 頁 〕)。アスコリア ἀσχολία という 語 そのものは、「ひま」や「 余 暇 」を 表 わすスコレーσχολή という 語 に 否 定 接 頭<br />
辞 がついた 形 をしている。つまり、 暇 でないという 意 味 で「 多 忙 business」を 意 味 する 語 である。アリストテレスにおい<br />
ては、スコレーは 観 想 に 捧 げられるべきものであった。アスコリアはその 観 想 に 対 立 する 時 間 をすべて 包 括 してい<br />
る。<br />
100 Ibid., p.13. ( 前 掲 訳 書 、26-27 頁 。)<br />
101 Ibid. ( 前 掲 訳 書 、27 頁 。)<br />
102 Ibid., p.14.( 前 掲 訳 書 、27-28 頁 。)<br />
103 Ibid.( 前 掲 訳 書 、28 頁 。)<br />
104 Ibid., p.15.( 前 掲 訳 書 、29 頁 。)<br />
105 Ibid.( 同 上 。)<br />
26
この 用 語 に、 非 常 に 限 られたものとはいえ 威 厳 が 与 えられているのは、 生 きている 肉 体 が 観 照 する<br />
場 合 に 必 要 とするものを〈 活 動 的 生 活 〉が 与 えるからである」 106 。<br />
見 ればわかるように、 基 本 的 な 構 図 はハイデガーのそれを 踏 襲 したかたちになっている。たしか<br />
にアーレントは、「〈 活 動 的 生 活 〉という 用 語 を 私 が 用 いるとき、 私 は、そのすべての 活 動 力 のもとに<br />
なっている 関 心 は〈 観 照 的 生 活 〉の 中 心 的 関 心 と 同 じものでもないし、それより 優 れたものでも 劣 っ<br />
たものでもないということを 前 提 にしているのである」 107 と 述 べて、 活 動 的 生 活 という、ハイデガーに<br />
おいては 軽 視 されていた 領 域 に 視 線 を 向 ける。 彼 にとっては、 活 動 的 生 活 は 観 想 のための<br />
(Um-zu)のものであり、 観 想 こそが「それを 目 的 とするそれ Worumwillen」であった。しかしアーレン<br />
トは 活 動 的 生 活 独 自 の 意 味 を 強 調 する。だが、この 段 階 ではまだ、 思 考 もまた 観 想 のほうからしか<br />
捉 えられていない。 観 想 とは「 絶 対 的 な 静 」であり、 本 質 的 には「 見 る」ことである。それは「 受 動 性 」<br />
、、、<br />
であり、 活 動 力 = 能 動 性 とは 言 えない。 別 言 すれば、 人 間 の 精 神 的 活 動 力 を、 彼 女 は 看 過 してし<br />
まっていたのだ。<br />
タミニオーが 言 うように、 職 業 的 思 想 家 に 対 するアーレントの「アイロニーが 生 まれ、 実 質 的 なも<br />
ビ オ ス・ テ オ レティ コ ス<br />
のになったのは、 自 らの 人 生 を 完 全 に 観 想 的 生 活 に 捧 げている 者 たちが、 単 に 活 動 的 生 活 の 本<br />
質 的 特 徴 を 知 り 損 なうのみならず、 思 考 それ 自 体 を 種 々の 誤 謬 に 包 みこんでしまうのだということに、<br />
彼 女 が 気 づいたときであった」 1<strong>08</strong> 。 彼 女 は、 思 考 者 が 活 動 的 生 活 を 見 損 なうとき、 思 考 そのものもま<br />
た 損 なわれるという 点 に 気 がついたのである。「 彼 女 は〔 略 〕『 人 間 の 条 件 』について 反 省 を 巡 らせ<br />
たとき、 自 分 の 1958 年 の 本 〔『 人 間 の 条 件 』〕が、 知 らず 知 らずに『ソピステス』 講 義 の 影 響 下 に、 未<br />
だ 留 まっていたということに 気 づいた。 実 際 、〔 略 〕 彼 女 の 本 は、 思 考 は 窮 極 的 には 観 想 的 であると<br />
いう 暗 黙 の 前 提 に 依 っているのである」 109 。アーレントはこの 問 題 に、 最 終 的 に『 精 神 の 生 活 』にお<br />
いて 取 り 組 んでゆくこととなる。<br />
第 11 節 観 想 的 生 活 から 精 神 的 生 活 へ――『 精 神 の 生 活 』における 理 解<br />
ウィータ・コンテンプラティワ<br />
『 人 間 の 条 件 』において、 観 想 的 生 活 vita contemplativa は 殆 ど 考 察 されることなく、ましてそれ<br />
は 思 考 という 活 動 力 と 混 同 されていたきらいすらあった。しかし『 精 神 の 生 活 』においては 観 想 的 生<br />
活 の 位 置 付 けがより 明 確 にされ、「 受 動 性 passivity」と 理 解 されるようになる 110 パッシヴィティ<br />
。この 受 動 性 という 表<br />
ア ク テ ィ ヴ ィ テ ィ<br />
現 は、 当 然 活 動 力 = 能 動 性 activity との 対 比 において 捉 えられるべきだ。アーレントは 思 考 ・ 意 志 ・<br />
メ ン タ ル ・ ア ク テ ィ ヴ ィ テ ィ<br />
判 断 の 諸 能 力 を 受 動 性 と 捉 えることはなく、 精 神 的 活 動 力 ( 精 神 的 能 動 性 )mental activity と 呼 ぶ。<br />
メ ン タ ル ・ パ ッ シ ヴ ィ ティ<br />
この 区 別 を 踏 まえて 観 想 的 生 活 も 捉 え 返 されねばならない。 要 言 すれば、 精 神 的 受 動 性 の 体 験 と<br />
ウィータ・コンテンプラティワ メ ン タ ル ・ ア ク テ ィ ヴ ィ テ ィ ライフ・オブ・ザ・マインド<br />
しての 観 想 的 生 活 に 対 して、 精 神 的 活 動 力 の 発 現 として 精 神 の 生 活 を 理 解 しなければならないと<br />
いうことである。( 実 はアーレントは、すでに『 人 間 の 条 件 』のなかでも 次 のように 述 べていた。すな<br />
わち、「 思 考 や 推 理 とは 明 らかに 異 なる 人 間 的 能 力 として 観 照 (theoria)が 発 見 された」 111 、と。ここ<br />
106 Ibid., p.16.( 前 掲 訳 書 、30 頁 。)<br />
107 Ibid., p.17. ( 前 掲 訳 書 、32 頁 。)<br />
1<strong>08</strong> TAMINIAUX, op.cit., pp.17f.<br />
109 Ibid., p.18.<br />
110 ARENDT, The Life of the Mind: One/ Thinking (op.cit.), p.6. ( 前 掲 訳 書 、9 頁 。)<br />
111 ARENDT, The Human Condition (op.cit.), p.16. ( 前 掲 訳 書 、30 頁 。)<br />
27
で 観 想 contemplation, θεωρία が、 思 考 とは「 明 らかに 異 なる」とアーレントが 述 べている 点 に 注 意 す<br />
れば、 観 想 ( 的 生 活 )と、 思 考 という 活 動 力 との 区 別 を 精 密 化 することになるのは、 論 理 の 必 然 であ<br />
ったともいえる。)<br />
アーレントは、 観 想 的 生 活 について『 精 神 の 生 活 』では 次 のように 書 いている。<br />
〔 観 想 的 生 活 様 式 contemplative way of life が 至 上 であるとする〕この 視 座 にあっては、 活 動<br />
的 生 活 様 式 active way of life は、「 苦 労 が 多 い laborious」ものであり、〔 他 方 〕 観 想 的 様 式 は 全<br />
くの 静 寂 である。 活 動 的 生 活 は 公 共 において、 観 想 的 生 活 は「 砂 漠 」において 営 まれる。 活 動<br />
的 生 活 は「 隣 人 の 必 要 性 」のために、 観 想 的 生 活 は「 神 を 見 ること vision of God」のためにある。<br />
〔 略 〕 観 想 が 精 神 の 至 上 の 状 態 であるという 観 念 は、 西 洋 哲 学 そのものと 同 じだけ 古 い。〔 略 〕<br />
換 言 すれば、 思 考 は 観 想 を 目 的 とし aims at、 観 想 において 完 結 する ends in のである。そして<br />
観 想 とは 活 動 力 = 能 動 性 activity ではなく、 受 動 性 passivity であった。すなわちそれは 精 神<br />
的 活 動 力 が 安 らうようになる 地 点 だったのだ。 112<br />
アーレントの 観 想 的 生 活 に 対 する 評 価 は、『 人 間 の 条 件 』におけるそれと 基 本 的 には 変 わらないが、<br />
一 点 重 要 なのは、それが「 受 動 性 」であるという 評 価 をはっきりと 下 している 点 である。しかし 精 神 的<br />
活 動 力 まで 究 極 的 には 受 動 性 であると 捉 えてしまうのは、 問 題 ではないか。そのように 考 えたアー<br />
レントは、『 人 間 の 条 件 』を 次 のカトーの 言 葉 で 終 えていた。「ヒトハ 何 モ 為 サナイ 時 ホド 活 動 的 デア<br />
ルコトハナク、 孤 独 デアル 時 ホド 孤 独 デナイコトハナイ numquam se plus agere quam nihil ageret,<br />
numquam minus solum esse quam cum solus esset」 113 。この 謎 めいた 一 節 を 理 解 するには、アーレ<br />
ントの『ウィータ・アクティーワ』におけるドイツ 語 訳 を 見 るのがよい。アーレントはそこで 次 のように 訳<br />
、、、<br />
している。「ひとは、 外 見 上 dem äußeren Anschein nach 何 もしていないときほど 活 動 的 であることは<br />
、、、、、、、、<br />
なく、 自 己 とともにある mit sich 孤 独 のうちにおいて 一 人 であるときほど 一 人 でないときはない」( 傍 点<br />
は 橋 爪 ) 114 。つまり 彼 女 は「 見 かけ 上 活 動 的 でないとき(すなわち 活 動 力 を 発 揮 していないように 見<br />
えるとき)ですら、 人 間 は 活 動 的 なのではないか」という 気 づきをこの 言 葉 に 託 していたのである。そ<br />
して、 外 見 上 一 人 で 思 索 しているように 見 えるときでさえ、それは 神 を 観 想 するという 受 身 の 状 態 で<br />
はなく、「 自 分 自 身 を 伴 った 対 話 」という 能 動 的 な 活 動 力 なのではないか、というのが、さらなるアー<br />
レントの 問 いだった。 言 い 換 えれば、アーレントはここで 精 神 の 活 動 力 があること、それが 問 題 化 さ<br />
れるべきであることを 示 したのだ。「カトーが 正 しかったと 仮 定 しよう。そのとき、 問 いは 明 らかである。<br />
我 々がなにも 為 さずただ 考 えているとき、 我 々はなにを『 為 す』のか 普 通 は 常 に 仲 間 に 囲 まれ<br />
ている 私 達 が、 誰 も 伴 わず 自 分 自 身 と 共 にあるとき、 我 々はどこにいるのか」 115<br />
112 ARENDT, The Life of the Mind: One/ Thinking (op.cit.), p.6. ( 前 掲 訳 書 、6 頁 。 但 し 橋 爪 が 訳 しなおした。)<br />
113 ARENDT, The Human Condition (op.cit.), p.325 ( 前 掲 訳 書 、504 頁 )に 引 用 されている。また、ARENDT, The Life<br />
of the Mind: One/ Thinking (op.cit.), pp.7f. ( 前 掲 訳 書 、10 頁 )に 再 引 用 されている。 訳 文 は、アーレントによる 英<br />
訳 を 参 照 しつつ、 彼 女 が 引 用 しているラテン 語 の 原 文 から 直 截 訳 した。<br />
114 ARENDT, Vita activa (ebenda), S.415.<br />
115 ARENDT, The Life of the Mind, One: Thinking (op.cit.) p.8.<br />
28
アーレントはこうして、「 精 神 的 生 活 」という 問 題 に 至 りついた。 受 動 性 としての 観 想 的 生 活 から、<br />
精 神 の 活 動 力 という 能 動 性 へと、 問 いをシフトさせた。そして、 孤 独 における 観 想 から、 自 己 との 内<br />
話 としての 思 考 をこそ 問 題 化 するのだ。だが、アーレントが 実 際 思 考 、そして 精 神 的 活 動 力 というこ<br />
とでなにを 問 うたかは、ここでは 取 り 扱 わない。ここで 重 要 なのは、 本 論 を 大 きく 前 半 と 後 半 に 分 け<br />
る、 二 対 の 基 本 的 範 疇 があることである。すなわち、 活 動 的 生 活 と 精 神 的 生 活 がその 二 つであり、<br />
この 二 つの 区 別 が、アーレントの 時 間 論 においても 枢 要 な 区 別 として 立 ち 現 われてくるのだ。それ<br />
ゆえ 以 下 の 論 は、 先 ず 活 動 的 生 活 の 時 間 論 を 取 り 上 げ、 然 る 後 に 精 神 的 生 活 の 時 間 論 を 取 り 上<br />
げるという 構 図 を 取 ることとなる。<br />
29
本 論 部 アーレントの 時 間 論<br />
ウィータ・ア クティーワ<br />
第 一 部 活 動 的 生 活 の 時 間 性<br />
第 三 章 仕 事 work の 時 間 性<br />
兄 弟 たち、わたしはこう 言 いたい。 定 められた 時 は 迫 って<br />
います。<br />
――「コリントの 信 徒 への 手 紙 1」 7:29<br />
わたしがいまのべてきたことや、これからのべることは、 歴<br />
史 哲 学 にかんする 事 柄 にしても。 単 なる 前 提 事 項 というだ<br />
けでなく、 全 体 をながめわたしたあとに 得 られる 結 論 事 項<br />
、、、<br />
でもあって、その 結 論 をわたしが 知 っているのは、わたしが<br />
すでに 全 体 を 認 識 しているからです。<br />
――ヘーゲル『 歴 史 哲 学 講 義 』<br />
第 12 節 活 動 的 生 活 の 三 活 動 力 の 共 存<br />
『 人 間 の 条 件 』は、そもそも 活 動 的 生 活 vita activa の 研 究 であったとアーレント 本 人 は 言 っている<br />
116 。そこでは 主 に 活 動 的 生 活 が 問 題 となっており、 活 動 的 生 活 の 時 間 性 の 探 求 は、 基 本 的 には<br />
『 人 間 の 条 件 』の 読 解 において 行 なわれることとなる。(ただし、「はじまり」beginning の 問 題 ――こ<br />
れは、アーレントの 政 治 学 のなかでも 際 立 って 独 特 の 概 念 であるが――に 関 しては、『 革 命 につい<br />
て』On Revolution のなかで 更 に 具 体 的 に 扱 われているゆえ、 第 五 章 で 活 動 を 扱 う 際 は、そちらの<br />
著 作 にもあたることになるだろう。)<br />
さて、 活 動 的 生 活 には 三 つの 基 本 的 な 活 動 力 が 属 していることは 既 に 述 べた。この 第 一 部 では<br />
その 三 つの 活 動 力 にそれぞれ 固 有 の 時 間 経 験 があることを 示 し、かつそれぞれの 時 間 経 験 特 有<br />
の 性 格 というものを 浮 かび 上 がらせたい。ところで、これら 三 つの 活 動 力 は、それぞれ 相 互 にどのよ<br />
うに 連 関 しているのだろうか。そもそも、そのような 相 互 に 連 関 など 見 られるのだろうか。それら 活 動<br />
力 は 結 びつきがまったくなく、たがいにばらばらに 存 在 しているのだろうか。あるいは、 活 動 力 は 交<br />
替 的 に 現 われるのだろうか。 例 えば、 活 動 をしている 人 間 が、 活 動 を 停 止 して 仕 事 をはじめるという<br />
ことはありうるのだろうか。それとも「 活 動 」とは 或 る 人 間 に 特 有 の「 才 能 」であって、 仕 事 や 労 働 をす<br />
116 「 出 版 社 は、 私 の 研 究 を 賢 しらにも“ 人 間 の 条 件 ”と 呼 んだが、しかし 私 はより 控 えめに、それを“ウィータ・アクテ<br />
ィーワ”〔 活 動 的 生 活 〕の 探 究 として 意 図 していた」(ARENDT, The Life of the Mind: One/Thinking [op.cit.], p.6 〔 前 掲<br />
訳 書 、8 頁 〕)。<br />
30
る 人 間 は、 活 動 することはないのだろうか。ちょうど、 画 家 が 同 時 に 優 れたアスリートであることが 稀<br />
であるように。<br />
問 題 を 単 純 化 して 言 い 直 せば、そもそも 二 つ 以 上 の 活 動 力 が 一 つの 人 間 存 在 に 同 居 すること<br />
があるのだろうか、ということになろうが、あらかじめ 答 えるなら、この 問 いには「 然 り、 同 居 する」と 答<br />
えることになる。まず、アーレントによる 三 つの 基 本 的 活 動 力 の 説 明 を 思 い 出 したい。 曰 く、 労 働 ・ 仕<br />
事 ・ 活 動 という「 三 つの 活 動 力 が 基 本 的 だというのは、 人 間 が 地 上 の 生 命 を 得 た 際 の 根 本 的 な 条 件<br />
に、それぞれが 対 応 しているからである」 117 。その 人 間 の 条 件 human condition と、 対 応 する 三 つの<br />
活 動 力 の 内 容 をここで 軽 く 一 瞥 しよう。<br />
まず「 労 働 は、 人 間 の 肉 体 の 生 物 学 的 過 程 に 対 応 する 活 動 力 である。 人 間 の 肉 体 の 自 然 な 成<br />
長 、 新 陳 代 謝 、そして 最 終 的 な 衰 退 は、 労 働 によって 生 産 され、 生 命 過 程 へと 供 給 される 生 命 の<br />
必 要 物 〔vital necessities〕に 拘 束 されている。そこで、 労 働 の 人 間 的 条 件 は 生 命 それ 自 体 である」<br />
118 。 第 二 に 仕 事 は、「 人 間 的 実 存 〔human existence〕の 非 自 然 性 に 対 応 する 活 動 力 である。〔 略 〕 仕<br />
事 は、すべての 自 然 環 境 と 際 立 って 異 なる 物 の『 人 工 的 』 世 界 を 作 り 出 す。その 物 の 世 界 の 境 界<br />
線 の 内 部 で、それぞれ 個 々の 生 命 は 安 住 の 地 を 見 いだすのであるが、 他 方 、この 世 界 そのものは<br />
ワールドリネス<br />
それら 個 々の 生 命 を 超 えて 永 続 するようにできている。そこで、 仕 事 の 人 間 的 条 件 は 世 界 性 である」<br />
119 。 最 後 に、 活 動 は、「 物 あるいは 事 柄 の 介 入 なしに 直 接 人 と 人 との 間 で 行 われる 唯 一 の 活 動 力<br />
であり、 複 数 性 〔plurality〕という 人 間 の 条 件 、すなわち 地 球 上 に 生 き 世 界 に 住 むのが 大 文 字 の 人<br />
間 〔Man〕ではなく、〔 複 数 の〕 人 間 たち〔men〕であるという 事 実 〔the fact〕に 対 応 している。〔 略 〕この<br />
複 数 性 こそ、 全 政 治 生 活 の 条 件 であり、その 必 要 条 件 であるばかりか、 最 大 の 条 件 である」 120 。<br />
かくして、 三 つの 活 動 力 と、それに 対 応 する 三 つの 人 間 的 条 件 human conditions が 抽 出 された。<br />
人 間 存 在 が 生 物 学 的 な 生 命 をもつこと、 世 界 を 構 築 すること( 世 界 性 )、 複 数 で 存 在 していること<br />
( 複 数 性 )、 以 上 の 三 つをアーレントは 人 間 の 条 件 として 認 めるのである。アーレントは、 人 間 が 複<br />
フ ァ ク ト<br />
数 的 であることを「 事 実 」と 呼 んでいる 121 が、 実 際 、 上 の 条 件 は 全 て 人 間 存 在 にとっての「 事 実 性<br />
Faktizität」であり、 人 間 存 在 はその 事 実 に「 投 げ 込 まれている」という 意 味 で、それらの 人 間 的 条 件<br />
ファクティッシュ<br />
は 事 実 的 faktisch なのである。<br />
ところで、ハイデガーは、 現 存 在 ( 人 間 )の 存 在 性 格 について、 次 のように 言 っている。「それの 由<br />
来 と 帰 趣 については 暗 やみに 包 まれていて、それだけはいよいよ 露 骨 に 開 示 されている 現 存 在 の<br />
、、<br />
存 在 性 格 ――この《とにかくある》という 事 実 を、われわれはこの 存 在 者 の、その 現 のなかへの 被 投<br />
、<br />
性 (Geworfenheit)となづける。すなわち、 現 存 在 は、みずから 世 界 = 内 = 存 在 としておのれの 現 を<br />
存 在 するというありさまで、おのれの 現 のなかへ 投 げられているのである。 被 投 性 という 言 い 方 は、<br />
、、、、、、、、、、<br />
この 引 き 渡 しの 既 成 事 実 性 (Faktizität der Überantwortung)を 示 唆 しようとするものである」 122 。<br />
117 ARENDT, The Human Condition (op.cit.), p.7. ( 前 掲 訳 書 、19 頁 。)<br />
118 Ibid. ( 同 上 。)<br />
119 Ibid. ( 同 上 、19-20 頁 。)<br />
120 Ibid. ( 同 上 、20 頁 。)<br />
121 アーレントは、『ウィータ・アクティーワ』(ARENDT, Vita activa oder Vom tätigen Leben [ebenda], S.17)では、「 複 数<br />
性 という 事 実<br />
ファクトゥム<br />
」(das Faktum der Pluralität)という 言 い 方 をしている。<br />
122 HEIDEGGER, Sein und Zeit (ebenda), S.135. ( 前 掲 訳 書 、 上 、294 頁 。)<br />
31
フ ァ ク テ ィ ツ ィ テ ー ト<br />
おそらくアーレントの 人 間 の 条 件 は、ハイデガー 的 な 既 成 事 実 性 であり、その「 由 来 と 帰 趣 につ<br />
いては 暗 やみに 包 まれてい」るから、 問 うことは 出 来 ない。 人 間 存 在 はその 条 件 へと「 投 げ 込 まれて<br />
いる」(geworfen)。ハイデガーは、かような 世 界 内 存 在 としての 現 存 在 分 析 を、 存 在 論 一 般 に 至 る<br />
ための 準 備 として 行 う。この 現 存 在 の 実 存 論 的 分 析 論 (existenziale Analytik des Daseins)をハイデ<br />
ガーは 基 礎 的 存 在 論 (Fundamentalontologie)と 名 指 す 123 が、こういってよければアーレントの 政 治<br />
学 とは、ハイデガーの 基 礎 的 存 在 論 を 存 在 論 一 般 に 繋 げることなく、そこに 留 まって 徹 底 したもの<br />
である。<br />
、、、<br />
それはさておき、アーレントはその 基 本 的 条 件 を「 人 間 の条 件 」と 呼 んでいるのであるから、これ<br />
らの 三 つの 人 間 的 条 件 は、 人 間 であれば 誰 しもがそこへと 投 げ 込 まれているような、 誰 にでも 遍 く<br />
妥 当 するような 条 件 であるだろう。この 点 から、まずは 単 純 に、 人 間 にとって 三 つの 条 件 は 併 存 的<br />
であると 答 えねばならない。むしろ 逆 に、そこから 脱 却 することは 人 間 存 在 にとっては、(さしあたり)<br />
不 可 能 である。そして 人 間 にとってそれらの 条 件 が 併 存 的 に 存 在 しているという 事 実 から、それぞ<br />
れに 対 応 する 諸 活 動 力 もまた、 人 間 存 在 にとって 併 存 的 に 備 わっていなければならない、というこ<br />
とができる。かくして、 端 的 には、 三 つの 活 動 力 が 同 居 し 得 る、むしろ 同 居 せざるを 得 ないということ<br />
が、 明 らかとなった。<br />
人 間 には 三 つの 活 動 力 が 根 源 的 に 備 わっている。それは 人 間 の 条 件 という 被 投 性 のなかで、 自<br />
らの 可 能 性 を 活 動 力 において 投 企 しうることを 意 味 している。しかし、 無 論 ある 活 動 力 が 一 人 の 人<br />
間 のなかで 目 立 って 発 現 するということはあろう。 実 際 、ギリシア 人 やローマ 人 で 活 動 しえた 人 間 は、<br />
奴 隷 に 労 働 や 仕 事 を 押 し 付 けて 自 由 を 獲 得 した 家 父 長 たちであったし、 反 対 に 現 代 世 界 におい<br />
ては、いわば「 政 治 忘 却 」とでも 言 うべき、 活 動 の 後 退 が 見 られる。 物 作 り( 仕 事 )は 現 代 においては<br />
専 門 職 となっていたり、 機 械 の 仕 事 となっていたりする。 農 業 ( 労 働 )も 一 部 の 人 間 しか 従 事 してい<br />
ない。しかし、それでもやはり 各 々の 人 間 はそれぞれの 活 動 力 をいつも 発 揮 しているのだ。たとえ<br />
ば、 思 考 をノートに 書 きつける 作 業 も 実 は 仕 事 であるし、 調 理 や 掃 除 は 自 然 性 と 渡 り 合 う 人 間 的 能<br />
力 である 点 で 労 働 と 呼 ぶべきである。 他 方 出 来 上 がった 食 物 を 消 費 する 行 為 も、アーレントによれ<br />
ば 実 は 労 働 と 呼 ばれるべきものなのである。<br />
いずれにせよ、これ 以 降 の 活 動 力 分 析 のなかで 重 要 なことは、それぞれの 活 動 力 はなんら 特 別<br />
な 専 門 的 能 力 ではなく、あらゆる 人 間 のうちに 併 存 しているということである。それは 人 間 の 条 件 と<br />
渡 り 合 うための 人 間 的 能 力 であり、 可 能 性 である。<br />
第 13 節 仕 事 = 制 作 ――ハイデガーにおける 制 作 の 概 念<br />
我 々は、 個 別 の 活 動 力 に 備 わる 時 間 性 を 分 析 してゆこうと 思 うが、その 際 先 ずアーレントが 仕 事<br />
work と 名 指 す 活 動 力 から 取 り 上 げたい。しかし、アーレントは『 人 間 の 条 件 』において 三 つの 活 動<br />
力 を 語 る 際 、 労 働 ・ 仕 事 ・ 活 動 という 順 序 で 論 を 展 開 している。その 順 序 に 些 か 逆 らうことになるが、<br />
そのことの 妥 当 性 はあるのだろうか。 逆 に 問 えば、アーレントが 三 つの 活 動 力 を 取 り 上 げたその 順<br />
番 は、 果 たして 妥 当 だったのだろうか。<br />
123 Ebenda, S.13. ( 前 掲 訳 書 、50 頁 。)<br />
32
ところで、アーレントは 仕 事 work という 活 動 力 を 頻 繁 に 制 作 fabrication と 言 いかえているし、また<br />
ドイツ 語 版 『ウィータ・アクティーワ』においては 仕 事 の 活 動 力 を「 仕 事 Werk」と 呼 ぶことはなく、 制 作<br />
Herstellen と 呼 びなおしている。<br />
この 制 作 という 表 現 は、ある 種 の 活 動 力 を 表 わすのに、アリストテレス 以 来 用 いられているもので<br />
あった。すでにハイデガーにおける 観 想 的 生 活 と 政 治 的 生 活 のアリストテレス 的 分 節 を 問 題 にした<br />
際 にも 取 り 上 げた、ポイエーシス ποιήσις という 活 動 力 がそれである。「 人 間 の 行 為 を、 行 為 そのもの<br />
を 目 的 とする 実 践 praxis と、 行 為 は 手 段 であり、その 結 果 生 み 出 されるものを 目 的 とする 制 作<br />
poiesis に 区 分 することは、ギリシャ 以 来 知 られたことであり、そして、この 区 別 は 今 日 においてもな<br />
おしばしば 踏 襲 される」 124 。このあたりの 事 情 は 既 に 見 たとおりであるが、ここでもやはりハイデガー<br />
の 考 えを 参 照 すると、 制 作 Herstellung という 概 念 が 持 つ 射 程 が 明 らかになるだろう。ハイデガーに<br />
おいては、まさしく 存 在 をどう 捉 えるかという 存 在 論 的 な 文 脈 において 制 作 の 問 題 も 立 ち 上 がって<br />
来 る。<br />
ハイデガーの 主 張 とは、「 古 代 存 在 論 、つまりプラトン/アリストテレスの 哲 学 の 基 本 概 念 はすべ<br />
て 人 間 の 制 作 行 為 に 定 位 して 形 成 されているのであり、それに 照 らしてはじめて 理 解 可 能 になる」<br />
125 というものであった。ふつう、ギリシア 人 は「イデア( 形 )の 観 取 に 人 間 精 神 の 最 高 の 境 位 を 見 るプ<br />
テオーリア<br />
ラトンの 教 説 などからしても、きわめて 視 覚 的 で 観 照 的 な 民 族 とみなされているが、ハイデガーはギ<br />
ポ イ エ イ ン<br />
リシア 哲 学 がその 基 本 概 念 の 形 成 にあたって 定 位 したのは 制 作 行 為 〔ポイエーシスの 動 詞 形 不 定<br />
法 〕だと、まったく 逆 の 主 張 をする」 126 。ハイデガーはこのような 主 張 を、 古 代 哲 学 の 基 本 概 念 を<br />
一 々 確 かめることを 通 して 裏 付 けているそうだが 127 エ イ ド ス ヒ ュ レ<br />
、ここでは 所 謂 「 形 相 」と「 質 料<br />
ー」に 関 する 説 明 の<br />
みを、 木 田 元 の 解 説 に 依 りながら 参 看 しよう。<br />
エイドス テオレイン<br />
ギリシア 人 の 考 えでは、〔 略 〕〈 形 〉は 魂 の 眼 によって 観 取 される。〔 略 〕ハイデガーによれば、<br />
ポイエーシス<br />
ギリシア 的 〈 制 作 〉の 本 領 は、〔 略 〕〈イデア〉を 観 取 し、それをこちらに 招 き 寄 せ、 眼 前 の<br />
ヒ ュ レ エ イ ド ス ヒ ュ レ ー<br />
〈 材 料<br />
ー〉のうちに 据 えるところにこそあるのである。 言 うまでもなく、〈 形 ・ 形 相 〉と〈 材 料 ・ 質 料 〉と<br />
いう 対 概 念 も、この 制 作 の 場 面 ではじめて 生 まれてきたものである。 128<br />
さらにハイデガーは、アリストテレスが「 存 在 」を 表 示 するために「ウーシア οὐσία」という 語 を 用 いて<br />
いる 点 に 注 目 する。ウーシアは「エイナイ εἶναι」(ある)という 動 詞 の 現 在 分 詞 女 性 形 に 由 来 するた<br />
め、 勿 論 「 存 在 」という 意 味 に 通 ずるのだが、「 当 時 の 日 常 語 では〈 家 屋 敷 ・ 財 産 〉を 指 していた」 129 。<br />
124<br />
田 崎 、 前 掲 書 、90 頁 。<br />
125<br />
木 田 元 『ハイデガーの 思 想 』 岩 波 新 書 、1993 年 、118-119 頁 。<br />
126<br />
同 上 、119 頁 。<br />
127 μορφή( 格 好 )、εἶδος( 形 相 )、ἰδέα(イデア)、τὸ τί ἦν εἶναι(なにであったか= 本 質 )、γένος( 種 )、ὅρος( 定 義 )、<br />
ὅρισμος( 定 義 )といった 概 念 である( 木 田 、 前 掲 書 、119 頁 以 下 )。 括 弧 内 に 示 した 各 概 念 の 訳 語 は、 出 隆 によるも<br />
のを 取 った(アリストテレス、 出 隆 訳 『 形 而 上 学 』 上 下 、 岩 波 文 庫 、1959-1961 年 )。<br />
128<br />
木 田 、 前 掲 書 、120 頁 。<br />
129<br />
同 上 、123 頁 。<br />
33
なぜこのような 日 常 語 に 類 する 単 語 を 抽 象 的 な「 存 在 」という 概 念 に 充 てたのか そこには「アリス<br />
トテレスの、さらには 古 代 ギリシア 哲 学 に 特 有 な〈 存 在 了 解 〉がうかがわれる〔 略 〕。つまり、とくにそう<br />
した 意 味 をもつ 日 常 語 を 選 んで〈 存 在 〉を 指 す 術 語 に 使 ったということは、 彼 が 家 や 財 産 のもつよう<br />
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、<br />
な『 被 制 作 性 にもとづいて 存 在 者 にそなわるようになったその 使 用 可 能 性 ないしその 現 前 性 』を 存<br />
在 者 の 基 本 的 な 在 り 方 と 見 ていたからにちがいない」( 傍 点 は 橋 爪 ) 130 。<br />
ヘアゲシュテルトハイト ヘアシュテレン<br />
被 制 作 性 Hergestelltheit とは、 文 字 通 りに「 制 作 Herstellenされてあること」を 意 味 する。それが<br />
「 現 前 性 」と 同 質 に 語 られるのは、ハイデガーの「 考 えている〈 現 前 性 〉〔Anwesenheit〕とは、〈 制 作 さ<br />
れ 終 わって、それ 自 体 で 自 立 して 存 在 し、いつでも 使 用 されうる 状 態 で 眼 前 に 現 前 している〉という<br />
ことにほかならない」 131 ためである。ここで 制 作 が 存 在 論 と 結 びつく。 彼 は「 存 在 = 被 制 作 性 」という<br />
存 在 概 念 がギリシア 哲 学 に 備 わっていることを 見 出 したのだ。この 存 在 概 念 が、それ 以 降 の 存 在 論<br />
の 歴 史 を 全 て 規 定 している。だが、 彼 によるとここに 既 に 存 在 の 捉 え 損 ないが 萌 している。なぜなら<br />
なかんずく<br />
被 制 作 性 とは 存 在 者 の―― 就 中 人 間 の 道 具 の―― 存 在 様 式 であって、それを 以 って 存 在 を 語 る<br />
のはすでにしてカテゴリーエラーであるからだ。ハイデガーはそれゆえ 道 具 の 存 在 様 式 に 関 しての<br />
詳 細 な 分 析 を、『 存 在 と 時 間 』で 行 っている。<br />
話 を 戻 せば、 実 はアーレントの 仕 事 work= 制 作 Herstellen という 概 念 にはこれだけの 思 想 史 的<br />
重 みがある、という 点 が 重 要 である。 実 際 アリストテレスにおける 人 間 の 行 為 の 区 分 は「 観 想 」「 制 作 」<br />
「 実 践 」であり、これはそれぞれ『 人 間 の 条 件 』における「 思 考 」「 仕 事 」「 活 動 」と 対 応 する。じつは<br />
「 労 働 」というのは、むしろマルクスらにおいて 詳 細 に 論 じられた 活 動 力 であり、そういう 意 味 ではひ<br />
とつだけ 近 代 的 な 概 念 である(アリストテレスにおいて 労 働 は 奴 隷 に 属 するものであった)。そのた<br />
め、アーレントは 労 働 を 自 らの 思 考 のなかに 位 置 づける 上 で、 仕 事 ( 制 作 )との 関 係 において 定 義<br />
したりする 場 面 が 多 い。アーレントは 制 作 というハイデガーの 概 念 を 継 承 しつつ、それを 変 奏 して、<br />
自 己 の 概 念 に 育 てて 行 ったのであるが、 労 働 に 関 して 対 応 する 概 念 は、 管 見 の 限 りハイデガーの<br />
うちには 見 られない 132 。だからアーレントは 労 働 を 三 つの 活 動 力 のうちで 最 初 の 章 に 充 てておきな<br />
130<br />
同 上 、123-124 頁 。<br />
131<br />
同 上 、124 頁 。<br />
132<br />
若 干 の 先 取 りになるが、 労 働 は 人 間 の 生 命 に 対 応 する 活 動 力 であり、 端 的 に 言 えば「パンを 作 る」 能 力 、すなわ<br />
ち 食 べなければ 生 きられない 生 命 としての 人 間 が、 食 料 を 生 み 出 していく 活 動 力 である。このような 活 動 力 は、ハイ<br />
デガーにおいては 殆 ど 見 られてないと 言 っていい。レヴィナスがいうように、「ハイデガーの 現 存 在 は 飢 えを 知 らな<br />
い Le Dasein chez Heidegger n’a jamais faim」。レヴィナスは 言 う。「 世 界 という 概 念 を 諸 対 象 の 総 和 の 概 念 から 分 離<br />
する 試 みのうちに、 私 たちは 躊 躇 なくハイデガー 哲 学 のもっとも 深 遠 な 発 見 のひとつをみとめる。しかし『 世 界 ‐ 内 ‐<br />
存 在 』を 記 述 するために、このドイツ 人 哲 学 者 はほかでもない 存 在 論 的 合 目 的 性 の 助 けを 求 め、その 合 目 的 性 に 世<br />
界 内 の 諸 対 象 を 従 属 させるのだ」。しかし「 世 界 内 に 与 えられているものがすべて 道 具 なのではない。『 兵 営 』の 宿<br />
舎 や 掩 蔽 壕 は、 軍 隊 の 兵 站 部 にとっては〈 糧 〉である。 兵 隊 にとっては、パンや 上 着 やベッドは 資 材 ではない。それ<br />
は『のための』ものではなく、それ 自 体 が 目 的 なのだ。〔 略 〕 食 物 にいたってはなおのこと、『 資 材 』のカテゴリーには<br />
入 らない」(LÉVINAS, Emmanuel. 西 谷 修 訳 『 実 存 から 実 存 者 へ』ちくま 学 芸 文 庫 、2005 年 、86-87 頁 )。「 対 象 がぴっ<br />
たりと 欲 望 と 符 合 するというこの 構 造 は、 私 たちの 世 界 ‐ 内 ‐ 存 在 総 体 を 特 徴 づけている。いたるところで 行 為 の 対 象<br />
は、 少 なくとも 現 実 のなかでは、 実 存 することへの 気 遣 いには 結 びつかない。 私 たちの 実 存 をなしているのはこの 行<br />
為 の 対 象 なのである。 私 たちは 呼 吸 をするために 呼 吸 し、 飲 みかつ 食 らうために 飲 み 食 いし、 雨 を 避 けるために 雨<br />
、、、<br />
宿 りし、 好 奇 心 を 満 足 させるために 学 び、 散 歩 するために 散 歩 する。それらすべては 生 きるためにあるのではない。<br />
そのすべてが 生 きることなのだ。 生 きるとは 真 摯 さだ」( 同 上 、89 頁 )。「 世 界 を 日 常 的 と 呼 び、それを 非 ‐ 本 来 的 なも<br />
のとして 断 罪 することは、 飢 えと 渇 きの 真 摯 さを 見 誤 ることだ」( 同 上 、91 頁 )。<br />
アーレントは 労 働 を 概 念 化 することを 通 して、レヴィナスの「 現 存 在 は 飢 えを 知 らない」というハイデガー 批 判 に、<br />
34
がら、 仕 事 という 活 動 力 と 対 比 させながら 定 義 してゆくという、 些 か 回 りくどい 道 のりを 取 らざるを 得<br />
なかったのではないかと 思 う。 本 当 は 仕 事 から 展 開 していった 方 が 体 系 的 な 記 述 として 筋 の 通 った<br />
ものになったのではないかとまで 思 わせるが、それはさておくとして、 本 論 文 では 仕 事 ( 制 作 )という<br />
活 動 力 を 最 初 に 取 り 上 げるのはこのような 理 由 からなのである。<br />
第 14 節 「 世 界 」の 概 念 ―― 物 の 世 界 性<br />
アーレント 自 身 は 仕 事 をどのように 定 義 しているか。<br />
仕 事 〔work〕は 人 間 的 実 存 〔human existence〕の 非 自 然 性 に 対 応 する 活 動 力 である。 人 間 的<br />
実 存 は、〔 人 間 という〕 種 の 永 遠 に 続 く 生 命 循 環 〔the species’ ever-recurring life cycle〕にはめ<br />
込 まれていることはなく、その 必 死 性 は、 種 の 生 命 循 環 が 永 遠 だということによって 慰 められる<br />
、、 、、、 、、<br />
ものでもない。 仕 事 は、すべての 自 然 環 境 と 際 立 って 異 なる 物 の「 人 工 的 」 世 界 を 作 り 出 す。<br />
その 物 の 世 界 の 境 界 線 の 内 部 に、それぞれ 個 々の 生 命 は 住 まうのであるが、 他 方 、この 世 界<br />
そのものはそれら 個 々の 生 命 を 超 えて 存 続 し、 超 越 するよう 意 図 されている。そこで、 仕 事 の<br />
ワールドリネス<br />
人 間 的 条 件 は 世 界 性 である。〔 強 調 は 橋 爪 〕 133<br />
アーレントが 仕 事 という 活 動 力 を 定 義 する 際 の 強 調 点 は、「 物 thing」、そして「 世 界 world」にある。<br />
仕 事 は「 物 の『 人 工 的 』 世 界 」を 生 産 するというのだ。その 際 、 物 が 持 つ 世 界 を 構 築 する 力 が 重 要 に<br />
なる。 後 に 扱 う 労 働 との 違 いが 際 立 つひとつの 点 も、この 点 である。というのは、「 労 働 と 仕 事 の 区<br />
別 は、もし 生 産 された 物 〔produced things〕の 世 界 的 性 格 〔worldly character〕―― 世 界 においてそ<br />
れが 占 める 場 所 、 機 能 、 滞 在 期 間 ――が 考 慮 に 入 れられなければ、 実 際 単 なる 程 度 の 差 でしかな<br />
くなる」し、「 世 界 における『 平 均 余 命 』がほとんど 一 日 をでないようなパンと 人 間 の 数 世 代 以 上 も 楽<br />
に 生 き 残 ることのできるテーブルとの 相 違 は、もちろん、パン 屋 と 指 物 師 の 相 違 よりもはるかに 明 白<br />
であり、 重 要 である」 134 からだ。つまり、 仕 事 の 生 産 物 は、 世 界 に 長 く 存 在 する。それゆえ「 仕 事 とそ<br />
の 生 産 物 である 人 間 の 工 作 物 〔human artifact〕は、 死 すべき 生 命 の 空 しさと 人 間 的 時 間 のはかな<br />
い 性 格 に 一 定 の 永 続 性 〔permanence〕と 持 続 性 〔durability〕を 与 える」 135 というわけだ。すなわち、<br />
物 は、 個 々の 人 間 の 生 命 を 超 えて 存 続 する 世 界 を 構 成 するものとなるのである。<br />
別 のかたちで 応 答 しているとも 言 うことが 出 来 る。<br />
レヴィナスは、 上 の 議 論 に 続 けて、「 経 済 的 人 間 から 出 発 するマルクス 主 義 哲 学 の 偉 大 な 力 は、 説 教 の 欺 瞞 を 徹<br />
底 的 に 排 するその 能 力 にある」と 讃 える( 同 上 )。「 志 向 の 真 摯 さ、 飢 えと 渇 きという 一 途 な 善 意 のなかに 身 を 置 いて、<br />
この 哲 学 が 提 起 する 闘 争 と 犠 牲 的 行 為 の 理 想 、そしてこの 哲 学 が 誘 う 文 化 は、これらの 志 向 の 延 長 にほかならない。<br />
マルクス 主 義 がひとを 魅 了 しうるのは、それが 自 称 唯 物 論 だからではなく、この 提 言 とこの 誘 いが 保 持 している 本 質<br />
的 な 真 摯 さのためである」( 同 上 )。アーレントもまた、 労 働 という 活 動 力 に 気 づいた( 正 確 に 言 えば、 労 働 と 制 作 の<br />
区 別 に 気 づいた)のは、マルクス( 主 義 ) 研 究 を 通 してであると 伝 えられる( 例 えば、 森 川 輝 一 『〈 始 まり〉のアーレント<br />
「 出 生 」の 思 想 の 誕 生 』 岩 波 書 店 、2010 年 、 第 4 章 第 1 節 を 参 照 されたい)。ここでレヴィナスとアーレントは、 現 存 在<br />
批 判 という 第 三 項 によって 邂 逅 する。<br />
133 ARENDT, The Human Condition (op.cit.) p.7. ( 前 掲 訳 書 、19-20 頁 。)<br />
134 Ibid., p.94. ( 前 掲 訳 書 、147 頁 。)<br />
135 Ibid., p.8. ( 前 掲 訳 書 、21 頁 。)<br />
35
ここで、 勿 論 世 界 world という 概 念 にも 注 意 しなくてはならないだろう。アーレントが 世 界 という 単<br />
語 を 使 うとき、やはりそれは 現 象 学 や 基 礎 的 存 在 論 に 由 来 する 特 別 な 意 味 合 いを 持 っているから<br />
だ。アーレントは 言 う。<br />
ここでいう 世 界 とは 地 球 とか 自 然 のことではない。 地 球 とか 自 然 は、 人 びとがその 中 を 動 き、 有<br />
機 的 生 命 の 一 般 的 条 件 となっている 限 定 的 空 間 にすぎない。むしろ、ここでいう 世 界 は、 人 間<br />
の 工 作 物 や 人 間 の 手 が 作 った 製 作 物 に 結 びついており、さらに、この 人 工 的 な 世 界 に 共 生 し<br />
ている 人 びとの 間 で 進 行 する 事 象 に 結 びついている。 136<br />
それゆえここでハイデガーにおける 世 界 Welt の 概 念 を 想 起 しておくことは、 無 益 ではないだろう。<br />
ハイデガーにおいては、 現 存 在 ( 人 間 存 在 )は、まさに 世 界 内 存 在 In-der-Welt-sein という 存 在 構 成<br />
Seinsverfassung をもっていた 137 。 世 界 内 存 在 は 存 在 論 的 な 現 存 在 の 構 成 であって、 彼 はそのこと<br />
を「 世 界 性 Weltlichkeit」と 名 指 す。この 世 界 性 を 具 体 的 に 考 察 するさい、 彼 は「 道 具 Zeug」の 分 析<br />
に 着 手 する。 前 節 で 触 れた 被 制 作 的 存 在 者 は、『 存 在 と 時 間 』にあってはまさに 道 具 として 描 かれ<br />
ているので、ここで 世 界 性 の 意 味 と、 被 制 作 性 の 意 味 とが 同 時 に 明 らかとなる。<br />
厳 密 な 意 味 では、ひとつだけの 道 具 は 決 して「 存 在 」しない。 道 具 が 存 在 するには、いつもす<br />
でに、ひとまとまりの 道 具 立 て 全 体 がなければならない。この 道 具 がまさにこの 道 具 であるのは、<br />
このような 道 具 立 て 全 体 においてなのである。 道 具 というものは 本 質 上 、《……するためにある<br />
もの》(»etwas, um zu…«)である。 138<br />
この「するためにある」»Um-zu«という 指 示 に 従 うとき、すなわち 物 が 道 具 として 用 いられるとき、その<br />
道 具 に 特 有 の 便 利 さが 発 見 される。ハイデガーは「 道 具 がこのようにそれ 自 身 の 側 から 現 われてく<br />
るような 道 具 の 存 在 様 態 を、〔 略 〕 用 具 性 〔Zuhandenheit〕となづける」 139 。 世 界 のなかで 出 会 われる<br />
物 は 用 具 的 zuhanden であり、それゆえ「 手 元 に 備 わる zuhanden」ものである。このような 道 具 と 交 渉<br />
する 態 度 を 彼 は 配 慮 Besorgen と 呼 び、このように 道 具 を 指 示 関 係 において 見 る 見 方 を 配 視<br />
Umsicht というが、「 世 界 = 内 = 存 在 とは、 道 具 全 体 の 用 具 的 存 在 にとって 構 成 的 な 機 能 をもつさ<br />
まざまな 指 示 関 係 のなかへ、 非 主 題 的 に 配 視 的 に 融 けこんでいることである」 140 。つまり、 世 界 内 存<br />
、、、、、<br />
在 は、 道 具 の 指 示 関 係 のなかに、その 指 示 関 係 に 気 付 かずに親 しみきっているのだ。「 世 界 とは、<br />
、、、、、、<br />
現 存 在 が 存 在 者 としていつもすでに『そのなかで』 存 在 してきたところ」 141 であり、 上 で 述 べたような<br />
136 Ibid,. p.52. ( 前 掲 訳 書 、78 頁 。)<br />
137 アーレントにおいて、 世 界 が 地 球 や 自 然 を 意 味 しなかったのと 同 様 、ハイデガーもまた、「 世 界 のなかにある」と<br />
いうことを、 単 純 に 世 界 という「 空 間 」の 内 部 にあることと 解 釈 してはならないと 注 意 を 向 ける。ハイデガーはそのよう<br />
な 単 純 に 或 る 空 間 の 中 にあることを 内 部 性 Inwendigkeit と 呼 び、 存 在 論 的 な 世 界 内 存 在 と 鋭 く 区 別 している。<br />
138 HEIDEGGER, Sein und Zeit (ebenda), S.68. ( 前 掲 訳 書 、 上 、162 頁 。)<br />
139 Ebenda, S.69. ( 同 上 、163 頁 。)<br />
140 Ebenda, S.76. ( 同 上 、177 頁 。)<br />
141 Ebenda. ( 同 上 。)<br />
36
指 示 関 係 の 全 体 性 である。「すなわち、それ〔 現 存 在 〕が 存 在 するとともに、 本 質 上 すでに、ひと 組<br />
の 用 具 的 なものの 連 関 が 発 見 されている。 現 存 在 は、それが 現 に 存 在 しているかぎり、いつもすで<br />
に 自 己 をそこで 出 会 う『 世 界 』へ 向 けて 委 ねている」 142 。そしてそのような 道 具 は、 制 作 されてある<br />
hergestellt という 存 在 様 態 を 持 っている。(ここでハイデガーの 古 代 存 在 論 批 判 の 意 義 が 浮 かび 上<br />
がる。 存 在 を 被 制 作 性 と 捉 えるとき、それは 道 具 の 存 在 を 問 うているに 過 ぎない。)<br />
アーレントが、 物 は 世 界 性 をもつという 言 い 方 をするとき、このハイデガーの 世 界 性 の 概 念 のもと<br />
にその 意 味 を 理 解 してもよいと 思 う(もちろん 差 異 は 存 在 するが、ここではその 問 題 は 措 こう)。 彼 女<br />
はそういう 側 面 をあまり 強 調 しないが、 世 界 内 存 在 としての 人 間 が、そのなかで 生 きるところの、 意<br />
味 全 体 性 が 世 界 である。 彼 女 がハイデガーよりも 一 歩 進 んだのは、ハイデガーにおいてはそのよう<br />
な 世 界 を 構 成 する 契 機 が 明 らかとなっていなかったのに 対 し、その 契 機 を 仕 事 という 人 間 的 活 動 力<br />
に 基 づいて 分 析 するのに 成 功 した 点 であろう。 仕 事 という 工 作 物 を 生 み 出 す 活 動 力 が、 同 時 に 世<br />
界 を 建 設 する 力 にもなっているのである。 彼 女 は 仕 事 ( 制 作 )という 活 動 力 そのものの 分 析 を 展 開 し<br />
て、 世 界 の 構 築 の 場 面 に 立 ち 会 うのだ。<br />
ついでに 言 及 しておけば、 物 が 世 界 性 を 持 ち、 世 界 を 構 築 しうるのは、 物 が 持 続 性 durability,<br />
Dauerhaftigkeit を 持 つためであると 述 べたけれども、 物 はその 持 続 性 の 性 質 ゆえに「 客 観 性<br />
objectivity」という 性 質 をも 持 っている。<br />
世 界 の 物 は、たしかに、 人 間 が 生 産 し、 使 用 するものである。しかし、 世 界 の 物 がその 人 間<br />
から 相 対 的 に 独 立 しているのは、〔 略 〕 持 続 性 〔durability〕のおかげである。しかも、 世 界 の 物<br />
は、それを 作 り 使 用 する 生 きた 人 間 の 貪 欲 な 欲 求 や 欲 望 にたいし、 少 なくともしばらくの 間 は<br />
抵 抗 し、「 対 立 し〔stand against〕」、 持 ちこたえることができる。それは、 世 界 の 物 の「 客 観 性<br />
〔objectivity〕」のゆえである。この 視 点 から 見 ると、 世 界 の 物 は、 人 間 生 活 を 安 定 させる 機 能 を<br />
もっているといえる。なるほどヘラクレイトスは、 人 間 は 二 度 と 同 じ 流 れの 中 に 入 ることはできな<br />
いといったし、 人 間 の 方 も 絶 えず 変 化 する。それにもかかわらず、 事 実 をいえば、 人 間 は、 同<br />
じ 椅 子 、 同 じテーブルに 結 びつけられているのであって、それによって、その 人 間 の 同 一 性 、<br />
すなわち、そのアイデンティティを 取 り 戻 すことができるのである。 世 界 の 物 の「 客 観 性 」という<br />
、、、、、、、、、、、、、、、 、、、、、、<br />
のはこの 事 実 にある。いいかえると、 人 間 の 主 観 性 に 対 立 しているのは、〔 略 〕 人 工 的 世 界 の<br />
、、、、、、、、<br />
客 観 性 なのである。〔 傍 点 は 橋 爪 〕 143<br />
142 Ebenda, S.87.( 同 上 、200 頁 。)<br />
143 ARENDT, The Human Condition (op.cit.), p.137. ( 前 掲 訳 書 、224-225 頁 。) 私 はここで、 邦 訳 では「 耐 久 性 」と<br />
訳 されている durability を、 持 続 性 の 語 で 訳 しなおした。 世 界 の 中 で 簡 単 には 毀 損 されないという 物 の 性 質 を 表 現<br />
する 上 で 耐 久 性 とするのは 分 かりやすいが、 反 面 その 語 が 含 み 持 つ 哲 学 的 な 含 意 が 損 なわれてしまうからだ。<br />
この durability という 語 は、 一 目 見 てわかるように、 英 語 の duration やフランス 語 の durée、ラテン 語 の duratio と 語<br />
源 を 共 有 している。これらの 語 は 普 通 「 持 続 」と 訳 される。この 語 はベルクソンが 独 特 の 意 味 を 与 えたことでよく 知 ら<br />
れるが、 本 来 持 続 とは、「 一 定 の 対 象 、 表 象 内 容 、 体 験 などが 時 間 的 に 維 持 されること。すなわち 一 般 に 継 起<br />
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、<br />
Sukzession が 時 間 における 変 化 交 替 を 意 味 するのにたいし、 持 続 はむしろかかる 継 起 を 通 じて 同 一 性 が 保 たれる<br />
、、、、、<br />
ことをいう」( 荒 川 他 編 『 哲 学 辞 典 』〔 前 掲 〕「 持 続 」の 項 〔 強 調 は 橋 爪 〕)。つまり、 時 間 の 変 化 に 絶 えて 不 変 のものこそ、<br />
持 続 するものなのだ。だから「スコラ 哲 学 者 は 持 続 を 存 在 の 不 易 性 とみ、カントはこれを 実 体 の 範 疇 におけるア・プリ<br />
オリな 原 則 であると 考 えた」( 同 )。<br />
37
物 は、「 客 観 性 」objectivity を 持 つ。なぜなら、それは 耐 久 性 を 備 えるからである。つまり、 人 間 の 欲<br />
望 や 思 考 に 対 して、 独 立 した 立 ち 位 置 を 持 ち、さらに 言 えば 人 間 に「 対 立 する」 144 。それゆえ 人 間<br />
マ テ リ ア ル<br />
たちがその 中 に 住 まうところの 世 界 を 構 築 することが 出 来 るのだ。さらに、 物 はその 質 料 的 な 性 質<br />
のゆえに、 人 間 に「リアリティ」を 与 える。 工 作 物 が 世 界 性 を 備 えているということのもう 一 つの 意 味<br />
は、 工 作 物 が 人 間 にリアリティを 与 えているということでもあるのだ。「 人 間 世 界 のリアリティと 信 頼 性<br />
は、なによりもまず、 私 たちが、 物 によって 囲 まれているという 事 実 に 依 存 している。なぜなら、この<br />
物 というのは、それを 生 産 する 活 動 力 よりも 永 続 的 であり、 潜 在 的 にはその 物 の 作 者 の 生 命 よりも<br />
はるかに 永 続 的 だからである」 145 。 人 間 のリアリティは、 物 が 耐 久 性 を 備 え、 持 続 的 に 存 在 するとい<br />
う 点 から 生 まれてくる。 仕 事 とは、そのような 物 を 生 み 出 す 活 動 力 なのであり、その 物 からなる 世 界<br />
を 構 築 する 能 力 でもある。<br />
このように 見 てくると、アーレントの 仕 事 の 議 論 は、ハイデガーの 世 界 内 存 在 ―― 配 慮 する 世 界<br />
内 存 在 ――の 議 論 の 焼 き 直 しであるかのようである。ならば 出 雲 春 明 が 言 うように、アーレントの<br />
「 制 作 は〔 略 〕ハイデガーの〔 略 〕 配 慮 に 対 応 して」 146 おり、「『 制 作 』はハイデガーの 言 う『 恒 常 的 事<br />
物 存 在 性 (ständige Vorhandenheit)』という 時 間 性 を 有 することが 判 然 となる」 147 と 言 って 差 し 支 えな<br />
いのだろうか<br />
いや、 時 間 性 に 関 してこのように 結 論 付 けるのはまだ 早 いだろう。 出 雲 は、 仕 事 の 活 動 力 が 生 み<br />
だす 物 の 持 つ 持 続 性 と、 仕 事 の 活 動 力 そのものの 時 間 性 とを 混 同 している。そこに 欠 けているの<br />
は、 前 述 のように、ハイデガーの『 存 在 と 時 間 』における 議 論 が 世 界 内 存 在 の 分 析 に 留 まっていた<br />
のに 対 し、アーレントにおいてはまさにその 世 界 を 構 築 する 契 機 たる 活 動 力 の 分 析 にまで 歩 を 進<br />
めたという 点 である。 我 々はこのような 物 の 世 界 を 生 み 出 す 仕 事 という 活 動 力 そのものが、いかなる<br />
ものであるかをみなくてはならないのだ。<br />
アーレントが、 物 が「 客 観 的 」であると 言 うことができるのは、 持 続 がこのようなスコラ 的 意 味 で 了 解 されているから<br />
であると 考 えられる。つまり 注 意 すべきはこの 物 の 特 異 な 時 間 性 なのだ。 本 来 は 実 体 や 存 在 を 表 現 していた 持 続 と<br />
いう 範 疇 が、このように 物 に 転 用 されることによって、 物 こそが 人 間 の 同 一 性 や 一 貫 性 の 根 拠 となるのである。このこ<br />
とはまた、アーレントが 人 間 的 実 存 をどこまでも 時 間 的 なものであると 捉 えていることとも、 無 関 係 ではないだろう。す<br />
べてが 変 化 する 時 間 的 世 界 において、 安 定 的 な 拠 り 所 となりうるのは、 物 の 持 続 性 なのだ。<br />
144<br />
対 立 する stand against という 表 現 は、object という 単 語 のエティモロジーから 得 られている。「このこと〔stand<br />
against〕は、 後 に 我 々の 言 う“object”がそこから 由 来 するところのラテン 語 の 動 詞 obicere において、また object に 当<br />
たるドイツ 語 の 単 語 Gegenstand において、 示 唆 されている。“object”は 文 字 どおりには『 投 げだされたもの』、『 対 置<br />
されたもの』を 意 味 する」(ARENDT, ibid., p.137, note 2 〔 前 掲 訳 書 、274 頁 、 注 (2)。 志 水 訳 のこの 箇 所 は 明 らかな 誤<br />
訳 が 含 まれている〕)。<br />
我 々は、ここで、アーレントが「 客 観 性 」という 言 葉 を 注 意 深 く 用 いていることにも 気 をつけたい。アーレントは「 客<br />
観 性 」という 表 現 を、 人 間 の 欲 望 によって 使 い 果 たされたり、 思 考 によって 容 易 に 変 形 されたりしない「 物 thing」の 性<br />
質 を 指 すのに 用 いている。これは 当 然 、カント 以 来 の 認 識 論 的 な 主 観 = 客 観 モデルの 乗 り 越 えの、ひとつの 試 みと<br />
見 ることが 出 来 るであろう。しかしここでは 深 く 立 ち 入 らない。<br />
145 ARENDT, ibid., pp.95f. ( 前 掲 訳 書 、150 頁 。)<br />
146<br />
出 雲 春 明 「 活 動 の 時 間 性 ――H・アレント『 人 間 の 条 件 』 第 33、34 節 読 解 ――」『 倫 理 学 』23 号 、 筑 波 大 学 倫 理<br />
学 原 論 研 究 会 、2007 年 、194 頁 、 注 17。<br />
147<br />
同 上 、184 頁 。<br />
38
第 15 節 仕 事 の 目 的 論 的 性 格<br />
アーレントは、 三 種 類 の 活 動 力 それぞれに 対 して、 対 応 する 人 間 類 型 ないし 人 格 の 表 現 を 与 え<br />
ア ニ マ ル ・ ラ ボ ラ ン ス マン・オブ・アクション<br />
ている。 労 働 する 人 間 は「 労 働 スル 動 物 animal laborans」、 活 動 する 人 間 は「 活 動 の 人 man of<br />
ホモ・ファーベル<br />
action」と 呼 ばれ、 仕 事 という 活 動 力 に 対 応 する 人 間 類 型 のことは「 工 作 人 homo faber」と 呼 んでい<br />
る。 労 働 スル 動 物 と 活 動 の 人 に 関 しては、それぞれに 対 応 する 活 動 力 を 問 題 とする 際 に 触 れること<br />
にしよう。<br />
さて、 工 作 人 という 表 現 そのものはベルクソンに 由 来 する 148 が、ベルクソンとはことなり、アーレン<br />
トはそれを 根 本 的 な 人 間 規 定 と 位 置 付 けることはない 149 。 人 間 は 仕 事 ( 制 作 )という 活 動 力 を 行 使<br />
するときに 限 り、 工 作 人 であるのだと 言 えよう(あるいは、 人 間 は 端 的 に 工 作 人 のみであるのではな<br />
、、、、<br />
く、 工 作 人 でもあるのだ、と 言 ってもよい)。さてその「〈 工 作 人 〉の 仕 事 である 製 作 〔fabrication〕は、<br />
物 化 〔reification〕にある」 150 。このアーレントの 簡 潔 な 公 式 がなにを 意 味 するか―― 仕 事 という 活 動<br />
力 の 分 析 は、 端 的 に 言 ってこの 疑 問 を 解 くことに 終 始 する。<br />
リエフィケイション 、、 レース<br />
制 作 は 物 化 である。 物 = 化 rei-fy とは、 何 かを 物 res にすることである。 仕 事 work とは 何 かを<br />
物 thing にする 活 動 力 である。ここで 生 ずる 疑 問 は、 大 きく 三 つである。すなわち、なにを 物 にする<br />
のか 物 にするとはどういうことか 物 とはなにか このなかで、 第 三 の 疑 問 ――すなわち 物<br />
とはなにか――に 関 しては、 世 界 や 世 界 性 に 関 する 考 察 において、 実 質 的 には 答 えられていた。<br />
物 とは、 人 間 を 超 えて 存 続 するものであり、 時 間 論 的 にいえば 持 続 性 を 備 えているものであった。<br />
マ テ リ ア ル<br />
それは 人 間 の 思 考 から 独 立 するその 質 料 的 な 性 格 ゆえに 客 観 性 を 持 ち、その 客 観 性 ゆえに 世 界<br />
を 構 築 するものであった。<br />
、、<br />
それでは、なにを 物 にするのか。<br />
、、、、、、、<br />
アーレントによれば、 仕 事 は「 対 象 を 作 り 上 げる 際 に 従 うべきモデルに 導 かれて 行 なわれる」( 傍<br />
点 は 橋 爪 ) 151 。「このモデルは、 場 合 によっては、 精 神 の 眼 によって 見 られるイメージでもあろうし、ま<br />
た 場 合 によっては、イメージが 仕 事 による 物 化 をすでに 実 験 的 に 表 現 している 青 写 真 でもあろう」<br />
152 。この「 精 神 のイメージは、〔 略 〕 物 化 に 役 立 つ。 私 たちはあるイメージ、たとえばあるベッドの『イ<br />
デア』を 自 分 の 心 の 眼 の 前 に 思 い 浮 かべることなしにベッドを 作 ることなどできない」 153 。<br />
このイメージ、すなわち「イデア」こそが、 物 化 されるものである。「 製 作 の 仕 事 を 導 くもの」――す<br />
なわちイデア――「は 製 作 者 の 外 部 にあり、 実 際 の 仕 事 過 程 に 先 行 している」 154 。それは「 製 作 の<br />
148 たとえば、BERGSON, Henri, « Introduction (deuxième partie): De la position des problèmes », dans: La Pensée et<br />
le mouvant: Essais et conferences (op.cit.), pp.105ff. ( 河 野 与 一 訳 『 思 想 と 動 くもの』 岩 波 文 庫 、1998 年 、125 頁 以<br />
下 )。<br />
149 「どの 哲 学 者 も、ベルグソン 以 上 に 人 間 の 生 産 的 労 働 をこのように 高 く 位 置 づけ、よりふさわしくたたえたものは<br />
いない。ベルグソン 以 前 に、 人 間 がその 崇 高 さをたたえるのは 物 作 りにおいてであることをひじょうにはっきりとのべ<br />
た 者 はいない。ベルグソンのおかげで、ホモ・ファーベル〔ものを 作 る 人 〕はホモ・サピエンス〔 知 恵 のある 人 〕の 同 義<br />
語 となった」(TILGHER, Adriano, 小 原 耕 一 / 村 上 桂 子 訳 『ホモ・ファーベル―― 西 欧 文 明 における 労 働 観 の 歴 史 』<br />
社 会 評 論 社 、2009 年 、92-93 頁 )。<br />
150 ARENDT, The Human Condition (op.cit.), p.139. ( 前 掲 訳 書 、227 頁 。)<br />
151 Ibid., p.140. ( 前 掲 訳 書 、229 頁 。)<br />
152 Ibid. ( 前 掲 訳 書 、229-230 頁 。)<br />
153 Ibid., p.141. ( 前 掲 訳 書 、230-231 頁 。)<br />
154 Ibid., pp.140f. ( 前 掲 訳 書 、230 頁 。)<br />
39
始 まる 以 前 からすでに 存 在 し、 製 作 が 終 わった 後 にも 残 る。 要 するに、それは、 製 作 されて 存 在 す<br />
るに 至 ったすべての 使 用 対 象 物 〔use objects〕を 超 越 して 存 続 する」 155 。このイメージないしモデル<br />
の、このような 永 続 性 permanence の 経 験 は「 永 遠 のイデアというプラトンの 説 に 強 い 影 響 力 を 与 え<br />
た」 156 というアーレントの 説 明 は、 既 に 見 てきたハイデガーの 指 摘 と 軌 を 一 にするものである。プラト<br />
ポイエーシス<br />
ンがイデアやエイドスという 言 葉 を 使 ったのは、「 実 をいえば〔 略 〕 製 作 の 経 験 によっていた」 157 。そ<br />
れはさておき、 仕 事 の 活 動 力 は、その 明 確 な 始 まりをイデア=エイドスとして 持 っているということが<br />
明 らかとなった。<br />
仕 事 をする 人 間 ―― 工 作 人 ――は、それゆえ、 物 ( 使 用 対 象 物 )を 制 作 するために、 孤 立<br />
isolation しなくてはならない。 言 いかえれば、 複 数 の 人 間 ( 共 同 存 在 )を 離 れ、 一 人 にならなくては<br />
マスターシップ<br />
ならない。「というのは、 職 人 芸 は、ただ 物 のあるべき 精 神 的 イメージ、すなわち『イデア』だけを 相<br />
手 にすることによって 成 り 立 つものだからである」 158 。このイデアを 眺 める 工 程 は、 実 際 思 考 をはじ<br />
めとする 精 神 的 活 動 力 にむしろ 近 く、その 工 程 の 間 は 他 者 とともにある 現 われの 世 界 から 撤 退 しな<br />
くてはならないのである。ついでに 言 えば、アーレントは 思 考 の 生 み 出 すものですら、 仕 事 の 活 動<br />
力 を 通 さなければこの 世 界 に 現 われることはなく、 他 者 に 共 有 されることもないと 考 えている。たとえ<br />
ば、 思 考 は 文 字 として 書 かれ、 本 になるなどしなければ、その 場 で 消 滅 してしまう 儚 さを 持 っている。<br />
本 を 書 く 作 業 もまた、 一 種 の 仕 事 の 活 動 力 なのである。<br />
エ ン ド<br />
それでは 仕 事 の 活 動 力 はその 終 わり をどこに 持 っているのか 無 論 それは 仕 事 = 制 作 の 結 果<br />
エ ン ド<br />
生 産 される 物 である。「 製 作 された 物 は、 生 産 過 程 がそこにおいて 終 わる 〔 略 〕ということ、そして、 生<br />
エ ン ド<br />
産 過 程 が 完 成 品 というこの 目 的 を 生 み 出 す 唯 一 の 手 段 であるということ、この 二 重 の 意 味 で<br />
エ ン ド ・ プ ロ ダ ク ト<br />
最 終 生 産 物 である」 159 エ ン テ ィ テ ィ<br />
。 仕 事 の 終 わりははっきりしており、「 独 立 した 存 在 者 entity として 世 界 に 留 ま<br />
りうるほどの 持 続 性 をもった、 完 全 に 新 しい 物 が 人 間 の 工 作 物 につけ 加 えられたとき、 製 作 過 程 は<br />
終 わるのである」 160 エ ン ド<br />
。この 物 の 性 格 は、すでに 説 明 したとおりである。 他 方 仕 事 の 終 わり である 物 は、<br />
エ ン ド<br />
仕 事 の 目 的 でもある。 仕 事 の 活 動 力 はこの 物 以 外 に 如 何 なる 目 的 を 持 つこともない。それゆえ、 仕<br />
事 の 過 程 、すなわち「 製 作 過 程 それ 自 体 は、 手 段 means と 目 的 ends のカテゴリーによって 完 全 に<br />
決 定 されている」 161 。 故 に 仕 事 は、 目 的 である 物 以 外 をすべて 手 段 へと 変 えてしまう。こうして 仕 事<br />
テ ロ ス テ レ オ ロ ジ カ ル<br />
は 目 的 end, τελός を 持 つこと、つまり 仕 事 = 制 作 という 活 動 力 が 目 的 論 的 な 性 格 を 持 つことが、 判<br />
明 した。<br />
このように、 仕 事 は 始 まりと 終 わりを 持 つ。それどころか、 実 際 、「 明 確 な 始 まりと 明 確 で 予 見 でき<br />
る 終 りをもっているというのが 製 作 の 印 であり、 製 作 は、この 特 徴 だけでも 他 のすべての 人 間 の 活 動<br />
力 から 区 別 されるのである。たとえば 労 働 は、 肉 体 の 生 命 過 程 の 循 環 運 動 にとらえられていて、そ<br />
こには、 始 まりもなければ 終 りもない。また 活 動 は、 明 確 な 始 まりをもつ 場 合 があるとはいえ、 後 に 見<br />
155 Ibid., p.142. ( 前 掲 訳 書 、231 頁 。)<br />
156 Ibid. ( 同 上 。)<br />
157 Ibid. ( 同 上 。)<br />
158 Ibid., p.161. ( 前 掲 訳 書 、256 頁 。)<br />
159 Ibid., p.143. ( 前 掲 訳 書 、232 頁 。)<br />
160 Ibid. ( 同 上 。)<br />
161 Ibid. ( 同 上 。)<br />
40
、、、、、<br />
るように、 予 見 できる 終 りがない」 162 。アーレントが 立 てているこの 区 別 は、 時 間 論 的 に極 めて 重 要<br />
である。 仕 事 の 時 間 性 を 図 形 的 に 表 現 するならば、それは 始 まりと 終 わりの 二 つの 点 を 結 ぶ 線 分 と<br />
いう 形 を 取 るであろう(すなわち 真 木 悠 介 の 社 会 学 的 時 間 論 における「 線 分 的 時 間 」は、 根 源 的 に<br />
、、、、、、、 、、、、、、、<br />
は 制 作 の 時 間 性 から 発 源 すると 言 うことも 可 能 だ)。 仕 事 の 時 間 性 は、かくして、 目 的 論 的 時 間 性<br />
、、、<br />
である。<br />
第 16 節 目 的 論 的 時 間 了 解<br />
仕 事 は、 目 的 論 的 な 時 間 了 解 を 持 つ。 仕 事 とは、 始 まりとしてのイデアから、 終 わりとしての 物 =<br />
シュテンディゲ・フォアハンデンハイト<br />
目 的 に 至 る 過 程 である。 出 雲 春 明 が 言 っていたような、「 恒 常 的 事 物 存 在 性 」は、おそらく、 仕 事 が<br />
生 みだした 物 が 持 つ 時 間 性 である。しかしながら、 仕 事 が 生 みだした 物 のもつ 時 間 性 は、 仕 事 のそ<br />
のものの 時 間 性 とは 関 係 がない。なぜなら、アーレント 自 身 が 言 っているように、 物 が 出 来 たとき、<br />
「 製 作 過 程 は 終 わる」 163 からだ。 仕 事 は、 実 際 、 出 来 上 がった 物 とは 関 係 がない。なぜなら 物 が 出<br />
来 上 がったときには 仕 事 の 活 動 力 そのものは 消 滅 しているからだ。つまり 物 を 仕 事 の 時 間 性 で 語 る<br />
ことは 出 来 ないし、 仕 事 の 時 間 性 を 物 の 時 間 性 から 語 ることは 出 来 ない。それは、 仕 事 という 活 動<br />
力 の 始 まりであるイデアが 永 遠 性 という 性 格 を 持 っているからといって、 仕 事 を 永 遠 性 の 時 間 性 か<br />
ら 語 ることが 許 されないのと 同 様 である。 言 いかえれば、 仕 事 の 始 まり(イデア)と 終 わり( 物 )そのも<br />
のは、 仕 事 という 活 動 力 の 外 部 に 存 在 しており、 仕 事 の 論 理 に 従 っているかぎりそれらを 語 り 出 す<br />
ことは 出 来 ないのだ。すなわち 仕 事 の 原 理 に 従 った 哲 学 や 思 想 は、 根 源 的 に 始 まりそのものと 終<br />
わりそのものの 論 理 を 語 り 出 せない。 仕 事 の 活 動 力 が 備 える 存 在 論 的 な 機 制 の 要 求 するところに<br />
従 う 限 り、 始 まりと 終 わりは 接 近 不 可 能 なものに 留 まる。<br />
さて、 既 にハイデガーの 批 判 において 垣 間 見 られたとおり(またアーレント 自 身 もその 批 判 を 踏<br />
ポイエーシス<br />
襲 しているわけであるが)、プラトン 哲 学 ・アリストテレス 哲 学 の 基 礎 経 験 は、 制 作 に 根 ざしていた。<br />
そのもっとも 典 型 的 な 例 が、プラトンのイデア 論 であり、あるいはアリストテレスの 形 相 = 質 料 という<br />
存 在 論 的 カテゴリーである。イデア・エイドスという 考 え 方 は、ギリシア 哲 学 に 端 を 発 する 西 洋 哲 学<br />
たていと<br />
を 貫 く 経 となった。その 制 作 的 存 在 論 は、キリスト 教 神 学 との 合 流 を 通 じて 目 的 論 的 性 格 を 強 化 し、<br />
ヘーゲルの 歴 史 哲 学 において、その 性 格 を 完 全 に 発 現 させたと 言 っていいだろう。<br />
キリスト 教 の 歴 史 観 は、 終<br />
エスカトロジーに 末 論 裏 打 ちされている。すなわち、 歴 史 はいつか 終 焉 を 迎 え、 神 の<br />
永 遠 の 王 国 へと 移 行 する。 実 際 は「 移 行 」という 表 現 が 適 切 かどうかは 疑 わしい。 永 遠 とは 時 間 の<br />
、、<br />
、、、<br />
否 定 であり、 歴 史 の 終 焉 とは 時 間 の終 わりそのものであるからだ。それはさておき、この 歴 史 観 にお<br />
いては、 時 間 とは 終 わりに 向 かう 一 回 的 で 直 線 的 なものと 考 えられることになる(これを 真 木 悠 介 が<br />
「ヘブライズムの 時 間 」として 抽 出 した 時 間 性 であると 捉 えることも 可 能 である)。<br />
ヘーゲルの 哲 学 においては、 不 断 の 止 揚 という 弁 証 法 的 運 動 を 続 ける 精 神 が、ついに 絶 対 精<br />
神 へといたる 過 程 が、その 中 心 問 題 となっていた。 絶 対 精 神 とは 知 の 完 成 であり、 歴 史 の 目 的 であ<br />
り、 精 神 の 発 展 はそこで 終 わり、 同 時 に 歴 史 がそこで 終 わる。 逆 にいえば、 歴 史 の 全 過 程 は 絶 対 精<br />
162 Ibid., pp.143f. ( 前 掲 訳 書 、233 頁 。)<br />
163 Ibid., p.143. ( 前 掲 訳 書 、232 頁 。)<br />
41
神 への 道 程 であり、 歴 史 のなかで 起 こる 出 来 事 は 絶 対 精 神 へと 至 る 手 段 なのだ。 手 段 という 言 い<br />
モ メ ン ト<br />
方 が 適 切 でなければ、 目 的 との 関 係 において 捉 えられるべき、 歴 史 の 展 開 に 組 み 込 まれる 契 機<br />
Momente であった、と 言 い 換 えてもよい。<br />
ヘーゲル 哲 学 の 絶 対 精 神 は、イデアという 概 念 の 一 変 種 であり、その 意 味 でヘーゲル 哲 学 の 論<br />
理 学 ( 存 在 論 )もまた、 制 作 的 存 在 論 の 範 疇 で 思 考 を 展 開 していた。それゆえ、 絶 対 精 神 に 至 る 過<br />
程 として 全 歴 史 を 叙 述 するヘーゲルの 歴 史 哲 学 の 方 法 は、プラトンのイデア 論 が 宿 していた 制 作<br />
的 時 間 概 念 の 可 能 性 の、 全 面 展 開 であると 言 えよう。<br />
ヘーゲル 哲 学 を 批 判 的 に 継 承 したマルクスにおいても、この 事 情 は 変 わらない。 確 かにマルクス<br />
は、「 弁 証 法 は 彼 〔ヘーゲル〕において 頭 で 立 っている。〔 略 〕これをひっくり 返 さなければならない」<br />
164 フ ォ ル ム<br />
と 述 べ、ヘーゲルを 批 判 する。そして 実 際 に、イデア、すなわち 形 相 優 位 であったヘーゲルの<br />
イデアリスムス マ テ リ ー マテリアリスムス<br />
観 念 論 から、 質 料 ( 物 質 ) を 優 位 に 立 たせる 唯 物 論 へと 問 題 を 転 回 させた。その 手 際 は 次 のような<br />
ものである。<br />
マルクスとエンゲルス 曰 く、「ヘーゲルの 体 系 によれば、 理 念 、 思 想 、 概 念 が、 人 間 たちの 現 実 的<br />
な 生 活 、 彼 らの 物 質 的 な 世 界 、 彼 らの 実 在 的 な 諸 関 係 を 産 出 し、 規 定 し、 支 配 してきた」 165 。すな<br />
わち、 理 念 が 先 行 し、 理 念 のほうが 物 質 的 な 世 界 を 動 かし、 作 ることになっている。しかし、「われわ<br />
れが 出 発 点 とする 諸 前 提 は、なんら 恣 意 的 なものではなく、ドグマでもなく、 仮 構 の 中 でしか 無 視 で<br />
きないような 現 実 的 諸 前 提 である。それは 現 実 的 な 諸 個 人 であり、 彼 らの 営 為 であり、そして、 彼 ら<br />
の 眼 前 にすでに 見 出 され、また 彼 ら 自 身 の 営 為 によって 創 出 された、 物 質 的 な 生 活 諸 条 件 である」<br />
166 マ テ リ エ ル<br />
。つまり 思 考 の 産 物 であるような 思 想 、 観 念 、 理 念 を 前 提 に 掲 げるのではなく、 物 質 ( 質 料 ) 的 な<br />
もののほうを 前 提 条 件 として 設 置 するのだ。<br />
、、、、<br />
生 産 の 様 式 は、〔 略 〕すでに、これら 諸 個 人 の 活 動 の 一 定 の 方 式 、 諸 個 人 の 一 定 の 生 活 様 式<br />
である。 諸 個 人 がいかにして 自 分 の 生 を 発 現 するか、それが、 彼 らの 存 在 の 在 り 方 である。 彼<br />
、、<br />
らが 何 であるかということは、それゆえ、 彼 らの 生 産 と 合 致 する。すなわち、 彼 らが 何 を生 産 す<br />
、、、<br />
るか、ならびにまた、 彼 らがいかに生 産 するかということと 合 致 する。それゆえ、 諸 個 人 が 何 で<br />
あるかということは、 彼 らの 生 産 の 物 質 的 諸 条 件 に 依 存 する。 167<br />
164 MARX, Karl, Das Kapital: Kritik der politischen Ökonomie, 1.Bd., Berlin: Dietz Verlag, 1977, S.27. ( 向 坂 逸 郎<br />
訳 『 資 本 論 』( 一 ) 岩 波 文 庫 、1969 年 、32 頁 。)<br />
165 MARX, Karl/ ENGELS, Friedrich, hrsg. von Wataru HIROMATSU, Die Deutsche Ideologie, Neuveröffentlichung des<br />
Abschnittes 1 des Bandes 1 mit text-kritischen Anmerkungen, Tokio: Kawadeshobo-shinsha Verlag, 1974, S.3. ( 廣<br />
松 渉 編 訳 、 小 林 昌 人 補 訳 『 新 編 輯 版 ドイツ・イデオロギー』 岩 波 文 庫 、2002 年 、17 頁 。 引 用 に 際 し、 短 剣 符 〔†〕で<br />
囲 まれている 部 分 は、 削 除 部 ではあるが 本 文 としてそのまま 取 り、〈…〉に 挟 まれている 部 分 は 削 除 部 として 除 外 し<br />
た。さらに、 文 庫 版 ではフォントの 区 別 によりマルクス・エンゲルスどちらの 書 いたものかを 差 別 化 しているが、ここで<br />
はフォントの 区 別 も 無 視 する。 記 号 の 意 味 の 詳 細 に 関 してはここでは 割 愛 するので、 詳 しくは 文 庫 版 の 凡 例 を 参 照<br />
されたい。 以 下 も 断 りがない 限 りこのルールに 従 って 引 用 する。)<br />
166 Ebenda, S.23. ( 前 掲 訳 書 、25 頁 。)<br />
167 Ebenda, S.25. ( 前 掲 訳 書 、27 頁 。)<br />
42
つまり、 物 質 的 生 産 様 式 こそが、 思 想 や 観 念 の 条 件 であって、 逆 ではないのだ。それゆえ「 自 分 た<br />
ちの 物 質 的 な 生 産 と 物 質 的 な 交 通 を 発 展 させていく 人 間 たちが、こうした 自 分 たちの 現 実 と 一 緒 に、<br />
自 らの 思 考 や 思 考 の 産 物 をも 変 化 させていくのである。 意 識 が 生 活 を 規 定 するのではなく、 生 活 が<br />
意 識 を 規 定 する」 168 。 彼 らにとっては、 絶 対 精 神 の 発 展 の 代 わりに、 生 産 様 式 の 発 展 こそが、 歴 史<br />
、、<br />
、、、<br />
の 条 件 なのである。「 人 間 たちは 彼 らの 生 を 生 産 せざるをえないがゆえに、しかも 一 定 の様 式 でそ<br />
うせざるをえないがゆえに、 歴 史 をもつ」 169 。この 発 展 が、ブルジョアジーへの 富 の 集 中 を 促 し、 反<br />
、、<br />
作 用 的 にプロレタリアの 団 結 を 用 意 して、 革 命 を 準 備 するのだ。「すなわち、およそ 革 命 には、 受 動<br />
、、 、、、、<br />
的 な要 素 が、 物 質 的 な基 礎 が 必 要 である」 170 。<br />
しかしながら、まさにそのゆえに、 彼 らの 理 論 もまた 発 展 、さらには 階 級 の 消 滅 、 労 働 の 消 滅 とい<br />
う 目 的 という、 目 的 論 的 道 具 立 てを 必 然 的 に 含 みこむことになった。 換 言 すれば、 彼 らの 理 論 もま<br />
た、 仕 事 の 時 間 性 から 世 界 を 解 釈 するということに 終 始 してしまったのである。 発 展 は、ある 目 的 を<br />
立 てることによってしか 正 当 化 できない。 目 的 を 立 てるとき、 人 間 の 歴 史 と 全 営 為 は、すでにその 目<br />
的 に 向 けて 投 企 されてしまっている。 歴 史 は、その 目 的 のほうから、その 目 的 めがけて、 解 釈 される<br />
ことになるのだ。それはまさに 制 作 という 活 動 力 と 同 根 源 的 な 解 釈 のふるまいである 171 。<br />
しかし、 仕 事 = 制 作 のカテゴリーで 以 て 人 間 の 活 動 を 解 釈 することには、 常 に 危 険 が 伴 う。 第 一<br />
の 問 題 として、 既 に 述 べたように、 仕 事 の 活 動 力 と 同 根 源 的 である 手 段 = 目 的 範 疇 means-end<br />
category, Zweck-Mittel Kategorie に 従 うことにより、 工 作 人 は 仕 事 するときにはある 目 的 ( 仕 事 の 結<br />
果 としての 物 )を 立 て、 同 時 にその 目 的 を 達 成 するために 他 のあらゆる 物 事 を 手 段 化 してしまうとい<br />
うことがある。「 目 的 として 定 められたある 事 柄 を 追 求 するためには、 効 果 的 でありさえすれば、すべ<br />
ての 手 段 が 許 され、 正 当 化 される」 172 。これは 好 悪 、まして 善 悪 の 問 題 ではない。それは 制 作 という<br />
活 動 力 に 存 在 論 的 に 備 わる 性 格 なのであり、 仕 事 の「 本 質 的 」 特 徴 なのだ。しかし「こういう 考 えを<br />
追 求 してゆけば、 最 後 にはどんなに 恐 るべき 結 果 が 生 まれるか、 私 たちは、おそらく、そのことに 十<br />
分 気 がつき 始 めた 最 初 の 世 代 であろう」 173 。アーレントは、だからといって 仕 事 の 能 力 を 否 定 するわ<br />
168 Ebenda, S.31. ( 前 掲 訳 書 、31 頁 。)<br />
169 Ebenda, S.26, Anm. 10. ( 前 掲 訳 書 、56 頁 。)<br />
170 MARX, Karl, “Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung,” in: Marx-Engels Werke, Bd.1, Berlin:<br />
Dietz Verlag, 1977, S.386. ( 城 塚 登 訳 「ヘーゲル 法 哲 学 批 判 序 説 」『ユダヤ 人 問 題 によせて ヘーゲル 法 哲 学 批 判<br />
序 説 』 岩 波 文 庫 、1974 年 、87 頁 。)<br />
171 マルクスの「 労 働 Arbeit」 概 念 は、アーレントにとっては 仕 事 ということになろう。マルクスは、ヘーゲル『 精 神 現 象<br />
学 』と 弁 証 法 という 否 定 的 運 動 の 成 果 は、「ヘーゲルが 人 間 の 自 己 生 産 を 一 つの 過 程 としてとらえたこと、 対 象 化 の<br />
働 きを 対 象 から 離 反 する 外 化 の 過 程 として、さらには、この 外 化 の 克 服 として 捉 えたことにある」と 考 え、ヘーゲルは<br />
「 労 働 の 本 質 をとらえたのであり、 対 象 的 な 人 間 を―― 現 実 的 であるがゆえに 真 なる 人 間 を―― 当 人 自 身 の 労 働 の<br />
成 果 として 概 念 的 にとらえた」と 見 る(MARX, Karl, Ökonomisch-philosophische Manuskripte, 2.Aufl. Leipzig: Verlag<br />
Philipp Reclam, 1970, S.235 〔 長 谷 川 宏 訳 『 経 済 学 ・ 哲 学 草 稿 』 光 文 社 古 典 新 訳 文 庫 、2010 年 、178 頁 〕)。 人 間 の<br />
類 的 な 力 を 現 実 化 していくこととしての「 対 象 の 生 産 は、さしあたり、 疎 外 の 形 式 においてしか 行 なわれえない」<br />
(Ebenda 〔 同 上 、179 頁 〕)。そして「 自 己 意 識 の 外 化 によって 物 の 世 界 が 設 定 される。 人 間 = 自 己 意 識 なのだから、<br />
人 間 の 外 された 対 象 的 存 在 たる 物 の 世 界 は、 外 化 された 自 己 意 識 に 等 しく、この 外 化 によって 物 の 世 界 は 設 定 さ<br />
れる」(Ebenda, S.238 〔 同 上 、183 頁 〕)。マルクスの 労 働 は、こうして、 類 的 本 質 の 外 化 としての 仕 事 = 制 作 というこ<br />
とになる。 労 働 は、ここでは、たとえば 自 然 に 介 入 して、 人 間 にとって 有 意 味 な 世 界 に 作 りかえる。それはハイデガ<br />
ー 風 にいえば 世 界 = 内 = 存 在 としての 人 間 が、その 世 界 を 作 ることである。つまり 仕 事 である。<br />
172 ARENDT, The Human Condition (op.cit.), p.229. ( 前 掲 訳 書 、359 頁 。)<br />
173 Ibid.( 前 掲 訳 書 、359-360 頁 。)<br />
43
けではない。 仕 事 とは、 世 界 性 という 人 間 の 条 件 に 対 応 した 人 間 的 能 力 であったということを 我 々<br />
は 想 起 すべきである。 人 間 は 仕 事 という 活 動 力 なしではやはり 人 間 的 ではない。アーレントの 警 戒<br />
は、 我 々はカテゴリーエラーを 犯 すべきでないという 点 に 尽 きる。 制 作 とは 物 を 作 る 場 面 、 世 界 を 建<br />
設 する 場 面 において 用 いられるべき 活 動 力 であり、 人 間 たちの 事 柄 ( 政 治 )において 応 用 されるべ<br />
きでないのだ。そのことは、 次 にあげる 第 二 の 点 において、より 先 鋭 的 な 問 題 と 化 す。<br />
テ ロ ス<br />
仕 事 の 時 間 性 においては、「 時 間 の 終 わり 」が、 始 めから 見 えている。なぜなら、 仕 事 は 必 ず<br />
テ ロ ス<br />
目 的 を 立 てるからだ。ゆえに、ここで 時 間 はある 全 体 的 なものとして 了 解 される。それゆえ 仕 事 とい<br />
う 活 動 力 に 備 わる 了 解 は、 物 事 を 時 間 の 終 わりのほうから 見 て、 全 体 的 構 造 から 物 事 の 意 味 を 付<br />
与 する。 要 するに、 仕 事 は、 時 間 の 始 まりから 終 わりまで、すべてを 把 握 していることになる。<br />
アンテリジャンス<br />
このような 知 的 態 度 を、ベルクソンは「 知 性 intelligence」と 呼 んでいる。 知 性 は 次 のように 世 界<br />
を 了 解 する。「 外 的 な 世 界 は 数 学 的 な 法 則 に 従 っている。ある 瞬 間 における 物 質 的 宇 宙 のあらゆる<br />
原 子 電 子 の 位 置 と 方 向 と 速 度 を 知 っている 超 人 間 的 な 知 性 があるとすれば、それはわれわれが 日<br />
蝕 や 月 蝕 に 対 してするようにこの 宇 宙 のどんな 未 来 の 状 態 でも 計 算 するであろう」 174 。しかし、ベル<br />
クソンは「そういう 世 界 は 抽 象 にすぎない」 175 と 批 判 する。ベルクソンによれば、この 世 界 像 は 意 識<br />
や 生 命 を 欠 いている。しかし、 生 命 は 創 造 création という 契 機 を 持 っている。つまり 生 命 は 因 果 律 を<br />
はみ 出 し、 新 たな 物 事 を「はじめる」のである。しかしながら 人 間 の 知 性 は「 規 則 性 安 定 性 を 好 む」<br />
176 ファブリカシオン<br />
。というのも、 知 性 は 我 々の 制 作 fabrication の 支 えとなるものを 得 ようと 努 めるためである。 実<br />
際 このような 了 解 においては 全 体 を 把 握 することが 出 来 る。しかしそれは 生 命 を 無 視 したものであり、<br />
現 実 に 適 用 しても、 生 命 の 創 造 的 側 面 を 了 解 しえないために、 未 来 を 完 全 には 予 測 しえないもの<br />
となる。 我 々の 未 来 予 測 は、 世 界 の 安 定 的 側 面 ( 物 質 matière)を 取 り 上 げるのみなのだ。<br />
アーレントは、 生 命 が 創 造 的 契 機 を 持 つとは 言 わないが、しかし、 人 間 には「はじめる」 能 力 があ<br />
ると 言 う。 人 間 は、 実 際 、 前 例 もなく 予 想 もつかないことを「はじめる」 存 在 なのだ。それゆえ 仕 事 の<br />
もつ 知 性 的 な 了 解 は、 人 間 の 活 動 を 予 測 することは 出 来 ない。 制 作 的 知 は 未 来 (の 人 間 の 活 動 )<br />
を「 織 り 込 み 済 み」として 把 握 するが、 活 動 において 未 来 はまさしく「 未 知 」である。<br />
仕 事 = 制 作 のカテゴリーで 人 間 の 活 動 を 理 解 しようとするのは、「 仕 事 と 制 作 に 固 有 の 固 さを 人<br />
間 事 象 の 領 域 に 与 えるため」 177 であった。まさしく 予 測 不 能 である 人 間 の 活 動 の 不 安 定 性 を 除 去<br />
するために、 安 定 的 な 制 作 の 概 念 を 用 いて、 人 間 の 活 動 を 安 定 化 させ 予 測 しようというのである。<br />
人 間 の 知 性 の「 安 定 化 する 傾 向 Sicherungstendenz」 178 が、こうした 解 決 を 求 める。それは 同 時 に 未<br />
174 BERGSON, « Le possible et le réel » (op.cit.), p.116. ( 前 掲 訳 書 、138 頁 。ただし、intelligence の 訳 語 が「 悟 性 」と<br />
されているのを、「 知 性 」と 直 した。 以 下 同 様 。)<br />
175 Ibid. ( 前 掲 訳 書 、139 頁 。)<br />
176 Ibid., pp.120f. ( 前 掲 訳 書 、143 頁 。)<br />
177 ARENDT, The Human Condition (op.cit.), p.225. ( 前 掲 訳 書 、355 頁 。)<br />
178 HEIDEGGER, Phänomenologie des religiösen Lebens (Gesamtausgabe, Bd. 60) (ebenda), S.45ff. ハイデガーはこ<br />
の 講 義 において、 客 観 化 されていない( 主 観 = 客 観 として 了 解 されていない) 人 間 的 現 存 在 の「 経 験 」に 踏 み 込 もう<br />
としている。 氣 多 雅 子 が 言 うように、ここでハイデガーは「 事 実 的 な 生 の 経 験 は、 絶 えずそれ 自 身 から 離 反 し、 客 観<br />
に 類 するものへと 滑 り 落 ちるおそれがある」と 考 えている( 氣 多 「 事 実 と 事 実 性 」〔 前 掲 〕13 頁 )。 言 いかえれば、 学 問<br />
は、 人 間 の「 歴 史 的 な historisch」、「 事 実 的 生 経 験 faktische Lebenserfahrung」を、 客 観 的 なもののように 把 握 しようと<br />
する 傾 向 がある。このように 安 定 を 求 める 傾 向 を、ハイデガーは「 安 定 傾 向 Sicherungstendenz[en]」と 呼 んでいる。<br />
ハイデガーは、「 安 定 傾 向 」は 三 つの 道 を 取 ると 言 う。 第 一 の「プラトン 的 な 道 」においては、 時 間 的 なものを 超 時<br />
44
来 を 予 測 しながら 活 動 する 人 間 に 安 心 を 与 えるが、しかしながら、 人 間 の 活 動 を 了 解 する 際 には、<br />
根 本 的 な 捉 え 損 ないを 起 こさずにはいられないのである。なぜなら、 存 在 論 的 にいえば 現 存 在 は<br />
常 に 可 能 性 であり、 政 治 的 にいえば 人 間 ははじめる 能 力 を 持 つからである。 近 代 合 理 主 義 的 な 政<br />
治 哲 学 は 人 間 の 活 動 を 制 作 のモデルで 把 握 しようとした。しかし「 私 が 作 ろうとするものだけが 現 実<br />
的 であるという 観 念 は、たしかに、 製 作 の 領 域 では 完 全 に 真 実 であり、 正 統 的 なものであった」が、<br />
「この 観 念 は、 出 来 事 の 現 実 的 な 進 路 によって 永 遠 に 打 ち 砕 かれてしまう」。<br />
出 来 事 〔event〕の 場 合 には、まったく 予 期 しない 事 が 最 も 頻 繁 に 起 こるからである。 制 作 の 形<br />
式 で 活 動 すること、そして「 結 果 を 計 算 する」 形 式 で 推 理 するということは、 予 期 せざるもの、す<br />
なわち 出 来 事 そのもの〔the event itself〕を 考 慮 の 外 におくという 意 味 である。なぜなら「 無 限 の<br />
非 蓋 然 性 」にすぎないものを 予 期 するのは 非 理 性 的 であろうから。しかし、「まったくありそうも<br />
ないことがいつも 起 こる」ような 人 間 事 象 の 領 域 の 内 部 では、 出 来 事 こそリアリティの 織 地 を 作<br />
り 上 げているのである。そうである 以 上 、 出 来 事 を 考 慮 に 入 れないこと、つまり、 安 心 して 考 慮<br />
に 入 れることのできないものを 考 慮 に 入 れないことは、 極 めて 非 現 実 的 である。 179<br />
「 想 定 外 」のことは、 制 作 的 な 了 解 には 始 めから 存 在 しないのである。「 無 限 の 非 蓋 然 性 」にすぎな<br />
、、、、、、、、<br />
いものを 予 期 するのは( 制 作 という 活 動 力 の 観 点 からすれば) 非 理 性 的 であり、 制 作 するためには<br />
、、、、 、、、、、、、、、、、 、、<br />
どこかで「 割 り 切 らないといけない」のだ。<br />
それはさておき、このことは、 時 間 論 的 には、 人 間 の 活 動 は 制 作 の 目 的 論 的 時 間 概 念 では 了 解<br />
できないことを 意 味 している。 人 間 の 活 動 = 実 践 は 遂 行 的 であり、その 全 体 意 味 は 活 動 の 最 中 に<br />
は 明 らかにはならない。いいかえれば、 人 間 の 活 動 の 結 果 は、まさに 活 動 しているそのときには、<br />
明 らかにならない。<br />
プラクティッシュ 、、、、<br />
マルクスも、 革 命 が 実 践 的 praktisch であると 指 摘 はしていた(「 実 際 には、そして 実 践 的 な唯 物<br />
、、、、、<br />
論 者 すなわち 共 産 主 義 者 にとっては、 現 存 する 世 界 を 革 命 的 に 変 革 すること、 眼 前 に 見 出 される<br />
事 物 を 実 践 的 に 攻 略 し 変 革 することこそが 問 題 である」〔 傍 点 は 原 文 のまま、ゴシック 体 は 橋 爪 による〕 180 )。<br />
間 的 なイデアとの 関 係 において 捉 え、「 歴 史 的 なものを 副 次 的 なものにすることによって 安 定 化 を 図 ろうと」( 氣 多 、<br />
前 掲 論 文 、13 頁 )する。 第 二 の「シュペングラー 的 な 道 」においては、 歴 史 的 なものを「 歴 史 の 構 造 を 自 由 に 成 形 す<br />
る 主 観 性 の 所 産 とすることによって」( 同 ) 安 定 化 を 図 る。 第 三 の 道 は、 最 初 の 二 つの 中 間 的 妥 協 であるという。そし<br />
てそれが「 歴 史 的 弁 証 法 」という 往 き 方 なのである(HEIDEGGER, ebenda, S.46)。「 歴 史 的 現 実 性 という 理 論 に 基 づき、<br />
それ〔 第 三 の 道 〕は 安 定 化 の 傾 向 を 実 現 しようと 努 める。ひとつの『 歴 史 的 弁 証 法 』が、 歴 史 哲 学 の 課 題 として 描 出<br />
され、 時 間 的 なるものと 超 時 間 的 なるものとの 対 照 は、その 緊 張 と 止 揚 において 追 及 されねばならない。そこから 歴<br />
イデーン<br />
史 的 なるものの 弁 証 法 的 法 則 性 が 得 られるように。 私 は 一 方 で 歴 史 の 中 におり、 他 方 では 理 念 に 向 けて 統 御 され<br />
ヒ ン ア イ ン シ ュ テ レ ン<br />
ねばならない。つまり 私 は 時 間 的 なるものに 投 入 し・ 設 置 する ことを 通 して、 超 時 間 的 なものを 現 実 化 する」(Ebenda,<br />
S.46f. 〔 拙 訳 〕)。<br />
マルクスの 弁 証 法 においては、 一 見 するとイデア 的 なものは 廃 棄 されている。しかし、マルクスにおいては、 物 質<br />
的 なものが、 目 的 を 目 処 して「 発 展 する 生 産 力 」として、 理 念 の 代 替 を 果 たしてしまっている。このかぎりにおいて、<br />
マルクスの 弁 証 法 もまた、 第 三 の 道 から 自 由 でない。<br />
179 ARENDT, The Human Condition (op.cit.), p.300. ( 前 掲 訳 書 、471-472 頁 。)<br />
180 MARX/ ENGELS, hrsg. v. Wataru HIROMATSU, Die Deutsche Ideologie (ebenda), S.16. ( 前 掲 訳 書 、43 頁 。) この<br />
部 分 は、 所 謂 フォイエルバッハ・テーゼの、 有 名 な 第 11 番 の、より 具 体 的 な、 一 種 の 書 き 換 えであると 思 われる。 第<br />
45
プ ラ ク シ ス テオーリア<br />
しかし 実 践 = 活 動 は 観 想 との 関 係 においてしか 捉 えられず、マルクスの 弁 証 法 も 結 局 、ヘーゲル<br />
ポイエーシス<br />
的 な 観 想 は 逆 立 であると 指 摘 しながらも 制 作 の 範 疇 の 枠 内 に 留 まったのである。 要 するに 実 践 と<br />
制 作 と 同 一 視 したのだ。マルクスが 透 徹 した 未 来 予 測 を 行 なった( 科 学 的 社 会 主 義 )のも、 時 間 論<br />
的 には、 仕 事 の 目 的 論 的 時 間 了 解 において 歴 史 を 把 握 していたからであると 言 えよう。たとえば、<br />
絶 対 的 窮 乏 化 説 が 外 れたのは、 社 会 学 的 には「 自 滅 予 言 」(ロバート・マートン)として 説 明 できるか<br />
もしれない 181 。つまり、 正 しい 予 言 に 対 して 人 々が 回 避 するための 対 応 を 取 ったために、 予 言 は 外<br />
れたのだと 言 うことが 出 来 る。しかし、 政 治 的 にいえば、 全 体 としてマルクスの 共 産 主 義 社 会 の 到 来<br />
という 予 言 がうまくいかなかったのは、 人 間 の「はじめる」 能 力 のせいであると 思 われる。 実 際 彼 の<br />
「 科 学 性 」は、 人 間 事 象 の 領 域 に 徹 底 して 制 作 的 カテゴリーを 導 入 することによって 得 られているか<br />
らだ。<br />
我 々にとって 明 らかになったのは、 次 のことである。 仕 事 の 活 動 力 、 人 間 の 制 作 行 為 には、それ<br />
特 有 の 時 間 経 験 が 属 している。その 時 間 は 仕 事 の 活 動 力 と 同 根 源 的 であり、 仕 事 がある 目 的 を 目<br />
がけて 行 なわれるということに 由 来 する 目 的 論 的 な 時 間 了 解 であった。 目 的 論 的 な 時 間 概 念 にお<br />
いては、 時 間 の 全 体 構 造 が 明 らかであり、 過 去 と 現 在 は 未 来 における 目 的 のための 手 段 と 成 り 下<br />
がる。この 活 動 力 においては 未 来 が 優 先 的 であり、 活 動 力 そのものもそれ 自 体 で 完 結 しておらず、<br />
活 動 力 そのものからすれば 外 部 に 当 たる 目 的 に 向 けて、 自 らを 投 企 するという 構 造 を 有 している。<br />
そのような 活 動 力 に 備 わる 了 解 から、 人 間 事 象 を 理 解 しようとするとき、 凡 そ 二 つの 困 難 に 突 き 当 た<br />
る。 第 一 にそれは 過 去 と 現 在 、そして 人 間 を 手 段 化 してしまうということ、 第 二 に 人 間 に 特 有 の「はじ<br />
める」 能 力 ――これは 後 に 第 五 章 の 主 題 となるが――に 由 来 する 人 間 の 不 可 予 言 性 ゆえに 未 来<br />
を「 既 知 」のごとく 扱 う 仕 事 的 了 解 には 人 間 事 象 を 了 解 できないということである。<br />
、、、、<br />
、、、、<br />
11 テーゼとは、「 哲 学 者 たちはただ 世 界 をさまざまに 解 釈 してきたにすぎない。 肝 腎 なのは、 世 界 を 変 革 することで<br />
ある」というものである(MARX, Karl, “Thesen über Feuerbach,” in: Marx-Engels Werke, Bd. 3, Berlin: Dietz Verlag,<br />
1969, S.7〔「[フォイエルバッハに 関 するテーゼ]」 廣 松 渉 編 訳 、 小 林 昌 人 補 訳 『 新 編 輯 版 ドイツ・イデオロギー』 岩<br />
波 文 庫 、2002 年 、240 頁 〕)。<br />
181<br />
竹 内 洋 『 社 会 学 の 名 著 30』ちくま 新 書 、20<strong>08</strong> 年 、204 頁 以 下 。<br />
46
第 四 章 労 働 labor の 時 間 性<br />
――われわれは 永 遠 にわたってめぐり 戻 ってこなければな<br />
らないのではなかろうか――<br />
――ニーチェ『ツァラトゥストラはこう 言 った』<br />
第 17 節 二 つの 生 の 区 別<br />
我 々は 次 に、 労 働 labor, Arbeit と 呼 ばれる 活 動 力 の 時 間 経 験 を 分 析 したい。アーレント 自 身 によ<br />
る 労 働 という 活 動 力 の 定 義 は 既 に 引 用 したことがあるが、 次 のようなものであった。「 労 働 〔labor〕は、<br />
人 間 の 肉 体 の 生 物 学 的 過 程 に 対 応 する 活 動 力 である。 人 間 の 肉 体 の 自 然 な 成 長 、 新 陳 代 謝 、そ<br />
して 最 終 的 な 衰 退 は、 労 働 によって 生 産 され、 生 命 過 程 へと 供 給 される 生 命 の 必 要 物 〔 vital<br />
necessities〕に 拘 束 されている。そこで、 労 働 の 人 間 的 条 件 は 生 命 それ 自 体 〔life itself〕である」 182 。<br />
アーレントによれば 労 働 の 活 動 力 は 生 命 そのものに 関 わるという。ここでいう「 生 命 life」の 意 味 を<br />
はっきりさせておくことは、 後 の 分 析 を 進 める 上 で 重 要 であろう。 実 際 この life という 単 語 は 幾 分 問<br />
題 含 みである。たとえば、 既 に 我 々は「 活 動 的 生 活 」と「 精 神 的 生 活 」という 二 種 の 生 活 様 式 の 分 節<br />
に 関 して 詳 細 に 見 てきたが、ここでいう「 生 活 」もまた、 英 語 では life という 単 語 が 使 われている。 生<br />
物 学 的 生 命 と 人 間 的 生 活 を 分 節 しないという 事 情 は、 管 見 の 限 り 西 洋 語 全 般 に 広 く 当 てはまるよう<br />
だ 183 。 要 するに、 日 本 語 では「 生 命 」と「 生 活 」という 分 節 が 与 えられている 概 念 が、 西 洋 語 におい<br />
てはひとつの 単 語 において 表 現 されているため、 西 洋 語 でそれらの 概 念 的 区 別 を 描 写 するために<br />
は 若 干 の 特 別 な 努 力 を 要 するということである。しかしながら、 実 は 古 典 ギリシア 語 においては、 両<br />
者 は 截 然 と 区 別 されていた。すなわちビオス βίος とゾーエーζωή の 区 別 である。アーレントはこのギ<br />
リシア 的 区 別 を 手 がかりに、life を 二 つの 意 味 方 向 に 分 節 しようと 試 みる。<br />
ビ オ ス ・ ポ リ テ ィ コ ス ビ オ ス・ テ オ レティ コ ス<br />
さきに 我 々はアリストテレスによる「 政 治 的 生 活 」と「 観 想 的 生 活 」の 区 別 を 参 照 したが、ここで「 生<br />
活 」と 訳 されていた 語 がビオスであった。このことから 端 的 に 看 取 されるように、ビオスとは 人 間 的 な<br />
ゾ ー ィ オ ン ・ ロ ゴ ン ・ エ コ ン<br />
「 生 活 」、「 人 生 」を 意 味 している。これに 対 してゾーエーという 語 は、「 言 葉 を 持 つ 動 物 ζῷον λόγον<br />
ゾー ィ オ ン ・ ポリ テ ィコ ン<br />
ἔχον」や「ポリス 的 動 物 ζῷον πολιτικόν」というアリストテレスの 人 間 定 義 においても 現 われる、「 動 物 」<br />
を 意 味 するゾーィオン ζῷον なる 語 と、 語 幹 を 同 じくしており、このことからわかるように、 動 物 的 な<br />
「 命 」を 意 味 する 語 である。<br />
ゾーエーは 動 物 的 な 生 命 であるが、それは 不 死 immortal である 点 において 特 徴 付 けられる。そ<br />
れは、 個 々の 動 物 が――つまりあの 犬 やこの 猫 が―― 不 死 であるという 意 味 ではない。 確 かに 動<br />
物 も 個 体 においては 死 ぬ。それは 経 験 的 事 実 の 通 りである。しかしながら「 種 」という 観 点 から 見 た<br />
とき、それは 不 死 なのだ。なぜなら、 種 は 巨 大 な 生 命 の 円 環 というかたちで 存 在 しており、そこでは<br />
個 々の 動 物 、 個 々の 生 命 は 問 題 にならないからである。 個 々の 生 命 は、より 巨 大 な 円 環 、 生 命 の<br />
182 ARENDT, The Human Condition (op.cit.), p.7. ( 前 掲 訳 書 、19 頁 。)<br />
183<br />
英 語 の life をはじめ、Leben(ドイツ 語 )、vie(フランス 語 )、жизнь(ロシア 語 )、vita(ラテン 語 )と、 日 本 語 では 意 味<br />
論 上 区 別 される「 生 活 」「 生 命 」「 人 生 」「 生 涯 」「 暮 らし」「 命 」などが、これらの 単 語 においては 一 括 りにされている。<br />
47
無 限 循 環 へと 止 揚 されている。それゆえゾーエーは 不 死 なのである。 個 々の 生 命 は 滅 ぶが、 種 は<br />
、、、、<br />
滅 びない。 生 物 学 的 生 命 は 滅 びを 知 らないのである。<br />
このような 不 滅 のゾーエー―― 不 死 の 自 然 と 不 死 の 神 々として 表 象 された、 宇 宙 の 万 物 ――に<br />
囲 まれながら、「しかし、その 中 で 人 間 だけが 死 すべきものであり、したがって、 必 死 性 が 人 間 存 在<br />
の 印 となった」 184 。それは、「 動 物 と 違 って、 人 間 は、 単 に、その 不 死 の 生 命 〔すなわちゾーエー〕を<br />
生 殖 によって 保 証 する 種 の 一 員 ではないからである」 185 。 無 論 人 間 もまた 生 命 であり、 生 物 学 的 生<br />
命 としてのヒトという 種 でもある。しかし「 人 間 的 実 存 は、 種 の 永 遠 に 続 く 生 命 循 環 にはめ 込 まれて<br />
いることはなく、その 必 死 性 は、 種 の 生 命 循 環 が 永 遠 だということによって 慰 められるものでもない」<br />
186 のだ。 人 間 は、 種 としての 存 在 (ゾーエー)とは、 活 動 力 においても、また 時 間 論 的 にも、 異 なる<br />
別 の 存 在 ( 生 )のモードを 備 えている。<br />
一 個 の 生 命 は、なるほど 生 物 学 的 生 命 から 生 まれる。しかし、それは、 生 から 死 までのはっきり<br />
とした 生 涯 の 物 語 〔life-story〕をもっている。 人 間 の 必 死 性 はこの 事 実 にある。いいかえれば、<br />
この 個 体 の 生 命 は、その 運 動 が 直 線 を 辿 るということによって、 他 のすべてのものと 異 なってい<br />
る。その 直 線 運 動 は、いわば、 生 物 学 的 生 命 の 円 環 運 動 を 切 断 している。つまり、 一 切 のもの<br />
が――それが 動 いているとして―― 円 環 にそって 動 いている 宇 宙 にあって、 直 線 にそって 動<br />
くこと、これが 必 死 性 である。<br />
人 間 は、 生 から 死 への 直 線 的 な 時 間 を 生 きることによって、ゾーエーの 円 環 を 逸 脱 する。 翻 ってい<br />
モ ー タ リ テ ィ<br />
えば、 人 間 が 死 ぬという 事 実 ( 必 死 性 )は、 人 間 がゾーエーに 収 まりきらない 過 剰 を 抱 えていること<br />
に 淵 源 している。なぜなら、ゾーエーとしての 生 命 は、 種 としての 全 体 性 が 問 題 であるので、 決 して<br />
死 ぬことはないからである。 人 間 が 死 ぬことの 可 能 性 の 条 件 が、まさに 人 間 の 生 涯 が 直 線 的 な 時<br />
、<br />
間 であることに 由 来 するのである( 逆 にいえば、 円 環 的 時 間 を 存 在 する 種 としてのヒトは、 決 して 死<br />
、、、<br />
なないのだ)。 時 間 論 的 な 問 題 ということで 殊 更 強 調 しておけば、 自 然 的 生 命 (ゾーエー)としてのヒ<br />
ト man-kind は 円 環 を 生 きているし、 自 然 的 時 間 は 円 環 的 である。<br />
それに 対 して、 人 間 的 生 涯 の 示 す 時 間 論 的 構 造 である 直 線 性 こそが、ビオスである(あるいは、<br />
それは 出 生 と 死 という 二 つの 画 期 により 区 切 られている 点 で、 真 木 悠 介 が 区 別 したような 意 味 で 線<br />
分 的 時 間 であるいってもよいが)。<br />
、、、、、、、、、<br />
もし「 生 命 」という 言 葉 が 世 界 に 関 連 づけられ、 生 から 死 までの 期 間 を 意 味 するように 考 えられ<br />
る 場 合 には、それはまったく 異 なった 意 味 をもつ。その 場 合 、 生 命 は、 始 まりと 終 りによって 区<br />
、、、、、、、、、、、<br />
切 られ、 世 界 における 出 現 と 消 滅 という 二 つの 最 高 の 出 来 事 に 制 限 されて、 完 全 に 直 線 的 な<br />
運 動 を 辿 る。〔 略 〕この 特 殊 に 人 間 的 な 生 命 の 出 現 と 消 滅 が 世 界 の 出 来 事 を 構 成 するのであ<br />
、、、<br />
、、<br />
るが、その 主 要 な 特 徴 は、 人 間 の 生 命 が、 出 来 事 〔event〕に 満 ちており、その 出 来 事 は、 最 後<br />
184 ARENDT, The Human Condition (op.cit.), p.18. ( 前 掲 訳 書 、33 頁 。)<br />
185 Ibid., pp.18f. ( 前 掲 訳 書 、33-34 頁 。)<br />
48
、、<br />
には物 語 〔story〕として 語 ることのできるものであり、 評 伝 を 作 り 上 げることのできるものであると<br />
プラクシス<br />
いう 点 にある。アリストテレスが「ともかく 一 種 の 活 動 である」〔『 政 治 学 』〕といったのはこの 生 命 、<br />
ビオス<br />
つまり 単 なる 生<br />
ゾーエーと 命 区 別 された 生 についてである。〔 傍 点 は 橋 爪 〕<br />
アーレントのこの 定 義 に 関 して、まず 注 意 すべき 点 は、 人 間 的 生 (ビオス)が、 世 界 に 関 わるという<br />
点 である。 我 々は 世 界 が 如 何 なるものか 既 に 見 てきたところである。 世 界 とは、 仕 事 によって 生 み<br />
出 される 物 から 成 り 立 ち、それゆえに 客 観 性 と 持 続 性 ( 耐 久 性 )を 備 えた、そこで 人 間 が 生 きるとこ<br />
ろであった。「 世 界 は、 絶 えざる 運 動 の 中 にあるのではない。むしろ、それが 耐 久 性 〔= 持 続 性 〕を<br />
もち、〔 人 間 の 実 存 に 対 して〕 相 対 的 な 永 続 性 をもっているからこそ、 人 間 はそこに 現 われ、そこか<br />
ら 消 えることができるのである。いいかえれば、 世 界 は、そこに 個 人 が 現 われる 以 前 に 存 在 し、 彼 が<br />
そこを 去 ったのちにも 生 き 残 る。 人 間 の 生 と 死 はこのような 世 界 を 前 提 としているのである」 187 。 人 間<br />
を 単 なるゾーエー 的 生 命 から 救 いだし、 人 間 的 な 有 意 味 な 生 (ビオス)を 送 ることを 可 能 にするのは、<br />
世 界 (の 持 続 性 )である。<br />
ところで、すでに 見 てきた 仕 事 の 時 間 経 験 もまた 直 線 的 ―― 正 確 にいえばアルケーとテロスで<br />
区 切 られる 線 分 ――であった。 我 々は、 活 動 する 人 間 の 生 としてのビオスが 持 つ 時 間 の 直 線 性<br />
( 線 分 性 )を、 仕 事 の 時 間 経 験 と 同 一 視 し、ビオス 的 時 間 は 仕 事 的 時 間 と 同 じであると 考 えて 差 し<br />
支 えないだろうか この 同 一 視 は、 端 的 に 言 って 誤 っている。 始 まりと 終 わりがあるという 点 にの<br />
み 注 目 して 両 者 のもつ 時 間 論 的 構 造 を 同 一 視 した 結 果 、 既 存 の 政 治 哲 学 が 制 作 のカテゴリーを<br />
活 動 の 分 野 に 持 ち 込 むという 致 命 的 な 失 敗 を 犯 してきたということを、 我 々は 既 に 見 た。それは 人<br />
間 にとって 死 というテロス―― 終 わりではあるが 目 的 ではない――が、 生 きている 限 り 常 に 可 能 性<br />
であるという 点 に 関 わる。 人 間 の「 物 語 」は、その 人 間 が 死 なない 限 り 書 くことは 出 来 ない。なぜなら<br />
人 間 のビオスの 全 体 意 味 は、その 死 を 以 って 存 在 が 完 結 しない 限 り、 明 らかにならないからだ。 人<br />
間 は 存 在 論 的 に 言 えばつねに 可 能 性 であり、 政 治 的 に 言 えば「 始 める」 能 力 を 持 つがゆえに、そ<br />
ビオス<br />
の 生 は 出 来 事 event, Ereignis に 満 ちている。 出 来 事 自 体 event itself の 生 起 は、 既 に 見 たように 制<br />
クレアシヨン<br />
作 の 因 果 論 的 カテゴリーでは 了 解 も 予 測 も 出 来 ない、ベルクソンならば 創 造 と 呼 びそうな、「 無 カラ<br />
ex nihilo」 出 来 するものであった。それに 対 して、 仕 事 = 制 作 においては、その 行 為 の 意 味 も 始 まり<br />
も 目 的 も、つまり 制 作 の 全 体 意 味 が、すべて 始 めから 明 らかになっている。その 意 味 で、 仕 事 の 時<br />
間 性 と 活 動 の 時 間 性 は 決 して 同 一 視 すべきでないのだ。いずれにしても、ビオスの 問 題 の 詳 細 な<br />
分 析 は、 活 動 の 活 動 力 を 分 析 する 章 に 譲 ることにして、ゾーエーの 問 題 に 戻 ろう。<br />
人 間 的 な 生 とはビオスであるが、 人 間 が 生 き 物 であることも 事 実 であり、それゆえゾーエーという<br />
生 のモードをも、 人 間 は 備 えている。これから 分 析 する 労 働 の 活 動 力 は、 人 間 が 動 物 であるというこ<br />
と、 人 間 がゾーエーという 生 の 様 態 を 備 えていること、 時 間 論 的 に 言 いかえれば、 人 間 が 円 環 的 な<br />
自 然 的 時 間 をも 生 きていることに 由 来 する。 換 言 すれば、 労 働 とは、 生 命 という 人 間 の 条 件 に 対 応<br />
186 Ibid., p.7. ( 前 掲 訳 書 、19 頁 。)<br />
187 Ibid., pp.96f. ( 前 掲 訳 書 、152 頁 。)<br />
49
ア ニ マ ル ・ ラ ボ ラ ン ス<br />
する 活 動 力 である。また、それゆえに、 労 働 する 人 間 類 型 は「 労 働 スル 動 物 animal laborans」と 呼 ば<br />
れる。 労 働 する 人 間 は、 人 間 でありながら 動 物 と 活 動 力 を 共 有 しているのである。<br />
第 18 節 労 働 の 活 動 力 とその 生 産 物<br />
それでは 労 働 の 活 動 力 そのものを 見 て 行 こう。 労 働 は、 既 に 見 た 仕 事 の 活 動 力 と 比 較 しながら<br />
分 析 していった 方 が、 理 解 しやすい。というのは、 我 々はすでに 仕 事 を 分 析 した 際 に、 併 せて 世 界<br />
性 や 物 といった 概 念 をも 考 慮 の 対 象 に 含 めたが、その 世 界 性 の 観 点 から 見 たとき、 労 働 の 生 産 物<br />
と、 仕 事 の 生 産 物 ( 工 作 物 、 使 用 対 象 物 )とが、 全 く 違 ったものとして 現 われてくるからであり、その<br />
差 異 のうちにこそ、 労 働 という 活 動 力 そのものの 性 質 に 迫 るひとつの 道 が 存 している。<br />
労 働 の 生 産 物 は、 世 界 性 ―― 物 の 客 観 性 、 耐 久 性 ――において 眺 めたとき、 仕 事 の 生 産 物 と<br />
は 著 しい 対 照 をなす。<br />
実 際 、 背 後 になにも 残 さないということ、 努 力 の 結 果 が 努 力 を 費 やしたのとほとんど 同 じくらい<br />
早 く 消 費 されるということ、これこそ、あらゆる 労 働 の 特 徴 である。しかもこの 努 力 は、その 空 虚<br />
さにもかかわらず、 強 い 緊 迫 感 から 生 まれ、 何 物 にもまして 強 力 な 衝 動 の 力 に 動 かされている。<br />
なぜなら 生 命 そのものがそれにかかっているからである。 188<br />
ここで 言 う「 生 命 そのもの」とは、 既 に 見 たところのゾーエーを 指 しており、 人 間 の 自 然 的 な 部 分 に<br />
関 わる 生 のモードが 問 題 になっていることがわかる。 労 働 の 生 産 物 は「 背 後 になにも 残 さない」。 仕<br />
事 の 生 産 物 を 表 現 するときに 用 いた 表 現 を 思 い 出 せば、 仕 事 の 生 産 物 ( 使 用 対 象 物 )が 耐 久 性 =<br />
持 続 性 durability を 備 えていたのに 対 し、 労 働 の 生 産 物 はそれを 殆 ど 持 たない。それゆえそれは、<br />
仕 事 の 生 産 物 とは 異 なり、 客 観 性 を 殆 ど 持 つことなく、 世 界 を 構 築 することはない。すなわち 労 働<br />
の 生 産 物 は、すぐに「 消 費 」consume されるのだ。すでに、アーレントが「パン 屋 と 指 物 師 」よりも「パ<br />
ンとテーブル」を 比 較 した 方 がよいと 述 べた 箇 所 を 引 用 したが、パンとテーブルでは、 世 界 に 滞 在<br />
する 時 間 が 全 く 異 なる。テーブルが 耐 久 性 をもって 世 界 に 留 まるのに 対 して、パンは 作 られるや 否<br />
や 消 費 されねばならない。「 触 知 できる 物 のうちで 最 も 耐 久 性 の 低 い 物 は、 生 命 過 程 そのものに 必<br />
要 とされる 物 である。それを 消 費 する 時 間 は、それを 生 産 する 時 間 よりも 短 い」 189 。というのは、「 世<br />
界 にわずかな 時 間 滞 在 した 後 、それは、 動 物 としての 人 間 の 生 命 過 程 の 中 に 吸 収 されるか、 腐 蝕<br />
するか、いずれにしても、それを 生 み 出 した 自 然 的 過 程 に 戻 る」 190 からである。「それは、たしかに<br />
人 工 物 の 形 をとることによって、 人 工 物 の 世 界 に 束 の 間 の 場 所 を 獲 得 するが、 世 界 のいかなる 部<br />
分 よりも 早 く 消 滅 する。 世 界 性 という 点 から 考 えると、それは、 最 も 世 界 性 がなく、 同 時 に、すべての<br />
物 のうちでもっとも 自 然 的 である。それは、 人 工 物 であるとはいえ、 絶 えず〔 繰 り 返 し〕 循 環 する 自 然<br />
188 Ibid., p.87. ( 前 掲 訳 書 、140-141 頁 。)<br />
189 Ibid., p.96. ( 前 掲 訳 書 、151 頁 。)<br />
190 Ibid. ( 同 上 。)<br />
50
の 運 動 〔ever-recurrent cyclical movement of nature〕に 従 って、 生 まれ、 去 り、 生 産 され、 消 費 される。<br />
生 命 ある 有 機 体 の 運 動 も 循 環 する〔cyclical〕」 191 。<br />
すでに 見 てきたように、 自 然 はゾーエーという 不 死 のモードを 備 えている。「 世 界 性 がない」、「 自<br />
然 的 である」とは、ゾーエーの 特 徴 でもある。ゾーエーもやはり 円 環 的 な 時 間 を 生 きていた。 労 働 の<br />
生 産 物 であるパン( 食 べ 物 )は、ゾーエーとしての 単 なる 生 命 のために 存 在 する 物 であり、それゆえ<br />
ゾーエーの 円 環 的 な 時 間 のなかに 組 み 込 まれるのである。 個 々の 人 間 は 生 から 死 へと 至 るビオス<br />
を 生 きるが、 種 としてのヒトはゾーエーとして 自 然 の 時 間 を 生 きている。だから「 人 間 の 肉 体 も 例 外<br />
ではない」 192 。<br />
ビオスにおいて 生 きる 人 間 、あるいは 個 としての「この 犬 」「あの 猫 」は、 確 かに「 死 ぬ」のである 193 。<br />
故 に、「 生 命 とは、 至 るところで 耐 久 性 を 使 い 尽 し、それを 消 耗 させ、 消 滅 させる 一 つの 過 程 である。<br />
そして、 死 んだ 物 体 とは、 結 局 のところ、 小 さな、 単 一 の、 循 環 する 生 命 過 程 の 結 末 にほかなら」な<br />
い 194 。しかしながら、それらを「 種 」という 観 点 から 見 たとき 個 々の 生 命 は 意 味 を 失 い、それらは 死 ん<br />
だときに「 一 切 を 含 む 自 然 の 巨 大 な 循 環 〔circle〕の 中 に 帰 ってゆく」 195 ことになるのだ。つまり、 弁 証<br />
法 の 概 念 を 用 いて 図 形 的 に 表 現 すれば、 点 としての 生 命 は 円 環 としての 全 体 的 生 命 に 止 揚 されて<br />
いる。 個 は 全 体 を 構 成 することによって 個 であるのであって、ここでは 全 体 が 個 に 先 立 つ。 比 喩 的<br />
に 言 えば、 個 は、 円 環 としての 全 体 的 生 命 を 微 分 したときにはじめて 生 ずる、とも 言 えるだろうか。<br />
いずれにしても、ゾーエーにおいてはこの 円 環 的 な 全 体 性 が 本 質 なのである。そして「この 円 環 の<br />
中 では、 始 めもなければ 終 りもなく、すべての 自 然 物 が、 変 化 もなければ 死 もない 繰 り 返 しの 中 で<br />
回 転 しているのである」 196 。<br />
労 働 の 生 産 物 は、このような 自 然 としての 生 命 (ゾーエー)に 対 応 しているがために、 自 然 の 円 環<br />
運 動 cyclical movement of nature に 従 って、 生 命 同 様 「 生 まれ、 去 る」、すなわち「 生 産 され、 消 費 さ<br />
れる」。それゆえ、 仕 事 の 生 産 物 に 比 べ、 世 界 性 がない。 言 い 換 えると、 耐 久 性 = 持 続 性 がないた<br />
めに、 労 働 の 生 産 物 はすぐにこの 世 界 から 消 え 去 る。 労 働 は、 生 命 の 円 環 性 という 人 間 の 条 件 に<br />
対 応 して、そのような 生 産 物 を 生 み 出 す 活 動 力 なのである。<br />
この 二 つのこと、すなわち 人 間 における 生 物 学 的 過 程 と 世 界 における 成 長 と 衰 退 の 過 程 に 共<br />
通 する 特 徴 は、それらの 過 程 が 自 然 の 循 環 〔= 円 環 〕 運 動 の 一 部 であり、したがって 無 限 に 繰<br />
り 返 されるということである。だから、これらの 過 程 を 扱 わなければならない 人 間 の 活 動 力 は、<br />
すべて、 自 然 の 循 環 に 拘 束 されており、 適 切 にいえば、そこに 始 まりもなければ、 終 りもない。<br />
191 Ibid. ( 同 上 。)<br />
192 Ibid. ( 同 上 。)<br />
193<br />
付 言 しておけば、「この 犬 」「あの 猫 」が「 死 ぬ」のは、 犬 や 猫 がビオスという 生 のモードをもちうるからではない。<br />
犬 や 猫 の 死 ぬ 可 能 性 を 基 づけているのは、 人 間 の 死 ぬ 可 能 性 ( 必 死 性 )である。 人 間 のビオスにおいて、 犬 や 猫 は<br />
「 死 に」 得 る。なぜならそれらは 種 としての 犬 ・ 猫 一 般 として 存 在 しているのではなく、 一 回 性 を 備 えた 人 間 的 生 との<br />
ユニークネス<br />
関 わりに 於 いて 唯 一 性 を 受 け 取 るからである。<br />
194 ARENDT, The Human Condition (op.cit.), p.96. ( 前 掲 訳 書 、151 頁 。)<br />
195 Ibid. ( 前 掲 訳 書 、151-152 頁 。)<br />
196 Ibid. ( 前 掲 訳 書 、152 頁 。)<br />
51
、、<br />
仕 事 は、その 対 象 物 が 完 成 し、 物 の 共 通 世 界 につけ 加 えられるばかりになったとき 終 わるので<br />
、、<br />
あるが、これと 違 って 労 働 は、 常 に 同 じ 円 環 に 沿 って 動 くのであり、その 円 環 は 生 ある 有 機 体<br />
の 生 物 学 的 過 程 によって 定 められ、この 有 機 体 が 死 んだときはじめてその「 労 苦 と 困 難 」は 終<br />
わる。<br />
、、、、、、、、、、、、<br />
すでに 確 認 したように、 自 然 の 運 動 は 円 環 である。それゆえ、 自 然 の 時 間 は 円 環 的 である。そうし<br />
た 自 然 の 円 環 的 時 間 を、ゾーエーとしての 生 命 も 共 有 している。 故 に、ゾーエー 的 な 生 のモードも<br />
兼 ね 備 えている 人 間 にとって、ゾーエーという 人 間 の 条 件 に 対 応 する 活 動 力 が 求 められるわけだ<br />
、、、、、、、<br />
が、それこそが 労 働 である。そして 労 働 が 自 然 の 円 環 性 と 対 応 しているがゆえに、 労 働 の 時 間 経 験<br />
、、、 、、、、、 も 円 環 なのである<br />
197<br />
。<br />
第 19 節 円 環 的 時 間 経 験 ―― 永 劫 回 帰<br />
前 節 で 我 々にとって 明 らかとなったのは、 労 働 が、 円 環 的 なゾーエーに 従 うものであるために、<br />
それ 自 身 円 環 的 な 時 間 を 持 つことであった。 人 間 にとって、 意 味 ある 生 、すなわちビオスという 生 の<br />
モードを 可 能 にするのは、 世 界 であった。 世 界 は、 持 続 的 にして 客 観 的 であり、それゆえ 無 限 の 円<br />
環 のうちで 変 化 する 自 然 のなかで、 相 対 的 に 永 続 的 な 人 間 が 安 らう 場 を 与 えてくれる。「だから 人<br />
間 がその 中 に 生 まれ、 死 んでそこを 去 るような 世 界 がないとすれば、そこには、 変 化 なき 永 遠 の 循<br />
環 〔 永 劫 回 帰 eternal recurrence〕 以 外 になにもなく、 人 間 は、 他 のすべての 動 物 種 と 同 じく、 死 のな<br />
い 無 窮 〔deathless everlastingness〕の 中 に 放 り 込 まれるだろう。ニーチェは、 存 在 の 最 高 原 理 として<br />
『 永 劫 回 帰 』(ewige Wiederkehr)を 肯 定 したが、このような 肯 定 に 到 達 しないような 生 の 哲 学 は、 自<br />
分 自 身 の 語 っていることを 弁 えていないのである」 198 。<br />
アーレントはここで、 円 環 的 な 生 命 の 時 間 ――それは 同 時 に 労 働 の 時 間 経 験 でもある――につ<br />
いて、ニーチェの 永 劫 回 帰 ewige Wiederkehr になぞらえて 語 っている。ニーチェの 永 劫 回 帰 思 想<br />
とは、なによりも 時 間 論 の 思 想 であった。そのことを 考 慮 に 入 れて、ニーチェの 思 想 を 参 看 すること<br />
は、 労 働 の 時 間 経 験 を 理 解 する 上 でも 資 するところはあろう。<br />
197<br />
勿 論 、 真 木 悠 介 のいう 円 環 的 時 間 も、この 活 動 力 から 発 源 している 時 間 性 であると 考 えて 差 し 支 えない。さらに<br />
は、ギリシア 語 に 見 られたホーラという 時 間 性 も、 同 様 であろう。 問 題 は、 同 じような 自 然 のリズムに 支 配 された 時 間<br />
性 として「 反 復 的 時 間 」という 時 間 性 も 存 在 しているという 点 である。けだし、 反 復 的 時 間 もまた、 労 働 という 活 動 力 か<br />
ら 発 源 したものであろう。なぜならそれはゾーエーとしての 単 なる 生 命 の 要 請 に 対 応 していると 見 て 間 違 いないと 思<br />
われるからである。 反 復 的 時 間 と 円 環 的 時 間 との 差 異 について、 真 木 は 時 間 に 対 する 数 的 な 把 握 という 契 機 を 挙<br />
げている。 時 間 が 等 分 性 、 均 質 性 を 備 えているか 否 かが、 両 者 の 差 異 である。たとえば 昼 と 夜 とが 異 質 な 二 世 界 と<br />
して、また 一 方 から 他 方 への「 移 項 」が 世 界 の 転 換 として 経 験 されるには、 時 間 が 数 的 に 把 握 されていてはならない。<br />
なぜなら、 時 間 が 数 的 である 限 りにおいて、 昼 と 夜 とは 連 続 しており、したがって 一 方 から 他 方 への「 移 項 」は 経 験 さ<br />
れず、むしろそれは 連 続 的 な「 移 行 」として 経 験 される。<br />
別 の 言 い 方 をすれば、それは「 眠 り」が 時 間 意 識 のうちに 組 まれているか 否 かという 点 に 係 っているのではないだ<br />
ろうか。 生 命 は「 眠 り」において「 断 絶 」を 経 験 する。ゾーエーは 確 かに 無 限 の 円 環 であるが、それは 死 と 同 様 に 眠 り<br />
を 含 んでいる。 眠 りの 断 絶 が 深 刻 に 受 け 止 められるとき、 時 間 は 断 絶 したものとして 経 験 されるだろう。しかし 均 質 な<br />
時 間 性 においてはその 断 絶 は 失 われる。こうして、 生 命 は 均 質 な 時 間 においては 言 わば「 不 眠 」となるのだ。<br />
198 ARENDT, The Human Condition (op.cit.), p.97. ( 前 掲 訳 書 、152 頁 。)<br />
52
ニーチェの 永 劫 回 帰 思 想 は、『ツァラトゥストラはこう 言 った Also sprach Zarathustra』において、あ<br />
る 程 度 まとまった 形 で 現 われる。「 幻 影 と 謎 」と 題 される 章 において、ツァラトゥストラが 幻 影 のなかで<br />
「 重 力 の 魔 」という 魔 物 と 語 らう 場 面 が、その 現 場 である。<br />
「この 門 を 通 る 道 を 見 るがいい! 小 びとよ」とわたしは 言 いつづけた。「それは 二 つの 面 をも<br />
っている。 二 つの 道 がここで 出 会 っている。〔 略 〕/この 長 い 道 をもどれば、 永 遠 にはてしがな<br />
い。またあちらの 長 い 道 を 出 て 行 けば、――そこにも 別 の 永 遠 がある。/かれらはたがいに 矛<br />
盾 する、――この 二 つの 道 は。かれらはたがいに 反 撥 しあう。――そしてこの 門 のところこそ、<br />
かれらがまさにぶつかっている 場 所 なのだ。 門 の 名 は 上 に 掲 げられている。――『 瞬 間 』<br />
〔>Augenblick
いることはこれまでに 無 限 回 にわたって 繰 り 広 げられたことの 再 演 なのであり、そしてこれから 先 も<br />
永 遠 に 繰 り 返 されるはずである。この 考 え 方 を 基 礎 づけているのは、 実 はニュートン 力 学 と、19 世<br />
紀 当 時 最 新 学 説 であった「エネルギー 恒 存 の 法 則 」(エネルギー 保 存 則 )であるといわれる。ニュー<br />
トン 力 学 においては、ある 運 動 が 発 生 するためには、 必 ず 原 因 としての 力 が 存 在 していることにな<br />
る。また 反 対 に、ある 運 動 は、 別 の 物 体 に 必 ず 作 用 する。つまり、ある 運 動 は、 必 ず 何 らかの 原 因<br />
の 帰 結 であり、 反 対 に 必 ずなんらかの 帰 結 の 原 因 になるのだ。この 時 点 で「エネルギーは 恒 存 であ<br />
る」と 言 えるはずだが、 実 際 は 抵 抗 や 摩 擦 力 によりエネルギーは 保 存 されない。ところが、ローベル<br />
ト・マイヤーらが「 作 用 のなかに 仕 事 (W)のほかに 熱 量 (Q)をふくめ、〔 略 〕 広 義 のエネルギー 保 存<br />
則 が 成 立 することを 確 かめた」 201 。ニーチェが 依 拠 しているエネルギー 恒 存 の 法 則 はこの 段 階 のも<br />
のだ。 要 するにこの 理 論 に 依 って、 全 ては 原 因 と 結 果 の 連 鎖 として 繋 がると 言 うことが 出 来 るのだ。<br />
ツァラトゥストラはこう 言 っていた、「 一 切 の 事 物 は 固 く 連 結 されているので、そのためにこの 瞬 間<br />
、、、、、、<br />
はこれからくるはずのすべてのものをひきつれている」と。「 一 切 の 事 物 は 固 く 連 結 されている」とい<br />
う 言 葉 は、ニュートン 力 学 的 な 意 味 で 解 釈 できる。つまり、 事 物 の 一 切 は 互 いを 原 因 と 結 果 としてい<br />
、、、、、、<br />
るということだ。そして「そのためにこの 瞬 間 はこれからくるはずのすべてのものをひきつれている」。<br />
つまり、「 瞬 間 」は 原 因 として、 結 果 としての 未 来 の 一 切 を 規 定 し、 決 定 し、 動 かしえないものとする。<br />
しかもその「 瞬 間 」もまた、これまでの 過 去 に 支 配 され、 決 定 されている。そして 時 間 は「 円 環 」であ<br />
るから、 一 切 は 全 く 同 じ 順 序 で、 全 く 同 じ 内 容 で、 何 の 変 化 もなく、 永 遠 に 繰 りかえすことになる。<br />
ところで、なぜ「 円 環 」になる 必 要 があるのか。 過 去 が 規 定 されていたとして、またそれゆえに 瞬<br />
間 が 未 来 を 規 定 するとしても、 円 環 である 必 要 はない。 言 いかえれば、「 一 切 は 繰 りかえす」という<br />
考 えに 至 りつくは、 論 理 の 必 然 としてなのか。 原 因 が 結 果 を 全 て 規 定 しているという 考 え 方 は、 因<br />
果 律 と 呼 ばれ 実 際 よく 知 られている( 例 えば 有 名 な「ラプラスの 魔 物 」のような)。つまり 因 果 律 は 従<br />
来 円 環 のモデルで 語 られてきたわけではないのだ。 竹 田 青 嗣 は、 比 喩 を 用 いてこの 疑 問 に 答 えて<br />
いる。「この 世 界 観 のもっとも 単 純 なモデルとして、たとえばまったく 抵 抗 のないビリヤードの 台 の 上<br />
でたくさんの 球 が、 摩 擦 によって 力 を 失 うことなく 永 遠 にぶつかり 合 って 動 き 回 っている、という 状 態<br />
をイメージしてみるとよい。 時 間 は 無 限 にあるから、 一 定 の 空 間 の 中 で 一 定 のエネルギーがその 力<br />
を 減 じることなく 運 動 していると、いつかある 時 点 で、 以 前 のどこかの 時 点 で 存 在 したとまったく 同 じ<br />
物 質 の 配 置 、 配 列 が 戻 ってくる 可 能 性 があるはずだ。すると、その 次 の 時 点 から、 一 切 が『 何 から 何<br />
までことごとく 同 じ 順 序 と 脈 絡 』で 反 復 することになる、というわけである」 202 。 始 まりと 終 わりがないの<br />
、、、、、、、<br />
であれば、そしてエネルギー 恒 存 の 法 則 が 正 しいならば、 論 理 的 に 考 えて、いっさいは 回 帰 するほ<br />
かない。<br />
ツァラトゥストラ(ニーチェ)が 戦 慄 するのは、この 永 劫 回 帰 の 真 理 である。 永 劫 回 帰 は、 一 切 が 回<br />
帰 するという 点 で 従 来 の 因 果 律 や 決 定 論 とは 異 なる。また、 永 劫 回 帰 は、 過 去 と 未 来 の 一 切 が 決<br />
定 されているという 点 で 従 来 の 輪 廻 思 想 や 円 環 的 な 時 間 論 とも 異 なる(「わたしはふたたび 来 る。こ<br />
の 太 陽 、この 大 地 、この 鷲 、この 蛇 とともに。―― 新 しい 人 生 、もしくはより 良 い 人 生 、もしくは 似 た 人<br />
201<br />
202<br />
荒 川 他 編 『 哲 学 辞 典 』( 前 掲 )「エネルギー」の 項 。<br />
竹 田 青 嗣 『ニーチェ 入 門 』ちくま 新 書 、1994 年 、152 頁 。<br />
54
、、<br />
生 にもどってくるのではない」 203 )。 生 が 永 劫 に 繰 り 返 すとしても、 別 の 人 生 はもっと 良 いものかもし<br />
れない。より 良 い 来 世 があるかもしれない、よりよい 彼 岸 があるかもしれない―― 永 劫 回 帰 において<br />
、、、、、、、、、、、<br />
はこういったナイーブな 希 望 すらも、ことごとく 破 壊 してしまう。いっさいはただ 繰 り 返 す。ニーチェが<br />
耐 えられないのはこの 点 である。それは 実 存 から 可 能 性 を 剥 奪 し、 有 意 味 性 をも 破 壊 する。 因 果 律<br />
の 体 裁 を 取 りながら、 目 的 も 存 在 しない。 永 劫 回 帰 は、 人 間 の 生 きる 拠 り 所 をすべて 宙 づりにしてし<br />
まうのである。それは、 実 際 、それを 克 服 した 人 間 が「 超 人 Übermensch」と 呼 ばれるに 足 るほどに、<br />
過 酷 な 真 理 であった。 克 服 は 可 能 なのだろうか<br />
ツァラトゥストラは、しかし、 永 劫 回 帰 の 克 服 を 果 たし、ついには 永 遠 に 対 する 愛 の 言 葉 まで 述 べ<br />
、、、、、、、、<br />
るようになる 204 。 重 要 なのは、ツァラトゥストラが「 永 遠 であっても 愛 せる」と 言 っているのではなく、<br />
、、、、<br />
、、 、、<br />
「 永 遠 を 愛 する」と 述 べている 点 だ。 譲 歩 や 妥 協 ではない。むしろ 永 遠 でないものは 愛 するに 値 し<br />
、、<br />
ないとさえ 言 っているように 思 える。それは 180 度 の 転 換 であり、 肯 定 である。なぜ、 肯 定 するに 至<br />
ったのか。<br />
嘆 きは 言 う、「 終 わってくれ! 去 ってくれ、こんな 嘆 きは!」と。しかし、すべての 苦 悩 するもの<br />
は 生 きたいと 思 う。 成 熟 し、よろこびをおぼえ、あこがれを 抱 きたいと 思 う。/――あこがれは、<br />
より 遠 いもの、より 高 いもの、より 明 るいものに 向 かう。「わたしはあとを 嗣 ぐものがほしい」と。す<br />
、、、、、<br />
べての 苦 悩 するものは 言 う、「わたしは 子 どもがほしい。このわたしではなく」。――/よろこび<br />
は、しかし、あとを 嗣 ぐ 者 を 欲 しない。 子 どもたちを 欲 しない、――よろこびは 自 己 自 身 を 欲 す<br />
る。 永 遠 を 欲 する。 回 帰 〔Wiederkunft〕を 欲 する。 一 切 のものの 永 遠 の 自 己 同 一 〔Alles-sichewig-gleich〕を<br />
欲 する。 205<br />
この 世 を 嘆 くものたちは、 嘆 きに「 終 わってくれ!」と 言 う。その 嘆 きが 二 度 と 来 ないことを 欲 する。そ<br />
して、よりよい「 次 」を 求 める。それは、 輪 廻 説 においては「 来 世 」であり、 目 的 論 的 な 時 間 意 識 にお<br />
いては「 次 世 代 」や「 未 来 」となる( 目 的 によって 現 在 は 手 段 化 される)。いずれにせよ、 彼 らが 求 め<br />
、、、、、、、、 、、<br />
るのは、じぶんたちじしんではない。 全 く 同 じもの( 人 生 ・ 歴 史 ・ 宇 宙 )が 繰 りかえす 永 劫 回 帰 に 彼 ら<br />
は 耐 えられないだろう。 彼 らには 自 分 の 生 を 肯 定 することが 出 来 ないからだ。しかし、 嘆 きには 二 度<br />
、、<br />
と 帰 ってきてほしくないかもしれないが、 喜 びはどうか もし 次 の 生 が 今 の 生 と 同 一 でないとしたら、<br />
、、、、、、、<br />
、、、、、、、<br />
嘆 きは 回 避 できるかもしれないが、 今 の 生 の 喜 びが 再 び全 く 同 じに繰 りかえすことはありえない。 至<br />
、、、、 、、、、 、、、、、、、、、、、、、、、<br />
福 の 喜 びがあったならば、むしろそれが 全 く 同 じかたちで、 寸 分 の 違 いもなく 帰 ってくることが 望 ま<br />
、、、、 、、 、、 、、、、<br />
しいのではないか。だから 喜 びは「 自 分 自 身 を 欲 する」「 永 遠 を 欲 する」「 回 帰 を 欲 する」「 自 己 同 一<br />
を 欲 する」。それゆえただ 喜 びだけが、「 永 劫 回 帰 」に 耐 え 得 る、それどころか、むしろそれに 対 して<br />
203 NIETZSCHE, ebenda, S.224. ( 前 掲 訳 書 、138 頁 。)<br />
204 「おお、どうしてこうしたわたしが、 永 遠 をもとめるはげしい 欲 情 に 燃 えずにいられようか 指 輪 のなかの 指 輪 、<br />
最 高 の 結 婚 指 輪 、――あの 回 帰 の 円 環 をもとめる 思 いに/わたしはまだこれまでにわたしの 子 を 産 ませたい 女<br />
性 に 出 会 ったことがなかった。このひとにだけは 子 を 産 ませたい。なぜなら、おお、 永 遠 よ、わたしはあなたを 愛 する<br />
、、、、、、、、、、、、、、 、、 、、、<br />
からだ!/わたしはあなたを 愛 するからだ、おお、 永 遠 よ!」(Ebenda, S.232. 〔 前 掲 訳 書 、154 頁 。〕)<br />
205 Ebenda, S.326.( 前 掲 訳 書 、324-325 頁 。)<br />
55
「 然 り」と 告 げることが 出 来 る。それは、 同 時 に 嘆 きをも 肯 定 することになるのだ。というのは、その 喜<br />
びを 因 果 に 従 って 形 づくるのは、その 嘆 きにほかならないためである。 喜 びの 永 遠 性 を 求 めたとき、<br />
ひとはむしろ 永 劫 回 帰 と、 嘆 きとを、ともに 肯 定 しなくてはならないのだ。こうして、ニーチェは 時 間<br />
の 全 体 を 肯 定 する。 喜 びによって 永 遠 を 言 祝 ぐ。<br />
このニーチェの 理 論 は、 単 なる 思 考 実 験 からは 区 別 されなくてはならない。 少 なくとも、 哲 学 史 上<br />
大 きな 転 換 であると 見 られる 点 は、 哲 学 を 目 的 論 から 解 放 している 点 である。「 自 己 自 身 を 欲 する」<br />
ことで、 目 的 を 外 に 置 く 思 考 様 式 からの 脱 却 がはかられている。 目 的 を 外 化 することにより、 現 在 は<br />
手 段 化 されてしまう。 既 に 見 たように、これはヘーゲルやマルクスの 思 考 法 の 陥 穽 でもあった。しか<br />
し、「 神 は 死 んだ」というニーチェにとっては、 目 的 を 立 てて 現 在 を 手 段 化 するという 術 は 許 されない<br />
ものだったのだ。<br />
けだし、 実 はこの 試 みは、 時 間 が 円 環 でないとしても 有 意 義 である。ニーチェの 言 う 自 己 同 一 は、<br />
円 環 の 時 間 のなかでは 永 遠 に 回 帰 する。しかし、 喜 びという 一 点 において 因 果 の 全 体 性 を 肯 定 で<br />
きるのであれば、 仮 に 時 間 が 回 帰 しないとしても、それが 時 間 の 全 体 を 肯 定 したことに 変 わりはな<br />
いからだ。ニーチェの 思 考 の 意 義 は、じつは 時 間 が 回 帰 するという 発 想 よりも、このような 主 体 的 肯<br />
定 のほうにある。 時 間 が 回 帰 するという 思 考 実 験 そのものは、 歴 史 から 起 源 と 目 的 を 除 去 すること<br />
に 役 立 っている。そのとき、 人 間 は 自 分 の 意 味 を 外 部 に 求 めることはできなくなる。ニーチェの 思 考<br />
の 極 端 さは、このような 目 的 の 取 り 外 しを 意 図 しているために 生 まれる。 永 劫 回 帰 という 極 限 におい<br />
ても、なお 生 を 肯 定 しうるのであれば、 人 間 には 自 ら 生 と 時 間 全 体 を 肯 定 する 力 が 備 わっていると<br />
、<br />
いうことになる。それは 仮 に 時 間 が 直 線 的 であろうと、 無 限 に 輪 廻 しようと、 同 じはずである―― 因<br />
、、、、、、、、、、、、、 、<br />
果 が 絶 対 であるとするかぎりは。<br />
ところで、アーレントが 労 働 の 時 間 性 を「 永 劫 回 帰 」と 呼 んでいる 点 には、 実 は 違 和 感 がある。 実<br />
際 、「 永 劫 回 帰 」というのは、やや 大 胆 な 比 喩 というほどに 受 け 取 らねばなるまい。というのは、ニー<br />
チェの 時 間 概 念 は、 実 は 制 作 的 な 時 間 了 解 の 延 長 上 にあるからである。それは、ニーチェが 永 劫<br />
回 帰 の 説 を、 因 果 論 から 引 き 出 したからである。ニーチェは 古 典 文 献 学 の 専 門 家 であり、その 回 帰<br />
的 な 時 間 論 も、 実 は 古 代 の 円 環 的 時 間 経 験 から 大 きな 影 響 を 受 けていると 指 摘 されている。しかし、<br />
結 果 として 生 まれた 永 劫 回 帰 は、 因 果 律 の 極 北 と 呼 ぶべき 理 論 である。そして 因 果 律 は、 仕 事 に<br />
おいて 力 を 発 揮 する 範 疇 なのである(ベルクソンにおいて、 両 者 の 結 びつきが 判 りやすく 示 されて<br />
いる。 因 果 律 の 絶 対 性 は、 工 作 人 が 制 作 するために 必 要 なものだった)。ニーチェは、「 神 は 死 ん<br />
だ」と 宣 言 することによって、 目 的 論 的 時 間 の 両 端 の 留 め 金 であった 起 源 と 目 的 とを 同 時 に 外 して<br />
たわ<br />
しまった。ニーチェの 永 劫 回 帰 説 は、あたかも、 留 め 金 が 外 れ 緊 張 が 解 け 撓 んだ 時 の 因 果 の 糸 を<br />
落 ち 着 けるために、 再 び 始 まりと 終 わりとを 結 って 円 環 に 仕 上 げようとする 試 みのようである。その 意<br />
味 で、ニーチェの 時 間 論 は、 制 作 的 時 間 了 解 をヘーゲル 以 上 につきつめたものであると 言 っても<br />
過 言 ではない。<br />
しかし、そのことで、 永 劫 回 帰 という 表 現 が 労 働 の 時 間 経 験 の 何 ほども 表 現 していない、というこ<br />
とにはならない。 時 間 が 円 環 であると、どういうことになるかという 可 能 性 が、ニーチェにおいて 思 考<br />
されている。ツァラトゥストラを 苦 しめた 事 実 は、 永 劫 回 帰 においては 起 源 も 目 的 も 失 われ、 人 間 は<br />
56
そのなかでちょうど 海 を 漂 う 木 片 のごとく、あらゆる 繋 がりを 失 って 無 意 味 に 存 在 せねばならないと<br />
いうことである。 労 働 においても、 人 は 無 意 味 さに 耐 えねばならない。 実 際 それは 終 りがなく、いっ<br />
たん 終 わったかに 見 えても 実 はそれが 始 まりであるという、シーシュポスの 労 働 である。 終 りも 始 まり<br />
もなく、ただ 種 の 保 存 のための 保 存 を 繰 り 返 すというのが、ゾーエーにおける 存 在 仕 方 であった。ニ<br />
ーチェが 開 示 した 目 的 なき 生 の 絶 望 は、じつは 労 働 スル 動 物 にも 備 わるものであったのだ(ただし、<br />
本 当 の 動 物 はその 類 の 絶 望 を 抱 くこともないが)。<br />
ところが、ニーチェの 理 論 は 実 は 破 綻 している。ニーチェの 超 人 は、 永 劫 回 帰 を 自 覚 し、 自 らも<br />
また 意 味 も 理 由 も 目 的 もなく 永 遠 に 回 帰 するという 事 実 を 受 け 取 って、それでもなお 生 と 時 間 とを<br />
肯 定 する、そういう 主 体 であった。ところが、 永 劫 回 帰 の 理 路 を 真 面 目 に 受 け 取 れば、 回 帰 する 世<br />
界 のなかの 主 体 すらも 実 は 回 帰 するものであるために、 永 劫 回 帰 を 主 体 的 に 肯 定 するか 否 かは、<br />
主 体 的 決 断 に 委 ねられないはずだ。 言 いかえれば、 永 劫 回 帰 の 肯 定 という 主 体 的 決 断 もまた、 永<br />
劫 回 帰 の 因 果 性 の 結 果 であり、 主 体 的 とは 言 い 難 い。 超 人 の 主 体 性 は、 永 劫 回 帰 においてこそ 存<br />
在 するが、じつは 永 劫 回 帰 そのものにその 根 を 掘 り 崩 されている。<br />
超 人 の 決 断 は、 永 劫 回 帰 の 理 論 全 体 を 転 覆 させてしまうほど、 決 定 的 矛 盾 を 孕 んでいる。しかし、<br />
それは、 時 間 を 単 数 的 に 捉 えることをやめたとき、 一 つの 示 唆 に 満 ちた 説 となる。 永 劫 回 帰 は、ア<br />
ーレントにおける 労 働 の 時 間 了 解 であった。この 日 常 的 時 間 了 解 は、ただひたすら 無 意 味 に 永 続<br />
するものであるが、 人 間 がもしそのなかで 逆 説 的 に 主 体 的 な 決 断 をすることが 可 能 であるとすれば、<br />
それは 永 劫 回 帰 を 変 成 させてしまう。 主 体 的 決 断 において 本 来 性 を 取 り 戻 した 超 人 においては、<br />
永 劫 回 帰 の 意 味 そのものが 変 化 する。それはハイデガー 風 に 言 えば 被 投 性 における 投 企 として、<br />
人 間 的 実 存 の 本 来 性 を 獲 得 するための 決 断 を 意 味 する。その 時 、 人 間 が 永 劫 回 帰 という 時 間 のモ<br />
ードを 生 きつつ、 同 時 に 別 の 時 間 様 態 を 生 きる 可 能 性 が 開 示 される。 人 間 は 決 断 において 本 来 性<br />
モディフィケーション<br />
を 取 り 戻 し、そのとき 永 劫 回 帰 全 体 もまた 変 様 を 被 る。 永 劫 回 帰 そのものの 意 味 が 変 じ、それ<br />
は 肯 定 される。その 肯 定 の 可 能 性 の 根 拠 は、 永 劫 回 帰 とは 別 の 時 間 を 生 きることが 人 間 には 可 能<br />
であるという 事 実 である。<br />
人 間 は、 種 においては 確 かに 永 劫 回 帰 の 時 間 を 生 きている。しかし 同 時 に 永 劫 回 帰 の 無 意 味 さ<br />
とは 無 縁 な――そして 全 てを 手 段 に 貶 めてしまう 目 的 論 的 時 間 了 解 の 暴 力 性 とも 無 縁 な―― 別 の<br />
時 間 を 生 きる 可 能 性 を 備 えている。そして、その 可 能 性 こそが、 人 間 の「 始 める」 力 であり、 活 動 の<br />
活 動 力 である。 超 人 による 永 劫 回 帰 の 肯 定 という 決 断 に 萌 していたのは、 実 は 人 間 存 在 の「 始 める」<br />
力 であった。<br />
補 論 時 計 的 時 間<br />
我 々はアーレントにおける、 労 働 と 仕 事 の 活 動 力 の 分 析 を 終 えた。ここで、その 成 果 を 考 慮 に 入<br />
れつつ、「 時 計 」という 物 の 意 味 を 考 えてみたい。<br />
時 計 は、 真 木 悠 介 の 比 較 社 会 学 における 分 類 で 言 えば、 円 環 的 な 時 間 と 直 線 的 な 時 間 両 方 を<br />
表 現 しうる。それは、アナログ 時 計 がいまだに 円 形 をしている 事 実 からも 看 取 できる。アナログ 時 計<br />
は、 円 環 的 な 時 間 、 何 度 も 巡 る、 終 わりがまた 始 まりであるような 時 間 を 表 現 できる。それに 対 して、<br />
57
デジタル 時 計 は、12 か 月 、30 ないし 31 日 、24 時 間 、60 分 、60 秒 を 単 位 とする、ひたすら 加 算 的 な<br />
計 算 に 基 づいて 時 間 を 表 示 する(たとえば 2011 年 12 月 17 日 16 時 39 分 28 秒 という 時 間 は、<br />
20111217163928 という 数 であるともいうことができる。ただし、 桁 によって 十 進 法 でない 場 所 がある<br />
ので、 年 や 月 に 分 割 して 表 示 した 方 が 都 合 がいいが)。それゆえ、 時 間 はデジタル 時 計 において<br />
は 直 線 的 に 表 象 されうる。<br />
すでに 序 章 で 確 認 したように、 時 間 は、 人 間 が 行 為 する 際 に、その 行 為 と 同 根 源 的 に 生 ずる。<br />
ツァイティグング<br />
時 間 は 人 間 の 行 為 そのものから 発 源 する。 人 間 は、 行 為 を 通 して 自 らを 時 間 化 する。このような 時<br />
間 と 人 間 の 関 係 にあって、 時 計 は、 人 間 の 行 為 と 時 間 の 同 根 源 性 を 除 去 するかのような 役 割 を 果<br />
たす。 時 間 は、 人 間 の 行 為 における 人 間 の 時 間 化 であったが、 時 計 において 時 間 は 疎 外 される。<br />
あたかも、 時 間 は 人 間 の 行 為 とは 独 立 に 存 在 するかのように、そしてむしろ 人 間 の 行 為 こそ 時 間 の<br />
内 側 で 行 われるかのように、そのとき 考 えられるようになる。 人 間 の 活 動 力 から 発 源 してくるはずの<br />
時 間 が、 物 象 化 reified する。<br />
しかし、このような 時 計 の 時 間 経 験 も、 本 来 は 人 間 の 活 動 力 から 発 源 してきたものだったはずだ。<br />
それは 労 働 の 活 動 力 から 発 源 してきた 時 間 経 験 である。すでに 見 たとおり、 労 働 の 活 動 力 は 人 間<br />
が 自 然 的 な 生 命 として 自 然 を 生 きている 動 物 であるという 事 実 に 由 来 する。 人 間 が、「 喰 わねば 死<br />
んでしまう」 生 命 に 対 応 するための 活 動 力 であった。それゆえ、その 時 間 経 験 は、 円 環 的 な 自 然 の<br />
時 間 、 地 球 という 惑 星 の 運 動 に 由 来 する 時 間 に 淵 源 する。<br />
地 球 の 時 間 は 二 つのアスペクトを 持 つ。 一 つは 地 球 の 自 転 運 動 であり、いま 一 つは 地 球 の 公 転<br />
運 動 、 換 言 すれば 太 陽 と 地 球 の 運 動 の 関 係 性 だ。 前 者 は「 日 」( 昼 と 夜 )という 時 間 として、 後 者 は<br />
「 年 」という 時 間 として、 表 象 される。「 一 日 」と「 一 年 」は、 人 間 的 に 概 念 化 されているとはいえ、 本 来<br />
バ イ オ ロ ジ カ ル<br />
はむしろ 生 物 そのものに 含 みこまれている 生 物 学 的 な 時 間 経 験 でもある。 地 球 の 環 境 、 地 球 という<br />
「 条 件 」において、 生 命 として 存 在 するために、 生 物 たちは 時 間 の 経 験 を 持 っている。 地 球 の 回 転<br />
と、 特 定 の 方 向 から 当 たる 陽 光 が、 地 球 の 時 間 を 分 節 し、 昼 夜 という 区 別 をもたらしている。そして<br />
この 原 的 な、 地 球 的 分 節 性 が、そのまま 地 球 上 の 生 命 にも「 時 間 」のなかを 生 きる 運 命 を 与 えてい<br />
るのである。 労 働 の 時 間 は、 労 働 という 活 動 から 発 源 し、また 労 働 は 生 命 から 発 源 する 活 動 力 であ<br />
る。ゆえに、 労 働 の 時 間 経 験 は、 生 命 的 な 時 間 経 験 と 通 底 している。 地 球 が 誕 生 し、そこに 生 命 が<br />
出 現 するという 順 序 が 意 味 していることは、 生 命 がそもそもこの 地 球 的 時 間 にあわせて 創 造 されて<br />
いることを 206 比 喩 的 に 表 現 している。<br />
人 間 が 最 初 に「 計 る」ようになるのは、このような 地 球 的 時 間 、 天 体 の 関 係 を 通 して 了 解 される 時<br />
間 である 207 。 空 には 星 々が 見 える。さらに 太 陽 を 含 む 空 の 動 き 自 体 が、 地 球 の 自 転 の 動 きに 対 応<br />
206<br />
聖 書 で、 神 は 地 球 を、つまり 地 球 の 運 動 を、 人 間 よりも 先 に 創 造 している。「 初 めに 神 が 天 地 を 創 造 された。<br />
〔 略 〕 神 が、『 光 あれよ』と 言 われると、 光 が 出 来 た。 神 は 光 を 見 てよしとされた。 神 は 光 と 暗 黒 との 混 合 を 分 け、 神 は<br />
、、、、、、、 、、、、、、、<br />
、、<br />
光 を 昼 と 呼 び、 暗 黒 を 夜 と 呼 ばれた。こうして 夕 あり、また 朝 があった。 以 上 が 最 初 の 一 日 である」(『 創 世 記 』、1:1-5<br />
〔 関 根 正 雄 訳 『 旧 約 聖 書 創 世 記 』 改 版 、 岩 波 文 庫 、1967 年 、9 頁 〕。 傍 点 は 橋 爪 )。 神 が 生 物 を 作 り 出 したのは 第<br />
五 日 と 第 六 日 、 人 間 を 作 りだしたのは 第 六 日 である。つまりユダヤ=キリストの 神 は、 生 命 と 人 間 を 地 球 の 運 動 のも<br />
とに、それにあわせて 創 造 したのだ。その 運 動 を 時 間 として 経 験 するのは 人 間 であるが、その 運 動 そのものは 人 間<br />
にとって「 先 験 的 」であると 言 える。<br />
207 ジャック・アタリによれば、「 計 時 とは 何 にもまして 天 文 学 に 属 す 行 為 であり、〔 略 〕 非 常 に 長 いあいだ、 空 が 主 要<br />
58
したものであるから、 空 を 見 ることもまた 自 転 と 公 転 への 同 時 的 な 眼 差 しに 他 ならない。<br />
こうした 計 時 に 幾 分 か「 正 確 さ」を 導 入 しようという 試 みが 日 時 計 であった。その 試 みは「 脅 迫 的 な<br />
自 然 の 真 只 中 に 人 工 をためらいがちに 存 在 させるもの」 2<strong>08</strong> でしかなかったが、「 世 界 を 最 初 に 合 理<br />
化 したもの」 209 でもあった。「もっとも 原 初 的 な 文 明 にも、 天 文 学 的 な 日 時 計 に 対 する 知 識 はみられ」<br />
210 カドラン・ソレール き し ん<br />
、「 今 日 跡 づけできる 最 古 の 小 型 日 時 計 は 前 14 世 紀 のエジプトの 晷 針 で、これはただ 一 本 の<br />
棒 を 鉛 直 に 立 てて 太 陽 高 度 を 測 るものだった」 211 が、その 後 精 度 の 高 い 日 時 計 がギリシアにおい<br />
て 現 われた 212 。<br />
水 時 計 は 日 時 計 に 匹 敵 する 古 さをもつ。これは 液 体 の 流 れるリズムを 用 いて 計 時 するのだが、<br />
「 日 時 計 よりも 精 度 においてかなり 劣 る」 213 ものだった。しかしギリシアで 天 文 時 計 と 水 時 計 の 合 わ<br />
せられた 時 計 が 作 り 出 される。こうした〈 天 文 = 水 時 計 〉は、ギリシアにおいてすさまじい 発 展 を 見 せ、<br />
「 歯 車 装 置 と 推 進 軸 の 伝 達 ・プログラミング 技 術 全 体 の 開 発 」 214 によって 一 日 中 時 刻 を 計 る 水 時 計<br />
まで 生 まれたという。こうした 水 時 計 はすでに、 人 間 の 時 間 経 験 が「 客 観 的 時 間 」として 物 象 化 し、<br />
自 然 や 生 命 、そして 労 働 の 活 動 力 から 乖 離 する 端 緒 であろう。 水 時 計 は、ギリシアにおいて 早 くも<br />
、、、、、、、、<br />
「メカニズム」として 完 成 していた。 日 時 計 はどこまでいっても 地 球 の 運 動 の 表 現 にすぎないが、「メ<br />
カニズム」としての 水 時 計 は、 地 球 の 運 行 とはほとんど 関 係 なく 動 く。もっともその 水 時 計 も、〈 天 文<br />
= 水 時 計 〉として、 天 体 や 地 球 との 関 係 をいまだに 色 濃 く 反 映 していたのであるが。 水 時 計 は 永 続<br />
的 に 動 いているはずもなく、 日 時 計 を 基 準 に 訂 正 された。このため 生 命 と 時 間 はまだ 直 截 的 な 繋 が<br />
りを 保 っていた。<br />
中 世 の 終 わりに 機 械 仕 掛 けの 時 計 が 出 現 する。 角 山 栄 によれば「 中 世 ヨーロッパに 出 現 した 機<br />
械 時 計 は、いままでの 時 計 とは 根 本 的 に 原 理 がちがう」 215 お も り<br />
。 水 に 代 って、 重 錘 の 落 下 を 時 計 の 動 力<br />
として 採 用 するようになったのだ 216 エ ス ケ ー プ メ ン ト<br />
。 更 に 脱 進 装 置 が 重 錘 の 力 を、 時 計 を 駆 動 する 動 力 に 転 換 す<br />
る 仕 組 みとなった。 時 計 は 人 間 の 手 を 離 れつつあった。<br />
クロッカ<br />
ところで 中 世 の 時 代 に 現 われた 教 会 の「 鐘 」は、 時 間 の 物 象 化 ということに 関 連 して、 別 の 問 題<br />
を 突 き 付 けている。 教 会 はローマで 用 いられていた 24 時 ではなく、 独 自 の 7 時 制 を 採 用 していた。<br />
この 七 定 時 課 は、ローマの 24 時 制 よりも 人 々の 生 活 に 適 合 していたため、 当 時 のキリスト 教 圏 に 広<br />
がった。そして「 一 日 という 尺 度 で 七 定 時 課 を 計 時 基 準 として 課 すために、そして 旧 来 の 時 刻 決 定<br />
法 を 一 掃 するために、 新 しい 権 力 は 以 後 一 千 年 の 長 きにわたって、ヨーロッパの 時 間 測 定 と 時 間<br />
な 計 時 具 であった」(ATTALI. 前 掲 訳 書 、52 頁 )。<br />
2<strong>08</strong><br />
同 上 、52 頁 および 53 頁 。<br />
209<br />
同 上 、52 頁 。<br />
210<br />
同 上 、53 頁 。<br />
211<br />
同 上 。<br />
212 ユニヴェルセル<br />
「パルメニオン〔 略 〕が 最 初 の 本 格 的 な 日 時 計 、つまりオリエンテーションが 太 陽 につれて 動 く 日 時 計 を 考 案 し<br />
た」( 同 上 、57 頁 )。<br />
213<br />
同 上 、59 頁 。<br />
214<br />
同 上 。<br />
215<br />
角 山 栄 『 時 計 の 社 会 史 』 中 公 新 書 、1984 年 、7 頁 。<br />
216 お も り<br />
「すなわち 初 期 の 機 械 時 計 の 原 理 は、 紐 に 吊 した 重 錘 が 落 下 してゆく 力 を、 一 定 の 時 間 間 隔 で 規 則 的 に 落 下<br />
するように 機 械 で 調 整 したものである。その 落 下 するスピードを 調 整 する 装 置 が、 歯 車 の 歯 止 めの 役 目 をする 冠 形<br />
59
管 理 の 歴 史 を 特 徴 づけるようになる、 新 しい 計 時 具 に 基 盤 を 置 く」 217 。 鐘 である。 修 道 院 で 鳴 らされ<br />
る 鐘 は 都 市 や 農 村 に 響 きわたり、その 生 活 のリズムを 成 形 していった。 刻 む 時 間 こそ 7 時 間 制 で<br />
我 々とは 異 なるが、ここに 単 一 の 時 間 が 多 くの 人 々の 時 間 を 組 織 するという 事 態 が 見 られる。 換 言<br />
すれば、 時 間 が 一 つの 共 同 性 を 喚 起 しているのだ。<br />
ベル<br />
さらに「 機 械 時 計 のことを『クロック』というのは、ラテン 語 の CLOCCA つまり〈 鐘 〉からきている」 218 。<br />
機 械 時 計 が 最 初 に 作 られたのは 修 道 院 においてで、それは「 修 道 院 の 中 では 修 道 僧 が 昼 も 夜 も<br />
一 定 の 時 刻 に 神 に 祈 りを 捧 げていたわけで、 彼 らにとって 正 確 な 祈 りの 時 間 を 知 る 必 要 があったか<br />
らである。 時 間 がくれば 自 動 的 にチンチンと 鐘 が 鳴 る 機 械 時 計 があれば、 夜 昼 となく 祈 りの 時 間 を<br />
気 にしなくてすむ。そういうわけで 機 械 時 計 には、その 出 現 の 当 初 から 必 ず 鐘 がついていた」 219 。<br />
示 唆 的 なのは、 修 道 院 において 修 道 僧 は「 昼 も 夜 も 一 定 の 時 刻 に」 祈 りを 捧 げていた、という 点 で<br />
ある。それはつまり 修 道 僧 の 生 きる 時 間 が 自 然 の 時 間 からある 程 度 分 離 されていたことを 意 味 する。<br />
言 い 換 えれば、 彼 らは 一 種 の「 客 観 的 な 時 間 」を 生 きていたのだ。それを 裏 付 けるのは、 時 計 がも<br />
はや 自 然 的 な 動 力 源 から 分 離 し「 自 動 的 に」 鐘 を 鳴 らしているということである。さらに、その「 客 観<br />
的 な 時 間 」が、「 鐘 」という 器 具 によって 都 市 や 農 村 の 人 々に 共 有 されている。 人 間 の 外 部 に 独 立 し<br />
た 時 間 が 生 まれ、 時 間 が 人 間 を 逆 に 動 かしつつある。 機 械 の 時 計 は 時 計 の「 客 観 性 」を 強 化 した。<br />
ストッカージュ<br />
重 錘 と 鐘 とに 続 く 技 術 革 新 は、「 統 御 可 能 なエネルギーの 貯 蔵 庫 として」 220 のゼンマイであり、そ<br />
れが 促 す 小 型 化 を 通 して、 時 計 はポータブルとなった。ついに「 時 計 のサイズが 十 分 小 型 化 し、 衣<br />
服 につけて 携 帯 や 誇 示 のできる 計 時 具 となった」 221 。そのゼンマイが、もう 一 つの 新 技 術 である「 振<br />
り 子 」と 結 びつき、 懐 中 時 計 に 組 み 込 まれたとき、「それは 時 間 が 身 体 の 上 に 持 ち 込 まれたことを 意<br />
味 する」 222 。そしてそれは「 労 働 」(ここでは、 必 ずしもアーレントの 言 う 労 働 ではない)の 形 態 にも 影<br />
響 する。「より 精 度 を 増 した 時 計 は、 律 動 的 で 恒 常 的 な 新 しい 分 節 化 した 時 間 をひとつ 創 り 出 す。<br />
、、、、<br />
正 確 な 労 働 時 間 がそれであった。いわゆる 先 端 技 術 によって、 労 働 時 間 がきちんと 測 られるような<br />
ったのである。そこではもはや 社 会 的 身 体 は 集 団 的 な 時 間 に 服 従 せず、 各 個 人 は 一 個 の 時 計 とし<br />
て、 機 械 として 考 えられていた」 223 。この 技 術 革 新 は、 重 錘 がもたらした 時 計 の 自 動 化 、 鐘 がもたら<br />
した 時 間 の 共 同 化 を、 同 時 に 推 し 進 めたのである。 時 間 は 偏 在 するものと 化 した。この 偏 在 性 はそ<br />
の 後 腕 時 計 という 形 で 具 現 化 し、 今 では「 時 計 」という 形 態 すら 失 ってあらゆる 機 械 の 中 へと 入 り 込<br />
んでいる。<br />
他 方 、 時 間 の「 正 確 さ」も 飛 躍 的 に 進 歩 している。20 世 紀 に 入 ると、まず 水 晶 に 電 気 をかけた 際<br />
の 規 則 的 振 動 から「1 秒 」を 定 義 する 水 晶 時 計 が 開 発 され、 後 にはセシウム 原 子 の 電 波 の 振 動 数<br />
から「1 秒 」を 定 義 する 原 子 時 計 が 発 明 される。 原 子 時 計 にいたっては 百 億 分 の 一 秒 をも 測 定 する<br />
の 脱 進 装 置 (エスケープメント)と、 時 間 の 調 整 をするテンプである」( 同 上 )。<br />
217 ATTALI, 前 掲 訳 書 、78 頁 。<br />
218<br />
角 山 、 前 掲 書 、7-8 頁 。<br />
219<br />
同 上 、7 頁 。<br />
220 ATTALI. 前 掲 訳 書 、167 頁 。<br />
221<br />
222<br />
223<br />
同 上 、174 頁 。<br />
同 上 。<br />
同 上 、179 頁 。<br />
60
ことができるという。このような「 時 間 」は、もはや 感 覚 的 理 解 を 受 け 付 けない。この 窮 極 的 に 客 観 的<br />
な《1 秒 》の 積 み 重 ねである《24 時 間 》は、ローマ 人 の「24 時 間 」と 似 ているとしても、 全 く 別 物 である。<br />
ローマ 人 の「24 時 間 」には 自 然 と 生 命 から 発 源 する 時 間 性 が 反 映 していたが、 我 々の《24 時 間 》は、<br />
原 子 から 発 生 する 電 波 の 振 動 を 機 械 的 にトレースすることによって 測 られ、 機 械 を 通 してかろうじて<br />
理 解 できるような「 時 間 」である。それは、 人 間 の 主 観 が 入 り 込 む 余 地 のない、 下 手 をすると 誰 にも<br />
理 解 できなくなってしまうほど、 恐 ろしいまでの「 客 観 性 」を 帯 びた「 時 間 」なのだ。 実 際 、このような<br />
時 間 が「 何 を 意 味 しているのか」、 我 々には 殆 ど 理 解 できない。たとえば、 次 のような 思 考 実 験 をし<br />
てみよう。 宇 宙 のどこかに、 宇 宙 ステーションのような 居 住 空 間 を 設 けて、そこにただ 一 人 住 むので<br />
ある。そこには 昼 も 夜 もない。ここで 時 計 に 何 の 意 味 があるのか。それが 示 す「 時 間 」は、 自 分 にと<br />
って 遠 い 惑 星 に 流 れる、 地 球 と 太 陽 の 運 動 の 関 係 性 の 表 現 としての 時 間 にすぎない。ここに 時 間<br />
の「 正 確 さ」という 概 念 が、ひとつの 倒 錯 であるということが 理 解 される。その 数 的 な「 正 確 さ」は、む<br />
しろ 数 を 以 って 表 現 したからこそ 求 められているのであって、 逆 ではない。 地 球 や 太 陽 の 運 動 も、<br />
( 文 字 通 り) 天 文 学 的 な 長 さの 時 間 の 中 では 変 化 する。その 相 対 的 な 変 化 に 従 って、 生 命 から 発 源<br />
する 時 間 経 験 も 変 化 するはずである。<br />
「 正 確 な 時 間 」という 要 求 は、むしろ 時 計 の「 客 観 的 」な 性 格 から 生 じるものである。ここで 言 う「 客<br />
観 性 objectivity」は、アーレントの 言 う 意 味 において 理 解 されねばならない。つまり、 人 間 の 意 識 に<br />
よって 簡 単 に 変 化 することなく、それゆえに 複 数 の 人 間 によって 共 同 的 にリアリティとして 認 められ<br />
るということを 意 味 する。それは 時 間 を 共 有 する 要 求 には 合 致 しているが、「 客 観 的 」な 時 間 は、 時<br />
間 が 人 間 の 活 動 力 から 発 源 しているという 事 実 を 人 間 から 忘 却 させ、 逆 に 人 間 を 縛 り、 支 配 し、 動<br />
かすようになる(セシウムの 振 動 数 から「 精 確 な」 一 秒 を 確 定 するという 倒 錯 !)。 時 間 の 客 観 化 は、<br />
地 球 規 模 での 人 間 の 協 働 を 可 能 にする 条 件 でもある。だが、 他 方 その 代 償 として 個 々の 人 間 の 時<br />
間 を 圧 殺 し、 搾 取 する 性 格 を 帯 びかねない。<br />
時 計 的 な 時 間 経 験 そのものは、 労 働 の 時 間 経 験 に 由 来 するが、 時 間 の 物 象 化 reification にお<br />
いて、 時 間 が 人 間 の 活 動 力 と 経 験 から 発 源 するということは 忘 れられる。しかし 時 間 は、 物 となるこ<br />
と、 物 化 reification を 通 して、 世 界 の 一 部 となる。 物 化 によって 得 られる「 客 観 性 」は、 複 数 の 人 間<br />
が 共 通 して 認 め 得 るようなリアリティの 性 格 を、 時 間 に 与 え、 人 間 の 協 働 Zusammenwirken の 基 礎<br />
を 与 えるのである。<br />
61
第 五 章 活 動 action の 時 間 性<br />
時 ハ 変 転 シ、 我 々ハソノ 時 ノナカデ 変 転 スル。<br />
Tempora mutantur et nos mutamur in illis.<br />
――ラテン 語 の 古 諺<br />
第 20 節 活 動 の 性 格 ―― 唯 一 性 と 始 まり<br />
人 間 は、 世 界 を 建 設 するために 仕 事 をする。その 仕 事 は 目 的 論 的 性 格 を 備 えており、 始 まりから<br />
終 わりへという 確 かなコースを 持 っていた。さらに 仕 事 の 活 動 力 そのものは、その 目 的 を 達 成 して<br />
物 が 作 られると 消 滅 する。これが 仕 事 の 目 的 論 的 な 時 間 経 験 である。 人 間 は 同 時 に 飢 える。それ<br />
は 人 間 もまた 生 命 であるという 事 実 性 に 淵 源 している。 人 間 は 食 べねばならず、 眠 らねばならない。<br />
生 命 という 人 間 の 条 件 に 対 応 するために 人 間 は 労 働 する。 労 働 には 本 性 上 終 わりはない( 終 わりと<br />
見 做 される 瞬 間 は、すでに 次 の 労 働 の 始 まりである)。 労 働 の 時 間 は 円 環 をなし、その 時 間 経 験 は<br />
永 劫 回 帰 という 時 間 論 に 帰 結 する。<br />
活 動 action, Handeln は、「 物 あるいは 事 柄 の 介 入 なしに 直 接 人 と 人 との 間 で 行 われる 唯 一 の 活<br />
動 力 であり、 複 数 性 〔plurality〕という 人 間 の 条 件 、すなわち 地 球 上 に 生 き 世 界 に 住 むのが 大 文 字<br />
の 人 間 〔Man〕ではなく、〔 複 数 の〕 人 間 たち〔men〕であるという 事 実 に 対 応 している。〔 略 〕この 複 数<br />
性 こそ、 全 政 治 生 活 の 条 件 であり、その 必 要 条 件 であるばかりか、 最 大 の 条 件 である」 224 。<br />
活 動 という 活 動 力 がそこから 発 源 するところの 事 実 性 ( 人 間 の 条 件 )は 複 数 性 plurality である。<br />
人 間 がただ 一 人 ではないという 点 が、ここで 強 調 される。だが、 人 間 が 一 人 でなく 複 数 であるという<br />
のならば、 動 物 はそうではないのか。あるいは 物 でさえ 複 数 あるのではないのか。そういう 疑 問 がこ<br />
こで 生 じる。 実 際 、 物 や 動 物 が 数 多 くあることと、 人 間 が 複 数 であることとは、 異 なっている。アーレ<br />
ディスティンクトネス ア ザ ネス ユ ニー ク ネス<br />
ントは 差 異 性 と 他 性 、そして 唯 一 性 の 違 いとして、その 相 違 を 描 いている。 存 在 するあらゆる 物 は、<br />
「 他 と 異 なる」という 単 純 な 意 味 において、 他 性 を 備 えている。それはちょうど、 路 傍 の 石 ころがすべ<br />
て 異 なった 形 状 をしているというような 事 実 に 対 応 している。 極 端 な 例 を 出 せば、 砂 漠 を 形 づくる 無<br />
数 の 砂 粒 のうち、ひとつとして 他 の 砂 と 同 じ 形 をしたものはないであろう。 有 機 的 生 命 もそれぞれの<br />
デ ィ ス テ ィ ン ク ト<br />
種 の 内 に 多 様 な 個 体 を 抱 えているが、そうした 有 機 的 生 命 にあっては 個 体 差 が 際 立 っている 。つ<br />
ディスティンクトネス<br />
まり 個 体 は 成 長 や 行 動 を 通 して 個 性 的 に 振 舞 うだろう。 差 異 性 とはそのような 多 様 性 である。 人<br />
間 もまた 差 異 性 を 備 えていて 個 々の 人 間 はそれぞれ 異 なるのだが、 単 に 異 なる( 単 に 個 性 的 であ<br />
ユ ニ ー ク<br />
る)のみならず、 唯 一 的 なのである。「したがって、 人 間 の 多 数 性 とは、 唯 一 的 存 在 者 の 逆 説 的 な 複<br />
数 性 である」 225 。<br />
人 間 が 唯 一 的 unique であるとはどういうことであるか。そしてそれが 多 数 性 と( 一 見 ) 相 容 れない<br />
とは、どういう 意 味 においてであろうか それは、 唯 一 性 uniqueness という 属 性 が、 伝 統 的 にどう<br />
いうことを 意 味 していたのか、ということを 考 えると 理 解 しやすい。 唯 一 性 とは、 特 に 神 学 において、<br />
224 ARENDT, The Human Condition (op.cit.), p.7. ( 前 掲 訳 書 、20 頁 。)<br />
225 Ibid., p.176. ( 前 掲 訳 書 、287 頁 。)<br />
62
神 の 属 性 であった。たとえば、あるキリスト 教 神 学 者 は 次 のように 書 く。「 三 位 一 体 の 玄 義 は 神 の 唯<br />
一 性 に 基 づく。 絶 対 自 存 の 神 が、もとより 二 つとあり 得 ようはずはない。 二 つあれば 矛 盾 である」 226 。<br />
ギリシア 神 話 のゼウスのような、 多 神 の 主 宰 者 「は 皆 同 位 の 多 数 中 の 優 越 者 であって、 首 長 たる 神<br />
も 従 属 する 神 々も、 同 列 中 の 優 劣 を 争 うにすぎぬ」のであるが、これに 対 しキリスト 教 の 神 は「one<br />
among many にあらずして unique で」 227 、「その 一 なるは 二 、 三 、 四 ……に 対 する 一 ではなくて、 超<br />
ユ ニ タ ス<br />
越 性 の 唯 一 性 による」 228 。この 文 章 から 唯 一 的 unique という 言 葉 の 含 意 は 明 白 に 読 み 取 ることが 出<br />
来 る。 神 が 唯 一 であるということは、その 神 のほかに 神 はいないということを 意 味 するのだ。たとえば、<br />
ゼウスのほかにヘラやアテナ、ポセイドンなどといった 具 合 に 複 数 の 神 々がいる 場 合 、 如 何 にゼウ<br />
ワ ン ・ ア マ ン グ ・ メ ニ ー<br />
スの 実 力 が 他 を 圧 倒 しているとしても、 彼 は「 多 数 のうちのひとつ 」にすぎないのである。<br />
仮 に「 犬 」がユニークな 存 在 であると 仮 定 するなら、それが 意 味 するのは、その「 犬 」の 他 に 犬 は<br />
一 匹 もいないということである。 実 際 には 犬 は 沢 山 存 在 しているから、 犬 はユニークではありえない。<br />
ただし 犬 は 沢 山 いるとしても、 概 念 としては「 犬 」という「 類 」として 扱 うこともできる。<br />
人 間 ではどうなのか。「 私 」という 人 間 がユニークであるとするならば、この 神 学 的 な「ユニーク」の<br />
定 義 を 受 け 継 ぐ 限 りは、「 私 」という 人 間 の 他 に 人 間 は 全 くいないという、 独 我 論 的 な 結 論 にならざ<br />
るを 得 ない。 現 実 には、 人 間 は 複 数 存 在 している( 独 我 論 のような、リアリティを 欠 いた 空 想 を 別 と<br />
すれば)。いったいどうして、 人 間 がユニークであると 言 えるだろうか。ましてや、アーレントは「 大 文<br />
字 の 人 間 Man ではなく、 複 数 の 人 々men が 存 在 する」と 述 べていたではないか。アーレントの「 唯<br />
一 的 存 在 者 229 の 逆 説 的 な 複 数 性 」とは、まさにこのことを 言 っているのだ。アーレント 自 身 、それが<br />
パラドクス<br />
伝 統 的 な 思 考 法 からすれば 逆 説 であることを 表 明 している。この 逆 説 を 解 消 する 鍵 が「 始 まり」とい<br />
う 概 念 にある。<br />
言 論 と 活 動 〔speech and action〕は、このユニークな 差 異 性 を 明 らかにする。そして、 人 々は、<br />
デ ィ ス テ ィ ン ク ト デ ィ ス テ ィ ン グィ ッシ ュ ・ ゼ ム セ ルヴス<br />
単 に 差 異 がある だけでなく、 言 論 と 活 動 を 通 して 自 ら 互 いを 区 別 する 。つまり 言 論 と 活 動 は、<br />
人 間 たちが、 物 理 的 な 対 象 としてではなく、 人 々として、 相 互 に 現 われる 様 態 である。この 現 わ<br />
イニシアティヴ<br />
れは、 単 なる 肉 体 的 存 在 と 違 い、 人 間 が 言 論 と 活 動 によって 示 す 創 始 〔initiative〕にかかっ<br />
ている。 230<br />
アーレントはここでは 創 始 と 名 指 しているが、これは 始 める 能 力 に 他 ならない。 人 間 は 活 動 によって<br />
ものごとを「 始 める」。この 始 める 力 が、 単 純 な 差 異 性 を 超 えたユニークさ、 唯 一 性 を 人 間 に 与 える<br />
のである。 犬 は 新 しいことを 始 めたりはしない。だからどんなに 個 性 的 であっても 究 極 的 には「 犬 」と<br />
226<br />
岩 下 壮 一 『カトリックの 信 仰 』 講 談 社 学 術 文 庫 、1994 年 、94 頁 。<br />
227<br />
同 上 、95 頁 。<br />
228<br />
同 上 。<br />
229 「 唯 一 的 存 在 者 」と 訳 した 語 は、unique beings である。この 表 現 自 体 、 伝 統 的 な 形 而 上 学 や 存 在 論 や 神 学 から<br />
すれば、「 形 容 矛 盾 contradictio in adjecto」である。<br />
230 ARENDT, op.cit., p.176. ( 前 掲 訳 書 、287 頁 。)<br />
63
いう 類 概 念 でまとめて 取 り 扱 えるのだ。しかし 人 間 は「 類 」としてまとめることはできない 231 。 人 間 は<br />
各 々が 新 しいことを 始 めるので 単 に 個 性 的 であるということを 超 えてユニークなのである。<br />
この 始 める 力 もまた、 後 で 詳 しく 見 るが、 従 来 の 哲 学 においては 唯 一 、 神 に 与 えられる 権 能 であ<br />
った。 人 々は、 伝 統 的 な 哲 学 における 神 のように、それぞれが 自 ら 始 めることで、それぞれの 唯 一<br />
性 を 示 すのである 232 。そして 我 々の 時 間 論 的 探 究 においても、この 始 まりという 特 性 こそは、 活 動<br />
の 時 間 経 験 をもっともよく 特 徴 付 ける 性 質 である。 活 動 の 時 間 性 は、 始 まりという 時 間 経 験 に 集 約 さ<br />
れる。<br />
第 21 節 「 始 まり」の 時 間 論 的 性 格<br />
それでは、 始 まりとはなにか。 始 めるとはなにをすることなのか。<br />
すでに 引 用 した 箇 所 からも 読 みとれるが、 活 動 することと 始 めることを、アーレントは 殆 ど 同 じもの<br />
テイク・アン・イニシアティヴ<br />
として 描 く。「『 活 動 する』というのは、 最 も 一 般 的 には、『 創 始 する 』、『 始 める』という 意 味 であり<br />
(ギリシア 語 のアルケイン、つまり「はじめる」、「 導 く」、そして 最 終 的 に「 支 配 する」、という 単 語 が 示<br />
セット・イントゥ・モーション<br />
しているように)、またなにかを 運 動 させる という 意 味 である(これはラテン 語 のアゲレなる 動 詞 の 原<br />
義 である)」 233 。さらに 彼 女 によれば「ギリシア 語 とラテン 語 は、 近 代 語 と 違 って、『 活 動 する』という 動<br />
詞 を 指 示 するのに、まったく 異 なる、しかし 相 互 に 関 連 する 二 つの 単 語 をもっている」 234 。つまり、<br />
「ギリシア 語 の 二 つの 動 詞 アルケイン(「 始 める」、「 導 く」、そして 最 後 に「 支 配 する」)とプラッテイン<br />
セット・イントゥ・モーション<br />
(「 通 り 抜 ける」、「 達 成 する」、「 終 える」)は、 二 つのラテン 語 の 動 詞 アゲレ(「 運 動 させる 」、「 導 く」)<br />
とゲレレ(その 原 義 は「 担 う」)に 対 応 している」 235 。アーレントは、このように 活 動 するという 動 詞 が 二<br />
つの 動 詞 に 分 かれていることについて、 活 動 そのものが 二 つの 部 分 に 分 かれるものであると 指 摘<br />
する。「すなわち、 第 一 が、 一 人 の 人 物 が 行 なう『 始 まり』であり、 第 二 が、 人 びとが 大 勢 加 わって、<br />
ある 企 てを『 担 い』、『 終 わらせ』、 見 通 して、その 企 てを 達 成 する 過 程 である」 236 。<br />
なぜ 一 人 の 人 間 が 始 めたことが、 複 数 の 人 々によって 終 えられることになるのか。それも 人 間 が<br />
単 数 者 でなく 複 数 者 であるという 事 実 に 由 来 する。「 活 動 者 〔actor〕は 他 の 活 動 する 存 在 者 たちの<br />
なかを、それらに 係 わりながら、 動 くのであるから、 決 して『 行 為 者 〔doer〕』であるのみならず、 常 に<br />
231 アーレントがマルクスの 類 的 存 在 Gattungswesen という 人 間 規 定 に 反 発 することの 基 礎 は、このような 人 間 理 解<br />
にあると 考 えられる(もちろん、アーレントにとっても、 労 働 スル 動 物 animal laborans としての 人 間 は、 類 的 存 在 であ<br />
るが)。<br />
232 デリダは、『 死 を 与 える』において Tout autre est tout autre という 謎 めいた 命 題 を 与 えている(DERRIDA, Jacques,<br />
Donner la mort, Paris : Édition Galilée, 1999, pp.114ff. 〔 廣 瀬 浩 司 / 林 好 雄 訳 『 死 を 与 える』ちくま 学 芸 文 庫 、2004<br />
年 、169 頁 以 下 〕)。このフランス 語 は「あらゆる 他 者 / 全 くの 他 者 」は「あらゆる 他 者 / 全 くの 他 者 」である、というよう<br />
に 四 通 りに 訳 すことができる。ここで「 全 くの 他 者 」と 取 る 場 合 、それは 絶 対 他 者 としての 神 を 意 味 することになる。と<br />
ころが「あらゆる 他 者 は 全 くの 他 者 である」とこの 文 を 理 解 した 場 合 、すべての 他 者 が 神 のような 絶 対 他 者 であるとい<br />
うことを 意 味 してしまう。このように 理 解 すると 伝 統 的 な 哲 学 的 了 解 からすると 矛 盾 を 含 むことになるが、デリダはあえ<br />
てこのように 読 むことで、( 人 間 の) 他 者 の 絶 対 的 他 者 性 を 強 調 しようとするのである。このような 神 の 絶 対 他 者 性 を<br />
人 間 に 読 み 込 むという、 謂 わば「 神 学 の 人 間 学 的 転 釈 」は、アーレントの 唯 一 性 の 議 論 に 通 ずるものがある。むしろ、<br />
デリダの Tout autre est tout autre という 命 題 は、アーレントの 始 まりの 議 論 によって 基 礎 づけられるだろう。<br />
233 ARENDT, op.cit., p.177. ( 前 掲 訳 書 、288 頁 。)<br />
234 Ibid., p.189. ( 前 掲 訳 書 、305 頁 。)<br />
235 Ibid. ( 前 掲 訳 書 、305-306 頁 。)<br />
236 Ibid. ( 前 掲 訳 書 、306 頁 。)<br />
64
アクション<br />
同 時 に 被 害 者 〔sufferer〕でもあるのだ。〔 略 〕なるほど 活 動 は、それ 自 体 新 しい『 始 まり』である。しか<br />
リアクション<br />
し、 活 動 は 人 間 関 係 の 網 の 目 という 環 境 の 中 で 行 なわれる。この 環 境 の 中 では、 一 つ 一 つの 反 動<br />
が 一 連 の 反 動 となり、 一 つ 一 つの 過 程 が 新 しい 過 程 の 原 因 となる」 237 。 人 間 は 複 数 存 在 するため、<br />
一 人 の 人 間 の 始 めることは、 必 ず 他 の 人 間 たちと 共 にある 世 界 において 始 められ、 他 の 人 間 たち<br />
リアクション<br />
の 反 応 を 呼 び 起 こすのである。つまり 始 めることは 人 々のなかで、ひとつの 過 程 の 原 因 となることで<br />
あり、ひとつの 過 程 を 始 めることである。<br />
人 間 が 始 めることが 可 能 であるのは、 人 間 そのものが 始 まりであるからだとアーレントは 考 える。<br />
ユ ニ ー ク<br />
それは、「 人 間 は 一 人 一 人 が 唯 一 的 であり、したがって、 人 間 が 一 人 一 人 誕 生 するごとに、なにか<br />
新 しいユニークなものが 世 界 にもちこまれるためである。この 唯 一 的 な 誰 かについていえば、たしか<br />
に、 以 前 にはだれもいなかったといえるだろう」 238 。 言 いかえれば、「 活 動 の 能 力 は、 存 在 論 的 には<br />
出 生 〔natality〕という 事 実 にもとづいている」 239 イニティウム<br />
。「 人 間 は、その 誕 生 によって、 始 マリ 〔initium〕、 新<br />
イニシアティヴ<br />
参 者 〔newcomers〕、 創 始 者 〔beginners〕となるがゆえに、 創 始 を 引 き 受 け、 活 動 へと 促 される」 240 。<br />
彼 女 は、アウグスティヌスの「 始 マリガ 存 在 センガタメニ、 人 ハ 創 造 サレタノデアリ、ソレ 以 前 ニハ 誰<br />
モ 無 カッタ[Initium] ergo ut esset, creatus est homo, ante quem nullus fuit」 241 という 言 葉 はこのことを<br />
意 味 していたと 捉 えている。 人 間 は 一 人 一 人 が 始 まりであり、「この 唯 一 的 な 誰 かについていえば、<br />
たしかに、 以 前 にはだれもいなかったといえる」。 無 論 この 解 釈 は 些 か 曲 解 的 ではあるが 242 、 彼 女<br />
はアウグスティヌスの 言 葉 を、 複 数 の 人 間 たちの 一 人 一 人 に 関 しても、 適 用 しうると 捉 えるのである。<br />
人 間 は、 自 らが 出 生 によってこの 世 界 に 出 現 する 始 まりであるために、この 世 界 で 新 しい 過 程 を 始<br />
めることが 出 来 る。それが 活 動 なのだ。<br />
ところで、このような「 始 まり」そのものは、どのように 性 格 づけることが 出 来 るだろうか。そもそも、<br />
アーレントに 限 らず、 始 まりとはなにを 意 味 していると 考 えるべきだろうか。 始 めることそのものは、 別<br />
段 難 しいことには 思 われない。 我 々はいつもなにかを「 始 めて」いる。しかし、ある 過 程 を 始 めること<br />
そのものは、 本 当 に 可 能 なのだろうか。たとえば、ある 人 が 料 理 を「 始 める」とき、その 過 程 を 始 めた<br />
のは 本 当 にその 人 自 身 の 自 発 的 意 志 によるのか その 人 が 料 理 をはじめたのは、 他 人 に 振 舞 う<br />
ためであったにせよ、 自 身 空 腹 であったためにせよ、また 料 理 がその 人 の 生 業 であったにせよ、い<br />
ずれにしても、なんらかの 他 の 原 因 ないし 目 的 に 従 った 結 果 であると 考 えられるだろう。では「 始 ま<br />
り」はその 人 の 空 腹 なのか。だがそれらの 原 因 もまた、それ 自 身 「 始 まり」であるとは 言 い 難 い。とい<br />
うのは、その 人 が 空 腹 を 感 じるのは 生 きているためであり、 生 きていること 自 体 もなにかの 原 因 によ<br />
237 Ibid., p.190. ( 前 掲 訳 書 、307 頁 。)<br />
238 Ibid., p.178. ( 前 掲 訳 書 、289 頁 。)<br />
239 Ibid., p.247. ( 前 掲 訳 書 、385 頁 。)<br />
240 Ibid., p.177. ( 前 掲 訳 書 、288 頁 。)<br />
241 AUGUSTINUS, De civitate Dei, XII, XXI. ( 前 掲 訳 書 、160 頁 。 但 し、ここではアーレントの 意 を 汲 むかたちで 訳 し<br />
直 してある。この 文 章 の 解 釈 に 関 しては、 直 後 に 述 べたとおりである。)<br />
242 ここでアウグスティヌスが「 人 間 homo」と 言 っているのは、(ラテン 語 には 定 冠 詞 がないため、 一 般 名 詞 的 に 受 け<br />
取 ることが 可 能 であるとはいえ) 特 定 の 人 間 、 要 するに 原 初 の 人 間 であるアダムのことであると 考 えられる。アウグス<br />
ティヌスがこのことを 強 調 したのは、 始 まりなどないとする 円 環 的 な 時 間 性 の 主 張 に 対 する 対 決 においてであって、<br />
このこと 自 体 には「 始 まり」という 概 念 を 時 間 論 的 思 考 に 導 入 したという 成 果 は 認 められるが、アーレントの 理 解 して<br />
いるような 意 味 は 厳 密 にはここでは 認 められないだろう。ここでの 始 まりは、 神 によるものなのだ。<br />
65
るからだ。このような 具 合 に「 始 まり」はどこまでも 辿 り 得 るのではないか、というパラドクスが 存 在 す<br />
る。<br />
このような 無 限 後 退 のパラドクスに 答 えるために、アリストテレスは、 自 らは 動 かず、それでいて 他<br />
の 全 てを 動 かす「 不 動 の 動 者 」を 想 定 した 243 。 要 するに、 因 果 の 系 列 の「 始 まり」にある「なにか」を、<br />
理 論 上 置 かざるを 得 なかったのである。もしその「なにか」 以 前 に 別 のものがあるとすれば、それは<br />
すでに「 始 まり」ではないことになる。それゆえ、この 絶 対 的 な「はじまり」である「 不 動 の 動 者 」 以 前<br />
にはなにものもありえようがなく、この「 不 動 の 動 者 」こそは、 自 ら 以 外 に 原 因 を 持 たない「 自 己 原 因<br />
causa sui」であり、「 第 一 原 因 πρώτη αἰτία, causa prima」 244 なのだ。このような「 始 まり」の 存 在 は、<br />
( 大 雑 把 な 言 い 方 ではあるが) 神 学 において 神 と 呼 ばれることになる。「 始 まり」が 神 に 属 するもので<br />
あったというのは、この 意 味 である。もし 神 を 想 定 しないのであれば、 始 まりの 存 在 しない 円 環 を 考<br />
えるほかない。アウグスティヌスは、 神 による 世 界 と 時 間 の 始 まりを 強 調 しているが、それはこのよう<br />
な 円 環 的 時 間 という 命 題 に 対 抗 する 手 立 てに 他 ならなかった。<br />
しかしながら、アーレントの 言 う 始 まりは、アリストテレスやアウグスティヌスのそれとはかなり 異 なる。<br />
アーレントは、 複 数 の 人 々がそれぞれ「 始 める」ことができると 言 うのだ。これは 従 来 の 哲 学 や 神 学<br />
の 議 論 を 逆 撫 でするような 主 張 である。 複 数 の 人 々が、それぞれユニークであり、それぞれ 始 める<br />
ことができるというこの 主 張 は、 単 に 反 抗 的 であるだけでなく、 実 際 に 主 張 そのものから 来 る 困 難 を<br />
孕 んでいるように 見 える。 始 まりそのものには、それ 自 身 のほかになんの 原 因 もあってはならない。<br />
そして 現 在 の 世 界 がなんらかの 先 行 する 状 態 の「 結 果 」であるとすれば、あらゆる 状 態 に 先 行 する<br />
起 源 なるものはただひとつあるとしか 考 えられない。 反 対 に、この 世 界 の 人 間 が 行 なっていることは、<br />
すべてなんらかの 原 因 から 来 る 結 果 であるように 思 われる。 少 なくとも、 人 間 は 自 由 になにかを「 始<br />
める」には、 制 約 が 多 すぎるように 思 われる。なんらかの 制 約 がある 時 点 で、その 人 間 の 活 動 は 自<br />
由 であるということが 出 来 るのだろうか。<br />
だが、これらの 反 論 はすべて 因 果 律 の 絶 対 性 に 縛 られている。アーレントはこう 言 う。<br />
すでに 起 こった 事 にたいしては 期 待 できないようななにか 新 しいことが 起 こるというのが、「 始 ま<br />
り」の 本 性 である。この 人 を 驚 かす 意 外 性 という 性 格 は、どんな「 始 まり」にも、どんな 始 原 にも<br />
そなわっている。〔 略 〕 新 しいことは、 常 に 統 計 的 法 則 とその 蓋 然 性 の 圧 倒 的 な 予 想 に 反 して<br />
起 こる。このような 予 想 というのは、 日 々の 実 際 的 な 目 的 から 言 えば、 確 実 性 にも 等 しいのであ<br />
る。したがって、 新 しいことは、 常 に 奇 跡 の 様 相 を 帯 びる。そこで、 人 間 が 活 動 する 能 力 をもつ<br />
という 事 実 は、 本 来 は 予 想 できないことも、 人 間 には 期 待 できるということ、つまり、 人 間 は、ほ<br />
とんど 不 可 能 な 事 柄 をなしうるということを 意 味 する。 245<br />
243<br />
以 下 の 記 述 において、 熊 野 純 彦 『 西 洋 哲 学 史 古 代 から 中 世 へ』 岩 波 新 書 、2006 年 、112 頁 以 下 を 参 照 した。<br />
244<br />
第 一 原 因 とは、「アリストテレスでは 運 動 の 究 極 原 因 ( 第 一 形 相 ないし 神 )であって、それ 自 身 は 運 動 しないで 他<br />
のものの 運 動 の 原 因 となる「 不 動 の 動 者 」のこと。すなわち、 動 くものはなにものかによって 動 かされるが、この 原 因 、<br />
結 果 の 系 列 をどこまでも 追 求 すれば、 究 極 にはみずからは 動 かされないで、しかも 他 を 動 かす 原 因 を 考 えなければ<br />
ならない。〔 略 〕なお、 宗 教 的 には 神 が 万 物 の 創 造 者 、 支 配 者 として 第 一 原 因 とされる」( 荒 川 他 編 『 哲 学 辞 典 』〔 前<br />
掲 〕「 第 一 原 因 」の 項 )。<br />
245 ARENDT, The Human Condition (op.cit.), pp.177f. ( 前 掲 訳 書 、289 頁 。)<br />
66
たしかに、 人 間 には 世 界 を 創 造 することは 出 来 ない。そうしたはじまりは 人 間 の 能 力 を 超 えている。<br />
だからといって、 世 界 に 生 起 する 出 来 事 はすべて 世 界 のはじまりという 原 因 からの 系 列 に 通 じてい<br />
なくてはならないということにはならない。 新 しいことというのは、むしろ 原 因 を 持 たず( 言 い 換 えれ<br />
ばそれ 自 体 を 原 因 として)、 突 然 生 じるのである。 実 際 的 目 的 からすれば 確 実 性 にも 等 しい 法 則 や<br />
予 期 をも 踏 み 破 って 出 来 事 が 起 こって 来 るのは、それ 自 身 が 法 則 や 予 期 から 自 由 なはじまりであ<br />
るからにほかならない。そして 人 間 は、 常 に 法 則 によって 支 配 されることなく、なにかをはじめてきた。<br />
アーレントがはじまりと 呼 んでいるものは、このような 原 因 からも 目 的 からも 自 由 な 人 間 の 活 動 であり、<br />
人 間 自 身 が 出 来 事 の 原 因 になり 得 ると 彼 女 は 主 張 する。たとえば 現 代 の 世 界 は、 文 明 が 興 ったそ<br />
のときからすれば、とても 予 想 できるものではなかった( 実 際 、 予 想 や 予 言 なるものは 少 数 の 例 外 を<br />
除 いては、 外 れることをその 本 質 としているかのようである)。 人 間 にははじめることが 可 能 であると<br />
いう 命 題 は、たしかに 知 性 によっては 証 明 不 能 であるが、 現 象 的 な 証 拠 がこの 思 考 を 裏 付 けている。<br />
それに、 証 明 不 能 であるという 点 について 言 えば、 因 果 律 の 絶 対 性 もまた 証 明 しえないのである。<br />
すくなくとも、 両 方 の 命 題 はアンチノミーとして、 互 いに 等 しい 可 能 性 を 持 っていると 言 えるだろう。<br />
そう 考 えると、 人 間 ははじめることが 可 能 であるとするアーレントの 主 張 は、 経 験 的 現 実 により 多 く 適<br />
っているとさえ 言 えるのではないか。<br />
まとめると、 人 間 は 因 果 律 や 自 然 の 強 制 から 自 由 に、 新 しい 過 程 を 始 めることができる。それは<br />
宇 宙 の 始 まりのような 時 間 全 体 の 始 まりではないが、 因 果 からは 自 由 なのだ。(ただし、このような 始<br />
める 能 力 としての 活 動 にさらに 先 立 つのが、 意 志 である。 意 志 は 活 動 を 準 備 する 精 神 的 活 動 力 で<br />
あるが、それは 第 七 章 で 扱 われる。)<br />
世 界 に 新 しいことが 起 らないという 考 え 方 は、 工 作 人 的 であると 指 摘 することができる。 既 に 述 べ<br />
たように、ベルクソンによれば 人 間 の 悟 性 は 制 作 のために 因 果 律 に 従 って 運 動 する 部 分 を 掴 むの<br />
に 長 けているからである。 実 際 、 制 作 においては、 結 果 が 予 想 できなければ 文 字 通 り「 仕 事 になら<br />
ない」。だがそれ 故 に 制 作 的 な 悟 性 は、 生 命 がもたらす 創 造 を 捉 える 事 が 出 来 ない。 創 造 は、 生 命<br />
が 因 果 性 を 突 き 破 って 何 らかの 過 程 を 開 始 する 力 であり、まさに「はじまり」なのである。ベルクソン<br />
もここで「 創 造 」という 言 葉 を 生 命 全 般 に 当 てはめることによって 神 学 に 反 逆 している。なぜならキリ<br />
スト 教 思 想 において 創 造 というのは、 神 による 世 界 と 人 間 の 創 造 を 措 いて 他 にはあり 得 ないからだ。<br />
いずれにしても、 制 作 の 過 程 においては 因 果 性 や 目 的 から 逸 脱 した 絶 対 的 に 新 しいことというもの<br />
は、 起 こってはならないのである。しかしベルクソンは、 創 造 の 概 念 を 導 入 することによって、むしろ<br />
因 果 律 こそ 倒 錯 であると 断 言 する。 我 々が 見 るのは 出 来 事 そのものだけであり、むしろその 出 来 事<br />
から、 過 去 の 出 来 事 を 見 たときにその 過 去 の 出 来 事 が「 原 因 」のごとく 映 ずるのであり、 逆 ではない。<br />
翻 ってその 原 因 のほうから 今 起 こっている 出 来 事 を 見 たとき、その 出 来 事 は「 結 果 」に 見 える。<br />
アーレントもまた、「はじまり」を 人 間 の 世 界 に 導 入 した。このことによって、 制 作 的 な 知 に 頼 って<br />
いた 哲 学 も 政 治 学 も、 足 場 を 失 う。そこかしこで 新 たな 過 程 がはじまる 人 間 世 界 に 相 応 しいのは、<br />
それ 自 体 時 間 のなかに 存 在 する 思 考 であろう。こうして 思 考 そのものも、 超 時 間 的 であることをやめ、<br />
67
時 間 のなかの 活 動 となる。とにかく、 人 間 が 複 数 いるこの 世 界 は、 不 確 定 性 に 満 ちたものへと 変 じ<br />
たのである。<br />
第 22 節 物 語 と 歴 史<br />
出 来 事 event, Ereignis は 因 果 性 から 自 由 に 突 然 生 起 する。 活 動 は、このような 出 来 事 を 引 き 起 こ<br />
す 活 動 力 である。 出 来 事 自 体 はいかなる 因 果 からも 帰 結 しないので、 出 来 事 から 結 果 を 予 測 する<br />
ことも 出 来 ない。だから 出 来 事 から 成 る 人 間 の 生 涯 は、どのような 結 果 をもつのか 言 い 当 てることは<br />
出 来 ないのだ。 人 間 の 生 涯 は、 終 わってはじめて 有 意 味 な 物 語 story として 語 り 出 すことが 可 能 に<br />
なる。「 言 論 と 活 動 はともに、 新 しい 過 程 を 出 発 させるが、その 過 程 は、 最 終 的 には 新 参 者 のユニ<br />
ークな 生 涯 の 物 語 として 現 われる」 246 。この 物 語 こそ、 人 間 の 歴 史 の 基 礎 であり、 条 件 でさえある 247 。<br />
物 語 は、 人 間 の 生 涯 が 終 わったときはじめて 語 りだされるのだが、 我 々はすでに 第 四 章 で、このよ<br />
うな 生 涯 がビオスと 呼 ばれることを 確 認 しておいた。ビオスとは、 円 環 的 な 種 の 生 命 としての 自 然 的<br />
ゾーエーを 逸 脱 する、 始 まりと 終 わりを 持 つ 線 分 的 な 生 命 であった。ビオスとは、 物 語 性 を 持 つ 人<br />
間 の 生 涯 のことだったのである。<br />
ところでこのような 物 語 の 線 分 性 は、 始 まりと 終 わりを 持 ち、 線 分 的 に 表 象 される 点 において、 制<br />
作 の 時 間 経 験 がもつ 目 的 論 的 な 時 間 像 に 似 通 っている。このような 線 分 性 を 見 る 限 り、 果 たして 活<br />
動 の 時 間 性 と 制 作 の 時 間 性 とは、 等 しいものなのだろうか しかしまさにこのような 混 同 こそが、<br />
活 動 を 制 作 的 観 点 から 捉 え、 歴 史 を 目 的 論 として 把 握 する 誤 りに 通 じているのだ。 人 間 の 生 は 始 ま<br />
りに 満 ちており、 不 確 定 性 の 連 続 である。それゆえ、 人 間 の「 終 わり」は、 常 に 可 能 性 として 存 在 す<br />
るにとどまる。いま 生 きている 人 間 は、 常 に 未 完 結 なのであり、その 全 体 性 は 明 らかにならない。ハ<br />
イデガーはそれを、 常 住 の 未 完 結 性 ständige Unabgeschlossenheit と 呼 ぶ。<br />
この 存 在 者 〔 現 存 在 としての 人 間 〕の 全 体 存 在 ( 全 たき 姿 で 存 在 する)というようなことは、 現<br />
存 在 の 構 造 全 体 の 全 体 性 をなしている 関 心 の 存 在 論 的 意 味 に、 明 らかに 矛 盾 することである。<br />
なぜなら、 関 心 構 造 の 第 一 次 的 契 機 ――《おのれに 先 立 って〔Sichvorweg〕》――は、 現 存 在<br />
はいつでもおのれ 自 身 を 主 旨 として 存 在 している、ということである。 現 存 在 は、「 存 在 している<br />
間 は」その 終 末 に 至 るまで、おのれの 存 在 可 能 に 関 わり 合 っている。〔 略 〕 関 心 にそなわるこの<br />
、、、、、、<br />
構 造 契 機 は、 現 存 在 のなかには、いつになってもまだ 済 まずにいる、ということを 紛 れもなく 告<br />
、、、、、、、<br />
げているのである。こうして、 現 存 在 の 根 本 的 構 成 の 本 質 には、 常 住 の 未 完 結 性 が 含 まれて<br />
いるわけである。 現 存 在 が 全 体 性 を 欠 いているということは、このように 存 在 可 能 の 未 済 分 が<br />
あることを 意 味 する。 248<br />
246 Ibid., p.184. ( 同 上 、298 頁 。)<br />
247 「 生 から 死 に 至 る 個 体 の 生 活 は、いずれも 最 終 的 には、『 始 まり』と 終 りをもつ 物 語 として 語 ることができる。それ<br />
を 語 ることができるということは、『 始 まり』も 終 りもない 大 きな 物 語 である 歴 史 の 前 政 治 的 、 前 歴 史 的 な 条 件 である」<br />
(Ibid. 〔 同 上 、299 頁 。〕)。<br />
248 HEIDEGGER, Sein und Zeit (Ebenda), S.236. ( 前 掲 訳 書 、 下 巻 、31-32 頁 。)<br />
68
「 現 存 在 は、なによりもまず 可 能 的 に 存 在 すること」 249 である。それゆえに、 現 存 在 の 全 体 性 は 常 に<br />
不 明 である。その 全 体 性 が 明 らかになるのは、 現 存 在 が 可 能 性 でなくなったとき、いいかえれば 現<br />
存 在 の 可 能 性 が 消 滅 したときである。しかしそのときには、「 現 存 在 を 存 在 者 として 経 験 することは、<br />
もはや 全 く 不 可 能 になるのである」 250 。それゆえハイデガーは「 全 体 存 在 は、 原 理 的 にいかなる 経<br />
験 可 能 性 にも 及 びえないものなのである」 251 と 断 ずる。 彼 はそこで、 先 駆 的 覚 悟 性 によって 死 を 先<br />
取 りすることで、 人 間 は 自 らの 固 有 の 存 在 に 到 達 できると 考 えた。<br />
アーレントが、 活 動 する 人 間 は「 始 める」 能 力 を 持 つということを 述 べるが、それはハイデガーの<br />
可 能 存 在 としての 現 存 在 を 独 特 に 理 解 したものだと 言 えよう。しかしアーレントは 人 間 の 全 体 存 在<br />
は、 人 の 死 のあとに、 物 語 として 了 解 可 能 であると 考 えている。「 物 語 というのは、 行 為 の 束 の 間 の<br />
瞬 間 が 過 ぎ 去 った 途 端 に 始 まり、その 時 になって、 物 語 は 物 語 となる。そこで、 厄 介 なのは、〔 略 〕<br />
活 動 の 意 味 が 完 全 に 明 らかになるのは、ようやくその 活 動 が 終 わってからと 言 うことである」 252 。ハイ<br />
デガーは、おのれの 存 在 可 能 を 他 ならぬ 自 らの 死 に 投 企 することとして、 現 存 在 の 全 体 存 在 を 了<br />
解 しようとしたが、アーレントは 人 間 の 全 体 存 在 は 他 者 に、 物 語 として 現 われるものであると 考 えた<br />
のだ。 人 間 の 物 語 は、 終 わって 初 めてその 意 味 が 開 示 されるから、「 誰 モ 死 ヌ 前 ニ 幸 福 デアルトハ<br />
言 ワレ 得 ナイ Nemo ante mortem beatus esse dici potest」 253 。<br />
制 作 にはこのような 未 完 結 性 はない。 制 作 する 者 ―― 工 作 人 ――は、イデアと 向 かい 合 うことか<br />
、、、、<br />
ら 制 作 をはじめ、そして 制 作 が 完 了 した 結 果 としての 物 を 生 き 抜 く。「 製 作 の 場 合 、 完 成 品 を 判 断 す<br />
る 光 は、 職 人 の 眼 が 前 もって 知 覚 しているイメージやモデルによって 与 えられている」 254 。つまり、<br />
仕 事 において、 工 作 人 ははじめから 終 わり= 目 的 を 見 通 している。そして 結 果 としての 物 は、 制 作<br />
行 為 の 全 体 存 在 として、そこに 存 在 する。 仕 事 ははじまりにおいて 既 に 終 わりに 達 していると 言 って<br />
、、、、、、、、、、<br />
もよい。 制 作 は、いわば「あとは 終 わらせるだけ」なのだ。そこに 不 確 定 性 も 未 完 結 性 もない。ところ<br />
が 制 作 の 場 合 とは「 対 照 的 に、 活 動 の 過 程 、したがって 歴 史 過 程 全 体 を 照 らす 光 は、ようやく 過 程<br />
が 終 わったときにのみ 現 われ、 場 合 によっては、 参 加 者 全 員 が 死 んだあとで 現 われる」 255 。<br />
つまり 歴 史 history は 制 作 的 な 確 定 性 から 考 えられてはならない。なぜならそれは 人 間 の 活 動 と<br />
いう 出 来 事 の 結 果 である 物 語 story の 連 続 から 成 るからである。 歴 史 を 制 作 の 観 点 から 考 える 過 ち<br />
、、、、、、、、、、<br />
についてはすでに 第 三 章 で 見 てきた。それは、 科 学 的 である 代 わりに、 蓋 然 性 を 見 逃 してしまう。<br />
、、、、、、、、、、、、<br />
「 歴 史 の 大 いなる 未 知 は、 近 代 の 歴 史 哲 学 を 悩 ませてきた。それは、 歴 史 が 全 体 として 考 えられ、<br />
歴 史 の 主 体 である 人 類 というのは、 結 局 、 一 つの 抽 象 物 にすぎず、 活 動 的 な 行 為 者 とはけっしてな<br />
りえないということが 判 ったとき 現 われた」( 傍 点 は 橋 爪 ) 256 。だが 歴 史 を 全 体 として 考 えることは 出 来<br />
ない。 歴 史 の「 主 役 」がいるとすれば、それは 複 数 の 始 める 力 をもつ 活 動 者 たちなのだ。それゆえ<br />
249 Ebenda, S.143. ( 前 掲 訳 書 、 上 巻 、311 頁 。)<br />
250 Ebenda, S.236. ( 前 掲 訳 書 、 下 巻 、32-33 頁 。)<br />
251 Ebenda. ( 同 上 、33 頁 。)<br />
252 ARENDT, The Human Condition (op.cit.), pp.191f. ( 前 掲 訳 書 、310 頁 。)<br />
253 Ibid., p.192. ( 前 掲 訳 書 、311 頁 。ただし 訳 書 はラテン 語 文 をそのまま 掲 載 しているのみなので、 拙 訳 。)<br />
254 Ibid. ( 前 掲 訳 書 、310 頁 。)<br />
255 Ibid. ( 同 上 。)<br />
256 Ibid., p.184. ( 前 掲 訳 書 、299-300 頁 。)<br />
69
アンプレディクタビリティ<br />
に 活 動 は 結 果 を 予 測 できない「 不 可 予 言 性 」を 持 っている。「これは、 単 に、ある 特 定 の 活 動 の 論 理<br />
的 帰 結 は、いずれも 予 見 できないという 問 題 ではない。このような 問 題 なら、 電 子 計 算 機 が 将 来 を<br />
予 見 できるだろう。そうではなくて、この 不 可 予 言 性 は、 活 動 の 結 果 である 物 語 から 直 接 生 じている<br />
のである」 257 。だから、「 活 動 が 完 全 にその 姿 を 現 すのは、 物 語 作 者 である 歴 史 家 が 過 去 を 眺 める<br />
ときだけである。そして 実 際 、いったい 何 事 が 起 こったのかよく 知 っているのは、 常 に、 参 加 者 よりも<br />
歴 史 家 のほうである」 258 。そのとき 重 要 となってくる 精 神 的 活 動 力 こそが、 判 断 judging である。 判 断<br />
こそは、 出 来 事 として 起 こった 物 事 を、 物 語 として、 歴 史 として 理 解 するための 活 動 力 なのである。<br />
だがその 問 題 はここでは 措 こう。<br />
時 間 論 的 には、 活 動 の 時 間 性 の 特 徴 は、その 全 体 的 構 造 を 図 式 的 に 表 現 できないところにある。<br />
仕 事 ( 制 作 )の 時 間 性 は、はじまりから 終 わりへと 伸 びる 線 分 として、 図 示 することが 可 能 であった。<br />
また、 労 働 の 時 間 性 は、 永 遠 的 な 生 命 の 運 動 と 調 和 する 円 環 運 動 として 示 すことが 出 来 た。これら<br />
の 時 間 性 から 発 源 する 歴 史 像 は、 共 に、 図 形 的 に 了 解 しやすいことを 特 徴 としていると 言 ってよい。<br />
それに 対 してアーレントが 提 示 するはじまりの 時 間 性 は、たしかに 一 つの 人 生 としては、はじまりか<br />
ら 終 わりまでの 直 線 として 描 くことが 可 能 である。しかし、 実 際 にははじまりは 複 数 の 人 間 がそこかし<br />
こではじめているものであり、それゆえに、もし 本 当 に 全 体 像 を 描 こうと 思 えばこうした 複 数 のはじま<br />
りと 終 わりが 一 望 できるような 仕 方 を 考 えださねばならないだろう。 敢 えてそれを 図 示 するのならば、<br />
コンステラチオン<br />
それは 星 座 のごときものとなるのではないだろうか。 宇 宙 では、 異 なった 時 に、 異 なった 場 所 で、<br />
それぞれの 星 は 自 らがどのように 映 るかも 知 らずに、 自 由 に 自 ら 輝 いている。だがその 星 々を、 遥<br />
か 彼 方 のある 一 点 、 宇 宙 全 体 からすれば 砂 粒 のような 惑 星 上 の 観 測 者 の 眼 から――それも 悠 久 の<br />
時 間 のなかのある 特 定 の 時 代 に―― 眺 めたとき、それらはあたかもその 並 びが 必 然 であるかのよう<br />
に、 一 つの 姿 と 神 話 を 示 すことになるのだ。 輝 く 星 々はただ 自 ら 輝 いているにすぎないのが、 遠 くの<br />
観 察 者 にとってはひとつの 星 座 として、ある 秩 序 ある 全 体 のなかで 輝 いているかのように 映 ずる。だ<br />
がそれは 単 なる 理 解 のためのイメージであり、たんなる 比 喩 にすぎない。そのようなイメージが 活 動<br />
の 指 針 になることもないし、 時 間 の 全 体 像 の 理 解 を 容 易 にするわけでもない。それに 比 べれば 線<br />
分 や 円 環 というイメージのほうが、 遥 かに 理 解 しやすく、そして 行 為 の 指 針 をも 与 えたことに 違 いな<br />
い。<br />
第 23 節 活 動 の 遂 行 的 性 格 ――エネルゲイアないしプラクシスとして<br />
前 節 で 確 認 したのは、 活 動 の 意 味 が 明 らかになるのは 活 動 の 過 程 が 終 わってからだということで<br />
ある。それは、 究 極 的 には 人 間 の 生 涯 の 意 味 が、 死 の 後 にのみ 開 示 されるということとして 経 験 さ<br />
れる。しかしそれは 歴 史 としての 意 味 であって、まさに 活 動 しているさなかの 活 動 者 にとっての 意 味<br />
というものも、たしかにあるはずである。 前 者 が 活 動 の 意 味 の 全 体 性 を 明 らかにすることから 全 体 意<br />
パフォーマティヴィティ<br />
味 と 名 づけられるとすれば、 後 者 は 活 動 の 遂 行 性 そのもののうちにある 遂 行 意 味 Vollzugssinn<br />
257 Ibid., p.191. ( 前 掲 訳 書 、309-310 頁 。)<br />
258 Ibid., p.192. ( 前 掲 訳 書 、310 頁 。)<br />
70
である。 全 体 意 味 と 遂 行 意 味 はまったく 異 なる。 全 体 意 味 の 問 題 は、 物 語 の 問 題 として、 最 終 的 に<br />
は 判 断 という 活 動 力 に 委 ねられるのだ。 判 断 者 judge の 問 題 はしかし、 第 八 章 で 取 り 上 げる。<br />
活 動 は 遂 行 performance, Vollzug である。このことを 理 解 するために、まずは 遂 行 performance<br />
ないし 遂 行 性 performativityとはなにかを 明 らかにしておこう。アーレントはまず、 遂 行 ということをア<br />
リストテレスのエネルゲイアの 概 念 から 説 明 しようとする。<br />
アクチュアリティ<br />
アリストテレスのエネルゲイア(「 現 実 性 」)という 観 念 のうちに 概 念 化 されたのは、 人 間 が 為 し<br />
得 る 偉 大 な 達 成 としての 生 きた 行 為 と 語 られた 言 葉 への、この 強 調 であった。アリストテレスは、<br />
ア テ レ イ ス パ ラ ウ タ ー ス ・ エ ル ガ<br />
エネルゲイアという 概 念 で、 目 的 を 追 わず( 無 目 的 であり)、 何 の 作 品 も(ソレ 自 身 以 外 ノ 作 品<br />
は 全 く 〔259〕 )あとに 残 さず、その 完 全 な 意 味 を 遂 行 そのもののうちに 尽 くしているような、そういう<br />
活 動 力 全 般 を 指 していた。 逆 説 的 な「 目 的 自 体 」がそのもともとの 意 味 を 引 き 出 してくるのは、<br />
アクチュアリティ<br />
このような 完 全 な 現 実 性 の 経 験 からである。なぜなら、この 場 合 、 活 動 と 言 論 の 目 的 (テロス)<br />
は 追 求 されておらず、 活 動 力 それ 自 体 の 中 にあり、それゆえにこの 活 動 力 はエンテレケイアと<br />
なる。そして 言 論 と 活 動 の 作 品 とは、 過 程 を 追 い、それを 消 滅 させるものでなく、 過 程 の 中 には<br />
めこまれているものである。 遂 行 こそ 作 品 なのであり、エネルゲイアである。 260<br />
「 活 動 の 目 的 は 活 動 そのものの 中 にある」ともいえるし、 活 動 している 者 は「 目 的 そのもののさなか<br />
にある(エンテレケイア)」 261 とも 言 える。 同 様 に、 活 動 は 作 品 を 作 りだすことがないために、 活 動 して<br />
いる 人 間 そのものが「 人<br />
エルゴン・トゥー・アントロープー」であると、つまり、その 間 トイウ 作 品<br />
人 間 は「 作 品 のうちにある(エネルゲイ<br />
ア)」 262 とも 言 える。 活 動 はつまり「 目 的 自 体 」、なにかのためのもの(in order to…)ではなく、それ 自<br />
体 意 味 あるもの(for the sake of…)として 追 求 されるものなのである 263 。エネルゲイアは 音 楽 の 演 奏<br />
に 喩 えられる。 演 奏 は、 演 奏 し 終 わることが 目 的 ではない( 演 奏 し 終 わることでなにか 生 産 物 が 生 ま<br />
れるわけではない)。むしろ 演 奏 している 最 中 、まさにその 遂 行 においてそれを 楽 しむことができる。<br />
細 川 亮 一 は、「アリストテレスは 生 きることもエネルゲイア( 生 きると 同 時 に 生 きてしまった)と 考 えて<br />
259<br />
原 文 は no par’ autas erga。 最 初 の no は 勿 論 英 語 で、それにつづくパラウタース・エルガという 表 現 は、ギリシア<br />
語 の παρ’ αὐτὰς ἔργα である。つまり、「それら 自 身 以 外 の 作 品 」という 意 味 である。アーレントははっきりと 書 いてない<br />
が、この 表 現 は『ニコマコス 倫 理 学 』の 第 一 巻 第 一 章 からの 引 用 のようで、 次 の 文 章 のなかに 現 われている。<br />
“διαφορὰ δέ τις φαίνεται τῶν τελῶν: τὰ μὲν γάρ εἰσιν ἐνέργειαι, τὰ δὲ παρ᾽ αὐτὰς ἔργα τινά” (ARISTOTELES, Ethica<br />
Nicomachea, 1094a3-5 〔 前 掲 訳 書 、15 頁 〕). この 文 章 を 見 ると、αὐτὰς が 指 しているのが ἐνέργειαι、すなわちエネル<br />
ゲイアの 複 数 形 であることが 判 る。つまりパラウタース・エルガとは、エネルゲイアの 外 にある 作 品 ということになろう。<br />
なお、 引 いたギリシア 語 の 邦 訳 は、「 種 々の 場 合 の 目 的 とするものの 間 には、しかしながら、 明 らかに 一 つの 差 別 が<br />
見 られるのであって、すなわち、 活 動 それ 自 身 が 目 的 である 場 合 もあれば、 活 動 以 外 の 何 らかの 成 果 が 目 的 である<br />
場 合 もある」。<br />
260 ARENDT, op.cit., p.206. ( 前 掲 訳 書 、331 頁 。)<br />
261 エンテレケイア ἐντελέχεια とは、ἐν+τέλος+ἔχειν という 語 の 組 み 合 わせから 成 っている 語 である。つまり、「 目 的<br />
( 終 わり)の=うちに=あること」がエンテレケイアである。 木 田 、 前 掲 書 、117 頁 以 下 参 照 。<br />
262 エネルゲイア ἐνέργεια もまた ἐν+ἔργον、すなわち「 作 品 ( 働 き)=のなか」という 意 味 を 持 つ。 前 注 と 同 じく 木 田 、<br />
前 掲 書 、117 頁 以 下 参 照 。<br />
263 このような「 目 的 自 体 」となる 営 みは、 社 会 学 においてもコンサマトリーconsummatory な 行 為 として 知 られている。<br />
真 木 『 時 間 の 比 較 社 会 学 』( 前 掲 ) 終 章 、 見 田 宗 介 「 現 代 社 会 の 社 会 意 識 」 福 武 直 監 修 , 見 田 宗 介 編 『 社 会 学 講 座<br />
12 社 会 意 識 論 』 東 京 大 学 出 版 会 、1976 年 、15 頁 、または 若 林 幹 夫 『 社 会 学 入 門 一 歩 前 』NTT 出 版 、2007 年 、15<br />
章 などを 参 照 。<br />
71
いる」 264 と 述 べる。つまり「 生 きることは 生 きることの 外 にある 目 的 へ 向 かう 運 動 、 生 き 終 わるための<br />
運 動 ではない」 265 。 簡 単 に 言 えば、 生 きることは、なにかのために 生 きることではなく、 生 きるために<br />
生 きることなのだ。 人 間 の 生 涯 は 一 種 の 遂 行 であるとアリストテレスが 考 えていたならば、アーレント<br />
はその 考 えを 忠 実 に 引 き 継 ぎ、 活 動 の 理 論 として 結 実 させたということができる。<br />
細 川 によれば、エネルゲイアとはキネーシスの 対 概 念 として 用 いられるらしい 266 。キネーシスは<br />
「 運 動 」を 意 味 するが、ここでは 目 的 へと 向 かう 運 動 を 特 に 意 味 している。それに 対 して 目 的 そのも<br />
のをうちに 含 んだエネルゲイアがある。ここでこのエネルゲイア=キネーシスの 対 称 に、プラクシス<br />
=ポイエーシスという 対 称 267 を 重 ねてもよいだろう。ある 物 を 生 み 出 すことを 目 的 とした 行 為 が、ポ<br />
イエーシス、つまり 制 作 であった。 目 的 をもった 行 為 としてポイエーシスはキネーシスと 通 ずるところ<br />
がある。 他 方 プラクシスはそれ 自 体 が 目 的 として 追 求 されるものであり、エネルゲイアと 重 なる(アー<br />
レントのいう 活 動 、アクションは、プラクシスの 訳 語 である)。 活 動 の 遂 行 性 は、エネルゲイア=プラ<br />
クシスの 無 目 的 性 から 理 解 可 能 だ。つまり 遂 行 は、なにかを 目 的 とするキネーシス=ポイエーシス<br />
と 区 別 される、 無 目 的 の、 役 に 立 たないものである。 無 目 的 であるというのは、それ 自 体 が 目 的 であ<br />
り、 有 意 味 であることを 意 味 しているのだ。<br />
アーレントは、このような 遂 行 性 としての 活 動 を 確 かに 強 調 している。 他 方 、アーレントが 新 しいの<br />
は、そのような 活 動 を 物 語 ないし 歴 史 として 語 り 出 し 得 るという 点 を 同 時 に 強 調 していることである。<br />
ところで、 問 題 は、 活 動 自 体 が 遂 行 であり、かつ、 文 字 通 りの 意 味 で「 史 上 類 を 見 ない」、「 前 例<br />
のない」 出 来 事 を 引 き 起 こすという 性 格 をもつがゆえに、 活 動 の 正 当 性 はなにを 根 拠 にして 導 き 得<br />
るのかということである。この 問 題 は、 繰 り 返 すが、 判 断 の 問 題 として 考 えられることになる( 第 八<br />
章 )。<br />
活 動 についてまとめよう。 活 動 はまず、 始 めること 殆 ど 同 義 であり、 始 めることとは、 因 果 性 から 自<br />
由 に、 自 発 的 に 始 めることであった。 実 際 、 人 間 が 複 数 者 であることの 基 礎 は、それぞれの 人 間 が<br />
自 由 に 始 めることでユニークな 存 在 となることなのである。こうしたユニークな 活 動 が 引 き 起 こす 出<br />
来 事 は、 文 字 通 り「 類 を 見 ない」ものであるから、 知 性 によって 予 想 を 立 てることはできない。それは<br />
ただ 出 来 事 が 終 わった 後 に 物 語 として 語 りだすことができるのみなのだ。そして 出 来 事 が 全 体 とし<br />
てどういう 意 味 をもっていたのか( 全 体 意 味 )は、 歴 史 家 が 物 語 として 語 りだすときに 明 らかになる。<br />
しかしながら、 活 動 はそれ 自 体 が 目 的 として 追 求 されるプラクシスないしエネルゲイアとしての 意 味<br />
を 持 つのであって、その 点 では 遂 行 そのものが 有 意 味 なのであった( 遂 行 意 味 )。 活 動 の 時 間 性 は<br />
始 まりそのものであって、その 時 間 経 験 の 帰 結 としてその 予 測 不 可 能 性 や 物 語 性 や 遂 行 性 が 現 わ<br />
れてくるのだ。(ここで、1 活 動 を 自 発 的 に 始 めることに 対 応 する 精 神 的 活 動 力 〔 意 志 〕と、2 起 った<br />
出 来 事 の 正 / 不 正 などを 判 断 するための 精 神 的 活 動 力 〔 判 断 〕はなんなのかという 問 題 が 生 ずる<br />
が、それらは 第 七 ・ 八 章 で 取 り 上 げよう。)<br />
264<br />
265<br />
266<br />
267<br />
細 川 亮 一 『ハイデガー 入 門 』ちくま 新 書 、2001 年 、149 頁<br />
同 上 。<br />
同 上 、148 頁 。<br />
第 9 節 、 第 13 節 も 参 照 。<br />
72
補 論 革 命 の 時 間 論<br />
アーレントが、はじまりが 政 治 現 象 として 現 われてくる 代 表 的 な 場 面 として 取 り 上 げたのが、 歴 史<br />
における 革 命 revolution であった。「 革 命 は、 直 接 的 かつ 必 然 的 にわれわれをはじまりの 問 題 に 直<br />
面 させる 唯 一 の 政 治 的 事 件 」 268 なのだ。しかしながら、アーレントによれば、 革 命 が「はじまり」であ<br />
、、<br />
ったと 言 えるのは、ただアメリカ 革 命 ――ただし、 一 般 にはアメリカ 独 立 戦 争 として 認 識 されることが<br />
多 いが――のみが、 歴 史 における 実 例 であるということになる。<br />
a)「 革 命 revolutio」の 原 義<br />
革 命 はすぐれて 時 間 論 的 な 現 象 である。それは 変 化 そのものであるからだ。 時 間 という 経 験 が 変<br />
化 から 発 源 してくることは、すでに 第 一 章 で 探 究 した 通 りである。しかし 時 間 的 であるからといって、<br />
出 来 事 そのものとしてのはじまりを 含 んでいるかどうかは、 別 の 問 題 である。<br />
古 代 においては、 革 命 にあたる 現 象 は 知 られていなかったとアーレントは 指 摘 する。<br />
ム タ チ オ ・ レ ー ル ム ス タ シ ス<br />
現 代 の 革 命 はローマ 史 の 事 物 ノ 変 化 (mutatio rerum)やギリシアのポリスを 混 乱 させた 内 紛<br />
メタボライ<br />
(στάσις)と 共 通 するところはほとんどない。またそれを、プラトンのいう 変 化 (μεταβολαί)、すな<br />
わち 一 つの 統 治 形 態 から 他 の 統 治 形 態 への 擬 似 自 然 的 な 変 化 や、ポリュビオスのいう<br />
ポリテイオーン・アナキュクローシス<br />
政 体 ノ 循 環 (πολιτεὶων ἀνακύκλωσις)、すなわち、 人 間 事 象 は 常 に 諸 々の 極 点 へと 駆 り<br />
立 てられているがゆえに、そこへと 結 びつけられているという、 定 められた 循 環 性 のサイクルと<br />
同 一 視 することも 出 来 ない。 269<br />
たしかに、 革 命 的 な 暴 力 的 政 治 現 象 は 古 代 から 知 られていたが、「しかし 古 代 世 界 においては、 変<br />
動 や 暴 力 が 何 かまったく 新 しいものをもたらすとは 考 えられなかった。〔 略 〕 歴 史 過 程 は 新 しいはじ<br />
まりを 開 始 するどころか、 人 間 事 象 の 性 格 そのものによってあらかじめ 決 定 されているのであり、し<br />
たがって、それ 自 体 は 不 変 の 一 過 程 を 辿 りつつ、サイクルの 異 なった 段 階 にたちもどるものと 考 え<br />
られた」 270 。そしてこのようなサイクル、つまり 円 環 的 な 時 間 の 構 造 は、 既 に 見 てきたとおり 労 働 の 時<br />
間 経 験 から 発 源 しているものである。それゆえ、「ポリュビオスは 政 府 が 次 々と 変 化 することが 起 こる<br />
のは、κατὰ φύσιν、つまり 自 然 に 従 ってであると 述 べる」 271 わけである。 労 働 の 時 間 経 験 は 自 然 的<br />
生 命 としてのゾーエーから 発 源 しているために、 円 環 的 な 時 間 構 造 を 取 る。 同 時 に 歴 史 が 自 然 の<br />
観 点 から 理 解 されるとき、その 時 間 的 構 造 も 円 環 であると 認 識 されるのだ。<br />
たしかに、「 変 化 は 死 すべきものすべてを 支 配 しているというのは、〔 略 〕 古 代 の 最 後 の 数 世 紀 に<br />
支 配 的 な 気 分 で」 272 あり、とりわけ「ギリシア 人 は、 死 すべきものであるかぎり、 死 すべきものの 領 域<br />
に 起 る 変 わりやすさは 変 えることができないと 確 信 していた。それはネオイ〔νέοι〕、つまり『 新 しいも<br />
268 ARENDT, Hannah, On Revolution, London: Penguin Books Ltd., 1990, p.21. ( 志 水 速 雄 訳 『 革 命 について』ちくま<br />
学 芸 文 庫 、1995 年 、27-28 頁 。)<br />
269 Ibid. ( 前 掲 訳 書 、28 頁 。)<br />
270 Ibid. ( 同 上 。)<br />
271 Ibid., p.284, note 3. ( 前 掲 訳 書 、81 頁 。)<br />
73
の』である 若 者 はたえず 現 状 の 安 定 性 をおびやかしているという 事 実 を 根 拠 にしていた」 273 。しかし、<br />
彼 らにとって 結 局 は、「 人 間 事 象 はたえず 変 化 するが、 完 全 に 新 しいものは 何 も 生 み 出 さない。もし、<br />
日 の 下 に 新 しいものがあるとすれば、それは、 人 間 が 世 界 に 生 まれたという 意 味 で、 人 間 それ 自 身<br />
だった。しかし、ネオイ、つまり 新 しい 若 いものが、どれほど 新 しくあろうとも、 彼 らはすべて 幾 世 紀 を<br />
通 じて 本 質 的 にいつも 同 じ 自 然 的 、 歴 史 的 光 景 のなかに 生 まれ、 死 ぬだけであった」 274 。それはま<br />
さに「 歴 史 は 繰 り 返 す」 275 という 経 験 だったのだ。<br />
ところで、 革 命 という 語 の 語 源 は、まさにこのような、 繰 り 返 す 円 環 的 な 時 間 性 を 指 していた。<br />
レヴォリューション<br />
「 革 命 」という 言 葉 は、もともと 天 文 学 上 の 用 語 であり、コペルニクスの『 天 体 ノ 回 転 ニツイテ』<br />
De revolutionibus orbium coelestium を 通 して 自 然 科 学 で 重 要 性 を 増 していた。この 言 葉 の 正<br />
確 なラテン 語 の 意 味 は、このような 科 学 上 の 用 語 法 のなかに 表 現 されており、 天 体 の 周 期 的<br />
で 合 法 則 的 な 回 転 運 動 を 意 味 していた。この 運 動 は、 人 間 の 力 を 超 えており、したがって 抵<br />
抗 できないものであることが 知 られていたので、もちろん、 新 しさとか 暴 力 をその 特 徴 としたも<br />
のではなかった。それどころか、むしろこの 言 葉 は 循 環 する 周 期 的 運 動 をはっきりと 示 している。<br />
つまりそれは、やはりもともとは 天 文 学 上 の 用 語 で 政 治 の 領 域 に 比 喩 的 に 用 いられたポリュビ<br />
、、<br />
オスの 循 環 (ἀνακύκλωσις)という 言 葉 の 完 全 なラテン 語 訳 である。 地 上 の 人 間 の 問 題 に 用 い<br />
られるばあい、それは、いくつかの 周 知 の 統 治 形 態 が 永 遠 の 循 環 を 続 けながら 死 すべき 人 間<br />
の 世 界 を 回 転 するということだけを 意 味 した。そのばあい、その 力 は、 前 もって 定 められた 天 空<br />
の 軌 道 に 沿 って 天 体 を 回 転 させている 力 と 同 じくらい 抵 抗 しがたいものであった。<br />
レウォルチオ<br />
革 命 という 語 ―― 正 確 に 言 えばレヴォリューションという 語 ――は、 回 転 が 語 源 であり、 新 しいもの<br />
がはじまるという 観 念 とは、 実 際 全 く 以 て 縁 遠 い 語 なのである。この 用 語 が 政 治 的 語 彙 として 登 場 し<br />
てきたとき(17 世 紀 )、その 比 喩 の 内 容 は、「すでに 以 前 確 立 されたある 地 点 に 回 転 しながら 戻 る 運<br />
動 、つまり、 予 定 された 秩 序 に 回 転 しながら 立 ち 戻 る 運 動 を 暗 示 するのに 用 いられて」 276 いた。<br />
このような 歴 史 概 念 ―― 人 間 の 世 界 に「 新 しいもの」は 決 して 現 れえないという――を 覆 したのは、<br />
アウグスティヌスの 歴 史 観 、すなわちキリスト 教 神 学 の 歴 史 概 念 であった。「 全 く 新 しいもの」の 観 念<br />
は、 直 線 的 な 時 間 像 を 除 いては 不 可 能 である。そして 直 線 的 時 間 像 というのは、すでに 見 てきたよ<br />
うに 制 作 的 な 時 間 経 験 から 出 てくるものであり、 世 界 をある 目 的 に 向 けて 理 解 するものであった。<br />
「そのうえキリストの 誕 生 は 人 間 の 世 俗 的 時 間 のなかに 起 り、 一 回 限 りのくり 返 すことのできない 出<br />
、、、、<br />
来 事 であると 同 時 に 新 しいはじまりであるから、キリスト 教 哲 学 は 古 代 人 の 時 間 概 念 と 手 を 切 ったの<br />
である」 277 。 確 かにアウグスティヌスは「 一 定 の 周 期 をもって 宇 宙 は 際 限 なくくり 返 して 生 じては 消 滅<br />
272 Ibid., p.27. ( 前 掲 訳 書 、36 頁 。)<br />
273 Ibid., p.28. ( 前 掲 訳 書 、36-37 頁 。)<br />
274 Ibid., p.28. ( 前 掲 訳 書 、37 頁 。)<br />
275<br />
諺 として 知 られているが、もとはローマの 歴 史 家 クルティウス・ルーフスの 言 葉 であるという( 尚 学 図 書 編 『 故 事 俗<br />
信 ことわざ 大 事 典 』 小 学 館 、1982 年 、1232 頁 )。<br />
276 ARENDT, op,cit., pp.42f. ( 前 掲 訳 書 、58 頁 。)<br />
277 Ibid., p.27. ( 前 掲 訳 書 、36 頁 。)<br />
74
するという」 278 ような 人 々を 論 難 している。それに 対 してアウグスティヌスは 創 造 という 出 来 事 の 一 回<br />
性 を 強 調 し、そのことで 歴 史 にはじまりを 導 入 するのだ。とはいえ、「アウグスティヌスが 強 調 してい<br />
るように、このような 出 来 事 は 一 回 起 っただけであり、 時 の 終 りまで 二 度 と 起 らないだろう」 279 。つまり、<br />
この 歴 史 観 では、 未 だに、 革 命 は 勿 論 のこと、 新 しいことをはじめる 人 間 の 活 動 能 力 すら 了 解 する<br />
ことは 出 来 ないのである。<br />
b) 革 命 の 制 作 的 モデル――フランス 革 命<br />
レヴォリューション<br />
アーレントは、 革 命 という 言 葉 には、 第 二 の 天 文 学 的 含 みが 存 在 していることを 指 摘 している。<br />
「それはこの 言 葉 の 現 代 的 使 用 法 に 非 常 にはっきりと 残 されている。 不 可 抗 力 性 〔irresistibility〕の<br />
概 念 がそれである。すなわち 天 体 の 回 転 運 動 は 前 もって 決 定 されている 軌 道 を 通 り、 人 間 の 影 響<br />
力 の 範 囲 外 にあるという 事 実 である」 280 。アーレントは、ラ・ロシュフコー=リアンクール 公 爵 が、バス<br />
ティーユ 陥 落 に 関 して「これは 革 命 だ c’est une révolution」と 述 べたのが、この 言 葉 が 不 可 抗 力 性<br />
に 重 点 を 置 いて 用 いられた 最 初 の 例 としている 281 。「 今 や 強 調 されているのは、その 運 動 が 人 間 の<br />
力 では 捕 捉 できないものであり、したがって、それ 自 身 法 則 であるという 点 である」 282 。そして、「この<br />
不 可 抗 力 的 な 運 動 という 概 念 は、19 世 紀 になるとすぐに 歴 史 的 必 然 〔historical necessity〕という 観<br />
念 に 概 念 化 されるのであるが、フランス 革 命 のページの 最 初 から 最 後 まで 響 きわたっている」 283 。<br />
フランス 革 命 の 進 行 は、 人 間 の 意 志 を 超 えて 動 いているように 思 われた。それはまるで、「 自 分<br />
自 身 の 活 動 のコースに 関 する 人 間 の 無 力 さ」 284 を 見 せつける「 見 世 物 spectacle」であった。「 昨 日 、<br />
啓 蒙 期 の 幸 福 な 日 々には、 人 間 とその 活 動 の 自 由 のあいだに 立 ちふさがっているように 思 われた<br />
のは 君 主 の 専 制 的 な 権 力 だけであったのに、 今 日 突 然 、 人 びとをその 意 志 どおりに 動 かすもっと<br />
強 力 な 力 があらわれたのである。それは、そこから 解 き 放 されることもできず、 反 抗 も 逃 亡 も 不 可 能<br />
な 歴 史 の 力 、 歴 史 的 必 然 なのであった」 285 。そして、この 歴 史 的 必 然 が 見 えたのは、この 革 命 に 参<br />
加 していた 人 々――つまり 活 動 者 actor ではなく、この「 見 世 物 spectacle」を 見 ていた「 観 客 たち<br />
spectators」であった、 哲 学 者 であった。ゆえに、「 理 論 面 でいえば、フランス 革 命 のもっとも 深 い 帰<br />
結 はヘーゲル 哲 学 における 近 代 的 歴 史 概 念 の 誕 生 に 見 られる」のであり、「ヘーゲルの 真 に 革 命<br />
的 な 観 念 は、それまで 哲 学 者 たちの 説 いていた 古 い 絶 対 者 が、 人 間 の 経 験 領 域 、 人 間 事 象 の 領<br />
域 にまさにあらわれるという 点 にあった」 286 のだ。つまり、この 絶 対 者 は 歴 史 的 必 然 へと 置 き 換 わり、<br />
必 然 性 を 通 して 歴 史 的 に 展 開 するものとなったのである。この 主 張 の 最 大 の 矛 盾 点 は、 自 由 という<br />
ものが 必 然 の 観 点 から 理 解 されることである。ヘーゲルは、 世 界 史 が 自 由 の 実 現 の 過 程 であると 考<br />
え、「 世 界 史 とは 自 由 の 意 識 が 前 進 していく 過 程 であり、わたしたちはその 過 程 の 必 然 性 を 認 識 し<br />
278 AUGUSTINUS, De civitate Dei, XII, XII. ( 前 掲 訳 書 、124 頁 。)<br />
279 ARENDT, op.cit., p.27. ( 前 掲 訳 書 、36 頁 。)<br />
280 Ibid., p.47. ( 前 掲 訳 書 、65 頁 。)<br />
281 Ibid. ( 前 掲 訳 書 、65 頁 以 下 。)<br />
282 Ibid., p.48. ( 前 掲 訳 書 、66 頁 。)<br />
283 Ibid. ( 前 掲 訳 書 、67 頁 。)<br />
284 Ibid., p.51. ( 前 掲 訳 書 、71 頁 。)<br />
285 Ibid. ( 同 上 。)<br />
75
なければなりません」 287 と 述 べている。「これが 有 名 な 自 由 と 必 然 の 弁 証 法 であり、そのなかで 結 局 、<br />
自 由 と 必 然 は 一 致 するのである」 288 。だが、 政 治 的 に 言 えば、アーレントがいうように、「これは 近 代<br />
思 想 のなかでもっとも 恐 ろしい、そして 人 間 の 立 場 からいえばもっとも 耐 えがたい 逆 説 」 289 ということ<br />
になる。 彼 女 によれば、 自 由 は 活 動 において 実 現 し、 活 動 そのものはいかなる 原 因 や 目 的 にも 支<br />
配 されないからだ。いずれにしても、「 永 遠 に 循 環 する 輪 が 近 代 で 断 ち 切 られたにもかかわらず、<br />
歴 史 に 固 有 の 特 質 としての 必 然 性 が、 依 然 として 生 き 残 っているという 事 実 、そして 本 質 的 に 直 線<br />
的 な 運 動 のなかに、したがって 以 前 知 られていたものに 回 転 して 立 ち 戻 るのではなく、 未 知 の 未 来<br />
に 伸 びて 行 く 運 動 のなかに 再 びその 姿 を 表 わしているという 事 実 ――この 事 実 は、 理 論 的 思 弁 で<br />
はなく〔フランス 革 命 という〕 政 治 的 経 験 と 現 実 的 な 出 来 事 の 過 程 から 生 じたものである」 290 。つまり、<br />
歴 史 の 過 程 は、 直 線 でありながら 必 然 的 なものとなり、それはおそらくは、 一 つの 目 的 = 終 わり―<br />
―たとえば 自 由 の 実 現 のような、たとえば 労 働 の 廃 絶 のような――をもつもの、すなわち 我 々の 言<br />
い 方 でいえば 目 的 論 的 な 時 間 了 解 から 理 解 されるべきものとなったのである。<br />
「ヘーゲルと 彼 の 弟 子 たちによれば、 歴 史 の 運 動 は 弁 証 法 的 であると 同 時 に、 必 然 によって 展<br />
開 するものである」 291 。この 考 えはフランス 革 命 においてヘーゲルに 芽 生 え、そしてそれはマルクス<br />
ネ セ シ テ ィ<br />
においても 維 持 された。そしてマルクスにおける 必 然 性 とは、 文 字 通 りの 必 然 性 = 貧 窮 であった。<br />
つまり、 生 物 (ゾーエー)としての 人 間 が 抱 える、 我 々の 生 命 過 程 の 必 然 性 であり、つまり 空 腹 の 強<br />
制 力 である。「われわれが 意 識 的 に 行 動 し 活 動 することが 少 なければ 少 ないほど、この 生 物 学 的 過<br />
程 はますます 強 力 に 自 己 を 主 張 し、それに 固 有 の 必 然 性 を 押 しつけ、 全 人 類 の 歴 史 の 基 礎 にある<br />
オートマティズム<br />
純 粋 な 偶 発 事 の 宿 命 的 な 自 動 性 でわれわれを 威 圧 する」 292 。マルクスが 歴 史 をこの 必 然 性 に 委<br />
ねたとき、 活 動 は 労 働 の 範 疇 へと 押 し 込 められ、 自 由 は 必 然 に 屈 服 したのだ。そのとき 歴 史 の 主 体<br />
は 複 数 の 人 々ではなく、 国 民 nation や 人 民 le peuple という「 群 衆 multitude」、すなわちひとつの 人<br />
格 、 一 者 となった。それは 多 数 性 の 廃 棄 であり、 複 数 の 人 間 の 自 由 な 活 動 を 放 棄 することであると<br />
アーレントは 言 うのだ。フランス 革 命 における「 主 権 者 」は 人 民 の 単 一 の 意 志 となったのだった。<br />
c) 自 由 の 創 設 としての 革 命 ――アメリカ 革 命<br />
しかし、アーレントの 捉 える 革 命 の 意 義 は、フランス 革 命 が 示 したものとは、 正 反 対 のものである。<br />
すなわち、 必 然 性 に 拘 束 されることなく 自 由 に 活 動 できる 空 間 の 樹 立 こそが、 彼 女 の 考 える 革 命 の<br />
意 味 なのだ。そして 彼 女 によれば、その 活 動 のための 空 間 を 創 設 する 事 業 そのものが、 活 動 だっ<br />
たのである。つまりそれははじまりであった。これがアメリカ 革 命 を、 近 代 以 前 の 循 環 的 な 変 化 やフ<br />
ランス 革 命 (そしてフランス 革 命 の 模 倣 としてのロシア 革 命 )と、 鋭 く 区 別 しているものなのである。<br />
286 Ibid., pp.51f. ( 前 掲 訳 書 、72 頁 。)<br />
287 HEGEL, Georg Wilhelm Friedlich. 長 谷 川 宏 訳 『 歴 史 哲 学 講 義 』 上 巻 、 岩 波 文 庫 、1994 年 、41 頁 。<br />
288 ARENDT, op.cit., p.54. ( 前 掲 訳 書 、75 頁 。)<br />
289 Ibid. ( 同 上 。)<br />
290 Ibid., p.55. ( 前 掲 訳 書 、76 頁 。)<br />
291 Ibid., p.54. ( 前 掲 訳 書 、75 頁 。)<br />
292 Ibid., p.59. ( 前 掲 訳 書 、90 頁 。)<br />
76
革 命 を 引 き 起 こすのは、 人 々の 相 互 的 な「 約 束 promiss」に 基 づく 契 約 から 生 じる 権 力 power で<br />
ある。その 契 約 は 自 分 たちの 力 を 放 棄 して 一 者 に 委 ねる「 社 会 契 約 」とは 異 なる。 社 会 契 約 におい<br />
て、 人 々は 複 数 者 として 捉 えられることはなく、 単 一 の 意 志 をもつ 一 者 として 現 われる。そこでは<br />
プルーラリティ<br />
複 数 性 は 破 壊 されてしまう。そうではなくて、 複 数 の 人 間 が 互 いの 自 由 な 活 動 に 基 づいた 約 束 によ<br />
って 結 びつく 場 合 に 権 力 は 生 じる。 約 束 の 力 とは、 未 来 が 予 測 できないという 人 間 の 活 動 の 性 格<br />
に 対 して、 一 定 の 安 定 性 を 与 えるものである。 約 束 は、「 不 確 実 性 の 大 海 ―― 未 来 は 本 性 上 そうで<br />
ある――の 中 に、 安 全 な 小 島 を 打 ち 立 てるのに 役 立 つ。このような 小 島 がなければ、 人 間 関 係 に<br />
おいて 耐 久 性 はもとより、 連 続 性 さえ 不 可 能 である」 293 。ただし、「 約 束 が、 不 確 実 性 の 大 洋 におけ<br />
る 確 実 性 の 孤 島 としての 性 格 を 失 う 途 端 、つまり、この 能 力 が 誤 用 されて、 未 来 の 大 地 全 体 を 覆 い、<br />
あらゆる 方 向 に 保 証 された 道 が 地 図 に 書 き 込 まれるとき、 約 束 はその 拘 束 力 を 失 い、 企 て 全 体 が<br />
自 滅 する」 294 。 約 束 は 未 来 全 体 を 規 定 するわけではない――それは 制 作 的 な 未 来 の 把 握 である。<br />
未 来 全 体 が 規 定 されたとき、 活 動 の 性 格 そのものが 失 われ、 自 由 は 挫 折 する。それゆえ、 活 動 と 自<br />
由 のうえに 立 脚 する 約 束 の 力 も 働 かなくなるのだ。<br />
アーレントのいう 権 力 power は、この 約 束 の 能 力 に 立 脚 する 契 約 によって 構 成 される。そして 権<br />
力 とは、「 公 的 空 間 、つまり 活 動 し 語 る 人 びとの 間 に 現 われる 可 能 的 な 現 われの 空 間 〔potential<br />
space of appearance〕を 存 続 させるものである。 権 力 という 言 葉 そのものが、たとえば、ギリシア 語 の<br />
dynamis にしても、ラテン 語 の potentia にしても、ラテン 語 から 派 生 したさまざまな 近 代 語 にしても、ド<br />
イツ 語 の Macht(これは mögen〔「できる」を 意 味 する 可 能 の 助 動 詞 〕や möglich〔「 可 能 的 な」という<br />
形 容 詞 〕からきているのであって、machen〔「 為 す、 作 る」を 意 味 する 動 詞 〕からきているのではない)<br />
ポテ ン シ ャ ル パ ワ ー パ ワ ー ・ ポテ ン シ ャ ル<br />
にしても、いずれも 権 力 の『 可 能 的 』な 性 格 を 示 している。 権 力 とは、 常 に 力 の 潜 在 性 であって、<br />
エ ン テ ィ テ ィ<br />
〔 略 〕 不 変 の、 測 定 できる、 信 頼 できる 現 実 的 存 在 者 ではない、といっていいだろう」 295 。 実 際 、 権 力<br />
power という 語 は、フランス 語 では pouvoir であり、pouvoir は 英 語 の can にあたる 可 能 の 助 動 詞 で<br />
ある。それゆえ、 権 力 の 実 質 は「 私 は= 為 し 得 る the I-can」ということにある 296 。それは 公 的 空 間 を<br />
維 持 し、 人 々の 自 由 な 活 動 を 可 能 にするものなのだ。<br />
ところで、 活 動 に――つまり 同 時 に 革 命 に――ひそむ 難 問 とは、それが 前 例 のないことであるが<br />
ゆえに、その 正 当 性 の 根 拠 をどこから 引 き 出 し 得 るのか、ということである。これははじまりそのもの<br />
が 内 蔵 する 難 問 である。 既 に 見 てきた 二 つの 歴 史 観 において、まず 円 環 的 時 間 性 においては、は<br />
じまりのない 円 環 というモデルを 採 用 することでこの 難 問 の 成 立 そのものを 回 避 しているが、それゆ<br />
えに 出 来 事 そのものを 捉 え 損 ねている。またフランス 革 命 においては、その 制 作 的 な 暴 力 性 を、 人<br />
民 の 単 一 の 意 志 を 主 権 者 とすることによって、そこに 基 づけることで 理 解 し、 解 決 しようとした。しか<br />
しこの 解 決 策 もまた、 本 来 の 人 間 の 複 数 性 という 事 実 と、それに 由 来 する 活 動 の 活 動 力 を 無 視 して<br />
293 ARENDT, The Human Condition (op.cit.), p.237. ( 前 掲 訳 書 、372 頁 。)<br />
294 Ibid., p.244. ( 前 掲 訳 書 、382 頁 。)<br />
295 Ibid., p.200. ( 前 掲 訳 書 、322 頁 。)<br />
296 ARENDT, On Revolution (op.cit.), p.150. ( 前 掲 訳 書 、234 頁 。)<br />
77
しまっている。 実 際 これは 殆 ど 解 決 不 可 能 な 難 問 に 思 われる。 活 動 は、 因 果 や 目 的 から 自 由 なも<br />
のである。そのような 活 動 の 正 当 性 を 引 き 出 し 得 る 根 拠 は、あり 得 ないのではないか。<br />
はじまりは 原 因 と 結 果 のたしかな 連 鎖 に 拘 束 されていない。つまり、それぞれの 結 果 がすぐに<br />
将 来 の 発 展 の 原 因 へと 転 換 するような 連 鎖 にしばられていない。それどころか、はじまりは、い<br />
わばそれがしがみつくべきものを 何 ももっていないのである。それは 時 間 においても、 空 間 に<br />
おいても、まるで 出 発 点 を 持 たないかのようだ。しばらくのあいだ、はじまりの 瞬 間 には、<br />
ビ ギ ナ ー<br />
はじめる 者 が 時 間 の 連 続 性 そのものを 廃 止 したか、あるいは、 行 為 者 たちが 時 間 の 秩 序 とそ<br />
の 連 続 から 放 りだされたかのように 見 える。 297<br />
「はじまりの 起 源 」などという 言 葉 があればそれは 文 字 通 り 形 容 矛 盾 である。だからこそアーレントは、<br />
活 動 は 目 的 からも 理 由 からも 正 当 化 できるものでないと 考 えるのだ(それは 偉 大 さによってのみ 判<br />
断 されると 彼 女 は 述 べていた)。こうなると、はじまりはその 正 当 性 を 引 き 出 す 根 拠 をどこにももちえ<br />
ないのだろうか はじまりとは 端 的 に 恣 意 的 なものなのだろうか<br />
アーレントは 答 える。<br />
はじまりの 行 為 がその 恣 意 性 から 救 われるのは、その 行 為 がそれ 自 身 のなかに、それ 自 身 の<br />
ビ ギ ニ ン グ プリンシプル プリンキピウム<br />
原 理 をもっているからである。もっと 正 確 にいえば、はじまり と 原 理 、 始 マリ 〔principium〕と<br />
プリンシプル<br />
原 理 〔principle〕、は 互 いに 関 連 しているだけでなく、 同 時 的 なものだからである。はじまりは<br />
自 己 の 妥 当 性 の 根 拠 となり、いわば、それに 内 在 する 恣 意 性 から 自 分 を 救 ってくれる 絶 対 者<br />
を 必 要 とするが、そのような 絶 対 者 とは、はじまりとともに 世 界 にその 姿 を 現 わす 原 理 にほかな<br />
らない。はじめる 者 が、 彼 のおこなおうとすることを 開 始 したそのやり 方 (way)が、その 企 てをと<br />
もに 完 成 させるために 彼 に 加 わった 人 びとの 活 動 の 法 を 定 める。そのようなものとして、 原 理 は<br />
その 後 につづく 行 為 を 鼓 舞 し、そして、 活 動 がつづくかぎり、 明 白 に 姿 を 現 わしつづけるので<br />
ある。 298<br />
、、、、<br />
はじまりの 原 理 は、はじまりそのものに 含 まれているのだ。 言 いかえれば、はじまりによってはじまっ<br />
、、 、<br />
たものは、はじまりそのものが 含 む 原 理 によって 展 開 するのである。これははじまりの 難 問 すべての<br />
殆 ど 唯 一 の 解 決 方 法 であり、はじまりの 本 性 が 要 求 する 回 答 であるように 思 われる。たとえばここで、<br />
若 きマルクスが 学 位 論 文 (『デモクリトスの 自 然 哲 学 とエピクロスの 自 然 哲 学 との 差 異 』)において、<br />
エピクロスの 哲 学 の 可 能 性 を 救 いだした 際 の 身 振 りを 思 い 出 してもよい。<br />
エピクロスの 自 然 哲 学 の 奇 妙 な 特 徴 は、 彼 が 原 理 ἀρχή として 認 めている 原 子 に、 偏 り<br />
Deklination という 性 質 を 与 えたところにある。 原 子 はまず 直 線 に 沿 って 落 下 するという 第 一 の 性 質<br />
をもつのだが、 同 時 になんの 原 因 にも 依 らずに、ひとりでに 直 線 から 逸 れるのというのである。それ<br />
297 Ibid., p.206. ( 前 掲 訳 書 、329 頁 。)<br />
298 Ibid., pp.212f. ( 前 掲 訳 書 、338-339 頁 。)<br />
78
が 偏 りであるが、 多 くの 人 間 ――キケロなど――はその 点 がエピクロスの 欠 陥 であると 考 え、「 原 子<br />
、、、、、<br />
の 偏 りが 原 因 なしにおこる、ということを 非 難 する」 299 。しかしこれは「 原 子 がすべてのものの 原 因 で<br />
あり、それゆえそれ 自 身 としては 原 因 をもたない、と 考 えているものにとっては、 明 らかに 無 意 味 な<br />
問 いである」 300 。 原 子 は 原 因 そのものであって、それに 原 因 を 求 める 問 いは 自 己 破 綻 している。そ<br />
うではなくて、 原 子 ははじまりであるのだから、それには 原 因 はないのだ。そして「エピクロスは、 空<br />
虚 のただなかですら、 原 子 は 直 線 からすこし 偏 る、と 想 定 し、 自 由 はそれから 生 ずる、と 言 った」 301 。<br />
つまり、この 偏 りは、ここで 自 由 の 可 能 性 の 根 拠 にもなるのである。<br />
アメリカ 革 命 は、 先 に 述 べたような 複 数 性 に 基 づく 権 力 によって 実 現 されたのだとアーレントは 考<br />
える。「この 革 命 は 勃 発 したのではなく、 共 通 の 熟 慮 と 相 互 誓 約 の 力 にもとづいて、 人 びとによって<br />
つくられたものだからである。 創 設 が〔 制 作 のように〕 一 人 の 建 築 家 の 力 ではなく、〔 活 動 として〕 複<br />
数 の 人 びとの 結 合 した 権 力 によってなされたあの 決 定 的 な 時 期 を 通 じて 明 らかになった 原 理 は、<br />
相 互 約 束 と 共 同 の 審 議 という、 内 的 に 連 関 した 原 理 だった」 302 。つまり、 革 命 そのものを 動 かした 原<br />
理 は、 革 命 そのものを 通 して 明 らかになったのだった。だがその 意 味 はいまだに 遂 行 性 の 内 側 で<br />
了 解 されており、 革 命 の 原 理 を 永 続 させるのに 必 要 となったのが、 判 断 という 精 神 的 活 動 力 なので<br />
あった。 判 断 は、いかなる 外 的 基 準 もないときに、それでもなお 判 断 を 下 す 力 であるが、それは 精<br />
神 的 活 動 力 を 取 り 上 げる 際 に 問 題 とすべきであろう。<br />
299 MARX, Karl, “Differenz der demokritischen und epikureischen Naturphilosophie,” in: Marx-Engels Werke,<br />
Ergänzungsband, Schriften bis 1844, Erster Teil, Berlin: Dietz Verlag, 1968, S.282. ( 岩 崎 允 胤 訳 「デモクリトスの 自<br />
然 哲 学 とエピクロスの 自 然 哲 学 との 差 異 」『マルクス=エンゲルス 全 集 』 第 40 巻 、 大 月 書 店 、1975 年 、210 頁 。)<br />
300 Ebenda. ( 前 掲 訳 書 、210-211 頁 。)<br />
301 Ebenda, S.279 ( 前 掲 訳 書 、207 頁 。)<br />
302 ARENDT, op.cit., pp.213f. ( 前 掲 訳 書 、340 頁 。)<br />
79
ライフ・オブ・ザ・マインド<br />
第 二 部 精 神 的 生 活 の 時 間 性<br />
第 六 章 思 考 thinking の 時 間 性<br />
哲 学 こそが、 人 間 を 孤 立 させるのである。 哲 学 の 力 によっ<br />
て 人 は、 苦 しむ 人 を 眺 めても、 勝 手 に 死 ぬがよい、わたし<br />
は 安 全 な 場 所 にいるのだからと、ひそかに 呟 くことができ<br />
る。<br />
――ルソー『 人 間 不 平 等 起 源 論 』<br />
第 24 節 精 神 的 生 活 の 時 間 論<br />
アーレントが『 人 間 の 条 件 』において 行 なった 試 みは、 哲 学 史 において 不 当 な 評 価 をされてきた<br />
「 活 動 的 生 活 vita activa」の 再 評 価 であった。 伝 統 的 な 哲 学 的 了 解 にあっては、 活 動 的 生 活 は「 観<br />
、、<br />
想 的 生 活 vita contemplativa」という 目 的 のための 手 段 であるとされ、 貶 められていた。マルクスや、<br />
「 生 の 哲 学 」(ニーチェ、ベルクソンら)において、 観 想 よりも 生 命 が 重 視 され、 伝 統 的 な 順 位 がはじ<br />
めて 逆 転 されたが、それでもなお 活 動 の 能 力 、 政 治 的 活 動 力 は 問 題 化 されなかったのである。ア<br />
ーレントは、ひとまず 忘 れられていた 活 動 的 生 活 の 復 権 を 試 み、そしてなかんずく 活 動 の 意 義 を 強<br />
調 したのである。その 分 析 においては、 人 間 の 精 神 的 活 動 力 mental activity は、いわば 陰 画 をな<br />
すのみであった。われわれは 活 動 的 生 活 の 時 間 性 の 分 析 を 終 え、いまや 精 神 的 生 活 の 時 間 経 験<br />
の 発 源 の 仕 方 をとりあげるべきときである。アーレントはここで、もはや 観 想 的 生 活 は 問 題 にせず、<br />
精 神 的 生 活 life of the mind を 問 題 にしているが、その 理 由 は 序 論 部 第 二 章 で 明 らかにした 通 りだ。<br />
テオーリア<br />
すなわち、 精 神 的 活 動 力 mental activity とは、 観 想 ( 見 ること)という 精 神 的 受 動 性 mental passivity<br />
の 経 験 ではけっしてなく、まさに 活 動 力 としての 能 動 性 activity だというのが、 彼 女 の 主 張 なのであ<br />
る。<br />
そうした 精 神 的 生 活 にあっては、 我 々の 活 動 的 生 活 における 経 験 は 停 止 する。 諸 活 動 力 は 現 象<br />
界 space of appearance で 行 なわれていたのに 対 し、 精 神 的 活 動 力 における 自 我 は 現 象 から 退 きこ<br />
もる。そして 現 象 界 では 他 者 とともにあった 自 我 は、ただ 自 己 とのみ 共 にあるようになる。このような<br />
精 神 的 活 動 力 の 経 験 において、 点 的 な 現 在 の 連 続 であった 時 間 もまた、まったく 別 様 に 変 貌 する。<br />
我 々の 関 心 であるアーレントの 時 間 論 もまた、ここで 転 回 するのである。 要 するに、 活 動 的 生 活 の<br />
時 間 論 とは 全 く 異 なる 分 析 が、 精 神 的 生 活 の 時 間 論 にあっては 要 求 されているのである。<br />
以 下 では、 思 考 の 活 動 力 を 分 析 してゆくが、その 分 析 においておそらくは 精 神 的 活 動 力 全 般 が、<br />
つまり 精 神 的 生 活 が 有 する 一 般 的 特 徴 も、 或 る 程 度 明 らかになっていくだろう。 問 題 となるのは、 思<br />
考 する 自 我 の 存 在 する「 場 所 」と「 時 間 」である。 先 取 り 的 に 述 べておけば、ここで「 場 所 」の 問 題 は<br />
「 時 間 」の 問 題 へと 集 約 されていくこととなる。だから 精 神 的 活 動 力 の 問 題 においてこそ、 時 間 の 問<br />
題 はその 重 要 度 を 増 すのだ。<br />
80
第 25 節 思 考 する 自 我 の「 場 所 」と「 一 者 のなかの 二 者 two in one」<br />
活 動 的 生 活 と 精 神 的 生 活 の 最 大 の 違 いはどこにあるのか。もちろん、それは 後 者 が 精 神 に 関 わ<br />
るという 点 である、ということはできる。だがそれではなにも 説 明 した 事 になっていない。というのは、<br />
前 者 、つまり 活 動 的 生 活 にあっても、 決 して 精 神 的 なものが 関 わらないわけではないからだ。 単 純<br />
に 精 神 に 関 わるというだけではない、もう 少 し 踏 み 込 んだ 解 釈 が 必 要 であろう。その 際 主 要 な 参 照<br />
点 となるのが、 精 神 的 活 動 力 の「 場 所 」をめぐる 問 いなのである。さしあたり、「 思 考 する 自 我<br />
thinking ego」の 場 とはどこなのか、と 問 うことにしよう。<br />
このとき 活 動 的 生 活 の「 場 所 」とはどこであるか、ということを 考 えるのは、その 問 いへの 手 引 きと<br />
アクティヴィティ<br />
なる。 活 動 的 生 活 においては、 我 々の 活 動 力 ( 行 為 )は「 見 られ、 聞 かれる」、つまり「 現 象 する<br />
appear 」。つまり、 存 在 するものはすべて 現 象 しなくてはならないような、「 現 象 界 space of<br />
appearance」こそが、 活 動 的 生 活 の 舞 台 なのである(ここでは 存 在 するものはすべて 現 象 しなくては<br />
、、、<br />
、、、、、、、、、<br />
ならないから「 存 在 と現 象 とは 共 に 起 こる coincide」 303 )。すでに 第 一 部 で 見 てきたように、 労 働 や 仕<br />
事 や 活 動 は「 世 界 world」において 行 なわれる 世 界 内 的 な 活 動 力 であるが、「すべての 生 命 体 にと<br />
っては 世 界 が〈 私 にはこう 見 える〉〔it-seems-to-me〕という 仕 方 で 現 象 してくる」 304 。「 現 象 が 優 位 に<br />
立 っているということは、 科 学 者 も 哲 学 者 も 逃 れることのできない 日 常 生 活 の 事 実 であり、 研 究 や 思<br />
索 の 末 にいつもそこへと 立 ちもどらなければならないのである。しかも、 現 象 から 退 きこもって 何 を<br />
発 見 したとしても、 現 象 はけっして 変 更 されることも 歪 めることもできないほどの 確 たる 力 を 有 してい<br />
る」 305 。<br />
活 動 的 生 活 の 諸 活 動 力 の 場 としての 現 象 界 に 対 して、 思 考 する 自 我 の 場 はどのように 描 写 しう<br />
るのか。その 際 、「 生 命 体 にとっては 現 象 の 優 位 は、 我 々がこれから 扱 おうとしている 話 題 にとって<br />
大 変 重 要 なのだ――つまり、 我 々が 他 の 動 物 から 自 分 たちを〔 人 間 として〕 区 別 する 根 拠 をなす、<br />
あの 精 神 的 活 動 力 にとって。というのは、この〔 三 つの〕 精 神 的 活 動 力 というのはそれぞれ 大 きく 異<br />
、、、、、<br />
なるけれども、 世 界 から 退 きこもり〔withdrawal〕、 自 己 の 側 に 立 ちもどるという 点 ではみな 共 通 であ<br />
るからだ」 306 。 差 し 当 たり 消 極 的 な 規 定 に 留 まるが、 現 象 界 における 諸 活 動 力 に 対 して、 思 考 する<br />
自 我 は 現 象 界 から 退 きこもり withdraw、 自 己 self へと 戻 るのである。また、このことは、「 現 象 界 と、<br />
それに 条 件 づけられている〔 活 動 的 生 活 の〕 諸 活 動 力 の 観 点 から 見 た 場 合 、 精 神 的 活 動 力 の 主 要<br />
、、、、<br />
特 徴 はその 不 可 視 性 である」 307 というように 言 い 換 えることも 出 来 る。だから「エピクロスのラテー・ビ<br />
303 ARENDT, The Life of the Mind: One/Thinking (op.cit.), p.19. ( 前 掲 訳 書 、23 頁 。なお、 引 用 文 中 の 傍 点 はアーレ<br />
ントによるイタリック 強 調 を、ゴシック 体 はアーレントが 意 図 して 語 頭 を 大 文 字 にしている〔 例 :Being〕のを 反 映 してい<br />
る。さらに 橋 爪 が 強 調 を 加 える 場 合 、 下 線 を 加 える。 以 下 でも、 本 書 からの 引 用 の 場 合 はそのように 表 記 する。)ア<br />
ーレントのこのテーゼは、バークリーの「 存 在 スルコトハ、 知 覚 サレルコトデアル esse est percipi」のもじりであると 考 え<br />
ることも 可 能 である( 岩 崎 稔 「 生 産 する 構 想 力 、 救 済 する 構 想 力 ――ハンナ・アーレントへの 一 試 論 ――」『 思 想 』<br />
807 号 、 岩 波 書 店 、1991 年 、171 頁 )。<br />
304 ARENDT, op.cit., p.22. ( 同 上 、27 頁 。)<br />
305 Ibid., p.24. ( 同 上 、30 頁 。)<br />
306 Ibid., p.22. ( 同 上 、27-28 頁 。)<br />
307 Ibid., p.71. ( 同 上 、84 頁 。)<br />
81
オーサス〔lathe biosas〕、つまり『 隠 れて 生 きよ』は、 思 慮 分 別 の 勧 めであったかもしれないが、 思 考<br />
ローカリティ<br />
する 人 間 のトポス、すなわち 場 所 の、すくなくとも 消 極 的 には 正 確 な 描 写 でもあるのだ」 3<strong>08</strong> 。<br />
思 考 する 自 我 は、 現 象 界 から 退 きこもる。すると、 現 象 界 においては 現 前 するものを 感 覚 によっ<br />
、、<br />
て 捉 えていたのが、その 現 前 するものがなくなるということになる。そこで 精 神 は、 感 覚 に 現 前 して<br />
、、、<br />
いないものを 現 前 させなければならない。「 不 在 のものを 現 前 させるという 再 = 現 前 作 用<br />
ユ ニー ク ギ フ ト<br />
ギ フ ト 、 、 、<br />
〔 re-presentation : 表 象 〕 は 、 精 神 に 特 有 な 天 賦 の 才 で あ り 、 〔 略 〕この 天 賦 の 才 は 構 想 力<br />
〔imagination〕と 呼 ばれる」 309 。 思 考 は、 構 想 力 によって 現 前 しないものを 再 = 現 前 ( 表 象 )するが、<br />
そのために 必 要 なのは、「 感 覚 に 与 えられる 個 別 的 なものを、 不 在 のときにも 扱 うことができるよう 用<br />
意 する」 310 ことである。つまり「 脱 = 感 覚 化 de-sense」の 操 作 が 必 要 なのだ。 感 覚 にともなって 形 成 さ<br />
れるイメージが、 記 憶 として 保 存 される 過 程 がそれである。この 過 程 を 経 ると、 現 前 していたものが、<br />
メンタル・イメージ<br />
心 像 として 想 起 されるものとなり、そうして 精 神 にとって 扱 いうるものとなるのだ。この 過 程 は 思 考<br />
のみならず、 意 志 や 判 断 のような 精 神 的 活 動 力 の 不 可 欠 の 前 提 でもある。<br />
ただし 思 考 はさらに 先 へ 進 む。 精 神 は 現 前 しないものの 扱 いに 習 熟 すると、「 常 に 不 在 のもの、<br />
感 覚 経 験 に 対 して 現 前 したことが 決 してないがために 思 い 出 されることがあり 得 ないものへと」 311 進<br />
むのである。それはつまり 概 念 や 理 念 、カテゴリーといったものである。これらは 決 して 目 の 前 に 現<br />
前 することはない。 概 念 などの 精 神 のみが 扱 いうるものは、 結 局 感 覚 に 現 前 していたものからは 二<br />
重 の 操 作 を 受 けることになり、 現 実 的 生 活 からは 遠 く 離 れたものになってしまうのである。<br />
それはさておき、このようにして 思 考 する 自 我 にとって、「 現 実 と 実 存 が 一 時 停 止 し、その 重 さを<br />
失 い、 併 せてその 意 味 を 失 うことが 可 能 になる。 今 や、 思 考 が 活 動 している 間 、 有 意 味 的 になった<br />
のは、 蒸 留 物 、 脱 = 感 覚 化 の 生 産 物 である」 312 。こうした 蒸 留 物 が、かつては「 本 質 essence」と 名 指<br />
されたのだとアーレントは 述 べる。「 本 質 は 局 所 的 なものではありえない」 313 ので、 本 質 を 扱 う 思 考<br />
、、、、、<br />
は、「 個 別 的 なものの 世 界 を 離 れ 去 り、 必 ずしも 普 遍 的 に 妥 当 しないが、 一 般 的 に 有 意 味 的 なもの<br />
を 探 しに 出 る」 314 。 思 考 の 働 きは、それゆえ、あるものを 一 般 化 generalization において 思 考 し、そし<br />
て 有 意 味 性 を 与 えることにある。<br />
だから、このような 一 般 的 に 有 意 味 なものは、 偏 在 的 であって 局 在 的 ではないゆえに、 場 所 を 持<br />
たない、つまり「どこにでもある」がゆえに「どこにもない」。 思 考 する 自 我 は 時 空 を 超 え、 時 間 と 空 間<br />
の 隔 たりを 消 し 去 ってしまう。 未 来 を 予 期 したり、 過 去 を 想 起 したりするのも、 精 神 のこうした 性 格 が<br />
可 能 にしている。 実 際 、 思 考 はどこからでもいつからでもその 対 象 を 持 ちだせるから、 時 空 そのもの<br />
を 消 し 去 ってしまっている。 後 で 詳 しく 見 るが、アーレントはこのような 思 考 する 自 我 の 時 間 経 験 を<br />
「 静 止 スル 現 在 nunc stans」という 中 世 哲 学 の 概 念 で 言 い 表 している。<br />
3<strong>08</strong> Ibid. ( 同 上 。)<br />
309 Ibid., p.76. ( 同 上 、89 頁 。)<br />
310 Ibid., p.77. ( 同 上 、90-91 頁 。)<br />
311 Ibid.( 同 上 、91 頁 。)<br />
312 Ibid,. p.199. ( 同 上 、229 頁 。)<br />
313 Ibid. ( 同 上 。)<br />
314 Ibid. ( 同 上 。)<br />
82
それでは 思 考 の 経 験 そのものは、どのようなものなのか。アーレントによれば、 退 きこもりをとおし<br />
て、 思 考 する 自 我 は 反 省 reflection へと 入 り 込 む。<br />
、、、<br />
、、、<br />
すべての 精 神 的 活 動 力 は 反 省 的 本 性 によって、 意 識 に 内 在 する 二 元 性 をおのずから 証 して<br />
いる。 精 神 的 活 動 力 を 行 使 する 者 〔mental agent〕は、〔 略 〕 自 分 自 身 へと 立 ち 戻 って 行 為 する<br />
ほかは、 活 動 的 になることはできない。〔 略 〕 精 神 的 活 動 力 、そして( 後 に 見 ることになるが) 特<br />
に 思 考 ―― 自 我 のそれ 自 身 との 音 声 なき 対 話 ――はあらゆる 意 識 に 内 在 する 私 と 私 自 身 の<br />
コギターレ<br />
根 源 的 な 二 元 性 ないし 分 裂 を、 現 実 化 させたものであると 了 解 できる。〔 略 〕あらゆる 思 考<br />
コ ー ギ ト ー ・ メ ・ コ ギ タ ー レ<br />
cogitare は、その 対 象 がなんであれ、また 我 ハ 思 考 スルト 我 ハ 思 考 スル cogito me cogitare であ<br />
ヴ ォ リ シ ョ ン ウ ォ ロ ー ・ メ ・ ウ ェ ッ レ<br />
る。あらゆる 意 志 行 為 は 我 ハ 意 志 スルト 我 ハ 意 志 スル volo me velle である。<br />
315<br />
アーレントは 精 神 的 活 動 力 における、 自 我 の 二 重 性 を 問 題 化 する。つまり 精 神 的 活 動 力 において<br />
私 は「 私 と 私 自 身 me and myself」という 分 裂 を 経 験 する。アーレントはこのような「 私 と 私 自 身 」の 発<br />
見 をソクラテスに 帰 しているが、「 近 代 的 個 人 の 同 一 性 と 対 照 的 に、この〔ソクラテス 的 な〕 人 格 の 同<br />
ワ ン ネ ス ト ゥ ー ・ イ ン ・ ワ ン<br />
一 性 は 単 一 性 によってではなく、 一 者 のなかの 二 者 の 絶 えざる 往 復 運 動 によって 形 成 される。この<br />
アクチュアリティ<br />
運 動 の 最 高 の 形 態 ともっとも 純 粋 な 現 実 態 は 思 考 の 対 話 のなかにあった。そしてソクラテスが 思 考<br />
オ ペ レイ<br />
の 対 話 だと 考 えたのは、 帰 納 、 演 繹 、 結 論 などのようにたった 一 人 の『 操 作<br />
ター』しか 者 必 要 としない 論<br />
理 操 作 ではなく、 私 と 私 (me and myself)のあいだでおこなわれる 会 話 の 形 式 であった」 316 。その 実<br />
質 はそれぞれの 精 神 的 活 動 力 によって 異 なるけれども、いずれにしても 精 神 的 生 活 は 私 と 私 自 身<br />
のいわば「 内 話 」として 展 開 されるのだ。 特 に 思 考 においては、この「 内 話 」の 性 格 は 強 い。<br />
思 考 は、 私 と 私 の 対 話 として、 複 数 者 の 対 話 である。つまり、 活 動 的 生 活 における 活 動 が 複 数 性<br />
という 人 間 の 条 件 のもとでなされるのと 同 じように、 精 神 の 内 側 での 二 者 性 が、 思 考 を 成 り 立 たせる<br />
のだ。<br />
プルーラリティ<br />
複 数 性 は 地 上 の 人 間 生 活 の 基 本 的 実 存 的 条 件 の 一 つである〔 略 〕のだから、 一 人 だけでいて<br />
ライフ・オブ・ザ・マインド<br />
自 分 と 交 流 していることは、 精 神 的 生 活 の 際 立 った 特 質 である。 精 神 がそれ 自 体 の 生 活 を 持<br />
っていると 言 いうるのは、 精 神 がこの 交 流 を 実 現 し、そこで、 実 存 的 にいえば、 複 数 性 が 二 者<br />
性 へと 還 元 されているかぎりにおいてである 。このことは 事 実 においても、また「 意 識<br />
consciousness」あるいは〔ギリシア 語 の〕シュネイデナイ syneidenai( 自 分 自 身 と 一 緒 に 知 る)と<br />
いう 言 葉 にも 示 されている。 317<br />
思 考 を「 私 と 私 」の 二 者 性 として 捉 えるのは、アーレント 以 外 には 見 られない 洞 察 である 318 。アーレ<br />
、、、、<br />
ントは、 思 考 が 二 者 性 として 展 開 されることをとらえて、「 人 間 が 本 質 的 に複 数 で 存 在 しているという<br />
315 Ibid., p.74f. ( 前 掲 訳 書 、88 頁 。)<br />
316 ARENDT, On Revolution (op.cit.), p. 102.( 前 掲 訳 書 、151 頁 。)<br />
317 ARENDT, The Life of the Mind: One/ Thinking (op.cit.), p.74.( 前 掲 訳 書 、87 頁 。)<br />
318 ただし、 反 省 を 一 種 の 自 己 内 対 話 として 捉 えることは、ヤスパースから 得 た 着 想 だと 思 われる。 詳 しくは 第 29 節<br />
83
ことを、おそらく 何 よりも 雄 弁 に 物 語 っている」 319 と 述 べているが、 逆 に 言 えば、アーレントが 人 間 を<br />
本 質 的 に 複 数 者 として 捉 えているがゆえに、 思 考 をも 複 数 者 の 活 動 力 として 捉 えることが 可 能 であ<br />
った、ということになる。そしてこの 二 者 性 こそが、 思 考 を「 真 の 活 動 力 true activity」 320 にしている。<br />
つまりそれは 真 理 をただ 受 け 入 れるような 精 神 の 受 動 性 passivity ではなく、 活 動 的 生 活 における<br />
活 動 action のように、それ 自 体 有 意 味 な 実 践 praxis としての 能 動 的 活 動 力 activity なのである。そ<br />
こでは「 私 が 問 うものであると 同 時 に 答 えるものにもなる」 321 。つまり 私 と 私 の 問 答 として、それは 精<br />
アクション<br />
神 のなかでの 活 動 という 意 義 を 帯 びてくるのだ。<br />
第 26 節 思 考 の 意 味 ―― 他 の 精 神 の 働 きと 区 別 しつつ<br />
思 考 はなにかの 役 に 立 つのか この 問 いを 考 えるとき、 思 考 以 外 の 精 神 の 働 きを 考 慮 に 入 れ<br />
るのが 有 益 である。 先 程 思 考 は 活 動 力 activity であり、 実 践 praxis であると 述 べたが、その 意 味 は<br />
比 較 においてより 鮮 明 になる。<br />
まず 認 識 cognition はどうであるか。アーレントによれば、「 思 考 と 認 識 は 同 一 のものではない」 322 。<br />
認 識 はまず、「 常 にはっきりとした 目 的 を 追 及 している」 323 。 認 識 は 対 象 に 関 しての 知 を 得 ることを<br />
目 的 としており、 目 的 を 持 つという 点 において 制 作 ( 仕 事 )に 類 似 している。「いったんこの 目 的 が 達<br />
成 されると、 認 識 過 程 は 終 わる」という 点 も、 制 作 の 活 動 力 が 物 を 仕 上 げると 終 わるのに 同 様 である。<br />
認 識 の 完 成 形 は 科 学 であり、「 認 識 作 用 によって 生 み 出 された 科 学 的 成 果 は、〔 略 〕 人 間 の 工 作 物<br />
につけ 加 えられる」 324 。 認 識 は 精 神 における 制 作 の 活 動 力 であり、その 意 味 で 目 的 論 的 な 働 きで<br />
ある。 目 的 に 支 配 されているために、 純 粋 な 活 動 力 として 目 的 を 持 たないプラクシスであるとは 言 え<br />
、、、、、、、<br />
ない。しかも、それはあくまで「 対 象 についての」 認 識 であり、 精 神 は 受 動 的 に 反 応 する。むしろそ<br />
れは 受 動 性 passivity なのである。<br />
つぎに、 知 性 intellect はどうだろうか 325 。アーレントは『 人 間 の 条 件 』ではそれを 論 理 的 推 理 力<br />
logical reasoning と 呼 んでいるが、 論 理 的 推 理 力 とは、 公 理 や 自 明 の 命 題 からの 演 繹 、 特 殊 な 現 象<br />
の 帰 納 、 論 理 的 に 結 論 を 導 出 する 作 業 における、 人 間 精 神 の 働 きである。アーレントはそれを「 頭<br />
脳 力 brain power」と 呼 び、やはり 思 考 や 認 識 と 区 別 する。それが、 我 々が 知 性 intelligence と 呼 ぶも<br />
のなのだ。 知 性 は、その 法 則 性 を、ちょうど 自 然 法 則 同 様 に、 発 見 することができる。それは、この<br />
精 神 的 能 力 が、 人 間 の 頭 脳 構 造 に 依 るからである。いいかえれば、 論 理 的 な 推 理 や 知 性 の 働 きに<br />
おいては、 人 間 の 頭 脳 のもつ 法 則 性 が、 強 制 力 として 働 くのである。アーレントのよく 出 す 例 を 使 え<br />
、、、、<br />
ば、2+2=4 は 強 制 的 な真 理 なのだ。 自 然 の 強 制 という 必 然 性 に 従 うという 意 味 では、 活 動 的 生 活 に<br />
を 参 照 のこと。<br />
319 ARENDT, op.cit., p.185. ( 同 上 、215 頁 。)<br />
320 Ibid. ( 同 上 。)<br />
321 Ibid. ( 同 上 。)<br />
322 ARENDT, The Human Condition (op.cit.), p.170. ( 前 掲 訳 書 、268 頁 。)<br />
323 Ibid. ( 同 上 。)<br />
324 Ibid., p.171. ( 同 上 、269 頁 。)<br />
325 ちなみにアーレントは、カントの Verstand を、 知 性 intellect と 翻 訳 している。ARENDT, The Life of the Mind: One/<br />
Thinking (op.cit.), p.15( 前 掲 訳 書 、17 頁 ) 参 照 。<br />
84
おける 労 働 の 活 動 力 と 特 徴 を 共 有 しており、 法 則 性 に 支 配 されているためにやはり 純 粋 な 活 動 力 、<br />
プラクシスであると 言 うことはできない。 知 性 もまた、 強 制 的 な 真 理 への 受 動 的 な 態 度 なのである。<br />
これらの 精 神 の 働 きに 対 し、 思 考 は「その 外 部 に 終 わりもなければ、 目 的 もない、 結 果 を 生 み 出<br />
すことさえない」 326 。 思 考 は 知 識 を 得 ることとは 異 なる。 知 識 を 得 ることが 目 的 なら、それは 認 識 であ<br />
る。つまり 思 考 してもなにも 知 ることはできない。また 倫 理 的 に 有 益 ななんらかの 価 値 を 生 むことも<br />
、、<br />
ない。 思 考 は 役 には 立 たない useless が、しかし 有 意 味 である meaningful。アーレントは 思 考 はその<br />
、、、<br />
外 部 に目 的 はないと 述 べているが、それは 思 考 の 活 動 力 が 目 的 自 体 であるということを 意 味 してい<br />
る。それはアリストテレスの 区 別 に 従 うなら、 制 作 的 なポイエーシスと 区 別 される 実 践 活 動 としてのプ<br />
ラクシスであると 言 える。それは 活 動 action に 通 ずる、それ 自 体 のために 追 及 される 活 動 力 なので<br />
ある。「 思 考 は 生 に 伴 うものであり、 思 考 自 体 が 生 きることから 物 質 的 な 面 を 取 り 除 いた 精 髄 なので<br />
、、、、、、、、、、、、、、、、、<br />
ある。 人 生 は 過 程 なのであるから、その 精 髄 は 実 際 の 思 考 過 程 にこそあるのであって、こりかたまっ<br />
た 結 果 とか 特 定 の 思 想 にあるわけではない」( 傍 点 は 橋 爪 ) 327 。つまり 思 考 の 有 意 味 性 は、それを 実<br />
践 すること 自 体 にある。 特 定 の 成 果 が 得 られればもう 思 考 する 必 要 はない、ということにはならない<br />
のだ。ちょうど、 音 楽 が 演 奏 されているかぎりにおいて、 楽 しむことができるように。<br />
ところで、 思 考 はその 活 動 力 の 副 産 物 として、 日 常 性 を 停 止 するという 効 果 を 持 つ。「 思 考 活 動<br />
、<br />
があると、どんな 行 為 も、どんな 日 常 の 活 動 も、それがなんであれ、 妨 げられる。あらゆる 思 考 は〈 立<br />
、、、、、<br />
ち 止 まって考 えること〉を 必 要 とする」 328 。 思 考 は 日 常 性 において 役 に 立 たないどころか、それを 阻<br />
害 するのだ。「 世 に 受 け 入 れられている 行 動 規 則 を 補 強 するというよりは、むしろ 解 体 させる」 329 。し<br />
かしこのことは、 必 ずしも 否 定 的 に 捉 えられるべき 事 実 ではない。そのことは、 反 対 に、 思 考 がなさ<br />
れない 場 合 、「 思 考 の 欠 如 thoughtlessness」の 状 況 を 考 えて 見 るとよくわかる。<br />
思 考 の 不 在 というのは、 人 間 の 営 みのなかで 実 に 強 力 な 要 因 をなすもので、 統 計 的 に 言 えば、<br />
ア ・ ス コ リ ア<br />
一 番 強 力 なものである。〔 略 〕まさに 人 間 の 営 みの 切 迫 性 、 暇 ノ= 無 サ 〔a-scholia〕が、その 場<br />
しのぎの 判 断 、または 習 慣 と 伝 統 への 依 拠 、すなわち 偏 見 への 依 拠 を 要 求 する。 330<br />
このような 思 考 の 欠 如 が、アイヒマンのような 人 間 を 生 み 出 したとアーレントは 考 えている。アイヒマ<br />
ンは 知 的 でないとか、 特 別 邪 悪 な 精 神 を 持 っているとか、そういった 理 由 から、ユダヤ 人 の 大 量 殺<br />
戮 に 加 担 したのではない。 知 的 であっても、 彼 には 思 考 が 欠 如 しており、それが 彼 を 悪 へと 導 いた<br />
のである。 思 考 自 体 には 善 を 発 見 するような 作 用 はないが、 思 考 の 営 みそのものが、 偏 見 や 伝 統<br />
へと 偏 向 する 状 態 を 停 止 させる。そのことが、「ただ 日 常 を 営 むだけで 引 き 起 こされる 巨 悪 」を 食 い<br />
止 めるのだ。アーレントは、「 良 心 conscience」という 語 が「 共 に= 知 ること con-science」というかたち<br />
326 ARENDT, The Human Condition (op.cit.), p.170. ( 前 掲 訳 書 、268 頁 。)<br />
327 ARENDT, The Life of the Mind: One/ Thinking (op.cit.), p.191. ( 前 掲 訳 書 、222 頁 。)<br />
328 Ibid., p.78. ( 同 上 、93 頁 。)<br />
329 Ibid., p.192. ( 同 上 、223 頁 。)<br />
330 Ibid., p.71. ( 同 上 、84 頁 。)<br />
85
をしている 事 実 を、このことと 結 びつける。つまり、 自 分 との 対 話 である 思 考 を 通 して、 良 心 も 賦 活 さ<br />
れるのだ。<br />
だが、このことはあくまで 副 次 作 用 にすぎない。 思 考 のはたらきそのものは、プラクシスであり、 自<br />
らの 成 果 を 次 々に 自 ら 打 ち 消 してゆく。アーレントが「 思 考 」について 考 える 際 、その 思 考 とは、 端<br />
的 に 言 って 哲 学 (と 呼 ばれてきた 営 み)のことを 指 していると 考 えてよいが、 哲 学 は、 知 性 が 知 り 得<br />
ないもの、 認 識 しえないものを 前 にしても、 止 まることはない。むしろそのようなものを 前 にしてはじ<br />
めて 思 考 はその 本 領 を 発 揮 する。たとえば「 時 間 」について 思 考 するとき、その 目 的 は、 誰 にとって<br />
も 同 一 的 で 普 遍 的 に 了 解 可 能 な「 真 理 」を 提 示 することではない。 真 理 は 知 性 に 対 応 するものであ<br />
り、 知 性 や 認 識 の 営 みは 真 理 を 得 るとともに 停 止 する。「 時 間 とはなにか」と 問 うて、 最 終 的 で 究 極<br />
的 な 解 答 ( 真 理 )は 得 られないであろう。しかし、すくなくとも「 時 間 」の「 意 味 」を 考 えることはできる。<br />
、、、<br />
つまり「 時 間 とは…である」ということを、 知 ることはできなくとも 考 えることができるのだ。<br />
考 えだされた 意 味 は、 真 理 ではないので、 自 然 のもつ 強 制 力 を 持 たない。このことが、 思 考 が 知<br />
性 や 認 識 とは 異 なり「 無 制 約 的 」であることを 示 している。 先 取 り 的 に 言 えば、このことは 思 考 に 限 ら<br />
ず、 意 志 や 判 断 にも 当 てはまる。アーレントが 思 考 、 意 志 、 判 断 の 三 活 動 力 を「 基 本 的 」と 見 做 すの<br />
は、「それらが 自 律 的 〔autonomous〕だからである」 331 。アーレントは 真 理 に 向 かう 態 度 を 受 動 性<br />
passivity と 見 做 しているが、これらの 活 動 力 activity は 強 制 を 受 けず 自 律 的 に 働 くのだ。 彼 女 が 精<br />
神 的 な 営 みの 中 でもとりわけてこの 三 つを 扱 ったのは、そういう 理 由 からで、これらを 除 いた 精 神 の<br />
営 みは、 活 動 力 = 能 動 性 とは 認 められない 332 。つまり 三 つの 基 本 的 精 神 的 活 動 力 は 無 制 約 的 な<br />
のである。 思 考 はなににも 拘 束 されることなく 意 味 を 考 え、 知 り 得 ないものについても 思 考 し、 意 志<br />
は 人 間 の 条 件 に 反 するもの――たとえば 不 死 ――をも 意 志 することができる。<br />
このように 思 考 された 意 味 は、 現 実 に 直 接 影 響 を 与 えることはない。しかし「 我 々が 行 動 する 際 の<br />
原 則 と 我 々が 自 分 の 生 活 について 判 断 し 行 動 する 際 の 基 準 は、 究 極 的 には 精 神 の 生 活 に 依 って<br />
いる。 要 するに、それらの 原 則 や 基 準 は、これらの 一 見 無 益 な、 何 の 結 果 も 生 み 出 さず『 直 接<br />
パワー・トゥ・アクト<br />
活 動 の 力 を 与 えはしない』(ハイデガー) 精 神 の 営 みを 遂 行 することに、 依 存 している」 333 。 人 間 の<br />
実 存 は 意 味 に 満 ちている。 知 性 にとっては、 人 間 の 生 存 は( 目 的 に 結 び 付 けられないので) 単 に 無<br />
意 味 に 映 るのみであるが、 思 考 はその 無 制 約 性 において、 人 間 の 生 存 に 意 味 を 見 出 すのだ。<br />
331 Ibid., p.70. ( 同 上 、82 頁 。)<br />
332 ここで、『 人 間 の 条 件 』における、 労 働 、 仕 事 、 活 動 のうち、 真 の 活 動 力 として 認 めうるのは、『 精 神 の 生 活 』にお<br />
ける 議 論 からすれば、 活 動 のみということになるのではないか、と 考 えることも 出 来 る。 労 働 はまぎれもなく 自 然 の 強<br />
制 力 に 従 うものであり、その 意 味 では 受 動 的 な 営 みでもある。それは 人 間 の 条 件 としての 生 命 に 従 っており、それを<br />
超 え 出 ない、 制 約 された 活 動 力 である。 他 方 仕 事 = 制 作 もまた、 世 界 性 という 人 間 の 条 件 に 支 配 されており、 物 と<br />
いう 目 的 、ないしはその 物 に 先 行 する 設 計 図 としてのイデアに 導 かれる 目 的 論 的 な 活 動 力 であるという 点 では、 制<br />
約 的 な、 受 動 的 な 活 動 力 である。このなかでただ 活 動 だけは、 制 約 性 をはねのけるような 可 能 性 を 持 っている。 活<br />
動 の 人 間 的 条 件 は 複 数 性 plurality であるが、これは 人 間 の 自 由 の 妨 げになるものではない。むしろ 複 数 性 のなか<br />
でこそ 人 間 は 自 らのユニークな 存 在 ――ヤスパース 風 に 言 えば、 固 有 の 本 来 的 自 己 ないし 実 存 ――を 示 すことが<br />
できるのだ。ようするに、 複 数 性 は、 人 間 が 己 の 卓 越 性 を 示 すための 可 能 性 の 条 件 となっている。この 意 味 で 活 動<br />
だけが 制 約 的 でない、 真 の 活 動 力 ということになろう。<br />
333 ARENDT, op.cit., p.71. ( 同 上 、83-84 頁 。)<br />
86
第 27 節 思 考 の 時 間 経 験 ――「 静 止 スル 現 在 nunc stans」<br />
それでは、 以 上 のような 特 徴 をもつ 思 考 は、いかなる 時 間 経 験 をもつのか。 思 考 する 自 我 は、 思<br />
考 の 活 動 力 において、 時 間 性 のなかで 自 らをどのように 時 間 化 するのか。<br />
すでに 見 たとおり、 思 考 は 普 遍 的 なもの、「 本 質 」に 関 わる。それゆえ、 思 考 は 場 所 にも 時 間 にも<br />
囚 われない。 空 間 的 には、 本 質 は、どこにあっても 意 味 を 持 つがゆえに、かえっていかなるトポスも<br />
持 たない。つまり「どこにもない」。そして 不 在 のものに 関 わる 思 考 は、「もはやない no more」ものと<br />
しての 過 去 も、「まだない not yet」ものとしての 未 来 も、それらがあたかも 現 前 するかのように、 扱 うこ<br />
とができる。<br />
思 考 のもっとも 基 本 的 な 段 階 は「 想 起 remembrance」である。 既 に 述 べたが、 感 覚 に 伴 うイメージ<br />
を 想 起 し、それを 構 想 力 によって 現 前 させる 段 階 が、 思 考 の 基 礎 的 な 前 提 となっていた。この 構 想<br />
力 がなければ、「どんな 思 考 の 過 程 も 思 考 のつながり〔trains of thought〕もまったく 不 可 能 であろう」<br />
334 。 記 憶 と 思 考 のつながりの 大 きさは、ドイツ 語 において Gedächtnis( 記 憶 )と Gedanke( 思 考 )が 語<br />
源 を 共 有 している 335 ことからも 推 し 量 られる(というより、アーレントが 両 者 を 関 連 付 けて 思 考 してい<br />
るのは、このようなドイツ 語 の 言 語 感 覚 を、 基 礎 的 な 経 験 として 備 えていたことに 由 来 するのだろう)。<br />
今 の 文 脈 で 重 要 なのは、 記 憶 が 思 考 の 基 礎 となる 事 実 よりも、 思 考 する 自 我 が、 記 憶 というかたち<br />
で 過 去 を 現 前 するもののようにして 扱 うことができることである。つまりここでは 不 在 の 過 去 は 現 前 に<br />
置 き 換 わっている。<br />
同 様 にして、 思 考 は 未 来 へも 手 を 伸 ばす。「まだない」 未 来 について、 思 考 する 自 我 は「 予 期<br />
anticipation」という 形 式 で 関 わり 合 う。ただ、この 予 期 は 過 去 からひろってきた 材 料 に 基 づいて 行 な<br />
われる(「 思 考 のなかで 未 来 を 予 期 する 能 力 というのは 過 去 を 想 起 する 能 力 から 由 来 している」 336 )<br />
ので、 実 際 は 想 起 に 非 常 に 似 ている。この 点 で、 後 に 見 る 意 志 の 能 力 、 意 志 する 自 我 が 関 わる 未<br />
来 とは、 実 は 異 なっている。 意 志 が 関 わるのは 絶 対 的 に 新 しいものであり、これまで 決 して 現 前 も 存<br />
在 もしなかったものである。その 意 味 で、かつて 現 前 したものに 基 づく 思 考 では、このような 未 来 に<br />
は 触 れ 得 ない。そのあたりは 意 志 の 時 間 性 を 問 題 にするときに 再 び 取 り 上 げよう。<br />
とにかく、このようなかたちで 未 来 や 過 去 と 関 わりうる 思 考 する 自 我 が 経 験 する 時 間 は、 現 象 界 に<br />
おいて 人 間 が 経 験 する 常 識 的 な 時 間 とは、 全 く 異 なったものとなる。 現 象 界 において 人 間 が 経 験<br />
する 時 間 は、 過 去 ・ 現 在 ・ 未 来 の 三 つの 時 制 が 順 番 に 継 起 し、 過 去 から 未 来 へとスムーズに 進 行<br />
するものとして 経 験 される。 現 象 界 での 営 為 、すなわち 労 働 ・ 仕 事 ・ 活 動 を 根 本 的 に 支 配 している<br />
のは、この 時 間 了 解 であるということになる( 仕 事 は 過 去 優 位 、 活 動 は 未 来 優 位 の 時 間 了 解 におい<br />
てでなければうまく 理 解 できないが、それは 理 解 しようとする 営 みにおいてそうなるのであって、そ<br />
れらの 活 動 力 を 経 験 する 人 間 にとっては、 時 間 はやはり 連 続 的 に 継 起 して 経 験 される)。 現 象 界 で<br />
334 Ibid., p.85. ( 同 上 、100 頁 。)<br />
335 ヘーゲルはこのことを 捉 えて、「ドイツ 語 は 記 憶 に 高 い 位 置 を 与 えて、 思 想 と 直 接 親 しい 関 係 にあるものとしてい<br />
る」と 述 べている(HEGEL, Georg Wilhelm Friedlich, 樫 山 欽 四 郎 / 川 原 栄 峰 / 塩 谷 竹 男 訳 『 世 界 の 大 思 想 II-3 ヘ<br />
ーゲル エンチュクロペディー』 河 出 書 房 、1968 年 、369 頁 。Cited in: RICHTER, Gerhard, “Acts of Memory and<br />
Mourning: Derrida and the Fictions of Anteriority,” in: RADSTONE, Susannah/ SCHWARZ, Bill (eds.), Memory:<br />
Histories, Theories, Debates, New York: Fordham Univ. Press, 2010, p.152)。<br />
336 ARENDT, op.cit., p.86. ( 同 上 、101 頁 。)<br />
87
は 現 在 こそが、 非 常 に 捉 え 難 いものである。「 現 象 界 では『 今 』<br />
の 連 鎖 が 絶 え 間 なくころがって 進 行 していくので、 現 在 は 過 去<br />
と 未 来 とを 不 安 定 につなぐものだと 理 解 されている。すなわち、<br />
我 々が 現 在 を 把 握 しようとする 瞬 間 には、 現 在 は『もはやない』<br />
か、『まだない』のである」 337 。<br />
思 考 する 自 我 は、 時 間 を 過 去 → 現 在 → 未 来 の 契 機 としては、<br />
もはや 経 験 しない。 過 去 と 未 来 があたかも 現 前 のごとく 現 われる<br />
精 神 の 領 域 においては、 過 去 と 未 来 とが 同 じ 強 度 を 持 って、 人<br />
間 に 襲 いかかって 来 るのだ( 過 去 → 現 在 ← 未 来 )。つまりその<br />
ARENDT, The Life of the Mind: One/<br />
「 場 」は「 過 去 と 未 来 のあいだ between past and future」、 過 去 と<br />
Thinking (op.cit.), p.2<strong>08</strong> ( 前 掲 訳 書 、<br />
未 来 の「 間 隙 gap」となる。ここでは 過 去 と 未 来 がともに 現 前 して<br />
240 頁 )より 引 用 。<br />
いるため、 時 間 はもはや 流 れない。つまり 時 間 は 停 止 する。そ<br />
れゆえ、アーレントによれば、このような 思 考 の 時 間 経 験 はスコラ 哲 学 において「 静 止 スル 現 在<br />
nunc stans」として 概 念 化 され、ベルクソンはそれを「 持 続 する 現 在 présent qui dure」と 名 づけた 338 。<br />
アーレントはこのような 時 間 経 験 を 上 図 のように 図 示 し、 次 のように 説 明 を 加 えている。 長 くなるが、<br />
これ 以 上 適 切 な 説 明 は 無 いので、そのまま 引 用 する。<br />
理 想 的 に 言 えば、 平 行 四 辺 形 を 形 成 する 二 つの 力 の 行 動 から 生 まれてくるのは 第 三 の 力 と<br />
いうことになるし、 結 果 として 出 てくる 斜 線 が 生 まれてくるのは 力 がぶつかりそこで 作 用 するとこ<br />
ろだということになろう。この 斜 線 は 同 じ 平 面 に 留 まり、 時 間 の 諸 力 の 次 元 から 飛 び 出 しはしな<br />
い。だが、 諸 力 の 結 果 である 斜 線 は、その 諸 力 とは 一 つの 重 要 な 点 で 異 なっている。 過 去 と 未<br />
来 の 二 つの 対 立 する 力 はその 起 源 からすると 両 方 とも 無 限 定 なものである。 真 ん 中 にある 現<br />
在 の 視 点 からすると、 一 方 は 無 限 の 過 去 からやってくるし、 他 方 は 無 限 の 未 来 から 来 る。それ<br />
らの 始 まりは 知 られないが、 区 切 られた 終 わりがあり、その 点 でそれらは 出 会 いぶつかるのだ<br />
が、これが 現 在 なのである。これとは 逆 に、 斜 辺 の 力 にははっきりとした 起 源 があり、その 出 発<br />
点 は 他 の 二 つの 力 の 衝 突 するところなのである。ところが、その 終 わりに 関 しては、 無 限 に 起<br />
源 を 持 つ 二 つの 力 が 一 緒 になって 作 用 したところから 生 まれてきたので、 無 限 であろう。この<br />
ような 斜 線 の 力 の 起 源 は 分 かっており、 方 向 は 過 去 と 未 来 によって 規 定 されているが、その 力<br />
の 及 ぶところはまるで 無 限 に 届 くように 無 限 定 の 終 わりなのである。 339<br />
図 についてはこれ 以 上 説 明 する 必 要 はないだろう。 思 考 は、 過 去 と 未 来 の 両 方 の 力 を 受 け 止 める。<br />
過 去 と 未 来 の 両 方 と 十 分 な 距 離 を、しかも 等 距 離 で 取 り、そのようにして 両 方 の 意 味 を 思 考 する。<br />
思 考 する 自 我 は、 時 間 が 絶 えまなく 連 続 する 現 象 界 から 離 れて、 普 遍 的 な 意 味 を 了 解 する 可 能 性<br />
を 自 らに 許 すのだ。<br />
337 ARENDT, Hannah, The Life of the Mind: Two/ Willing (op.cit.), p.13. ( 前 掲 訳 書 、15 頁 。)<br />
338 Ibid., pp.11f. ( 前 掲 訳 書 、14 頁 。)<br />
88
まとめよう。 思 考 する 自 我 は、 現 象 界 から 退 きこもる。そこでは 過 去 と 未 来 は 順 番 に 継 起 すること<br />
をやめ、 共 に 精 神 にとって 扱 いうる 現 前 へと 変 形 される。 思 考 する 自 我 の「 場 」は 現 象 界 の「どこに<br />
ヌ ン ク ・ ス タ ン ス<br />
もない」が、このように 過 去 と 未 来 とを 包 摂 するような 現 在 、 時 間 の 停 止 としての「 静 止 スル 現 在 」に<br />
おいて、 存 在 する。そこで 思 考 は 過 去 と 未 来 の 両 方 から 力 を 受 け 取 り、それを 無 制 限 な 可 能 性 をも<br />
つ「 意 味 」へと 向 けてゆく。 一 言 で 言 えば、 思 考 は 連 続 する 時 間 のなかにあって 時 間 の 停 止 を 経 験<br />
するのだ。だから 思 考 の 時 間 性 は「 静 止 スル 現 在 」である。<br />
339 ARENDT, The Life of the Mind: One/ Thinking (op.cit.), p.209. ( 前 掲 訳 書 、240 頁 。)<br />
89
第 七 章 意 志 willing の 時 間 性<br />
かく 心 の 中 、 胸 の 内 に 思 いめぐらしつつ、あわや 大 太 刀 の<br />
鞘 を 払 おうとした 時 、アテネが 天 空 から 舞 い 降 りてきた。<br />
――ホメロス『イリアス』<br />
第 28 節 意 志 の 哲 学 史<br />
『 精 神 の 生 活 』 第 二 巻 『 意 志 』の 中 核 は、 意 志 の 哲 学 史 となっている。というのは、 意 志 の 問 題 は<br />
「 表 の」 哲 学 史 においてはむしろ 忘 却 されたり 低 く 見 られたりしていた、とアーレントが 考 えているか<br />
らだ。 意 志 とは、 過 去 に 決 して 現 前 したことがなく、 今 決 して 存 在 していないようなものを 意 志 する 能<br />
力 であるが、このようなものとしての 意 志 は 哲 学 史 においてほとんど 認 められなかったのである。そ<br />
れゆえ、 意 志 の 活 動 力 の 特 徴 を 描 く 試 み 自 体 が、 哲 学 における 意 志 の 忘 却 の 歴 史 をなぞることに<br />
なっているのである。<br />
アリストテレスは、 存 在 論 上 の 様 相 modality の 区 別 、すなわち「 偶 然 による κατὰ συμβεβηκός」も<br />
のと「 実 体 ὑποκείμενον」との 区 別 を 立 てることを 通 して、「 意 志 に 対 する 哲 学 の 態 度 の 基 礎 を 据 えた」<br />
340 。 必 然 的 に 存 在 する 実 体 に、 偶 然 的 な 属 性 が 付 与 するということである。ここで 偶 然 的 なもので<br />
ある 意 志 が 理 解 される 可 能 性 が 開 けた。 意 志 は、ある 行 為 を「しないでおくままにすることもできた<br />
/することもできた」というかたちでのみ、 自 我 に 経 験 される。その 意 味 で、すぐれて 偶 然 的 なもの<br />
であり、まずは 偶 然 的 な 存 在 の 様 相 を 認 めることが、 意 志 の 哲 学 の 出 発 点 となる。<br />
とはいえ、アーレントによれば、 意 志 の 能 力 はアリストテレスには 知 られていなかったという。アリ<br />
ストテレスの 存 在 論 において、 存 在 者 は 可 能 態 δύναμις から 現 実 態 ἐνέργεια へと 生 成 する。 裏 を 返<br />
せば、 現 実 的 にはまだ 存 在 していないものでも、 可 能 的 には 存 在 しているということになる。この 存<br />
在 論 においては、 新 しいもの、 出 来 事 そのもの event itself は 認 められず、 暗 黙 のうちに 未 来 は 過<br />
去 の 帰 結 であるという 時 間 概 念 が 前 提 されている。アリストテレスが 認 めたのは 絶 対 的 にあたらしい<br />
プロアイレシス<br />
ものを 意 志 するような 意 志 ではなく、 選 択 προαίρεσις であった 341 。これはつまり「 二 つの 可 能 態 の<br />
内 での『 選 択 』、あるいはむしろ、 別 の 活 動 よりある 活 動 を 我 々が 選 ぶ 際 の 選 好 である」 342 。しかし、<br />
意 志 は 選 択 ではなく、 新 しいことをはじめるような 精 神 的 活 動 力 であるから、そこに( 或 る 行 為 と 別 の<br />
340 ARENDT, The Life of the Mind: Two/ Willing (op.cit.), p.14. ( 前 掲 訳 書 、17 頁 。)<br />
341 プロアイレシスという 言 葉 は、 語 根 に αἵρεσις (hairesis)という 語 を 含 んでいる。これだけで 既 に 選 択 を 意 味 するの<br />
だが、この 語 は 同 時 に「 異 教 ・ 異 端 heresy」の 語 源 でもある。このことに 着 目 して、ジャック・デリダは、 人 間 の「 責 任 は<br />
異 教 〔hérésie〕へと、つまり 選 択 、 選 好 、 好 み、 傾 向 、 立 場 としての[h]airesis へと、つまり 決 断 〔décision〕へと 運 命 づ<br />
けられている」(DERRIDA, Jacques, Donner la mort [op.cit.], p.46 〔 前 掲 訳 書 、58 頁 〕)と 言 っている。このテクスト<br />
(『 死 を 与 える』)は 宗 教 論 と 言 われているが、 実 態 は 人 間 的 責 任 と 人 間 的 自 由 のつながりを 論 じており、 異 教 という<br />
キーワードはここでは、 公 式 教 義 に 従 うという「 無 責 任 な」 宗 教 的 態 度 と 対 比 されている。 異 教 とは、 教 義 にただ 従 う<br />
という 自 動 化 された 信 仰 と 区 別 され、 固 有 の 実 存 的 な「わたし」が 自 らの 決 断 によって 信 仰 へ 進 むことを 意 味 してい<br />
るのだろう。つまりデリダは 責 任 と 決 断 の 問 題 を 結 びつけるうえで、むしろ 選 択 的 な 決 断 という 契 機 を 重 要 視 している。<br />
ここでのデリダの 関 心 ――つまり 責 任 と 自 由 と 決 断 との 結 びつき――は、アーレントの 意 志 の 問 題 に 通 ずる 部 分 も<br />
ある。 両 者 が「 選 択 」という 点 に 関 して 為 す 解 釈 の 差 は 興 味 深 い。<br />
342 ARENDT, op.cit., p.15. ( 同 上 、19 頁 。)<br />
90
行 為 というような) 選 択 肢 が 与 えられることはない。 選 択 、プロアイレシスにおいては、「 我 々は、 目<br />
、、<br />
的 に 至 るための 手 段 についてのみ 熟 考 するのであって、 目 的 については 自 明 のことと 思 っており、<br />
選 択 することはできない」 343 リベルム・アルビトリウム<br />
。この 選 択 の 能 力 はラテン 語 では 選 択 ノ 自 由 liberum arbitrium として 知<br />
られているが、やはりそれは、 絶 対 的 に 新 しいことを 始 める 能 力 としての 意 志 の 自 由 ではない。<br />
意 志 の 経 験 は、ポリスの 経 験 ではなく、 内 面 の 発 見 という 経 験 と 同 根 源 的 であったとアーレントは<br />
考 える。それは、 宗 教 的 体 験 、 具 体 的 にはパウロの 経 験 と 結 びついているのだ。パウロの 経 験 とは、<br />
「 善 をなそう」とするときに、「 悪 」が 起 こるということである。 律 法 により 罪 が 罪 として 示 され、そのこと<br />
で、なにが 悪 であるか 知 られ、 悪 をなすことも 可 能 となる。「 律 法 が 実 行 されないということ、 律 法 を<br />
実 行 しようとする 意 志 が 他 の 意 志 、つまり 罪 を 犯 そうとする 意 志 を 活 動 させるということ、それに、 一<br />
方 の 意 志 が 他 方 の 意 志 抜 きでは 存 在 しないということ」 344 が、パウロの 発 見 であった。これは 意 志 の<br />
ウ ォ ロ ー ・ メ ・ ウ ェ ッ レ<br />
反 省 的 性 格 ―― 我 ハ 意 志 スルト 我 ハ 意 志 スル volo me velle――の 発 見 であり、 意 志 する 自 我 は 精<br />
神 的 活 動 力 のなかでも 最 も 反 省 的 性 格 が 強 いのである。 意 志 ( 私 は= 意 志 する volo, I-will)が 発<br />
動 するとき、かならず 反 抗 意 志 ( 私 は= 否 と 意 志 する nolo, I-nill)が 反 対 に 生 ずる。 意 志 する 自 我<br />
において「 私 は= 意 志 する」と「 私 は= 否 と 意 志 する」とが 抗 争 する。この「 私 は= 否 と 意 志 する<br />
I-nill」は「 私 は 意 志 しない I-will-not」とは 訳 すことはできない 345 。「 私 は= 否 と 意 志 する」は、 意 志 す<br />
、、、、、、 、、、、 、、<br />
ることをそもそも 放 棄 することではなく、あることをしないことを「 意 志 する」ことなのである。<br />
こうして、 意 志 する 自 我 は、 対 話 的 な 思 考 における「 一 者 のなかの 二 者 」とは 異 なる、 抗 争 的 な<br />
「 一 者 のなかの 二 者 」をもつのだ。パウロはこの 調 停 しがたい「 一 者 のなかの 二 者 」、 意 志 と 反 抗 意<br />
志 の 争 いを、 神 の 慈 悲 によって 解 決 しようと 画 策 する(しかし 慈 悲 はもはや 意 志 の 問 題 の 外 である。<br />
「 慈 悲 は、 努 力 して 得 られるようなものではないからである」 346 )。パウロは 結 局 、 意 志 と 反 抗 意 志 の<br />
、、<br />
反 目 において、「 私 は= 意 志 する=そして= 出 来 ない I-will-and-cannot」という、「 意 志 の 無 力<br />
impotence」を 発 見 するに 留 まったのである。<br />
パウロが 意 志 の 無 力 を 発 見 したのに 対 し、エピクテトスが 見 出 したのは「 意 志 の 全 能 」と 呼 ぶべき<br />
ものであった。エピクテトスによれば、 人 間 を 悩 ませるものは 人 間 にふりかかるものそのものではなく、<br />
それに 対 する 人 間 の 判 断 なのである。 精 神 は 外 的 な 事 物 の 世 界 から 内 面 に 退 きこもってしまえば、<br />
内 面 の 独 立 を 保 つことができる。 肉 体 は 外 界 の 影 響 を 被 らずにはおれないが、 精 神 は 内 面 におい<br />
て 外 界 の 影 響 から 自 由 であることができる。むしろ 外 界 の 実 在 性 、 現 象 界 の 現 実 性 は、それが 私 に<br />
とって 現 実 であるためには、 私 の 同 意 を 必 要 とするのだ。その 意 味 で、 意 志 は 内 面 において 全 能<br />
である。しかし 結 局 は、 意 志 は 外 界 の 現 実 と 衝 突 し、「 私 が 意 志 するように 出 来 事 が 生 じること」は<br />
望 めないのだ。それゆえ「 出 来 事 が 生 ずるままを、 私 が 意 志 する」ことが、 結 局 意 志 の 全 能 性 を 証<br />
343 Ibid., p.62. ( 同 上 、73 頁 。)<br />
344 Ibid., p.68.( 同 上 、81 頁 。)<br />
345 Ibid., p.89. ( 同 上 、1<strong>08</strong> 頁 。) アーレントは、will と nill という 二 つの 動 詞 を 対 照 させ、will と will not という 対 照<br />
との 違 いを 強 調 している。それはラテン 語 の velle と nolle という 動 詞 を 適 切 に 翻 訳 するためであるとアーレントは 述<br />
べている。アーレントは nolle を 能 動 的 ・ 積 極 的 な 活 動 力 を 示 す 動 詞 と 理 解 し(つまり 消 極 的 な 活 動 力 の 停 止 ではな<br />
く)、それを will not でなく nill と 訳 すのだ(この 動 詞 は 一 応 古 い 英 語 に 存 在 しているようである[cf. willy-nilly])。し<br />
かしながら、nolle は 例 えば non vult (「 彼 は 意 志 しない」)というような 変 化 もし、 一 部 の 人 称 では non という 否 定 辞 を<br />
出 現 させる。アーレントが 言 うように、nolle にそこまで 積 極 的 な 意 味 を 見 ることができるかは、 些 か 疑 わしい。<br />
91
、<br />
明 するということになるのだ 347 。たしかに、 意 志 は 外 界 の 現 実 をそのまま 意 志 することも可 能 である。<br />
だがこれは 意 志 の 自 由 を 認 めることにはつながらないだろう。 意 志 の 全 能 性 は 外 界 をそのまま 意 志<br />
する 時 以 外 には 認 められないためだ。この 全 能 性 と、パウロの 発 見 した 無 能 さとの 中 庸 の 道 を 取 る<br />
のが、アウグスティヌスとスコトゥスである。<br />
、、<br />
アーレントはアウグスティヌスを「 最 初 の 意 志 の 哲 学 者 」と 呼 んでいる。ギリシア 的 な 哲 学 の 枠 組<br />
みで、パウロの 宗 教 的 経 験 において 発 見 された 意 志 を 考 えようとした 初 めてのひとであったためで<br />
、、<br />
ある。アウグスティヌスは、 意 志 に 先 立 つ「 意 志 の 原 因 」がないことを 発 見 した。 意 志 はいかなる 原 因<br />
をも 持 たないということを 固 有 の 性 質 にしている。 意 志 はそれゆえ 因 果 性 においては 説 明 されえな<br />
い。<br />
アウグスティヌスは、 意 志 とその 他 の 精 神 的 能 力 との 関 係 に 関 しても 考 察 している。ただし、ここ<br />
で 他 の 精 神 的 能 力 と 言 っているのは 思 考 と 判 断 ではない。 前 章 で 確 認 した 通 り、 三 つの 基 本 的 精<br />
神 的 活 動 力 は 自 律 的 であり、 互 いには 左 右 されないのである。ここで 意 志 と 関 わりをもつのは 記 憶<br />
memory と 知 性 intellect である。「 意 志 は、 保 持 すべきことと 忘 れるべきこととを 記 憶 に 命 じる。 意 志<br />
は、 知 性 に、 理 解 するために 選 ぶべきことを 命 じる。 記 憶 と 知 性 とは、 共 に、 観 想 的 なものであり、<br />
そうしたものとして、 受 動 的 である」 348 。(なお、トマス・アクィナスにとっては、むしろ 知 性 が――それ<br />
はなにを 意 志 するべきかを 意 志 に 教 えるから―― 意 志 に 対 して 優 位 にあるとされる。) 意 志 は 記 憶<br />
と 知 性 に 対 して 自 律 的 なのだ。 記 憶 すべきものと 理 解 すべきものは、 外 界 に 存 在 する 特 殊 的 なもの<br />
、、、<br />
である。だから「 意 志 は、 注 意 力 によって、はじめて 我 々の 感 官 と 現 実 世 界 とを 意 味 ある 仕 方 で 統<br />
一 」し、「この 外 的 世 界 を 我 々 自 身 の 内 へと 引 き 入 れ、 外 的 世 界 を 記 憶 、 理 解 、 肯 定 と 否 定 といった<br />
、<br />
一 層 の 精 神 的 機 能 にふさわしいようにする」 349 。 一 般 的 なものと 関 わる 思 考 とは 異 なり、 意 志 は 特<br />
、、、、、、、、<br />
殊 なものと 関 わる。しかもこのような 意 志 は「 活 動 が 発 源 する 源 spring of action」 350 なのである。 我 々<br />
が 活 動 的 生 活 において 見 てきた 活 動 の 活 動 力 が 発 動 するその 源 には、 意 志 という 精 神 的 活 動 力<br />
がある、ということである。「 感 覚 の 注 意 力 を 指 示 し、 記 憶 に 刻 印 された 印 象 を 統 括 し、 理 解 のため<br />
の 材 料 を 知 性 に 提 供 することによって、 意 志 は、 活 動 が 生 じうる 地 盤 を 準 備 する」 351 。<br />
意 志 と 活 動 との 結 びつきの 強 さは 重 要 である。 意 志 は、それが 意 志 である 限 り、「 私 は= 意 志 す<br />
る」と「 私 は= 否 と 意 志 する」との、つまり 意 志 と 反 抗 意 志 という 一 者 の 中 の 二 者 の 対 決 であった。こ<br />
の 意 志 の 葛 藤 を 調 停 するものがなんであるのかというのがパウロの 難 問 であったとすれば、アウグ<br />
スティヌスは 活 動 がそれであると 答 えたのだった。 意 志 は 自 分 の 反 対 者 を 排 除 も 否 定 もしないし、<br />
できないのだが、 行 為 においてこの 対 立 は 解 消 される。なぜなら 二 つのことを 同 時 に 行 なうことはで<br />
きないからだ。 意 志 は 活 動 に 移 行 することによって、その 役 目 を 終 える。<br />
346 Ibid., p.70.( 同 上 、84 頁 。)<br />
347 Ibid., p.81.( 同 上 、98 頁 。)<br />
348 Ibid., p.99. ( 同 上 、122 頁 。)<br />
349 Ibid., p.100. ( 同 上 、123 頁 。)<br />
350 Ibid., p.101. ( 同 上 。)<br />
351 Ibid. ( 同 上 。)<br />
92
ドゥンス・スコトゥスの 哲 学 において 明 らかになるのは、 意 志 において 人 間 の 自 由 、つまり 外 的 強<br />
制 をすべて 退 けることができるということである。 意 志 は 知 性 や 理 性 の 提 示 するものも( 困 難 である<br />
かもしれないが) 拒 否 することができる。また 自 然 を 超 えることもでき、 幸 福 を 切 り 捨 てることさえ 可 能<br />
である。ただし 意 志 が 完 全 に 自 由 であるのは、 精 神 の 領 域 に 退 きこもっているかぎりにおいてであ<br />
る。アウグスティヌスの 考 えたように、 意 志 は 行 為 ( 活 動 )においてのみ 調 停 される。しかし 活 動 にお<br />
いて、「 意 志 は 現 実 的 効 果 をおよぼすという 点 ではけっして 全 能 ではない」 352 。つまりここで 問 題 は<br />
「 私 は= 意 志 する I-will」から「 私 は= 出 来 る I-can」へと 遷 移 している。この 点 が、 意 志 の 自 由 を 疑<br />
わしいものにしている 源 泉 なのであるが、 意 志 とその 意 志 した 内 容 が 可 能 かどうかは 別 の 問 題 なの<br />
だ。そのことは 意 志 の 限 界 に 由 来 している。ひとつは、 単 純 に 活 動 や 行 為 は 現 象 界 に 属 するもの<br />
であり、 精 神 のもつ 無 制 約 性 が 解 除 されると 言 うことである。 第 二 に、(ニーチェが 発 見 した 353 ように)<br />
意 志 は「 存 在 を 完 全 に 消 し 去 ることはできない」 354 し、「『 後 ろ 向 きに 意 志 する』ことができない」 355 こ<br />
とである。「 過 去 は『 絶 対 的 に 必 然 的 』であるからこそ 意 志 の 手 には 届 かない」 356 。 意 志 が 活 動 や 行<br />
為 へと 転 化 するやいなや、それは「 存 在 」や「 過 去 」に 変 形 する。この 過 去 は 意 志 にはどうすることも<br />
できない。だがこれらのことは、 少 なくとも 精 神 の 領 域 での 意 志 の 自 由 を 否 定 するものではない。 活<br />
動 において、この 無 制 約 的 な 自 由 に 制 限 が 加 わるのだ。<br />
アーレントの 哲 学 史 の 追 跡 は、スコトゥスで 一 応 終 わる。その 後 ドイツ 観 念 論 やニーチェ、ハイデ<br />
ガーが 問 題 にされているが、それらはどちらかといえば 意 志 の 忘 却 の 過 程 のごとく 扱 われている<br />
(ただし、ヘーゲルや 進 歩 の 観 念 の 問 題 は、 意 志 の 問 題 群 として 思 考 されている。アーレントによ<br />
れば、 進 歩 が 要 求 するのは 未 来 優 位 の 時 間 意 識 であり、それは 意 志 と 通 ずる)。それゆえここで 一<br />
度 哲 学 史 の 追 跡 で 得 られた 意 志 の 特 質 を 要 約 しよう。<br />
意 志 の 問 題 が 可 能 になったのは、 偶 然 的 なものと 不 変 的 実 体 との 存 在 論 的 区 別 の 上 に 成 り 立<br />
つ。 意 志 は、「しないことも 可 能 である」という 意 味 で、すぐれて 偶 然 的 なものに 関 わるからだ。そうし<br />
た 意 志 は 絶 対 的 に 新 しいことをはじめる 能 力 であって、 決 まった 目 的 のための 手 段 を 選 択 する<br />
リベルム・アルビトリウム 、、、、、、、、<br />
「 選 択 ノ 自 由 」とは 区 別 されねばならない。「 自 由 意 志 は〔 略 〕それ 自 体 のために〔for their own<br />
sake〕 追 求 される 目 標 を 自 由 に 定 めるのであり、 意 志 だけがこのことをできる」 357 。 意 志 は 精 神 的 活<br />
動 力 である 以 上 退 きこもり withdrawal を 経 験 し、そのなかで 一 者 のなかの 二 者 two-in-one へと 分 裂<br />
する 反 省 となる。だがこのときの 二 者 は 意 志 と 反 抗 意 志 であり、それは 思 考 における 対 話 とは 異 な<br />
る 衝 突 、 対 決 なのだ。このような 対 決 を 調 停 する 可 能 性 はただ 意 志 の 内 容 を 行 為 や 活 動 として 現<br />
352 Ibid., p.131. ( 同 上 、159 頁 。)<br />
353 NIETZSCHE, Also sprach Zarathustra (ebenda), 2. Teil, „Von der Erlösung“ ( 前 掲 訳 書 、 上 、「 救 済 」)を 参 照 。<br />
354 ARENDT, op.cit., p.130. ( 同 上 、157 頁 。)<br />
355 Ibid., p.140. ( 同 上 、169 頁 。)<br />
356 Ibid. ( 同 上 。)<br />
357 Ibid., p.132. ( 同 上 、160 頁 。) なお、「それ 自 体 のために“for the sake of...”=“um... willen”」は、『 人 間 の 条 件 』<br />
において、「~のために“in order to...”=“um... zu”」と 区 別 されている。アリストテレス 的 区 別 に 従 えば、 後 者 はポイ<br />
エーシス( 制 作 ) 的 な 了 解 に 通 じており、 手 段 としてなんらかの 目 的 を 追 求 する。それに 対 し 前 者 はプラクシス 的 で、<br />
それ 自 体 が 目 的 として 追 求 されるようなものの 価 値 を 示 す。 意 志 の 目 標 は 自 体 的 に 追 及 される 価 値 をもつことにな<br />
る。<br />
93
実 化 するよりほかにない。ところが、 活 動 や 行 為 において 現 実 化 してしまったものは 意 志 には 取 り<br />
消 せないし、しかも 行 為 は 意 志 と 異 なり 全 能 ではないので、 意 志 は 必 ずしも 実 現 されるとは 限 らな<br />
い。そのような 意 志 は、しかしながら 意 志 であるかぎりにおいて、つまり 精 神 的 活 動 力 であるかぎり<br />
において、 無 制 約 性 を 備 えている。つまり、「 意 志 が 到 達 する 決 定 は、 欲 求 の 機 構 やその 決 定 に 先<br />
行 する 知 性 の 熟 慮 からは 決 して 導 出 されえない。 意 志 は、 自 分 を 拘 束 するような 動 機 の 全 因 果 連<br />
鎖 を 中 断 する 自 由 な 自 発 性 の 器 官 である」 358 。 意 志 は 自 然 にも 知 性 にも 拘 束 されない。 因 果 が 停<br />
止 した 場 所 で、ただ 自 分 だけを 根 拠 にして 意 志 するのだ。<br />
第 29 節 意 志 に 関 する 思 考 の 源 泉 ――ハイデガー・ヤスパース<br />
見 てきたように、アーレントは 哲 学 史 において、とりわけ 近 代 において 意 志 の 概 念 は 殆 ど 閑 却 さ<br />
れてきたと 考 えている。しかし、これまで 見 てきた 諸 思 想 家 とは 別 の、 彼 女 の 意 志 に 関 する 了 解 の<br />
源 泉 が、おそらく 存 在 している。その 源 泉 とは、ハイデガーとヤスパースという、 彼 女 の 二 人 の 師 の<br />
思 想 である。アーレントの 理 解 は、 間 違 いなくこの 二 者 の 思 考 に 先 導 されている。 彼 女 の 活 動 的 生<br />
活 の 分 析 (『 人 間 の 条 件 』)は 実 は、 直 接 は 言 及 されていないハイデガーやヤスパースの 思 想 に 負<br />
うところが 大 きかった。 言 うなれば、レファレンスとしてはっきりと 言 及 している 思 想 家 の 数 々が、 彼 女<br />
にとっての「 意 識 」を 構 成 しているのに 対 して、あたかもハイデガーやヤスパースの 思 想 は「 無 意 識 」<br />
を 構 成 しており、そして「 無 意 識 」であるがゆえにかえってその 分 析 を 根 底 的 に 支 配 しているかのよ<br />
うである。このような 経 緯 に 鑑 みるに、『 意 志 』において 殆 ど 言 及 されない(まったく 言 及 されないわ<br />
けではないが、 幾 分 か 不 当 な 扱 いを 受 けていると 言 わざるをえない)この 二 人 の 思 想 こそが、 彼 女<br />
の 意 志 の 分 析 に 決 定 的 な 影 響 を 与 えているということは、 十 分 ありそうなことである。(もっとも、ハイ<br />
デガーに 関 しては 最 後 のほうで 一 節 与 えられている。しかし 我 々が 取 り 上 げるハイデガーの 思 想 は、<br />
アーレントがあまり 言 及 していない 部 分 である。)<br />
アーレントは、ハイデガーに 関 して、つぎのごとく 述 べている。<br />
、、、、、、、、、、、、、、、、、<br />
ハイデガーは、その 初 期 の 著 作 においては、「 根 源 的 本 来 的 時 間 性 の 第 一 義 的 現 象 は、<br />
、、 、、、、、<br />
将 来 〔Zukunft〕なのである」 〔359〕 とし、 近 代 という 時 代 が、 未 来 を 時 間 の 決 定 的 本 質 として 強 調<br />
ゾ ル ゲ<br />
したことにくみしていた。しかも 関 心 を 人 間 の 存 在 の 中 心 にある 実 存 的 事 実 として 提 出 してい<br />
ゾ ル ゲ<br />
た。なお、 関 心 Sorge は、『 存 在 と 時 間 』において 初 めて 哲 学 用 語 として 登 場 したドイツ 語 であ<br />
って、「~に 配 慮 する」と 同 時 に「 未 来 について 心 配 する」ということを 意 味 する。 十 年 後 、ハイ<br />
デガーは、ニーチェ 論 の 第 二 巻 で、 近 代 哲 学 全 体 と 絶 縁 した。 彼 が 絶 縁 したのは、〔 略 〕 近 代<br />
という 時 代 自 身 が、いかに 意 志 の 支 配 に 依 拠 しているかということに 気 付 いたからである。ハイ<br />
358 ARENDT, The Life of the Mind: One/Thinking (op.cit.), p.213. ( 前 掲 訳 書 、246 頁 。)<br />
359 アーレントは 出 典 を 明 記 していないが、HEIDEGGER, Sein und Zeit (ebenda), S.329 ( 前 掲 訳 書 、 下 巻 、220 頁 )か<br />
らの 引 用 。ここでは 引 用 部 のみ 細 谷 貞 雄 訳 の『 存 在 と 時 間 』( 前 掲 )から、 多 少 修 正 して 引 いている。<br />
94
デガーは、 自 らの 後 期 の 哲 学 を「 意 志 しないと 意 志 する」〔willing-not-to-will〕という 一 見 すると<br />
パラドクシカルな 命 題 で 締 めくくった。 360<br />
アーレントは 一 応 、 彼 の 初 期 著 作 、とりわけて『 存 在 と 時 間 』において 意 志 の 問 題 に 触 れていること<br />
を 取 り 上 げている。このことをもってハイデガーが 近 代 哲 学 の 了 解 に 与 していると 評 価 するのは、い<br />
かがなものかと 思 うが、 初 期 ハイデガーのほうが 後 期 よりも 意 志 の 問 題 に 接 近 しているという 評 価 は<br />
正 当 だと 考 えられる。<br />
、、<br />
アーレントの 評 価 によれば、「 関 心 ――『 存 在 と 時 間 』では、 自 分 自 身 の 存 在 に 関 心 を 寄 せる 人<br />
間 の 実 存 の 基 本 的 様 態 とされている――は、いくつかの 特 徴 を 意 志 と 明 らかに 共 有 しているが、 意<br />
志 のために 単 純 に 姿 を 消 すことはない」 361 。 彼 女 は、『 存 在 と 時 間 』における 配 慮 と 意 志 の 活 動 力 と<br />
の 親 近 性 を 認 めている。しかし、それは 正 しいにしても、ハイデガーにおいて 意 志 の 問 題 との 親 近<br />
性 を 持 っている 概 念 はそれだけではない。あらかじめ 挙 げておけば、「( 先 駆 的 ) 決 意 性<br />
vorlaufende Entschlossenheit」や、「 良 心 を= 持 とうとする= 意 志 Gewissen-haben-wollen」といった<br />
一 連 の 概 念 が、 意 志 の 問 題 系 と 似 たような 問 題 系 を 築 いている。<br />
ハイデガーは、 存 在 論 の 問 いを、まずは 問 いとして 仕 上 げるために、 存 在 を 了 解 する 存 在 者 とし<br />
ての 人 間 存 在 、すなわち 現 存 在 の 実 存 論 的 分 析 から 出 発 する。つまりその 都 度 一 回 的 な 歴 史 性 を<br />
生 きる 人 間 の 実 存 を 出 発 点 として、 基 礎 的 存 在 論 を 展 開 するのだ。 現 存 在 はその 日 常 性 において<br />
は 世 界 内 存 在 と 共 同 存 在 とに 頽 落 しているが、 死 という 極 限 の、しかも 絶 対 的 に 固 有 の 可 能 性 に<br />
向 き 合 うことを 通 して、 自 分 の 固 有 の 存 在 に 向 かうことができるようになる。そしてこの 自 分 の 固 有 の<br />
存 在 を 問 うことが、 実 存 であると 言 える。<br />
現 存 在 はその 頽 落 において、 良 心 Gewissen の 呼 び 声 Ruf を 聞 き 取 る。それは 日 常 性 に 頽 落 し<br />
ている 現 存 在 に、 被 投 性 と 死 とを 思 い 起 こさせ、そのことによって 自 らの 固 有 で 本 来 的 な 存 在 へと<br />
向 かうよう 呼 びかけてくるのだ。「 良 心 の 呼 びかけをまともに 聞 くことは、ひとごとでない 自 己 の 存 在<br />
、、、、、<br />
可 能 においておのれを 了 解 すること、すなわち、ほかならぬ自 己 が 本 来 的 に 負 い 目 を 負 って 存 在<br />
していることへむかって 自 己 を 投 企 すること」 362 を 意 味 する。ここで 良 心 は、 本 来 的 自 己 を 決 断 する<br />
こととしての 実 存 へ 通 ずるという 点 において、 意 志 に 肉 薄 する。「その 呼 び 声 を 了 解 することは、 選<br />
択 することである――、しかし、 良 心 を 選 択 することではない。 良 心 はもともと 選 択 されえないものな<br />
、、、、<br />
のである。 選 択 されるのは、 良 心 を 持 つこと、すなわち、ひとごとでないおのれの 負 い 目 ある 存 在 へ<br />
、、、、、、、、、、、、 、、、、、、、、、<br />
むかって 開 かれている 自 由 存 在 である。すなわち、 呼 びかけを 了 解 することは、 良 心 を 持 とうとする<br />
、、<br />
、、、、、、、、<br />
意 志 (Gewissen-haben-wollen)のことなのである」 363 。 良 心 を 選 択 することはできない、というのは、<br />
良 心 はつねにすでに 現 存 在 をその 固 有 の 存 在 、ひいては 存 在 者 の 存 在 としての 存 在 性 のほうへと<br />
呼 びかけているからである。しかし、その 呼 び 声 を 聞 いて 存 在 へと 向 かうかどうかは 現 存 在 に 委 ね<br />
られている。 言 い 換 えると、ここで 現 存 在 の 意 志 にその 選 択 が 任 される。<br />
360 ARENDT, The Life of the Mind: Two/ Willing (op.cit.), p.22. ( 前 掲 訳 書 、27 頁 。)<br />
361 Ibid., p.181. ( 前 掲 訳 書 、217 頁 。)<br />
362 HEIDEGGER, Sein und Zeit (ebenda), S.287. ( 前 掲 訳 書 、 下 巻 、138 頁 。)<br />
363 Ebenda, S.288. ( 前 掲 訳 書 、 下 巻 、139 頁 。)<br />
95
「 良 心 を 持 とうとする 意 志 は、この 負 い 目 ある 存 在 へ、 決 断 的 におのれを 明 けひらく〔Das<br />
Gewissen-haben-wollen entschließt sich für dieses Schuldigsein 〕 。 決 断 的 な 覚 悟 性<br />
〔Entschlossenheit〕の 本 来 の 趣 旨 からいえば、それは 現 存 在 が 存 在 しているかぎりおびているこの<br />
負 い 目 ある 存 在 へむかっておのれを 投 企 するのでなければならない」 364 。 我 々にとって 重 要 なの<br />
は 、 現 存 在 の 存 在 仕 方 に お い て 、 自 ら の 本 来 的 存 在 に 至 る に は 、 意 志 に よ っ て 決 断<br />
Entschlossenheit する 必 要 があるという 点 である。つまり、 本 来 的 存 在 というのは、 哲 学 史 でいうとこ<br />
ろの「 実 体 」のごときすでに 与 えられたものではなく、 自 らの 決 意 をとおしてそれへと 成 って 行 くとこ<br />
ろの、 未 来 に 属 するものなのである。<br />
、、<br />
覚 悟 性 は、そのつど 事 実 的 な 状 況 をおのれに 示 し、かつそのなかへおのれを 連 れだす。 状 況<br />
とは、 把 握 されることを 待 っている 客 体 的 なものではなく、したがって、あらかじめ 予 測 し 提 示 さ<br />
れるわけにはいかないものである。 状 況 は、 自 由 な 自 己 決 定 において――すなわち、 先 廻 りし<br />
て 規 定 されない、しかしそのつど 規 定 されることのできる 自 由 な 決 断 のなかで――はじめて 開<br />
示 されるのである。 365<br />
現 存 在 は、 関 心 Sorge に 伴 う「おのれに 先 立 って Sich-vorweg」という 機 制 を 備 えていて、それゆえ<br />
につねに 存 在 可 能 である。だから「おのれ 自 身 を 透 察 するようになった 覚 悟 性 は、 存 在 可 能 につき<br />
まとう 無 規 定 性 はそのつどの 状 況 のへの 決 断 においてそのつど 規 定 されるよりほかはないことを 了<br />
解 する」 366 。<br />
さきほど 引 用 した 通 り、アーレントは 配 慮 と 意 志 との 類 似 性 を 多 少 なり 認 めているが、 自 由 に 裏 付<br />
けられた(あるいは 自 由 を 裏 付 けるような) 決 断 や 覚 悟 性 は、アーレントの 自 由 な 意 志 の 活 動 力 に<br />
実 際 かなり 近 い。その 意 味 で、 彼 女 の 意 志 に 関 する 思 考 は、ある 程 度 は 間 違 いなくハイデガーの<br />
了 解 に 従 っていると 考 えられる。 意 志 は、なんの 所 与 も 与 えられることなく 決 断 する。かりに 所 与 が<br />
ある 程 度 与 えられたとしても、そうなのである。というのは、 所 与 が 意 味 をなさなくなるような 例 外 状<br />
況 でこそ、 意 志 は 意 味 をもつし、 必 要 ともされるからだ。つまり 決 断 や 決 意 の 概 念 と 意 志 は、 同 じ 硬<br />
貨 の 裏 表 のごときものである。たとえば、ハイデガーは、『 形 而 上 学 入 門 』において、なにかを「 問 う」<br />
ことに 関 連 して、 決 意 と 意 志 の 関 係 を 述 べている。<br />
、、、、<br />
問 いの 意 向 はむしろ 知 ることを= 意 志 する〔Wissen-wollen〕という 点 にある。 意 志 する<br />
ヴ ォ レ ン<br />
――とい<br />
うことは 単 なる 欲 求 することや 追 求 することではない。 知 ることを 欲 求 する 者 も、 表 面 では 問 うて<br />
いるかに 見 える。が、 彼 はこの 問 いを 口 にすること 以 上 には 出 ない。 彼 はこの 問 いが 始 まるち<br />
ょうどその 所 で 立 ちどまる。 問 うとは 知 ることを= 意 志 することである。 意 志 する 人 、 彼 の 現 存 在<br />
364 Ebenda, S.305. ( 同 上 、173 頁 。) 訳 の「 決 断 的 におのれを 明 けひらく」は sich entschließen の 訳 であるが、 少 々<br />
訳 しすぎのきらいがある。 動 詞 の 単 純 な 意 味 としては、「( 自 ら) 決 意 する」。<br />
365 Ebenda, S.307. ( 同 上 、177 頁 。)<br />
366 Ebenda, S.3<strong>08</strong>. ( 同 上 、178 頁 。)<br />
96
の 全 体 を 一 つの 意 志 の 中 へと 置 く 人 、そういう 人 は 決 意<br />
エントシュロセン<br />
してある<br />
、、<br />
。 決 意 〔Entschlossenheit〕<br />
はぐずぐず 延 ばしたり、こそこそ 逃 げたりしないで、その 瞬 間 からして、しかも 絶 え 間 なく 行 動<br />
する。 決 = 意 は 決 して 単 なる 行 動 の 決 心 ではなくて、 行 動 の 決 定 的 始 まりであり、すべての 行<br />
動 に 先 んじ、すべての 行 動 を 徹 頭 徹 尾 貫 いている 始 まりである。 意 志 するとは 決 意 してある<br />
ことである。〔 傍 点 は 原 文 、ゴシック 体 強 調 は 橋 爪 〕 367<br />
、、、<br />
ここで 決 意 、すなわち 意 志 は 始 まりと 並 べられている。 始 まりはアーレントにおいても 活 動 の 原 理 で<br />
あり、また 意 志 がもたらすものである。こうして 見 てくれば 明 瞭 なことだが、ハイデガーにおいても 意<br />
志 の 問 題 はかなり 大 きいものであった。<br />
だが、アーレントとハイデガーが 重 なり 合 うのもここまでである。ここから 先 は、アーレントの 指 摘 は<br />
かなり 的 確 なものとなる。そしてここから 先 に 取 り 上 げる 部 分 が、ある 意 味 アーレントとハイデガーの<br />
分 離 を 決 定 的 なものにしている 場 所 でもある。アーレントによれば、「 転 回 Kehre」 以 降 のハイデガ<br />
ーにおいて、「 関 心 はその 機 能 を 根 本 的 に 変 える。それは、 自 己 関 係 的 な 性 格 、 人 間 の 自 分 の 存<br />
在 への 関 わりを 大 方 失 ってしまう」 368 。そのかわり、「 重 点 はそれ 自 身 に 対 する 心 配 や 関 心 としての<br />
、、、、<br />
ゾルゲから、 配 慮 をもつこととしてのゾルゲ、しかもそれ 自 身 に 対 するものではなく 存 在 に 対 するゾ<br />
ルゲへと、 移 行 した」 369 。もとより、 良 心 を=もとうとする= 意 志 もまた、 呼 び 声 に 従 うものであった。<br />
この 呼 び 声 はどこから 発 するとも 言 われないが、 存 在 そのものの 生 起 に 由 来 することは 間 違 いない。<br />
『 存 在 と 時 間 』の 時 点 でもすでに 意 志 は 存 在 に 先 行 されている。<br />
さらにハイデガーは 意 志 に、 過 去 を 破 壊 しようという 破 壊 的 な 性 格 を 見 出 したのだとアーレントは<br />
言 う( 過 去 を 破 壊 しかねない 性 格 は、 過 去 をどうすることもできない 意 志 の 本 性 に 由 来 する)。「テク<br />
ノロジーの 端 的 な 本 性 は、 意 志 する 意 志 、つまり 世 界 全 体 を 意 志 の 支 配 と 統 治 権 に 従 わせることで<br />
あり、この 統 治 によって 当 然 のことながら 結 果 としては、ただ 全 面 的 な 破 壊 に 終 わるだけのことであ<br />
る。こうした 統 治 に 代 わるものといえば、ただ、『 放 置 しておくこと』であり、この 放 置 は 活 動 として 見<br />
れば、 存 在 の 呼 び 声 に 従 う 思 考 の 働 きである。 思 考 における 放 置 にあふれる 気 分 は、 意 志 の 働 き<br />
における 目 的 的 性 格 とは 反 対 である。 後 に〔 略 〕ハイデガーは、それを『 放 下 』〔Gelassenheit〕と 呼 ん<br />
だ。すなわち、 放 置 に 対 応 する、『 意 志 でない 思 考 』に『 我 々を 備 えさせる』 平 穏 さ〔calmness〕のこと<br />
である」 370 。<br />
さきほど『 形 而 上 学 入 門 』を 引 用 したが、 続 く 箇 所 で、ハイデガーはこう 書 いている。「ここで 意 志<br />
リ ヒ ト ゥ ン グ 、<br />
することの 本 質 は 決 = 意 へと 取 り 戻 される。だが 決 = 意 の 本 質 は 人 間 の 現 存 在 が 存 在 の 空 開 処 の<br />
、、、<br />
ために露 = 呈 されていることであって、 決 して『はたらき』の 力 を 内 に 蔵 していることではない。<br />
ラ ッ セ ン ラ ッ セ ン<br />
〔 略 〕 存 在 への 関 連 はさせる ということである。すべての 意 志 することがさせる にもとづいているとい<br />
367 HEIDEGGER, Einführung in die Metaphysik (Gesamtausgabe Bd.40) (ebenda), S.23. ( 前 掲 訳 書 、43 頁 。)<br />
368 ARENDT, The Life of the Mind: Two/ Willing (op.cit.), p.181. ( 前 掲 訳 書 、217 頁 。)<br />
369 Ibid., p.182. ( 同 上 。)<br />
370 Ibid., p.178. ( 同 上 、213-214 頁 。)<br />
97
うことは 常 識 的 な 悟 性 を 驚 かせる」( 傍 点 強 調 は 原 文 、ゴシック 体 強 調 は 橋 爪 ) 371 。このような 点 をアーレン<br />
トは「 意 志 しない 意 志 」と 見 做 し、 自 分 の 意 志 に 関 する 考 えと 区 別 するのである。<br />
アーレントのヤスパースに 対 する 評 価 は、ハイデガーに 対 するそれよりも 或 る 意 味 不 当 なもので<br />
あるといいたくなる。「ヤスパースも〔 略 〕 自 分 の 哲 学 では 意 志 を 人 間 能 力 の 中 心 に 置 かなかった」<br />
372 というアーレントの 指 摘 は、 実 際 にヤスパースを 読 んでみると、 疑 わしい。ここでは、ヤスパースの<br />
主 著 『 哲 学 』の 第 2 巻 、『 実 存 開 明 』を 取 り 上 げて、ヤスパースにおける 意 志 の 問 題 の 扱 いを 見 てみ<br />
よう。ここでヤスパースは 第 5 章 を「 意 志 Wille」、 第 6 章 を「 自 由 Freiheit」と 題 し、 意 志 の 問 題 に 一<br />
定 の 紙 幅 を 割 いている。<br />
ヤスパースの 哲 学 においては、ハイデガーにおけると 同 様 、 人 間 という 存 在 者 のその 都 度 の 歴<br />
史 的 = 時 間 的 存 在 、すなわち 実 存 Existenz が 問 題 となっている。ただし、ハイデガーにおいて 実<br />
存 範 疇 が 存 在 論 一 般 に 至 るための 基 礎 的 存 在 論 として 問 われていたのに 対 し、ヤスパースは 実 存<br />
を 実 際 に 探 究 し、「 開 明 する erhellen」ことを 重 要 視 していた。ヤスパースによれば、 人 間 は、ハイデ<br />
ガーにおける 人 間 存 在 が 世 界 を 生 きていたように、さしあたり 知 性 的 に 了 解 可 能 な 世 界 現 存 在<br />
Weltdasein を 生 きている。しかしながら、 人 間 の 知 性 や 悟 性 は、 世 界 のなかで、あるときその 限 界 に<br />
突 き 当 たる。 可 能 的 実 存 mögliche Existenz、すなわち 実 存 へと 至 る 可 能 性 をもつ 存 在 者 としての<br />
人 間 は、そのとき「 不 満 Unbefriedigung」を 抱 き、 自 らに 固 有 の 本 来 的 存 在 としての 実 存 へと 目 ざめ<br />
させられる。ヤスパースにおいても、 人 間 の 本 来 的 存 在 として 実 存 は、 未 来 に 属 するものである。<br />
、、、、<br />
「 経 験 的 な現 存 在 としての 私 はまだ 究 極 的 なものではなく、 私 はまた 未 来 としての 可 能 性 をもつ。な<br />
ぜなら 私 は、 私 が 成 るところのものを 通 して、 私 が 何 であるかをなお 決 定 するからである」 373 (とはい<br />
え、「 未 来 に 属 する」という 理 解 もヤスパースからすれば、まだ 悟 性 的 である。なぜなら「 実 存 するも<br />
のとしての 私 の 本 質 は 時 間 を 超 越 する 意 味 のうちにある」 374 からである。 実 存 は 言 表 = 命 題<br />
Aussage においては 矛 盾 的 にしか 表 現 されえない。つまり 実 存 は 時 間 的 な 世 界 における 永 遠 の 瞬<br />
間 なのである)。<br />
それゆえヤスパースにおいては 自 己 反 省 Selbstreflexion という 表 現 も、 伝 統 的 な 哲 学 とは 異 なっ<br />
た 意 味 を 持 つ。 自 己 を 反 省 するとは、なにか「 実 体 」のように 固 定 的 に 存 在 する「 私 そのもの」を 知 る<br />
なり 認 識 したりすることではない。「 私 を 私 に 関 係 づけることはすでに 私 自 身 であるのではなく、 内<br />
的 行 為 において 自 己 を 期 待 することを 意 味 している、 自 己 存 在 の 根 源 として、このように 自 己 が 自<br />
、、、、、、、、<br />
己 に 関 係 することの 本 質 のうちにおいて、 対 象 的 となった 存 立 状 態 において 私 の 私 との 同 一 性 が<br />
、、、、、<br />
可 能 であることは 根 柢 において 無 効 になる。 私 は、 私 に 積 極 的 に 関 係 するがゆえに、 自 己 存 在 の<br />
、、、<br />
、、、、、、、、、、、、、、<br />
可 能 性 にすぎない。それゆえ 私 は 時 間 のうちにおいては 私 にとってけっして 終 極 もなければ 完 成 も<br />
371 HEIDEGGER, ebenda, S.23. ( 前 掲 訳 書 、43 頁 。)<br />
372 ARENDT, The Life of the Mind: Two/ Willing (op.cit.), p.22. ( 前 掲 訳 書 、26 頁 。)<br />
373 JASPERS, Karl, Philosophie, Bd.2: Existenzerhellung, München/ Zürich: Piper, 1994, S.46. ( 小 倉 志 祥 / 林 田 新<br />
二 / 渡 辺 二 郎 訳 『 哲 学 』 中 公 クラシックス、2011 年 、79 頁 。なお、この 訳 書 では 亀 甲 括 弧 〔…〕が 原 書 の 丸 括 弧 (…)<br />
に 対 応 して 用 いられているが、 本 論 文 では 橋 爪 による 挿 入 ないし 訳 者 の 捕 捉 を 表 わすために 亀 甲 括 弧 を 用 いてき<br />
た 経 緯 があるので、ここでは 訳 書 の 亀 甲 括 弧 は 丸 括 弧 に 直 してある。 以 下 も 同 書 からの 引 用 は 同 様 に 対 処 する。)<br />
374 Ebenda. ( 同 上 。)<br />
98
、、<br />
ないので、 私 は 私 自 身 を 知 ら」 375 ない。ハイデガーの 現 存 在 が、 自 分 が 可 能 性 であるがゆえに 自<br />
分 の 全 体 存 在 を 決 して「 知 ら」なかったのと 同 様 に、ヤスパースにとっての「 私 自 身 」もまた 自 分 の 完<br />
、、、 、、、、<br />
成 を「 知 ら」ない。というのも、 自 己 反 省 は、 自 己 をまさに 創 造 するような、 自 己 への 関 わりかたであ<br />
るからだ。それゆえ、「 私 は 自 身 について 憂 慮 し、 自 己 自 身 に 関 係 することにおいてさらに 自 身 が<br />
何 であるかを 決 断 する 存 在 である」(ゴシック 体 強 調 は 橋 爪 ) 376 。<br />
ここでは、 決 断 entscheiden, Entscheidung という 語 が 鍵 となっている。ハイデガーにおいても、 決<br />
意 Entschloß や 覚 悟 性 Entschlossenheit という 契 機 が 重 要 であった。 語 としては 別 だが、 相 当 に 近<br />
接 したニュアンスの 語 を 使 っているところからも、 彼 らの 思 想 の 共 通 性 を 読 みとることができると 思 う<br />
( 決 断 や 決 意 、 決 定 主 義 という 問 題 は、あとでシュミットの 思 想 を 見 る 際 にもう 一 度 振 り 返 ることにな<br />
るだろう)。ただし、 決 断 と 意 志 との 関 係 は、ヤスパースにあっては 多 少 ややこしい。「 自 己 自 身 であ<br />
る 者 は、 己 れの 歴 史 的 一 回 性 において 選 択 するのであり、その 選 択 において、 己 れ 自 身 と 他 の 実<br />
存 とに 対 してみずからを 開 示 しながら、 選 択 するのである。〔 略 〕この 選 択 は、 現 存 在 のなかで 私 自<br />
身 であろうとする 決 断 である。〔 略 〕 決 断 は、――そのことは 意 志 に 対 してやはり 贈 与 されたものとし<br />
て 与 えられるのであるが―― 私 が 意 欲 しつつ 本 来 的 でありうるということなのであり、その 決 断 に 基<br />
づいて 私 が 意 志 することはできるが、その 決 断 自 体 を 意 志 することはもはやできないようなものであ<br />
る」 377 。 一 方 では 決 断 は 意 志 に 先 立 つものである。だが「 決 断 は、〔 略 〕 単 に 直 接 的 な 恣 意 などとい<br />
うものではなくて、 私 の 現 存 在 の 歴 史 的 具 体 性 において 私 が 何 を 意 志 しているかを、そこで 私 が 知<br />
るようなものである」 378 というように、 知 性 にとっては、 意 志 は 決 断 を 通 して 知 られる。つまり 知 性 的 な<br />
、、、<br />
了 解 にとっては、 決 断 は 意 志 を 導 き、 同 時 に意 志 が 決 断 のあとに 判 明 するというような、 矛 盾 的 なも<br />
のと 映 る。 意 志 と 決 断 は、いわば 同 時 分 節 的 である。 現 在 の 決 断 が 未 来 の 本 来 的 自 己 を 決 定 し、<br />
、、、、、、<br />
その 本 来 的 自 己 から 私 の 過 去 の 意 志 の 意 味 (「 私 がなにを 意 志 していたか」)が 知 性 にとっても 明 ら<br />
かになるのだ。つまりここでも 時 間 性 の 第 一 義 的 現 象 は 未 来 に 属 するということが 言 える。<br />
それゆえ、 決 断 においてなにが 選 択 されるか、ということも、 知 性 的 に 了 解 できるものではない。<br />
選 択 された 本 来 的 自 己 は 未 来 に 属 するからである。<br />
、、、<br />
実 存 的 選 択 は、 諸 動 機 の 争 いの 結 果 (それは 一 つの 客 観 的 過 程 であろう)ではないし、ま<br />
た、いわば 正 しい 結 果 としてのある 結 果 をもたらす 計 算 問 題 の 成 果 に 従 うような、 単 なるみせ<br />
かけの 決 定 でもないし( 計 算 問 題 の 成 果 であれば、 不 可 抗 的 なものであろうし、 私 はそれをた<br />
だもう 明 証 なものとして 承 認 してそれを 標 準 とすることができるのだが)、さらにまた、 客 観 的 に<br />
定 式 化 された 命 法 への 服 従 (そのような 服 従 は、 自 由 に 先 立 つ 形 式 であるか 自 由 の 逸 脱 であ<br />
、、<br />
るかのいずれかである)でもない。むしろこの 選 択 の 決 定 的 な 点 は、 私 が選 択 するということで<br />
375 Ebenda, S.36. ( 同 上 、61 頁 。)<br />
376 Ebenda, S.35. ( 同 上 、60 頁 。)<br />
377 Ebenda, S.180f. ( 同 上 、300-301 頁 。)<br />
378 Ebenda, S.181. ( 同 上 、302 頁 。)<br />
99
、、<br />
ある。〔 略 〕 歴 史 的 な 内 実 というものが、〔 略 〕 本 来 的 自 己 の 根 源 的 な 必 然 性 の 意 識 によって、<br />
現 存 するに 至 るのである。 379<br />
未 来 の 本 来 的 自 己 を 選 択 するような 決 断 において、その 自 己 は 文 字 通 り「 比 類 ない」。つまり 通 時<br />
的 にも 共 時 的 にも「 私 」と 同 じ 人 間 は 見 つからない。それゆえ 私 による 自 己 の 決 断 はあらゆる 依 拠<br />
、、、、、<br />
が 停 止 した 地 点 で 行 なわれねばならないのである。 選 択 はたしかに「 徹 底 して 媒 介 されたものであ<br />
る。 実 存 の 絶 対 的 な 決 意 が 言 葉 を 発 してくるのは、 可 能 的 なものの 空 間 のうちにあるすべての 客 観<br />
的 なものに 直 面 してであり、また 主 体 の 無 限 の 反 省 で 検 証 された 上 でのことである。しかし 実 存 の<br />
決 意 は、もろもろの 考 慮 の 結 果 ではない――もちろんこの 決 断 はそのような 考 慮 によって 貫 徹 され<br />
ており、それゆえその 考 量 なしにはありえぬものであるにもかかわらず、そうなのである。 決 断 それ<br />
、、<br />
自 体 は、 飛 躍 のうちにはじめて 存 在 する」( 傍 点 強 調 は 原 文 、ゴシック 体 強 調 は 橋 爪 ) 380 。なぜなら 論 理<br />
的 必 然 性 や、 先 例 や 伝 統 、 考 慮 、つまり「 私 の 外 にあるなにか」に 少 しでも 依 拠 しているならば、そ<br />
の 決 断 は 決 断 でなくなる。そういった 参 照 項 が 働 かなくなるとき、それでもなお 何 かを 決 定 しなくて<br />
はならないとき、 私 はそこではじめて 本 来 的 自 己 を 決 断 するのである。<br />
アーレントに 先 行 する、アーレントの 師 でもある 二 人 の 哲 学 者 が、このような 決 断 の 哲 学 を 築 いて<br />
いたことは、 傾 注 に 価 する。 少 なくとも 否 定 的 にであれ、 影 響 を 被 っているのはまず 間 違 いない。 実<br />
際 この 二 人 の 師 の 哲 学 を 参 照 することによって、アーレントの 意 志 がどのような 性 質 のものであるの<br />
かが、よく 了 解 される。アーレントが 意 志 の 問 題 と 取 り 組 んだのは、まず 間 違 いなく 彼 女 の「 始 まり」<br />
の 理 論 に 関 連 して、である。 人 間 が「 始 める」ことが 可 能 であるというときの、その 始 めることの 捉 え<br />
難 さは、すでに「 活 動 」をあつかった 第 五 章 で 見 てきたとおりである。つまり 新 しく 始 められたことは<br />
絶 対 的 に 新 しく 無 根 拠 であるがゆえに、 人 間 の 知 性 や 悟 性 の 了 解 には 受 け 入 れがたい。しかし、<br />
本 来 的 自 己 を 求 める 実 存 哲 学 的 な 思 考 のなかでは、 絶 対 に 固 有 の 自 己 という 難 問 に 向 き 合 うなか<br />
で、 同 じ 問 いがすでに 問 われていたのだ。 固 有 の 自 己 は、つねに 可 能 的 な 存 在 者 としての 人 間 に<br />
とっては、つねに 未 来 に 属 する。それゆえ 決 断 としての 意 志 は、 未 来 的 な 本 来 的 自 己 からして、 自<br />
、、、、<br />
己 を 了 解 する。つまりそれは 単 なる 知 性 的 な 了 解 ではなく、 未 来 の 自 己 を 創 造 することなのであ<br />
る。<br />
第 30 節 意 志 の 時 間 経 験 ――「まだない not yet」<br />
以 上 見 てきたような 意 志 の 特 徴 から、その 時 間 経 験 の 性 質 を 描 出 できる。<br />
アーレント 自 身 強 調 するのは、 意 志 の 未 来 優 位 な 性 格 である。 意 志 する 自 我 は 思 考 する 自 我 同<br />
様 に 現 象 界 から 退 きこもる。そこで 思 考 する 自 我 は 未 来 と 過 去 とに 等 距 離 をとり、 両 方 から 力 を 得 て<br />
無 限 の 思 考 を 展 開 する。 意 志 の 場 合 はそうはいかない。それは、 意 志 が 過 去 に 手 を 伸 ばせないた<br />
めだ。 意 志 は 後 ろ 向 きに 意 志 することはできない。 意 志 は 存 在 を 消 すことはできないのだ。 過 去 は<br />
379 Ebenda, S.180f. ( 同 上 、300 頁 。)<br />
380 Ebenda, S.181. ( 同 上 、301 頁 。)<br />
100
必 然 性 であり、 意 志 はそれに 対 して 苛 立 つ(もし 可 能 であればそれを 全 滅 させようとする)。しかし<br />
出 来 ることはせいぜい、 知 性 に 命 令 を 下 し、 必 然 性 に 対 して「なぜ」という 問 いを 立 てることくらい<br />
である。<br />
意 志 が 投 企 project するのは、「けっして 存 在 しなかったもの、まだ 存 在 しない〔not yet〕もの、それ<br />
に 多 分 存 在 しないようなもの」 381 である。つまり、これまでは 存 在 していなかったようなことを 意 志 す<br />
ることとして、 予 期 や 予 想 とは 区 別 されねばならない。 予 期 において、 人 間 が 相 手 にするのは、 実<br />
は 過 去 である。 過 去 ――そしてせいぜい 現 在 ――から 得 られた 材 料 をもとに 未 来 を 理 解 しようとす<br />
る 思 考 の 働 きが 予 期 である。だがそれは 根 本 的 に 新 しいものを 見 出 すことはない。それに 対 して、<br />
意 志 は、 意 志 する 当 人 にとってさえ、その 到 来 が 予 想 できない。「 常 に、 我 々が 実 際 に 行 ったことを<br />
行 わないままにしておくこともできたはずだ、ということ 我 々が 知 っている」 382 ことから、 意 志 の 自 由<br />
はが 知 られるということは、 示 唆 的 である。それは 知 性 にもなににも 導 かれないから、 突 然 の「 決 断 」<br />
として、 回 顧 的 にしか 把 握 されないのだ(「 決 断 」がそういう 性 格 を 持 つものであることは、ヤスパー<br />
ア テ ナ<br />
スらの 理 論 においても 理 解 できる)。その 決 断 はちょうど、アキレウスに 降 りてきた 女 神 のようなものと<br />
して 経 験 されるものであろう 383 。<br />
この 点 が 思 考 や 認 識 や 知 性 、あるいは 活 動 的 生 活 における 仕 事 の 能 力 とは 区 別 されるところで<br />
ある。 仕 事 の 能 力 においても、 人 間 はある 未 来 の 物 を 制 作 しようとして、 一 見 未 来 を 優 先 しているか<br />
に 見 える。ところが、そこで 投 企 されるものは、 全 く 新 しいものではなくて、 過 去 から 存 在 しているあ<br />
るイデアなのである。つまり 仕 事 においては 存 在 の 意 味 は 過 去 から 了 解 される。 第 四 章 で 確 認 した<br />
ように、マルクス 的 な 革 命 の 理 念 を 最 終 的 に 失 敗 に 追 い 込 むのは、このように 仕 事 から 人 間 の 活 動<br />
、、 、、、、、、、、、、、、、、、<br />
を 了 解 しようという 時 間 了 解 であると 考 えられる。いわば 仕 事 = 制 作 にとっての 時 間 の 第 一 義 的 現<br />
、、、、、、、<br />
象 は 過 去 なのだ。<br />
話 を 元 に 戻 すと、 意 志 が 投 企 するものは、かつて 決 してなかったもの、 今 も 決 してないものである。<br />
つまり、これまでの 言 い 方 を 思 い 出 せば、それは「はじまり beginning」の 力 なのだ。 新 しいことを 始<br />
めることの、 精 神 における 基 礎 が、 意 志 なのである。それゆえ、 意 志 においては 未 来 が 優 位 になる。<br />
381 ARENDT, The Life of the Mind: Two/ Willing (op.cit.), p.14. ( 前 掲 訳 書 、17 頁 。)<br />
382 Ibid., p.5. ( 前 掲 訳 書 、7 頁 。)<br />
383 ホメロス『イリアス』の 第 一 巻 は、アキレウスとギリシア 軍 の 総 大 将 アガメムノンの 争 いからはじまる。アガメムノンの<br />
強 欲 に 対 して 怒 り 心 頭 に 発 したアキレウスは、「 鋭 利 の 剣 を 腰 より 抜 いて 傍 らの 者 たちを 追 い 払 い、アトレウスの 子<br />
〔=アガメムノン〕を 打 ち 果 すか、あるいは 怒 りを 鎮 め、はやる 心 を 制 すべきかと」(HOMERUS, Ilias, I: 190-2 〔 松 平 千<br />
秋 訳 『イリアス』 上 、 岩 波 文 庫 、1992 年 、20 頁 〕)と 考 える。しかしそこに 突 然 戦 女 神 のアテナが 降 りてきて、アキレウ<br />
スが 斬 りかかろうとするのを 止 めるのである(「かく 心 の 中 、 胸 の 内 に 思 いめぐらしつつ、あわや 大 太 刀 の 鞘 を 払 おう<br />
とした 時 、アテネ〔アテナのイオニア 方 言 形 〕が 天 空 から 舞 い 降 りてきた」〔HOMERUS, ibid., I: 193-5 [ 同 上 ]〕)。この<br />
場 面 をどう 解 釈 すべきであるか。 川 島 重 成 は「 現 代 の 小 説 家 なら、アキレウスが 心 の 中 での 葛 藤 を 経 て 主 体 的 にそ<br />
う 決 断 したと 描 くところでしょう。だから、ホメーロスは 現 代 流 の 心 理 描 写 を 知 らないので 神 を 登 場 させざるを 得 なか<br />
ったのだ、つまりアテーネーとはアキレウスにおける 心 理 描 写 の 神 話 的 表 象 にすぎない、と 一 応 説 明 できそうです」<br />
( 川 島 『『イーリアス』 ギリシア 英 雄 叙 事 詩 の 世 界 』〔 前 掲 〕、66 頁 )と 書 いている。 川 島 はアテナの 表 象 を「 葛 藤 」とし<br />
て 心 理 学 的 に 理 解 しているが、 私 としてはむしろ「 決 断 」のほうに 重 点 を 置 きたい。 実 際 、『イリアス』のこの 場 面 ほど、<br />
意 志 の 経 験 の 適 切 な 描 写 はないのではないだろうか。 決 断 は、 固 有 の 自 己 からなされるのであるが、それは 知 性 や<br />
思 考 とは 切 り 離 されたものとしてなされるので、あたかも 外 から 到 来 したかのように 経 験 されるのである。アキレウスが<br />
迷 っているあいだは、「 心 の 中 、 胸 の 内 」というようにそれがアキレウスの 内 面 的 経 験 のように 描 写 されるが、 決 断 の<br />
瞬 間 は「 降 りてくるアテナ」として、 絶 対 に 固 有 の 決 断 であるがゆえに 外 的 に 到 来 するものであるかのごとく 表 現 され<br />
るのだ。<br />
101
ゾ ル ゲ<br />
アーレントはハイデガーの 関 心 が 意 志 に 似 ていることを 指 摘 しているが、そもそもこのような 未 来 優<br />
、、、、、、、、、、、<br />
位 の 時 間 了 解 を 発 見 したのはハイデガーの 功 績 と 言 っていいだろう。「 根 源 的 本 来 的 時 間 性 の 第<br />
、、、、、、 、、 、、、、、<br />
一 義 的 現 象 は、 将 来 〔Zukunft〕なのである」 384 というハイデガーの 言 明 は、 本 来 的 自 己 は 未 来 に 属<br />
し、 現 在 や 過 去 はむしろそこから 了 解 されることを 意 味 している。つまり、 時 間 は 未 来 から 出 来 する。<br />
デリダ 風 に 表 現 すると、 時 間 は 脱 構 築 的 な 構 造 をもち、 過 去 は、 未 来 からその 意 味 付 けを 受 ける 前<br />
未 来 ( 未 来 完 了 )futur antérieur 的 なものとなる 385 。 過 去 や 現 在 の 意 味 は、 未 来 に 属 する 本 来 的 な<br />
自 己 によって 意 味 づけられるのであるから、 不 断 に 無 規 定 的 であり 続 けるのだ。アーレントは 初 期<br />
ヘーゲルの 読 解 386 をしつつ、 次 のように 述 べている。<br />
精 神 は、 未 来 のための 精 神 の 器 官 である 意 志 の 力 によってのみ、 時 間 を 創 造 するのであり、こ<br />
うした 点 からすれば、 未 来 がまた 過 去 の 源 泉 なのである。つまり、 過 去 は、 精 神 が 第 二 の 未 来<br />
を 予 知 することによって 精 神 的 に 生 じるのであり、この 第 二 の 未 来 から 見 ると、 直 接 的 な「 私 は<br />
=ある=だろう〔I-shall-be〕」が「 私 は=あった=ことになっているだろう〔I-shall-have-been〕」に、<br />
なってしまっているであろう〔will have been〕。こうした 構 図 からすれば、 過 去 は 未 来 によって 産<br />
出 される。 387<br />
意 志 は 未 来 から 時 間 を 了 解 することで、 未 来 から 現 在 、 過 去 へと 時 間 を 出 来 させる( 未 来 → 現 在 →<br />
過 去 )。ようするに、アーレントの 意 志 の 持 つ 時 間 了 解 は、ハイデガーの 言 う 本 来 的 時 間 性 と 等 しい<br />
のである。 意 志 の 時 間 性 は、まだないもの not yet に 関 わる、 未 来 優 位 的 なものである。<br />
そして 意 志 は 活 動 に 先 立 ち、その 地 盤 を 提 供 するものであった。 活 動 自 体 もまた、 絶 対 的 に 新 し<br />
いことをはじめる 能 力 であり、 意 志 が 精 神 の 領 域 でのみ 新 しいことを 意 志 するのに 対 して、 現 象 界<br />
でその 内 容 を 現 実 化 させようとする。その 意 味 で 意 志 の 活 動 力 そのものは 活 動 の 遂 行 においてそ<br />
の 役 目 を 終 え、 消 滅 する。 活 動 は「 私 は= 出 来 る I-can」ということに 関 わる 活 動 力 であり、 意 志 がな<br />
んでも 意 志 することが 可 能 であったのに 対 して、 活 動 は 必 ずしもなんでも「 出 来 る」わけではない。<br />
すでに 第 五 章 で 見 てきたように、 複 数 者 が 生 じさせる 権 力 power がなければ、 人 間 は 事 業 を 実 現<br />
することはできない。とはいえやはり 活 動 もまた 未 来 優 位 の 時 間 了 解 に 立 っており、その 点 が 仕 事<br />
= 制 作 の 活 動 力 との 根 本 的 な 差 異 をなしていた。つまり 意 志 と 活 動 は、 未 来 を 優 位 に 捉 える 点 で<br />
は 共 通 しているのだ。<br />
384 HEIDEGGER, Sein und Zeit (Ebenda), S.329. ( 前 掲 訳 書 、 下 、220 頁 。)<br />
385 ゲルハルト・リヒターによれば、デリダにおける 記 憶 の 意 味 は、 時 間 の 脱 構 築 的 な 構 造 に 関 わる。デリダにとって<br />
現 在 の 行 為 は、 未 来 の 承 認 を 待 つ「 約 束 promise」という 意 味 を 持 ち、その 約 束 が 第 一 の 肯 定 yes である。しかしそ<br />
の 行 為 の 意 味 が 最 終 的 に 承 認 legitimate されたり、 制 裁 sanction されたりしてその 意 味 を 本 当 に 明 らかにするのは、<br />
未 来 における 第 二 の 肯 定 においてなのである。 記 憶 は、 第 一 の 肯 定 を、 第 二 の 肯 定 まで 覚 えておくために 機 能 す<br />
る。つまり 記 憶 は 根 本 的 に 前 未 来 的 な 時 間 了 解 を 前 提 としているのだ(RICHTER, “Acts of Memory and Mourning:<br />
Derrida and the Fictions of Anteriority” [op.cit.].)。<br />
386 アーレントは、アレクサンドル・コイレによるヘーゲルの 時 間 論 の 研 究 (『イエナのヘーゲル』)に 依 拠 しつつ、ヘ<br />
ーゲルがハイデガー 的 な 未 来 優 位 の 時 間 論 を 既 に 発 見 していたということに 賛 意 を 示 している(ARENDT, op.cit.<br />
chap.6 〔 前 掲 書 、 第 6 章 〕)。ヘーゲルの 未 来 優 位 の 時 間 論 は「 進 歩 」の 観 念 に 繋 がるが、それは 結 局 「 体 系 system」<br />
という 観 念 と 齟 齬 をきたし、 矛 盾 は 結 局 解 決 されないままとなる。<br />
387 ARENDT, ibid., p.43. ( 同 上 、53 頁 。)<br />
102
このような、 人 間 に 与 えられた「 始 める」ための 能 力 は、 伝 統 的 な 神 学 が「 創 造 creation」として 理<br />
解 してきたものに 似 る(そのことが、 神 学 や 哲 学 における 意 志 への 不 信 にもつながった)。まったく<br />
新 しい 一 連 の 行 為 の 過 程 を 始 める 自 発 性 の 能 力 は、ちょうど 小 さな 創 造 の 行 為 に 見 える。だがそ<br />
れは 宇 宙 をすべて 作 りかえるような 創 造 の 行 為 ではない。 因 果 性 から 自 由 に、しかも 新 たな 因 果 性<br />
の 系 列 を 生 むと 言 う 点 で、 創 造 的 なのだ。アーレントはアウグスティヌスが 世 界 の 始 まりとしての<br />
principium と 人 間 的 始 まりとしての initium を 区 別 した 点 に 注 目 している。 人 間 は principium を 生 み<br />
出 すことができるわけではない。しかし、 自 発 的 に、 因 果 性 から 自 由 に 新 たな 活 動 を 始 めるための<br />
initium を 生 み 出 すことはできる。ベルクソンは 意 識 存 在 ( 生 命 )が 創 造 的 な 契 機 をもつこと、つまり<br />
因 果 法 則 とは 関 係 ない 営 みをするということを 強 調 した。だからこそ、 現 実 が 可 能 性 によって 先 取 り<br />
されていることにベルクソンは 反 対 するのである。 可 能 性 とはむしろ 創 造 によって 突 然 出 来 した 現<br />
実 のほうから、 遡 及 的 に 過 去 にあったものとして 想 定 される、 前 未 来 時 制 のものなのだ。ベルクソン<br />
風 の 創 造 という 言 葉 を、 人 間 の 意 志 と 活 動 の 営 みにも 転 用 することが 許 されるならば、 古 い「 連 続<br />
創 造 continual creation」 388 という 仮 説 が、 俄 然 真 実 味 を 増 すと 考 えられないだろうか。 人 間 は 意 志 と<br />
活 動 において 新 しいことの 創 造 者 である。もちろん、 全 能 でなんでも 創 造 できるわけではなく、あた<br />
らしく 宇 宙 を 作 ることができるわけではない。しかし、 人 間 の 意 志 と 活 動 が 新 しいことを 次 々と 始 めて<br />
いることによって、 人 間 の 世 界 は 維 持 され、 更 新 される。 反 対 に 新 しいことが 始 められることがなくな<br />
ったとき、 人 間 の 世 界 はなくなる。 人 間 の 世 界 は「 人 間 的 連 続 創 造 human continual creation」によ<br />
って、はじめて 維 持 される。そのように 考 えると、 連 続 創 造 という 説 は、むしろ 人 間 的 世 界 、 人 間 的<br />
営 為 ――つまりアーレントの 言 う 政 治 ――を 了 解 するための 理 論 を 提 供 する 可 能 性 があるように 考<br />
モ ー ド<br />
えられる。 連 続 創 造 とは、 人 間 の 存 在 の 様 態 なのだ。<br />
しかし、ここで 問 題 が 生 ずる。 意 志 と 活 動 とは 全 く 自 由 であるために、そしてそれらが 為 すことは<br />
これまでになく 現 在 もない、 決 して 現 前 したことのないものであるために、それらが 正 しい/ 正 しくな<br />
いといった 判 断 judge を 下 すことが 著 しく 困 難 なのである。それが「 正 しい」とか「 正 義 にかなう」とか<br />
を 決 めるのは 知 性 には 難 しい。なぜなら「 正 しさ」そのものが 未 来 から 到 来 するために、それを 帰 納<br />
的 に 理 解 するためのカテゴリーなど、 知 性 には 備 わっていないからだ。むしろそれは 直 接 、 突 然 目<br />
の 前 に 現 われ、これまでのカテゴリーや 了 解 の 標 準 などを 全 て 更 新 してしまうような 新 しさを 備 えて<br />
いるのである。だから 残 された 問 題 は 判 断 の 問 題 ということになる。 出 生 natality という 事 実 性 によっ<br />
388<br />
連 続 創 造 説 theory of continual creation は、とくにデカルトやマルブランシュに 見 られるとされる。「デカルトにお<br />
いては、 時 間 の 瞬 間 は 相 互 に 独 立 しており、 瞬 間 はそのつどの 創 造 であると 考 えられている」(LÉVINAS, 西 谷 修 訳<br />
『 実 存 から 実 存 者 へ』〔 前 掲 〕、68 頁 、 訳 注 2)。デカルトによれば「 私 の 一 生 の 全 時 間 は、 無 数 の 部 分 に 分 割 される<br />
ことができ、しかもおのおのの 部 分 は 残 りの 部 分 にいささかも 依 存 しないのであるから、 私 がすぐまえに 存 在 したとい<br />
うことから、いま 私 が 存 在 しなくてはならないということは 帰 結 しない。そのためには、ある 原 因 が 私 をこの 瞬 間 にいわ<br />
ばもう 一 度 創 造 するということ、いいかえれば、 私 を 保 存 するということ、がなければならないのである。/ 実 際 、 時 間<br />
の 本 性 によく 注 意 する 者 にとっては 明 らかなことだが、どんなものも、それが 持 続 するところの 各 瞬 間 において 保 存<br />
されるためには、そのものがまだ 存 在 していなかった 場 合 に 新 しく 創 造 するに 要 したとまったく 同 じだけの 力 とはたら<br />
きを 要 するものなのである。それゆえ、 保 存 と 創 造 とはただ 考 え 方 のうえで 異 なるにすぎない」(DESCARTES, Lené,<br />
井 上 庄 七 / 森 啓 訳 「 省 察 」『 世 界 の 名 著 22 デカルト』 中 央 公 論 社 、1967 年 、268-269 頁 )。<br />
103
て「 自 由 たるべく 運 命 づけられている」 我 々が、 起 こった 出 来 事 をどう 判 断 することができるのか、と<br />
いう 難 題 がたちあがるのだ。<br />
補 論 決 断 を 巡 る 思 考 ――シュミット<br />
カール・レーヴィットは、 法 学 者 カール・シュミットの 思 想 について、ハイデガーの 覚 悟 性 の 思 想 と<br />
の 類 似 点 を 指 摘 しつつ、「 機 会 原 因 論 的 決 定 主 義 」と 呼 んでいる 389 。また、 同 様 の 着 想 に 導 かれた<br />
大 部 の 研 究 として、クリスティアン・グラーフ・フォン・クロコウの『 決 断 』 390 がある(ただし、ここではクロ<br />
コウの 理 論 は 扱 えない)。クロコウも、レーヴィット 同 様 、ハイデガーとシュミット(そしてユンガー391 )<br />
の 思 想 の 類 縁 性 を 指 摘 しているのだ。 前 節 から 明 らかなように、 決 定 や 決 断 と 呼 ばれているものを<br />
巡 る 一 連 の 議 論 は、アーレントの 意 志 の 哲 学 に 接 近 する 上 で、 参 考 になる。つまり、 我 々はここで<br />
アーレントの 意 志 論 にある 決 断 主 義 的 な 側 面 を 見 出 そうと 試 みている、と 言 い 換 えることも 出 来 るか<br />
もしれない。(このことは、アーレントがシュミットを 読 んで、その 影 響 下 において 思 想 を 構 築 した、と<br />
いうことを 意 味 しない。もちろん 同 時 に、シュミットを 読 んでいないということも 意 味 しない。 反 対 に、<br />
むしろアーレントはたぶんシュミットを 読 んでいただろうと 思 われる。アーレントは、それでもやはり、<br />
シュミットの 影 響 を 受 けて 思 想 を 構 築 したようには 思 えない〔その 点 について 深 入 りはしないが〕。 以<br />
下 で、アーレントより 以 前 に 主 著 の 多 くを 書 いているシュミットを、〔ハイデガーやヤスパースとの 間<br />
でのような〕 影 響 関 係 ではなく、 或 る 種 の 同 時 代 的 現 象 として 扱 っているのは、そのためである。)<br />
シュミットは『 政 治 神 学 』において、 主 権 者 の 定 義 を 以 下 のように 下 している。<br />
主 権 者 とは、 例 外 状 況 にかんして 決 定 をくだす 者 をいう。 392<br />
このシンプルな 定 義 に、 決 定 を 巡 る 問 題 が 十 全 に 含 みこまれているので、 以 下 はしばらくこの 一 文<br />
の 解 釈 を 拡 げることになろう。シュミットによれば、「 例 外 状 況 にかんする 決 定 こそが、すぐれた 意 味<br />
において、 決 定 なのである。なぜなら、 平 時 の 現 行 法 規 があらわしているような 一 般 的 規 範 では、<br />
絶 対 的 例 外 はけっして 把 握 しえず、したがってまた、 真 の 例 外 事 例 が 存 在 しているという 決 定 は、<br />
完 全 には 根 拠 づけられないからである」 393 。この 言 葉 に 従 えば、 例 外 状 況 における 決 定 以 外 は、 実<br />
は 決 定 ではない、 少 なくとも 本 来 的 な 決 定 ではないということになる。それでは、その 例 外 状 況 とは<br />
何 か。<br />
、、、、、、、、、、、、、、、<br />
例 外 事 例 すなわち 現 行 法 規 に 規 定 されていない 事 柄 は、せいぜいのところ、 極 度 の 急 迫 、 国<br />
家 の 存 立 の 危 急 などとあらわされうるにとどまり、 事 実 に 即 して 規 定 されることはない。〔 略 〕い<br />
389 LÖWITH, Karl, 田 中 浩 / 原 田 武 雄 訳 「カール・シュミットの 機 会 原 因 論 的 決 定 主 義 」C.シュミット、 田 中 浩 / 原 田<br />
武 雄 訳 『 政 治 神 学 』 未 来 社 、1971 年 、89-163 頁 。<br />
390 VON KROCKOW, Christian Graf, 高 田 珠 樹 訳 『 決 断 ユンガー、シュミット、ハイデガー』 柏 書 房 、1999 年 。<br />
391 ちなみに、LÖWITH, 前 掲 論 文 の 冒 頭 エピグラムは、ユンガーの 引 用 である。レーヴィットは VON KROCKOW, 前<br />
掲 書 について、 同 論 文 のなかで 言 及 している(145 頁 、 注 85)。<br />
392 SCHMITT, Carl, 田 中 浩 / 原 田 武 雄 訳 『 政 治 神 学 』 未 来 社 、1971 年 、11 頁 。<br />
393<br />
同 上 。<br />
104
かなるばあいにも 急 迫 事 態 が 存 在 するといえるかを 推 定 可 能 な 明 白 さで 挙 示 することもできな<br />
ければ、またもし、 現 実 に 極 度 の 急 迫 事 態 となり、その 除 去 が 問 題 とされるばあい、このような<br />
事 態 で、なにを 行 なうことが 許 されるのかを、 内 容 的 に 列 挙 することもできない。 権 限 の 前 提 も<br />
、、、、、、、<br />
内 容 も、ここでは 必 然 的 に 無 規 定 のままなのである。〔 傍 点 は 橋 爪 〕 394<br />
例 外 事 例 は、 現 行 法 規 の 一 般 的 規 範 には 規 定 されていない。つまり 言 説 的 な 法 では 記 述 しつくせ<br />
ない 過 剰 、いわば「 法 の 外 」を 表 現 している。 法 は、 現 実 のすべてを 汲 み 尽 くすことはできない。 法<br />
そのものはその 外 部 の 存 在 なしには 存 在 しえない。 法 の「 外 部 の 存 在 」といったが、 法 だけが「 存 在 」<br />
であるとすれば、 法 の 外 部 は「 存 在 しない」、つまり「 非 存 在 」であり、「 無 」である。とにかく、「 例 外 と<br />
は、 推 定 不 可 能 なものである。それは、 一 般 的 把 握 の 枠 外 にでる」 395 。 例 外 とは、「 例 外 である」とい<br />
うことの 他 に 積 極 的 positive な 規 定 をなにも 持 たない。それは 実 定 的 positive な 法 規 定 を 作 ることを<br />
、、、、<br />
とおして形 成 される 否 定 的 negative な 法 の 外 部 である。つまり 例 外 とは、「 一 般 的 把 握 」、さらにいえ<br />
ば「 把 握 一 般 」をとおして 把 握 しえないものである。「 把 握 しえない」ことこそが 例 外 状 態 の「 本 質 」で<br />
ある。それゆえ「 緊 急 事 態 に 対 する 合 理 主 義 的 無 視 」 396 が 生 じるのであるし、「 例 外 はなにひとつ 証<br />
明 しないのであって、 常 態 こそが 科 学 的 関 心 の 対 象 でありうる、とのべるならば、それは 合 理 主 義<br />
者 として 論 理 一 貫 しているといえよう」 397 。( 概 念 的 に 把 握 しえないのだから、 実 存 的 存 在 は 存 在 し<br />
、、<br />
ないと、 悟 性 主 義 的 な 言 説 は 述 べるであろう――そのように 実 存 主 義 的 に 言 い 換 えてもよい。)<br />
このような 例 外 状 況 において、 主 権 者 が 決 定 を 下 すことの 内 実 とは、どういったものであろうか。<br />
この 主 権 者 は、 現 に 極 度 の 急 迫 状 態 であるかいなかを 決 定 すると 同 時 に、これを 除 去 するた<br />
めになにをなすべきかをも 決 定 するのである。 主 権 者 は、 平 時 の 現 行 法 秩 序 の 外 に 立 ちなが<br />
ら、しかも 憲 法 が 一 喝 停 止 されうるかいなかを 決 定 する 権 限 をもつがゆえに、 現 行 法 秩 序 の 内<br />
にある。 398<br />
例 外 状 態 は「 法 の 外 」であるがゆえに、そもそも 或 る 状 態 が「 例 外 」であるか 否 かすら、「 法 的 に」は<br />
決 定 できない。さらに、 主 権 者 は、ある 状 態 が「 法 外 」な 状 態 であると 判 断 した 場 合 、それに 対 処 す<br />
、、、、<br />
るために 法 を 停 止 できる。「 現 行 法 を 廃 棄 する 権 限 が、まさに 主 権 の 本 来 の 識 別 徴 標 なのであ」 399<br />
る。このように 法 が 停 止 している 以 上 は、 主 権 者 はその 決 定 ないし 決 断 にさいして、いかなる 準 拠<br />
、、、、、、、、、、、、、<br />
枠 も 持 たない。 主 権 者 は、いわば 決 定 にのみ 従 って 決 定 を 下 す(この 文 章 は 常 識 的 な 時 間 観 念 か<br />
らすれば 矛 盾 するが)。<br />
394<br />
395<br />
396<br />
397<br />
398<br />
399<br />
同 上 、12-13 頁 。<br />
同 上 、20 頁 。<br />
同 上 、22 頁 。<br />
同 上 。<br />
同 上 、13 頁 。<br />
同 上 、15-16 頁 。<br />
105
決 定 の 理 念 としては、およそ 絶 対 的 に 宣 言 的 な 決 定 は 存 在 しえない、ということがある。 基 礎 と<br />
なる 規 範 の 内 容 からみるならば、〔 略 〕 本 質 規 定 的 ・ 特 殊 的 な 決 定 契 機 は、 新 しい 異 質 なもの<br />
、、、、、、 、、、 、、、、、、、、、、、、<br />
である。 規 範 的 にみて、 決 定 は、 無 から 生 じているのである。 決 定 の 法 的 効 力 は、 論 証 の 結 果<br />
とは 別 のものである。 規 範 の 採 用 がみこまれるのではなく、 逆 に、 帰 属 点 からして、なにが 規 範<br />
であり、なにが 規 範 的 正 当 性 であるかが 定 まるのである。〔 傍 点 は 橋 爪 〕 400<br />
「 決 定 は、 無 から 生 じている」! 「 規 範 的 にみて」ということは、けだし、 知 性 的 かつ 言 説 的 な 了 解<br />
においては、ということである。 知 性 や 言 説 なるものは、およそ 因 果 を 結 びつけることによって、 現 象<br />
の 意 味 を 理 解 しようとする。ところが、 決 定 としての 決 定 である 主 権 者 の 決 定 は、それが 準 拠 を 一 切<br />
持 たないがゆえに、そういった 因 果 的 な 了 解 様 式 では、 意 味 を 理 解 できない。このような「 無 カラノ<br />
ex nihilo」 決 定 は、それゆえ、 論 証 の 結 果 でもあり 得 ない。 論 証 は 既 存 の 法 秩 序 や 知 性 的 了 解 に<br />
従 っているものであり、それは 例 外 状 況 には 対 応 できない。そうではなくて、「 決 定 はたちまち、 論<br />
証 から 独 立 のものとなり、 独 立 の 価 値 をもつにいたる」 401 。シュミットは、「まさにきわめて 重 大 なこと<br />
がらにあっては、 決 定 されるということが、いかに 決 定 されるかよりも 重 要 なのであるから、 決 定 それ<br />
自 体 が 価 値 をもつのだ」 402 とまで 述 べる。むしろ 決 定 は、その 論 証 から 独 立 の 位 置 において、 法 や<br />
論 証 の 源 泉 となるような「はじまり」なのである 403 。<br />
レーヴィットによれば、シュミットがこのような「 決 定 主 義 」を 掲 げるのは、 政 治 的 ロマン 主 義 とシュミ<br />
ット 自 身 が 呼 ぶものに 対 する、 反 論 の 意 味 を 込 めてであるという。ロマン 主 義 の 政 治 とは、「 命 令 な<br />
いし 明 白 な 断 言 ではなく、『 永 遠 の 対 話 』であって、きまった 始 まりも 目 標 もなく、その 時 々に 刺 激 と<br />
なる 論 調 」であり、「あらゆる 範 疇 をごっちゃにする」 404 。だから「 一 義 的 な 区 別 や 決 定 をし、 明 白 な<br />
断 定 をすることができ」ず、「えせ 政 治 的 であるにすぎない」 405 。しかし、シュミットの 考 えでは、「いか<br />
なる 時 代 であれ、 決 然 たる 人 びとが 人 間 的 事 象 の 運 行 を 規 定 するものであるから、このことは、ロマ<br />
、、<br />
ン 主 義 の、 実 質 を 欠 いた 優 柔 不 断 さにとって、かれらが 意 志 に 反 して 他 者 の 決 定 に 奉 仕 するという<br />
400<br />
同 上 、44 頁 。<br />
401<br />
同 上 。<br />
402<br />
同 上 、72 頁 。<br />
ネチェシタ<br />
403<br />
今 村 仁 司 によれば、マキャベリの「 必 然 necessità」の 概 念 は「たんなる『 必 要 性 ・ 必 然 性 』のことではない」(『ベン<br />
ヤミン「 歴 史 哲 学 テーゼ」 精 読 』 岩 波 現 代 文 庫 、 2000 年 、119 頁 )。それはまさにシュミット 的 な 例 外 状 態<br />
Ausnahmezustand であり、ネチェシタにおいては「 正 常 な 流 れは 中 断 され、 伝 統 的 価 値 のいっさいが 宙 づりにされる。<br />
しかしまだあたらしい 価 値 は 創 造 されていない。それは 中 間 の 期 間 であり、 権 力 論 的 には『 空 位 期 』である」( 同 上 )。<br />
このネチェシタにおいて、ヴィルトゥ virtù――つまり、ギリシア 語 のアレテーであり、 徳 とか 卓 越 性 と 呼 ぶべき 力 のこと<br />
だが――をもつ 君 主 が「 導 くもの」として 現 われる。「この 君 主 自 身 もまた、いっさいの 伝 統 から 解 放 されている 異 端<br />
児 であり、アウトローであ」る( 同 上 )。「このような 君 主 だけが 緊 急 事 態 〔ネチェシタ〕を 使 いこなし、フォルトゥナ( 幸 運 )<br />
の 女 神 に 恵 まれるなら、この 例 外 状 態 を 乗 り 越 えて、たんに 過 去 を 回 復 するのではなく、 新 しい 権 力 と『 新 しい 国 家 』<br />
〔 略 〕を 創 造 する 見 込 みがある。これが、マキアヴェリの 構 想 であった」( 同 上 、119-120 頁 )。 今 村 の 指 摘 が 正 しいな<br />
らば、マキャベリもまた、「 始 まり」を 巡 る 政 治 的 の 問 題 の、 先 駆 的 な 理 論 家 だったということになる。アーレント 自 身 マ<br />
キャベリには 思 い 入 れを 示 しているが、そのことも 納 得 できるが、マキャベリの 例 外 状 態 の 理 論 を 扱 うことは 私 の 手 に<br />
は 負 えないので、ここではこれ 以 上 深 入 りしない。なお、マキャベリにおけるネチェシタ 概 念 の 重 要 性 を 教 えてくれ<br />
たのは、 阿 部 嵩 彦 氏 である。ここに 記 して 感 謝 を 示 したい。<br />
404 LÖWITH, 前 掲 論 文 、99 頁 。<br />
405<br />
同 上 。<br />
106
意 味 をもつ」 406 。それゆえ、レーヴィットによれば、シュミットはロマン 主 義 を「 機 会 原 因 論 的 」――つ<br />
まり 偶 然 的 な 原 因 にしたがっているのみの 偶 因 論 的 態 度 ――として 批 判 する。<br />
だが、レーヴィットは、シュミットの 決 定 主 義 こそ 機 会 原 因 論 的 であるとして 論 難 を 加 える。という<br />
のも、「シュミットの 無 信 仰 的 決 定 主 義 のばあいは、 前 世 紀 にみられる 神 学 的 ・ 形 而 上 的 、さらには<br />
また 人 道 主 義 的 ― 道 徳 的 諸 前 提 が 欠 けているのだから、 機 会 原 因 的 なものとならざるをえないの<br />
である」 407 。シュミットは、『 政 治 神 学 』において、ドゥ・メーストルやドノソ・コルテスといった、 反 革 命<br />
的 なカトリック 神 学 者 に 依 拠 しつつ、 決 断 や 決 定 の 重 要 性 を 説 くのであるが、レーヴィットは、シュミ<br />
ットには 彼 らにあったような「 基 準 となる 中 心 領 域 」や「 神 学 的 基 盤 」すら 欠 いていると 主 張 する。そ<br />
のために、「かれの、それ 自 体 以 外 のなにものにも 依 拠 せぬが 故 に 宙 に 浮 いた 決 定 は、『 接 続 する<br />
もの』を、いかなる 大 きな 政 治 運 動 においても、『 瞬 間 瞬 間 を 切 り 離 す』ために 逸 してしま」 4<strong>08</strong> う。だ<br />
からシュミットの 主 権 的 決 定 の 政 治 学 「の 内 容 をなすものは、その 時 々の 政 治 状 況 という 偶 然 的 な<br />
誘 因 からのみでてくるものなのであ」 409 ることになる。その 結 果 として、「 主 権 的 決 定 の 概 念 によって<br />
政 治 的 なものを 規 定 するために、いかなる 中 心 的 事 実 領 域 からも 遊 離 するとするならば、 決 定 の 目<br />
的 として 残 るものは、 論 理 上 ただ、すべての 事 実 領 域 を 超 越 し、それら 領 域 自 体 をあやしげな 存 在<br />
としてしまう 戦 争 でしかない。すなわち 虚 無 への 即 応 、 国 家 〔 略 〕に 生 命 を 捧 げるという 意 味 での、<br />
死 への 即 応 でしかない。 政 治 的 なもののためのシュミットの 決 定 は、 宗 教 的 、 形 而 上 的 ないし 道 徳<br />
的 といった、およそ 精 神 的 な 決 定 のばあいのように、 特 定 の 基 準 となる 事 実 領 域 のための 決 定 なの<br />
、、、、、、<br />
ではなく、なんのためかにはいっさいかかわらず、 果 断 への 決 定 以 外 のなにものでもない」 410 。<br />
レーヴィットはこの「 決 定 のための 決 定 」とでもいうべきものに 関 して、 疑 わしいと 感 ずるのである。<br />
、、<br />
むしろ「 決 定 の 基 準 としての 最 高 機 関 を、すなわち『 神 』や『 人 類 』を」 411 彼 は 求 める。 結 局 は、この<br />
ような「 決 定 としての 決 定 」を 求 める 決 定 主 義 こそが、ナチズムに 通 ずる 破 局 的 思 考 法 であると、レ<br />
ーヴィットは 考 える。「 国 民 社 会 主 義 がかかわるのは、 国 家 的 ・ 社 会 的 なものであるよりはむしろ、い<br />
かなる 論 議 や 強 調 をも 拒 否 し、ただそれ 自 身 のみを、つねに 独 自 の(ドイツ 的 な) 存 在 可 能 のみを<br />
よりどころとする 徹 底 的 な 果 断 および 力 動 性 なのである」 412 。<br />
レーヴィットの 指 摘 は、 確 かにいちいち 当 を 得 ている。 実 際 、 決 定 主 義 や 決 断 は、それが 恣 意 と<br />
ほとんど 区 別 されない 点 に、 大 きな 問 題 を 抱 える。たとえばそれが 個 人 的 な「 実 存 」の 問 題 であれ<br />
ばその 影 響 は 小 さいかもしれないが、 政 治 の 問 題 と 繋 がったとき、 国 家 社 会 主 義 や 全 体 主 義 に 通<br />
じる 危 険 性 は 否 定 できないものである。というのは、 決 断 は「 主 権 者 」がするものであるからだ。 主 権<br />
者 の 行 為 の 正 当 性 は、その 決 断 を 措 いてほかになにも 存 在 しない。もっといえば、それは 伝 統 的 な<br />
価 値 観 や 道 徳 や、 法 秩 序 に 逆 らう 可 能 性 もある。しかもその 内 実 は 論 理 的 に 引 き 出 されるべきもの<br />
ではないから、 実 際 的 には 決 定 主 義 はなにも 言 っていないに 等 しいとも 言 える。「おれは 決 心 した<br />
406<br />
407<br />
4<strong>08</strong><br />
409<br />
410<br />
411<br />
412<br />
同 上 。<br />
同 上 、105 頁 。<br />
同 上 。<br />
同 上 、105-106 頁 。<br />
同 上 、112 頁 。<br />
同 上 、140 頁 。<br />
同 上 、155 頁 。<br />
107
ぞ――なにをかはわからんが」 413 。おそらくアーレントも、このような 決 断 主 義 を 全 面 化 することは 認<br />
めない。アーレントの 政 治 の 考 えは、むしろシュミットの 批 判 する「 政 治 的 ロマン 主 義 」に 近 いものが<br />
ある。 複 数 者 の 不 断 のコミュニケーションとでも 呼 ぶべきものが、アーレントの 活 動 概 念 の 根 柢 には<br />
ある。シュミットが「 決 断 はそれ 自 身 のゆえに 肯 定 される」と 言 うとすれば、アーレントは「 政 治 (つまり<br />
複 数 者 の 対 話 )はそれ 自 身 のゆえに 肯 定 される」と 言 うであろう。<br />
しかし、 我 々はレーヴィットの 主 張 にも 問 題 点 を 見 出 すことができる。 彼 はマルクスやキルケゴー<br />
ル、さらにはドノソ・コルテスらを、 彼 らが 決 断 における 基 礎 をもっているという 点 において、シュミット<br />
よりは 内 実 をもっていると 評 価 する。しかし、それは 彼 らのその 決 断 の 基 礎 が、なんらかのかたちで<br />
先 行 把 握 Vorgriff されている 前 提 でなければならないと 言 うことにならないだろうか。いいかえれば、<br />
「 神 」や「 人 類 」といった 理 念 に 正 当 性 を 与 える 根 拠 は、どのようにして 引 き 出 しうるのだろうか シ<br />
ュミットの 例 外 状 態 という 規 定 は、ある 意 味 体 系 的 思 考 の 必 然 的 な 帰 結 なのである。つまり、 根 拠 を<br />
辿 っていく 過 程 であるときそれ 以 上 遡 及 しえないような 限 界 に 突 き 当 たるというのがそれである。こ<br />
の「 始 まり」の 難 問 に 直 面 した 時 、シュミットのように 例 外 を 設 けるのは、むしろ 論 理 の 必 然 的 要 請 に<br />
従 ってのことであると 言 わざるを 得 ない。 例 外 状 況 としての 法 の 停 止 する 場 面 というのは、まったく<br />
ありえないどころか、 法 が 存 在 する 限 り、ないはずがない。レーヴィットの 論 は、このような 局 面 に 対<br />
する 法 学 的 基 礎 を 与 えたシュミットの 功 績 を 見 逃 している。シュミットは、 法 の 外 側 や、 法 の 構 築 場<br />
面 に 目 を 向 けている。だから 彼 は、ケルゼンのように、すべてを 法 や 規 範 の 内 側 で 片 付 けようとする<br />
ものを 批 判 する。パウロが 言 うように、「 全 て 法 が 言 うところのものは、 法 の 内 側 にある 人 々に 語 りか<br />
ける」 414 にすぎないのだから、その 法 そのものを 問 いに 付 すような 契 機 というものこそ、 問 わねばな<br />
らない。(ついでに 述 べておけば、このような 人 間 の 作 った 法 とその 外 部 という 問 題 は、 実 定 法<br />
positive law と 自 然 法 natural law の 問 題 として、 思 考 されていた。)アーレントが 意 志 として 問 題 化 し<br />
たのも、 同 様 の「 始 まり」の 問 題 に 直 面 してのことであったと 考 えられる。<br />
ただ、レーヴィットの 論 が 我 々の 興 味 をひくのは、 彼 がハイデガーとシュミットの 論 の 内 的 連 関 に<br />
注 意 を 向 けている 点 である。 実 際 シュミットの 論 は、 意 志 のパラドクシカルな 働 き 方 に 理 論 を 与 えよ<br />
うというハイデガーの 試 みと、 交 叉 している。それは 実 存 哲 学 の 問 題 系 と 重 なり 合 っており、ヤスパ<br />
ースの 問 題 の 立 て 方 にも、 勿 論 通 じている。つまりそれは、 概 念 や 体 系 というものが、 個 別 的 な 次<br />
元 を 例 外 として、 扱 い 得 ないものとして 放 置 することなしには、 機 能 しないということに 関 わっている。<br />
ハイデガーの 意 志 は、 知 性 的 な 了 解 や、 世 界 内 存 在 ・ 共 同 存 在 への 頽 落 から 離 れた「 不 気 味 な<br />
unheimlich」 不 安 において、ただ 良 心 の 呼 び 声 を 聞 くことを 通 して 実 存 を 決 意 する 覚 悟 性 であった。<br />
ヤスパースにおいても、 可 能 的 実 存 である 人 間 存 在 は、みずからの 現 存 在 (つまり 知 性 的 に 了 解<br />
可 能 な 世 界 を 生 きる 存 在 者 )における 不 満 から、 飛 躍 を 経 て 実 存 へと 至 ろうと 決 断 するのである。<br />
つまり 両 者 もともに、 意 志 は 知 性 や 悟 性 や 概 念 的 ・ 言 説 的 了 解 が 停 止 した 場 所 で 決 断 するのだ。<br />
413<br />
同 上 、150 頁 。<br />
414 “ὅσα ὁ νόμος λέγει τοῖς ἐν τῷ νόμῳ λαλεῖ” (「ローマの 信 徒 への 手 紙 」3:19 〔NESTLE-ALAND, Novum<br />
Testamentum Graece, 26.Aufl. Nördlingen: Gesamtherstellung C. H. Beck, 1979, S.414.〕)。 文 脈 からある 程 度 自 由<br />
に 引 用 したので、ここではギリシア 語 原 文 から 直 接 訳 した。なかでも νόμος という 語 は、 普 通 キリスト 教 的 文 脈 の 中 で<br />
は「 律 法 」と 訳 される。 参 考 までに 新 共 同 訳 の 同 箇 所 を 挙 げておくと、「すべて 律 法 の 言 うところは、 律 法 の 下 にいる<br />
1<strong>08</strong>
それはシュミットの 主 権 者 が、 法 の 停 止 したところでなににも 依 拠 することなく 決 断 するのに 似 てい<br />
る。<br />
人 々に 向 けられています」( 新 共 同 訳 『 新 約 聖 書 詩 編 つき』 日 本 聖 書 協 会 、1989 年 )。<br />
109
第 八 章 判 断 judging の 時 間 性<br />
またほかの 場 所 では 多 数 の 人 間 が 集 会 場 に 集 まっている。<br />
ここでは 係 争 が 起 っており、 殺 された 男 の 補 償 をめぐって、<br />
二 人 の 男 が 言 い 争 っている。 一 方 は、 町 の 人 々にも 事 情<br />
を 説 明 して 償 いはすべて 支 払 い 済 みであると 公 言 するの<br />
に 対 して、 他 方 は 何 も 受 け 取 っておらぬという。 双 方 は 仲<br />
裁 者 の 裁 定 を 望 み、 民 衆 はそれぞれの 側 に 味 方 し、 二 派<br />
に 分 れて 声 援 を 送 り、 触 れ 役 たちが 出 て 制 止 にかかる。<br />
――ホメロス『イリアス』<br />
過 去 を 歴 史 的 に 関 連 づけることは、それを「もともとあった<br />
とおりに」 認 識 することではない。 危 機 の 瞬 間 にひらめくよう<br />
な 回 想 を 捉 えることである。<br />
――ベンヤミン『 歴 史 哲 学 テーゼ』<br />
第 31 節 観 客 としての 判 断 者<br />
『 精 神 の 生 活 』の 第 二 巻 は、もともと 意 志 と 判 断 の 問 題 が 扱 われる 予 定 であったが、 第 二 巻 は 結<br />
局 意 志 の 問 題 のみで 完 結 し、 判 断 の 問 題 は 第 三 巻 に 持 ちこされた。しかし、アーレントはこの 第 三<br />
巻 の『 判 断 』というタイトルと 二 つのエピグラムだけ 書 いて、 急 逝 してしまった。その 代 わりと 考 えられ<br />
ているのは、1970 年 秋 学 期 の『カント 政 治 哲 学 講 義 』 415 である。しかし 分 量 からいっても『 精 神 の 生<br />
活 』の 第 一 巻 、 第 二 巻 に 比 べ 遥 かに 少 なく、とくに 我 々の 関 心 ―― 時 間 性 ――に 関 する 記 述 は 殆<br />
どない。それゆえ 彼 女 の 判 断 の 理 論 を 問 題 にすることには 自 然 と 困 難 が 付 きまとう。 判 断 を 再 構 成<br />
することがそもそも 難 題 であるのに、その 時 間 性 にまで 踏 み 込 もうというのは、 無 謀 な 試 みかもしれ<br />
ない。しかし、ここでは、『カント 政 治 哲 学 講 義 』や『 精 神 の 生 活 』 第 一 ・ 二 巻 に 含 まれる 判 断 に 関 す<br />
る 記 述 から、 判 断 の 能 力 とその 時 間 経 験 を 可 能 な 限 り 構 成 してみよう。また、そのさい『カント 哲 学<br />
講 義 』に 付 されている 編 者 ロナルド・ベイナーの「 解 釈 的 試 論 」と、ベンヤミン『 歴 史 の 概 念 について<br />
( 歴 史 哲 学 テーゼ)』が 参 考 になる。 前 者 はアーレントの『 判 断 』をまさに 再 構 成 しようという 試 みであ<br />
415 『カント 政 治 哲 学 講 義 』(ARENDT, Hannah, ed. by Ronald BEINER, Lectures on the Kant’s Political Philosophy)の<br />
原 書 を 参 照 することはかなわなかった。ここでは 浜 田 義 文 監 訳 『カント 政 治 哲 学 の 講 義 』 法 政 大 学 出 版 局 、1987 年<br />
および、 仲 正 昌 樹 訳 『 完 訳 カント 政 治 哲 学 講 義 録 』 明 月 堂 書 店 、2009 年 の 両 方 を 参 照 している。 敢 えて 二 つ 参 照<br />
したのは、 一 つには 原 書 を 参 照 できなかったことを、 二 つの 訳 書 を 参 照 することで 多 少 なりとも 補 おうと 考 えたため<br />
である。 実 際 、 原 語 を 表 示 している 箇 所 が 異 なったりするので、これは 読 解 に 資 した。より 実 際 的 な 理 由 として、 私 は<br />
仲 正 訳 で 通 読 したのだが、 仲 正 訳 はです・ます 調 で 訳 されていて、 引 用 に 際 して 本 稿 の 文 体 に 合 わないので、 浜<br />
田 監 訳 のほうから 採 った。 以 下 では 基 本 的 に 引 用 は 浜 田 監 訳 から 行 い、 場 合 によっては 仲 正 訳 を 参 照 することにし<br />
ている。<br />
110
り、 後 者 はアーレント 自 身 が 間 違 いなく 読 んでおり 416 、おそらくは 判 断 に 関 する 思 考 を 形 成 する 際<br />
の 隠 れた 参 照 項 になっていると 思 われる。<br />
そのまえに、なぜ 判 断 という 独 特 な 活 動 力 が 求 められるのか、ということについて 振 り 返 っておこ<br />
う。アーレントは『 人 間 の 条 件 』の 時 点 ですでにこの 問 題 に 気 付 きつつあったと 考 えられる。 彼 女 は<br />
「 活 動 を 判 断 できるのは、ただ 偉 大 さという 基 準 だけである。なぜなら、 活 動 は 本 性 上 、 一 般 に 受 け<br />
入 れられていることを 打 ち 破 り、 異 常 なるものに 到 達 するようになるからである。そこでは、 一 般 的 日<br />
ユ ニ ー ク<br />
常 生 活 で 真 実 であるとされるものがもはや 不 適 当 となる。というのは、 存 在 するものはすべて 唯 一 的<br />
ス イ ・ゲ ネリ ス<br />
で、 自 体 的 であるからである」 417 と 述 べていた。 前 章 では 意 志 から 活 動 が 開 始 されることを 確 認 した<br />
が、 意 志 も 活 動 も、 知 性 によっても、 倫 理 によっても、 因 果 によっても 理 解 できないような、それ 自 体<br />
に 原 理 を 含 むような 始 まりとして、 理 解 されていた。ここで 自 発 性 そのものが 難 問 を 生 み 出 す。 活 動<br />
の 正 / 不 正 を 理 解 する 標 準 も 同 時 に 失 われるのだ。 活 動 は 確 かに、その 遂 行 自 体 が 意 味 をもつ<br />
プラクシスないしエネルゲイアとして、 目 的 自 体 として 追 求 されるものであった。それを 我 々は 遂 行<br />
意 味 と 名 づけたが、しかし 人 間 の 活 動 は、 終 わった 後 物 語 として 語 られる、 全 体 意 味 をも 持 ってい<br />
るのだ。『 人 間 の 条 件 』では、 彼 女 はそれを「 偉 大 さ」という 基 準 によって 測 ろうとしていた。 外 的 な 基<br />
準 を 以 っては、 活 動 は 判 断 のしようがないからである 418 。だがその「 偉 大 さ」がどのようにして 決 めら<br />
れるのか、ということは 未 解 決 であった。その 解 決 が、 判 断 の 議 論 に 託 されているのである。<br />
つまり 判 断 の 最 も 基 本 的 な 働 きは、 活 動 や 出 来 事 の 正 / 不 正 を 判 断 することにある。しかしその<br />
際 、 判 断 の 活 動 力 は、 思 考 や 意 志 と 同 様 に、 自 律 的 なものである。つまり、 判 断 は 思 考 にも 意 志 に<br />
も 左 右 されないし、ましてや 知 性 intellect や 認 識 cognition に 含 まれているようなものでもない。つま<br />
り「…は 正 しい/ 正 しくない」ということは、 論 理 的 にきめることもできないし、 思 考 や 意 志 に 合 わせ<br />
て 決 めるものでもない。その 点 はあとで 実 際 の 働 き 方 modus operandi を 見 る 際 に 詳 しく 見 ることに<br />
するが、とにかく 自 律 的 であるということが、 判 断 が 活 動 力 として 認 定 されている 理 由 である。 判 断<br />
は 自 分 で 自 分 の 原 理 を 定 めているのだ。<br />
判 断 する 者 ( 判 定 者 = 裁 判 官 judge) 419 もまた、 思 考 する 自 我 、 意 志 する 自 我 同 様 に 退 きこもり<br />
withdrawal を 経 験 する。だが 判 断 における 退 きこもりは 思 考 や 意 志 において 自 我 が 経 験 するそれ<br />
416 ベイナーによれば、「アーレントの 議 論 に 近 いベンヤミンの『 歴 史 哲 学 テーゼ』を 読 むことによってこそ、 我 々は<br />
最 後 にアーレントの 意 図 の 諸 次 元 を 測 ることを 期 待 できよう」(BEINER, Ronald, 「ハンナ・アーレントの 判 断 作 用 につ<br />
いて」 ARENDT, Hannah, ed. by Ronald BEINER, 浜 田 義 文 監 訳 『カント 政 治 哲 学 の 講 義 』 法 政 大 学 出 版 局 、1987 年 、<br />
236 頁 )。アーレントは、パリにいた 時 期 にベンヤミンと 出 会 っており、かなり 親 しかったようである。アーレント=ブリュ<br />
ッヒャー 夫 妻 はパリからマルセイユに 逃 れる 際 、「ベンヤミンから『 歴 史 哲 学 テーゼ』ほかの 草 稿 を 預 かることになった」<br />
( 村 井 洋 「 解 説 」ARENDT, Hannah, 阿 部 齊 訳 『 暗 い 時 代 の 人 々』ちくま 学 芸 文 庫 、2005 年 、444 頁 )。 夫 妻 は『 歴 史 哲<br />
学 テーゼ』を 実 際 に 声 に 出 して 読 み 上 げ、 内 容 を 吟 味 していたとも 伝 えられる( 岩 崎 稔 先 生 の 御 教 示 による)。アー<br />
レントは『 歴 史 哲 学 テーゼ』を 含 むベンヤミンの 論 文 集 『イルミネーションズ』を 出 版 しており、その 序 文 は『 暗 い 時 代<br />
の 人 々』に 収 録 されている(「ヴァルター・ベンヤミン――1892-1940」『 暗 い 時 代 の 人 々』〔 前 掲 〕、239-322 頁 )。<br />
417 ARENDT, The Human Condition (op.cit.), p.205. ( 前 掲 訳 書 、330 頁 。)<br />
418 パ フ ォーマ ン ス<br />
「 偉 大 さ、あるいは 各 行 為 の 特 殊 な 意 味 は、ただ 行 為 遂 行 そのものの 中 にのみ 存 在 することができ、その 動 機<br />
づけや 結 果 の 中 にはない」(Ibid., p.206. 〔 同 上 、330-331 頁 〕)。<br />
419 ちなみに「 判 断 する 自 我 judging ego」という 表 現 は 見 たところ 出 てこない。アーレントが『 判 断 』を 書 いていたらそ<br />
ういう 言 葉 が 用 いられたかもしれないと 想 像 することも 可 能 であるが、おそらくは 判 断 において 反 省 作 用 が 弱 いこと、<br />
(このあと 見 るように)それがむしろ 共 同 主 観 的 であるということに 由 来 すると 見 る 方 が、 的 確 だと 思 う。<br />
111
とは 異 なる。 思 考 においては、 現 象 界 をはなれ、この 世 界 の「どこにもない」ところへと 退 きこもる。そ<br />
れに 対 して、 判 断 する 者 のモデルは、 劇 場 における 観 客 spectator である。つまり 観 客 が 退 きこもる<br />
「 場 所 は 世 界 の 中 にあるし、その『 高 貴 さ』は、ただ 今 進 行 していることに 関 与 しないでそれをただ<br />
見 せ 場 〔spectacle〕として 眺 めるということにある」 420 。 見 せ 場 を 演 じているのは、 活 動 者 = 俳 優 actor<br />
であり、 彼 らはまさに 活 動 action に 参 与 して、その 役 = 一 部 part を 演 技 action している。「 観 客 とし<br />
てはその 見 せ 場 がなにに 係 っているのか、という『 真 理 』を 理 解 できるかもしれない。しかし、その 代<br />
償 にそれに 関 与 できなくて 退 きこもるのである」 421 。<br />
プレイ<br />
観 客 がなぜ「 高 貴 」かというと、「ただ 観 客 だけが 全 体 の 劇 を 見 ることのできる 位 置 を 占 める」 422 か<br />
らである。「 直 接 巻 き 込 まれないで 退 きこもり、ゲーム〔 略 〕の 外 側 に 立 つことは、 判 断 することの、つ<br />
、、<br />
まり 進 行 している 争 いの 最 終 的 な 判 定 者 であるための 条 件 であるだけでなく、 劇 の 意 味 を 理 解 する<br />
ための 条 件 でもある」( 傍 点 は 橋 爪 ) 423 。 劇 、つまり 起 っている 出 来 事 が、なんの「 意 味 」をもつか――<br />
それは、 活 動 者 には 理 解 されることがなく、 観 客 のみに 理 解 されることなのだ。 全 体 意 味 が「 明 らか<br />
ヒューマン・アフェアーの<br />
になるのは、 活 動 を 通 じてではなくて 観 想 によるのである。 活 動 者 ではなくて 観 客 が 人 間 事 象<br />
意 味 の 鍵 を 担 っている」 424 。たとえば、カントがフランス 革 命 を 世 界 史 的 な 事 件 と 捉 えたのも、 決 し<br />
て 活 動 者 の 立 場 からではなく、 観 客 の 立 場 からなのである。<br />
第 32 節 判 断 と 歴 史<br />
判 断 の 能 力 は「 過 去 を 扱 うための」 425 ものであり、つまり 歴 史 history や 物 語 story と 深 いかかわり<br />
を 持 っている。というより、 歴 史 とは 本 来 判 断 の 能 力 によって 生 み 出 されると 言 ってもよいかもしれな<br />
い。アーレントは 歴 史 と 判 断 との 結 びつきを 示 すために、 再 び 語 源 に 立 ちかえる。 歴 史 history は、<br />
「どうであったかを 伝 えるために 探 究 すること」を 意 味 する 動 詞 ヒストレイン ἱστορεῖν に 由 来 している<br />
426 。しかしこの 動 詞 ヒストレイン 自 体 は 更 にその 語 源 をヒストール ἵστωρ に 持 っており、アーレントは<br />
それを「いわば 歴 史 家 〔historian〕」 427 であると 訳 す。このヒストールという 単 語 はホメロスが 使 ってい<br />
る。<br />
多 数 の 人 間 が 集 会 場 に 集 まっている。ここでは 係 争 が 起 っており、 殺 された 男 の 補 償 をめぐっ<br />
て、 二 人 の 男 が 言 い 争 っている。 一 方 は、 町 の 人 々にも 事 情 を 説 明 して 償 いはすべて 支 払 い<br />
済 みであると 公 言 するのに 対 して、 他 方 は 何 も 受 け 取 っておらぬという。 双 方 は 仲 裁 者<br />
420 ARENDT, The Life of the Mind: One/ Thinking (op.cit.), p.93. ( 前 掲 訳 書 、109-110 頁 。)<br />
421 Ibid. ( 同 上 、110 頁 。)<br />
422 Ibid. ( 同 上 。)<br />
423 Ibid., p.94. ( 同 上 。)<br />
424 Ibid., p.96. ( 前 掲 訳 書 、113 頁 。)<br />
425 Ibid., p.216. ( 前 掲 訳 書 、250 頁 。)<br />
426 Ibid. ( 同 上 。)<br />
427 Ibid. ( 同 上 。)<br />
112
〔ἴστορι〕の 裁 定 を 望 み、 民 衆 はそれぞれの 側 に 味 方 し、 二 派 に 分 れて 声 援 を 送 り、 触 れ 役 た<br />
ちが 出 て 制 止 にかかる。 428<br />
ヒ ス ト リ ア ン<br />
つまりこの「ホメロス 的 な 歴 史 家 は、 判 定 者 〔judge〕である」 429 。 引 用 した『イリアス』の 場 面 を 見 ると 分<br />
かるように、ここでヒストールは、 二 者 のうちどちらの 言 い 分 が 正 しいのかを 判 断 しようとするものであ<br />
る。アーレントはこのような 判 断 者 judge こそが 本 来 の 歴 史 家 であると 考 えているのだ。<br />
判 断 は 歴 史 に 関 わるとしたうえで、アーレントは「ヘーゲルかカントか」という 選 択 肢 を 挙 げる。<br />
「 我 々はヘーゲルと 共 に、『 世 界 史 は 世 界 法 廷 である』(Die Weltgeschichte ist das Weltgericht)と 述<br />
べて、その 究 極 的 判 断 を 成 功 に 委 ねることができる。あるいはカントと 共 に、 人 々の 精 神 の 自 律 を<br />
維 持 し、 今 存 在 する 事 象 〔things as they are〕、 既 に 生 成 してしまった 事 象 〔things as they have come<br />
into being〕からの、 精 神 の 独 立 を 維 持 することもできる」 430 。 一 見 意 味 不 明 なこの 比 較 は、アーレン<br />
トの 引 用 しているカトーの 言 葉 と、ベンヤミンとを 合 わせて 参 照 することで、 理 解 できるようになる。<br />
アーレントが 引 用 しているカトーの 言 葉 は 次 のようなものである。「 勝 者 ノ 大 義 ハ 神 々ヲ 喜 バセタ<br />
、、、<br />
ガ、 敗 者 ノ 大 義 ハカトー ヲ 喜 バセタ Victrix causa deis placuit, sed victa Catoni」 431 。 神 々を 喜 ばせる<br />
のは「 勝 者 の 大 義 」であるというが、これはヘーゲルが 判 断 の 基 準 としている「 成 功 」と 一 致 する。つ<br />
、、、<br />
まり 勝 者 の 大 義 が 喜 ばしい、あるいは 正 しいとするとき、 歴 史 における 人 物 や 試 みの 正 当 性 は、そ<br />
れが「 成 功 したか 否 か」に 関 わることになる。つまり 歴 史 は「 勝 者 の 歴 史 」となるのだ。しかしアーレン<br />
トが 同 意 しているのは、あきらかに「 敗 者 の 大 義 」に 喜 ぶカトーのほうであって、その 大 義 は 勝 敗 と<br />
は 関 わりのない、 自 律 的 な 基 準 による 判 断 に 従 って、 是 とされている。カントを 選 ぶとは、つまり 成<br />
功 や 勝 利 を 判 断 の 基 準 とせずに、 精 神 の 自 律 において 判 断 それ 自 身 の 基 準 に 従 って 判 断 するこ<br />
とを 意 味 する。つまりここでは 勝 敗 に 関 わりなく、その 出 来 事 固 有 の 意 味 において、 出 来 事 が 救 済<br />
される。<br />
ベンヤミンも、 明 らかにカトーとカントに 賛 同 するだろう。『 歴 史 哲 学 テーゼ』の 第 七 テーゼにおい<br />
て、 彼 は 歴 史 主 義 の 歴 史 記 述 者 は「 明 らかに 勝 利 者 に 感 情 移 入 しているのだ」 432 と 述 べている。<br />
いつの 時 代 でも 支 配 者 は、かつての 勝 利 者 たち 全 体 の 遺 産 相 続 人 である。したがって 勝 利 者<br />
への 感 情 移 入 は、いつの 時 代 の 支 配 者 にも、しごくつごうがよい。〔 略 〕こんにちにいたるまで<br />
の 勝 利 者 は 誰 もかれも、いま 地 を 倒 れているひとびとを 踏 みにじってゆく 行 列 、こんにちの 支<br />
428 HOMERUS, Ilias, XVIII: 497-501. ( 前 掲 訳 書 、 下 、218 頁 。)これは、アキレウスの 盾 に 描 かれた 細 工 を 説 明 した<br />
もの(エクフラシス)で、このような 図 柄 が 盾 の 一 部 に 描 かれているのはなぜか、というのも 一 つの 謎 である。<br />
429 ARENDT, op.cit. ( 同 上 。)<br />
430 Ibid. ( 前 掲 訳 書 、249 頁 。)<br />
431 Ibid. ( 前 掲 訳 書 、250 頁 。)なお、 書 かれざる『 精 神 の 生 活 』 第 三 巻 『 判 断 』の 遺 稿 に 掲 げられていた 二 つのエピ<br />
グラムのうち、 一 つがこの 言 葉 である。<br />
432 BENJAMIN, Walter, „Über den Begriff der Geschichte,“ in: ausgewählt und mit einem Nachwort von Alexander<br />
HONOLD, Erzählen: Schriften zur Theorie der Narration und zur literalischen Prosa, Frankfurt a.M.: Suhrkamp<br />
Verlag, S.132. ( 野 村 修 訳 「 歴 史 哲 学 テーゼ( 歴 史 の 概 念 について)」 今 村 仁 司 『ベンヤミン「 歴 史 哲 学 テーゼ」 精 読 』<br />
岩 波 現 代 文 庫 、2000 年 、62 頁 。)<br />
113
配 者 たちの 凱 旋 の 行 列 に 加 わって、 一 緒 に 行 進 する。 行 列 は、 従 来 の 習 慣 を 少 しもたがえず、<br />
戦 利 品 を 引 き 廻 して 歩 く。 戦 利 品 は 文 化 財 と 呼 ばれている。 433<br />
しかし 彼 は「 歴 史 的 唯 物 論 者 」として「できるかぎりこのような 伝 達 から 断 絶 する。かれは、 歴 史 をさ<br />
かなですることを、 自 己 の 課 題 とみなす」 434 。だからベンヤミンは、「 過 去 への『 感 情 移 入 』とか、『あ<br />
るがままの 事 実 』を 主 張 する 実 証 主 義 」 435 に 反 対 する。そういう 姿 勢 の 歴 史 意 識 は、 過 去 の 支 配 者<br />
へ 感 情 移 入 し、そうすることで(その 相 続 人 である) 現 在 の 支 配 者 に 感 情 移 入 する。「それをもって<br />
現 在 の 社 会 をあるがままに 正 当 化 する」 436 (ヘーゲルが 時 にプロイセン 国 家 の 御 用 学 者 であると 見<br />
做 されることが 想 起 される)。<br />
もし 勝 者 の 歴 史 だけが 歴 史 ならば「 歴 史 という 名 の 偽 りの 神 」 437 が 過 去 の 判 断 者 ということになろ<br />
、、、、<br />
う。だが、 歴 史 家 は 過 去 について 判 断 する探 究 者 として「 人 間 の 尊 厳 の 返 還 」 438 を 求 めねばならな<br />
、、、、、<br />
い。 人 間 こそが、 自 律 的 な 判 断 の 能 力 において 過 去 を 判 定 し、 歴 史 を 編 むのだ。それが「 過 去 の<br />
救 済 としての、あるいは 物 語 による 意 味 の 創 造 としての 判 断 力 」 439 なのである。<br />
だが、 歴 史 を 語 りだす 能 力 としての 判 断 の 困 難 は、まさにここから 生 じる。「 勝 者 の 歴 史 」を 描 くこ<br />
とは、「 均 質 で 空 虚 な 時 間 をみたすために、 大 量 の 事 実 を 召 集 する」 440 だけで 済 む。なぜなら 歴 史<br />
の 進 展 そのものが、 放 っておいても 誰 が 正 当 性 を 備 えているかを 教 えてくれるからだ( 歴 史 に 勝 者<br />
が 存 在 する 限 り)。しかし、 歴 史 に 簒 奪 された 判 断 の 権 利 を 回 復 するとき、 人 はなにを 基 準 に 出 来<br />
、、、、<br />
事 や 人 や 試 みの 正 当 性 を 保 証 できるのか 言 い 換 えれば、 判 断 する 者 が 自 律 的 に――つまり<br />
、、、、、、、、、<br />
何 にも 従 うことなく―― 判 断 するとき、 何 にも 従 わないにもかかわらず「 正 しい/ 正 しくない」といっ<br />
たことを 決 めることができるのは――それが 恣 意 によるのでないのなら――、なにに 依 るのか こ<br />
とによると、もしその 判 断 が 恣 意 によるのならば、 歴 史 主 義 や 実 証 主 義 以 上 に 危 険 な 歴 史 観 ( 例 え<br />
ば 歴 史 修 正 主 義 のような)に 落 ち 込 みかねないのではないか これが 判 断 の 難 問 である。<br />
第 33 節 判 断 はどのように 働 くのか―― 趣 味 、 構 想 力 、 共 通 感 覚<br />
過 去 の 出 来 事 の 正 当 性 や 美 しさ、 偉 大 さを 判 定 する 活 動 力 としての 判 断 judging は、 非 常 に 神<br />
秘 的 な 働 き 方 をする。その 神 秘 ――それは 同 時 に 困 難 でもあるが――は、ひとえに 判 断 が 自 律 的<br />
に 判 断 するという 事 実 に 存 する。その 謎 を 解 決 するためにアーレントが 依 拠 したのが、カントである。<br />
以 下 、アーレントのカント 読 解 を 分 析 し、 判 断 の 袋 小 路 を 脱 出 しうる 道 を 追 跡 しよう。<br />
433 Ebenda. ( 同 上 。)<br />
434 Ebenda. ( 同 上 。)<br />
435<br />
今 村 『ベンヤミン「 歴 史 哲 学 テーゼ」 精 読 』( 前 掲 )114 頁 。<br />
436<br />
同 上 、114-115 頁 。<br />
437 ARENDT, op.cit., p.216. ( 同 上 、250 頁 。)<br />
438 Ibid. ( 同 上 。)<br />
439<br />
岩 崎 「 生 産 する 構 想 力 、 救 済 する 構 想 力 」( 前 掲 )180 頁 。<br />
440 BENJAMIN, ebenda, S.138. ( 前 掲 訳 書 、78 頁 。)<br />
114
判 断 は 知 性 には 従 わない。つまり「すべての 人 間 は 死 すべきである、ソクラテスは 人 間 である、ゆ<br />
えにソクラテスは 死 すべきである」というような 論 理 的 操 作 によって 判 断 することはできない 441 。 言 い<br />
かえれば、「なんと 美 しいバラだろう!」と 言 うとき、「すべてのバラは 美 しい、この 花 はバラである、<br />
それゆえこのバラは 美 しい」という 論 理 的 操 作 で 判 断 するわけではない 442 。 判 断 とは、 美 一 般 という<br />
カテゴリーへの 包 摂 や 帰 納 ではない。<br />
ここでヒントとなるのは、 趣 味 taste である。 趣 味 こそは、 判 断 の 基 礎 となる。 趣 味 は 快 / 不 快 を 告<br />
げるものであるが、いくつかの 西 洋 語 では「 味 覚 taste」と 同 じ 語 で 表 現 される 443 。つまり 趣 味 の 基 本<br />
経 験 は 味 覚 の 経 験 において 明 らかになる。 味 覚 は「 全 く 私 的 で 伝 達 不 可 能 な 内 的 感 覚 を 与 える」<br />
444 。また 特 徴 的 なのは、 味 覚 は「 判 別 的 discriminatory」であり、「〈 私 が 快 または 不 快 を 感 じること〉<br />
は 直 接 的 で 抵 抗 することができない」 445 し、「いかなる 思 考 や 反 省 によっても 媒 介 されない」 446 ことで<br />
ある。このような 味 覚 = 趣 味 、つまり 快 / 不 快 は、まったく 私 的 なので 伝 達 不 可 能 である。だからこ<br />
こでは 正 / 不 正 の 議 論 は 起 こり 得 ない 447 。なぜこのような 趣 味 が、 正 / 不 正 を 判 断 する 判 断 力 の<br />
基 礎 になりうるのか その 手 懸 りとなるのが 構 想 力 および 共 通 感 覚 である。<br />
構 想 力 imagination は、 思 考 においても 働 いていた。 感 覚 sense に 対 して 現 前 present していたも<br />
のを、 脱 = 感 覚 化 de-sense し、 精 神 に 扱 いうるイメージとして 加 工 して 再 = 現 前 ( 表 象 )re-present さ<br />
せる 作 用 が、 構 想 力 と 呼 ばれていた。たとえば 視 覚 で 得 た 映 像 は、 精 神 においてイメージとして 再<br />
= 現 前 させることができる。しかし、 味 覚 に 関 しては、 味 そのものを 再 = 現 前 させることはできない。<br />
この 場 合 再 = 現 前 された「 対 象 は、 対 象 についての 直 接 的 知 覚 ではなく、 人 の 快 ・ 不 快 を 刺 激 する」<br />
448 。つまり 味 覚 ならば、 味 そのものが 再 = 現 前 するのではなく、それを 味 わった 時 の 快 / 不 快 のほ<br />
うが、 反 省 において 再 = 現 前 するのだ。<br />
構 想 力 によって、 感 覚 の 対 象 そのものは 消 滅 し、ただ 再 = 現 前 としての 表 象 において、 快 / 不<br />
快 を 与 えるものに 変 形 される。このとき、 対 象 は 現 前 を 止 めるので、 非 関 与 性 、 没 利 害 性<br />
disinterestedness が 成 立 し、それを 判 断 するための 距 離 を 取 ることが 可 能 になる。 趣 味 = 味 覚 は 直<br />
、、、、、、<br />
接 快 / 不 快 を 引 き 起 こすのでそれとは 距 離 をとれないが、「 我 々は、 快 を 感 じるという 事 実 そのもの<br />
を 是 認 あるいは 否 認 することができる」 449 。こうして 快 / 不 快 そのものを 肯 定 / 否 定 するのは、もは<br />
、、<br />
や 趣 味 ではなくて 判 断 なのである。そして 快 / 不 快 自 体 も 判 断 に 従 属 するのだ。そしてこの 判 断 に<br />
おいては 快 / 不 快 が 決 められるのではなく、 正 / 不 正 、 重 要 / 無 関 係 、 美 / 醜 というようなことが<br />
判 断 されることになる。<br />
441 ARENDT, op.cit., p.215. ( 前 掲 訳 書 、248 頁 。)<br />
442 ARENDT, 浜 田 監 訳 『カント 政 治 哲 学 の 講 義 』( 前 掲 )13 頁 以 下 。<br />
443 ARENDT, 仲 正 昌 樹 訳 『 完 訳 カント 政 治 哲 学 講 義 録 』( 前 掲 )160 頁 、 訳 注 36 を 参 照 。 英 語 taste のほかにドイツ<br />
語 Geschmack、フランス 語 goût などである。<br />
444 ARENDT, 浜 田 監 訳 『カント 政 治 哲 学 の 講 義 』( 前 掲 )97 頁 。<br />
445<br />
同 上 。<br />
446<br />
同 上 、100 頁 。<br />
447 「 私 が 牡 蠣 を 好 まない 場 合 、いかなる 議 論 をもってしても、 牡 蠣 を 好 むように 私 を 説 得 することは 不 可 能 である」<br />
( 同 上 、101 頁 )。<br />
448<br />
同 上 、98 頁 。<br />
449<br />
同 上 、105 頁 。<br />
115
問 題 はいまや、この 判 断 はなにを 基 準 にして 行 なわれるのか、ということである。それこそが 共 通<br />
感 覚 common sense, sensus communis なのだ。ここでの 共 通 感 覚 は、 共 同 体 の 仲 間 と 共 通 している<br />
感 覚 を 意 味 し、 他 者 を 志 向 するものである。 極 めて 私 的 な 感 覚 sensus privatus である 趣 味 が、 共 通<br />
のものになるというのは、 矛 盾 に 思 われる。しかし、「 我 々は 自 分 の 趣 味 が 他 者 のと 一 致 しないとき<br />
には、 恥 を 感 ずる」 450 。 反 省 における 判 断 においては、 我 々は 自 分 の 趣 味 を 他 者 とあわせようとす<br />
る。このような 間 主 観 性 において 趣 味 の 私 的 な 性 格 は 克 服 され、 伝 達 可 能 性 communicability と 公<br />
共 性 publicness という 尺 度 において 判 断 されるようになるのだ。 他 者 とその 感 情 を 考 慮 に 入 れた 反<br />
省 において、 判 断 は 妥 当 性 を 得 る。 判 断 の 妥 当 性 は 認 識 命 題 や 科 学 的 命 題 のような 強 制 的 な 妥<br />
当 性 はない。だから 自 分 の 判 断 への 同 意 を 他 人 に 強 制 することはできず、 同 意 はただせがんだり、<br />
請 うたりすることができるのみだ。 基 本 的 には、 可 能 な 他 者 がそれを 快 と 認 めるだろうものを 快 と 判<br />
断 しようと、 人 は 考 える。だから、 判 断 者 は 退 きこもりにおいて、 一 者 の 中 の 二 者 になるのではなく、<br />
可 能 的 他 者 との 共 同 性 において、 判 断 することになる。<br />
第 34 節 範 例 ―― 判 断 を 補 助 する 特 殊 事 例<br />
判 断 は、 特 殊 的 なものを、その 特 殊 性 において 判 断 するという 点 で、 極 めて 特 異 な 能 力 である。<br />
判 断 力 は「 特 殊 と 普 遍 とを 不 可 思 議 な 仕 方 で 結 合 する 能 力 である」 451 が、 規 定 的 判 断 力 と 反 省 的<br />
判 断 力 との 二 種 類 がある 452 。<br />
前 者 は 特 殊 なものを 一 般 的 な 規 則 に 包 摂 してゆく 能 力 だが、それは 基 準 ( 法 則 ・ 規 則 ・ 原 理 )を<br />
外 部 から 借 りてくるので、「 比 較 的 容 易 」である 453 。 前 節 で 挙 げた 例 で 言 えば、「ソクラテス( 特 殊 )は<br />
人 間 ( 一 般 )である」という 部 分 がやっかいで、 問 題 は 単 に 規 則 に 当 てはめるだけでも、その 当 ては<br />
めること 自 体 のための 規 則 は 与 えられていないということにある。ソクラテス= 人 間 と 結 びつける 部<br />
分 は 依 然 として 神 秘 的 なのだ(この 問 題 にはここでは 立 ち 入 らないことにしよう)。<br />
後 者 、 反 省 的 判 断 力 のほうが、 我 々の 関 心 にとってより 重 要 である。この 場 合 判 断 力 は「 規 則 を<br />
特 殊 なものから『 導 出 する』」 454 。この 場 合 、 判 断 のための「 基 準 を 経 験 から 借 りることはできず、また<br />
経 験 の 外 から 手 に 入 れることもできないから」 455 困 難 は 増 す。アーレントは「 範 例 的 妥 当 性<br />
exemplary validity」という 概 念 を 用 いてこの 困 難 を 克 服 しようと 試 みる。「 範 例 example」は「そのまさ<br />
に 特 殊 性 において、 他 の 仕 方 では 明 らかにしえぬような 普 遍 性 を 顕 にする 特 殊 なものであ」る 456 。<br />
具 体 例 を 見 よう。<br />
範 例 は、それ 自 身 のうちに 概 念 または 一 般 的 規 則 を 含 む 特 殊 なもの、あるいは 含 むと 見 ら<br />
れる 特 殊 なものである。 例 えば、いかにして 人 はある 行 動 を 勇 気 あるものと 判 定 し、 評 価 するこ<br />
450<br />
同 上 、102 頁 。カントの 引 用 と 思 われるが、 引 用 元 は 不 明 。<br />
451<br />
同 上 、117 頁 。<br />
452 ARENDT, The Life of the Mind: One/ Thinking (op.cit.), p.69. ( 前 掲 訳 書 、81 頁 。)<br />
453 ARENDT, 浜 田 監 訳 『カント 政 治 哲 学 の 講 義 』( 前 掲 )117 頁 。<br />
454<br />
455<br />
456<br />
同 上 、128 頁 。<br />
同 上 、117 頁 。<br />
同 上 、119 頁 。<br />
116
とができるのであろうか。そうした 判 定 を 下 すとき、 人 は 一 般 的 規 則 からの 演 繹 によらずに、 全<br />
く 自 発 的 に、「この 男 は 勇 気 がある」と 言 う。ギリシア 人 ならば、「 心 の 奥 底 で」アキレスを 範 例 と<br />
するかも 知 れない。〔 略 〕また、ある 者 を 善 良 な 男 だと 言 うときにも、 我 々は 心 の 奥 で、 聖 フラン<br />
シスやナザレのイエスを 範 例 とする。 判 断 力 は、 判 例 が 適 切 に 選 ばれるかぎりにおいて、 範 例<br />
的 妥 当 性 を 有 する。 457<br />
判 断 者 は、 人 が「 勇 気 をもつ」と 見 做 すとき、 勇 気 あるアキレスを 範 例 として、その 人 が 勇 気 を 持 つと<br />
判 断 する。アキレスは 極 めて 特 殊 なものでありながら、 一 般 的 な 意 味 をもつ 範 例 として 参 照 されるの<br />
である。それは 英 雄 性 でもよいだろう。 誰 かを 英 雄 的 であると 判 断 するとき、 比 類 なき 個 性 としての<br />
アキレスが、まるで 一 般 的 な 概 念 のように 働 き、アキレスに 似 ているという 点 で、その 人 は 英 雄 的 で<br />
あると 判 断 することになるのだ。さらに、アーレントは 歴 史 学 と 政 治 学 のカテゴリーは 殆 どこのような<br />
範 例 であると 述 べる。<br />
フランス 史 の 文 脈 で、 私 は 特 殊 な 一 個 人 としてのナポレオン・ボナパルトについて 語 ることがで<br />
きるが、しかし、ボナパルティズムの 話 に 移 るや 否 や、 私 はナポレオンを 一 範 例 とすることにな<br />
る。この 範 例 の 妥 当 性 は、ナポレオンの 同 時 代 人 としてか、この 特 殊 な 歴 史 的 伝 統 の 継 承 者 と<br />
、、、、、、<br />
してか、ナポレオンについての 特 殊 な 体 験 を 有 する 者 に、 限 定 されるであろう。 歴 史 学 や 政 治<br />
、、、、、、、、、、、、、 、、、、、、、、、、、、、、、、、 、、、、 、、、、、<br />
学 における 概 念 のほとんどは、この 種 の 限 定 された 性 格 をもっている。それらは、ある 特 殊 な<br />
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 、、、、、、、、 、、、、、、、、、、、<br />
歴 史 上 の 出 来 事 にその 起 源 をもつものであるが、 後 になって 我 々が、その 特 殊 なもののうちに<br />
、、、、、、、、、、、、、、、、、 、、、、 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、<br />
より 多 くの 事 例 に 妥 当 する 事 柄 を 見 ようとして、その 出 来 事 を 範 例 とするようになるのである。<br />
〔 傍 点 は 橋 爪 〕 458<br />
歴 史 学 や 政 治 学 の 対 象 、つまり 人 間 事 象 human affairs の 領 域 においては、 人 びとの 意 志 と 活<br />
動 によって 比 類 なき、 絶 対 的 に 新 しい 出 来 事 が 起 こる。 特 殊 な 出 来 事 そのものが、その 特 殊 性 をそ<br />
のままに、 歴 史 学 的 了 解 のカテゴリーを 拡 張 するのだ。 例 をあげれば、(アーレントのボナパルティ<br />
、、、、 、、 、、、、、、<br />
ズムでもよいが)フランス 革 命 という「 大 革 命 」の 存 在 によって、 我 々ははじめて「 革 命 」というものを<br />
、、、<br />
知 ったということになろう。その 後 何 らかの 歴 史 的 事 件 を「 革 命 」と 呼 ぶとき、 我 々は 密 かに「 大 革 命 」<br />
を 範 例 として 召 喚 しているのである(アーレントにとっては 革 命 の 範 例 はアメリカ 革 命 であろうが、こ<br />
こでは 一 般 的 な 歴 史 学 の 理 解 に 沿 ってフランス 革 命 を 挙 げた。 第 五 章 補 論 を 参 照 のこと)。それは<br />
人 を 英 雄 と 呼 ぶときに 密 かにアキレスを 呼 びだすのと 等 しい( 我 々はアキレスによってはじめて 英<br />
雄 とはなにかを 知 ったのだ)。あるいは、 政 治 ( 学 )politics という 出 来 事 が 問 題 にされる 際 、まさにそ<br />
れはポリス 的 なもの the political であるとして、つねにすでにポリスを 範 例 として 参 照 しているのも、<br />
同 じことであろう。<br />
457<br />
458<br />
同 上 、129-130 頁 。<br />
同 上 。<br />
117
しかしながら、 問 題 は、そのような 範 例 となる 事 件 そのものが 起 ったとき、それを 如 何 に 判 断 する<br />
か、という 点 にある(アーレントはその 辺 りについてあまり 書 いていないので、ここから 先 はやや 想 像<br />
力 を 逞 しくしていかねばならない)。 言 いかえれば、 例 に 挙 げたフランス 革 命 が 起 った 直 後 に、その<br />
正 right/ 不 正 wrong を 判 断 するのは、どういう 範 例 に 依 ればいいのか。もっといえば、とりわけ 政<br />
治 的 な 状 況 において、「なにが 正 義 justice か」を 判 断 することを 可 能 にするものは、なんなのか。<br />
おそらく 我 々が 拠 り 所 とするのは、フランス 革 命 以 前 の 事 件 、そのなかでも 正 義 を 告 げているよう<br />
な 事 件 であろう。だがそれらはそれ 自 体 特 殊 な 諸 事 件 である。それらの 事 件 はつねに、そのつど 特<br />
殊 な 状 況 のなかで 正 義 を 体 現 しているので、その 正 義 を(「 正 義 は…のことである」というように) 一<br />
般 化 することはできない。しかし 諸 々の 事 件 は、それぞれが 特 殊 に 正 義 を 体 現 したものとして、 範<br />
例 たりうる。 判 断 は 論 証 的 に 得 られるものではなく、さらには 範 例 によっても 強 制 されるものではな<br />
い。 範 例 はあくまで 判 断 を 補 助 するにすぎない。だから、 正 義 の 実 現 とみなされる 出 来 事 を 範 例 と<br />
して、つまりそれを 比 較 ノ 第 三 項 tertium comparationis として、 正 義 とフランス 革 命 を 結 びつけると<br />
いうことが、 判 断 者 のなかで 行 なわれたに 違 いない。<br />
( 法 学 的 に 言 えば、 範 例 は 判 例 precedent に 等 しいと 考 えられる。 判 例 はそれぞれが 正 義 の 発 現<br />
ということになる。 誤 解 してはならないのは、 裁 判 における 判 決 = 判 断 judgment は、 法 律 から 機 械<br />
的 に 導 きだされるものではないという 点 である。 裁 判 官 、すなわち 判 断 者 judge は、 判 断 を 自 律 的<br />
に 行 う。 無 論 、それは 法 をまったく 無 視 することでもない。 法 という 一 般 的 規 則 を、 個 々の 事 件 という<br />
特 殊 なケースに 結 びつける 場 合 を 考 えて 見 ても、 結 びつけること 自 体 の 規 則 はない。この 結 びつけ<br />
は〔 規 定 的 な〕 判 断 なのである。 規 則 の 適 用 自 体 は、 法 の 外 、 法 が 停 止 したところで、 裁 判 官 が 構<br />
想 力 と 共 通 感 覚 に 依 拠 しつつ、 自 律 的 に 判 断 するのに 委 ねられる。そのさい 判 例 は 範 例 として、<br />
正 義 の 実 現 の 特 殊 な 例 として 呼 び 出 されるだろう〔 事 実 としては de facto とても 正 義 の 実 現 とは 言 え<br />
ないような 判 例 が 数 多 く 含 まれているだろうとして、すくなくとも 権 利 上 は de jure〕。だが 判 例 には 強<br />
制 力 はなく、ただ 判 断 を 助 けるのみである。 裁 判 官 はあくまで 自 律 的 に 判 断 する。そしてあくまで 特<br />
殊 なケースに 対 する 判 断 が、 正 義 に 適 っていると 見 做 されるとき、それは 新 たな 範 例 = 判 例 となる。<br />
つまり、 起 こったことを 了 解 するための 新 しいカテゴリーとなるのだ。)<br />
第 35 節 判 断 の 時 間 経 験 ――「もうない no more」<br />
さて、いよいよ 判 断 の 時 間 経 験 を 考 えてみたい。そのためにまず、 前 節 までの 議 論 をまとめてお<br />
こう。<br />
判 断 の 問 題 に 焦 点 が 当 たったのは、 意 志 と 意 志 が 引 き 起 こす 活 動 が 含 む 困 難 のためであった。<br />
つまり、 意 志 と 活 動 は 歴 史 上 類 を 見 ないような 全 く 新 しい 出 来 事 を 起 こす 能 力 であったために、 起<br />
こった 出 来 事 を 歴 史 として 語 るとき、なにを 基 準 にその 偉 大 さ、 正 当 性 (あるいは 個 人 の 生 ならば 幸<br />
福 )を 判 断 することが 可 能 なのか、ということが 理 解 できなくなってしまったのだ。 原 義 からすれば 判<br />
断 者 である 歴 史 家 は、 自 律 的 に( 歴 史 という 神 に 依 らずに) 出 来 事 の 意 味 を 判 断 しなくてはならな<br />
い。そのためにまず 判 断 者 は 活 動 からは 退 きこもり、 観 客 という 立 場 を 取 らなくてはならない。 活 動<br />
者 は 特 定 の 利 害 に 巻 き 込 まれて、 全 体 を 把 握 することが 出 来 ないからである。 判 断 者 は 観 客 席 か<br />
118
ら 全 体 を 見 渡 す。 判 断 の 袋 小 路 を 脱 出 する 可 能 性 は、 趣 味 にある。 趣 味 は 極 めて 特 殊 なものに 関<br />
わる 私 的 な 感 覚 であるが、 構 想 力 による 再 = 現 前 においてその 快 / 不 快 そのものを 肯 定 / 否 定<br />
するとき、それはもはや 判 断 であり、その 判 断 においては 共 通 感 覚 によって 他 者 の 判 断 が 想 定 され、<br />
もはや 趣 味 の 私 的 性 格 はなくなり、 公 共 性 が 回 復 される。さらにここで 問 題 は 快 / 不 快 ではなく、<br />
「 私 がそれに 同 意 できるか 否 か」、つまり 正 / 不 正 の 問 題 へと 変 化 するのだ。このとき 正 / 不 正 を 判<br />
断 する 補 助 となるのが、 範 例 であった。 範 例 はあくまで 例 であり、 強 制 力 のある 真 理 ではない。 判 断<br />
者 は 特 定 の 事 例 ( 例 えばフランス 革 命 )に 目 を 向 け、それを 正 義 の 範 例 と 捉 えて、その 事 例 と 比 べ<br />
ることである 事 件 の 正 / 不 正 を 判 断 する。その 際 判 断 はあくまで 自 律 的 である。このようにして、<br />
ヒ ス ト ー ル<br />
歴 史 家 = 判 断 者 は 歴 史 や 物 語 を 記 述 するのである。<br />
アーレントがいうように、 判 断 は 過 去 に 関 わる 能 力 である。 過 去 に 関 わるとき、 思 考 は 安 定 して 変<br />
化 することの 無 い 過 去 から 思 考 の 材 料 を 集 めてきた。また 意 志 は「 後 ろ 向 きに 意 志 できない」、つま<br />
り 実 在 としての 過 去 を 変 えることは 意 志 できなかった。ここで 判 断 に 託 された 課 題 は「 今 存 在 する 事<br />
象 〔things as they are〕、 既 に 生 成 してしまった 事 象 〔things as they have come into being〕からの、 精<br />
神 の 独 立 を 維 持 する」ことができるか、なのである。つまり 実 在 や 変 化 しえない 過 去 に 対 して、 精 神<br />
が 自 律 的 に 活 動 力 を 発 揮 する 可 能 性 はあるのか、が 焦 点 になっている。アーレントはそこで、 過 去<br />
を「 判 断 する」ことに 結 び 付 け、 過 去 の 意 味 付 けを 人 間 の 活 動 力 に 託 した。 思 考 は 現 在 を 離 れず、<br />
意 志 は 未 来 に 向 かっているが、 判 断 は 過 去 に 対 して 人 間 が 自 律 的 に 行 為 する 可 能 性 を 開 いたの<br />
である。<br />
しかしここで 時 間 そのものはどこから 到 来 するのか、ということを 考 えると、 問 題 はややこしくなっ<br />
てくる。ハイデガー 風 に 言 えば、 時 間 性 の 第 一 義 的 現 象 はどの 時 制 にあるのか、という 問 題 である。<br />
判 断 は 過 去 に 対 して 自 律 的 に 行 為 する 活 動 力 であるから、 過 去 が 判 断 の 第 一 義 的 な 時 制 なのだ<br />
ろうか つまり 時 間 は 過 去 から 時 熟 するのだろうか<br />
ところで、その 問 題 を 考 える 際 、アーレントの 判 断 の 議 論 で、 奇 妙 な 役 割 を 果 たしているのが、 進<br />
歩 の 概 念 である。 既 に 見 たように、アーレントは 歴 史 を 判 断 者 とするヘーゲルの 歴 史 観 には 反 撥 し<br />
ている。 歴 史 の 進 行 自 体 が 正 / 不 正 を 判 断 するという 考 え 方 から、 判 断 者 としての 尊 厳 を 人 間 に<br />
回 復 しなくてはならないと 彼 女 は 言 っていた。しかし、アーレントはカントが 抱 いていた 進 歩 の 観 念<br />
には、 両 義 的 とでも 言 えるような、 妙 な 態 度 を 取 っていた。<br />
〔カントの〕 歴 史 を 判 断 する 基 準 としての 進 歩 は、 物 語 の 意 味 は 終 局 においてのみあらわにな<br />
る〔 略 〕、という 古 くからの 原 理 をいくぶん 覆 すものである。カントにおいて、 物 語 や 出 来 事 の 重<br />
要 性 は、 精 密 にはその 終 局 にあるのではなく、それが 未 来 のために 新 しい 地 平 を 開 く 点 にあ<br />
る。フランス 革 命 をあれほど 重 要 な 事 件 としたのは、それが 来 るべき 世 代 のために 含 んでいた<br />
希 望 である。 459<br />
459<br />
同 上 、84-85 頁 。なお、 原 文 は 確 認 できていないが、 文 脈 上 「 将 来 」の 訳 語 を「 未 来 」に 直 したことを 断 わっておき<br />
たい。 些 か 横 着 ではあるが、 仲 正 訳 (105 頁 )でも「 未 来 」と 訳 されているので、 問 題 ないものと 判 断 した。<br />
119
このように 述 べたうえで、アーレントはカントとヘーゲルの 区 別 をつける。ヘーゲル(とマルクス)にと<br />
って 重 要 なのは、 歴 史 が 終 局 をもつことなのだ。「 過 程 は 無 限 ではなく、それ 故 物 語 には 終 局 があ<br />
る。この 終 局 のためにのみ、 多 くの 世 代 と 世 紀 が 生 ずる 必 要 がある。〔 略 〕 最 終 的 に 姿 を 現 わすの<br />
は〔 人 間 ではなく〕 絶 対 精 神 であり、 人 間 の 偉 大 さは、ただ 最 後 に 人 間 が 絶 対 精 神 を 理 解 しうる 限 り<br />
で 実 現 されるにすぎない」 460 。ヘーゲルにあっては、「 歴 史 が 終 局 を 迎 えた 後 に 人 間 の 為 しうること<br />
は、 完 成 された 歴 史 過 程 をただ 永 遠 に 再 考 することだけである」 461 し、「 他 方 、マルクス 自 身 の 考 え<br />
では、 富 裕 さに 基 づく 無 階 級 社 会 ないし 自 由 の 王 国 では、 万 人 が 何 らかの 趣 味 に 耽 っておればよ<br />
い、ということになる」 462 。それに 対 して「カントでは、 進 歩 は 永 続 するものであり、 進 歩 に 終 局 はない。<br />
それ 故 歴 史 にも 終 局 はない」 463 。にもかかわらず、 判 断 する 者 たち、つまり 観 客 は、「 全 体 について<br />
の 理 念 を 持 つことで、 個 々の 特 殊 な 出 来 事 のうちに 進 歩 がなされているか 否 かを 判 断 するのである」<br />
464 。ようするに、すくなくともカントにとっての 判 断 者 は、 進 歩 を 想 定 していると 理 解 するほかない。さ<br />
らに 我 々を 混 乱 させるのは、「カント 政 治 哲 学 講 義 」の 謎 めいた 結 びである。<br />
カント 自 身 のうちには 次 のような 矛 盾 がある。 無 限 の 進 歩 は 人 類 の 法 則 である。ところが 同 時<br />
に、 人 間 の 尊 厳 は、 人 間 ( 我 々のうちの 各 個 人 )がその 特 殊 性 において 見 られ、またそのよう<br />
なものとして――しかし 比 較 を 絶 し、 時 間 とは 独 立 して―― 人 類 一 般 を 反 省 する 者 と 見 られる<br />
ことを 要 求 する。 換 言 すれば、まさしく 進 歩 の 観 念 そのものが〔 略 〕カントの 考 える 人 間 の 尊 厳<br />
という 概 念 に 矛 盾 するのである。 進 歩 を 信 ずることは 人 間 の 尊 厳 に 反 する。さらに、 進 歩 とは 物<br />
語 が 決 して 終 わらぬことを 意 味 する。 物 語 そのものの 終 わりは 無 限 の 彼 方 にある。 我 々が 静 か<br />
に 佇 み、 歴 史 家 のもつ 後 ろ 向 きの 眼 差 しでもって 歴 史 を 回 想 するような、いかなる 地 点 も 存 在<br />
しないのである。 465<br />
アーレントはカントの 矛 盾 を 解 くことなく、そのまま 講 義 を 終 えてしまう。この 矛 盾 がしかし、アーレン<br />
トにおける 進 歩 の 捉 え 方 を 読 む 鍵 であるように 思 われる。<br />
カントの 矛 盾 とは、1 個 々の 人 間 がその 特 殊 性 において、 人 類 一 般 を 反 省 することと、2 無 限 に<br />
進 歩 すること、つまり 人 類 一 般 ということがいつまでも 無 規 定 でありつづけることの、 二 つの 矛 盾 で<br />
ある。「 時 間 とは 独 立 して、 人 類 一 般 を 反 省 する」ためには、ヘーゲルのように 歴 史 の 終 わりに 立 た<br />
ねばならないだろう。しかし、「 後 ろ 向 きの 眼 差 しで 歴 史 を 回 想 するいかなる 地 点 も 存 在 しない」。<br />
我 々は、 人 類 一 般 という 理 念 と 無 限 の 進 歩 という 理 念 のどちらか 一 方 を 切 らねばならないように 見<br />
える。だが、さきほどの 引 用 をいまいちど 思 いかえそう。「 物 語 や 出 来 事 の 重 要 性 は、 精 密 にはその<br />
終 局 にあるのではなく、それが 未 来 のために 新 しい 地 平 を 開 く 点 にある。フランス 革 命 をあれほど<br />
重 要 な 事 件 としたのは、それが 来 るべき 世 代 のために 含 んでいた 希 望 である」。ここで、この 矛 盾 は<br />
460<br />
461<br />
462<br />
463<br />
464<br />
同 上 、86 頁 。<br />
同 上 。(KOJÈVE, Alexandre, “Hegel, Marx and Christianity,” in: Interpretation, 1 [1970]: 37.)<br />
同 上 。<br />
同 上 。<br />
同 上 、88 頁 。<br />
120
調 停 されている。というのは、 人 類 一 般 の 理 念 は、 無 規 定 の 未 来 のうちにあるからだ。 過 去 の 意 味<br />
は 未 来 から 出 来 するのだ。<br />
未 来 の 希 望 が 過 去 の 出 来 事 にある(あるいは 過 去 の 出 来 事 の 意 味 が 未 来 にある)という 着 想 の<br />
原 点 に、ベンヤミンの 歴 史 哲 学 が――あるいは 少 なくともその 影 響 が――あると 見 ても、 大 きく 外 れ<br />
てはいないだろう。ベンヤミンの「メシア 的 な 時 間 」は、まさに 過 去 を 救 済 する 時 間 であった。そのイ<br />
メージはつぎのようなものだった。<br />
「ホモ・サピエンスのけちな 五 万 年 は」、と 近 代 の 一 生 物 学 者 はいう、「 地 球 上 の 有 機 的 生 命 の<br />
歴 史 にくらべれば、 二 四 時 間 の 一 日 のおしまいの 二 秒 ほどにあたる。 開 化 した 人 類 の 歴 史 は、<br />
この 尺 度 にあてれば、 最 後 の 一 時 間 の 最 後 の 一 秒 の 五 分 の 一 ばかりだろう」。〈いまというと<br />
き〉〔Jetztzeit〕が、メシア 的 な 時 間 のモデルとして、 全 人 類 の 歴 史 をおそろしく 短 縮 して 総 括 す<br />
、、<br />
るとき、それは、 人 類 の 歴 史 が 宇 宙 のなかにおかれたときの、あのイメージとぴたりと 符 合 する。<br />
466<br />
24 時 間 の 長 さの 意 味 が 明 らかになるのは、 終 わりの 1/5 秒 という 時 である。 終 わりの 1/5 秒 がそれま<br />
での 歴 史 の 全 てを 救 済 するのだ。だから「どんな 事 実 も、 何 かの 原 因 だからというだけでは、まだ 歴<br />
史 的 事 実 ではない。それが 歴 史 的 事 実 になったのは、いわば 死 後 であって、それとは 数 千 年 も 離<br />
れているかもしれぬ 諸 事 件 によってである」 467 。そのことを 知 るベンヤミンの 歴 史 家 、 歴 史 的 唯 物 論<br />
者 は「メシア 的 な 時 間 のかけらが 混 じえられている〈いまというとき〉としての 現 在 の 概 念 を、 基 礎 づ<br />
ける」 468 。このような〈いまというとき〉はモナドの 比 喩 で 表 現 されている。このモナドは 静 止 した 結 晶<br />
、、、<br />
であるが、そこにすべてを 映 し 込 んでいるのだ(「ひとつの 仕 事 のなかにその 人 間 の 仕 事 が、ひとり<br />
、、、<br />
、、、<br />
の 人 間 の 仕 事 のなかに時 代 が、ひとつの 時 代 のなかに全 歴 史 の 経 過 が、 保 存 され、 止 揚 されてい<br />
、、、、、、、、、<br />
る〔 略 〕」 469 )。だから 歴 史 家 は、その 都 度 一 回 的 な〈いまというとき〉において、その 都 度 一 回 的 な 歴<br />
、<br />
史 を 認 識 するのだ。それゆえ「 過 去 の 真 のイメージは、ちらりとしかあらわれぬ。 認 識 を 可 能 とする<br />
一 瞬 にまさに 閃 き、そして 永 久 にもどってこない――そういうイメージとして、 過 去 はしっかと 掴 まれ<br />
ねばならない」 470 。これまでの 全 歴 史 の 意 味 がそこから 了 解 されるような 一 瞬 、メシア 的 でモナド 的<br />
な〈いまというとき〉、このその 都 度 一 回 的 で 歴 史 的 な 現 在 から、 歴 史 は 了 解 されるべきである。だか<br />
、、、、、、、、、、、、<br />
ら「 歴 史 主 義 は 過 去 の『 永 遠 の』 像 を 提 出 するが、 歴 史 的 唯 物 論 者 は、 過 去 という 現 に 在 る 唯 一 の<br />
、、<br />
ものの 経 験 を、 提 出 する」 471 。 過 去 は 永 遠 に 不 変 のものではないのだ。<br />
465<br />
同 上 、119-120 頁 。<br />
466 BENJAMIN, „Über den Begriff der Geschichte“ (ebenda), S.139. ( 前 掲 訳 書 、80 頁 。„Jetztzeit“の 訳 を 改 めた。ま<br />
た 訳 文 では 原 文 のイタリック 強 調 を〈…〉で 囲 むことによって 示 しているが、 傍 点 強 調 に 改 めた。)<br />
467 Ebenda. ( 同 上 。)<br />
468 Ebenda. ( 同 上 。)<br />
469 Ebenda, S.138. ( 同 上 、78-79 頁 。)<br />
470 Ebenda, S.131. ( 同 上 、59 頁 。ただしこの 箇 所 はかなり 意 訳 されていたので、 或 る 程 度 訳 しなおした。)<br />
471 Ebenda, S.138. ( 同 上 、77 頁 。)<br />
121
カントを 思 い 返 すと、 個 々の 人 間 がその 特 殊 性 において 人 類 一 般 を 反 省 することが、 人 間 の 尊<br />
厳 とされていた。「 個 々の 人 間 がその 特 殊 性 において」というのは、 実 存 哲 学 的 に 言 いかえれば、<br />
「そのつど 一 回 的 な 歴 史 性 において」ということを 意 味 する。それはまさにベンヤミンの〈いまというと<br />
き〉と 重 なる。「 認 識 を 可 能 にする 一 瞬 」は 一 回 的 で、その 都 度 的 な 個 々の 人 間 に、 個 々の「わたし」<br />
に、 属 するのである。つまり 判 断 のときは、 一 回 的 で 歴 史 的 な 瞬 間 である。その 瞬 間 に 全 歴 史 の 意<br />
味 が 明 らかになるように、 判 断 は 為 される。<br />
このことと「 無 限 の 進 歩 」、というより、 人 間 の 歴 史 の 終 わりがないこととは、 矛 盾 するだろうか。たし<br />
かに、そのような 判 断 は 歴 史 の 終 わりのとき(1/5 秒 )にしかできないように 感 じられる。しかし、 我 々<br />
が 生 きる 時 間 はつねに〈いまというとき〉であり、 認 識 を 可 能 にする 一 瞬 は、つねにその〈いまというと<br />
き〉なのである。べつの 言 い 方 をすれば、 時 間 を 直 線 的 に 考 えれば、 我 々はいつも 最 後 の 末 端 を<br />
生 きているのだ。 過 去 は「 永 遠 」のものではない、いいかえれば、 過 去 もまた 時 間 的 なのだ。つまり<br />
時 間 の 展 開 に 従 って 捉 えられる 過 去 の 可 能 性 も 変 化 する。あらゆる 世 代 にあらゆる 世 代 の〈いまと<br />
いうとき〉があり、 未 来 にもその〈いまというとき〉、 過 去 の 救 済 の 可 能 性 は 存 在 している。「 未 来 のあ<br />
らゆる 瞬 間 は、そこをとおってメシアが 出 現 する 可 能 性 のある、 小 さな 門 だったのである」 472 。つまり<br />
歴 史 に 終 わりがないかぎりは、 判 断 の 活 動 力 は 終 わることはないのだ。 歴 史 が 終 わらないかぎり、と<br />
いうのは、つまり 人 間 が 存 在 し、そして 意 志 し 活 動 して 新 しいことを 生 み 出 してゆく 限 り、ということで<br />
ある。 新 たなことが 出 現 し、そのつど 一 回 的 な 現 在 が 生 きられるとき、その 現 在 、その〈いまというと<br />
き〉によって、 過 去 が 救 済 される 可 能 性 があるのだ。<br />
だが、さらにアーレントはここでベンヤミンを 離 れ、「 物 語 や 出 来 事 の 重 要 性 は、 精 密 にはその 終<br />
局 にあるのではなく、それが 未 来 のために 新 しい 地 平 を 開 く 点 にある。フランス 革 命 をあれほど 重<br />
要 な 事 件 としたのは、それが 来 るべき 世 代 のために 含 んでいた 希 望 である」と 述 べているのだ。ア<br />
ーレントの 判 断 者 は、 出 来 事 を 判 断 する 際 、それが 未 来 の 希 望 をもつことに 賭 ける。 判 断 はたしか<br />
に〈いま〉なされる。しかしその 判 断 が 与 える 意 味 の 源 泉 は 未 来 に 委 ねられているのだ。つまりこの<br />
判 断 は 前 未 来 的 な 現 在 において 行 なわれる。 過 去 の 意 味 は 未 来 から、 現 在 を 通 りぬけて、 過 去 へ<br />
と 与 えられる。だからここでも 時 間 性 の 一 義 的 な 現 象 は 未 来 であると 考 えることができる。 判 断 は「も<br />
はやない no more」ものに 関 わるが、そのもはやないものの 意 味 を 救 済 する 可 能 性 は 未 来 から 到 来<br />
するのだ。<br />
472 Ebenda, S.140. ( 同 上 、81 頁 。)<br />
122
結 論<br />
我 々はアーレントの 時 間 論 という 問 題 を 立 て、その 関 心 に 沿 って 彼 女 の 思 想 を 概 観 してきた。 最<br />
後 に、 本 論 文 の 成 果 を、 全 体 を 振 り 返 りながら 確 かめつつ、 全 体 を 考 慮 に 入 れてはじめて 可 能 な<br />
捕 捉 を 加 えたい。<br />
我 々の 考 察 はまず 時 間 の 形 式 的 規 定 を 確 かめることから 始 めた。アリストテレスやアウグスティヌ<br />
スに 依 拠 しつつ、 時 間 は 運 動 と 変 化 がなければ 存 在 しないことを 確 認 した。ただし、ハイデガーも<br />
言 うように、その 運 動 はそれを 時 間 として 経 験 する 意 識 存 在 がなければ、 時 間 化 ( 時 熟 )しない。つ<br />
まり 時 間 そのもの Zeit an sichはありえない。 時 間 はつねにすでに 経 験 された 時 間 なのである。 人 間<br />
は 行 為 (アーレントのいう 活 動 力 )において、 自 らを 時 間 的 に 変 化 させる。そしてその 時 間 を 自 ら 経<br />
験 するのである。だから 人 間 は 自 ら 時 間 化 する sich zeitigen のだ。このような 時 間 の 生 成 の 全 体 性<br />
を、 我 々は 時 間 性 temporality と 名 づけた。<br />
アーレントにおいては、 活 動 力 によってそれぞれ 異 なる 時 間 経 験 がされるのではないか、という<br />
のが 本 論 の 着 想 であったから、 以 降 は 活 動 力 ごとの 時 間 の 生 成 の 仕 方 ( 時 間 性 )を 細 かく 検 証 した。<br />
その 前 提 作 業 となるのが、 二 つの 生 活 の 区 別 、 活 動 的 生 活 vita activa と 精 神 的 生 活 life of the<br />
mind の 区 別 であった。 前 者 は 現 象 界 での 活 動 力 の 総 称 であり、 後 者 は 現 象 界 から 退 きこもり、 反<br />
省 をする 精 神 的 活 動 力 の 総 称 である。<br />
活 動 的 生 活 は 労 働 labor、 仕 事 work、 活 動 action の 三 つに 分 かれる。 労 働 と 仕 事 は、ヤスパー<br />
スで 言 うところの 現 存 在 、ハイデガーのいう 世 人 自 己 ないし 世 界 内 存 在 としての 人 間 に 関 わる。つ<br />
まり 固 有 の 自 己 を 示 すためではなく、なんらかの 目 的 や 外 的 強 制 に 支 配 された 自 己 である。 他 方<br />
活 動 は 労 働 と 仕 事 から 自 由 になったとき、 自 らの 固 有 の 存 在 を 複 数 者 のなかで 示 すことを 可 能 に<br />
する 活 動 力 である。これはヤスパースならば 交 わりにおける 実 存 、ハイデガーならば 本 来 的 自 己 と<br />
名 指 すものであろう。<br />
他 方 精 神 的 生 活 は 思 考 thinking、 意 志 willing、 判 断 judging の 三 つを 指 す。これら 三 つは 活 動<br />
的 生 活 の 三 つの 活 動 力 よりも 自 由 で、 自 律 的 なものであると 考 えられている。 自 我 はこれらの 自 律<br />
的 な 活 動 力 において 強 制 を 受 けず、 自 由 であるから、その 意 味 では 自 己 の 本 来 性 に 直 結 している<br />
(このため、 労 働 と 仕 事 を、 本 当 の 意 味 で 活 動 力 = 能 動 性 activity として 扱 ってよいのかが 迷 われ<br />
る。『 人 間 の 条 件 』の 時 期 と『 精 神 の 生 活 』の 時 期 との 齟 齬 であるといってもよいが、その 点 について<br />
深 入 りするのはよそう)。<br />
労 働 は、 生 命 の 強 迫 的 なリズムに 追 い 立 てられるようにして 展 開 される。 労 働 は 始 まりから 終 わり<br />
へ、というような 線 分 的 な 過 程 ではない。 始 まりはすなわち 終 わりであり、 終 わりはそのまま 次 の 仕<br />
事 の 始 まりに 繋 がっている。アーレントはその 時 間 経 験 を 永 劫 回 帰 eternal recurrence, ewige<br />
Wiederkehr と 名 づけた。 労 働 の 場 合 、 時 間 はどこから 到 来 するのだろうか。 労 働 の 時 間 は 円 環 をな<br />
すので、 未 来 は 過 去 に 繋 がり、 過 去 は 未 来 につながる。いいかえれば、 回 転 があるのみで、 過 去 も<br />
123
、、、、、、<br />
、、<br />
未 来 も 永 劫 回 帰 には 存 在 しないのだ。 更 に 言 えば、 労 働 には 現 在 しかないのである。つまり 労 働<br />
、、、 、、、、、、、、、、、、、、、、<br />
の 場 合 、 時 間 性 の 第 一 義 的 現 象 は 現 在 となる。<br />
ところで、 思 考 は、 労 働 とは 異 なり 強 制 されるものではないが、 時 間 経 験 の 面 ではやや 似 たところ<br />
がある。 思 考 は、 過 去 と 未 来 を 近 距 離 に 置 いてしまい、その 両 方 から 思 考 の 原 動 力 を 獲 得 すること<br />
ができた。 精 神 の 領 域 では 時 間 も 空 間 も 消 滅 してしまうからだ。それゆえ、 思 考 は「 静 止 スル 現 在<br />
nunc stans」において 営 まれるのだ。つまり 思 考 にも 実 は 現 在 しか 存 在 しない。ここで 思 考 にとっても<br />
時 間 の 第 一 義 的 時 制 は 現 在 なのだ。<br />
仕 事 の 場 合 、 時 間 は 始 まりから 終 わりまでという 線 分 的 直 線 として 理 解 される。 仕 事 は 過 去 から<br />
変 化 しないイデアに 向 き 合 う 段 階 から 始 まり、そのイデアを 物 として 物 化 reification したときに 終 わ<br />
る。 仕 事 は 制 作 fabrication, Herstellung とも 呼 ばれるが、それはアリストテレスのポイエーシス<br />
ποιήσις の 訳 語 としての 制 作 であり、つまり( 目 的 のないプラクシスと 区 別 される 意 味 での) 有 目 的 的<br />
な 行 為 としてポイエーシスなのだ。つまりここでの 時 間 理 解 は 目 的 論 的 である。そしてこの 場 合 、 時<br />
間 の 目 的 は 未 来 にあるのだから、 一 見 すると 時 間 の 意 味 は 未 来 から 理 解 されるように 思 われる。し<br />
かし、 実 はこの 活 動 力 において 支 配 的 なのは 始 めから 終 わりまで 最 初 に 看 取 されるイデアなので<br />
あり、 目 的 論 的 な 過 程 はイデアの 実 現 の 過 程 なのだ。これは、 過 去 にすべて 決 定 しており、あとは<br />
、<br />
それが 現 実 化 するのみであるという、アリストテレス 的 な 可 能 態 = 現 実 態 の 理 解 と 重 なる。ここで 優<br />
、、、、、、、、、、 、、、、、、、、、、、、、、、、<br />
位 な 時 制 は 過 去 である。すなわち 時 間 性 の 第 一 義 的 現 象 は 過 去 である。<br />
章 を 割 いて 取 り 上 げなかった 精 神 の 営 みに、 認 識 や 知 性 を 挙 げた。 実 は 認 識 や 知 性 の 時 間 経<br />
験 もまた 過 去 優 位 なのではないのだろうか、と 私 は 考 えている。 認 識 や 知 性 は、 自 律 的 ではない。<br />
アーレントがこれらを 精 神 的 活 動 力 として 取 り 上 げなかったのはそのためである。 自 律 的 でないと<br />
言 うのは、たとえば 認 識 の 場 合 その 対 象 が 先 立 っており、 知 性 の 場 合 は 強 制 力 のある 真 理 を 相 手<br />
にしているからである。これらの 精 神 的 な 営 みにおいては、すでにある 実 在 、 人 間 が 変 えられない<br />
ような 実 在 を 相 手 にすることになる。だから 営 みの 意 味 は 過 去 から 理 解 されると 言 えるだろう。<br />
活 動 は 新 しいことを 始 める 能 力 であり、その「 始 める」ことの 意 味 とは、 因 果 の 流 れや 強 制 から 自<br />
由 に、 固 有 の 自 己 を 表 現 することであったといえる。 活 動 者 は、ハイデガー 風 にいえばつねに 可 能<br />
性 であり、それゆえその 固 有 の 自 己 はつねに 未 来 に 属 するのだ(「 誰 も 死 ぬ 前 に 幸 福 であるとは 言<br />
われえない」)。<br />
活 動 を 準 備 する 精 神 的 活 動 力 が 意 志 willing だったのであり、 意 志 はやはり 因 果 律 から 自 由 に<br />
ただ 自 らを 原 因 として、 意 志 するのだ。 意 志 は 未 来 に 関 わる 精 神 の 器 官 であり、 未 来 への 投 企<br />
project がその 活 動 力 の 本 質 である。 反 対 に、 過 去 へ 意 志 を 向 けることはできない。なぜなら 過 去 の<br />
実 在 は 意 志 には 変 えることはできないからだ。<br />
そしてそのようにして 起 こった 出 来 事 を 判 断 し、 歴 史 として 記 述 するのが、 判 断 judging の 活 動 力<br />
である。 判 断 は、 過 去 へ 後 ろ 向 きの 眼 差 しを 向 け、その 意 味 を 固 有 の 現 在 から 判 断 する。ただし、<br />
判 断 における 意 味 は 未 来 から 到 来 する。<br />
124
こうして 見 たとき、 意 志 → 活 動 → 判 断 という 三 つの 活 動 力 は、ハイデガーの 言 う 本 来 的 時 間 性 、<br />
、、、、、、、、、、、、、、、<br />
つまり 未 来 を 時 間 の 第 一 義 的 現 象 とするような 時 間 性 を 共 有 していると 考 えられる。そこでは 新 しい<br />
ことが 起 る 余 地 があり、 次 々と 生 起 する 新 しい 出 来 事 が、 時 間 を 固 定 させない。おそらくはこの 時 間<br />
性 こそがアーレントにとって 政 治 の 時 間 性 なのであろう。 政 治 とは、 人 間 が 複 数 性 のなかで 固 有 の<br />
自 己 を 発 揮 することのできる 場 である。 複 数 の 人 間 が 始 めることにおいてそれぞれのユニークさを<br />
示 していくこの 場 においては、 時 間 は 連 続 創 造 的 に 生 起 する。つまり、それぞれが 創 造 の 瞬 間 で<br />
あり、 現 実 性 は、 元 々あった 可 能 性 が 現 実 化 しただけだとは、 考 えられないのだ。だから 時 間 の 意<br />
味 は 未 来 から 了 解 される。<br />
以 上 が 我 々の 時 間 論 的 探 究 の 結 論 である。<br />
最 終 的 に、 我 々を 導 いた 着 想 が 裏 付 けられたと 考 えたい。つまり 時 間 は 活 動 力 から 発 源 し、その<br />
活 動 力 によって 人 間 は 自 らを 時 間 化 するのである。そして 活 動 力 は 複 数 存 在 するので、 時 間 の 経<br />
験 もそれに 従 って 多 様 化 されるのだ。 従 って、アーレントの 活 動 力 の 区 別 からは、それと 同 根 源 的<br />
な 時 間 経 験 の 区 別 が、 導 かれる。そのことは 個 々の 活 動 力 について 確 認 された。つまり 時 間 は 複<br />
数 形 で in plural 存 在 する。この 時 間 の 複 数 性 こそが、アーレントの 時 間 論 の 最 大 の 特 徴 である。<br />
ホ モ ・ テ ン ポ ラ リ ス<br />
我 々の 生 は、 徹 底 的 に 時 間 的 である。 人 間 は 時 間 を 生 み 出 し、 時 間 を 了 解 する、 時 間 的 人 間 で<br />
ある。だから 我 々の 生 (ビオス)の、 実 存 の 意 味 は、 時 間 のなかで 了 解 される。 行 為 ( 活 動 力 )から 人<br />
間 の 意 味 を 了 解 しようという 試 みは、 結 局 時 間 から 人 間 の 意 味 を 了 解 することを 意 味 すると 思 われ<br />
る。ニーチェやヘーゲル、マルクスも、それぞれ 別 々のかたちではあるが、 結 局 時 間 のほうから 実<br />
存 の 意 味 を 理 解 しようとしていたことになる。だが、 時 間 は 人 間 から 発 源 し、 人 間 が 経 験 するもので<br />
あるから、その 時 間 の 経 験 そのものも 時 間 的 であり、 行 為 の 変 化 によって 時 間 の 経 験 そのものも 多<br />
様 に 変 化 する、というのがアーレントの 時 間 論 ということになる。それまでの 哲 学 者 は、 時 間 をただ<br />
ひとつの 様 態 で 了 解 しようとしたために、それを 捉 え 損 なったということになる。おそらく、ハイデガ<br />
ーがはじめて 時 間 の 多 様 な 了 解 を 可 能 にする 前 提 (つまり「 時 間 は 時 間 化 する」)を 整 えた。アーレ<br />
ントは、そのような 時 間 の 多 様 性 の 思 考 をさらに 展 開 しているのだ 473 。<br />
473 ただし、アーレントの 時 間 論 的 探 究 の 結 論 として 言 えば、アーレントは 結 局 、 固 有 の「わたし」の 意 味 は 未 来 から<br />
了 解 されるというハイデガーの 本 来 的 時 間 性 の 理 解 に 与 していると 言 えるだろう。「わたし」の 固 有 性 が 明 らかになる<br />
「 政 治 」の 場 の 時 間 経 験 は、 未 来 優 位 であるからだ。アーレントの「はじまり」の 概 念 は、 実 はこのことを 含 意 している<br />
(アーレントはそれを「 本 来 的 」 時 間 性 とは 呼 ばないが)。 少 なくとも、 政 治 の 時 間 性 は、 未 来 から 出 来 するからである。<br />
つねに 存 在 可 能 であるようなホモ・テンポラリスにとっては、 自 己 の 本 来 性 は 未 来 から 了 解 されねばならないだろう。<br />
自 己 の 本 来 性 は、 共 同 存 在 において 自 ら 創 造 するものであるから。<br />
125
参 考 文 献<br />
一 次 文 献<br />
※ 順 序 は 原 著 の 発 表 順 に 準 ずる。なお、アーレントの 本 を 引 用 する 際 は 邦 訳 も 参 照 したが、 訳 語 の 統 一 や 解 釈 な<br />
どの 問 題 から、かなりの 部 分 を 訳 しなおした。<br />
ARENDT, Hannah, The Human Condition, 2nd ed., with an introduction by Margaret CANOVAN,<br />
Chicago/ London: The Univ. of Chicago Press, 1998 (orig. 1958). ( 志 水 速 雄 訳 『 人 間 の 条 件 』ち<br />
くま 学 芸 文 庫 、1994 年 。)<br />
――――, On Revolution, London: Penguin Books Ltd., 1990 (orig. 1963). ( 志 水 速 雄 訳 『 革 命 に<br />
ついて』ちくま 学 芸 文 庫 、1995 年 。)<br />
――――, Vita activa oder Vom tätigen Leben, ungekürzte Taschenbuchausgabe, 6. Aufl. München/<br />
Zürich: Piper Verlag, 2007 (orig. 1967).<br />
――――, 阿 部 齊 訳 『 暗 い 時 代 の 人 々』ちくま 学 芸 文 庫 、2005 年 (orig. 1968)。<br />
――――, The Life of the Mind: One/Thinking, San Diego/ New York/ London: Harcourt Inc., 1978.<br />
( 佐 藤 和 夫 訳 『 精 神 の 生 活 上 第 一 部 思 考 』 岩 波 書 店 、1994 年 。)<br />
――――, The Life of the Mind: Two/ Willing, San Diego/ New York/ London: Harcourt Inc., 1978.<br />
( 佐 藤 和 夫 訳 『 精 神 の 生 活 下 第 二 部 意 志 』 岩 波 書 店 、1994 年 。)<br />
――――, ed. by Ronald BEINER, 浜 田 義 文 監 訳 『カント 政 治 哲 学 の 講 義 』 法 政 大 学 出 版 局 、1987<br />
年 。および、 仲 正 昌 樹 訳 『 完 訳 カント 政 治 哲 学 講 義 録 』 明 月 堂 書 店 、2009 年 。<br />
古 典 的 文 献<br />
※ 古 典 的 文 献 の 表 記 は 慣 例 に 従 い、ラテン 語 形 で 著 者 および 書 名 を 表 記 した。 邦 訳 、 及 び 原 文 の 出 典 はその 後<br />
に 括 弧 に 入 れて 示 しておいた。アリストテレスの 文 献 を 表 示 する 際 は、これも 慣 例 に 従 い、ベッカー 版 アリストテレ<br />
ス 全 集 の 頁 、コラム、 行 で 引 用 箇 所 を 示 した。アウグスティヌスに 関 しては、 巻 ・ 章 で、 聖 書 からの 引 用 は 章 ・ 節 で、<br />
それぞれ 引 用 箇 所 を 示 している。『イリアス』からの 引 用 に 際 しては 巻 ・ 行 で 示 した。<br />
ARISTOTELES, Ethica Nicomachea. ( 高 田 三 郎 訳 『ニコマコス 倫 理 学 』 上 、 岩 波 文 庫 、1971 年 。 原<br />
文 ・ 英 訳 は、with an English trans. by H. RACKHAM, Aristotle XIX: The Nichomachean Ethics,<br />
new and revised ed., Cambridge/ Massachusetts: Harvard Univ. Press, 1975 [orig.1926] を 参 照 し<br />
た。)<br />
――――, Metaphysica.( 出 隆 訳 『 形 而 上 学 』 上 下 、 岩 波 文 庫 、1959-1961 年 。)<br />
――――, Physica. ( 出 隆 / 岩 崎 允 胤 訳 『アリストテレス 全 集 3 自 然 学 』 岩 波 書 店 、1968 年 。 原<br />
文 は、with an English trans. by Philip H. WICKSTEED/ Francis M. CORNFORD, Aristotle IV:<br />
Physics I, revised ed., Cambridge/ Massachusetts: Harvard Univ. Press, 1970 [orig. 1929] および<br />
texte établi et trad. par Henri CARTERON, Aristote Physique (I-IV), 7 ème tirage, Paris : Les Belles<br />
Lettres, 1990 [orig. 1926] を 参 照 した。また、 併 せてそれぞれの 英 訳 ・ 仏 訳 も 参 照 した。)<br />
AUGUSTINUS, Aurelius, De civitate Dei. ( 服 部 英 次 郎 訳 『 神 の 国 』3 巻 、 岩 波 文 庫 、1983 年 。)<br />
126
HOMERUS, Ilias. ( 松 平 千 秋 訳 『イリアス』 上 下 巻 、 岩 波 文 庫 、1992 年 。 原 文 は Perseus Digital<br />
Library〔http://www.perseus.tufts.edu/hopper/〕 所 収 のものを 参 照 した。)<br />
NESTLE-ALAND, Novum Testamentum Graece, 26.Aufl. Nördlingen: Gesamtherstellung C. H. Beck,<br />
1979.<br />
関 根 正 雄 訳 『 旧 約 聖 書 創 世 記 』 改 版 、 岩 波 文 庫 、1967 年 。<br />
新 共 同 訳 『 新 約 聖 書 詩 編 つき』 日 本 聖 書 協 会 、1989 年 。<br />
その 他 の 文 献<br />
※ 外 国 語 の 文 献 に 関 して、 原 書 が 併 記 されているものに 関 しては、 引 用 に 際 し 原 文 も 確 認 し、 本 論 における 文 脈 に<br />
合 わせて 訳 文 を 修 正 した 箇 所 もある。<br />
ATTALI, Jacques, 蔵 持 不 三 也 訳 『 時 間 の 歴 史 』 原 書 房 、1986 年 。<br />
BEINER, Ronald, 「ハンナ・アーレントの 判 断 作 用 について」ARENDT, Hannah, ed. by Ronald<br />
BEINER, 浜 田 義 文 監 訳 『カント 政 治 哲 学 の 講 義 』( 前 掲 )133-238 頁 、および 仲 正 昌 樹 訳 『 完 訳<br />
カント 政 治 哲 学 講 義 録 』( 前 掲 )175-303 頁 。<br />
BENJAMIN, Walter, „Über den Begriff der Geschichte,“ in: ausgewählt und mit einem Nachwort von<br />
Alexander HONOLD, Erzählen: Schriften zur Theorie der Narration und zur literalischen Prosa,<br />
Frankfurt a.M.: Suhrkamp Verlag, S.129-140. ( 野 村 修 訳 「 歴 史 哲 学 テーゼ( 歴 史 の 概 念 につい<br />
て)」 今 村 仁 司 『ベンヤミン「 歴 史 哲 学 テーゼ」 精 読 』 岩 波 現 代 文 庫 、2000 年 、51-83 頁 。<br />
BERGSON, Henri, « Introduction (deuxième partie) : De la position des problèmes », dans : La<br />
Pensée et le mouvant: Essais et conferences, 4 ème éd., Paris : Librairie Félix Alcan, 1934,<br />
pp.33-113. (「 諸 論 ( 第 二 部 )」 河 野 与 一 訳 『 思 想 と 動 くもの』 岩 波 文 庫 、1998 年 、41-134 頁 )。<br />
――――, « Le possible et le réel », dans : ibid., pp.115-134.(「 可 能 性 と 事 象 性 」 前 掲 訳 書 、<br />
135-161 頁 。)<br />
DERRIDA, Jacques, Donner la mort, Paris : Édition Galilée, 1999. ( 廣 瀬 浩 司 / 林 好 雄 訳 『 死 を 与 え<br />
る』ちくま 学 芸 文 庫 、2004 年 。)<br />
DESCARTES, Lené, 井 上 庄 七 / 森 啓 訳 「 省 察 」『 世 界 の 名 著 22 デカルト』 中 央 公 論 社 、1967 年 、<br />
223-307 頁 。<br />
とき<br />
ELLENBERGER, Henri F. 中 井 久 雄 訳 「 精 神 療 法 におけるカイロスの 意 味 ―― 理 解 と 真 の 解 釈 の 秋 」<br />
中 井 久 雄 編 訳 『エランベルジェ 著 作 集 2 精 神 医 療 とその 周 辺 』みすず 書 房 、1999 年 、233 頁 か<br />
ら 249 頁 。<br />
ENDE, Michael, Momo oder Die seltsame Geschichte von den Zeit-Dieben und von dem Kind, das<br />
den Menschen die gestohlene Zeit zurückbrachte, Schulausgabe mit Materialien, Stuttgart/ Wien:<br />
Thienemann Verlag, 2005. ( 大 島 かおり 訳 『モモ 時 間 どろぼうと 盗 まれた 時 間 を 人 間 にとりかえ<br />
してくれた 女 の 子 のふしぎな 物 語 』 岩 波 書 店 、1976 年 。)<br />
HEGEL, Georg Wilhelm Friedlich, 樫 山 欽 四 郎 / 川 原 栄 峰 / 塩 谷 竹 男 訳 『 世 界 の 大 思 想 II-3 ヘ<br />
ーゲル エンチュクロペディー』 河 出 書 房 、1968 年 。<br />
127
――――, 長 谷 川 宏 訳 『 歴 史 哲 学 講 義 』 上 巻 、 岩 波 文 庫 、1994 年 。<br />
HEIDEGGER, Martin, Sein und Zeit, 11. unveränderte Aufl., Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1967.<br />
( 細 谷 貞 雄 訳 『 存 在 と 時 間 』 上 下 、ちくま 学 芸 文 庫 、1994 年 。)<br />
――――, Platon: Sophistes (Gesamtausgabe, Bd. 19), Frankfurt a.M.: Vittorio Klostermann, 1992.<br />
――――, Einführung in die Metaphysik (Gesamtausgabe Bd.40), Vittorio Klostermann: Frankfurt<br />
a.M., 1983. ( 川 原 栄 峰 訳 『 形 而 上 学 入 門 』 平 凡 社 ライブラリー、1994 年 。)<br />
――――, Phänomenologie des religiösen Lebens (Gesamtausgabe, Bd. 60), Frankfurt a.M.:<br />
Vittorio Klostermann, 1995.<br />
HESIODUS, Theogonia.( 廣 川 洋 一 訳 『 神 統 記 』 岩 波 文 庫 、1984 年 。)<br />
保 坂 幸 博 『ソクラテスはなぜ 裁 かれたか』 講 談 社 現 代 新 書 、1993 年 。<br />
細 川 亮 一 『ハイデガー 入 門 』ちくま 新 書 、2001 年 。<br />
今 村 仁 司 『ベンヤミン「 歴 史 哲 学 テーゼ」 精 読 』 岩 波 現 代 文 庫 、2000 年 。<br />
――――『マルクス 入 門 』ちくま 新 書 、2005 年 。<br />
岩 崎 稔 「 生 産 する 構 想 力 、 救 済 する 構 想 力 ――ハンナ・アーレントへの 一 試 論 ――」『 思 想 』807 号 、<br />
岩 波 書 店 、1991 年 、164-184 頁 。<br />
岩 下 壮 一 『カトリックの 信 仰 』 講 談 社 学 術 文 庫 、1994 年 。<br />
出 雲 春 明 「 活 動 の 時 間 性 ――H・アレント『 人 間 の 条 件 』 第 33、34 節 読 解 ――」『 倫 理 学 』23 号 、 筑<br />
波 大 学 倫 理 学 原 論 研 究 会 、2007 年 。<br />
JASPERS, Karl, Philosophie, Bd.2: Existenzerhellung, München/ Zürich: Piper, 1994. ( 小 倉 志 祥 /<br />
林 田 新 二 / 渡 辺 二 郎 訳 『 哲 学 』 中 公 クラシックス、2011 年 。)<br />
――――, 草 薙 正 夫 訳 『 哲 学 入 門 』 改 版 、 新 潮 文 庫 、2005 年 。<br />
河 合 隼 雄 『 昔 話 の 深 層 』 講 談 社 プラスアルファ 文 庫 、1994 年 。<br />
川 島 重 成 『『イーリアス』 ギリシア 英 雄 叙 事 詩 の 世 界 』 岩 波 書 店 、1991 年 。<br />
氣 多 雅 子 「 事 実 と 事 実 性 ――ハイデッガーとアーレントを 中 心 に――」『 京 都 大 學 文 學 部 研 究 紀 要 』<br />
45 号 、 京 都 大 學 大 學 院 文 學 研 究 科 ・ 文 學 部 、2006 年 、1-31 頁 。<br />
木 田 元 『ハイデガーの 思 想 』 岩 波 新 書 、1993 年 。<br />
熊 野 純 彦 『 西 洋 哲 学 史 古 代 から 中 世 へ』 岩 波 新 書 、2006 年 。<br />
LÉVINAS, Emmanuel. 西 谷 修 訳 『 実 存 から 実 存 者 へ』ちくま 学 芸 文 庫 、2005 年 。<br />
LÖWITH, Karl, 田 中 浩 / 原 田 武 雄 訳 「カール・シュミットの 機 会 原 因 論 的 決 定 主 義 」C.シュミット、 田<br />
中 浩 / 原 田 武 雄 訳 『 政 治 神 学 』 未 来 社 、1971 年 、89-163 頁 。<br />
真 木 悠 介 『 時 間 の 比 較 社 会 学 』 岩 波 現 代 文 庫 、2003 年 ( 原 著 1981 年 )。<br />
MARX, Karl, „Differenz der demokritischen und epikureischen Naturphilosophie,“ in: Marx-Engels<br />
Werke, Ergänzungsband: Schriften bis 1844, Erster Teil, Berlin: Dietz Verlag, 1968, S.257-373.<br />
( 岩 崎 允 胤 訳 「デモクリトスの 自 然 哲 学 とエピクロスの 自 然 哲 学 との 差 異 」『マルクス=エンゲルス<br />
全 集 』 第 40 巻 、 大 月 書 店 、1975 年 、185-241 頁 。)<br />
――――, „Thesen über Feuerbach,“ in: Marx-Engels Werke, Bd. 3, Berlin: Dietz Verlag, 1969,<br />
128
S.5-7. (「[フォイエルバッハに 関 するテーゼ]」 廣 松 渉 編 訳 、 小 林 昌 人 補 訳 『 新 編 輯 版 ドイツ・イ<br />
デオロギー』 岩 波 文 庫 、2002 年 、229-240 頁 。)<br />
――――, Ökonomisch-philosophische Manuskripte, 2.Aufl. Leipzig: Verlag Philipp Reclam, 1970<br />
( 長 谷 川 宏 訳 『 経 済 学 ・ 哲 学 草 稿 』 光 文 社 古 典 新 訳 文 庫 、2010 年 。)<br />
――――, „Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung,“ in: Marx-Engels Werke, Bd.1,<br />
Berlin: Dietz Verlag, 1977, S.378-391. ( 城 塚 登 訳 「ヘーゲル 法 哲 学 批 判 序 説 」『ユダヤ 人 問 題<br />
によせて ヘーゲル 法 哲 学 批 判 序 説 』 岩 波 文 庫 、1974 年 、69-96 頁 。)<br />
――――, Das Kapital: Kritik der politischen Ökonomie, 1.Bd. Berlin: Dietz Verlag, 1977. ( 向 坂<br />
逸 郎 訳 『 資 本 論 』1-3 巻 、 岩 波 文 庫 、1969 年 。)<br />
MARX, Karl/ ENGELS, Friedrich, hrsg. von Wataru HIROMATSU, Die Deutsche Ideologie,<br />
Neuveröffentlichung des Abschnittes 1 des Bandes 1 mit text-kritischen Anmerkungen, Tokio:<br />
Kawadeshobo-shinsha Verlag, 1974. ( 廣 松 渉 編 訳 、 小 林 昌 人 補 訳 『 新 編 輯 版 ドイツ・イデオロ<br />
ギー』 岩 波 文 庫 、2002 年 。)<br />
見 田 宗 介 「 現 代 社 会 の 社 会 意 識 」 福 武 直 監 修 、 見 田 宗 介 編 『 社 会 学 講 座 12 社 会 意 識 論 』 東 京<br />
大 学 出 版 会 、1976 年 、1-26 頁 。<br />
森 川 輝 一 『〈 始 まり〉のアーレント 「 出 生 」の 思 想 の 誕 生 』 岩 波 書 店 、2010 年 。<br />
NIETZSCHE, Friedrich, Also sprach Zarathustra, Frankfurt a.M.: Insel Verlag, 1982. ( 氷 上 英 廣 訳<br />
『ツァラトゥストラはこう 言 った』 上 下 、 岩 波 文 庫 、1968-1970 年 。)<br />
RICHTER, Gerhard, “Acts of Memory and Mourning: Derrida and the Fictions of Anteriority,” in:<br />
RADSTONE, Susannah/ SCHWARZ, Bill (eds.), Memory: Histories, Theories, Debates, New York:<br />
Fordham Univ. Press, 2010, pp.150-160.<br />
斎 藤 環 『 戦 闘 美 少 女 の 精 神 分 析 』ちくま 文 庫 、2006 年 。<br />
SCHMITT, Carl, 田 中 浩 / 原 田 武 雄 訳 『 政 治 神 学 』 未 来 社 、1971 年 。<br />
竹 田 青 嗣 『ニーチェ 入 門 』ちくま 新 書 、1994 年 。<br />
竹 内 洋 『 社 会 学 の 名 著 30』ちくま 新 書 、20<strong>08</strong> 年 。<br />
TAMINIAUX, Jacques, trans. fr. the French by Michael GENDRE, The Thracian Maid and the<br />
Professional Thinker: Arendt and Heidegger, Albany: State Univ. of New York Press, 1997.<br />
田 崎 英 明 『 無 能 な 者 たちの 共 同 体 』 未 来 社 、2007 年 。<br />
TERDIMAN, Richard, “Memory in Freud,” in: RADSTONE, Susannah/ SCHWARZ, Bill (eds.), Memory:<br />
Histories, Theories, Debates (op.cit.), pp.93-1<strong>08</strong>.<br />
TILGHER, Adriano, 小 原 耕 一 / 村 上 桂 子 訳 『ホモ・ファーベル―― 西 欧 文 明 における 労 働 観 の 歴<br />
史 』 社 会 評 論 社 、2009 年 。<br />
角 山 栄 『 時 計 の 社 会 史 』 中 公 新 書 、1984 年 。<br />
内 田 隆 三 『ミシェル・フーコー』 講 談 社 現 代 新 書 、1990 年 。<br />
VON KROCKOW, Christian Graf, 高 田 珠 樹 訳 『 決 断 ユンガー、シュミット、ハイデガー』 柏 書 房 、<br />
1999 年 。<br />
129
若 林 幹 夫 『 社 会 学 入 門 一 歩 前 』NTT 出 版 、2007 年 。<br />
WEIL, Simone, 渡 辺 一 民 ・ 川 村 孝 則 訳 『ヴェーユの 哲 学 講 義 』ちくま 学 芸 文 庫 、1996 年 。<br />
辞 書 ・ 辞 典 類<br />
荒 川 幾 男 他 編 『 哲 学 辞 典 』 平 凡 社 、1971 年 。<br />
AUTENRIETH, Georg, trans. fr. the German by Robert P. KEEP, revised by Isacc FLAGG, A Homeric<br />
Dictionary for Schools and Colleges, New York: Harper & Brothers, 1895.<br />
今 村 仁 司 編 『 現 代 思 想 を 読 む 事 典 』 講 談 社 現 代 新 書 、1988 年 。<br />
高 津 春 繁 『ギリシア・ローマ 神 話 辞 典 』 岩 波 書 店 、1960 年 。<br />
LIDDELL & SCOTT, A Lexicon Abridged from Liddell and Scott’s Greek-English Lexicon, Oxford:<br />
Oxford Univ. Press, 1983.<br />
織 田 昭 編 『 新 約 聖 書 ギリシャ 語 小 辞 典 』 改 訂 第 2 版 、 大 阪 聖 書 学 院 、1965 年 。<br />
尚 学 図 書 編 『 故 事 俗 信 ことわざ 大 事 典 』 小 学 館 、1982 年 。<br />
130
あとがき<br />
あの 大 地 震 が 襲 ったのは、 本 研 究 の 最 初 の 数 ページを 書 いているころのことであった。2011 年 3<br />
月 11 日 の 地 震 と、それに 引 き 続 き 起 こった 福 島 第 一 原 子 力 発 電 所 のカタストロフによって、この 論<br />
文 は 否 が 応 でも 中 断 された。なかでも 福 島 の 原 発 事 故 は、いまだに 現 在 進 行 形 の 出 来 事 である<br />
(この「いま」や「 現 在 」に、とくに 日 付 を 付 そうとは 思 わない。というのも 少 なくとも 今 後 百 年 は、この<br />
事 故 は「 現 在 進 行 形 」の 出 来 事 であり 続 けるであろうから)。 二 ヶ 月 ばかりは 原 発 の 問 題 を 考 えたり<br />
で 集 中 力 を 割 かれてこの 論 文 を 再 開 することはなかなかできなかった。しかし 一 方 で、アーレントの<br />
思 考 を 相 手 にしているまさにそのときあの 災 害 に 直 面 し、そのために 気 付 いた 問 題 もまた、いくつも<br />
あった。なによりもまず、 地 震 も 津 波 も、そして 原 発 事 故 も、アーレントが 言 う 意 味 での( 同 時 にハイ<br />
デガー 的 な 意 味 での)「 世 界 」を 破 壊 するのだ、ということがひとつである。 世 界 は、アーレントによ<br />
れば、 持 続 性 のある 物 から 成 り、 人 間 の 外 部 (もしくは 人 間 と 人 間 のあいだ)に 存 在 するため、 人 間<br />
の 同 一 性 と 安 定 性 とを 保 証 している。このことを 逆 向 きに 言 い 直 せば、 世 界 がないとき、 人 間 は 同<br />
一 性 も 安 定 性 も 失 ってしまうということである。 西 洋 的 な 強 い「 主 体 」は、 時 間 的 で 壊 れやすい 世 界<br />
に 対 して、むしろ「 実 体 」として 存 続 する、 不 壊 のもののごとく 捉 えられてきた。しかし、 人 間 が 世 界 を<br />
失 ったとき、その「 主 体 」などというものは、すっかり 怪 しいものとなるというのが、 実 際 なのだ。 人 間<br />
的 な 有 意 味 性 の 連 関 としての「 世 界 」が、 人 間 的 な 居 場 所 を 定 めるとすれば、 地 震 や 津 波 が 街 を 破<br />
壊 したとき、 同 時 に 破 壊 されたのはこの「 世 界 」なのである。そして 原 発 事 故 は、 人 間 が 長 年 にわた<br />
り 居 住 できない「 反 世 界 」―― 人 間 の 居 住 する 空 間 が「 世 界 」であるとすれば、すぐれた 意 味 でそれ<br />
は「 反 世 界 」である――を 生 み 出 した。 不 気 味 なのは、それが 見 かけの 上 では「 世 界 」を 破 壊 してい<br />
ない 点 である( 勿 論 、 爆 発 で 吹 き 飛 んだ 原 子 炉 建 屋 は 別 であるが)。そういう 意 味 では、 人 間 的 制<br />
作 の 手 が 加 わることの 少 ない 自 然 や、 物 が 崩 れ 去 って 秩 序 を 喪 失 している 状 況 といったような、「 非<br />
世 界 」とはことなる。 世 界 は 持 続 しつつ、それでありながら 人 間 には 住 めない 反 世 界 へと 転 化 したの<br />
だ。そして 人 間 的 な 持 続 性 をはるかに 上 回 る 放 射 性 物 質 の 拡 散 が、 世 界 の 持 続 性 にたいする 反<br />
世 界 の 持 続 性 を 形 づくっている。<br />
ところで、アーレントの 師 であり、また 終 生 の 友 人 でもあったヤスパースは、あるところでつぎのよ<br />
うに 書 いていた。<br />
最 初 はある 一 人 の 主 要 な 哲 学 者 を 選 ぶだけで 結 構 であります。この 哲 学 者 がもっとも 偉 大<br />
な 哲 学 者 の 中 の 一 人 であるということはたしかに 望 ましいことです。しかしながら、 偶 然 に 最 初<br />
に 出 会 って、 深 い 印 象 を 受 けた 哲 学 者 が、 第 二 流 第 三 流 の 人 であっても、この 哲 学 者 によっ<br />
て 道 を 発 見 するということもありうるのです。 徹 底 的 に 研 究 されるならば、どんな 哲 学 者 でも、 一<br />
歩 一 歩 に、 哲 学 全 体 と 哲 学 史 の 全 体 とへ 導 き 入 れてくれるものです。〔JASPERS, 草 薙 正 夫 訳 『 哲<br />
学 入 門 』( 前 掲 )231-232 頁 。〕<br />
131
本 論 文 を 書 くことを 通 して 実 感 されたのは、まさにこの 言 葉 が 正 しかったということだったと 思 う。ア<br />
ーレントが「もっとも 偉 大 な 哲 学 者 」でも「 第 二 流 第 三 流 の 哲 学 者 」でもない、そもそも「 哲 学 者 」です<br />
らないとしても、そうなのである。わたしもまた、アーレントを「 徹 底 的 に 研 究 」したとはとても 言 えない。<br />
しかし、それでも、アーレントと、そしてその 時 間 論 という 問 題 とを 通 して、わたしは「 哲 学 ( 史 )の 全<br />
体 」へと 初 めて 導 き 入 れられたような 気 がする。アーレントの 思 想 を 読 み 解 くという 作 業 だけでも、 古<br />
代 から 現 代 までの 哲 学 を 考 え 合 わせることなしには、 困 難 であるということがあきらかとなった(もち<br />
ろん、 古 代 から 現 代 までの 哲 学 をきちんと 参 照 するというのは、 私 の 力 量 を 超 えた 作 業 であり、 不 十<br />
分 なかたちでしか 出 来 なかったが)。<br />
* * *<br />
この 論 文 を 書 くさい、 多 くの 方 にお 世 話 になりました。ここでは 特 にお 世 話 になった 方 々の 名 前<br />
を 記 して 感 謝 を 示 したいと 思 います。<br />
初 期 ハイデガーの 講 義 『 宗 教 的 生 の 現 象 学 』の 読 書 会 に 混 ぜてくださった、 最 上 直 紀 氏 、 樽 田<br />
勇 樹 氏 の 両 先 輩 、ならびに、 忙 しいなかでヤスパース『 哲 学 』の 読 解 につき 合 っていただいた 唐 川<br />
恵 美 子 氏 、 村 上 由 起 氏 、 村 田 香 織 氏 にお 礼 を 申 し 上 げます。<br />
ゼミに 出 席 させて 頂 いた 岩 崎 務 先 生 、 吉 本 秀 之 先 生 、 西 山 雄 二 先 生 ( 首 都 大 学 東 京 )、さらに、<br />
拙 稿 を 読 みコメントを 下 さった 西 谷 修 先 生 、 中 山 智 香 子 先 生 、ありがとうございました。<br />
最 後 に、 指 導 教 員 である 岩 崎 稔 先 生 へ 感 謝 を 申 し 上 げたいと 思 います。<br />
私 がハンナ・アーレントというひとを 知 ったのは、 岩 崎 先 生 の 二 年 のドイツ 語 購 読 の 授 業 で、ブラ<br />
イアーの『ハンナ・アーレント 入 門 』を 読 んだときです。 三 年 時 のゼミでは『 人 間 の 条 件 』と『 革 命 につ<br />
いて』を 続 けて 読 み、そのときアーレントの 思 想 の 大 きさと 深 さに 惹 かれて、そのまま 卒 業 論 文 の 題<br />
材 にしています。 岩 崎 先 生 のもとで 学 んでいなければ、 文 字 通 りの 意 味 でこの 論 文 は 書 かれてい<br />
ませんでした。ありがとうございました。<br />
橋 爪 大 輝<br />
132