講義要綱 PDFファイル【冊子版】※2013/3/11現在 - 慶應義塾大学-塾生HP
講義要綱 PDFファイル【冊子版】※2013/3/11現在 - 慶應義塾大学-塾生HP
講義要綱 PDFファイル【冊子版】※2013/3/11現在 - 慶應義塾大学-塾生HP
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
共通授業科目<br />
• どうして「熊をとる」とは言えても、「ライオンをとる」とは<br />
言えないのか。<br />
• どうして英語で"He is dying"というとまだ生存中のに、日本語<br />
で「死んでいる」というと生存中ではないのか。<br />
• どうして「ツマヨウジが一本あれば、なんとあっという間に空<br />
気を抜くことができるんです!」の「れば」は「たら」で置き<br />
換えることができるのに、「教科書には『二酸化マンガンに過<br />
酸化水素水を加えれば、酸素が発生する』と書いてあった」の<br />
「れば」は「たら」でうまく置き換えることができないのか。<br />
春学期の言語学Iを履修していることが望ましいが、言語学IIからの<br />
履修も可。<br />
テキスト(教科書):<br />
プリントを配布する。<br />
言語学Ⅰ 2 単位(春学期)<br />
言語を科学するとは何か<br />
【文経法政商医薬】<br />
【文経法政商医薬】<br />
前島 和也<br />
授業科目の内容:<br />
言語学はとりわけ19世紀以降、著しい多様化を経て現代に至って<br />
いるため、簡潔に定義するのは困難な状況です.これはそもそも言<br />
語というものが、思想、心理、社会, 文芸、etc.と云った多岐にわた<br />
る観点から考察可能な事に起因するとも云えます.仮に言語研究全<br />
般に共通了解があるとすれば、言語現象には規則性があり、規則の<br />
集約がそれぞれの研究分野である、と云うことになるでしょうか.<br />
この授業では言語学に漠然としたイメージしかない受講者を対象<br />
に、一般に親しみやすいと思われる意味、統辞や音韻の問題を、特<br />
に日本語のデータを中心に考察する事で、言語分析の実際を学んで<br />
いただきたいと思います.<br />
他方、現代言語学は19世紀後半から20世紀前半にかけて徐々に整<br />
備されたというのが言語学史の「常識」となっていますが、言語と<br />
論理、言語と思考といった問題は既に古代インドとりわけギリシャ<br />
においてかなり徹底的な議論が行われていました.哲学・論理学か<br />
ら「離陸」することで近代の言語研究が成立した訳ですが、人称、<br />
テンスや名詞限定といった概念が古代文法の残滓を残している事も<br />
事実です.文法概念の吟味を通して、今日の言語学が古代の言語研<br />
究から継承しているものと近代以降の発想に負っているものを峻別<br />
できれば言語学に対する理解も深まるのではないかと思います.<br />
最後の数回は受講者による研究発表と討議を行う予定です.<br />
言語学Ⅱ 2 単位(秋学期)<br />
言語を科学するとは何か<br />
前島 和也<br />
授業科目の内容:<br />
言語学はとりわけ19世紀以降、著しい多様化を経て現代に至って<br />
いるため、簡潔に定義するのは困難な状況です.これはそもそも言<br />
語というものが、思想、心理、社会, 文芸、etc.と云った多岐にわた<br />
る観点から考察可能な事に起因するとも云えます.仮に言語研究全<br />
般に共通了解があるとすれば、言語現象には規則性があり、規則の<br />
集約がそれぞれの研究分野である、と云うことになるでしょうか.<br />
この授業では言語学に漠然としたイメージしかない受講者を対象<br />
に、一般に親しみやすいと思われる意味、統辞や音韻の問題を、特<br />
に日本語のデータを中心に考察する事で、言語分析の実際を学んで<br />
いただきたいと思います.<br />
他方、現代言語学は19世紀後半から20世紀前半にかけて徐々に整<br />
備されたというのが言語学史の「常識」となっていますが、言語と<br />
論理、言語と思考といった問題は既に古代インドとりわけギリシャ<br />
においてかなり徹底的な議論が行われていました.哲学・論理学か<br />
ら「離陸」することで近代の言語研究が成立した訳ですが、人称、<br />
テンスや名詞限定といった概念が古代文法の残滓を残している事も<br />
事実です.文法概念の吟味を通して、今日の言語学が古代の言語研<br />
究から継承しているものと近代以降の発想に負っているものを峻別<br />
できれば言語学に対する理解も深まるのではないかと思います.<br />
最後の数回は受講者による研究発表と討議を行う予定です.<br />
14<br />
言語学Ⅲ 2 単位(春学期)<br />
ことばの科学:神経言語学と進化言語学から心と言語を考える<br />
【文経法政商医薬】<br />
辻 幸夫<br />
授業科目の内容:<br />
ヒトはどのようにことばを獲得したのか、生物学、生態学、心理<br />
学、神経科学、記号学の立場などさまざまな角度からの研究成果を<br />
言語学の基礎的な考え方に組み入れるとどうなるか学生と考察しま<br />
す。その際、系統発生と個体発生の両側面が問題になりますが、春<br />
学期は特に前者に焦点を当てて検討します。<br />
テキスト(教科書):<br />
必要と判断された場合は教科書販売所に掲示しますので参照して<br />
ください。<br />
言語学Ⅳ 2 単位(秋学期)<br />
ことばの科学:心理言語学と社会言語学から心とことばを考える<br />
【文経法政商医薬】<br />
辻 幸夫<br />
授業科目の内容:<br />
言語の習得や運用は、個人的・心理的なプロセスであるのと同時<br />
に、社会で共有されるコードの形成過程であり、かつそれぞれの表<br />
現行動と理解行動でもあります。両者の側面がどのように相互に関<br />
係しているのか、それぞれについて概観しつつ、特に言語習得の個<br />
体発生的諸問題について考察します。その上で、春学期の言語学III<br />
の議論をもとに、さらに発展させて、言語と言語学の内奥に迫りた<br />
いと思います。詳細な言語習得の実験・観察データはテキストに譲<br />
り、授業ではなるべくその本質について議論していきたいと思いま<br />
す。<br />
テキスト(教科書):<br />
M. Tomasello著(辻幸夫他訳)『ことばをつくる:言語習得の認知言<br />
語学的アプローチ』<strong>慶應義塾大学</strong>出版会 2008年<br />
言語認識論 2 単位(春学期)<br />
認知言語学入門<br />
【文経法政商医理薬】<br />
【文経商医理薬】<br />
【文経商医理薬】<br />
小原 京子<br />
授業科目の内容:<br />
本講義では、私達にとって身近で本質的なを通じて、<br />
の働きを探っていきます。このような研究領域を認知言<br />
語学と呼びます。本講義では、認知言語学の主要な概念を紹介しつ<br />
つ、日本語や英語その他の言語の分析例を交えてことばの普遍的な<br />
特徴を取り上げることにより、ことばから見たこころの働きについ<br />
て考察します。<br />
一部演習形式を採り、学生たちが意見を述べる機会を設けます。<br />
テキスト(教科書):<br />
第1回授業で指示します。<br />
現代芸術論 2 単位(春学期)<br />
第二次世界大戦以降の美術<br />
近藤 幸夫<br />
授業科目の内容:<br />
第二次世界大戦後、世界の美術の中心は、パリからニューヨーク<br />
へと移りました。授業では、この時期から現代までの美術の動きに<br />
ついての基礎的な知識の習得を目的とします。適宜、現代美術のタ<br />
イムリーな話題や展覧会のはなしを織り交ぜながら授業をすすめて<br />
いく予定です。<br />
テキスト(教科書):<br />
ありません<br />
現代芸術論 2 単位(春学期)<br />
現代芸術論 2 単位(秋学期)<br />
現代芸術の諸相<br />
*春・秋とも同一の内容です。<br />
髙桒 和巳<br />
授業科目の内容:<br />
「現代」芸術論と銘打たれていますが、中心的に扱うことになるのは<br />
20世紀前半になります。


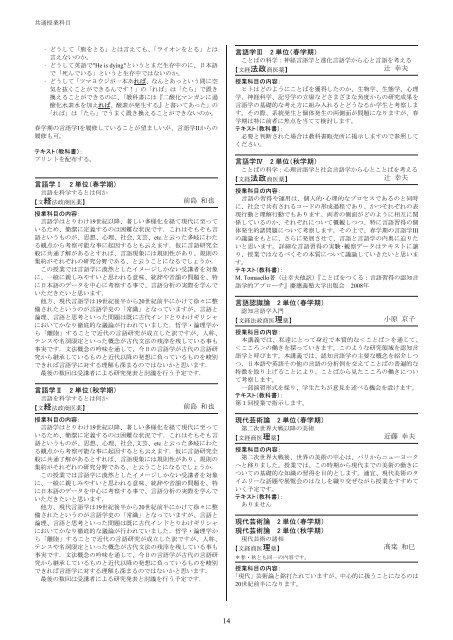
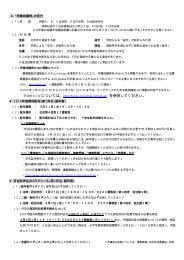
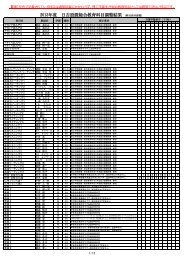








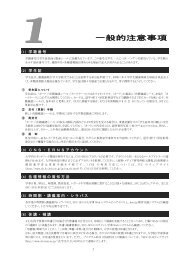
![文学部時間割表[2 ・3年生(07学則)]](https://img.yumpu.com/21046130/1/184x260/2-307.jpg?quality=85)


