文学部(塾内用) - 慶應義塾大学-塾生HP
文学部(塾内用) - 慶應義塾大学-塾生HP
文学部(塾内用) - 慶應義塾大学-塾生HP
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
テキスト(教科書):<br />
講義時にプリント配布<br />
題材として映像を鑑賞<br />
参考書:<br />
『ドキュメンタリー映画の地平 愛蔵版』佐藤真著 凱風社 2009<br />
年 ISBN:9784773633139<br />
『ジャーナリズムの条件 4 ジャーナリズムの可能性』野中章弘<br />
編 岩波書店 2005年 ISBN:4-00-026400-1 C0336<br />
『反空爆の思想』 吉田敏浩 日本放送出版協会 2006年 ISBN-10:<br />
4140910658<br />
『北朝鮮からの脱出者たち』石丸次郎 講談社+α文庫 2006年<br />
ISBN-10: 406281000X<br />
授業の計画:<br />
春学期は刀川和也、吉田敏浩、石丸次郎が分担して講義する。<br />
刀川は主にドキュメンタリー映画製作について(内容は下記参<br />
照)、吉田はルポルタージュについて(5、6月に集中講義、内容は<br />
下記参照)、石丸はマスコミができない取材と表現についてのガイダ<br />
ンス的講義を行う。<br />
吉田敏浩<br />
「ルポルタージュとはなにか」<br />
ルポルタージュの取材をして書くときに、とても大切なのは当事<br />
者の切実な言葉と姿に学ぶことです。<br />
私はビルマ(ミャンマー)の内戦の現場や森と共に生きる少数民<br />
族の生活と文化、日本社会における夫婦の絆、意識障害者の介護、<br />
過労死・過労自殺、ホスピス、自然葬、四国遍路など生と死をめぐ<br />
る問題を取材してきました。また、自衛隊の海外派遣や自衛官の自<br />
殺、日米軍事一体化、在日米軍基地、空爆の歴史、米兵犯罪裁判権<br />
に関する日米地位協定の密約、人を使い捨てにする「人的資源」の<br />
発想の歴史と現状(派遣労働者の置かれている深刻な現状など)な<br />
ども取材してきました。<br />
その経験を通じて、国や民族などの違いを越えて共通する人間の<br />
生と死の有り様にふれました。他者の痛みに思い至ることの難しさ<br />
を実感するとともに、他者・相手の立場からは現実はどう見えるの<br />
かを考えることの意味も知りました。また、理不尽な問題を引き起<br />
こしている政治・経済の構造を見抜くことの重要性も知りました。<br />
それは、当事者の切実な言葉と姿に学び、ジャーナリストとして<br />
の独自の視点と問題意識、在野の批判精神をつちかう、終わりのな<br />
いプロセスでもあると思っています。<br />
刀川和也<br />
「テレビドキュメンタリーとドキュメンタリー映画の功罪、そしてド<br />
キュメンタリーの可能性」<br />
私が関わった数本のテレビドキュメンタリーと現在製作中のドキ<br />
ュメンタリー映画を紹介しながら、実際に抱えた問題や困難さ、あ<br />
るいは面白さを履修されたみなさんと共有し、ドキュメンタリーの<br />
豊かさと可能性について一緒に考えていきます。<br />
担当教員から履修者へのコメント:<br />
現代芸術論Ⅰ(春学期)と現代芸術論Ⅱ(秋学期)は講義内容が<br />
連続している。両講義を合わせて履修することが望ましい。<br />
成績評価方法:<br />
平常点:出席状況および授業態度による評価<br />
レポートによる評価<br />
現代芸術Ⅱ 2単位 (秋学期)<br />
ジャーナリズムにおける新しい表現の方法と実践 Ⅱ<br />
講師 野中 章弘<br />
講師 石丸 次郎<br />
講師 吉田 敏浩<br />
講師 刀川 和也<br />
授業科目の内容:<br />
本講義は、独立系ジャーナリスト集団、アジアプレス・インター<br />
ナショナル(以下、アジアプレス)の現役のジャーナリストが行う。<br />
アジアプレスは既存のマスメディアに所属するのではなく、個々の<br />
自立し、屹立した表現の獲得のために設立された団体である。各々<br />
のジャーナリストたちは、様々な道具(スティールカメラ ビデオ<br />
カメラ インターネット等)を駆使して独自の取材と発表を試みて<br />
きた。また、アジアを中心した国際報道、人権や環境や生き方など<br />
多岐にわたるテーマについて、新聞、テレビ、雑誌などのマスメデ<br />
ィアでの発表のみならず、独自の出版・インターネット配信などを<br />
21<br />
通じて、「伝えること、記録すること」というジャーナリズムの営み<br />
に、新しい表現の方法を模索・実践したてきた。<br />
それは講師を務めるジャーナリストたちの個性やテーマ、伝えた<br />
い対象によって実に様々だ。ルポルタージュという書く表現を追及<br />
している者、ドキュメンタリー映画製作を続ける者、また映像、執<br />
筆という表現行為のボーダー越え、テレビ、雑誌、ネット、書籍と<br />
いった多様なメディアをひとりで縦横無尽に使いこなす者。そのよ<br />
うなジャーナリストたちが現場で実践し格闘しながら獲得してきた<br />
「ジャーナリズムにおける新しい表現の方法と実践」について講義す<br />
る。自立した表現とはなにか、また独立したジャーナリズムとはな<br />
にかを考えていきたい。<br />
アジアプレス・インターナショナルのホームページ<br />
http://asiapress.org/<br />
テキスト(教科書):<br />
講義時にプリント配布<br />
題材として映像を鑑賞<br />
参考書:<br />
『ドキュメンタリー映画の地平 愛蔵版』佐藤真著 凱風社 2009年<br />
ISBN:9784773633139<br />
『ジャーナリズムの条件 4 ジャーナリズムの可能性』野中章弘編<br />
岩波書店 2005年 ISBN:4-00-026400-1 C0336<br />
『反空爆の思想』 吉田敏浩 日本放送出版協会 2006年<br />
ISBN-10:4140910658<br />
『北朝鮮からの脱出者たち』石丸次郎 講談社+α文庫 2006年<br />
ISBN-10: 406281000X<br />
授業の計画:<br />
秋学期は石丸次郎、野中章弘、刀川和也、が分担して講義する。<br />
石丸は主に「北朝鮮を伝える」「インターネットジャーナリズム」<br />
について、野中は主に「マスメディアを超える新しいジャーナリズ<br />
ムの模索」について、刀川は主にドキュメンタリー映画製作につい<br />
て(内容は下記参照)講義する。<br />
刀川和也<br />
「テレビドキュメンタリーとドキュメンタリー映画の功罪、そしてド<br />
キュメンタリーの可能性」<br />
私が関わった数本のテレビドキュメンタリーと現在製作中のドキ<br />
ュメンタリー映画を紹介しながら、実際に抱えた問題や困難さ、あ<br />
るいは面白さを履修されたみなさんと共有し、ドキュメンタリーの<br />
豊かさと可能性について一緒に考えていきます。<br />
担当教員から履修者へのコメント:<br />
現代芸術論Ⅰ(春学期)と現代芸術論Ⅱ(秋学期)は講義内容が<br />
連続しています。両講義を合わせて履修することが望ましいです。<br />
成績評価方法:<br />
平常点:出席状況および授業態度による評価<br />
レポートによる評価<br />
詩学Ⅰ 2単位 (春学期)<br />
名誉教授 古屋 健三<br />
授業科目の内容:<br />
永井荷風が本塾教授に着任し、「三田文学」を発刊してから100<br />
年がたちます。<br />
荷風は教師として文学者としてどんな活動をし、なにを残したのか。<br />
小泉信三、佐藤春夫、久保田万太郎、堀口大學、水上瀧太郎など荷<br />
風に触発された才能を通して多面的に探っていきます。また森鷗外、<br />
夏目漱石、上田敏など荷風が敬愛する作家との交流を通して、荷風<br />
に受けつがれたものもみていきます。ゾラ、モーパッサンなど荷風<br />
が愛読した外国作家にも話は及ぶでしょう。しかし、この講義は文<br />
学史ではありません。荷風論でもありません。荷風とはいったい何<br />
者か。いま、荷風を読むことにいかなる意味があるのか。われわれ<br />
自身のあり方を問う試みです。<br />
テキスト(教科書):<br />
荷風自身のテキストはもとより、言及する各作家の文章を多数読<br />
むことになると思いますが、とくにひとつの作品を通して検討する<br />
ことはありません。<br />
参考書:<br />
そのつど指示しますが、この講義の実体を掴みかねている方は「三<br />
田文学」(100号,2010年冬季号)を開いてくだされば、凡その察し<br />
はつくはずです。<br />
総<br />
合



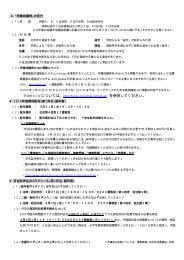
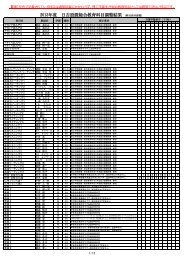








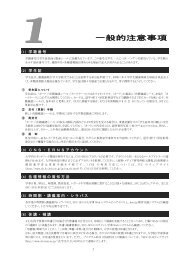
![文学部時間割表[2 ・3年生(07学則)]](https://img.yumpu.com/21046130/1/184x260/2-307.jpg?quality=85)


