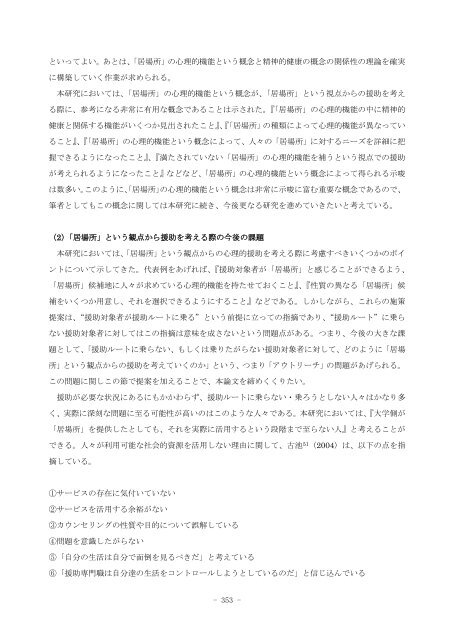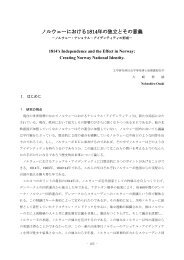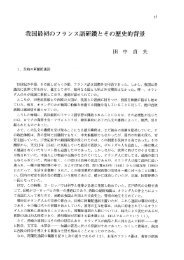大学生における「居場所」と精神的健康に関する一研究 - 創価大学
大学生における「居場所」と精神的健康に関する一研究 - 創価大学
大学生における「居場所」と精神的健康に関する一研究 - 創価大学
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
といってよい。あとは、「居場所」の心理的機能という概念と精神的健康の概念の関係性の理論を確実<br />
に構築していく作業が求められる。<br />
本研究においては、「居場所」の心理的機能という概念が、「居場所」という視点からの援助を考え<br />
る際に、参考になる非常に有用な概念であることは示された。『「居場所」の心理的機能の中に精神的<br />
健康と関係する機能がいくつか見出されたこと』、『「居場所」の種類によって心理的機能が異なってい<br />
ること』、『「居場所」の心理的機能という概念によって、人々の「居場所」に対するニーズを詳細に把<br />
握できるようになったこと』、『満たされていない「居場所」の心理的機能を補うという視点での援助<br />
が考えられるようになったこと』などなど、「居場所」の心理的機能という概念によって得られる示唆<br />
は数多い。このように、「居場所」の心理的機能という概念は非常に示唆に富む重要な概念であるので、<br />
筆者としてもこの概念に関しては本研究に続き、今後更なる研究を進めていきたいと考えている。<br />
(2)「居場所」という観点から援助を考える際の今後の課題<br />
本研究においては、「居場所」という観点からの心理的援助を考える際に考慮すべきいくつかのポイ<br />
ントについて示してきた。代表例をあげれば、『援助対象者が「居場所」と感じることができるよう、<br />
「居場所」候補地に人々が求めている心理的機能を持たせておくこと』、『性質の異なる「居場所」候<br />
補をいくつか用意し、それを選択できるようにすること』などである。しかしながら、これらの施策<br />
提案は、“援助対象者が援助ルートに乗る”という前提に立っての指摘であり、“援助ルート”に乗ら<br />
ない援助対象者に対してはこの指摘は意味を成さないという問題点がある。つまり、今後の大きな課<br />
題として、「援助ルートに乗らない、もしくは乗りたがらない援助対象者に対して、どのように「居場<br />
所」という観点からの援助を考えていくのか」という、つまり「アウトリーチ」の問題があげられる。<br />
この問題に関しこの節で提案を加えることで、本論文を締めくくりたい。<br />
援助が必要な状況にあるにもかかわらず、援助ルートに乗らない・乗ろうとしない人々はかなり多<br />
く、実際に深刻な問題に至る可能性が高いのはこのような人々である。本研究においては、『大学側が<br />
「居場所」を提供したとしても、それを実際に活用するという段階まで至らない人』と考えることが<br />
できる。人々が利用可能な社会的資源を活用しない理由に関して、古池 51 (2004)は、以下の点を指<br />
摘している。<br />
①サービスの存在に気付いていない<br />
②サービスを活用する余裕がない<br />
③カウンセリングの性質や目的について誤解している<br />
④問題を意識したがらない<br />
⑤「自分の生活は自分で面倒を見るべきだ」と考えている<br />
⑥「援助専門職は自分達の生活をコントロールしようとしているのだ」と信じ込んでいる<br />
- 353 -