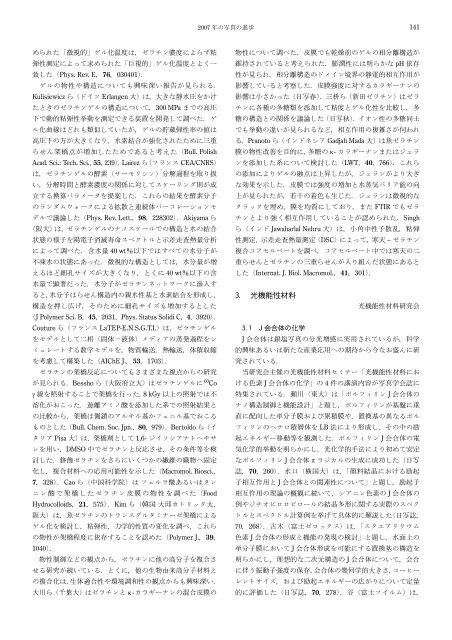2007 年の写真の進歩 - 日本写真学会
2007 年の写真の進歩 - 日本写真学会
2007 年の写真の進歩 - 日本写真学会
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
められた「微視的」ゲル化温度は,ゼラチン濃度によらず粘<br />
弾性測定によって求められた「巨視的」ゲル化温度とよく一<br />
致した(Phys. Rev. E,76,030401).<br />
ゲルの物性や構造についても興味深い報告が見られる.<br />
Kulisiewicz ら(ドイツ Erlangen 大)は,大きな静水圧をかけ<br />
たときのゼラチンゲルの構造について,300 MPa までの高圧<br />
下で動的粘弾性挙動を測定できる装置を開発して調べた.ゲ<br />
ル化曲線はどれも類似していたが,ゲルの貯蔵弾性率の値は<br />
高圧下の方が大きくなり,水素結合が強化されたために三重<br />
らせん架橋点が増加したためであると考えた(Bull. Polish<br />
Acad. Sci.: Tech. Sci.,55,239).Lairez ら(フランス CEA/CNRS)<br />
は,ゼラチンゲルの酵素(サーモリシン)分解過程を取り扱<br />
い,分解時間と酵素濃度の関係に対してスケーリング則が成<br />
立する換算パラメータを提案した.これらの結果を酵素分子<br />
のランダムウォークによる拡散と連続体パーコレーションモ<br />
デルで議論した(Phys. Rev. Lett.,98,228302).Akiyama ら<br />
(阪大)は,ゼラチンゲルのナノスケールでの構造と水の結合<br />
状態の様子を陽電子消滅寿命スペクトルと示差走査熱量分析<br />
によって調べた.含水量 40 wt%以下ではすべての水分子が<br />
不凍水の状態にあった.微視的な構造としては,水分量が増<br />
えるほど細孔サイズが大きくなり,とくに 40 wt%以下の含<br />
水量で顕著だった.水分子がゼラチンネットワークに滲入す<br />
ると,水分子はらせん構造内の親水性基と水素結合を形成し,<br />
構造を押し広げ,そのために細孔サイズも増加するとした<br />
(J Polymer Sci. B,45,2031,Phys. Status Solidi C,4,3920).<br />
Couture ら(フランス LaTEP-E.N.S.G.T.I.)は,ゼラチンゲル<br />
をモデルとして二相(固体-液体)メディアの蒸発過程をシ<br />
ミュレートする数学モデルを,物質輸送,熱輸送,体積収縮<br />
を考慮して構築した(AIChE J.,53,1703).<br />
ゼラチンの架橋反応についてもさまざまな視点からの研究<br />
が見られる.Bessho ら(大阪府立大)はゼラチンゲルに 60 Co<br />
γ 線を照射することで架橋を行った.8 kGy以上の照射では不<br />
溶化がおこった.遊離アミノ酸を添加した系での照射結果と<br />
の比較から,架橋は側鎖のアルキル基かフェニル基でおこる<br />
ものとした(Bull. Chem. Soc. Jpn.,80,979).Bertoldo ら(イ<br />
タリア Pisa 大)は,架橋剤として 1,6- ジイソシアナトヘキサ<br />
ンを用い,DMSO 中でゼラチンと反応させ,その条件等を検<br />
討した.修飾ゼラチンをさらにいくつかの繊維の織物へ固定<br />
化し,複合材料への応用可能性を示した(Macromol. Biosci.,<br />
7,328).Cao ら(中国科学院)は フェルラ酸あるいはタン<br />
ニ ン 酸 で 架橋したゼ ラ チン皮膜の 物 性 を 調べた(Food<br />
Hydrocolloids,21,575).Kim ら(韓国 大邱カトリック大,<br />
阪大)は,魚ゼラチンのトランスグルタミナーゼ架橋による<br />
ゲル化を検討し,粘弾性,力学的性質の変化を調べ,これら<br />
の物性が架橋程度に依存することを認めた(Polymer J.,39,<br />
1040).<br />
物性制御などの観点から,ゼラチンに他の高分子を複合さ<br />
せる研究が続いている.とくに,他の生物由来高分子材料と<br />
の複合化は,生体適合性や環境調和性の観点からも興味深い.<br />
大川ら(千葉大)はゼラチンと κ-カラギーナンの混合皮膜の<br />
<strong>2007</strong> <strong>年の写真の進歩</strong> 141<br />
物性について調べた.皮膜でも乾燥前のゲルの相分離構造が<br />
維持されていると考えられた.膨潤性には明らかな pH 依存<br />
性が見られ,相分離構造のドメイン境界の静電的相互作用が<br />
影響していると考察した.皮膜強度に対するカラギーナンの<br />
影響は小さかった(日写春).三枡ら(新田ゼラチン)はゼラ<br />
チンに各種の多糖類を添加して粘度とゲル化性を比較し,多<br />
糖の構造との関係を議論した(日写秋).イオン性の多糖同士<br />
でも挙動の違いが見られるなど,相互作用の複雑さが伺われ<br />
る.Pranoto ら(インドネシア Gadjah Mada 大)は魚ゼラチン<br />
膜の物性改善を目的に,多糖の κ- カラギーナンまたはジェラ<br />
ンを添加した系について検討した(LWT,40,766).これら<br />
の添加によりゲルの融点は上昇したが,ジェランがより大き<br />
な効果を示した.皮膜では強度の増加と水蒸気バリア能の向<br />
上が見られたが,若干の着色も生じた.ジェランは微視的な<br />
クラックを埋め,膜を均質にしており,また FTIR でもゼラ<br />
チンとより強く相互作用していることが認められた.Singh<br />
ら(インド Jawaharlal Nehru 大)は,小角中性子散乱,粘弾<br />
性測定,示差走査熱量測定(DSC)によって,寒天 – ゼラチン<br />
複合コアセルベートを調べ,コアセルベート中では寒天の二<br />
重らせんとゼラチンの三重らせんが入り組んだ状態にあると<br />
した(Internat. J. Biol. Macromol.,41,301).<br />
3. 光機能性材料<br />
光機能性材料研究会<br />
3.1 J 会合体の化学<br />
J 会合体は銀塩写真の分光増感に実用されているが,科学<br />
的興味あるいは新たな産業応用への期待から今なお盛んに研<br />
究されている.<br />
当研究会主催の光機能性材料セミナー「光機能性材料にお<br />
ける色素 J 会合体の化学」の 4 件の講演内容が写真学会誌に<br />
特集されている.瀬川(東大)は「ポルフィリン J 会合体の<br />
ナノ構造制御と機能設計」と題し,ポルフィリンが基盤に垂<br />
直に配向した単分子膜および累積膜や,置換基の異なるポル<br />
フィリンのヘテロ積層体を LB 法により形成し,その中の励<br />
起エネルギー移動等を観測した.ポルフィリン J 会合体の電<br />
気化学的挙動を明らかにし,光化学的手法により初めて安定<br />
なポルフィリン J 会合体 π ラジカルの生成に成功した(日写<br />
誌,70,260).水口(横国大)は,「顔料結晶における励起<br />
子相互作用と J 会合体との関連性について」と題し,励起子<br />
相互作用の理論の概観に続いて,シアニン色素の J 会合体の<br />
例やジチオピロロピロールの結晶多形に関する実際のスペク<br />
トルとスペクトル計算例を挙げて具体的に解説した(日写誌,<br />
70,268).古木(富士ゼロックス)は,「スクエアリリウム<br />
色素 J 会合体の形成と機能の発現の検討」と題し,水面上の<br />
単分子膜において J 会合体形成を可能にする置換基の構造を<br />
明らかにし,理想的な二次元構造の J 会合体について,会合<br />
に伴う振動子強度の保存,会合体の幾何学的大きさ,コーヒー<br />
レントサイズ,および励起エネルギーの広がりについて定量<br />
的に評価した(日写誌,70,278).谷(富士フイルム)は,