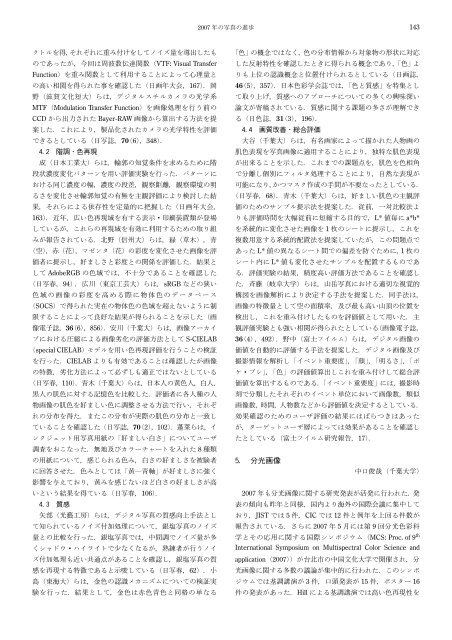2007 年の写真の進歩 - 日本写真学会
2007 年の写真の進歩 - 日本写真学会
2007 年の写真の進歩 - 日本写真学会
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
クトルを得,それぞれに重み付けをしてノイズ量を導出したも<br />
のであったが,今回は周波数伝達関数(VTF: Visual Transfer<br />
Function)を重み関数として利用することによって心理量と<br />
の高い相関を得られた事を確認した(日画年大会,167).岡<br />
野(滋賀文化短大)らは,デジタルスチルカメラの光学系<br />
MTF(Modulation Transfer Function)を画像処理を行う前の<br />
CCD から出力された Bayer-RAW 画像から算出する方法を提<br />
案した.これにより,製品化されたカメラの光学特性を評価<br />
できるとしている(日写誌,70(6),348).<br />
4.2 階調・色再現<br />
成(日本工業大)らは,輪郭の知覚条件を求めるために階<br />
段状濃度変化パターンを用い評価実験を行った.パターンに<br />
おける同じ濃度の幅,濃度の段差,観察距離,観察環境の明<br />
るさを変化させ輪郭知覚の有無を主観評価により検討した結<br />
果,それらによる依存性を定量的に把握した(日画年大会,<br />
163).近年,広い色再現域を有する表示・印刷装置類が登場<br />
しているが,これらの再現域を有効に利用するための取り組<br />
みが報告されている.北野(信州大)らは,緑(草木),青<br />
(空),赤(花),マゼンタ(花)の彩度を変化させた画像を評<br />
価者に提示し,好ましさと彩度との関係を評価した.結果と<br />
して AdobeRGB の色域では,不十分であることを確認した<br />
(日写春,94).広川(東京工芸大)らは,sRGB などの狭い<br />
色 域 の画像の彩 度を高める際 に 物 体 色 のデータベ ース<br />
(SOCS)で得られた実在の物体色の色域を超えないように制<br />
限することによって良好な結果が得られることを示した(画<br />
像電子誌,36(6),856).安川(千葉大)らは,画像アーカイ<br />
ブにおける圧縮による画像劣化の評価方法として S-CIELAB<br />
(special CIELAB)モデルを用い色再現評価を行うことの検証<br />
を行った.CIELAB よりも有効であることは確認したが画像<br />
の特徴,劣化方法によって必ずしも適正ではないとしている<br />
(日写春,110).青木(千葉大)らは,日本人の黄色人,白人,<br />
黒人の肌色に対する記憶色を比較した.評価者に各人種の人<br />
物画像の肌色を好ましい色に調整させる方法で行い,それぞ<br />
れの分布を得た.またこの分布が実際の肌色の分布と一致し<br />
ていることを確認した(日写誌,70(2),102).蓬莱らは,イ<br />
ンクジェット用写真用紙の「好ましい白さ」についてユーザ<br />
調査をおこなった.無地及びカラーチャートを入れた 8 種類<br />
の用紙について,感じられる色み,白さの好ましさを被験者<br />
に回答させた.色みとしては「黄―青軸」が好ましさに強く<br />
影響を与えており,黄みを感じないほど白さの好ましさが高<br />
いという結果を得ている(日写春,106).<br />
4.3 質感<br />
矢部(光藝工房)らは,デジタル写真の質感向上手法とし<br />
て知られているノイズ付加処理について,銀塩写真のノイズ<br />
量との比較を行った.銀塩写真では,中間調でノイズ量が多<br />
くシャドウ・ハイライトで少なくなるが,熟練者が行うノイ<br />
ズ付加処理も近い共通点があることを確認し,銀塩写真の質<br />
感を再現する特徴であると示唆している(日写春,62).小<br />
島(東海大)らは,金色の認識メカニズムについての検証実<br />
験を行った.結果として,金色は赤色青色と同格の単なる<br />
<strong>2007</strong> <strong>年の写真の進歩</strong> 143<br />
「色」の概念ではなく,色の分布情報から対象物の形状に対応<br />
した反射特性を確認したときに得られる概念であり,「色」よ<br />
りも上位の認識概念と位置付けられるとしている(日画誌,<br />
46(5),357).日本色彩学会誌では,「色と質感」を特集とし<br />
て取り上げ,質感へのアプローチについての多くの興味深い<br />
論文が寄稿されている.質感に関する課題の多さが理解でき<br />
る(日色誌,31(3),196).<br />
4.4 画質改善・総合評価<br />
大谷(千葉大)らは,有名画家によって描かれた人物画の<br />
肌色表現を写真画像に適用することにより,独特な肌色表現<br />
が出来ることを示した.これまでの課題点を,肌色を色相角<br />
で分離し個別にフィルタ処理することにより,自然な表現が<br />
可能になり,かつマスク作成の手間が不要なったとしている.<br />
(日写春,68).青木(千葉大)らは,好ましい肌色の主観評<br />
価のためのサンプル提示法を提案した.従前,一対比較法よ<br />
りも評価時間を大幅従前に短縮する目的で,L* 値毎に a*b*<br />
を系統的に変化させた画像を 1 枚のシートに提示し,これを<br />
複数用意する系統的配置法を提案していたが,この問題点で<br />
あった L* 値の異なるシート間での偏差を防ぐために,1 枚の<br />
シート内に L* 値も変化させたサンプルを配置するものであ<br />
る.評価実験の結果,精度高い評価方法であることを確認し<br />
た.斉藤(岐阜大学)らは,山岳写真における適切な視覚的<br />
構図を画像解析により決定する手法を提案した.同手法は,<br />
画像の特徴量として空の面積率,及び最も高い山頂の位置を<br />
検出し,これを重み付けしたものを評価値として用いた.主<br />
観評価実験とも強い相関が得られたとしている(画像電子誌,<br />
36(4),492).野中(富士フイルム)らは,デジタル画像の<br />
価値を自動的に評価する手法を提案した.デジタル画像及び<br />
撮影情報を解析し「イベント重要度」,「顔」,「明るさ」,「ボ<br />
ケ・ブレ」,「色」の評価値算出しこれを重み付けして総合評<br />
価値を算出するものである.「イベント重要度」には,撮影時<br />
刻で分類したそれぞれのイベント単位において画像数,類似<br />
画像数,時間,人物数などから評価値を決定するとしている.<br />
効果確認のためのユーザ評価の結果にはばらつきはあった<br />
が,ターゲットユーザ層によっては効果があることを確認し<br />
たとしている(富士フイルム研究報告,17).<br />
5. 分光画像<br />
中口俊哉(千葉大学)<br />
<strong>2007</strong> 年も分光画像に関する研究発表が活発に行われた.発<br />
表の傾向も昨年と同様,国内より海外の国際会議に集中して<br />
おり,JIST では 5 件,CIC では 12 件と例年を上回る件数が<br />
報告されている.さらに <strong>2007</strong> 年 5 月には第 9 回分光色彩科<br />
学とその応用に関する国際シンポジウム(MCS: Proc. of 9th International Symposium on Multispectral Color Science and<br />
application(<strong>2007</strong>))が台北市の中国文化大学で開催され,分<br />
光画像に関する多数の議論が集中的に行われた.このシンポ<br />
ジウムでは基調講演が 3 件,口頭発表が 15 件,ポスター 16<br />
件の発表があった.Hill による基調講演では高い色再現性を