商学部(塾外用) - 慶應義塾大学-塾生HP
商学部(塾外用) - 慶應義塾大学-塾生HP
商学部(塾外用) - 慶應義塾大学-塾生HP
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
参考書:<br />
・『こどもをナメるな』(中島隆信著,ちくま新書)<br />
・『獄窓記』(山本譲司著,ポプラ社)<br />
理論経済学各論(マクロ・エコノミクス) 2単位 (春学期)<br />
准教授 渡部 和孝<br />
授業科目の内容:<br />
標準的な学部生向けの中級教科書を用い,経済成長,マクロ経済<br />
学のミクロ的基礎付けについて学ぶ。<br />
テキスト(教科書):<br />
N. グレゴリー・マンキュー著,足立英之他訳「マンキューマクロ<br />
経済学Ⅱ」,東洋経済新報社<br />
理論経済学各論(マネタリー・エコノミクス) 2単位 (秋学期)<br />
マネタリー・エコノミクス<br />
准教授 渡部 和孝<br />
授業科目の内容:<br />
金融政策の理論と実務,銀行経営,銀行規制などについて,米国<br />
の実践的テキスト,日本の政策エコノミストが執筆したマクロ経済<br />
学の上級テキストをベースにした講義を行う。<br />
テキスト(教科書):<br />
講義の大部分は参考書に沿った形で進みます。二冊全範囲をカバ<br />
ーするわけではないので教科書には指定しませんが,参考書がある<br />
と講義の理解は大幅に向上します。<br />
参考書:<br />
・ Frederic S. Mishkin and Stanley G. Eakins,“Financial Markets +<br />
Institutons sixth edition,” Pearson Education, Pearson Education<br />
ISBN-13: 978-0-321-55211-2<br />
・ 加藤涼著,「 現代マクロ経済学講義」東洋経済新報社<br />
ISBN4-492-31370-2<br />
経済政策 4単位 (秋学期集中)<br />
市場と政府の役割<br />
教授 樋口 美雄<br />
授業科目の内容:<br />
経済のグローバル化,産業構造の変化,少子高齢化の進展により,<br />
日本経済は大きな変革に迫られている。日本経済の特質を理解し,<br />
市場メカニズムと制度政策の関係について,マクロ経済学,ミクロ<br />
経済学の視点から考察し,これからの経済社会のあり方を検討して<br />
いくのがこの授業の目的である。<br />
参考書:<br />
樋口美雄『雇用と失業の経済学』日本経済新聞社、<br />
八田達夫『ミクロ経済学Ⅰ・Ⅱ』東洋経済新報社<br />
その他は授業中に指示する<br />
経済統計Ⅰ(05学則) 2単位 (春学期)<br />
経済統計Ⅱ(05学則) 2単位 (秋学期)<br />
経済統計(99学則) 4単位 (通年)<br />
経済学部教授 辻村 和佑<br />
(春学期)<br />
授業科目の内容:<br />
もとより計量経済学は,現実の経済事象を観察してそこに法則性<br />
を発見し,これをもとに理論仮説を設定して,この仮説を検証し,<br />
必要に応じて仮説を修正するといった,一連の作業に立脚した学問領<br />
域である。この際に重要な役割を果たすのが統計資料であることは<br />
言うまでもない。たとえばミクロ経済学の消費者行動理論はエンゲ<br />
ル法則という素朴な観察事実にその原点がある。このような消費者<br />
行動の経験法則を理論化するための用具として開発されたのが限界<br />
効用理論であり,効用関数を特定化することで,ここから導出され<br />
た需要関数が観察事実と整合的であるかどうかを統計的に検証する。<br />
いかに統計的検定の方法が精緻なものであろうとも,検証に利用す<br />
る統計資料がこれに見合うものでなければ,なんの意味も無い。た<br />
とえば家計の所得や支出配分に関する資料を収集する場合にも,収<br />
支が均衡しているかどうかを精査する必要がある。しかし家計が貯<br />
蓄をしたり,これを取り崩したりしている場合には,なにを貯蓄と<br />
定義するかといった問題を抜きにしては,収支の均衡を語ることす<br />
11<br />
らできない。春学期の授業では,主として経済統計の基礎概念を,<br />
具体的な統計資料を例として講義する。<br />
参考書:<br />
参考文献については,テーマごとに指示する。<br />
(秋学期)<br />
授業科目の内容:<br />
たとえば「実質GDP」といった用語は,専門の学術書ばかりでな<br />
く,新聞やテレビでもごく日常的に耳にする。しかし,それが厳密<br />
にどのような意味を持ち,さらにはそれがどのようにして測定され<br />
ているのかを知る人は,驚くほど少ない。実は「実質GDP」という<br />
用語ひとつを理解するためにも,国民経済計算体系(SNA)の5 勘<br />
定のひとつである産業連関表についての,かなり深い理解が必要で<br />
ある。その反面,産業連関表のみならず,国民経済計算体系全体を<br />
理解すれば,経済のさまざまな事象の相互依存関係を体系的に知る<br />
ことができる。とくにこの統計が優れているのは,バブルとその崩<br />
壊,あるいは恐慌といった実物事象と金融事象の相互依存の結果と<br />
して生ずる経済事象を分析できる点にあり,これは他の統計資料に<br />
は見られない特徴である。秋学期の授業では,他部門勘定体系とし<br />
ての国民経済計算の全体像を,主体の内部均衡,主体間均衡,異時<br />
点間均衡という,主として3 つの視点から講義する。<br />
参考書:<br />
春学期参照<br />
経済統計各論(産業連関分析) 2単位 (秋学期)<br />
産業研究所准教授 野村 浩二<br />
授業科目の内容:<br />
産業連関表は、国民経済計算体系(SNA)において中核的な勘定<br />
を与える経済統計としての役割を持つ一方、需要や価格の変化、あ<br />
るいは技術進歩など産業間の相互依存性を通じた経済への影響を算<br />
定するための分析道具として広く利用されている。また工学的情報<br />
との接合による環境・エネルギー分析や、雇用や投資・ストックな<br />
どとの接合によってより包括的な経済モデルを構築するなど、広い<br />
応用可能性を持つ。現実の政策シミュレーションに多用される応用<br />
一般均衡モデル(CGE)においても、その多くでは産業連関表が基<br />
盤を与えている。ここでは産業連関に関する理論、国民経済計算体<br />
系における位置づけと役割、作表の実際、一次統計との対応、産業<br />
連関体系の拡張性(投資、貿易、環境など)、そして部分均衡的なモ<br />
デルから一般均衡モデルの概略まで講義をおこなう。<br />
テキスト(教科書):<br />
授業において適宜指定。<br />
参考書:<br />
・W. レオンティエフ『経済学の世界』(日本経済新聞社)<br />
・尾崎巌『日本の産業構造』(<strong>慶應義塾大学</strong>出版会)<br />
・新飯田宏『産業連関分析入門』(東洋経済、1978年)<br />
・宮沢健一『産業連関分析入門』(日経文庫)<br />
経済統計各論(指数論) 2単位 (春学期)<br />
産業研究所准教授 野村 浩二<br />
授業科目の内容:<br />
経済変数としての数量と価格,その測定を適切におこなうために,<br />
様々な理論的・実証的な課題が検討されてきています。個々の財に<br />
おいては、数量と価格を分離することができても,集計量としての<br />
金額の変化は,数量と価格の変化へとどう分離したら良いでしょう<br />
か。消費者物価指数(CPI),国内総生産(GDP),購買力平価(PPP)<br />
など,各種の経済指標はどのように構築されていて,どんな意味と<br />
限界を持っているのでしょう。時系列的なあるいは横断面的な数量<br />
と価格の認識において,財の品質の変化をどう取り扱うことができ<br />
るのでしょうか。新聞紙上に毎日見る各種の経済指標の意味を適切<br />
に理解するためにも,さらに経済の実証分析のためには,指数(Index<br />
Number)の理解は不可欠な共通言語となっています。ここでは指数<br />
の理論と実際,そしてその応用に関して講義をおこないます。<br />
テキスト(教科書):<br />
授業において適宜指定。<br />
参考書:<br />
・森田優三『物価指数理論の展開』(東洋経済新報社)<br />
・G. ステューヴェル『経済指数の理論―指数問題とその解』(同文館)<br />
・OECD『Understanding National Accounts』<br />
[ 05 ] 専<br />
攻<br />
科<br />
目<br />
Ⅲ<br />
類<br />
( [ 99 ] Ⅳ<br />
類<br />
)



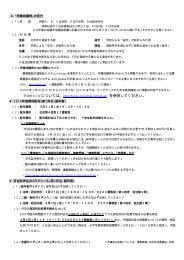
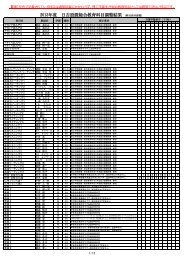








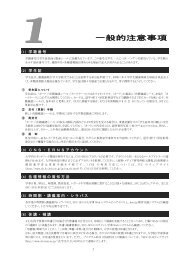
![文学部時間割表[2 ・3年生(07学則)]](https://img.yumpu.com/21046130/1/184x260/2-307.jpg?quality=85)

