商学部(塾外用) - 慶應義塾大学-塾生HP
商学部(塾外用) - 慶應義塾大学-塾生HP
商学部(塾外用) - 慶應義塾大学-塾生HP
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
経済学と法制度 2単位 (春学期)<br />
独占禁止法の法と経済学<br />
産業研究所准教授 石岡 克俊<br />
授業科目の内容:<br />
経済学(殊にミクロ経済学)は,経済(の諸活動)に関連し,そ<br />
の資源配分に関わる諸問題を主に理論的見地から解明・考察しよう<br />
とする学問領域である。ここでいう経済の諸活動には,生産・交換・<br />
消費といった活動が含まれるが,これらはいずれも私有財産制や契<br />
約自由などの私法制度や私法原則によって支えられている。他方,<br />
前世紀における福祉国家の登場以来,国民国家単位での経済政策の<br />
必要性に応じ政府・公権力の経済活動への介入は日常的なものとな<br />
った。法治国家であるわが国においては,こうした権力作用を根拠<br />
づける法は不可欠であり,これまで社会政策立法として労働法・社<br />
会保障法などの社会法および経済政策立法として独占禁止法を中核<br />
とする経済法を構想してきた。しばしばわが国などの先進資本主義<br />
諸国の経済システムを指して「市場経済体制」との呼び名が通用し<br />
ているが,この市場経済こそ私法制度によりその基礎を与えられた<br />
ものであり,また,社会法・経済法は市場経済の「失敗」や「暴走」<br />
の修正・補完のためにこそ存在する。このように,法(学)の領域<br />
は,経済(学)の領域の全面を覆うわけではないが,その多くの部<br />
分において密接に結びついている。確かに,経済問題の分析や経済<br />
学の研究にあって,法や法制度は所与であり前提であり,そして,<br />
しばしば懸念の対象でもある。だが,法学者の目から見ると,経済<br />
分析の成果が法律論の枠組みと大きく乖離しているために,しばし<br />
ばその成果の意義にも関わらず,無価値な容貌を呈することがある。<br />
モデルに用いられる変数が,法的判断の際に参照される諸要素と必<br />
ずしも一致していないためである。そこで,本講義では,かかる経<br />
済(学)と法(学)のギャップを埋めるべく,両学問分野に共通す<br />
るいくつかの経済問題を設定し,経済学的な方法論を身につけた受<br />
講生に対し,法的思考や方法論,また,経済法的な発想とはいかな<br />
るものかを説明していく。真の学際的な研究とは,互いの学問領域<br />
に精通した者の間の議論により成立するのではなく,互いの学問領<br />
域の方法論にまで踏み込んで(欲を言えば,相手方の学問領域の専<br />
門家になるほどに)互いが理解しあった上で成立するものと信じる<br />
からである。<br />
テキスト(教科書):<br />
講義初回に扱うテキストについて受講者と相談し決定する。昨年<br />
度は、岡田羊祐・林秀弥編著『独占禁止法の経済学—審判決の事例分<br />
析』(東京大学出版会、2009年)を用いた。<br />
参考書:<br />
特に指定しないが,内容との関係で有意義と認められるものにつ<br />
いては,講義を進めて行く中で都度紹介する。<br />
43<br />
戦略の経営・会計 2単位 (秋学期)<br />
准教授 三橋 平<br />
講師 西村 優子<br />
授業科目の内容:<br />
戦略について経営学と会計学の立場からアプローチし,総合的に<br />
考察することが目的である。1 回目にオリエンテーションを行った<br />
後,経営学から6 回の講義,会計学から6 回の講義を行う。<br />
参考書:<br />
西村優子著『研究開発戦略の会計情報』白桃書房<br />
戦略の経済・商業 2単位 (春学期)<br />
授業科目の内容:<br />
授業のガイダンス(第1 回)<br />
教授 木戸 一夫<br />
准教授 鄭 潤澈<br />
戦略の経済学的視点(第2 回~第7 回)<br />
担当 木戸 一夫<br />
ごく目先の利益ではなく,長期的視点での利益を考えた時,どこ<br />
にその利益を見出し,いかにしてそれを実現していくのか,といっ<br />
たことを考えるのが戦略的思考と言えよう。本講義では,その中で<br />
も,利益の源泉の部分に特に焦点を当て,コア・コンピタンスとな<br />
るような補完性の利益の数理的構造を学ぶ。<br />
・さまざまな補完性(1 回)<br />
・補完性の定式化と基本性質(2 回)<br />
・補完性を示す方法(1 回)<br />
・スーパーモジュラー関数の最適化と単調比較静学(1 回)<br />
・スーパーモジュラー・ゲーム(1 回)<br />
相互依存関係から見た戦略(第8 回~第13 回)<br />
担当 鄭 潤澈<br />
講義の後半では,応用ミクロ経済学の観点で経済主体の様々な戦<br />
略的行動プロセスを考察していく。まず企業間の競争に関する分析<br />
方法論を学び,それからその応用として情報と戦略の関係,そして,<br />
取引と組織における戦略を学習する。<br />
・企業間の競争(2 回)<br />
・情報と戦略の関係(2 回)<br />
・取引と組織における戦略(2 回)<br />
テキスト(教科書):<br />
各講義担当者が必要に応じて指示する。<br />
参考書:<br />
各講義担当者が授業中に適宜紹介する。<br />
[ 05 ] 商<br />
学<br />
関<br />
連<br />
科<br />
目<br />
( [ 99 ] 専<br />
攻<br />
科<br />
目<br />
Ⅳ<br />
類<br />
)


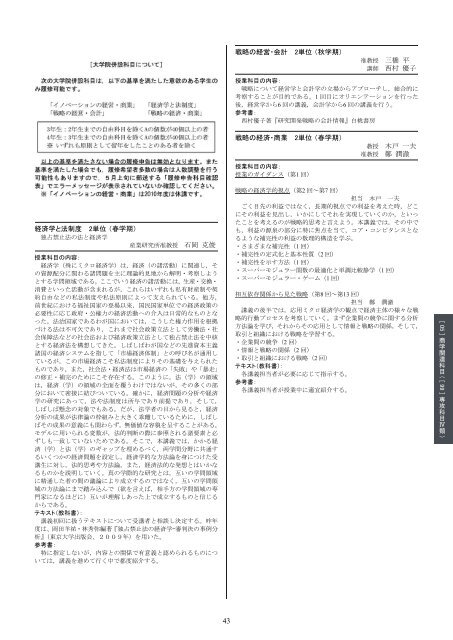
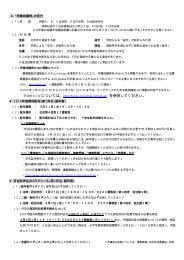
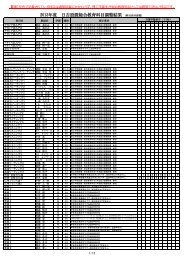








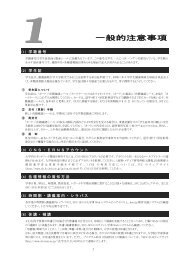
![文学部時間割表[2 ・3年生(07学則)]](https://img.yumpu.com/21046130/1/184x260/2-307.jpg?quality=85)

