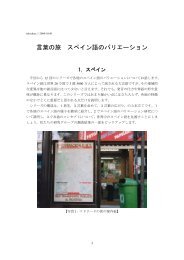スペイン語と日本語の音声の対照的研究 - 東京大学
スペイン語と日本語の音声の対照的研究 - 東京大学
スペイン語と日本語の音声の対照的研究 - 東京大学
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
いわば「つまみ食い」のような研究であった。 (…) そののち、両言語体系の全体に<br />
ついて異質なものも同質な点も同時に同等に扱って、網羅的に対照しなければなら<br />
ないという考え方が発展し、そのための名称に konfrontativ という表現が使われたよ<br />
うである。<br />
さらに大きな観点をもつ一般音声学的枠組みの中に両言語を位置づける方法もある。しか<br />
し、これは最初に言語普遍的な枠を設定してしまうのではなく、あくまで個々の言語の音声<br />
的事実を記述しそれを他の言語と比較していきながら、さらに大きな一般音声学的枠組みを<br />
構成していくべきである。全体の方向は個別言語音声学→対照音声学→一般音声学の順とな<br />
るだろう。<br />
1. 3. 資料<br />
本論文で用いられる資料は、主として(1)文献によるものと、(2)筆者の観察によるものに大<br />
別される。<br />
現在までに筆者が入手できたスペイン語および日本語の音声を扱った文献では、その対象<br />
が異なる方言であったり、また同一の音声事実を示すと思われるものが異なった表記で記述<br />
されていることもある。このような不統一のためにそのままの形では直接に資料として使う<br />
ことができない。よって、これらの資料を同一のレベルで扱えるようにするため、これらを<br />
評価し記述の精度や音声の表記もなるべくむらのないように統一した 21 。<br />
本研究の直接的資料は、筆者が日本人の立場から観察し研究したスペイン語の音声である。<br />
調音的記述には、信用ある音声学書を参考にしながらも筆者自身の調音感覚を重視した。<br />
発音のスタイルは、(1)ぞんざいな発音(easy), (2)普通体(usual), (3)丁寧な発話(careful)の 3 種<br />
に分け、(2) を主に、(1), (3) を参考にした。(1)~(3) は相対的なもので、明確な境界線は引<br />
けないが、(1) は親しい間柄での通常の会話などに見られる発話、(2)は会話が幾分丁寧にな<br />
される場合で、たとえばスペイン語話者が外国人に向かって話すときのスタイル 22 、(3) は発<br />
話自体に意識を向けた場合で、たとえば録音を意識した発話がこれにあたる 23 。<br />
筆者の個人語を考えてみると、日本語本来の音韻と外来性の音韻が混在していることがわ<br />
かる 24 。そこで「日本語の」音声の記述として、どこまでを取り上げるべきか、またそれらを<br />
同じレベルで扱うか、区別するかという問題がある。Bloch (1950; 1975: 115) は次のように述<br />
べている。<br />
どの単語が借用語であるかを決定できるような純粋に記述的な基準はないし、分析<br />
21 ほとんどの場合、I. P. A. を採用したが、若干の追加がある。また日本語との比較の必要か<br />
ら、従来のスペイン語音声学の慣用 (R. F. E. , 1915) にない記号を用いた場合もある。cf.<br />
Internatinal Phonetic Association (1949), 大西 (1950).<br />
22 Fries (1945, 1957m p. 110)の”matter-of-fact conversation”より少し丁寧な発話。<br />
23 Ebeling (1967). 金田一 (1965; 1967: 367-391)のいう「丁寧な発音」。<br />
24 cf. Fries and Pike (1949).<br />
15




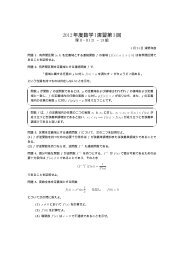




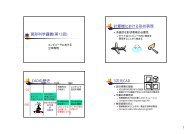




![『スペイン語逆引き辞典』[PDF] - 東京大学](https://img.yumpu.com/14471643/1/184x260/pdf-.jpg?quality=85)