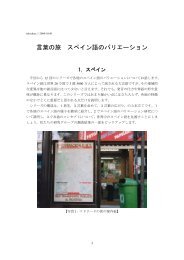スペイン語と日本語の音声の対照的研究 - 東京大学
スペイン語と日本語の音声の対照的研究 - 東京大学
スペイン語と日本語の音声の対照的研究 - 東京大学
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
れず、そのため「バック」、「ベット」のように/Q/の後の子音が無声化される傾向がある。そ<br />
こで日本語の音韻を記述するときには、先の環境における/h/も含めておくことが望ましい。<br />
それは、日本語話者がスペイン語の hijo「息子」['ixo]を/iQho/としがちな理由の 1 つとして考<br />
えなければならないからである。<br />
このように、外来語音のうち頻度の少ないものでも日本語の音韻体系に統合されていると<br />
考えられる音も日本語の音として含めなければならない。第 2 章以下で稀にしか用いられな<br />
い語が例としてあげられるのは、この理由によるのである。スペイン語の音声記述について<br />
も同様である。<br />
以上は両言語を個別に扱った音声資料の問題であるが、次に対照音声学の資料について述<br />
べる。一次資料は筆者が教室で観察した学生の発音である。幸い、高校生にスペイン語を教<br />
える機会があったので、そのときに気づいたことをメモにとり、それを分類して整理した。<br />
高校生であるためか、英語の干渉などが少なく音声的に素朴な資料を得ることができた 28 。<br />
逆に、スペイン語話者の日本語に見られる干渉は、知人の発音を観察した。不明な点は直接<br />
聞く (尋ねる) ことにした 29 。<br />
次に、いわゆる「二言語併用者」(bilingue) や「二言語兼用者」(diglotte) 30 の発話に見られ<br />
る日本語やスペイン語の干渉を二次的資料として用いた。これを二次的としたのは話者の個<br />
人的な経歴や当該言語との接触状態を客観的に判断する手立てがなかったからである。つま<br />
り、両言語の音韻の違い以外の要素が入っている可能性があるためである。これは初歩の学<br />
習者の純粋性と区別されなければならない 31 。しかし、初歩の学習者のおかす誤りとは違って、<br />
ほとんど完全な域に近いので、そこで見られる干渉はよほど克服が困難なものであると想像<br />
される。これは学習の難易度決定の重要な資料となるであろう。難易度の決定は理論的にも<br />
可能であるが 32 、二言語使用者の言語的背景の様々な要因と外国語音の習得度との相関関係を<br />
分析することによって、さらに具体的なものになる 33 。<br />
三次資料として外来語があげられる。楳垣 (1943; 1963: 2) によれば、外来語の研究の目的<br />
として、(1) 外来語を資料としての言語研究、(2) 外来語を通じての日本文化史の研究、(3) 外<br />
28 もっとも、留学から帰国した学生には英語の干渉が強く、たとえば無声閉鎖音の気息音化<br />
(tú['t h u])や非強勢母音の弱化(de España[dəs'paɲə])などが観察された。<br />
29 言語調査ではインフォーマントに meta-language に属することは質問すべきではない、と言<br />
われる(たとえば、太田 1959: 14ff) 。しかし、対照的に音声を研究するときは話者の直接的な<br />
経験が問題点の解決の重要な糸口になることがある。音素分析において資料提供者は<br />
"gathering"の段階で必要なのであって、"collation"の段階では必要でないが(Hockett, 1958m p.<br />
103ff)、対照音声学における資料提供者への meta-linguistic な interview はこの gathering の段階<br />
に属する部分が大きい。<br />
30 cf. Tabouret-Keller (1967; 1972): 262.<br />
31 太田(1965: 3)は、初歩の学習者から二言語併用者に近い段階までを連続的にとらえ、音体<br />
系を習得する過程を考えている。<br />
32 Stockwell and Bowen (1965), pp. 9-18.<br />
33 たとえば Hirano Weitzman (1967).<br />
17




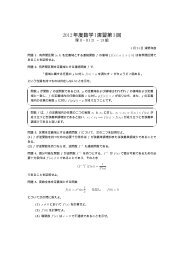




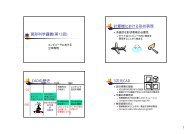




![『スペイン語逆引き辞典』[PDF] - 東京大学](https://img.yumpu.com/14471643/1/184x260/pdf-.jpg?quality=85)